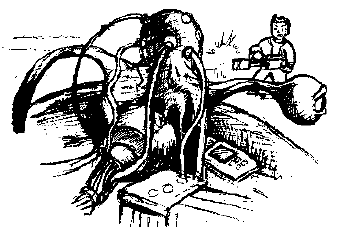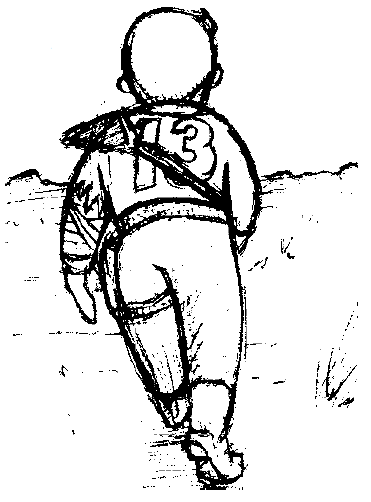マニュアルの巻頭に掲載されているVaultの住人の回想録を和訳したものです。
序文
年を取ることで一ついいことがあるとすれば、自分のやりたいようにやれるということだ。部族の新しい指導者たち(彼らは私がこの世を去るまで「長老」と呼ばれることを拒否している。しかし、私の運がよければ、そのときはまもなく訪れるはずだ)から、将来を担う世代の者たちのために、その知識を記録として残してほしいと求められている。バカバカしい!彼らが必要とするであろう知識、それは血と汗を流して獲得すべきものだ、ページの上の文字から得られるものではない。とはいえ、未来とは大いに未知なるもの、彼らの考えにも一理はある。彼らを喜ばせるため、私が大切であろうと感じたことを、ここに書き留めておこう。(大事なのは結局、“私が大切であろうと感じた”という言葉なのだ)
彼らは私に回想録を書くよう求めている。いいだろう。書いてやる。だが、歌にあるように、すべては心の決めたままにだ。私はすでに、そうできるだけの年齢を重ねているのだから。
戦争
私もあの戦争のことはほとんど知らないが、別にたいしたことじゃない。大量の核爆弾の炸裂によって、世界のほぼすべてが破壊され、多くの人々が死んだのだ。もし核爆弾が何かわからないなら、思いつくかぎり最悪のものを想像してみるといい。核爆弾とは、それよりもさらに最悪なものだ。
Vault
部族ができた当初からのメンバーである者たちと同じく、私もVaultの出身だ。あの戦争の前、合衆国政府――とてつもなく多くの民を抱えた村を数千も従える存在だと思ってくれればいい――が、山々に巨大な穴を掘り、地下に金属と石でできた小屋を建てさせた。これがVaultだ。Vaultはいくつもあった。町のすぐ近くにもあったし、遠く離れたところにもあった。これらVaultは、核戦争の際の避難所とするために作られたものだ。その通り、核戦争が起きたとき、君たちの先祖はとあるVaultへと入ったのだ。そう、Vault 13にな。
それから数世代の間、私たちの先祖はVaultの中で生活を送った。彼らからすれば、Vaultを出ようとするなんて、あまりにも危険すぎることだったのだ。彼らはVaultの中で食物を育て、廃棄物をリサイクルし、本を読み、仕事をし、眠り、家庭を持ち、さらには水の浄化までしていた。私はそんなVaultの養護施設で生まれ、コミュニティ(とロボット)によって育てられた。幸福な生活だった。しかし、よいことはいつまでもは続かぬものだ。戦争が終わってからおよそ3世代目を迎えた頃、新鮮な水を作るために不可欠なウォーターチップが故障してしまったのだ。予備の部品はすべて行方がわからないか壊れてしまっていたため、代わりのウォーターチップを見つけないかぎり、Vaultは滅亡する運命にあった。何とかしなければならなかった。
監督官は、16歳から35歳までの健康な若者を集めると、くじを引かせた。さて、どうなったと思う?私は「当たり」を引いてしまったのさ。そうでなきゃ、物語が始まらないだろう?
私がVaultを旅立ったのは、その翌日のことだった。
外の世界
最初の数日は、控えめに言ってもつらく苦しいものだった。本来の姿よりも明らかに巨大で攻撃的な変異ネズミたちを撃退しつつ、私は歩を進めた。唯一の手がかりは、ナンバー15のVaultの位置情報だけだ。そうして2日ばかり荒野をうろついていたところ、偶然小さな集落を見つけた。私は助けを求めてそこへ立ち寄った。そこは、シェイディ・サンズという小さな村だった。私は彼らに力を貸し、そうすることで、彼らも私に力を貸してくれた。よく覚えておいてくれ、生き延びるためには、たとえ信頼の置けない相手であっても、力を合わせ、協力することが必要になるのだ。まあとはいえ、このおかげで、私はシェイディ・サンズの2人の中心的人物――タンディとその父親アラデシュの信頼を得ることができた。
彼らの知識に、イアンという男の力も借りて、私はVault 15への旅を再開した。より正確に言えば、Vault 15の廃墟への旅だが。時による風化に加え、スカベンジャーに荒らされたせいで、Vault 15はもはや何の助けにもならなくなっていた。ウォーターチップがあるはずの司令室は、何トンもの岩の下に埋まっていた。私は、先へ進まねばならなかった。
レイダーども――私ばかりか、のちに部族を何年もの間悩まし続けることになる連中だ――とのちょっとしたいざこざがあったあと、ジャンクタウンにたどり着いた。私はこの町で、何よりも大切な原則を学んだ。善行をなす者は、ときにそのために極悪人とみなされるものである。ジャンクタウンでの思い出は苦々しいものだ。しかし、そこでした行いには一片の後悔もない。ある一匹の犬と出会ったのも、この町だった。彼は私を主人と認め、忠実な友となってくれた。ドッグミート、今でも君が恋しいよ。
ジャンクタウンはトレーダー(そしてトレイター)の町だったが、ウォーターチップはなかった。時間的余裕は十分にあったため、その時点ではまださほど焦ってはいなかったのだが、私はすぐに次の目的地へと旅立つことになった。幸運にも、ウェイストランドで最も大きな町、ハブの情報を得ることができたのだ。
ハブは、ジャンクタウンとシェイディ・サンズを合わせたよりもさらに大きな町だ。たとえVaultをその中へ落としたとしても、おそらく誰も気づきもしないだろう。だが、ハブの人々は人生を生きてはいなかった。どれだけ栄えていても、他と同じく荒廃した場所だったのだ。とはいえ、私はこの町でいくらか心の重荷を軽くすることができた。商人を雇い、Vault 13へ水を届けてもらったのだ。今振り返ってみれば、そんなことはやるべきではなかっただろう。しかし、当時の私はまだ、文明の廃墟に潜む悪意というものに対してあまりにも無知だったのだ。
わずかな手がかりをもとに、ネクロポリスと呼ばれるグールの町へ向かった。武装した巨大なミュータントと出会ったのは、この場所だ。やつらは、どこから手に入れたものやらわからぬ武器を持っていた。そして、このことは深い悲しみとともに記しておかねばなるまい。この死の町で、イアンが命を落とした。一体のスーパーミュータントに、火炎放射器で焼き尽くされたのだ。たとえどれだけ時がたとうと、あの臭いと光景は決して頭から消えることはない。しかし、彼の犠牲は無駄ではなかった。ネクロポリスの地下で、ついにウォーターチップが見つかったのだ。私はいくぶん軽やかな足取りで、Vault 13への帰路についた。
国家の敵(Enemies of the State)
監督官は、私がウォーターチップとともに生還したのを見たときは見るからに嬉しそうにしていたが、スーパーミュータントについての報告を聞くと、まったく取り乱したようになってしまった。水商人と取引したことが間違いだったと気づいたのは、このときだ。私は、水商人をはじめとする外の世界の者たちに、故郷のありかを教えてしまっていたのだ。居場所を知られては、Vaultが滅ぼされてしまう可能性も出てくる。Vault 15のたどった運命をこの目で見ていながら、私はあまりにもうかつだったのだ。
監督官は、私に新たな使命を課した。スーパーミュータントの根源を見つけ出し、その脅威を排除せよ。
私は再びVaultを旅立った。このときは、前回よりも気は楽だった。しかし今にして思えば、このとき、他のVault住民や監督官の本心を察しておくべきだったのだ。
私はハブへ戻り、手がかりを探した。そうしてしばしの時がたった頃、この大都市の喧騒の中に潜む裏社会の存在を見つけ出した。やつらは私をうまく操れると考えていたようだが、そんなことは間違いだと証明してやったうえ、逆に利用してやった。連中に捕らえられていた、Brotherhood of Steelの若い男を救出したのだ。数名のトラブルメーカーが止めようとしてきたが、Vaultを旅立って以来、私はすでに多くの生きる術を身につけていた。
しばらくの間はハブを離れるのが得策だろうと考え、件のBrotherhoodのもとへと向かった。求める情報が得られることを期待して、彼らのメンバーになろうと試みたが、その前に、ある場所の探索に行くよう要求された。そのくらい簡単だと思い、私は彼らがグロウと呼ぶ場所へ行くことを承諾した。しかし、核戦争の恐ろしさというものがこれほど明白な形をとって私の前に現れるとは、そのときの私は予想だにしていなかった。
Brotherhoodは、戻ってきた私を見て仰天した。私が生還しただけでなく、探索を成功させたことを知ると、さらに驚いていた。彼らは、こちらの求めていた情報と、彼らの持つテクノロジーの一部を提供してくれた。そして私は、ボーンヤードへと旅立った。
その途中、旧友たちに会うため遠回りをしてネクロポリスに立ち寄った。悲しいことに、そこは本当の意味での死の町となっていた。グールたちは皆殺しにされており、巨大なミュータントが通りを徘徊していた。生き残りが一人いたのを見つけ、話を聞くと、やつらは私が町を出たすぐ後に襲撃してきたらしい。そのグールは死ぬ前に、ミュータントたちが純系の人間、なかでも特定の一人の人物を探していたことを語ってくれた。その人物の特徴は、私と完全に一致する。沈む心のなかに、冷たい炎を燃え上がらせながら、私はボーンヤードへと歩を進めた。
マスター
戦争の前のロサンゼルスは、きっと世界一大きな都市だったに違いない。どこまでも果てしなく続くLAボーンヤード、そこではビルの骨組みが灼熱の太陽の下にさらされていた。風さえも、この死都には入り込んではこないのだ。
このボーンヤードでは、多くの敵と、少数の味方を得た。必要とあらば殺しもいとわず、私は追い求める真の敵の正体を探り出していった。
地下の奥深く――ミュータント軍の背後に潜む悪はそこにいた。暗く不気味なVaultの内部、人肉が壁をしたたり、断末魔の叫びがこだまするそこには、数多くの邪悪な生き物とミュータントがいた。
姿形の醜く歪んだ者たちの間を通りつつ、私はやつらのしもべの一人を殺し、そのローブを身につけた。敵の中に身を隠しながら、Vaultの下層へと進んでいく。奥へ進むごとに、その道程はよりぞっとするものとなっていった。人肉の量はますます増え、Vaultの壁とほとんど一体化していた。さらに恐ろしいことには、その人肉は生きており、そればかりか、私の存在にも気づいているふうだった。
しばらくして気がつくと、私の前にはこれ以上ないほどのおぞましい光景が広がっていた。このときの体験は、今となっても書き記す気にはなれない。だが、これだけは言っておこう。私が去るときには、あの化け物は死に、もはやミュータント軍のマスターではなくなっていた。
培養槽
私の役目はまだ終わってはいない。もう一つやるべきことが残っていた。マスターは、文字通り次々とミュータントを産み出しては、自らの軍に組み入れていた。人間、なかでもとりわけ放射線による遺伝子の損傷をほとんど受けていない人間が標的となり、拉致され、培養槽のもとへと連れていかれていた。犠牲者たちはそこでFEVと呼ばれるものにひたされ、巨大でグロテスクなミュータントへと姿を変えられていたのだ。
私はこの培養槽を見つけ出し、破壊しなければならなかった。さもなくば、マスターにとってかわり、ミュータント軍の増強を続ける者が現れるかもしれない。幸いにも、Brotherhoodの友人たちがいくつかの手がかりを持っており、目的を達する手助けをしてくれた。
培養槽のある基地へ侵入すると、さらに多くのミュータントとロボットに出くわした。しかし、私を止められるものはなかった。私には任務があった。使命があった。そして、その手には巨大な銃を持っていたのだ。ドッグミートが命を落としたのは、この場所だった。強力なフォースフィールドの犠牲となったのだ。あの犬のことは、今でも恋しく思う。
その日、私は培養槽を破壊した。それは同時に、ミュータント軍の破滅をも意味することだった。最後に聞いたところでは、やつらは散り散りとなり、荒野の中へと消えていったらしい。
Vault 13への帰還
Vault 13へ帰ると、そこで待っていたのは、英雄に対する歓待ではなかった。監督官は、巨大なVaultドアの外で私を出迎えると、私のVaultへの功績はいつまでも語り継がれるであろうこと、私――あるいは、変わってしまった私をもはや信用することはできないということを、率直に告げた。そして、君はVaultを救ってくれただの何だのと語ると、すぐに出ていってくれと言い放ったのだ。クソ野郎が。
そうして、私はVaultを去った。
それからの数週間はつらく厳しいものだった。Vaultの外で出会った数少ない本当の友人たちとは、みな旅の途中で死に別れた。そして今は、家族と思っていた人々から故郷を追い出され、二度と戻ってきてはならないと告げられた。私は叫び、そして泣いた。そして少しずつだが、監督官のしたことは正しかったのかもしれないと思い始めるようになった。私は変わってしまった。Vaultの外はまったく別の世界であり、そして私も、まったく別の人間になってしまっていたのだ。とはいえ、監督官がした仕打ちを、私は決して許すことはできない。
私は荒野をさまよい歩いた。しかし、故郷のVaultを外の世界から覆い隠している山脈からは、決して遠く離れることはしなかった。もしかしたら、無理やり押し入ってでも、あるいは泣きついてでも、帰りたいとそのときは思っていたのかもしれない。しかし幸いにも、そんなことにはならなかった。少人数のVault住民の一団を見つけたのだ。私の身に起きた話を聞いた彼らは、Vaultを去り、私の味方になろうと決心したのだ。彼らは外の世界のことはほとんど何も知らない。私の助けがなければ、死んでしまっていただろう。
私たちは共に北へ向かった。Vaultから離れた北へ、過去から遠く離れた北へ。私は彼らに、少しずつ自らの経験から学んだことを教えていった。私たちは共に、繁栄するための術を学んでいったのだ。
部族
時がたつとともに、私たち寄せ集めの集団は一つの部族となっていった。私はそのうちの一人と恋に落ち、他の部族の仲間たちと同様に、家族をもうけた。
私たちは、大きな崖を越えた場所に村をつくった。皆の努力の甲斐あって、そこは非常に安全な住まいとなった。私たちと同じようにVaultを出た人々を助けようと、故郷の方角へ斥候を送った時期もあったが、その頻度もだんだんと減っていった。今はもはや、誰も南へ行くことはない。その後、Vault 13やそれ以外のVaultはどうなっただろうと好奇心にかられることもしばしばあったが、再び探索に出る時間が得られることはついになかった。
私は皆へ、過酷な環境を生き抜き、強く成長するために必要な技術を教えた。食料を得るための狩猟や農業、住居を建造するための工学と科学、そして自らと村を守るための戦い方を。
愛する人と私は、共に村と部族を導いた。二人の助けによって、部族は力強く成長していった。だが、どんなことにも終わりはあるものだ。今や、息子や娘たちの世代が村の指導者となっている。彼らの導きのもと、部族はさらに強く成長していくことだろう、私はそう確信している。
我が愛する人がこの世を去ってからもう何年にもなる。しかし、パットのことを思わぬ日は一日とてない。子供たちを見るたび、その面影が目に浮かぶ。この回想録は、彼らやその子供たち、そして部族の皆への私からの遺産である。
以上、誰がなんと言おうと、これが私の“大切であろうと感じたこと”だ。
ーさすらい人(The Wanderer)
最終更新:2019年09月18日 21:54