©World Health Organization Regional Office for the Western Pacific 2005
www.wpro.who.int/publications/PUB_139789290613169.htm
This book calls for a bold transformation of health care and health systems in the 21st century.
Quality of care has become an increasingly important issue for the World Health Organization’s South-East Asia and Western Pacific Regions, and a policy framework for people-centred health care was endorsed by Member States in September 2007.
Specific policy reforms and interventions necessary to transform health care to a more holistic, people-centred approach will need to be determined by leaders and policy-makers at local and national levels in consultation with their constituencies and all interested stakeholders. This book, which is designed to bring members of the public into that debate, is a necessary first step in encouraging dialogue.
WHO South-East Asia and Western Pacific Bi-regional
Publication
2007,88 pages
ISBN13 9789290613169
Price: 14.66 US$/ 17.00 Swiss Fr.
Price for developing countries: 10.26 US$/ 11.90 Swiss Fr.
www.wpro.who.int/media_centre/press_releases/pr_20071126.htm
 Tokyo,
25 November 2007–The World Health Organization (WHO) today called for
a major overhaul of the way patients are treated in Asia’s health facilities,
saying medical care has become depersonalized and out of touch with the
public’s rights and needs.
Tokyo,
25 November 2007–The World Health Organization (WHO) today called for
a major overhaul of the way patients are treated in Asia’s health facilities,
saying medical care has become depersonalized and out of touch with the
public’s rights and needs.
Despite all the advances in medical science and technology in recent decades,
many people are still not satisfied with the quality of care they receive, said
Dr Shigeru Omi, WHO Regional Director for the Western Pacific and one of the
driving forces behind the call for change. “Health care continues to fall short
of people’s expectations. There is growing concern about quality, access and
responsiveness, as well as about safety.”
One of the problems, he said, is that the approach to healing has become too narrow, with the patient viewed as little more than a set of symptoms. This fails to take into account the fact that body and mind are linked, and that psychosomatic and social factors also affect health. What is needed, Dr Omi said, is a new approach where the many hidden factors associated with illness and hospitalization, such as anxiety, loneliness and cultural and social alienation, are also taken care of in a multidisciplinary manner. This care should be delivered in a spirit of partnership, where the dignity of the patient is fully respected and where individuals, families and communities are also part of a dialogue that responds to health needs in humane and holistic ways.
“Knowledge and technology are our great allies,” Dr Omi said, “but we must use them judiciously and holistically, within a people-friendly system that views members of the public as full and equal partners in preventing disease and enhancing health and well-being.”
Dr Omi acknowledged that the transition to a new approach would be neither quick nor easy, but he argued that much of Asia, as home to some of the world’s fastest-growing economies, was ready for the challenge. But the change would not necessarily be limited to the stronger economies. “What we are proposing is relevant to all forms of health systems at all stages of their development,” he said.
The costs would not be great, Dr Omi said. “We are talking mainly about inexpensive, strategic adjustments in the work environment, plus some retraining of healthcare staff and auxiliaries.” Dr Omi said the new approach would not divert resources away from the numerous health problems still facing Asia. “We will continue to tackle them with all our energy,” he said.
Dr Omi’s appeal was issued in a statement to mark an international symposium in Tokyo titled“People-centred Health Care: Reorienting Health Systems in the 21st Century”. Attended by some of the world’s most eminent experts on healthcare reform, the 25 November gathering was preceded by a national conference of the Japanese Society for Quality and Safety in Health Care. The three days of discussions were expected to produce a declaration that will act as a blueprint for people-centred care in Asia and the Pacific. The people-centred health care initiative is a joint project by WHO’s Western Pacific Region and South-East Asia Region.
Dr Omi’s call for reform was backed by Dr Samlee Plianbangchang, WHO Regional Director for South-East Asia, who said the overarching goal was recognition that good health is “a state of complete
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” For this to happen, he said, health systems also have to change. “Policymakers need to recognize that health cannot any longer be viewed in isolation,” Dr Samlee said. “Other factors, such as labour laws, the environment, education, and trade and finance, all impact on health. This should be taken into consideration when health systems are being designed.”
Dr Omi added: “We need to harmonize people and systems, within the health sector and between health and other sectors. Health must be seen in a broad sense, with all stakeholders involved. Multidisciplinary and multisectoral partnerships will be required more than ever to enable people to achieve optimal health and well-being.”
From the patient’s point of view, a more holistic, people-centred approach would bring many benefits, depending on the circumstances. They would include:
The benefits would also spin over to the hospital side in terms of the professional satisfaction doctors and other medical staff would feel from enhanced patient trust and respect.
Health systems are at a turning point, Dr Omi said. “The way things are done today does not respond to what the public wants. The need for a more balanced system is clear. What we have to do now is to take the action that will make that change happen.”
For more information, please contact Mr Peter Cordingley, spokesman for WHO in the Western Pacific Region, at mobile: +63 917 844 3688 or email[email protected].
リンダ・ミラン WHO西太平洋事務局健康地域開発部長
高久史麿 医療の質・安全学会理事長
ジョー・ハクネス 国際患者団体連合理事長
唐澤祥人 日本医師会会長
舛添要一 厚生労働大臣
尾身 茂 世界保健機関西太平洋地域事務局長
「正しい知識・情報を持ち、権限を付与された個人、家族、地域社会」
アンジェラ・コトラー 欧州ピッカー研究所所長
「有能で対応力ある医療従事者」
アレジャンドロ・ディゾン
フィリピン・セント・ルークス医療センター医療改善会議議長、外科局長
「効果的で効率的な医療組織・機関」
ロビン・ヤングストン
ワイタケレ病院 指導臨床医(クリニカル・リーダー)
ニュージーランド・指導臨床医協会 創設者/理事長
「『“人”が中心の医療』を支える医療システム」
金昌燁
大韓民国健康保険審査評価院院長
兼ソウル国立大学保健大学院保健政策・経営学研究室助教授
司会:
ディーン・シュウェイ WHO/WPRO保健サービス開発課長
ドン・マッセソン ニュージーランド保健省国際課長
13:30 イントロダクション
13:40 ベンデット・サラセノ WHO精神保健・薬物乱用部長
14:00 ジョー・ハクネス 国際患者団体連合理事長
14:20 ジェームス・キリングスワース
ジョイント・コミッション・インターナショナル専務理事
14:40 リアム・ドナルドソン卿
WHO患者安全世界共同行動プログラム議長
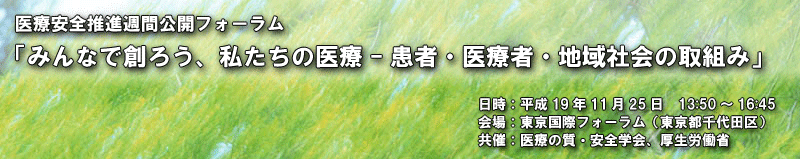
qsh.jp/2007/pci/forum/index.html

3.パネル討議ディスカッション
「パートナーシップに基づく新しい医療のかたちを創るために」司会 開原 成允(国際医療福祉大学大学院院長)
山内 桂子(医療の質・安全学会パートナーシップ・プログラム代表)
パネリスト
・デボラ・ホフマン
(ダナ・ファーバーがん研究所患者と家族のためのセンター)
・赤津 晴子(ピッツバーグ大学 内分泌代謝内科 准教授)
・藤井 裕志(下関市医療相談窓口(下関市立下関保健所)主任)
・伊藤 雅治((社)全国社会保険協会連合会理事長)
・大平 勝美(社会福祉法人はばたき福祉事業団理事長)
・「新しい医療のかたち」受賞団体代表

【感想】
・講演者、パネリストの口から、当たり前のように“患者中心の医療”というキーワードが出てきたところには驚いた。
・フジテレビのキャスター黒岩さんやその他の人が、“患者中心の医療”をはき違えていないか? という発言をされている点が
印象的であった。
今の医療-患者関係の影の部分をよく理解されておられると思う。
・医療に、サービス提供者と消費者(お客さん)という図式は、おかしい。
医療を受ける国民。その国民である、患者さんも意見を出し、皆で協力し、お互いの目線と密なコミュニケーションで
その人にとっての最善の道を見つめて歩む医療へと。という趣旨のディスカッションがあった。
People-Centred Health Care
舛添要一 厚生労働大臣
●分娩:救済制度
1st.:真相究明、
●人中心の医療の:
●Global Health:2015年に向けた
2008年中間評価
母子保健、HIV感染症、3つの目標
HIV,マラリア、TB
●母子保健:
3/1000、乳幼児、母体死亡率低下の成功→発展途上国へ
日本経済発展の基礎の一つ
●国際保健協力:
とても重要な日本の国際貢献
●G8:
来年、日本が主催国
●日本の医療の長期体制
国民中心の
30年先を見越した

〇
■テーマ1:「正しい知識・情報を持ち、権限を付与された個人、家族、地域社会」
アンジェラ・コトラー 欧州ピッカー研究所所長
貼り付け元 <http://www.qsh.jp/2007/pci/index.html>
Hospital
![]()
Prevention Health
![]()
![]()
Self care
2015年
洞爺湖 国際的行動指針
母子健康保険 母子手帳
感染症対策
インドネシアにおける、母子健康手帳の導入
パレスチナ
「みんなで創ろう、私たちの医療 ― 患者・医療者・地域社会の取組み」
「新しい医療のかたち」選考委員会
委員長 大熊由紀子
「新しい医療のかたち」賞授賞式
貼り付け元 <http://www.qsh.jp/2007/pci/forum/suisen.html>
貼り付け元 <http://www.qsh.jp/2007/pci/forum/suisen_kekka.html>
「みんなで創ろう、私たちの医療 ― 患者・医療者・地域社会の取組み」
岡本 浩二(厚生労働省大臣官房参事官)
貼り付け元 <http://qsh.jp/2007/pci/forum/index.html>
医療安全推進センター:各市町村に設置
上原 鳴夫(医療の質・安全学会第2回学術集会会長)
人が中心
変わるのを待っていたのではないか?→医療を変える。
2. 患者本位の医療をめざす患者・医療者・地域社会の取組み
司会 佐原 康之(厚生労働省医政局医療安全推進室室長)
丸木 一成(国際医療福祉大学大学院教授)
(1) 患者さんの取組み; 本田麻由美(読売新聞社記者)
(2) 医療機関の取り組み;岡本左和子
(元ジョンズホプキンス大学病院Patient Advocate)
(3) 地域社会の取組み;前村 聡(日本経済新聞社記者)
貼り付け元 <http://qsh.jp/2007/pci/forum/index.html>

画面の領域の取り込み日時: 2007/11/25 14:02
(1) 患者さんの取組み; 本田麻由美(読売新聞社記者)
癌患者→日本では、未承認→患者の会
迅速な承認
医療の適正配置
腫瘍内科医の育成
・患者の会→“病気とともに生活する”経験を蓄積した専門家としての医療への参画
患者の代表としての発言者 (“患者中心の医療”を履き違えた活動にならないよう対策が必要)
島根県における「がんサロン」の活動
・医療格差は知っていたが、患者の意識格差の大きさに驚いた。
(2)医療者・医療機関を中心とした取り組み部門
医療機関の取り組み;岡本左和子
(元ジョンズホプキンス大学病院Patient Advocate)
・患者中心の医療、医療側の取り組み
・医療安全Patient Safety:
部下や他業種が問題点を指摘することの安全性を保証する
・Bridge Gaps:Patient Advocate。不確実性の理解、フラストレーションを
爆発させる前に引き出して対応。
●新葛飾病院
・医療安全対策室、医師
対策職員に実際の医療被害者をあえて採用して活動;
豊田さん、読売新聞、「・・・」
3.地域社会の取り組み部門
・医療崩壊、10年前から医療者は認識していた。
もっと早い段階で、患者(国民)を巻き込んだ活動をしても
よかったのでは?
・NPO法人コミュニティケアリンク東京 の活動 東京・小平
発表者:河邉さん
・各部門が1つの施設内にある。亀田的。デイケア、入所施設。ホスピスケア。
・在宅死:85%。うち:70%がガン
・在宅診療のみならず、地域のコミュニティー。人の集まる場。
子育て支援、相談支援事業 → 子供の安全な遊び場、キッズボランティア
豊かな庭造り、展示、販売、バザー。
「パートナーシップに基づく新しい医療のかたちを創るために」
3.パネル討議ディスカッション
「パートナーシップに基づく新しい医療のかたちを創るために」
司会 開原 成允(国際医療福祉大学大学院院長)
山内 桂子(医療の質・安全学会パートナーシップ・プログラム代表)
パネリスト
・デボラ・ホフマン
(ダナ・ファーバーがん研究所患者と家族のためのセンター)
・赤津 晴子(ピッツバーグ大学 内分泌代謝内科 准教授)
・藤井 裕志(下関市医療相談窓口(下関市立下関保健所)主任)
・伊藤 雅治((社)全国社会保険協会連合会理事長)
・大平 勝美(社会福祉法人はばたき福祉事業団理事長)
・「新しい医療のかたち」受賞団体代表

貼り付け元 <http://qsh.jp/2007/pci/forum/index.html>
●デボラ・ホフマン
委員会
待ち時間
法改正の際に
異なる意見を吸い上げることができる
●赤津 晴子 さん
アテンションゲッター:車の事故;運転能力、事故対策
→医療における安全;臨床能力、事故対策
方略として:良質なチーム医療
・たとえが最良
・ピアレビュー
●藤井 裕志(下関市医療相談窓口(下関市立下関保健所)主任)
www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/browser
・医療安全支援センター について
・小さな疑問・悩み → 放置により、不信
・体に“負担の少ない”手術 → “簡単な”手術
・医療者側に、リスクの説明が少ない
・患者側にも自分のことをうまく表現できない。という問題が!
一見、わがままに見える。
・患者になる前に、日頃からもっと医療について考え、知る機会が必要
→ 出前講座、講演 10人程度いればOK
医療制度、コミュニケーション、などの項目が多い。
医療制度を知っていれば、トラブルを回避できた事例もある。
----------------------------------------------------------------------------
www.anzen-shien.jp/center/index.html
----------------------------------------------------------------------------
●伊藤 雅治((社)全国社会保険協会連合会理事長)
医師、厚生省
・ものを決めてゆくプロセスにいかに国民に参加してもらうかが重要になってきている
・大平 勝美(社会福祉法人はばたき福祉事業団理事長)
・
●パネルディスカッション:
・大平 勝美(社会福祉法人はばたき福祉事業団理事長)
・日本の患者会の問題点:持続性(-).裁判後解散。
それ以外で、あまり行政に働きかけるなど。変えようとする意識は少ない。
・地域の活動が、以外に行政に上がって来ない。患者会、
・自己実現の場を与えられると、もっとpowerを発揮できるのではないか?
・
医療の質・安全学会パートナーシップ・プログラムについて