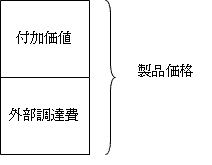交易条件が悪化する原因の1つは輸出価格の伸び悩みにあった。安い価格で輸出していることが所得流出をもたらしている。このことに対する方策として「高付加価値」の製品作りがよく言われる。付加価値という言葉はよく調べてみると奥深い意味を持っている。付加価値のイメージを図にした。
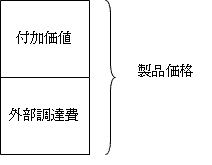
付加価値は製品価格から生産のために外部から調達した原材料などの費用を差し引いた金額である。付加価値の中身はいくつか種類がある。2つの方式を表にした。
| 日銀方式 |
財務省方式 |
| 人件費 |
役員報酬 |
|
従業員給料手当て |
|
福利費 |
| 経常利益 |
営業利益 |
| 租税公課 |
租税公課 |
| 金融費用 |
支払利息割引料 |
|
動産・不動産賃借料 |
| 減価償却費 |
|
付加価値は労働者、企業、資金提供者に分配されることが分かる。
「高い付加価値」というフレーズを聞くと企業に高い利潤をもたらすというようなイメージではないだろうか。しかし、定義を見るとそのような意味は無い。労働者に高い賃金を払って作った場合でも付加価値は高くなる。賃金を抑え込んで製造した製品は付加価値が低くなるのだ。
付加価値が高い=価格が高い製品を買ってくれるかはユーザーが決めることである。高い付加価値を求めて経営者が頑張っても結局は消費者次第である。
付加価値を高めるには①ユーザーの評価を高める、②技術開発、③調達コストを下げる、の3つがおもな手段である。どうも調達コストを下げることで企業が対処しているように思えてならない。
日本が貿易で利得を得るには高い値段でも買ってもらえる製品を作る必要がある。できれば労働者にまっとうな賃金を支払って価格が高くなっても売れる製品である。どういうものがあるだろう?
例えば、伝統工芸品である。南部鉄瓶は修業を積んだ人が手間暇をかけて製造していて人件費がかかっている。しかしながら海外では評判が良く高く売れるらしい。こうしたモノづくりの方向性もあることを指摘したい。
最終更新:2011年05月03日 15:09