ゲシュタルト心理学
言語説明
ゲシュタルトとは、「それ以上、バラバラにすると意味をなさない一塊りとして、扱うべきもの。」の事である。
以下の絵は点の集合である。
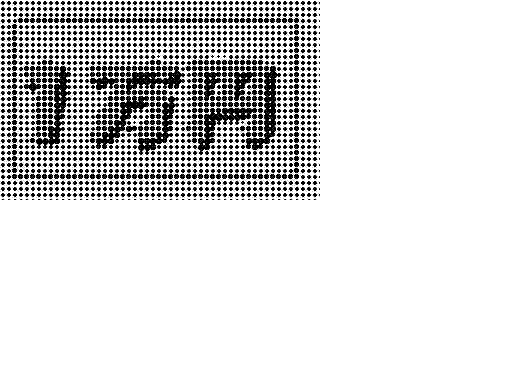
しかし、1つ1つの点には何の意味もない。
この点が、この絵のように集まって初めて、「1万円」という文字が浮かび上がる。
この絵では、点がいくつあるかが重要ではなく、点の集まり具合が重要なのである。
一つ一つの点には意味はないが、たくさんの点が集まった、その全体の形には意味があるのだ。
つまり、この絵は1つ1つの点に分けてしまうと意味をなさないのである。
このような集まりの事をドイツ語で「ゲシュタルト」と言う。
なぜ、ドイツ語なのかと言うと…
ゲシュタルト心理学は、
ヴントを中心とした要素主義・構成主義の心理学に対する反論として、20世紀初頭にドイツにて提起された経緯を持つからである。
しかし、精神分析学や
行動主義心理学に比べると、元々の心理学に近いとも言える。ユダヤ系の学者が多かった事などもあって、ナチスが台頭してきた時代に、同学派の主要な心理学者がアメリカに亡命した。その後、同学派の考え方は知覚心理学、社会心理学、
認知心理学などに受け継がれた。その自然科学的・実験主義的アプローチや、全体性の考察に力学の概念を取り入れた事など、現代の心理学に与えた影響は大きい。
ゲシュタルトの法則
ヴェルトハイマーはゲシュタルトを知覚するときの法則について考察し、以下に挙げるような法則を示した。これらは視知覚によるものだが、後の研究で記憶や学習、思考などにも当てはめられる事が判明している。
近接しているもの同士はひとまとまりになりやすい。例えば以下の図では、近接している2つの縦線がグループとして知覚される。離れた縦線同士はグループには成りにくい。空間的なものだけでなく、時間的にも近いものは、まとまって認識されやすい。
{ || || || }
いくつかの刺激がある時、同種のもの同士がひとまとまりになりやすい。以下の図では、黒い四角と白い四角のグループが交互に並んでいるように知覚される。黒白、白黒のグループが交互に並んでいるようには知覚されにくい。
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
互いに閉じあっているもの同士(閉じた領域)はひとまとまりになりやすい。例えば以下の図では、閉じた括弧同士がグループを成すように認識される。〕と〔 同士では、グループとして認識されにくい。
〕〔 〕〔 〕〔 〕〔
いくつかの曲線になり得る刺激がある時、よい曲線(なめらかな曲線)として連続しているものは1つとして見られる。例えば、「ベン図」(2つの円の一部分が重なった図。数学の
教科書などで、集合の解説によく用いられる)では、「円が2つある」と認識され、「欠けた円が2つと、ラグビーボールのような形が1つある」とは認識されにくい。 なお、「よい連続の要因」と似た法則として「よい形の要因」(よい形とは規則的な形を表す)もある。
ゲシュタルト崩壊
全体性を失って、個別のみを認識するようになる事。例えば、同じ漢字を長時間注視していると、その漢字がバラバラに見えたりする現象である。ただしこの際、静止網膜像のように、消失は起きないとされる。 また、「借」と言う字を見たときに起きやすいようである。
ゲシュタルト心理学の展開
ゲシュタルトの基本的な概念として、対象を全体として捉えるという事が言える。
例えば音楽もゲシュタルト性がある。なぜなら、音を1つ1つに分解してしまうと、音楽ではなくなってしまうからだ。この言葉の初まりは、オーストリアの心理学者エーレンフェルスという人である。このゲシュタルトという考え方は、ゲシュタルト心理学の基本的理念である。ゲシュタルト心理学流の言い方にすれば、「全体とは、部分の単純な総和(合計)以上のものである。」といった感じだろう。音楽は、個々の音を聞いた時よりも大きな効果を与える。
また、図形も中途半端な線や点であっても、丸や三角などそれを見た人間がパターンを補って理解する(逆に錯覚・誤解を引き起こす原因とも言える)。
例えば、下にトロフィーのような絵がある。

よく見ると、トロフィーの軸の部分では、二人の顔が向き合っているようにも見える。
心の中で、トロフィーをクローズアップすると、向かい合った顔はただの背景に見える。
向かい合った顔に注目すると、トロフィーは背景に見える。
何か一つものを意識すると(図と言う)、その他のものは背景(地と言う)と感じる性質がある。
人間が物事を知覚するときの性質である。
次の絵は、二つの図のうち横棒の長さは同じである。
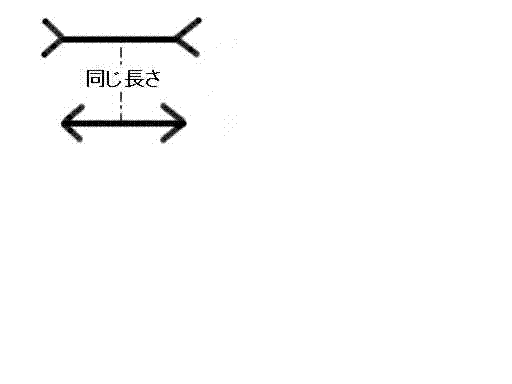
しかし、人間が知覚する横棒の長さは、くっついている矢印の影響を受ける。
たいていの人が上の方が長く見えると知覚するだろう。
横棒の長さを見ようとするとき、この図全体の影響を受けてしまう。
その部分は、どのような全体の中に組み込まれているかによって、見え方が変わってしまうのだ。
これも、人間が物事を知覚するときの性質である。
次の絵は、三角形ではないが、たいていの人が三角形だと感じるだろう。

辺がとぎれた部分を補ってとらえてしまうのだ。
つまり、人間が物事をとらえるとき、単純化と最小限の操作でおなじみの形に変化させてとらえるのである。
このような知覚の性質の研究から、記憶、思考の研究へと、人の心を探っていこうというのがゲシュタルト心理学である。
ゲシュタルト心理学は被験者の人間が感じることを整理分類して、人間の感覚構造を研究した。そのため、図形による印象などの研究が中心であった。
ゲシュタルト心理学の応用
近接や類同の原理が、ラジオボタンの配置等、コンピュータのユーザインタフェース設計へ応用される。またコンピュータによる画像解析(コンピュータビジョン)にも応用されている。
りえ
最終更新:2007年11月08日 01:30