M-Tea*3_2-星と空の話(二)山本一清
2010.8.7 第三巻 第二号
星と空の話(二)山本一清
三、太陽
四、日食と月食
五、水星
六、金星
七、火星
八、木星
imageプラグインエラー : ご指定のURLまたはファイルはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLまたはファイルを指定してください。
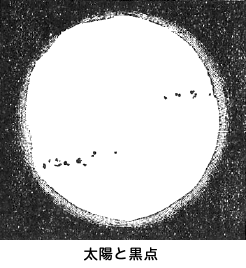
定価:200円 p.163 / *99 出版
付録:別冊ミルクティー*Wikipedia(47項目)p.313
※ DRM などというやぼったいものは使っておりません。
飛び出せ! 週刊ミルクティー*
太陽の黒点というものは誠におもしろいものです。黒点の一つ一つは、太陽の大きさにくらべると小さい点々のように見えますが、じつはみな、いずれもなかなか大きいものであって、(略)最も大きいのは地球の十倍以上のものがときどき現われます。そして同じ黒点を毎日見ていますと、毎日すこしずつ西の方へ流れていって、ついに太陽の西の端(はし)でかくれてしまいますが、二週間ばかりすると、こんどは東の端から現われてきます。こんなにして、黒点の位置が規則正しく変わるのは、太陽全体が、黒点を乗せたまま、自転しているからなのです。太陽は、こうして、約二十五日間に一回、自転をします。(略)
太陽の黒点からは、あらゆる気体の熱風とともに、いろいろなものを四方へ散らしますが、そのうちで最も強く地球に影響をあたえるものは電子が放射されることです。あらゆる電流の原因である電子が太陽黒点から放射されて、わが地球に達しますと、地球では、北極や南極付近に、美しいオーロラ(極光(きょっこう))が現われたり、「磁気嵐(じきあらし)」といって、磁石の針が狂い出して盛んに左右にふれたりします。また、この太陽黒点からやってくる電波や熱波や電子などのために、地球上では、気温や気圧の変動がおこったり、天気が狂ったりすることもあります。(略)
太陽の表面に、いつも同じ黒点が長い間見えているのではありません。一つ一つの黒点はずいぶん短命なものです。なかには一日か二日ぐらいで消えるのがありますし、普通のものは一、二週間ぐらいの寿命のものです。特に大きいものは二、三か月も、七、八か月も長く見えるのがありますけれど、一年以上長く見えるということはほとんどありません。
しかし、黒点は、一つのものがまったく消えない前に、他の黒点が二つも三つも現われてきたりして、ついには一時に三十も四十も、たくさんの黒点が同じ太陽面に見えることがあります。
こうした黒点の数は、毎年、毎日、まったく無茶苦茶というわけではありません。だいたいにおいて十一年ごとに増したり減ったりします。
 3_2.rm
3_2.rm
(朗読:RealMedia 形式 504KB、4'04'')
山本一清 やまもと いっせい
1889-1959(明治22.5.27-昭和34.1.16)
滋賀県出身の天文学者。水沢緯度観測所勤務・京大理学部助教授を経て1925年京大教授。その間1920年には日本で最も歴史の長い天文同好会・東亜天文学会(略称・OAA)を結成した。1928年京大花山天文台が設立されると台長に就任。1938年京大を退官し私設天文台の山本天文台を設立。生涯を通じてプロの天文学者とアマチュア天文家の橋渡しをし、天文学の広範な普及・発展に大きく貢献した。
底本
難字、求めよ
オルフ
オルファ
三沢 みさわ 先生。
大正十二年《じゆういちねん》 ?
ペライン
メロト
スリーパーズ日記
「圓(まる)く」を「丸(まる)く」に、
「コペルニク」を「コペルニクス」に、
「スキヤパレリ、スキヤパレーリ」を「スキャパレーリ」に、
「カナーリ」を「カナール」に、
「週期」を「周期」に、
「牛」を「おうし」に、
「五分時間」を「五分間」に、
「あだかも」を「あたかも」に置きかえた。
ピケリングはウィリアム・ピッカリングか。そのままとした。時系の表記は、1930(昭和5)年2月の出版当時のままとした。表組みの罫線は省略した。
八月一日(日)天気晴れ。山形の最高気温、三十五度。いずみやでずんだアイスのどら焼きを2つ購入。大イチョウの下で食事。山寺、峯の浦本院跡発掘調査、現地説明会に参加。主催と報道を含めて約八〇名。七〇代が多く、女性が五名、小学生が二名ほど。
本院跡は標高三一一m、バレーボールコート半分ぐらい。周囲を杉林がかこみ湿気がこもる。以前はタバコ畑だったという。修験場跡と同様の傾斜がある。調査会長の川崎利夫氏は、(1) 北畠顕家の息「円そく」と「円ゆう院」にちなむ遺跡、(2) 最上と伊達の争いの際、伊達側についた山寺が最上家臣の天童勢から攻撃されたときの跡、の二つの可能性を示唆。周囲の遺物に記されるのは北朝の年号ばかり。全体から炭化物が出土。
副会長の新関氏によれば、礎石のような角の取れた平たい河原石は山寺周辺にはない。どこから運んだものか。現場の上に石切場があるともいう。出土した人骨を見せてもらうのを忘れた。新関さんに赤文殊で採取した岩石サンプルを見てもらったところ「鉄……」との速答。「周囲から有毒ガスが出るという」とも。そして、立板に水のごとき赤山明神の解説を聞く。
川崎さんに、佐藤栄太氏のことをたずねてみる。佐藤さんとの思い出を語ってもらう機会を作ってもらえないか、お願いしてみる。「はい」という快い返事。昼すぎ、山寺をあとにする。
旧暦七月六日、山寺夜行念仏。翌七日、磐司祭、聖霊菩提獅子踊り。
2010.8.10:公開
2010.8.11:更新
目くそ鼻くそ/ハゲダガ。PoorBook G3'99
転載・移植・印刷は自由です。
カウンタ: -
最終更新:2010年08月11日 00:38

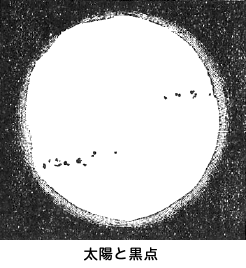
 3_2.rm
3_2.rm