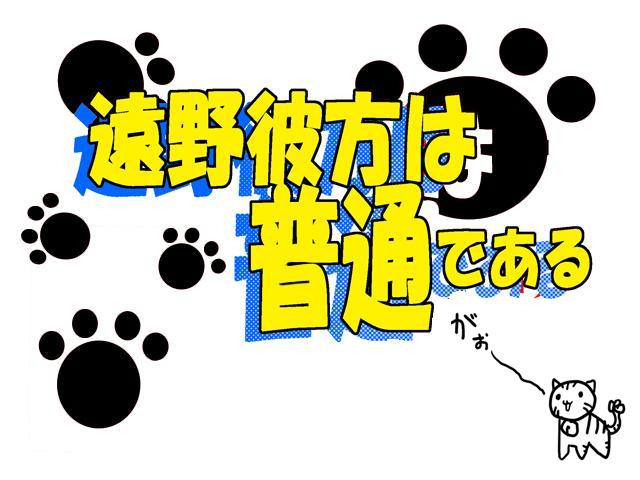「【遠野彼方は普通である その2】」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
【遠野彼方は普通である その2】 - (2009/07/21 (火) 20:27:18) の編集履歴(バックアップ)
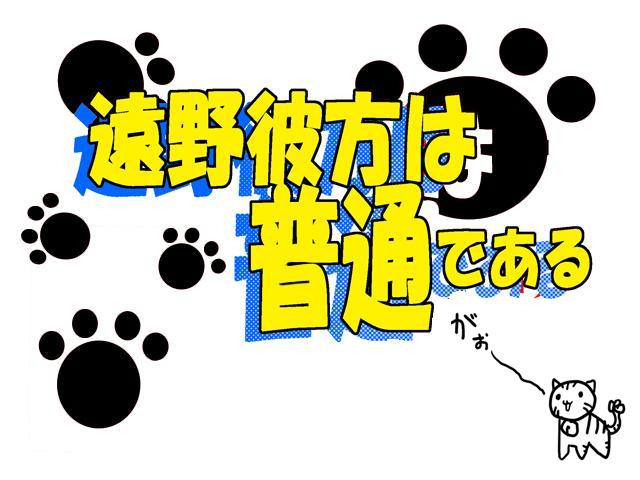
【遠野彼方は普通である】 その2
遠野彼方をひとことで言い表すならば「普通」であろう。
容姿をはじめ勉強もスポーツも平均よりややまし、ましてや異能も持たない彼はごく普通の「どこにでもいる学生」に過ぎない。
個性といえば、物怖じしない性格からやたらと社交的で顔が広いというところだろうか。
そんな彼方の趣味というと『猫好き』というものがある。
遠野彼方は、静寂に支配されつつある放課後の校舎裏を歩いていた。
自然に垂らした前髪。長く伸ばした後ろ髪は、地味な茶色のゴムで結わえている。
縁のない丸眼鏡をかけた相貌は、涼やかに整っていた。
細く切れ上がった眼は狐のそれを連想させ、かといってそれが狡猾そうな見た目に繋がらないのは、その口元に浮かんでいる微笑のせいである。
別に、夕暮れに侵食されつつある学校に退廃的で皮肉なおかしみを感じているわけでもなく、思い出し笑いをしているわけでもない。
それが彼方にとってのごく自然な表情だった。ぽややんとかほにゃららなどと呼ばれている所以である。
すらりと背筋を伸ばし、手には買い物袋を提げ、気取りのない足取りでとある場所に向かっている。
「うん、ちょうどいい時間かな」
彼方は掌を額の上にかざして夕暮れの陽をよけ、もともと細い眼をさらに糸のように細めた。
目的地は猫場ある。
猫場――猫の集会所や餌場の通称である。猫好きの者ならばその情報はぜひとも押さえておきたいところだ。
♪夜を守れ、我らの誇りを守れ、そして手にするのは陽だまりの昼寝の時間
彼方が口ずさむのは古い歌。
まだ幼かった頃に放映されていたテレビアニメの曲で、闇と戦う猫の戦士達の歌である。
夜は猫が守っている──そんな歌いだしから始まり、猫達が夜を守るために怖い闇と戦っているという内容のもので、当時は流行歌として子供達に好評であった。
♪夜を守れ、それが我らの誇り。それがあれば他には何もいらない、メザシがあるのなら貰うけど~とお気に入りのフレーズを歌い続けて缶の蓋を開ける。
パキュっという音ともに流れ出す匂いに誘われてか、周囲の草むらから猫たちが姿を現す。猫缶だけでなく歌に惹かれてきたのなら嬉しいんだけどね、と微笑みながら缶の中身を紙皿の上にあけていく。
猫達が奇麗に食べられるように、また猫場を汚したりしないようにゴミはちゃんと持ち帰る。彼方はマナーを守るのだ。
4、5、6匹と次々と寄ってくる猫達。どれもまだ幼い。
この双葉区である人工島にどうして野良猫がたくさん住み着くようになったのかは諸説ある。
島の建設に関わっていた人間が持ち込んだ猫が逃げ出した。
飽和状態の都市部を離れ、新天地を目指して双葉大橋を集団で渡って来た。
さらには猫は魂源力を持っており、この地に封じられた何かが出てこないように見張り役として連れてこられた、などというものまである。
ともあれ理由はどうであれ、学園の敷地はおろか島内双葉区のどこにでも猫達の姿は見られる。
通常は野良猫への餌付けは問題になるのだが、双葉区では猫といえば地域猫として住民有志の手によって食事を与えられるのが当たり前のことであった。
この猫場にいる猫達にしてみれば、毎日ではないとはいえ猫缶を手に現れる彼方のことを「ハムの人」ならぬ「猫缶の人」として認識しているのだろう、恐れることなく寄ってくる。
皿から少し離れて待つ。いきなり手を伸ばしたりはしない。まずは彼らの食事が済むのを待つのである。
遠野彼方は普通に猫が好きである。
猫やそれに近い姿をしたものが好きであり、それらを見れば撫でてみたいと思う。
醒徒会長藤神門御鈴の式神、「白虎」をダッコしてぎゅーした強者の一人として一部猫好きから羨望と賞賛の目を向けられているが、本人曰く普通に触らせてもらっただけである。
猫に触れるにはそれなりのマナーがあるのだ。
皿にあけられた猫缶に群がる猫達をぽややんと見やる彼方。
食事を終えた猫に指先を伸ばせば気まぐれに舐めてくるものもいる。ここですぐさまナデナデしたりするのは下手なやり方だ。猫と接する際には細心の注意を払わねばならない。
指だけでなく手の甲まで舐め上げてくる。これは猫にとって仲間への毛づくろいを意味する。それだけ心を開いてくれたというわけだ。
ここでようやく彼方は猫の身体に手を触れる。まずは首筋。優しくなでる。時折強く、けれども決して嫌がられない程度の刺激。熟練の娼婦の性技のようになまめかしい愛撫。
ぐるぐると喉を鳴らしはじめる猫達に囲まれ、彼方は至福の時を過ごしていた。
がさり、と背後の草むらがなる。それだけであったならば他の猫がやってきたと思ったであろう。
だが続けて聞こえてきたのは耳障りな金属音であった。
ギャリギャリギャリ
まるで噛み合ない歯車のような音。
「――!?」
それとともに姿を現したのは、異形の存在であった。
「なに、これ」
遠野彼方は普通である。
異能を持っているわけでもなければ、代々受け継がれてきた古武術の使い手でもない。
危険と思われる存在と出会った際、自身の身を守ることすらおぼつかないただの少年だ。
できることといえばせいぜい悲鳴をあげて逃げ出すことだろう。
だから彼方はそうする筈だった。──一人であったならば。
まだ幼い猫達が威嚇の声をあげる。だがその爪を異形につき立てることはとうてい叶うまい。
恐怖で萎えそうになる身体を叱咤するために謡う。
「夜を守れ、それが我らの誇り」
左手で足下の猫達を抱え上げ、右手を腰のホルダーに伸ばす。
そこにあるのは怪物を撃ち倒す拳銃でもなく、悪を断ち切る剣でもない。
ただの携帯電話だ。
遠野彼方は普通である。
だから、普通なりのやり方がある。それは信じることである。
逢洲等華は放課後の警邏中であった。
職務という観点では単独で行うものではないし、その立場からすれば部下に任せておくべき仕事だろう。
だが彼女の趣向を知っているものならば理由は分かる。
言ってしまえば趣味と実益。
警邏の理由は表向きには治安の維持。そしてもう一つの理由は学園内に点在する猫場の確認。いわゆる猫参りである。
等華は誰もが恐れる風紀委員の委員長で、凛とした佇まいの美人である。すれ違う誰もが背筋を伸ばしてその姿を目で追う。そんな彼女ではあったが。
風紀委員長。逢洲等華──彼女もまた、猫好きの一人であった。
今日も一通り巡回をし、寄るべき所に寄り、喧嘩の仲裁をし、変態を叩きのめした。後は好きなだけ猫達に会ってから醒徒会室に戻るだけである。
残念ながら好きな時に好きな場所へ行ける立場ではないが、彼女の異能は効率良く猫達がいる猫場を見つけることができる。
さて、一番近くの猫場はどうだろう、と異能を発動させようとした所、携帯からの発信音がそれを止めた。
発信者──遠野彼方
猫好き仲間の一人だ。
友人というほど親しいわけではないが、何度か猫参りの際に会ったことがあり、気が付けば携帯の番号を交換していた。同級生というが広大な学園では普段顔を見る事も無い。ああそういえば先日は何故か醒徒会室で白虎を抱き締めていたな、と思い出す。
「どうした?」
『逢洲さん!? 猫場に変なのが! うわっ!』
「おい!」
しかし答えはなく、ギャリギャリギャリという耳障りな金属音とともに通話は途切れた。
「――!!」
反応は早い。
彼方の携帯の位置情報を確認。これは醒徒会権限の強制閲覧をせずとも公開されていた。──近い。ふたつ向こうの校舎裏。
躊躇なく駆け出した。本来ならば付近の委員に連絡をいれてからがセオリーなのだが、今は一瞬でも時間が惜しい。
「ラルヴァか」
ここ最近、学園敷地内にすらラルヴァの出現が幾つも報告されている。近年出現するラルヴァは人間の生息域に密接に関わっているのではないかという報告がある。
次代の異能者育成機関の総本山、双葉学園。だが、その日常のすぐ脇には深い闇があった。
疾く駆ける。
等華の異能は身体強化ではない。”確定予測”という近知能力である。しかしその走る速度は常人を超えていた。
学園では割と良く見かける剣術使い。だがそれも皆伝級ともなればその体捌きも並ではない。またその異能を用いて進路上の障害物の位置を先読みして回避することによって僅かな時間で目的地に到達する。
ギャリギャリギャリ!
異形の叫び声。まるで噛み合ない歯車のような音。
等華の目に映るのは複数の猫を抱きかかえた少年と、それを押し倒しのしかかろうとする異形の姿。
体長は2メートル近くはあるだろう。
四肢を持つところから獣のように見える。
だがその身体は鋼で出来ていた。
金属質の光沢をもつ骨格。それにまとわりつくチューブからはしゅうしゅうと何かが漏れる音がきこえ、不気味な痙攣にも似たきごちない動きで前脚らしきものを彼方に突き出している。
その先は指もなければ爪もない。しかしハンマーのように丸みをおび重厚そうなそれはたやすく人間の頭すら粉砕するであろう。
尾と思わしき物体はこれまた複数のワイヤーが絡まり合ったようにグネグネと蠢動しており生理的な嫌悪感を抱かせる。
何よりも、その出鱈目な機械でできたかのような身体にボロキレのような表皮がまとわり付いていることが恐ろしい。まるで生きた動物から皮を剥ぎ取り身に着けているようなおぞましさがあった。
「遠野、動くな!!」
数メートルもの距離を一足飛びで詰め、腰に差した二振りの刀を抜き放つ。
一閃。
異形の前脚が飛ぶ。
異形の首が飛ぶ。
「月陰」「黒陽」二振り一対の刀による砕魔滅殺の一撃。
彼方の目には黒い旋風が駆け抜けたとしか見えなかった。
そして次の一撃は閃光のように映る。
すれ違いざまの一撃から反転。長い黒髪とスカートの裾をまるで翼のようにひるがえし、その回転力をそのままに異形に刃を叩き付ける。
カンっと乾いた音がして、異形の胴体が十時に分断されて地に伏した。
「ふっ」
僅かな残心の後に刀を一振りして鞘に戻す。血糊はおろか歯こぼれひとつない。業物であり、またそれを扱う等華の技のなせることである。
「大丈夫か?」
等華が声をかける。
尻餅をついた彼方は暫く呆然としていたが腕の中の猫達があげる声で我にかえる。
「え、あ、うん大丈夫。ありがとう」
緩めた腕から猫達が飛び降り草むらに逃げ出していく。
「怪我はないか?」
しょうがないか驚かせちゃったしな、と寂しくはあるが大事なかったことを素直に喜ぶべきだろう。
「うん、皆無事だよ」
彼方のその答えに等華が苦笑を浮かべる。
「猫達もそうだがキミ自身はどうなのだ? 立てるか?」
と差し出された手をとり彼方は立ち上がる。幸い腰が抜けたという醜態は晒さずに済んだ。
「ん、こっちも大丈夫。携帯は……と、こっちも壊れてないみたい」
異形の獣に飛び掛られた際に取り落としてしまったが、せいぜい表面に擦り傷が付いた程度だ。
「それよりもありがとう。まさかこんなに早く助けがくるとは思わなかったよ」
「近くに来ていたからな。だが私に連絡する前に逃げるという手もあったはずだぞ?」
異能をもたない一般生徒がラルヴァと対峙して無事であったのは僥倖だ。今回はたまたま良い結果となったが下手に近寄らず、手を出さずに逃げろと学園側は指導している。
「いやぁ、僕だけなら逃げてたよ、うん」
と草むらに視線を向ける。
逃げ出したはずの猫達が顔を覗かせてこちらを伺っていた。
「なるほど……遠野は凄いな」
「え? なんで?」
凄いといえば颯爽と現れてラルヴァを倒した等華の方だろう。先ほど握った手は思ったより少女らしく細く柔らかかったが、その手によって放たれる技は一流の剣士のものだ。
「自分より強いモノを前にして、自分より弱いものを守ろうとする。なかなかできることではない」
「そうかなぁ? 普通だと思うよ」
等華にしてみればベタ褒めと言っていい程の評価ではあったが、彼方はその賞賛を受けることなく放り投げた。
「僕は弱いけど、強い人が助けを呼べば来てくれるって信じてたからね。だからだよ」
「……キミは、異能使いが怖くないのか?」
驚くほどのほほんとしている彼方につい疑問を投げかける。異能者ではない一般生徒にしてみればラルヴァも異能者もある意味等しく恐怖の対象でもある筈だ。
風紀委員として人前で異能を使うことが多い等華にとって、感謝よりも畏れを抱かれる方が多いと言える。差し伸ばした手に怯えられることも何度かあった。しかし。
「なんで?」
彼方は首を傾げる。
遠野彼方は普通である。
そして、異能に対する態度も普通であった。
「うーん、凄いとか便利そうだなぁとは思うけどね」
それって足が早いとか料理が得意とかとあまり変わらないと思うんだよね、と彼方は軽く言葉をおく。
「キミは、変わっているな」
嘘をついているのでも等華に気を遣っているのでもない。素で言っていると分かる。
「えー、普通だよ。皆そんな感じだと思うよ?」
「……そうか、普通か。ならば窮地にあれば呼ぶがいい。私達はそのためにいるのだから」
「うん、頼りにしてる。ありがとう」
風紀委員は必要な存在ではあってもやはりどこか疎まれるものだ。そのような素直な信頼を向けられるのは等華にとっても悪い気分ではない。
「ああほら、皆もありがとうだって」
見やれば猫達が草むらから出てきており、二人の足元に擦り寄ってきていた。
等華を見上げてにゃーんと鳴く猫達が、揃って礼を言っているようで思わず赤面する。どんなラルヴァの攻撃よりも強烈な一撃であった。
「う、うむ。無事でなによりだ」
強靭な意思でもって視線を外す。このままでは風紀委員の威厳を投げ捨てて猫達をモフりかねない。
「礼はいい、当然のことをしたまでだ」
「それが我らの誇り。それがあれば他には何もいらない?」
と彼方がおどけて聞く。
「──メザシがあるのなら貰うけどな」
薄い胸をそらし、不敵ともいえる笑みを浮かべ、等華は答えた。
幼少時から剣術家として厳しい環境で育てられた等華が知る数少ない娯楽のなかのひとつ。忘れもしない闇と戦う猫の戦士達の歌。
そうだ、私は戦うだろう。夜を守る猫の戦士達とともに。
『夜を守れ、我らの誇りを守れ、そして手にするのは陽だまりの昼寝の時間』
彼方と等華、二人で微笑んで謡う。
猫達がそれに唱和するように鳴いた。
「でもどうしてここにラルヴァが現れたんだろう?」
同じ猫好きの同士──猫ダチの前だからと、はばかるのをやめて猫達を撫でる等華に、彼方は疑問をぶつけた。
「うむ。そうだな。猫場にラルヴァが出現するというのは問題だな」
ラルヴァの屍骸を見やる。死ぬと消滅するタイプではないようで、その金属製の身体はその場に残っている。
「遠野──」
「なに?」
「この件、私に預けてくれないか」
ラルヴァの屍骸、いや残骸の中にあるものを発見した等華は風紀委員としての顔でそう言った。
異能は戦闘能力としての発現にとどまらず、様々なかたちで顕現する。知能指数や記憶力、発想力などでもそうだ。そんな能力者達はその異能をもって優れた科学技術や道具を生み出すことができる。
その中でも特に超科学と呼ばれる類いのトンデモ発明を行う能力者達が集う部活動がある。
ロボット研究会──通称ロボ研。
古来より日本人はヒトガタに並々ならぬ思い入れを持ち、それを作り出すことに心血を注いできた。ヒトガタには魂が宿り易いというのがその理由のひとつであり、神々が身近な存在であったこの国ではそれを禁忌として遠ざけることなく取り組んで来た。
また、某漫画の神様達の手により、日本人のDNAには「ロボットは強くて、いい奴で、人間の友達」という情報が書き込まれたことから科学によるヒトガタを生み出すという情熱は信仰ともいえるほどにまで昇華されていた。
そしてそれから派生したロボットに対する情熱は、ここ双葉学園でも当然のように燃え盛っている。
さらにラルヴァと戦う異能者を助ける為にと、その技術開発への支援も続けられており、上は政府から資金が投入されるほど、下は個人の趣味のレベルとさまざまな規模でロボットに関する研究開発が行われていた。
そういった人間の集団がロボ研と呼ばれる組織である。
さらに人数や規模が増えるにつれ分裂と増殖を繰り返し、今では未登録のものも含めると数10ものロボ研が存在していた。
逢洲等華が部下数名を連れて訪れたのは、そのロボ研の中でも最下層の規模の部室であった。
ロボット研究会第43部室。
43というのはそれだけ下位という意味だ。一応同好会としての規定人数に達している為、プレハブ棟の一室が提供されていた。
──結論から述べると、彼方が遭遇し、等華が倒した異形はラルヴァではなかった。
ロボット研究会43部が作り出したロボット、というのが異形の正体であった。
ロボ研に限らず、トンデモ科学系によって生み出される産物はしばしば事件を引き起こすので、その作品には製造元を明記する事が義務づけられている。
等華が異形の残骸の中に見付け出したものはこの43部の名が刻まれたプレートであった。
部員わずか5名。ガラクタで埋まった狭い部室で事情聴取は行われた。
曰く。ロボットは部で開発していた動物型のもので、自律稼働の実験中に見失ったものである。
曰く。人を襲ったというのは誤解で、あれは人間にじゃれつくようにプログラムされていた。
曰く。見た目がアレなのは低予算で外装である着ぐるみに金をかけられなかったから。
言い分はもっともである。
今回の被害者と言えば、驚いて尻餅をついた彼方ぐらいのもので怪我人というほどでもない。
口頭による厳重注意。それが適当な落としどころであろう。
だが、風紀委員は伊達ではない。
部員達の態度が不審なのは明らかであることから有無を言わさず家宅捜索が行われ、とある計画書が発見される。
『動物型ロボットによる光学記録装置の有効活用研究』
ご大層なタイトルではあるが、その下に手書きで『ロボ猫にカメラ搭載してウハウハ計画』などと書かれていては台無しである。
まあ大雑把に言ってしまえば猫型ロボットにカメラを仕込んで盗撮しようという身も蓋もない計画である。
可愛い猫をだっこしてぎゅーしたい女性は世に溢れている。また、スカートを履いた女性の足下から猫の視点で見上げればどうなるかは分かるだろう。
だがしかし、なによりも驚くべきは、あの異形の鋼でできた獣が『猫』であったということだ。
そのサイズや見た目から察するに、技術力もセンスも到底実用に耐えるものではなく、完成したとしても計画が成功することはなかったであろう。もっともその程度だからこそこのプレハブ棟にいるのだろうが。
そしてその日。
ロボ研の第43部室に粛清の嵐が吹き荒れた。
この事件の顛末についての風紀委員長のコメント。
『あんなものは断じて猫ではない』
逢洲等華は放課後の警邏中であった。
すらりとした痩躯に凛とした空気を纏い、見る者の背をしゃんと伸ばさせる様はいつもの通り。
学園では毎日大小さまざまなトラブルが起き、なかなか気の休まる時もないが等華はそれに不満はない。
己がすべきこと、出来ることが分かっているからだ。
颯爽と歩く等華の携帯に、メールの着信を知らせる音が流れる。
「遠野からか」
等華は先日の事件の後、彼方を経由して猫好きのコミュニティの輪に参加するようになっていた。猫ダチの輪というやつだ。
──三浦さんちのタマちゃんが猫場に子連れデビューしました。場所はアスカ公園の南側猫場
簡潔な文と親子連れの猫の画像。
残念ながら好きな時に好きな場所へ行ける立場ではないが、異能を使わずともこうして新たな猫場を見つけることができるようになった。
今日は無理かもしれないが、明日にでも時間を作って行ってみるとしよう。
口元に浮かんだ微かな笑みを消し、携帯をしまって目の前の人だかりと喧噪に向かって声をあげる。
「風紀委員だ! 道をあけろ!」
逢洲等華は風紀委員である。
時には人から疎まれ、畏れられることもある。それでも等華は今日も征く。
猫が夜を守るなら、私は猫とともにこの学園を守る。それが私の誇り。私の普通だ。
遠野彼方をひとことで言い表すならば「普通」であろう。
容姿をはじめ勉強もスポーツも平均よりややまし、ましてや異能も持たない彼はごく普通の「どこにでもいる学生」に過ぎない。
個性といえば、物怖じしない性格からやたらと社交的で顔が広いというところだろうか。
そんな彼方は今日もあちらこちらとフラフラ歩く。
行く先々で声をかけ、またかけられてはちょっとした頼みを引き受けたり、また頼み込んだりをする。
それが彼方の日常。
猫ダチにメールを送った後に猫場を離れ、公園脇の商店街へと足を踏み入れてみれば、泣き出しそうな初等部の少年を前に考え込む顔見知りの店主の姿。しかも少年の背後に立つのは巨大な鎧武者ときた。
「どうしました?」
「ああ遠野くん、いいところに。実はだな……」
遠野彼方は普通である。
異能を持っているわけでもなければ、代々受け継がれてきた古武術の使い手でもない。
危険な目に遭っている誰かの前に颯爽と現れて敵を倒すことはできない。
また、難病で苦しんでいる人を治すこともできなければ、莫大な医療費を立て替えることもできない。
遠野彼方は普通である。
だから、普通なりのやり方がある。それは信じることである。
自分には助けることは出来ずとも、助ける事が出来る人が居ることを知っている。彼らは困っている人がいれば迷わず手を貸してくれるだろう。
「どうしたのかな?」
少年に向かって身をかがめる。
彼方は信じている。
♪夜を守れ、我らの誇りを守れ、そして手にするのは陽だまりの昼寝の時間
夜は猫が守っているし、猫とともに戦う人もいる。
遠野彼方は普通である。
痛いこと、悲しいことは好きじゃない。だからそれをなくせるのならば。
誰かに声をかけることでそれをなくせるのならば。
「何か僕に出来ることはある? まあ僕には無理でもなんとかなるよ」
そう言って少年に微笑みかける。
それが遠野彼方の日常。「普通」であった。
おわり
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (がおー白虎.JPG)
フェードアウト
画面隅でビャコにゃんががおーと叫ぶ