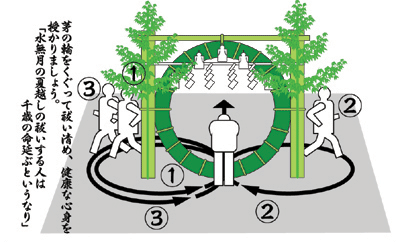太陽社長@岡本大助の送る『オヤシロWiki』へようこそ。
このWikiでは神社や神道にまつわる事を随時更新してゆきます。
茅の輪くぐり
茅の輪くぐり(ちのわくぐり)とは、毎年6月に行われる神道の行事である。
「茅輪神事」、「輪超祭」とも呼ばれる。
茅の輪とは「茅(ちがや、かや)」を束ねてつくった大きな輪っかのこと。
起源
日本神話において、ヤマタノオロチを倒した素盞鳴尊(すさのおのみこと)が南海で旅をしている途中、蘇民将来(そみんしょうらい)、巨旦将来 (こたんしょうらい)という兄弟のところで宿を求めた。
弟の巨旦将来は裕福であるにも関わらず宿泊を拒んだのに対し、兄の蘇民将来は貧しいながらも喜んで厚くもてなした。
その数年後、再び蘇民将来のもとを訪ねた素盞鳴尊は「もし悪い病気が流行ることがあった時には、茅で輪を作り腰につければ病気にかからない」と教えた。
そして疫病が流行したときに巨旦将来の家族は病に倒れましたが、蘇民将来とその家族は茅の輪で助かった。
この言い伝えから「蘇民将来」と書いた紙を門にはっておくと災いを免れるという信仰が生まれた。
当初は腰に付けられる程度の大きさだった茅の輪は、江戸時代初期頃から大きくなり、茅の輪をくぐって罪や災いと取り除くという神事になったという。
茅の輪のくぐり方
(1) 茅の輪の前に立って軽く礼をする。
左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻る。
(2) 茅の輪の前で軽く礼をする。
右足からまたいで輪をくぐり、右回りに回って元の位置に戻る。
(3) 茅の輪の前で軽く礼をする。
左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻る。
(4)茅の輪の前で軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、
ご神前まで進み、二拝二拍手一拝の作法でお詣りする。
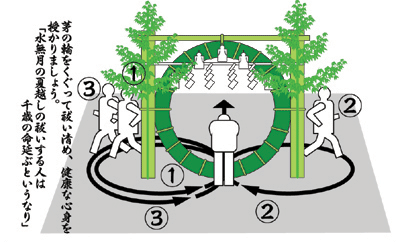
神社によっては、6月と12月の年2回茅の輪くぐりを行うところもある。
最終更新:2017年04月04日 15:42