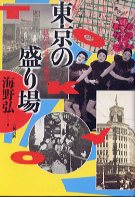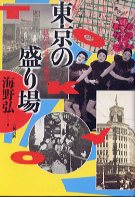
書名
東京の盛り場 江戸からモダン都市へ
書誌情報
- 出版社(叢書・シリーズ名)
- 発行年月日
- 版型 造本データ ページ数
- 定価
- 装丁
異版
目次
- Ⅰ 東京の盛り場
- Ⅱ 東京の感性
- 新東京百景を歩く 66
- 世界と東京、一九二〇年代 92
- 都市のアンダーワールド 105
- ジャズとモダン都市 114
- 昭和三年のモダン東京 125
- 東京のエロス 129
- Ⅲ 都市の装置
- 帝国ホテルの時代 136
- 東京のデパートの歴史 151
- モダン銀座と広告 163
- 遊園都市論への序章 167
- Ⅳ モダン都市と文学
- 谷崎潤一郎 178
- 梶井基次郎 190
- 広津和郎 199
- 秦 豊吉――ベルリンから東京へ 204
- Ⅴ 私の東京地図
- 東京一九二〇―八〇紀行――浅草・神田・銀座 228
- 東京舟行――隅田川・神田川・日本橋川 238
- 馬込文学散歩 242
- マイ・トレイル――渋谷 249
- 親しい街――新宿・銀座 252
- 私の好きな美術館――渋谷・目黒 254
- あとがき 260
- 初出一覧 264
あとがきより
この本は、『
モダン都市東京――日本の一九二〇年代』(中央公論社 一九三八)、『
東京風景史の人々』(中央公論社 一九八八)につづく、私の三冊目の東京論である。内容は、書下しの「東京の盛り場」を中心にして五章に分けられている。
盛り場の背後には、つねに都市のアンダーワールドがひそみ、それがまた、私たちの想像力をかきたてる。盛り場と裏街は都市における最も無駄ではかない部分だ。そこは、機能や生産からはずれた消費だけが、幻想をつくりだす地区なのだ。
第二章「東京の感性」では、モダン東京の盛り場にタイム・トラベルして、そのいくつかのシーンを浮かび上がらせようとしている。
第三章「都市の装置」では、モダン都市に不可欠ないくつかの装置、すなわちホテル、百貨店、博覧会、遊園地といったものについて触れている。
第四章「都市と文学」では、谷崎潤一郎、梶井基次郎、広津和郎、秦豊吉の文学と都市の関係をあつかっている。
第五章「私の東京地図」は、文学と都市論の境界として、紀行文を考えている。
あらためて全体をふりかえると、この本は、私の東京論の新しい地点を示している。これまで〈一九二〇年代〉を核としてきた私は、一方で、そこから時代をさかのぼり、〈江戸〉に入っていこうとしているとともに、もう一方で、時代を下り、現代に近づこうとしている。これから、〈五〇年代〉、〈現代〉の東京を書かなければならない。
一九九一年に、私は歴史小説『
慶長茶湯秘聞』(角川書店)と、都市小説集『
リヨンの夜』(河出書房新社)を出した。私にとって未知のフィクションの世界を試みようとしている年に『東京の盛り場』を出すことは決して無縁ではないだろう。
最後に、ここに収めた文章を書く機会を与えてくれた方々に厚く感謝する。まとめるにあたっては、六興出版の伊藤秋夫さんにお世話になった。
主な初出
『別冊太陽』『芸術新潮』『近代庶民生活誌』『國文學』『評決――昭和三年の陪審裁判』パンフレット『マリ・クレール』『太陽』『東京人』『クラシック銀座』『無限大』『文学』『広津和郎全集』普及版第九巻月報『言論は日本を動かす』第六巻『マダム』『婦人と暮し』『馬込文学地図』『シティページ24』『ゲスト・インフォメーション』関東版『東京・美術館への散歩道』
補記
最終更新:2007年03月19日 21:36