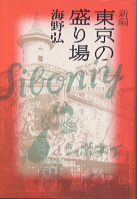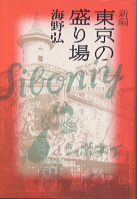
書名
書誌情報
- 出版社(叢書・シリーズ名)
- 発行年月日
- 版型 造本データ ページ数
- 定価
- 装丁
異版
目次
- Ⅰ 東京の盛り場
- ボヘミアンが都市の盛り場をつくる 8
- 東京の盛り場 16
- Ⅱ 東京の感性
- 新東京百景を歩く 76
- 失われたモダン都市を求めて 101
- 世界と東京、一九二〇年代 125
- 都市のアンダーワールド 137
- ジャズとモダン都市 146
- 昭和三年のモダン東京 157
- モダン都市東京をバスが行く 160
- 東京のエロス 172
- Ⅲ 都市の装置
- 帝国ホテルの時代 180
- 東京のデパートの歴史 193
- モダン銀座の魅惑 205
- モダン銀座と広告 209
- 喫茶店 213
- 路地の都市論 216
- 遊園都市論への序章 220
- 街 そして公園 230
- 大都市とコロニー 240
- Ⅳ 私の東京地図
- 東京一九二〇―八〇紀行――浅草・神田・銀座 246
- 東京舟行――隅田川・神田川・日本橋川 256
- 馬込文学散歩 260
- マイ・トレイル――渋谷 266
- 親しい街――新宿・銀座 268
- 私の好きな美術館――渋谷・目黒 269
- 中野のマジック・シティ 275
- 武蔵野の春 278
- あとがき 281
- 初出一覧 284
あとがきより
初めの版は、一九九一年に六興出版から出された。残念なことに、まもなく版元が倒産したので、そのまま埋もれてしまった。
その後、私は東京からさかのぼって、江戸に興味を持つようになり、『
江戸の盛り場』(青土社 一九九五)を書いた。そのような江戸への遊歴の間に
二十世紀が終わろうとしている。そして私はあらためて、東京にもどり、中断していた東京論を、江戸からのパースペクティヴを含めて、新しくはじめたいと思うようになった。
埋もれていた『東京の盛り場』を甦らせたい、と私は思った。そしてあらためて、出すためには、そのままではなく、やはり今の視点を入れることにした。
一番大きな変化は、初版の「モダン都市と文学」の章をはずし、東京紀行を多く加えたことである。それによって、私が今、東京を歩いていくという現代性が強まったと思っている。
第一章「東京の盛り場」は、〈盛り場〉が都市計画をこえてダイナミックに移って行くという視点から、東京の盛り場の歴史に触れる。
第二章「東京の感性」は、私が現代都市への最も重要な曲がり角と考えている、一九二〇年代の都市、モダン東京へのタイム・トラベルである。
第三章「都市の装置」では、ホテル、デパート、カフェー、路地、遊園地、公園といった都市に舞台装置のように置かれ、人々を街のドラマへと誘う〈都市装置〉について、その歴史と今をたどる。
第四章「私の東京地図」は、私の東京への、ささやかな旅である。
この本を新しく編んで甦らせてくれたのは伊藤秋夫さんである。かつて六興出版時代、伊藤さんは、この本と『
風景劇場』という私にとって愛着の深い二冊を編集してくれた。そしてこの本が埋もれていることを惜しんで、もう一度世に出す機会をつくってくれた。この本によって結ばれた友情が失われなかったことがとてもうれしい。
主な初出
『東京人』『別冊太陽』『サントリークォータリー』『芸術新潮』『近代庶民生活誌』『國文學』『評決――昭和三年の陪審裁判』パンフレット『マリ・クレール』『太陽』『ブルーガイド『東京』』『クラシック銀座』『『血の婚礼』プログラム』『無限大』『いーでも』『DBC』『マダム』『婦人と暮し』『馬込文学地図』『シティページ24』『ゲスト・インフォメーション』関東版『東京・美術館への散歩道』『小説CLUB』『日本海新聞』
補記
『
東京の盛り場』の増補新版。「ボヘミアンが都市の盛り場をつくる」「失われたモダン都市を求めて」「
モダン都市東京をバスが行く」「モダン銀座の魅惑」「喫茶店」「路地の都市論」「街 そして公園」「大都市とコロニー」「中野のマジック・シティ」「武蔵野の春」を増補、「谷崎潤一郎」「梶井基次郎」「広津和郎」「秦豊吉」を削除。
最終更新:2007年03月19日 21:39