道仔@Wiki
xfy 迷
最終更新:
taox
-
view
ジャストシステムのXML複合文書プラットフォームxfyのページ
本ページが容量超過となったため(質より量か)、2006年6月28日分より「續 xfy 迷」に移行することにした。て、まだつづけるつもりらしい・・・
ジャストシステムが世界に問う統合XMLアプリケーション開発・実行環境xfy。
Just Arkの後継かと思ったら大間違い。大化けしたよ。XMLプログラマでも何でもないけど何かと使っていこうと思う。ミーハー的に。
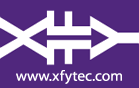
Just Arkの後継かと思ったら大間違い。大化けしたよ。XMLプログラマでも何でもないけど何かと使っていこうと思う。ミーハー的に。
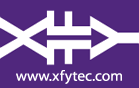
xfytec.com:総本山(日本語)
Tips & Info in Japanese:xfy Community Forumの日本語エリア
かわちょうぃき:徳島発かわちょさんのWiki(xfy関係リンクが豊富)
xfy.memo:shin_itaniさんのxfy技術ブログ(公式リファレンスの要約ほか)
FrameMaker使いのInDesign XML:DTPをxfyで編集してる人
Amaya Binary Releases:XML複合文書を編集するW3Cのオープンソース
Flickrにxfytecタグ(期間限定?)
本地のxfyはスゴイぞ(^^)♪
Tips & Info in Japanese:xfy Community Forumの日本語エリア
かわちょうぃき:徳島発かわちょさんのWiki(xfy関係リンクが豊富)
xfy.memo:shin_itaniさんのxfy技術ブログ(公式リファレンスの要約ほか)
FrameMaker使いのInDesign XML:DTPをxfyで編集してる人
Amaya Binary Releases:XML複合文書を編集するW3Cのオープンソース
Flickrにxfytecタグ(期間限定?)
本地のxfyはスゴイぞ(^^)♪
web中心再び
今年2月1日のメモで
世界の隅っこでxfyのweb中心化を叫ぶのは(当分)あきらめることにする
と書いたのだが(どーでもいいよってか?)、6月20日のメモに対して
xfy に足りないのは、ブラウザから起動できる仕組みや Java アプレット板?
という追記があったので(知らない誰かさん、ありがとう)改めて数秒ほど考えてみて、その通りだなと思った。アプリケーションであることによってxfyの機能・性能が最大限に発揮できることは十分理解できるが、xfyが目指していく世界というものを空想してみると、それ(アプリケーション)ってちょっと違うかもと思えてならないのだ。これは最初から感じていた違和感ではあるのだが、しかしRAD環境としてDB2 ViperやOracle 10gのFEP的なアプローチをするのだとしたら何も制約の多いブラウザ上で動く必要もあるまいと思い、一時撤回したのだが、そうこうしている間にも世界はいわゆる2.0的な方向へとどんどん動いていくばかりだ。もちろん、(繰り返しになるが)ソリューションツールはその目的に沿って最適化されていることが第一で、必ずしも“オープン”でなくても構わないし、まして実態が今ひとつはっきりしない2.0的なやり方を選択する必要もないのだが。
で、結局これはxfyをどうしていきたいのかということと大いに関係がある問題なんだろうな。じゃ、ぼくが口を出す話じゃないってことになるんだけど、ただ個人的にはブラウザで動いてくれたほうが何かと便利だし、たぶんみんなもそう思うんじゃないだろうか……
で、結局これはxfyをどうしていきたいのかということと大いに関係がある問題なんだろうな。じゃ、ぼくが口を出す話じゃないってことになるんだけど、ただ個人的にはブラウザで動いてくれたほうが何かと便利だし、たぶんみんなもそう思うんじゃないだろうか……
- 2006年6月26日
Blogエディタに先を越された、かも
xfyとは全く関係ない話だが、先日開かれたサン・マイクロシステムズ主催の「2.0時代のテクノロジートレンドセミナー」でのプレゼンテーション資料がサンのサイトに掲載された。でも、当日一番勢いのあったfeedpath@小川浩さんの資料が載っていない。Blogエディタのデモとか、現在ローカライズ中のAjaxベースのグループウェアの紹介とか、おもしろい内容だったのに。“使いやすくなったWeb”、これが彼のWeb2.0解釈。簡潔でわかりやすい。それにしてもBlogエディタは凄い、これってxfyでやろうと思えばできたことじゃないかな。
↑ブログに投稿したり過去の記事を一覧するクライアントアプリケーションは前からあるので、xfy でやっても、既存のと同じですよね。Feedpath のブログエディタは Web アプリで、ブラウザ上でできるのが便利なんだと思います。そういう点から見ると、xfy に足りないのは、ブラウザから起動できる仕組みや Java アプレット板?
- blogエディタでぼくが瞠目したのは、別のサイトをコピペで丸呑み(デザインごと貼付)できたのと、WYSIWYG編集ができた点。こういうのって、xfyがというよりもジャストシステムがやらなきゃいけないことだと思ったよ -- taox (2006-06-26 22:43:46)
- 2006年6月20日
論より証拠のサンプルアプリケーション群
xfyで何ができるの? と聞かれた時、これまでは下手くそな説明をしていて却ってナンノコッチャと言われていたけど、最近は「とりあえずこれ試したら」と言えるようになった。xfy Online Pavilion。xfyによる“マッシュアップ”アプリケーションのサンプル群(XVCD)が日本語で紹介されている。moreをクリックすると旧来の英語ページに飛んじゃうのはご愛敬。
で、これまでアップされたものを含め幾つか試してみているけど、極東のエプシロンブロガー(造語)にはちと敷居が高いXVCDが多いかも。ま、欲しけりゃやっぱり自分で作れってことか。
で、これまでアップされたものを含め幾つか試してみているけど、極東のエプシロンブロガー(造語)にはちと敷居が高いXVCDが多いかも。ま、欲しけりゃやっぱり自分で作れってことか。
- 2006年6月14日
Web2.0を支える「マッシュアップ」・米国で早くもブームに陰り?
日経IT+のコラム。
マッシュアップがウェブサービスの過渡技術として消え去るのか。それともウェブ2.0の基幹技術として大衆化してゆくのか。その将来が見えるまでには、もう少し時間がかかりそうだ
- 2006年5月29日
ジャストシステム技術者が語るxfyの魅力
23日のEnterprise Watchにこんな記事が。羽鳥さんじゃあ~りませんか。あ、22日には浮川社長のインタビュー記事も。
- 2006年5月25日
xfyの新たな解釈
“What's xfy”への新しい回答はマッシュアップ・プラットフォームらしい。文中“マッシュアップとは、複数のWebサービスを組み合わせて新しい価値を生み出すこと”とある。IT系の最新用語のようだけど、ググったらこんな説明が。ふーん。そう言えば2006 JavaOne Conference初日のニュースリリースにも“Web2.0時代のxfy Mashup Platform”とあったっけ。プログラマ向けにはこれで、エンタープライズ系にはUltra RAD環境というアピールをしていくってことね。
- 2006年5月24日
xfy BE 1.3(β) リリース
待ちに待ったxfy BasicEdition 1.3 betaが遂にリリースされた。噂のxfy ViewDesigner 1.0(β)が同梱されている(チュートリアル)。それに伴いxfy BasicEdition 1.3 フォーラムもオープン。
まずはxfyプラットフォーム1.0からの変更点をみる。xfy BasicEdition 1.0 用 XVCD をxfy Basic Edition 1.3 BETAで使用するためにはドメイン名記述の修正が必要、とのこと。とりあえずチュートリアルやxfyデベロッパーズガイドを読み直す必要がありそうだ。
まずはxfyプラットフォーム1.0からの変更点をみる。xfy BasicEdition 1.0 用 XVCD をxfy Basic Edition 1.3 BETAで使用するためにはドメイン名記述の修正が必要、とのこと。とりあえずチュートリアルやxfyデベロッパーズガイドを読み直す必要がありそうだ。
おお、shin_itaniさんのxfy.memoにはもう詳細が。みると
XHTML コンポーネントが改善され、 XHTML 要素群に名前空間接頭辞が付与されなくなった
とある。そのほかにもちょこちょこと。動作環境の変更も大きいな。
いずれにしても、まずこのxfy.memoを読むのが一番速いね。いつものことだけど。
いずれにしても、まずこのxfy.memoを読むのが一番速いね。いつものことだけど。
- 2006年5月16日
xfyの背中
なんだかんだですっかり間が抜けて……基、間が空いてしまい、xfyのことも“今浦島”状態。一応、この間も気にはしていたけど、xfyそのものに目立った動きはなかったみたい。
総本山を覗くと、日本語化に伴ってxfy Community YOKOSO Forumが活気づいてきた感じ。一時の、鵺が啼いていた時代が嘘のよう。xfy Community Downloadsにも続々と新しいXVCDが追加されていて、追いつくのがちょっとたいへんかも(^^;)
ぼくが一番頼りにしているshin_itaniさんのxfy.memoには、なんと未知のXMLボキャブラリ用のXVCD「Unknown XVCD」が! これ、例のアイコン表示されてしまうプライベートボキャブラリの内容を表示してくれるという優れもの。もちろん、早速頂戴いたしました。shin_itaniさんに多謝。幾つになっても甘えんぼ(by 間寛平)で、恩を受けるばかりの立場です。
もう一つ、これもぼくにとってはニュース。KawaChokiさんのWikiが、なくなりそう。ドメインを引っ越すそうだ。引っ越し先はこちら。xfy発表当時はここしか情報がなかった、いわば老舗(て言う?)。Emacs/Meadow3でもお世話になっていただけに、ちと残念。KawaChokiさん、お会いしたことはありませんが、梁“tony”朝偉や林“brigitte”青霞にも言及していたので、勝手に朋友扱いしてた。唔該!
閑話休題。ロードマップ通りなら、夏から秋にかけて大きな動きがあるようだし(たぶんソリューション中心かな)、その時になって周章狼狽しないよう、ぼちぼち追いかけていこうと思う。
総本山を覗くと、日本語化に伴ってxfy Community YOKOSO Forumが活気づいてきた感じ。一時の、鵺が啼いていた時代が嘘のよう。xfy Community Downloadsにも続々と新しいXVCDが追加されていて、追いつくのがちょっとたいへんかも(^^;)
ぼくが一番頼りにしているshin_itaniさんのxfy.memoには、なんと未知のXMLボキャブラリ用のXVCD「Unknown XVCD」が! これ、例のアイコン表示されてしまうプライベートボキャブラリの内容を表示してくれるという優れもの。もちろん、早速頂戴いたしました。shin_itaniさんに多謝。幾つになっても甘えんぼ(by 間寛平)で、恩を受けるばかりの立場です。
もう一つ、これもぼくにとってはニュース。KawaChokiさんのWikiが、なくなりそう。ドメインを引っ越すそうだ。引っ越し先はこちら。xfy発表当時はここしか情報がなかった、いわば老舗(て言う?)。Emacs/Meadow3でもお世話になっていただけに、ちと残念。KawaChokiさん、お会いしたことはありませんが、梁“tony”朝偉や林“brigitte”青霞にも言及していたので、勝手に朋友扱いしてた。唔該!
閑話休題。ロードマップ通りなら、夏から秋にかけて大きな動きがあるようだし(たぶんソリューション中心かな)、その時になって周章狼狽しないよう、ぼちぼち追いかけていこうと思う。
- 2006年4月18日
XMetaL買収
ジャストシステムがBlast Radius社の「XMetaL」事業部門の買収したとの発表について、shin_itaniさんがxfy.memoでわかりやすく説明してくれている。多謝。
XMetaLは製品デモをみる限り、極めてよくできたワードプロセッサという印象だ。それもそのはず、shin_itaniさんの説明によれば一時Corel社が保有していたというではないか。同社はWordPerfectを買い取った会社だ。tag view機能とかをみていると、かつてMacintosh Quadra 700でWord Perfectを使っていた時代を思い出す。整形タグを直接制御できる仕組みをもっていて使いやすかった。エディタで入力して整形専用ソフトで書式を整えるというお作法は、この時に身についたものだ。
CNET japanの報道「ジャストシステム、XMLプラットフォーム事業強化へXMetaLを買収」にはマーケティング観点での説明が載っていたが、肝心のxfyは影響を受け、XMLエディタとして完成度を高めていけるのか、気になる。
XMetaLは製品デモをみる限り、極めてよくできたワードプロセッサという印象だ。それもそのはず、shin_itaniさんの説明によれば一時Corel社が保有していたというではないか。同社はWordPerfectを買い取った会社だ。tag view機能とかをみていると、かつてMacintosh Quadra 700でWord Perfectを使っていた時代を思い出す。整形タグを直接制御できる仕組みをもっていて使いやすかった。エディタで入力して整形専用ソフトで書式を整えるというお作法は、この時に身についたものだ。
CNET japanの報道「ジャストシステム、XMLプラットフォーム事業強化へXMetaLを買収」にはマーケティング観点での説明が載っていたが、肝心のxfyは影響を受け、XMLエディタとして完成度を高めていけるのか、気になる。
- 2006年3月10日
追記:驚き! Word Perfectはまだ売られていた。残念ながら英語版のみ。懐かしの旧Borland QuattroやParadoxも生き残っているではないか。どちらも使い勝手のいいアプリケーションだったよなあ……(と、感慨に耽りつつfadeout
xfy=Ultra RAD説の秘密
ORACLE OPEN WORLDでのジャストシステム浮川社長の講演。
前半はxfyの概要でこれまでも聞いたことがある内容だったが、後半はxfy View Generatorを用いたeXtensible Business Reporting Language(XBRL)のハンドリングと、先日発表されたxfy Enterprise Solution Plus for Oracle Database 10gをデモ。
XBRLのハンドリングでは実際にXBRL Japanのダウンロードサイトから税務用財務諸表タクソノミ(だったと思う)を引っ張ってきてxfy View Generatorで解析・表示してみせた。説明によればXBRLのハンドリングはとりわけ繁雑とのことで、それがxfyを使えば簡単に実行できる(実際、見ているとあっという間だった)と強調していた。
続くxfy Enterprise Solution Plus for Oracle Database 10gのデモでは、xfy Query Generatorを用いてOracle Database 10gからデータを抽出し、それを前述のxfy View Generatorでビュー表示する様子が紹介された。ビューは複数用意されていて、メニューを切り替えるだけでデータの見え方が変化する。
今日のデモで一番重要と思われたのは、ビュー画面上でたとえば支店Aの売上データを分析した後、B支店のデータを取り込みむと、改めて計算式などを入れ直すことなく結果を得られるという点だった。つまり、あるデータを取り込んで何らかの処理(ここでは売上分析)を行うと、その処理プロセスがコンポーネント化されるのだ。“データハンドリングが即機能化される”とでも言えばいいのだろうか。ジャストシステムは最近、xfyを“Ultra RAD”と称しているのが、それはもしかするとこのあたりのことを指しているのかも知れない。
全体で約1時間少々の本日の講演、少し詰め込みすぎという印象をもった。もっともっとシンプルな構成にしないとついていけない聴衆もいたのではないだろうか(て、自分のことじゃん)。
前半はxfyの概要でこれまでも聞いたことがある内容だったが、後半はxfy View Generatorを用いたeXtensible Business Reporting Language(XBRL)のハンドリングと、先日発表されたxfy Enterprise Solution Plus for Oracle Database 10gをデモ。
XBRLのハンドリングでは実際にXBRL Japanのダウンロードサイトから税務用財務諸表タクソノミ(だったと思う)を引っ張ってきてxfy View Generatorで解析・表示してみせた。説明によればXBRLのハンドリングはとりわけ繁雑とのことで、それがxfyを使えば簡単に実行できる(実際、見ているとあっという間だった)と強調していた。
続くxfy Enterprise Solution Plus for Oracle Database 10gのデモでは、xfy Query Generatorを用いてOracle Database 10gからデータを抽出し、それを前述のxfy View Generatorでビュー表示する様子が紹介された。ビューは複数用意されていて、メニューを切り替えるだけでデータの見え方が変化する。
今日のデモで一番重要と思われたのは、ビュー画面上でたとえば支店Aの売上データを分析した後、B支店のデータを取り込みむと、改めて計算式などを入れ直すことなく結果を得られるという点だった。つまり、あるデータを取り込んで何らかの処理(ここでは売上分析)を行うと、その処理プロセスがコンポーネント化されるのだ。“データハンドリングが即機能化される”とでも言えばいいのだろうか。ジャストシステムは最近、xfyを“Ultra RAD”と称しているのが、それはもしかするとこのあたりのことを指しているのかも知れない。
全体で約1時間少々の本日の講演、少し詰め込みすぎという印象をもった。もっともっとシンプルな構成にしないとついていけない聴衆もいたのではないだろうか(て、自分のことじゃん)。
本日のお土産


- 2006年3月3日
総本山が日本語化
総本山を訪れてびっくり、日本語サイトができていた。うれしい、と言うより助かった(^_^;)
今回新たに掲載されたWhy xfyを読んでみると、もはや複合ドキュメントプラットフォームという表現は影を潜め、XMLアプリケーション開発環境という打ち出し。全体のトーンもそうだし、たとえば次のような一文
今回新たに掲載されたWhy xfyを読んでみると、もはや複合ドキュメントプラットフォームという表現は影を潜め、XMLアプリケーション開発環境という打ち出し。全体のトーンもそうだし、たとえば次のような一文
xfyは、XMLを情報として取り扱うだけでなく、XMLを機能部品としてシステム開発できるアーキテクチャとして登場しました
当初は、XML文書のランタイム環境であり作成ツールであり開発環境でもある、みたいな言い方をしていたと記憶しているが、DB連携などエンタープライズのソリューションプラットフォームとしての色彩を強める中、訴求の軸足を開発環境に定めることにしたんだろうな(と、一知半解)。上記文中には“Ultra RAD”なんて用語もあるし。RADってRapid Application Developmentだろ? これ4GL華やかなりし頃によく聞いたっけ。ところで
xfyは、今後の企業情報システムに求められるデータ統合やプロセス統合に対して、ネイティブXMLアプリケーションというアプローチで応えます。これは、静的データだけでなくプロセスや処理の記述が行えるというXMLの特性を活かしたXML機能部品を素早く作成し、自由自在に組み合わせることによって実現されます
さらりと書いてあって意味がつかみにくいところがあるけど、これってxfyの本質なんだよね、きっと。ORACLE OPEN Worldのジェネラルセッション「UltraRADシステム xfyのご紹介」でこのあたりの話が出てくるのだろうか。
- 2006年3月2日
xfy technology demo正式公開
Cell Phone Compound Document is an example of compound document using XHTML, SVG and MathML vocabulary.
- 2006年2月19日
xfy デモ動画(こっそり公開)
shin_itaniさんのxfy.memoに
先日参加したセマンティック Web コンファレンス 2006 (のジャストシステムのデモ展示コーナー) で、xfy technology のデモが展示されていました。展示されていたデモは、 xfytec.com で公開されているデモ・ムービー (下記)で使われているものの一つだったようです
とあったので、飛んでいったらあったあった。
アップされていたのはxfy Basic Edition、xfy View Generator、DB2 Viper Extension Kit、そしてComponent Linkage、Product Review の5本(最後は静止画)。よく見つけたなあ、shin_itaniさん。
ナレーションが英語なので正確な理解はできなかったけど、百聞は一見にしかずで、xfyの特長をつかむにはいいアプローチだと思う。そう言えば今度の一太郎2006にも動画を用いた解説CDが同梱されていた。
また、shin_itaniさんはxfy Community forumでデモ公開を求める書込もされていました。
もっともジャストシステム側の回答に
アップされていたのはxfy Basic Edition、xfy View Generator、DB2 Viper Extension Kit、そしてComponent Linkage、Product Review の5本(最後は静止画)。よく見つけたなあ、shin_itaniさん。
ナレーションが英語なので正確な理解はできなかったけど、百聞は一見にしかずで、xfyの特長をつかむにはいいアプローチだと思う。そう言えば今度の一太郎2006にも動画を用いた解説CDが同梱されていた。
また、shin_itaniさんはxfy Community forumでデモ公開を求める書込もされていました。
もっともジャストシステム側の回答に
可能な限り公開したいとは思っているのですが、プロトタイプモジュールが含まれていたりするものもありますので、どうしても公開できないものが多い
とあるので、この情報(動画アップ)はあまりオープンにしちゃいけないのかも・・・て、ますますオープンにしてるじゃん、ぼく(^0^)/(ジャストシステムさん、まずかったらこのWikiエントリをまるまる削除してね。もしこれを読んでいるならの話だけど)
当該スレッドにはさらに、サーバ上のXML文書編集の可否に関するやり取りもあり、
当該スレッドにはさらに、サーバ上のXML文書編集の可否に関するやり取りもあり、
将来的にはいろいろなシステムに対応していきたい、対応できるようなプラグインを用意していきたいと思っていますので、blogもそうですが「今後」ということになると思います
との回答を引き出していた。すごいや、shin_itaniさん。
- 2006年2月15日
世界の隅っこでxfyのweb中心化を叫ぶのは止めよう、と思った
最近のxfyの情報を見ると照準はSIerに定めていることがわかる。DB2 ViperのFEPになる話などは、アプリケーション開発のプラットフォームとしてのxfyという色合いが相当濃い。もちろんドキュメントオーサリングとしてのxfy、コミュニケーションプラットフォームとしてのxfyという側面がなくなるわけではないのだが……。
そんな中、Linux Zaurusの情報源としてお世話になっている、塚本牧夫さんのWalrus,Visitに上がったエントリ“なぜ「業務にPerlは使えない」のか?”が非常に参考になった。xfyとは全く無関係なエントリなのだが“xfyがWeb中心になってくれるとうれしい”などというぼくの妄想に飛び蹴りを喰らわせてくれた。
そんな中、Linux Zaurusの情報源としてお世話になっている、塚本牧夫さんのWalrus,Visitに上がったエントリ“なぜ「業務にPerlは使えない」のか?”が非常に参考になった。xfyとは全く無関係なエントリなのだが“xfyがWeb中心になってくれるとうれしい”などというぼくの妄想に飛び蹴りを喰らわせてくれた。
Web開発の世界では不特定の利用者や様々なクライアントで利用できる、XMLやRSS、RPC、SOAP、ATOMといったオープン・スタンダードな技術で構成し、それらを活用することが重要です。一方のSIの世界、オープン・システムでの開発の世界ではしばしば、まるでスタンダードがない技術分野のオープンでもない技術を抜きには「やってられない」ことがあります
xfyそのものは前者の世界のプログラムだが、後者を置いてきぼりにはできないのだ。それどころか、後者の世界こそxfyの恩恵を蒙ることができるのだと思う。となれば、Web中心などと(現時点では)言ってはいられない「やってられない」ということだ。
そんなワケで、世界の隅っこでxfyのweb中心化を叫ぶのは(当分)あきらめることにする。
そんなワケで、世界の隅っこでxfyのweb中心化を叫ぶのは(当分)あきらめることにする。
- 2006年2月1日
ExcelシートをWikiに変換するwebサービス
これまでExcelシートに情報を入力してから、それをメールでほかの人に送っていた人のための製品
とのこと。
Wikiなので単なる表示だけでなくデータの追記・編集も可能だ。そうして作成されたシートはCSV形式で保存できる。
こちらのブログによれば“日本語は通るが、フォントサイズや一部セルの指定などで制約がある”らしい。
先日のwritelyといい、なんかいい感じ。
現行β版だが3月頃までには正式なサービスが開始されるそうだ。
xfyとは関係ないのだが、でも汎用ブラウザで情報をやり取りできるのはやっぱり便利じゃない? ってなんとなくプレッシャをかけてみたよ(^^;)
Wikiなので単なる表示だけでなくデータの追記・編集も可能だ。そうして作成されたシートはCSV形式で保存できる。
こちらのブログによれば“日本語は通るが、フォントサイズや一部セルの指定などで制約がある”らしい。
先日のwritelyといい、なんかいい感じ。
現行β版だが3月頃までには正式なサービスが開始されるそうだ。
xfyとは関係ないのだが、でも汎用ブラウザで情報をやり取りできるのはやっぱり便利じゃない? ってなんとなくプレッシャをかけてみたよ(^^;)
こちらの記事でも取り上げられている
- 2006年1月15日
xfyとFirefoxでのXHTML表示の相違
shin_itaniさんによるxfy技術ブログxfy.memoに XHTML コンポーネントの実装状況(その1)として“xfy Basic Edition 1.0 と Mozilla Firefox 1.5 とでの表示結果の違い”が掲載されていた。逆読みするとXHTMLベースのwebページをxfyで表示させるためのポイントがわかる。xfyを意識してwebを作成する必要はないだろうだが……
Slide View for XHTML XVCDを使ってみた
年末年始のばたばたを言い訳にお勉強をサボっていたらxfy Community DownloadsにSlide View for XHTMLというXVCDがアップされた。何をするものかというと
"Slide View for XHTML" gives "Slide View" to the source XHTML document. "Slide View for XHTML" enables you to do presentation directly with your XHTML document. No need to maintain two versions of files for a single document: for reading and for presentation.
ということで、XHTMベースのスライドを生成するXVCDらしい。
このXVCD一式をscriptsフォルダに格納するとボキャブラリコンポーネント切換メニューにDo Presentationというボキャブラリが追加される。任意のXHTML文書を読み込んだ上でメニューからDo Presentationを選択すると、<h2>タグで示された文字列ごとにスライドのページ(section)に切り替わるという仕組みだ。
ドキュメントを読まずにいきなり使い出してみたがなかなかおもしろい。各スライドのページタイトルを示すタグが<h2>なのでその前に<h1>タグが必要なこと(スライドモードでは非表示)、スライド全体のタイトルは<title>タグで記述するなどの“お約束”を守らないと機能しないが、既存のXHTML文書を変換することなしにプレゼンテーション用途に変身させることができるのは便利かも。作成者はYamahigeさんとなっている。感謝。
このXVCD一式をscriptsフォルダに格納するとボキャブラリコンポーネント切換メニューにDo Presentationというボキャブラリが追加される。任意のXHTML文書を読み込んだ上でメニューからDo Presentationを選択すると、<h2>タグで示された文字列ごとにスライドのページ(section)に切り替わるという仕組みだ。
ドキュメントを読まずにいきなり使い出してみたがなかなかおもしろい。各スライドのページタイトルを示すタグが<h2>なのでその前に<h1>タグが必要なこと(スライドモードでは非表示)、スライド全体のタイトルは<title>タグで記述するなどの“お約束”を守らないと機能しないが、既存のXHTML文書を変換することなしにプレゼンテーション用途に変身させることができるのは便利かも。作成者はYamahigeさんとなっている。感謝。
- 2006年1月12日
ブラウザで使えるワードプロセッサwritely
Ajaxを用いたWeb版ワードプロセッサ「writely」というのがあった。サイボウズの経営企画室・安田智宏氏のブログ「経営企画室調査日報」で知った。
Writelyはブラウザで利用するWebベースのワープロソフトで、Microsoft Wordのdocファイルを読み込みHTMLに変換可能。他にもOpenDocument、RTFといったワープロソフトが対応することが望ましいファイル形式が一通りサポートされている様子。今回新たにファイルをPDFで保存する機能も搭載した
いやはや、すごい。
ぼくがxfyに望んでいるのも、こんなこと。ブラウザさえあればいつでもどこでもだれとでも文書情報をやりとりできる。
ざっと試してみたが、一部整形に制限はあるものの日本語は通るし動きもまあまあ。ただしWin98+Firefoxでは頻繁に落ちる。
ぼくがxfyに望んでいるのも、こんなこと。ブラウザさえあればいつでもどこでもだれとでも文書情報をやりとりできる。
ざっと試してみたが、一部整形に制限はあるものの日本語は通るし動きもまあまあ。ただしWin98+Firefoxでは頻繁に落ちる。
- 2005年12月19日
追加予告されているツールの提供はいつ?
下記のような書き込み(xfyではXMLオブジェクトの作成が必須)をどなたかがしてくださった。ぼくのあまりの無知に呆れてのことだね。感謝感謝。
コードを書くスキルのないユーザはViewGeneratorやViewDesignerを待つほかないということのようだ。
そういえばxfyデベロッパーズガイドXVCDによるボキャブラリコンポーネントの開発手段
にも
コードを書くスキルのないユーザはViewGeneratorやViewDesignerを待つほかないということのようだ。
そういえばxfyデベロッパーズガイドXVCDによるボキャブラリコンポーネントの開発手段
にも
対話形式で実行して簡単にJARファイルを作成できるツールを、xfy Developer's Toolkitに含めて提供することを予定しています
とか
xfy Developer's Toolkitでは、このほかにもボキャブラリコンポーネントの作成を支援するツールや機能を追加提供することを予定しています
といった一文がある。エンタープライズ版の登場まで待つことになるのかな。
書き込みにあった
ユーザーとしてはFirefoxとかのプラグインとしてXVCD Viewer(Acrobat Reader)みたいなのが欲しいところ
は激同です。
- 2005年11月28日
xfyではXMLオブジェクトの作成が必須
Justsystemのxfyリリース記事では
xfyを利用することで、それぞれのユーザーが意図や目的に応じてユーザーインターフェース、データ活用アプリケーションを自由に構築し、最適な環境をマルチプラットフォーム上で実現できます
とあるが、これはxfyのユーザーが自分でXMLオブジェクトを作成する必要があるのだと気づいた。
IT MediaのXML 2005 Conference Reportにも
xfyの基本的な働きは、XMLオブジェクトの作成/編集だといってよい
とある。
いきなりxml文書をxfyで開いて編集できるわけではなく、まずはXVCDまたはJavaでボキャブラリコンポーネント(XMLオブジェクト = データ活用アプリケーション)を作らないといけないということだ。
作成したXMLオブジェクトをxfyにプラグインとして登録することで初めて、自分のxml文書が編集可能となる。
作成したXMLオブジェクトをxfyにプラグインとして登録することで初めて、自分のxml文書が編集可能となる。
つまり、xml文書を編集して、IEやFirefoxなどのブラウザに表示させたいときは、XVCDの場合、最低限2つファイルを作成しないといけない。
- XVCDファイル(XML文書編集用)
- XSLT(ブラウザ表示用)->XSLTの骨組みはXVCDと一緒
加えて、こんなファイルを作ることもある。
- リソースファイル(多言語対応用)
- マニフェストファイル(xfyに登録用)
XVCDとXSLTの構造が同じなら、ユーザーとしてはFirefoxとかのプラグインとしてXVCD Viewer(Acrobat Reader)みたいなのが欲しいところ。同じ構造のものを二度作成するのは面倒くさい。
ちなみに、すべてのユーザーがXVCDやJavaを知っているわけではないので、ViewGenerator(XVCDを自動生成)やViewDesigner(XVCDを作成)を提供するのだろう。で、この二つは有料(たぶん)。
- 2005年11月26日
xfy Enterprise Solution plus for DB2 Viper
Justsystemが17日に発表したxfy Enterprise Solution plus for DB2 Viperのリリース記事に
xfy Enterprise Solution plus for DB2 Viperは、XMLスキーマやXQueryの結果までも含め、既存のXMLリソースから半自動的かつリアルタイムにアプリケーションを作成することもできます
という一文があったが、昨日の「IT Mediaエンタープライズ」にそのデモを紹介した記事が載っていた。
デモの内容は、Viperからデータを抽出してレポートにまとめる(Query Application)というもので、xfy上にDBオブジェクトを配置すると、表形式のデータが貼り付けられていくらしい。この時、貼り付けられているのはデータではなく、クエリの手順そのものがXVCDプログラムとしてレポート(XNLファイル)の中に格納されるのだそうだ。つまり、データの抽出作業がそのままQuery Applicationを開発することにもなる、と。View Generatorという仕組みがこれを可能にしているらしい。
「データとクエリアの発行を区別して考えることなくXMLオブジェクトありきで操作できるのがxfyの世界」(要旨)と記事はまとめている。
・
・
・
これって、OOPの仕来りをXMLの世界に持ち込んだってこと? だとすると、すごい話なのかも。
デモの内容は、Viperからデータを抽出してレポートにまとめる(Query Application)というもので、xfy上にDBオブジェクトを配置すると、表形式のデータが貼り付けられていくらしい。この時、貼り付けられているのはデータではなく、クエリの手順そのものがXVCDプログラムとしてレポート(XNLファイル)の中に格納されるのだそうだ。つまり、データの抽出作業がそのままQuery Applicationを開発することにもなる、と。View Generatorという仕組みがこれを可能にしているらしい。
「データとクエリアの発行を区別して考えることなくXMLオブジェクトありきで操作できるのがxfyの世界」(要旨)と記事はまとめている。
・
・
・
これって、OOPの仕来りをXMLの世界に持ち込んだってこと? だとすると、すごい話なのかも。
- 2005年11月19日
xfyでワードプロセシング:哭泣篇
エディタで起こしたプレインテキストをxfyで編集していたが、途中で疲れてしまい、結局エディタでタグ打ちする羽目に……。
何が疲れるって、扱いなれていないということもあるのだろうが、書式指定するのが結構面倒なのだ。
たとえば、先頭文字列に<xhtml:h1></xhtml:h1>(xfyでは見出し1)を指定するといきなり全文h1になる。あちゃ~、と哭泣し2行目以降を元の書式に戻そうと解除指定すると、今度は先頭行まで解除されてしまう。再び哭泣。
では、どうすればいいのかと言うと、改行してやるのである。すると段落終了タグ(</xhtml:p>)が挟み込まれる。これを段落を分けたいと思う全ての箇所で行わなければいけないのだった(エディタで入れた改行コードは<xhtml:br></xhtml:br>となる)。
ここが一般のワードプロセッサと大きく異なるところで、謳い文句の“ワープロライク”はあくまでもlike(似)であって同一ではないということだ。たしかに相手はXML文書なのだから、当然ちゃあ当然なのだが、これがGUIでの作業効率を低下させる要因になる。
この面倒を回避するには、最初からxfyで文書を起こすか(これがフツーか、やっぱり)、もしプレインテキストを読み込む場合は先頭から順に指定していくということになる。こことここの文字列はh2で、こことここの段落はリスト指定を、なんて芸当はなかなかできそうにない(リストタグなんか入るとさらにややこしいことになって、もう改行したくらいじゃ抜け出せないことに……涙)。
とりあえずの解としては、やはりソース画面で直接Sourceをいじれるように機能変更(拡張?)してくれることだと思うのだが、どうだろう。Source Likeと別にソースというメニューが用意されているところをみると、そうする予定があるのだろうか。ソースへのアクセスは
何が疲れるって、扱いなれていないということもあるのだろうが、書式指定するのが結構面倒なのだ。
たとえば、先頭文字列に<xhtml:h1></xhtml:h1>(xfyでは見出し1)を指定するといきなり全文h1になる。あちゃ~、と哭泣し2行目以降を元の書式に戻そうと解除指定すると、今度は先頭行まで解除されてしまう。再び哭泣。
では、どうすればいいのかと言うと、改行してやるのである。すると段落終了タグ(</xhtml:p>)が挟み込まれる。これを段落を分けたいと思う全ての箇所で行わなければいけないのだった(エディタで入れた改行コードは<xhtml:br></xhtml:br>となる)。
ここが一般のワードプロセッサと大きく異なるところで、謳い文句の“ワープロライク”はあくまでもlike(似)であって同一ではないということだ。たしかに相手はXML文書なのだから、当然ちゃあ当然なのだが、これがGUIでの作業効率を低下させる要因になる。
この面倒を回避するには、最初からxfyで文書を起こすか(これがフツーか、やっぱり)、もしプレインテキストを読み込む場合は先頭から順に指定していくということになる。こことここの文字列はh2で、こことここの段落はリスト指定を、なんて芸当はなかなかできそうにない(リストタグなんか入るとさらにややこしいことになって、もう改行したくらいじゃ抜け出せないことに……涙)。
とりあえずの解としては、やはりソース画面で直接Sourceをいじれるように機能変更(拡張?)してくれることだと思うのだが、どうだろう。Source Likeと別にソースというメニューが用意されているところをみると、そうする予定があるのだろうか。ソースへのアクセスは
とのことだったが。
一方で、これも当然といえばその通りなのだが、xfyは作成・編集の自由度が高い分、ぼやっとしていると文書が非構造なものなってしまう危険性も孕んでいる。h1の次にh3が来て、その後h2となって、さらにh1を入れてしまうなんてトな文書を作れてしまうのだ。そんな輩は使うなよ、って話もあるが。
そうならないためにはパーサとか載せてもらえたらいいのかな、一太郎に修太があるように。
一方で、これも当然といえばその通りなのだが、xfyは作成・編集の自由度が高い分、ぼやっとしていると文書が非構造なものなってしまう危険性も孕んでいる。h1の次にh3が来て、その後h2となって、さらにh1を入れてしまうなんてトな文書を作れてしまうのだ。そんな輩は使うなよ、って話もあるが。
そうならないためにはパーサとか載せてもらえたらいいのかな、一太郎に修太があるように。
xfyはArk後継ではないので、ワードプロセシング的なことを期待すべきではないと思うが、個人ユーザとしてはやっぱり、ね。
- 2005年11月16日
ShapeML component追加
コンポーネントの更新情報をみるとBEのバージョンが1.0.1.0から1.0.2.0に上がっていた。目につく変更点はヘルプにサンプルというメニューが追加されたことぐらい。
同時に、これまで読むことのできなかったShapeML component for xfy 操作マニュアルの閲覧が可能に。
同時に、これまで読むことのできなかったShapeML component for xfy 操作マニュアルの閲覧が可能に。
ShapeML コンポーネントは、xfy Basic Edition上で図形を表示・編集するために使います。ShapeML コンポーネントでは直線・長方形・円などの基本図形に加え、矢印・十字形・星形・吹き出しなどを簡単に描画・編集できます
とのこと。さらに、使い方として
shapemlディレクトリのサンプルをクリック
とあるのだが、見当たらない。
・
・
・
とここで、はたと気付いて(まただよ)xfy_combo_pack_051114.exeを実行して旧版と入れ替えた結果、当該ディレクトリが表示された。コンポーネントの更新のみでよいものと勘違いしていた。おやおや。
・
・
・
とここで、はたと気付いて(まただよ)xfy_combo_pack_051114.exeを実行して旧版と入れ替えた結果、当該ディレクトリが表示された。コンポーネントの更新のみでよいものと勘違いしていた。おやおや。
- 2005年11月16日
プライベートボキャブラリの表示
β版では個人が作成した名前空間、いわゆるプライベートボキャブラリはicon表示のみだったが、製品版ではとりあえず文字列が表示されるようになったようだ。たとえば
xmlns:taox="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
と宣言した上で(taoxが独自要素ね)、任意の場所に
<p><taox:index>歎異抄</taox:index><taox:body>善人なおもて往生を遂ぐ、況や悪人おや</taox:body></p>
とすると
<taox:index>
歎異抄
</taox:index>
<taox:body>
善人なおもて往生を遂ぐ、況や悪人おや
</taox:body>
となる。もちろん<p>と</p>の間であれば独自タグの前後に文字列を入れることも可能。
これって、たしか傭兵改めyohei-yさんが取り上げていた話と一緒かもかもエブリバデイ。
これって、たしか傭兵改めyohei-yさんが取り上げていた話と一緒かもかもエブリバデイ。
……で、いいんだよな、xmlns:taoxと宣言して。
- 2005年11月15日
Think different No.2
XMLを直接編集できないユーザは次期のOfficeや、XHTMLに対応したオーサリングツール使うだろうし...そういうツールはそもそもXMLとか言う必要性が薄いです。そう考えるとxfyが想定しているユーザー層って謎です...
- 2005年11月15日
XVCDコンポーネント、続々登場
製品版リリース以降、xfy Community Downloadsに少しずつではあるがコンポーネントがアップされ始めている。
中でも最初に登場したAutoChart XVCDはkishiさんという日本のユーザが作ったもので、この方とはおそらく10月19日のOff-line Meetingでお会いしていたと思われ。
そのほか最近、Justsystem製のwiki XVCDも登録されるなど、xfyの可能性を引き出すコンポーネント群が徐々に現れつつあるようだ。この調子でxfy文書をブラウザ表示できたり、PDFに変換してくれるものが出てこないかな……、などと情けないことを言ってみる。
中でも最初に登場したAutoChart XVCDはkishiさんという日本のユーザが作ったもので、この方とはおそらく10月19日のOff-line Meetingでお会いしていたと思われ。
そのほか最近、Justsystem製のwiki XVCDも登録されるなど、xfyの可能性を引き出すコンポーネント群が徐々に現れつつあるようだ。この調子でxfy文書をブラウザ表示できたり、PDFに変換してくれるものが出てこないかな……、などと情けないことを言ってみる。
- 2005年11月9日
このURLをWebブラウザで開く
xfyでインターネット上のサイトを表示させようとするとW3Cのようなところを除いてほとんど失敗する。例外はThe Web KANZAKIで、これはまあ、神崎さんが偉いと言うべきだろう。
そんな状態の中、製品版になってURLの取得に失敗すると標記のようなボタンが表示されるようになった。クリックするとブラウザが起動し、サイトへ飛んでいけるというわけだ。
そんな状態の中、製品版になってURLの取得に失敗すると標記のようなボタンが表示されるようになった。クリックするとブラウザが起動し、サイトへ飛んでいけるというわけだ。
- 2005年11月3日
名前空間接頭辞xhtmlの扱い
xfyでXHTML文書を作成すると、名前空間接頭辞としてxhtmlが附与される。
昨日、この接頭辞のあるタグとそうでないタグが混在した文書はxfyで扱えないようだと書いたが、これは正しい表現ではなかった。要は書き方の問題で、名前空間の使用を宣言してやれば問題はない。
試みに通常のXHTMLを読み込んだ後、xfyで編集を加えると部分的に接頭辞xhtmlを含むタグが生成される。たとえば
昨日、この接頭辞のあるタグとそうでないタグが混在した文書はxfyで扱えないようだと書いたが、これは正しい表現ではなかった。要は書き方の問題で、名前空間の使用を宣言してやれば問題はない。
試みに通常のXHTMLを読み込んだ後、xfyで編集を加えると部分的に接頭辞xhtmlを含むタグが生成される。たとえば
<p>文字列</p>
にリストを設定すると、ソースは
となる。この後、ソースファイルで直接xhtmlの部分を削除し
<ul><li>文字列</li></ul>
としても問題は生じない。
ただしxfy上で文書を編集後ソースをみると、なぜか各パラグラフの先頭に空タブが挿入されている。実害はないが、ちょっとうるさい。
- 2005年11月2日
既存のXHTMLファイルが読み込めない、なんてことある? ←ない!
早速製品版で遊んでみようと、自分で作成したXHTMLファイルを開いてみたが、なぜかIcon表示されてしまう。β版では問題なく読込・表示されていた文書だ。
xfyで作成した文書はタグがすべて<xhtml:p>文字列</xhtml:p>となるが、てことは何か? 製品版ではタグにこの名前空間接頭辞xhtmlの記述がないものは扱えなくなったってこと? たしかにこんな記述があるにはあるが、まさかね。
ううん、やっぱりドキュメント群を読んでからだな、遊ぶのは(ションボリ
・
・
・
その後はたと思い当たり、デスクトップ機に残っていた別のXHTML文書を読み込ませたところ、あっさりと表示できた。原因はβ版で編集しているうちに接頭辞xhlmが附されたタグと、そうでないタグが混在してしまったことにあったようだ。愚か。
xfyでXHTML文書を扱うためには、接頭辞xhtmlの記述が必須というのではなく、記述の有無を統一させる必要があるということだ。当たり前っちゃあ当たり前だが、β版では気がつかなかった。
尚、再確認のために再現させてみたところ、ボキャブラリコンポーネントエリアでErrorを選択することで誤り箇所を特定できることにも気づいた。
xfyで作成した文書はタグがすべて<xhtml:p>文字列</xhtml:p>となるが、てことは何か? 製品版ではタグにこの名前空間接頭辞xhtmlの記述がないものは扱えなくなったってこと? たしかにこんな記述があるにはあるが、まさかね。
ううん、やっぱりドキュメント群を読んでからだな、遊ぶのは(ションボリ
・
・
・
その後はたと思い当たり、デスクトップ機に残っていた別のXHTML文書を読み込ませたところ、あっさりと表示できた。原因はβ版で編集しているうちに接頭辞xhlmが附されたタグと、そうでないタグが混在してしまったことにあったようだ。愚か。
xfyでXHTML文書を扱うためには、接頭辞xhtmlの記述が必須というのではなく、記述の有無を統一させる必要があるということだ。当たり前っちゃあ当たり前だが、β版では気がつかなかった。
尚、再確認のために再現させてみたところ、ボキャブラリコンポーネントエリアでErrorを選択することで誤り箇所を特定できることにも気づいた。
- 2005年11月1日
Think different
そもそもXMLはデータが人間に読めるようにというのを目指しているはずなんですが、こういうUIが吐き出すXMLってUIが発達すればするほど可読性が落ちるってのには、どこかで道を誤っているんじゃないかって気がしてます
- 2005年11月1日
製品版ファーストインプレッション(てほどか?)
本日、日本時間正午、xfy製品版の提供が開始された。
ダウンロードサイトからxfy_combo_pack_051031.exeをダウンロードしてインストール。その際、言語設定や格納フォルダの選択パネルが表示されるなど、いかにも製品版になったという雰囲気。また、これまで個別にインストールしていたxfy Developer's Toolkitもこのパッケージに含まれ、自動的に格納される。
xfy Combo Pack 051031にはこのほか、Outline View component for xfyというコンポーネントも同梱されている。これはOutline View component for xfy 操作マニュアルによれば、ドキュメントのアウトラインを表示するためのもの。
ダウンロードサイトからxfy_combo_pack_051031.exeをダウンロードしてインストール。その際、言語設定や格納フォルダの選択パネルが表示されるなど、いかにも製品版になったという雰囲気。また、これまで個別にインストールしていたxfy Developer's Toolkitもこのパッケージに含まれ、自動的に格納される。
xfy Combo Pack 051031にはこのほか、Outline View component for xfyというコンポーネントも同梱されている。これはOutline View component for xfy 操作マニュアルによれば、ドキュメントのアウトラインを表示するためのもの。
アウトラインにはドキュメント内のタイトルが抽出され、階層的に並べられます。
たとえば、XHMLドキュメントではh1、h2、h3、...、h6の各要素が階層的に表示されます。
とある。
ただしXHTML、SVG及び両者のコンパウンドドキュメントは特に設定することなくアウトライン表示可能とのこと。アウトラインの設定方法はここ。
ただしXHTML、SVG及び両者のコンパウンドドキュメントは特に設定することなくアウトライン表示可能とのこと。アウトラインの設定方法はここ。
起動してみたところ、インタフェイス的にはこれまでと大きく変わっていないようだが、よくみるとファイル履歴表示や再読込ボタンの追加、さらにはコンポーネントの更新チェックが可能になるなど、随所で利便性の向上が図られている。……にしても、反応が鈍い。普段使用しているLibretto L5では実用にならない、かも。
xfy Basic Edition操作マニュアルを始めとするドキュメント類はβ版の時と比較して大幅に充実した。まずはこちらにあるドキュメントに目を通さねばと思うが、相当の分量だぞこりゃ。Zz……
xfy Basic Edition操作マニュアルを始めとするドキュメント類はβ版の時と比較して大幅に充実した。まずはこちらにあるドキュメントに目を通さねばと思うが、相当の分量だぞこりゃ。Zz……
- 2005年10月31日
製品版、なんと無償配布\(^-^)/
本日、統合XMLアプリケーション開発・実行環境「xfy Basic Edition 1.0」製品版を10月31日(月)より提供開始とのリリース記事が発表された。
今回提供するxfy Basic Edition 1.0およびxfy Developer's Toolkit 1.0は、
個人使用と学術研究目的使用に加えて、企業内での使用においても無償とします
余計なお世話だろうが、斯くなる上は何としてもこのビジネスが成功してもらいたいと切に願うばかりである。
- 2005年10月28日
緊急xfytech.com Off-line Meeting開催
JustMeet2006に行ってきた。受付で渡された資料はすべてConceptBase Search関連のものばかり。辛うじて展示ブースに2種類、簡素なパンフレットが置かれていたのみ。やはり急遽、お披露目することにしたのだろうか。
にもかかわらず基調講演と特別講演はxfy一色で、ゲストスピーカーにはRELAXの、と言うよりMr.XML村田真さんが\(^0^)/
午後、「xfy Technologyとその応用」が終演したところで
にもかかわらず基調講演と特別講演はxfy一色で、ゲストスピーカーにはRELAXの、と言うよりMr.XML村田真さんが\(^0^)/
午後、「xfy Technologyとその応用」が終演したところで
この後、xfytech.com Off-line Meetingを開催いたしますので云々……
とのアナウンスがあった。おいおい聞いてないぞ、そんなの。
後ほど確認したところ、突如決定したので昨日登録者宛にメールを送ったとのこと。来ていない(; ;)
慌てて受付で頼み込み参加させてもらった。受付にいた人はなんとxfy Community YOKOSO Forumのmoderator氏だった。思わず名刺もらう(ミ~ハ~♪
Off-line Meetingは昨日の今日ということもあって、参加者は10名弱。寂し~。が、始まってすぐにJustsystemの社長、専務、さらにxfy関係者が続々合流し計20名に(^^;) xfyに賭けるJustsystem 側の並々ならぬ決意が伝わってくる布陣であった。
近くリリースする製品版のことや(無料との噂も)、今後の展開、フリートークなど、1時間足らずだったが貴重な話を聞くことができた。今後も機会があればこういう場をぜひ設けてもらいたいと思う。もっと早めにわかっていればぜひ声をかけたい人もいたし……。
後ほど確認したところ、突如決定したので昨日登録者宛にメールを送ったとのこと。来ていない(; ;)
慌てて受付で頼み込み参加させてもらった。受付にいた人はなんとxfy Community YOKOSO Forumのmoderator氏だった。思わず名刺もらう(ミ~ハ~♪
Off-line Meetingは昨日の今日ということもあって、参加者は10名弱。寂し~。が、始まってすぐにJustsystemの社長、専務、さらにxfy関係者が続々合流し計20名に(^^;) xfyに賭けるJustsystem 側の並々ならぬ決意が伝わってくる布陣であった。
近くリリースする製品版のことや(無料との噂も)、今後の展開、フリートークなど、1時間足らずだったが貴重な話を聞くことができた。今後も機会があればこういう場をぜひ設けてもらいたいと思う。もっと早めにわかっていればぜひ声をかけたい人もいたし……。
Off-line Meetingでもらったお土産


ところで。ここへきてxfyは着々と企業向けソリューションプラットフォームとしての体裁を整えつつあるが、一方でぼくのような個人ユーザにとっても魅力的なツールなので、そうした匂いはどこかで残してもらえたらなあ、と思う。たしかCS Searchも当初は個人向けのデスクトップ検索ツールだったなあ、などと述懐すること小一時間。
もちろん個人向けのアプリケーションなどもはや金にならない時代なのだから、ぜひ企業向けソリューションとして大きな成功を収め、Justsystemには成長・発展を遂げて欲しい。そして、その利益を個人向けの……おいおい(^^ゞ
もちろん個人向けのアプリケーションなどもはや金にならない時代なのだから、ぜひ企業向けソリューションとして大きな成功を収め、Justsystemには成長・発展を遂げて欲しい。そして、その利益を個人向けの……おいおい(^^ゞ
そんな身勝手きわまりない個人ユーザの妄言として、前回のエントリにも書いたのだが、編集不能でも良いのでxfyで作成した文書をブラウザに吐き出すコンポーネントを標準で添付してくれると嬉しい。そうするとxfy+browser=Acrobat+Acrobat Readerという図式になり、XHTML文書がPDF文書に取って代わっていくのでは?(んなこたぁないか)
- 2005年10月19日
JustMeet2006で国内発表!
ジャストシステムが今月19日に開催を予定しているプライベートカンファレンスJustMeetでxfyのプレゼンテーションがあるようだ。開催趣旨に載っていなかったので見落としていたが、プログラム・講演のところに「xfy Technologyとその応用」とある。日本国内では初めてのxfyお披露目となる。
日程の調整がつけば行ってみたい。
この間、いろいろやってみて改めて感じたのは、やっぱりブラウザ上で作成・編集できたらいいよなあ、ということ。もちろん使われ方にもよるのだろうけど……。
日程の調整がつけば行ってみたい。
この間、いろいろやってみて改めて感じたのは、やっぱりブラウザ上で作成・編集できたらいいよなあ、ということ。もちろん使われ方にもよるのだろうけど……。
と、こんなことを書き連ねつつふと過去の記述を見直していたら7月28日のエントリにMr.Xなる人物が追記をしてくれていた。ビックリ!
全然気がつかなくて2ヶ月も放置してしまったよ。ごめんなさい。
scriptsフォルダはbinの兄弟フォルダですよ、とある。
えーと、これはXVCDを作成したらscriptsフォルダをbinフォルダと同じレイヤに作れということかな。
まずは感謝 > Mr.X
全然気がつかなくて2ヶ月も放置してしまったよ。ごめんなさい。
scriptsフォルダはbinの兄弟フォルダですよ、とある。
えーと、これはXVCDを作成したらscriptsフォルダをbinフォルダと同じレイヤに作れということかな。
まずは感謝 > Mr.X
それにしてもこんなページを見ている人がいたなんて……ちと恥ずかしい……
- 2005年10月5日
BE(β)Release 3
Release 3が配布された。ヒストリディレクトリに起因した起動トラブルが修正されたとのこと。xfy Forumでアナウンスされていた現象だ。
ぼくの抱える問題とは無関係でした。
ぼくの抱える問題とは無関係でした。
- 2005年8月3日
再読込のたびにエラー発生
先日も書いたがxvcdコンポーネントの配置や記述を変更後、XML文書に反映させるために表示→最新の情報に更新を実行すると、そのたびに必ず致命的エラーが発生する。xfrコンポーネントを扱った後も同様だ。
文書が落ちるということはないのだが、そのたびに再起動させるのは結構面倒である。特にまだ扱いもよくわからない段階ではあれやこれやと書き換えたりすることが多いので尚更だ。
ただし、サンプル文書ではこのようなことは起こらないでの、もしかするとぼく固有の問題かも……(可能性大)。
それとやはり再読込ボタンはあった方が便利だと思う。TP版には存在していたぞ、たしか。
文書が落ちるということはないのだが、そのたびに再起動させるのは結構面倒である。特にまだ扱いもよくわからない段階ではあれやこれやと書き換えたりすることが多いので尚更だ。
ただし、サンプル文書ではこのようなことは起こらないでの、もしかするとぼく固有の問題かも……(可能性大)。
それとやはり再読込ボタンはあった方が便利だと思う。TP版には存在していたぞ、たしか。
- 2005年7月31日
xvcdでジタバタ:calendarコンポーネント編
調子に乗ってサンプルxvcdを次々ビルドしてみたところ、calendarがうまく取り込めない。icon表示のみとなってしまう。
いったんcalendar.xmlを表示させてみるときちんと出てくる。Write Scheduleをクリックしてソースを見てみると
いったんcalendar.xmlを表示させてみるときちんと出てくる。Write Scheduleをクリックしてソースを見てみると
"<cal:month>
"<cal:month year="2005" index="7">
"<cal:day index="29" type="normal" />
"</cal:month>
と追記された(行頭"マークは実際には無関係。当該Wikiが解釈してしまうために任意で附与した)。そこで
"<cal:month />
と記述してやるとようやく表示された。こりゃあ、先が思いやられるぞ、道仔。
- 2005年7月29日
BE(β)Release 2配布
本日、Release2が配布された。更新内容は“幾つかのメディアタイプの扱いにおける問題の解決”となっているが個人的には遭遇していないので具体的なことは不明。同時にDeveloper's Toolkitも更新されたが、こちらについては何の記載もない。
xvcdについてのジタバタだが、まず同梱されていたaddressbookを試しに取り込んでみた。
チュートリアル:XVCDで作成するボキャブラリコンポーネントによればDeveloper's Toolkitがインストールされている場合は
チュートリアル:XVCDで作成するボキャブラリコンポーネントによればDeveloper's Toolkitがインストールされている場合は
作成したXVCDファイルをxfy technologyユーザエージェントの実行環境にあるscriptsフォルダに配置して、XML文書に自動的に割り付けることができます
とあるが、scriptsフォルダが見当たらず、さらにフォルダを作成してその中にaddressbook.xvcdを放り込んでみたが、自動的に割り付けられなかった(xfy technologyユーザエージェントの実行環境フォルダとはbinフォルダのことだと概要:xfy technologyの機能拡張に記載されている)。
そこで、
そこで、
そのほか、次の方法でXVCDをXML文書に割り付けることができます
とあったので、以下の処理命令を記述してみた。
<?com.xfytec vocabulary-connection href="file:///[addressbook.
おお、みごとにXML文書中にビルドされたではないか!
一番簡単なのはxvcdをXML文書と同じディレクトリに配置して
一番簡単なのはxvcdをXML文書と同じディレクトリに配置して
<?com.xfytec vocabulary-connection href="addressbook.xvcd" ?>
とすることだろう。
……と書いて気が付いたのだが、前掲の
……と書いて気が付いたのだが、前掲の
作成したXVCDファイルをxfy technologyユーザエージェントの実行環境にあるscriptsフォルダに配置
とは、“XML文書と同じフォルダに配置”の誤りなのだろうかと思いやってみたがダメだった。しかたなく再び処理命令を記述して表示→最新の情報に更新を実行したところ、致命的なエラーとなって再起動を促された(再現性あり)。
尚、サンプルを見るとaddressbook.xfrも割り付けることになっているようだが、記述がなくても問題なく機能する。なんだろうこれ、と思って調べてみると、
リファレンス:XFR(XML Formatting Rule)という文書が。
尚、サンプルを見るとaddressbook.xfrも割り付けることになっているようだが、記述がなくても問題なく機能する。なんだろうこれ、と思って調べてみると、
リファレンス:XFR(XML Formatting Rule)という文書が。
XFRは、保存するXML文書の書式を整える書式整形規則を記述するために使用します。XML文書で使用する要素ごとに、その要素の配置方法や要素内の空白の扱い、インデント位置を指定して、XML文書をソース表示したときの体裁を整えます
とのこと。ざっと眺めたが当面デフォルトのままで構わないようなので今回は無視することとした(でいいよな)。
とりあえず用意されたコンポーネントの取り込みはできた、ということで納得。今後はいよいよ、プライベートボキャブラリの作成に挑戦である。大丈夫か……。
とりあえず用意されたコンポーネントの取り込みはできた、ということで納得。今後はいよいよ、プライベートボキャブラリの作成に挑戦である。大丈夫か……。
- scripts は bin の子フォルダではなく兄弟フォルダです -- Mr.X (2005-08-03 23:47:52)
- こんなかたちでコメント漬けて良かったんでしょうか?適当に編集してください。 -- Mr.X (2005-08-03 23:48:51)
- ありがとうございます。全く気づかなくて2ヶ月も放置してしまいました。すみません。 -- taox (2005-10-05 23:13:36)
- 2005年7月28日
xvcdでジタバタ
xfyサイトに上がっているxfy technology技術文書インデックスによれば
対話形式で実行して簡単にボキャブラリコンポーネントを作成できるツールを、xfy Developer's Toolkitに含めて提供することを予定しています
とのことだが、それまで待っていられないので少しジタバタしてみることにする。
と言っても、上記文書はJava One 2005に合わせてアップされたためかXSLTやJavaをスラスラ書ける人相手の内容になっていてぼくにはほとんど役に立ちません。どうせいッてのよ、これで……。
と言っても、上記文書はJava One 2005に合わせてアップされたためかXSLTやJavaをスラスラ書ける人相手の内容になっていてぼくにはほとんど役に立ちません。どうせいッてのよ、これで……。
- 2005年7月25日
FireFoxでXML複合文書を表示
xfyで複合文書を試作してみたが(きわめて稚拙なやつね)現状、xfyがないとそれを表示することができない。FireFoxで閲覧できれば第三者に文書を渡すこともできるのに。
「そんなのXSLTとかで処理すりゃいい話だろ」「て言うかXVCDさっさと覚えろよ」とか突っ込まれちゃいそうだけど、スクリプト書くの面倒、いや自信ないし……
なんてことを考えていたら、知らぬが無知蒙昧、MozillaプロジェクトでXML関連の実装を進めているらしい。
それを知ったのは、BE(β)に同梱されていた複合文書のサンプル(compound1.xml)をFirefoxで表示させようとした時だ。
MathML用のフォントCMYS10、CMEX10、Math2、Math4を入れろと叱られ、わからなければhttp://www.mozilla.org/projects/mathml/fontsを見ろとあった。
はいはい、とTrueType形式の最新バージョンの特殊MathematicaフォントMathematica 4.2をダウンロードし、指示どおり次の2カ所にフォントを流し込んだ。
「そんなのXSLTとかで処理すりゃいい話だろ」「て言うかXVCDさっさと覚えろよ」とか突っ込まれちゃいそうだけど、スクリプト書くの面倒、いや自信ないし……
なんてことを考えていたら、知らぬが無知蒙昧、MozillaプロジェクトでXML関連の実装を進めているらしい。
それを知ったのは、BE(β)に同梱されていた複合文書のサンプル(compound1.xml)をFirefoxで表示させようとした時だ。
MathML用のフォントCMYS10、CMEX10、Math2、Math4を入れろと叱られ、わからなければhttp://www.mozilla.org/projects/mathml/fontsを見ろとあった。
はいはい、とTrueType形式の最新バージョンの特殊MathematicaフォントMathematica 4.2をダウンロードし、指示どおり次の2カ所にフォントを流し込んだ。
c:\Windows\Fonts\
c:\Wolfram Research\Mathematica\4.2\SystemFiles\Fonts\TrueType\
でも、やはりダメ。Mathematica 4.2にCMYS10、CMEX10、Math2、Math4は入っていないらしい(て、間違ってるかも)。
見ると、√記号の部分のフォントが墨塗り状態だ。刑務所からの手紙か。
例によって深追いは止めて^_^;)、次はSVGの表示を試みる。
Mozilla SVGプロジェクトのサイトを訪れると次のような御神託が。
見ると、√記号の部分のフォントが墨塗り状態だ。刑務所からの手紙か。
例によって深追いは止めて^_^;)、次はSVGの表示を試みる。
Mozilla SVGプロジェクトのサイトを訪れると次のような御神託が。
SVGは現時点で、Windows 版 Firefox(GDI+ 描画バックエンドを使用)および
Mac OS X 版 Firefox (Cairo 描画バックエンドを使用)の
ナイトリービルド に含まれています。Windows XP 以外の Windows システムでは GDI+ をインストールする必要があります。Linux は近い将来 Cairo を用いて使用できるようになる予定です(Bug 286422)。
ナイトリービルド(Nightly Builds)とは動作保証なしのテスト版のことらしい。大丈夫かなあ、などと心配する間もなくFor Developerのページからfirefox-1.0+.en-US.win32.installer.exeをダウンロードした。
ファイル名を見ると、現行のFireFox v1.04とは異なるものらしい。
c:\Deer Park Alpha2フォルダにインストール後、起動させてみると、やっぱりである。ブックマークや機能拡張はそのまま引き継いでくれたがメニューは英文字。Options→LanguagesでJapanese[ja]を追加しておく。
サンプル複合文書を読み込ませると、みごとSVGが表示された。半分満足、半分失望で今日の作業を終える。
ファイル名を見ると、現行のFireFox v1.04とは異なるものらしい。
c:\Deer Park Alpha2フォルダにインストール後、起動させてみると、やっぱりである。ブックマークや機能拡張はそのまま引き継いでくれたがメニューは英文字。Options→LanguagesでJapanese[ja]を追加しておく。
サンプル複合文書を読み込ませると、みごとSVGが表示された。半分満足、半分失望で今日の作業を終える。
- 2005年7月11日
Sauce Likeで作業ができない
WYSIWYG画面での入力・編集は確かにラクチンだが、時にはスクリプト画面で直接編集したいこともある。
xfyはその両モードを備えているところがミソだと思っていたのだが、なぜか今回のBE(β)ではスクリプト画面、つまりSauce Like&Sauce Like Twinモードにカーソルが入らない。確かTP版では作業できたはずだったのだが。
試しにMacintoshに残っていたTP版で操作してみたら問題なく作業できた。
ぼくの環境がおかしいのか、それともBE(β)では作業不可になったのか。
面倒なのでxfy Community のForumに質問を投げてしまった。バカ晒すようでイヤだったのだが……。
xfyはその両モードを備えているところがミソだと思っていたのだが、なぜか今回のBE(β)ではスクリプト画面、つまりSauce Like&Sauce Like Twinモードにカーソルが入らない。確かTP版では作業できたはずだったのだが。
試しにMacintoshに残っていたTP版で操作してみたら問題なく作業できた。
ぼくの環境がおかしいのか、それともBE(β)では作業不可になったのか。
面倒なのでxfy Community のForumに質問を投げてしまった。バカ晒すようでイヤだったのだが……。
追記:
10日に回答がもらえた。
10日に回答がもらえた。
ソースライクの編集では別途各XMLボキャブラリで想定している型情報などに沿った編集は出来ない(例えば、SVGで数値を入力すべき所に数値以外のデータを書き込める)ため、あえてはずしてあります
とのこと。納得。
- 2005年7月9日
インプレスTVのJavaOneレポート
後半はxfy一色。
- 2005年7月8日
Duke Avatar
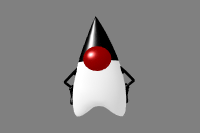
xfyが100%PureJavaコードで書かれているので。
- 2005年7月8日
既存のXHTML文書をxfyで編集してみた
WYSIWYG環境での変更は確かにラクチン。タグを手打ちするよりも効率はいい。
ただ、始めに既存文書がエラーとなってなかなかxfy上で開けなかった。リンク先のURLにh1の文字が混じっていたのが原因でした。
ううむ、手強い……。
ただ、始めに既存文書がエラーとなってなかなかxfy上で開けなかった。リンク先のURLにh1の文字が混じっていたのが原因でした。
ううむ、手強い……。
- 2005年7月8日
InfoPathとの印象の違いを書いている人がいた
- 2005年7月7日
1.0BE(β)の第一印象
Version 1.0 BasicEdition(β)が日本時間6月28日午前0時に総本山にアップされた。コミュニティ登録後、ダウンロード(夕方からサイトリニュアルが始まっていたので待ち構えていたのでした)。
デザインがぐっとシンプルになって動作も思ったより軽快だ。TP版はもう死んじゃったのかと思ったくらい鈍かったもの。
デザインがぐっとシンプルになって動作も思ったより軽快だ。TP版はもう死んじゃったのかと思ったくらい鈍かったもの。
標準添付のテンプレートは、XHTMLとSVG。これにスプレッドシートとプレゼンが追加されたら……Ark2になっちゃうじゃない。
試しにXHTMLを書き出したら全てのタグにxhtmlという名前空間接頭辞が。
試しにXHTMLを書き出したら全てのタグにxhtmlという名前空間接頭辞が。
<xhtml:html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xhtml:head>文字列</xhtml:head>
そりゃそうだ、コンパウンドドキュメント環境だもんね。
段々慣れたらリッチ環境はこれに移行するか(できるか、だろ?)。
段々慣れたらリッチ環境はこれに移行するか(できるか、だろ?)。
- 2005年7月6日