| ◇おしゃべり◇ |
| BBS |

| 百地章 | 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) |
| 阪本昌成 | 「統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という」(『憲法1 国制クラシック』p.26) |
| 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。 これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。 後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。 が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) | |
| 長谷部恭男 | 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。 広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) |
| 芦部信喜 | ※後述するように、芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。 |
| 佐藤幸治 | ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 |
| りっけん-しゅぎ 【立憲主義】 (constitutionalism) <広辞苑> |
憲法を制定し、それに従って統治する、という政治のあり方。 この場合の憲法とは、<1>人権の保障を宣言し、<2>権力分立を原理とする統治機構を定めた憲法、を指し、そうでない場合を外見的立憲主義という。 | ||
| りっけんしゅぎ 【立憲主義】 constitutionlism <日本語版ブリタニカ> |
(1) | 法の支配 rule of the(※注:原文ママ) law に類似した意味をもち、①およそ権力保持者の恣意によってではなく、②法に従って権力が行使されるべきでる、という政治原則をいう。 | |
| (2) | 狭義においては、とくに | ||
| <1> | 政治権力を複数の権力保持者に分有せしめ、 | ||
| <2> | その相互的抑制作用を通じて権力の濫用を防止し、 | ||
| <3> | もって、権力名宛人の利益を守り、政治体系の保全を図ろうとする、政治原則である | ||
| (2)狭義における立憲主義は、既に古代ギリシア、ローマ、あるいは中世ヨーロッパの一定の都市国家などに見出されるが、近代市民革命を経て、近代立憲主義に変貌した。そこでは、 | |||
| [1] | 国民の一定の範囲における国政参加を前提に、 | ||
| [2] | 権力分立構造を通じて国民個々人の権利・自由の保全を図ろうとする意図が明確にされ、 | ||
| [3] | それを具備する成文憲法を制定することが肝要である、と考えられるようになった。 | ||
| 立憲主義に立脚する民主制が立憲民主制であり、君主制と結合している場合が立憲君主制である。 | |||
| constitutionalism <ODE> |
[mass noun] constitutional government: | ||
| ・adherence to a constitutional system of government: | |||
| constitutionalism <英文wikipedia> |
Constitutionalism, in its most general meaning, is "a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law".[1] A political organization is constitutional to the extent that it "contain[s] institutionalized mechanisms of power control for the protection of the interests and liberties of the citizenry, including those that may be in the minority".[2] As described by political scientist and constitutional scholar David Fellman: Constitutionalism is descriptive of a complicated concept, deeply imbedded in historical experience, which subjects the officials who exercise governmental powers to the limitations of a higher law. Constitutionalism proclaims the desirability of the rule of law as opposed to rule by the arbitrary judgment or mere fiat of public officials…. Throughout the literature dealing with modern public law and the foundations of statecraft the central element of the concept of constitutionalism is that in political society government officials are not free to do anything they please in any manner they choose; they are bound to observe both the limitations on power and the procedures which are set out in the supreme, constitutional law of the community. It may therefore be said that the touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law |
| Usage Constitutionalism has prescriptive and descriptive uses. Law professor Gerhard Casper captured this aspect of the term in noting that: "Constitutionalism has both descriptive and prescriptive connotations. Used descriptively, it refers chiefly to the historical struggle for constitutional recognition of the people's right to 'consent' and certain other rights, freedoms, and privileges…. Used prescriptively … its meaning incorporates those features of government seen as the essential elements of the … Constitution."[4] | |
| Descriptive One example of constitutionalism's descriptive use is law professor Bernard Schwartz's 5 volume compilation of sources seeking to trace the origins of the U.S. Bill of Rights.[5] Beginning with English antecedents going back to the Magna Carta (1215), Schwartz explores the presence and development of ideas of individual freedoms and privileges through colonial charters and legal understandings. Then, in carrying the story forward, he identifies revolutionary declarations and constitutions, documents and judicial decisions of the Confederation period and the formation of the federal Constitution. Finally, he turns to the debates over the federal Constitution's ratification that ultimately provided mounting pressure for a federal bill of rights. While hardly presenting a "straight-line," the account illustrates the historical struggle to recognize and enshrine constitutional rights and principles in a constitutional order. | |
| Prescriptive In contrast to describing what constitutions are, a prescriptive approach addresses what a constitution should be. As presented by Canadian philosopher Wil Waluchow, constitutionalism embodies "the idea … that government can and should be legally limited in its powers, and that its authority depends on its observing these limitations. This idea brings with it a host of vexing questions of interest not only to legal scholars, but to anyone keen to explore the legal and philosophical foundations of the state."[6] One example of this prescriptive approach was the project of the National Municipal League[7] to develop a model state constitution.[8] | |
| Authority of government Whether reflecting a descriptive or prescriptive focus, treatments of the concept of constitutionalism all deal with the legitimacy of government. One recent assessment of American constitutionalism, for example, notes that the idea of constitutionalism serves to define what it is that "grants and guides the legitimate exercise of government authority."[9] Similarly, historian Gordon S. Wood described this American constitutionalism as "advanced thinking" on the nature of constitutions in which the constitution was conceived to be "a" set of fundamental rules by which even the supreme power of the state shall be governed.'"[10] Ultimately, American constitutionalism came to rest on the collective sovereignty of the people - the source that legitimized American governments. | |
| Fundamental law empowering and limiting government One of the most salient features of constitutionalism is that it describes and prescribes both the source and the limits of government power. William H. Hamilton has captured this dual aspect by noting that constitutionalism "is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order."[11] (以下省略) | |
| (翻訳) |
| ほう-の-しはい 【法の支配】 (rule of law) <広辞苑> |
イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。 コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 | |
| ほうのしはい 【法の支配】 rule of law <日本語版ブリタニカ> |
法至上主義的な思想、原則。 | |
| (1) | どんな人でも、通常裁判所が適用する法律以外のものに支配されない、あるいは、 | |
| (2) | 被治者のみでなく、統治者・統治諸機関も、法の支配に服さなければならぬ、とする、「法のもとにおける統治」の原理。 | |
| イギリスの伝統に根ざす思想であり、自然法思想にも淵源をもつ、法の権力に対する優位性の主張である。 | ||
| A.ダイシーは、その著『憲法入門』(1885)のなかで、①議会主権と、②法の支配、がイギリスの2大法原理である、としたが、 | ||
| <1> | ここから、人間とその自由を権力から守るイギリス型法治主義の原則が確立され、 | |
| <2> | アメリカにおいては、司法権優越の原理を生んだ。 | |
| 20世紀に入り、経済・社会情勢の著しい変化につれ、伝統的な法支配の原則に対するいろいろな批判も起っている。 | ||
| rule of law <collins> |
The rule of law refers to a situation in which the people in a society <1> obey its laws and <2> enable it to function properly. | |
| (翻訳) 法の支配とは、ある社会における人々が、<1>その諸法を遵守しており、かつ、<2>社会を適切に機能させている、状況をいう。 | ||
| + | ... |
※以下、芦部憲法論の具体的内容をチェック。 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 p.3以下 <目次> 一. 国家と法一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力をもつ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会を国家と呼ぶ。 従って、領土と人と権力は、古くから国家の三要素と言われてきた。 この国家(*)という統治団体の存在を基礎づける基本法、それが通常、憲法と呼ばれてきた法である。
二. 憲法の意味憲法を勉強するには、まず、憲法とは何かを明らかにしなければならない。 研究の対象を正確に捉えることは、あらゆる学問の出発点である。 憲法の意味を本格的に解明しようとすると、憲法がどのようにしてつくられてきたのか、どのような思想に支えられて登場したのか、という憲法思想史の背景を研究しなければならないが、ここでは、憲法の意味とその法的特質に関する基本的な事柄について概説的に説明するにとどめる。 ◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法憲法の概念は多義的であるが、重要なものとして三つ挙げることができる。 ◇(一). 形式的意味これは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である。 形式的意味の憲法と呼ばれる。 たとえば、現代日本においては「日本国憲法」がそれにあたる。 この意味の憲法は、その内容がどのようなものであるかには関わらない。 ◇(ニ). 実質的意味これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。 成文であると不文であるとを問わない。 実質的意味の憲法と呼ばれる。 この実質的意味の憲法には二つのものがある。 (1). 固有の意味国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。 国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。 この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 (2). 立憲的意味実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。 一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。 18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。 その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。 この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。 以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。 従って、憲法学の対象とする憲法とは、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。 そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 ◆2. 立憲的憲法の特色◇(一). 淵源立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。 中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。 この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。 もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、
このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 ◇(ニ). 形式と性質立憲的憲法は、その形式の面では成文法であり、その性質においては硬性(通常の法律よりも難しい手続によらなければ改正できないこと)であるのが普通であるが、それはなぜであろうか。 (1). 成文憲法まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることも出来るが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。 それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。 (2). 硬性憲法また、立憲的憲法が硬性(rigid)であることの理由も、近代自然法学の主張した自然権および社会契約説の思想の大きな影響による。 つまり、憲法は社会契約を具体化する根本契約であり、国民の不可侵の自然権を保障するものであるから、憲法によってつくられた権力である立法権は根本法たる憲法を改正する資格をもつことは出来ず(それは国民のみに許される)、立法権は憲法に拘束される、従って憲法の改正は特別の手続によって行わなければならない、と考えられたのである(*)。
三. 憲法の分類◆1. 伝統的な分類憲法の意味の理解を助けるために、憲法はいろいろの観点から類別されてきた。 ◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類まず、
しかし、このような伝統的な分類は、必ずしも現実の憲法のあり方を実際に反映するものではないことに注意しなければならない。 たとえば、①については、イギリスのように単一の成文憲法典をもたない国もあるが、イギリスでも、実質的に憲法にあたる事項は多数の法律で定められており、基本的な事項は、実際には、容易に改正されない。 ところが、②にいう硬性の程度が強い憲法でも、実際にはしばしば改正される国は少なくない。 ◇(ニ). 国家形態による分類また、憲法の定める国家形態ないし統治形態に関する分類として、
たとえば、君主制でも、イギリスのように民主政治が確立している国もあり、共和制でも、政治が非民主的な国は少なくない(従って、民主制か独裁制かという観点からの分類の方が意味がある)。 大統領制や議院内閣制にも、いろいろの形態がある(例えば、両者の混合形態もあるし、同じ大統領制でも、アメリカのような民主的なもの、南米ないし中近東の諸国のような独裁的なもの、の別がある)。
◆2. 機能的な分類このような形式的な分類に対して、戦後、憲法が現実の政治過程において実際にもつ機能に着目した分類が主張されるようになった。 たとえば、レーヴェンシュタイン(Karl Loewenstein, 1891-1973)という学者は、
このような存在論的(ontological)な分類は、主観的な判断が入る可能性がある点で問題もあるが、立憲的意味の憲法が、どの程度現実の国家生活において実際に妥当しているのかを測るうえで、有用なものであると言えよう。 四. 憲法規範の特質以上述べてきたところのまとめを兼ねて、近代憲法の特質を箇条的に列挙すると、次のようになる。 ◆1. 自由の基礎法近代憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。 それは、自由の法秩序であり、自由主義の所産である。 もちろん、憲法は国家の機関を定め、それぞれの機関に国家作用を授権する。 すなわち、通常は立法権、司法権、行政権、および憲法改正手続等についての規定が設けられる。 この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範が憲法に不可欠なものであることは言うまでもない。 しかし、この組織規範・授権規範は憲法の中核をなすものではない。 それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。 このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。 この自然権を実定化した人権規定は、憲法の中核を構成する「根本規範(*)」であり、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。
◆2. 制限規範憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。 このことは、近代憲法の二つの構成要素である権利章典と統治機構の関係を考えるうえで、とくに重要である。 本来、近代憲法は、すべて個人は互いに平等な存在であり、生まれながら自然権を有するものであることを前提として、それを実定化するという形で制定された。 それは、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎においている。 従って、政治権力の究極の根拠も個人(すなわち国民)に存しなくてはならないから、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定権力(*)の保持者であると考えられた。 このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にあるのである。 また、国民の憲法制定権力は、実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので、人権規範は主権原理とも不可分の関係にあることになる(第18章三3図表参照)。
◆3. 最高法規憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。 日本国憲法98条が、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めているのは、その趣旨を明らかにしたものである(*)。 もっとも、憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。 従って、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって、とくに憲法の本質的な特性として挙げるには及ばないということになろう。 最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が《実質的に法律と異なる》という点に求められなければならない。 つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。 これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。 日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であることを宣言する97条は、硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。 このように、憲法の実質的最高規範性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の《根本規範》(basic norms)と考えるので、憲法規範の《価値序列》を当然に認めることになる。 この考えが、人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果すかについては、後に述べることにする(第五章-第13章・第18章)。
なお、憲法の最高法規性と関連して、憲法98条の列挙から「条約」が除外されていることが問題となるが、これは条約が憲法に優位することを意味するわけではない。 両者の効力の優劣関係については後述する(第18章ニ4(ニ)(1)参照)。 条約は公布されると原則としてただちに国内法としての効力をもつが、その効力は通説によれば、憲法と法律の中間にあるものと解されている。 実務の取扱いもそうである。 ただ、98条2項に言う「確立された国際法規」すなわち、一般に承認され実行されている慣習国際法を内容とする条約については、憲法に優位すると解する有力説がある。 地方公共団体の条例・規則は、「法律・命令」に準ずるものとみることが出来るので(第17章ニ3参照)、それに含まれると解される。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は法の支配(rule of law)の原理と密接に関連する。 ◆1. 法の支配法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。 それは、専制的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。 ジェイムズ一世の暴政を批判して、クック(Edward Coke, 1552-1634)が引用した「国王は何人の下にもあるべきでない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Henry de Bracton, ?-1268)の言葉は、法の支配の本質をよく表している。 法の支配の内容として重要なものは、現在、
◆2. 「法の支配」と「法治国家」「法の支配」の原理に類似するものに、《戦前の》ドイツの「法治主義」ないしは「法治国家」の観念がある。 この観念は、法によって権力を制限しようとする点においては「法の支配」の原理と同じ意図を有するが、少なくとも、次の二点において両者は著しく異なる。 ◇(一). 民主的な立法過程との関係第一に、「法の支配」は、立憲主義の進展とともに、市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図ること、従って権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定すること、を建前とする原理であることが明確となり、その点で民主主義と結合するものと考えられたことである。 これに対して、戦前のドイツの法治国家(Rechtsstaat)の観念は、そのような民主的な政治制度と結びついて構成されたものではない。 もっぱら、国家作用が行われる形式または手続を示すものに過ぎない。 従って、それは、如何なる政治体制とも結合し得る形式的な観念であった。 ◇(ニ). 「法」の意味第二に、「法の支配」に言う「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。 これに対して、「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることが出来る容器のような)形式的な法律に過ぎなかった。 そこでは、議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかったのである。 もっとも、《戦後の》ドイツでは、ナチズムの苦い経験とその反省に基づいて、法律の内容の正当性を要求し、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用されるに至った。 その意味で、現在のドイツは、戦前の形式的法治国家から《実質的法治国家》へと移行しており、法治主義は英米法に言う「法の支配」の原理とほぼ同じ意味をもつようになっている。 ◆3. 立憲主義の展開◇(一). 自由国家の時代近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。 そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。 そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。 当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 ◇(ニ). 社会国家の時代しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。 その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。 そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。 こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。
◆4. 立憲主義の現代的意義◇(一). 立憲主義と社会国家立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。 そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。 しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。 この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。 戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。 すなわち、
民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。 戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。
|
| + | ... |
LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ 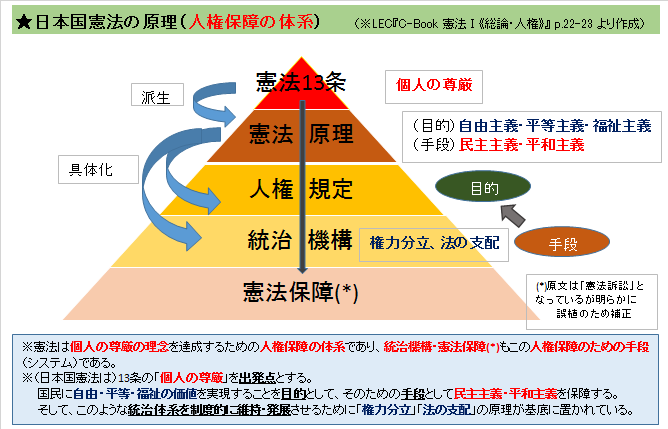
※上図は基本的に芦部信喜説(通説)に基づく憲法構造の理解だが、何故13条が根本原理とされるのか根拠不明であり、芦部説に対する批判がそのまま当てはまる(→芦部信喜『憲法 第五版』抜粋参照) 第一編 憲法総論 <目次> ■1.憲法の意義と立憲主義の展開◆1-1 憲法の意義◇一 憲法の意味1 はじめに(1) 憲法の必要性
(2) 憲法の意義
2 憲法と国家
3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法
4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法
◇ニ 憲法の法源法源(Source of Law)とは、かなり多義的に使われるが、法解釈で使われる法源は法の認識根拠、存立形態をいい、具体的には裁判官が判決理由で援用して裁判の理由と為し得る法形式を意味する。 日本国憲法が明示的に認めている法源としては、憲法改正、条約、法律、議院規則、最高裁判所規則、命令、政令、条例がある。 法源のなかで、憲法規範の存在形式を有するものが憲法の法源である。 憲法の法源とは、実質的意味の憲法の規範が存在する様々な法形式をいう。 1 成文法源実質的意味の憲法が成文化されるときは、まず、憲法という形式で行われるのが通常であるが、すべてを規定し尽くすということは殆ど不可能なので、憲法典では原則的なことのみを決め、より具体的な定めは他の法形式に委ねるのが通常である。 日本国憲法の成文法源として以下のものが挙げられる。
2 不文法源一般に不文法源としては慣習法と判例が問題となるが、憲法についても憲法慣習(法)と憲法判例が問題となる。
◇三 憲法の分類
◇四 憲法規範の特質1 授権規範性
2 制限規範性
3 最高法規性
4 基本価値秩序としての憲法
◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開(省略) ■2. 憲法の基本原理◆2-1 基本原理◆◆2-1-1 根本価値としての個人の尊厳
◆◆2-1-2 憲法原理◇一 五つの憲法原理の相互関係
◇ニ 自由主義(省略) ◇三 民主主義(省略) ◇四 平等主義(省略) ◇五 福祉主義(省略) ◇六 平和主義(省略) ◆◆2-2 法の支配◇一 法治主義1.はじめに定義:司法は独立した裁判所により法律を適用して行われ、行政は法律に基づき法律を適用して行われるという原則
2.分類
3.法律の留保
◇二 法の支配1.はじめに定義:すべての国家権力が正しい法に拘束されるという原則
2.法の支配の内容
3.日本国憲法における法の支配の現れ「正しい法 = 憲法」によって「法の支配 = 憲法による支配」
◇三 「法の支配」と「法治主義」1.「法の支配」と「法治主義」
2.憲法適合性の判断権者
■3. 憲法の持続と変動◆3-1 憲法の変動◆◆3-1-1 憲法改正◇一 憲法改正1 意義憲法改正とは、
2 改正の手続(省略) 3 形式的効力(省略) 4 国民投票無効の訴訟(省略) ◇ニ 憲法改正の限界《問題の所在》
《考え方の筋道》
《アドヴァンス》
《One Point》
◆◆3-1-2 憲法の変遷◇1 意義憲法の変遷とは、一般には、憲法の定める憲法改正の手続を経ることなしに、憲法を改正したのと同じ効果が生じることをいう。 ◇2 憲法の変遷の概念
◇3 解釈学的意味での憲法の変遷の肯否社会学的意味での憲法の変遷という現象が存在することについては争いはないが、解釈学的意味での憲法変遷を認めるかどうかにつき争いがある。
◆3-2 憲法保障(省略) ■4. 日本国憲法の成立過程◆4-1 日本国憲法の制定◇一 憲法制定行為の問題《問題の所在》
《考え方の筋道》
《アドヴァンス》
《One Point》
◇二 日本国憲法の成立と展開(省略) ◆4-2 日本国憲法の構造(省略) ■5. 国民主権の原理◆5-1 国民主権◇一 主権の意味
◇ニ 国民主権の意味《問題の所在》
《考え方の筋道》
《アドヴァンス》
《One Point》
《How To》
◆5-2 天皇制(省略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 <目次> ■1.第一節 憲法の生成と展開◆Ⅰ 「憲法」の語「憲法」という語は、
ところで、constitution はラテン語の constitutio に由来するが(constitutio は皇帝の制定法とか、後には教会の規則などを意味した)、当初は国家の法一般の意味で用いられたようである。 しかし、国家の全法秩序の中には、より基礎的な根本法(fundamental law)があるという観念がイギリスにおいて成立し、それとロックに代表される自由主義的な近代自然法思想における社会契約の観念とが結合して、ここに国家の根本法としての近代的な憲法観念が成立し、そのような姿において constitution が徳川末期に我が国に入ってきたのである。 ◆Ⅱ 立憲主義の成立と展開◇(1) 近代以前と立憲主義憲法は、最広義においては、およそ国家の組織・構造の基本に関する法を意味する。 かかる意味での憲法なき国家はあり得ず、それはあらゆる時代のあらゆる国家について妥当する。 ところで、およそ国家統治の本質は権力であり、その権力の背後には顕在的もしくは潜在的に強制力が控えている(レーヴェンシュタイン)。 原初的段階にある国家にあっては、この権力を扱う権力保持者による権力服従者に対する権力行使のあり方に関し、何らかの拘束力ある明確な規則というようなものはなく、宗教的信条とか伝統的な慣習あるいはときには単なる便宜ないし恣意に委ねられていた。 しかし、人間の本性の省察に基づき、権力保持者による権力の濫用を抑制するための装置を積極的に創出し、それを政治過程に嵌め込むことによって、あるべき国家体制の保全を図り、権力名宛人の利益を守ろうとする努力がみられるようになってくる。 我々は、それを既に古典古代ギリシャ、ローマにおいてみることができる(ギリシャ人は、自由社会を自分たちの言葉として語り、意識し、それを築こうとした最初の人間であるということは広く承認されている)。 そこでは、政治権力を幾つかに分割し、それらの相互的な牽制によって権力の濫用を防止しようとする様々な試みがなされている。 このように権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、権力名宛人の利益保護を憲法の終局の目的と捉えた場合、この段階に至ってはじめて人類は憲法をもったと称することができる。 ここにおいてはじめて憲法に基づいて政治を行なうということの意義が認められるもので、これを立憲主義と呼ぶならば、立憲主義は近代固有のものではなく、既に古典古代において成立していたということができる。 これを立憲主義の第一段階ないし古典的立憲主義と呼ぶことにする。 この立憲主義は中世およびルネサンス期のイタリアの都市国家などでもみられるもので、とりわけヴェネツィア共和国は、権力濫用を抑制し独裁的な絶対主義を阻止するための極めて複雑かつ多元的な抑制・均衡のシステムを案出し保持したことで知られている。 ◇(2) 近代立憲主義の登場古典的立憲主義は、中世の封建体制下において、また近代絶対主義国家における君主の圧倒的な支配の前に、背後に退くことを余儀なくされたが、近代市民革命を契機に、新たな理念と構想の下に再生した。 近代市民革命は、市民階級の経済活動面における絶対君主制に対する不満を梃子に、かつ、ルネッサンス運動期に醸成された個としての自覚を媒介とする個人の自由という基本観念の下に、生起したといわれる。 つまり、近代市民革命は、国家(公)に対して個人の自由の領域(私的領域)の存在を設定し、かつそれを積極的に評価し、国家(公)はかかる私的領域の確保のためにこそ存在理由があり、従って国家の活動もそのような目的のためのものに限定されると捉えるところに本質をもち、そのための具体的方策として憲法の意義が明確に自覚され、そのあり方をめぐる認識が深められるところとなったのである。 かくして国民の自由・権利と、そのための権力の構成と行使のあり方を、正式な文章において確認するという考え方が生まれた。 議会制が発達し、マグナ・カルタやコモン・ローの発展などによって国王の権力濫用に対する抑制装置が既に十分に確立されたイギリスでは成文憲法の制定をみるところとはならなかったが(もっとも、クロムウェルの統治典範(インストルメント・オブ・ガヴァメント)(1653年)のような例がみられた)、アメリカやフランスにおいて相次いで成文憲法の制定をみるに至った。 1776年のヴァージニア権利章典はロック流の天賦人権・国民主権・革命権などを規定し、次いで採択された「政府の組織(Frame of Government)」において権力分立機構を定め、ここに近代的成文憲法の範型が成立した。 1789年のフランスの「人および市民の権利宣言」は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」(16条)と宣明しているが、我々はここに近代立憲主義の心髄の簡潔な要約をみることができる。 立憲主義といっても、上述の古典的立憲主義は、国家(公)に対する「私」の積極的評価の観念の下に成立したものではなく、むしろ個人の幸福は国家の幸福(公的幸福)の中にこそ存するとの考え方を基盤とするものであった点が注意されなければならない。 このように近代立憲主義は、成文憲法を制定して個人の人権を保障し、権力分立を定め、その一環として国民の国政参加への途を開いたが(従って、近代立憲主義は同時に立憲民主主義であった)、しかし、近代立憲主義は国民大衆の積極的な政治参加に必ずしも好意的ではなかったという側面をもっていたことに注目する必要がある。 元来革命というものは国民に直結する議会に権力を集中しようとする傾向(いわゆる会議制的統治形態)をもつが、アメリカの諸邦でも当初議会全能の傾向を現出せしめた。 そのことは革命保守派の警戒心を強めるところとなり、ここに主権者たる国民を憲法制定権力として把握し、国民の直接の関与の下に成立した憲法をもって議会の活動を抑制しようとする構想が登場することになる。 1780年のマサチューセッツ憲法がそれで、憲法制定に憲法制定会議と人民投票を採用した最初の憲法であるが、それは国民主権を建前としてたてつつ議会の権力を抑え込もうとする巧妙な考案であった。 1788年発効の合衆国憲法は、このマサチューセッツ憲法の延長線上にあるといえる。 違憲立法審査制もかかる背景において生まれてくる。 フランスでは、中道左派を多数とする国民議会が、1789年の人権宣言を前文とする憲法を1791年に成立せしめたが、この憲法では、人民大衆に対する警戒から、意識的にルソー流の「人民主権」を避けて「国民主権」とされ、主権者たる国民はただ「委任」によってのみその主権を行使できるものとされた(この点については、第四節Ⅱ(57頁)で論及する)。 この「委任」は包括的・集団的な代表委任であって、代表者を拘束するような国民の意思の存在は忌避され、代表者は国民の選挙によって選ばれることを不可欠の要素としなかった(議会とともに国王も代表者とされた)。 英米でもフランスでも制限選挙制であった。 ◇(3) 成文憲法の普遍化18世紀末のアメリカおよびフランスにおける成文憲法の制定は他の諸国にも強い刺激となり、19世紀に入ると国家という国家のほとんどが成文憲法を制定するようになった。 君主国とて例外ではなかった。 かかる現象を捉えて19世紀は「憲法の世紀」とも呼ばれることがあるが、成文憲法の普遍化時代であり、立憲主義の第三段階と称することもできよう。 ただ、それとともに、超越的ないし道徳的な自然権思想が後退して実証主義的な権利観念が強まり、憲法概念も、価値的ないし目的的要素を希薄化ないし消失せしめて、形式化していった。 そうした傾向の中で、立憲主義の外見によって旧体制の温存を図ろうとするようなものもみられるようになる。 いわゆる外見的立憲主義である。 大日本帝国憲法もかかる系譜に連なるものである。 このような限界はあったが、成文憲法の普遍化という現象は、後の世代がより徹底した自由・権利の保障と民主主義を要求する基盤を提供するという機能を果たした点は看過してはならないであろう。 ◆Ⅲ 現代立憲主義◇(1) 近代立憲主義の変容既に示唆したように、近代立憲主義は、各個人の自由かつ自律的な活動の中にこそ人間の幸福の鍵があり、各個人の競合のうちに見えざる手の働きにより社会的調和が形成維持されると措定し、国家は個人のかかる自由な活動と社会の自律的運行の外的条件の必要最小限の整備にその役割を限定されるべきで、極端に表現すれば国家権力の活動の場が少なければ少ない程よいとの考え方に立脚していた(消極国家ないし最小限国家)。 かかる考え方と制度を背景に、経済面についていえば、資本主義が進展するところとなったが、しかし、それとともに国民の間に貧富の差が拡大し、各種の矛盾と社会的緊張を惹起するところとなった。 人間の自由・権利の享受の実質的平等を要求し、政治の民主化を通じてその達成を図ろうとする動きが顕著となり、それとの対応において近代立憲主義も変容を迫られるところとなった。 ◇(2) 積極国家(社会国家)化右の動きに対して政府は当初強圧策をとったが、やがて国民の社会・経済生活に積極的に介入し、経済危機の回避と社会的緊張の緩和に努めるようになった(積極国家化)。 政府自らによる積極的な産業基盤の整備、厖大な国家財政資金の投融資などの推進、最低賃金・労働時間規制法などの制定、各種社会保障政策の積極的展開がそれである。 かかる傾向を、憲法レヴェルではじめて体系的に表現したのがドイツの1919年のワイマール憲法であった。 同憲法は、「所有権は義務を伴う。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきである」(153条)と規定し(こうした規定の仕方は、「権利の倫理化」傾向を示すものといえる)、社会権的基本権と呼ばれる労働基本権などの保障や包括的保険制度の設立などについて規定するに至った。 その後生まれた憲法は、多かれ少なかれこの種の規定を採り入れた。 その傾向はとりわけ第二次大戦後顕著であって、1946年のフランス第四共和制憲法は自らを「社会的共和国」と宣言し、1947年のイタリアの憲法は「労働に基礎をおく民主共和国」と謳い、1949年のドイツの憲法はその性格規定として社会的法治国家たる旨宣言した。 なお、二世紀程前の憲法がなお妥当しているアメリカ合衆国の場合は、社会権的基本権が憲法上明記されるには至っていないが、憲法判例の変更の結果労働条件などの改善に関する法制化が進み、また既存の平等条項やデュー・プロセス条項などの解釈操作を通じて社会権的なものを憲法的に保障しようとするようになっている。 もっとも、この社会権的基本権が現代国家の憲法の人権保障体系の一大支柱をなすに至ったとしても、そのことは、自由主義的な近代国家を基礎づけた自由権的基本権体系と権力分立ないし抑制・均衡の体系を放擲し、あるいはそれを単に克服さるべき対象として捉えるに至ったことを意味しない。 むしろ、両者の調和ある共存を企図しているところに現代立憲主義の特徴がある。 そのことは、ドイツの憲法が社会的《法治国家》性を謳っていることの中にも示されている。 ただ、社会国家の追求は、国家の巨大化・硬直化を内包する“管理化国家”ともいうべき事態を惹起する危険を随伴していることは否定できない。 ◇(3) 議会制の変貌 - 政党国家一般に(アメリカの場合はやや事情を異にするが)近代議会制は、国民代表観念により選挙民の指図から解放された議員よりなる議会に、国民の自由の守護と統合の機能を発揮せしめようとした。 が、資本主義の進展に伴う社会的矛盾と緊張を背景とする政治の民主化の要求の高揚は、選挙権の拡大(終局的には普通選挙の確立)を帰結するところとなり、それと共にかってのように議会の超然さを許さなくなり、むしろ議会は実在する民意を忠実に反映・代弁すべきであると考えられるようになる。 このような事態は、フランスでは、古典的な「純粋代表」に対比して「半代表」という言葉で表現されることがある。 イギリスにおいて、「法的主権は議会にあるが、政治的主権は選挙民にある」といわれるような事態も、かかる文脈において理解できるものである。 この過程で重要な役割を果たしたのは政党である。 そして政党は、組織化を強め、国政レヴェルにおけるその重要性を高めて行く(政党国家の現象)。 その結果、議員は議会における自由な討論に基づいて意思を形成し表決するというよりも、政党の党議に従って行動する存在と化し、議会における意思形成は政党間の確執と妥協の下に行なわれるようになる。 そして、社会の階級対立の激しさに比例して政党間の妥協が困難となり、議会の意思形成・統合能力を失わせることになり、ドイツのように「左」「右」の挟撃にあって議会制が沈没してしまうところも出てきた。 第二次大戦は、議会制を潰した後には結局最悪の圧制しかあり得ぬことを実感せしめるところとなって、大戦後種々の方策を講じて議会制の修復・維持が図られることになる。 この点については後に詳述するが、一つは、政党を憲法体系上明確に位置づけようとする試みであり、第二は、直接民主制の部分的導入と地方自治の拡充によって議会制を補完せしめようとする試みである。 ◇(4) 行政権の役割増大 - 行政国家積極国家化は、政府による社会・経済過程へのきめ細かな対応・介入を随伴し、しかもこの対応・介入は立案された計画の下に進められることが要請される(計画行政)。 この計画化は、一方では資本主義体制下では果たして真に可能かという疑念(真の計画化は社会主義国家においてのみ可能であるという主張)、他方では“隷従への道”であるとの批判(ハイエク)に曝されながら、客観的事実としては国民の各生活領域におし拡げられ、それに随伴して行政権とりわけ官僚の役割増大を帰結している(行政国家)。 かってのような権威と統合機能を喪失した議会が、専門的知識と技術を要求される現代的行政需要に迅速かつ的確に対応することはあまり期待できない。 法律は行政をしばるというよりも、自由なる行政の根拠を一般的に提供するという役割を果たすことになりかねない。 かかる状況で編み出された一つの方途は、行政の長を国民の直接の選出にかからしめてその基盤を強化し、行政権に民意を反映させつつ官僚に対する指導力・統制力を発揮せしめようとすることである。 フランス第五共和制憲法下の大統領制は、その典型例である。 が、それは独裁制への危険を内包するとともに、そのような方途によって多面的な民意の各種行政への反映や行政の公正さを直ちに達成できるかの疑問は残る。 各種行政委員会や審議会の設置、オンブズマン構想、国民の権利に影響する計画策定や行政決定過程に利害関係者を参加せしめて適正さを確保しようとする試み(行政手続法制の整備)、情報公開制度の確立、行政の司法的統制強化への志向などは、リヴァイアサン化した行政国家に対する対応方法の模索を表わすものである。 ◇(5) 憲法の規範力強化への試み - 司法国家議会の相対的地位の低下と関連して、憲法の規範力を裁判所を通じて確保・強化しようとする傾向が顕著となってきている点も、現代立憲主義の特徴である。 近代国家と比較して、現代国家における憲法の規範力の低下を指摘する声も強い。 が、アシカにそういえる余地のあることは否定できないとしても、少なくとも憲法制度的にみるならば、憲法の規範力強化への志向が顕著であることも事実である。 かつて議会は自ら憲法の擁護者をもって任じ、法律が人間理性の発露たる一般的・抽象的規範と観念されていた段階では、議会による憲法侵害という問題は顕在化せず、憲法と法律との質的区別さえそれ程明確ではなかった。 この点、革命初期の立法権全能思想の下での経験に照らして形成された憲法下において、いち早く違憲立法審査制を確立せしめたアメリカ合衆国の例はきわめてユニークなものであった。 それが、上述の議会制の凋落-立法権不信を背景に、かつ基本的人権保障の緊要性の自覚の下に、立憲民主制下の諸国の憲法体系に採り入れられるところとなったのである。 この推移は、「自然的正義」→「実定的正義」ないし「法的正義」→「憲法的正義」として表現されることがある(カペレッティ)。 もっとも、「憲法的正義」実現の方法は、各国の歴史的事情を反映して一様ではない。 裁判所に対する信頼感の強い英米法系の国では、通常の司法裁判所が「憲法的正義」の実現の主たる担い手となったのに対し、大陸法系の国では、憲法裁判所という特別の裁判所がその任にあたる傾向がある。 旧体制(アンシャン・レジーム)下における経験から伝統的に裁判所不信が強いフランスでは、裁判所以外の機関(第四共和制憲法下の憲法委員会、第五共和制憲法下の憲法院)に憲法審査を行なわせる傾向がある(憲法院の審査は予防的にすぎず、アメリカ型の付随的審査ともオーストリア=ドイツ型の抽象的審査とも異なるが、理由を付した形で審査結果が示され、1789年の人権宣言が審査基準とされるなど司法的審査への接近を思わせる。こうした憲法院の活動に伴って、憲法学の法律学化の傾向がみられるという)。 ◇(6) 平和国家への志向元来戦争は立憲主義にとって最大の敵であるはずである。 とりわけ現代戦争は総力戦であって、人権(私的領域)の徹底的な制限・破壊を伴い、立憲主義体系に壊滅的な打撃となる。 第一次大戦、とくに第二次大戦はこのことを痛感せしめるところとなり、平和主義・国際協和主義への志向を憲法体系の中に取り込み、憲法自体において明記するものがみられるようになった。
◇(7) 憲法とその措定する人間像の変容近代立憲主義には、いわば抽象的な「完全な個人」を措定し、そうした人間像を前提に人権や統治のあり方が考えられたようなところがある。 そして、「身分」からの自我の解放を目指した近代人にとって、集団ないし結社は自我の確立を妨げ、個人の自由な活動の前に立ち塞がり、あるいは公共性をかき乱し、安定した外的な統治機構を瓦解に至らしめるものと映じたようである。 しかし、現実の人間は、自己を取り巻く様々な社会経済的諸条件に縛られ、その関係する様々な人間集団の規律や方針などとの絡み合いの中で行為するところが少なくないはずである。 上述のように、資本主義の進展は、近代立憲主義がその出発点とした建前と現実との乖離を次第に露わなものとした。 ここに、社会の中における具体的人間に即して、権利の保障や統治のあり方が考えられるようになった。 社会権的基本権の保障に象徴される、上述の積極国家観の登場である。 人間にとっての集団の意義も自覚され、実際、各種組織が発生した。 しかし、そうした積極国家は、具体的人間像を出発点としながら、ともすると人間を抽象化し、管理化された機構の中に人間を封じ込めてしまう契機をもっているかにみえる。 全体主義はそうした危険の極大化現象ともいえるが、例えばドイツの憲法にみられるように、第二次大戦後生まれた憲法が「人間の尊厳」を謳っているのは、そうした経験の反省に基づくものである。 近代立憲主義が「完全な個人」を措定した点は問題だとしても、各個人が普遍的な「自然権」をもつとする道徳原理を基礎に据えながら、現実の国家状況の中で、そのような権利の具体化のあり方を探り続けることがますます重要な課題となっているといえよう。 現代人権論において、人格権とか人格的自律権の意義が説かれるのも、この課題と関係している。 ◆Ⅳ 社会主義国家の憲法◇(1) 社会主義国家の出現と展開先に近代立憲主義とその変容としての現代立憲主義の展開をみてきたが、現代国家のもう一つのあり方を示すものとして社会主義国家の憲法体系が注目されてきた。 1917年の10月革命によって成立したソヴィエト政権は、翌年1月「勤労し搾取されている人民の権利の宣言」を発したが、それは「人間による人間のあらゆる搾取の廃止、階級への社会の分裂の完全な廃絶、搾取者に対する容赦ない抑圧、社会主義的な社会組織の確立、およびあらゆる国における社会主義の勝利」を謳うもので、その後の社会主義的人権保障体系の発展の基本的性格を規定するとともに、社会主義国家における統治構造のあり方をも規定する重要な意義をもつものであった。 同年、この権利宣言を第一編に収めてロシア社会主義連邦ソヴィエト共和国憲法が成立し、その後24年のソヴィエト社会主義共和国憲法を経て、36年にいわゆるスターリ憲法が制定され、ソ連邦は「労働者と農民の社会主義国家」であることを謳う(1条)とともに、「ソ連邦の政治的基礎は・・・・・・プロレタリアート独裁の獲得の結果として成長し堅固になった勤労者代議員ソヴィエトである」と規定した(2条)。 そして1977年の憲法は、ソ連邦を「成熟した社会主義的社会関係の存する社会」(前文)と規定し、18年、24年、36年の憲法の「思想と諸原則を継承し」た上で成立するところの、「労働者階級、農民、インテリゲンチア・・・・・・の意思と利益を表現する社会主義的全人民国家である」と定めた(1条)。 ソ連邦の影響の下に、第二次大戦後の社会政治的革命を通じて、東欧諸国などにおいて人民民主主義憲法が誕生した。 中国では、建国当初に臨時憲法の役割を果たした「中国人民政治協商会議共同綱領」(1949年)の後に、新民主主義から社会主義への過渡期型の1954年憲法、プロレタリア階級独裁下の継続革命思想を謳った「文革」型の1975年憲法、政策転換期型の1978年憲法、現代化推進に踏み切った 1982年憲法というように、四つの憲法の制定をみている。 ◇(2) 社会主義憲法の特徴上述の現代立憲主義が近代立憲主義を修復補正しつつその延長線上に立とうとするのに対し、社会主義諸国の憲法はむしろ近代立憲主義の原理を否定し、全く新しい社会主義革命の原理を具現しようとする点で大きな特徴をもつ。 かかる目的のために社会主義諸国の憲法は、権力分立制を否定し、中央集権的な会議制的統治形態を採用した。 例えば、
◇(3) 社会主義国家の激変社会主義国家は、右のような特徴をもつ憲法の下で、社会主義の理想を追求したが、いわゆる民主集中制は巨大化・硬直化する官僚制的支配を帰結し、その徹底した情報管理・情報統制と相俟って、社会のダイナミズムの欠如をもたらした。 世界的規模で進行する情報社会化の波に抗しきれず、また、社会経済的諸困難に直面して、社会主義国家は、あるいは瓦解しあるいは大きな変貌を余儀なくされた。 例えば、ソ連邦は解体し、1993年12月に公布、即日施行さえた「ロシア連邦憲法」は、「ロシアは、共和制統治形態の民主的な連邦法治国家である」(1条)と謳い、条文上は明確に立憲主義憲法の系譜に属するものとなっている。 これに対し、中華人民共和国は、1982年憲法の政治体制を維持しつつ、社会主義市場経済の発展を図ろうとしている(1993年の憲法改正により、「改革開放を堅持」することを序言の中に明文化している)。 ■2.第ニ節 憲法の意義・種別・特性・効力◆Ⅰ 憲法の意義◇(1) 実質憲法と形式憲法既に述べたように、憲法は国家の根本法の意であるが、委細にいえば、憲法は様々な意味に用いられる。 まず、憲法の存在様式に関連して、形式的意味における憲法ないし形式憲法と実質的意味における憲法ないし実質憲法との別が生ずる。
形式憲法の内容のすべてが必ずしも実質憲法とは限らず(その例として、1874年のスイス憲法典中のユダヤ的屠殺方法の禁止規定などが挙げられるが、その国の歴史的状況との関係で国家的ないし国民的重要性をもつものであるためかも知れない)、また、実質憲法がすべて形式憲法に取り込まれるとは限らない(明治憲法下の皇室典範がその例)。 ◇(2) 固有の意味の憲法と立憲的・近代的意味の憲法上述のように、およそ国家は、その組織や構造の基本に関する法の存在を前提とするが、これを固有の意味での憲法ないし本来の意味での憲法という。 この固有の意味での憲法と先の実質憲法とは、結局同一の事柄を指しているのであるが、固有の意味での憲法は事柄の性質に着眼してのものであり、実質憲法は事柄の存在形式に着眼してのものであって、着眼点の違いによるものである。 この固有の意味での憲法に対して、とくに権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、権力名宛人の利益保護を終局の目的とする憲法を立憲的意味における憲法といい、この種の憲法の体系的展開が近代国家に至ってみられるようになったことから近代的意味における憲法と呼ばれることが多い(1789年のフランス人権宣言が「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」と規定する例に象徴される憲法観である)。 上述のように、近代的意味における憲法は一般に形式憲法として登場し存在しているが、イギリスのような例外(そこでは、実質憲法は、慣習法や法律などの形で存在する)もある。 なお、実質憲法について、広狭二義を区別し、広義においては「国家の根本法」を、狭義においては「立憲政の国家に於ける国家の根本法のみ」を意味すると解する立場もある(美濃部達吉)。 ◇(3) 法規範としての憲法と事実状態としての憲法憲法に相当する外国語の constitution, Verfassung には、構造とか組織とかあるいは体質とかいった意味が含まれており、実際、国家という政治的統一体の存在のあり様それ自体を指して使用される場合がある。 「事実上の権力関係」をもって「憲法」の本質とみるラッサールの所説、あるいは、「政治的統一と社会秩序の全体状態」の意味において「憲法」を捉え(「絶対的意味での憲法」)、また「憲法」(Verfassung)と「憲法律」(Verfassungsgesetz)とを区別し、前者の「憲法」をもって憲法制定権力による政治的統一体の形式と態様に関する根本的決断とし(「積極的意味での憲法」)、「憲法律」はかかる「憲法」を前提にして初めて妥当し規範性を発揮し得るとするシュミットの所説、などにその用例をみることが出来る。 これらの所説は、政治的激動期において主張されたものであり、憲法が「政治」と深い関わり合いをもつことを鋭く指摘したものといえる。 しかしながら、憲法の本質をそのようなものとしてのみ捉えることは、憲法が「政治」に呑み尽くされ、憲法学を「政治」の侍女たらしめる危険を内包している点は看過できない。 日本語としての「憲法」は、法規範《のみ》を示唆し、constitution を必ずしも正確に表現しているとは言い難いが(なおⅣ(1)(23頁)参照)、安易に事実と混同することがあってはならない(因みに、シュミットの「憲法」〔Verfassung〕は単純に事実状態の意ではない)。 ◇(4) 実定法的意味の憲法と法論理的意味の憲法実定法的意味における憲法とは、およそ国家においてその組織・構造および作用の基本に関する規範であって、国法秩序の基礎をなすものを指すのに対し(これは上述の固有の意味における憲法に相当する)、そのような実定法的意味における憲法の効力根拠として想定される規範として法論理的意味における憲法がいわれることがある。 これは、純粋法学的思惟において、実定法的意味における憲法を効力あるものとして認識するために前提とされる始源的仮設規範である。 ◆Ⅱ 憲法の種別◇(1) 存在形式による種別憲法は種々の視点から分類できるが、従来しばしば行われる分類方法の一つに、存在形式に着眼してのものがあり、かかる視点から成文憲法と不文憲法、成典憲法と不成典憲法とが種別される。
にも拘らずイギリスがしばしば不文憲法国と呼ばれるのは、イギリスの憲法がとくに憲法典という形式をとって存在していない点に着眼してのことで、その場合の不文憲法は不成典憲法の意味で用いられている。 このように、成文憲法といっても必ずしも一義的ではなく、狭義においては成典憲法を指すが、広義においては憲法典を含めてさらにそれより広く根本法の趣旨で特別に定立された制定法一般を指し(例えば、フランス第三共和制では三つの憲法的法律が存在した)、最広義においてはおよそ成文化された実質憲法を指す(イギリスでは、狭義および広義の成文憲法は存しないが、最広義の成文憲法は存在しているということになる)。 ◇(2) 改正手続による種別
今日成典憲法主義が一般的になり、ほとんどが硬性憲法であるから、硬性か軟性かの区別は実はあまり意味はなく、むしろ「硬さ」が具体的にどのようなものであるか或いはどのようにすべきかに真の問題がるといえよう。 硬性憲法は憲法の安定性・永続性を企図してのものであるが、硬ければそれだけ憲法の安定性・永続性が保障されるというものでもない。 ◇(3) 制定権威の所在による種別制定権威の所在如何により、欽定憲法、民定憲法、協約憲法の種別が生ずる。
欽定憲法か民定憲法かという種別は、このように誰の権威を憲法制定の根拠とするかにある。 フランスの91年憲法は立憲君主制をとるものではあるが、国民主権に立脚して国民を制定権威としている点で民定憲法である。 また、日本億憲法は後述のように明治憲法所定の改正手続により成立したものではあるが、同じく国民主権原理に立って国民を制定権威としている点で民定憲法とみられる。 欽定憲法か民定憲法かという種別は、憲法成立の由来の区別に過ぎず、法的には特別の意味はないとの見方もあり得る。 しかし、欽定憲法の場合は、その制定権威者はそれ自体活動能力を有する存在である点で、民定憲法の場合とは違った法的帰結を導き得る点は看過されてはならない。 ◇(4) 規定内容による種別憲法の規定内容は各種の観点から分類でき、例えば国家体制如何により単一国憲法と連邦憲法、君主制憲法と共和制憲法といった種別が可能であるし、歴史的観点から近代憲法と現代憲法、あるいは、その措定する社会・経済的構造の観点から資本主義憲法と社会主義憲法、といった種別を行なうことができる。 あるいはさらに、規定内容の全体がイデオロギー的・綱領的性格を強くもっている憲法(イデオロギー的・綱領的憲法)と実利主義的志向を強くもつ憲法(実利的憲法)とに種別することもできる。 ◇(5) 一種の存在論的な種別これはレーヴェンシュタインの提唱にかかるもので、憲法規範に実際上の妥当性に着眼して、規範的憲法、名目的憲法および意味論的憲法が区別される。 規範的憲法とは、現に統治の規律として規範性を発揮している憲法をいい、名目的憲法とは、法的妥当性を欠いてはいないが、全体としてまたは少なくとも重要な部分について実際に規範性を発揮するに至っていない憲法をいい、意味論的憲法とは、政治権力保持者のためにその時点の権力状況を憲法的用語を用いて外観的に定式化したに過ぎないような憲法をいう。 この分類は、主観的価値判断の介入を避けられない点で問題を残すが、新しい分類の試みとして注目すべきものをもっている。 ◆Ⅲ 憲法の特性◇(1) 総説既述のように憲法は国家の根本法であるが、ここに根本法とは、より詳しくいえば、憲法が国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範であるという意味においてである。 国家のあり方について規律する法は憲法以外にも存在するが、憲法が根本法たるゆえんは、憲法が国家全体という根本的立場において規律している点にある。 そして、およそ法規範が妥当するためにはその法規範の定立をサンクション(※注釈:sanction には、 ①(権威筋からの正式な)許可・認可・是認・裁可・批准、②(法的な)制裁・処罰・賞罰、の二義があるが、ここでは①の意味)する法規範が先行することを前提とするが、憲法が根本法たるゆえんは、憲法が国法秩序の成立・展開をサンクションする究極の実定法規範であるという点にある。 ◇(2) 憲法の授権規範性右のサンクションをより具体的にいえば、法規範Aが妥当するためには最小限それを定立する機関・権能および手続を定めた法規範Bの存在を前提とし、AはBのいわば授権に基づいて初めて妥当するということであって、憲法は国法秩序の中にあって最終的な授権規範としての性格をもつ(憲法の手続法的性格)。 その際授権が全く白紙委任的であれば、受権者はいかなる内容の法規範も定立できることになるが、一般に授権はある種の枠づけ(制限)を伴うから、授権規範は同時に制限規範としての性格をもつのが通例である。 換言すれば、制限規範性は、授権関係の内容面に関する関係ということができる。 近代的意味における憲法は、特に国民の権利・自由の保障ということを重要な構成要素とするから、その種の憲法は制限規範性を顕著にもつ授権規範ということができる(憲法の実体法的性格)。 なお、法的思惟を純粋に授権関係に局限する立場に立てば、憲法典も何らかの上位の法規範によって授権されたものと考えるべきではないかという帰結があり得る。 ケルゼンの「根本規範」はその種の発想にかかわる。 それは、既に触れたように(Ⅰ(4)(17頁)参照)、「実定法的意味における憲法」を効力あるものとして認識するために前提とされる始源的仮設規範であり、「法論理的意味における憲法」などと呼ばれるものである(もっとも、我が国では、実質的・価値的な内実を込めて、実定法レヴェルでの「根本規範」がいわれることがある)。 ◇(3) 憲法の最高法規性手続と実体両面にわたる最終的授権規範としての憲法は、国法秩序の中で最も強い形式的効力をもつとき、それに相応しいより十全な姿を獲得する。 理論上も実際上も、憲法が、立法機関に対して通常の立法手続をもって憲法規範を改廃する権限を明示的に授権することがあり得るが(軟性憲法)、授権規範としての法規範性は希薄となる。 それに対して、憲法がそれ以外の国法形式による改廃の対象とはなり得ず、その改正には通常の立法手続と異なるとくに厳重な手続が要求され、憲法規範と矛盾する一切の国法の効力を認めないという強い形式的効力をもつとき、憲法は名実共に最終的授権規範に相応しい地位を獲得する。 憲法がかかる強い形式的効力をもつとき、その憲法は「最高法規」であるといわれる。 換言すれば、厳密には憲法の「最高法規」性は硬性の成文憲法の場合にのみ妥当し、逆に硬性の成文憲法であれば当然に「最高法規」である。 日本国憲法はとくに「最高法規」の章を設け、98条1項は「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定しているが(*1)、特別の厳重な改正手続に関する96条が存する以上、98条1項は当然の帰結である。 なお、憲法の形式的効力とは別に憲法の根本法性(法のもつ根本的なる性質・内容)に着目して「最高法規」がいわれることがある。 ただ、憲法に最も強い形式的効力を認めるのは、国家の根本法性に鑑みてのことで、形式的効力面にかかわる「最高法規」性と性質・内容面にかかわる「最高法規」性との間には密接な関連がある。 日本国憲法の「最高法規」の章の冒頭に、基本的人権の本質に関する97条が置かれていることにつき、その位置を誤ったものと解する見解があるが、そのように解すべきではなく、むしろ、それは、日本国憲法の「最高法規」性の実質的根拠が何よりも人権の実現にあることを明確にしようとする趣旨であろうと解される。 もっとも、憲法が「最高法規」であるといっても、他の国法形式の憲法適合性を誰が認定するかの問題がある。 立法機関が立法を為すにあたって憲法適合性について判断する権能と義務を有すると解されるが、かつてはその判断をもって最終的とするのが一般的であった。 従って、憲法が「最高法規」であるといっても、他律的強制規範性の乏しいものであったといえる。 しかし、既にみたように、現代立憲主義は、立法権不信と人権保障の緊要性の自覚の下に、立法機関以外の第三者機関に最終的認定権を付与し、「最高法規」としての憲法の実効性を確保しようとするに至っている。 この第三者機関としては各種のものが想定され得るが、日本国憲法は裁判所をもってその機関としており(81条)、従って「最高法規」としての憲法典は原則として裁判規範であることになった。 なお、日本国憲法は、憲法の「最高法規」性に関連して、公務員に対して憲法尊重擁護義務を課しているが(99条)、この点については後述する(第三節Ⅳ(2)(45頁)参照)。
◇(4) 憲法と国際法以上は憲法の特性を専ら国法秩序内部の問題としてみた場合のもであって、国際法秩序を視野に入れるとまた違った様相を呈する可能性があるが、この点については後述する(Ⅳ(5)(29頁)参照)。 ◆Ⅳ 憲法の法源と効力◇(1) 憲法の法源「法源」という語は種々の意味で用いられる。 法規範の妥当根拠の意味でいわれる場合(例えば、法の妥当根拠として神の意思だとか、国民の意思だとか、あるいは理性だとかいわれる場合)もあるが、通常は法規範の存在する形式の意味において用いられる。 後者の意味において「法源」をいう場合、憲法(実質憲法)は、成文憲法(成典憲法)国にあっては、主として制定法たる憲法典として存在する。 もっとも、憲法典は「法典」である以上、民法典や商法典などの場合と同様、網羅的体系性を備えるはずであるが、憲法典の場合には、一般にある差し迫った政治状況において、政治的妥協ないし決断の所産として各種の政治的配慮の下に成立することが関係して、網羅的で完璧な体系性・精密性を備えることは困難である。 当然に憲法事項と考えられるものが故意に規制対象から外されたり、意識的に含みの多い伸縮可能な形で規定されたりすることがしばしばあり、また、憲法改正に特別の手続が必要となることなどを考慮して、憲法に明記せずに後の解釈と運用に委ねるというようなこともよくみられるところである。 例えば、明治憲法では、君主国において元来重要な憲法事項たるはずの皇位継承などの問題は、その独特の「国体」観念に基づき、議会が関与すること(憲法典に規定されれば、その改正に議会の議決が必要)を嫌って、憲法典ではなく皇室典範で定められていたし、また、選挙に関する事項は選挙法に一任された。 ここに「法典」としての憲法典の特殊性が認められ、従って、成文憲法国にあっても、憲法(実質憲法)が憲法典以外の形式において存在することは否定され得ない。 例えば、憲法(実質憲法)が法律その他の制定法の形式において存在し、あるいは条約が国内法化されて憲法の法源となることもあり得る。 このような成文法源のほか、不文法源として、慣習法、判例、条理(あるいは学説)、習律というような形をとって存在することもあり得る。 一定の行為が長期にわたって反復持続され、そこに明確な規範意識が発生し、国家がその規範を強要するものと考えられるとき、そこに慣習法が成立し、それは「憲法的慣習法」とか「慣習憲法」とか呼ばれる。 しかし、実際上は法的規律とほとんど同じように遵守され、国家としても遵守することを待望するけれども、国家としてそれを強要するという程には至らず、それに違反することがあっても不法とはいわれないような類のものもあり、それは「憲法的習俗律」とか「憲法的習律」とか呼ばれる(第三節Ⅲ(41頁)参照)。 条理(あるいは学説)に法源性を認め得るかについては議論の存するところであるが、法典としての憲法典の特殊性からその意義は否定し難いと思われ、従来から憲法の法源として、「憲法的理性」を含めて「不文憲法」の意義が強調されてきたところである(例えば、美濃部達吉)。 判例についても法源性を認め得るかについて様々な議論が存するが、積極に解すべきものと思われる((4)(27頁)参照)。 このように憲法法源には各種のものがあるあ、硬性の憲法典の存する場合にはそれに抵触しない限りにおいてその存在が認められる。 かつて成文憲法よりも「不文憲法」とりわけ「憲法的理性」の優位性を正面から認める見解もあったが(少なくとも戦前の美濃部は、人間の習慣性の力ないし理性の力を徹底的に重視し、端的にそれに制定法改廃力を認めたし、あるいはフランスなどの学説の一部には、国民の絶えざる憲法制定権力の行使という考えの下に、慣習法に憲法典の改廃力を認めたものがある)、立憲主義の本来の趣旨からするならば、あくまでも憲法典を土台として、それを補充・発展させるものとしての「不文憲法」が考えられなければならない。 もっとも、憲法典の文言に真向から反するわけではないがその趣旨と異なる慣習について、「憲法的習律」としてならば認め得る余地がある(第三節Ⅲ(41頁)参照)。 なお、憲法判例は憲法典そのものではなく、制定法たる憲法典に準ずる効力しかもたないと解されるから、判例変更の可能性のある点は注意を要する(なお(4)(27頁)および第三編第二章第三節Ⅳ(378頁)参照)。 ◇(2) 憲法典の地位と機能右において憲法典が必ずしも憲法(実質憲法)のすべてを網羅するものではなく、憲法の法源として限界を有することをみたが、本質面からみても、憲法典は実質憲法と完全な一体性を達成することが不可能であることが知られなければならない。 そのことは、一国において憲法典の消滅・交替にもかかわらず、その国家が国家としての同一性を失うことはなかったという例が少なくないという歴史的事実に徴し明らかであろう。 つまり、国家の滅失は直ちに憲法典の滅失を意味するが、憲法典の運命とは別に国家の運命があり得るのである。 そして、国家の統治活動の合法性を支える究極の正当性の根拠となる主権は、理論上憲法典によって定まるのではなく、むしろ憲法典を成立せしめ、それを支えるものである。 もっとも、近代立憲主義に立脚する成文憲法は、国家権力の行使を憲法典の規定するところに限定し、実質憲法を形式憲法に封じ込めようとするところに基本的狙いをもつ。 しかし立憲主義的方法では、憲法体制、ひいては国家の存立そのものを危くする文字通りの非常の事態においては、憲法典に規定がなくとも、何らかの非常措置がとられることが容認されざるを得ないのであって(この点については、第三節Ⅳ(3)(48頁)参照)、実質憲法と形式憲法の裂け目が顕現する。 既に示唆したように、憲法の特性は、憲法より下位の法規範の定立の権限と手順を定め、それを権威づけるところにある。 従って憲法典成立後は、その所定の手続による以外に法規範の成立する余地はない。 が、そのことは、ある憲法典の下で妥当する法規範のすべてがその憲法典所定の立法手続によって成立するものでなければならないということを直ちには意味しない。 実際に、明治憲法下で制定された民法典などは日本国憲法下でも妥当している。 もちろん、日本国憲法の実体規定に抵触するものは効力を有し得ず、民法典なども日本国憲法の施行に伴って手直しをうけ、また刑法典の尊属殺重罰規定のように後になって最高裁判所によって違憲無効とされるという例もあるが、これらの法典が日本国憲法所定の立法手続によって成立したものではないという事実は残る。 最高裁判所は、明治憲法下の法律は、その内容が日本国憲法の条規に反しない限り、なお法律としての効力を有するとし、そのことは日本国憲法98条の規定によってうかがわれるとする(最(大)判昭和23年6月23日刑集2巻7号722頁)。 が、憲法の特性を授権規範性に求めるとすれば、同条にそのような意味を読み込むことは、同条に加重負担を強いるものではなかろうか。 後にみるごとく、明治憲法と日本国憲法との間には主権の変動があり、その意味では「革命」があったとみなければならないが、その「革命」は国家の同一性にかかわるようなものではなく、しかも、そのことに加えて、国民の生活のあり方を大きく左右する私法秩序の独自性を基本的に認めている点で明治憲法と日本国憲法とで共通するものがあるのであって、民法典などの引き続いての妥当性の根拠はむしろそうした点に求められるべきであろう。 ◇(3) 憲法の前文の効力憲法典には「前文」が付されているのが通例である。 「前文」の様式や内容には各種のものがあり(単に憲法制定の由来を説くにとどまるものもあれば、フランス第四共和制憲法のように権利章典に該当するものを規定しているものもある)、従ってその法的性質も一律に論じきれないところがあるが、大別して、法的規範性承認説と法的規範性否認説(前文は単に歴史的事実を陳述したにとどまるとか政治的・道徳的理想を表示したにとどまるとされる)とに分かれる。 日本国憲法の「前文」は「日本国憲法」という題名の後におかれ、憲法制定の由来・目的および憲法の基本原理・理想に関して述べるかなり詳細なものであるが、そのことから、「前文」は憲法典の一部を構成し(従って法規範性を有する)、その改変は憲法改正手続によらなければならないとする点では学説は概ね一致している(さらに、憲法典内部に形式的効力の違いを認める立場からは、憲法制定権力の所在を示し、基本的人権尊重主義など憲法の基本原理・理想を謳う「前文」は一般に憲法改正の限界をなすとされる)。 「前文」が法規範性を有する以上、それに抵触する下位規範の効力は理論上排除されることになるが(98条1項参照)、「前文」がさらに直接の裁判規範性をもつか否かについては肯定説と否定説とに分かれる。 否定説は、法規範の中には裁判規範性をもたないものがあるとの基本的前提に立って、「前文」の内容の抽象性・非具体性などを根拠とするが、肯定説もかなり有力で、下級審の判決例の中には肯定説によっているものがみられる(例、長沼訴訟第一審判決たる札幌地判昭和48年9月7日判時712号24頁)。 もっとも、否定説も、「前文」が憲法本文の各条項の解釈の基準となることを承認しており、判例もその趣旨のものと解され得る点は注意を要する(例、最(大)判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)。 ◇(4) 憲法判例そもそも判例が法源性を有するか否かについては議論の存するところであるが、既に示唆したように、憲法判例を含めて積極に解さるべきであり(我が国の現行法上、憲法判例は、民事・刑事・行政の各具体的事件の解決に必要な限りにおいて為される、憲法典に関する解釈にかかわる判例として成立する)、最高裁判所の憲法判決は先例拘束性をもつと解される。 それは、日本国憲法の定める司法権がアメリカ流のものと解されるということの他に、基本的には同種の事件は同じように扱わなければならないという公正の観念によるものであり、日本国憲法の解釈論的にいえば、憲法14条の法の下の平等原則、32条の裁判をうける権利(ここでの裁判は当然に公正な裁判の意でなければならない)、および憲法31条の定める罪刑法定主義に根拠する。 但し、その場合、先例として拘束力をもつのは、憲法判決中の ratio decidendi の部分であって、法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で《直接》必要とされる憲法規範的理由づけである点が留意されるべきである。 憲法判例については、通常の判例と違った特殊性が考慮されなければならないが、その点については後述する(第三編第二章第三節Ⅵ(378頁)参照)。 この先例拘束性の原則の下に、最高裁判所は自らの憲法判例に拘束されるとともに、下級審は最高裁判所の憲法判例に拘束される(但し、最高裁判所の判例に下級審が従わないからといって、現行法上破棄される可能性があるにとどまる)。 もっとも、その場合、拘束力をもつのは判決中の抽象理論ではなくて ratio decidendi であること、そのことに関連して下級審は英米法にみられる“区別(distinction)”を通じて相当の創造性を発揮し得る余地をもつこと、最高裁判所の考え方に変化ないしその兆しがみられるときはその新傾向を先取りすることが正当化されることがあること、などの点が留意さるべきである。 なお、右のような理解に対しては、憲法の解釈論として、憲法76条3項に「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とあることに注目し、さらに裁判所法4条に「上級審の裁判所の裁判における判断は、《その事件について》下級審の裁判所を拘束する」(傍点(※注釈:《》内)著者)とあること(その反対解釈として、上級裁判所の判例は下級裁判所に対して法的拘束力をもたないとみる)にも言及しながら、判例の法源性に否定的な見解が存する。 が、憲法76条3項にいう「憲法及び法律」には命令・規則・条例などの他慣習法など不文の法規範も含まれると解するのが一般的であり、またそう解すべきである。 裁判所法4条については、先例拘束性の問題と全く無関係とみることもできるし、あるいは、先例拘束性のあることを前提に、ただその事件との関係では下級裁判所を絶対的に拘束する趣旨を明らかにしたものと解することも出来ないではない。 このように、先例拘束性の原則を認めるには、憲法上および法律上の障害はないと解すべきであるが、我が国では、判例法主義の英米法系とは違って制定法主義の国であって、判決も《事実上の》拘束力をもつにとどまると解するのがむしろ一般的である。 けれども、判例法主義と制定法主義といった二分法がそもそも妥当なものか否か、制定法主義であるから先例拘束性は認められないとするのはあまりに図式的な結論ではないか、《事実上の》拘束力という観念は明確性を欠くところがないか、むしろ《事実上の》拘束力という観念の下に最高裁判所の示す抽象的な法理論が下級裁判所に対してかえって強い影響力を与えてきたという面はなかったか、といった疑問がある。 ところで、政治部門は、その権能行使にあたってその憲法適合性について判断する権限と義務をもつが、その際憲法判例にどのような態度をとるべきか。 結論的にいえば、国会は、その権能行使にあたってその憲法適合性について判断する際に、憲法判例を考慮すべきではあるが、それに法的に拘束されると考えるのは妥当ではなく、判例の示す憲法解釈は正確であろうとの推定を覆すに足る確信をもつ場合には、“訴訟において違憲とされるかも知れないが、自己の責任で”という立場で行動できると解される。 このように国会に対して法的拘束力はないと解される理由は、国権の最高機関にして国の唯一の立法機関である国会(41条)を核とする代表民主制とそこにおける最高裁判所が占めるべき地位・性格に求められる。 なお、特定の事件判決で違憲とされた法律自体にまつわる問題については後述する(第三編第二章第三節Ⅴ(373頁)参照)。 内閣は、「法律を誠実に執行」すべき立場にあるが(73条1号)、最高裁判所によって違憲とされた法律は一般的に執行できない状態に置かれると解される。 もっとも、国会が違憲とされた法律を何らかの理由で廃止するときは、そのことを期待して、テスト・ケースを提供すべく、当該法律を敢えて執行することは憲法上禁止されていると解することはおそらく妥当ではないであろう。 また、ある訴訟で違憲とされた法律とは別に国会が同種の法律を独自の判断と責任で新たに敢えて制定したような場合には、内閣は、その法律を執行すべき義務を負うことになると解すべきであろう。 ◇(5) 憲法と国際法(イ) 国際法と国内法との関係既にみたように、硬性憲法にあっては、「国の最高法規」として、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」の効力を排除する(98条1項)という帰結が導かれる。 しかし、これは国内法秩序との関係において考察してのことであって、国際法秩序との関係を視野に入れた場合はどうなるか。 国際法と憲法以下の国内法との関係について、理論上、両者はその妥当根拠において全く次元を異にするところの別個の法秩序であるとみるか(二元論)(この関係は、ごく簡単には、「国際法は国内法を破らないし国内法も国際法を破らない」と表現される)、両者は一個の統一的法秩序を構成しているとみるか(一元論)、のいずれかが可能である。 そして後者の一元論の場合には、さらに、国際法をもって国内法を委任する上位秩序とみるか(国際法優位説)(この関係は、「国際法は国内法を破る」と表現される)、または逆に、国際法の妥当根拠を、国家がそれぞれの憲法に基づいてそれを承認するところに求め、l国際法をもっていわば国内法により委任された法秩序とみるか(国内法優位説)、のいずれかが可能である。 右の諸説のうち、国内法優位説は結局国際法を否定するに等しく(国際法は対外的国内法と化す)、そのことの故に今日ほとんど支持を失っているが、国際法優位説と二元論との争いは必ずしも決着がついていない。 国際法優位説によれば、国内法は国際法によって委任された秩序ということになり、純粋法学的思惟にあっては、憲法の効力根拠は始源的仮設規範ではなく、実定国際法の規範ということになり、さらにその実定国際法の妥当根拠としての始源的仮設規範が想定されなければならないということにある。 もっとも、国際法優位説は現実の国際法秩序の実証的分析抜きの規範論理的帰結であって、純理論的にはそれを是としつつも、現実の国際法秩序を前提に二元論に与する論者も少なくないようである。 二元論に徹すれば、国際法と国内法とは全く無関係の法秩序であって、国際法が国内法的効力を有するためには必ず国内法への「変形」が要求されるということになる。 しかし、実際のところ、両者の違いを過度に強調するのは問題があるようである。 国際法優位説の論者も、多くは、国際法は《究極的には》国内法を破るものと捉え、他方二元論者といえども、多くは、国家として“国際法違反”の国内法を放置しておくことは許されないと考えているからである。 (ロ) 憲法と国際法の国内法的効力国際法がその実をあげるには、関係国内において実施に必要な措置が講じられなければならないが、その国際法がいかにして国内で妥当するかの問題は、各国の憲法体系に委ねられているのが現状である。 この点、国によっては国際法の国内実施のためいちいち立法措置(いわゆる「変型」)を必要とするところもあるが、憲法の明文または慣行により国際法をそのままの形で包括的に国内法化する国際法の一般的受容形式をとる傾向 - 一元論《的》傾向 - が顕著である。 日本国憲法の解釈論としては、立法措置を要しないとする明治憲法下の慣行を考慮し、かつ現憲法に至って国会による民主的コントロールが可能となったこと(73条3号参照)および国際法の誠実遵守の趣旨(98条2項)からみて、ことさらに立法措置が必要であるとみるべき根拠に乏しいと解される。 実際、自動執行的条約(self-executing treaty)は、特別の立法措置を講ずることなしにそのまま国内法的効力をもつものとして扱われてきている。 もっとも、自動執行的条約でない条約については、それを実施するために必要な国内法的措置は講じられなければならない。 このように国際的にみて一元論《的》傾向が顕著だとしても、何が自動執行的条約かについてそれぞれの国の独自の判断が働いたり、この種の条約以外の条約について立法措置を講ずることを怠ったり、条約の執行に必要な予算措置を講じなかったり、等々というようなこともなくはないようで、一元論《的》な考え方が純粋な形で実現されているわけでは必ずしもない。 (ハ) 国際法の国内法秩序における効力順位国際法と国内法との効力の上下関係についても、各国の憲法体系に委ねられている。 合衆国では条約と法律とは同位とされ、ドイツでは「国際法の一般原則」については法律に優位するものとされているが、総じて法律より上位におく傾向があるようである。 この点、我が国では、条約の締結につき国会の承認を要するとされていることや98条2項ないしその精神を根拠に、国際法が法律に優位するということについてはほぼ異論はない。 しかし、憲法と国際法との効力関係については説が分かれ、98条2項の精神やさらに前文・9条などを根拠とする国際法優位説も有力である。 が、条約締結権は憲法に根拠を有し、締結および国会による承認は憲法の枠内においてのみ許容されること、憲法改正については厳重な手続が定められているにも拘わらず、国際法優位説によればその手続によらないで憲法改正が為されてしまう結果になってしまうこと、などを考慮すると、国際法優位説は多分に疑問である。 従って、憲法優位説が妥当と解され、判例も条約が違憲たり得ることを否定しない(最(大)判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)。 ただ、憲法優位説に立つ場合でも、国際法が《一般的に》違憲審査の対象となり、現実に無効とされ得るかは一応別個の問題である。 また、憲法優位があらゆる国際法について妥当するかも問題で、「確立された国際法規」(国際社会で一般に承認・実行されている慣習国際法)を成文化した条約や、あるいは領土や降伏などに関する条約は憲法に優位するとみるべきであろう(ポツダム宣言受諾・降伏文書調印は、明治憲法典の予定する主権国家体制さえ否認するものだから違憲であると主張されたことがあるが、明治憲法は戦争の可能性を否認せず、戦争には勝敗がつきものであって、国家として生き延びるために降伏し、ために憲法典の定める通りには行かなくなる可能性は否定され得ない)。 なお、憲法優位説によるとき、憲法違反とされた条約は国内的に執行不能となるが、国際法としては依然として妥当する。 従って、その場合には、憲法に適合するよう条約の改正に向けて努力するか、条約に適合するような憲法改正を試みるかする必要が生ずる。 それでは条約締結手続が憲法に違反する場合はどうか。 この点については、従来、国際法上不成立(無効)とみる説と成立する(有効)とみる説とに分かれていたが、「条約法に関するウィーン条約」によれば、条約締結権限に関する国内法違反が明白かつ基本的に重要な規定にかかわるものでない限り、条約無効を申し立てることは出来ないとされている。 ■3.第三節 憲法の変動と保障◆Ⅰ 憲法の変動◇(1) 憲法の性質憲法は国家のあり方・運営の基本に関する規範であるが、同時にそれはその社会の政治的・社会経済的および文化的諸関係によって規定され、それら諸関係の反映でもある。 憲法は、その規範性を確保するため各種の方法を講ずるのが例である(憲法の保障)。 しかし、政治社会はそれ自体生物であって生物と同様不断の変化を免れず、憲法も一種の生きた有機的組織体ともいうべき性質をもつことは避けられない(広義の憲法変遷)。 このことは、憲法典についても基本的に妥当する。 憲法典は、一定時の政治的・社会経済的および文化的諸勢力間の妥協・調整による決断を基盤に、国政のあり方を、一定の理想・価値観の下に、将来に向かって枠づけ・固定しようとして制定される。 けれども、そのような諸勢力間の関係は時の経過とともに変化し、理想や価値観も変容して行くのが常である。 かかる変化・変容は、憲法典のあり方に不可避的に投射される。 ◇(2) 憲法変動の諸態様右の変化・変容は、通常は憲法解釈の変化を通じて顕現するが、それが不可能な場合には憲法典の正文の形式的変更(憲法改正と呼ばれるもの)の必要が生ずる。 憲法は、その安定性・固定性を希求しつつも、このような場合を予想して、憲法改正の手続について規定しているのが通例である。 憲法改正はこのように憲法正文の意識的・形式的な変更であるが、そのほかに、憲法典の意識的・形式的変更を伴わない無意識的ないし発生的(オーガニック)な憲法変動たる憲法変遷(狭義の憲法変遷)が語られることがある。 なお、憲法によっては、憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえることを認めたり(全部改正)、憲法典の特定条項の効力を一定期間排除することを認めることがある(憲法停止)。 右の憲法変動は、憲法自体が予定し、憲法所定の手続に従って行なわれるという意味で立憲的憲法変動と称し得るが、その他にも革命やクー・デターなどによって憲法変動が生ずることがある(シュミットは、憲法制定権力の所在の変更を伴う既存の憲法の排除を「憲法廃棄」と呼び、憲法制定権力を維持しつつ既存の憲法を排除することを「憲法排除」と呼んで両者を区別する)。 この種の変動は憲法がもとより予定し容認するところではないという意味で、非立憲的憲法変動と称することができる。 ◆Ⅱ 憲法の改正◇(1) 総説憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行なうことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改を為すことをいう。 このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。 後者の場合は新憲法の《制定》であって、通常法的連続性の断絶を意味する。 ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記し、その手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタインによれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。 ◇(2) 改正の手続(イ) 手続の諸類型硬性憲法の改正手続としては、次のような諸類型が認められる。
(ロ) 日本国憲法の改正手続(a) 総説日本国憲法は、憲法改正につき、①「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」による国会の「発議・提案」と、②「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」における国民の過半数の賛成による「承認」とを要求して、先の〈c〉型によることを明らかにし、最後に③天皇によって「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」直ちに「公布」されるものとしている(96条)。 (b) 国会の「発議・提案」発議とは、国民に提案すべき改正案を決定することをいう。 つまり、ここにいう発議には、通常の意味における発議(例えば、国会法56条1項には「議員が議案を発議するには、・・・・・・」などとある)とは異なって、議決が含まれており、発議されるものの原案、すなわち憲法改正案を国会に提示することではなく、国民に提案すべき改正案を国会が決定することをいう。 この発議は、「各議院」の「総議員の三分の二以上の賛成」で為される。 ここに「各議院」とはもとより衆議院および参議院のことで、衆議院の優越は認められていない。 ここにいう「総議員」の意味については、各議院の議員の法定数とするもの(A説)、現在議員の総数とするもの(B説)、院内事項であって合理性を失わぬ限り各議院で定め得るとするもの(C説)、に分かれるが、おそらくB説をもって妥当としよう(もっとも、B説によらなければ違憲であると断じ去らなければならないというような厳格な趣旨においてではない)。 なお、憲法を改正するには、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」において国民の過半数の賛成による「承認」を要求しているのに、その「発議・提案」について「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」という要件を課すのは憲法改正手続として過重に過ぎないかの批判はあり得よう。 憲法には、発案県や審議の方法あるいは国民に対する提案の方法について明記するところがない。 まず、発案権については、各議院の議員が有することは明らかというべきであるが、内閣が有するか否かについては肯定説(Y説)と否定説(Z説)とに分かれる。 Z説には、内閣は法律および憲法の両者について発案権を有しないとするもの(Z1説)と、法律の発案権は認めつつも、憲法については、憲法改正は遥かに強度に国民の意思の発現であるべきで(国民投票が要求されているのはその現われ)、その発案権も国民に直結する国会議員に留保されていると解すべきであるとするもの(Z2説)、の二種がある。 憲法改正の場合と法律の場合とを単純に同一視するのは疑問で、Z2説は説得力をもつが、発議それ自体は両議院の議決による国会の意思の決定ということであって、発案権は国会議員に限るということを当然に意味するとは解されず、また、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が必然的に害されるとはいえないと思われるので、国会の審議の素材を提供するというような意味合いで、法律によって内閣にも発案権を認めることは憲法上許されないわけではないと解される(内閣法5条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し・・・・・・」と定め、特に憲法改正案を掲げていない。「議案」に含まれると解する余地もないではないが、憲法改正の特殊性を考慮する必要があろう。そうだとすれば、現行法上内閣に憲法改正の発案権を認める規定は存しないということになるが、国民投票など憲法改正手続の詳細について法律で定める際に内閣の発案権についても規定すべきものということになろう)。 なお、各議院の議員が憲法改正案の原案を提出する場合の要件については法律で具体的に定め得るという趣旨であろう(現行国会法によれば、通常の議案の場合と同じく、衆議院では20人、参議院では10人の賛成があれば足りるということになるのであろうが〔国会法56条1項参照〕、憲法改正の特殊性に鑑み、その要件を加重するということは考えられ得る)。 審議の方法については、憲法に特別の規定がない以上法律案の場合に準ずる趣旨と解されるが、定足数に関しては若干問題がある。 総議員の三分の二以上の出席がなければそもそも議決不能であることに鑑み、その定足数を三分の二と解するのが通説であるが、単なる審議段階の定足数については、一般の議事の場合と同様三分の一で足りるとする説(56条1項参照)と、議事の重大性を考慮して三分の二以上の出席が必要または望ましいとする説とに分かれている。 この点、憲法上一義的には決め難い。 明治憲法の例(73条2項参照)からいっても、三分の二以上という要件は不当に重きに失するとはいえないと思われ、三分の一以上とするか或いはそれより加重にするかは法律で具体的に定め得ると解すべきであろう。 最後に、国民に対する提案の方法についても、技術上の問題があるが、憲法は国会の議決するところに委ねる趣旨と解される。 (c) 国民の「承認」憲法改正行為はこの承認によってはじめて成立するもので、国民主権の純粋な発現形態とみることができる。 国民投票は、「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際行はれる投票」のいずれかによって行なわれる。 今日に至るまでまだ国民投票の方法などについて定める法律は制定されていない(※注釈:佐藤幸治『憲法 第三版』は1995年刊であり、その後第一次安倍政権で2007年に国民投票法が成立済み)。 「特別の国民投票」があるのは、事柄の重大性に鑑みてのことで、最高裁判所裁判官の国民審査の場合と異なるところである。 承認の要件に関して述べられる「過半数」の意味について、有権者総数の過半数(A説)、投票者総数の過半数(B説)、有効投票総数の過半数(C説)の三説が理論上可能であるが、C説が有力である。 A説によれば、棄権するのも投票に行って否を投ずるのも全く一緒になって不合理であるが、投票者総数の過半数とするか有効投票総数の過半数とするかは国会が決定することができると解される。 (d) 天皇の「公布」天皇が「国民の名で」公布するとは、憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣旨である。 「この憲法と一体をなすものとして」とは、憲法改正が日本国憲法と同じ形式的効力を有する国法形式であるとして、という程の意味で、憲法改正の体裁の如何 - 全面改正、一部改正または増補 - はこの点に関係がない、と説かれることが多い。 が、改正規定は日本国憲法という一体としての憲法典の中に組み入れられ、変更関係を明らかにする趣旨に解せられ、そのことと関係して「全部改正」は日本国憲法として予想していないとみられる。 ◇(3) 憲法改正行為の性質と限界(イ) 改正権の本質憲法改正権の本質については、
硬性憲法の特性を上述のように理解した場合、A説は妥当でないと解される。 C説は、
しかし他方、C1説については、次のような疑問があり得る。
(ロ) 改正の限界(a)従来憲法改正における限界の有無をめぐって、肯定説(Y説)と否定説(Z説)との対立があり、種々議論されてきた。 肯定説の主張内容および根拠は多様であるが、大別して、
否定説も、大別して、
(b)右の諸説については、改正権の本質を上述のようにB2説的に解した場合、まずY1説とZ1説は妥当でないということになる。 Y2説については、かかる自然法規範にかかわる規定と然らざる規定とを区別することは容易であるか否か、仮にかかる自然法規範にかかわるか否かによって憲法の各条章につきその価値・重要度において段階づけが可能だとしても、そのことから直ちに憲法の各条章の形式的効力面における違いを帰結できるのか否か、の疑問があり得る。 Y2説の徹底した考え方は、憲法制定権力をも拘束する自然法規範の存在を主張するが(この立場に立てば、憲法制定権力と改正権とを区別することは殆ど意味をなさないことになろう)、一体そのような自然法規範の内容を誰がどのような方法と手続で認識するのか、その認識の正しさは如何にして確定可能なのか、の問題を残している。 それではZ2説ないしZ3説が妥当かということになるかも知れないが、むしろ次のように考えるべきである。 (c)まず、理論上、改正手続を根拠に、憲法典を支える最終的権威である憲法制定権力の担い手の変更はあり得ないと解される。 その変更は、憲法の法的連続性の切断を意味する。 明治憲法から日本国憲法への変動は、まさにそのようなものであったといえる。 第二に、憲法の改正は、もとの憲法典の存続を前提としてのことであって、従って憲法典自体にとくに全部改正を認める規定がない限り(但し、その場合でも憲法制定権力の所在の変動などは不可能と解される)、新しい憲法典にとってかえるとか、もとの憲法典との同一性を失わせるようなものは、法的な改正行為としては不可能と解される。 改正禁止規定については、
(d)右の「限界」を越えた行為は改正ではなく、もとの憲法典の立場からは無効ということになるが、新憲法の制定として完全な効力をもって実施されるということは十分あり得る。 そして、改正の「限界」内にとどまるものか否かの判定権が改正権者自身の手にあるとされる限り、理論上新憲法の制定とみざるを得ないものが改正の名において行なわれることはあり得る。 ◆Ⅲ 憲法の変遷◇(1) 憲法変遷の意味イエリネックは、「事実は法を破壊し、法を創造する」点に注目し、「事実の規範力」論を説き、その延長線上に憲法変遷論を展開した。 我が国でも、この所説の影響の下に、憲法の変遷がいわれるようになった。 もっとも、憲法の変遷(狭義のそれ)の概念規定は論者によって必ずしも一定しない。
そして、憲法変遷を法理論的にどう受けとめるかについて、
C説は折衷説的であるが、厳密にはB説の系譜に属するものといえよう。 ◇(2) 評価(イ)まず、成文憲法規範と実際の憲法状態との間に各種各様のずれが生ずる可能性は、一般に否定されない。 問題は、かかるずれを憲法解釈論上どう受けとめるかにある(これはしばしば「法解釈学的意義の変遷」と呼ばれ、前者の客観的事実認識のレヴェルでの「法社会学的意義の変遷」と区別される)。 先の憲法変遷肯定論(A説)と否定論(B、C説)の対立は、このレヴェルでのものである。 (ロ)その場合、憲法変遷の概念規定を明確にしておくことが重要である。 憲法変遷の概念規定として、上述のようにしばしば「憲法条項に違反・矛盾する」憲法実例とか「憲法条項の改廃」という用語が使用されるが、字義通り憲法条項に違反・矛盾する行為(例えば、憲法明文上間接選挙制になっているのに直接選挙制を採用したり、或いはその逆のこと)ないし憲法条項の改廃は、硬性憲法下の立憲的憲法変動としてはあくまで憲法所定の改正手続を通じて達成さるべきで、憲法条項に違反・矛盾する実例が当該憲法条項に代わって憲法規範性を獲得することを認め得る余地はないことが確認されなければならない。 右のような意味での憲法変遷を、国民の絶えざる憲法制定権力の行使という観点から肯定する論もあるが、上述のように(先のⅡ(3)(38頁)参照)、憲法制定権力は憲法典定立後は(ごく例外的な場合を除いて)いわば法制度化された制定権力たる改正権としてのみ活動するとみる立場からは、憲法制定権力の絶えざる行使という考え方をとる余地はない(仮に憲法制定権力の絶えざる行使という観念をとるとしても、それは政治部門による憲法実例には妥当し得ても、裁判所によるそれには妥当しにくいことになろう)。 従って、憲法変遷を語ることが許されるとすれば、それは、あくまでも「憲法に違反するものではない」との前提の下での、憲法条項の客観的意味変化の意でなければならない。 憲法に対するアプローチとして、
Y説によった場合、その一定時の意味理解からの離脱に対して法上否定的評価になるのが自然で、憲法変遷否定論には結局この種の主張と解されるものも見受けられる。 確かに憲法解釈にあたって憲法起草者の意図(制憲意思)は重要視さるべきであるが、その確認は必ずしも容易ではなく、また歴史学の進展に伴って変わり得るものである点は注意さるべきであるし、制憲意思の確認が絶対的であるとすれば、憲法解釈学は歴史学と化そう。 憲法規定の明文に反せず、憲法全体の理念・論理構造を破棄しない範囲内において、時代の知識・必要物・経験などを加味しつつ憲法規定を解釈する必要のあることは否定し得ず、かかる解釈が国民の一般的な憲法規範意識によって裏打ちされて、憲法規定の客観的意味内容が変化することのあることは承認されなければならない。 アメリカ合衆国憲法の州際通商条項やデュー・プロセス条項などの軌跡に、その典型例をみることができる。 ただ、それはなお憲法解釈の変化という形をとっているのであり、端的に憲法の正文に反するが憲法規範としての地位を獲得するに至ったという性質のものではない。 或いはまた、アメリカの大統領選挙制のように、起草者の特別の意図の下に採用された間接選挙制が、意識的な解釈行為によってというよりは、生きた政治の過程で自ずと形骸化し、その実質において国民の直接選挙制に変化してしまったものもある(しかし、間接選挙制の形式はあくまでも維持されていることに注意)。 ある機関が《法的には》ある行為を為すことが可能でありながら、実際には行使しないという習律が成立して、実際に行使すれば constitution 違反と非難されるというようなこともあり得る。 つまり、憲法の正文(憲法規範)はそのままに、それとは異なるプラクティスがいわば発生的に生じ、一国の constitution の重要な構成要素となる場合があるということである。 ただ、この場合も、いわゆる「憲法的習律」としての地位をもつにとどまり、法規範としての憲法正文にとって代わったというような性質のものではない。 一時的な単なる解釈の変化とは異なるところの、かかる憲法規定の客観的・実質的な意味変化、あるいは発生的な妥当性の変化を、立憲的憲法変動の一局面を解明する概念として、憲法変遷と呼ぶことが許されよう。 (ハ)右のアメリカの大統領選挙制のように特別の国家機関の行為なしに憲法変遷の生ずる場合もあるが、一般には憲法の有権的解釈権者の行為が大きな契機となる。 立法者が憲法適合性についての最終的認定権をもつ場合には立法行為が決定的意味をもつが、例えば裁判所に違憲審査権が認められている場合には当該機関の認定行為が重要な意味をもつ(もちろん全ての立法が審査にかけられるとは限らないし、また統治行為などの問題のあることに注意)。 もちろんかかる国家機関の憲法解釈が不当な場合が想定され得るが、最終的認定権者の行為である以上単なる事実とはいえず、憲法はそのことを予定していると考えられるべきであり(この関係は、規範学的に、「裏からの授権」とか「規範簒奪」などの用語で表現されることがある)、それだけに、かかる認定行為を契機に不当な憲法変遷の招来されることを阻止しまたは既に憲法変遷g生じてしまった場合には正しい姿に回復せしめるために、国民の間における国政批判の自由が大事である。 そして、憲法の保障する自由も、かかる文脈において把握される必要がある。 ◆Ⅳ 憲法の保障(合憲性の統制)◇(1) 憲法の保障の意義と諸方法(イ) 意義ここに憲法の保障ないし合憲性の統制とは、最高法規である憲法の規範内容が、下位の法形式や措置を通じて端的に踏みにじられまたは不当に変質せしめられないように統制しようとする国法上の諸々の工夫を指す。 立憲主義憲法は元来かかる憲法の保障の意義の自覚の下に形成されているもので、実際、1788年のアメリカ合衆国憲法のように明文で大統領などに憲法擁護の宣誓義務を課す例や、1818年のバイエルン憲法のように「憲法の保障」の下に国王・摂政などの憲法忠誠の宣誓や高級官吏の弾劾訴訟あるいは憲法改正手続などを定める例もみられたが(憲法典も制定法の一つとして改正が不可避であるとすれば、それに要求される特別の手続は「憲法の保障」の意義をもち得る)、憲法の保障の問題が複雑化しかつ緊要の課題となったのは現代国家においてであることは既に垣間見たところである(第一節Ⅲ(7頁))。 (ロ) 諸方法憲法の保障の方法は多様であり、各様の観点から分類できる。 まず、平常時におけるものか否かにより、正規的憲法保障と非常手段的憲法保障の別が生ずる。 非常手段的憲法保障としては、抵抗権と国家緊急権が問題となるが、この点については後述する。 非常手段的憲法保障が問題となるのは、憲法の危機状況においてであって、憲法保障の本来の意味はむしろ如何にしてかかる状況に陥るのを回避するかにある。 この正規的憲法保障については、
権力分立や抑制・均衡のシステムは、間接的保障にして予防的保障ということができる。 予防的保障のその他の例としては、公務員の憲法尊重擁護義務の宣言とか厳格な憲法改正規定をあげることができる。 諮問的保障の例としては、カナダなどでみられるところの、裁判所の行なう勧告的意見の制度がある。 違憲立法審査制は、もとより直接的保障にして拘束的保障、また一般に事後的保障である。 違憲立法審査制は一般に裁判所型であるが(これはさらに司法裁判所型と憲法裁判所型とに分かれる)、フランスの憲法院のように政治機関型もみられた(憲法院が裁判所型に変容しつつあることについては、第一節Ⅲ(5)〔10頁〕参照)。 日本国憲法は、権力分立制下の国政運営を前提に、憲法の最高法規性(98条)を確保するため裁判所型の違憲立法審査制を採用した(81条)。 その委細についてはそれぞれ関係の個所で論及することになるので、ここでは日本国憲法尊重擁護の責任と義務について一般的に触れるにとどめる。 ◇(2) 憲法尊重擁護の責任と義務(イ) 公務員の憲法尊重擁護義務日本国憲法は、「最高法規」の章で、天皇、摂政、国務大臣(ここにいう「国務大臣」には、解釈上内閣総理大臣も含まれる)、国会議員、裁判官その他の公務員の憲法尊重擁護義務を明記している(99条)。 本条は、これら公務員が国政の運営にあたり、憲法の運用に直接または間接に関与する立場にあることに鑑み、その憲法尊重擁護義務をとくに明記したもので、かかる例は、上述のアメリカ合衆国憲法など多くの憲法でみられるところである。 本条の定める憲法尊重擁護義務は、一般に、「法律的義務というよりはむしろ道徳的要請を規定したもの」(東京地判昭和33年7月31日行集9巻7号1515頁。また、百里基地訴訟に関する東京高判昭和56年7月7日判時1004号3頁)と解されている(*1)。 ただ、憲法を尊重・擁護するという積極的作為義務違反は場合によっては政治的責任追及の対象となり得るにとどまるが、憲法の侵犯・破壊を行なわないという消極的不作為義務違反については法律による制裁の対象となることがあり得る点は注意を要する。 例えば、公務員の懲戒事由や裁判官の弾劾事由とされる「職務上の義務違反」(国家公務員法82条、裁判官弾劾法2条)の中には、憲法の侵犯・破壊行為も含まれ得る。 なお、国家公務員法97条およびそれに基づく政令は、憲法99条を受けて、憲法遵守の宣誓を要求しており(「職員の服務の宣誓に関する政令」によれば、その「宣誓書」の様式は、「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います」とされている)、公務員が宣誓を拒否すれば、職務上の義務違反として懲戒事由となり得る(国家公務員法82条2号参照)。 また、国家公務員法38条は、職員の欠格事由として、「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」(同条5号)をあげている。 公務員の具体的な表現活動に関し、憲法99条と表現の自由の保障に関する憲法21条とを如何に調和させるかという難しい問題がある(公務員の職種、職務権限、表現の内容・態様等々を総合しながら、個別具体的に検討する必要がある)。 なお、天皇、摂政、国務大臣、国会議員などについては、弾劾制度が存しない以上、本条を根拠に政治的責任追及を為し得るにとどまる(なお、天皇・摂政については、天皇無答責の原則から、内閣がその責任を負う)。 これまで、例えば、鈴木内閣当時の奥野法務大臣の「自主憲法論」のように、国務大臣の憲法に関する発言が本条との関係で時折問題となった。 憲法が改正手続について定めている以上、閣僚が政治家として改正に関する主張を為し得るのは当然であるが、改正されるまで憲法に誠実に従って行動する義務があり、さらに、憲法およびその下における法令に従って行なわれるべきその職務の公正性に対する信頼性を損なうような言動がるとすれば、本条の義務に反する可能性があろう。 その意味で、閣僚の憲法改正に関する発言には、国会議員の場合と違った慎重さが求められるということになろう。 (ロ) 国民の憲法尊重擁護の責任日本国憲法は、憲法の保障する国民の自由および権利につき、国民が「不断の努力によつて」保持すべきことを呼びかけている(12条)。 憲法の保障の各種制度はそれぞれ固有の問題と限界を有しているのであって、国民主権下において、憲法制定権力の担い手である国民こそが憲法の保障の最終的責任の担い手である。 憲法12条はこの事理を表現するものといえる。 ただ、上述の憲法99条中には国民が含まれていないことには注意を要する。 あるいはこの点むしろ、憲法制定権力の担い手である国民が憲法を尊重擁護すべき立場にあるのは当然のことで、99条はその当然の前提に立つと解するのが一般的であるといえよう。 実際、外国の憲法の中には、国民の憲法遵守義務を明示するものも少なくない(例、イタリアの憲法54条、旧ソ連憲法59条)。 が、日本国憲法12条が「国民の不断の努力」による自由・権利の保持を強く呼びかけながら、憲法全般の尊重擁護に関する99条において国民を含めなかったことにはそれなりの理由があると解すべきである(*2)。 つまり、日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者であることを自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち(もっとも、憲法の定立自体は単なる相対主義ではない)、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害されることを恐れた結果であると解されるのである。 従って、憲法的秩序に反するというだけで団体および政党を禁止するドイツの憲法のような行き方は、日本国憲法に馴染むものではないと解される。
◇(3) 非常手段的憲法保障(イ) 総説上述のように、憲法の保障の各種方法・手段は、一般に、ノーマルな平和状態において作動すべく設計されているものであるから、外国からの侵入や内乱、大規模な自然災害などによって、あるいは政府の著しい権力濫用によって、国家および憲法秩序が重大な危機に曝されるとき、憲法秩序を回復するために、正規的憲法保障方法とは異なる非常手段的憲法保障方法に訴えざるを得なくなるのではないかの問題が生ずる。 国家緊急権と抵抗権がこの問題にかかわる。 (ロ) 国家緊急権をめぐる問題(a) 意義ここに国家緊急権とは、戦争、内乱その他の原因により、平常時の統治機構と作用をもっては対応し得ない緊急事態において、国家の存立と憲法秩序の回復を図るためにとられる非常措置権のことをいう。 立憲主義国家にあっては、立憲主義体制を一時停止して多かれ少なかれ権力集中を伴うのを通例とする。 緊急権は、前提となる事態の緊急性の程度やそれに応じてとられる措置の種類に従って類型化することができる。 よく行われるのは、
①の例としては、ワイマール憲法下の大統領の独裁権や英米のコモン・ロー上または議会制定法上のマーシャル・ルール(*3)などがあげられる。 ②は「必要は法を知らず」を地で行くもので、もはや法の世界に属する事柄ではないといえるが、ここにこそ国家緊急権の本質があるともいえる。 そして①と②との区別は相対的であることが注意されなければならない。 つまり、非常措置権を憲法的に厳格に枠づけようとすれば、②の可能性が大きくなり、②の可能性を嫌って非常措置権を包括的・抽象的に定めれば、非常措置権に対する憲法的統制の実が失われ、緊急権の濫用の危険が増大する。 国家緊急権のパラドックスは、立憲主義を守るために立憲主義を破るということであり、その実定法化には右のようなディレンマがつきまとう。 従来緊急状態に直面しつつも曲りなりに立憲主義体制を維持し得てきた国においては、国家緊急権はあうまでも立憲主義体制を維持し、国民の自由と権利を守るためのものであるという目的の明確性、従ってとられる非常措置の種類と程度は当該緊急事態に対処するための一時的かつ必要最小限のものでなければならないという自覚、従ってまた緊急権濫用を阻止するため可及的対策を講じ、事後において議会や裁判所などの立憲制度上の正規の機関を通じて緊急権行使の適正さを厳しく審査し、責任を追及する途を開いておくことの不可欠性についての認識が、国民の間に相当程度浸透している結果であったといえる。
(b) 国家緊急権と日本国憲法日本国憲法は、戒厳大権や非常大権などを定める明治憲法(14条・31条など)と違って、緊急権について定めるところがない(憲法54条は参議院の緊急集会について定めているが、固有の意味の緊急権規定といえるかどうかは疑わしい)。 その背景には、総司令部のアメリカ的発想、明治憲法やワイマール憲法下での緊急権の濫用に対する反省、あるいは憲法前文・9条にみられる徹底した平和主義・国際協調主義の姿勢等々が作用していたのかも知れない。 日本国憲法の緊急権についてのこの沈黙の法的意味について、
憲法典上の規定の有無おみで緊急権の問題を割り切れるかどうかは問題であろう。 憲法典中に規定をおくと濫用される危険があることは否めず、それを規定しないことは一つの見識であるが、放置すれば憲法典の実効性ないしその生命そのものが失われる緊急事態に不幸にして陥った場合、その救済を図るため非常措置を講ずることは不文の法理として肯定せざるを得ないのではないか。 そしてその場合、かかる非常措置は、日本国憲法の立場にあっては、単に「国家の存立」のためということではなく、個人の自由と権利の保障を核とする憲法秩序の維持ないし回復を図るためのものでなければならない(目的の明確性の原則)。 そのことに関連して、右に触れたように、非常措置の一時的かつ必要最小限度性の原則、濫用阻止のための責任性の原則が貫徹されなければならない。 現在、内閣総理大臣に緊急事態の布告を発する権限を認める警察法(*4)(71条)、内閣総理大臣に防衛出動・治安出動命令を発する権限を認める自衛隊法(76条・78条・81条)が存するが、国家緊急権との関連でどう解するかの問題をはらんでいる(*5)。
(ハ) 抵抗権(a) 意義立憲主義憲法の保障の一局面として抵抗権をいう場合、それは、政府が権力を濫用し、立憲主義憲法を破壊した場合に、国民自ら実力をもってこれに抵抗し、立憲主義憲法秩序の回復をはかる権利をいう。
C説については、「歴史の発展法則」とは具体的に何であり、それは如何にして認識し得るかの課題がある。 B1説とB2説とは、抵抗権の根拠とされる自然法の性格・内容についての理解を異にしている。 B2説のように、抵抗権をもって実定法上の義務を《それ以外の何らかの義務》を根拠にして否認するものであると理解する限り、抵抗権が実定法上の権利たり得ないのは当然の帰結となる。 が、抵抗権はそのように広く漠然と捉えるべきではなく、近代立憲主義の背景にある「自然権」思想を基盤に構成さるべきであろう(もっとも、ここにいう「自然権」は、B1説の想定するように、必ずしも自然法の存在を前提とするものではない。第四編第一章第三節Ⅰ〔392頁〕参照)。 従って、「自然権」を基盤とする立憲主義憲法の下では抵抗権は実定法上の権利たり得るが、「自然権」を基盤としない反立憲主義憲法体制下にあっては非実定法的な革命権として存在するにとどまることになる。 (b) 抵抗権行使の条件立憲主義憲法秩序が維持されている限り、個々の不正・不法の国家行為に対しては、言論・出版・集会・請願などの憲法上の自由・権利の行使により、あるいは訴訟を通じてその違法性・違憲性を争うことにより、それを匡す途が開かれており、人権を侵害する個別的公務執行行為に対する実力による抵抗も違法性阻却の法理による適正な処理の途がある。 このような状況の場合に敢えて抵抗権を問題にする必要はないし、抵抗権は《実力による闘争》であるから(このように抵抗権は実力の行使を伴う点で、法違反行為でありながら非実力的・非暴力的ないわゆる市民的不服従と区別される)、その濫用は立憲主義体制を不当に混乱せしめる危険を内包していることも注意する必要がある。 従って抵抗権の行使は、政府権力の濫用などによって立憲主義憲法秩序が重大な危機に曝され、人権の行使が一般的に妨げられるようになった状況において、はじめて問題となるものと解される。 この点について、
ただ、憲法の一条規違反であっても、立憲主義憲法体制の重大な変質をきたすような場合が考えられ得るのであって、①の要件をあまり厳格に解するのは疑問とすべきであろう。 この抵抗権に比べて、より現実的・具体的意義をもつものとして、先にも触れた市民T系不服従がある。 市民的不服従は、立憲主義憲法秩序を一般的に受容した上で、異議申立の表現手段として法違反行為を伴うが、それは「悪法」を是正しようとする良心的な非暴力的行為によるものであるところに特徴があり、そのような真摯な行為の結果、「悪法」が国会によって廃止されたり、裁判所によって違憲とされて決着をみることがあり得、そのことを通じてかえって立憲主義憲法秩序を堅固なものとする役割を果たし得る。 かかり市民的不服従を一個の権利と称するかどうかはともかく、それは、究極的には抵抗権と相通ずる性質をもちつつ、正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない状況に立ち至ることを阻止する役割を果たすものとして注目される。 ■4.第四節 憲法と国家と主権◆Ⅰ 国家◇(1) 国家の概念上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 右のように、まず国家は一定の地域をその存立の基盤としており、国家がその支配権を原則として排他的に及ぼし得るこの区域は「領土」と呼ばれ、領陸、領海および領空よりなる。 換言すれば、領土はその国家法秩序の空間的妥当範囲であって、その範囲は国家の領有意思を基礎に国際法によって規定される。 憲法中に領土に関する規定が置かれることもあるが、日本国憲法にはその種の規定はない。 現在の我が国の領土は、基本的にはポツダム宣言および平和条約の定めるところによっている。 国家の人的要素たる所属員は「国民」と呼ばれ、この国民たる身分(国籍)を如何なる範囲において認めるかはそれぞれの国家の定めるところによる。 日本国憲法は国籍の取得・喪失について法律の定めるところに譲っているが(10条)、この点については後述する(第二編第一章第一節(87頁))。 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。
◇(2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 ◆Ⅱ. 主権◇(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権
(ハ)国家主権権国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 ◇(2)実定法上の主権観念以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
<目次>
◆1.1 憲法と国家◇1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味
現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◇1.1.2 実質的意味の憲法と国家国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。
◇1.1.3 国家の正当性に関する諸理論国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◇1.1.4 法の3つの役割本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 (1) 調整問題の解決調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 (2) 公共財の提供ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 (3) 人権の保障以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。 ◆1.2 立憲的意味の憲法◇1.2.1 近代立憲主義市民革命と近代立憲主義 実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。 一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。 これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。 この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。 そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。 「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。 近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。
なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 ◇1.2.2 近代憲法から現代憲法へ近代憲法の特徴 近代立憲主義が確立した当初の憲法においては、権利宣言においても、思想・信条の自由、表現の自由、人身の自由、財産権の保障などの個人の権利を国家権力に対して防衛するという色彩が濃く、団体行動の権利や社会権は、ほとんど顧みられていない。 また、統治機構の面でも、国民の代表によって制定された法律によって行政権および司法権を厳格に拘束しようとする考え方が強く、立法権そのものを拘束しようとする考え方はあまり見られなかった。 さらに、当時は、参政権も納税額や性別によって限定されており、「教養と財産(Bildung und Besitz)」を有する市民層という国民の限られた部分の意見が議会に強く反映する構造になっていたことも見逃してはならない。 現代憲法への転換 強要と財産を持つ人々による政治という考え方から、できるだけ多くの人々が国政に参加すべきだとの考え方への転換が行われたのは、ヨーロッパにおいても19世紀後半から20世紀初めにかけてのことに過ぎない(その背景には、主要各国の軍事戦略の転換がある。この点については、長谷部 [2006] 第4章参照)。 そして、選挙権の拡大とともに、国家が大衆の要求に応ずる必要が生じたこと、また他方で、社会主義思想が、近代憲法の保障する人権が単に形式的な自由と平等を保障するにとどまり、真に人間らしい生活を保障する役割を果たしていないとの主張を広めるに従って、国家の任務と限界に関する考え方も大きな変化を遂げた。 ドイツのワイマール憲法やフランス第四共和政憲法など、第一次大戦以降にヨーロッパ諸国で制定された諸憲法の権利宣言においては、従来の個人レベルの自由権と並んで、集会の自由・結社の自由のような集団的自由権、労働者の団結権・団体交渉権・争議権のような労働基本権が保障される他、最低生活の保障や勤労権、教育権など、実現のために国家の積極的な介入を要するような権利も謳われている。 日本国憲法も、これらの点で例外ではない。 また、権利宣言として成文化された権利のカタログに示されない領域でも、国家には、景気変動や経済成長の調整、社会資本の整備など、積極的な役割が期待されている。 次に、憲法による制約の対象についても考え方の変化が見られる。 現代社会においては、国家権力とそれ以外の社会的権力、つまり大企業や政党、労働組合、私立大学などの違いは絶対的なものではなく相対化しており、従ってこれらの社会的権力の行為も憲法による直接あるいは間接の制約の対象にすべきだとの見解が主張されている。 統治機構への影響 以上のような近代憲法から現代憲法へ、言い換えれば、夜警国家から福祉国家への国家観の変容は、統治機構の面でも重大な変化をもたらしている。 まず、福祉給付行政に見られるような行政裁量の拡大は、議会立法による行政権の厳格な拘束という法の支配(1.2.5 参照)の理念を後退させる状況を生み出した。 また、政府の活動領域の拡大は、政府が産業界や労働界をはじめとする社会内のさまざまな利益集団と協議する必要を生み出し、国会を通じて国民の利益が一元的に代表されるとの近代憲法の建前に反して、多様で個別的な利害が政府と直接に交渉する特権を得る状況をもたらしている。 他方、大衆の政治参加に伴って成長した政党組織は、議会内での議員の規律を強め、その結果、政党の領袖からなる内閣による議会の支配を現出した。 選挙権者の数が限定されていた近代社会においては、地方の名望家が独自の資金と組織によって当選し、議会内で緩やかな議員組織を形成していたが、現代の普通選挙制度の下では、政党の政策・組織・資金に頼らない限り、議員の地位を獲得することはきわめて困難となり、そのため党組織への議員の従属が見られる。 さらに、戦間期から第二次大戦中のファシズムの経験から、立法府による侵害から国民の権利を守る制度が必要だとの考え方が強まり、戦後、多くの国で違憲立法審査制度が導入されることとなった。 ◇1.2.3 国民主権主権とは 主権という言葉の主な用法としては、
統治権という意味の主権の用例としては、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ極限セラルベシ」がある。 統治権の最高独立性を示す主権の用例としては、憲法前文3項における「自国の主権を維持し」がある。 これに対し、日本国憲法前文で「主権が国民に存する」といわれ、1条で「主権の存する日本国民」といわれる場合には、③の意味の主権が国民に帰属することが述べられている。 国民主権の内容 国民主権の原則は、
前者は、国民主権の権力的契機、後者は、国民主権の正当性の契機といわれることがある。 君主主権の下においては、君主自身が統治権のかなりの部分を行使し得たために、権力的契機と正当性の契機とは重なり合っていたが、国民主権の下においては、市民が常時政治に直接に参与することは不可能であるため、両者は乖離し、正当性の側面が強調されることになる。 国民主権の原理が、国民の実際の政治参加をどの程度まで要求するかについては、代表制の観念とも関連して議論の対立が見られる(12.1.1 参照)。 主権概念の見直し 国家の主権および国家における主権は、唯一不可分で最高独立であり、無制約であるという考え方が伝統的には支配的であった。 しかし、実際には、連邦国家のように中央政府と各州政府に統治権が分割されることもあるし、違憲審査制によって国民を代表する議会の立法権が裁判所によって制約されることもある。 また、国際的な慣行や条約によって国家の行動が制約されることも珍しくない。 主権が無制約であるとの考え方は、権力分立や違憲審査など、さまざまな制度によって国家権力を制約しようとする近代立憲主義の考え方と正面から対立する。 「国民主権」の原理が国民の政治参加を広範に要請するという前提をとったとしても、そうして政治過程に参加する国民は、さまざまな制度の枠組みを乗り越えて無制約に国政を決定し得るわけではない。 主権が唯一不可分で無制約であるとの考え方にさほど理由がないとすると、国家という単位で法のあり方を考えることも必然的ではないことがわかる。 1.1.4 で述べた法の役割を、国際的な法や組織が効果的に果たすのであれば、国家を単位として社会生活を規律することに必ずしもこだわる必要はない。 地球環境の保全や国際平和の維持という公共財は、個々の国家を超えるルールや組織を要求するであろうし、地域ごとの実情に応じた統治権の行使は地方政府への大幅な権限の委譲を正当化するかも知れない。 「国民主権」の下で、市民の直接の政治参加をどのような制度的枠組みの下で、どこまで認めるのが妥当かも、1.1.4 で述べた法の役割をどのような制度が適切に果たすかという視点から検討する必要がある。 主権という概念に基づく議論の限界に留意し、この概念にあまり多くのものを読み込み過ぎないようにしなければならない(長谷部 [1999] 第5章)。
◇1.2.4 権力分立原理の変容権力分立の原理は、モンテスキュー(de Montesquieu, C. L.)によって確立されたと考えられている。 『法の精神』(1748)で示された彼の理論は、当時のイギリスの政治体制をモデルとして組み立てられており、その内容は、権力集中の排除を目的とする消極的原理と権力の抑制均衡を狙う積極的原理の2つに区分することができる(モンテスキュー [1987] 第11篇第6章)。 権力集中の排除 まず、消極的原理は、国家の統治権を、立法・司法・執行の三権に区別し、そのうち2つ以上が、1つの機関によって独占されないよう、政治体制を構成する必要があるとする。 このような独占は、専制政治、つまり人々の自由の抑圧をもたらすからというのがその理由である。 確かに、立法機関と法を具体的な場面に適用する機関とが融合すれば、個別の事情やその時々の考慮によって法は伸縮自在に適用されることとなり、あらかじめ定められた一般的な法に従って予見可能な形で国家権力が行動するという「法の支配」は失われることになる(1.2.5 参照)。 司法権と執行権とが融合した場合にも、立法権の定めた法による拘束は名目的になり、同様の専制がもたらされるおそれが強い。 権力の抑制均衡 もっとも、国家権力の集中を排除する消極的な原理だけでは、憲法の構成原理として不十分であり、モンテスキューは、積極的な原理として、権力の抑制均衡の仕組みを提唱する。 これは、司法や執行を支配する最高の権能である立法権の構成に関する原理である。 モンテスキューによれば、当時のイギリスの立法府は、市民階級の代表からなる庶民院、貴族からなる貴族院、さらに立法裁可権を有する国王の三者から構成され、三者すべての合意がない限り、新たな法律が制定されない仕組みになっていた。 執行権を有する国王が立法裁可権を持つことにより、議会が執行権を簒奪するような法律を制定することを防ぐことができる。 また、三者のすべての同意がない限り法律が制定されない以上、制定された法律は、すべての社会階層の利益にかなう、自由を守る法律であるはずである。 モンテスキューの発想にならって行政権の首長に立法拒否権を認めた憲法として、フランスの1791年憲法やアメリカ合衆国憲法がある。 現代の権力分立 もっとも、モンテスキューが権力分立の原理を提唱したのは、国民主権の原理が確立せず、君主や貴族階級がなお大きな政治的発言権を有していた制限王政時代のイギリスをモデルにしてのことであった。 このような時代を背景とする権力分立論が果たして現代国家でも有効であり得るかが問題とされねばならない。
このような現代の権力分立が提起するおそらく最大の問題は、国民主権原理との関係である。 議会が、主権者たる国民の直接の代表であることを考えれば、なぜ行政権や裁判所がそれに従属することなく、かえって、ときには議会の行動を抑制し得るのかが問われることとなる。 このうち、行政権に関する限りでは、日本は議院内閣制度を採用していることから、機構上、行政権を担当する内閣が議会の多数派と行政権とは実は融合していることを示しており、その限りで権力分立原理は変容を被っていることになる。 ただ、議院内閣制の下では、内閣が辞職の自由を持つことと、場合によっては自己の政策の是非を有権者に問うために議会を解散し得る点で、行政府が議会の意思に無原則に従う議会統治制よりは、内閣の独自性が保たれているといえよう(13.1.1 (2))。 しかし、内閣総辞職の後、あるいは解散-総選挙の後に組織される新内閣は、議会多数派の意思を反映していなければならない。 フランス第五共和政やアメリカ合衆国では、行政権の長である大統領が、議会と同様に、有権者を直接に代表するという形で、権力分立と国民主権との整合性が図られている。 分立原理の変容 もっとも、行政権が立法権と対抗し得る存在と考えられるに至った実質的な理由は、モンテスキューの時代と異なり、現代の行政権が単なる法律の執行にはとどまらず、立法活動自体の指導をも含む統治活動を担当しているからである(13.1.2 (1))。 国家に最小限の役割のみが期待されていた時代においては、各身分の既存の権利が新たな法律によって侵害されない仕組みを作り出すことが肝要であった。 これに対して、国家の役割が増大した今日においては、行政権の担当する統治活動を民主的にコントロールすることが重要な課題となる。 議院内閣制や大統領の公選制も、このような視点からその意義を理解する必要がある。 他方、裁判所については、伝統的には、司法は法律を個別の事件にあてはめて、それを解決するだけであり、裁判官の個人的な良心や倫理観がそこに介入する余地はないと考えられてきた。 従って、司法が正しく運営されるためには、政治部門の介入を排除し、法律の忠実な適用を保障しなければならないこととなる。 そこから、裁判官の職権の独立や身分保障の必要が説明される。 もっとも、実際には、法の解釈適用において、裁判官の個人的な考えが全く働かないということはあり得ない。 とくに、抽象的な憲法の条文の解釈に基づいて、国民を代表する議会の制定法の効力を審査する違憲審査制度を如何にして正当化できるかが、議論の焦点となっている。 議会を含む民主的な政治過程そのものの正常な機能を維持するため、あるいは個人の自律を多数決による政策的決定から守るために違憲審査が要請されるという議論など、さまざまな考え方が提示されている(14.4.8. 参照)。
◇1.2.5 法の支配法の支配は、国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようとする理念である。 法の支配の内容 「人の支配」ではなく、「法の支配」を実現するためには、何よりもそれが従うことの可能な法でなければならず、法に基づいて社会生活を営むことが可能でなければならない。 そのためには、①法が一般的抽象的であり、②公示され、③明確であり、④安定しており、⑤相互に矛盾しておらず、⑥遡及立法(事後立法)が禁止され、⑦国家機関が法に基づいて行動するよう、独立の裁判所によるコントロールが確立していること、が要請される(長谷部 [2000] 第10章)。 このような法の支配の要請は、法令の公布に関する規定(憲法7条1号)や憲法41条の「立法」の概念、司法の独立(憲法76条以下)の他、憲法31条以下の諸規定に具体化されている(8.3.2. (3) 【法の支配との関係】 参照)。 「善き法」の支配 法の支配は、「善き法」の支配と同視されることがある。 形式的法治国と実質的法治国の概念を対置し、法の支配を後者と同視する考え方もその一例である。 また、個人の尊厳や基本的人権の保障、国民主権など、近代立憲主義の諸要請がすべて法の支配に含まれるとする者もいる。 しかし、このように法の支配を濃厚な意味で理解してしまえば、この概念を独立に検討する意義は失われる。 確かに、法の支配の内容とされる法の一般性・抽象性・明確性・安定性、および遡及立法の禁止は、法が法として機能するための、つまり法が人の行動の指針として機能するための必要条件である。 立法が個別的にしかも事後的に為され、法の文言も不明確であり、しかも朝令暮改のありさまでは、人々は国家機関の行動について如何なる予測を立てることもできず、そのため法に従って行動することは不可能となるであろう。 しかし、人種差別立法や出版物の検閲制度を設定する法も、やはり法として機能するためには、これらの特徴を備えている必要がある。 これらの特徴はいずれもそれ自体としては、悪法の支配とも十分に両立し得る。 また、前述のような法の支配の内容は、法が民主的に定められるか否かとは関係がない。 法が法として機能するために、今掲げたような幾つかの条件が必要であることが、法と道徳との必然的なつながりを意味するといわれることもあるが、これも誤りである。 切れ味の良いことがナイフの道徳性を示していないのと同様、法が法として機能するための条件を備えていることは、法の道徳性を示していない。 今述べたとおり、きわめて不道徳な目的を持つ法も、法として機能するためには、このような条件を備えていなければならない。 法の支配の限界 さらに、法の支配は、法が備えるべき条件の一つに過ぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もあることに留意しなければならない。 法の支配の要請がどこまで充足されるべきかは程度問題であり、個別の企業を国有化するための立法や女性のみを保護対象とする労働立法も、一般抽象性の点で悖(もと)るところがあるとしても、政府の役割の拡大した福祉国家の下においては肯認され得るであろう。 法の支配を支える根拠となる個人の自律や社会の幸福の最大化という目的自体が、国家の役割の拡大をもたらしているからである。
◇1.2.6 硬性憲法改正手続による区分 憲法が通常の法律よりも厳格な手続によらなければ改正出来ない場合、それを硬性憲法と呼び、通常の法律と同様の手続で改正し得る場合、軟性憲法と呼ぶ。 硬性憲法と軟性憲法の区別は、ブライス(Bryce, J.)によって為されたもので、彼は、成典か否かの区別を前提とせずに、憲法一般にこの分類をあてはめた(J. Bryce [1901] pp.128-33)。 一国における実質的意味の憲法がすべて成典化されることは実際上あり得ず、従って、それがすべて硬性化されることもあり得ない。 硬性憲法の国か軟性憲法の国かの区別は、その国に硬性の憲法典があるか否かの区別として捉えられるべきである。 現在のイギリス、建国当初のイスラエルなどが、軟性憲法の国家の例として知られる。 硬性憲法の特長 近代立憲主義は、一般に憲法の成典化とその硬性化とを推し進めた。 国家機関への拘束と人民の権利の内容を成典化し、明確にすればその遵守を期待することが出来るし、そうして生まれた成典憲法を、通常の法律より厳格な手続でしか変更できない憲法とすれば、そのときどきの議会多数派の手から少数者の権利や社会生活の基礎となる価値を保障することが出来、また改正手続に国民投票を取り入れることで、国民の意思を憲法に反映すると同時に、憲法の正統性を強めることも可能となる。 さらに、連邦国家においては、連邦を構成する各州の承認が改正のために必要となる。 もっとも、憲法改正手続が厳格であることは、必ずしも実際の改正が困難であることを意味しない。 改正が為されるか否かは、政治情勢や憲法擁護に対する国民の考え方にも大きく依存する。 他方、改正が困難であると、実際の状況に合わせて不文の慣習が補充的にあるいは憲法典に反する形で成立することがある。 しかし、憲法典の解釈が柔軟に為されるならば、憲法典が同一のままであっても、さまざまな状況の変化に対応することが可能となる(1.3.4、1.3.5 参照)。 日本国憲法は、硬性の憲法典であり、改正のためには、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民の承認とが必要とされる(1.4.1 参照)。
◇1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分憲法の2つの部分 近代立憲主義が国民の権利・自由を保障するうえで、議会・内閣・裁判所などの国家機関の仕組みや権限に着目するのは、これらの機関こそが国家権力の実際の担い手であると考えるからである。 この前提は、現代社会において権力が行使される状況を正確に反映しているであろうか。 バジョット(Bagehot, W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。 前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。 バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット [1970] 第1章)。 現代憲法の機能的部分 この区別に即して現代の日本の政治制度を分析するとどうなるだろう。 天皇制は明らかに尊厳的部分に属しているが、さらに、唯一の立法機関とされる国会や行政権を統括するはずの内閣も、次第に尊厳的部分へと追いやられているように見える。 実際に統治活動の中心にあるのは、大部分の法案を準備し予算案を編成する中央官僚機構と、財界・産業界・各種圧力団体の要請と支援を受け、ときには外国政府の圧力を受けて官僚の活動に影響力を行使する政権政党である。 そして、統治活動の態様も、法律およびそれに基づく国民の権利自由の制約ではなく、補助金の交付や行政指導、人員の派遣など、法的コントロールに馴染みにくい形をとることが増えている。 このような憲法の機能的部分の活動を厳格な法のコントロールの下に置くことは、とりわけ行政活動の肥大した現代国家では難しい。 それは、彼ら自身が立法・行政活動の主体でもあり、そうである以上、法的措置をとる以前に、他の方法で所期の効果を達成することができるからである。 いずれにしろ最後は法的措置を取られると分かっている以上、相手方も長期的観点からなるべくコストがかからず、摩擦の少ない形で機能的部分の要求に対処しようとするであろう。 機能的部分に対する制約 もちろん、機能的部分に属する人々も全く無制約で活動するわけではない。 数年ごとに行われる国政選挙のため、有権者の意思を無視することは許されない。 従って、世論に影響を与えるマスメディアの批判も大きな効果を持つ。 また、機能的部分の権力の主要な源泉が、国会や内閣など憲法の尊厳的部分の活動をコントロールし得る点にある以上、国会や内閣の活動を規律する憲法典、各種の法令および慣習は遵守せざるを得ない。 もっとも、これらのルールは、そのすべてが裁判所によって強行されるわけではないため、彼ら自身によって承認されている限りにおいて、彼らの行動を縛るという性格は残る。 裁判所の違憲審査権が行使される場合でさえ、最終的な有権解釈権者たる最高裁判所によって解釈された限りにおける憲法が適用されるに過ぎない。 権力の拘束を使命とする憲法は、究極的には、権力者自身によって受け入れられている限りにおいて、権力を拘束することができる(この点については 1.3.3、1.4.2、1.4.3 を見よ)。 もちろんそうは言っても、憲法と現実の距離には許容限度があろう。 憲法を単なる神話として軽視することは、機能的部分の権力の基礎を掘り崩すことになる。 機能的部分の機能性もその神話によって支えられているからである。 ◆1.3 憲法の法源と解釈◇1.3.1 成文法源と不文法源法源という言葉も様々な意味で用いられるが、広義では、法の存在形式を指す。 実質的意味の憲法が国法体系においていかなる形をとって現れるかにより、各種の法源が存在することになる。 このうち、憲法典、条約、法律など成文化されたものを成文法源、慣習、判例などのように成文化されていないものを不文法源と呼ぶ。
後述するように(1.3.4)、判例については、それが狭義の法源にあたるか否か、そして慣習については、それが最狭義の法源にあたるか否かが問題とされている。 ◇1.3.2 日本国憲法主な成文法源としては、憲法典である日本国憲法、さらには国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、皇室典範などの法律の他、衆議院規則、参議院規則、最高裁判所規則などがある。 このうち最も重要なものは日本国憲法であり、実質的意味の憲法のうち極めて重要な部分が、この法典によって定められている。 日本国憲法は近代立憲主義の系譜に属しながら現代的な特質をも備えた硬性の憲法典であり、前文と全11章からなる本文とによって構成されている。 前文については、これを単なる政治的宣言と見なし、その法源性を否定する見解み見られるが、少なくとも立法や解釈の指針としての役割は果たし得るとする見解の方が有力である。 法源性を否定する根拠としてしばしば掲げられるのは、前文の規定の抽象性であるが、そのことだけを取ってみれば、本文の規定についても同様に当て嵌まる事柄である。 また、前文の改正には96条の定める手続を踏むことが必要であり、その限りで憲法典の一部たる性格を失わない。 ◇1.3.3 最高法規憲法の最高法規性 憲法98条1項は、日本国憲法を「国の最高法規」とし、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は「その効力を有しない」と定める。 ここにいう最高法規とは、形式的効力において最高の法という意味である。 憲法の条文自体あ、このように定めているというだけでは、憲法を最高法規とする根拠として不十分である。 「私は正直者です」という者が、必ずしも正直者とは限らないことと、事情は同様である。 通常は、96条の定める改正手続の硬性と81条が明定する違憲審査制とが、憲法の最高法規性を制度面で裏付けているとされる。 また、97条の述べる基本的人権の性格は、前文並びに1条、9条で明らかにされた国民主権主義および平和尊重主義と相俟って、憲法が最高法規たる実質的理由を基礎づけているとされる。 法の運用者による受容 もっとも、日本国憲法が硬性の改正手続や違憲審査制の設置などの制度的特徴を備えていること、そして、日本国憲法がその内容において、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義などの正当な原則を掲げていることは、日本国憲法の日本における最高法規性を直接に基礎づけるわけではない。 この種の正当性を標榜する法文は世界に数多く存在するが、当然のことながら、それらのすべてが日本の最高法規と見なされてはいない。 日本国憲法が日本の最高法規である直接の理由は、日本社会において法の運用に携わる人々-官僚、裁判官、議員等-が、「日本国憲法を最高法規として扱うべし」というルールを受け入れ、それに則って行動しているからである。 つまり、日本国憲法が国の最高法規なのは、「日本国憲法を最高法規として扱うべし」という実質的意味の憲法が事実上存在するからであり、そのような実質的意味の憲法が存在するのは、それを法の運用者が事実上受け入れ、それに則って行動するからである。 もちろん病理的な政治体制を除くと、法の運用者によって受け入れられているルールは、社会の大多数のメンバーによっても受け入れられているであろう(ハート・法の概念第6章参照)。 法の運用者になぜそのようなルールを受け入れるのかと問えば、日本国憲法が基本的人権を保障するから、あるいはそれが硬性の憲法典だからと答えるかも知れないが、単に、そんなことは当たり前だと応ずるかも知れない。 平常時にこのような問い掛けをする人間は稀であろう(1.4.2 参照)。 経過規定 憲法98条1項に関しては、それが従前の法令の効力について定める経過規定としての意味を有するかという問題が議論される。 支配的学説や判例(最大判昭和23.6.23刑集2巻7号722頁)は、この問題を積極に解し、98条1項は、日本国憲法施行の際に存する明治憲法下の法令のうち、憲法の条規に反しないものについては、引き続き効力を有する旨をも意味しているとする。 明治憲法下の法令のうち、法律事項を規定するものには法律としての、それ以外の事項を規定するものには命令としての効力を暫定的に認めた1947年法律72号、政令14号も、この趣旨を受けたものとされる。 しかしながら、98条1項が経過規定としての意義を持たず、そのため日本国憲法が経過規定を全く欠いていたとしても、法秩序が革命的な変革を受けた場合にそうであるように、民事・刑事の事件を日々解決すべき裁判所などの法適用機関は、成立時において有効に制定された法令である以上、制定の根拠となる規範(この場合は、明治憲法)が消滅した後も当該法令の内容が新たな憲法に違反するなどの特別な理由のない限り有効に存在し続ける続けるものとして適用するはずである。 さもなければ、安定した法秩序に基づく市民生活の継続は不可能となる(芦部・憲法学Ⅰ100頁)。 憲法の大規模な改正を理由に下位の法令をすべて無効とすれば、従来の法を前提として生活してきた人々の期待を覆し、「法の支配」の要請に著しく反することになる。 民法および不動産登記法が新憲法の成立によって失効したか否かが争われた事件で、最高裁が「法律は一旦適法に制定された以上その後の法律により改廃せられない限り効力を失うものではない」と述べているのも同様の趣旨と考えられる(最判昭和30.4.5民集9巻4号456頁)。 つまるところ、98条1項が経過規定であるか否かという問題は、さほど重要なものではない。 占領法規の効力 占領時代に制定された法令の独立後の効力についても、同様に考えることが出来るはずである。 最高裁の判例は、連合国最高司令官の要求の実施を政府に義務づけた昭和20(1945)年緊急勅令542号およびそれに基づく政令(いわゆるポツダム命令)について、日本国憲法施行にかかわりなく憲法外において法的効力を有していたとの立場をとった(最大判昭和28.4.8刑集7巻4号および最大判昭和28.7.22刑集7巻7号1562頁)。 平和条約発効後の同勅令に基づく命令の効力については、当初、
通説は憲法98条1項が経過規定としての意義を持つとの前提から第②説の立場をとる(清宮・憲法Ⅰ26頁、宮沢コメ806頁)。
◇1.3.4 不文法源不文の法源としては、慣習と判例とが問題とされる。 慣習や判例が法源であるか否かが問われる際には、暗黙のうちに、一般的抽象的な形で妥当すべき規範を確定している制定法こそが本来の法源でると前提されたうえで、このような性格を持たない慣習や判例を果たして法源として認めることが出来るかという形で問いが立てられることが多い。 判例について厳格な先例拘束性が当て嵌まる場合にのみ、それを法源と呼ぶことが出来るという主張は、できるだけ判例を制定法に近づけて解釈しようとする試みの一つである。 逆に、具体的な事例から構成される慣習や判例に現れた社会の伝統的な考え方こそが、その共同体における人々の行動のあり方を示す法の本来の姿であり、制定法こそが例外的な現象であるとの理解もありえよう。 以下では、一般的抽象的な規範を確定的に示す制定法が、典型的な法源であるとの前提の下に、慣習と判例とがどこまで、法源としての性格を備えているかという問題を扱う。 以下、分説する。 (1) 憲法慣習慣習の合理的基礎 慣習が、少なくとも憲法典よりも形式的効力の劣る法源として、実質的意味の憲法の一部たり得ることは、多くの論者が認めるところである。 そのような慣習の成立要件については議論の対立が見られる。 一つの見解は、イギリスにおける憲法習律についての議論にならい、慣行が規範意識をもって遵守されていることに加えて、その慣行に合理的理由のあることを要求する(伊藤・憲法80-82頁)。 たとえば、衆議院の解散を実質的に決定する権限の所在、および解散の許される要件については憲法典に明確な規定がないが、慣例上は、1948年12月の第一回解散以来、内閣が実質的な決定を行い、しかもほとんどの場合、憲法69条所定の衆議院の議決なしに解散が行われてきた。 解散に先立って内閣不信任の議決が行われたのは、1952年8月、1953年3月、1980年5月および1993年6月の4回の解散にとどまる。 そして、議院内閣制の下における議会と内閣との均衡を保ち、かつ重大な政治問題について時機を失することなく有権者の審判を仰ぐためには、内閣に自由な解散権を与えることにも合理性があると考えられることから、このような慣行は習律としての地位を得たとの有力な見解がある(解散権の所在と行使の要件については 13.3.3を、習律については 13.3.3 (3) 【憲法習律】を見よ)。 もっとも、慣習の主要な機能を、社会で反復して発生するさまざまな調整問題状況を解決することに求めるならば、当該慣習に、他の選択肢と比較して特別の合理性を要求することにはさほど意義が認められないことになる。 他の選択肢と比べて、その慣習がはるかに合理的なのであれば、そもそも、その問題は調整問題ではなかったということになろう。 解散権の行使の要件の問題についても、内閣に広い裁量を与えることが、裁量を狭めることに比べて、明らかに合理的であるか否かは疑わしい。 広い裁量は、党利党略に基づく解散を引き起こす危険を増し、政権党に有利な形で解散権が行使される可能性を広げることになる。 もちろん、慣習の機能が調整問題状況の解決にある以上は、たとえ慣習として成立した選択肢が他の選択肢に比べてとくに合理的であるとはいえなくとも、なお、その慣習に従うことには合理性があることになる。 憲法典に反する慣習 他方、憲法慣習が憲法典を改廃する効力を持ち得るかについては、厳しい意見の対立がみられる。 慣習が憲法典を改廃し得るとする主張は、憲法改正手続によらずに憲法の意味内容が慣習によって変化し得ると認めることになり、法的意味における憲法の変遷を認めることとなる(1.4.3)。 憲法制定者が制定当時に想定した状況のその後の変化に対応する必要性や、国政のあり方に対する主権者たる国民の決定権を強調する人々は、国民の合意を得た憲法慣習による憲法典の改廃を認めようとするが、硬性憲法の意義を重視する人々は、主権者の意思とされるものが多くの場合、立法府や行政府など国家機関の意思に過ぎないことを指摘し、憲法慣習に憲法典と並ぶ効力を認めることは危険であるとする。 少なくとも、合意(consensus)を理由に、憲法の変更を主張することは出来ないであろう。 同意(consent)と異なり、単なる意見の一致である合意が法的効力を基礎づけることはあり得ない。 世論調査が国民投票の代わりになり得ない一つの理由はここにある。 3つの論点 慣習が憲法典を改廃し得るかという問題については、3つの点に留意する必要がある。
(2) 判例判例とは裁判の先例をいう。 判決や決定などの裁判が、具体的事件を解決する限りにおいて法としての意味を持つことは当然のことである。 問題となるのは、本来、具体的事件を解決するために下された裁判が、後の裁判を拘束する一般的な規範としての意義を持ち得るか否かである。 このような意味での判例となるのは、通常、先例とされる裁判の判決理由中の判断のうち、主文を導くための直接の論拠となっている部分(ratio decidendi)に限られ、それ以外の傍論部分(obiter dictum)に判例としての意義が認められることはないといわれるが、実際には傍論部分の判断が後の裁判で論拠として援用されることも少なくない。 判例の拘束力 先例拘束主義(principle of stare decisis)の妥当する英米法圏においては、判例は「法的拘束力」を持つが、日本を含めてそれ以外の諸国では、「事実上の拘束力」を有するに過ぎないといわれることがある。 もっとも、イギリスにおいても、厳格な先例拘束主義が確立したのは、せいぜい19世紀の後半からのことである。 判例法の特質はむしろ個別の事件ごとに背景となる正当化根拠に応じて柔軟な解決を目指す点にあり、そもそも先例の権威ある定式化を許さない。 予測可能性と法的安定性を図るたまに厳格な先例拘束主義を導入することは、古典的な判例法の考えからすれば逸脱であり、先例の拘束力のみに着目して判例法を論ずるのはむしろ制定法国の見方ではないかとの疑問もある。 他方、事実上の拘束力と法律上の拘束力との間にどれほどの実質的な違いがあrのかという問題もある。 法律問題の最終的な有権解釈権を持つ裁判所が、判例に事実上拘束されるということは、取りも直さず判例が法的な拘束力を持つことを意味するのではないかとの疑問を提起することも可能である。 憲法典や法律が法源であり得るのも、裁判所がそれらを事実上適用するからであり、裁判所が憲法典や法律を適用しなくなれば、それらはもはや法源ではあり得ない。 実際、もし裁判所が、何が ratio decidendi であるか、あるいは、当該事件は先例と区別(distinguish)され得るかなどという問題に頭を悩ますこともなく、事実上先例を援用して具体的事件を解決しているのであれば、事実上の拘束力は法的拘束力よりもむしろ強力であるといえる(樋口・憲法430-33頁参照)。 少なくとも、最高裁判所の判例が下級裁判所に対して持つ拘束力に関する限り、事実上の拘束力説と法的拘束力説との間に意味のある違いはない(最高裁判所の判例が最高裁判所自身を拘束するかという問題については、14.4.7 を見よ)。 法源としての判例 国民主権の理念を徹底させる立場からは、国会や内閣と異なり、国民に対して政治責任を負うこともなく、従って必ずしも国民の意見を反映していない裁判所の裁判が、法源として扱われることには疑義を呈し得る。 これに対しては、判例を法源とすることによって国民に裁判の結果についての予測可能性を保障し得ること、そして法律によって判例を覆す権限を持つ国会が判例を放置すること自体、国会の黙示の承認を意味すると反論することができよう。 判例が狭義の法源にあたることは承認できるとしても、最狭義の憲法法源、つまり合憲・違憲の判断基準になり得るか否かは別問題である。 この問題は、慣習を最狭義の法源と考えるべきかという問題の一事例である。 判例が最狭義の憲法法源であるとすると、判例は同じレベルの後法として憲法典を改廃し得ることになる。 この問題については、憲法慣習について述べたこと、そして憲法の変遷について後述すること(1.4.3 (2))がそのまま妥当する。 ◇1.3.5 憲法の解釈憲法典や法律などの法源の中には、なんらの意識的な解釈を要することなく、一読して直ちに意味を了解し得るものもある。 あらゆる条文、あらゆる文言が解釈を必要とするとすれば、解釈の結果たる言明もさらに解釈を要するはずであり、この解釈の連鎖は終わることはなく、条文の意味は永遠に不明となろう。 しかし、法源の中には、不明確な概念を用いていたり、相互に衝突するかに見える複数の条文が存在することから、さまざまな解釈を許すものもあり、そのような場合、裁判所をはじめとする法適用機関は、まず、適用されるべき法源の意味を解釈によって確定する必要に迫られる。 裁判所も各種の法源によって一義的に拘束されているわけではなく、議会が一定の憲法典の解釈に基づいて法律を制定するように、裁判所による裁判をある種の立法作用として見ることも可能である(ケルゼン・一般理論242-43頁)。 解釈の条件 さまざまな意見の対立が見られる法律問題について如何なる解釈を選択すべきかは、重要な問題である。 一般に、正当な解釈の満たすべき条件としては、以下のようなものが挙げられる。
もちろん、このような条件を満たす解釈があらゆる法律問題について必ず一つだけ定まるというわけではない。 裁判所の有権解釈が定まった後においてもなお、正当な解釈が何かについての論争が続くことの方が普通である。 ◆1.4 憲法の変動と保障ここでは、憲法の変動の類型と保障の方法のうち、憲法改正について論ずる。 憲法の保障の方法のうち、違憲審査制については、14.4 での説明を、また、抵抗権の問題については、5.1.3 (2) の説明を見よ。 なお、本節の議論は、日本国憲法を典型とする近代立憲主義の系譜に属する硬性の憲法典を持つ国家を念頭に置いている。 ◇1.4.1 憲法改正の手続憲法改正とは、憲法典に定められた特別の手続を踏んで憲法を修正することであり、その点で、憲法典に定められた手続を踏まずに憲法の意味内容を変更する憲法変遷とは異なる。 憲法典も、特定の目的を実現するために作り出された一種の社会的技術であり、道具である。 道具が、当初の目論見どおりに働かなかったり、あるいは目的自体が変わった場合には、道具としての憲法典を修正する必要が生ずる。 作り直しの必要があるか否かは、実際に使ってみたうえでなければよく分からない。 多くの憲法典は、自ら修正の手続を定めており、日本国憲法も例外ではない。 日本国憲法の改正手続は、発案、発議、承認という3つの段階を経ることとなっている。 発案 発案とは、国会による発議の前提として、国会のいずれかの議院において、改正の議案が提出されることをいう。 その院の議員が、この発案を為し得ることは疑いがない。 内閣が、この発案を為し得るか否かについて議論が為されているが、憲法上、大臣の過半数は国会議員でなければならないため、たとえ内閣に発案権がないといても、大臣は議員としての資格で、発案を為し得る。 発議 国会による発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされている(憲法96条1項)。 改正手続に関しては、衆議院の参議院に対する優越は認められない。 総議員の意味については、
欠員が反対票に数えられるのは不合理だとするのが②説の論拠であるが(清宮・憲法Ⅰ400頁、宮沢・コメ790頁)、欠員がある分だけ改正が容易になるのも同様に不合理であるし、出席議員の3分の2の賛成で反対派を除名することにより改正を容易にする道を防ぐためには(憲法58条)、①説の方が妥当である(伊藤・憲法 654頁)。 承認 国会の発議の段階で各議院に必要な数の賛成を得られない議案については、その時点で手続は中止する。 もし必要な賛成が得られたならば、次に国民投票にかけられ、国民の承認を求めることになる。 国民の承認については、必要なのが、①有権者の過半数か、②無効票を含めた総投票の過半数か、③有効投票の過半数か、という対立がある。 有効投票の過半数と考えるべきであろう。 2007年5月に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、国民投票の手続について定めるとともに、国会による発議に関する手続を整備するための国会法の改正を行うものである。 改正案の原案の発議は、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成をもって「内容において関連する事項ごとに区分して行われる」(同法151条、国会法68条の2、68条の3)。 国民投票は、国会が改正を発議した日から起算して60日以後、180日以内において、国会の議決した期日に行われ(同法2条1項)、国民投票において、改正案に賛成する投票数が有効投票総数の2分の1を超えたときは、憲法96条1項にいう国民の承認があったものとされる(同法126条1項)。 ◇1.4.2 改正の限界憲法改正に限界があるか否かについては、一般に、
そして、これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている。 日本国憲法の下では、国民主権の原理に「反する一切の憲法・・・・・・を排除する」と述べる前文の文言、戦争、武力による威嚇または武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては「永久にこれを放棄する」と述べる憲法9条1項、この憲法が国民に保障する基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とする憲法11条が、実体的改正禁止規定の例として挙げられることがある。 改正手続規定は、憲法96条がそれにあたる。 憲法制定権の存否と限界の有無 もし、改正権の上位に、改正権を制約する憲法制定権はないと考えるならば、改正権には限界はないという答えが出て来ると考えられている。 上の3つの論点に即していえば、たとえ実体的禁止規定が存在したとしても、それ自体を改正してしまえばよいし、そのような禁止規定がない場合に改正に限界が存在しないことは当然である。 また、所定の改正手続を踏みさえすれば、改正手続規定自体を改正することにも障害はない。 これに対して、改正権は、上位にある憲法制定権により授権された権限であると考えるならば、改正権は憲法制定権自体の根拠となっている「根本規範」を変更することはできず、そのような改正がたとえ行われたとしても、それは法的には「革命」であって「改正」ではない。 もし、実体的な改正禁止規定が、憲法制定権自体を構成する根本規定の内容を確認するものであれば、そのような改正禁止規定を変更することはできない。 さらに、改正手続規定についても、改正権がこれを変更することは、自らが憲法制定権に成り代わることを意味するので、原則として許されない。 限界の有無は何によって決まるか 以上のような考え方については、以下のような論点に留意する必要がある。 第一に、憲法の最高法規性に関する状況(1.3.3)と同様、憲法改正の限界の有無に関しても、直接には、憲法改正に関与し得る人々-国会議員、官僚、裁判官、広くは有権者一般-が、実際に何等かの限界を受け入れているか否かが問題である。 何等かの限界がこれらの人々に事実上受け入れられていれば、その事実上のルールに則した形で限界は存在する。 ここでも、日本国憲法という憲法典が改正の限界について何事かを語っているか、あるいは、普遍的妥当性を有する政治道徳の原則が憲法の背景に存在するかという問題への答えは、改正の限界の有無を直接には導かない。 また、憲法制定権が改正権のさらに上位に存在するか否かという問題も、限界の存否とは直接には結びつかない。 改正権が最高機関であれば、改正に限界はないという議論は、憲法典のみが憲法の領域における実定法であるという誤った前提に立脚したものであり、改正権が最高機関であること自体が、法の運用者によって受け入れられている限りで成り立つという事情を見逃している。 さらに、改正権が最高機関であるという前提からは、改正権を構成している規範を自ら改変することはできないという結論、つまり一定の論理的な改正の限界があるという結論をも導き得る。 一般に、法が存立するためには、それを定める立法機関を構成する授権規範が別に存在している必要がある。 法は、その存立の根拠を自らに与えること、つまり自己授権を行うことはできない(清宮・憲法Ⅰ17頁、長谷部 [1991] 27-28頁)。 立法機関を構成する授権規範は、①立法権者、②立法の手続、③立法の内容、を定める三種類の規範から成り立つ。 現在の日本における形式的意味における法律の場合でいえば、
つまり、法律の制定権を基礎づける授権規範は、憲法典がこれを定めている。 法律の制定機関である国会は、自己の権限を構成し、その根拠となっているこれらの授権規範を変更することは許されない。 他方、憲法改正権も一種の立法権である。 それを構成する授権規範は、
従って、改正手続規定を変更することも、実体的改正禁止規定を変更することも許されないという結論が、そこから導かれる。 これに対しては、国会の立法権の授権規範は、憲法のみではなく、国会法など国会自身の制定する法律によっても定められており、これらの法律については国会自身が改正することが出来るのだから、憲法改正権もやはり憲法典によって定められている限りで自分自身を構成する授権規範を改正することは可能であるとの反論があり得る。 しかし、憲法典の定める国会の授権範囲は、それなくしては立法権者たる国会が存在し得ない原初的な規範であり、国会法などの法律による規定はそれを補足するものに過ぎない。 同様に、憲法典によって定められた改正権の授権規範も改正権をはじめて構成する原初的な規範であって、改正権自身による改正を許さない。 憲法改正権の上位に、憲法制定権が存在するという前提に立って、はじめて、憲法制定権を構成する根本規範(それは憲法制定権を構成する授権規範である)に反しない限りで、実体的改正禁止規定を改正し、あるいは改正禁止規定を改正する余地が生まれる。 憲法制定権の存在は、改正の限界をむしろ縮小し、改正し得る範囲を拡大する(根本規範によって構成されない、制約のない始源的な憲法制定権力なる概念が筋の通ったものではあり得ない点については、1.2.3【憲法制定権力】参照)。 「改正の限界」の意味 第二に、「改正の限界」という概念の意味である。 改正権に限界があると主張する論者も、そのような限界を超える改正が事実として起こり得ないと考えるわけではなく、そのような「改正」が行われたとしても、それは法的な観点から見れば「改正」とは評価し得ず、変更後の憲法と変更前の憲法との間には、法的連続性はない、つまりそれは「改正」ではなく「革命」であるとするにとどまる。 従って、新しい憲法は、前の憲法とは異なる根本規範に立脚した憲法だということになる。 何等かの改正の限界が、実際上広く受け入れられていたとしても、それに反する「改正」が行われる可能性はある。 このような革命的変動の後、若干の政治的動揺を経て、元の憲法が復活した場合には、もともとの改正の限界が再び受容され、中間期の憲法の変動は、「違法な改正」として説明され、処理されることになるであろう。 他方、革命的変動がその後長期に亘って定着し、変動後の憲法体制が当該社会の法運用者によって、そして最終的には社会の大部分のメンバーによって広く受け入れられたとすると、このとき、革命は完成したわけであり、以前の改正の限界に関するルールも「旧法」として、つまり現在では効力を有しない法として説明され、処理されることになるであろう。
◇1.4.3 憲法の変遷2つの「憲法変遷」 憲法の変遷という言葉も、様々な意味で用いられる。 非常に広い意味では、実質的意味の憲法の内容が変化することを一般的に指す。 この意味での憲法の変遷は、いかなる社会でも、常に見られることだろう。 ただ、憲法の変遷が重要な意義を持つのは、硬性の憲法典を持つ国家で、憲法所定の手続を経ずに、憲法の意味内容が変化することが認められるか否かという問題についてである。 この場合でも、憲法典の内容に反する法律や裁判が、実質的意味の憲法として通用することはあり得る。 これは社会学的意味における憲法変遷と呼ばれる現象である。 このような意味での憲法変遷があり得るからこそ、それに対処するために、各国で違憲審査の制度が設けられている。 他方、憲法所定の手続を経ずに、憲法典自体の意味内容が変化することを、法的意味における憲法変遷と呼び、このような意味での憲法変遷があり得るかについて、対立がある。 この問題は、先に述べたように(1.3.4 (1))、憲法慣習が憲法典を改廃する効力を持つか否かという問題と重なり合う。 (1) 社会学的意味における変遷実際には、社会学的意味における憲法変遷がいかにして可能であるかを説明することもそれほど容易ではない。 上位の法に反する下位の法は無効であり、存立し得ないと単純に考えるならば、社会学的意味における憲法変遷もあり得ないはずである。 幾つかの説明の仕方がある。
これに対して、違憲の法律はそもそも無効であるという立場を貫くならば、誰もが、自らの判断で違憲無効の法律を無視して行動し得ることとなり、無政府状態を招くことになろう。 人々が実定法を尊重するのは、(2)で述べるように、そうすることで重要な調整問題が解決され、各自の利益そして社会全体の利益にかなうからである。 (2) 法的意味における変遷法的意味の変遷はなぜおこるか 法的意味における憲法の変遷、つまり憲法典の改廃が、改正手続を経ることなく生じ得るかという問題については、憲法典の最高法規性それ自体も、憲法典を最高法規として扱う不文のルールが法の運用者によって受け入れられている限りではじめて成立しているという認識から出発する必要がある(1.3.3)。 憲法典以外の慣行や法令が、憲法典に代わるルールとして法運用者によって受け入れられ、それに則って法運用者が行動する場合には、憲法典が改廃されたか否かに関わりなく、最高法規たる憲法の意味内容は変動したことになる。 変遷は正当化できるか もっとも、このような実定法の認識の問題として憲法の変遷があり得るかという問題とは別に、このような憲法の変遷が正当化されるか(変遷した後の憲法に従うべきか)という問題を立てることは可能である。 あるルール(の集合)が憲法典という法形式を備えているという事実が、そのルールの拘束力を意味するという事情は、法律・命令・裁判などその他の法形式の場合と基本的には異ならない。 あるルールが特定の法形式を備えている、つまり実定法であるがゆえに、それに従うべしという実践上の法実証主義は、人々が実定法に従うことで社会生活上の多様な調整問題を解決できるという功利主義的配慮によって正当化される。 憲法は、1.1.2 で述べたように主として国家機関を組織しその権限内容と手続を定める法であるから、取引法上のルールなどとは違って調整問題の解決という役割はないとの疑問があるかも知れない。 しかし、国家が果たすべき役割を、実際にはどの機関(人々)が、どのような組織と権限を通じて果たすのかという問題は、それ自体、調整問題であり、従って、社会の大部分の人々は、各自、社会の大部分の人々が受け入れるルールを、自分も進んで受け入れようとするはずである。 大部分の人々が「国会」だと思う機関の制定した法に従うのが誰にとっても利益となるし、大部分の人が「裁判所」だと思う機関の下した裁判でなければ、それに従うことにさして意味はない。 そのような誰が国家機関かに関するルールを憲法典という特別の法形式によって定め、容易には変動しない旨を定めておけば、この調整問題の解決を期待する人々にとって便利であろう。 その限りで、憲法典を最高法規とし、かつ硬性として容易な変更を許さないとすることには正当性があることになる。 しかし、この問題が所詮、調整問題である限り、憲法典と異なる組織・権限・手続に基づいて国家機関が構成され活動を継続したとすると、多くの人々にとっては、その実効的なルールに従うことが自己の利益にも、また社会全体の利益にもかなうこととなろう。 つまり、憲法変遷を認める「べき」かという問題は、調整問題の解決という役割によって支えられる実践上の法実証主義が、「憲法典」という具体の実定法に関して有する射程の問題である。 目的が調整問題の解決である限り、憲法典の外に生じた実効的な慣習が憲法典より適切に調整問題を解決している以上は、憲法の変遷を認めるべきである。 つまり憲法典という実定法を尊重すべきだというルールをさらに支える正当化根拠により適合している。 しかしながら、憲法の果たすべき役割は調整問題の解決には限られていない。 変遷したか否かが問題となる条文の役割が、その時々の政治的・社会的多数派によっては変更されるべきでない公共財の実現にかかわるものであるとき、あるいは、社会全体の利益に抗して守られるべき人権にかかわるとき、憲法の変遷を正当化し、そのような実効的な慣行に従うべきだと主張することは出来ない。 |
| + | ... |
阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 p.45以下
<目次> ■第一節 憲法(典)の存在理由[48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある「自由」という言葉は多義的である。 本書でいう「自由」とは、強制のないこと、すなわち、「消極的自由」(negative freedom)をいう。 その自由は、他者からの強制を受けることなく、各人の望むところを、自ら有する知識に立脚して追求し得ることをいう(ハイエク『自由の条件Ⅰ』)。 「消極的自由」は、政治参加して権力を獲得すること(「国家への自由」と呼ばれる政治的自由)ではなく、「求めるものを実現する力」でもなく、また、平等の実現でもない。 さらに、「消極的自由」は、「国家による自由」と呼ばれる各人の幸福実現でもない。 「自由」とは、万人に共通する究極目的の存在を否定し、究極の目的設定とその実現を各人に委ねることを意味する(自由の意義および価値については『憲法理論Ⅱ』 [48]~[53]で詳論する)。 このように、真の自由は究極目的を知らない。 ただし、自由は、各人の意図追求にとって必要な手段についてのみ合意を生み出す。 各人がその望むところを追求するにあたって必要とするその手段こそ、共通の体系的ルールであった。 自由な国家に共通の善が存在するとすれば、それは、個人的意図の追求に便宜となる普通妥当な共通のルール、すなわち法を国家が提供し、維持することである。 [49] (二)強制は避けられないいかに自由な社会であっても、強制は避けられない。 自由は強制を基本的には忌避するものの、貴方の自由に対して強制を加える者に、国家機構が強制を加えざるを得ない。 強制を排除して、貴方の自由を保護するためには、国家機構の強制に拠らざるを得ないからである。 これを「自由のパラドックス」という(「自由」全般については『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 法という一般的抽象的ルールは、その強制を最小化し、自由を最大化するための工夫として、人間が長期に亘って学習し、受容してきた自生的装置であり、抽象的な知識である。 法は、国家による強制を最小化しつつ貴方の自由を最大化すること以外の目的を持ってはならない。 また、法は一定の条件を満たす成員全員に等しく向けられていなければならず、特定の目的を持ってはならない。 法は、ある人が何を為さなければならないかを決定できないのであり、何を為してはならないかを受範者を特定しないで決定するものでなければならない(それは、丁度我々がルールによって「フェアプレイ」を求めたとしても、それが何であるか語り尽くせず、ただ「アンフェアなプレイ」だけを具体的な文脈の中で排除できることと似ている。先の[47]で「負の力」という表現を用いたのは、これを念頭に置いている)。 法の中でも憲法(典)は、国家機構による強制の及び得る範囲を画定し、各人の自由を最大化することを目的としている。 [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない「自由」は、各人の生活設計について各自の判断に委ねるよう指示するものの、万人にとっての共通の目的を持たないだけに、統治機構の具体的なあり方については何も指示しない。 「自由」は統治権力に対する「負の力」にとどまる。 そこで我々は、「自由」のために、憲法(典)において、歴史的経験的に学びながら、「自由」を諸基本権カタログとして類型・具体化し、なおかつ、各人の選好を強制のない中で統治に反映させながら、「制限された政府」として相応しい統治の機構(強制を最小化する国家機構)を定めようとするのである。 その結果、憲法は、「統治機構と基本権の部から成る」、と言われるに至る。 中でも、ヨーロッパ大陸では、その絶対主義の崩壊期に、政治的統一体としての国家を維持するためには、組織的な統一性を法文書として書き込むことが必要であった。 それが、成文憲法、すなわち、憲法典である。 成文憲法の原点は、この観点からすれば、個人の自由権を文書の上で確定することにあるのではなく、政治的統一体としての国家の構成を明示することにあった。 換言すれば、憲法典は、第一に、国家との関係で市民が自由に行為できる領域を確認すること、第二に、市民の自由な領域を最大化するに相応しい国家機構を設計図として描くこと、を目的として制定されたのである。 [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という近代立憲主義的意味での憲法とは、強制の不存在という意味での消極的自由を擁護するために、「配分原理」および「組織技術」(権力分立という統治技術)を内容として組み込んだルールをいう(権力分立については、後の第10章の [185] 以下でふれる)。 「配分原理」とは、自由は法の許容(国家の意思)によってもたらされるものではないからこそ、原則として無限定に各人に保障されるのに対し、その領域を侵害する国家の権能は限定されることをいう。 近代立憲主義は、多くの場合、成文、成典かつ硬性の形式をもつ憲法典のもとでの統治を実現しようとした(この時点から、憲法と憲法典とが同視され易くなる)。 立憲主義憲法は、「実質的意味での憲法」(成文、不文を問わず、およそ国家の組織・作用の基礎に関する constitution)を、「形式的意味での憲法」(憲法典という成文成典形式で存在する憲法)の中に可視化させながら可能な限り閉じ込めた。 そればかりでなく、憲法典は、最高法規という実質をもつことによって下位法に対する拘束力を併せ持った。 またさらに、それは、権力分立という組織技術に拠りながら、統治権力の行使を制限することによって、国民の自由を保障するという「配分原理」を狙ったのである。 もっとも、国民の自由とは消極的自由をいう、と先に定義づけたものの、近代立憲主義のモデルを、フランス革命に求めるか、それともアメリカ革命に求めるかによって、「自由」や憲法の存在理由を捉える方向は変わってこよう。 この点は、次の[54]でふれる。 [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である「立憲制とは、制限された政府を意味する」(ハイエク)といわれる。 近代立憲主義的意味での憲法は「制限された政府」を実現するための法文書である。 そのためには、統治に先行しそれを指導する規範を可能な限り明文化することによって、統治権力を制約することを構想しなければならない(もっとも、その規範が全面的に明文化されることはない)。 そのルールこそ「法の支配」という思想である(この点は、後の第四章[64]~[75]でふれる)。 ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」[53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である「自由」とは、[48]で述べたように、外的強制のないことをいう。 自由主義とは、国家の強制力を制限し、法がどうあるべきか(または、誰が権限保持者であれ、権力者に課せられるべき制限、国家活動の範囲にかかわる体系)に関する思想体系である。 自由主義は、個人の自由を最優先する思想体系であるが、それは、次の二つの要素から成る。
真の自由主義は、国家の経済政策をも法の支配のもとに置くことを考えたのである。 自由の領域から防御権としての個別的な基本権が生ずるとした場合(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [55] で述べる)、基本権は超国家的・前国家的に存在するものであって、国家が法律によって授与するものではない、と考えられ易い(その思考法が自然権思想である)。 しかし、自由といえども国家内に存在し、国家によって保護されると考えるのが正しい。 国家と憲法の存在理由は、個人の自由領域を保護し、それをカタログとして例示し、自由を根源とする基本権保護に奉仕する点にある。 もっとも、自由と基本権とは同義ではない。 自由は、諸基本権を獲得するための条件を各人に提供する基盤である。 諸基本権は、一般的自由を基幹として保障されるに至るのである(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [52]~[55] 参照)。 民主主義なる語は、個人的自由を尊重する体制を指すものとして度々用いられてきている。 ところが正確には、自由と民主は包摂関係にも、対立関係にもない、相互独立の概念である。 [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である自由は法と対立するものか否か、歴史を通じて絶えず論争されてきた。 かたや古代ギリシャ時代の主流思想から始まって、ロック、スコットランドの自由主義者から、今日のアメリカの政治学者に至るまで、《自由は法なしには存在しない》と説いてきた。 彼らにとって、法は、個人に何を為すべきかを指示するものではなく、個人の選択の機会を保障するものとされ、そのために、自由と法とが不可分であると考えられたのである。 他方、ホッブズ、ベンサム、フランスの思想家、そして近代の法実証主義者たちは、法は基本的に自由への侵害であり、従って、「自由とは法の禁じていないことを為す一切の権利である」(ベンサム)と説いてきた。 この見解の対立は、法に対する見方の違いを反映している。 法実証主義者は、法が人間の合理的設計(意思)に従って作られるであろうことに期待を寄せ、法(law)と立法(legislation)とを同一視しながら、設計の外に漏れやすい自由を法(立法)に従わせようとする。 このため、法と自由が対峙され、法の自由侵害性が説かれるのである。 これに対してスコットランド啓蒙思想の流れを汲む自由論者は、法は合理的設計によって語り尽くされるものではなく、人々の自由な営為の積み重ねのなかで修得されて生まれ出るものであって、権力者の意思(立法)がその法を侵害しないところにこそ自由あり(【N. B. 9】参照)、とみるのである。
[55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である民主主義とは、多数意見による決定方式に基づきながら、何が法となるかについての教義をいう。 その教義は、これまで国民主権の理論のみならず、基本的人権の尊重思想と不可分の形で、あたかも統治の目的であるかのように議論されてきた(目的としての民主主義観)。 民主主義が自由の条件であるかのように説くとすれば、それは民主主義という用語の濫用である。 自由の範囲は、政治的意思決定の及ぶ干渉の範囲によって左右されるのである。 民主主義とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 それは、誰が権力を如何に行使するかを問うのである。 自由主義と民主主義との関係の捉え方は、次のように様々である。
「民主主義」(democracy)は、ギリシャ語のデーモス(demos = 多くの人々)のクラトス(kratos = 権力)を語源とすることから分かるように、「権力は人々に属す」の意であり、「多くの人々による支配」を表すにとどまる。 「民主」なる用語の濫用の典型例が、「実体的民主主義」とでもいうべき民主主義観である。 この立場は、実体価値として、特に「自由で平等なる市民(シティズン)としての価値」を重視し、市民を自由で平等な道徳的・自律的存在として処遇することこそ民主主義的である、とみるのである。 先にふれたように、この見方が、残念ながら我が国にも深く浸透してきた。 確かに、民主制を専制と対比しながら、前者の特徴が「自律」による統治または「自己統治」にあり、後者のそれは「他律」による統治にある、と説くことは、専制に対するプロパガンダとしては有効であった。 ところが、個人の尊厳保障を民主制の条件と説いて、自由または平等にまで言及することは、あまりに実体的価値を吹き込んだ誤用である。 また、利益・選好を異にする多数者国民による政治的決定を「自己決定」と呼ぶことはできない。 「自己決定」は、あくまで個人についていい得るだけである。 これに対して、先に示した民主主義の意義づけは、「手続的民主主義」とでもいえる考え方であり、これは、国民が被統治者であるという事実を率直に承認しながら、その政治参加の手続(投票、言論、請願、ロビー活動等)を民主主義の中身におくのである。 [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか民主主義がなぜ正当であるのかという疑問に関しては、通常、次のような解答が寄せられてきた。
被治者が治者に対して有効な統制を加える最大の機会が選挙である。 選挙権の法的性質については後にふれるが([167]以下参照)、選挙とは機関としての国民(または主権者としての国民)の行為ではなく、各人の手続的な権利として捉えられねばならない。 もっとも、民主主義は、選挙後の平和的な政権交替の前提として、投票期において次のような条件を満たしていなければならない。
[57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という民主主義の正当化理由もさることながら、それを制度化するに当っての条件の検討も必要である。 その検討は、R. ダールによって為された。 彼は、ポリアーキィ(※注釈: polyarchy)(民主制に最も近い「多頭制」という政体)の条件として、次の諸点を挙げている(ダール『ポリアーキー』)。
■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項[58] (NO TITLE)憲法典とは、国家の統治の基本的事項、つまり、constitution の内容を組織的に編纂した法典(実定法)をいう。 それを「国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範」と言い換えてもよい(佐藤・20頁)。 憲法典には、日本国憲法やアメリカ合衆国憲法のような単一成文典方式と、スウェーデン、フランス第三共和国のような複数制定方式とがある。 明治憲法時代には、大日本帝国憲法と皇室典範という二つの成文成典から成る複数制定方式が採られた。 憲法典が、国家の統治の基本的事項を規制するものである以上、その規制事項としては、
その他、対外的独立性という意味での主権や、国家の支配権という意味での主権の及ぶ範囲(領土)等に言及している例もあるものの、これらは、国際法上決定されるものであって、国内法たる憲法典で規制しても無力である。 ■第四節 憲法典の特性[59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である憲法典の特質として、通常、「法の法としての憲法」に言及され、それはさらに、①授権規範としての憲法典、②制限規範としての憲法典、③最高規範としての憲法典、に分類される(清宮Ⅰ・16~38頁)。 そのことを、ハート流にまとめれば、憲法典とは、ある実定法体系内での「確認のルール」のうち、最上位に位置するルールである、ということになろう([47]参照)。 憲法典は、統治に関する制限規範(実体規範)であると同時に、最上位の授権規範(手続規範)である。 換言すれば、憲法典は、赤裸々な政治上の事実の力によってもたらされがちな政治的秩序を、「確認のルール」のもとで統制し、なまの力である権力(power)を権威(authority)へと転化させるばかりでなく、憲法典以外の法規範に対して妥当性(validity)を付与する成文の法規範である。 [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される法規範が、妥当性と実効性とを持たなければならないとした場合、憲法典という法規範は、常に、両者について疑問視され、「憲法の規範性問題」として論議され続けている。 憲法典に規範性を持たせる一つの工夫が違憲審査制(憲法典に裁定のルールを組み入れること)である。 しかし、全ての憲法的紛争が、権威をもって最終的に裁定されるわけではなく、その制度をもってしても、規範性を確保し続けることは困難である。 [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない憲法典の妥当性について、通常は、人民の意思(合意)によって作られたことがその根拠として挙げられる。 しかし、意思の力はあくまで事実上の力であって、意思が妥当性をもたらすという保証はない(Iこの点は、憲法制定権力の性質を論ずる際に [118]~[132] で再びふれることになろう)。 たとえ社会契約に示された意思が妥当性をもたらすとしても、その妥当性は、政治的統一体の始源的権力の創出および獲得の段階についてまで言い得るに過ぎない。 始源的権力によって作り上げられた憲法典と、憲法典上の統治機構によって行使される権限の妥当性は、いまだ謎に包まれたままである(社会契約によって創出された政治的統一体と、憲法契約によって創出された権限とは、同一ではない)。 憲法典と憲法典上の統治機構の妥当性を意思に基礎づけようとする論者は、憲法典が民意を反映する統治メカニズムを組み入れていることを挙げたり(この点は、ときに「実定憲法上の構成原理としての統治制度の民主化の要請」といわれることがある [佐藤・100頁])、人民による定期的な選挙に服することを挙げたりして、その正当性を説いてきた(ロック)。 しかしながら、この説明が憲法の規範性問題の解決に成功している訳ではない。 意思を基礎とする理論は、その意思それ自体を拘束するルールを解明しない限り、意思から生ずる万能の権力を説かざるを得なくなるであろう(シュミットが述べた如く、「意欲すれば足りる」という仕儀に至る)。 憲法典の妥当性の根拠を意思以外に求める思考として、憲法典自身に授権する「根本規範」または「始源規範」を仮定するものがある。 その根本規範の妥当性は、疑問視され得ないものとして仮定されるのである。 基本法である憲法典に対して妥当性を付与するその実体は何であろうか(この点については、最高法規性を論ずる第六章の [93]~[95] で再述する)。 [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される制裁規定に発する拘束力をもつのが通例である他の法令とは違って、憲法は、簡潔・大綱的でその細目と制裁方法とを下位法に委ねているために、拘束力(または実効性)をもたず、常に実効的であるとは限らない。 ケルゼン流に、拘束力をもつ法規範(「もし、・・・ならば、その場合は・・・・・・」という仮設の形で示されて、後件に制裁を用意しているもの)だけを「真正の法規範」と呼ぶとすれば、憲法は、真正の法規範ではない(ただし、彼の理論の是非をここでは問うてはいない)。 ケルゼンはこういう。 「実質的憲法の諸規範は、それを基礎として創設されたサンクションを定める諸規範との有機的な結合においてのみ法」となるのであって、憲法諸規範自体は、独立した完全な規範ではない(ケルゼン『法と国家の一般理論』240頁)。 こうした特性をもつことに着目して、憲法され自体は「直接有効な法ではない」といわれることがある(小嶋・29頁)。 アメリカ憲法典が、司法審査制を導入し、「国の最高法規」であると自ら宣言したのは、憲法典を、その内部から「直接有効な法」にしようとした試みである。 我が憲法典もこれに倣った。 それでも、その内部的装置の妥当性を根拠づける規範問題が解決されたわけではなく、またさらに、憲法典のなかには、政治的マニフェストやプログラム規定が残されていることを考慮に入れれば、すべての憲法上の規定が直接有効とされるわけでもない。 [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧であるその他、憲法の特質として、根本性、基礎性、大綱性等が指摘されることが多いが、いずれも不明確といわざるを得ない(例えば、美濃部『憲法撮要』71頁は、憲法とは、国家の組織および作用に関する基礎法をいうとして、基礎性の要素を、国家の領土の範囲、国民たる資格要件、国家の統治組織の大綱、国家と国民との関係に関する基礎法則をあげるが、これらの事項が基礎性という特性を有しているといえるか、疑問である)。 本書は、憲法典が「究極の確認のルール」に基礎を置きつつ、他の実定法に妥当性を付与する「確認のルール」である点にその特質をみてとる([47]参照)。 ■ご意見、情報提供※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第四章 立憲主義と法の支配 p.59以下
<目次> ■第一節 立憲主義の歴史的展開[64] (一)最古の意味での立憲主義にいう constitution はルール概念と結びついていた立憲主義(constitutionalism)の体系は、18世紀になって確立された([3]参照)。 もっとも、その起源は、古代ギリシャに遡り、封建時代にあってもその思想は消え去らなかった。 それは、ときには宗教的な主張として、ときには歴史的な主張として、その内容に変遷をみせながらも、宗教的・歴史的な秩序による統治者(統治権)の制限を説く理論から、道徳哲学によって支えられた法体系による制約論へと、理論体系化されたのである。 その過程は、円滑なものではなかった。 最古の立憲主義は、国家権力の恣意的行使(専制政治)を防ぐために、constitution によってそれを統制することを目指した。 そこでの constitution は、先にふれたように([30]参照)、「ルールを定める行為」またはかく定められた「ルール」を意味した。 もっとも、それは、政体の長所短所を判定する物差しにとどまり、強制力をもつものではなかった。 その後、中世までは、恣意的統治に対する法の勝利は、莫大な血とエネルギーの代価の割には、緩慢であった。 なぜなら、正常時においては、領主とその下の領民は、旧き良き法、良き慣習によって包まれる法共同体であったために法の必要は意識されず、不正規状態にあっては、それまでの立憲主義は、constitution に反する恣意的な統治に対して有効な「制裁」を用意していなかったからである。 それでも、立憲主義の思想は、歴史から消え去ることはなかった。 [65] (ニ)中世における constitution は「統治」と「司法」との区別を知っていたイギリスにおいては、「立法」という思考はなく、法は作られるのではなく発見され維持されるものであると考えられてきている。 中世におけるコモン・ローは、宣言された法の集積であり、基本的な法の体系とみられたが、王権全体を統制する法力まで持たなかった。 その法上の空隙部分は、王権といえども法のもとにあるという理論によって補充され続けた。 13世紀の法律家H. ブラクトンは、王権にも、法によってその行使の制限されている領域と、制限されざるそれとがあることを指摘した。 前者は jurisdictio (司法)と呼ばれ、後者は gubernaticum (統治)と呼ばれた(マクワルワイン著、森岡敬一郎訳『立憲主義 その成立過程』)。 ブラクトンは、jurisdictio の領域に関しては、王権の行為であっても、立法行為であっても、コモン・ローによって拘束されていると説き、また、H. ボーリングブルクは、国民の歴史から確定されるはずの実体的な制約原理として、太古からの憲法(ancient constitution)が存在してきた、とも主張した。 これが後世の立憲主義思想の母胎となる。 これに対して、ヨーロッパ大陸諸国では、この思想は、意図的に排斥されてしまう。 ■第ニ節 「法の支配」の観念の成立[66] (一)立憲主義的 constitution は「基本法」による統治を求める「人間に服従するのではなくて、ただ法に服するときに、人々は自由である」(I. カント)。 「神の支配」や「人の支配」に代わる「法の支配」は、自由の法的表現であり、近代立憲主義の追究してきたのは、まさにこの点にある。 constitution は、近代に至って初めて「基本法」(fundamental law)としての属性をもつに至る。 その属性をもつに至った歴史的背景を、イギリスについてみれば、次の通りである。
こうした歴史的背景は、フランスについても基本的に妥当する。 同国においても、フランスの国王の至上権を拘束してきた三つの枷として、16世紀の思想家たちは(J. ボダンでさえ)「王権の基本法」、「司法」および「宗教」に言及していたのである(同国の政治的実践は、現実にはこれを侵犯してしまう。それでも、立憲主義思想は、完全に死滅することはなく、市民革命という形で一挙に噴出したのである。それは、立憲主義の見方をも根本的に変えたという意味でも、まさに「革命」だった)。 [67] (二)「基本法」のもとでの統治は「法の支配」を意味する「基本法」にいう「基本」(fundamental)とは、統治に先立って存在し、統治を先導し、拘束する性質をもつこと、そして、通常の法的手続によって改廃されないこと、をいう。 また、“law”(法、法則)とは、人間の意思を超える永遠の真理を表した。 これらが含意することこそ「法の支配」の意である。 「法の支配」(rule of law)とは、語源からみると、「法(則)による統治」(government by law)を意味した。 立憲主義(constitutionalism)とは、基本法としての属性をもった憲法による統治を指す。 18世紀末にみられた市民革命は、統治者が「法」(law)と「立法」(legislation)、「司法」と「統治」との区別を無視したために勃発した。 当時の立憲主義は、統治権からの法や司法への侵入に対して、それを保護する法的制裁方法に欠けていたために、ブルジョアジィからの実力による制裁として発生したのである。 「法の支配」の前提には、次のような思想が流れている。
こうした思想は、さらに、統治が憲法上の限界を逸脱しているか否かの判定を為す独立機関の必要性を気づかせ、それがまずは司法府の独立保障として、そして、やがてアメリカにおける司法審査制として結実するのである。 右のような思想を底流にもつ「法の支配」は、次第に、統治者を拘束するための具体的な内容と形式とを持つものとして次のように実定法体系中に明示化されていき、法執行の正しさをも実現しようとしている。
[68] (三)18世紀のイギリスにおいて法の支配は定着期を迎える裁判官が法を発見して、それを伝える口述者としてふさわしい権能をもつためには(法の支配の一内容である右の(d)を実現するためには)、原則的に、その地位を他の政治部門の影響の外に置かなければならない。 イギリスにおいては1701年の王位継承法が裁判官の独立保障につき次のように謳ったのは、この点に配慮したためである。 「裁判官の任命は、『罪過なきかぎり』続くものとして為されるべきであり、その俸給は不動のものとする。但し、議会の両院の奏上に基づいて裁判官を罷免することは、合法である。」 この裁判官の独立保障は、後世代によって権力分立の一要素であると理論構成されるばかりでなく、裁判官の準拠する法は、君主の「命令意思としての法」ではないこと(「法を確認し維持する《司法》」と「君主の意思を確認し執行する《裁判》」との違い)を気づかせる契機となったのである([412]、[501]参照)。 その他、法の支配の内容として、前記(a)、(b)、(c)を具体化する罪刑法定主義や、一般的・抽象的法の定立と、そのもとでの平等な処遇を意味する「法の平等保護」が摘示されるようになる。 人の自由に対して強制を加えるときには、《未知の無数の将来の事例に等しく適用される法に拠らなねばならない》と考えられたからである(法の一般性・抽象性・平等普遍性)。 この「法の支配」の原型は、D. ヒュームの法哲学に求めることができる。 彼は、自由な国家においては、為政者の恣意的な裁量が廃止されるべきこと、為政者は「すべての政府構成員と被治者に予め知られている一般的で平等な法に従って行動しなければならない」こと、「法が明確に犯罪と定めた行為以外は、いかなる行為も犯罪とされてはならない」ことを述べた(ヒューム著、小松茂夫訳『市民の国について(下)』162、216頁)。 ところが、イギリスにおいて、議会主権という観念と慣行が形成されると共に、議会が制定したものが「法」である、と考えられがちとなって、ヒューム的思考は後退していった。 これに対して、植民地アメリカにおける人々は、当初、旧き良き法の保障する権益に訴えかけることによって、イギリス人としての生命・自由・所有権を正当化しようとしたが、独立戦争を契機として、自然法と結びついた「法の支配」思想を強調するに至った。 それが独立宣言中の「自然の法と自然の神の法」との表明となったのである。 [69] (四)「法の支配」は、その後一時低迷するところが、その後法の支配の理念は、フランス革命と、大陸的合理主義哲学(真の自由を知らない抽象的理論、人民の意思が法を作るとする意思中心主義、民主主義と自由主義とを区別しない理論)の影響によって、停滞する。 というのも、意思中心主義を採る限り、誰の意思によって制定されるかという手続が明示的に形式化されれば「法」となると観念されてしまうからである。 ここに、議会または多数者の意思が定めたものであれば、正当な意思の源泉がそこに示されている、といわれることになる([60]において既にふれた、憲法典の正当性を人民の意思に根拠づけようとする理論も、これと無関係ではない)。 こうした思考が、すぐ後の[72]でふれる形式的法治主義に繋がるのである。 [70] (五)法の支配はアメリカにおいて新たに継承・発展させられた独立戦争は制限君主制を求めて勃発した。 為にアメリカにおいては、統治機関は人民によって委託された権能だけを行使するものと考えられた。 そのために、全ての統治機関は、基本的な法文書によって特定の権力を与えられ(授権規範としての憲法)、同時にその権力も「基本法としての憲法典」のもとで、厳格に限界を定められなければならない(制限規範としての憲法)とされた。 《憲法典は法の支配を具体化した法文書である》と観念することは、法規範の構造を階梯的に捉えることでもある。 アメリカ合衆国憲法上、司法審査に関する明文規定がないにも係わらず、裁判所は、憲法典に違反する下位法の効力を否定しうるとされてきたのは([444]参照)、法規範構造を階梯的に捉えた帰結である([93]でふれるケルゼンの法段階説と比較対照せよ)。 統治機関が人民によって委託された権能だけを行使するということは、全ての権力が人民に由来することでもある。 これは、国家機関の創設権限を有する国民、すなわち、後述する憲法制定権力の主体としての国民、という考え方をアメリカが最初に実定憲法に取り込んだことを表す([118]参照)。 これ以降、「法の支配」が憲法典のもとでの統治と同視されがちとなった。
■第三節 「法の支配」の公式化[71] (一)法の支配はA. ダイシーによって公式化されたA. ダイシー(1835~1922年)は、「法の支配」を成文憲法典による政治権力の統制として捉えなかった(巻末の人名解説をみよ)。 彼は、イギリス独特の不文法的伝統のなかで、法の支配を公式化したのである。 彼のいうその内容は、次の三つである。
[72] (二)ダイシーの法の支配の理解は完全無欠ではなかった右のような「法の支配」の理念は、その後、誇張され、あたかも不動の価値であるかのように説かれていく。 もともとダイシーのいう「正規の法」が何を意味するか定かではなく、正規の法によって自由を中心とした基本権が守られるというのも、イギリスが不文憲法の国であるとする誇張のうえに成立していた。 また、彼の理論は、大陸における法の支配が不完全であるという誤った前提に立っていた。 ダイシーは、大陸法上の欠陥が行政権の行使につき司法審査(適法性審査)の及ばない点にあるとみた。 そのために、行政行為を通常裁判所によって審査する点こそ法の支配にとっての鍵であるとみたのだった。 ところが、実際には、フランスにおいても、ドイツ(プロイセン)においても、法の支配と同じ観点から「法治主義」が説かれていたのである。 もっとも、フランス第三共和国やプロイセンにおいては、その理論が実践に取り込まれないまま、通常裁判所とは系列を異にする、行政機関のための行政裁判所が設置されてしまう([443]参照)。 これを契機に、R. グナイスト(1816~95)によって理論的に(政治的に)歪められた法治主義の考え方が1860年以降、支配的となる。 そして、その後は、ドイツ的法治主義、すなわち議会の定めたものをもって法とする形式的法治主義と、英米的法の支配とは、あたかも、水と油であるかのように今日まで語り継がれているのである。 形式的法治主義は、ルールが従うべき手続上の制約を課すのみである。
[73] (三)H. ハートは「法の支配」を形式的・手続的正義として公式化し直した「法の支配」とは何であるか、積極的に定義づけ、さらにその論拠を呈示しようとすることは、容易な業ではない。 法の支配は、よく次のように説明される。
ところが、この解明では、
上の(ア)の疑問に関しては、こう解答することも出来なくはない。 すなわち、《人権をよりよく保障することが、法の支配のいいたいところである》、とか、《個人の尊厳をよりよく保護することである》と説くこと、これである。 ところが、法の支配を個人の尊厳の実現と関連づけることは、《法の支配が何を目指すか》という問に対する解にとどまり、《法の支配にいう法とは何であるか》という、法の内実を問う際の解ではない。 法の支配の意義を積極的に呈示する方向として、二つの見方が存在してきた。
法の一般性・抽象性・普遍平等性という形式は、次のような普遍可能性原理の応用編である。
以上は、要するに、《全ての人々の観点から受け入れられることのできる原理を法は組み込むべし》、とする思考である(『憲法理論Ⅱ』 [36] もみよ)。 法の支配の要諦は、法が、特定の人々に対して、特定の仕方で、処遇してはならない、という形式性にある。 その形式性は、「具体的効果を知らないこと、これらのルールがどのような目的を促進するか知らないこと」を含意するのである(ハイエク著、一谷藤一郎訳『隷従への道』108、103頁)。 ところが、ヘーゲル=マルクス主義は、この形式性こそ、人々に対して形式的平等と形式的自由だけを与えるものと批判したために、特定の個人の置かれた地位を配慮して、実質的平等・実質的自由を保障する法令が正義に適う、と考えられがちとなって、法の支配の思想が侵食されていったのである。 法の支配の復権にとって重要な視点を提供したのがH. L. A. ハートである。 ハートは、法の支配の内実として、法としての適正の原理と、自然的正義の原理を挙げる。
法と道徳との必然的関連性を否定するハートは、法の支配の中に、「公正」とか「実体的正義」を含めることに躊躇せざるを得なかった。 この点は、「法律は悪法で、不公正であるかも知れないが、しかし、それを一般的で、抽象的な形に成文化することにより、この危険は極小にまで押さえられる」と考えたデュギーも同様であった。 正義の実体は、いつも論争されてきた。 その論争の中で我々は、得てして過剰な実体を求めがちとなる。 ハート、デュギーが懸念したのはその点であった。 法は最小限の正義を体現すべきものなのである。 その正義は、誰にも積極的な義務を課すことなく、不正義を為さないよう求める消極的なものでなければならない(負の力としての正義。[47]もみよ)。 [74] (四)「法の支配」の小括「法の支配」とは、統治機関(立法権を含む)が強制力を用いる場合には、公知の、事前に予知可能で(確実性・公開性を持ち)、平等に適用される、一般的・抽象的立法を要請する「基本法」(fundamental law)のもとでの統治をいう。 「基本的」法は、立法とそのもとでの統治がどうあるべきかに関するルールである(統治を先導するための規範)。 「基本的」であるか否かは、法の権威の源泉(誰の意思が法をつくるか)によって決まるわけではない。 それは、一般性・抽象性・平等普遍性といった形式的正義や、両当事者の意見を聴くべしといった手続的正義に従っているかどうかによって決せられる。 この意味での正義は、先にふれたように、誰にも積極的な義務を課すことはなく、個別的な文脈の中で発見され宣言されるに過ぎない。 では、立法がこうした正義を具備しているか否かを判断するに相応しい構造をもっている機関はいずれであるか。 それは、個別的な文脈のもとで、合理的な手続を踏みながら公正な観察者の視点から法を宣言し維持する権限を与えられている司法府である。 「法の支配」が、司法府の独立のみならず、司法的手続の整備の要請、司法審査制と結びつくのは論理必然的である([446]参照)。 「法の支配」による統治機関の統制は、国家が人の自由に対して強制を加える領域に及ぶ。 もっとも、今日では、いわゆる政府の受益的活動についても「法の支配」を必要とするという立場もみられる。 国家の財政政策を法の支配に服せしめることも重大な視点であろう。 [75] (五)日本国憲法も、法の支配の思想に強く影響されている日本国憲法は、多方面にわたって法の支配の思想を具体化している。 そのことは、
もっとも、以上の諸条規に言及するだけでは、日本国憲法が法の支配を組み込んでいることを論証したことにはならない。 なぜなら、ある法体系内の公理を出発点として当該体系の公理を論証しようとすることは、決定不可能だからである。 これを「自己言及のパラドックス」という。 ■ご意見、情報提供※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第五章 立憲主義の展開 p.71以下
<目次>
■第一節 近代立憲主義の特質[76] (一)近代国家は統治権力を合法的に独占する点に特徴をもつ近代国家は、
近代立憲主義は、[74]でふれた「法の支配」思想のもとで近代国家の統治権力を形式的な合法的権威に転化させるべく、一般性・抽象性・平等普遍性を満たす立法の制定と、そのもとでの行政。司法という定式を憲法典で実現した。 そうすることによって、リヴェイアサンともなりうる国家から、自由を中心とする基本権を守ろうとした。 すなわち、近代立憲主義とは、基本権保障と権力分立という内容を、正式の法文書という形式で確認する思想をいう。 それは、先に述べた「配分原理」と「組織技術」(分立技術)とを、成文憲法典で確認することと同義である([53]参照)。 [77] (ニ)責任政治の原則も近代国家の特徴であるしかし、それだけではない。 近代立憲主義国家においては、統治者が法に対する責任を負うことばかりでなく、政治的にも被治者に対して責任を負うことをも、謳われなければならない。 これを「責任政治の原則」という。 責任政治の原則を具体化するものとしては、大臣責任制、そのための弾劾制度、その後に登場した内閣不信任制度(内閣の連帯責任制)がある。 また、何よりも、選挙制度が忘れられてはならない。 もっとも、これらの責任政治のための制度が、現実の統治過程で有効に機能するとは限らない。 現代立憲国家に登場してきた政党は、責任政治を実質化するために「反応よき統治」(responsive government)を目指すのである。 [78] (三)近代立憲主義は国民の積極的政治参加に警戒的であったでは、近代立憲主義は国民の政治参加についてどう見ていたか。 この点に関しては、一方で、近代立憲主義は民主主義と結びついて国民の政治参加に肯定的であったとする見解(芦部『憲法講義ノートⅠ』28頁)と、他方で、近代立憲主義は積極的な国民の政治参加に好意的ではなく、自動制御装置的政治機構を望んだとする見解がある(佐藤幸治編著『憲法Ⅰ』15頁)。 そのうちのどちらが妥当であるか。 その解答はどの国を念頭に置くか、誰の理論をモデルとするかによって、当然異なってくる。 概していえば、理念上は積極的な政治参加が説かれながらも、いざそれを現実に法制化する段になると、統治者たちは慎重な態度に出た。 その理由を理解するためには、近代立憲主義の拠って立つ理念上の人間観・国家観と、現実のそれとの乖離が解明されなければならない。 ■第二節 近代立憲主義の人間観・国家観[79] (一)近代立憲主義は理性的な人間像を前提にしていた市民社会は、私的所有または自由意思の主体たる個人の集合体と考えられた。 個人の私的領域の総計が社会的領域と観念されたのである(この見方が、本書の冒頭の [1] でふれた「方法論的集団主義」の典型である)。 「私的領域」とは、いかなる領域をいうか。 また、それをどう評価するか、という争点は、そこに生きる人間への見方によって変動する。 近代立憲主義は、身分制の桎梏から解放された、自由で独立した合理的・理性的個人を想定した。 それは、個々人の示す事実上の違いを捨象した抽象的な人(人格)として捉えられた。 この人間観の発生には、キリスト教、なかでも改革派の説いた、内心または道徳の内面・絶対性、法の外面・形式性という考えが大きく影響している。 中世にあっては、「神の法→自然法→人間の法」という序列が「信仰→(信仰を通して発見される)理性→(理性を具現する法による)利害関心の調整」という序列に対応していたのである。 ところが、宗教改革後、信仰の内面性または多様性が承認された段階で、その対応関係は消滅し、人間社会の利害関心の調整は「(人間に自然に備わっている)理性によって発見される自然法による統制」や「自然法による人為法の統制」という、人の内面とは別個の規準に委ねられるものと再構成された。 その際の基軸は、《人は道徳的で人格的な理性的存在だ》という、人間存在の特質に求められた。 こうした歴史的展開の影響のもとで、人間の合理的で自由な意思を信奉する近代合理主義哲学を基礎として、法学は、「私的領域」を、理性的、道徳的存在としての個人の精神的集合体であると想定してきた。 自然法、自然権思想を支える人間観は、これと無縁ではない。 国家以前の自然状態における個人は、まさにこのような存在として仮定されたのであった。 例えば、ロックの社会契約論は、理性的な決定を為し得る、没社会的な神人同型の個人を前提としていた。 [80] (二)私的領域といえども国家によって設定され保護されている近代市民法または伝統的法学は、こうした人間観に立って、「公的領域/私的領域」の峻別を説いてきた([4]参照)。 そして、私的領域について国家の不介入や「自由放任」があたかも自明であるかのように扱ってきた。 近代立憲主義国家が消極国家である、といわれてきたのは、こうした意味あいを込めてのことである。 しかしながら、消極的国家または夜警国家のもとですら、国家は、一方で、社会・個人の一定領域を保護してきたのが現実であり(その領域に関してオフ・ハンドでいたことは決してなく)、他方で、権力組織としてその領域を浸食する主体でもあった。 その意味で、個人的領域と政治的領域との分離といわれる場合でも、その分離は、国家内に存在し、国家によって維持されるのである。 その個人的領域は、法のもとでの自由の意味であって、法の欠如でもなければ、「自由放任」でもなかった([54]参照)。 また、「公的(公権力の)領域/私的(市民社会の)領域」という二分法も、社会のある部分をときに「公的」と呼び、経済市場をときに「私的」と呼ぶに至った段階で、相互の浸潤現象を否定しさることも出来ずに、次第に通用力を失っていく。 それは、人間の本性への見方の変容を反映してもいる。 [81] (三)近代立憲主義は「自己統治」を制約するものについて解答を寄せなかった楽観的人間観に立つ近代立憲主義、なかでも大陸のそれは、国王の権力を制限するための諸理論と手段を発見したものの、人民による「自己統治」(または国民の意思から発するとされる主権)を制約する手段を見出してはいなかった。 有効な制約手段がないために、近代立憲主義は、制憲権を国民の意思の発動とみながら、理念的な国民主権([127]でふれる正当性原理としての国民主権)を説く一方で、実際の統治に当っては、民意を遮断するための諸メカニズム(例えば、代表制、二院制、間接選挙制等)を考案したのである。 さらに、オリュー、デュギーの如く、論者によっては、主権概念自体を否定するものすらみられるのも([8]参照)、主権を統制するものを解明できなかったからである。 近代立憲主義は、人間の本性に対する楽観的な信頼の上に成立していた。 [82] (四)近代合理主義哲学の礎を提供してきた「理性」は再検討を迫られてくる近代立憲主義を支えた啓蒙思想は、政治または権力とは異なる次元に属するところの理性(またはそれを客観的に具現する正義(イウス))のもとに、政治的利害関心や抗争を従属させ、統制しようとしてきた。 当時、理性は、自然、人、社会を律する客観的な秩序を意味していた。 理性の主体である人は、秩序づけられたこの世界にスッポリと違和感なく収まりきる存在であった。 個々人は、その事実上の違いを捨象されて、普遍的に「人格」として捉えられた。 ところが、国民国家の枠組みが顕著となるにつれて、制度的支えのない普遍的人格を語ることの限界が、G. ヘーゲルによって鋭く突かれた。 人を人格として超越論的に扱うだけでは済まなくなったのである。 この時点で、近代啓蒙思想体系は、一度、打ち砕かれることとなった。 国家と市民社会のなかで生きていく人々の本質的特徴は、行動すること、他者と共同して生活すること、労働すること、消費することにある。 人格として存在することではないのである。 そうなると、法的地位、生産能力、消費量等々、個々人はそれぞれに異なっていることに気づかれてくる。 近代立憲主義の想定する人間観は通用性を失って、再検討を迫られたのである。 こうした再検討のなかで出てくるのが「現代立憲主義」である。 近代立憲主義が中世立憲主義とは異質な様相をもって登場したと同じように、現代立憲主義は近代立憲主義を否定する中で誕生したのである。 現代の憲法理論が近代啓蒙の時代に安閑と依拠してはおれない理由は、ここにある。 ■第三節 「現代立憲主義」へ[83] (一)19世紀後半以降の哲学は意思中心主義に批判的である19世紀後半以降のマルクス主義と労働者階級の勃興は、近代合理主義哲学が説いてきた意思中心主義、個人(主体)主義への反省を迫った。 それは具体的には、
この方向は、人間存在や法の見方のみならず、国家の見方までの変更を思想家に迫らざるを得なかった。 近代国家を法的に統制しようとして出てきた近代立憲主義は、この変容を一部取り込みながらもその根幹を維持しようとするが、様々な課題・矛盾を背負い込んで、様々な変更を余儀なくされる。 [11] でふれた「現代国家」の実相に応じて変容されてきつつある立憲主義を「現代立憲主義」という。 [84] (ニ)「現代立憲主義」は個々人の置かれた地位を振り返る「現代立憲主義」は、理性的でもあるが、同時に、私利私欲をもった経済的に合理的な人間像を反映したものとなってくる。 この時点で、客観的な秩序を意味していた理性は、目的に対する手段の適合性を判断する主観的能力を意味するものに確実に変わった。 それは、道徳的実践理性よりも、道具的理性を優先させる人間像への転換を承認することでもあった。 中でも「現代立憲主義」は、個々人の置かれた具体的な生活の状況を考慮しながら、経済的自由市場がもたらす経済上の恐怖や脅迫から市民を「自由」にすべく、国家による非干渉経済を一部断念するのである。 国家の市場介入を容認するために、「弱肉強食」という根拠のない表現が乱発された。 [85] (三)「現代立憲主義」は夜警国家観を超える現代国家は、人間の私利私欲から発生する弊害を予防または除去し、各人の生存に配慮するために、「公共政策」の名のもとに、財・サーヴィスの供給者、規制者、創造者(企業家)、またさらには審判者として、「社会的領域」に進出し、各人が幸福となるための条件を各人に約束し始める([11]をみよ)。 それが、「社会的法治国家」、「積極国家」または「福祉国家」と通称される国家である。 それは、既にふれたフランス啓蒙思想の影響である([54]での【N. B. 9】参照)。 現代国家は、権力組織としての顔と、実質的平等・実体的正義の実現や、さらには結果の平等までをも意識して国民の生存を配慮することなどといった高次の目的にも仕える二つの顔をもつ(現代国家の特徴については、[11]でふれた)。 こうした変化は、自由権のうちでも経済的自由権を変質させて相対化し、人権論のなかでは、象徴的(スローガン風)に、「自由権から社会権へ」といわれ、国家論のなかでは、「夜警国家から社会(福祉)国家へ」といわれる中にみられる。 なかでも、その国家における行政の特徴は、生存配慮のために為される社会保障行政に表れる。 [86] (四)福祉国家は「隷従への道」?片や権力を独占し、片や各人に幸福を約束するという二つの顔をもつ国家の統治は、余剰権力を発生させ、パターナリズムのもとで、各人の自由領域に干渉し、ほとんど全ての領域を政治領域としそうな勢いを示している。 それは、あるいは我々が既にハイエクの最も警戒する「隷従への道」を歩んでいることを示唆しているのかも知れない。 なぜなら、不平等を是正して幸福を各人にもたらすために提唱される「分配的正義」(社会保障に代表される所得再分配)は、国家が人々の置かれる位置まで決定し監視せざるを得なくさせるからである。 そのための国家権限は、我々が自由な営為のなかで獲得した地位をパターン付き社会に適合させるべく、我々の為すべきことまで決定する権限ともなろう。 こうした危機を目前にして、ハイエクは、「法の支配は、配分的正義を排除する」といい、Th. ローウィは、明確な基準を欠く所得再分配(福祉行政)は、官僚と一定集団とが癒着する利益集団自由主義を生むといい、M. フリードマンは、財産権の侵害であるといい、R. ノージックは「道徳的に正当化され得ない国家となる」という。 この病理に対処するために、全ての行政活動に法律の留保を求める「全部留保説」が唱えられるものの、それは、かえって社会領域の政治化を呼ぶばかりでなく、無数の委任立法に拠らざるを得ないこととなろう。 配分的正義を実現するために説かれてきた「現代立憲主義」国家像は、かくて、脆弱な姿を露呈することになる(その最も強力な擁護論は、すぐ後にふれるJ. ロールズの政治哲学であるが、それとても弱点がない訳ではない)。 [87] (五)「自由」を尊重する国家は福祉国家とはならないはずである「自由」とは、強制の加えられることのない状況下で、各人が各人の望むところを各自の知識に従って追求するチャンスを与えられていることである。 知識の程度と範囲は人によって異なり、その活用の程度もまた各人の機会が異なるために、違ってこざるを得ない。 その結果、各自の生み出すもの、獲得するものに相違が出てくるのも当然である(「生産」と「分配」は対応する)。 「自由」は、「機会の平等」とは両立するものの、生産と分配との区別を前提とする「結果の平等」とは両立しない。 となれば、「自由」を尊重することは、結果の平等を志向する福祉国家理念とは、基本的に、相容れないばかりであんく、結果を予め計画して、それへの邁進を目指す共産主義とも対立する(この点については『憲法理論Ⅱ』 [135]~[137]、『憲法理論Ⅲ』 [415]~[416] をみよ)。 自由主義のもとでは、成果を発生させる過程での各人の努力は、国家によって評価されてはならないのである。 [88] (六)「現代立憲主義」国家は司法国家化によって救われるか代表機関としての議会に信頼を寄せた近代立憲主義に対して、「現代立憲主義」は、不断に活動する執政府に頼らざるを得なくなる。 執政府は、法令の執行に携わるだけでなく、委任立法に従事し、さらには、国家の基本政策の形成・実行・検証のみならず、社会領域における自動調整システムの機能不全に対処すべく、計画・統制へと乗り出してくる。 それは、それだけの自由裁量的権限と機構とを備える「行政国家」への変質を意味する(古典的な意味での「行政国家」とは、執政権行使が司法裁判所の統制から除外される国家を指した)。 ところが、「自らが公共善とみなすものに専ら関わる効率的な専門行政官が、自由に対する最大の脅威となる」(ハイエク)。 その脅威を最小化するために、執政府活動に対する司法的統制が期待されてくる。 「司法国家」への変質の要請である。 その際、執政府の活動も通常裁判所の判断に服するという「法の支配」理念が再び強調されることになる。 また、議会が、法律で独立行政委員会を設置するのも、執政府を統制するための対応である(後述の[405]参照)。 しかしながら、肥大する執政府を前にして、議会や司法がその統制に成功しているとは思われない。 特に補助金の交付にみられる資金助成行政は、特定目的をもって、特定人(法人を含む)を対象として為される私的・個別的契約であると理論構成されるために、一般的抽象的ルールのもとに執政府を置こうとする近代立憲主義または法の支配の思想から大きく逸脱する。 近時、ノージックのように、福祉国家観に正面から反対する自由尊重主義者が夜警国家への回帰を提唱しているのは、この点を真剣に懸念しているからである。 [89] (七)夜警国家がもっともユートピアに近いとする理論もあるノージックは、各人が「獲得、移転または匡正」という経緯を通して得た物(自らが作り出した物、他人から譲渡されて得た物、そして他人からの賠償によって得た物)は各人の物であって、各人はそれに対して正当な権原(entitlement=自然権としての資格)を有し、何人もそれを侵さないことが正義である、という(権原の正義論または経緯の正義論。巻末の人名解説をみよ)。 この正義論は、正義や人権を達成されるべき国家目標とみないで、国家権力を制約する原理(横から制約する原理)と考えている点に特徴がある。 権原の正義論は、彼のいう最小限国家、つまり警察国家だけを正当とし、彼のいう拡張国家、つまり福祉国家を道徳的に正当とはしない。 なぜなら、拡張国家は、所得再配分によって個人の「権原」を侵害するからである。 以上のようなノージックの理論は、すこぶる評判が悪い。 例えば、「大きな権原」(持てる者)と「小さな権原」(持たざる者)との差は、権力関係を反映したものとなって、自発的な獲得・移転等といわれるものを歪めるのではないか、さらには、貧富の差をさらに拡大し、いわゆる「社会的正義」に反しないか、と強い批判に晒されている。 彼の理論からすれば、自由尊重主義は、必然的に、自由経済体制(資本主義)擁護のための理論となることになろうが、巨大法人(組織)によって支配されたように見える市場システムの評価の仕方によって、その理論の是非が決定されよう(「市場/組織」の二分法がどこまで通用するか疑問である)。 その是非はともかく、ノージック理論は現代国家の実態に対して痛烈な批判となっている。 [90] (八)自由でかつ平等な国家を構想するJ. ロールズの国家観が注目されているロールズの国家観は、最近の政治哲学のうちでも、最も強い影響力を各方面に与えてきている(巻末の人名解説をみよ)。 彼の理論は、ノージックとは正反対に、自由と平等(なかでも「結果の平等」)との調整が可能であることを説きながら、国家による所得再分配を、「公正としての正義」の名のもとで、次のような思考順序で正当とする理論である。
以上の原理には、第一に自由を、第二に機会の平等を、第三に格差原理を、という優先順位が想定されている。 [91] (九)超越論的な哲学に基づいて「社会的正義」を実現する国家を模索すべきではないこのロールズの見解に対しては、「無知のヴェール」のもとで人々が二つの正義原理を選択するという保証があるか、余りに理念的な人間像を前提としていないか(「記憶喪失の哲学」と批判される理由はそこにある)、といった疑問が残る。 彼の哲学は、非経験的な知によって人間の本性を把握しようとする超越論的哲学から離れようとしながらも、その枠内にとどまっている。 政治哲学の出発点は、現実的なありのままの人間でなければならないはずである。 ありのままの人間から法や国家をみるという視点は、スコットランドの啓蒙知の伝統にみられる。 その知によれば、共に自由に生きたいという一般の人々の願望を実現するために、一般的・抽象的ルールを提供し維持することこそ、国家の存在理由なのである([28]参照)。 確かに、現代立憲国家は、近代立憲国家における「社会」がもたらしたといわれる様々な弊害を、人為的で個別的なルールによって除去し、「社会的正義」を実現しようとして登場した。 しかしながら、社会は、一般的・抽象的ルールのもとで各人が自由に行為するよう保障した結果として自生的に登場する秩序である、と考えるのが正しい。 その秩序に対して「社会が責任を持たなければならない」と主張することはナンセンスである。 「正義」なる観念は人間の行為についてのみ問われなければならない。 社会は、個々人の自由な営為の結果として生まれ出た秩序であって《主体ではない》のである。 「社会的正義」の名のもとで、巨大な官僚の監視機構を背景にして、強制的に所得再分配をしようとする国家こそ、社会的正義を破壊しているのである。 これこそが、現代立憲主義国家の病理である。 その病理は、国家が個人の私的領域に介入する「国家の社会化」に現れるだけでなく、利益の分配を巡って利益集団が政治過程へと深く侵入する「社会の国家化」によって、さらに深刻化する。 近代立憲主義を人間の意図(設計主義)によって修正し、「社会的正義」を追求し実現しようとする「現代立憲主義」には大きな期待はかけられない。 [92] (十)現代国家は大量殺戮兵器と癌細胞としての軍隊の統制問題を抱え込む現代国家の病理はそれだけではない。 大量殺人兵器の登場、秘密事項で武装された軍隊の存在は、国内国外の平和をいかに実現するか、「開かれた政府」をいかにして貫徹するか、という問題を「現代立憲主義」に突きつけて久しい。 これに対応すべく諸国家は、侵略戦争の放棄を憲法典上で謳い、民主的統治の理念に立って情報公開制度を実現しつつある。 なかでも、「現代立憲主義」は、20世紀になって、政治と軍隊との関係(civil-military relations=軍政関係または民軍関係)について、具体的な解決策を迫られる。 というのは、政治が、軍隊という機能集団を管理する専門技術・知識・装置を修得すべしとされて以来、法制度上、専門職業的将校団を看過するとなれば、軍隊こそ典型的な暴力機構であるだけに、国民の自由やときには民主制にとって最大の危機と成り得るからである。 専門職業的将校団を、法的に有効に統制しようとする試みが、文民の優勢の体制(civilian control=一般には「文民統制」と訳出されている)である。 もっとも、文民統制なる用語も極めて多義的である。 それは広義には、非軍人を意味する文民の政治的指導によって軍隊を効果的に管理することをいう。 その広義の文民統制のもとでは、将校団は軍事面だけの専門的知識を文民たる政治家に助言するにとどまるよう、政治的中立の枠内に閉じ込められる(「政治家が戦争目的を決定し、軍隊は戦争に勝利することを目的とする」といわれる)。 狭義の文民統制とは、軍隊の最高司令官が非軍人であることを指す(これに対して、日本国憲法にいう「文民統制」は、特異な内容と狙いを持つ。通常いわれる「文民統制」は、広義であれ、狭義であれ、軍隊または将校団の存在を所与のものとして、それをいかに有効に管理するかのやり方を示した。ところが、正規軍を持たないはずの日本国憲法にあっては、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定められているため、その趣旨を巡って論争されることになる。この点は周知のように、文民とは、職業軍人の経歴を持たない者をいうとする説、職業軍人の経歴を有し、しかも強い軍国主義思想の持ち主である者以外をいうとする説の二説が対立していた。ところが、自衛隊が設置されて以降、文民とは現役軍人以外の者をいうとする説が登場するに至る)。 こうした努力にも係わらず、主権国家の独立性や平和の確保が最終的には武力によってもたらされる、という冷厳な国際政治の現実は、これまでと同様、不動のようにみえる。 この現実を前に、現代立憲主義が、「平和国家」や「開かれた政府」に向かいつつあるか否か、定かではない。 軍事秘密によって武装されて肥大する軍隊をみれば、夜警国家が最小国家である、とは必ずしも言い得ないのである。 現代国家の病理は国家機構の肥大に象徴的に現れるが、その病巣は政策遂行のために使用される手段にある。 それが、無数の、個別立法ともいうべき、無数の人為法の制定である。 現代立憲主義は、「社会的正義」を即効的にもたらそうと、ときに、所得の再分配のための立法、ときに、需給調整のための立法、ときに、「社会的弱者保護」のための立法等々、望ましい社会秩序実現のための法制定を「公益」の美名のもとで要請してきた。 そればかりでなく、無数の個別立法をきめ細かくし執行するための行政機関の肥大をもたらしてきた。 実は、「社会的正義」、「公益」なる抽象的概念に客観的判定基準はない。 また、現実の政治過程での最終決定因は、正義という理念ではなく、利得である。 そのために、利益集団が民主主義過程に食い込み、一般性・抽象性・平等普遍性という法の属性から自分だけ免除するよう求めてくるのである。 それは、自由経済体制がもたらす「市場の失敗」よりも、是正困難な「政策立案過程での失敗、立法の失敗、執行の失敗」をもたらさずには置かないのである。
■ご意見、情報提供※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第6章 立憲主義 本文 p.26以下
<目次> ■1.立憲主義の意義と展開[18] (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。 統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。 この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。 統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。 近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。 これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。 [18続き] (2) 立憲主義の展開立憲国家は、先の [7] でふれたように、18世紀の啓蒙思想の産物だった。 その理論は、絶対主義国家論が余りにも不可能な前提に立脚していたことの反省から生じた。 神の如き君主は、現実には存在しないこと、君主の意思が必ずしも人民の利益に一致しないことが判明したのだ。 立憲国家の理論の起源となると、それは中世に遡る。 [19] 〔A〕中世立憲主義中世においては、“君主を君主たらしめる法が基本法だ”と考えられた。 旧い歴史的産物のもつ力、すなわち、慣習が基本法の内容を成した。 その具体的な内容は、君主の世襲制、長子による王位継承、領土の不可譲性、そして「君主の権利/領主の権利/臣民の権利」という身分制秩序の維持である。 これらの基本法が君主権限を支えるための論拠だった。 “課税するには身分制会議の同意を要する”という命題が基本的内容として確立されるのは、その後である。 「君主を君主たらしめる法」は、君主権限を統制するためにも言及された。 それが「神の法と旧き善き法」である。 これらは、君主の権限よりも上位にあるという意味で「基本法」と考えられた。 こうした主張を「中世立憲主義」という。 もっとも、中世立憲主義は、善き君主となるための帝王学でもあったにとどまり、悪しき王が出現したとき、無力だった。 「中世立憲主義」は実のところ国家統治権を統制する思想ではなかったのである。 [19続き] 〔B〕近代立憲主義の源流?「旧き善き法」の主張はさらにリファインされていった。 例えば、ある論者は、君主の主権の行使を「統治/司法」に分けたうえで、“君主は統治領域においては無制約の権力を有してきたのに対して、司法領域においては旧き善き法によって統制されている”と主張した。 また、別の論者は、国民の歴史から確定されるはずの実体的な原理として、太古からの憲法 ancient constitution がある、と主張した。 [20] 〔C〕近代立憲主義への転回
市民革命は、幾つかの歴史的な条件が整わなければ実現しなかった。 この条件とは、宗教改革運動と近代啓蒙思想の勃興である(⇒[23])。
一時的な社会契約を乗り越えるために憲法協約が定められたからといって、それでもなお、人々の結合関係が安定するわけではない。 自然権保全という共通目的には同意した人々といえども、他の面においては利害を異にし、対立し得る。 ここに国家の統治の必要が現れるのだ。 憲法協約によって成立した結合関係が共同体とは別種であるからこそ、利害対立を調整する一元的な強制の力、すなわち、国家の統治が立ち現れざるを得ないのである。 先に私が「国家は国民の政治的共同体だ、などというべきではない」と指摘した理由は、ここにある(⇒[1])。 統治は特定の組織(統治構造)とそのための人材を必要とする。 この法的地位が統治機関であり、治者である。 統治が治者という階層を必要としている以上、「治者/被治者」の区別は不可避・必然である([8]もみよ)。 憲法協約が自然権保全に相応しい統治構造を決定するばかりでなく、被治者の基本権を列挙するのは、そのためである。 その際、啓蒙思想家は“統治権力が特定の機関に集中しないで、分割されていること”、すなわち、権力分立構造が組み込まれていることを以って、憲法協約の「基本要素」と考えた。 権力分立構想が歴史上確固となるためには、先の [14] でふれた「執行/司法」の区別に加えて、「立法/執行」の別、さらには、「法律/命令」の別が明確にされる必要があった。
この「一般性/個別性」という区別が、《臨機の法(個別的な命令)は立法ではない》との主張を支えた。 次いで、“たとえ君主の立法が一般的・抽象的であっても、それは「命令」という法形式であって、議会が立法する法形式、すなわち「法律」とは別だ”と主張された。 これが「議会の立法/君主の立法」、「法律/命令」という分離と、命令に対する法律の優位という主張を支えた。 こうした主張が「司法/議会の立法(法律制定権)/残余の君主権限」という権力分立構造を産み出したのである。 自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。 この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。 つまり、
今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。 が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。 フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 [21] 〔D〕近代立憲主義の枝分かれ
[22] (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。 見方を換えていえば、
他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。 J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。 そのために、議会中心の統治が理想とされた。 これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。 アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。
私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。 法の支配については、後にふれる(⇒[31]以下)。 なお、立憲主義の必須要素として忘れられてはならないものが政教分離である。 近代の立憲国家は、宗教の教義にとらわれることなく、宗教的に中立であるところに成立したのである。 [22a] (4) もうひとつのモデル - ドイツの「法治国原理」市民革命の歴史をもたないドイツにおいては、「立憲主義」といえば立憲君主制を連想させてきた。 このため、同国は「立憲主義」よりも「法治国原理」というタームを好んで用いてきている。 立憲主義と法治国原理とは厳密にいえば、異質の構想である。 両者の違いは、予想以上に大きい。 要注意点である。
上のふたつを比較すれば、法治国原理には、立憲主義における必須要素である法の支配と「国家/市民社会」二分法がみられない、という違いが浮かび上がる。 この違いは、ドイツにおいては、市民の「自由と財産」にとっての危険が君主からやってくることに対して、議会制定法を以って対処しようとしてきたこと、これに対して、英米においては、市民社会にとっての危険は全ての国家機関からやってくると想定して、自由の砦を議会制定法に求めようとしなかったことに起因する。 上のふたつの違いは、「市民社会」の捉え方とその評定の違いを反映している。 英米においては、市民の自由と市民社会の自律性とをポジティブに捉えてきたのに対して、大陸においては、次にふれるように、市民社会をネガティブに捉え、市民社会の欠陥を議会制定法によって補正していこうと、国家指導に期待して「法律国家」(法治国家)を国制のモデルとしたのである。 ■2.近代立憲主義の転回 - 現代立憲主義へ[23] (1) 市民社会の成立立憲主義国家は、それが自然権であるかどうかは別にしても、人の基本権を最大限尊重するための統治構造をもつ国家である。 身分制国家から立憲主義国家への変転は、次のような革命的な思考が法の世界に定着したことを示している。 すなわち、
上の命題は、「身分から契約へ」という有名なフレーズで表されたり、近代法の大原則といわれたりする。 この命題は、視点を変えれば、国家が人々の自由や財産を法的に取り扱うにあたって、
自由で自律的な意思主体は誰でも契約の当事者となり得ることとなった。 このとき、人は「市民」(*注2)と呼ばれ、市民どうしの法的関係によって形成される自律領域は「市民社会」と呼ばれ始めた。 市民社会は、国家がこれまで保護してきた特権階級とその既得権を否認し、個々人(といっても、通常は成人男性)による水平的な法関係形成の自由を法認するところに成立した。 この市民社会は、身分制社会や統治機構における位階構造ではない点に注目され、「公(政治)的領域/私的領域」という公私二分論を支えてきた。 近代立憲国家の役割は、いつかは誰でも利用することになる公共財(警察・司法作用、道路港湾等の建設、経済自由市場の取引ルール)を提供すること、および市民社会の自律的な動きを円滑にさせる私法体系を整備することにあった。 国家の作用は、市民社会の機能とは性質を異にしていた。 市民社会は、国家のように特定の組織規律をもたない自律領域であり、統治の領域からはどんどんズレていった。 市民社会が成熟するにつれて、これまでのような(個人-家族-共同体-国家)という同心円のイメージではこの世を捉えきれなくなったのだ。 だからこそ、市民社会は国家の組織規律とは異なる領域だと強調されて、「国家/市民社会(私的領域)」の二分論となったのだ。 この二分論は、《国家は理由なく市民社会に介入することなかれ》という国家権力の制限のために援用された。
[24] (2) 市民社会批判論自律的な個々人と、自律的に形成される市民社会は、常に警戒の目で見られ、次第に非難の対象となってきた。 “市民社会は、道徳を忘れた、私的欲望を賞賛する社会とならないか”“経済的な豊かさが実現されても、精神的な荒廃を呼ばないか”と自由主義者ですら、警戒的だった。 その自由主義者の不安に乗じて出てきたのが、マルクス主義だった。 自律的な個人像に対する批判は、“個々人は決して自律的ではなく、貧富の差があるとき、富者の経済的力に屈する弱者だ”となった。 自律的な市民社会に対する批判は、“富者である資本家が貧者である労働者を搾取する階級社会である”“貧富の格差を拡大する不公正な構造をもっている”となった。 上のマルクス主義的批判は、相当数の自由主義者をも巻き込んで進んできた。 そして、近代立憲主義とその国家に対する、大きな批判のうねりとなった。 “近代立憲主義は、人間を形式的・抽象的に捉えるばかりで、階級間の経済格差・権力格差を看過している”“自由と平等という人権は、形式的に捉えられたとき、階級間対立を隠蔽するイデオロギーとなる”というわけだ。 換言すれば、「立憲国家の実態は、階級国家だった」というのだ。 この批判は、現状の生活に満足していない労働者、弱者を自称する人々に歓迎され、穏健な自由主義者たちを大いにたじろがせた。 “市民社会とは、資本主義社会だったのか”“自由主義は、資本主義という影の部分を引きずってきたのか”との見方が普及していった。 そして、こういわれることとなった。
このターニング・ポイントとなったのがヴァイマル憲法だった。 その14条は「所有権は義務を伴う」と宣言した。 これは、財産権の国有・公有化を目指す社会主義からは一定の距離を保ちつつ、民主過程(議会制定法)を通して社会政策(ブルジョア社会を改良して社会的正義を実現すること)に乗り出す「社会国家」像を国制とすることの表明である。 [25] (3) 現代立憲主義かくして、国家は「正義」を実現するための強制の機構となった。 ある特定の正義・目標を定め、それに近づくために強制力を用いる国家である。 この正義は、ときに「社会的正義」と呼ばれ、それを実現する国家が「社会国家」といわれる。 この正義原理を憲法に組み入れた国家は「現代立憲主義国家」といわれたりもする([74]もみよ)。 が、不思議なことに、「社会」「現代」が正確には何を指すのか、深く追究されることはなかった。 それは、暗黙のうちに「労働者を中心とする弱者、または、ブルジョア足らざる者に優しい世」を指した。 これらの者の実質的自由を実現することが社会的正義の意だと了解された(後の [74] をみよ)。 だからこそ、「市民法原理」に代わる「社会法原理」が喧伝されてきたのだ。 そして、いつのまにか、農民も、中小企業の経営者も、高齢者も、はたまたときに女性も、“自分たちの実質的な自由は国家によって保護されなければならない”と主張されるようになった。
現実を冷静に見直したとき、現代立憲主義国家は、身分上の新たな特権を産み出してしまったのだ。 これは法の支配を侵食しないではおかないはずだ。 近代立憲国家の憲法典は、人の類型として「臣民または市民」、「国籍保有者」そして「外国人」しか知らなかった(⇒[8])。 ところが、マルクス主義の勃興以降の憲法典は、各人の置かれた人的条件を意味する「身分(estate)」という類型を意識し始め、その一定種を強行法規によって保護してきたのだ。 法学者のみならず相当数の社会科学者は、望ましい経済水準や生活水準は人為的に達成できると信じてきたようだ。 そのため、国家は財政・金融政策を通して積極的に経済市場に介入すべきだ、とか、望ましい生活水準を実現するために国家が国民の所得を再分配してよい、と推奨されてきた。 これが「積極国家」といわれるものだ。 今のところ、積極国家の成果は乏しいどころか、マイナスに出ているようにみえる。 現代立憲主義の提唱者は、積極国家における官僚団の数と権力とが必然のごとく肥大すること、そのための行政コストは膨大であること、そのコストは結局のところ国民が負担せざるを得ないこと等々を軽視してきたようだ。 現代立憲主義国家または積極国家のマイナス面は、何も経済的コストばかりではない。 官僚団の規模権限、それを正当化するための無数ともいえる法令が、我々の自律領域に任されてきたはずの領域を閉塞状態に追い込んではいないか? 官僚団が我々の自由を管理の対象としてはいないか? 現代立憲主義国家の病巣は、予想以上に深いようだ。 ■3.立憲主義にいう「自由」と「民主」[26] (1) 民主制におけるフランス型とイギリス型
こういう見方に対して、実体的民主主義観に立つ論者は“フランスのみならず、アメリカにおいても同様に考えられているではないか”と反論するかも知れない。 アメリカでも相当数の社会科学者が実体的民主主義観に立っている。 それには、アメリカで“リベラリズム”といわれるとき、「社会民主主義」を指すことが多いという事情が影響している。 社会主義を連想させる“リベラリズム”という用語に代わって、“デモクラシー”が自由の保障までをも含む用語として日常化してしまったのだ。 それでも、アメリカでの指導的な政治学者は、実体的民主主義観によることはなかった。
[27] (2) 民主制の市場モデルアメリカでの厳密な民主制理論は、経済市場モデルを基礎として打ち立てられた。 政治の生産者と、その消費者との関係として、次のように捉えるのである。
以上の見方を要約すれば、
民主制とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 こう考えれば、自由と民主とは独立の概念として捉える立場が妥当だ、ということが分かるだろう。 両者が、相互に独立の概念であることは、それぞれの反意語を考えれば了解されるだろう。 democracy の反対物は authoritarianism (=独裁制)であり、liberalism の反対物は totalitarianism (=全体主義)である。 [28] (3) 民主制の正当性実体的価値から解放された民主制は、なぜ正当であるか? この疑問に関しては、これまで、次のような解答が寄せられてきた。
[29] (4) 自由主義の意義「民主主義」と訳出されるデモクラシーは主義主張のことではなく、正確には政治体制を表す用語である(それは「民主制」と訳出されるべきだった)。 これに対して、リベラリズムすなわち自由主義は、まさに“主義”にかかわる。 自由主義とは、個人の自由を最優先する思想体系である。 それが、国家統治との関連についていわれるとき、
国家の強制力を最小化するための重要な視点は、次の3つである(*注4)。
以上の第一ないし第三は、相互に無関係ではない。 強制国法によって保護される独占は市場における自由競争を妨げるからである。 (※注釈:自由主義は)機構としての国家の活動のみならず、国家の経済政策をも法の支配のもとにおいて、透明なルールに基づいた事後規制社会を考えているのだ。 では、法の支配とは何か?
※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第四章 立憲主義と法の支配 第五章 立憲主義の展開 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ■要約・解説・研究ノート■ご意見、情報提供阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第7章 法の支配 本文 p.41以下
<目次> ■1.「法の支配」の捉え方[30] (1) 法の支配とは何でないのか「法の支配」は、多くの人が口にする基本概念でありながら、その実体につき合意をみない難問である。 とはいえ、法の支配の目指すところについては、論者の間におおよその合意がある。 “その目的は、可能な限りすべての国家機関の行為を法のもとにおいて、その恣意的な活動を統制し、もって人々の基本権を保障せんとするところにある。” が、この機能論的な説明は、法の実体の解明にはなっていない。 また、法の支配とは何でないのか、という疑問についても、法学者の間で合意がみられる。 その解答としては、次のふたつがある。
[30続き] (2) 法の支配と法治主義上の第一の「恣意的な人の支配」に代わろうとしたのが第二の法治主義である。 法治主義(*注1)は、民主的な国民代表機関に法規を創造する権限を集中さえ(法規という特異な概念については、[111]でふれる)、非民主的な行政機関と裁判所とを議会制定法(人為法)のもとに置こうとする民主化の思想だった。 「法の支配」にいう法は、民主的機関である議会の制定する法律をも統制し、主権者の意思をも統制する機能をもっている。 この機能については、法学者は異論を唱えないだろう。 未解決の争点は、“その狙いのために、法の支配にいう「法」がいかなる属性をもっているのか”というところにある。 法の支配を考えるに当たって重要なことは、
《法の支配とは、何であるのか》真剣に正面から検討することが必要である。
[31] (3) 法の支配と正義法の支配とは、《主権者といえども、人為の法を超える高次の法のもとにある》という思想を起源とする。 それは、法(law)と立法(legislation)との区別のもとで、前者が後者を指導する、という思想である。 高次の法 higher law とは、[11]でふれた“fundamental law”と同じである。 Higher law または fundamental law の内容は、《正義に適っているルール》を指してきた。 ところが、「正義」の捉え方は歴史によって変転し、論者によって様々となっているために私たちを混乱させているのだ。 法の支配を正義と関連づけるとき、その捉え方には、大きくふたつの流れがみられた。
長い歴史のうえで、盛んに説かれてきたのが、第一の立場だった。 神こそこの世の中心だ、と考えられていた時代にあっては、不可謬の神の意思がこの世の法則決定者だと考えられ、人間こそこの世の中心だと考えられるに至った時代にあっては、人間の理性がこの世の法則を決定づけている、とみられた。 神の意思や人間の理性と、法の支配とを関連づける立場は、“法とは実質的正義を体現しているものをいう”と理解しているのである。 実質的正義に依拠する法の支配論は、今日においても根強い。 なかでも、人間の理性的能力を強調する見解は、“恣意を理性によって統制すべし”とする法の支配の考えと調和的であるために、人々を納得させがちである。 が、「理性/恣意」の峻別は容易ではない。 「理性」は、実に多義的で、恣意的に用いられてきた。 また、人間が理性の塊ではないことは、C. ダーウイン、G. フロイトによって暴露された以上、人間理性と正義(法)とを関連づける理論の信憑性は疑わしい。 かといってこれ以外に実質的な正義の中味をいうとなると、常に論争を呼ぶ「神々の闘争」となって決着はつきそうもない。 そのために、法の支配と密接不可分な正義概念を、手続的に、または、形式的に捉えようとする論者が登場するのである。 「実質的正義/形式的正義」という正義論のふたつの流れは、国法の役割を考えるに当たって、無視できない違いをもたらしている。
■2.「法の支配」の理論と憲法典[32] (1) 法の支配の理論化法の支配を脱実体化しながら理論体系としたのが、イギリスの法学者A. ダイシー(1835~1922年)である。 彼は、臨機(場当たり)でなく、誰もが知りえて、特定可能な対象にではなく、誰に対しても等しく恒常的に適用され得る法の形式を、「正規の法 regular law」と呼んだ。 それは、《類似の事案は同じように法的に解決される》という平等原則の中から浮かび出た形式である。 それは、多年にわたる実践と蓄積のなかで、次第しだいに、人間が獲得してきた法的知識だった。 その法的知識を専門的に修得するのが法曹であり、なかでも裁判官である。 身分の独立保障をうけてきた裁判官は、当事者の主張に耳を傾けながら、正しい解決のために、誰に対しても等しく適用されてきた論拠を発見するのである。 公正な判断を求めようとする法的紛争の当事者は、誰であれ、この裁判の手続にのるよう求められる。 ダイシーは、このことを《何人も通常の裁判所の審判権に服する》と表現した。 フランスと違って、イギリスが行政裁判所という特別の裁判所を持たないことが、誰に対しても特権を与えない正規の法の表れでもあったのだ。 さらに、ダイシーにとって、国家の強制力を「人権保障規定」によって統制しようとすることは、必要でないばかりか、望ましくもなかった。 自由や権利は、正規の法の展開がもたらすはずのものであって、人為的な法規定によって与えられるべきものではなかった。 ダイシーの法の支配理論は、上のように、
[33] (2) 法の支配の突出部形式的正義論をベースとする法の支配の考え方には、
これらの命題は、法の予見性・安定性に資し、経済自由市場における交易を一挙に促進することとなった。 自由市場の生育を可能としたのは、法の支配という憲法上の基本概念だった。 法の支配が、経済的自由、身体・生命の自由その他の自由へと拡大するにつれて、自由主義国家の基盤が出来上がっていったのだ。 法の支配は、経済市場における諸自由だけでなく、国家の刑罰権と課税権とを有効に統制する論拠となった。 罪刑法定主義と租税法律主義が、法令の遡及的適用を排除したり、慣習を法源足り得ないとしたり、法令の裁量的適用に警戒的であるのは、法の支配の思想が、一部実定法上に突出したためである。 それでも法の支配にいう法は実定化され尽くすことはない。 法の支配は、我々の権利義務に関する実定法(人為法)を指導するメタ・ルールである。 法の支配という思想は、あるルールを実定化するにあたって実定法を先導する上位のルールである。 たとえ憲法を含む実定法が法の支配を謳ったとしても、それこそが「自己言及のパラドックス」にすぎないのだ([11]での脚注参照)。 [34] (3) 法の支配と憲法との関係法の支配は、国家の不正義を最小化するための理念として、歴史上様々な論者がそれに肉付けしてきた。 この理念は、sovereignty、なかでも、君主の有してきたそれをまず統制しようとした。 sovereignty は、「主権」と訳出されるが、この訳語では伝えきれないニュアンスをもった言葉である。 それは、「主権」というよりも、絶対権または最高権といったほうがいいだろう(⇒[37])。 憲法は、最高・絶対の主権を統制するための「基本法」として、歴史に登場した。 このことからも分かるように、憲法は、法の支配という構想の必須部なのだ(が、しかし、憲法が法の支配にいう法ではない)。 主権の帰属先が君主から国民になった場合でも、法の支配の理念に変更はない。 今日においても、すべての国家機関、なかでも国民の主権と、国民代表機関である議会とを、法のもとにおく必要があるのだ。 そのために、憲法は法の支配の理念の一部を組み込もうとする。
法の支配と憲法との関係を考えるに当たって最も重要な視点は、権力分立構造という全体的なパースペクティブ(※注釈:見通し、展望、大局観)を持つことだ。 権力分立構造は、ある時点から、違憲審査制または司法審査制の実現によって大きな「変容」をみせるが、この「変容」も、法の支配と関連している(この点に関しては、後の [55] でもふれるが、しかし、違憲審査制は法の支配の内容ではなく、法の支配を有効とするための装置である)。 教科書の中には、法の支配について、
もし、この思考が法の支配の論拠を日本国憲法典に求めようとしているのであれば、ひとつの体系内に根拠を求める「自己言及のパラドックス」に陥ってしまっている。 もし論拠を示したものではなく、“法の支配がかような諸点に現れている”というのであれば、(イ)と(ウ)はダブルカウントであり、(エ)は法の支配の内在的な要素ではなく(英国には、司法審査制はない)、法の支配を有効にするための手段に過ぎないことの説明に欠けている。 このように、憲法と法の支配との関係をみるとしても、要注意点は、《憲法典という実定化された法が法の支配にいう“法”ではない》ということである。 確かに、憲法典は法の支配の理念を一部活かしている。 が、しかし、「憲法典=法の支配」ではない(⇒[82])。 [34続き] (4) 法の支配と主権との関係《法の支配は憲法典や主権をも統制する》とのテーゼを理解するためには、次の(ア)~(ウ)に留意しておかなければならない。
では、「憲法典によって主権を統制することは出来ない」とき、主権(制憲権)は何によって規範的な拘束を受けているのだろうか? 実体的正義論者は、自然法、人間の理性、人間の尊厳、等をあげるだろう。 これらの実体的要素はいずれも客観性に欠けるとみる批判的な論者であれば、「主権者の自己拘束だ」というかもしれない。 それらの解答を、私はいずれも受容しない。 《主権を規範的に統制するもの、それが法の支配だ》、これが私の解答である。 法の支配にいう「法」とは、実定的な法ではなく、最低限の形式的正義のことだ、と私は理解している。
[35] (5) 法の支配と法律との関係法の支配は、先に触れたように、国民の主権や、国民代表機関である議会の権限(法律制定権)をも統制する理念である。 では、法の支配は、議会の立法権(法律制定権)をどのように統制するか? 実体的正義論者は、この問に関しても、主権を統制するものについて与えた解答と同じものを挙げるだろう。(※注釈:自然法、人間の理性、人間の尊厳、等) 「主権の自己拘束」説に立つ論者は、ここでの問に対して「議会の自己拘束だ」と答えるだろうか。 どうもそうではなく、解答は与えられていないようだ。 私のような、形式的正義論者は、こう解答するだろう。 《議会が法律を制定するにあたっては、一般的普遍的な形式をもたせなければならない》。 この解答は、日本国憲法41条の「立法」の解釈に活かされるだろう(後述の [116] を参照せよ)。 立法(法律)が一般的普遍的であるという形式を満たすとき、それは第一に、一定の要件を満たす限り誰に対しても適用され得るとする点で道徳的にみて正当であり、第二に、予見可能性・法的安定性を増すという点で経済的にみて合理的である。 法の一般性・普遍性とは、法規範の名宛人が事前に特定可能でないことをいう。 法の支配にとって最も警戒され続けてきた点は、法が人的な属性に言及しながら、特定可能な人びとを特別扱いすることだった。 法の支配は、人的な特権を忌避して、誰であれ自分の限界効用を自由に(国家から公法規制や指令を受けないで)満足させてよい、とする思想でもあるのだ。 近代法が、なぜ人間を「人」または「人格」と抽象的に形式的に言い表したのか、我々は近代法のこの発想の基本をもう一度振り返ったほうがよさそうだ(⇒[23])。 そうすれば、正義の女神が、なぜ目隠しをしているのか、すぐに理解できるだろう。 正義とは不正義を排除することなのだ。 ところが、現代法は「強者/弱者」という曖昧な二分法を強調することによって、「人」というケテゴリーの中に様々なサブ・カテゴリーを作り上げて社会的正義を積極的に人為的に(行政法や社会法という実定法を通して)実現しようとしてきている(⇒[25])。 これが正義というものだろうか? 「社会的正義」とは一体何だったのだろう? ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第四章 立憲主義と法の支配 第五章 立憲主義の展開 「法の支配(rule of law)」とは何か ■要約・解説・研究ノート■ご意見、情報提供阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第1章 日本国憲法における立憲主義 本文 p.111以下
<目次> [74] (1) 立憲主義の意義立憲主義は、大きく、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」に区別することが出来る。 前者の近代立憲主義は、また大きく、「立憲君主制」と「立憲民主制」とに分けることが出来る(但し、私自身は、「立憲民主制」というタームは避けることにしている。なぜなら、既に [22] でふれたように、近代立憲主義の狙いは、民主制の実現にはなかったからである。立憲民主制なる用語は、「君主制でも、貴族制でもなく、僭主制でも寡頭制でもない立憲主義」を表そうとして選択されたのだろう。が、それは、立憲主義の本来のニュアンスである《憲法によって統治権を制限すること》を表し切れていない、と私は確信している)。 体系書または教科書は、上のような幾つかの立憲主義を念頭に置いたうえで、「近代立憲主義から現代立憲主義へ」の展開に言及することが多い(⇒[24]~[25])。 このふたつの違いと展開は、通常、こう説明される。
ところが、不思議なことに、「社会国家」の真の意味は明確にされたことがない。 私の推察するところ、それは、「ブルジョア(市民)/労働者または弱者(社会)」という亀裂を念頭に置いて(⇒[8])、“社会権(社会保障)を充実させることが国家の任務だ”という国家観をいう(「社会」の意味は、「市民法秩序/社会法秩序」といわれるとき、最も明確に浮かび上がる。この点については [25] をみよ)。 社会国家の原型は、ヴァイマルそして今のドイツにあり、思想的論拠は「社会民主主義」にあり、その最大の特徴は所得再分配政策である。
日本国憲法が採用している、法の支配、権力分立、議会制、議員の地位、条約締結、普通選挙制、自由権保障等々は、近代立憲主義に忠実である。 また、議会(国会)について二院制を採用していること、各院に強い自律権を保障していること、執政府について内閣制を採用していること、司法府について自律権を保障しアメリカ型司法審査権まで付与していること(司法審査制はアメリカ建国時に既に気づかれていた)、硬性憲法としていること等も、日本国憲法が近代立憲主義、なかでも古典的な種類のそれに属していることの反映だといえる。 社会権はこの例外だ、と考えたほうがいいだろう([80]もみよ)。 [75] (2) 日本国憲法の特異さもっとも、日本国憲法における統治構造には、主要立憲主義国の現行憲法には見出し難い、独自の特徴が見出される(基本権保障については、ここではふれない)。
我が国の憲法学界は、明治憲法に否定的な評価を与え、他方で、日本国憲法を“民主的に”解釈すればするほど正しい姿勢である、といてきたところがある。 確かに、現実の統治過程には、明治憲法におけるプラクティスまたは習律が、時々顔を覗かせており、私にとっても気になるところがある。 上にふれた天皇の処遇以外について、少しばかり例を挙げると、
なかでも(5)は、統治の要であるはずの法の支配が我が国に根付かないことの原因となっている。
[75続き] (3) 日本国憲法と法の支配以下では、近代立憲主義が法の支配とセットとなって歩んできたことの重要な意味に留意しながら、日本国憲法の統治構造を概観していこう。 その基本的な構造を理解するには、第Ⅰ部でみた基礎理論を応用すればいい。 そのままのかたちで応用できない箇所があれば、その理由を考えればいいのだ。 もっとも、「基礎理論を応用する」といっても、その応用の仕方には、論者それぞれの選好が反映される。
この第Ⅱ部では、自由主義的に構成された基礎理論をさらに自由主義的に日本国憲法へ刻み込もうと私は努めるだろう。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第四章 立憲主義と法の支配 第五章 立憲主義の展開 ■要約・解説・研究ノート■ご意見、情報提供 |
| + | ... |
<目次>
中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。
統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。
今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。
|
| + | ... |
|
| ほうち-しゅぎ【法治主義】 <広辞苑> | ① 人の本性を悪と考え、徳治主義を排斥して、法律の強制による人民統治の重要性を強調する立場。 韓非子がその代表者。ホッブズも同様。 ② 王の統治権の絶対性を否定し、法に準拠する政治を主張する近代国家の政治原理 → 法の支配 |
| ほうちしゅぎ【法治主義】 rule of law(※注:原文ママ) <日本語版ブリタニカ> |
行政は議会において成立した法律によって行われなければならない、とする原則。 <1>行政に対する法律の支配を要求することにより、 <2>恣意的・差別的行政を排し、国民の権利と自由を保障することを目指したもので、立憲主義の基本原則の一つに挙げられている。 この原則に基く国家を、法治国家という。 |
| ほうち-こっか【法治国家】 <広辞苑> |
国民の意思によって制定された法に基づいて国家権力を行使することを建前とする国家。 ①権力分立が行われ、②司法権の独立が認められ、③行政が法律に基いて行われる、とされる。 法治国 → 警察国家 |
| ほうちこっか【法治国家】 Rechtsstaat <日本語版ブリタニカ> |
行政および司法が、あらかじめ議会の制定した法律によって行われるべきである、という法治主義の国家。 すなわち、全国家作用の法律適合性ということが、法治国家の本質とされたのであるが、 <1>その際、イギリス法の「法の支配」 rule of law と違い、 <2>行政および司法が、国民の代表機関たる議会によって制定された法律に適合していればよい、という形式的側面が重視された結果、 法治国家論は、法律に基きさえすれば、国民の権利・自由を侵害してよい、という否定的な機能を果たし、法や国家の目的・内容を軽視する法律万能主義的な傾向を内包していた。 (1)第二次世界大戦後、西ドイツは、この点に反省を加え、 (a)立法・行政および裁判を直接に拘束する不可侵・不可譲の基本的人権を承認し、 (b)これを確保するために憲法裁判所を設置して、これに法令の憲法適合性を審査する権限を与えた。 (2)日本の場合も、憲法は、裁判所に、いわゆる法令審査権を与えている(81条) このようにして、 [1]行政・司法が単に法律に適合している、という形式面のみならず、 [2]その法律の目的・内容そのものが、憲法に適合しなければならない、 という原則が確立され、それによって、いわば法治主義の実質的貫徹が期されている。 |