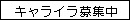14スレ目の74(ななよん)の妄想集@ウィキ
パートB
最終更新:
14sure74
-
view
窓から差し込む光で目が覚めると、私はベッドの上に居た。
あまり掃除がされていないのか部屋の至る所に埃が溜まっていた。
私はそれが不衛生極まりなく感じて、反射的に両手で口元を押さえた。
その時、何かが身体の上からずれ落ちて私の視界に入ってきた。
「――――!?」
それを見た瞬間、私の身体を芯から激しく戦慄かせる昏い【くらい】激動が湧き上がってきた。
その正体が何なのかはよく分からなかった。ただ、途轍【とてつ】もなくそれが怖くて私は叫んだ。
「イヤあああああアアああああぁぁぁああぁあああアァァァぁぁぁぁああああア!!?!」
「なんだ!?なんだ!?どうしたってんだ!?」
私の叫び声を聞いたこの部屋の主と思われる人物が、慌てた様子で扉を開けて入ってきた。
その人物は頭を押さえて叫び続ける私へと手を差し伸べてきた。
「イヤッ!いやぁぁ!!来ないで!助けてっ!うわあああ!!」
「うわっ!イテぇっ!お、落ち着け!なんもしねぇって!」
私はその人物の手を思い切り払い除けた。
その人物から、私を根底から揺るがす激動と同じ臭いを感じたからだった。
兎に角、この恐怖から解放されたい。その一心で、私は暴れていた。
そんな私をその人物は何回も押さえつけようとしてきた。
身体の彼方此方を蹴られ、殴られ、引掻かれ、それでも『落ち着け』と連呼しながら私を押さえようとしてきた。
「離して!怖い!うあああぁぁー・・・あっ!?」
「ダイジョブだ!怖くねぇ!俺は・・・なんもしねぇ!」
私は突然、その人物に強く抱きしめられた。
あの激臭が私の身体を包み込み、私の全てを激しく震わせた。
私は両手でその人物の背中に何度も爪を立てた。
「うわああああぁぁ!!離して!!やあぁああ!!」
「もう、怖くねぇ!なんも、怖いもんなんかねぇ!」
「――あっ?」
耳元でその人物が私に言い聞かせるように声を掛けた時、私は初めてその人物が私より年上の若い男性であることを知った。
彼の蒼い瞳に紅い瞳の私が映りこんだ。
その途端、今まで彼に纏わり【まとわり】ついていたあの激臭が感じられなくなり、同時に全身を震撼させたあの激動も少しずつその存在感を薄めていった。
「なっ?もう怖く・・・ねぇだろ?」
「あ・・・ああ・・・うぁ・・・・・・ぁ・・・・・・。」
彼の体温がじんわりと伝わってきて、私の身体を包み込んだ。
それは少し熱かったけど、とても心地良くて、私は全身の力がゆっくりと抜けていくのを感じていた。
「落ち着いたか・・・。少し、寝た方がいい。安心しな、俺が傍に居てやるからよ。」
「・・・・・・・・・うん・・・。」
・・・実を言うと、私はこの辺りのことはよく覚えていない。
殆ど全てが後で彼から伝え聞いたことだ。兎に角、それが私とあの人、”師”との出会いだった。
~~~~
私が再び目を覚ました時、彼は隣でベッドに項垂れて眠っていた。
私は頭が少し重いのを我慢してゆっくり上半身を起こした時だった。
「きゃあっ!?」
「Zzz・・・うおっ!?なんだ!?今度はなんだ!?」
私は彼の手をずっと握っていたことに気付いて、思わずその手を払い除けて叫んでしまった。
何故そうしてしまったのかははっきりと覚えていない。
多分、当時の私は化物人間ではない、ただの人間だったからだと思う。
「あっ!・・・ごめんなさい。」
「いや、別に謝らんでもいいぜ。気にしてねぇからよ。」
彼は笑顔で私に答えた。
その笑顔が私には何だか眩しくて、私は思わず視線を逸らしてしまった。
それから、彼は軽く自己紹介をしてくれた。
彼は各地を転々としてギルドや教会の依頼をこなす流れ者のファイターで、此処は現在の活動拠点だと教えてくれた。
「それで、俺は仕事を終わらせてあの集落で一休みしていた時に巻き込まれたってワケだ。」
「・・・あの集落?」
「ん?ほらっ、アンタを助けたあの・・・。」
「えっ?・・・私を・・・・・・助けた・・・・・・?・・・・・・其処で?」
彼は話にでてきた集落について、アレコレと説明を加えてくれるが何故か全く身に覚えがない。
まるで真っ暗な空間に手を突っ込んで中を弄っているかのような感覚だった。
「・・・アンタ、名前は?何処に住んでたんだ?」
「えっ・・・?」
そういえば、私は何処に住んでたのだろう。
そういえば、私は何て名前なんだろう。
そういえば、私は・・・誰なんだろう?
私は頭の中で自分自身に何度も問いかけたが、答えが返ってくることはなかった。
「名前・・・えっと・・・あ、あれ・・・・わ、私・・・・・・なまえ・・・・・・」
「・・・なるほどな。ま、仕方ねぇっちゃぁ、仕方ねぇか・・・。」
「私の・・・私は・・・・・・うぁ・・・・・・ぁぁ・・・・・・わたしぃ・・・・・・!!」
「うわっ!?もういい!もういいから無理すんな!なっ!?」
気付けば私は頭を抱えて泣いていた。
自分自身のことについて何一つ覚えていないということが、これほど恐ろしくて心細いことだったとは知らなかった。
彼は何か別の話題を振ろうとしてくれたのか、一度部屋を出て白くて長い布を持ってくると私に手渡した。
「・・・・・・これは?」
「それ、昨日アンタの手元に置いといた箱の中にあったヤツさ。」
「そう・・・なの・・・・・・ぅっ・・・。」
「わわっ!?まさか、勝手に開けちまったのマズかったのか!?すまねぇっ!!」
手渡された物を見ていると、再び涙が込み上げてきた。
最初の涙は違う意味を持った涙だったのは分かるが、それがいったいどんな意味を持っていたのかは今でも分からない。
彼は再び泣き出してしまった私に慌てふためいた様子で蒼いアンダーテイルを揺らしながら何度も謝っていた。
涙の理由は少なくとも彼の行ったことのせいではない。
私は彼にそのことを伝えた。
「ひっくっ・・・ち、違うよ・・・そういうワケじゃ、なくて・・・。」
「へっ!?なんだ、違うのかぁ~・・・いやぁ~びっくりしたぜ・・・。あは、あははは・・・・・・。」
「・・・・・・ふふふっ♪」
恥ずかしそうに頭を掻いて乾いた笑い声をあげる彼が何故だかとても面白く見えて、私はつい噴出してしまった。
「おっ、やっと笑った♪」
「えっ?」
彼は私に子供のように無邪気な笑顔を見せた。
「うん、やっぱアンタ、笑った顔が一番、可愛いぜ?」
「~~!?」
異性から可愛いなんて言われたのは、多分この時が初めてだった。
私は何故か恥ずかしくて気付けば頬を真っ赤に染めてまごついてしまっていた。
彼は私のそんな様子を見て高笑いをしていた。
「――――ネール=A=ファリス。」
「・・・えっ?」
突然、笑うのをやめて彼が真剣な顔で私を見つめた。
「って、まぁあの紙箱に描いてあった名前なんだが・・・。」
「『ネール・・・アルマーニ・・・ファリス』・・・。」
恐らく、それは私の名前ではない。
紙箱に態々自分の名前を描くワケがないし、何より私の中で言葉にならない感情が私の名前ではないと叫んでいた。
「とりあえず、本当の名前が思い出せるまでのアンタの名前ってことでいいか?・・・イヤなら、別の名前を考えるが。」
「・・・うん、いいよ。」
私の名前ではない。だが、この名前には私が失った何か大切なものが込められている気がした。
それに、彼が私のために見つけてきてくれた名前だ。無碍【むげ】に断るのは気が引けた。
「いよっし!じゃあ、たった今からアンタの名前はネール=A=ファリスだ!よろしくなっ♪ネス♪」
「えっ?ネ・・・『ネス』・・・?」
「おう、アンタの呼び名だ♪俺はバカだから、フルネーム覚えるの苦手なんだ・・・勘弁な?」
「そう、なんだ・・。」
聞けば彼は知り合いには必ずと言っていいほど別の呼び名を付けているそうだ。
その名付け方も大概はフルネームの最初と最後を捩った【もじった】物で、今にして思えば彼らしい名付け方だった。
「もしかして、知り合った人全員に・・・?」
「おう♪えっと、ハルだろ、アスだろ、ラスだろ、あとは・・・あれ?アイツはロウだったっけ、ロトだったっけ?」
自分が過去に付けた呼び名を思い出そうと難しい顔をして首を傾げる彼を見ていたら、何だかとても安心した。
自分自身のことが何一つ分からなくなって、不安と絶望で凍り付いていた心がゆっくりと溶けていった。
「ふふっ!呼び名付けても忘れてるじゃん!」
「う、うるせぇ~!今日は、その、アレだ!風邪気味だから頭が働かないだけだって!」
「アハハッ♪じゃあ、そういうことにしておくネッ♪」
「だ~か~ら~!そういうことなんだってぇーっ!」
・・・何も無くなってしまった私の世界に、新しい物をくれたのは彼だった。
今の私は、この時に彼がくれた物から広がった世界に居る。
~~~~
彼が名前と呼び名を付けてくれた日から、私は彼の棲家で暮らすことになった。
森の中の開けた所にポツンとあるその家は、昼間でも遠くの方で鳥のさざめき声が聞こえるだけのとても静かな場所だった。
「ふわぁ~・・・おはよ・・・早いんだネ・・・。」
「あっ、わりぃ。起こしちまったか?」
彼の朝は早かった。
夜が明ける頃には起きていて、家の外で只管剣を振っていた。
「ナニ、やってるの?」
「まっ、朝の運動ってトコかな。何せこの身体とコレだけが俺の商売道具だし。」
そう言って彼は自分の剣を自慢げに見せ付けてきた。
この時の私は剣なんて握ったことがなかったし興味もなかった。
「へぇー・・・。」
「むっ、なんだその『興味ない』って顔!コレはな、ただの剣じゃねーんだぜ?」
私の反応が希薄だったことが気に食わなかった彼は、自慢の剣について語り出した。
「コレは、ブレイクオブエクスなんたら・・・、まぁブレイカーって言ってだな。世界で一番硬くて強くて重い剣なんだぜ。」
「そうなんだ・・・。」
「そうなの。コレを片手で振り回せるのは、世界広しと言えど俺ぐらいなもんだぜっ♪」
楽しそうに語る彼に半ば付いていけない物を感じながらも、私は彼の剣を振る姿をずっと見ていた。
剣を振っている時の彼はとても輝いていて、私はその輝きに何時しか惹き込まれていた。
それからというもの、仕事に出た彼の帰りを待つ間、私は暇潰しも兼ねてその辺に落ちている木の枝で彼の練習を真似ていた。
あの輝きに少しでも近づきたい。そう思うようになっていた。
そして数日後、私は思い切って彼と練習したいと申し出ることにした。
「・・・ん?どうした?こんな朝早くに。」
「えっと・・・あのね、私も一緒にやりたいなーって・・・思って。」
「ああ、いいぜ♪その辺から木の枝でも拾ってきな♪」
「えっ!?ホントに!?」
正直、断られると思っていたのであっさりと一緒に練習することを許してくれたことに私は驚きを隠せなかった。
「ホントにいいの!?邪魔じゃない?」
「何言ってんだよ、運動すんのに邪魔も何もねぇって。寧ろ【むしろ】、運動は一緒にやった方が楽しいだろ?」
「よかった!ありがとー!!」
私は小走りで家から飛び出すと、いつも一人で練習する時に使っていた木の枝を引っ張り出した。
「ほほぉー・・・やっぱ、その木の枝はアンタのだったか。」
「えっ?」
「いやなに、薪にはできそうにないのに、最近家の傍にずっと置いてあったからさ。」
一応バレないように置いてあったつもりだったのだが、彼にはバレていたらしい。
私は顔が赤くなっていくのを感じた。
「興味あるんだったら、一言一緒にやろうと言ってくれりゃぁよかったのに。」
「じゃ、じゃあ誘ってくれたってよかったじゃない!」
「あっ、そういやそうだな。いやさ、アンタ興味なさそうだったもんでよ・・・。」
「・・・もう!早くはじめようよ!」
何故、あの時私は怒っていたのかはよく分からない。
彼は私の態度に少し戸惑いながらも剣を構えいつもの練習を始めた。
私は相変わらずの輝きを放つ彼につい見とれてしまったが、気を持ち直して私も木の枝を振り始めた。
「・・・あれっ?アンタ、もしかして剣を握ってたことがあったりなんかした?」
彼は私の練習光景を見るなり、剣を振るのをやめて問いかけてきた。
「えっ?んと・・・多分、ないよ。」
「だよなぁ・・・。どう見てもなさそうだしなぁ・・・。」
彼は急に首を捻って唸り出した。
私は自分が何か仕出かしてしまったのか不安で堪らず、首を捻り続ける彼に恐る恐る問いかけた。
「私、なにか悪いこと・・・した?」
「えっ!?いやいやいや!!アンタ、剣を握ったことないとは思えないぐらい筋がいいんでびっくりしちまっただけだ。」
「ほ、ほんと!?」
「ウソなんか言ってどーすんだよ。アンタの才能は凄い、この俺が保証する!」
嬉しかった。
才能がどうのこうのというよりも前に、彼を笑顔にできたことが嬉しかった。
彼の輝きに少し近付けたことが嬉しかった。
同時に、もっと彼の輝きに近づきたい。そう思うようになった。
それからの私は、より一層練習に打ち込むようになった。
彼が帰ってくるまでずっと木の枝を振り回し続け、彼がその成果をみて笑顔を見せてくれるのを思い描いていた。
そして彼が笑顔を見せてくれる度、私はまた少し彼の輝きに近付けたという達成感と、もっと近づきたいという欲に心が満たされていた。
しかし、この時の私には、この思いの根底に在るものが何なのかは分からなかった。
ただ、彼のことを思い描いていると胸の奥がじんわりと暖かく、ふわふわと浮いているような感じがして、それがとても心地良かった。
日々私の中で彼の輝きに近づきたいという思いが存在感を増していき、彼の仕事について行きたいという思いへ変わるのに時間はあまり掛からなかった。
彼の仕事について行けば、彼が帰ってくるのを待ちわびて独り寂しく木の枝を振り続ける必要がなくなるからだ。
そしてある日、ついに私は彼にそのことを打ち明けた。
あまり掃除がされていないのか部屋の至る所に埃が溜まっていた。
私はそれが不衛生極まりなく感じて、反射的に両手で口元を押さえた。
その時、何かが身体の上からずれ落ちて私の視界に入ってきた。
「――――!?」
それを見た瞬間、私の身体を芯から激しく戦慄かせる昏い【くらい】激動が湧き上がってきた。
その正体が何なのかはよく分からなかった。ただ、途轍【とてつ】もなくそれが怖くて私は叫んだ。
「イヤあああああアアああああぁぁぁああぁあああアァァァぁぁぁぁああああア!!?!」
「なんだ!?なんだ!?どうしたってんだ!?」
私の叫び声を聞いたこの部屋の主と思われる人物が、慌てた様子で扉を開けて入ってきた。
その人物は頭を押さえて叫び続ける私へと手を差し伸べてきた。
「イヤッ!いやぁぁ!!来ないで!助けてっ!うわあああ!!」
「うわっ!イテぇっ!お、落ち着け!なんもしねぇって!」
私はその人物の手を思い切り払い除けた。
その人物から、私を根底から揺るがす激動と同じ臭いを感じたからだった。
兎に角、この恐怖から解放されたい。その一心で、私は暴れていた。
そんな私をその人物は何回も押さえつけようとしてきた。
身体の彼方此方を蹴られ、殴られ、引掻かれ、それでも『落ち着け』と連呼しながら私を押さえようとしてきた。
「離して!怖い!うあああぁぁー・・・あっ!?」
「ダイジョブだ!怖くねぇ!俺は・・・なんもしねぇ!」
私は突然、その人物に強く抱きしめられた。
あの激臭が私の身体を包み込み、私の全てを激しく震わせた。
私は両手でその人物の背中に何度も爪を立てた。
「うわああああぁぁ!!離して!!やあぁああ!!」
「もう、怖くねぇ!なんも、怖いもんなんかねぇ!」
「――あっ?」
耳元でその人物が私に言い聞かせるように声を掛けた時、私は初めてその人物が私より年上の若い男性であることを知った。
彼の蒼い瞳に紅い瞳の私が映りこんだ。
その途端、今まで彼に纏わり【まとわり】ついていたあの激臭が感じられなくなり、同時に全身を震撼させたあの激動も少しずつその存在感を薄めていった。
「なっ?もう怖く・・・ねぇだろ?」
「あ・・・ああ・・・うぁ・・・・・・ぁ・・・・・・。」
彼の体温がじんわりと伝わってきて、私の身体を包み込んだ。
それは少し熱かったけど、とても心地良くて、私は全身の力がゆっくりと抜けていくのを感じていた。
「落ち着いたか・・・。少し、寝た方がいい。安心しな、俺が傍に居てやるからよ。」
「・・・・・・・・・うん・・・。」
・・・実を言うと、私はこの辺りのことはよく覚えていない。
殆ど全てが後で彼から伝え聞いたことだ。兎に角、それが私とあの人、”師”との出会いだった。
~~~~
私が再び目を覚ました時、彼は隣でベッドに項垂れて眠っていた。
私は頭が少し重いのを我慢してゆっくり上半身を起こした時だった。
「きゃあっ!?」
「Zzz・・・うおっ!?なんだ!?今度はなんだ!?」
私は彼の手をずっと握っていたことに気付いて、思わずその手を払い除けて叫んでしまった。
何故そうしてしまったのかははっきりと覚えていない。
多分、当時の私は化物人間ではない、ただの人間だったからだと思う。
「あっ!・・・ごめんなさい。」
「いや、別に謝らんでもいいぜ。気にしてねぇからよ。」
彼は笑顔で私に答えた。
その笑顔が私には何だか眩しくて、私は思わず視線を逸らしてしまった。
それから、彼は軽く自己紹介をしてくれた。
彼は各地を転々としてギルドや教会の依頼をこなす流れ者のファイターで、此処は現在の活動拠点だと教えてくれた。
「それで、俺は仕事を終わらせてあの集落で一休みしていた時に巻き込まれたってワケだ。」
「・・・あの集落?」
「ん?ほらっ、アンタを助けたあの・・・。」
「えっ?・・・私を・・・・・・助けた・・・・・・?・・・・・・其処で?」
彼は話にでてきた集落について、アレコレと説明を加えてくれるが何故か全く身に覚えがない。
まるで真っ暗な空間に手を突っ込んで中を弄っているかのような感覚だった。
「・・・アンタ、名前は?何処に住んでたんだ?」
「えっ・・・?」
そういえば、私は何処に住んでたのだろう。
そういえば、私は何て名前なんだろう。
そういえば、私は・・・誰なんだろう?
私は頭の中で自分自身に何度も問いかけたが、答えが返ってくることはなかった。
「名前・・・えっと・・・あ、あれ・・・・わ、私・・・・・・なまえ・・・・・・」
「・・・なるほどな。ま、仕方ねぇっちゃぁ、仕方ねぇか・・・。」
「私の・・・私は・・・・・・うぁ・・・・・・ぁぁ・・・・・・わたしぃ・・・・・・!!」
「うわっ!?もういい!もういいから無理すんな!なっ!?」
気付けば私は頭を抱えて泣いていた。
自分自身のことについて何一つ覚えていないということが、これほど恐ろしくて心細いことだったとは知らなかった。
彼は何か別の話題を振ろうとしてくれたのか、一度部屋を出て白くて長い布を持ってくると私に手渡した。
「・・・・・・これは?」
「それ、昨日アンタの手元に置いといた箱の中にあったヤツさ。」
「そう・・・なの・・・・・・ぅっ・・・。」
「わわっ!?まさか、勝手に開けちまったのマズかったのか!?すまねぇっ!!」
手渡された物を見ていると、再び涙が込み上げてきた。
最初の涙は違う意味を持った涙だったのは分かるが、それがいったいどんな意味を持っていたのかは今でも分からない。
彼は再び泣き出してしまった私に慌てふためいた様子で蒼いアンダーテイルを揺らしながら何度も謝っていた。
涙の理由は少なくとも彼の行ったことのせいではない。
私は彼にそのことを伝えた。
「ひっくっ・・・ち、違うよ・・・そういうワケじゃ、なくて・・・。」
「へっ!?なんだ、違うのかぁ~・・・いやぁ~びっくりしたぜ・・・。あは、あははは・・・・・・。」
「・・・・・・ふふふっ♪」
恥ずかしそうに頭を掻いて乾いた笑い声をあげる彼が何故だかとても面白く見えて、私はつい噴出してしまった。
「おっ、やっと笑った♪」
「えっ?」
彼は私に子供のように無邪気な笑顔を見せた。
「うん、やっぱアンタ、笑った顔が一番、可愛いぜ?」
「~~!?」
異性から可愛いなんて言われたのは、多分この時が初めてだった。
私は何故か恥ずかしくて気付けば頬を真っ赤に染めてまごついてしまっていた。
彼は私のそんな様子を見て高笑いをしていた。
「――――ネール=A=ファリス。」
「・・・えっ?」
突然、笑うのをやめて彼が真剣な顔で私を見つめた。
「って、まぁあの紙箱に描いてあった名前なんだが・・・。」
「『ネール・・・アルマーニ・・・ファリス』・・・。」
恐らく、それは私の名前ではない。
紙箱に態々自分の名前を描くワケがないし、何より私の中で言葉にならない感情が私の名前ではないと叫んでいた。
「とりあえず、本当の名前が思い出せるまでのアンタの名前ってことでいいか?・・・イヤなら、別の名前を考えるが。」
「・・・うん、いいよ。」
私の名前ではない。だが、この名前には私が失った何か大切なものが込められている気がした。
それに、彼が私のために見つけてきてくれた名前だ。無碍【むげ】に断るのは気が引けた。
「いよっし!じゃあ、たった今からアンタの名前はネール=A=ファリスだ!よろしくなっ♪ネス♪」
「えっ?ネ・・・『ネス』・・・?」
「おう、アンタの呼び名だ♪俺はバカだから、フルネーム覚えるの苦手なんだ・・・勘弁な?」
「そう、なんだ・・。」
聞けば彼は知り合いには必ずと言っていいほど別の呼び名を付けているそうだ。
その名付け方も大概はフルネームの最初と最後を捩った【もじった】物で、今にして思えば彼らしい名付け方だった。
「もしかして、知り合った人全員に・・・?」
「おう♪えっと、ハルだろ、アスだろ、ラスだろ、あとは・・・あれ?アイツはロウだったっけ、ロトだったっけ?」
自分が過去に付けた呼び名を思い出そうと難しい顔をして首を傾げる彼を見ていたら、何だかとても安心した。
自分自身のことが何一つ分からなくなって、不安と絶望で凍り付いていた心がゆっくりと溶けていった。
「ふふっ!呼び名付けても忘れてるじゃん!」
「う、うるせぇ~!今日は、その、アレだ!風邪気味だから頭が働かないだけだって!」
「アハハッ♪じゃあ、そういうことにしておくネッ♪」
「だ~か~ら~!そういうことなんだってぇーっ!」
・・・何も無くなってしまった私の世界に、新しい物をくれたのは彼だった。
今の私は、この時に彼がくれた物から広がった世界に居る。
~~~~
彼が名前と呼び名を付けてくれた日から、私は彼の棲家で暮らすことになった。
森の中の開けた所にポツンとあるその家は、昼間でも遠くの方で鳥のさざめき声が聞こえるだけのとても静かな場所だった。
「ふわぁ~・・・おはよ・・・早いんだネ・・・。」
「あっ、わりぃ。起こしちまったか?」
彼の朝は早かった。
夜が明ける頃には起きていて、家の外で只管剣を振っていた。
「ナニ、やってるの?」
「まっ、朝の運動ってトコかな。何せこの身体とコレだけが俺の商売道具だし。」
そう言って彼は自分の剣を自慢げに見せ付けてきた。
この時の私は剣なんて握ったことがなかったし興味もなかった。
「へぇー・・・。」
「むっ、なんだその『興味ない』って顔!コレはな、ただの剣じゃねーんだぜ?」
私の反応が希薄だったことが気に食わなかった彼は、自慢の剣について語り出した。
「コレは、ブレイクオブエクスなんたら・・・、まぁブレイカーって言ってだな。世界で一番硬くて強くて重い剣なんだぜ。」
「そうなんだ・・・。」
「そうなの。コレを片手で振り回せるのは、世界広しと言えど俺ぐらいなもんだぜっ♪」
楽しそうに語る彼に半ば付いていけない物を感じながらも、私は彼の剣を振る姿をずっと見ていた。
剣を振っている時の彼はとても輝いていて、私はその輝きに何時しか惹き込まれていた。
それからというもの、仕事に出た彼の帰りを待つ間、私は暇潰しも兼ねてその辺に落ちている木の枝で彼の練習を真似ていた。
あの輝きに少しでも近づきたい。そう思うようになっていた。
そして数日後、私は思い切って彼と練習したいと申し出ることにした。
「・・・ん?どうした?こんな朝早くに。」
「えっと・・・あのね、私も一緒にやりたいなーって・・・思って。」
「ああ、いいぜ♪その辺から木の枝でも拾ってきな♪」
「えっ!?ホントに!?」
正直、断られると思っていたのであっさりと一緒に練習することを許してくれたことに私は驚きを隠せなかった。
「ホントにいいの!?邪魔じゃない?」
「何言ってんだよ、運動すんのに邪魔も何もねぇって。寧ろ【むしろ】、運動は一緒にやった方が楽しいだろ?」
「よかった!ありがとー!!」
私は小走りで家から飛び出すと、いつも一人で練習する時に使っていた木の枝を引っ張り出した。
「ほほぉー・・・やっぱ、その木の枝はアンタのだったか。」
「えっ?」
「いやなに、薪にはできそうにないのに、最近家の傍にずっと置いてあったからさ。」
一応バレないように置いてあったつもりだったのだが、彼にはバレていたらしい。
私は顔が赤くなっていくのを感じた。
「興味あるんだったら、一言一緒にやろうと言ってくれりゃぁよかったのに。」
「じゃ、じゃあ誘ってくれたってよかったじゃない!」
「あっ、そういやそうだな。いやさ、アンタ興味なさそうだったもんでよ・・・。」
「・・・もう!早くはじめようよ!」
何故、あの時私は怒っていたのかはよく分からない。
彼は私の態度に少し戸惑いながらも剣を構えいつもの練習を始めた。
私は相変わらずの輝きを放つ彼につい見とれてしまったが、気を持ち直して私も木の枝を振り始めた。
「・・・あれっ?アンタ、もしかして剣を握ってたことがあったりなんかした?」
彼は私の練習光景を見るなり、剣を振るのをやめて問いかけてきた。
「えっ?んと・・・多分、ないよ。」
「だよなぁ・・・。どう見てもなさそうだしなぁ・・・。」
彼は急に首を捻って唸り出した。
私は自分が何か仕出かしてしまったのか不安で堪らず、首を捻り続ける彼に恐る恐る問いかけた。
「私、なにか悪いこと・・・した?」
「えっ!?いやいやいや!!アンタ、剣を握ったことないとは思えないぐらい筋がいいんでびっくりしちまっただけだ。」
「ほ、ほんと!?」
「ウソなんか言ってどーすんだよ。アンタの才能は凄い、この俺が保証する!」
嬉しかった。
才能がどうのこうのというよりも前に、彼を笑顔にできたことが嬉しかった。
彼の輝きに少し近付けたことが嬉しかった。
同時に、もっと彼の輝きに近づきたい。そう思うようになった。
それからの私は、より一層練習に打ち込むようになった。
彼が帰ってくるまでずっと木の枝を振り回し続け、彼がその成果をみて笑顔を見せてくれるのを思い描いていた。
そして彼が笑顔を見せてくれる度、私はまた少し彼の輝きに近付けたという達成感と、もっと近づきたいという欲に心が満たされていた。
しかし、この時の私には、この思いの根底に在るものが何なのかは分からなかった。
ただ、彼のことを思い描いていると胸の奥がじんわりと暖かく、ふわふわと浮いているような感じがして、それがとても心地良かった。
日々私の中で彼の輝きに近づきたいという思いが存在感を増していき、彼の仕事について行きたいという思いへ変わるのに時間はあまり掛からなかった。
彼の仕事について行けば、彼が帰ってくるのを待ちわびて独り寂しく木の枝を振り続ける必要がなくなるからだ。
そしてある日、ついに私は彼にそのことを打ち明けた。