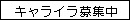14スレ目の74(ななよん)の妄想集@ウィキ
突発的な妄想
最終更新:
14sure74
-
view
――瞬間。
空の色が、喧騒とした街の音が、悠久に流れる時間が。
彼女を取り巻く一切が、消え去る。
(・・・っ!)
彼女はゆっくりと目を見開く。
次第に昂ぶっていく感情に合わせて、呼吸が激しくなる。
彼女の”人間”の証ともいうべき血の流れる音が、一切を失った彼女の世界を突如として引き裂く。
(ふっ・・・! あ・・・っ! くっ・・・!!)
引き裂かれた彼女の世界が、声にならない断末魔をあげる。
その衝撃で全身が震え、身体が急激に熱を帯びていく。
あまりの熱量に苦しくなった彼女は、激しく身を捩って悶える。
(あの・・・コ・・・か・・・ッ!)
沸騰した意識が蒸発していく最中、彼女は声なき声をあげた。
一切が消え去った世界に僅かに映る残像を、視線で必死に手繰り寄せる。
まるで小動物のような少し気弱そうな顔立ちをした、美しいブロンド髪の残像を手繰り寄せる。
(かワ・・・イい・・・ッ!!)
彼女の意識はそこで途絶えた。
~~~~
――瞬間。
あまりに唐突過ぎた出来事に、彼はただへたり込むしか出来なかった。
(なっ、なんだって、なんだって、んだ・・・よぉ!!)
なんでもいいから兎に角叫びたい、そんな衝動に駆られ彼は声を出そうと試みる。
しかし、何度試みても出るのは言葉にならない声ばかりだった。
(くそっ! お、オレが・・・オレがなんで・・・こんな、こんなっ!)
思うように言葉がでないもどかしさが無性に腹立たしくなり、彼は激しく頭を振る。
陽の光を受け美しく輝くブロンドの髪が宙に暴れる。
次第に目頭が熱くなるのを感じた彼は、唇をきつく噛む。
(くそぅ! くそぅ!! 泣くなんて! 流石にカッコワル過ぎるっ、だろっ、オレッ!!)
どうにかして鎮めようと、持てる限りの力を右腕に込めて彼は目をこすった。
その時。
「――そこのきみ。」
「――ヒャヒッ!?」
頭の上から降ってきた言葉に素っ頓狂な声をあげて、彼は顔を上げる。
まだ少しぼやけている視界に映ったのは、心配そうな表情をした黒目黒髪の少年だった。
背格好からして、自分と同世代か少し下だろう。
そう思った途端、彼の中で暴れていた感情が急激に勢いを失っていく。
「大丈夫でしたか? お怪我は、ありませんか?」
中々返答がこないことを不安に思ったのだろう。
少年は彼に再び問いかける。
彼は少年の二度目の問いかけに、大きく深呼吸をしてから応えた。
「あ、ああ・・・。 だ、大丈夫、だ。」
彼の返答を聞いた少年の表情がにわかに明るくなる。
「そうですか、それはよかった。」
そういうと少年は彼に向かって笑顔で手を差し伸べた。
彼は軽く礼を言って少年の手を取り、ゆっくりと起き上がる。
「何方かは存じませんが、この度は恐ろしい体験をさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。」
そう言うと少年は深く頭を下げた。
「い、いやっ、その、そんな謝らなくても、いいよ。」
少年があまりに唐突に、本当に申し訳なさそうに頭を下げたので、彼は慌ててやめさせた。
「ぼくは金森といいます。」
「あ、ああ、えっと、オレはラッセル。」
「ラッセルさん、ですね。 本当に申し訳ございません。」
再び彼は頭を下げる。
「い、いやあ、もういいよ。 金森が悪いワケじゃあないんだし・・・。」
「いえ、あんなのでも一応はぼくのマスターですので、マスターの失態はぼくの失態でもあります。」
「えっ?」
ブロンド髪の彼、ラッセルは黒目黒髪の少年、金森の台詞から普段聞き慣れない単語を聞き、思わず聞き返した。
「マスター、って?」
「あ、ああ。 まだ、説明しておりませんでしたね。」
そういうと金森は遠方を指を指して答える。
「この先、322.34メートルの所でだらしのないアヘ顔でノビている彼女が、ぼくのマスター、つまり創造主です。」
「ああ、そうなんだ、なるほど、そう・・・――っぞうしゅだってぇ!?」
金森があまりに淡々と、さも当然のように答えるので、ラッセルは釣られて納得してしまいそうになって慌てて叫んだ。
「そそ、それは、えっとだ! つまり、その、金森は作られた人!?」
「はい、そうです。 僕はマスター、リベット=G【ギャラクト】=ウィンストンによって作られたお手伝いロボットです。」
ラッセルはその場にまたへたり込みたい衝動に駆られた。
人が人を作ることなど到底できないことだと、ラッセルはずっと思っていたからだ。
呆然と立ち尽くすラッセルに構う様子もなく、金森は言葉を続ける。
「では、僕はマスターの回収に向かいますね。 ラッセルさんもこの場を早く離れてくださいね。」
「あっ? あ、ああ・・・。」
軽く会釈する金森に、ラッセルは生返事を返すことしかできなかった。
~~~~
「んぅ・・・。」
鈍く響く砂利の音で彼女は目を覚ました。
「ふにゅぅぁぁ・・・。」
酷く全身が重く、気だるい。
彼女は大きく欠伸をして、なんとか気だるさを抜く。
「ぬぅぅ・・・?」
彼女は今、自分の置かれている状況が全く分からなかった。
そこでまずは状況を把握しようと、彼女はゆっくりと意識を覚醒させる。
「――っ!?」
全身に意識をいきわたらせた途端、頬の辺りに激痛が走った。
彼女は思わず、全身全霊を込めて叫んだ。
「ったぁあぁあぁあいぃぃーっ!!」
一頻り叫び終えると、彼女は全てを悟った。
自分が今置かれている状況も、意識が戻るまでの出来事も、激痛の理由も。
「もぉぉう!!」
そして、激痛の原因も。
「かなやん! ちょっとはぁ、手加減をぉ、しなさいよぉー!」
彼女は全身をばたつかせて叫んだ。
「開口一番でなにを仰るかと思えば・・・。 手加減しろ、ですか。」
彼女の背中から冷やかで落ち着いた様子の声がした。
「今回の出力は最大時の45.98%ですので、前回よりも手加減を致しましたよ。」
背中の声は淡々と答える。
「前回より0.02%しか、落としてないじゃないのぉ! なんのためのぉ、超高性能AIなのよぉ!」
「前回より0.02%出力を落とせばマスターの指定した衝撃度に収まると、ぼくの超高性能AIは結論をだしましたよ?」
「ウソよぉ、全然落ちてないじゃないのぉ・・・!」
少し泣きそうな声で反論する彼女を、鼻で笑ってから背中の声は答える。
「それは貴女が、僕に記憶されている貴女の最高速度よりも遥かに高速で飛び込んだからですよ、マスター。」
「っ・・・!」
彼女は思わず言葉を詰まらせた。
彼女の反応を予想していたかのように、背中の声は淡々と言葉を続ける。
「僕の計算はあくまで僕に記憶されている最高速度を基にしています。 従って、本来であればしっかりと計算どおりに収まるはずでした。」
「ぬ、ぬぅぅ・・・!」
「しかし、実際には貴女は僕に記憶されている最高速度以上で飛び込んだ。 不思議ですね。」
「ふ、不思議ってぇ、なによぅ!」
彼女の不貞腐れた反応に、声の主はわざとらしく大きな溜め息をつく。
「・・・貴女の身体の殆どは機械、”なにもせずに”最高速度を超えられるはずがありません。」
「――っ!」
急に大人しくなった彼女に、声の主は呆れきった声色で問い掛ける。
「内緒でチューンアップ、しましたね?」
「・・・ハヒ。」
彼女は観念した様子で力なく答えた。
「大方、僕が駆けつけるよりも早く飛びかかろうという魂胆でしょう?」
「・・・セウデス、スミバゼン、モウシマセン。」
「全く、こんな節操なしの短絡的思考の人間が僕のマスターだなんて、情けなさすぎて、涙もでません・・・。」
声の主は一際大きな溜め息をついた。
「あらぁ、かなやんは、元々血も涙もないロボットじゃないのぉ。」
「最長飛距離、もう更新しますか?」
「エンリョシマフ。」
声の主の若干殺意の篭った冷やかな問いかけに、彼女は即答した。
彼女はその後、自宅に着くまでずっと声の主に首根っこを掴まれ、引き摺られたままだった。
END
空の色が、喧騒とした街の音が、悠久に流れる時間が。
彼女を取り巻く一切が、消え去る。
(・・・っ!)
彼女はゆっくりと目を見開く。
次第に昂ぶっていく感情に合わせて、呼吸が激しくなる。
彼女の”人間”の証ともいうべき血の流れる音が、一切を失った彼女の世界を突如として引き裂く。
(ふっ・・・! あ・・・っ! くっ・・・!!)
引き裂かれた彼女の世界が、声にならない断末魔をあげる。
その衝撃で全身が震え、身体が急激に熱を帯びていく。
あまりの熱量に苦しくなった彼女は、激しく身を捩って悶える。
(あの・・・コ・・・か・・・ッ!)
沸騰した意識が蒸発していく最中、彼女は声なき声をあげた。
一切が消え去った世界に僅かに映る残像を、視線で必死に手繰り寄せる。
まるで小動物のような少し気弱そうな顔立ちをした、美しいブロンド髪の残像を手繰り寄せる。
(かワ・・・イい・・・ッ!!)
彼女の意識はそこで途絶えた。
~~~~
――瞬間。
あまりに唐突過ぎた出来事に、彼はただへたり込むしか出来なかった。
(なっ、なんだって、なんだって、んだ・・・よぉ!!)
なんでもいいから兎に角叫びたい、そんな衝動に駆られ彼は声を出そうと試みる。
しかし、何度試みても出るのは言葉にならない声ばかりだった。
(くそっ! お、オレが・・・オレがなんで・・・こんな、こんなっ!)
思うように言葉がでないもどかしさが無性に腹立たしくなり、彼は激しく頭を振る。
陽の光を受け美しく輝くブロンドの髪が宙に暴れる。
次第に目頭が熱くなるのを感じた彼は、唇をきつく噛む。
(くそぅ! くそぅ!! 泣くなんて! 流石にカッコワル過ぎるっ、だろっ、オレッ!!)
どうにかして鎮めようと、持てる限りの力を右腕に込めて彼は目をこすった。
その時。
「――そこのきみ。」
「――ヒャヒッ!?」
頭の上から降ってきた言葉に素っ頓狂な声をあげて、彼は顔を上げる。
まだ少しぼやけている視界に映ったのは、心配そうな表情をした黒目黒髪の少年だった。
背格好からして、自分と同世代か少し下だろう。
そう思った途端、彼の中で暴れていた感情が急激に勢いを失っていく。
「大丈夫でしたか? お怪我は、ありませんか?」
中々返答がこないことを不安に思ったのだろう。
少年は彼に再び問いかける。
彼は少年の二度目の問いかけに、大きく深呼吸をしてから応えた。
「あ、ああ・・・。 だ、大丈夫、だ。」
彼の返答を聞いた少年の表情がにわかに明るくなる。
「そうですか、それはよかった。」
そういうと少年は彼に向かって笑顔で手を差し伸べた。
彼は軽く礼を言って少年の手を取り、ゆっくりと起き上がる。
「何方かは存じませんが、この度は恐ろしい体験をさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。」
そう言うと少年は深く頭を下げた。
「い、いやっ、その、そんな謝らなくても、いいよ。」
少年があまりに唐突に、本当に申し訳なさそうに頭を下げたので、彼は慌ててやめさせた。
「ぼくは金森といいます。」
「あ、ああ、えっと、オレはラッセル。」
「ラッセルさん、ですね。 本当に申し訳ございません。」
再び彼は頭を下げる。
「い、いやあ、もういいよ。 金森が悪いワケじゃあないんだし・・・。」
「いえ、あんなのでも一応はぼくのマスターですので、マスターの失態はぼくの失態でもあります。」
「えっ?」
ブロンド髪の彼、ラッセルは黒目黒髪の少年、金森の台詞から普段聞き慣れない単語を聞き、思わず聞き返した。
「マスター、って?」
「あ、ああ。 まだ、説明しておりませんでしたね。」
そういうと金森は遠方を指を指して答える。
「この先、322.34メートルの所でだらしのないアヘ顔でノビている彼女が、ぼくのマスター、つまり創造主です。」
「ああ、そうなんだ、なるほど、そう・・・――っぞうしゅだってぇ!?」
金森があまりに淡々と、さも当然のように答えるので、ラッセルは釣られて納得してしまいそうになって慌てて叫んだ。
「そそ、それは、えっとだ! つまり、その、金森は作られた人!?」
「はい、そうです。 僕はマスター、リベット=G【ギャラクト】=ウィンストンによって作られたお手伝いロボットです。」
ラッセルはその場にまたへたり込みたい衝動に駆られた。
人が人を作ることなど到底できないことだと、ラッセルはずっと思っていたからだ。
呆然と立ち尽くすラッセルに構う様子もなく、金森は言葉を続ける。
「では、僕はマスターの回収に向かいますね。 ラッセルさんもこの場を早く離れてくださいね。」
「あっ? あ、ああ・・・。」
軽く会釈する金森に、ラッセルは生返事を返すことしかできなかった。
~~~~
「んぅ・・・。」
鈍く響く砂利の音で彼女は目を覚ました。
「ふにゅぅぁぁ・・・。」
酷く全身が重く、気だるい。
彼女は大きく欠伸をして、なんとか気だるさを抜く。
「ぬぅぅ・・・?」
彼女は今、自分の置かれている状況が全く分からなかった。
そこでまずは状況を把握しようと、彼女はゆっくりと意識を覚醒させる。
「――っ!?」
全身に意識をいきわたらせた途端、頬の辺りに激痛が走った。
彼女は思わず、全身全霊を込めて叫んだ。
「ったぁあぁあぁあいぃぃーっ!!」
一頻り叫び終えると、彼女は全てを悟った。
自分が今置かれている状況も、意識が戻るまでの出来事も、激痛の理由も。
「もぉぉう!!」
そして、激痛の原因も。
「かなやん! ちょっとはぁ、手加減をぉ、しなさいよぉー!」
彼女は全身をばたつかせて叫んだ。
「開口一番でなにを仰るかと思えば・・・。 手加減しろ、ですか。」
彼女の背中から冷やかで落ち着いた様子の声がした。
「今回の出力は最大時の45.98%ですので、前回よりも手加減を致しましたよ。」
背中の声は淡々と答える。
「前回より0.02%しか、落としてないじゃないのぉ! なんのためのぉ、超高性能AIなのよぉ!」
「前回より0.02%出力を落とせばマスターの指定した衝撃度に収まると、ぼくの超高性能AIは結論をだしましたよ?」
「ウソよぉ、全然落ちてないじゃないのぉ・・・!」
少し泣きそうな声で反論する彼女を、鼻で笑ってから背中の声は答える。
「それは貴女が、僕に記憶されている貴女の最高速度よりも遥かに高速で飛び込んだからですよ、マスター。」
「っ・・・!」
彼女は思わず言葉を詰まらせた。
彼女の反応を予想していたかのように、背中の声は淡々と言葉を続ける。
「僕の計算はあくまで僕に記憶されている最高速度を基にしています。 従って、本来であればしっかりと計算どおりに収まるはずでした。」
「ぬ、ぬぅぅ・・・!」
「しかし、実際には貴女は僕に記憶されている最高速度以上で飛び込んだ。 不思議ですね。」
「ふ、不思議ってぇ、なによぅ!」
彼女の不貞腐れた反応に、声の主はわざとらしく大きな溜め息をつく。
「・・・貴女の身体の殆どは機械、”なにもせずに”最高速度を超えられるはずがありません。」
「――っ!」
急に大人しくなった彼女に、声の主は呆れきった声色で問い掛ける。
「内緒でチューンアップ、しましたね?」
「・・・ハヒ。」
彼女は観念した様子で力なく答えた。
「大方、僕が駆けつけるよりも早く飛びかかろうという魂胆でしょう?」
「・・・セウデス、スミバゼン、モウシマセン。」
「全く、こんな節操なしの短絡的思考の人間が僕のマスターだなんて、情けなさすぎて、涙もでません・・・。」
声の主は一際大きな溜め息をついた。
「あらぁ、かなやんは、元々血も涙もないロボットじゃないのぉ。」
「最長飛距離、もう更新しますか?」
「エンリョシマフ。」
声の主の若干殺意の篭った冷やかな問いかけに、彼女は即答した。
彼女はその後、自宅に着くまでずっと声の主に首根っこを掴まれ、引き摺られたままだった。
END