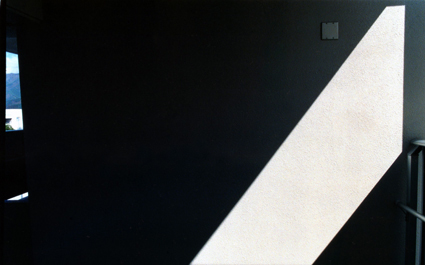土肥 志保美 shihomi DOHI
1978年 長野県生まれ
2008年 東京藝術大学 美術学部 先端芸術表現科 入学
2012年 東京藝術大学 美術学部 先端芸術表現科 卒業
グループ展
2008年 『art path 2008』 東京藝術大学 取手校地 (茨城/取手)
2009年 『art path 2009』 東京藝術大学 取手校地 (茨城/取手)
2010年 『print/action exhibition』CCAAアートプラザ ランプ坂ギャラリー (東京/四谷)
『art path 2010』 東京藝術大学 取手校地 (茨城/取手)
2011年 『parallel circuit』SPC GALLERY(東京/茅場町)
『東川町国際写真フェスティバル インディペンデンス展』 東川町文化ギャラリー (北海道/東川町)
『団地を掘り下げる。SANT展』 IAVオープンスタジオ2011(茨城/取手)
『写真表現演習Ⅲ』 東京藝術大学 大学会館展示室(東京/上野)
『
磯野迪子/土肥志保美 二人展』佐藤時啓研究室 space 8×8(茨城/取手)
2012年 『GEIDAI SENTAN 2012』BankArt Studio NYK (神奈川/横浜)
『PRIVATE PROJECT Ⅺ』Pepper's Gallery(東京/銀座)
個展
2010年 『なにごともなく なにげないとき』佐藤時啓研究室 space 8×8 (茨城/取手)


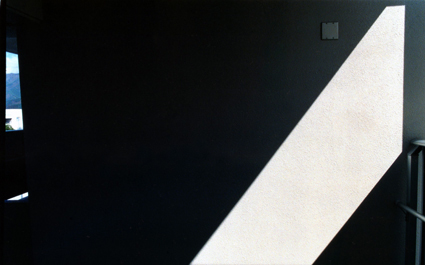





『here_there』2011














『still_move_journey』2011

art path 2010 『a-b-c-d』ミクストメディア

GEIDAI SENTAN 2012 『still_move』ミクストメディア
EMAブックレポート
世界の調律 サウンドスケープとはなにか(1986 平凡社)
R.マリーシェーファー
先端芸術表現科 1108210 土肥 志保美
第4章 町から都市へ
P93 『(教会の)鐘は祭礼、誕生、死、結婚、火事、そして反乱を知らせる音の暦(アクースティック・カレンダー)だった。』
第5章 産業革命
P130 『汽笛は、辺境の町では最も重要な音である。それは外部の世界との接触を告げる唯一のものであった。それは教会の鐘のようにいつごろに聞こえてくるかを予測でき、人々を元気づける、小さな共同体の時計であった。』
先日、JR常磐線に乗り窓の外を眺めていると、電車の汽笛が鳴った。線路沿いで作業をしていた作業員たちが手を止め、一斉に運転士に向かって手を挙げ合図した。私はこの何気なくありふれた光景を目にした時、音と共に毎日暮らす、働く、生きるということが当たり前でささやかかもしれないけれど、とてもかけがえのないものだと感じた。教会の鐘は日本ではあまり馴染みのないものかもしれないけれど、防災無線放送(町内放送)、学校のチャイム、お寺の鐘、火の用心の拍子木など似た役割を果たす音がある。
教会の鐘も汽笛もこのふたつに共通することは時、暦、場などの変化を知らせる音であり、人々の暮らしをさりげなく、しっかりと寄り添って支えている音だと思う。その音の示す意味が直接自分には関係がなく、聞き流し忘れたり、または聞かなかったとしても、音を取り巻く環境の中で暮らしていると、その状況が心の深層に強く残っているはずであるし、何かをきっかけに思い出したり、自分を構成する要素の一部分になっているはずである。朝起きたら天気が良くて気持ちいい、洗濯しよう、布団を干そう、花に水をあげよう、散歩に出かけよう、何を食べようかと音は暮らしの中に意識されていなくても、常に私たちと一緒に暮らしている。そして記憶され、忘れ、また何かをきっかけに思い出したりする。音が記憶を呼び起こす直接の要因になる場合もあるし、何かを体験し見たり触ったり、匂いでその音と状況を思い出したりする。
「あー鳴ってるね、そういえば鳴ってたね、今日は鳴ってなかったかもね」と記憶が曖昧になっていて、日常生活の主役にならないとしても、いないと成立しないベテラン大御所名脇役として音の存在はいつでも必要だと感じる。ただしあまりにもさりげなく、また音は目に見えないということから、日常生活の中で重要ではあるけれど、忘れられがちな水や空気のような存在であるかもしれない。しかしなくなった時にあらためてその存在の大きさを感じて後悔する前に、なかなか気付きにくい名脇役を自ら発見し気付いて、見出す、また調和を損なうことなくもっとアクティブに指し示す(作品化する)、そして鑑賞者に認知してもらうことができるようにしていきたい。
第12章 シンボリズム
P250 マンダラとベル 求心性と遠心性
音には何か危険を喚起する音(遠心性)と何かを引きつける音(求心性)の2種類があると著者は言っているが、どちらにも分け難い音も存在するような気がする。またその時の状況、聞き手の精神状態などでも変わってくるのではないかとも思う。例えば私が今住んでいる茨城(取手)には元気な暴走族が未だ現役で、爆音を轟かせて夜な夜な蛇行運転している。深夜のバイト帰りなんかに遭遇してしまうと「わ、やばい」と明らかに危険を喚起する音として認識する。しかし、警戒しながらも様子を伺っていると、「♪咲いたー、咲いたー、チューリップの花がー♪」とアクセルをふかす音でメロディーを鳴らしていたりして、思わず音程が合っているか聞き入ってしまう時もある。爆音を轟かせ、深夜に大変迷惑な輩ではあるが、「俺は大人なんて信じられない、危険だぜ近づくな、でも面白いところもあってかわいいでしょ」と遠心性とも求心性とも言い難い、または両義的な音のようにも聞こえてくる音(行為)だと思う。
第19章 沈黙
P370 『世界の音のデザインを改良したいと望んだとしても、それは沈黙がわれわれの生活の中で積極的な状態として回復された後に初めて実現されるものであろう。心の内なる雑音をしずめること—これがわれわれの最初の仕事だ。そうすれば、他のすべては時のたつうちに自然にすすんでいくだろう。』
昨年、大学の研究旅行で寺社仏閣を沢山巡った。正直仏像などあまり興味が持てなかったし、2週間も団体行動をしなければならなかったので苦痛だったが、縁側に座って寺の庭をぼーっと(疲れて、ぐったりと、喋る気も失せて)眺めていると、ある瞬間から視界が急に開けて今まで見えなかったものが見えてきて、聞こえなかった音がきこえてきた。「疲れた、しんどい」という雑音(雑念)が消え、自分が透明になって環境と一体になるような感覚を味わった。このような体験(状態)になるにはきっとポジティブな開き直りのような、諦めの状態のほんのちょい先に開けてくる地点があるのではないかと思った。そのような悟りのような、より繊細で見えにくい(見えない)現象をキャッチするには、やはり沈黙が必要なのではないかと思う。現れてくることばと思考の一切を沈黙にして、心と体を外界に浸す(開く)、お茶を飲んだりぼーっとしたり、考えないでしばらく待つと開けてくる地点に辿り着く。そのためには沈黙になりただ自然に待つ、自分をカラッポにして介入してくる余地をつくる。無であり間をつくることが体現する上でも、作品づくりにおいても重要になってくるのではないかと考えている。
教会の鐘の音や汽笛、暴走族の爆音など求心的な音と遠心的な音が日常には存在しているが、どれも結局私にとっては求心的で(集める、呼ぶ、気を引くなど)人の心を引きつける魅力的な音である。私は日常の中でこのような生活音(環境音)に可能性を感じている。今の社会はそれぞれがバラバラで個別の価値観を持っていて、世代を超えて、また身近な人とさえもまとまったり共有しづらくなっている。バーチャルな世界では繋がることはできるのかもしれないけれど、どこかまだ危うくて頼りない。個々がそれぞれ別々な考えをもち、バラバラに生きていたとしても、音の存在はさりげなく、でもしっかりと人と人とを繋げてくれるかもしれないという期待を持っている。
積極的に前に出て音を提示し、リリースする(作品化する)という動的行動、そして一番遠いところで沈黙し、待ち、聞こえてくる音や現象をキャッチするという静的行動を繰り返しながら社会や人と関わり、人と人を繋げていけたらと思う。日常生活を始発点とし、視覚として認識できるイメージ(写真や映像)と音のあいだを探り、自分なりの方法で調和するポイントを見つけて行きたいと思う。そして日常から非日常へ、記録から記憶へ鑑賞者が往来できる作品を展開させたい。そのためにはこれからも右往左往しながらも、面白い音や人に出会って経験と知識を深めて行きたいと思う。
最終更新:2011年12月02日 03:11