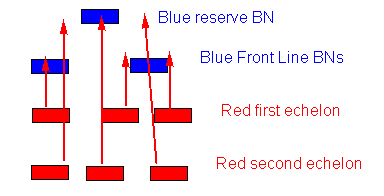攻撃の原則
序
攻撃の目的は敵戦力を壊滅させる、あるいはそれが占める土地を奪取することにある。このことをもう一度読んで暗記し、モニターに刻み込むのだ。側面での交戦に巻き込まれ、何をなすべきかを見失ってしまうというケースがあまりに多すぎるのである。
攻撃は一般的に防御よりも重要かつ強力とみなされている。これはもし一か所にとどまって敵の攻撃を待っていても、敵がこちら側より自分が弱いときに攻撃を仕掛けてこなければ決して勝利はできないからである。攻撃側は生来的にいくつかの利点を得ることになる。
- 攻撃側は攻撃する時間・場所を自分の好きなように選ぶことができる一方、防御側はたとえ待ち構えていなくても攻撃を受け入れなければならない。(ただし降伏・撤退する場合は除く)
- 攻撃側は限定された地域に集中して攻撃を仕掛けられる(そしてそうしなければならない)一方、防御側は全ての場所への攻撃に備えなければならないため、広がって薄くならなけらばならない。
- 攻撃側はどの目標をどの順序で行うかを決定できる一方、防御側は攻撃側がこの後本当は何を仕掛けてくるのか決してわからない。
機動の形態
合衆国軍野戦教範100-5、作戦によると、機動の形態には以下のものがある。
- 包囲:戦力を敵側面を敵主力と遭遇しないように回り込ませること
- これには包囲戦力が敵側面に移動するのに十分なマップのスペースとできれば無防備の地形とが必要である。
- 包囲戦力は正面攻撃を発動するのと同時に敵の側面を攻撃するように動けなければならない。さもなければ敵は双方の戦力を各個撃破できるであろう。
- 包囲戦力は敵がそれを止めるために戦力を転じることができる前に敵側面に到達しなければならない。
- 迂回機動:敵側面へと部隊をこれが常に敵主力と接敵しているように回り込ませること
- 迂回戦力は敵主力の近くに居続けることで敵に圧力をかけることができる。(この点は機動を完了するまでは会敵しない包囲部隊とは違う)
- 迂回部隊が敵側面を接触を保ちながら回り込んでいる際に、それによって敵が部隊を側面へと移動させ正面に残った部隊と側面に移動した戦力の間に間隙が生じることがあるかもしれない。これが起こるかどうかに注意を払い、この間隙につけ込むための予備兵力を用意せよ。
訳者より注:この二つの用語の定義、通常のものとは明らかに異なっており、筆者が何らかの勘違いをしていた可能性が高い。だが、原文を尊重し、そのまま訳すこととした。
- 浸透:敵後方へと気付かれないように移動する
- 通常ユニットを小集団に分けてまとめて、ゆっくりと視線(LOS)を妨げる地形を通って移動させることになる。
- これはこの目的のための特別なユニット、すなわち特殊部隊・パルチザン・偵察部隊などで行うのが成功率を高くできる。
- 突破:敵前線のごく一部に部隊を集結させ、これを圧倒して他の敵前線にいる部隊を無視して深くに移動すること
- これは古典的な電撃戦の戦術である。
- 敵戦線の一部を圧倒するのを援護するため、視界を限定させこれを支援砲火から隔離せよ。低視界のシナリオではこれが自然に起こることになる。あるいはそうでなければ煙幕を用いて突破部隊の側面の部隊の突破部隊への射撃を防ぐことができる。
- 敵戦線の一部を圧倒するのを援護するため、砲兵の間接射撃で突破予定地点への、あるいはからのルートを遮断し、更なる部隊が援軍に来ること、あるいは突破予定地点に既にいる部隊が撤退・遅滞戦闘を行うのを防げ。
- 正面攻撃:広正面で攻撃を行うこと
- これはどこに、どれだけの戦力の敵部隊がいるかわからないときに最も便利なやり方である。
- 前進するにしたがって抵抗の中心と防御があまり堅くない箇所がわかってくるはずだ。防御の堅い箇所からは部隊を撤退させ、進める箇所から前進できるように備えておくべし。
- このやり方は敵に対して圧倒的優勢を得ているときに最も適したやり方である。例:シナリオの構成がそれを行うようになっている時、あるいはほとんどの敵ユニットを壊滅させ崩壊した部隊に対して前進する時など
- 比喩としてはダムに濁流が押し寄せそこにできた割れ目から水が溢れ出す様子を想像すればいいだろう。
これらの機動は地形に対してではなく、敵に対して行わねばならない。勝利判定は獲得した勝利ヘクスとユニットの損傷比の組み合わせで決定されるため、必要な時間で勝利ヘクスの確保のための機動と敵部隊の撃破を目的とした機動のバランスをとる必要がある。しかしながら、もし好都合な地形を確保すべく機動を行えば敵と接触した際に優勢を得ることができる。何種類かの攻撃が様々に組み合わされて用いられる。
どの種類の攻撃を用いるにかかわらず、攻撃の成功のためには全ユニットが同調されて各自の役割を果たす結束した行為としてこれが計画、遂行される必要がある。もし敵がこの同調を崩すことができれば、すなわち攻撃部隊を時間的あるいは空間的に分離することができれば攻撃は失敗するだろう。攻撃側は防御側がこの同調を乱すような作戦をとってくることを防ぐことに注意を払わなければならない。このことは以下によって可能となる
- 敵ユニットを射撃して撃破、あるいは制圧し、敵がこちらを妨害できないようにせよ。
- 奇襲・警戒・欺瞞を以て敵方に躊躇いを生じさせ、どのようにこちら側を妨害すればよいのかわからなくさせよ。
どの種類の攻撃を用いるのかはMETT-T分析によって定まる。すなわち作戦任務、敵の相対的兵力・地形・天候・時刻である。
攻撃を成功させられるかは慎重に自軍部隊を同調させてこれを位置につかせて敵ユニットを撃破する一方で敵の同調を崩して団結した防御をできなくさせられるかにかかっているのだ。
攻撃を計画する
攻撃を成功させる基本は防御側の生来的な利点を取り除いて攻撃側が戦闘を強要できるような簡潔な作戦方針である。シナリオを開始したらまずは作戦方針を立てなければならない。作戦方針とはどのように戦闘を指揮するかの考えあるいは大まかな声明である(詳細な計画ではない)。戦闘開始時に地形は固定されているが通常戦力の選択には柔軟性が残っている。選択する必要のある戦力は何か、どのように地形を横切って目標地点へと到達するか、どのように防御側がこちらを妨害しようとしてくるかを考慮しなければならない。以下例:
- 開平地と長距離射程の利点を生かして北側を戦車部隊で攻撃し、中央と南は対戦車砲と歩兵の反斜面陣地で防御する。
- 北側を対戦車砲と砲兵で開平地をカバーして守り、中央と南では林に覆われた丘陵地帯を通って浸透する。
どちらを選ぶかは相手に対するこちらの部隊の相対的利点によるものである。詳細については以下で議論する。
通常、攻撃を完全に成功させるためにはいくつかの任務を達成しなければならない。これは通常いくつかの地域で勝利ヘクスを確保し、場合によってはゲーム開始時からこちらの保有する勝利ヘクスを守備してこちらの部隊の損害を抑えつつ敵ユニットを壊滅させるということを意味する。計画を策定さいはこれらすべてを達成できるような手段を包括しなければならない。これをなす順序と時間枠はどうなるのか?これらの任務に割り当てる兵力はどれくらいにするのか?航空機の出撃回数と砲兵の弾薬を一つの目標を攻撃するのに使い果たしてしまった場合、作戦継続のためには戦力が弱くなりすぎてしまうはずだ。これは戦闘の最後まで連続的な作戦を進行できないマズい作戦計画である。最初の目標を奪取した後に運動量を失ってしまうのを避けるためには、最終的な勝利を目指して計画を立てなければならない。これはつまり、最初の任務を達成した後何をするかについての計画を立てておかなくてはならないということだ:
- 相手のバランスを崩し、敵が組織的な防御ができなくなった場合は情け容赦ない攻撃と戦果拡張に転換できる。
- もし十分な勝利条件に到達できたら急速防御に転じ、相手にこちらへの攻撃を強制できる。
敵後方深くにいる予備逆襲戦力と敵火力支援ユニット(FOユニットを含む)は攻撃戦力にとって大きな脅威となる。なぜなら敵前線への攻撃では最初これらに影響を与えることができないからだ。こちら側がこれらを難なく即座に一か所に釘付けにすることはできないため、敵はこれらの部隊に関して行動の自由を保持している。これらの部隊がこちらに対して使用されることを予想しなければならない。偵察部隊を指揮してこれらの部隊を発見し、間接射撃や戦力機動によって無力化しなければならない。浸透部隊・空挺部隊がこの役割を果たせたといえる戦例が存在する。
究極的には防御側を打ち負かさなくてはならない。そうするためには敵戦力とその防御計画はどのようなものかを認識し、そしてそれに打ち勝つ計画を立てなければならないのだ。
- 防御側の生来的な利点とは何かを参照し、このシナリオで敵が優位に立てるのはどちらかを推測せよ。
- 防御の形態を参照し、勝利のメカニズムがどのようなものかを推測せよ。
- 戦闘の最初から最後まで偵察部隊に備え、これらの推測を確認、あるいは否定せよ。
攻撃の基礎
可能な限り敵戦力を戦場全体で同時に攻撃することで、敵が攻撃下にない地域から部隊を危機にある地域へと移動させることを防ぎ、相手に同時に一つ以上の方面で戦うことを強い、相手の行動の自由を減らさなくてはならない。しかし戦力を薄く広げ過ぎて各個撃破を招くのを避けることとのバランスを必ず取らなくてはならない。砲兵は広範囲にわたって敵を釘付けにする一つの方法である。高速移動する射撃可能な偵察ユニット・斥候の浸透も敵の注意を重要な戦闘から後方に逸らせるのも一つの方法だ。
自軍の運動量の保持を追及し、いかなる時でもこちら側が戦闘のペースを決定しなければならない。いつ、どこで、どれだけの戦力で戦うのかをこちら側で決定し、敵にこれらの要素を決定させないようにしなくてはならない。予備そして/あるいは増援の投入が運動量(流れ)をこちら側に決定的に変えるほんの一瞬に特に気を付けよ。
以下の方法で行動の自由を保持せよ:
- 複数の、互いに支援し合う攻撃軸で攻撃せよ。一つの主作戦しかない場合でも、主攻として開始されるはずの攻撃から作戦を成功しつつある攻撃の方に変更する準備をしておかねばならない。攻撃軸は互いを支援できるほどには近く、一方への攻撃がもう一方を拘束してしまうほどには近くないようにしなければならない。これは一方の軸にいるユニットがもう一方の軸にいるユニットに援護射撃を行える位置まで1・2ターンで移動できなければならないということだ。
- 偵察と援護を使ってこちらを釘付けにできる敵部隊に突っ込むことは避けよ。
- 奇襲を成功させよ:
- 最も明らかなルートをとったり一番良い地形を通って攻撃を仕掛けたりを常にはやるべきでない。これらは一番防御がなされている可能性が最も高いのだ。
- 欺瞞を行え。攻撃あるいはフェイントを用いて、敵を打ち負かすのではなく、これを引きずり出して自らの位置を暴露させ、主攻勢を行う箇所の敵部隊に躊躇いを生じさせよ。
また運動量を保つには以下の方法を用いよ:
- 予備の運用:予備と増援の項参照。
- 戦力の梯形編成:ソヴィエトの標準的な戦術技術である。戦力は梯形陣で運用される。それぞれの梯形には敵深くに指定目標がある。梯形は運用する部隊と関係がある。つまり連隊はその麾下にある大隊のそれぞれを梯形に分ける一方、連隊はそれ自体師団の梯形となっているということだ。例えば、第一梯形を構成する1個大隊の目標は敵第1戦線の大隊を蹂躙、連隊第二梯形の大隊は第一梯形を追い越して防御側の予備大隊を攻撃するという風である。これは戦闘力をごっちゃになることなく集結させる手段といえる。梯形は第1梯形がその任務を達成するのにかかる時間が次の梯形がその後ろに追いつくのにかかる時間となるような距離をとる。この方式では第1・第2梯形が集結しない限り密集した目標にはならなくなる。ただ、もしそうした場合でも2つの梯形はともに友軍の戦線の近くあるいは直上にあるため、友軍に死傷者を出させる危険を冒さなければこれらは火力支援や逆襲で釘付けにはされえないのである。またこれによって第一梯形がその任務を達成するだけの力しか持っていなかった場合に攻撃の運動量を保つこともできる。第一梯形がそうなっていた際は燃え尽きて更なる攻勢作戦ができなくなっている。第一梯形が進撃を続行できなくなった丁度その時に、第二梯形が進撃を開始して第一梯形を追い越す。ゆえに防御側は弱体化した攻撃側に逆襲を行う機会を決して得られないのである。[注:第2梯形を砲兵・ミサイル・散布型地雷・航空機の火力で阻止してその戦闘投入を遅滞し、合衆国軍の主陣地部隊に第一梯形を各個撃破する機会を開くのは80年代に開発された合衆国軍のエアランドバトルドクトリンの最終目標であった。]第二梯形にも各自の作戦任務があるため、これを予備と考えるべきではない。各梯形は予備を持つことがありうるが、それは全部隊の3分の1である通常の予備とは異なり部隊全体の9分の1程度のものである。
- 随伴支援:合衆国軍のドクトリンにおける標準的な戦術である。予備として随伴するユニットはその前を行くユニットの進撃軸に沿って移動することとなる。必要な際は先行するユニットをその進撃を継続させる形で援護するいくつかの任務を遂行することになる。随伴支援が行い得る任務の例には以下のようなものがある。
- 敵抵抗を拭い去り捕虜を捕獲する
- ダメージを受けた車両を戦場から非難させる
- 先行するユニットの後方地域の警戒
梯形の例
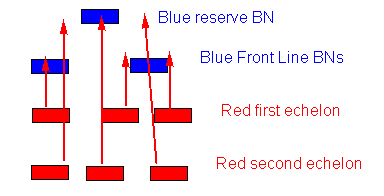
この例では赤の部隊2個大隊を梯形にして伝統的な2アップ1ダウン配置の青の連隊に攻撃を行っている
偵察部隊を用いよ。攻撃が成功する時にはほとんどがその前に偵察を成功させているのだ。
勝利する指揮官は戦闘を推し進めるものである。攻撃の形態とテンポに変化をつける必要はあるだろうが、運動量は一定にしているのである。敵味方双方の情勢を予想し、心に描く能力は攻撃において非常に重要だ。決断することもまたカギとなる。これは何をするかのみならず何時かを知ることも含んでいる。
攻撃は(警戒・奇襲・欺瞞・対偵察戦闘を以て)秘密裏のままで開始され、敵が何らかの事前情報を得た上で反応してくることを防がなくてはいけない。そして実際の攻撃は暴力的かつ急速で、敵にショックを与えて自軍部隊が防御線を撃破するまで敵を立ち直らせないものでなくてはならない。
障害物を避け(これについてはおそらく観測と射撃の項を見ればよいだろう)、警戒を保ちながら、機動と反撃射を用いて敵砲火への露出を最小限にしなければならない。
作戦目標をめぐっての戦いでは必ず組織性を保たなくてはならない。組織性がなくなれば自軍は互いに同調できず、相互支援を行うこともできなくなり各個撃破を招くであろう。しかし、ユニットを散り散りにしないようにして組織性を保つ(たとえそれが抑圧の上がったユニットの立て直しを行うために待機しているだけだったとしても)のと使用可能なユニットで攻撃を強行して運動量を保持する(可能な時は抑圧の上がったユニットも追随させるが)ことの間には二律背反の関係がある。もしあまりに積極的に攻撃を強行すると、気付いたころには戦列が伸びきり、各個撃破に脆弱となっているであろう。まさにAIがなっているそれである。対して、集結した状態を保てるだけの速度でゆっくり移動した場合(だいたいはよいことなのだが)、敵に回復と反撃の猶予を与えてしまう。このバランスを見出すためのカギは良い偵察である。どこに敵がいるのかわかっていれば自軍が伸びきり、分散してしまう前にどのように戦力が展開されうるのかを知ることができるのである。発見した敵ユニットが少なければ少ないほど、死の咢に飛び込むのを防ぐためより積極的にならないようにしなければならないのだ。
攻撃は作戦目標への強力にして暴力的な強襲から開始される。状況が明らかになった際に主努力を変更するため機動部隊が準備される。射撃・機動・戦闘支援の同調は(攻撃の前に自軍に弾薬補給車で再補給を行え、弾薬を使い果たして困るであろう)攻撃地点に優勢な戦闘力を得るうえで非常に大切だ。砲兵の準備砲撃と制圧射撃、(従って敵戦力の孤立)、戦闘力の集中、そして敵の蹂躙のすべてが組み合わされて防衛部隊を撃破できるのだ。
攻撃開始時から敵に使用可能な全火力を集中させよ。敵部隊の近くでユニットを攻撃する場合、敵抵抗を暴力的な火力集中と急速な進撃で圧倒しなければならない。攻撃のこの段階における速度は損害を減らし、攻撃停止を防ぐためのカギなのである。
攻撃の運動量を保つためには攻撃部隊の戦力交代を行って攻撃に新しいユニットを投入する必要があるだろう。このような戦力交代は部隊が戦闘の山場の後の戦果拡張、追撃に入った時によく見られるものであるが、攻撃それ自体の間にももし以前投入したユニットがひどく苦戦し、その作戦目標に到達できない場合には必要となってくるであろう。攻撃部隊の戦力交代は適切な戦力交代として行われるだろうが、理想的には攻撃のテンポに有意の休止が発生しないように行われる。
攻撃の運動量を敵が対処できないテンポで保ちながらカギとなる時間と場所に戦闘力を継続的に集中する能力は重要である。予想(シナリオを始める前の良い作戦計画を通しての)と調整(戦闘中の偵察に基づいた)は攻撃作戦の成功のカギとなるものである。
最後に、勝ったと思った時には警戒を保ってこれを確実にせよ。つまり自軍の周りに警戒線を張ってこれが奇襲されることを防ぎ、戦場を掃討して逆襲のために集結する敵戦力がないことを確実にするのだ。この後半の作戦行動は装甲車と歩兵からなる小集団を形成して文字通り横一列になって戦場を横断することからなるだろう。これらの部隊が敵ユニットに出くわしたらこれを撃破する際には互いに支援し合い、必要ならば援護射撃を行ってより多くのユニットが投入できるまでこれを釘付けにせよ。だが、これについては慎重にならなければならない。もし濃霧だったり夜間だったりの場合は敵ユニットに遭遇・突然の近接強襲で撃破される形で多くの車両を失うことになるであろう。この場合、急速防御に移行したほうがよいであろう。
良い攻撃計画の特徴
- 来るべき作戦への転移を容易にせよ:これは、任務を一つ達成したら、すぐさま次に移行できる状況にあるか?あるいは機動する余白のない窮屈な地形にひと固まりになっているのか?ということである。
- ユニットの急速な集中と分散を可能にせよ。一点への集中を開始した場合は自分の意図を敵に暗示することになる。自軍部隊が数個の作戦目標へと移動できるようにやや分散するように移動すれば、防御側を考えさせ、そのバランスを崩し続けることができるのだ。そうしたら急速に集中し、敵が反応できる前にある地域で防御側を圧倒せよ。目標を達成したらすぐさま再び分散して敵砲兵の集中射撃を避け、次にこちらが何をするのかを再び考えさせるようにさせよ。
- 攻撃のテンポを保ち、防御側が回復・反撃をできないようにせよ。戦果拡張のため新しい部隊を投入し、他の部隊を休ませよ。何ターンも射撃し射撃されたユニットは一度に適用される(そして命中率のために準備する)射撃数が少なくなり、おそらくは自分の抑圧値を下げられなくなってくる。どちらのユニットに射撃させるのかをくるくる変えてゆくことにより、これらの部隊がその全力を回復することが可能になる。全ユニットを決定的な交戦状態にしてはいけない。なぜならそうするとこれらの部隊が撤退・次の場所に移るまで攻撃を続行することができないためだ。もちろん戦闘の頂点に達したときは全てを投入し自分に有利になるように天秤を傾ける必要がある。
- 戦力を保護せよ。キャンペーンでは乗員を生き残らせて経験値を得ることが来るべき戦闘での勝利に非常に重要になってくる。これは単独の戦闘でも重要である。なぜなら決定的勝利を得るためには勝利ポイント比10:1が必要になるためだ。こちらがユニットを失うということはこれの埋め合わせのため敵ユニット数個を必ず撃破しなければならないということなのだ。
- 戦闘作戦をその継続時間いっぱいまで持続させよ。これは主にマズいタイミングで弾薬を使い果たしてしまわないことを意味している。ただ持っていればいいというものでもなく、限りある弾薬は本当に必要な射撃のために保存される必要があるだろう。例えば戦争初期のドイツ軍自走砲の保有弾薬は約10発である。これらはただあらゆる敵ユニットを撃つという用途に用いられるべきではない。あるいは、もし使用可能な弾薬補給車がある時は作戦のペースを落とすか再補給ができるようユニットを順番に後退させてゆく必要が出てくるであろう。
- 防御側の兵力とその主となる勝利のメカニズムを知らなければならない。そしてそれを打ち負かせる手段を持たなければならない。
最終更新:2014年05月14日 13:16