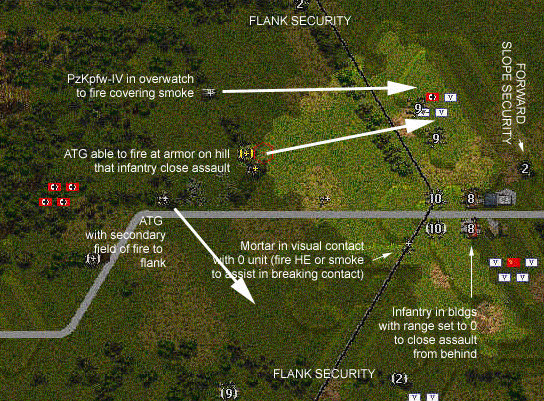防御の原則
序
防御は一般に戦闘の攻勢形態よりも弱く、より決定的でないとみなされる。これは防御が、そのまさに本質なのだが、一般に先手というよりむしろ後手に回るものだからだ。しかしながら、防御側には攻撃側に対して天然の優勢がある。
- 防御側は巧みな後退と機動により攻撃の時間を選ぶことができる可能性がある。
- 防御側はどこを防御地点に選ぶかによって攻撃の行われる地点を選ぶことができる可能性がある。
- 防御側は戦闘乗数としてはたらく好ましい地形的特徴のみならず防御施設や障害物を利用することができる。
- 防御側はほとんどのシナリオの開始時においてデフォルトで勝者である。つまり、防御側は勝利している状況を制御し、攻撃側が何も(あるいは何も実効性のあることを)しようとしなければ防御側が勝利するということである。
防御の形態
防御ドクトリンによれば、防御には戦術レベルで二つの大まかな形態がある。
- 地域防御:この形態においては強力な固定陣地あるいは連動した射撃を行える火点群と障害に拠ることになる。敵はそれぞれの陣地に連続して攻撃を仕掛けるかそれを通過するのに時間を浪費するかをしなければならず、消耗してゆくこととなる。これは縦深が浅く、地形を死守しなければならない場合に一番良いやり方だ。自軍ユニットのほとんどは防御陣地にあり、少数が予備とされる。この利点はそれが割れない硬いクルミのようになりうるという点にある。いくつかの陣地を失っても、願わくば敵は損耗し、多くの時間を浪費して勝利することができなくなるだろう。While this may be true, it is important to remember that hope is not a course of action. 防御側を十分に損耗させられることを確実にすべく注意深くこれを計画しなければならない。敵戦力はどれぐらいの兵力になり得、こちらの防御を打ち破るためにはどれだけの兵力と時間が必要かを推測せよ。この防御形態の弱点はもし敵が防御陣地を突破した場合、敵は残存の陣地に固定された部隊の横を通過していってしまい、これを止めるものはほとんどないということであり、加えてこれが非常に受動的な戦いのやり方だということである。ただそこに座して敵に自陣地を一つずつ減らさせようとさせるだけになるのだ。
- 機動防御:この形態においては軽機動警戒部隊と敵の進撃を妨害する障害(時間が許せば)に拠って、敵を展開させ、しかる後に撤退させることになる。一度敵が遅滞・妨害されれば自軍部隊の大半を以て逆襲を開始するのである。この防御形態の利点は逆襲を開始する際、いつ、どこで主導権を確保するかをこちらが選べることだ。攻撃側の主力を撃破してしまえばもうそこからは攻勢に転移して続けて敵の完全な掃討を行うことができるのである。この弱点はこれが単一の決定的勝利のメカニズムに頼っているということである。主導権をとって決定的戦闘を行うのはよいことなのだが、一つのことに全てをかけるのはあり得ないことだろう。
どちらの形態あるいはその組み合わせを選ぶにせよ、防御側は攻撃側の生来の利点に打ち勝つような勝利のメカニズムを計画しなければならない。
- 地域防御の勝利のメカニズムは敵の損耗である
- 機動防御の勝利のメカニズムは決定的な逆襲である
どの勝利のメカニズムを選ぶかは下で議論するMETT-T要素に依存する。
これらの防御形態双方で警戒地帯と主防御地帯を用いることとなる。これらについては下で説明する。
どちらの形態でも妨害攻撃を行うことになるだろう。これは防御陣地から出て開始され、敵に脅威を与えることでこれを無視できないようにし、これに対処しなければならなくさせそれゆえに敵の注意とリソースを敵主攻撃から分散させる攻撃である。阻止攻撃は実際のところ敵ユニットの撃破を意図したものであったり、単に敵に反応させて相手が気付いたときには妨害攻撃部隊は実際にほとんどあるいはまったく戦闘を行わずに撤退を完了させていることで時間を無駄にさせることを意図したものであったりする。
どの防御形態を使用するかは下で詳細について述べるMETT-T要素と早期に主導権をつかもうとする必要があるかどうかに大きく決定される。
さらに、防御は時間と目的、使用可能なリソースによって急速防御と計画防御に細分化される。
- 急速防御:一般的に急速防御は攻撃の前の小休止時に部隊を一時的に守るため用いられる。攻撃中・移動中の部隊が状況がそのまま攻撃・移動を続けるには好ましくないと判断するかもしれない。敵があまりに強力過ぎたり、地形や天候が好ましくなかったり、他の友軍部隊が持ちこたえられなくなったり…等のことがあるかもしれない。このような場合には以下を開始せよ。
- 自軍ユニットが連動して射撃できるような好ましい射撃位置を見つけ、自軍部隊を位置につけて地形の利を得よ。
- 複数の陣地を用意し、ユニットが移動して欺瞞によって警戒を行えるようにして敵がこちらの部隊は2つの陣地に一つのユニットがいるのか二つのユニットがいるのかわからないようにせよ。
- 後方に横向きの移動ルートを決め、部隊をあまり激しい攻撃を行っっていない地区から攻撃を激しく行っている地区へ戦力を移動できるようにせよ
- 予備のためによい陣地を決定せよ(主予備一つでも小予備数個でも接近ルートとなると思われる街路の付近に布陣せよ)
- 障害物を敷設せよ(SPWAWでゲーム中にできるのは橋を落とすのと工兵に地雷を敷設することだけである)
- 計画防御:一般的に計画防御はこちらが敵を攻撃では打ち負かせないことがわかっているが、なおも決定的会戦を行いこれを撃破したい時に用いられる。計画防御には急速防御にあるものすべてがあるが全てより多くがあるわけではない。実際のところ防御は急速防御から始まり、ゆっくりと最終的には計画防御になるといえるだろう。
- 陣地より奥にいる警戒部隊に対偵察戦闘を行わせ主力を守り警戒を行え
- さらなる防御施設や障害を通例は層状・帯状に構築し、防御の縦深を確保せよ。
防御の基礎
攻撃側はこちらよりも兵力が大きいと考えなくてはならない。もしそうでない場合は攻撃を以て敵を撃破できるのだ。こちらの防御は自軍が全ユニット同調して互いに支援し合い戦闘乗数の利点をいかせるかどうかにかかっている。もし攻撃側がこちらの防衛の一部に攻撃を集中でき、なおかつ残りの自軍防衛が攻撃を受けている箇所の援護をできないようにさせられたとき、攻撃側が勝つことになる。同様に、攻撃側はそのユニットを同期させ、これを互いに支援し合いなおかつこちらが回復・反応できる時間的空白を常に生まないように攻撃を行おうとするであろう。もし攻撃側のユニットの同調を乱すことができたり、空間的・時間的にこれを分割することができればこちらが攻撃側を各個撃破して勝利できるであろう。防衛計画は以下のことを可能にしなけらばならない:
- 団結し、連動し、相互に支援し合う防御
- 攻撃してくるユニットをバラバラにし、こちらが回復、反応できるようにする手段
敵を警戒地帯でこちらの強力な部隊の射程範囲に引きずり込んで叩くことで防御を行うことを選ぶか、代わりに主防御地帯で敵と決定的戦闘を戦うことを選ぶかをするであろう。特定の地域を保持する必要がない場合は敵を自軍の防御深くに引きずり込んでその側面・後方を撃つというのもありだろう。妨害攻撃で敵の機先を制することを選択することも、もし状況がそのような戦術を行うのに好ましい場合はありうるであろう。
防御でも攻撃と同様奇襲を成し遂げなければならない。欺瞞と対偵察がこれをなすために一番に重要な手段となってくる。最も好ましい高地頂上は先制して敵の間接射撃の目標になる可能性があるのでそこではなく、それよりはよくないが適当な地形で防衛することを考えることになるだろう。
トップに戻る
防御を計画する
「全ての地点を防御するものはどこも防御できない」というのは自明の理である。全ての敵接近路に敵をそれぞれ単独で撃破するのに十分なユニットを置けるだけの兵力があるのならば、敵兵力の数倍の兵力を持っていることになるだろうし防御などしてはいないのである。優先順位を決めなくてはならない。最も危険で最も可能性の高い敵接近路を判断せよ。全ての敵接近路に警戒部隊を置け。最も可能性の高い敵接近路に敵を打ち負かすため自軍兵力の大部分を置き、防御を支援するための予備を最も可能性の高く最も危険な敵接近路に置け。
防御計画の基本となるものは敵の主攻・支攻の察知・牽制・撃破である。利用可能なリソースすべてを駆使して敵の数的有利を相殺し、危険な脅威を特定し、攻撃部隊の脆弱な箇所に戦闘力を集中せよ。特に、間接的な接近路と長距離射撃・浸透・空挺降下・航空攻撃による自軍後方への戦闘力展開の能力を予想せよ。
トップに戻る
防御陣地
敵がたやすく回避できる陣地は敵がこれに攻撃するよう誘導されえない限り防御の上での価値はほとんどない。(これは敵を遅滞する役に立つことになる)
連動:
- 各陣地は連動しなければならない。つまり複数の陣地から複数のユニットが同じ目標を射撃できるようにしなければならない。
- このやり方では攻撃側が一つの陣地に指向した場合も防御側は他の陣地から敵側面への射撃を行うことができる
- 加えて、もしある陣地が陥落した場合も失われた陣地の射撃範囲だった地域は他の防御陣地の射撃の射程範囲内に収められるため防御に突破口が生じることはなくなる。
反斜面陣地:
- この作戦テクニックは自軍ユニットを高地裏の斜面に配置するものである。これらの部隊は攻撃側のユニットからは見えない位置におり、攻撃側の部隊が反斜面陣地前の高地の頂上に立つまでこれらは発見も攻撃もされない。それゆえ攻撃側は長距離射撃(直接射撃でも間接射撃でも)を行うことができない。敵は離れて陣地を射撃することはできないが、代わりに近距離(少なくともライフルグレネード・対戦車砲・対戦車ロケットランチャーのような歩兵携行対戦車兵器が使えるだけの距離。だが近接強襲が使える1ヘクス距離(隣接)が理想的)での戦闘を行わねばならない。敵ユニットは防御側の複数のユニットから近距離ゆえに貫通力と精確性の増した突然かつ不意の攻撃を受けることとなるのである。
- 応用として防御側は手近の都合のよいあらゆるもの、すなわち建物・森林の後ろ、谷の中、火災が発生しているヘクスの後ろ等に隠れることも可能である。
- この防御テクニックは突然の攻撃に依存しているため、奇襲が重要になってくる。これは翼部に警戒ユニットを配置し、敵が高地(あるいはこちらがその陰に隠れているあらゆるもの)を大きく迂回して接近し効果的に防御を行うために必要な近距離から離れないようにすることで達成できるであろう。
- この防御テクニックの弱点は攻撃側がこちらのユニットに馬乗りになることを許してしまうことである。もし攻撃してきたユニットを撃破するあるいは抑圧値を重度に上げることに失敗した場合、こちらがその場に釘付けにされ、決定的会戦を挑まれて各個撃破されることとなるだろう。
- この防御テクニックはユニットを少し後ろ(理想的には後方に隣接した高地の前斜面)にただし陣地正面の高地(あるいはその背後に隠れているあらゆるもの)の陰には隠れるようにおくことでさらに強化できる。これらのユニットは監視部隊としてはたらくことができる。これらのユニットはまた高地を越えてきた攻撃側ユニットと交戦することができるが、釘付けにされない程度には十分に離れていられる。これらの部隊は援護射撃を行って反斜面陣地の部隊が後退するのを可能にすることができる。加えて、もし攻撃側が高地を回り込んできた場合反斜面陣地の部隊を補完して攻撃側をこれら2部隊の連携で十字砲火の中に捕らえることができるのである。
- これはWW2のドイツ軍の防御に好まれたテクニックである。
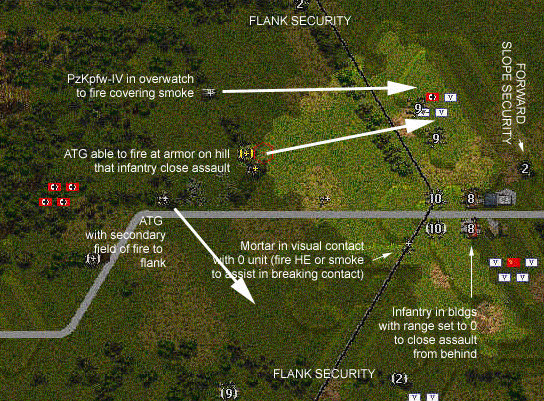
正斜面陣地:
- これは反斜面陣地の逆である。こちらは高地の頂上に布陣し、敵が開平地をこちら目がけて進撃してくるのを長距離で射撃するのである。
- これはこちらが敵に対して砲撃における優勢を得ている時に最もうまく働く
- これは煙幕で隠蔽されることと間接射撃で制圧されることに対して非常に脆弱である。
全方位防御:敵が思わぬ方向から現れたり防御を突破して後方から陣地を攻撃してきたり、側面攻撃をかけてきたり、部隊を浸透させて来たり等のことがあるかもしれない。その場合こちらの陣地はあらゆる方向からの攻撃に対処できるように準備されているか安全な(例:敵の視線が通っていない)撤退ルートを確保しているか必ずしていなければならない。防御地域の端部全周に警戒部隊を配置し、その深部においても防御陣地を転換・再指向するのに必要な時間を稼げるようにしなければならない。
防御施設:防御施設の項を参照せよ。
障害:障害の項を参照せよ。
防御に適した種類の地形についての詳細についてはSPWAWマニュアルの41ページ「新しい地形の種類」と67ページ「地形が移動と戦闘にもたらす影響」を参照せよ。特に、荒地地形にいる歩兵は車両では排除することがほとんど不可能であり、歩兵(ピンチの際には降車した車両乗員)が必要となる。彼らは速やかにこれを行うことができるのである。
車両は荒地や石造建築物のヘクスではハルダウンが可能である。また「in cover」状態、射撃しているユニットより高い位置にいる、塹壕のヘクスにいる。正面から射撃されている場合もハルダウンができる。詳しくはSPWAWマニュアルの66ページを参照せよ。
警戒地帯
警戒地帯とはこちら側の固定したユニットが進撃してくる敵ユニットに対して偵察・戦闘を行う地域のことである。
- 偵察はこのガイドの他のところでも大きく取り扱われている。防御における偵察の目的は自軍兵力を移動させてゲーム開始時の配置(攻撃側の行動を予想して形成したもの)からより好ましい部隊配置(攻撃側の実際の行動に基づいたもの)へと修正できるようにすることである。あまりに簡単に配置の転換を行うのは注意せよ。敵の欺瞞作戦に引っかかる可能性があるからだ。
- 敵ユニットを攻撃するにあたっては以下を目的とせよ:
- 敵部隊が抑圧を受けずに前進し、統制を保ったままこちらの主力部隊へと攻撃を加えることを防げ。これによってこちらの主目的(こちらの勝利のメカニズム)を打ち負かす能力を削り取るのだ。
- 敵部隊がこちらの防御配置の正確な情報を得ることを防げ。対偵察戦闘の項を参照せよ。
- 警戒地帯にいるこちらのユニットが決定的戦闘を挑まれ各個撃破されることを許すことを避けよ。
主戦闘地帯
主防御地帯はこちらの勝利メカニズムを用いててきを打ち負かすことを意図する地域である。
これは可能な限りの縦深をとって防御側ユニットの機動を可能にしなければならない。
これは優先順位付けを受けたやり方で全ての可能性のある接近路を防御していなければならない。
注:正面幅と縦深についての全詳細はドイツ軍とソヴィエト軍のドクトリンの項を参照せよ。一つの部隊はその2段階下の単位で構築された警戒地帯を持つ。連隊が防御を行う際には1500m~2500m(25~45ヘクス)の縦深を持つことになる。その警戒地帯は中隊数個が担当し、主戦闘地帯の縦深の1/3(約10ヘクス)の縦深を持つ。SPWAWのマップのほとんど、特にキャンペーンジェネレーターで作成されたランダムマップには縦深の限界があるため、これらについて歴史的に正しい幅の縦深をとることが不可能な場合もあるだろう。だが、主戦闘地域前面における警戒の原則はたとえ警戒部隊が狙撃兵と偵察班の前哨線一重で全部になることを余儀なくされたとしてもなお達成することができるのである。
最終更新:2014年07月07日 02:32