基本情報
青森市は、青森県の県庁所在地で、青森県のほぼ中央に位置しています。


人口
約26万人
青森県の中で1位
青森県の中で1位
面積
825km²
青森県の中でむつ市に次ぐ2番目の大きさ
青森県の中でむつ市に次ぐ2番目の大きさ
気候
気候は夏が短く、冬が長く、涼しい、たくさん雪が降る
青森市の市章
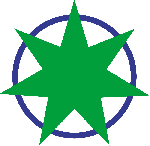
市を表すシンボルマークのことを「市章」といいます。
青森市の市章は、青森市の頭文字「青」をモチーフにデザインされています。
円は「青」の字の月を、星の七つの突角は「青」の字の月を除いた部分を表していて、北斗七星をイメージしています。
青森市の木・花・鳥・昆虫
市の木「アオモリトドマツ」
アオモリの名が木の名前として採用されているのは大変珍しく、市を象徴するのにふさわしい、四季を通じて美しい常緑樹です。
市の花「ハマナス」
多くの歌や詩に詠われるなど、花が大変美しく、可憐で匂いもよく、赤い実がさらに美しさを醸し出しています。
市の鳥「ふくろう」
世界のいろいろな国で幸せを呼ぶ鳥(ラッキーバード)として親しまれています。浪岡地区のりんご園を中心に生息し、大切に守られている貴重な鳥です。
市の昆虫「ホタル」
豊かな自然の象徴であり、昔から人々とに親しまれています。細越地区や吉野田地区などに生息くし、大切に守られている貴重な昆虫です。
青森市のキャラクター
ねぶたん

ハネトン

あぷたん

ほたてん
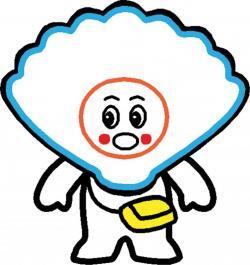
セイラ
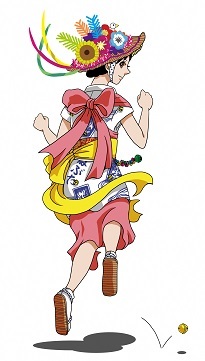
もっぷるちゃん

ばさらくん
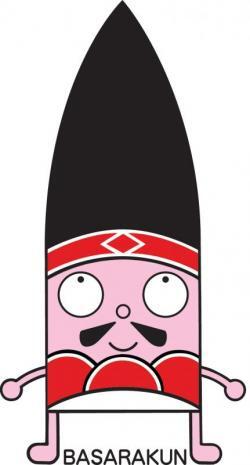
ナマポン
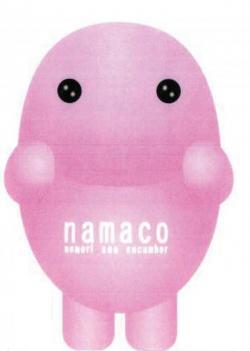
歴史
室町時代、南部の浪岡地方には北畠氏の子孫が移り住み、浪岡城を拠点としてこの地に勢力を奮いました。
その後、羽州街道の宿場町として栄え、多くの人や物資が行き交ったのです。
一方で、市の中央から北部は江戸時代初期まで寒村だったものの、弘前藩二代藩主・津軽信枚によりこの地に港が造営されました。
当時は漁師たちが青森と呼ぶ小さな丘があったため、藩は青森村と命名。
あわせて、土地の無償提供や免税など移住奨励策を積極的に実施したのです。
結果として各地から商人が集まり、地域を代表する商港にまで成長しました。
それに伴い、青森市全域が徐々に活性化していきます。
その後、羽州街道の宿場町として栄え、多くの人や物資が行き交ったのです。
一方で、市の中央から北部は江戸時代初期まで寒村だったものの、弘前藩二代藩主・津軽信枚によりこの地に港が造営されました。
当時は漁師たちが青森と呼ぶ小さな丘があったため、藩は青森村と命名。
あわせて、土地の無償提供や免税など移住奨励策を積極的に実施したのです。
結果として各地から商人が集まり、地域を代表する商港にまで成長しました。
それに伴い、青森市全域が徐々に活性化していきます。
日本一
1位 おいしい水
1位 昭和大仏(青銅大日如来像)
1位 ねぶた祭
1位 酸ケ湯温泉
1位 カシス(黒房すぐり)
1位 昭和大仏(青銅大日如来像)
1位 ねぶた祭
1位 酸ケ湯温泉
1位 カシス(黒房すぐり)
農業・水産業
農業
青森市の気候は夏が短く、冬が長いのが特徴。そのため、一年を通して比較的涼しい生育環境のもと、稲作を行う農家が多い他、トマトやピーマンなどの野菜は国の産地指定を受けるほど生産が盛んです。また、果物の産地としても広く知られており、特にりんごは、浪岡地区での生産が多く、県内で出荷量順に見ても、高い水準に位置しています。市は約30万人の消費者を抱える産地という利点を活かすため、地産地消への取り組みも推進。市内には農家から直送された新鮮な野菜などを手に入れられる、農産物の直売所がたくさん存在しているのも特徴です。
水産業
水産業においては、全国でも有数のホタテガイの漁場である陸奥湾がよく知られています。陸奥湾では、ホタテガイ、カレイ、イワシ、コウナゴ、ヒラメ、タラなどが生息・来遊し、かつては、これらを対象に小型定置網や巻き網、小型機船底引き網などの漁業を行っていました。加えて、1970年(昭和45年)頃からはホタテガイの養殖技術が確立。その後の青森市の重要な産業のひとつとなりました。ホタテガイの他には、青森市水産振興センターによる、ナマコ種苗の生産も有名です。1994年度(平成6年)から青森市の海域に放流され、ナマコの種苗を安定的に生産・供給するための、増殖の研究や試験が進められています。
工業・産業
青森市は県庁所在地として、行政、金融、各種サービスが充実している他、大学や病院などの生活基盤インフラが整備されている中核都市です。第二次産業と呼ばれるような「ものづくり」産業よりも、卸売業、小売業、金融業、サービス業をはじめとする第三次産業の割合が比較的高いのが特徴となっています。
青森市の工業は軽工業を主とし、南部工業団地や西部工業団地などを中心にモノづくりが行われています。特に、豊富に取れる農産物や海産物を活かした食料品製造業が盛んで、工業全体に占める割合は半分近くにも上るほど。また、経済規模としては、大きくはないものの「善知鳥彫ダルマ」、「ねぶたハネト人形」、「津軽びいどろ」、「津軽裂織」、「こぎん刺し」、「錦石」など、多くの伝統工芸品も作られています。こぎん刺しは、青森県津軽に伝わる刺し子の技法のひとつであり、野良着のことを「こぎん」と呼んでいたのが名前の由来です。
また、青森市が属する津軽地域では、半導体、電子部品・情報通信、医療機器などを扱う企業が増加。特に光ファイバー、画像処理装置、半導体検査装置等の光技術を応用した製品の研究開発・製造に取り組む光技術関連企業が集積しています。
商業・サービス業
青森市には、市の玄関口に位置する「青森市新町商店街」をはじめ、15の商店街が展開しています。
青森市新町商店街は、JR青森駅を起点として新町通り沿いに東へ続き、戦前よりデパート「松木屋」が立地していたエリアです。太平洋戦争により、1945年(昭和20年)に市街地は空襲に見舞われましたが、戦後には復興を遂げ、高度成長期には、複数のビルが建ち並びました。当時から、ビル屋上でのビアガーデンやレストランなど商業施設が充実。1960年(昭和35年)9月には、アーケードが設けられ、110店舗以上が集う商業エリアとして、時代の変化に対応しながら発展し続けています。
その他、新町通りと交差する各通り沿いにも、複数の商店街が点在し、下町の風情を感じられる場所が少なくありません。例えば、夜店通り沿いには、1916年(大正5年)頃に初めて夜店ができたと言われる「青森市夜店通り商店街」が立地。現在は、若者向けのファッションを取り扱う店舗が多く集うエリアとしても人気です。
なお市内には、ファッションやグルメが楽しめる「青森駅ビルLOVINA」(ラビナ)や駅前再開発ビル「AUGA」(アウガ)、ショッピングセンターなど、近代的な大型商業施設も充実しています。特に、青森駅からアクセスしやすい所は、市営バスで約15分のショッピングタウン「サンロード青森」や、専用シャトルバスで約15分の「ガーラタウン」。いずれも、食料品や生活雑貨、ファッションなどの買い物だけでなく、グルメや映画などのレジャーが楽しめる施設も併設しており、休日には、家族やお子様連れでも飽きることなく、終日過ごすことができます。
観光・レジャー
県庁所在地が置かれている青森市は、陸奥湾を臨む海の街。青森市の北東にある夏泊半島は陸奥湾に突き出た形をしており、その付け根にある「青森県営浅虫水族館」は人気の観光スポットです。本州最北端の水族館としても知られており、陸奥湾や世界各地の珍しい水生生物を500種以上飼育・展示しています。浅虫水族館の目玉は「イルカショー」。津軽三味線や笛の音色に合わせ、イルカ達がダイナミックなパフォーマンスを見せてくれます。その他にもラッコやアザラシ、アシカなどの海獣も見られ、日本で初めて繁殖に成功したオオカミウオも水族館のアイドルとして人気です。
県庁所在地が置かれている青森市は、陸奥湾を臨む海の街。青森市の北東にある夏泊半島は陸奥湾に突き出た形をしており、その付け根にある「青森県営浅虫水族館」は人気の観光スポットです。本州最北端の水族館としても知られており、陸奥湾や世界各地の珍しい水生生物を500種以上飼育・展示しています。浅虫水族館の目玉は「イルカショー」。津軽三味線や笛の音色に合わせ、イルカ達がダイナミックなパフォーマンスを見せてくれます。その他にもラッコやアザラシ、アシカなどの海獣も見られ、日本で初めて繁殖に成功したオオカミウオも水族館のアイドルとして人気です。
また、海にまつわるスポットとしては、青森港にある「青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸」は、かつて、函館市と青森市の間で運行していた青函連絡船の歴史を伝える海上博物館。1964年(昭和39年)〜1988年(昭和63年)まで青函航路で運航していた「八甲田丸」がそのまま博物館となっており、甲板や操舵室、通信室などを見ることができます。特に4階の煙突展望台からの眺めは絶景。360度のパノラマ景色を楽しめます。
青森県を代表する祭りといえば、毎年夏に開催される「青森ねぶた祭」が有名です。例年8月2〜7日にかけて開催される青森県最大のイベントで、来場者は延べ300万人以上。高さ5mにも及ぶ大型のねぶたが街を練り歩き、その周囲を「ハネト」と呼ばれる踊り子がラッセーラの掛け声で踊ります。なお、ハネトの衣装を着用すれば、一般の方でも参加が可能です。


