
充分な養生期間をとって基礎が固まったら、いよいよ基礎の上に土台を載せます。
基礎の上の部分の色が違うのは、レベラーという部分です。基礎の高さ調整をした部分で、基礎の上に追加された部分です。
その上に、通気のためのパッキンがあります。ロングタイプの、土台の下部全面にわたる物を使用しています。
その上に土台が載ります。色が赤いのは、防蟻剤のためです。
基礎の上の部分の色が違うのは、レベラーという部分です。基礎の高さ調整をした部分で、基礎の上に追加された部分です。
その上に、通気のためのパッキンがあります。ロングタイプの、土台の下部全面にわたる物を使用しています。
その上に土台が載ります。色が赤いのは、防蟻剤のためです。

大引きの部分は90センチ間隔になります。
交点の部分を、金属製の床束が支えます。
床は剛床工法を使い、大引きを90センチ間隔で縦横に配し、その上に24ミリの合板を載せます。
通常工法では大引きの間に根太と呼ばれる木材が組まれて床を支えますが、剛床工法では分厚い床板の強度で床部分を支えるため、根太がなくともそれ以上の強度を保てる形になります。
交点の部分を、金属製の床束が支えます。
床は剛床工法を使い、大引きを90センチ間隔で縦横に配し、その上に24ミリの合板を載せます。
通常工法では大引きの間に根太と呼ばれる木材が組まれて床を支えますが、剛床工法では分厚い床板の強度で床部分を支えるため、根太がなくともそれ以上の強度を保てる形になります。

今回書庫があるので、その部分のみ補強として、床束のかわりに基礎の立ち上がりを大引きの下に配しています。
基礎部分は配筋の間隔を半分の10センチにし、床板は28ミリに強化しています。
通常、本棚は100キロ近くあり、書庫ですと平米あたりに2つ以上設置され、そこに閲覧者が一人ないし二人立つということになるため、相当量の加重となりますが、それに充分耐えうる形の補強となっています。
他の工法では、部屋の床をベタ基礎まで下げる方法もありますが、床下通気が犠牲となります。
基礎部分は配筋の間隔を半分の10センチにし、床板は28ミリに強化しています。
通常、本棚は100キロ近くあり、書庫ですと平米あたりに2つ以上設置され、そこに閲覧者が一人ないし二人立つということになるため、相当量の加重となりますが、それに充分耐えうる形の補強となっています。
他の工法では、部屋の床をベタ基礎まで下げる方法もありますが、床下通気が犠牲となります。
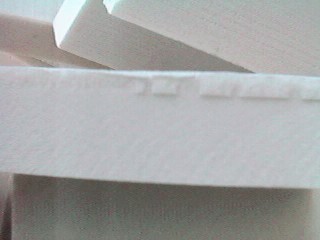
工程としては柱が立った後になりますが、断熱材として40ミリのフォームを大引きの間に隙間なくはめ、その上に床板が載ります。




最後に、モルタルの化粧塗りがされます。