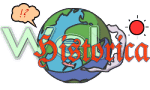WelHistorica
東方問題(一)
最終更新:
welhistorica
-
view
|
|
東方問題(一)
 |
| ランケ 「史料批判に基づく実証的な近代歴史学の父。ランケはメッテルニヒ外交の研究から「東方問題」にも関心を持ち、ヨーロッパ列強を中心に近代世界史を構成した。このランケ的な視点がオスマン帝国の解体過程を「東方問題」として捉える場合、列強の帝国分割政策や勢力均衡の観点から論じられる傾向にあることに影を落としている |
| 「東方問題(一)」では、ナポレオンの時代までの東方問題を対象とする。それ以降は「東方問題(二)」「東方問題(三)」を参照。 |
東方問題(とうほうもんだい)とは、オスマン帝国?およびその支配地域をめぐるヨーロッパ諸国の外交問題。広義にはオスマン帝国成立以来、キリスト教?ヨーロッパ世界がイスラム?教国であるオスマン帝国の圧迫を受け、それに関わるヨーロッパ諸国間の外交問題。狭義においては18世紀以降のオスマン帝国の解体過程に伴って生じ、19世紀に顕著となったオスマン帝国領内での紛争に関連するヨーロッパ諸国間の国際問題を意味し、今日一般的にはこの用法で使われる。
定義と特徴
広義の「東方問題」は15世紀以降オスマン帝国のバルカン進出によって形成されたヨーロッパの外交問題で、対オスマン十字軍やオスマン帝国を利用したブルボン家?の対ハプスブルク家?外交などを含み、18世紀以降のオスマン帝国解体期に帝国領の分配を巡っての列強の勢力均衡外交を経て、最終的にはベルリン会議?で決着したとされるもの。
狭義の、そして今日一般に使われる意味での「東方問題」は上記のうち、特に後半期の18世紀後半から19世紀にかけて生じたヨーロッパの外交問題で、利害の対立するヨーロッパ諸国間の勢力均衡をヨーロッパから見て「東方」に位置するオスマン帝国領で調整しようとするもの。バルカン半島のオスマン帝国領は1699年のカルロヴィッツ条約?以降縮小・解体に向かい、1821年以降のギリシャの独立運動などに代表されるように、バルカン諸民族が独立に向けて活発化するようになる。オスマン帝国治下の民族分布は複雑に錯綜しており、これらの民族が国民国家を形成しようとする場合、その領域の決定には民族問題が不可避に関わる状況であった。このような状況に際し、オスマン帝国側もヨーロッパの国際関係を利用して自国の領土と利益を守るために主体的に外交紛争に関わった。しかしこのことは同時に「東方」の状況自体がヨーロッパ諸国の政策を規定する側面もあり、また「東方問題」の解決がバルカン半島の民族問題の最終的な解決でなかったことは、民族問題に関係して、第一次世界大戦?が勃発する要因ともなった。
狭義の、そして今日一般に使われる意味での「東方問題」は上記のうち、特に後半期の18世紀後半から19世紀にかけて生じたヨーロッパの外交問題で、利害の対立するヨーロッパ諸国間の勢力均衡をヨーロッパから見て「東方」に位置するオスマン帝国領で調整しようとするもの。バルカン半島のオスマン帝国領は1699年のカルロヴィッツ条約?以降縮小・解体に向かい、1821年以降のギリシャの独立運動などに代表されるように、バルカン諸民族が独立に向けて活発化するようになる。オスマン帝国治下の民族分布は複雑に錯綜しており、これらの民族が国民国家を形成しようとする場合、その領域の決定には民族問題が不可避に関わる状況であった。このような状況に際し、オスマン帝国側もヨーロッパの国際関係を利用して自国の領土と利益を守るために主体的に外交紛争に関わった。しかしこのことは同時に「東方」の状況自体がヨーロッパ諸国の政策を規定する側面もあり、また「東方問題」の解決がバルカン半島の民族問題の最終的な解決でなかったことは、民族問題に関係して、第一次世界大戦?が勃発する要因ともなった。
「東方問題」という形で、オスマン帝国の解体過程を見る場合、あくまでヨーロッパ諸国の外交秩序にオスマン帝国およびその支配領域が組み入れられていく過程として捉えられる傾向にある。そこではオスマン帝国における近代化へ向けた自己改革運動はしばしば無視あるいは軽視され、列強の外交問題の延長上にそれらを位置づける姿勢が見られる。「東方問題」という捉え方ではドイツ?・オーストリア?の「汎ゲルマン主義?」とロシア?の「汎スラヴ主義?」の対立、エジプト?とオスマン帝国の紛争およびそれに関わる英?仏?の中近東政策の対立、ロシアの南下政策とイギリスの帝国主義政策の対立、イギリスの3C政策?とドイツの3B政策?の対立などを軸として語られることが多い。列強はオスマン帝国との取引において利害を調整し、一国が「一人勝ち」する構造を排除することで、各国のパワーバランスの維持に努めた。この「東方問題」は19世紀後半にヨーロッパの外交秩序が東アジアまで拡大されると、相対的に重要性を低下させ、列強の勢力均衡は中近東をこえて極東をも含めて全世界規模で調整されるようになる。
「東方問題」で扱われた問題は、列強にとっては「外交問題」、バルカン諸民族にとっては「民族問題」、オスマン帝国にとっては「領土問題」であった。したがって列強間の外交問題である「東方問題」はベルリン会議でほぼ最終的な決着を見たが、その民族問題・領土問題は今日まで持ち越されている。「東方問題」自体は今日すでに解決された過去の問題であると言えるが、そこで扱われた問題はいまなお解決されていないものが多い。
歴史的展開
 |
| ピョートル1世 大帝。彼の治世にロシアは近代化を進めて急速に台頭し、スウェーデン、ポーランドにかわり北欧・東欧の大国として列強に加わった |
18世紀初頭までのヨーロッパ内での勢力均衡は、ブルボン家とハプスブルク家の間の大きな利害対立をイタリア?で調整することによって成り立っていた。中世以来分裂傾向にあったイタリア半島をヨーロッパの辺境と位置づけ、イタリア半島すべてを直接支配する勢力を排除することにより、この辺境で局地的な勢力均衡を実現して利害を調整し、全ヨーロッパ的な勢力均衡を保っていた。ところが、1789年のフランス革命?とその後のナポレオン戦争?の進展により、国民主義の風潮は全ヨーロッパに波及し、イタリアの人々の国民国家を求める意向を無視して分裂の状態にとどめておくことは困難を伴うようになってきた。
一方で、ピョートル1世?のもとで近代化政策を推し進め、大北方戦争?での勝利者となったロシアは、積極的に黒海への南下を図り、同時にダニューブ川沿岸にも影響を及ぼそうとしていた。このことはこの地域に同じく影響を拡大しようとしていたハプスブルク家のオーストリアとの利害対立を生じさせた。オーストリア自身はその支配体制の構造から、バルカン・東欧方面への拡大と中欧・南欧(ドイツ・イタリア)方面への拡大との二方面の選択肢があった。しかしドイツ方面への進出にはプロイセンという有力な対抗勢力がおり、イタリアでも国民国家を形成する運動がオーストリアの影響力の排除を望むかたちとなって現れた。そして最終的には1871年のドイツ帝国成立によりドイツの統合からはずされ、アウスグライヒ?体制(すなわちオーストリア・ハンガリー帝国?)を形成して東欧の大国を目指すこととなった。またイギリスは自国と植民地インドを媒介する経路を確保しようとしていたが、伝統的に地中海に大きな影響力を保持しているフランスと対立する傾向にあった。
このようなヨーロッパの状況によって「東方問題」が顕在化するのは、1736年ロシアがアゾフをめぐってオスマン帝国と開戦した事例(1736年露土戦争?)である。開戦の1年後に同盟国オーストリアはロシアを支援する形で参戦したが、休戦交渉においてオーストリアはロシアの敵国フランスの懸念を利用してロシアの主張を抑え込もうとした。ここにはヨーロッパの勢力均衡が著しく損なわれるのを防ぐために、紛争の当事者以外が「東方」をめぐる紛争に介入するという「東方問題」の基本的な構造が現れている。
1878年のベルリン会議によって列強間の利害問題としての「東方問題」に一応の決着がつけられ、1880年代のヨーロッパは「ビスマルク体制?」のもとで一応の安定が見られるとともに「東方問題」も安定したかに思われた。しかし実際にはバルカン諸民族はこのベルリン会議の決着に納得しておらず、バルカン半島は紛争の火種を抱えて「ヨーロッパの火薬庫?」でありつづけた。
東方問題の形成
 |
| 1683年、膨張の極みに達したオスマン帝国の最大版図 最近の研究ではこの時代のバルカン半島を「パクス・オトマニカ」のもと統合と共存、平和を享受していたとみる傾向にある |
「東方問題」以前、バルカン半島はオスマン帝国の統治により「パクス・オトマニカ」(オスマンの平和)の安定のもとにあったとされる。オスマン帝国によるバルカン制圧当初はイスラームの支配を嫌う住民が流出し、人口減少に襲われたが、16世紀には帝国のバルカン統治は安定化した。
17世紀にはいると、徐々にオスマン帝国の国力は弱まり、それに伴って「東方問題」の素地が形成された。1683年を境にオスマン帝国は縮小の方向に転じた。第二次ウィーン包囲の失敗により1699年のカルロヴィッツ条約でハンガリー?を失った。オスマン帝国はこれ以降東欧での拡大が阻止され、オーストリアの重大な脅威とはならなくなり、東欧では再びヨーロッパ諸国が支配的となった。
18世紀初頭にはオーストリアはオスマン帝国との戦争で連勝を続け、1718年のパサロヴィッツ条約?ではオスマン帝国はベオグラード?を一時的に失った。同時期ロシアも南下を進め、1700年には黒海沿岸のアゾフを獲得し黒海支配の足がかりを得たが、1711年のプルート戦役?で敗北してアゾフ?を返還した。これによりオスマン帝国に対するロシアの脅威はいったん弱まった。この時期オスマン帝国はチューリップ時代?と呼ばれる西欧宥和政策を展開する時代を迎え、1719年ウィーンに、1720年にはパリに外交使節を派遣した。これらの事実はオスマン帝国の外交姿勢が従来の恩恵外交政策、いわゆるカピチュレーション?中心の外交から転換したことを示すものであった。1736年には露土戦争がおこり、ロシア・オーストリアと戦った。結果1739年のベオグラード条約?ではロシアのアゾフ領有が確定し、ロシアの黒海進出を招いたものの、オーストリアからはベオグラードを奪還した。
しかしながら、ヨーロッパ政治において「東方問題」は1768年の露土戦争まではそれほど重要ではなかった。この戦争の結果1774年にキュチュク・カイナルジ?条約が結ばれ、この条約でロシアがオスマン帝国の支配下にある正教徒の保護権を認められたことから、ロシアはこれを内政干渉の理由として行使しようとし、黒海沿岸において主要な政治勢力として台頭することで「東方問題」がようやくヨーロッパ政治において重要性を帯びてくることとなった。
 |
| ダーダネルス海峡 黒海と地中海の接点であり、ロシアは南下政策をヨーロッパ側で成功させるにはどうしてもここを確保する必要があった |
しかしながら、ヨーロッパ政治において「東方問題」は1768年の露土戦争まではそれほど重要ではなかった。この戦争の結果1774年にキュチュク・カイナルジ?条約が結ばれ、この条約でロシアがオスマン帝国の支配下にある正教徒の保護権を認められたことから、ロシアはこれを内政干渉の理由として行使しようとし、黒海沿岸において主要な政治勢力として台頭することで「東方問題」がようやくヨーロッパ政治において重要性を帯びてくることとなった。
1787年にロシアとオスマン帝国の間で再び戦端が開かれると(1787年露土戦争?)、同盟に基づいてオーストリアのヨーゼフ2世?も参戦した。この際両国の間でオスマン帝国領を分割する約束がされ、イギリス・フランス・プロイセンなどに警戒を抱かせたが、1791年にオーストリアは戦争から手を引かざるを得なくなり、結果1792年のヤシ条約?ではロシアが黒海支配を大きく進めることとなった。
19世紀前半にはオスマン帝国の問題に関する列強の位置は明確になった。ロシアは「東方問題」において最も直接的な影響力を持った。ロシアはボスポラス?・ダーダネルス?両海峡およびコンスタンティノープル?の港を確保して、黒海を支配し、さらに地中海へ進出する足がかりを得ることに関心があった。ロシアはオスマン帝国の海域での商船や軍艦の航行権を、列強に先んじて確保し優位に立つことを望んでいた。また相対的に重要性は落ちるものの、オスマン帝国内の正教徒がロシアの管理のもとに置かれるように関心を持っていた。
このようなロシアの立場に対してオーストリアが最も直接的に対立した。弱体化したオスマン帝国に比べると、ダニューブ川沿いに進出しようとするロシアの脅威のほうがはるかに重大であった。またオスマン帝国の崩壊によって、オーストリア自身が抱える民族問題に飛び火し、自国内で民族の独立運動が激化するのを危惧した。したがってオーストリアはオスマン帝国の保全を考えるようになり、インドへの交通路を確保するためにロシアによる進出を警戒していたイギリスの立場と似たものとなった。イギリスはロシアがボスポラス海峡を支配し、東地中海に進出するのを警戒し、さらにオスマン帝国の崩壊によってヨーロッパの勢力均衡が崩れる懸念をもっていたために、オスマン帝国の保全を優先した。
ナポレオンの時代
 |
| メッテルニヒ ウィーン体制前後のヨーロッパ外交を主導した。彼はロシアとフランスの同盟がオスマン帝国の崩壊を招くことを警戒した |
19世紀の初頭になると、フランスでナポレオン?が台頭し、ヨーロッパはこれに注意を向けるようになった。ナポレオンはヨーロッパにおける覇権を確立するために1807年ティルジット条約?を結んでロシアと同盟関係を形成、ロシアはイギリスとの戦争を支援することを約束した。このことと引き替えに、ロシアがモルダヴィア?とワラキア?をオスマン帝国から獲得することが約束され、もしオスマン帝国がこれを拒絶したならば、両国は協力してオスマン帝国と戦争することが確認された。またオスマン帝国のヨーロッパ側領土は両国の同盟国間で分割されることが約束された。このことはオスマン皇帝だけでなく、イギリス・オーストリア・プロイセンにも脅威と取られたが、これらの国々は実質上この問題に介入する力を持っていなかった。フランスとロシアがオスマン帝国と開戦した場合、明らかにオスマン帝国を崩壊させると考えたオーストリアは外交により両国のオスマン帝国への攻撃を回避することを望んでいた。しかしもしこれを防ぐのに失敗するようならば、両国の主導するオスマン帝国の分割を支持しようとオーストリアの宰相メッテルニヒ?は考えていた。そのほうが南東ヨーロッパすべてをロシアが支配する事態になるよりは幾分ましだったからである。
しかし結果的にはフランス・ロシアによるオスマン帝国攻撃は実現しなかった。1812年に始まったナポレオンのロシア遠征によってティルジットでの同盟が瓦解する結果となったためである。1815年には列強の反撃によってナポレオンのヨーロッパ支配は終わり、列強はウィーン会議?で戦後の外交秩序を形成したが、オスマン帝国領に関する問題は話し合われなかった。この会議の結果形成された神聖同盟からオスマン皇帝が除外されるとともに、「東方問題」もロシアの国内問題であるという解釈が支配的であった。
| 以降「東方問題(二)」へ続く |
出典
- 尾形勇ほか編『歴史学事典』弘文堂、1999年
- 鈴木董著『オスマン帝国の解体』ちくま新書、2000年
- 森安達也著『スラブ民族と東欧ロシア』山川出版社、1986年
- 山内昌之著『オスマン帝国とエジプト』東京大学出版会、1984年
- 木戸蓊著『東欧現代史』有斐閣選書、1987年
- 樺山紘一ほか編『岩波講座世界歴史16 主権国家と啓蒙』岩波書店、1999年
- S・J・ウルフ著、鈴木邦夫訳『イタリア史 1700-1860』法政大学出版局、2001年
- Duggan, Stephen P. (1902). The Eastern Question: A Study in Diplomacy. London: P.S. King & Son.[1]
- Taylor, Alan John Percivale. (1980). Struggle for Mastery in Europe 1848 1918. Oxford: Oxford University Press.[1]
| [1]ウィキペディア英語版の参考文献。 |
使用条件など
| この記事はGFDL文書です。 このページに掲載されている画像はウィキコモンズに公開されているものを使用しています。 |
-