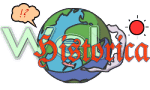WelHistorica
東方問題(三)
最終更新:
welhistorica
-
view
|
|
東方問題(三)
 |
|
ナポレオン3世とビスマルクの会談の様子(普仏戦争におけるセダンの戦いの後) 普仏戦争によってナポレオン3世が没落し、ヨーロッパ政治は大きく転回した。以後ビスマルクの主導する形で列強の外交秩序が形成される時代となる |
| 「東方問題(三)」では、クリミア戦争後の東方問題を対象とする。それ以前は「東方問題(一)」「東方問題(二)」を参照。 |
東方問題(とうほうもんだい)とは、オスマン帝国?およびその支配地域をめぐるヨーロッパ諸国の外交問題。広義にはオスマン帝国成立以来、キリスト教?ヨーロッパ世界がイスラム?教国であるオスマン帝国の圧迫を受け、それに関わるヨーロッパ諸国間の外交問題。狭義においては18世紀以降のオスマン帝国の解体過程に伴って生じ、19世紀に顕著となったオスマン帝国領内での紛争に関連するヨーロッパ諸国間の国際問題を意味し、今日一般的にはこの用法で使われる。
歴史的展開
| 「東方問題(二)」から続く |
ヘルツェゴビナの反乱
 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ ベルリン会議でオーストリアの管理下に置かれ、青年トルコ人革命が起きると混乱に乗じてオーストリアに併合された。このことが第一次世界大戦の要因となる |
1875年にヘルツェゴビナ?で、ボスニア?とブルガリア?の暴動に呼応してオスマン帝国に対する反乱が起こった。この反乱が流血にまみれた悲惨な戦争をバルカン半島にもたらさないよう、列強は介入する必要があると考えた。当時三帝同盟を結んでいたドイツ?、オーストリア・ハンガリー?、ロシア?の三国は共通の姿勢を取ることを決め、アンドラーシ・ノートという形で方針がまとめられた。この文書は、南東ヨーロッパで大規模な紛争が起きないよう火種をなくすために、キリスト教徒の宗教上の差別をなくすなどさまざまな改革をオスマン皇帝に求めるものであった。また適切な改革を保証するために、イスラム教徒とキリスト教徒の合同委員会を設けることも求めていた。イギリスとフランスの承認を経て、この文書はオスマン皇帝に提出され、1876年1月31日には皇帝の承認を得た。しかしながらヘルツェゴビナの側(反乱者たち)の指導者は以前もオスマン皇帝は改革の約束をしたが、改革は一向におこなわれていないという理由からこれを拒絶した。
三帝同盟の各国代表は、ベルリンで再び会合し、ベルリン覚え書きを合意した。覚え書きでは、オスマン皇帝が改革の約束を守るとヘルツェゴビナの指導者に納得させるために、国際的な代表団が反乱した地域での改革の実施状況を監督することが認められることを求めていた。しかしオスマン帝国政府が覚え書きを受け入れる前に、オスマン帝国内部で権力抗争がおこり、オスマン皇帝アブデュルアズィズ?はクーデターにより廃位された。つづくムラト5世?も精神錯乱がなおらずに3ヶ月で退位し、混乱の末アブデュルハミト2世?が登極した。国庫は空っぽで、ボスニア・ヘルツェゴビナだけでなくセルビア?とモンテネグロ?も反乱し、オスマン帝国の困窮は極まった。しかし1876年の8月にはなんとか反乱は終息に向かったが、汎スラヴ主義?を掲げるロシアの介入を招き、ロシアは南東ヨーロッパのオスマン帝国領の割譲を画策した。
反乱がほとんど鎮圧された頃、オスマン帝国による住民虐殺の噂がヨーロッパに衝撃を与えた。ロシアはこの状況を利用してオスマン帝国領を割譲させるために介入しようとしていた。列強はイタリアを加えて平和を維持するためにコンスタンティノープルで協議したが、オスマン皇帝はボスニア・ヘルツェゴビナに改革を監督する国際代表団を受け入れることが独立をおびやかすことになるのを懸念して、列強の要求を拒絶した。1877年になってから列強はもう一度オスマン帝国と交渉を試みたものの、強い拒絶にあった。
1877年4月24日、ロシアはオスマン帝国に宣戦布告した。オーストリア・ハンガリーは戦争によりロシアがベッサラビア?を、オーストリア・ハンガリーがボスニア・ヘルツェゴビナを獲得することを約束したライヒシュタット協定?に基づき中立を保持した。イギリス?は南アジア方面でのロシアの脅威を危惧していたが、戦争に介入することはしなかった。オスマン帝国は孤立し、1878年2月、ロシアは圧倒的な勝利を得た。サン・ステファノ条約?が結ばれ、「1.ルーマニア、セルビア、モンテネグロの独立、2.ブルガリアを独立、3.ボスニア・ヘルツェゴビナでの改革、4.アルメニアやドブルジアのロシアへの割譲」を認めさせ、多額の賠償金を得た。ロシアは新たな独立国に対しても保護権を確保し、南東ヨーロッパでの影響力を増大させた。しかしこのようなロシアの勢力拡大を警戒したイギリスをはじめとする列強は反発し、ベルリン会議?を開いて勢力を調整した。
ベルリン会議によってサン・ステファノ条約は調整された。ルーマニア、セルビア、モンテネグロの独立はそのまま承認されたが、境界は狭められた。ブルガリアはロシアの影響力を警戒されて大きく二つ(ブルガリアと東ルメリア?)に分割された。ボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリアの管理下におかれた。
 |
| ベルリン会議 この会議の結果、ドイツとロシアの間に禍根が生じ、両国の関係は一時的に冷却した。ビスマルクは巧みな外交でロシアとの関係の維持・回復に努めたが、徐々にロシアはフランスへと接近していった。また紛争に直接関わらなかった二国、英仏も「分け前」を得た。すなわちイギリスはキプロスを獲得し、フランスはチュニジア進出に対する列強の暗黙の了解を得た |
ベルリン会議によってサン・ステファノ条約は調整された。ルーマニア、セルビア、モンテネグロの独立はそのまま承認されたが、境界は狭められた。ブルガリアはロシアの影響力を警戒されて大きく二つ(ブルガリアと東ルメリア?)に分割された。ボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリアの管理下におかれた。
ドイツとオスマン帝国
19世紀後半にオスマン帝国をめぐる列強の位置は変化した。ロシア皇帝はベルリン会議でのサン・ステファノ条約の調整を不服として三帝同盟?を脱退した。ドイツはオーストリア・ハンガリーに接近し、1879年に2国間に同盟が結ばれた。またドイツはオスマン帝国に友好的であり、オスマン帝国はドイツの親密な同盟国となった。ドイツはオスマン帝国の軍事と財政の制度改革に協力し、そのかわりにバグダッド鉄道?の敷設権と商業上の特権を認められた。このことによりドイツは帝国内の重要な経済市場に参入した。一方で以前のオスマン帝国にとって重要な同盟国であったイギリスとオスマン帝国領内のさまざまな利権を巡って対立するようになった。イギリスは1904年にフランスとの間に英仏協商?を結び、両者の対立が和解され、協調関係に入った。さらに1907年にはロシアとの間に英露協商?を結び、三国協商?を形成した。
ボスニア危機
 |
| サライェヴォ事件 ボスニア・ヘルツェゴビナ併合の際のセルビア側の不満がテロリズムとなって第一次世界大戦の引き金を引くことになった |
1908年に「統一と進歩委員会?」が中心となって専制的なオスマン皇帝アブデュルハミト2世に対する青年トルコ人革命?がおこった。1909年には皇帝は廃位され、メフメト5世?が即位したが、彼はほとんど実権のない傀儡君主であった。さまざまな改革がおこなわれたが、国内における社会不安や混乱が続いた。
この情勢を利用して、オーストリア・ハンガリーはベルリン会議以来同国の管理下にあったボスニア・ヘルツェゴビナを併合した。青年トルコ党?員による憲法改正で、地方の州に大幅な自治が認められることになっていたが、このことがボスニア・ヘルツェゴビナにおけるオーストリアの権益を脅かし、オーストリアは同地域を保護すべきこと、およびオーストリアの保護が同地域に経済的な安定を及ぼすとの主張に基づいて行動した。オーストリアはロシア軍艦のダーダネルス海峡通航権が認められるのを支持するという約束をしてロシアの支持を取り付けた。オーストリア・ハンガリーはオスマン帝国の平和のために多額の援助をすることを約束し、ボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリアに併合された。しかしオーストリアの約束はロシアに何の益ももたらさなかった。ロシアは軍艦のダーダネルス海峡通航権をオスマン帝国に請求したが、イギリスとフランスの反対にあって頓挫した。
オーストリア・ハンガリーはしかし、セルビアの頑強な抵抗に遭い、セルビアはロシアに支援を求めた。だがロシアは日露戦争で敗北を重ねて疲弊していたので、これに応ずることができなかった。ドイツはこの情勢を見てオーストリア・ハンガリーを支持し、イギリスとフランスはこの件に無関心であった。孤立したセルビアはやむをえずボスニア・ヘルツェゴビナの併合反対を取り下げた。
「東方問題」における歴史学
「東方問題」成立の契機
 |
| 第二次ウィーン包囲 この遠征の失敗以後、オスマン帝国は縮小・解体に向かい、それに伴って「東方問題」が発生するようになる。この遠征の結果であるカルロヴィッツ条約によって、オスマン帝国は初めてヨーロッパ諸国と条約関係をもった |
「東方問題」の形成過程については3つの主要な契機がある。
- 1699年 カルロヴィッツ条約?により、オスマン帝国がヨーロッパ諸国と条約を結ぶ、またこれ以降オスマン帝国は縮小・解体の時期を迎える
- 1736年 露土戦争?により、ヨーロッパの勢力均衡を維持するために、紛争の当事者以外が「東方」の問題に介入するという「東方問題」特有の形式が出現
- 1774年 キュチュク・カイナルジ?条約により、ロシアがオスマン帝国内の正教徒の保護権を得る。ロシアがオスマン帝国に内政干渉して両国の紛争につながり、列強がそれに介入するという「東方問題」固有の構造が明確となる
「東方問題」のバイオリズム
 |
| ビスマルク 卓越した外交センスでヨーロッパに複雑で、それゆえに安定した外交秩序を構築した。彼はオーストリアとロシアの間で「東方問題」に関する紛争が起こるのを嫌い、「公正な仲裁人」と称してベルリン会議を開いた。彼はこの会議で列強の利害を巧みに調整した |
また、ヨーロッパ内の政治状況によって「東方問題」が安定化あるいはその重要性が相対的に低下する時期がある。
- 1807年~1815年 ナポレオンの時代
- 1840年~1853年 1848年の諸革命前後のヨーロッパ政治の動揺期
- 1856年~1871年 クリミア戦争後の安定期
- 1878年~1890年 ベルリン会議後、ビスマルク体制の終焉までの安定期
「東方問題」史観
オスマン帝国を15・16世紀の軍事的成功を伴う拡大期と19世紀の解体期に焦点を当てて記述し、とくに解体期を「東方問題」としてヨーロッパ外交秩序、列強の世界分割や勢力均衡の観点からのみ捉える見方は、いまなお支配的である。一種のオリエンタリズムに基づくこのような歴史観に対し、オスマン帝国を専門とする史家の多くがオスマン帝国の600年にわたる統治をより主体的に、いきいきと描き、アジアとヨーロッパの接点に位置し、両世界の交流の中に輝いた「世界帝国」として記述すべきと主張している。ただしそのような場合、「東方問題」は古い歴史学の遺跡のように言われることがある。たしかにオスマン帝国史がヨーロッパ側からのみ記述されてきたことは問題とされてよいし、オスマン帝国を含む「帝国」と呼ばれる広域国家の「世界性」を解明することは歴史学の大きな主題の一つといってよい。しかし同時に「東方問題」がヨーロッパ近代外交において主要因でありつづけたという事実が一方にある。したがって「東方問題」的な見方がすでに古い、あるいはもはや用をなさないとするのは早計であろう。近代のヨーロッパの政治構造、なかんずくその条約体制が世界を覆い尽くしていく過程を捉える場合、「東方問題」は貴重な財源として多くの事例を提供するものであり、そこには無限の主題がある。
出典
- 尾形勇ほか編 『歴史学事典』弘文堂、1999年
- 鈴木董著 『オスマン帝国の解体』ちくま新書、2000年
- 森安達也著 『スラブ民族と東欧ロシア』山川出版社、1986年
- 山内昌之著 『オスマン帝国とエジプト』東京大学出版会、1984年
- 木戸蓊著 『東欧現代史』有斐閣選書、1987年
- 樺山紘一ほか編 『岩波講座世界歴史16 主権国家と啓蒙』岩波書店、1999年
- S・J・ウルフ著、鈴木邦夫訳 『イタリア史 1700-1860』法政大学出版局、2001年
- Duggan, Stephen P. (1902). The Eastern Question: A Study in Diplomacy. London: P.S. King & Son.[1]
- Taylor, Alan John Percivale. (1980). Struggle for Mastery in Europe 1848 1918. Oxford: Oxford University Press.[1]
| [1]ウィキペディア英語版の参考文献。 |
使用条件など
| この記事はGFDL文書です。 このページに掲載されている画像はウィキコモンズに公開されているものを使用しています。 |
-