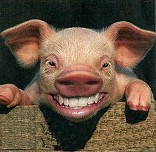豚小屋
オブジェクト指向に触れる
最終更新:
匿名ユーザー
-
view
第1回 オブジェクト指向に触れる ~はじめに~
オブジェクト指向は難しいと良く聞きます。実際そうなのかもしれません。
それにオブジェクト指向については私も完璧に理解してません。
ある程度といったところです。
それにオブジェクト指向については私も完璧に理解してません。
ある程度といったところです。
オブジェクト指向の開発で上位にあたる分析(OOA)の経験はありません。
システムをマクロな視点で捉える工程です。
システムをマクロな視点で捉える工程です。
私は、そこまでの経験と知識は現在ありません。
一応、設計(OOD)とプログラミング(OOP)をやる程度のものです。
一応、設計(OOD)とプログラミング(OOP)をやる程度のものです。
そんな私が語るのだから、若干視野が狭いかもしれません。
ベテランの方からすれば分かってないといわれるかもしれません。
ベテランの方からすれば分かってないといわれるかもしれません。
ですが、ちょっとのオブジェクト指向に対する理解で人生観が
変わることが多くありました。もちろん、よい意味です。
変わることが多くありました。もちろん、よい意味です。
それを伝えたい!という思いから、私なりに解説しようと思います。
第2回 オブジェクト指向に触れる ~理解する前に~
オブジェクト指向は、頭が整理できない論理欠如な人には非常に
敷居が高いです。
論理性が低い私が身を持って敷居の高さを経験しました。
敷居が高いです。
論理性が低い私が身を持って敷居の高さを経験しました。
オブジェクト指向をある程度理解するには
以下のような視点があれば楽になると思います。
以下のような視点があれば楽になると思います。
- 難しい単語に対する理解(役割など)
- 物事をマクロ、ミクロ両方の視点で見ることができる力
- 一つだけの考えに縛られない、別の見方も存在することを意識する
- 探究心(本質を理解しようという意思がメイン)
- 物事を複雑に考えず、地道に順序だてて整理し、単純に分かりやすくしようとする意識
挙げればキリがないと思うのですが、今思いつく限り列挙してみました。
私の場合、列挙した項目のうち殆どできない状況でした。
私の場合、列挙した項目のうち殆どできない状況でした。
列挙した項目の視点があれば楽のではないか?そう思います。
経験で言っているので、主観的ですが。
経験で言っているので、主観的ですが。
第3回 オブジェクト指向に触れる ~頭を使う~
私が列挙した項目は、日頃から面倒くさがらず
意識すれば身に付く能力と思っております。
意識すれば身に付く能力と思っております。
◆難しい単語に対する理解(役割など)
分からない言葉があれば、すぐ辞書を引く(最近はインターネットでもできます)
◆物事をマクロ、ミクロ両方の視点で見ることができる力
間近で見るのと遠くから見るのでは、見える景色ってずいぶん変わりますよね。
分からない言葉があれば、すぐ辞書を引く(最近はインターネットでもできます)
◆物事をマクロ、ミクロ両方の視点で見ることができる力
間近で見るのと遠くから見るのでは、見える景色ってずいぶん変わりますよね。
例:小泉首相の日本での評価(ミクロ)、小泉首相の世界での評価(マクロ)を調べてみる(笑)
◆一つだけの考えに縛られない、別の見方も存在することを意識する
思考を一本化させないように心がける必要があります。
思考を一本化させないように心がける必要があります。
例:正義という言葉があります。テロを起こすイスラムの人達は、アメリカに危害を加えるので制裁します。アメリカ視点で正義と定義します。
イスラムの人達からすればアメリカは自分達の宗教を弾圧し侵略してきます。それにまともに対応できる力がないのでテロを起こすことで対抗します。イスラム視点で正義と定義します。
◆探究心(本質を理解しようという意思がメイン)
常に物事に疑問を持つ事です。なぜ?という問いかけ必要になります。本質までにたどり着けるまで、一つの物事に問いかけを繰り返しましょう。
常に物事に疑問を持つ事です。なぜ?という問いかけ必要になります。本質までにたどり着けるまで、一つの物事に問いかけを繰り返しましょう。
例:なぜ?熊が人里に現れて、畑をあらすのでしょうか?
◆物事を複雑に考えず、地道に順序だてて整理し、単純に分かりやすくしようとする意識
例:算数や数学の文章問題を解いてください。または、時系列をわざと、ばらしているような小説を読むのも効果があるかもしれません。
これ以上、これらの視点にもっと踏み込んで解説すると哲学の領域に到達しそうなんできっかけ程度の解説にとどめておきます。
要は、オブジェクト指向を理解するには、頭を使う必要があるということです。
よく上司、親、先生から、「頭を使え!」といわれた事ありませんか?
よく上司、親、先生から、「頭を使え!」といわれた事ありませんか?
私は、こういった前提となるような視点をもたずにオブジェクト指向に
取り組んだので苦労しました。
取り組んだので苦労しました。
しかし、オブジェクト指向の具体的な解説まで前置きが長いですね(笑)
第4回 オブジェクト指向に触れる ~抽象と具象~
ざっくり言うと、オブジェクト指向は以下のようなことだと考えられます。
オブジェクト指向は複雑な要求(要件)や問題を分割し、分割した要求(要件)や問題を整理します。整理された要求(要件)や問題を個別に解決し、全体としての解を求めます。
分かりました?簡潔にまとめてみました。オブジェクト指向についてIT辞典で調べてもよく分からないことが多いです。
それは、複雑すぎるの専門的な単語を使ってまとめてあるので文章自体は単純ですが難解な意味になっています。
それは、複雑すぎるの専門的な単語を使ってまとめてあるので文章自体は単純ですが難解な意味になっています。
私が簡潔にまとめた内容は、小難しいオブジェクト指向に使われる単語を全く使わずに定義したものです。
これでも、捉えづらく感じる方もいると思います。なぜなら具体的さがないからです。具体的ではないので、ぼんやりとした印象を受けてしまうのです。
オブジェクト指向は、抽象という概念が取り入れられているのです。この抽象が
敷居を高くしている理由の一つです。
敷居を高くしている理由の一つです。
どうやら日本人は抽象的に物事を考えるのが苦手な民族みたいですね。
ですから抽象的に考える能力がなくとも、これから身に付けていけばいいのです。
ですから抽象的に考える能力がなくとも、これから身に付けていけばいいのです。
私自身、オブジェクト指向をある程度理解したといっても、最初から抽象的に考えるのは無理です。
最初から抽象を求めようとせず、発想を逆転させて複数のよく似た具体例を準備します。そこから共通する性質などを見出し、抽象に導いていくのです。
こういった訓練を積み重ねることによって抽象的な視点が身についていくと私は考えています。
こういった訓練を積み重ねることによって抽象的な視点が身についていくと私は考えています。
あなたが一つの抽象的な事を見出したと仮定します。今後、その見出した内容に近い具体的な事例と向き合った時は本質的なことを理解しているので、どういったことなのかが理解とイメージがつかみやすくなります。
前回、前々回で述べた内容は、少なからずとも抽象的に物事を考えるのに必要になってくる要素だと思います。