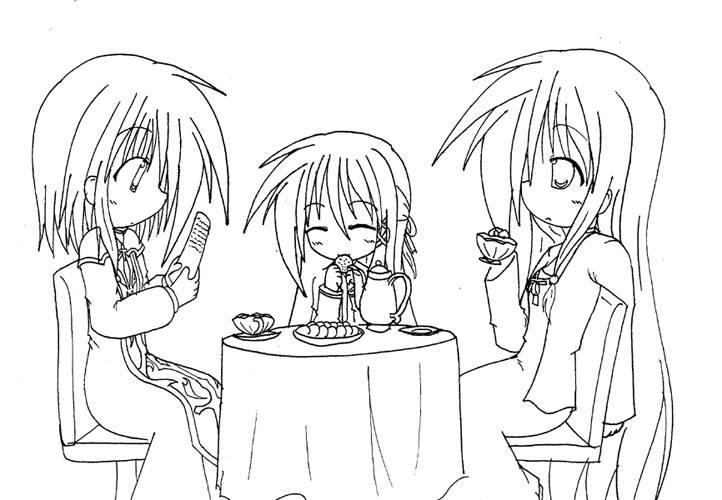3・エミリア・リスティ編
魔法とは突き詰めてしまえば『式』である。
術者のメンタルを元に、『能力』や『詠唱』という要素を付加していく事で、魔法という形を組み上げていく、一種のパズルのようなものでもある。
そして、その式は魔法を行使する、という意味から一般的に『術式』と呼ばれ、教会における聖術は、詠唱や術式が厳密に定義されているために、他の介入する余地は無いとされているのだが……
マージナルやネクロマンサの場合、同じような魔法でも詠唱などの過程は人によって違う場合が多い。
数学においても、違う数式を使っても結果的に同じ答えに辿りつく事がある。
それは、魔法の術式おいても同じ事なのだろう。
パピードラゴンと呼ばれている支援士、ティールが率いるギルド、リトルレジェンドの一室。
そこは一応のサブマスターとして位置づけられているエミリアの部屋で、ぱっと見こざっぱりして片付いているように見えるものの、その一角にある本棚には様々な魔導書や珍しい物語の本など、個人の所有物にしてはやたらとすごい書物ばかりが集まっている。
彼女の他のコレクションは、また別室を個人的な倉庫にして置いているようだが……
彼女以外の人間は、その中身を把握していない――というか色々と扱いが難しい物品も多く、完全に把握することなど、このギルドでは珍品名品に詳しい彼女にしかできないだろう。
「エミィさん、お茶入りましたよ」
「エミィおねえちゃん、おやつだよー」
机に向かっていたエミリアに向かって、ドアの向こう側から話しかける声。
それは彼女にとっても聞きなれた、親友の呼びかけだった。
「リスティ……と、イリスか。 すまぬな」
ひとまず手元の作業を中断し、がちゃりという音と共に開くドアに目を向ける。
そこにいたのは、いつも使っているティーセットが乗せられたトレイを手にしたリスティと、お茶請けのお菓子を持つイリス。
二人が揃っている時の三時を回るこの時間帯は、リスティとエミリアにとってはお茶の時間で定例化していた。
今日のようにイリスが混じるのも、時折ではあるが慣れた事である。
「いえ、こういうの好きですから」
手馴れた調子で部屋の隅にたてかけてあった折りたたみテーブルを組み立てるエミリアに、そう返事をするリスティ。
そして、組みあがって軽く叩き、崩れないことを確認した後に、手に乗せていたトレイをその上に置いた。
横では、イリスが適当な椅子を持ってきて既に座っていた。
「それにしても、ディンさんもヴァイさんも、もう少し待てばエミィさんが帰ってきてたのに……なんで、あんなに急いでたんでしょう」
「……ふむ?」
「いえ、実はグノルに依頼で二人で行っちゃったんですよ。 昨日エミィさんが帰ってきた、3時間くらい前に……」
「あぁ、それならティールに聞いたが。 別に気にする事でもないじゃろ」
そして、イリスに続けるようにして、二人も適当な椅子を置いて、そこに腰かける。
その一連の動作は妙にこなれていて、こういった突然のお茶会は今回が初めてでは無い事が伺いしれる。
「……なんだか、あっさりしてますね。 依頼の時は、いつも一緒なのに……」
「確かにチームは組んでおるが、お互いに色々事情があることも少なくない。 私を待たずに行ったと言う事は、あいつなりの理由があるということじゃよ」
「リスティおねえちゃん、クッキー食べていい?」
「あ、うんいいよ。 ……えっと、やっぱり、信頼してるんですね」
返事をすると同時にぱぁっと笑ってテーブルの上のクッキーに手を伸ばすイリスを横目に、話を元に戻すリスティ。
その瞬間の表情には、感心や喜びのようなものが浮かんでいた。
仲間の関係が良好なことは、自分にとっても喜ばしい事なのだろう。
「まぁそういうのは大抵私を驚かそうと何か企んでる時くらいじゃし……何かの材料でも採りに行ったってところじゃな」
「…………」
一転、苦笑。
お互いを知りすぎているというのも、日常のサプライズというものが薄くなってしまうのかもしれない。
リスティは、男女の距離感は難しいものだな、と妙な実感を覚えていた。
「それより、むしろお主がヴァイについていかなかったのが驚きじゃが……」
「あ、いえ。 私も教会の方で用事がありましたし……確かに早めに終わらせてついて行こうと思ったんですが、ヴァイさんが『グノルだから二人でも大丈夫だ』って言って、それで……」
「……ふむ」
確かに、グノルの浅いところはヴァイとディンの二人が揃っていれば全く問題は無いだろう。
……だが、それはあくまで『浅いところならば』の話であり……恐らく、リスティはグノル深層の事は知らされてはいない。
だからこそ、『グノル』という単語で思いつくレベルも、比較的低い場所でしかないのかもしれない。
とはいえ、深いところでも少々の事でやられる二人でもない……
直感的に二人は深い所にいると感じつつも、ぱりぱりとクッキーをかじりながらそんなことを思うエミリア。
心配が無いと言えば嘘になるが、今更気にしても何もできることはない。
―ヴァイが連れて行かなかったのは、リスティにとってあの場所はいい思い出はなさそう、という理由もありそうじゃがな―
考えられる事象は、いくらでもある。
が、実際に自分達がいくら考えてもそれは推測でしかなく、事実を知るのは本人だけだろう。
もっとも、エミリアはそれを突き詰めるつもりもなければ、他人の知られたくない一面を勝手に暴露する趣味も無い。
とりあえず、この場は何も言わないようにした。
「……ところで、何か読んでいたんですか?」
それから少し経過して、リスティがそう口にしながら向けた視線の先には、デスクの上に広げられた数冊の本が映っていた。
加えて、その周囲に数枚の紙とペンが一本置かれているのが気にはなるが……
「ああ、お兄ちゃ……兄さんから貰ってきた魔導書じゃよ」
「……あ、えっと……お、お兄さんって、エミィさんの家の跡継ぎでしたっけ……?」
何かを言い直したのには気付いていたが、あえて何も言わずに聞き流すリスティ。
……もとい、思わず何かを言いそうになって、慌てて口から出る言葉を修正していた。
「う、うむ……たまに珍しいモノが入るとくれたりするからのぉ」
あははは、とごまかすように笑いながらエミリアはそう返事をする。
―そういえば、ディンさんがエミィさんは甘えん坊なところがあると言っていた気がする―
いつ、と明確に思い出す事はできないが、エミリアがいない時に何気なく会話の中にでてきた一言だった。
普段どちらかといえば『お姉さん』的な立ち位置にいる彼女だが、ディン等の身近な年上の人間に対しては、時折そういうしぐさが見え隠れすることがあるらしい。
「これ、なんだかエミィおねえちゃんの腕の模様に似てるね」
……そうこうしていると、いつのまにやらデスクに近寄っていたイリスが、なにやら複雑な模様が描きこまれた紙を一枚手に取っていた。
寒い季節ということもあって今は目にする事が出来ないが、エミリアの二の腕には、ぐるりと一周するように紋章の羅列が両腕に刻まれている。
「まぁそれはまだ研究段階じゃが、確かに同じものじゃよ」
「……たしか、『式紋』でしたっけ。 口による詠唱の代わりになる、紋章による術式……」
「?? ……よくわかんない……」
「イリスにはまだ難しいかもしれぬな」
エミリアはふふ、と穏やかな笑みを浮かべながら、紋様をみつめて首をかしげるイリスにそう語りかける。
……が、あと一~二年もしたら、彼女もこの式を理解できるようになるのでは、という推測もたてているのも事実。
『アイリスの記憶』はエミリアが予測していたよりも早くイリスの中で解放されていて、使用できる属性こそ増えていないが、普通の人間では考えられない勢いで次々と新しい呪文を覚えていく――いや、『思い出していく』と言った方がいいかもしれない。
その内容はまだウィッチのレベルを超えてはいないのだが、アイリスの記憶は本人の『肉体と精神の成長』に応じて順次解放されていく、と、アルティアの英知を元にリスティが言っていたのは記憶に新しい。
この先の成長具合によっては、1年もしない内にマージナルに限りなく近いレベルになる可能性もありえなくはない。
「…………神代の時代からの記憶、か。 少しうらやましくはあるのぉ」
ある意味、彼女はこの世の理にもっとも近い存在なのかもしれない。
その記憶がすべて蘇るのが一体何年後になるのかは、全くわからないのがまたもどかしい。
「なぁに?」
もちろん本人にそんな自覚は無い。
明らかな自覚をするのは、もっと未来……それこそ、先代以前の思い出などといった、パーソナルな部分が解放されてくる段階になってからだろう。
自分では無い誰かの記憶が、自分の中にある―――きっと、彼女はいつかはそんな経験をすることになる。
それがどんな苦悩になるのかが想像できないだけに、記憶の継承も素直に喜べるものでもないのかもしれない。
「いや、何でもないよ」
まぁ、今は大人しく見守るのが吉。
『親』の立場にあるティールも、イリスからそれに近い信頼を持っているリスティもそう判断している。
だから、今は何も言わないことにしていた。
「……あの、エミリアさん。 以前話は聞いていたんですけど、やっぱりよく分からないです……」
「ん? 式紋のことかの?」
ひとまずイリスとの対話が終わった、と判断したのか、話を元に戻すリスティ。
紋章の羅列が詠唱の代わりになる――というのは目の前で照明されているので納得はできるが、その理屈についてはまだよくわかっていない。
少なくとも教会の教科書には、詠唱そのものを肩代わりできる術式など書かれてはいなかったのだから。
「…………ふむ……そうじゃな。 それを説明すると……」
「……エミィさん?」
そう言いながら、エミリアは真新しい紙を一枚取り出し、カリカリと文字を書きこんでいく。
その文字はイリスが持ってきたもののような紋章の羅列ではなく、世間一般的に使われている普通の文字の羅列。
……というより、数式のような文章だった。
「魔法というのは術者のメンタルに、詠唱という媒介を通して『属性』や『指向性』を定義し、具現されるものじゃ」
「あ、はい。 聖術も、そのあたりの理屈は同じだと思います」
「極端な話、数学における数式と同じようなものじゃよ。 メンタルという数値に、属性、指向性という数字を足したりかけたりするものじゃからな」
「……うー、難しいよ……」
「……いや、イリス。 無理して聞かなくてもいいんじゃが……」
イリスの精神年齢は八歳前後。
まだまだ理屈よりも『記憶』からくる本能的なものに頼って魔法を使っているだけに、こういった問いかけになってくると思考が追いつかないらしい。
すでにオーバーヒートしかけているのか、あたまをひねって難しい顔をしていた。
「……こほん。 まぁ、要するにメンタルに属性と指向性を与えられる媒体を声以外のモノで用意できれば、それで魔法を具現することは可能、というわけじゃな。 わかるかの?」
「は、はいなんとか……」
とりあえずイリスはクッキーに思考を逸らさせて知恵熱を防止。
少し苦笑しながらも、エミリアはリスティに式紋の理論の講釈を再会した。
「そこで用意されたのが、『紋章』じゃ。 魔導文字とも呼ばれているが、この図式にはそれぞれ意味があり、これは『氷』、これとこれを組み合わせれば『槍』になり、この二つの紋章の繋ぎとして、こっちの文字が間に入る」
「……あ、だったら、この式は氷の槍……『アイスニードル』ですね?」
「正解じゃ。 ……まぁ、これは極力単純にした式じゃから、これだけでは大きな力は得られん。 ここに色々とメンタルから魔法へと変換させる補助的な紋章を加えて行く事で、『言葉』による術式に匹敵する威力に近づけていくわけじゃな」
「はぁー……なるほど」
「ま、このあたりは紋章術の魔導書の受け売りじゃがな」
魔導文字――紋章自体は、教会でもある程度知られている。
が、やはりマージナルが使うような数多くの属性ではなく、聖術にのみ特化して伝えられているために、その道の者達とは随分差をつけられているのだろう。
……聖エルナンが定義した術式の完成度が、他の術式の追随を許さない程の高みにあるという影響があるのも、確かではあるのだが。
ユキの例もあるように、それを『式紋』やら『笛の音』で構築できるようにしてしまう彼女の研究のレベルも大したものなのかもしれない。
「……あれ? 式紋ってエミィさんのオリジナルの術式じゃなかったんですか? 受け売りって……」
以前、自分が独自に研究を進めている――などというセリフを耳にしたことがある。
その一言から、エミリア自身がゼロから組み上げたものだ、と思い込んでいたが……
「ん? ああ……違う違う。 式紋について残っている文献が少なくて、そもそも魔導文字を詠唱の代わりにできると知っている者が少ないからのぉ。 あの時『独自に』と言ったのは、独学で、という意味じゃよ」
「そ、そうだったんですか……」
「私も、式紋に関する文献は兄さんやお父さんの力が無いと集められなかったから……いくら家には迷惑はかけたくないと言っても、やっぱり頼ってしまう部分はあるのぉ」
「……エミィさん……」
基本的に、エミリアは実家の事を自分から話そうとしない。
だからといって別に否定しているわけでもなく、家出をしてきたわけでもない。
ただ、家がそれなりに有力な商家だから、と自慢したり頼ったりするのが嫌だというだけだ、と本人は言っていた。
「ふぅ、まぁ簡単に説明したらそんなところじゃな。 何か質問はあるかの?」
などとリスティが考え込んでいると、特になんでもないというような表情で、エミリアがそう呼びかけてくる。
「……あ、いえ。 なんとなくですが、理解できたと思います」
とりあえず自分も何事も無かったように返事をして、少し今回の説明を思い返しながらそう答えることにした。
よくよく考えてみれば面白い理論であるし、聖術にも適用できる事はディンやユキの例で証明されている。
……身体に直接刻み込むのはジョブのイメージ的にあまり好意的には見られないので、もし適用しようとするなら、本か簡単なアクセサリーを介する事になるかもしれないが……
今は自分の修行に手一杯であり、それに『術式』という重要な部分を外部から導入させるなど、自分一人の力で勧められるようなものでもない。
「でもやっぱり、教会では使いづらいですね……」
そう考え、リスティはとりあえずそれだけ言っておくことにした。
エミリアが勧めてきたわけではないが、なんとなく、そう言いたくなったのだ。
「じゃろうな。 まぁ、使いたい者が使えばいいだけの技術じゃから、私が推すこともないが」
それを受けて、軽く微笑むエミリア。
その時、リスティは、なんとなくこの場にいづらいような気分にかられていた。
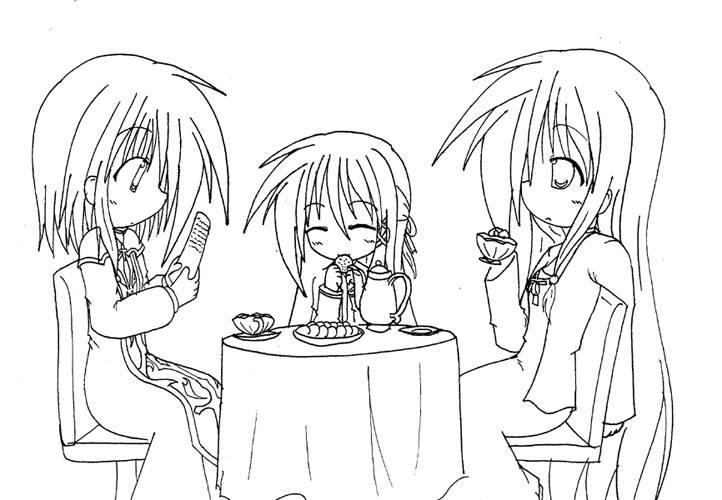
最終更新:2008年02月08日 22:33