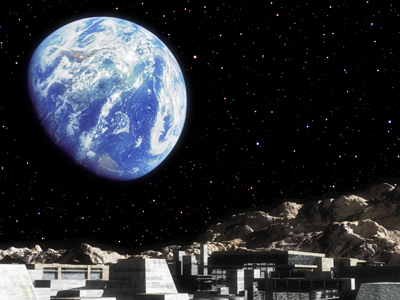『Zプロジェクト』
ルナチタニウム
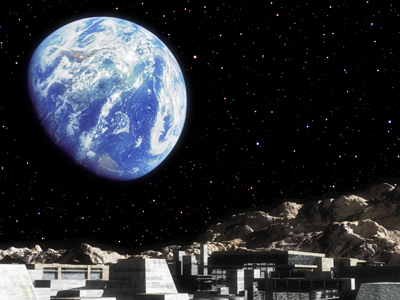
連邦軍が開発したガンダムが優秀だったのは、ルナチタニウムを潤沢に使用することができたからだといわれる。
ルナチタニウムとは、月面に産する純度の高いチタニウムを原材料とした新合金のことであり、高い耐熱性、
さらに優れた硬度や放射線絶縁性を持つ。加えて軽量でもあるため、MSの高性能化に最適の素材であった。
このルナチタニウム系の合金は、ガンダムの開発によって誕生したといっても過言ではなかったため、
後にガンダリウムと呼ばれるようになり、更なる高性能化が計られた。
ただし、最高性能のガンダリウムは、精錬技術が特殊であるうえ、レアメタルを多量に必要とするため
コストダウンが困難であり、量産効果もあまり期待できなかった。
それらの理由から、
一年戦争後に連邦軍製の量産機に採用された装甲材は組成が変えてあるといわれており、事実上、
標準的なチタン系合金とセラミックとの複合材である場合が多かったらしい。
それでも、ガンダムが優秀な機体であったことに変わりはなく、ビーム兵器という強力な矛と、
ガンダリウム製の装甲という強力な盾に匹敵する装甲材の開発は、公国軍のMS開発においても最重要課題の一つになっていた。
アクシズに逃げ延びた公国軍残党は、窮乏生活を続けながらもMS開発に全力をあげていた。
そして、ガンダムの強さ秘訣とも言える装甲材の開発において、ガンダリウムを越える装甲材や構造材の開発に成功した。
それがガンダリウムγ(ガンマ)である。

ガンダリウムとは、ガンダムが採用していた初期のルナチタニウム合金をガンダリウムαとし、
ガンダリウムβを経て開発されたため便宜上与えられた呼称である。
実際、一年戦争後のMS開発は、ガンダムをひとつの指標としており、
それは連邦軍においても公国軍残党においても同様だった。
アクシズにおいても、ガンダリウムという呼称が採用されていることが、それを雄弁に物語っている。
γガンダム
地球圏においてガンダリウムγが採用された初めての機体がリック・ディアスである。
リック・ディアスは、
アナハイム・エレクトロニクスが
エゥーゴのために開発した機体で、
シャア・アズナブルによってもたらされたガンダリウムγの採用を前提として開発された。
ガンダリウムγは、初期のガンダリウムが抱えていた量産性や加工性の問題が改善されており、
さらに既存の装甲材と同程度の強度が、数分の一の装甲厚で獲得できるという特性があった。
このため、機体全体の質量重量比が飛躍的に改善され、プロペラントの積載量も飛躍的に増量できるようになったのである。
つまり、一年戦争と同程度の機体であっても、装甲をガンダリウムγと換装するだけで性能が向上するとさえいわれている。
リック・ディアスはアナハイムがエゥーゴを支援するために建造した機体であったが、
連邦の査察を逃れるために制式番号の偽装登録などが施されており、ガンダリウムγが事実上の軍事機密であったことが窺える。それほどガンダリウムγという新合金は画期的なものだったのである。
ちなみに、リック・ディアスは、γガンダムと呼ばれていた時期があった。
これは、アナハイムやエゥーゴの指導者であるブレックスが好んで使用した開発コードであった。
つまり、リック・ディアスもまた、ガンダムという優秀な機体を指向して開発されていたのである。

さらに、このγガンダムという呼称は、初代のガンダムをαとして「アナハイムが開発した3番目のガンダム」という意味の
隠語でもあったらしい。その真意は不明だが、βに相当する2番目のガンダムがガンダムMk-Ⅱか、
あるいは
GPシリーズを指すのでないかとされている。
結局、リック・ディアスの名は、公国系の技術者が多く携わっていたこともあってか、クワトロ大尉ことシャア・アズナブルの
提言によって、喜望峰の発見者「バーソロミュー・ディアス」に因んで、リック・ディアスとされるようになったらしい。
Zガンダム

エゥーゴは、ガンダリウムγを採用したリック・ディアスを完成させたのと前後して、
さらなる次世代の超高性能を開発すべく「Zプロジェクト」を発動させた。
Zプロジェクトによって開発されていたMSは、汎用性が高く、複数の戦術に広く対応できることを目的としていた機体で、
通常のMSを越える性能が要求されていた。
その意味で、複数のミッションを同時にこなせる「可変MS=TMS(Transformable Mobile Suit)」は、
是が非でも手に入れなければならないものだったのだが、運用面からのコストパフォーマンスが検証できず、
実際的なプランとしては稼働の保証が望めないことなどから除外されていた。
単体で複数のアビリティを持つ機体の戦略的、戦術的な価値は計り知れず、
実際、連邦軍や
ティターンズが投入してくるTMSは、エゥーゴの戦略にとって、大きな障害となってはいたが、
抜本的な戦略差は歴然としていたため、現実的な選択肢として採用されていなかったのである。
しかし、U.C.0087年3月。ティターンズの施設から強奪されたガンダムMk-Ⅱの存在が状況を一変させた。
アナハイムは、この機体からムーバブル・フレームの技術を手に入れることで、TMSの開発に着手した。
同時期にエゥーゴに参加したカミーユ・ビダンの発案によるTMSのプロットをもとに、
既存のMSを大きく上回る汎用性を持った機体の開発が可能であると判断したからである。
その検証のため、Mk-Ⅱの大気圏突入用のオプションとしてフライング・アーマーを開発し、
ジャブロー攻略戦の後、既に開発されていた試作機MSZ-006X型をベースとして、
ウェーブライダーへの変形機構を持つ「Zガンダム」を完成させることができたのである。

Zガンダムは、宇宙空間から重力下までの連続運用を可能とする破格の汎用性を持つ機体である。
最も大きな特徴は「標準兵装のまま単体で大気圏再突入が可能」だということで、さらに、突入中の機動さえ可能としている。
通常のMSは、大気圏上層の熱圏においては行動を極端に制限されるが、Zガンダムは、その領域においてさえ戦闘能力を有するのである。
この機体にとって幸運だったのは、必要な技術がすべて蓄積されていたことであると言えるだろう。
軽量で堅牢なガンダリウムγ、可変機構に不可欠なムーバブル・フレーム。
そして、それを可能とする資金力や政治的な要請、時流的な環境などが整っていたからこそ、
圧倒的に高性能でありながら、非情に短期間で完成できたのである。
ただし、それはあくまでワンオフの機体だったから可能だったというのも事実であるといえる。
Zガンダムの開発ベースとなったプロトタイプZガンダムは、Mk-Ⅱの入手以前に開発されていた機体で、
アナハイム独自のブロックビルドアップの概念が導入されていた機体である。
これは、機体各部をブロックごとに分割することによって、生産性やメンテナンス効率を向上させようとするものであった。
しかし、各部を独立させることによる弊害も多く、制御系の改善が検討されていた機体でもあった。
そこにムーバブル・フレームの概念が導入され、「MSN-100 百式」のベースデザインが生まれた。
また、カミーユによるプロットが導入されたことにより、TMSとして再設計されることとなったのである。
つまり、Zガンダムは変形に必要なモジュールをムーバブル・フレームによって構成し、必要な兵装やジェネレーター等は、
プロトタイプのものを流用することで、非情に短期間のうちに完成することができたのである。
さらに、Zガンダムの最大の特徴である大気圏突入能力を検証すべくフライング・アーマーが開発され、
ジャブロー攻略戦に実戦投入された。
そして、フライング・アーマーは、大気圏突入時であってもある程度の機動が可能であり、
さらにSFS(Sub Flight System)としても運用することができた。
実際、フライング・アーマーは大気圏内においても、ド・ダイやベースジャバーなどのSFSに匹敵する機動性と
航続距離をMSに持たせることに成功し、Zガンダムがウェーブライダー形態に変形することの有用性を実証したのである。
それらのスペックは、Zガンダムそのものにも継承された。
驚くべきことにZガンダムは、自機が飛翔可能なだけではなく、謝って大気圏突入してしまった百式とともに
熱圏を突破したばかりか、SFSとしても十分に機能して見せたのである。
MSZ-006 ムーバブル・フレーム構造図
Zガンダムは、それまでに一般化していたMSの概念を覆すような基本構造を持っている。
この時期は、連邦軍が独自に開発した技術と公国軍が開発した技術の融合が積極的にはかられた時期であり、
それによってMSの関連技術は飛躍的な発展を遂げた。
そんな中でムーバブル・フレームに代表されるMSの基本構造の抜本的な変革は、
MSというものを非常にフレキシブルなシステムにまで概念化したのである。
ムーバブル・フレームは、ヒンジとしての機能とアクチュエーターとしての機能を併せ持っている。
つまり、関節としての機能を単独で獲得できるため、機体構造そのものを変更する場合においても、
デッドスペースがなくなるのである。しかも、かく関節は実用上必要な機能を内装でき、
一年戦争末期に連邦軍が開発したマグネットコーティング技術が採用されているため、
変形稼働においても支障が生じない時間内で瞬時に変形できる。
また、Zガンダムに採用されるガンダリウムγは、更なる軽量化と高剛性の獲得を実現した。
この新素材の採用がなければ、Zガンダムは機体各部の自重によって機動性や運動性を損ない、
変形に要する時間も短縮できず、実用兵器としては完成できなかったであろう。
Zガンダムに求められていた機能は、常識的にみれば相反する側面を持っている。
しかし、圧倒的な軽量化とムーバブル・フレームのもつフレキシビリティを最大限に活用し、
「変形」することによって、相容れない側面を併せ持つことを可能としたのである。
MSとウェーブライダーは、基本的な構造が異なるばかりでなく、全く違う技術が必要とされる。
しかし、だからこそ双方の特性を同時に実現することによってZガンダムは戦略的な意味を持つ。
これは、この機体の兵器のユニットとしての性格を任意に変更できることを意味する。
これは、それまでの戦術においてはあり得ないことだった。
もっとも端的な例を挙げれば、Zガンダムは自らのMSとしての機動戦闘能力を、自力で戦線に空輸できるのだ。
一年戦争における「ガンダム」の持つ汎用性が、それ以降のMSの指標とされたことは想像に難くないが、
それを最もドラスティックな形で実現した機体こそがZガンダムだったということができるだろう。
無論、アッシマーやギャプランといった機体が存在していることからも、
この時期のTMSが同様のコンセプトに基づいていたことがわかる。
U.C.0080年代以降のMSは、基本的に戦闘能力の拡充が重視され、ビーム兵器やジェネレーターの大出力化が計られていった。
そして、それらを稼働させるためのプロペラントの増加と内装兵器の複合化に伴う機体の大型化が一般的な傾向となっていた。
つまり、「MS」というシステム全体が、複数の要求を満たすために複雑化していったのである。
これは同時に、MSのスペックの悪戯なインフレーションを招くこととなり、ひいてはMS単体の開発費の高騰を招いた。
そして、量産機と試作機、高級機などといったヒエラルキーを決定的なものとし、実効的な戦力の拡充そのものよりも、
フラッグシップ機の開発が偏重されるという、非常に偏った設計コンセプトの蔓延にも結びついていったのである。
Zガンダムが変形するウェーブライダーは、単に大気圏への再突入を可能とするのみならず、
宇宙戦闘機クラスの空間戦闘能力と加速性を併せ持っている。なぜなら、変形することで機体各所に分散配置された
各部バーニア・スラスターのベクトルが機体後方に集中することにより、その全出力を加速のためだけに振り向けられるからである。
さらに大気圏内においては、フライングアーマーと胸部のインテークから大気を取り込む熱核ジェットによって、巡航飛行を可能としている。
ウェーブライダー時の機動は、基本的に機体各所のバーニア・スラスターによって行うが、緊急時の加速や急激な方向転換は、
機体上部の垂直尾翼にあたるロングテールバーニア・スタビライザーによって行う。
このモジュールは、戦後、MSに積極的に導入されたAMBACシステムの一種であるバインダーの概念を更に発展させたもので、
質量移動による方向転換や姿勢制御と同時に、機動も行う画期的なシステムであり、当然、MS形態時にも非常に有効なユニットである。
Zガンダムは、事実上、MSのスペックのインフレーションという傾向の端緒にある機体ではあったが、
機体の軽量化とジェネレーターの大出力化によって絶妙にバランスしているため、
むしろパワーウェイトレシオが重視されたU.C.0100年代以降のMSに近いといえる。
後に開発された系列機の優秀さも相まって、Zガンダムは非常に高く評価されている。
この時期以降、Z系のパイロットは「Z乗り」とも呼ばれ、エースパイロットの代名詞となっていった。
その意味でも、この機体の先見性や優秀さは破格のものであり、MSの進化を先取りしていた機体であるということができる。
Zの変遷

Zガンダムのウェーブライダー形態は、基本的に大気圏再突入のためのものだが、大気圏内での飛行も可能としている。
変形により空力特性が向上するため、高速移動の際には確かに有効だが、機体に十分な翼面積がある訳ではなく、
実際には膨大なプロペラントが必要となる。
そこで、航空能力を併せ持つ「ウェーブシューター」タイプのフライングアーマーなども考案された。
カラバによって少数量産されたZプラスなどは、戦闘機並の空戦能力を持つ機体として再設計されたものだと言われている。
Zガンダムのボディ・ユニットは独自のフレーム構造を持っている。そこには機体の変形機構のほとんどが集中しており、
非常に複雑な構造を持っている。ところがこの構造は、堅牢で自由度が高い上、コピーが容易なため、
この時期に数多くのバリエーションを生み出す要因となっている。
また、アーガマで運用されていた機体自体、時期によって様々な改装が施されているといわれている。
最終更新:2015年02月24日 13:09