『見習い君主の混沌戦線』第7回結果報告(後編)
(やっぱり、戦うのは怖いな……)
第六投石船団の
シューネ・レウコート
は、前回の防衛任務でのオーク達との戦いのことを思い出しながら、心の中でそう呟いた。出来れば、もう危険な任務には行きたくないという想いを抱いていた彼女であるが、かと言って、従騎士としてこの地に派遣されている身である以上、何もしないという訳にもいかない。他の従騎士から色々と励まされたことを思い出し、なんとか自分にも出来そうな任務を探し始める。
(学校設立の協力者募集、という話もあったけど、知らない子供相手に何かを教えるなんて、私には出来そうにないし……)
結局、悩んだ末に彼女は、再びこの街の防衛任務に就くことになった。と言っても、今回は前回とは異なり、まだ明確な被害者が現れた訳でもなければ、「敵」の正体どころか、そもそも「敵」と呼ぶべき存在がいるのかどうかも分からない、そんなあやふやな状態での任務であったため、実質的には「防衛」というよりも「調査」に近い任務であった。
ことの発端は数日前の深夜。カルタキアの領主の館に併設された書庫の中で、不審人物が発見された。その人物(?)はローブを深くかぶった「死神を彷彿とさせるような姿」で、書庫の中で何かを探すような素振りで徘徊していたらしい。深夜の書庫は基本的に施錠されている以上、普通の人間では入ることは出来ない筈であり、不審に思った職員が声をかけると、その「死神のような人物」は即座に姿を消したという。おそらくは投影体だったのではないかと推測されているが、今のところ、出身世界も正体も目的も、何もかもが不明である。
また、それと関係しているのかどうかは分からないが、ここ最近、夕方から夜にかけて、書庫の近辺で何匹かの「不気味な蝙蝠達」が蠢いている姿も発見されている。目撃者達の証言によると、その蝙蝠達もまた、書庫の内側に入り込む隙を伺っているように見えたらしいが、人間が近付くとすぐに逃げていったという。
もともと、領主の館の書庫には様々な特殊な文献が眠っていることもあり、中には危険な魔導書の類いも混ざっているという噂もある。カルタキアは「魔法」が機能しない土地である以上、それが「この世界の魔法師が生み出した魔導書」なのであれば、このカルタキア内でそれが害をもたらす可能性は低いが、「異界の魔導書」だった場合はその限りではないし、仮に前者であったとしても、カルタキアの外に持ち出して混沌災害をもたらす可能性もある以上、領主の館の書庫には地元の従騎士達がそれなりに厳重な警備を敷いている。
にもかかわらず、あっさりとその警備を掻い潜って侵入した者が現れたということは、相当に危険な投影体がこの街に潜んでいる可能性があるという判断から、書庫の警備と同時並行で、町中の人々からも目撃情報を集めるように、という領主のソフィアからの命令が下された。
(それなら、私にも出来るかな……。町中なら、戦いになる可能性は低いだろうし……)
シューネはそう判断した上で、せめて自分に出来ることだけでも頑張ろうと思い、書庫の近辺を中心にひたすら歩き回って、目撃情報を集めることにした。
と言っても、シューネは人と話すこと自体が苦手なので、誰彼構わず話しかけるというのは難しい。まずは遠目に観察して「話しかけても大丈夫な人」かどうかを判断してから話しかけるという前工程が必要になる。彼女は慎重に街行く人々を眺めながら、少しずつ話を聞いて回っていたのだが、そんな中、気になる「音色」が聞こえてくる。
「……ハーモニカ?」
それは、特殊な小型の吹奏楽器の音色であった。一人で同時に複数の音を発することが出来るという意味で、その音色はかなり独特であり、この世界では比較的珍しい楽器である。しかも、聞こえてくるその旋律は、それなりに音楽に精通したシューネですら聞いたことがない、独特の雰囲気を漂わせた曲構成になっていた。
気になったシューネがその音が聞こえる場所へと向かうと、そこでは一人の銀髪の少女(下図)が、何人かの聴衆を前にして、「銀色のハーモニカ」を演奏していた。見た目はシューネとあまり変わらない程度の年頃に見えるが、どこか微妙に浮世離れしたようなオーラをまとっており、全体的な雰囲気から察するに、明らかにカルタキアの地元民とは思えない。
|
+
|
銀髪の少女 |
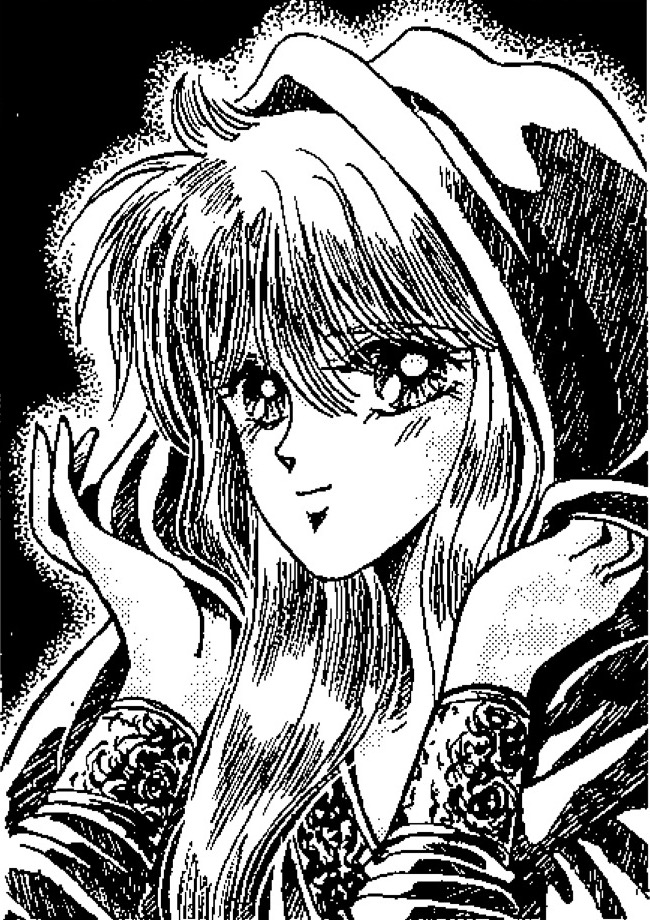
(出典:『イース テーブルトークRPG』 p.114)
|
(アトラタンからの旅人……? それとも……)
見た目は普通の人間のように見えるが、このような珍しい楽器を手にしているという時点で、投影体という可能性も十分にあり得る。だとしたら、今回の事件と直接関わっている者であるかもしれない以上、少なくとも、何も聞かずに放置して良い存在ではないだろう。
シューネがそんな思いを巡らせている中、そのハーモニカの少女は演奏を終え、聴衆達が拍手を送る中、少女はシューネと目が合い、ニコッと微笑む。この機を逃すべきではないと判断したシューネは、すぐにでも声をかけたかったが、まずは心を落ち着かせるため、ひとまず大きく深呼吸する。そして、周囲の聴衆達がその場から去っていく中、意を決して彼女に声をかけた。
「あ、あの……、すごく、良かったです、そ、その、演奏が……」
それが、最初にシューネの口から出てきた言葉であった。これは別に、会話のとっかかりを作ろうとか、相手の好感度を上げてから話の本題を切り出そうとか、そういうことを考えていた訳ではなく、ただ純粋に自分の中から湧き上がった感情が、そのまま口に出てしまっただけだったのだが、それに対してハーモニカの少女も素直に嬉しそうな顔を浮かべつつ、シューネに対して語りかける。
「あなたも、音楽を奏でる人ですよね?」
「え!? あ……、いえ……、まぁ、確かに、その……、か、軽く嗜んではいるというか、い、いや、でも、決して人様に聞かせられる程のものではなくて……」
想定外の質問を投げかけられたことにシューネは動揺しつつ、なんとか必死に冷静さを保とうとしながら、逆に聞き返す。
「……どうして、そう思われたのですか?」
「あなただけは、聞いている時の表情が違ったのです。明らかに『分かっている顔』でした」
シューネとしては、別に他人の演奏に対して音楽的な論評を下そうとしていた訳でもなく、ただ純粋に音楽に聞き入っていただけだったのだが、それでもこの少女から見れば、明らかに「音楽家」としての顔を浮かべながら聞いていたようである。
そして、少女の側はそう告げた上で満足そうな顔でその場を立ち去ろうとするが、そこで慌ててシューネが声をかける。
「あ、あの……、ちょ、ちょっとだけ、話、を、聞いてもらえ、ますか……? いや、別にその、大した話でもないというか、音楽とかとは全然関係ないこと、なん、です……、けど……」
「はい、なんでしょう?」
緊張した様子のシューネに対して、少女はさらっと問い返す。シューネはどうにか気持ちを落ち着かながら、質問を切り出した。
「この辺りで、その……、誰か、怪しい人とか、見かけませんでしたか?」
「怪しい人、ですか?」
「その……、なんというか、死神、みたいな姿というか……、あ、いや、その、私も、実際の姿を見た訳ではないので、はっきりとは分からないんですけど……、その……、よく分からない質問で、ごめんなさい……」
それに対して、ハーモニカの少女は、微妙に意味深な表情を浮かべつつ、静かに呟く。
「死神……」
「な、なにか、心当たりとか、あったり、とか……?」
「その『死神』が、この地で何かを引き起こしているのですか?」
少女のその問いに対して、シューネは書庫の関係者から聞いた話をそのまま伝える。その上で「書庫の近くに出現する蝙蝠」についても言及すると、少女は何かを察したような気配を瞳に宿しつつ、シューネに問いかけた。
「その書庫の中に『イース』と題された本が、何冊かあるのではありませんか?」
「イース……? え、えーっと……、私は、その……、書庫の中に何があるかまでは知らないので、その、なんとも……」
「そうですか。では、もう一つ確認したいのですが、この街に『赤毛の剣士様』はいらっしゃいますか?」
「赤毛、ですか……?」
確かに、今のカルタキアに滞在中の従騎士達の中には、何人か赤毛の者達がいる。しかし、彼女が言っている「赤毛の剣士」なる人物が、その中の誰を指しているのかは分からないし、そもそもシューネも彼等のことをそこまでよく知っている訳ではない。
あまりにも突拍子もない彼女の質問に対して、シューネがどう答えて良いのか分からずに困惑していると、ハーモニカの少女は穏やかな笑みを浮かべながら、静かにこう告げる。
「もし、私の推測が正しければ、その『死神』と『蝙蝠』を引き寄せているのは『イースの本』の中の『トバの章』と『ダビーの章』だと思います。ただ、彼等にその本を与えてはなりません。お気をつけ下さい」
そう告げて、少女はその場から立ち去ろうとする。シューネとしては、まだ詳しい話を色々と聞きたいところなのだが、話が急に広がりすぎて、まず何から聞けば良いのかが分からず、そのまま何も出来ずに硬直してしまう。そうこうしてる間に少女の姿が遠ざかっていく中、シューネは必死に言葉を絞り出した。
「あ、あの……!、あ、あなたの、お名前、は……?」
果たして、それが今回の調査において重要な情報なのかどうかは分からないが、それがシューネの中で咄嗟に出てきた言葉であった。ハーモニカの少女は立ち止まり、振り返りざまに笑顔で答える。
「『レア』です。あなたは?」
「わ、私は……、シューネ! シューネ・レウコートです!」
「では、シューネさん、縁があったら、またお会いしましょう」
レアと名乗ったその少女は、そう言ってシューネの前から去っていく。そんな彼女の後ろ姿を見送りながら、シューネの中で張り詰めていた緊張感が、ようやく解けた。
(よ、よかった……、ちゃんとお話できて……)
シューネは安堵のあまり、その場に崩れ落ちるように座り込む。明らかに何かを知っていそうな彼女からは、出来ればもっと詳しい話が聞きたかったし、可能ならばソフィアの元にまで連れていきたいところではあったが、初対面の相手にそこまで話を展開することは、今のシューネにはまだ難しい。とはいえ、対人恐怖症気味のシューネにとっては、ここまでの話を聞き出せただけでも、大きな進展であったと言えよう。
******
その日の夕方、今回の案件の解決に向けての会合が開かれた。領主のソフィア(下図)の他に、第六投石船団のカエラ(下図)とヴェント・アウレオのエイシス(下図)という三人の指揮官が顔を合わせ、幾人かの従騎士達が集まる中、住民への聞き込み調査に向かっていた者達がそれぞれに集めた情報を報告する。
とはいえ、実際のところ、直接的に今回の事件に関係しそうな情報を集められた者は少なかった。そんな中、シューネが伝えた情報に対しては、皆が強い関心を示す。最初に反応したのは、シューネの上司であるカエラであった。
「そのレアという少女、何者だと思う?」
カエラとしては、実際に会って話をしたシューネの直感的な印象を聞きたかったのだが、シューネには全く見当がついていないため、返答に窮する。
「え、えーっと……、その……」
「今回の事件の黒幕という可能性は、ありえると思うか?」
「い、いえ、そんな人ではない、と思うのですが……」
シューネとしてはそのような可能性までは考えていなかったようだが、いざそう問われると、明確にそうではないと言える根拠もないため、それ以上は何も言えなかった。微妙な沈黙が流れる中、今度はエイシスが口を開く。
「ひとまず、その少女が『悪意のある投影体』であるという可能性を考慮するとしても、実際にその『イースの本』なるものが存在するのか否かについては、確認してみる必要があるでしょう」
エイシスがそう言いながらソフィアに視線を向けると、ソフィアは頷きつつ、傍らにいた秘書官に命じて、蔵書目録を確認させる。
そんな中、エイシスの傍らにいた彼の部下の
コルネリオ・アージェンテーリ
は、シューネの報告の中に出てきた「赤毛の剣士」という言葉が気にかかっていた。
(いや、まさか、ね……)
彼の中では、同郷の同僚のことが一瞬頭をよぎる。一方で、彼と同じようにこの会議の場に参加していた第六投石船団の
グレイス
と、ヴァーミリオン騎士団の
アルス・ギルフォード
の脳裏には、鋼球走破隊の異形の女剣士が思い浮かぶ。
(確かに、あの勇猛壮健なるお嬢さんも赤髪だが……)
(さすがに無関係ですよね、きっと……)
実際のところ、カルタキア在中の従騎士達の中には他にも赤味を帯びた髪の持ち主は何人かいるし、この世界においてもそこまで珍しい髪色ではない以上、それだけで関連付けるのは早計であろう。
一方、星屑十字軍の
リューヌ・エスパス
は、書庫の警備に関する具体的な方針について確認する。
「これまでにも厳重な警備を敷いていたにもかかわらず、内側に侵入されたということは、書庫のどこかに、私達が想定していない『入り込める場所』があるのではないでしょうか? まずは、その侵入路を差出しだして、その経路を塞べきだと思いますが、いかがでしょう?」
確かに、常識的に考えればその通りである。ただ、現実問題として書庫の管理者達も当然、その可能性は考慮した上での対策を講じてはいるが、実際のところ、それらしき「抜け穴」となりそうな場所は見つかっていない。
この点については、ソフィアが回答する。
「おそらく、常識的な手段で入り込めるような場所は存在しない。ただ、もし侵入者が投影体だとすれば、いくらでも方法はある。たとえば、身体を小蝿程度にまで小さくすることが出来るような輩ならば、排気口などから侵入することも出来る。あるいは、もし例の『死神』とやらが幽霊のような存在なのだとすれば、壁を通り抜けてもおかしくはない。更に言えば、もし『我が聖印』と同じように『空間を操る能力』を有していたとしたら、それこそ止めようがないだろう」
実際、「投影体」がどのような能力を有しているのか、ということについては、可能性は無限であり、どうやっても対応しきれない可能性は当然ありうる。
「そもそも、このカルタキアの街の中においてすら、突発的に投影体が出現することはありえるのだ。もしかしたら、書庫の中で突発的に現れてすぐ消えただけの投影体かもしれない。もっとも、だからと言ってそれが無害とは限らないし、周期的にそのような現象を繰り返す投影体もいるらしいから、どちらにしても警戒は必要になるのだがな」
つまり、いくら外側を警備したところで、内側に入り込まれる可能性はどうやっても消せない。一方で、外から新たに(?)入り込もうとしている蝙蝠達のことを考えると、外側の警備もおろそかないは出来ないだろう。
この状況を踏まえた上で、この日の夜の警備に関しては、書庫の内側にエイシス、外側にカエラが配備されることになった。これに対して、最初に手を挙げたのはリューヌである。
「では、私も書庫の内側の警備に加えて下さい」
ありとあらゆる可能性が考えられる以上、何があっても対応出来るようにするためにも、彼等の目的地であると思しき「内側」に潜んで状況を確認する役回りを自分が担おう、と彼女は考えたようである。それに呼応するように、アルスもまた声を手を挙げた。
「私も、今回は書庫内での警備を担当しようと考えています」
以前に秘密結社の魔境で共闘した盟友の宣言に対して、リューヌは嬉しそうな顔を浮かべる。
「今回も頼りにしています、アルスさん」
「こちらこそ、よろしくお願いします」
二人がそんな会話を交わす一方で、今度はグレイスが発言する。
「私は得物が弓なので、やはり『外』ですかね」
蝙蝠が相手ということであれば、確かに弓使いのグレイスにとってはそちらの方が適任だろう。上司であるカエラが外側の警備に回っているのも、当然、同じ理由である。これに対して、彼等と同じ弓使いのコルネリオは、少し迷っている様子であった。
(どんな書物が狙われているのか、目星を付けたいと思ってたんだけど、もうそれらしい情報が出てしまってるからなぁ……)
そんな中、ソフィアに命じられて蔵書目録を調べていた秘書官が、調査結果を報告する。
「少なくとも、明確に『イース』と題された本は所蔵されていないようです。ただ……、『書名不明の書籍』の中に含まれている可能性までは、現時点では分かりません」
この報告に対して、コルネリオが首をかしげつつ問いかける。
「書名が分からないって、どういうこと?」
「こちらの書庫に所蔵されている本の中には『異界から投影された書物』も含まれます。その中には『異界の文字』のまま投影されている本もあるのです」
通常、異界から投影された物品に書かれている文字は「こちら側の世界の文字」に翻訳される形で出現することが多いが、稀に「現地の文字」のまま投影される代物もある。そして、それらの書物の中には、何らかの強大な魔力などを秘めている本も多いらしい。
「一応、一部の異界文字に関しては、既に辞書が作成されており、それを用いれば自力の翻訳も可能なのですが、今のカルタキアにはそこまで多くの文官が揃っていないこともあり、その翻訳作業も最近はあまり進んでおらず、未解明のままの異界魔書も多いのです」
つまり、レアという少女が語っていた内容が真実か否かについて、現時点ですぐには明確な答えが出せない、ということらしい。
その話を踏まえた上で、コルネリオは自身の方針を決めた。
「そういうことなら、僕も外側の警備に回ろうかな」
それは当然、得物の事情もあるだろうが、「書庫の内側から目星を付けるのが難しいなら、むしろ外側から潜入しようとする敵の動向を調べた方が、真実に近付けるかもしれない」という思惑も、彼の中ではあったようである。
こうして、ひとまず「内組」と「外組」の人員配置が決定したところで会議は終わり、シューネをはじめとする市中調査組のこの日の任務は、ひとまず終了となった。
******
書庫内の警備を管轄することになったエイシスは、リューヌとアルスに方針を告げる。
「目撃者の証言によれば、書庫内で発見された『死神』は、声をかけられたと同時に姿を消した、という話だったので、もし発見したとしても、こちらが迂闊に近づけば、また即座に逃げられてしまう可能性が高いでしょう。その正体と目的を突き止めるためにも、まずは書庫内で泳がせて、彼が探している本が何なのかを確認する必要があります」
先刻の会議の話題でも出ていた通り、厳重な警備をくぐり抜けて書庫内に侵入出来る存在である以上、少なくとも「ただの人間」ではない可能性が高い。もし物質としての身体を持たない霊体ならば、そもそも捕まえることは出来ないだろうし、瞬間移動が可能な存在だった場合も、捕縛することは難しい。そのため、今回は「最悪、逃げられても仕方がない」と割り切った上で、今後の対策を考えるための判断材料を手に入れることを第一目標とエイシスは考えていた。
その上で、シューネが手に入れてきた情報に基づいて考えると、その「死神」が探している本は、「異界言語のまま投影された投影書物」である可能性が高いため、そういった「異界魔書」が所蔵されている地下室の書庫を重点的に警備することにした。
「アルスさん、その盾は……?」
リューヌはアルスの装備を見て、思わずそう問いかけた。この日のアルスは、身を隠すためにいつもより大きめの外套に身を包んだ上で、いつもの「身体の半分以上を覆い隠す程の大型の盾」ではなく、右手に固定する形状の小型のバックラーを装備している。
「さすがに、いつもの盾では、狭い書庫の中だと戦いにくいですからね」
どうやら、彼女が継承する「ギルフォード流わらしべ盾術」は、盾の大きさにはこだわらないらしい。ひとまず、エイシスはリューヌとアルスに(身体に頑健性を与える)《壮健の印》を施し、二人は互いの巡回経路を確認した上で、物音を立てないように気をつけながら、地下書庫を巡回する。
書棚と書棚の間の空間は狭く、部屋中にびっしりと異界魔書が詰め込まれた異様な空間に潜みながら、リューヌは微妙に表情を曇らせる。
(この書庫内の全てが「混沌の産物」なんですよね……)
聖印教会の一員であるリューヌにとって、大量の投影物品に囲まれた空間というのは、さすがに馴染みがない。教会内のラディカルな教派の信徒達であれば、見た瞬間に即座に全て焼き払おうとするだろう。その意味では、リューヌがこの任務に就くことが認められたということは、それだけ彼女が(この書庫の主である)ソフィアから信頼されていることの証でもある。
この世界に害を与えるかもしれない危険な物品を目の当たりにしながら、複雑な心境で隠密警備を続けていく中、やがてリューヌは、部屋中に広がる混沌の気配の中から、新たに微妙な「揺らぎ」を感じ取る。
(これは……、新たな混沌の気配? でも、何かが投影された時のような混沌核の収束の気配とは違うような……)
その気配のする方面へと彼女が向かうと、そこには確かにアルスともエイシスともシルエットの異なる何者かの姿があった。地下室内の灯りは数箇所しか付けられていないため、その姿は確認しがたいが、全く足音も立てずに少しずつ微妙に移動しているように見える。
リューヌは声を押し殺しつつ、しばらく凝視を続けていると、やがてその数少ない「灯り」の近くに来た時点で、ようやくその外形を確認するに至る。そこにいたのは「『死神』を連想させるような不気味なローブをまとった何か」(下図)であった。
|
+
|
死神のような何か |

(出典:『イース テーブルトークRPG』 p.91)
|
(あれは……、死神!?)
その「死神」は周囲を物色するように首を動かしながら、書庫内の徘徊を続けている。足元はローブによって隠れているため見えないが、身体が全く上下に動いていないため、浮いた状態でスライド移動しているようにも見える。
リューヌが黙って観察を続ける中、やがてその「死神」は書庫の一角に到達した時点で、動きを止め、ゆっくりとその手を書棚へと伸ばし、一冊の本を手に取ろうとする。その瞬間、リューヌは書庫の影から飛び出した。
「侵入者です!!」
彼女はそう叫ぶと同時に、「死神」へと駆け寄り、短刀を突きつけながら言い放つ。
「脅すような真似をして申し訳ございませんが、貴方を拘束させていただきます」
だが、次の瞬間、彼女の目の前からその「死神」は即座に消滅した。
(……瞬間移動!? それとも、姿を透明化させた……?)
リューヌは判断に迷う。しかし、その直後に彼女は自身の背後にある一つ先のブロックの書庫列の端から、新たな気配を感じ取った。振り返ってみると、突き当りの壁から球体状の火炎の塊が現れ、彼女に向かって飛び込んでくる。
「えぇ!?」
何が起きたのか分からず困惑する彼女であったが、ここで隣の書棚の影から、一陣の風のように一人の少女がリューヌを庇うように飛び出して来る。先刻のリューヌの声に応じて駆けつけたアルスであった。
アルスは身を挺してリューヌの前に立ちはだかり、バックラーを掲げてその火炎球を受け止める。盾では炎の威力は防げず、激しい炎が彼女の身体を焼け焦がそうとするが、パラディンとしての力に目覚めていた彼女の身体は通常の従騎士を遥かに凌ぐほどに強化されており、更にそこに《壮健の印》による付加効果も相まって、アルスの身体は火炎球の猛威をあっさりと耐えきった。
「アルスさん!」
「大丈夫です。それより、侵入者は……?」
二人は周囲を見渡すと、リューヌは遠く離れた別の書棚の脇に、再び「死神」の姿を発見する。
「いました!」
リューヌはそう言って駆け出すが、彼女がその書棚の場所まで辿り着く前に、再びその「死神」は姿を消し、最初の書棚の場所に再び現れる。どうやら「瞬間移動」が正解だったらしい。
(これは、かなり厄介な相手……)
やむなくリューヌは元の書棚へと戻ろうとするが、その間に「死神」は書棚の中にあった一冊の本を手にする。だが、その直後、まだその書棚に近くにいたアルスが、右手のバックラーで死神に対して全力で殴りかかった。
「ギルフォード流わらしべ盾術奥義!『アンパンチ』!!」
彼女のその拳が死神に直撃しようとした瞬間、死神は再び姿を消す。しかし、この時点で死神が手にしていた本(下図)は、その場にポトリと落ちた。ひとまずアルスはその本を拾って確保した上で周囲を見渡すが、「死神」の姿が見当たらない。
|
+
|
謎の本 |

(出典:『イース テーブルトークRPG』 p.170)
|
そうこうしている間に、リューヌと、そして更に遠方からエイシスが、アルスの元へと駆け寄ってきた。リューヌとアルスがエイシスに事情を告げると、エイシスは推論を語り始める。
「おそらく、その『死神』は瞬間移動と火炎攻撃の能力を持つ投影体なのでしょう。その上で、
この本を一度手にした状態で、殴られそうになった時に『本をその場に遺した状態』で瞬間移動で逃げたということは、二つの可能性が考えられます。一つは、この本を手にしてみたものの、それが自分の探していた本ではなかった、と判断した可能性。そしてもう一つは、瞬間移動の際には『本人以外のもの』を持ったまま移動出来ない、という可能性です」
後者の場合、今の時点でアルスが手にしている本が「死神の目的物」である可能性が高い以上、この本の正体について確認する必要がある。そのため、ひとまずエイシスがその本を預かり、この地下の書庫の警備はリューヌとアルスに任せた上で、エイシスは領主の館で待機しているソフィアの元へとその本を届けることにした。
******
一方、書庫の外側では、書庫の入口付近にグレイス、裏口付近にカエラが常駐し、コルネリオが周囲を巡回しつつ、状況に応じて臨機応変に対応するという形での警備がおこなわれていた。
入口担当となったグレイスは、物陰に潜んだ状態で、扉付近に対して警備の目を光らせる。目撃者の証言によると、蝙蝠が発見されたのはいずれもこの入口付近であり、個体数もまばらで、どこから来たのかも分からず、人に気付かれるとすぐに飛び去り、闇に紛れてその姿も消えてしまう、という話であった。
そして、この日の夜もまた、前回目撃されたのと同じくらいの時間帯に差し掛かったところで、入口付近の軒下に一体の蝙蝠が潜んでいるのを、グレイスはあっさりと発見する。
(何体いるのか分からない以上、闇雲に撃ち落としても意味がない……)
グレイスはそう判断した上で、いつでも弓を放てる準備を整えた上で、じっくりとその蝙蝠の動きを観察するが、黙したまま、全く動こうとはしない。そうこうしている間に、書庫の入口の奥から、物音が聞こえてくる。
(誰かが、内側から外に出ようとしている……? だとしたら、ここで……?)
じっと蝙蝠の動きを注視していると、蝙蝠もその音を察したのか、微妙に体勢を変え、扉に向かって羽ばたこうとしているように見える。グレイスはその動きを見た上で、蝙蝠が扉の隙間に入り込む場合のルートをイメージした上で、矢をつがえる。そして扉が開いた瞬間、蝙蝠は軒下から飛び立つが、その動きを完全に読み切っていたグレイスはすぐさま矢を放つと、その一矢は見事に蝙蝠の右側の羽に直撃し、蝙蝠は奇声を上げながら真下へと墜落した。
「……お見事です」
その声の主は、開いた扉の奥から現れたエイシスであった。彼は、先刻アルスが確保した本をソフィアの元へと届けるために外に出ようとしたところで、このグレイスの妙技を目の当たりにすることになったのである。エイシスはすぐさま屈み込んで、足元で苦しみながらのたうち回っている蝙蝠を凝視する。そして、駆け寄ってきたグレイスに対して、こう告げた。
「見た目は普通の蝙蝠と変わらないようですが、明らかに混沌の気配を感じますね。それに、どこか挙動が不自然なようにも見える……」
「羽を射抜かれた状態の蝙蝠」という存在自体、あまり頻繁に見られる光景ではない以上、その状態でどのような苦しみ方を見せるのが「自然」なのか、ということは普通の人間には判別しにくいことなのだが、医学に通じているエイシスには、その辺りの微細な峻別も可能らしい。
そんなエイシスに対して、グレイスは懐から「鈴の付いた紐」を取り出しつつ、問いかけた。
「この蝙蝠の傷、治すことは可能ですか?」
エイシスはその鈴紐を見た瞬間、グレイスのその質問の意味を即座に理解した上で、奇声を上げながら暴れる蝙蝠の足と羽を抑えながらグレイスに向けて差し出しつつ、答える。
「大丈夫です。どうぞ」
そう言われたグレイスは、蝙蝠の身体に鈴紐を巻き付ける。そして、完全に固定されたのを確認した上で、エイシスは《治癒の印》を蝙蝠に施していく。そうこうしている間に、コルネリオがその現場へと駆け込んできた。
「何か今、変な鳴き声が……、って、あれ? エイシス様?」
「内側」担当のエイシスがいることにコルネリオは少し驚くが、そんな彼に対してエイシスは(グレイスに対して目配せしつつ)こう告げる。
「今からこの蝙蝠を放つので、追えるところまで追って下さい」
エイシスがそう言って、羽の傷が癒えた蝙蝠を解放すると、蝙蝠はリンリンと鈴音を鳴らしながら、書庫から遠ざかるように飛び去っていく。
「分かりました! あの音を辿ればいいんですね!」
そう言って、コルネリオは蝙蝠の後を追い、走り去って行く。そしてエイシスは、書庫の反対側を警備しているカエラと、書庫に併設された領主の館で待機っしているソフィアのに元に、この情報を伝えに向かうことにした。
******
(あの蝙蝠は、何のために書庫に入ろうとしていたんだろう……?)
飛び去っていく蝙蝠を追いながら、コルネリオはそんな疑念を脳裏に巡らせていた。通常の蝙蝠であれば「本」に興味を持つということはありえない。だとすると、本に込められている何らかの魔力に吸い寄せられているのか、蝙蝠を誰かが使役して本を盗み出そうとしているのか、それとも、発見された蝙蝠の正体が「蝙蝠に姿を変えた異界人」なのか。今のところ、可能性は無限である。だからこそ、この蝙蝠が向かった先を可能な限り特定することで、その正体の手掛かり掴みたいと考えていた。
無論、蝙蝠の飛行速度は人間の足を遥かに凌駕している以上、そのまま街の外にまで出られたら、さすがに追いかけようがない。だが、その鈴の音は、街の郊外の一角のあたりで、パタリと止まった。
(飛ぶのをやめた……? それとも、自力で鈴を外したのか……?)
コルネリオはひとまず、最後に音が聞こえた区画の辺りに向かって走り続ける。すると、やがて前方から、誰かの足音が聞こえてきた。目を凝らしてその方面を見ると、比較的小柄な(コルネリオと同じくらいの身長の?)人影のように見える。現状、夜間外出が禁じられている訳でもない以上、ごく普通の一般市民の可能性もあるのだが、コルネリオはなんとなく「常人とは異なる気配」を感じ取っていた。だが、この日は月が雲に隠れており、その姿が確認しにくい。
(よし……、こういう時こそ、この聖印で……)
先日、自身の聖印を第二段階まで覚醒させたばかりのコルネリオは、その場で聖印を現出させた上で高く掲げて、辺り一面を照らす。すると、足音のする方向から見えてきたのは、一人の「銀髪の少女」(下図)の姿であった。彼女は一冊の「本」を手にしている。
|
+
|
銀髪の少女 |
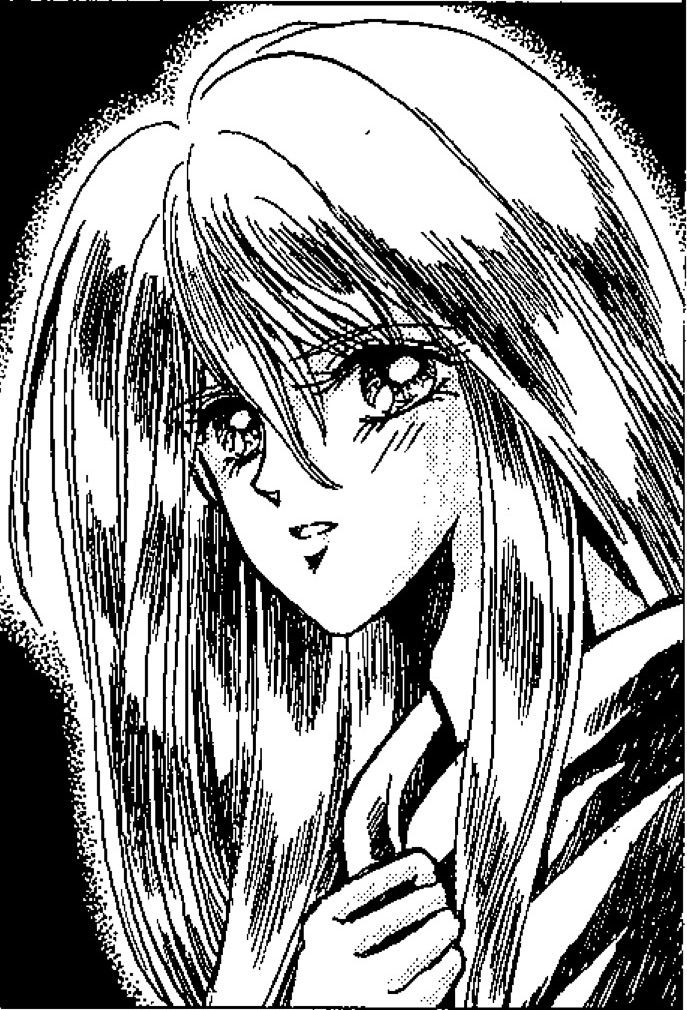
(出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.137)
|
(本を持った、銀髪の女の子……?)
彼女の姿を目の当たりにしたコルネリオは、即座に声をかける。
「そこの君!」
「……はい」
「もしかして、シューネさんが言っていた『レア』っていうのは、君のこと?」
その質問に対して、少女は一瞬の間の後に、穏やかな笑みを浮かべつつ、コルネリオへと近付いて来る。
「……そうですか、レアもここに来ているのですね」
彼女はそう呟きながら、手にしていた本(下図)をコルネリオに対して差し出した。
|
+
|
謎の本 |

(出典:『イース テーブルトークRPG』 p.170)
|
「この本は、あなたにお預けします」
「え?」
「あなたの掲げるその光の紋章は、きっと、この世界を救うための輝き。あなたであればきっと、この本を正しく用いることが出来るでしょう」
初対面の少女に唐突にそう言われたコルネリオは、困惑しながらもその本を受け取る。その表紙には、見たことのない記号のような文字が記されていた。
「えーっと……、これって……、もしかして『イースの本』ってやつ?」
「はい。これは『ハダルの章』。全ての始まりの章です。そしておそらく、この街には……」
銀髪の少女がそう答えている途中で、コルネリオの視線の端に、何体かの蝙蝠が飛んでいる姿が映る。鈴の音は鳴らしていないが、明らかに先刻の蝙蝠と同種の個体のように思えた。
「あれは……!」
コルネリオはひとまず受け取った本を握りつつ、蝙蝠達を追い始める。この少女にはまだ聞かねばならないことは山のようにあるが、ひとまず今は、当初の任務を果たさなければならない。
「ごめん! ちょっと待ってて!」
コルネリオは少女にそう告げたうえで、聖印を掲げて周囲を照らした状態のまま、蝙蝠の群体を必死で追走していく。すると、やがて路地裏の一角に差し掛かったところで、再び「鈴の音」が聞こえてきた。
「そこか!」
彼がその音のする区画へと向かうと、そこには一つの鈴の音と共に、数十体もの蝙蝠達が蠢いている光景が広がっていた。
「え……? こ、こんなに……?」
あまりにも不気味なその光景にコルネリオは驚いている中、そんな彼の目の前で、その蝙蝠達は一斉に「結集」し、そして巨大な一体の怪物へと「合体」する(下図)。それは、巨大な翼を生やした蝙蝠の擬人化体とも言うべき禍々しい姿であった(なお、この合体の過程で「鈴紐のついた蝙蝠」もその中に吸収され、鈴紐はその場に落ちて転がっていた)。
|
+
|
蝙蝠が合体した怪物 |

(出典:『イース テーブルトークRPG』 p.97)
|
「……!?」
目の前で起きたその怪現象に、思わずコルネリオは絶句する。そんな彼に対して怪物があからさまな敵意を向けてきたことで、ひとまず距離を取りつつ、弓で応戦しようと考えたが、問題は手に持っている「謎の本」である。
(この本を抱えたままじゃ、弓は使えない。でも、あの怪物がこの本を狙ってる可能性がある以上、手放す訳にもいかない……)
判断に迷ったコルネリオに対して、その怪物が鋭利な爪の生えた右腕で襲いかかろうとする。しかし、その次の瞬間、唐突にコルネリオの目の前の光景が一変した。
「え……!?」
郊外の路地裏にいた筈の彼の視界が、唐突に「領主の館と書庫の間の街道」へと切り替わり、そして目の前には領主のソフィアの姿があった。
「驚かせてしまって、すまない。今、『カエラと何人かの従騎士達』を『お主』と入れ替えさせてもらった」
エイシスからの報告を受けたソフィアは、ひとまず領主の館を警備していた従騎士達の中から、一人をカエラの代役としての「書庫の裏口の警備役」に回した上で、他の従騎士達とカエラを「鈴を付けた蝙蝠」の探索役として、飛び去った方面へと向かわせようと考えていた。幸い、コルネリオが聖印を空に掲げたことで、彼の現在位置はすぐに把握出来たのだが、カエラ達を向かわせようとしたところで、コルネリオの聖印からソフィアは「不穏な気配」を感じ取り、即座に《瞬換の印》を用いて、彼女達とコルネリオの居場所を入れ替えたのである。
(僕の聖印を見ただけで、僕が危機に陥っているということが分かった、ということ……?)
普通は、たとえ間近で聖印を見ていたとしても、そこまでのことを読み取ることは出来ない。それを、遠く離れた場所に現れた聖印を見ただけで感じ取ることが出来たということは、やはり、このソフィアという少女は「ただの君主」ではないようである。
「それで、今、『お前のいた場所』では何が起きている? 状況によっては、更に増援を差し向けることにするが」
「えっと……、その……、蝙蝠の大群が、一つに集まって、巨大な怪物になって……」
「ほう? それで、その本は?」
ソフィアがそう言ってコルネリオの本を指差すと、コルネリオは即座に少女のことを思い出す。
「……そうだ! 彼女のところに行かないと!」
蝙蝠の怪物の件はひとまずカエラ達に任せた上で、銀髪の少女から話の続きを聞くべく、コルネリオは再び、聖印を掲げた状態のまま、先刻の区画へと向かって走り出して行った。
******
だが、コルネリオが「銀髪の少女」のいた場所へと辿り着いた時には、既に彼女の姿はどこにもなかった。一方で、蝙蝠の怪物はカエラ達の手によって討伐・浄化された。幸いにも、その戦いで死者は出なかったが、それでも「捕獲を試みる余裕はなかった」とカエラが断言する程度には、手強い相手だったらしい。そして、この日の夜は、「蝙蝠」も「死神」も、再び書庫の近辺に出現することはなかった。
その後、「コルネリオが受け取った本」と「アルスが確保した(「死神」が手にしていた)本」を確認してみたところ、背表紙には明らかに同じ文字が記されている一方で、表紙には異なる文字と、そして似たような装飾が施されていた。その上で、更に書庫の中を調べてみたところ、「背表紙に同じ文字が記された本」は他に3冊存在していたことが判明する。
「ひとまずは、この5冊の内容を調べる必要があるな」
ソフィアはそう呟きつつ、司書の者達に、これらの書物に記された文字がどこの世界の文字なのかの解析を命じる。一方で、まだ「死神」が捕まっていないこともあり、書庫の内外の警戒体勢もしばらくの間はそのまま継続することになった。
☆合計達成値:85(23[加算分]+62[今回分])/100
→生活レベル1減少、このまま次回に継続(ただし、目標値は上昇)
※なお、後述の事情により、次回のCFは特殊なクエストとなる
先日まで、飛空船「ルルーシュ」の船長としてドクロの飛空船の行方を探っていた金剛不壊の
ウェーリー・フリード
は、肝心の敵船との決戦を前にして、今までに自分がまとめた諸々の調査資料をラマンに託した上で、あっさりと船長の立場を返上した。彼にしてみれば、自分が果たせる役割はあくまで「船同士の戦闘」の指揮であり、内側から切り崩すという方針が確定した以上、あとはラマン達に任せた方が良い、と判断したらしい。
それに加えて、仕事続きの日々に疲れていた彼としては、この辺りでそろそろ休暇がほしいと考えていたため、諸々の引き継ぎを終えた後は、しばらく宿舎の自室で引き篭もる算段であった。
「カルタキアに来る前は、気楽で良かったな……」
久しぶりに自室のベッドで横たわりながら、かつての穏やかな日々を思い出す。この地に来て以来、機械獣や飛空船との戦いが続き、ウェーリーは精神的にかなり疲弊していた。彼は自身の武功や名声には無頓着だが、いざ戦場に立った時には、可能な限り味方の犠牲を少なくするために常に思考を巡らせている。その結果として、いずれの任地においても彼の戦術は功を奏し、作戦の遂行に大きく貢献し続けた。だからこそ、もうそろそろこのタイミングで「長い休暇」をもらっても良いだろう、と彼は考えていたのである。
「正直、数年分は働いた気分だよ……。とりあえず、紅茶でも買いに行こうかな」
彼はそう呟きつつ、ゆっくりとベッドから起き上がり、最低限の身支度をして、街の市場へと向かう。すると、その途上で見覚えのある人物が、彼に声をかけてきた。
「よぉ! 船長じゃないか。これから討伐戦に向けての軍議か?」
その声の主は、先日の飛空船の調査任務で同行していたヴェント・アウレオの
アイリエッタ・ロイヤル・フォーチュン
である(なお、この時点ではまだドクロの飛空船の浄化作戦は遂行されていない)。彼女の手には、何やらジャラジャラと音を立てている布袋が握られていた。
「私はもう船長ではないよ。討伐戦には参加しないからね」
「え? そうなのか?」
「そのことを知らないということは、キミも参加していないようだね」
「あぁ。まぁ、そうだな。アタシはアタシで、ちょっとやりたいことが出来たから。あっちは騎士級以上の君主が三人もいるんだから、どうとでもなるだろうし」
「それは同感だね。ところで……」
ウェーリーは、アイリエッタが持っている布袋を指差す。
「その荷物はなんだい? 何やら物々しい音が響いているけど」
「あー、これはな、釘だよ、釘」
そう言ってアイリエッタが布袋を開くと、そこには大量の釘が詰め込まれていた。ウェーリーが怪訝そうな顔を浮かべる中、彼女は話を続ける。
「これから、学校を作ることになってさ」
「学校?」
「あぁ。今、この街には、世界の色んなところから、色んな連中が集まってるだろ? だから、そいつらが知ってることとか、身につけてきた技とか、そういうのをこの街の子供達に伝えるための学校を作ろうって話になったんだよ」
10年前の災害以来、この街の人々は「今」を生きることに必死で、子供達の教育にまで手が回る程の余裕がなかった。しかし、ようやく街全体の活気が取り戻されつつある中、未来を担う子供達に向けての投資に力を注ぐだけの余力が出来てきた、ということらしい。実際、従騎士達の中には上流階級出身であるが故に博識な者達も多く、講師役を務められそうな者も少なくない。
「まぁ、アタシも生まれた時からずっと船の上で過ごしてきたから、ちゃんとした教育ってのを受けたことはないんだよ。だから、アタシ自身は何も教えられるような立場じゃないんだけど、せめて何か役に立てることはないかな、って思って、何か出来ることはないかって相談したら、勉強するための設備が足りないって話になってさ」
「なるほど……、ということは、その釘は、そのための?」
「あぁ。勉強するために必要な、子供用の机や椅子が大量に必要になるって聞いたから、それを手伝うことにしたんだ。これまでにも、生きるために必要な道具とかは自分達で作ってきたし、船大工の手伝いとかもやってきたから、こういう作業なら役に立てるかなって」
現状の予定としては、空き家となった旧孤児院の建物を改造して仮校舎とする予定だが、もともと必要最低限の家具しかなかった建物なので、せめて子供達が集中して勉強出来るような机と椅子は新しく用意する必要があった。しかし、これまでこのカルタキアの中で「子供用の勉強机」なるものの需要が殆どなかったため、商品としては殆ど出回っておらず、自力で作ることにしたのである。
「そういや、あんた、次の任務はもう決まってんのか?」
「いや、しばらくは休暇をもらおうかと……」
「なんだ、暇なのか。だったら、あんたも先生になったらどうだ? 頭いいんだろ?」
「いや、だから、しばらくは休暇を……」
二人がそんな話をしている中、そこに星屑十字軍の
リーゼロッテ
が通りかかる。
「お前達も、学校設立に関わっているのか?」
どうやら、二人の話が微妙に聞こえていたらしい。そして、リーゼロッテもまた、今回の学校設立に積極的に協力している従騎士の一人であった。
「あぁ。こいつ、金剛不壊のウェーリーって奴だけど、すっげー頭いいんだぜ。たぶん」
実際のところ、アイリエッタにはウェーリーの智謀がどれほどのものかは分かっていない。だが、空賊戦の時に彼が立てた策によって多くの者達が救われたことは、その身で実感していた。
そして、その名に対してリーゼロッテも反応する。
「なるほど、聞いたことがある。貴君がルイス・ウィルドールと並ぶ金剛不壊の二大軍師の一人、ウェーリー・フリードか」
どうやらウェーリーの名は、既にカルタキアではそれなりに知られてしまっているらしい。
「いや、私はまだ未熟だし、誰かに何かを教えたこともないし、そもそも口下手だから、教師役が務まるとはとても……」
ウェーリーはそう言って断ろうとするが、そんな彼に対して、リーゼロッテは冊子状にまとめた一束の紙を差し出す。
「これは、私がまとめた教師用の指導書だ。参考程度にはなるだろう」
リーゼロッテは今回の学校設立にあたって、教科書の制作を買って出ていたのだが、その過程でこういった書物の制作にまで至っていた。
彼女の(無意識の)「圧」に押された結果、ウェーリーは戸惑いながらもその指導書を受け取りつつも、まだ逡巡した表情を浮かべている。
「しかし、私の言うことを子供達が聞いてくれるだろうか……」
それに対して、横からアイリエッタが更にダメ押しの一言を投げかけた。
「イカに言うこと聞かせるよりは楽だろ?」
「……まぁ、それはそうかもしれない」
前回、巨大飛行イカを調教していた時のことを思い出しながら、ウェーリーはしぶしぶ教師役を引き受けることになり、リーゼロッテはそんな彼に対して、学校設立計画の現状と今後の開講予定日などに関して、事細かに説明するのであった。
******
その後、宿舎の自室へと戻ったリーゼロッテは、机の上に積まれた大量の紙を目の当たりにした上で、気合を入れてペンを手にする。
「さぁ、今夜中に、歴史の教科書だけでも写本を終わらせなければ!」
エーラムのような文明の最先端の街ならばともかく、辺境の地であるカルタキアに活版印刷所などが存在する筈もない以上、教科書は全て手で書き写すことで量産していくしかない。彼女は、文字の練習帳から、算術、地理、歴史など、様々な分野の教科書を、様々な講師担当者と相談した上で自力で作成しつつ、その書き写し作業をも自力で続けていた。それは必然的に、途方も無い根気と集中力を必要とする。
そんな彼女の部屋に、同じ星屑十字軍の
ニナ・ブラン
が来訪する。彼女もまた今回の学校設立計画の参加者の一員であり、子供達に、日常生活で使えそうな応急手当などの技術の指南役を任されることになった身である。
「あのー、この間お願いした医術の入門書の件なんですけど……」
そう言っておずおずと入室したニナに対して、リーゼロッテは背中を向けた状態で作業を続けたまま、淡々と答える。
「それなら、もう予定していた分の写本は終わっている。そこの右側の棚の上から二番目だ」
「えぇっ!? もう、ですか?」
ニナとしては、自分が発注した入門書の写本を手伝うつもりで来たのだが、ニナの予想を遥かに上回る速度でその作業が完了していたことに対して、驚きの声を上げる。その上で、実際にその棚にあった入門書を見てみると、包帯の巻き方やマッサージの方法などについての説明が、図入りで一冊ずつ丁寧に描かれている。
「あ、ありがとうございます! でも、大丈夫ですか? もし良ければ、私も他の教科書の書き写しとか、お手伝いしましょうか?」
「いや、それには及ばない。お前の腕を信用しない訳ではないが、私は、自分で作るものは、きちんと最後まで自分の手で仕上げたいんだ」
実際のところ、書き写し作業だけなら、頼もうと思えば頼める相手はいくらでもいる。だが、読む子供達のことを考えた上で、一冊一冊の品質という点で妥協したくないらしい。
ちなみに、リーゼロッテがここまで教育に情熱を持って取り組もうとしているのは、自分自身が最初は無学な村娘だったからこそ、後に君主の元で教育を受けたことで様々な知識を身に付けることが出来たことの恩恵の深さを実感しているからでもある。そんな彼女の熱意が込められた背中を目の当たりにしつつ、ニナは(リーゼロッテの目には見えていないことを分かった上で)改めて頭を深々と下げる。
「本当に、ありがとうございます。この入門書、しっかりと役立たせて頂きます。ただ、リーゼロッテさんご自身も、無理してお身体を壊さないように、お願いします」
「あぁ、そうだな。これだけ偉そうな医術書を書いた者が『医者の不養生』となってしまっては、書物自体の説得力も無くなってしまう」
リーゼロッテは密かに苦笑しながらそう答えつつ、書き写し作業を続け、ニナは静かに彼女の部屋を後にする。
(こんなに丁寧に教材を作ってくれたんだから、私も頑張らないと!)
ニナはそう決意を新たにしつつ、今回の学校建設の責任者の一人でもあるレオノールの元へと打ち合わせに行こうとする。
(レオノール様は、どんなお話をされるんだろう? ワイスさんも、何か特別な講義を準備してるみたいだったし、色々と参考になるかも……)
そんなことを考えながら宿舎の廊下を歩いているところで、ふと、見知らぬ一人の少女が彼女に声をかけてきた。
「あの……、ニナ・ブランさん、ですか?」
それは、金色の瞳と赤い髪を持つ、ニナと同じかそれ以上に幼い風貌の少女であった。
「はい、そうですけど……、あなたは?」
「僕は
カシュ・コチータ
。幽幻の血盟の従騎士です。今回の学校建設計画にあたって、ニナさんのお手伝いをさせて頂けないかと思って、ご挨拶にきました」
カシュはニナより2歳年下の14歳。かつて祖国を失い、行き場をなくしていたところをソフィアに拾われた身であり、まだこれといった功績も上げてないが、少しでも自分に出来ることを探そうとして、今回の計画に参加することになったらしい。
純粋な瞳でニナを見つめながらカシュがそう伝えると、その唐突な申し出に対して、ニナはやや動揺する。
「え!? 私の? ど、どうしてですか? 講師の担当者なら、私以外にも沢山いるのに……」
「僕、一応、治療については少しだけ嗜んでるです。というか、それくらいしか出来ることがないから、出来れば、その技術を役立たせられる役回りはないかと思って調べてみたら、ニナさんが医療の実践講座のようなものを開かれるという話を聞いたので、それなら、僕も助手として、少しはお役に立てるもしれない、と思ったんです」
「あぁ、なるほど……」
確かに、現時点で治療関係の講座を開く予定なのは、ニナだけである。とはいえ、日頃は従騎士内でもどちらかと言えば「妹」的な存在として扱われやすいニナにしてみれば、いきなり年下の少女が自分の下で助手として働く、という状況が、なかなかイメージしがたいようで、彼女の意図を理解した上でも、まだ少し困惑していた。
「お邪魔でしたら、無理にとは言えませんけど……」
「い、いえ、そんなことはないです! ぜひ、一緒に協力して、子供達のために頑張りましょう!」
こうして、ニナにとっては初めての「妹分」との共同戦線が形成されることになった。
******
その頃、ニナやリーゼロッテの同僚である星屑十字軍の
リュディガー・グランツ
は、ややバツが悪そうな顔で、今回の学校建設の責任者の一人であるレオノールの元へと向かおうとしていた。
彼はここしばらく、あまり表立った任務には加わらず、後方支援に回っていた。というのも、彼はもともと「ヒト型の投影体」との戦いには抵抗があり、このカルタキアにおける戦いに関して、少し色々と考える時間がほしかったらしい。
(他の部隊が参加した作戦ではヒトもいたらしいし、おれは……、「そこにいるだけのヒト」に刃は向けられないなぁ……)
聖印教会の教義としては、どんな形状の投影体であろうと、混沌の産物は浄化すべき存在とされている(
皇帝聖印の成立を最優先するのも、そのためである)。しかし、リュディガーの中では、何の悪意もなくこの世界に投影されただけの存在を問答無用で虐殺することに対する抵抗感を拭えずにいた。
そんな葛藤を抱きつつ、ひとまず今回は戦いとは無縁な学校建設に協力するためにレオノールの私室の入口前に到着したところで、同僚の
ローレン・エドワルド
と遭遇する。彼もまた、今回の学校設立に協力しようとしていたらしい。
「あ、ローレン君……」
「おや、貴殿もこちらに来られていたのですね」
ローレンが本格的に任務に参加するようになったのとリュディガーが前線から一旦退いたのがほぼ同じタイミングだったので、カルタキアで顔を合わせるのは、今回が初めてであった。
「……ここ最近、成長痛が辛くて、大した仕事が出来なかったんです。情けないことですが」
さすがに「(ヒト型の)投影体と戦えない」と公言する訳にはいかないため、ひとまずリュディガーはそう言ってごまかすことにした。リュディガーの特異体質については星屑十字軍の中ではそれなりに知られているため、ローレンもその説明でひとまずは納得する。
「なるほど。そういえば、前に会った時よりも背が伸びてるというか、微妙に袖が足りなくなっていますね。成長痛は辛いでしょうが、あまりにも酷いようだったら鎮痛剤も処方しますので、いつでもご相談下さい」
医術に通じているローレンからのその言葉に対して、リュディガーが尚更バツが悪そうな顔を浮かべているところで、部屋の中からレオノール(下図)が現れる。
「あぁ、二人共よく来てくれたね。とりあえず、これがリーゼロッテが用意してくれた指南書だから、まずはこれに目を通しておいてほしい」
レオノールがそう言って冊子を二人に見せたところで、ローレンが問いかける。
「授業の割り振りや形式などは、どのような形になる予定なのでしょうか?」
「うん、その件なんだけどね。君達には、僕の授業を受ける子供達に対して、個別指導という形での補佐役をお願いしたいんだ。基本的には僕は年少組の授業を担当する予定なんだけど、これまで育ってきた環境が全然違う子供達が集まる以上、どうしても理解度に差が出来てしまうと思う。だから、適宜個別に対応するための人員がほしいんだよ」
ちなみに、レオノールが年少組を担当することになったのは、彼と同世代の子供達の中には「自分と同じかそれ以下の歳の講師に教えを請う」ということに抵抗のある者もいるだろう、という配慮である。
続いて、今度はリュディガーが冊子に目を通しながら問いかけた。
「教える内容は、文字の読み書きや簡単な計算などで良いのでしょうか?」
「そうだね。それ以上のことを知りたい子は、ワイスのクラスに回ってもらうことにしよう。ただ、出来ればそれ以外にも、子供達の抱えている悩み事や相談事にも応じてほしい。特に孤児院の子供達は、なかなか相談出来る相手もいなくて困っているかもしれないしね」
確かに、そういった方面にまで配慮するとなれば、個別の指導員は必須だろう。リュディガーもローレンも、自分の子供の頃のことを思い出しながら、どのような相談を持ちかけられることになるのか、それぞれに考えを巡らせ始めるのであった。
******
「あら、ヴァーミリオンの皆さんも、お揃いで」
「えぇ。そろそろ内装も完成したと聞いたので、拝見させて頂こうかと」
二人がそんな会話を交わす中、新参者のシオンは、先輩達の後方で、少し困った顔を浮かべていた。
(とりあえず、アストライア様についてはきたけど、僕は別に、人に教えるほど知識も技術もあるわけじゃないですし……、僕には何が出来るんでしょう?)
彼は辺境の騎士家出身の15歳の少年であり、あまり他人と関わるのが得意な方ではない。それでも、何か自分に出来ることを探そうと思って、今回の計画に協力することにしたのだが、その「何か」が何なのか、まだ自分でもよく分かっていなかった。
ただ、そのような消極的な姿勢で参加しているのはシオンばかりではない。トレニアが今回の任務を選んだのも、どちらかと言えば「消去法」であった。
(戦いには、少し疲れてしまったから、今回は戦う必要のない任務がいいな……)
それが彼女の本音であった。廃校の魔境の調査では、年長者ということで指揮官を任されていたものの、彼女もまた(リュディガーと同様)「ヒト型の敵との戦い」は苦手な気性だったため、ゴブリン達との連戦を通じて、心身ともに疲弊してしまったらしい。とはいえ、農村出身で学校に通ったこともない身である以上、特に何かが教えられるという訳でもなく、まずは自分に出来ることを探すところから始めなければならないという意味では、立場はシオンとあまり変わらなかった。
一方、ティカは今回の任務に際しては、それなりに前向きであった。彼も特別学問に秀でているという訳ではないが、ひとまずは自分の得意なことを教えれば良いと考えていた。それは、馬術である。
(とりあえず、覚えておいて損はない技術だよね。馬の扱い方を覚えれば、他の動物にも応用出来るだろうし)
カルタキアを含めた暗黒大陸北部では、馬の他にも、ラクダやロバなどを乗騎として用いる人々はいる。こういった動物を使役する術を身に着けておけば、将来の就業の選択肢を広げることにもなるだろう。
そして、ヴィクトルに関しては、自分が何かを教えるというよりは、様々な講師の面々が子供達に教えている様子を見てみたい、という思いから彼等に同行していた。
(いずれ故郷に帰った時の参考になりそうだしな)
四人がそんな思いを抱きながら旧孤児院に到着すると、その中の大部屋において、アイリエッタが自作の勉強机と椅子を並べながら、教室のレイアウトを考えていた。
「お、来てくれたようだな、先生方。どうだ? アタシの作ったこの机?」
アイリエッタが近くにあった机に手を付きながらそう問いかけると、シオンは素直に驚いた表情を浮かべながら問い返す。
「これ……、あなたが作ったんですか?」
「あぁ。お貴族様達から見れば、あんまりお上品な出来じゃあないと思うが、それなりに長く使えるように、頑丈な設計にしたつもりだ」
実際、どちらかと言えば質実剛健なデザインではあるが、表面はきちんと平らになるように研磨されており、勉強机としては申し分のない完成度である。
「あと、これが子供達を相手にした時のための指南書だそうだ。星屑の軍医殿が作った代物だが、使うかい?」
聖印教会の一員である星屑十字軍と、エーラム魔法師協会の影響下にあるヴァーミリオン騎士団とでは、根源的な思想が全く異なる。だからこそ、片方の考えに染まりすぎないように、今回の学校建設においては両陣営の指揮官が並び立つ形で責任者を務めることにしたのだが、アストライアは素直にその「対立陣営(?)の一員が作成した指南書」を受け取った。
「ありがたく、参考にさせてもらいます。私達はあくまで武人。教育者でも学者でもありませんから、どのような立場の方が作られたものであれ、こういった資料があるのは助かります」
穏やかな笑顔を浮かべながらアストライアがそう答えたところで、以前(引越直前)にこの旧孤児院に来たことがあるヴィクトルは、部屋全体を見渡しながら、不思議そうな顔を浮かべる。
「こんなに広い部屋だったか? 前は色々と中途半端な衝立で分割されていたような……」
「あぁ、アタシが全部ぶっ壊した」
もともと、それらの衝立は旧孤児院の建設後に、大部屋を区切るために追加で設置された壁だったため、排除したところで建物の構造には影響がないと判断され、アイリエッタが床との接合部分を破壊することで排除したらしい。
「で、その残骸の中で、使えそうな部分はこの机と椅子の材料になったって訳さ」
アイリエッタがそう語り終えたところで、部屋の奥の扉の向こう側から、ガラガラという音が聞こえてくる。ヴィクトルの記憶が確かなら、その扉の先には別の部屋があった筈である。
(これは、車輪の音……?)
「アイリエッタさん! この黒板、すっごく使いやすいのー!」
「おかげで算術の説明が捗りそうで、大変助かります」
二人がアイリエッタにそう語る一方で、トレニアはきょとんとした顔でその「板」を見つめながら、アイリエッタに問いかける。
「これは、なんですか……?」
「あー、『黒板』ってやつらしくてな。さすがにこれはアタシが作った訳じゃないんだけど、重くて運びにくそうだったから、下に車輪を付けてみたんだ」
この世界において「黒板」はそれほど一般に流通している代物ではないが、何度も書いて消してを繰り返すことが出来る便利な表示版であり、都心部の教育現場の一部では用いられている。学校に通ったことがないトレニアにとって、それは初めて見る代物であった。さすがに一枚しか入手することが出来なかったため、その一枚を状況に応じて各教室で使えるようにするために、アイリエッタが「車輪」と「脚部」を付加するという工夫を考案したようである。
「こうやって使うのー!」
ユージアルがそう言いながら、白い小さな棒状の何かを用いて「異界の怪物(をデフォルメした何か?)」のような絵を描き始める。物珍しそうな顔でトレニアがその様子を見つめる横で、シオンは素直に彼女達の技工に感服していた。
(設備を作ったり、指南書を書いたり、そういった形での貢献も僕には思いつかなかった……)
ますます自信を無くしはじめていくシオンであったが、密かに自分の手の中に出現させた聖印を見つめながら、自分に言い聞かせるように心の中で呟く。
(でも、何もしないわけにはいきません。それじゃ来た意味が無いんです)
シオンがそんな強い決意を抱いている一方で、ワイスは完成しつつある大教室を見ながら、何やら不敵な笑みを浮かべていた。
(子供達への教育、それは当方の目的達成のための重要な第一歩。この機会は有効に活用させて頂きましょう……)
この時点で、そんな彼女の思惑に気付いていた者は、誰もいなかった。
******
それから数日後。旧孤児院を改装して立てられた新たな学び舎において、子供達を相手にした授業が開始されることになった。
校舎内の最大規模の教室にて「混沌についての知識」についての授業を任されたウェーリーは、講義当日になってもまだ困った顔を浮かべながら、渋々教壇に立つ。授業を受ける子供達の年齢層は幅広く、かなり多くの人々が「混沌」について(良くも悪くも)強い興味を示していることが伺える。
(さて、何から話したものか……)
少し迷いながらも、彼は本題に入る前に、まず「混沌に対する向き合い方」について語り始めることにした。
「みんな、混沌って、何だと思う?」
開口一番、いきなりそんな言葉を投げかけられた子供達は少し戸惑うが、そんな中で、前の方の席に座っていた子供の一人が答える。
「この世界に怪物を連れてきたり、地震や大火事を起こしたりする危険なもの、ですよね?」
「そうだね。その考えは間違ってはいない。でも、それは混沌の本質じゃない。あくまで、混沌の結果として起きることの一つの側面でしかないんだ」
そう前置きした上で、ウェーリーは更に話を続ける。
「この世界に生きている人々はみんな、この世界の法則に従って生きている。それに対して、混沌はこの世界の法則を歪めるもの。だから、この世界の人達に害を与えることが多い。でも、混沌の存在そのものが危険という訳じゃないんだ。たとえば別の世界から投影されてくるものも、基本的には『それぞれの投影元の世界の中の法則』に基づいて生み出されたものである筈。だから、混沌から生まれたものだからと言って、常に敵や脅威になるとは限らない。たとえ投影体であっても、その本質を見極めれば、彼等の視点からこの世界がどう見えているのか、ということを理解出来ることもある。それを理解することによって、より柔軟な対応が可能になるんだ」
そんなウェーリーの説明に対して、子供達の半分くらいは意味を理解出来ずにいたようだが、熱心に聞いていた子供達の中から、手を挙げて意見を述べる者が現れた。
「他の世界のことなんて、本当に理解出来るんですか?」
「もちろん、それは簡単なことじゃない。でも、たとえばこのカルタキアの書庫には、過去にこの地の周辺で発生した沢山の魔境の記録が残っている。こういう形で、混沌と遭遇した人達が記録を積み重ねていくことによって、少しずつ色々な世界の混沌についての知識を、人類全体の間で深めていくことが出来る。その知識をみんなで共有するための場が、この授業なんだよ」
これに対して、また別の生徒が手を挙げた。
「でも、理解しようとする前に、いきなり襲われたら、どうしようもないじゃないですか」
「もちろん、その通り。だから、危険な投影体が目の前に現れた時、まず最初に考えるべきことは、自分の身の安全の確保だ。ましてや君達は、まだ身を守る力を持たない子供なんだから、危ないと思ったら、すぐに逃げてもらって構わない。その上で、自分が実際に目撃したその混沌に関する情報を皆に伝えてほしい。どんな小さな情報でも、その情報の積み重ねが、その投影体への理解、そして対処法に繋がることになるからね」
無論、これらはあくまでも原論的な話であり、実際には、混沌による投影元となる世界は無限にある上に、同じ世界から投影されたとしても全く異なる思考・形態の投影体が出現する以上、そう簡単に理解出来るものではない。とはいえ、最初から「敵」「脅威」としての認識しか持てなければ、いつまで経ってもその場しのぎの対処法を繰り返すことしか出来ない。だからこそ、たとえ僅かな手掛かりからでも、相手の思考や行動原理を理解しようとする姿勢を捨てるべきではない、というのがウェーリーの考えであった。
しばしの沈黙の後、最初に答えた子供が再び手を挙げる。
「じゃあ、危険な投影体って、どうやって見分ければいいんですか?」
これに対して、ウェーリーはあえて質問で返すことにした。
「君は、どう思う? どういう投影体のことを危険だと思うかな?」
「え……? なんかこう……、普通と違う、とか……?」
「普通って、なんだろう?」
「それは……、今まで見たことないような……」
その生徒が少し言葉に詰まったところで、ウェーリーは他の生徒達に対して、あえて何かを促すような視線を向ける。すると、それまで奥の方で控えめに話を聞いていた生徒の一人が、割って入ってきた。
「自分が見たことあるかどうかは、基準にならないと思います。僕達は、他の大陸の生き物のことは全然知りません。自分の知識だけで考えて、自分が見たことないものを全て投影体だと決めつけるのは、視野狭窄だと思います」
少し学のありそうな言い回しで語ったその生徒の言い分に対して、最初に答えた子供は少し苛立ったような声で言い返す。
「じゃあ、お前はどうやって見分けるんだよ?」
「無理に見分ける必要はないと思います。投影体であってもなくても、危険だと思えば逃げれば良いのではないでしょうか?」
「答えになってねーよ!」
「そもそも、君の問いの立て方が不毛なのです。先生がおっしゃっていたのは、危機回避の重要性であって、それは投影体か否かに限った話ではありません。違いますか?」
「いや、でも、これは『混沌についての知識』の授業だろ?」
議論が本題からズレかけている上に、やや喧嘩腰の雰囲気になってきたのを見て、ウェーリーは一旦彼等を止める。
「じゃあ、ここでちょっと話を整理しよう。『見知らぬ生き物』を見つけた時、それが『危険な生き物かどうか』を見分けることと『投影体かどうか』を見分けることは、別の問題だ。一つ目の問題について考えることが、身の安全を確保するために必要だということは、皆も分かると思う。じゃあ、二つ目の問題について考えることは、そもそも必要なのか。もし必要だとしたら、なぜ必要なのか? まず、この点から考えてみようか」
このようにして、ウェーリーが生徒達に様々な問題を問いかけ、彼等自身に考える機会を与えながら、授業を進めていく。それは、一方的に話だけを聞き続けるだけだと生徒達も退屈するだろう、という配慮であると同時に、自分が喋り続けて疲労することを回避するための方策でもあった。
******
(この地での子供達への教育を通じて、「強烈な悪意」と、それに対抗する「正義の心」、若しくは「己の手駒」を……)
そんなことを考えながら、ワイスは比較的小規模の教室へと向かう。ここに集められたのは、子供達の中でもより高度な知識を求めようとする、勤勉意欲の強い子供達であった。
ワイスの手には、自筆による独自の教育法がまとめられた本が握られている。そこには「(精神破壊や洗脳を含む)己の思うがままに教え子を操る術」がまとめられていた。
(さて、まずは最初の挨拶から。人心を掴むには最初が肝心ですからね)
不穏な笑みを浮かべながら、ワイスは教室の扉を開く。すると、そこにいたのはいかにも利発そうな、そして純粋に勉学に励もうとする澄んだ瞳の子供達であった。
「ワイス先生、よろしくお願いします!」
そんな生徒達の姿を見た途端、ワイスの中で、当初想定していなかった別の感情が生まれる。
(この子達が、当方の話を聞くために、こんな綺麗な目をして待っていてくれた……)
次の瞬間、彼女は唐突に火口箱を取り出し、彼等の目の前で上述の本に対して火を付ける。
「先生!? 何を!?」
突然の奇行に対して、当然のごとく生徒達は驚く。それに対して、ワイスは本を燃え崩れる本を眺めながら涼しい顔で答える。
「ふふっ。当方は一流ですので、こんなものは必要なくとも、と思いましてね」
彼女はそう答えながら、胸元に聖印を出現させる。
(えぇ、彼等は違う。まだ……、あれを試す機会はこれから幾らでもありますし、今回は表向きの目的の為の準備期間。そういう事にしておきましょう)
ワイスは自分にそう言い聞かせながら、改めて生徒達に対して語り始めた。
「さて、この授業では、数学について学んで頂きます。将来、商人になろうと農民になろうと、はたまた領主の元で働くことになっても……、戦場だろうと。どんな場所でも十全に活用できれば如何様にも道を作れるのが数学です。当方のすべてを出来得る限り伝えましょう。当方が長年かけて培ったそれを貴方方に伝えるのです。今から死ぬ程勉学に励んでもらいましょう。勿論死なせはしませんからご安心を」
彼女はそう告げると、手元には本も何も持っていない状態で、黒板を使って数学に関する授業を始める。彼女の中には、四則演算から三角関数、微分積分、更にはゲーム理論まで、あらゆる知識が詰め込まれている。どこまでそれらを伝授出来るかを、子供達の反応を見ながら見極めることにした。
さすがに辺境の地ということで、そこまで高度な数学を教えることは難しいかとも思えたが、生徒達の中には存外優秀な者達が多い。その大半は明らかに身なりの良さそうな(おそらくは裕福な家庭の)子供達であったが、そんな中で一人、やや見窄らしい服に身を包んだ黒髪褐色の少女がいた。ワイスの目には、その少女が最も貪欲に知識を吸収しようとしているように見える。
(あの少女の瞳……、まるで、子供の頃の自分を見ているような……)
ワイスがそんな感慨を抱いてる中、彼女はワイスが出した難問に次々と答えていく。その少女のことが気になったワイスは、初日の授業を終えた時点で、帰宅しようとしていた彼女を呼び止める。
「そこの君、名前は?」
「え? あ、はい。シーマ、です」
「シーマ。これまで、算術や数学を学んだことはありますか?」
「いえ……、私は孤児ですので、きちんと教えてもらったのは、今日が初めてです。ただ、もともと計算というか、『数』について色々考えるのは好きだったので……」
つまり、無意識のうちに独学で身につけていた基礎的な素養だけを元に、ワイスがこの日に提示した数学の法則を即座に理解し、すぐにそれを応用出来るだけの理解力の持ち主、ということらしい。
「では、君には今から特別な宿題を出します。少し、待っていなさい」
ワイスはそう言って、その場で紙とペンを取り出し、より高度な数学の問題を書き始める。シーマはそんな「宿題」に対して、興味深そうな視線を向けていた。
なお、後にこの少女は、ワイスの想定とは全く異なる形で「彼女の名」を引き継ぐことになるのであるが、それはまた別の物語である。
******
一方、レオノールが担当している年少組の教室では、この日は読み書きの練習から始まり、算術、地理、動植物などに関する基礎的な知識を、分かりやすく解説していた。
彼の補佐役として配備されたローレンとリュディガーは、それぞれに生徒達の様子を見ながら、誰がどこまで授業についてきているかを見定めようとする。そんな中、ローレンは子供達の中に、地理の授業の時にだけ異様なまでに強い興味を示している少年を発見する。彼は授業中、レオノールに対して何か質問いたいことがありそうな仕草を見せていたが、話を止めてまで手を挙げる勇気はなかったようで、どこかもどかしそうな様子であった。
やがてこの日の全ての授業が終わった後、少年は立ち上がり、レオノールの元へと向かおうとしたが、彼よりも先に、幾人かの少女達がレオノールを取り囲み、質問攻めを始めてしまったため、彼はやむなく残念そうな表情を浮かべながら帰宅しようとする。
そんな彼の様子を見ていたローレンは、ふと彼に声をかける。
「なにか聞きたいことがあるなら、私で良ければお答えしますよ」
「ホントか!?」
少年は目を輝かせながら、ローレンに向かって語り始める。
「あのさ、オレ、ハルーシアのこと、もっとよく知りたいんだよ」
「ほう? なぜですか?」
「昔から、ハルーシアの船乗りになるのが夢なんだ。ハルーシアの海軍って、世界最強なんだろ?」
「まぁ、諸説ありますが、最強候補の一つでしょうね」
現状、世界を二分する「幻想詩連合」の盟主国であり、豊富な資金力を持つことから、軍艦に備えられた兵装の性能に関しては世界最強と評価する者が多いが、海兵そのものの強さや実戦経験の面から、北海の雄であるノルド海軍をより高く評価する者もいる。だが、南国であるカルタキアの民にとっては、必然的にハルーシア海軍の方が馴染み深い。
「でもさ、さっきの話だと、ハルーシアって国は、名門貴族の力が強いって話だっただろ? そんな国の海軍が、田舎者のオレを受け入れてくれるのかってのが、気になって……」
「そういう話なら、ウェーリー殿に聞いた方が早いのでは?」
「オレもそうしたかったんだけど、あの先生の授業、人気すぎて入れなかったんだよ」
別に、授業を聞いていない者が質問に行ってはならない、という規則はないのだが、どうも先刻からこの少年の様子を見ていると、(乱雑な言葉遣いとは裏腹に)見知らぬ教員達に自分から話しかけるだけの度胸(図々しさ)は持ち合わせていないらしい。
「そういうことならば、私の把握している範囲でお答えしますが、金剛不壊の人々を見る限り、必ずしもハルーシア人でなければ入隊出来ない、という訳ではないようです」
「じゃあ、オレでも……!?」
「もっとも、それはラマン艦長が特殊なお人柄なだけかもしれません。ハルーシア海軍全体が同様なのかどうかは……」
「いや、金剛不壊に乗せてもらえるなら、十分だよ! そっかぁ、オレもあの船の一員に……」
目を輝かせながら少年はそう呟くが、ローレンはそんな彼に対して、冷静に話を続ける。
「しかし、金剛不壊も、いつまでカルタキアに停泊し続けるかは分かりません。私達駐留軍は、いずれこの地の混沌が一段落したら、この地を去る立場ですから」
「そっか……、まぁ、そうだよな……」
「ですから、君が本気で金剛不壊の船員となりたいなら、それまでの間に、ラマン艦長か、他の船員の誰かに話を聞きに行くべきでしょう。どうすれば船員になれるのか、ということを」
「うん、まぁ、そうなんだろうけど……」
少年は、再びもどかしそうな表情を浮かべる。やはり、自分から動き出す勇気が持てないらしい。先刻の少年の反応からして、おそらく彼はラマンとその従騎士達に対して、強烈な憧れを抱いているようで、だからこそ、畏れ多くて押しかけにいけない、という心境らしい。そんな少年に対して、ローレンはもう一つ問いかける。
「君がその夢を抱いていることを、君の親御さんは知っていますか?」
「いや、それもまだ……、っていうか、オレ、長男だからさ、ちょっと言い出しにくくて……」
つまり、彼はあくまでただの「夢見る少年」であって、まだ具体的なことは何一つ始めていないらしい。幼少期の子供にとって「強い海の男」への憧れはごくありふれた感情であり、それは時が経てば現実を知って冷める程度の熱かもしれない。ただ、先刻の彼の講義中の真剣な表情を見ると、その熱を持て余したまま動けずにいる彼に対して、どうしても伝えたいことがあった。
「君が本気で夢を叶えたいなら、まず何よりも『自分から動くこと』が大切です。この世の中、待っているだけでは何も始まりません。それは、どんな夢を叶えるにしても同じことです」
「そ、そうか……、まぁ、そうだよな。結局、思ってるだけで何も出来ないようなオレじゃ、とてもじゃないけど無理ってことだよな……」
「えぇ。『今の君』では無理です。でも、人は心の底から本気で願えば、変われるものです」
「……そうなのか?」
「逆に言えば、そこまで変わりたいと思えないなら、今の君の夢は、君にとってそれほど本気ではない、ということなのかもしれません」
その言葉に対して、少年は沈黙する。どうやら自分の中でも、自分の気持ちがよく分からないようである。
「君がどんな夢を抱くのかは君の自由ですし、どんな未来を選ぶのかは、全て君次第です。ただ、もう一度言いますが、この世の中、何かを始めたいと思ったら、自分から動き出さなければ、何も変わりません。待っているだけでは駄目です。このことだけは、絶対に忘れないで下さい」
ローレンのその言葉に、少年は真剣な瞳で聞き入る。そして、少し考え込んだ上で、彼はゆっくりと口を開く。
「……分かった。変われるかどうかはまだ分からないけど、変われるように、頑張ってみる。自分で動き出せる自分に」
「えぇ、最終的に、後悔することだけはないように祈っています」
「ありがとう。えーっと……、ローレン先生!」
そう告げて、少年は去っていった。ローレンの本音としては、彼のような澄んだ瞳の少年が戦争の駒となって死ぬことは、出来れば避けたい。その意味では、彼の夢そのものを無条件に応援する気にはなれないし、仮にハルーシア軍に加わることになったとしても、出来れば前線に立つことのない裏方要員になって欲しいという想いもあるが、そのことは口に出さなかった。
最終的に、自分の夢は自分で叶えるしかないし、自分の未来は自分で決めるしかない。この少年が、どんな道を歩むことになるにせよ、自分で自分の道を選び、歩み出せるようになってほしい、というのが、ローレンの切なる願いであった。
*******
もう一人の補佐役であるリュディガーは、レオノールの講義が終わった後、明らかに読み書きや四則演算の説明についていけていない何人かの子供達を相手に、補習授業をおこなっていた。子供達は当初はあまり乗り気ではなかったが、常に眉間にシワを寄せているリュディガーに逆らうのは怖いと思ったのか、おとなしく彼の言うことに従い、指導を受けることにしたようである。
リュディガーは懇切丁寧に一人一人に説明し、生徒達も少しずつ基礎的な部分から理解出来るようになっていったが、それでもやはり、どうしても勉強に意欲をもてない子供もいた。
「ねぇ……、勉強って、どうしてもやらなきゃいけないの?」
彼の補修を受けていた少女の一人が、気怠そうな声でそう問いかける。
「どうしても、という訳ではありません。でも、勉強しておくことは、きっと役に立ちます」
「役に立つって、たとえばどんな時に?」
「それは、あなたが将来、『どんな自分』になりたいか、によるでしょう」
しかめ顔のまま、リュディガーが真剣にそう答えると、少女はため息をつきながら呟く。
「……将来、かぁ」
「何か、夢とかないんですか?」
「無いわよ、そんなの。こんな、いつ何が起きるかも分からない街に住んでたら、将来のことなんて、考えられないわ。どうせいつまた混沌災害が起きるかも分からないんだもの。いくら考えたって、意味ないわ」
諦めきった顔で、少女はそう答える。この少女の見た目は10歳前後程度に見える。仮に10年前のカルタキアの混沌災害の時点で生まれていたとしても、おそらく記憶には無いだろう。それでもこのような気持ちを抱いてしまうということは、おそらく、子供の頃から彼女の周囲の大人達がそのような話ばかり続けていて、彼女自身も希望が持てなくなってしまったのではないか、と推測出来る。
(確かに、混沌がこの世界にある限り、人々が未来に希望を抱くことは難しい……)
リュディガーの故郷では、「人間に対して有効的な投影体」の加護により、長らく混沌災害から守られてきた(数年前にその投影体は他界し、今はその末裔が守護者となっている)。しかし、そのような特別な環境で暮らしている者達ばかりではない。ましてやこのカルタキアのように、周期的に異様なまでに大量の魔境が出現する地で過ごしていれば一部の大人達がそのような悲観的な考えに染まってしまうのも無理はないだろう。
彼女に対して、どう答えれば未来に希望を持ってくれるようになるのか、ということをリュディガーが考えていると、逆に少女の方から問いかけてきた。
「あなたは、未来に夢とか希望とか、持てるの?」
それに対して、リュディガーはあえて力強く答えた。
「夢というか……、『なりたい自分』はあります」
それは、自分に言い聞かせているようなものでもあった。
「どうなりたいの?」
彼女が更にそう問いかけてきた時、リュディガーは視線の先(部屋の窓の外)にレオノールがいることに気付いた上で、彼にも聞こえるように声量を上げながら答える。
「混沌から故郷を、人々を守るために戦う、そして、あなたのような人にも未来に希望を持ってもらえるような世界を作る、そんな君主です」
その言葉が、彼女にどこまで響いたのかは分からない。だが、少女は(先刻とはやや雰囲気の異なる)ため息をつきつつ、黙って勉強を再開する。そして、窓の外のレオノールは、静かに穏やかな笑みを浮かべていた。
******
「こんにちは、えっと、学校は楽しいですか?」
授業と授業の間の休み時間の間に教室を移動しようとしている生徒の一人に、シオンはそう語りかけた。彼は「今の自分に出来ること」について色々と試行錯誤した結果、子供達に個別に話しかけて、彼等の相談相手となりながら、自分のこれまでの人生経験を通じて得られた知見などを話せば良いのではないか、と思い立ち、まずは近くを通りかかった子供に声をかけてみることにしたのである。
(人に話しかけるのは苦手だけど、でも、そんなこと言ってたら何も出来ないし……)
そんな思いを抱きながら、勇気を出して話しかけたシオンに対して、声をかけられた少年は、微妙な表情で答える。
「うーん、面白かったと言えば面白かったけど……、なんか、今ひとつピンとこなかったな」
ちなみに、彼が直前に受けていたのは、シオンの上官のアストライアの講義である。
「ピンとこなかった、というのは?」
「色々なことを話してくれたんだけど、あんまり現実感がないというか……、世界の国の名前とか教えてもらっても、それがどういう国なのか、イマイチ想像出来なかったんだ。まぁ、どうせカルタキアの外に出る予定なんて無いし、別にどうでもいいと言えばどうでもいいんだけど」
少年はそう答えつつも、その表情から察するに、内心ではそんな現状に不満を持っているようにも見える。
(この子は、本当はカルタキアの外の世界に興味があるのかもしれない……)
シオンはなんとなく漠然とそんな印象を受ける。その上で、もしそうだとしたらなぜ彼がアストライアの授業を聞いた上で「ピンとこない」「現実感がない」と思ってしまったのか、という点についても考えてみた。
(もしかしたら、アストライア様は淡々と客観的に話しすぎたのかも……)
ヴァーミリオン騎士団はどの国にも属さない独立機関であるため、その団長である歴代の「アストライア」には常に冷静かつ公正中立な人格が求められる。現在の「11代目」もまた、そんな立場であるが故に、日頃から自分自身の感情を表に出すことが少ない。それ故に、地理の授業の際に世界の各国について語る際においても、あまりにも客観的すぎるが故に「味気のない授業」になってしまったのかもしれない。
そんな考えに至ったシオンは、あえて「自分の主観」に基づく話を、この少年に投げかけてみることにした。
「僕が旅してきた体験談とかで良かったら、聞いてもらえませんか? たとえば、アルトゥークで魔女の森に行った時の話とか……」
「魔女!? それって、エーラムの魔法師とはまた違うのか?」
「えぇ。自然魔法師と言って、エーラムから公認された特殊な魔法を使う人達です。まぁ、正確に言うと、白魔女と黒魔女という二種類がいるんですけど、そのうちエーラムから認められているのは白魔女の方で……」
シオンのその話に対して、明らかに少年は興味深そうな瞳を浮かべている。そして、近くを通っていた他の生徒達も、その話が耳に入ってきた時点で立ち止まり始める。どうやら、この「魔法の通じない土地」であるカルタキアに住む子供にとっては、「魔法」という存在自体が、一種の神秘的なロマンとして感じられるのかもしれない。
「それで、旅の途中でアルトゥークに立ち寄った時に、混沌災害に遭遇しそうになって、その白魔女の人に助けられたんです。それで、何かお礼が出来ないかと思って聞いてみたら、人狼の里への届け物を手伝うことになって……」
「人狼?」
「あぁ、えーっと、ライカンスロープの邪紋使いです。アルトゥークには、先祖代々『狼に変身する邪紋』を受け継いでいる人達がいて……」
カルタキアにおいては邪紋使いも珍しいため、そのような異能力者の話も、この少年達には興味深く聞こえるようで、徐々にシオンの周りに人が集まってきた。話の内容自体はただの「旅先でのお使い」なのだが、シオンはその光景を、子供だった頃の自分の視点で感情を込めて語り始めたことで、生徒達にもその時の情景が分かりやすく伝わっていく。
「正直、最初は僕も、旅に出るのは不安でしたし、なかなか決心が出来ませんでした。でも、そうやって旅に出てから、色々な人達に出会ったことで、自分の方から色々な人達に関わりにいけるようになって、それが自分にとっての大切な経験になったんです。だから、その……、もし、何か迷っている人がいたら、試しに一歩、踏み出してみるのがいいと思うんです。別に旅でなくてもいいんですけど、とにかく何か一歩踏み出してみることで、何かが変わることもありますから」
訥々とした口調ながらも、どうにか一通り伝えたいことを話し終えたシオンに対して、最初に声をかけた少年が語りかける。
「その旅の話って、まだ続きはある?」
「えぇ。まぁ、そんなに面白い話ではないですけど、他にも色々なところに行ったことはありますし」
「じゃあ、また明日も聞かせてほしいな」
その言葉に対して、シオンは笑顔で頷くのであった。
******
一方、星屑十字軍のトレニアは、校舎の外で退屈そうな顔で座り込んでいる少年を発見する。トレニアの記憶が正しければ、彼は朝の時点で入学手続きをした時に見たような気がする。
「授業、どうでしたか?」
いつも通りの笑顔を浮かべながら、トレニアは問いかけた。
「……受けてねーよ」
「あら、どうしてですか?」
それに対して、少年は俯きながら答える。
「…………だって、受けても意味ねーし」
「なぜ、そう思うんです?」
「俺たちみたいな貧乏人は、どうせ大人になったらひたすら労働するしかないんだから、勉強なんかせずに、今のうちに遊んでおいたほうが得じゃないのか?」
視線を合わせず、どこか達観したような口調で、少年はそう答えた。身なりからして、あまり裕福な家の子供では無さそうである。一応、この学校は義務ではなく、あくまでも任意での参加なのだが、おそらく彼の場合は、両親に言われて無理矢理通わされることになった、という経緯でここにいるのだろう。
(多分、この子の親御さんも、ひたすら毎日働かされ続けるだけの辛い日々を送っていて、この子もそれをずっと見ながら育ってきたのでしょうね……)
トレニアはそんなことを思いながら、自分自身が幼少期に毎日休む間もないほど懸命に農作業や重労働を強いられていたことに重ね合わせる。
(わたしは、このような貧しい人々を救うために戦わなければ……)
街が発展すれば、住民全体の富も蓄積する。それが公平に分け与えられるかどうかは為政者次第ではあるが、貧しい生活を送る人々の絶対数も少しずつ減っていくだろう。そのためには、まず混沌を祓わなければならない。そのために自分達がいるのだということを、改めて実感する。
その上で、トレニアは穏やかな笑顔を保ったまま、淡々と語り始める。
「あなたが将来『貧乏人』になるかどうかは、あなた次第です。生きていくためのお金を稼ぐ方法は、必ずしも重労働とは限りませんよ」
「どういうことだよ?」
「たとえば、あなたが今から一生懸命算術を勉強すれば、ソフィア様の下で経理の仕事を任されるようになるかもしれないし、それに加えて世の中の色々なことについて勉強すれば、商売を始めて大儲けすることだって、出来るかもしれません」
「……そんな上手くいく訳ねーだろ」
「そうですね。あなたが今のように、勉強も何もしないまま大人になってしまったら、そんな未来は絶対に来ません。でも、勉強すれば、そういう未来を選び取れる可能性もあります」
「……無理だよ、俺、頭よくねーもん」
「今まで、ちゃんと勉強したことは?」
「ねーよ」
「勉強したことないのに、どうして頭が良いかどうかが分かるんですか?」
「いや、だって、やる気起きねーし」
「じゃあ、やる気さえ出せば、勉強だって出来るかもしれないってことですよね」
少年が俯きながら黙り始めると、更にトレニアは話を続ける。
「もちろん、算術だけじゃないですよ。文字の読み書きがきちんと出来るようになれば、それだけでも色々な仕事の選択肢が増えます。あるいは、何か特殊な技術を身に付けることで『あなたにしか出来ない仕事』が出来るようになれば、多くの人達から重宝されることになるでしょう」
「俺にしか出来ない仕事って、なんだよ?」
「それは、わたしには分かりません。だからこそ、それを探すための場所が学校なんです。別に学校でなくても、そういったことを探せる場所はあるとは思いますが、少なくとも、何もせずにいるよりは、学校で色々なことを勉強する方が、将来の可能性は広がりますよ。そう考えるだけでも、やる気が出てきませんか?」
笑顔を崩さず、声色も変えずに、ただひたすら静かに語り続けるトレニアのその言葉には、どこか不思議な説得力が感じられた。
「……ホントに、そんなこと出来るのかよ?」
「分かりません」
「はぁ!?」
「あくまでも、勉強すれば可能性が広がる、というだけです。ただ、実際に、貧乏な家に生まれても、努力を重ねて裕福な仕事に就けるようになった人はいくらでもいます。あなたがそうなれるかどうかは、あなた次第です」
その言葉を受けて、少年は舌打ちしながら立ち上がった。
「まぁ、俺の仲間もみんな、勉強始めちまったみたいだし、遊び相手もいなくなって暇だから、その暇つぶし程度に聞いてやるか」
そう呟きながら、少年は校舎へと戻って行く。そんな彼の背中を、トレニアは変わらぬ笑顔を浮かべながら見送っていた。
******
同じ頃、校舎の入口付近に設置された「履修登録相談所」を担当していたユージアルの元には、新たな入学希望者が来訪していた。どうやら、「新設の学校が初日から賑わっているらしい」という噂が街中に広まっていたようである。
「とりあえず、楽な授業がどれなのか、教えてくれない?」
開口一番そう問いかけてきた少年に対して、ユージアルは困った表情を浮かべる。
「うーん、どれが楽かは、人によりけりなの。どんな前提知識をどこまで持っているかにもよるし、どれだけ興味のある科目かによって、勉強のモチベーションも変わってくるから……」
「いや、別にどの授業にも興味なんかないよ。ただ、親に行けって言われたから来てるだけだから、とりあえず簡単なのを教えてくれればいいんだ」
明らかにやる気のなさそうな顔で少年がそう告げると、ここでユージアルの目の色が変わる。
「そんなんじゃ駄目なの! ちゃんと目的意識を持って聞かないと、意味ないのー!」
彼女はそう言って、近くの廊下に置いてあった車輪付き黒板をガラガラと運んで来た上で、唐突にそこに「玉ねぎとクラゲを足したような珍妙な投影体」の絵を描き始める。
「たとえば、お姫様を助けに行きたいとして、手近なスライムを“ひのきのぼう”で倒してるだけじゃ、魔王の城には辿り着けないのー!」
「スライム?」
ユージアルの言っていることは全く伝わっていないが、彼女は気にせずそのまま続ける。
「お姫様を助ける、じゃなくてもいいの。天下布武でもポケ○ンマスターでも、なんでもいいから、とにかく夢は大きく持つの!」
やはり伝わっていないようだが、それでもユージアルは語るのをやめない。
「そして、その夢を叶えるために、自分に何が必要なのか、それを学ぶのが学校や書物、あるいは戦闘訓練なの。ただ漫然と簡単な授業を聞き続けるだけじゃ、何の役にも立たないの!」
「たとえ話」が消えたことで、ようやく少年は彼女の言いたいことを理解し始める。
「でも、別にこれと言って夢とかある訳でもないし……」
「だったら、それを探すためでもいいの! この学校で、色々な授業を受けて、世界の理を学ぶことができるようになったら、きっといつか自分が“やりたいこと”を見つけられるの……!」
ユージアルはそう語りつつ、聖印を覚醒させた時のことを思い出しながら、ルーラーの聖印を浮かべる。ユージアル自身、「自分のやりたいことが何なのか?」ということに気付けたのはつい最近のことであり、現時点ででこの少年がそれに気付けずにいること自体は、そこまで問題だとは思っていなかった
「とりあえず、今、やりたいことが無いのは仕方ないの。それなら、試しに色々な授業を受けてみることをオススメするの。だから、まず、今の時点で文字の読み書きが出来るのか、とか、そういうことを教えてほしいの」
「……一応、文字は読める。さっきアンタが言ってた難しい言葉は、よく分からなかったけど」
それは「難しい言葉」というよりは「ほぼ誰も知らない(ユージアルすらも理解しているか怪しい)異界の言葉」なのだが、さすがにそんなことまで少年に判別出来る筈もない。
「じゃあ、たとえば、この単語とかは、分かるのー?」
ユージアルはそう言いながら黒板に(普通の)文字を書き始める。こうしてまた一人、新たな少年が勉学への道へと歩み始めることになるのであった。
******
「アストライア先生! 質問があります!」
この日の授業を終えたアストライアが帰宅しようとした時、廊下で一人の少年が呼び止めた。彼の名はアナベル。カルタキアの孤児院の一員であり、最近はとある従騎士から学んだ技術を用いて「手袋」の作成に日々邁進しつつ、アストライアが担当する生徒の一人でもあった。
「なんですか?」
「俺みたいな、金もコネもない平民が君主になるには、何が必要ですか?」
その問いに対して、アストライアは少し間を開けてから答える。
「方法は二つあります。一つは、自力で混沌核から聖印を作り出すこと。ただし、これは失敗すると、最悪の場合は心身共に混沌に呑まれてしまう可能性がある以上、オススメは出来ません。そもそも、実際に成功した事例は殆どありませんし」
なお、実はこのカルタキアの従騎士達の中に、かつてその偉業を成し遂げた過去を持つ者もいるのだが、そのことを知る者は殆どいない。
「もう一つは、君主の誰かから『従属聖印』を受け取ることです。その場合の条件や基準は君主によって異なるので、何とも言えません」
「では、もし、アストライア様の従属君主になろうと思った場合、どうすればなれますか?」
真剣な瞳でそう問いかけるアナベルに対して、アストライアは静かな声色で答える。
「私の場合の判定基準は色々ありますが、まず第一条件は『戦場に連れて行っても大丈夫か否か』です。私達は『領土を持たない騎士団』であり、その任務の大半は『混沌との戦い』です。それに耐えられるだけの心身の持ち主でなければなりません」
「じゃあ、今の俺だったら、どうなんですか?」
これに対して、アストライアはじっと彼を凝視した上で、答える。
「素質はあります。まだ身体は発展途上のようですが、騎士見習いとしての最低限度の身体能力は、今の時点で備わっていると言えるでしょう。ただ……」
「ただ?」
「……今のあなたはまだ『目指すべき君主道』が、はっきりと見えていないように思える」
そう言われたアナベルは、一瞬、言葉に詰まる。
「あなた聖印を手に入れた上で、どんな君主になりたいのか、君主になって何がしたいのか、という具体的なイメージが、あなたの中で固まっていますか?」
「お、俺は……」
アナベルは何か言おうとするが、上手く言葉がまとまらない。
「そもそも、あなたは本当に『君主』になりたいのですか? それとも、『力』が手に入るなら、何でも良いのですか?」
畳み掛けるようにそう言われたアナベルは、自分が何を求めていたのかが、自分でもよく分からなくなってくる。そんな中、別の人物が彼の後方から声をかける。
「別に、力を求めようとすること自体は、悪いことではないと思うぞ」
その声の主は、ヴィクトルである。彼もまた授業を終えたアストライアに一声かけようとしていたのだが、アナベルに割り込まれ、話しかけるタイミングを逃していた。
「あんた、確か、孤児院の引っ越しの時に手伝ってくれた人、だよな?」
「まぁ、そう大したことはしていないんだが」
ヴィクトルはそう答えつつ、アナベルの表情と声色から、明らかに彼の中で様々な「迷い」が混在していることを察した上で、話を続ける。
「君主を目指すのも、力を求めるのも、それはお前の自由だ。ただ、それが本当にお前の願いなのか? 力を手に入れれば、確かに色々なものを守れるようになる。自分の周囲の者達の命も救えるかもしれない。ただ、誰かを守るということは、同時に、自分の命を危険に晒すことでもある。お前の周りの者達は、本当にそれを望んでいるのか? 何かを志すのも良いが、たまには一度立ち止まって、周りに目を向けてみるべきじゃないか?」
その言葉に対しても、アナベルは何も言えない。「(とある従騎士も含めた)自分の周囲にいる人々」のことを考え始めると、彼自身、自分の中で湧き上がっていた「君主となることへの衝動」の根源が何なのか、ますます分からなくなってきていた。
「夢を追いかけるのは悪いことじゃない。ただ、下手な無茶はするなよ。前ばかり見ている時に限って、大事な人が悲しむことになる。それに、命は一つしかないからな。夢を追いかけるなら尚更だ」
ヴィクトルはそこまで言い切った上で、自嘲気味な笑みを浮かべる
「まぁ、俺が偉そうに言えたことじゃないか」
彼はそう言いながら、アナベルの横を通り抜けて、アストライアの元へと向かう。アナベルはそんな二人に対して、静かに頭を下げた。
「お騒がせしました。もう少し、よく考えてみることにします」
そう言って、彼は二人の前から去っていく。そんな彼の後ろ姿を見ながら、ヴィクトルはふとアストライアに問いかけた。
「実際のところ、彼に君主としての資質はあると思いますか?」
「さぁ、どうだろうね。ただ、私の勘が間違っていなければ、彼は……」
そこまで言いかけて、アストライアは口をつぐむ。
「……いや、やめておこう。これ以上は、越権行為だ」
******
翌日。ニナとカシュによる治療技術の実演授業が開かれることになった。
(本当に、自分なんかが教えていいのかな……)
カシュは内心でそう呟きながら、ニナと共に子供達を相手に消毒の仕方、包帯の巻き方、添え木の当て方などを順々に披露していく。最初は交互に二人で相手の腕や足に対して処方する様子を見せた上で、子供達一人一人に実際にやらせてみることで、その理解度を確かめる。
どちらかと言えばニナが解説役、カシュが補佐役を担った上で、ニナが子供にも分かりやすい簡単な言葉を多用しつつ、カシュがそれに合わせて次々と道具を取り出しながら子供達に見せて回る、という形で授業を進めていた。用いられる道具の大半も、あくまで「一般家庭で日用品として手に入るもの」に限定することによって、少しでも一般の子供達にとって実践的な応急手当の方法を伝授していく。
「あんまり強く巻きすぎると、血の流れが止まってしまうから、気をつけて下さいね」
「……これくらいかな?」
「そうそう、上手ですねー。あとは、その先を切って結んで下さい。はさみが無い時は、こうやって……」
ニナと子供達の間でそんなやり取りをしている横で、カシュもまた懇切丁寧に一つ一つの動作を指導する。
「すごーい、分かりやすい、ありがとう! カシュ先生!」
「先生だなんて、そんな……」
カシュはやや恥ずかしそうに謙遜しつつも、子供達にそう言ってもらえたことで、自分の存在価値をより深く認識出来たようで、ほのかに笑みが溢れる。カシュとしては、このような形で少しでも自分に出来ることを見つけられたことが、何よりも嬉しいようである。
そして、それはニナもまた同様であった。今、彼女が教えている応急措置の技術は、彼女がカルタキアに来てから修得した技法だが、実際のところ、あまり戦線に立つことが少ないせいで、実践的な技術が見についていないという焦りを感じていたのである。だからこそ、自分が伝えた技術で少しでも子供達が救われてくれるのなら、それは彼女自身にとっての救いにもなる。
(こうやって教えたことが、いずれこの子達の役に立つといいな……)
ニナはそんな思いを抱きながら指導を続け、やがてこの日の授業は無事に終わる。だが、生徒達は自分と歳の近い彼女達に対して親しみを感じたのか、二人に対して友達のような態度で授業後も語りかけてきた。
「ねーねー、ニナ先生とカシュ先生って、いつもはなにやってるの?」
唐突にそう言われた二人は、思わず顔を見合わせる。先に答えたのはカシュの方だった。
「僕は、その、色々な人の下働きとして、その場その場で、色々なことをしています。だから、その、あんまりはっきりと『これが自分の仕事』って言えるようなものは、まだ無くて……」
困った顔でそう説明するカシュに続いて、ニナもまた軽く自嘲気味に答える。
「私も、似たようなものですね。まだまだ半人前なので、その時々に、色々な人達のお手伝いをしています」
「お手伝いって、どんな?」
「そうですね……、たとえば、温泉施設のデザイン案を考えたり、とか……」
「え!? あれって、ニナ先生がデザインしたの!?」
「あ、いえ、あくまで一部ですよ。それに、私だけで考えた訳じゃなくて、シューネさんとか、キリアンさんとか、色々な人達にも助言してもらいましたし。それに、まず何より、あの温泉はマリーナさん達が源泉を掘り起こして、リーゼロッテさんやユーグさんがその水質を確認して下さったからこそ、ちゃんと利用出来るようになった訳で、他にも……」
ニナは自分以外の協力者の面々について色々と語りつつ、ふと、あることを思いつく。
「そういえば、皆さんは他の先生の授業も受けてるんですよね?」
「うん。私はねー、ウェーリー先生と、アストライア先生と……」
「もしよかったら、他の先生達がどんな話をしていたのか、教えてもらえませんか?」
ニナとしては、他の人々が子供達を相手に何を伝えているのかが気になっていた。先日、自分と全く生い立ちの異なるアナベルに対して、何を伝えれば良いのかが分からなかったため、この機に色々な人々の意見を参考にしたいと思っていたのである。そして、それはカシュにとっても同様に興味深い話であり、二人は子供達と互いに情報交換しながら、それぞれに見識を深めていくのであった。
******
そして、この日の午後からは、ティカによる乗馬教室が開かれることになった。幸運にも乗馬場は旧孤児院から比較的近い場所にあったため、昼食後の子供達は、ティカに連れられて現地へと向かう。
「お馬さんに乗れるの、すっごく楽しみ!」
「もし、頭から落ちたら死んじゃうって聞いてるけど、大丈夫かな……」
子供達がそんな話をしていると、引率のティカが笑顔で答える。
「あの乗馬場の子達はみんなおとなしいから、大丈夫ですよ。でも、万が一の時に備えて、ちゃんとヘルメットはかぶっておいて下さいね」
そんな話をしている一方で、ややネガティブな表情を浮かべている子供もいた。
「でもさー、俺達が馬に乗れるようになったところで、それが将来役に立つことなんて、あるのかな? どうせ馬に乗れるのなんて、お偉いさん達だけだろ?」
カルタキアは海上交易が主体の街なので、馬自体がそれほど多くはない。そんな港町で生まれ育った子供の目には、馬はどちらかというと「嗜好品」もしくは「高価な軍用品」であるように思えたらしい。
「そんなことはないですよ。アトラタンでは普通の農家でも普通に使いますし、馬を使った輸送業者の人達は、別にそんなに特別な立場の人達という訳でもないですから」
「え? そうなのか?」
「カルタキアでも、周りの魔境が浄化されれば、陸路も今より活発になるでしょうし、浄化した後の土地を使って馬牧場を始める人も出てくるでしょう」
「へー、そっかぁ。いいなぁ、馬牧場……」
子供達がそんな思いを抱いている中、やがて彼等はティカと共に乗馬場へと到達するが、そこには既に先回りして到着していた一人の少女の姿があった。
「待ってたよ! ティカ先生!」
そこにいたのは、かつて岩礁の魔境の浄化の調査をティカ達に依頼していた、漁師アハブの娘アタルヤである。既に乗馬用のヘルメットも付けて、準備万端の様相であった。
「君は、あの時の……」
「今日は乗馬訓練、させてくれるんだよね?」
どうやら彼女もこの学校に入学していたらしい。そんなアタルヤに対して、彼女の顔見知りと思しき少年が問いかける。
「お前、船乗りになるんだろ? なんでここにいるんだよ」
「それはそれ、これはこれだよ。父さんにも言われたんだ。これから先は陸路の時代になるかもしれないから、馬くらい乗れるようになっておけ、ってね」
どうやら、彼女の父であるアハブも、基本的にはティカと同じ見解らしい。そして、彼等がそのように思えるようになったのは、ここまでの従騎士達の活躍によって、「いずれ魔境の脅威に怯えなくても済む時代になるかもしれない」という希望が、彼等の間で広がっていることが大きな要因なのだろう。
「分かりました。もちろん、歓迎しますよ」
「じゃあ、最初に乗るのは私でいいよね!? ここにも一番乗りだったんだし」
それに対して、他の生徒からは不満の声が上がる。
「お前、それはズルだろ! 俺達はちゃんと先生と一緒に来たのに!」
「別に、先生と一緒に行かなきゃいけないなんて、誰にも言われてないじゃない。むしろ、教えを請う立場なんだから、先生よりも先に来て準備して待ってるのが礼儀ってもんでしょ?」
子供達のそんなやり取りに、ティカは思わず苦笑する。
「まぁ、どっちがやる気があるかは別問題として、せっかくそこまで準備してくれたから、今回はアタルヤさんに最初に乗ってもらうことにしましょう」
「やったー! よろしくね、ティカ先生!」
他の子供達は微妙に不満なようだったが、ティカはそんな彼等に対して「ちゃんと後で順番は回ってきますから」と宥めつつ、まずは乗馬場の中で一番小柄な馬を連れてくる。その上で、馬の機嫌を取りながら、乗馬の手順を説明し始めた。
「いいですか、まず、こうやって馬の左肩横に立って、左手で手綱と馬のタテガミをつかみます。そして、左足を鐙にかけて、右足で地面を蹴ると同時に、右手で鞍の後ろのこの部分を掴んで身体を持ち上げながら、素早く右手を鞍の先のこの部分に移して、体を支えながら、腰を馬の背中に下ろします。これが基本動作です。」
ティカはそう告げた上で、言った通りにあっさりと馬に跨ると、そのまま右足も鐙にかけて、騎乗体勢を完了する。
「とはいえ、いきなりここまでやるのは難しいですし、失敗して馬を蹴り飛ばしてしまったら暴れて大変なことになるので、今日はまず、僕が『後ろ』に乗った状態で、手助けしながら乗馬体験してもらいます。アタルヤさん、まず、そこにある踏み台を持って来て下さい」
馬上からティカがそう言いながら騎乗用の踏み台を指差すと、彼女は言われた通りにそれを馬の横まで持って来た上で、その上に乗る。そして、ティカが上半身を後ろにそらした状態になると、アタルヤは左足を鐙にかけた上で、勢いよく右足を上げて身体を持ち上げた結果、見事に鞍上にその腰を載せることに成功する。
「あ、えーっと……、これで、合ってる?」
「お見事です! じゃあ、次は一緒に手綱を握って、少しずつ動かしていきましょう。船とは違って、馬は生き物ですから、あんまり急に刺激しないように気をつけて……」
ティカは囁くようにそう告げつつ、アタルヤに身体を密着させる。すると、アタルヤは一瞬、顔を紅潮させながらビクッと身体を震わせる。その振動が馬に伝わり、馬は怪訝そうな表情を見せた。
「大丈夫ですか?」
後ろからティカがそう言いつつ、覗き込むように横からアタルヤに声をかけようとするが、アタルヤは自分の緩んだ表情を見られないように首をそらしながら答える。
「う、うん、大丈夫……、ちょっと、その、ビックリしただけだから……」
そんな彼女の照れた様子を他の子供達はクスクスと笑いながら眺める中、ティカはゆっくり丁寧に乗馬の作法をアタルヤに伝授していくのであった。
生活支援(新規/成功)
☆合計達成値:195(40[加算分]+155[今回分])/100
→生活レベル1上昇、次回の「拠点防衛クエスト(CF)」に47点加算
※この結果、次回のCFはイレギュラーな「成功確定クエスト」となる
「そんなわけだからー、おしろさん、いぬがみぎょーぶさんをよろしくねー。すぐに力をつけて、戻ってくるよー。」
数日前、ヴァーミリオン騎士団の
ハウメア・キュビワノ
は、妖狸の投影体・隠神刑部を、同じ異世界から投影されてきた憑神使いの投影体・白に委ねて、君主としての自身の聖印の覚醒に専念することにした。
彼女はこれから先の自身の進むべき道を見定めるために、まずは、これまでの自分の歩みを思い返そうとした。最初に彼女が向かったのは、機械兵団との戦場の跡地である。
「ここでは、機械の軍勢と戦ったんだっけ……。アリスちゃんも、アルスちゃんも、みんな頼もしかったなー……。あーしは後ろで見てただけみたいなものだけどねー」
続いて、今度はカルタキア郊外の、自身で切り開いた農耕地へと向かう。
「ここをいっぱい開墾したんだよねー! 1からけーかくしてー、みんなに動いてもらって造ったんだよねー。大変だったけど、楽しかったなぁ……!」
彼女はそう呟きつつ、実った作物を改めて眺める。
「今はトマトも終わりかけでー……あ、おっきースイカだねー!」
暗黒大陸産の大型球形果実を目にしながら、収穫の日を楽しみにしつつ、今度は港へと向かう。今は静かに平和な取引がおこなわれているが、少し前にはこの海域で紛争が発生していた。
「くーぞく船と交渉もしたっけー。地味に活躍できたんじゃないかなー?」
あの時、彼女が交渉のために乗っていた船は、今も港も警備のために周囲を巡回している。その姿を眺めつつ、続いて彼女は医療施設の傍らに設置した薬草園へと向かう。
「アロエとか、凄いことになってるよねー。これがソフィアさまの力ー……?」
当初の想定以上の速度で育っている薬草を眺めつつ、彼女は今度は街から離れて南方の砂漠の先にある「桶狭間の魔境」の跡地へと赴いた。
「ここで、いぬがみぎょーぶさんと会ったんだよねー。なかなか凄い幻術だったのに、あんなに逃げ腰になるなんて、らしくなかったよーなー? ま、そー言うあーしは憑かれただけなんだけどねー」
そんな諸々の経緯を思い出しつつ、彼女は今後の自分の生き方に思いを馳せる。
「改めて振り返ってみるとー、沢山、できた事があったんだねー。ん。このまま続けていけば良さそーかなー……!」
カルタキアに来て以来、様々な任務に就いてきた。前線に立つことはなかったが、様々な形で彼女は自分に出来ることを探しながら、君主としての歩みを続けてきた。そして、ここから先もこれまで通りに《出来る分だけ着実に、積み上げていく》という誓いを改めて胸に刻んだ瞬間、彼女の聖印は「ルーラー」としての彼女の道を示す姿へと変わっていく。
だが、おそらく、彼女にとってそれは、大きな変化ではない。聖印の形がどうであろうが、彼女はこれから先も、これまで通りに、自分の道を歩み続けることになるのであろう。
******
同じ頃、鋼球走破隊の
ヨルゴ・グラッセ
もまた、これまでのカルタキアでの自分の歩みを思い返していた。
「自分の周りには、頑張ってる人しかいないよなぁ〜」
同じ鋼球走破隊の同僚達に関して言えば、小牙竜鬼の森の探索の際にはファニルが危険な最前線で索敵に従事し、未来都市での戦いではアルエットが敵の注意をそらすために吶喊を繰り返し、対ガーゴイル戦においてはヘルヘイムが自分の身を顧みずに必死の形相で戦い続けた。
他部隊の面々についても、医療施設のための木材伐採の際には献身的に働くリュディガーの姿を目の当たりにし、イナゴドローンの調査の際には自分が牢内で眠っている間に他の面々が敵の指揮官の捕縛作戦を完遂していた。これらの任務の過程において、アシーナ、キリアン、デルトラプス姉弟といった面々とは複数回に渡って同行し、その働きぶりには感服させられた。
これらの任務の過程において、実はヨルゴ自身もそれなりに(本人は無自覚のうちに)重要な役割を担う形で貢献してきたのであるが、貢献出来たか否か、ということ以前の問題として、そもそもこれまで「頑張らない人生」を歩んできた彼にとって、「頑張ってる人々」はそれだけで自分よりも価値があるように思えていた。
今までは、色々ありながらも運良く足を引っ張らずに過ごせてきたが、これから先もそう上手く行くとは限らない。むしろ、魔境との戦いがここから更に苛烈になっていく可能性を考えると、頑張ってる人たちの足手纏いになってしまうかもしれない。
「程々に生きるにしても、せめて足手纏いにはならないようにしないと……」
ヨルゴは自分にそう言い聞かせながら、今後、様々な戦場に出ることを想定した上で、敵の力量の見極め方、勝てそうにない敵と遭遇した時の逃げ方、そして逃げ切れなかった時に備えた敵の攻撃のかわし方やいなし方など、戦場において負傷せずに生き延びるための訓練を、いつもの八割増し程度の気概で取り組もうとする。
「とりあえず、逃げ足を確保するには、馬術の訓練もしておいた方がいいかもしれない」
そう呟きながら、兵舎にいた馬に騎乗しつつ、彼は平地の戦場において、自分が全力で逃げ回る姿をイメージし始める。すると、彼の聖印が微かに変化を始めた。だが、それは微弱な変化であったためか、ヨルゴはそのことに気付いていない。
ヨルゴはそのまま「頑張っている同僚達」と共に戦場を駆け巡る状況を想定しつつ、《頑張る人々の足手纏いにならない程度に力をつける》という誓いをうっすらと描き始めると、その聖印は少しずつ「キャヴァリアー」としての姿へと変容していくことになる。ただ、それはあまりにも遅々とした変容であったが故に、彼自身がそのことに気付いたのは、数日後のことであった。
******
一方、ヴェント・アウレオの
ヴァルタ・デルトラプス
は、自身の宿舎で双子の姉のラオリスとお揃いの宝剣を見つめながら、このカルタキアに来るよりも更に前の記憶に思いを馳せていた。
彼はかつて、ラオリスと二人で狩りをしながら暮らしていた頃、その地を治めていた領主によって姉と共に捕えられ、奴隷として売り飛ばされそうになったことがあった。どうにかラオリスの機転により、領主が所有していた一対の宝剣を彼女が奪い取った上で、ヴァルタと一緒に脱出を図ることになったのだが、その時、追手の弓兵が放った矢によって、ラオリスは脚を射抜かれてしまう。その後、傷ついた姉と共に自分達の住処の洞窟まで逃げ延びた上で、姉の脚を治そうとしていたところで、エイシスに出会い、彼の聖印の力で姉を助けてもらった後、二人は二振りの宝剣と共にヴェント・アウレオに加わることになった。
「あの時、僕がもっと強ければ……」
領主の元から逃げる時には姉を助けられ、その姉を救う際にはエイシスに助けられた。この時以来、自分の無力さを痛感していたヴァルタは、「姉を守れるような人間になる」という誓いを胸に生きてきた。
しかし、このカルタキアに来てからの最初の任務となった小牙竜鬼の森で、ラオリスが人食い草に食いつかれることで(逃亡時と同様に)脚を負傷し、更にコボルト・キャスターとの戦いでも姉を守ることが出来ずに大怪我を負わせてしまい、その仇討ちに挑んだ最終決戦でも、自分自身の手で仇敵を討ち果たすことは出来なかった。
いつまで経っても姉を守れるだけの強さが得られないことへの自己嫌悪から、一度はラオリスと距離を置こうとしたヴァルタであったが、港で出会ったスーノとの会話を通じて、考えを改めるようになる。
「僕一人で強くならなくても、姉さんと一緒に強くなれればいい」
自分の中でそんな新たな目標を抱いた上で、ヴァルタは改めて自分の進むべき道を考える。これまで、姉と共に前線で彼女を守る力を追い求めていたヴァルタであったが、自分の適正が前線向きではなく、むしろ支援役の方が得意であるということは自覚していた。その上で、《姉と一緒に強くなる》という誓いを果たすために最適な自分の未来像を思い描いた結果、彼の中でその姿がはっきりとイメージされると同時に、彼の聖印が姿を変えていく。それは、彼等にとっての首魁であるエイシスと同じ「メサイア」の聖印であった。
メサイアの聖印の持ち主は回復能力に長けていることで知られているが、その聖印は使い方次第によっては攻撃にも用いることが出来るということを、これまでずっとエイシスの背中を見てきたヴァルタは知っている。この力を極めていけば、いつかは姉と一緒に「二人で二人分以上の力」を発揮出来るようになるだろう。そんな未来を見据えながら、ヴァルタは姉よりも一足先に、君主として新たな一歩を踏み出していくことになった。
******
そんなヴァルタと同様に、潮流戦線の
エイミー・ブラックウェル
もまた、自室にて一人、銅貨を弄びながら、カルタキア来訪以前の自分のことを思い出していた。
まだ彼女が家族と共に実家で暮らしていた頃、一枚の銅貨によって導かれた
妹の死によって、彼女は「今の自分」を手に入れた。それ以来、彼女の中では、ずっと強烈な強迫観念が彼女の人生を支配してきた。
(両親にも、他の民達にも。そして……、彼にも。「選ばれる」のではなく、私しかいない。それ以外の選択肢など、初めから存在しない。そうでなければならないのです)
彼女は自分に対してずっとそう言い聞かせつつ、貴族令嬢「エイミー・ブラックウェル」として、婚約者と共にこの地へと赴き、彼と共に、未来都市由来の機械兵達や、秘密基地由来の怪人達との戦いに身を投じてきた。それらの戦場において、婚約者の青年は何度も彼女を助けながらも、気付いた時にはいつの間にか姿を消す、そんな彼の気まぐれに翻弄されながらも、どうにか彼女はここまで、混沌と戦う上での様々な戦い方を模索してきた。
ある時は突剣を使って斬り込み、その一方で聖印から光弾を放つ術を身に着けようとしたこともあった。更に言えば、聖印とは相反する「異界の力」をその身に宿して戦おうとしたこともある。そんな諸々の経験を経て、彼女は改めて、《自分だけの戦い方を確立させる》ということの必然性を強く自覚する。そして、そのことを新たな誓いとして心に刻み込んだ瞬間、彼女の聖印は姿を変え、新たな輝きを放ち始める。
(これが、私の力……)
それは、混沌を戦うことに特化された「パニッシャー」としての聖印の姿であった。従騎士といて、ようやく本格的な形での「聖印」を手に入れた彼女は、どこか複雑そうな表情を浮かべながらその輝きを見つめる。
(きっと、皆が期待する、「彼女」がなるはずだったそれとは、全く違うのでしょう)
もし「彼女」が生きていたら、彼女がどんな聖印を手にしていたのか、それは誰にも分からない。その場合、自分がどんな人生を歩むことになったかも、今となっては知る由もない。
(それでも。例え誰が何と言おうと、この力は、私だけのもの。そして、私の人生も、私だけのものなのです)
過去はあくまでも過去であり、仮定の歴史も実在しない。今この瞬間における「エイミー・ブラックウェル」は、今の自分以外には存在しない。これから先も、そうでなければならない。彼女にとっても、家族にとっても、領民にとっても、そして「彼」にとっても。
エイミーは改めて自分にそう言い聞かせつつ、手に持っていた銅貨と、いつも身に付けていた突剣をその場に置き、一人静かに部屋を出ていくのであった。
******
かつて、エーラム魔法学校に、フェルモ・ギンギラーシという名の少年がいた。しかし、彼は尊敬していた先輩に裏切られ、濡れ衣を着せられてエーラムからの逃亡を余儀なくされ、闇魔法師として生きることになった。その後、彼は逃亡の果てに
錆の戦車と呼ばれる特殊な魔境へと迷い込むことになる。
錆の戦車とは、漆黒の戦車のような外観を持つ神出鬼没の魔境であり、その内側に入り込んだ生物の「魂」を奪い、一つに纏めるという特殊な性質を有している。この地に入った者は生存を許されず、その精神だけが魔境の「中心部」へと送られる。その内側は、君主であっても騎士級以上の聖印を持たなければ呑まれてしまう程の「死の世界」であり、近年のカルタキア近辺に出現するどの魔境よりもその混沌の力は強大である。それでいて「強い者から離れる」という性質を有する移動式の魔境でもあるため、その発生地を特定すること自体が極めて困難であり、エーラム魔法師教会としても手に余る存在であった。
当然、そのような魔境に取り込まれたフェルモもまた、その魔境の内側において肉体は死を迎え、そのまま魂も吸収されることになる、筈であった。だが、肉体を失った彼の魂は、それまでに修得した混沌に関する知識と魔力を総動員して、この状況から生き残る道を模索した結果、その魔境内において比較的損傷の少ない一人の少女の肉体を発見する。
どうやら彼女の死体には聖印の残滓が宿っていた上に、その身にはもともと投影体の血が流れていたようで、そのおかげで「人としての肉体」がかろうじて維持されていたらしい。少年はその少女の死体に取り憑き、その残滓から聖印を再構築しつつ、その手に遺されていた護手鈎を駆使して魔境内を徘徊する大量の不死の怪物達と戦いながら、どうにか「錆の戦車」からの脱出に成功する。
なお、魔境の内側は時間の進み方が遅いようで、彼が魔境に囚われていた時の彼の体感時間は1日程度であったが、その外側では半年が経過しており、その間にフェルモの死体はエーラムの魔法師によって発見され、公式には彼の「死亡」が記録されていた。その後、フェルモの魂を宿した少女は、鋼球走破隊と出会い、以後は
フォリア・アズリル
と名を変えて、自身の聖印をタウロスに預けた上で、彼の一団に加わることになった(なお、「アズリル」の名は、少女の死体が手にしていた護手鈎に刻まれていた「Azur rill」の刻印に由来する)。
「あれから、もう2年か……」
先日の岩礁の魔境の浄化後、しばらく昏睡状態が続いていたフォリアは、その間に夢の中で上記の過去を思い出した上で、目覚めると同時にそう呟いた。あの時、「彼」が「彼女の死体」を乗っ取ることで、今の「フォリア・アズリル」という存在が生まれることになったということを、改めて思い出したのである。
「ぼくは『彼女』によって助けられた。そして、その後もいつも、誰かに助けられて生きている。ぼくの幸運は『生きていること』じゃなくて、『生かされていること』なんだ」
ちなみに、少女は魔境の中で、錆の戦車に対する強烈な復讐心を抱きながら命を落としていたため、その憎悪の心は今の「フォリアとしてのフェルモの魂」にも植え付けられている。その意味では「フォリア」自体が、極めて不安定なバランスの上に成り立っている存在なのである。
「……ならばぼくは、《恩も讐も忘れない》。受けた恩も返そう。与えた仇は贖おう」
フォリアは改めて護手鈎を握りつつ、そんな決意を固めると、やがて彼女(彼)の聖印は、タウロスやファニルと同じ「マローダー」としての紋様へと変容していく。だが、攻撃一辺倒の彼等とは異なり、どちらかと言えば、それは自分一人でも大軍を味方を守るための力を求めようとする彼(彼女)の想いの具現化体であった。
「拝啓 親愛なる妹 シャーロットへ……、と」
金剛不壊の
ルイス・ウィルドール
は、エーラムで修行中の実妹
シャーロット・メレテス
への手紙を書いていた。
シャーロットはルイスよりも3歳年下の12歳だが、幼少期に魔法の才能を見出されたことによって、エーラムの名門メレテス家の養女となり、現在は魔法師となるための勉学に励んでいる。気性は極めて真面目であり、風紀委員を務めているが、やや注意力散漫にな傾向もあり、やる気がから回って失敗してしまうことも少なくない。とはいえ、魔法師としては十分に優秀な素質の持ち主であることは疑いなく、おそらく数年以内に卒業して、契約魔法師となる資格を得ることになるだろう。
なお、一般的にはエーラム魔法学校の生徒は、入門した時点で実家との関係を断ち切られ、あくまでも「世界に対して中立の魔法師」となることが求められるが、シャーロットのように名門貴族家に生まれた「有資質者」の場合、例外的に手紙のやりとりなどが認められることもある。貴族家にとって、子供は一族の繁栄のために必要な「資産」の一部である以上、いくらエーラムからの要請があったと言っても、そう易々と無償で養子に出せるものではないため、何らかの条件を提示することもある。
シャーロットの場合は「卒業後には兄のルイスの契約魔法師として、ウィルドール家に連れ戻す」というのが、その条件であった。入門前からこのような約定を交わすことは本来の魔法師教会の理念には反するのだが、入門を拒否され、魔法の資質を有する者をエーラムの外で育成され続けるのもそれはそれで危険な話なので、エーラムとしてもやむなき妥協策なのだろう(なお、彼女の他にも、なぜか現在のエーラム魔法学校には貴族家出身の学生が多いらしい)。
ルイスは手紙を通じて、カルタキアでの近況を綴る。当初は君主としての様々な可能性を模索しようとしていた彼であったが、結局、最終的には自身の天分が「知」にあるということを再確認した上で、「知をもって民を護る君主」を目指す決意を固めることになった。その上で、いずれ自分が故郷に帰り、シャルロットもまた魔法師としての修行を終えて自身の契約魔法師となった時には、二人分の知識で一緒に頑張ろう、と書き記して筆を置く。
その上で、《シャーロットと再会した時、胸を張って立派な君主と言えるように》という誓いを胸に抱きつつ、机上に置いてあったインク瓶の蓋を閉めようとするが、ここで彼は、自身の内側に宿る聖印に「違和感」を感じる。
「あれ……? 今、何か……」
ルイスはその違和感の正体が気になったせいか、うっかり手元が狂って、インクをこぼしそうになってしまう。いや、彼の目には、確かに手元のインクが瓶から中身が溢れれ落ちる様子が映っていた。しかし、彼がその状況を止めたいと思った直後、彼の目の前の光景が「インクをこぼす直前」の状態にまで巻き戻っていた。ルイスはその一瞬の変化に驚きつつも、すぐさまインク瓶の蓋を締める。
「そうか、これが《巻き戻しの印》……」
どうやら彼の強い決意に応えるように、ルーラーとしての彼の聖印が、新たな力をルイスに与えていたらしい。先日ルーラーとして覚醒したばかりのルイスは、ここに来て、すぐさま君主としての「次の段階」へと急成長を遂げることになっていたようである。
******
一方、ルイスよりも先にルーラーとしての聖印を手に入れていた潮流戦線の
ハウラ
は、カルタキアの港の近くの海辺を散策しながら、先日の孤児院再建の際のヴィクトルとのやりとり、および(ミルシェによって再現された)「かつて自分が読んでいた絵本」を通じて、ノルドにいた頃の自分を思い出していた。
ハウラの父は故郷の地を治める領主ではあったが、ハウラはあくまで「愛人の子」であったため、実家の中では肩身が狭く、実質的には居場所がない状態だった。そのため、幼少期の彼女は家の書庫に籠もって本を読み漁る日々を送っていたのだが、そんな彼女を時折連れ出しては遊んでくれたのが、2歳年上の異母兄ヴィクトルであった。幼少期のハウラにとって、そんなヴィクトルが「兄以上の特別な存在」となったことも、無理からぬ話であろう。
その後、ハウラは医学の道を志し、ノルドと同じ大工房同盟に所属するユーミル(バルレア半島南東部)、ウィンザレア(ランフォード地方北西部)、アントリア(ブレトランド小大陸北部)といった国々を渡り歩きつつ、様々な医術の腕を磨きながら、今はダルタニアを中心とする同盟系混成部隊「潮流戦線」の一員として、カルタキアに辿り着き、そしてこの地で、ヴァーミリオン騎士団の一員となっていたヴィクトルとも再会することになった。
(私がこれまで研鑽し続けてきた医術の腕と、そしてこの身に宿った聖印の力を駆使することで、あの人の力になれるなら……、「あの物語」のように、側で支えられたなら……)
そんな気持ちを抱きつつ、ハウラは改めて聖印を掲げる。そして、自分の過去と現在、そしてこれから先の自分と向き合いながら、《あの人の側に立ち、支え続ける》という誓いを胸に抱く。
すると、彼女のその聖印に、微妙に新たな変化が生じた。ハウラは直後に、ルーラーとしての聖印を持つ者ならば誰でも可能な「時を僅かに遡らせる力」が、自分にも宿ったのではないか、という実感を得る。
彼女は試しに、近くに落ちていた小石を手にして、子供の頃にヴィクトルと共に遊んでいた頃を思い出しながら、「水切り」の要領で海面に向かって石を投げる。そして、彼女はその軌道を確認しながら、直後に自身の聖印に「やり直し」を願うと、彼女の周囲の時間が投石直前の状態にまで巻き戻された。彼女はそこから、最初とは微妙に角度を変えながら再び石を投げ込むと、先刻とは明らかに異なる軌道を描きながら、その石は海面に到達し、そこから3回撥ねた上で海の中へと消えていった。
「あー、これは巻き戻さない方が良かったかもしれないっすねー。最初の軌道のままだったら、5段くらいはいけたかも」
彼女はそう呟きつつ、確かに自分が《巻き戻しの印》を発動させていたことを自覚する。そして、この力があれば、自分が彼の隣にいることによって、彼を危機的状況から救えるかもしれない、という実感も得ていた。
叶わぬ恋とは知っていても、せめてこの地にいる間だけは、彼を支え続けたい。そんな願いを抱きながら、彼女は海辺を後にした。
******
そんなハウラと入れ替わりに、今度は潮流戦線のもう一人のルーラーである
ユリアーネ・クロイツェル
が海岸に現れる。既にすっかり陽は落ち、空には美しい月が輝く中、ユリアーネは蝙蝠のテレーゼと共に海岸を散策しながら、ふと月を見上げ、そして自らの聖印を掲げる。
「カノンさんがあれほど言うとは……。本当に無責任のお人よしなんですから」
ユリアーネは先日、この港にて、久しぶりにカノープスと遭遇した。その際に彼から「ユリアーネ自身の願望」について問われた。「ユリアーネに課せられた義務や役目」とは別の次元での、彼女自身の幸せについての見解を。
「私が『あのこと』を判断しなければいけないと言うのに」
彼女はそう呟きながら、あの時、彼に言われた言葉を思い返す。
「私の幸せを望んでいる……、なんて」
その言葉の意味を噛み締めながら、ユリアーネは改めて考える。自分と、彼と、彼と、そして彼女のことを。
「……」
言葉にならない思いが心の中を駆け巡る中、やがて彼女の中で「何か」が定まる。
「はぁ……。私も覚悟を決めましたわ。発した言葉には責任が伴いますし」
強い決意の瞳を浮かべながら、改めて彼女は、今の自分の状況に向き合うことにした。今の自分を取り巻く環境を踏まえた上での、自分自身の求めるものが何なのか。
「私が幸せになる道……、それだけならいくらでも思いつきます。何もかも捨てて逃げてしまえば、人並みの幸せなら簡単につかめますわ。でも、それでは駄目です。私は役割を放棄するわけにはいかないですし、それに……」
ここで彼女の心の中で、様々な人々の姿が思い浮かぶ。
「……私だけが人並みの幸せを得たとしても、それで私は満足しないです」
それが自分の偽らざる本音だと言うことに気付いた時点で、彼女はふと、あることに気付いて、一瞬、言葉を失う。
「……」
彼女はかつて、一人の従騎士に対して「欲張り」と評したことがあった。ユリアーネの目には、その従騎士が「手の届く範囲を全部守りたい」と考えているように思えたのである。自分自身の「欲」に気付いた時点で、その時の会話が思い起こされた。
「ふふふっ。私も相当の欲張りだったみたいですね」
自嘲気味にそう笑いながら、改めて彼女は、君主としての新たな誓いを立てる。それは、《私も幸せになる道を探す》という決意であった。
「どんな道になるのか、今は想像もできないですが……、まだまだここでやれることはあるはずですわ」
彼女がそう決意した瞬間、その掲げた聖印が新たな輝きを帯び始める。その光に引き寄せられたのか、一匹の羽虫のような何かが彼女に近付いてきたところで、ユリアーネの傍らにいた蝙蝠のテレーゼが、それを捕食しようとするが、テレーゼ自身もその光に見惚れていたために初動が遅く、逃げられてしまう。
だが、次の瞬間、ユリアーネの聖印が特殊な色彩を放ったかと思うと、テレーゼの周囲の時が一瞬だけ巻き戻った。そのことにテレーゼが気付いていたかは不明だが、ユリアーネに近付こうとしていた羽虫は(今度は)テレーゼの口の中にすっぽりと収まる。こうして、また一人、「時を巻き戻す力」を持つ者がカルタキアに現れたのであった。
******
ヴァーミリオン騎士団の
アレシア・エルス
は、焦っていた。先日、アレシアの中では「超えるべき存在」として据えていたカリーノがカルタキアに到着したことが、良くも悪くも彼女の中では刺激になったらしい。
そんな彼女の耳に、カルタキアの西方でゴブリンの群れの目撃情報が届いた。先日の廃坑の魔境の探索調査の際に、廃坑内にいたゴブリンは全て倒した筈だったが、どうやら彼女達の突入前にその廃坑から出て独自に行動していたゴブリン達の一団がいたらしい。
調査隊の本隊は廃坑の奥にある異世界の村へと向かう中、アレシアは一人でそのはぐれゴブリン達の殲滅任務を担うことにした。廃坑を通り抜ける際に愛馬アクチュエルを連れていくことが出来ない以上、野戦でゴブリン達を殲滅する方が自分には向いている、という考えもあっただろう。力無き民のために、かつて御伽噺で見たような英雄豪傑となるため、彼女は勇んでそのゴブリン達が生息していると思しき場所へと向かった。
だが、実際に現地へと向かった彼女を待っていたのは、予想以上の数のゴブリン達の群れであった。しかも、彼等を率いているのは、他のゴブリン達よりも一回り以上大柄な体躯の持ち主である。アレシアは、前回の調査時にアルエットから聞いたゴブリンに関する情報を思い出す。
「どうやら、彼女が言っていた『ホブゴブリン』という亜種のようだな」
鎧兜で表情が隠れた状態のままアレシアはそう呟きつつ、アクチュエルに騎乗した状態のまま、一気にそのホブゴブリンへと突撃し、馬上鑓で貫こうとする。大群とは言えども、所詮は下級妖魔の集団であり、指揮官さえ倒せば、統率を失ったゴブリン達など容易に殲滅出来ると考えていた。
しかし、彼女の一撃は確かにホブゴブリンの腹部に命中したものの、致命傷には至らず、突進の勢いを完全に止められる。その直後、他のゴブリン達が彼女を取り囲み、鞍上の彼女に対して斧を掲げて飛びかかるように襲いかかってきた。
「この程度の敵、あの御伽噺に出てきた英雄ならば、こうやって……」
彼女は強引に手綱を取ってゴブリン達の猛攻を避けつつ、そのままホブゴブリンに一撃を浴びせようとするが、さすがに無理のある体勢での騎操となってしまったこともあり、バランスを崩して落馬してしまう。
「な……!?」
突然視界が一変したことによる一瞬の困惑の中、アレシアから見て左側にいたゴブリンの斧が彼女の左腕に直撃し、激痛が響き渡る。すぐさま体勢を立て直そうとしたアレシアであったが、ここで彼女は、自分の左腕が満足に動かせない状態になっていることに気付く。どうやら、かなりの深傷だったらしい。
「大丈夫! 右腕一本だけでも、私は戦い抜いて見せる! 私は英雄となるんだ! たとえ満身創痍の状態でも、周りに味方がいなくても、あの御伽噺の英雄ならば……」
彼女が自分にそう言い聞かせながらゴブリン達に立ち向かおうとするが、そんな彼女の背中に対して、騎手を失ったアクチュエルが馬体を押し付けてくる。それはあたかも「一人で戦うな、自分も頼れ」と言っているかのような仕草であった。
そしてこの時、アレシアは思い出した。自分がこれまで共に闘ってきた仲間達の姿を。そして同時に、ローゼルにもらった絵本(不思議の国のアリス)の主人公の話や、ユージアルと交わした「誰かの真似じゃない、自分の物語の話」が頭をよぎる。
「そうだ……、私は『あの御伽噺に出てくる英雄』ではない。私が目指すべきは孤高の英雄ではなく、アクチュエルや他の仲間達と共に戦う『アレシアという名の一人の英雄』なんだ」
彼女はそう決意すると、自分の半身とも言える友の手綱を握り、再びその鞍上へと登る。すると、彼女の左手の聖印が浮かび上がり、右手の馬上鑓とアクチュエルが光を纏う。彼女は無意識のうちに《王騎の印》を発動させていたのである。
彼女はまずこの状況で「生き延びること」を優先すべきと判断した上で、自分を取り囲むゴブリン達の中から比較的包囲の脆そうな一角を見出し、一点突破を狙ってアクチュエルと共にその一角に向かって突進すると、見事にその包囲網を突破して、その戦場からの離脱に成功し、そのままひとまずカルタキアへと帰還する。
その後、彼女は他の従騎士達に対して自分の確認したゴブリン達の出現場所と状況を伝えつつ、改めて討伐隊を編成することを要請した上で、左腕の応急手当をおこなうと、ひとまず宿舎へと戻ることにした。
「これでいい。私は一人で戦う必要はない。これからは《皆を導く騎士アレシアとして、御伽噺の英雄と成る》」
アレシアは改めてそう誓いつつ、一刻も早く前線復帰出来るよう、今は怪我の治療に専念することにした。
最終更新:2022年03月06日 12:58