『見習い君主の混沌戦線』第11回結果報告(前編)
「この魔境に『たぬきさんが言ってた、きつねさん』が居るんだねー?」
カルタキアの軍議室にて、ヴァーミリオン騎士団の
ハウメア・キュビワノ
が、「京の魔境」の見取り図を見ながらそう呟いた。彼女の視線の先には、これまでの調査に参加していた金剛不壊の
メル・アントレ
と、
ペドロ・メサ
の姿がある。
先日まで彼女と共にいた妖狸・隠神刑部は、「桶狭間の魔境」の無限回廊を生み出したのは「九尾の狐」という妖狐であると言っていた。そして、この「京の魔境」では、帝に取り入る「玉藻前」と呼ばれる「大陸から渡ってきた化け狐」が暗躍しているらしい。同一個体かどうかは分からないが、その狐がこの京の魔境の鍵を握る存在である可能性は高そうである。
前回メル達が遭遇した茨木童子が言うには、玉藻前は「いつどこに現れるか分からない、不気味な存在」らしいが、帝の側近である以上、おそらく帝の住居である「御所」が本拠地なのだろう。そのことを踏まえた上で、ペドロはある一つの可能性に思い至っていた。
「前回、御所の場所を確認に行った時、『大陸から来たと思しき女性』の声が聞こえてきた。心に直接語りかけてきたところからして、何らかの妖術の使い手だと思う。もしかしたら、彼女がその『玉藻前』だったのかもしれない」
なお、彼女はペドロの中にかすかに残っていた「大陸の皇帝(劉備)の魂の残滓」に興味を示していた。どうやら「大陸の話」を聞きたいと考えていたらしい。
「一応、俺も『三国志演義』の内容は大体把握しているが、どうやらあの本に記されていた内容は『この京の魔境』よりも何百年も前の時代の出来事らしい。あの時の彼女の口ぶりからして、彼女達にとっての『最近の大陸の話』が聞きたいと考えているみたいだから、おそらく、俺の知識では彼女を満足させることは出来ないだろうな」
ペドロのその話を聞いたハウメアは、エーラム時代に聞いた話を思い出しながら、独り言のようにつぶやく。
「あー、さんごくしえんぎってのはー、聞いたことあるねー。たしか、クロードせんせーが話してたっけ。たしか、それとおなじ国の話で、おなじくらい人気のある、もっと後の時代の本もあるとかいってたような……」
彼女のその言葉に対し、メルが反応する。
「『三国志演義』がカルタキアの書庫にあったなら、その本もあったりするかな?」
「あるかもねー。ちょっと前に書庫でいろいろ仕事してたんだけど、その時におなじような世界の本が何冊かあるのを見かけたしー」
「題名、覚えてる?」
「えーっと、たしか、みずのほとりの……」
ハウメアが記憶を辿って思い出そうとしているところで、軍議室の扉が開き、京の魔境で出会った投影体の少女・清姫が現れる。
|
+
|
清姫 |

(出典:『平安幻想夜話 鵺鏡』p.172)
|
「安珍様! 私に隠れて女と密会ですか!?」
相変わらず、謎の妄想に取り憑かれた彼女は、メルに対してそう問い詰める。
「あー、いや、気持ちよさそうに寝てたから、起こすのも悪いかなー、って思って」
「言い訳なんか聞きたくありません! 誰ですか、その女!?」
「はじめましてー、あーしはハウメア。よろしくねー」
相変わらず、気の抜けた声で答えるハウメアであったが、清姫は鋭い視線で彼女を睨み続けている。しかし、メルはそんな彼女のことなど気にせず、話を続けた。
「その本が書庫にあるなら、それを利用して、僕は九尾の狐を探すことにしようと思う」
「じゃあ、あーしは御所に忍び込むことにしよーかなー。たてものの形が江戸とあんまり変わらないなら、床下から侵入することもできそーだし」
「それなら、俺は何人か他の従騎士達に協力を依頼して、その潜入を助けるための陽動役に回ることにしよう」
三人がそう話し合っているところに、清姫が更に割って入る。
「安珍様! また京に行くのですか!? まさか、下賎な関白にそのお身体を……」
先日の調査において、九尾の狐と並ぶ帝の側近である関白・藤原頼長は男色家で、美男子の色仕掛けに弱いという情報を得ていた。
「あー、その方法も考えたんだけど、さすがにちょっと襲われるのはイヤだから、そっちのルートは『別の従騎士』の人達に任せることにしたよ」
どうやら、前回の調査報告書を見た上で、自らその「汚れ仕事」を買って出てくれた者達がいるらしい。そしてこの時点で既に、彼等は一足先に京の魔境に潜入していた。
******
「ほほう、その髪色……、異人か?」
京の魔境の御所の近くに位置する屋敷にて、関白・藤原頼長は口元を緩ませつつ、目の前にかしずく小柄な美少年に対して声をかけた。
|
+
|
藤原頼長 |

(出典:『平安幻想夜話 鵺鏡』p.238)
|
「はい。私は異国より遠路はるばる、都の繁栄ぶりとその主の名声を聞きつけてきたのです」
そう答えた少年の名は、
コルネリオ・アージェンテーリ
。ヴェント・アウレオの一員である彼は、関白に対する「色仕掛け要因」として、この京の魔境に潜入していた。
「うむうむ、これはまた、未熟な少年ならではの芳しき香りを漂わせた、うるわしき出で立ちよのぉ。して、この館を訪ねてきたのは、いかなる要件でおじゃるか?」
「出来ることならば、この華やかなる京の御所の衛士として士官したいと考えています。そのためには、まずは絶大な力を持つ関白様にお頼みするのが良いと、そう聞いて…………」
「ほほう、衛士とな。志は立派じゃが、その歳で士官とは、まだ少し早いのではないか? まずは武士となる前に、この国で生きていくための手解きを、麿が手取り足取り……」
「いえ、まだ未熟かもしれませぬが、これまでにもこの弓で、数多の戦いを切り抜けてきました。今の私であれば、きっと関白様のお役に立てると思います」
コルネリオはそう言って、自身の弓を掲げる。
「ふむ……、異国の弓か。確かに、小柄な体型の割には精悍な手付きのようにも見える」
頼長は男色に溺れた堕落貴族とも言われているが、その一方で、政治家として実質的な最高権力者である関白まで登りつめただけのことはあり、相応の人物眼の持ち主でもあるらしい。
「お願いします、これまで主無くして磨いた弓の腕を、偉大な御方のために役立てたいのです。この大願が叶うなら”何だって”します」
コルネリオは目を輝かせながらそう訴える。彼は決して色事の類いに通じている訳ではなかったが、母が商人の妾だったこともあり、権力者を接待するために必要な視線や表情の作り方などに関しては、それなりに理解していた。その上で、この世界における実質的な最高権力者が好みそうな「無垢で素直な衛士に憧れる少年」を見事に演じきっていたのである。
「うむうむ、憂いやつよのう。ちこうよれ、麿にその顔を、もっとよく見せてたもれ」
頼長が身を乗り出しながらそう口にしたところで、コルネリオとは別の、中性的な声がその場に割って入るように響き渡った。
「関白殿下!」
その声の主は、コルネリオの傍らに侍っていた、もう一人の従騎士である。その従騎士は、顔まで隠れた全身鎧に身を包んだ状態であり、その物々しい姿故に、頼長は当初は訝しげな視線を向けていたが、その声を聞いた瞬間、その従騎士に対する目の色が変わる。
「……今のは、そちの声か?」
「はい。私もまた、関白殿下の名声を聞き及び、士官の道の手助けをして頂きたいと考え、参上した次第です」
「ほう……、そちもまた、なかなかに美しき声色の持ち主のようじゃが、麿を前にして兜を被ったままとは、無礼ではないか?」
「仰る通りではございますが、それはまだ出来ぬのです」
「む? それは何故じゃ?」
「我が一族には、武人が自らの素顔を見せて良いのは『生涯を捧げた相手』ただ一人のみ、という掟があるのです。故に、私がこの素顔を誰かに見られた時、私にはその者を『愛する』か『殺す』か、そのいずれかの道を選ばねばなりませぬ」
「ほほう、つまり、麿がそちを愛すれば良い、ということか」
頼長は口元を緩めながらそう言った。彼の耳にはその鎧騎士の声質が「うら若き美青年の声」のように聞こえたようで、脳内でその兜の下の素顔について妄想し始める。物々しい重装備の割には線の細い声のように聞こえたのだが、その違和感がまたより一層興味を掻き立てていた。
「はい。その通りです。しかし、今の私ではまだ殿下の寵愛を受けるに足る立場ではありませぬ。故に、堂々と殿下の愛を受けるに足るだけの存在となるために、まずは御所を守る衛士として推挙して頂きたいのです」
「なるほどのう……、その身持ちの固さに焦らされるのもまた一興。良かろう。二人とも、麿が御所の者達に話をつけてやろう。ついて参れ」
頼長はそう告げると、ニヤけた表情を浮かべながら、出立の支度を始める。
(言うだけタダだもんね。勿論、素直に言いなりになる気はないともさ)
コルネリオが内心でそう呟く一方で、隣の鎧騎士は密かに咳払いをしていた。
(少し無理して低い声を出してみたが、男性の声に聞こえただろうか……)
ヴァーミリオン騎士団の
アレシア・エルス
がそんな不安に駆られていることなど露知らず、関白・藤原頼長は、美少年と美青年に両脇に抱えた状態で酒色に溺れる未来図を思い浮かべながら、心を弾ませていた。
******
「兄弟一二三四五♪ 兄弟个十百千万♪」
メルはそんな歌を口ずさみながら、京の御所の近くを歩き回っていた。その傍らには、当然のごとく清姫の姿がいる。彼女はうっとりとした表情でメルの歌声に聞き入りつつ、彼の袖を引きながら問いかける。
「安珍様、それが『大陸の英雄達の歌』なのですか?」
「うん。カルタキアの資料によると、作られたのはもっと後の時代らしいけど、題材となっている英雄達は、だいたい『今』と同じくらい年代の大陸の人達らしいよ」
メルはそう答えつつ、周囲の人々が自分に好奇の視線を向けていることに気付きつつ、笑顔を振りまきながら、「大陸風の発音」で歌い続ける。
「兄弟相逢三碗酒♪ 兄弟论道两杯茶♪ 兄弟上阵一群狼♪ 兄弟拉车八匹马♪」
すると、やがてそんな彼の前に、一人の女性が姿を現した。その背後には、九本の狐の尾のような何かが蠢いている。
|
+
|
九尾を持つ女性 |

(出典:『平安幻想夜話 鵺鏡』p.214)
|
「なんとも懐かしき唐の国の言葉の響きよ。そなた、風貌からして西域……、いや、もっと西方からの渡来人か? あるいは……」
その女性は含みをもたせた笑みを浮かべながら問いかける。
「……アトラタン人か?」
どこか色香を漂わせたような声色の彼女に対して、清姫が敵意を剥き出しにして何か叫ぼとうとするが、それを事前に察したメルが手で制する。
「そうだよ。僕はメル、ハルーシアの軍艦『金剛不壊』の船員。アトラタンのことを知ってるってことは、君は……、理解してる人?」
「うむ、理解しておるぞ。わらわは投影体。混沌によって生み出された『本来のわらわ』の複製体。それがわらわの正体。違うておるか?」
「あー、うん、そこまで分かってるなら、話は早いね。というか、そこまで分かってるということは、もしかして君は、何度もこの世界に現れたことがあったりする?」
「そうさのう……、まぁ、わらわの身の上について話すのは構わぬが、その前に、その『歌』について聞かせてほしい。そこで謳われているのは、どのような物語なのかえ?」
彼女がそう問いかけると、メルは懐から一冊の本を取り出す。
「詳しくは、これを読めば分かると思うよ」
そう言ってメルが差し出した本の表題には『水滸傳』と記されていた。
******
「そろそろ、ハウメアさんの潜入の準備も整った頃かな……」
「今回は楽な仕事だな。とりあえず、目立つように暴れればいいんだろう?」
カリーノにとっては、これが「マローダー」としての初陣であり、「派手に大立ち回りして投影体達の注意を引く任務」と聞いて参戦を決意したようである。
「とはいえ、丸腰の連中を相手に暴れる気にもなれないしな。さて、手っ取り早く警備兵を集めるには、どうすれば……」
彼女がそう呟いたところで、ペドロの隣にいた「もう一人の従騎士」が長剣を掲げながら飛び出した。
「くたばれ! 化け物が!」
その声の主は、星屑十字軍の
コルム・ドハーディ
である。彼はあえて目立つように(現地人とは明らかに異なる)「いつもの正装」の身を包んだ上で、御所へと向かいつつある一台の「牛車」へと向かって走り込んだ。これは、京の都において主に「位の高い人物」の御装用に用いられている乗騎である。まさに、敵の目を引くための襲撃対象としては、うってつけの存在であった。
だが、そんな彼の前に、牛車の護衛をしていた「鎧騎士」が立ちはだかる。
「関白殿下! ここは私に任せてお逃げ下さい!」
アレシアである。別に何も示し合わせた訳ではなかったのだが、コルムが斬りかかったのは、御所に向かおうとしていた関白・藤原頼長の牛車だったのである。そして、彼女の姿が現れた瞬間、後方からカリーノが駆け込んで来た。
「どけ! そいつはアタシの獲物だ!」
楽しそうな表情を浮かべつつ、大剣を大上段に振り被った状態で突進してくるカリーノを目の当たりにして、兜の下のアレシアは驚く。
(な、なぜ彼女がここに……!?)
カルタキア来訪以前からの知己である二人だが、今回は互いに相手の動向を確認しないまま、それぞれの任務に就いていた。そんな中、カリーノの方はすぐに「この状況」を概ね把握した上で、あえてアレシアに対して全力で斬りかかる。
(やるからには「本気」でやらないと、関白とやらもお前のことを信用しないだろう?)
そんな彼女の意図を察したのか、アレシアも自身のその剣で彼女の猛攻を受け止める。
(剣圧が以前よりも重い……、そうか、聖印を覚醒させたのだな……)
とはいえ、「マローダーの聖印」の本領が発揮されるのは「一対多」の状況であり、一騎打ちにおいてはそこまで強大な効果は発生しない。一方で、アレシアもまた現状は(今回は戦う予定ではなかったため)愛馬アクチュエルを連れてきていないこともあり、「キャヴァリアーの聖印」の効果は発動出来ない。その結果、二人はしばらくの間、互いに自身の聖印の力を本格的活用出来ない状態のまま、「素の状態」での剣戟を繰り広げることになる。
一方、アレシアの相手をカリーノに譲ったコルムの前には他の護衛達が立ちふさがり、その間に関白を載せた牛車は御所へと全力で駆け込んでいく。現在のコルムもまた騎乗状態ではないため、キャヴァリアーとしての追走能力を発揮出来ず、そして関白の牛車の中からコルネリオが、コルムに向かって牽制の矢を放つ。
(まさか、ここで遭遇するとは思わなかったけど……、まぁ、これはこれでお互いにとって好都合かな)
コルネリオは《光弾の印》を用いた上でコルムの足元を狙って矢を放つと、コルムはそれに対して大袈裟に驚きながら叫ぶ。
「おのれ! 妖術を使うか! この、人の皮を被った怪物め!」
やや芝居がかった言い回しで周囲の視線を集めようとするコルムに対し、御所の周囲の検非違使達もまた反応して駆け込んでくる。
「こやつら、稀人か!?」
「生き埋めにしてくれるわ!」
検非違使達がそう叫びながらコルムを取り囲もうとするところで、今度はペドロが彼の背中を守るように立ちはだかる。
「我が名は劉備北瀞! 義を見てせざるは勇無きなり! 妖怪に媚び諂う信無き者達よ、我が聖印に跪け!」
地下帝国の魔境で身につけたハッタリ口上を再び用いた上で、彼は聖印を天に掲げて周囲を照らし出す。その輝きはより多くの人々の視線を彼等に向けさせることになるのであった。
******
(うんうん、いいカンジにもりあげてくれてるみたいだねー、ありがとー)
御所の近くに潜んでいたハウメアは、ペドロ達の陽動の間に「床下」への潜入に成功していた。彼女は研ぎ澄ませた霊感を駆使しつつ、床上の「人」がいないルートを探しながら、少しずつ御所の中心と思しき区画へと潜入していく。
(外からみた雰囲気からして、たぶん、こっちが『みかど』のすみかだと思うんだけど、こっちからはあんまりつよい混沌核の気配がしないんだよねー……)
それでもどうにか魔境の混沌核を探すため、必死で床下を這いずり回り続けたハウメアは、やがて「あること」に気付く。
(なんか、「下」の方から、へんな気配がする……?)
床下の更に「下」とは、すなわち地下である。魔境の混沌核が地下に眠っている可能性自体は十分にあり得る話だが、霊感が優れたハウメアには、それが「この魔境全体の混沌核」ではなく、それとはまた別の何かのように感じられた。
(……もしかして、この下にもうひとつ「別の魔境」がある……?)
明確な根拠はない。だが、彼女の直感がそう告げている。しかし、この「地下」に何が潜んでいるにせよ、さすがにこの状況から一人で掘り進めていくのは不可能である以上、今の「指揮官不在の調査部隊」に出来ることはない。いずれかの指揮官を中心に浄化部隊を編成した上で、全力でこの「御所」を制圧して掘り進めて調べるしかないだろう。
(じゃあ、せめてそのまえに、この「御所」の構造を、もうすこし調べておこうかな)
端から見ただけでは、この「御所」自体はあくまで「巨大な屋敷」であり、城や砦のような防衛機能は無いように見えるが、妖怪達が闊歩する世界である以上、何らかの結界などが張り巡らせられている可能性もある。ひとまず調査部隊として、今の時点で調べられる限りのことは調べておこうと考えた彼女は、そのまましばらく床下からの調査を続けることにした。
******
「ふむ、なるほどのう……。天然の要塞に立てこもった百八人の魔星か。わらわが大陸を離れている間に、そのようなことが起きていようとはな」
京の街角で九尾の狐は『水滸傳』を興味深そうな表情で読み耽っていた。そんな彼女の様子を、メルは改めてじっくりと観察する。
(かなり強大な混沌の気配を感じる。でも、前に桶狭間で見た「今川義元」とは、ちょっと違う気がする……、魔境全体の混沌核というよりは、また別の何かのような……)
メルがそんな疑念を抱いている傍らでは、清姫が相変わらず険しい表情を浮かべている。
「安珍様! なぜ、その女のことをそんな真剣な瞳で見つめているのですか! 私のことは、そんなにじっくりと見て下さったこともないのに! その女狐のことが、そんなに気になるのですか!」
彼女のそんな声には一切耳を傾けずに思考を巡らせるメルに対し、九尾の狐の方から声をかけてきた。
「わらわのことが気になるなら、そろそろ色々と話してやっても良いぞよ。なかなかに面白い書物を読ませてくれたからな」
どこか上機嫌そうな彼女に対して、メルは遠慮なく問いかけることにした。
「まず、君が『玉藻前』でいいのかな?」
「うむ、『今』はそう呼ばれておる」
「『隠神刑部』っていう狸のことは、知ってる?」
「四国の化け狸の頭領であったかな? まぁ、知っておると言えば知っておるが、特段縁がある訳でもない。辺境の小島の小妖怪のことなど、気にかける義理もない」
「桶狭間に無限回廊を作ったのは、君?」
「その通り。そのことを知っているということは、どうやらあの『魔境』を浄化したのも、そなたなのか?」
「僕が浄化した訳じゃないけど、その場にはいたよ」
メルはそう答えつつ、ここで一つの疑問が湧き上がる。桶狭間に無限回廊が生み出された時点で、「今の『京』の魔境」はまだ存在していない。あの時点でこの地に存在していたのは、「もっと前の時代の『京』の魔境」だった筈である。
「君があの時点で既にこの世界に投影されていたということは、君は『この京の魔境』の住人ではない、ということ?」
少なくとも、この九尾の狐が「今の『京』の魔境」よりも先に出現していたということは、彼女はこの魔境の副産物としての投影体とは考えにくい。
「いや、この街はわらわの住んでいた京の都そのもの。わらわの『本体』は、今も元の世界で、この京の都で生きておることであろうな」
「……じゃあ、どうしてこの魔境よりも先に、君がこの世界にいたの?」
「別に何もおかしな話ではなかろう。わらわがこの世界に投影されたのは、もう何百年も前のこと。そして、そのわらわがつい先日召喚に成功したのが今のこの京の都なのだから」
魔境の付属物としてではなく、独立した形で出現する投影体自体は、特に珍しい存在ではない(栃木の魔境の浄化時に救援に来ていた九十九ことりなども、その一人である)。しかし、「自ら魔境を生み出すことが可能な投影体」となると、極めて稀な存在である。ある意味、それは魔境そのものよりも危険な存在と言えよう。
「わらわは何百年も前から、『わらわの住んでいた京の都』をこの世界に投影させたいと考えておった。そのために自らの力を高め、世界各地を転々としながら、魔境の投影に適した土地を探して回った。そして、このカルタキア近辺の地では魔境の出現率が高いと聞き、綿密な下準備の上で、『わらわの京』の出現を試みたのじゃ」
彼女はメルが「魔境を浄化しようとする者」であることを承知の上で、あっさりとそんな話を語り聞かせる。彼女の中ではそれは「大陸の話」を聞かせてくれたことへの返礼のつもりらしいが、それと同時に「こんな矮小な君主に、自分の魔境が浄化される筈はない」という絶対的な自信もあるのだろう。
「しかし、残念ながら一回目の魔境投影は失敗であった。『わらわの京』とは似て非なる世界が投影されてしもうてな。もしかしたら、それは『わらわの京』の未来の姿なのかもしれぬが、いずれにせよ、それはわらわが望んだものではなかった」
おそらく、それがレオノールやジーベン達によって浄化された「最初の京(慶応元年の京)」だったのであろう。
「そして、気付けば東方にもまた『わらわの世界とは似て非なる東国の渓谷』が出現しておった。物々しい死霊の群れどもが京を目指して進軍して来るように見えたので、面倒なことになる前に無限回廊を生み出し、その中に封じ込めておいた」
玉藻前は、ここまで話したところで一瞬、「何かに気付いたような表情」を見せるが、メルはその表情の意味が分からないまま、黙って話を聞き続ける(なお、この「渓谷」が桶狭間の魔境のことを指していることは、当然メルも理解している)。そして、玉藻前は微妙に怪訝そうな顔を浮かべながらも、そのまま話を続けた。
「加えて、更にその東方にもまた『更なる東国の魔境』が出現しておったので、そちらの様子も確認しようと赴いてみたが、そこには矮小な河童共しかおらなんだ。故に、そちらは放置して、ひとまず『この地』に戻って来たら、既に『わらわの京とは似て非なる京』が消滅しておった。それを浄化したのも、そなた達なのか?」
「僕自身は参加してなかったけど、浄化したのは僕の仲間達だね」
「なるほどな。まぁ、どうせあの魔境は『失敗作』。むしろ消してくれたことは、わらわにとっても好都合。その上で、微妙に残っていた『京』の残滓を触媒とした上で、今度こそ、『わらわの京』の投影に成功した、ということだ。理解出来たかのう?」
「まぁ、なんとなく……」
メルはそう答えつつ、ふと気になったことを問いかけてみる。
「……そういえば、この『京』が君の住んでいた世界なのだとしたら、この魔境を召喚した時点で、他の住人達と一緒に『君自身』も投影されたの?」
同一存在が同時にこの世界に投影されるという現象は、アトラタンでは珍しい話ではない。
「あぁ。おったぞ。もっとも、わらわは二人も必要ない故、すぐに殺したがな」
その感性が投影体として正常なのかどうかは分からないが、彼女の中では、特にそこに抵抗感などは無かったらしい。
「さて、次はそなたの話を聞かせてもろうても良いかな?」
「……いいよ」
「そなたらは、この地を浄化するために来たのか?」
表情そのものはまだ笑みを浮かべているが、その漆黒の瞳からは、闇よりも暗い危険な気配が漂っていた。
「僕には、それを決める権限はないよ。ただ、この街の様子を確認に来ただけだから」
この状況では、そう答えるしかない。
「つまり、そなたの報告内容次第で、カルタキアの君主達が、この地を浄化しようと考えるか否かが決まる、ということか?」
「そういうことになるかな。少なくとも、僕が帰らなければ、もっと強力な君主が派遣されて来ることになるだろうね」
「今のカルタキアには、どれほどの戦力がいる?」
「僕も正確に全戦力を把握してる訳じゃないけど、まぁ、この土地では魔法が通じないからね。君主だけでどこまで戦えるかは分からないよ」
「魔法が通じないと言うても、それはあくまで『エーラムの魔法』のみであろう? 現に、先程そなたの背後に現れた『烏帽子の男』は、明らかに妖術の類を用いておったではないか」
「エボシの男?」
唐突に意味の分からないことを言われたメルは、思わず背後を見るが、そこには誰もいない。この「誰もいない」という状況から、ようやくメルは「あること」に気付く。
「あれ? 清姫!?」
「おや、気付いておらなんだのか」
「え?」
「つい先程、『烏帽子を付けた眼鏡の男』が、そなたの連れの娘を連れて、謎の異空間に消えていったぞ。てっきり、そなたの仲間かと思うておったが、違うのか?」
それは、玉藻前が「桶狭間の魔境」の話をしていた時に一瞬「何かに気付いたような表情」を見せた時の出来事であった。メルはそのことに全く気付いていなかったが、それがメルが彼女に対して全く無関心だったが故なのか、それとも、何か特殊な力による「気配遮断」の結果なのかは分からない。
この状況に対して明らかに困惑した様子のメルを見て、玉藻前は険しい表情を浮かべる。
「あの娘、見た目は幼いが、その内側に秘めたる力は、この京の都の魑魅魍魎達の大半よりも上の筈……。その彼女を、一瞬にして連れ去ることが出来るとしたら、相当な力の持ち主……。明らかに投影体のようではあったが、『わらわの京』であのような男を見た記憶はない……」
何らかの「嫌な予感」を感じ取った彼女は、御所に視線を向け、そして次の瞬間、メルの前からうっすらと消失していく。だが、おそらくそれは混沌核の消滅ではなく、何らかの妖術の類いによって姿を消したか、もしくはどこかに転移したのであろうとメルは推測する。
(なんだかよく分からないけど、これはかなり厄介な状態なのでは……?)
玉藻前が話していたことが本当なら、おそらく彼女を浄化してもこの魔境は消滅せず、別に存在するであろう「魔境の混沌核」を浄化する必要がある。だが、彼女が生きている限り、おそらく再び「自身の投影元の世界」を出現させようとするであろうから、どちらにしても彼女も浄化(もしくは説得)する必要がある。
更に、それに加えて「烏帽子の男」という、おそらくはこの魔境とは無関係に出現した強大な投影体にも対処する必要があるらしい。その男がなぜ清姫を連れ去ったのかは分からないが、状況次第ではこちらもまた何らかの危険要素となりかねない。
「とりあえず、皆と合流するか……」
メルはそう呟きつつ、ひとまず御所へと向かって走り出すのであった。
******
その頃、御所の近くの大路で戦いを繰り広げていたペドロ、コルム、カリーノの三人は、次々と現れる検非違使達の物量の前に、さすがに劣勢になりつつあった。
「……今回は、これだけ損害を与えれば十分か」
コルムはそう呟くと、ペドロとカリーノもその言葉に頷きつつ、三人はその場から路地裏の方へと撤退していく。検非違使達がそれを追いかけようとするが、三人が向かった先には、三頭の馬が繋がれていた。
これはコルムによる献策である。投影体を前にして無謀に突撃したように見えた彼であったが、実はあらかじめ、撤退時のことを想定した上で、カルタキアから馬を連れてきつつ、敵を油断させるためにそれらを密かに路地裏に隠していたのであった。
だが、ここで一つ、想定外の事態が発生する。ペドロが馬に飛び乗ろうとした瞬間、彼の目の前で突然、混沌核が収束を始めたのである。
「おぉっと!?」
思わず仰け反ってしまったペドロは、体勢を崩してしまう。その次の瞬間、彼の目の前には不気味な様相の妖怪が姿を現した。それは、前回の調査時に茨木童子の屋敷で遭遇した妖怪と同系統と思しき個体である。彼(?)は人間に対して本能的な敵意を有していたようで、出現した直後に、目の前にいたペドロに対して襲いかかってきた。体勢を崩していたペドロは、無防備な状態でその妖怪に腹を一突きされる未来が思い浮かんだが、次の瞬間、彼はすぐに体勢を立て直して、まるで時間が巻き戻ったかの如く、見事な剣捌きでその妖怪を薙ぎ払う。
(い、今のは……!?)
自分の身に何が起きたかも分からないまま、ひとまずペドロは馬に飛び乗り、そのままコルム、カリーノと共にその場から駆け去って行く。
そんな彼等の様子を、物陰から見守っていた従騎士がいた。ハウメアである。
(よかったー、《巻き戻しの印》がまにあったみたいだねー)
彼女は内心でそう呟きつつ、検非違使達の視線がペドロ達に向いている間に、ひっそりと自分もまたその場から立ち去って行く。
一方、カリーノとの間で「派手な立ち回り」を演じていたアレシアは、他の従者達よりも先に、御所へと向かって走り出していた。
(まったく、あそこまで本気でやらなくても良かっただろうに……)
身体の節々に感じる痛みを実感しつつも、久しぶりの盟友との手合わせに、アレシアはどこか充足感を感じてもいた。
そして、無事に御所の中へと駆け込んだアレシアに対して、頼長は怯えた様子で声をかける。
「おぉ……、無事であったか。あの賊共は、討ち果たしたのか?」
「ひとまず撃退し、現在は検非違使達が追走中です。殿下の御身には傷などはございまぬか?」
「う、うむ。どうにかな……。じゃが、どうやらこの御所内にも賊が入り込んでおるらしい」
「そうなのですか?」
「さきほど、あの弓使いの少年が、『怪しげな影』を見つけたと言って、あちらに駆け出して行ったのじゃ」
それがコルネリオの(頼長から離れるための)方便だろうということは、アレシアにもすぐに予想がつく。
「では、私も彼の加勢に向かいます。関白殿下は、ひとまず安全な場所へお隠れ下さい」
アレシアはそう告げた上で、彼女もまたコルネリオが向かったという方面へと向かって駆け出して行った。
******
(潜入成功! あの手の手合いは良いように転がしてなんぼ、ってね!)
コルネリオはそんなことを考えつつ、御所の内部を走り回りつつ、大声で叫び続ける。
「危険な賊が潜入しています! 衛士の皆さんは、帝や姫君達の警備に徹して下さい!」
彼のその声を聞いた御所の人々は、それぞれの私室内へと閉じ籠もり、衛士達の間にも動揺が広がる。そんな中、コルネリオは御所の一角から、強烈な混沌核の力を感じる。
(これは……、見つけたかも!?)
コルネリオがその気配のする方面へと向かって駆け出すと、その先から叫び声が聞こえてくる。
「き、貴様、何も……、ぐぁっ!」
「い、今、一体何を……、うっ……!」
それは、衛士と思しき者達の断末魔の叫び声だった。
(あれ……? アレシアさんが、僕よりも先に入り込んだのかな?)
先刻の状況からして、アレシアが自分よりも先に御所の奥地に入り込んでいるというのは奇妙な話である。そもそも、アレシアはあまり「人間(の形状をした投影体)の殺生」を好まない性格であり、あくまでも調査任務である今回の潜入作戦において、自ら率先して荒事を起こすとは考えにくい。
コルネリオがそんな違和感を感じながら、その声が聞こえてきた方角へと向かうと、そこには「心臓を抉り取られたような状態で倒れている衛士達の死体」が転がっていた。
(これは……、どう見てもアレシアさんの戦い方じゃない!)
そう確信した彼が視線をその先へと向かうと、そこは宝物庫のような部屋となっており、そこには一人の「烏帽子を付けた、眼鏡をかけた男」の姿があった。
彼の手には、奇妙な形状の「翡翠のような色の勾玉」が握られている。彼はそれを見ながらニヤリと笑いつつ、コルネリオが来たことに気付くと、彼に向かって話しかけた。
「カルタキアの従騎士か。一歩遅かったな」
「誰だ、あんたは!?」
「我が名は春日恭二。この魔境は、私が貰い受ける」
烏帽子の男はそう言い放ちつつ、その「勾玉」を強く握り締める。この時、コルネリオはその「男」と「勾玉」から、同じくらい強大な力を感じ取る。そして、それはどちらも「魔境全体の混沌核」と思しき気配を漂わせていた。
(え? どういうこと……?)
コルネリオが混乱する中、その烏帽子の男は「勾玉」を自身の心臓へと近付け、そのまま身体の中へと「取り込んで」いく。すると、両者の混沌核が一体化し、コルネリオがこれまでに見たことがない程の強大な混沌の力が彼の周囲に漂っている。
「さぁ、見るが良い! 『二つの京の魔境』が融合した姿を!」
彼がそう叫ぶと、地中から謎の力が湧き上がり、そして、魔境の姿が微妙に変容していく。
「え? なに!? なにが起きてるの!?」
事態を把握出来ないコルネリオの混乱が更に広がる中、烏帽子の男は目の前で何らかの「印」を結ぶような動作を始める。
「受けてみよ、『真の平安京』の支配者となったこの私の呪力を!」
彼がそう言い終えると同時に、謎の怪光がコルネリオを襲う。だが、そこへ激しい金属音と共に駆け込んで来る者がいた。
「アレシアさん!?」
コルネリオがそう叫んだ瞬間、彼の目の前でアレシアはその身を以って怪光を受け止め、そして彼女の身を包んでいた全身鎧は(兜の部分も含めて)一瞬にして弾け飛んだ。
当然、アレシアもまた、目の前にいる男が何者なのかは全く分かっていない。だが、それでも彼から溢れ出す混沌の力の強さから、おそらく彼が「魔境全体の混沌核」であろうことは推測出来る。どう考えても、本来の武具を備えていない今のこの二人で勝てる相手ではないだろう。
「撤退だ! 」
「う、うん、そうだね!」
二人はすぐさまその場から走り去る。烏帽子の男はそんな彼等を余裕の笑みを浮かべながら見送っていた。
「さぁ、せっかく手に入れたこの魔境、今からじっくりと整備を始めなくてはな。『他の私達』に遅れをとる訳にはいかぬ」
そう呟きなら、男はゆっくりと御所の最深部へと向かって行くのであった。
******
御所の内部で発生した「謎の怪現象」の影響を受けていたのは、御所だけではなかった。この「京の魔境」全体が、地中から発せられた謎の力によって、少しずつ変容を遂げていたのである。
そのことは当然、御所へと向かおうとしていたメルもまた実感する。
「これは……、魔境が作り変えられている……?」
メルが困惑する表情を浮かべる中、やがてメルの目の前に、清姫が姿を現す。だが、その表情は、以前の彼女とは一変していた。
「あなた、安珍様じゃなかったのね……」
その目には、激しい憎悪の炎が宿っていた。
「あ、うん、そうだよ。というか、僕は何度も君にそう言って……」
「騙してたのね……、許さない……、許さないんだから!!」
彼女はそう叫びつつ、これまで見たことがない程の強大な力を以って、メルに向かって襲いかかろうとする。だが、彼女の手がメルに届くよりも一瞬早く、御所の方面から駆け込んできた騎影が割って入った。ペドロ、コルム、カリーノの三人である。
「メル! 撤退だ!」
ペドロがそう叫びながらメルに手を伸ばし、そのまま彼を抱え上げるように自身の馬上に乗せる。当初、ペドロは二人の姿を見た時点で、二人共回収するつもりであったが、清姫の様子が明らかに異様であることに気付いた彼は、すぐさまメルに問いかける。
「彼女は、一体……?」
「分からないけど、とりあえず、今はこのまま逃げよう」
メルにそう言われたペドロ達は、そのまま京の都の外へと駆け出していくのであった。
******
その後、メル達四人は、ハウメア、コルネリオ、アレシアとも魔境の外で合流した上で、それぞれが得た情報を照らし合わせる形で、状況を整理する。
まず、「烏帽子の男」が名乗っていた春日恭二という名前は、現在調査中のもう一つの「魔境(21世紀の東京近郊の街)」に生息していると言われる投影体「ディアボロス」の異名(本名?)とほぼ同じである。完全に同一人物なのかどうかは分からないが、少なくとも無関係な存在ではないだろう。
その上で、この地に「京の魔境」を生み出した玉藻前自身が彼の存在を知らず、そしてハウメアが感じ取った「地中に存在するもう一つの魔境の気配」と、コルネリオの前でおこなわれていた「二つの混沌核の融合」という状況から察するに、以下のような推測が成り立つ。
おそらく、春日恭二が手にしていた「勾玉」は「地上に出現していた京の魔境」の混沌核だったと推測出来る。その上で、春日恭二と玉藻前はもともと「よく似た別の世界(平行世界)」の投影体であり、前者はこの地の地下に「自分の出身世界の魔境」を発生させ、自分自身がその魔境の混沌核となっていた。そして、「地上の京」の混沌核である勾玉を自身が吸収することによって、その「よく似た二つの京」が融合することになった、ということなのだろう。
その結果、この新たに出現した「融合京(?)」が、以前と比べてどこまで変容したのかは分からない。更に言えば、なぜ清姫の様子が変貌したのか、玉藻前が今どこにいるのか、茨木童子や藤原頼長がどうなったのかも分からない。しかし、少なくとも現状の魔境の混沌核が「春日恭二」という投影体であることは(彼を目の当たりにしたコルネリオとアレシアの直感に狂いが無い限り)間違いない以上、調査隊としての任務は既に完了したと言える。
こうなれば、いつも通りに指揮官達が率いる浄化部隊に後のことを委ねればいい、その筈であった。
ところが、カルタキアへの帰還の途中で、従騎士達の聖印に「異変」が発生する。最初に「それ」が発生したのは、コルムの聖印であった。
(…………総帥殿!?)
コルムの聖印は、星屑十字軍の総帥であるレオノールの従属聖印であり、彼の精神は常にレオノールと一定の「繋がり」を有している。その「繋がり」が唐突に途切れ、コルムの聖印が独立聖印と化したのである。
ここから推測出来る可能性は、以下の三つであった。
1、レオノールの聖印が消滅した
2、レオノールがコルムとの「精神的関係」を断ち切った
3、何らかの怪現象により、レオノールの聖印に想定外の異変が発生した
「1」の場合、レオノールが死亡したか、もしくは何らかの理由で聖印を手放した(奪われた?)か、あるいは(極めて稀な事例だが)聖印そのものが何らかの形で混沌核化してしまったという可能性もありうる。
「2」に関してはレオノール次第でいつでも可能だが、もし、レオノールの中で何らかの理由でコルムを「破門」しようとするなら、彼の従属聖印を没収する形になる可能性が高く(それは、どれだけ離れていても可能)、唐突に独立聖印化させるというのは、明らかに不自然である。
「3」については、具体的な実例が思いつかない以上、何とも推測の仕様がない。
(何が起きている……? 総帥殿は現在、結婚式場の建設に従事している筈。危険な任務に就いている訳でもないのに……)
コルムは明らかに動揺していたが、そのことは表に出さずに、少しでも早く状況を確認すべく、足早にカルタキアへの帰還を目指す。だが、その過程で、今度はペドロ、メル、アレシア、ハウメアの四人の聖印にも動揺の異変が発生した。
(え……!?)
(艦長!?)
(まさか、アストライア卿が……!?)
(なにがおきたの!?)
彼等の聖印の本来の持ち主であるラマンとアストライアは、いずれも現在、ソフィアと共に「天空の魔境」の浄化任務に就いている筈である。
そして、最終的にはコルネリオとカリーノの聖印もまた、それぞれエイシス、ジーベンとの関係が断ち切られることになった。
(エイシス!? どうしたのさ、エイシス!?)
(おいおい、嘘だろ、指揮官殿……?)
その後、カルタキアへと帰り着いた彼等は、意外な形で、それぞれの指揮官の身に何が起きたのかを知ることになる(
FR
に続く)。
☆合計達成値:233(48[加算分]+185[今回分])/140
→次回の最終クエスト(FB)の達成値に46点加算
(なお、FBの目標値は魔境融合により+80される)
カルタキアに建設された演芸場の近くに出現した「空間の歪」の先には、異世界「地球」の一角に存在する「21世紀の東京近郊の街」が魔境として投影されていた。この街の中では地球人達が、「異世界における本来の日常通りの生活」を送っている。おそらく彼等の大半は、この街が「投影(複製)された空間」だということも、自分達が「投影(複製)された存在」だということも知らずに、「いつも通りの日常」を送っているのだろう。
カルタキアには昔から「21世紀の地球」から投影される魔境の出現率が特に高く、昨今は「月匣」「秘密基地」「洞」「人口島」などが出現してきたが、このような形で「街」そのものが住民達と共に投影される事例は珍しい(なお、地下に出現していた「栃木県」も21世紀の地球という説はあるが、正確な年代は定かではない)。
また、より厳密に言えば、これらの魔境の投影元の世界は、それぞれが「他とは似て非なる独自の地球」であり、それぞれの世界ごとに固有の「本来の人間の限界を超えた能力者達(ウィザード、ヒーロー、執行者、撃退士、etc.)が存在していることが多い。現在出現している「東京近郊の街」もまたその例に漏れず、この街の投影元の世界には「レネゲイド・ウィルス」という名の病原体を身体に取り込むことで超能力を発揮する「オーヴァード」と呼ばれる者達がいる。それはいわば、アトラタンにおける「邪紋使い」に近い存在と言うことが出来よう。
だが、アトラタンの邪紋使い達とは異なり、この世界におけるオーヴァード達は、正体を隠して人類社会の中に潜伏しているらしい。彼等の大半は「ユニバーサル・ガーディアンズ・ネットワーク(以下、UGN)」と「ファルス・ハーツ(以下、FH)」という二つの地下組織のいずれかに所属しており、互いに対立関係にあるという。前者が正体を隠したまま非オーヴァードの人類と共存する世界の存続を願う一方で、後者はオーヴァード中心の新秩序を築こうとしていると言われているが、実際のところ、その内部組織構造は複雑で、彼等の正確な思惑までは不明である。
なお、本格的な調査前の段階で既にここまでの情報を入手出来ているのは、過去に何度もこの世界から同じ魔境が投影されたことがあり、その時の記録が詳細に残されているからである。そして、過去に何度もこの魔境から出現した投影体として「ディアボロス」もしくは「春日恭二」と呼ばれるFHのエージェントの名前が記録に残っている。ソフィアが言うには、10年前の大災害の時にも彼は出現しており、つい先日も彼の姿はカルタキアで暗躍していた姿が目撃されている。
「このディアボロスという人物が魔境全体の混沌核である可能性が高そうですが、その足取りや目的を探るためには、まず、FHという組織そのものを調べる必要がありそうですわね」
潮流戦線の
ユリアーネ・クロイツェル
は、カルタキアの書庫にて過去の資料を確認しながら、そう呟いた。そんな彼女の独り言が耳に入ったのか、近くにいた第六投石船団の
ツァイス
が彼女に声をかける。
「FHのアジトに、潜入するつもりか?」
「えぇ。これまでにも、いくつかの魔境で現地の投影体の人々との会話を通じて有益な情報が得られましたし、やはり、それが一番確実な方法のように思えるのです」
「確かにな。とはいえ、FHってのは、その世界の中でも『反体制側』の地下組織なんだろう? そう簡単に潜入出来るものなのか?」
「分かりません。ただ、現在出現している魔境が、ここに記されている資料の通りなのだとすれば、そのアジトの場所は既に特定出来ていますし、合言葉などもここに記されています。もともと彼等はかなり雑多な集団のようなので、『別の支部からの来訪者』を装えば、受け入れてもらえる可能性は高そうです」
ちなみに、現時点でカルタキアから直接繋がっているのは「N市」と呼ばれる街であり、この魔境は「N市」の外の領域まで投影されているらしいが、どこまで広がっているのかは不明である。
「なるほど……。とはいえ、さすがに一人で潜入するのは危険が高いだろう。他に同行者がいないなら、俺が一緒に行こうか?」
「それは大変心強いですわ。ツァイスさんには、前回の『塔』の踏破の時にも助けて頂けましたしね」
彼等がそんな会話を交わしているところで、また別の従騎士の声が聞こえて来る。ヴェント・アウレオの
ジルベルト・チェルチ
である。
「どうだ? この格好、似合うか?」
そう問いかけた彼は、高級そうな素材で作られた黒いスーツ(紳士服)を身にまとっていた。
「ジルベルト、その服は……?」
ツァイスにそう問い返されたジルベルトは、得意気に答える。
「あっちの倉庫で見つけたんだ。東京近郊の反社会組織の連中がよく着ている装束で、アルマーニっていうらしい」
「21世紀の東京近郊の街」は過去に何度もカルタキア近辺に投影されたことがあるため、変装用の衣服も豊富に所蔵されているようである。
「ってことは、お前も潜入捜査に行くつもりなのか?」
「あぁ。なんか色々と特殊な力を使う連中がいるって聞いて、ちょっと面白そうだと思ってさ」
彼がそう答えたところで、ユリアーネが一歩遅れて彼からの質問に答える。
「よくお似合いだと思います。ただ、その服、少し寸法が大きいのでは?」
ジルベルトは決して小柄な体型ではないが、それでも微妙に丈が余っているようにユリアーネには見えた。
「あー、やっぱりそうか……。多分、ラルフくらいの体型に合わせて作られた服なんだろうな。底上げの靴とかあれば、違和感なく着こなせるか……?」
彼がそう呟きつつ、もう一度倉庫に戻ろうとしたところで、ユリアーネが声をかける。
「もしよければ、私が裾上げしましょうか? 子供の頃から、お裁縫の心得はありますので」
「お、そうしてくれるか? じゃあ、頼むよ。デザインは気に入ってるから、出来ればこれ着て行きたいと思ってたんだ」
ジルベルトはそう答えつつ、先程のツァイスの発言を思い出す。
「そういえば、『お前も』って言ってたけど、アンタらも例の『街』の魔境に行くのか?」
「あぁ。ちょうど今、その話をしていたところだ」
「もしよかったら、ジルベルトさんも御同行しませんか?」
二人の提案にジルベルトも笑顔で頷く。そして彼等は改めて倉庫へ赴き、それぞれの変装用衣装を探しに行くのであった。
******
一方、彼等とはまた別に、密かに「東京近郊N市のFH支部」に潜入しようとする者がいた。潮流戦線の
ハウラ
である。
(風に聞いた噂では、どうやらこの魔境にはソラリスなる毒があるとかないとか)
中途半端に聞きかじった知識に基づいて、医学生風の装束を身にまとった状態で魔境に潜入した彼女は、事前に目を通した資料に載っていたFHのアジトの存在する廃ビルへと辿り着く。だが、ここで意外な人物が彼女の前に立ちはだかった。
「いらっしゃると思っていました、ハウラ様!」
ハウラの同僚にして同郷の幼馴染でもある
リンズ
である。メイド(給仕)服を身にまとった彼女は、ハウラの行動を予想した上で先回りしていたのだが、その表情はあまり好意的な様子ではなかった。
「FHは、私達の世界における『パンドラ』のような存在と聞いています。迂闊に忍び込むのはさすがに危ないので、帰りましょう」
「パンドラ」とは、エーラム魔法師教会と敵対する「闇魔法師」と呼ばれる者達の秘密結社であり、その目的は不明だが、現状の君主(聖印)中心の世界秩序を覆そうとしている者達と言われている。その意味では、確かにFHと似たような立場の者達なのかもしれない。
「んー、まぁ、確かに危険と言えば危険っすけど、虎穴に入らずんば虎子を得ずとも言うっすよ」
「君子危うきに近寄らず、とも言います。情報を得るにしても、もっと慎重な方法が……」
リンズがそう言いかけたところで、廃ビルから一人の男が姿を現す。その物音に気付いたリンズがやや慌てた様子で振り向くと、男はリンズに対してこう告げた。
「お、来たか。随分早かったな」
「……え?」
「秋葉原支部からのデリバリー・メイドだろ? 分かりにくいだろうが、こっちに入口がある」
どうやら、この男はリンズのことを「FHの別支部から派遣されたメイド(?)」だと勘違いしているらしい。リンズが困惑する中、いち早く理解したハウラが横から割って入る。
「そうっすー。ご主人さま、よろしくお願いするっすー」
「ん? 白衣オプションとか、付けた覚えはないんだが……」
「期間限定の無料サービスっすよー」
「そうか。まぁ、別に衣装はどうでもいいさ。掃除さえきちんとやってくれればな」
とりあえず、いかがわしいサービスを期待されている訳ではないらしい。
「わかったっすー。さぁ、リンズちゃん、一緒にお掃除、がんばるっすよー!」
「え……、あ、その……」
まだリンズは戸惑っている様子であったが、さすがにこの状況になってしまうと、ここで逃げようとする方が逆に危険なようにも思えてきた。
「……そ、そうですね! ご主人さまのために、一生懸命、ご奉仕します! 料理も洗濯も給仕も、何でもお申し付け下さい!」
リンズも腹を括った上で、二人はそのままアジトへと潜入していく。ただ、この時、ハウラはこの場に「もう一人」、誰かが隠れているような気配を感じ取る。
(あれ? 今のって、もしかして……)
彼女は背後を見渡すが、明確な人影は確認出来ない。
(……まぁ、気のせいっすよね、きっと)
******
それから数時間ほど経過した後、ユリアーネ、ツァイス、ジルベルトの三人は「この異世界における『裏社会』の正装」を模した黒を基調とした礼服で、同じ廃ビルへと辿り着いた。彼等は入口で「FHパレルモ支部の一員」と自称した上で、このアジトの責任者と話がしたいと告げると、奥の応接室へと通される。
やがて、そんな彼等の前に一人の男が現れた。少年とも青年とも呼べそうな年頃のその人物は「シューラ・ヴァラ」と名乗っており、その身体からはそれなりに強大な混沌核の力が感じ取れるが、おそらく「魔境全体の混沌核」と言える程ではないように思える。
|
+
|
シューラ・ヴァラ |
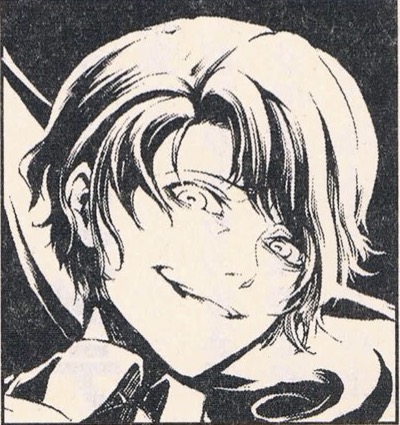
(出典:『ダブルクロス The 3rd Edition ルールブック1』p.359)
|
「海外からの来客とは、珍しいね。正直、パレルモと言われても、いまいちピンとこないんだけど、どこだっけ? イタリア?」
「はい。シチリアの州都ですわ。私はユリアーネ。こちらはツァイスとジルベルト。私達はボスからの密命を受けて、日本の鴻央会の内情を調べるために入国しましたの」
この「設定」は、ユリアーネが事前に入念に調べた地球の知識に基づいて作られた。ユリアーネは女スパイ、ツァイスは腕利きの用心棒、ジルベルトは最近力に目覚めたばかりの新人オーヴァード、という役回りである。
「シチリアってことは、マフィアの本場か。まぁ、日本語が堪能なのは助かるよ。で、ウチに何の用かな? 鴻央会の情報とか聞かれても、ウチとはあんまり繋がりもないんだけど」
「実は数日前から、パレルモとの通信が途絶えてしまいまして……」
「ほう?」
「私達の通信機のトラブルなのか、パレルモで何かが起きたのか、それとも、この国の通信状態そのものに異変が起きたのか、ひとまず状況を確認すべく、まずは現地のFHの方に話を伺いたいと考えた次第ですわ」
当然、彼女達はこの世界の通信機器など持っていない。だが、もし仮に魔境として投影されているのが「この街」だけなのだとしたら、異国の勢力との通信において何らかの異変が発生している可能性が高いと判断した上で、カマをかけてみたのである。
「うーん、そういう話だったら、僕の手に負える話じゃないな。もし、日本全体の通信環境がおかしくなってるなら、既に街中がトラブルになってる筈だから、その可能性は低いとは思うんだけど……、まぁ、とりあえず、ディアボロスが戻って来たら、話を聞いてみるか」
その名が出て来たところで、ユリアーネが更に食いつく。
「『ディアボロス』というのは、このN市の支部の責任者の方ですか?」
「いや、あいつは色々な支部を転々としているエージェントだよ。オーヴァードの素質のある者を見つけて、『こちら側』に引き込むのが仕事らしい。まぁ、僕もちょっと前に、彼に勧誘された一人なんだけどね」
ここで、今まで黙って聞いていたジルベルトが身を乗り出して割って入った。
「じゃあ、オレと同じような立場ってことか。アンタの能力って、どんなことが出来るんだ?」
自分と同世代と思しきジルベルトにそう問われたシューラ・ヴァラは、得意気に答える。
「僕のシンドロームは《モルフェウス》。こうやって、槍を作り出すことが出来るのさ」
彼はそう言い放つと、彼の目の前に奇妙なオーラをまとった槍が生み出された。「シンドローム」とは、彼等の身体に宿った病原体の種別を現す言葉であり、《モルフェウス》のシンドロームの感染者には、「何もないところから物品を作り出す能力」が備わりやすいと言われている。彼のコードネームである「シューラ・ヴァラ」も、伝説上の槍の名前であった。
「へー、なるほどな。カッコいいじゃねえか」
「そういう君は、何が出来るんだい?」
「オレのシンドロームは《エンジェルハィロゥ》。これが、オレの力の源だ」
ジルベルトはそう言いながら聖印を掲げると、シューラ・ヴァラは意味深な視線でその光を見つめる。
「ふーん……、これがキミの……」
彼がどこか意味深な声色でそう呟いたところで、応接室の扉を叩く音が鳴り響き、それに続けて少女の声が聞こえて来る。
「遅くなってすみません、エスプレッソをお持ちしました」
「ん? あぁ、秋葉原からの出張メイドか。うん、入っていいよ」
シューラ・ヴァラがそう告げると、扉が開き、エスプレッソ・コーヒーが注がれた器を載せた円形トレイを手にしたリンズが姿を現す。
互いに一切の相談もないまま、独自にこの地に潜入していたため、その姿を見た瞬間、「三人」は目を見開き、そしてリンズもまた驚きのあまりトレイを傾けてしまい、器からコーヒーがこぼれ落ちてしまう。
「あ……!」
すぐさま体勢を立て直したため、トレイの外にまで溢れることはなかったが、さすがにこの状態で客人に提供する訳にはいかない。
「おいおい、ドジっ娘属性までトッピングしてくれと頼んだ覚えはないんだけどね」
「申し訳ございません! すぐに淹れ直してきます!」
そう言ってリンズが立ち去ろうとしたところで、ジルベルトがすっと駆け寄る。
「オレの魂が生み出した輝きが、キミを驚かせてしまったようだな。お詫びに、手伝わせてもらえないか?」
聖印を掲げた状態のままジルベルトがそう告げると、リンズは彼の「意図」を理解する。
「え? あ、そんな……、でも、そうして頂けるなら……」
リンズはドギマギしたような演技をしながら、そのままジルベルトと共に扉の外へと出て行った。その様子を見ながら、シューラ・ヴァラは苦笑を浮かべつつ、ユリアーネに問いかける。
「やれやれ、これが噂に名高いイタリアの伊達男の習性、ってことなのかな?」
「えぇ。美しい女性を見かけたら放ってはおかないのが我が国の男性の流儀です。もし、彼女が傷物になってしまったら、その時は申し訳ございません」
「別に僕のモノじゃないし、構わないよ。それにしても、あんな幼い子供まで守備範囲とはね。ロリコンは日本人の専売特許じゃないってことか」
二人がそんな会話を交わしている中、ずっと黙った状態のままのツァイスは内心で様々な思惑を巡らせていた。
(もし、リンズの他にも一緒に潜入している者がいるのなら、このタイミングでジルベルトとの間で情報共有しつつ、このまま内部捜査を続けてもらえると助かる。そう考えると、こちらは少し話を引き伸ばしてでも時間稼ぎをした方がいいのかもしれないな……)
ここで、ふとツァイスは「あること」を思い出した。
(……そういえば、「アイツ」もこの街に潜入するとか言ってた気がするが……、既にこのアジトの中にいたりするのか?)
ツァイスが黙ってそんなことを考えている横で、ユリアーネは話を続ける。
「ところで、そのディアボロスという方は、最近、この街で何か異変が起きているとか、そういった話派していませんでしたか?」
「あー、そういえば、『もうすぐ、この世界が大きく変貌する』とか言ってたな」
「ほう?」
「詳しくはよく知らないけど、彼は昔から『世界を築くこと』が本懐とか言ってたらしいから、彼の中での野望が実現しつつある、ということなのかな。もっとも、今は『都築京香のなりそこないみたいな女』が色々と邪魔してるらしいけど」
その名前を聞いたユリアーネは、事前に調べたFHに関する書物の内容を思い出す。
「都築京香というのは、たしか、この国のFHの元締めの名前でしたか……?」
「元・元締めだね。僕が入った時にはもういなくなってたから、どういう人なのかは知らないけど、今は姿を変えて別組織を率いてるんだってさ。とはいえ、ディアボロスの言うことがどこまで信用出来るかは分からないからな。この街に来る前にも、T市やK市で色々と失態をやらかしてたらしいし」
どうやら、シューラ・ヴァラとディアボロスはあまり深い信頼関係にある訳ではないらしい。そのことを踏まえた上で、今度はツァイスが口を開いた。
「そういえば、そのディアボロスが勧誘してきた者達の中に、異国人らしき者はいなかったか?」
「ん? あぁ、そういえば、なんか色黒の女の子を一人連れてたな。まったく、外人の子供なんかにかまってる暇があったら、とっとと真花をどうにかしろって言ってるのに……」
数日前から、カルタキアの少女が一人行方不明となっており、ディアボロスと思しき男がその少女を物色するような目で見ていた、という情報も従騎士達の耳には届いている。ツァイスの中で嫌な予感が広がる中、再びユリアーネが問いかける。
「そのディアボロスさんという方は、いつ頃戻って来られる予定なのですか?」
「悪いけど、僕にも分からない。ただまぁ、別にここで待ってもらう分には構わないよ。僕も退屈していたところだ。暇潰しに、シチリアのマフィア達の話でも聞かせてくれると嬉しいな」
「では、そうさせて頂きます。とはいえ、あまり人様にお話出来るような話もございませんが」
現状、ジルベルトとリンズが何かを探ってくれているだろうと期待しつつ、しばらくの間、ユリアーネとツァイスは時間稼ぎに徹することにした。
******
その頃、ハウラはFHのアジトの資料室にて清掃活動に従事しているフリをしながら、この支部に存在するFHの面々に関する情報をこっそりと確認していた。
(んー、残念ながら、今のこのアジトには「ソラリス」の力を持っている人はいないっぽいすね。この「藤ヶ丘崇文」っていう人は「T市郊外の河川敷の戦いで死亡」、こっちの「北原雅道」とかいう人も「旧K市支部の壊滅時に死亡」っすか……)
資料を読む限り、「ソラリス」の特性を持つこの二人は既にこの世にいないらしい。その情報に彼女は少し落胆しつつも、そのままFHの資料室内に散らばっている諸々の書類に目を通す。
(この活動記録を見る限り、この世界が「異世界と繋がっている」ということを組織として認識している様子はない? ということは、戦うべき相手は「ディアボロス」だけで、他の人達のことは無視しても問題ない、ってことっすかね……?)
ハウラの中でそんな思惑が広がる中、背後からFH職員の声が聞こえてくる。
「おい! 勝手に書類を見るなと言っだろう! まさか、貴様、UGNの……」
その職員がそこまで言ったところで、激しい衝撃音が聞こえる。ハウラが驚いて後ろを振り返ると、そこでは、既に混沌の塵となって消えかけていく職員らしき男と、その背後で小型の鈍器を手にした、ハウラの同僚の姿があった。
「
エーギル
!」
「よっ! 心配だったから、こっそり助けに来たぜ」
機能性と隠密性を重視した黒装束のエーギルは、笑顔でそう答える。そんな彼の姿を目の当たりにしたことで、ハウラはアジトに潜入する直前のことを思い出していた。
「やっぱり、『さっきの気配』はエーギルだったんすね」
「あー、バレてたか。やっぱり、俺には隠密は向かないかな」
エーギルはそう呟いたところで、更に後方から、別の面々が走り込んでくる足音が聞こえる。リンズとジルベルトであった。この二人は先刻の時点での合流後、互いの状況を確認した上で、ひとまずハウラの元へと向かおうとしていたのである。
「あれ? エーギル様?」
「よぉ、久しぶり!」
「アンタも来てたんだな」
「さっき助けてもらったところっすよ」
四人はそんな言葉を交わしつつ、ひとまずエーギルとジルベルトが周囲を警戒した状態で、ハウラとリンズが引き続き資料捜索を続けていくことにした。すると、やがてハウラが「興味深い資料」を発見する。
「これ、何かの暗号みたいっすね……」
あえて暗号化しているということは、それだけ深い機密性が高い情報なのだろう。なお、ここまで発見された資料はいずれも「アトラタンの言語」に変換される形で投影されているため、おそらくこの暗号文も、アトラタン人である彼女達自身の知識で解読可能な筈である。
だが、ここでジルベルトが声を上げる。
「誰か近付いて来てる。この気配……、そこそこ強い混沌の気配を感じるぜ」
ジルベルトはそう告げつつ、リンズと共に部屋を出て(エスプレッソを淹れ直すために)台所へと向かう。それと同時にエーギルもまた何処かへと姿を隠し、そしてハウラは何食わぬ顔で部屋の清掃を装い始める。
すると、物々しい足音と共に、ややガラの悪い大柄の男がその部屋に現れた。
|
+
|
ややガラの悪い大柄の男 |

(出典:『テーブルトークRPG ダブルクロス』p.175)
|
「お前、新入りか?」
「あー、どーもー、秋葉原支部からの出向っすー……、ん?」
ハウラはその男の顔をよくよく凝視する。
「もしかして……、藤ヶ丘さんっすか?」
その顔は、先刻ハウラが見かけた「T市郊外の河川敷で死亡」と記されていた人物の写真とそっくりであった。
「おう、そうだ。秋葉原には知り合いはいなかった筈だが……」
「いやー、まぁ、暴走族『LEGACY』の噂は、秋葉原にも届いたっすからねー。でも、どうしてここに? というか、あなたは死……」
「色々あったんだ。それ以上は詮索しない方が、身のためだぜ」
「……分かったっすー」
強い興味を惹かれたハウラであったが、ひとまずこの場は何も言わずに清掃に戻る。その後、彼がいなくなったのを確認した上で改めて該当資料に深く目を通してみたが、どうやら彼は(「キュマイラ/ソラリス」ではあるものの)「毒使い」ではないらしい、ということを確認し、改めて落胆したハウラであった。
******
「お待たせしました。改めて、エスプレッソをお持ちしました」
「ごめんな、リンズ。俺が中途半端に手伝おうとしたせいで、逆に長引かせちまった」
リンズとジルベルトがそう言いながら応接室に戻ってくると、ユリアーネとツァイスは(そろそろ話題も無くなってきたので)「この辺りが頃合いか」という判断に至る。
「ありがとうございます。では、そちらを頂いたら、そろそろ御暇させていただこうかと」
「あれ? 僕としては、ディアボロスが戻って来るまで待ってもらって構わないと言ったつもりなんだけどな」
「そのお言葉ありがたいのですが、現実問題として、いつお戻りになられるかも分からないのであれば、これ以上、長居するのはさすがにご迷惑でしょうし。とりあえずは、近隣の支部を訪ねてみようかと」
「……残念だけど、そういう訳にはいかないんだよ」
「え?」
「『光の紋章を生み出すオーヴァード』を見つけたら生かして帰すなって、ディアボロスに言われてるんでね」
彼はそう告げると、先刻生み出した槍に手を伸ばす。そして次の瞬間、その槍は三つに分裂し、ジルベルト、ユリアーネ、ツァイスの三人に向かって投げ込まれた。
しかし、そのジルベルトはその動きを察知した上で、間一髪のタイミングでかわしつつ、リンズを連れてそのまま部屋の外へと逃げ出す。そして、ツァイスもまたその槍の動きを予想した上で、即座に《庇護の印》を発動することで、ユリアーネの元へと飛んでいった槍をその身で受け止めた。その結果、彼の身体には(もともと自分に向かって飛んで来た分も含めて)二本の槍が突き刺さる。
「ツァイスさん!?」
「大丈夫だ。この程度、こないだの塔の魔物の攻撃に比べれば、大した威力じゃない」
ツァイスはそう答えつつ、シューラ・ヴァラに対して言い放つ。
「俺達のことを疑ってたなら、迂闊に武器を出すべきじゃなかったな」
ジルベルトもツァイスも、槍が生み出されたのを見た時点で、それが「投擲用の槍」だと気付いていたらしい。
「そうだね……、先に光の紋章を見せてもらうべきだった。それを見ておけば、わざわざ手の内を晒したりもしなかったさ」
シューラ・ヴァラがそう言って再び槍を作り出そうとするが、ここで(ジルベルト達が出て行った扉とは反対側の)壁の向こう側から、激しい物音が聞こえる。
(まだ他にもいるのか!?)
それは、隣の部屋に潜伏していたエーギルによる撹乱策であった。シューラ・ヴァラがそちらに一瞬、気を取られた隙に、ツァイスとユリアーネもすぐさま扉の外へと脱出する。
「侵入者だ! 捕縛しろ! 絶対に逃がすな!」
シューラ・ヴァラはそう叫ぶが、「殺害」ではなく「捕縛」を命じられていたこともあり、FH職員達も本気で追撃は出来なかったようで、四人の従騎士はあっさりと廃ビルの外への逃走に成功する。そしてエーギルとハウラもまたその混乱に乗じて、それぞれに廃ビルからの脱出を果たしたのであった。
******
その後、六人は街の路地裏で合流した後、追手から逃れるために、ひとまず市内のカラオケボックスの一室へと身を潜めた上で、それぞれに集めた情報を擦り合わせることにした。
シューラ・ヴァラの反応から察するに、どうやらディアボロスは、自分の留守中に従騎士が潜入してくることは想定していたらしい。ただ、シューラ・ヴァラはあくまで「光の紋章を生み出すオーヴァード」としか聞いていなかったことから、おそらくディアボロスは他のFHの者達に対して、「今のこの街が異世界と繋がっている」ということは伝えていないようである(このことは、ハウラが調べた資料からの情報とも一致する)。
その上で、ハウラは資料室で見つけた「暗号文が記された資料」を皆に見せると、リンズが何かに気付いたような表情を浮かべる。
「これ、前にどこかで似たような暗号文を見たことがあるような気がします。多分、こうすれば解けるんじゃないかと……」
彼女はそう言いながら筆記用具を取り出し、暗号の解法を書き出し始める。それを見て、ハウラとユリアーネも彼女の意図を察した。
「あー、なるほど、そういうことっすかー」
「だとしたら、この部分は、こうなのではありませんか?」
こうして、女性陣がそれぞれに知恵を絞りつつ、三人とも《巻き戻しの印》を駆使しながら暗号解読に挑み、その間に男性陣は店側に対するカムフラージュのために、それぞれに故郷の歌などを(機械の使い方が分からないのでアカペラで)熱唱する。
その結果、リンズはどうにか暗号文の解読に成功した。そこに記されている情報によれば、どうやら先刻までいた廃ビルから少し離れた区画にある「廃工場」の地下に、FHの秘密の実験場が存在するらしい。そして、その実験場の責任者である「北原雅道」という人物は、オーヴァードの素質のある者を「ジャーム」と呼ばれる「暴走オーヴァード」へと覚醒させた上で洗脳する研究を進めているらしい。
(北原雅道……、確か、その人にも「ソラリス」の因子が入っていた筈……。でも、その人も既に書類上は死亡しているって書かれたような……)
ハウラが潜入時に読んだ資料を思い出しながら首を傾げている一方で、ツァイスとエーギルがすっと立ち上がる。
「じゃあ、『例の連れ去られた子』も、その工場にいるんじゃないのか?」
「だったら、今すぐ助けに行かないとな!」
だが、そんな彼等に対して、ユリアーネが意を唱える
「待って下さい、ツァイスさん。あなた、平気な顔をしていらっしゃいますけど、さっき私を庇った時に、相当な深手を負ってますよね?」
おそらく、あの時点でのシューラ・ヴァラは(捕縛するために)殺さない程度に手加減していたのだろうが、さすがに鎧も盾もない状態で「槍」を二本もまともに受けて平気な筈がない、ということはユリアーネも分かっていた。、実際、もし先刻のシューラ・ヴァラと同等の異能力者がその場にいた場合、今の手負い状態のツァイスが向かうのは危険である。
それに加えて、リンズも口を開く。
「多分、私達の顔はもう割れてますから、潜入するのも難しいでしょうね……」
彼女達が暗号を解読するまでの間にそれなりに時間がかかっている以上、おそらく廃工場側にも彼女達の情報は伝わっている可能性が高いだろう。
これに対して、今度はジルベルトが口を開く。
「だからと言って、放っておく訳にもいかないだろう。今からどこかで別の服を調達して変装し直せばごまかせるんじゃないか?」
しかし、この提案に対してもユリアーネは首を振る。
「残念ながら、全身のコーディネートをやり直せる程の服を買えるだけの『この世界の通貨』は持ち合わせていません。強奪しようとすれば騒ぎになるでしょうし、仮に盗み出せたとしても、『黒髪の人々』が大半を占めるこの街では、髪色だけっでも私達は特定されやすい存在です。ここは一旦退いた上で、第二次調査隊の派遣を……」
彼女がそこまで言いかけたところで、ハウラが手を挙げる。
「大丈夫っすよ。この街に潜入してるのは、私達だけじゃねーですから」
突然のその宣言に、リンズは驚いて声を荒げる。
「ハウラ様、本当ですか!?」
「ええ。色々ありすぎて話すタイミングがなかったんすけど、一応、魔境に入る前にワイスさんから、これを預かってたんすよ」
同郷の従騎士の名前を挙げながら、ハウラは鞄から「この世界の通信機器」を取り出すのであった。
******
(シーマ、一体、どこにいるのですか……)
星屑十字軍の
ワイス・ヴィミラニア
は、フルフェイスのヘルメットとライダースーツに身を包み、この街で調達した自動二輪車に乗って、町中を走り回っていた。マスクの下のその素顔では、いつになく焦燥した表情を浮かべている。
現時点で行方不明になっているカルタキアの少女・シーマは、ワイスが特に目をかけている学徒であり、彼女がディアボロスに連れ去られた可能性があると聞いたワイスは、自身の持つ全ての知識を駆使して、この世界における「乗騎」と「通信端末」を手に入れ、街中を捜索して回っていたのである(その入手経路については、聖印教会の面々はもちろんのこと、ハウラにも知らせていない)。
そして、彼女を乗せた自動二輪車の後部座席にはもう一人、ワイスと同様の装束を身にまとった従騎士がいた。幽幻の血盟の
エルダ・イルブレス
である。子供を守ることを常に第一に考えている彼女は、当然の如く今回もまた行方不明のシーマの捜索に協力することになった。
なお、自身の素顔を他人に見せることを禁忌としているエルダとしては、現在のこのヘルメット姿は好都合なのだが、いつもの鎧姿とは異なり、全身にフィットした服装であるため、日頃は隠れている「女性らしい体型」が露わになってしまっている。だが、無垢な少女が異界に連れ去られたかもしれないという現状においては、そんなことまで気にしていられる状況ではなかった。
(それにしても、なぜこの人はこんな「異界の乗騎」を乗りこなせるのだろう……? 聖印教会の人々は、そもそも投影装備を用いること自体、嫌う人が多いというのに……)
エルダはそんな疑問を抱きつつ、後部座席から霊感を研ぎ澄ませながら、周囲の混沌の気配を察知しようと試みていたが、この魔境内を闊歩している現地人達の混沌核の強さは概ね一定で、混沌の流れ自体も平坦のように思える。
(せめて……、せめて何か、断片でもいいから、手掛かりとなるような何かが……)
そんな想いを抱きながら、エルダが必死に霊感を巡らせていると、彼女は想定外のところから、ほんの僅かな「混沌の揺らぎ」を感じ取る。それは、ワイスが持っている鞄の中であった
「あの、すみません、今、あなたの鞄の中に、何かが入り込んできたような……」
「なんですって!?」
ワイスは驚きながら道路の脇に二輪車を留め、鞄の中を確認している。そして、彼女はすぐにエルダの言葉の意味を理解する。
「あぁ、この通信端末に着信があったんですね」
鞄に入っていた携帯端末を取り出しながら、ワイスはそう呟く。一応、着信時に音と振動が発生するように設定されていたのだが、自動二輪車の動力音と振動で気付けなかったらしい。そんな状況下で「電波の受信の際に発生する微弱な混沌の気配」に気付いたエルダの霊感の強さにワイスは感服しつつ、ひとまず内容を確認する。
「FHのアジトに潜入していたハウラからのメールですね……、ほうほう、なるほど……」
「何か有益な情報が見つかったのですか?」
「……えぇ。とりあえず、あの川を超えた先にある旧工場地区に向かうことにしましょう」
ワイスは街の東方を指差しながらそう告げつつ、再び通信端末に視線を移す。
「そうそう、この情報を『彼』にも伝えなければ」
彼女はそう呟きながら、魔境突入前に同じ端末を手渡していた「もう一人の従騎士」に向けて、ワイスのメールをそのまま転送した。
******
(悪くはないが、栃木で食べた餃子には遠く及ばないな……)
「この美味しさ……、烈火太陽脚なのー!」
「昔、旅先で食べたシャーンの味付けに似てるな」
「魚介の風味がよく効いたスープですね」
彼等もまたキリアン同様、それぞれに学生服を着て変装している。ユージアルは栃木の魔境でも女学生への変装経験があるため、見事に「清楚な女子高生」を装えている一方、アイリエッタは髪色と肌色もあって「ガングロギャル」のような風貌となっており、傍目には奇妙な取り合わせのように見える。一方、従騎士達の中で唯一、ディアボロスと面識のあるレオナルドは、ディアボロスと遭遇した時に彼に気付かれないように、髪型を変え、色眼鏡を掛けさせられていた。
この四人は、FHのエージェント・ディアボロスを探し出すために、この街に潜入していた。中華料理屋にいるのは、事前調査の段階で、カルタキアの書庫の一角に
「ディアボロスがラーメン屋で働いている物語」
が所蔵されていたのをアイリエッタが発見したからである(なお、この過程においてワイスが《巻き戻しの印》を用いて、彼女を手助けしていた)。
アイリエッタは炒飯を頬張りながら、小声でレオナルドに尋ねる。
「どうだ? 店員の中に、それらしい男はいるか?」
「残念ながら、今のところは見つからないですね。今日のシフトに入っていないだけかもしれませんが……」
「まぁ、そう簡単には見つからないよな……。ラーメン売ってる店って、他にも色々あるみたいだし、そもそも、『あの本』に出てきた街が『ここ』なのかどうかも分からないし……」
実際のところ、その書物で描かれていたのは別の街(T市)の物語だったのだが、さすがにそこまではアイリエッタには分からなかったらしい。
だが、このアイリエッタの目論見は、想定外の形で功を奏することになる。彼等が概ね料理を食べ終えた頃、店の扉が開き、一人の中年男性が入って来たのである。彼は店員に対してこう言いながら、カウンター席に着いた。
|
+
|
中年男性 |

(出典:『ダブルクロス The 3rd Edition』p.295)
|
「醤油ラーメン一つ、あと、生中もな」
その男を見た瞬間、色眼鏡の下のレオナルドの瞳が既視感を覚える。
「あの男……、似ていますね、ディアボロスに……」
視線をそらしながら彼がそう呟くと、今度は三人の視線が一斉にその中年男に向けられる。だが、ここでキリアンは首をひねる。
「あいつが……? 正直、あまり強大な混沌の気配は感じられないが……」
「えぇ。それで私も少し違和感がありました。先日カルタキア市中で遭遇した時は、もっと強烈な混沌のオーラをまとっていたのですが……、しかし、外見は確かに似ています」
レオナルドがそう答えたところで、キリアンの鞄の中に入っていた「ワイスから預かった通信端末」の着信音が響く。彼は、栃木の魔境において似たような通信端末を使った経験があったため、ワイスから「連絡役」として指名されていたのである(当然、ワイスがどこからこの物品を入手したのか、という疑問はキリアンの中にもあったが、深くは追求しなかった)。
キリアンは、その端末に送られてきた情報を確認した上で、小声で皆に内容を告げる。
「どうやら、川の向こう側の旧工場区に、FHの研究所らしき場所があるらしい。行方不明となっている少女がそこに囚われている可能性が高いということで、ワイスさんとエルダさんとしては、今すぐにでもそこに乗り込みたいとのことだが……、どうする?」
二人だけで突入させるのは危険なようにも思えるが、今、彼等の目の前に「ディアボロスかもしれない人物」がいるという状況である以上、こちらの捜索も続けたいところである。
これに対して、レオナルドが答える。
「私が援軍に向かいます。ここにいる『彼』が本物だとすれば、もう『識別役』としての私がここにいる意味はないですし、むしろ私がいるとこちらの正体に気付かれる危険性が高まります。一方で、もし彼が偽物で、工場の方に本物がいるのだとしても、彼の顔を知っている私が現地に向かった方が得策でしょう」
彼のこの判断には、その場にいる三人も納得する。それに続いて、今度はユージアルが口を開いた。
「そういうことなら、私も行くの。町中だと『これ』は使いにくいから、人が少ない旧工場区の方が、私の持ち味は活かせるの」
ユージアルの傍らには「この世界の弓道部員が使うような弓」が置かれている。この街に違和感なく持ち込めるギリギリの武器だが、さすがに町中でそれを使おうとしたら、街を警備する者達までもが介入して、面倒な事態になりかねない。その意味では、確かに彼女が工場跡地に向かうというのも有効な戦略のようにも思えるが、ここでキリアンの中では少し嫌な予感が過ぎる。
(どうも彼女は、何か危険なことを考えているような気がする……)
とはいえ、素手格闘に長けたキリアンとしては、町中での荒事に備えて「こちら側」に残った方が得策であろうし、その点では(素の腕力の強さという意味で)アイリエッタも同様である。ひとまずキリアンは「ユージアルの身の安全」をレオナルドに託し、二人が合流するために向かったという旨をワイスに連絡するのであった。
******
そして実はもう一人、密かにこの地に潜入している従騎士がいた。
「ふむ……、いけないとは思っているけれど、どうしても興味が惹かれてしまうな。この建築物とか……、服も機能性はともかくとして見た目も、好みではある」
ユージアルやアイリエッタとはまた別の女学生の制服を着て町中を歩いていたその人物は、鋼球走破隊の
フォーテリア・リステシオ
である。彼女は得意の占いを駆使しつつ、そこに現地の人々からの聞き込みを加えながら、独自にN市内におけるディアボロスの足跡を探して回っていた。
(さて、ここまでの諸々から推察するに、どうも「川の向こう側」が怪しいように思えるんだが……、おや? あそこにいるのは……、ユージィ?)
フォーテリアの視線の先に、工場跡地へと向かって走るユージアルの姿が映る。
(その隣にいるのは……、レオナルドくんか? なにやら似合わない色眼鏡をかけたりしてるようだが……、さて、ちょっとこれは危険な組み合わせのような気がするな)
これまで何度か「自分の身を危険に晒す無茶な計略」を繰り返してきたユージアルと、既に診療所の常連客になりつつある程の「死にたがり気質」と評されているレオナルドが一緒にいる様子を目撃してしまった以上、フォーテリアが心配しない筈もない。ひとまず彼女は二人の後を追うことにしたのであった。
******
一方、中華料理屋に残っていたキリアンとアイリエッタは、追加で頼んだ杏仁豆腐を食べながら、ディアボロス(仮)の様子を伺っていた。
(あの店員との様子からして、常連客のようだな)
(もともとラーメン好きだったってことか?)
二人がそんなことを考えている中、ディアボロス(仮)は淡々とラーメンとビールを腹に流し込み、支払いを済ませようとする。
「おい、アタシ達もすぐに勘定を済ませて、追いかけないと」
アイリエッタがやや焦った表情を浮かべながら小声でそう告げたのに対し、キリアンは眼鏡をかけ直しながら淡々と答える。
「いや、すぐ後に並んだら気付かれるかもしれない。金を払うのは、彼が店を出てからだ」
「え? でもそれじゃ、逃げられ……」
「大丈夫。あいつの混沌の気配は把握した。少し離れたところで、逃すことはない」
キリアンは先刻から、ずっと霊感を研ぎ澄ませて、ディアボロス(仮)の周囲の混沌の気配を読み取り続けていたのである。
「……よくそこまで分かるな。さっきは『大した混沌の気配じゃない』って言ってたのに」
「あぁ、最初はそう思った。だが、ずっと観察していて分かったんだ。あいつ、やっぱりただの投影体じゃない。上手く説明出来ないが、何か他の混沌にはない『違和感』が漂っている」
キリアンはそう答えつつ、ディアボロス(仮)が店を出たのを確認すると、この世界の紙幣を卓上に置いて立ち上がる。
「釣りはいらない。あと、餃子にはもう少し白菜を多めに混ぜた方が、風味が増すと思う」
彼は店員にそう告げると、アイリエッタと共に店を出て、あえて「視界の外」から「ディアボロス(仮)の気配」を尾行する。すると、この段階でアイリエッタは、事前に入手していた「N市の地図」を見ながら、彼の進行方向から一つの推測に至る。
|
+
|
N市の地図 |

(出典:『ダブルクロス The 3rd Edition』p.307)
|
「あいつ、旧工場区に向かおうとしてるんじゃないか?」
「……だとしたら、やっぱり、レオナルドの記憶は間違ってなかったということか」
キリアンはそう呟きつつ、手元の通信端末に文字を打ち込み始めた。
******
その間に、ユージアルとレオナルドは、工場区の近くにて、ワイス、エルダと合流していた。
「おまたせなのー」
「どの建物なのかは、既に特定出来ているのでしょうか?」
ユージアルとレオナルドがそう問いかけると、ワイスとエルダは(どちらもヘルメット被った状態のまま)答える。
「残念ながら、まだそこまでは至っていません」
「この区画全体の混沌濃度が高い気はするので、なかなか特定が難しいですね」
四人はそんな言葉を交わしつつ、ひとまずはエルダの霊感を頼りに、旧工場区へと足を踏み入れていく。そして、慎重に奥地へと歩を進めていく途中で、エルダがふと「何かに気付いたような表情」を浮かべた。
(今、どこか近くの建物から、強い混沌の気配が感じられたような……)
この時点で、エルダはその気配がどの方角から感じられたのか、はっきりとは認識出来ずにいたのだが、その直後、彼女はなぜかその「認識出来なかった筈の方角」を明確に特定出来ていた。
(これは……、《巻き戻しの印》?)
幽幻の血盟の一員であるエルダは、過去にソフィアの聖印によって同じ現象を経験したことがあるため、即座にその力の存在に気付く。
(この場にいる中で、この力が使える人は……)
エルダはルーラーであるユージアルに視線を向けるが、彼女は小首をかしげる。
「どうしたのー?」
この反応から察するに、どうやらユージアルではないらしい。
「あ、いえ、その、どうもあちらの方角から、何か禍々しい気配がするような気がして……」
エルダは呟きつつ、改めてその方角に向かって霊感を強めていくが、完全な特定までには至らない。しかし、ここで改めて今度はユージアルがはっきりと《巻き戻しの印》を発動させた結果、エルダは明確に「一つの建物」を指差す。
「あそこに、明らかに『他よりも強大な混沌核』の気配を感じます……、ただ、『魔境全体の混沌核』と言えるほどではないような……」
彼女がそう呟いたところで、再びワイスの通信端末が、キリアンからの着信を知らせる。
「おや……、例の料理店にいた『ディアボロスに似た男』が、店を出た後、この工場地区の方に向かって移動している、とのことです。彼等もそのまま尾行しているようですが……、さて、どうしましょうか」
これに対して、エルダが即座に答える。
「そのディアボロスが本物であろうと無かろうと、敵である可能性が高いなら、この地で合流される前に、この建物の中に踏み込むべきです。この中にはおそらく……」
「はい、シーマがいる可能性がある以上、私も同感です」
ワイスがそう返したところで、今度はユージアルが声を上げる。
「私にいい考えがあるの!」
彼女はそう宣言した上で、一つの「策」を提案するが、これに対してはエルダもワイスも反対する。
「確かに、敵の戦力を分断するという意味では有効かもしれませんが、さすがにそれはあなたの身が危険すぎます!」
「えぇ。そもそも、そのような役割を担うならむしろ……」
ワイスはそれに続けて「自分が」と言いそうになるが、ここでそれを提案すると話がややこしくなると判断し、一旦言葉を噤む。
一方、レオナルドもまた(キリアンから「ユージアルの身の安全」を任された身として)、容易に首を縦に振る訳にはいかなかった。
「まず、敵の正体も戦力も分かりませんからね。もし、彼が『本物』で、しかも『魔境の混沌核』だった時を考えて、せめて何か備えをしておかなければ……」
もともと、レオナルドは今回の調査を通じて、ディアボロスの戦力分析をおこなおうと考えていたのだが、現時点ではまだその準備が整っているとは言えない状態に思えた。
そんな中、物陰から一人の従騎士が姿を現す。その姿を見たユージアルが即座に声を上げる。
「フォーテリアさん!?」
「もうしばらく、後ろから見守っていようと思ったんだけどね。さすがに、ユージィが危険なことをやろうとしているのなら、黙ってはいられないよ」
フォーテリアがそう言って姿を現すと、エルダは先刻の「最初の《巻き戻しの印》」が彼女の聖印から発動されたものであろうと推察する。
「先程は、ありがとうございました」
「ん? いや、まぁ、大したことはしてないから、それは別にいいんだけどね。そんなことより、さっきあっちの旧工場を見て回ってたら、何か物騒な物が入ってそうな倉庫があったんだが、もしかして、それって何かに使えたりしないかな?」
彼女がそう言いながら背後にある建物を指差すと、ワイスとレオナルドがそちらに向かって走り出し、そして倉庫の中を確認する。
「ほほう、これは……」
ワイスがそう呟くと、レオナルドも興味深そうな表情を浮かべつつ、彼女に問いかける。
「使い方、分かりますか?」
「えぇ。私の見立てに間違いがなければ、おそらく……」
ひとまず彼女は改めて通信端末を取り出し、ディアボロス(仮)を尾行中のキリアンに一つの「方策」を伝えることにした。
******
「ディアボロスさん! 貴方が求めているのは、この『オーヴァード』の力なの!? ならば勝負するの!」
N市の中心部と旧工場区を隔てる川の上に架けられた橋の上で、ユージアルは自分の頭上に聖印を掲げつつ、全体を見渡しながらそう叫んだ。
もともとディアボロスの捜索を目的にこの地に潜入していたユージアルとしては、彼がこれに反応して出て来てくれれば目的を達成出来る。そして、もし彼が「魔境全体の混沌核」もしくはそれに匹敵する程の強大な混沌核なのだとすれば、現時点でエルダとワイスが「行方不明の少女」を探し出すまでの間、ユージアル自身が囮となることで、その妨害を防げるかもしれない。
(もし「さっきラーメン食べてた人」が偽物だったとしても、こうしていれば「本物」が来てくれるかもしれないの!)
ユージアルがそんな思惑を抱きつつ、橋の上で一人で演舞のごとく目立つポーズと宣言を繰り返していると、やがて街の中心部の方面から、まさにその「さっきラーメン食べてた人」が姿を現す。物陰からその様子を確認していたフォーテリアは、彼の外見的特徴から、その内面を分析しようと試みる。
(……手首に僅かな赤みがある。ほんの少し前まで装飾品を付けていた跡。それと、シャツの襟首にシミ……、新しい。これは食事の跡。スープか何かを急いで食べた。……ここから推測できる人物像は……、食事の前にスープに浸かりそうな装飾品を外す思考はあるが、その直後、時間がないと焦ってしまう人、つまり、神経質なくらいに慎重ではあるけれどそれ以上にすぐ焦ったり油断をしてしまうおっちょこちょい……)
このフォーテリアの推理が当たっているとしたら、この人物は典型的な「小物」である。実際、彼の身体からはそこまで強大な混沌の力は感じ取れない。
ただ、その一方で、彼はユージアルが掲げている聖印を見ても、一切驚いている様子はない。それを「オーヴァードの能力」と考えているのか、「異界の力」と考えているのかは不明だが、少なくともその様子から察するに、彼が「ただの一般人」ではないことは確かだろう。彼は穏やかな笑みを浮かべながら、橋のたもとまで来たところで、ユージアルに対して問いかける。
「こんなところで私を名指しで呼び出すとは、どういう了見かな?」
「あなたが、本物のディアボロスさんなの?」
「何を以って『本物』と言いたいのかは知らないが、私は確かにディアボロスだ」
彼がそう宣言すると同時に、急激に彼の周囲の混沌濃度が高まり始める。その変化は、後方から彼の気配を尾行し続けていたキリアンの霊感を大きく刺激する。
「なんだ……? 急に奴の混沌核の力が強大化しているような……」
そのあまりの凶々しさに、キリアンは思わず表情を歪め、その緊張感は隣にいたアイリエッタにも伝わる。
「力を隠してやがった、ってことか?」
「多分、そういうことだろうな。自分の内側の混沌核の力を隠蔽するなんてことは、少なくとも『普通の投影体』ではありえない」
彼はそう呟きつつ、ユージアルの身を心配して、アイリエッタと共にユージアル達の声が聞こえる方向へと向かって走り出す。
たが、彼等が到着するよりも前に、事態は急展開することになる。ディアボロスはユージアルの聖印を見つめながら、ニヤリと笑いつつ問いかける。
「で、君の頭上のその光は、本当にオーヴァードの力なのか?」
「その通りなの! 《オウガバトル》+《形なき剣》+《大地の加護》! くらうがいいのー!!」
ユージアルはそう叫びながら、包装状態にあった弓を取り出し、そして矢を放つ。当初、その軌道はディアボロスから大きく外れた軌道を描いているように見えたが、その直後、その場にいる者達全員の認識が書き換えられ、春日に直撃する。
ちなみに、彼女が日頃から用いている意味不明な語彙の数々は、かつて読んだ様々な異界魔書(ファミ通、ゲーメスト、etc.)に由来しているのだが、今回は「この魔境」とよく似た世界を描いた卓上遊戯の教本で学んだ知識に基づいているらしい。
「これが、射撃型ノイマン/オルクスの力なのー!」
誇らしげにそう言い放った彼女であるが、その一撃を直撃した筈の春日は、余裕の表情を浮かべながら、彼女に言い放つ。
「いい攻撃だ。しかし、君が本当にオーヴァードだというのなら、なぜ《コンセントレイト》を使わない?」
「コンセ……? 知らないのー! そんなデータは載ってなかったのー!!」
「そもそも、光を操る君達の能力の根源は、むしろエンジェルハィロゥと言ってくれた方がしっくりくるし、私も他の者達にはそのように説明している。だから君の場合も、ノイマン/オルクス/エンジェルハィロゥのトライブリードと名乗った方が説得力があるんだがね」
「えっ? トライ……ブリード? 何のことなの?」
(避ける素振りも見せずに甘んじてその攻撃を受けるとは……。言ってる言葉の意味はよくわからないけど、とにかく凄い自信だね。やはり、彼がこの魔境の……)
冷静にフォーテリアがそう分析している一方で、ユージアルは困惑した状態のまま、その場に立ち尽くしていた。当初の予定では、ユージアルは一撃を食らわせた後、工場側へと退く段取りだった筈なのだが、想定外の言葉を浴びせられたことで、完全に我を忘れてしまっている。
「ユージィ! 撤退だ! 下がれ!」
フォーテリアがそう叫ぶが、その声が届くよりも先に、ディアボロスが一気に橋を駆け渡り、ユージアルとの距離を詰める。
「わざわざ『俺の世界』まで来て、そこまで挑発したんだ。覚悟は出来ているんだろうな?」
彼はそう呟きながら、その右手を鋭利な武器状の何かに変化させようとする。この時点で、後方からその様子を見ていたレオナルドは、先日自分が腹を刺された時のことを思い出す。
(まだ彼女は「橋の上」にいるが……)
この時点で、彼の脳裏には「ユージアルの身体が貫かれる未来」が思い浮かんだ。
(……ここで起動させなければ、間に合わない!)
そう判断した彼は手元にあった「工場で発見した危険物」の起動レバーを動かす。その直後、激しい爆音と爆風が「ユージアルとディアボロスの足元」で巻き起こる。
「なに!?」
ディアボロスが驚愕の声を上げた直後、彼等の足元は消滅した。彼等は工場で見つけた爆薬を、橋の下に仕込んでいたのである。当初の計画では、ディアボロスを橋の上までおびき寄せた上で、ユージアルが橋から降りたタイミングで起動させる筈だったのだが、この状況では、ユージアルも一緒に川に落ちてもらう他に、彼女を救う道はないとレオナルドは判断したのである。
そして、二人は川にそのまま落下することになり、さすがにユージアルも正気に戻るが、岸まで泳ごうとした時点で、彼女は異様なまでの「水質の重さ」に気付く。
「な、なんなの、この水……!? きもちわるいのー!」
海軍の一員であるユージアルは、当然、水泳の訓練もそれなりに受けている筈だが、なぜかこの川の中では思うように身体が動かせない。どうやら、この川の水は特殊な何かが混入しているようである。おそらく、旧工場区内に設置されたFHの秘密研究所から、何らかの汚染物質が垂れ流されているのだろう。それに加えて、爆発の衝撃でそれなりに身体が損傷していたこともあり、彼女はまともに泳げる状態ではなかった。
だが、そんな濁流に呑み込まれそうになった彼女の身体を、水中で抱え込む者がいた。
「ユージィ!」
キリアンである。彼は橋が爆破されると同時に現地に到着し、そのまま反射的に川へと飛び込んでいた。体術に長けた彼は、混沌(?)の力で汚染された川の中で、ユージアルを抱えながらも、どうにか(自分が元々いた方の)岸へと向かって泳ぎ続ける。
「掴まれ!」
そう言って岸からアイリエッタが手を差し伸べると、キリアンはがっしりとその手を掴み、どうにかユージアルごと陸に上がることに成功する。
「あ、ありがとうなの……」
息も絶え絶えにユージアルがそう呟く中、キリアンは傾いた眼鏡をかけ直しつつ、目線を合わせずに答える。
「何があったのかは知らないが、敵を目の前にして硬直するなんて、戦場では命取りだ。君はやはり、前線に立つべきではない。人にはそれぞれ、向き不向きがある」
反論のしようのない正論を突きつけられ、俯くユージアルであったが、そんな彼に対して、アイリエッタが声をかける。
「それを言うなら、泳ぎについてはアタシの方が上だぜ。あんたが率先して飛び込む必要はなかったんじゃないか?」
「……彼女は第六投石船団の仲間だ。僕が助けに行くのが筋だろう」
二人に背を向けながらキリアンはそう答える。その声はなぜか微妙に震えていたのだが、そのことに気付いた者はいなかった。
一方、川の向こう側ではレオナルドとフォーテリアがユージアルの無事を確認した上で、それぞれに川に視線を向ける。
「ディアボロスが、浮かんでこない……?」
「生きてるにしても、死んでるにしても、普通、人間は浮かんでくる筈なんだけどねぇ……」
当然、キリアン達もまたその異変には気付く。
「まさか、この川の下がどこかに繋がっているのか?」
「いや、この水の流れからして、そんなことはないと思うぜ」
「私が川に落ちた時には、確かにあの人も一緒に落ちた筈なの……」
残念ながら、ユージアルが読んだ異界魔書(The 2nd Edition)には《瞬間退場》は掲載されていなかったようである。
******
一方、その頃、工場区の一角では、自動二輪車に跨り、フルフェイスのヘルメットを被ったライダースーツ姿の上から(なぜか)白衣を羽織ったワイスが、騎乗状態のまま「特殊な混沌の力が漂う建物」の「窓」へと特攻し、そのまま窓を突き破る形で工場内へと突入する。
「我が名は白い魔法使い! 賢者の石は返してもらおう!」
彼女はそう叫びながら、自分が突入した室内の様子を確認する。そこには(彼女ですらも)見たことのない特殊な異界の機械が立ち並び、そして一人の研究者風の男の姿があった。
|
+
|
研究者風の男 |

(出典:『レネゲイドアクションRPG ダブルクロス The 2nd Edition』p.206)
|
「賢者の石だと……? 何の話だ!?」
「その価値が分からぬ者に、彼女を渡す訳にはいかない!」
ワイスがそう叫ぶと、その研究者風の男は、一瞬、視線を「部屋の奥の扉」へと向ける。そんな彼の仕草を、窓の外から密かに様子を伺っていたエルダは見逃さなかった。
(あそこか!)
エルダは、男の視線がワイスに向いていることを確認した上で、密かに建物内へと潜入し、その扉の奥を目指す。日頃、全身甲冑を着て行動していることもあり、ライダースーツとヘルメットしか装備していない今のエルザは、まるで風の如き身軽さで駆け抜けていく。そんな彼女の動きを察知したワイスは、その足音をかき消すために、自動二輪車の動力を激しくふかし始めた。
「私の愛車と、これらの機械、どちらの耐久性が強いか、試してみようか!」
研究者が嫌がりそうなことを言いながら、周囲の機械に向かって突撃しようとする素振りを見せる彼女であったが、そこへ、建物の外から別の「ふかし音」が聞こえてくる。
「ん? この音は……?」
ワイスがその音が聞こえてくる方面に目を向けると、別の窓を突き破る形で、ワイスの乗機よりも更に大型の二輪車に乗った男が飛び込んでくる。その男は、ハウラがFHのアジトの資料室で遭遇した(資料上は既に死んでいる筈の)藤ヶ丘崇文であった。
「この工場区でバイクを乗り回すことを許されてるのは、オレだけの筈。貴様、何者だ?」
「通りすがりの仮面ライダーだ。しかしまぁ、随分とゴテゴテして不格好な二輪車だな」
ヘルメットの下で冷笑しながらワイスがそう挑発すると、男は表情を歪ませながら、研究者風の男に向かって叫ぶ。
「北原のダンナ、こいつはオレにやらせてくれ!」
「それは別にいいが、ここで暴れるのは許さんぞ!」
北原と呼ばれたその男がそう叫ぶと、ワイスは自身の乗機の向きを変える。
「いいだろう。確かにここはライダー同士の対決には狭すぎる」
彼女はそう言って建物の外へと向かって飛び出すと、藤ヶ丘もその後を追う。そしてこの一連のやりとりの間に、エルダはあっさりと扉の奥の部屋への潜入に成功していた。
******
(この部屋のどこかに、捕まっている少女が……?)
エルダは部屋の中を見渡すが、この部屋にも謎の機械などが並んでいるだけで、人の気配はなく、人が入れそうな大型の箱なども見当たらない。
(見当違いだったか? いや、仮にそうだとしても、せめて何か手掛かりを……)
彼女は冷静に周囲の様子を見合わたしながら、再び霊感に神経を集中させると、足元から何か微妙な違和感を感じ取る。
(まさか……)
彼女は床を凝視すると、ほぼ同じ色のタイルが敷き詰められている中、一箇所だけ微妙に色合いが違うタイルがあることに気付く。すぐさまそこに駆け寄ってタイルに手をかけると、それが取り外し可能な形状となっており、その下から微妙に物音がすることに気付く。
即座にそのタイルを引き剥がすと、そこには隠し部屋のような空間が広がっており、一人の少女が横たわっていた。
「シーマちゃん、ですか?」
エルダがそう声をかけると、少女は瞳を開く。だが、意識はまだ朦朧している様子である。
「シーマ……? そう、私はシーマ……、それが私の名前、その筈……」
どうやら、この施設で何らかの「処方」を施されていたらしい。そして、エルダは彼女の身体から微妙な混沌の気配を感じ取る。
(既に、身体に何かを植え付けられている……? いや、でも、大丈夫。ソフィア様ならきっと、この状態からでもお救い下さる筈……)
エルダがそんな思いを抱きながら、少女に手を伸ばし、その空間から彼女を引き上げる。そうこうしている間に、少女は少しずつ、意識をはっきりさせていく。
「そういえば、さっき、Dr.ワイズマンの声が聞こえたような……? いや、でも、そんな筈はない。私は、Dr.ワイズマンに会ったことはないんだから、声を知っている筈がない。じゃあ、さっきのあの声は……」
「とりあえず、その話は後で!」
エルダはそう言いながら少女を抱え上げ、部屋の窓から彼女と共に脱出を果たし、そして空に向かって聖印を掲げる。これは、ワイスとの間で交わした「救出完了」の合図であった。
******
(シーマ、良かった……)
エルダの聖印を確認したワイスは内心でそう呟きつつ、後方から迫りくる藤ヶ丘からの逃走に四苦八苦していた。
「待ちやがれ! このチキン野郎が!」
ノーヘル状態でそう叫びながら、藤ヶ丘は着実に距離を詰めてくる。
(残念ながら、エンジンの性能はあちらのバイクの方が上のようですね。コーナリングでごまかすにしても、限界が……)
目的を果たした以上、一刻も早くここから離脱したいところだが、先方はそう簡単に逃がしてくれそうにない。
そんな中、彼女は旧工場区の中で、一つだけ「明らかに建築様式が異なる建物」があることに気付く。しかも、その周囲の混沌の気配が、微妙に周囲とは異なっているようにも感じられた。
(あれは……、少し気になりますね……)
どちらにしても、これ以上は逃げ切れないと判断した彼女は、先刻と同様に窓ガラスを突き破りながら、その建物の中へと突入する。
すると、そこには五つの「巨大な球体」のような何かが浮かび、その周囲には謎の機械が設置されていた。その姿を確認するため、ワイスはヘルメットを外し、じっくりとその球体を凝視すると、彼女は微妙な既視感を感じる。
「まさかこれは……、混沌儀?」
それは、魔法都市エーラムに存在すると言われる巨大な混沌の球体である。さすがに聖印教会所属のワイスはその実物を見たことはないが、それらは以前に読んだ書物に描かれていた混沌儀と良く似た形状のように思えた。
更に、その周囲の謎の装置からも不気味な気配が漂っている。先刻の研究所の機械も相当に高度な文明の代物であろうことは分かったが、明らかにそれらとも次元が異なる。かつてテラーの秘密基地で見たテラー因子の製造機よりも禍々しい存在のように思えた。
「これはまた、随分とんでもない所に飛び込んでしまったようですね……」
ワイスはそう呟きつつ、今のこの状況に対して、もうひとつの違和感に気付く。
「……なぜ、私を追いかけて入ってこない?」
先刻までワイスを追いかけていた筈の藤ヶ丘が、この建物に入って来ようとしないのである。
「入らないのか、入れないのか、入らないように命じられているのか……、いずれにしても、ここは工場区の中でも特殊な空間、ということらしいですね」
ワイスがそう呟いたところで、建物の外から巨大な爆音が聞こえる、方角からして、川(橋)の方面だということは分かる。
(あちらも計画通りに進んでいる、ということでしょうか?)
ワイスがそう判断した直後、突如、彼女の目の前に「汚水にまみれた状態のディアボロス」が姿を現す。突然の出来事にワイスが驚愕の表情を浮かべる中、彼女と同等以上に驚いた様子のディアボロスが声を上げる。
「誰だ、貴様は!?」
「それはこちらの台詞、と言いたいところですが……」
ワイスは事前に聞いていたディアボロスの外見的特徴を思い出す。
「……はじめまして、ディアボロス。いえ、『春日恭二』が真の名なのでしたっけ?」
そんな彼女に対して、ディアボロスは平静を装いながら答える。
「ふん、どうやら貴様も従騎士の一人のようだな。俺の『瞬間離脱』の行き先まで予想して回り込むとは、大したものだ。」
それについては完全に偶然なのだが、ワイスは状況を概ね推察した上で、汚水の匂いを漂わせたディアボロスに対して語りかける。
「お褒めに預かり、光栄の至り。出来れば、私の賢者の石を奪ってくれたことへのお礼参りといきところなのですが、とりあえず、今は彼女を連れ帰ることの方が優先なので、これにて失礼させて頂きます」
彼女はそう言い残すと、再び二輪車に跨り、そして先刻とは反対側の窓を突き破って、外へと脱出する。ディアボロスはそんな彼女の後ろ姿を、あえて黙って見過ごした。
「色々とやってくれたようだな。だが、次はこうはいかん。歓迎の準備を整えた上で、迎え撃ってくれるわ」
彼はそう呟きつつ、部屋の中に浮かぶ「五つの球体」へと視線を移す。
「さて、こうなった以上、計画を早めなければな……」
その視線の先の一つの球体の中では、約900年前の京の都の光景が映っていた。
******
その後、従騎士達は三つの通信端末を用いて互いに連絡を取り合いつつ、ひとまず揃って魔境から離脱する。魔境全体の混沌核と思しきディアボロスに関しては、何らかの形で瞬間移動が可能な存在である以上、その居場所を明確に特定するのは困難だが、あの旧工場区、特にその中でも、ワイスが最後に潜入した「混沌義のような五つの球体が浮かんでいた部屋」が本拠地である可能性が高そうなので、浄化部隊が優先的に向かうべき先はその建物に絞って良いだろう。
なお、シーマに関しては、身体に何らかの混沌の力を埋め込まれた状態のようだが、今のところは「人」としての形状は保っており、おそらくはソフィアかエイシスの「浄化の印」の力があれば正常な身体に戻れるだろう、という結論に至る。
「本当に良かった……。彼女は、いずれこの世界を正しい方向に導く役目を担うであろう『賢者の原石』なのですから」
ワイスはそう呟きつつ、他の従騎士達と共にカルタキアへと帰還するが、その直後、彼女は自身の聖印の異変に気付く。
「……ロメオ総帥!?」
彼女の従属聖印が唐突に独立聖印化したのである。そして、しばらく時間を空けた後、他の従騎士達の聖印も(「京」の調査任務に向かっていた者達と同様に)次々と自身の指揮官との繋がりが絶たれていく。
果たして、指揮官達の身に何が起きているのか、従騎士達の間で動揺が広がる中、やがて彼等の前に「真相を知る者」が姿を現すことになる(
FR
に続く)。
☆合計達成値:244(3[加算分]+241[今回分] )/100
→次回の最終クエスト(FA)の達成値に72点加算
現在、カルタキアの上空には、異界から投影された天空の大地「イース」が浮遊している。このイースは、現状のまま放置していると地上へと落下し、未曾有の大災害を引き起こす可能性があるらしい。それを止めるためには、イースの中心にあるサルモンの神殿を破壊する必要があると、イースの双子の女神であるフィーナとレアは告げている。
|
+
|
フィーナ |
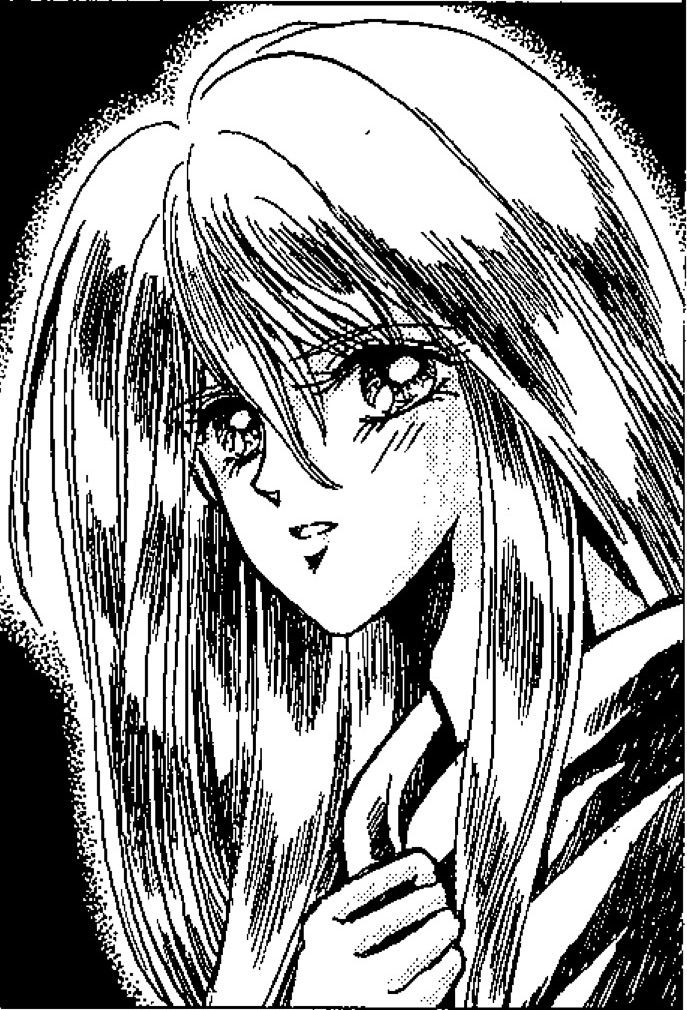
出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.137
|
|
+
|
レア |
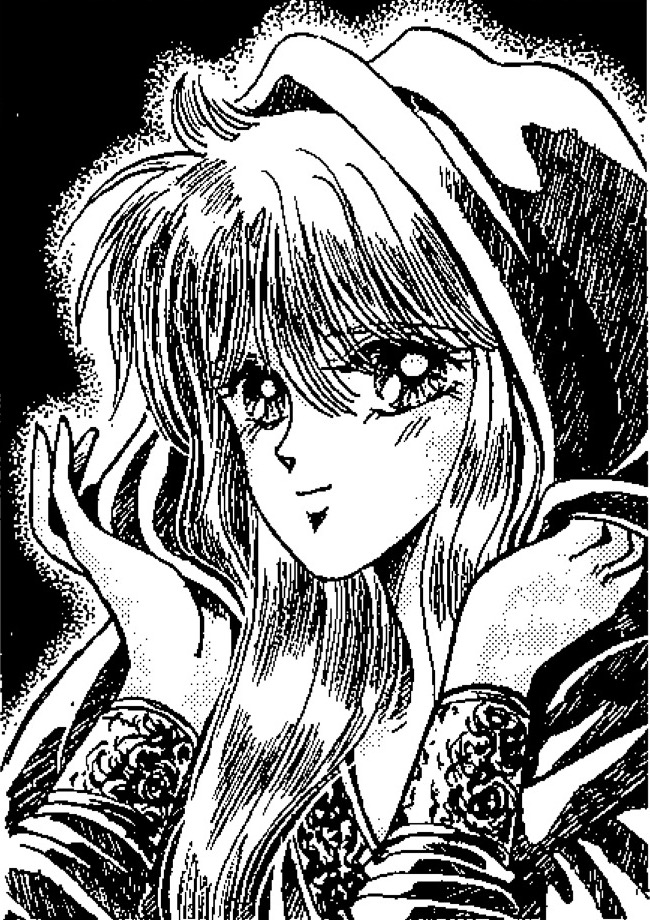
出典:『イース テーブルトークRPG』 p.114
|
彼女達は過去にもこの世界に投影されたことがあり、その際に多くの人々に助けられたことから、自分達の世界からの投影物がこの世界の人々に迷惑をかけることを避けたい、という思いがあるらしい。
先日手に入れた六冊の「イースの本」は既に確保しており、カルタキア内に出現した「塔」の最上階でそれらの本を天に翳せば、イースへと転送されるための光が出現するらしいのだが、問題は「帰路」である。イースを破壊した時点で「足場」が消滅してしまうため、そのまま落下してしまえば命はない。そこで、今回は《瞬換の印》を使用可能なカルタキア領主ソフィアが総指揮官を務めることになった。
これまでソフィアは街の守りに徹していたこともあり、彼女が魔境浄化に参加するのは(少なくとも現在の遠征部隊が常駐するようになって以降では)初である。彼女が領主の館にて出立の準備を整えている傍らには、上述の二人の女神と、そしてソフィアの従属君主である
ノルマ
の姿があった。
「ソフィア様の御身は、必ず私がお守りします」
いつになく強い決意を込めてノルマはそう語る。ソフィアへの忠誠心が人一倍強いノルマがソフィアの魔境行きに際して、並々ならぬ決意を以って同行するのは当然の成り行きであろう。ただ、そんな彼女に対してソフィアは、フィーナを指差しながらこう語る。
「その心意気は評価するが、我には、いざとなったら身を守る手段はいくらでもある。むしろ、今回の浄化作戦の鍵を握るのは、こちらの女神殿じゃ。イースの魔物を封じる力を持っておるのじゃろう?」
これに対しては、フィーナ自身が答える。
「確かに、私の女神としての力を用いれば、魔物を弱体化させることが出来ます。ただ、私は最終的にはイースと共にこの世界から消滅すべき存在。この世界の住人の方々には、あなたをお守りすることを優先して頂いた方が……」
「この世界の住人にとって最も優先すべきことは、この世界を守ることじゃ。そのために必要なのはお主の力。そして今のお主には、身を守る力が備わっておらぬ。ならば、お主の護衛を優先すべき。それだけの話じゃ」
「それは、そうかもしれませんが……」
フィーナが気まずそうな顔を浮かべると、ノルマは両者の意図を汲んだ上で改めて宣言する。
「私の主君はソフィア様ですので、やはり、ソフィア様の護衛を最優先させて頂きたいです。その上で、フィーナ様も含めて、守れる範囲にいる全ての人を守らせて頂きます」
戦局によってはそれが極めて難しい状況になる可能性も十分にあり得るのだが、今のノルマの中では、これ以外の答えは見出だせなかった。そんな彼女に対して、ソフィアは意味深な表情を浮かべながらこう告げる。
「お主がそうしたいならば、それで良い。最終的に誰を守るかを決めるのは、お主自身じゃからな。その責任を背負う覚悟を学ぶという意味でも、良い機会になるじゃろう」
ソフィアのその言葉には何か特別な意味が込められているようにも思えたが、それ以上に、ノルマには今のソフィアから微妙な違和感が感じられた。
(なんだろう……? いつものソフィア様と、少し違うような気がする……)
彼女の口調が普段よりも更に老成しているようにノルマには聞こえたのだが、何がその違いをもたらしているのか、今のノルマにはまだ分からなかった。
一方で、もう一人の女神であるレアが、ふと思い出したようにソフィアに問いかける。
「そういえば、私達の世界には『ソフィア』という名の知恵の妖精がいるのですが、この世界では『ソフィア』というのは一般的な名前なのでしょうか?」
「ふむ……、地域差はあるじゃろうが、少なくとも、珍しい名前ではないな。もともとは『叡智』を意味する古代語だったとも異界語だったとも言われておるらしいが、まぁ、詳しいことは分からぬ」
ソフィアはそう答えつつ、内心では「まぁ、10年前に適当に付けた名じゃからな」などと呟いていたのだが、そのことを知る者は誰もいない。
なお、ソフィアの《瞬換の印》は「別の場所にいる者達」の位置を入れ替えることを前提としているため、今回の浄化作戦において、最終的にイースにいる浄化部隊を地上に戻すためには、彼等と入れ替えるための「誰か」が地上に残っている必要となる。もう一人の女神であるレアは、その「交換要員」としての役割を担うために、イースには同行せず、地上に残る予定であった。
******
ただ、この作戦には一つ大きな問題がある。それは「どのタイミングで《瞬換の印》を使うのか」という点である。
魔境の混沌核を浄化した場合、その混沌核から生まれた「魔境の構成要素」は、段階的に少しずつ消滅していくこともあれば、一瞬にして全てが消滅することもある(この辺りは、魔境ごとに個体差がある)。そのため、もし後者だった場合、「浄化部隊全員」と「地上に残ったレア」を入れ替えようとしても、もしその時点で既にレアが消滅してしまっていると、《瞬換の印》が発動出来なくなってしまう。
したがって、最も確実に全員を地上へと帰還させるには、最低でも一人は「自力で空中から地上へ帰還可能な人物」が必要になる。その人物がいれば、浄化直前の時点でソフィアだけをイースに残した状態で《瞬換の印》を発動し、ソフィアが魔境を浄化した直後に自身とその人物の位置を入れ替えた上で、その人物には自力で帰還してもらう、という選択肢が可能となる。あるいは、その人物自身が魔境を浄化出来るだけの聖印の持ち主なら、最初からその人物だけをイースに残して浄化役を委ねる、という選択肢も可能になるだろう。
「……ということで、私に白羽の矢が立ったのだ」
従騎士達の宿舎の前でそう語ったのは、金剛不壊のラマン艦長である。彼は自身の乗騎に翼を与える《天騎の印》を発動可能であるため、まさにこの役回りに適任、というよりも、彼以外にこの任務を引き受けられる者は、今のカルタキアにはいなかった。
そして彼の視線の先には、直属の従騎士の姿があった。
「……そのことを私に話したということは、つまり、このまま私もイースの浄化任務にも参加しろ、ということですか?」
ため息を付きながらそう答えたのは、
ウェーリー・フリード
である。彼は前回の(イースに向かうための六冊の本の捜索を兼ねた)「塔」の調査任務にも参加していた。
「当然だろう。乗りかけた船の行く先がどうなるか、気にならないのか?」
「いや、まぁ、気にならない訳ではないですけど、別に私でなくてもいいんじゃ……」
「もちろん、どこか他の任務に就きたいというのであれば、止めはしないが」
「いや、別に、そういう訳でもないというか……」
実際、ウェーリーの中にも特にこれといって明確な方針はない。相変わらず、煮え切らない姿勢の彼に対して、ラマンはやや強い口調でこう告げる。
「このカルタキアに来て以来、お前はお前なりに、陰ながら他の従騎士達を助ける仕事をこなしてきたことは知っている。だが、いつもお前は『はっきりとした戦果』を上げる前に任務から降りてしまう。『飛空船の魔境』の時も、『地下帝国の魔境』の時も、そのまま浄化作戦にまで参加し続けていてれば、君主として更なる名声を上げられただろうに」
唯一、浄化作戦まで参加したのは「未来都市の魔境」であったが、この時も敵の戦術分析という形で地味に貢献してはいたものの、最後の最後で同僚のルイスが立案した鮮やかな殲滅作戦の影に隠れてしまったようで、あまり多くの人々の印象には残っていない。それ以降、ルイスは着実にルーラーとしての名声も実力も高めていったのに対し、ウェーリーは(様々な調査任務でその智謀を発揮しながらも)未だ聖印を覚醒させる段階にすら至っていなかった。その状況に対して、ラマンは色々と思うところがあるらしい。
「そろそろ本格的に『形に残る成果』を残した上で、『君主としてふさわしい姿』を見つけるべきではないのか?」
ウェーリーの中では、現状に対してこれといって焦りも不安もなかったのだが、上役であるラマンからそこまで言われたのに対し、改めて溜息をつきながら答える。
「……分かりました。今回の任務で、どうにか頑張りたいと思います」
相変わらずやる気のなさそうな表情を浮かべながら渋々そう答えつつ、彼は自分の「聖印」について考える。
(「君主として」ということは、そろそろ「これ」の使い方を考えないといけないのか……)
ウェーリーはこれまで、ほぼ自分自身の頭脳のみで諸々の任務に貢献しており、聖印の力を殆ど使っていない。彼が君主としてどのような「姿」を目指すにせよ、まずはこの「聖印」の力の使い方を戦場で活かす道を考える必要があった。
******
そしてもう一人、今回の任務に参加予定の指揮官がいた。ヴァーミリオン騎士団のアストライア団長である。上述のソフィアやラマンとは異なり、アストライアは今回の「空の魔境」を浄化するために必須の人員という訳ではないのだが、なぜか彼(彼女?)は今回の浄化作戦に際して、珍しく自分から積極的に参加を希望したらしい。
(この任務こそ、私がこの地に来た「もう一つの目的」を果たすべき好機……)
集合予定地である「塔」へと向かう道すがら、アストライアが密かに内心でそんな思惑を抱いている中、その左隣には直属の部下である
ティカ・シャンテリフ
の姿があった。
「私は今回は、仲間を支援する立場に回りたいと思います」
ティカはこれまで前衛で戦う任務に就くことが多かったが、この辺りでそろそろ、君主としての更なる成長のためにも、これまでとは異なる役回りを経験しておいた方が良いと考えたらしい。どちらにしても、今回の任地である「天空の大地」へと向かうためには、まず「塔」に登らなければならない以上、馬を連れて行く訳にはいかないので、戦場において彼の本来の持ち味を活かすのは難しい、という事情を考えれば、確かに今回の任務は「いつもとは違った役割」を担当してみるには好機なのかもしれない。
「そうだね。視野を広げるのはいいことだ。一歩退いた状態から、仲間の状況を確認しつつ、的確な指示を飛ばせるようになれれば、騎士としても一周り大きく成長出来るだろう」
アストライアはティカに対してそう告げた。日頃は丁寧語で話すことが多い彼(彼女?)だが、部下との対話においては、このような「くだけた口調」となる。
一方、そんなアストライアの右側には、もう一人の従属君主である
セレン
の姿もあった。
「それなら、今回はボクが大将首を狙いに行ってもいいかな?」
彼は以前に参加した「悪魔の館」の浄化任務において、鋼球走破隊のヘルヘイムとの連携策を通じて、彼女が悪魔(自称)を倒すのを
サポートすることに成功した。その成功体験を踏まえた上で、次は自分自身の手で戦功を上げたいと考えているらしい。
これに対して、アストライアは苦笑を浮かべながら答える。
「大将首といっても、今回の魔境の混沌核は『神殿』だからね。それを破壊するとなると、君の『突剣』とは相性が悪いんじゃないかな」
女神達の証言、および「イースの本」の記述によると、神殿は「クレリア」と呼ばれる特殊な鉱物で構成されているらしい。そのため、そもそも通常の武器で破壊出来るのかどうかもよく分からないが、いずれにしても、鎧の隙間を突くことを前提に造られている突剣では、神殿そのものの破壊には向かないのかもしれない。
「だけど、その『神殿』の周囲には魔物達もいるんでしょ?」
「まぁ、女神様はその可能性が高いと言ってるらしいね」
「だったら、ボクはその魔物達のリーダーの首を狙いに行くことにしようかな。だからティカ、サポートをよろしく頼むよ」
セレンがアストライア越しに同僚に対してそう声をかけると、ティカもしっかりと頷く。
「分かりました。少しでも力になれるように頑張ります」
そんな言葉を交わしながら、目の前にそびえ立つ塔に向かって、彼等は歩を進めていった。
******
「リュディガーさんと一緒に浄化作戦に行くのは、未来都市の魔境以来ですね」
「そうですね、ちょっと色々と思うところがあって、戦いからは離れていたので……」
リュディガーは「ヒト型の投影体」との戦いに抵抗感を覚える気性であり、無人の魔境であった未来都市の魔境では全力で戦うことが出来ていたが、他の魔境ではヒト(と思しき投影体)が出現することが多かったという話を聞き、しばらく前線から遠ざかっていたのである。
今回の任地である「天空の魔境」に異世界人が住んでいるかどうかは不明だが、魔境全体の混沌核が「神殿」ということもあり、それならばリュディガーにとっては(少なくとも生身の「ヒト」を相手にするよりは)まだ抵抗感は薄いのかもしれない。
そんな彼の手には、今回の破壊任務のために借りてきた建築用の大槌が握られているのだが、それを見たニナはふと問いかけた。
「そういえば、今回の破壊対象の『神殿』というのは、どれくらいの大きさなんでしょう?」
「分かりませんが、魔境の浄化のためには、神殿の全てを破壊しなくても良いのだと思います。おそらく、祭壇や神像など、ここを神殿たらしめる場所を重点的に壊せば良いかと」
リュディガーはそう答えつつ、自分がその「神殿」を破壊している光景を思い浮かべながら、心の中に湧き上がる思いを、いつも以上に表情を歪めながらニナに吐露する。
「私たちの神とは異なるとはいえ、ヒトの祈りの場を破壊するのは心苦しいと感じてしまいます……。かの神殿は投影された『紛い物』。わかっているのですが……、まだまだ精進が足りないようです」
そう呟く彼に対して、ニナはどこか親近感を覚えていた。理由は異なるとはいえ、しばらく前線から遠ざかっていた身という意味では、ニナも彼と立場はあまり変わらない。
「私も魔境から逃げていた時期が長かったので、戦いを避けたいと思う気持ちも、そのことで後ろめたさを感じる気持ちも分かります。でも、それは仕方のないことだと思います。誰だって、戦場に向かう時は、どこかで躊躇する心があるものだと思いますし。理由は人それぞれだとは思いますけど……」
ニナの中では、それは純粋な「恐怖心」だった。しかし、彼女は前回の塔の任務を通じて、自分と同様の悩みに苦しみながらも、戦場で自らの殻を破って戦果を挙げた同世代のシューネの活躍に励まされたこともあり、改めて今回の浄化作戦へと参加する決意を固めることになったのである。
(私にとって、あの人はライバル。そして、応援したい人……)
******
そんなニナの想いには気付かないまま、
シューネ・レウコート
もまた前回に引き続いて天空の神殿の浄化任務へと向かっていた。
(まだ怖いけど……、それでも、自分にも出来ることを見つけたんだし、今回も頑張って前に出て、魔物を倒さないと……!)
大鎌を握り締めながら、再び「塔」へと向かって歩を進めていく彼女の傍らには、同僚の
イーヴォ
の姿があった。彼は前回は「魔獣の魔境」の浄化作戦に参加していたため、「イース」由来の魔物と戦うのは、今回が初めてである。
「前の調査任務の時に塔で遭遇した魔物達には、何か共通する特徴はあったのかな?」
イーヴォのその問いかけに対して、シューネは前回の諸々を思い出しながら答える。
「え、えーっと……、正直なところ、その……、あんまり共通点はない、っていうか……、戦うだけで精一杯で、あんまりよく覚えていないというか……」
特に、最上階でのダルク・ファクトとの決戦においては、あまりにも唐突すぎる展開に、状況もよく分からないまま戦っていたため、どんな敵だったのかも記憶が曖昧であった。
「……あ、あと、その、女神様の力のおかげで、た、大半の魔物は無力化されてました、から……、今回もそうなるんじゃないかな、と……」
「なるほど。逆に言えば、僕達の前に立ちはだかるとしたら、その女神様の力が通用しないような強大な魔物ばかり、ということか……」
イーヴォはそう呟きつつ、少しずつ心を「戦場モード」へと切り替えていく。
(今回もまた、三人の指揮官が同行してくれるらしい。この機会に、その戦い方を学ばせてもらうことにしよう)
どれだけ訓練を重ねようとも、本当の意味での戦闘技術は本物の戦場でしか身につかない。カルタキアでの任務があとどれだけ続くのかは分からないが、この混沌との最前線の地にいる間は可能な限り多くのものを吸収出来るものは吸収しようと、改めて強く決意したイーヴォであった。
******
こうして、五つの部隊から三人の指揮官と八人の従騎士、そして二人の女神が「塔」の前に結集する。以前の調査時と同様、フィーナが女神の力を用いて「魔の力」を封印した上で、ウェーリーが道案内する形で塔を登っていくことになった。
前回の踏破の時点で「フィーナの力で抑えきれない魔物(=神官の子孫)」は一通り倒した筈であるが、魔境である以上、いつ再び彼等が再投影されるか分からない(更に言えば、それ以外のどんな魔物が追加投影されているかも分からない)ので、念入りに慎重に歩を進める彼等であったが、ひとまずはさしたる妨害も受けないまま、無事に再び25階(最上階)へと到着する。
「では、ここでイースの本を掲げて下さい。そうすれば、イースへと導かれる光が……」
フィーナがそこまで言いかけたところで、階段の方面から、誰かが走り込んで来る足音が聞こえてくる。
「魔物か!?」
イーヴォがそう叫びながら真っ先に弓を構え、セレンとシューネがそれぞれに突剣と大鎌を手に階段の方面へと向かうと、そこから現れたのは、誰も想定していない人物であった。
「あ〜、ごめんなさ〜い、遅れてしまいました〜、自分も連れて行ってくださ〜い」
そう言いながら、少し息を切らしつつ駆け込んできたのは、鋼球走破隊の
ヨルゴ・グラッセ
である。
「ほう、お主が参加するとは聞いておらんかったが、飛び入りか?」
ソフィアが意外そうな顔を浮かべながらそう問いかけると、ヨルゴは一旦その場に腰を落とし、息を乱した状態のまま答える。
「いや〜、その〜……、なんか、夢の中で、よく分からない人に『お前はイースに行け』って言われまして〜……、それで、慌てて塔に向かったんですけど〜、もう皆さんが上に向かっちゃった後だったみたいで〜」
ヨルゴ自身、その「誰か」が誰だったのかは分からない。ただ、なぜかヨルゴの中に眠る深層の別の魂が、「彼の言うことは聞いておけ」という強い衝動を引き起こしていたらしい。
「まぁ、戦力が増えるのは歓迎じゃ。それにしても、お主が全力で追いかけて来る程にやる気を出すとは、なかなか珍しいのう」
「……そうですね、自分でも、なぜかはよく分からないんですけど〜、その『夢の中の声』には従うべきのような気がして〜」
息を整えながらヨルゴがそう呟く中、彼の姿を見た二人の女神は、小声で密かに言葉を交わしていた。
「あの人、前にどこかで会ったような……?」
「私もそんな気がする……、もしかしたら別の人かもしれないけど、あの人から感じ取れるオーラの内側に、どこか既視感があるような……」
彼女達のこの既視感の原因もまた「ヨルゴの中の深層の別の魂の波動」なのだが、その正体が解明される日は永遠に訪れないのであった。
******
こうして、ヨルゴを加える形で仕切り直す形になった12人の浄化部隊は、フィーナと共に塔の最上階の中央に集まり、そしてレアだけは彼等から少しずつ離れていく。
「では、私は皆さんがイースへと導かれたのを確認した後に、地上へと戻ることにします」
過去に別の魔境で出現した「五重塔」の事例から察するに、魔境が消えた時点で塔の25階にいる者達は(投影体以外は)地上へと戻される可能性が高いが、それでも確実と言える保証はないため、少しでも危険性を回避するためには、その方が適切だろう(なお、塔の魔物を無力化することはレアでも可能である)。
無論、それを言い出すなら、最初からレアは塔を登る必要もなかったのだが、彼女の中では、せめてイースへと向かう瞬間までは見送りたいという気持ちがあったらしい。彼女はどこか意味深な笑みを浮かべながら、最後にシューネに声をかける。
「もし、次にまた私がこの世界に現れることがあったら、今度は『あなたの音楽』を聞かせて下さいね」
「そ、それは……、えーっと、その、いつのことになるか分からないんですよね……?」
「えぇ。だから、『その時点でのあなた』が判断してくれればいいです。それでは、どうかご武運を」
レアのその言葉に対して、シューネは黙って頷く。そしてソフィア達が「イースの本」を掲げると、天空から眩い光が彼等を包み込み、そして、その姿が消えていった。
******
次の瞬間、彼等は見たことのない草原の大地に降り立っていた。少し離れた場所には、いくつかの民家らしき建物が並んでいることが分かる。
「ここが、イース……?」
「アトラタンと、あまり変わらないね」
ティカとセレンがそんな言葉を口にする一方で、シューネは耳を澄ませながら呟く。
「あ、あの……、気のせいかも、しれないんですけど……、か、風の音が、少し、違うというか、今まで感じたことがないような、よく分からない、違和感みたいなものが、その、あるような気が、しなくもないというか……」
おそらく、もともと音感に優れたシューネでなければ聞き分け出来ない程度の、ほんの僅かな風音の違いなのだろう。それが、この大地が魔境だからなのか、それとも、高度が高いからなのかは分からない。
そんな中、ノルマは「民家らしき建物」とは反対方向に視線を向けながら、ソフィアに対して問いかける。
「地平線の形が、少し不自然な気がしませんか?」
幼少期に故郷を失い、各地を転々としていたノルマは、何もない荒野の地平線を目の当たりにすることも多かった。だが、この大地から見える地平線は、そんな彼女の記憶の中にあるどの地平線とも形状が異なっているように見える。
「そうじゃな。おそらくはそれこそが、ここが『空中に浮かんだ大地』であることの証なのじゃろう」
彼女がそう呟いたところで、今度はアストライアが口を開く。
「では、まずはそちらを確認することにしましょうか?」
「いや、それは不要じゃろう。この地がイースだという確証が女神殿の中にあるのならな」
ソフィアがそう言いながらフィーナに視線を向けると、彼女はこっくりと頷く。
「間違いありません。ここは確かに、イースの大地です。そして、あそこに見えるのが、ランスという名の辺境の村です。まずはあそこに向かった上で、状況をを確認しましょう」
彼女がそう告げると、浄化部隊の面々は彼女と共に村へと歩を進める。そして、この時点でアストライアの中では、ある一つの「確信」を得ていた。
(自分の現在位置すら正確に把握出来ていない状態でも構わない、ということか……。彼女の用いる《瞬換の印》は、魔法師教会の想定以上の性能らしい)
一般的なルーラーの聖印の持ち主が用いる《瞬換の印》は「視界にいる二組の者達」の位置を交換することしか出来ない筈である(そして、その射程距離も無限ではない)。しかし、ソフィアの《瞬換の印》は、明らかに視界外(しかも、通常ならば交換不可能な程に離れた距離)にいる者達同士でも立ち位置を入れ替えることが可能であり、しかも魔境の内側と外側でも可能という、規格外の効果を備えていることで知られている。
(ただ、それでも完全に万能という訳ではない。今回のような作戦を立てている時点で、少なくとも「一度も足を踏み入れたことがない場所」との交換が不可能であることは分かっている。あとは、今回の浄化任務を通じて、どこまでその真価を見せてくれるのか……)
カルタキアへの遠征が決まった時に、エーラム魔法師協会からアストライアに託された密命、それは「領主ソフィアの正体の解明」であった。未だ謎のヴェールに包まれた存在であるソフィアの実態を明らかにするという目的を果たす上で、彼女自身が魔境浄化へと赴くことになった今回の任務は、アストライアにとっては千載一遇の好機なのである。
そんな彼(彼女?)の思惑をよそに、浄化部隊はフィーナと共にランスの村へと向かっていくのであった。
******
「あそこに誰かいるようだが、さっきから、まったく動いていないような……?」
ランスの村が近付いてきた時点で、弓使いのイーヴォが遠方に存在する「人影」を指差しながらそう告げると、ラマンが遠眼鏡を取り出して様子を確認する。
「あれは人ではない。人の形をした『石像』だ。ただ、少し妙だな……。記念碑を建てるような場所では無さそうだし、造形的にも、あまり偉人としての風格を感じさせるようなデザインではないというか……、あまりにも『自然』すぎる」
それを聞いたフィーナは、表情を曇らせながら口を開く。
「おそらく、それは魔法によって『石化』されてしまった村人でしょう……。この距離まで来ても人の気配がしないことを考えると、おそらく、あの村の人達は、もう……」
この言葉に対して、ニナは寒気を覚える。
「『石化』って、人間を石に変えてしまうってことですか!?」
「はい。私達の世界には、そのような魔法を用いる者もいます。ただ、皆さんには私の加護を施しているので、おそらく通用しません。そして、私の力を使えば、石化を解くことも出来ると言えば出来るのですが……」
現実問題として、これから村人ごとこの世界(魔境)を消滅させようとしていることを考えれば、あえてここで一度呼び起こす必要もないだろう。おそらくは意識を失ったまま、石となって眠り続けたままの状態の方が、消滅の恐怖を感じずに済むことを思えば、このまま放置しておいた方が彼等のためにもなるようにフィーナには思えた。
この方針には従騎士達も概ね同意する。「地下帝国の魔境」の時のように、戦力として活用するという道も無くは無いが、(いかにこちら側に「女神」がいるとはいえ)彼等が事情を聞いた上で協力してくれる保証はない。
(むしろ、これから彼等の心の支えであろう『神殿』を壊すことを考えれば、そのままにしておいた方が無難なんだろうな……)
リュディガーは内心でそんなことを想いつつ、せめて「元の世界」において、彼等が平穏な生活を送れていることを密かに祈りながら村へと辿り着くと、フィーナの予想通り、この村の住人達は全員、石像と化していた。彼等の表情から察するに、突然現れた何者かに驚いた状態のまま、訳も分からずに石化させられてしまったように見える。
(無人の未来都市も異様な雰囲気だったけど、これはこれでまた不気味だな……)
ヨルゴがそんな感想を心の中で抱く一方で、ウェーリーは冷静に状況を分析しながら、敵の戦力についての憶測を展開していた。
(これほどまでの圧倒的な魔法を使えるのだとすれば、むしろ油断して警備が甘くなっている可能性もありうる……? いや、それは楽観視しすぎかな。少なくとも、あの塔の最上階にいたダルく・ファクトよりも厄介な敵が待ち構えていることは、覚悟しておくべきだろう)
他の従騎士達もそれぞれに内心で様々な感慨を抱きつつ、彼等はフィーナの指示に従いながらランスの村を素通りして、イースの中心部へと向かって歩を進める。なお、この時、ソフィアが妙に注意深く「村人達の石像」とその周囲の様子を凝視していたことに、アストライアだけは気付いていた。
******
その後、浄化部隊はフィーナの案内に従いながら、廃坑や氷壁などの障害を乗り越え(その過程で幾人もの人々の「石像」や、フィーナによって無力化された下級の魔物達が苦しんでいる様子を横目に見ながら)、やがてこの大地の中心部に位置する丘の上にそびえ立つ「サルモンの神殿」へと辿り着く。
「確かに、強大な混沌の力を感じるな……」
ソフィアがそう呟くと、他の者達も同様の感慨を抱く。おそらく、この建物のどこかに「魔境全体の混沌核」があることは間違いないだろう。
「神殿の中は複雑な構造になっています。中心部へと向かうには、一旦、地下水路を通ってもらうことになると思い……」
フィーナがそこまで口にしたところで、彼女は自身の背後に不吉な気配を感じて振り返る。そこには、顔まで隠れた兜を被り、ローブのようなもので身をまとった禍々しい風貌の人物の姿があった。
|
+
|
兜とローブの人物 |

出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.143
|
「……ダレス!?」
「奇妙な気配がすると思って来てみれば、やはり、女神であったか。異国の人間共を引き連れて、この神殿に足を踏み入れるとは、なんと愚……」
その人物がそこまで口にした瞬間、彼の姿が一瞬にして「石像」へと変わる。それはランスの村で見かけた「石化された村人」の一人の姿であった。
「え……?」
困惑した様子のフィーナに対して、ソフィアが語りかける。
「よく事情は分からぬが、今声をかけてきた者は『敵』なのじゃろう?」
「は、はい……、彼は魔道士ダレス。魔物達を率いる魔王ダームの配下の中でも最強の魔力の持ち主で、おそらく、人々を石へと変えたのも、彼の仕業です」
「なるほどな。もし手違いだったらすぐに『戻す』つもりじゃったが、そういうことなら、奴にはこのまま『ランスの村』にいてもらおう」
ソフィアのこの言葉で、ようやく皆は事態を理解する。つまり、ソフィアが《瞬換の印》の力を用いて、「ダレス」と「石化されたランスの村人」の位置を入れ替えたのである。
「まぁ、状況に気付けばすぐに戻ってくるじゃろうから、その前に神殿の破壊を進めさせてもらうことにしようかのう」
淡々とソフィアがそう語るのを見て、従騎士達は改めてソフィアの聖印の力に圧倒される。《瞬換の印》は、発動者よりも高位の君主や魔法師などを相手にした時には通用しないことが多いのだが、フィーナの力を以ってしても抑えられない程の魔力の投影体を、あっさりと(しかも視界外のはるか遠くの場所まで)転移させるというのは、常識外れにも程がある。
(この力があれば、私達の存在など不要なのでは……?)
(もし、この人が皇帝聖印争いに加わることになったら、どうなるんだろう……?)
皆が内心でそんな思いを抱く中、アストライアだけは、あることに気付いていた。
(今、彼女が力を発動する前に、ほんの一瞬だけ彼女の額に「第三の目」が開いた……。あれが「バロールの魔眼」だとすれば、おそらく魔法師協会の推測は正しい、ということになる……)
アストライアがそのことに気付けたのは、彼(彼女?)がずっとソフィアを凝視していたからである。そして、「その瞬間」において彼女(彼?)の目も大きく見開いていたのであるが、そのことに気付いていた者は誰もいない。
******
こうして、彼等は神殿の中へと突入を開始する。その途中、神殿および地下水路の通路上で、何体か「フィーナの力で抑え込めない魔物」が襲いかかってきたが、ラマンとアストライアの手によって次々と瞬殺されていった。いつもならば、従騎士達の成長のために彼等を前線に立たせるのが指揮官達の方針なのだが、今回は「ダレスが戻って来る前に魔境の混沌核を破壊する」という作戦上、戦力を出し惜しみせずに迅速性を重視する方針であった(そもそも通路の構造上、そう何人も横に立って戦うことは出来ない、という事情もあった)。
なお、屋内戦である以上、当然、馬は使えないため、ラマンは《小さき友の印》で愛馬ペルーサを小型化・収納した状態での戦いとなっていたのだが、キャヴァリアーとしての能力をほぼ封印された状態にも関わらず、彼はほぼ自身の長剣の技術だけで魔物達を圧倒していたのである。
(この人の実力は、まだまだ底が知れないな)
ラマンの従属聖印の持ち主であるウェーリーがそんな感慨を抱く中、アストライアもまた、本来は防御型聖印の持ち主であるパラディンの筈なのだが、この時は迅速性を優先して、自ら率先して攻めの姿勢で次々と魔物達を薙ぎ払っていく。
(やっぱり、団長の剣術の本質は攻防一体……)
(今まではボク達を育てるために、あえて守りに徹していたのか)
アストライアの直属の従騎士であるティカとセレンは、改めて自らの指揮官の実力を目の当たりにして、今の自分との実力差を実感させられる。
そんな彼等が道を切り開いていく中、従騎士達は神殿の周囲に視線を配らせながら、この魔境全体を探して回る。神殿の奥に向かえば向かうほど、着実に混沌の力が強まっていることは分かるのだが、それでも明確な確証は持てないまま、彼等は神殿と地下水路を結ぶ階段などを何度も上下しつつ、賢明に捜索を続ける。
やがて、彼等が神殿の最上階に位置する「鐘つき堂」へと辿り着くと、その中核に位置する巨大な「銀色の鐘」を発見する。
「ふむ、あれじゃな」
ソフィアがそう呟くと、従騎士達も納得した表情を浮かべる。その鐘からは確かに、魔境全体の中核と思しき混沌の力が漂っていた。
だが、彼等がその鐘に近付こうとすると、その前に、先刻の魔道士ダレス以上に禍々しい気配をまとった、黒い巨大な宝石を持った人物が現れる。
|
+
|
黒い巨大な宝石を持った人物 |
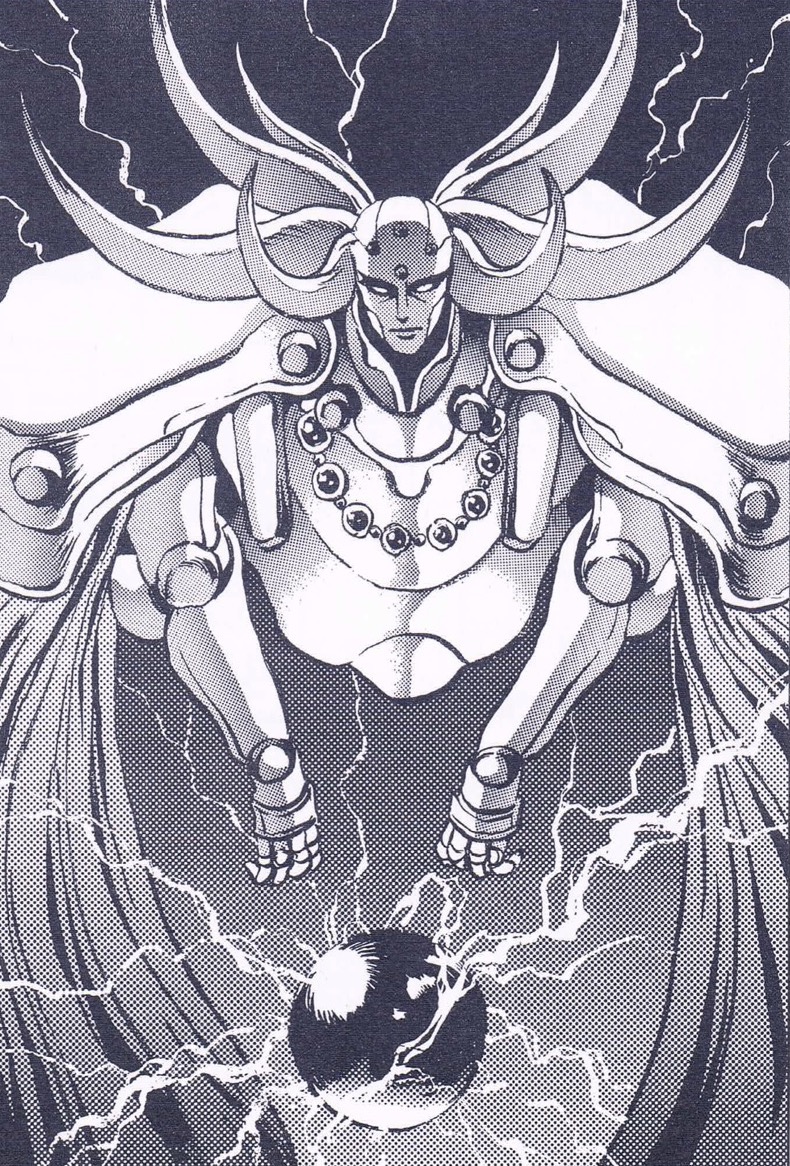
出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.143
|
「魔王、ダーム……!」
フィーナが表情を強張らせながらその名を呟いた直後、ソフィアはすぐさま《瞬換の印》を発動させ、その「魔王」と「ランスの村の住人の石像」を入れ替える。だが、その直後に、再びその「魔王」が彼等の前に姿を現した。
「……今、何をした?」
名乗る間もなくランスの村へと転移させられた「魔王」は、やや困惑した声色でフィーナに対してそう問いかけるが、それに対して横からソフィアが口を挟んだ。
「ほう、お主も瞬間移動が使えるのか。さすがに魔王と呼ばれるだけのことはあるな」
「……貴様の仕業か。異国の小娘よ」
「すまぬな。お主の相手は厄介そうじゃから、何度でも退散してもらう」
ソフィアはそう語りながら再び《瞬換の印》を用いて、「魔王」を「ランスの村の別の住人の石像」と置き換える。だが、その直後に再び「魔王」が姿を現した。
「何度やっても無駄だ。この魔王ダームに、そんな小細工は通用しない!」
「無駄かどうかは分かるまい。どちらかの力が尽きるまで、付き合ってもらうぞ」
そう言ってソフィアは更に《瞬換の印》を発動させる、魔王ダームも更にまた瞬間移動の力を用いてこの場に戻ってくる。傍目には、何をやっているのか分からない「奇妙な戦い」が発生する中、ソフィアは他の者達に目で訴えかける。
(今のうちに、鐘を破壊せよ!)
従騎士達がその意図を察すると、リュディガーが鐘を見据えながら、剣を大槌に持ち替える。すると、彼の大槌に対して、フィーナが自身に内包された「女神の力」を付与し、その大槌は鐘と同じ銀色の輝きを放ち始める。
「これで、クレリアと同等の力が備わった筈です」
フィーナは(力を使いすぎたのか)少し疲弊した声色でそう伝えると、リュディガーは静かに頷き、そして鐘へと向かって突撃する。
だが、そんな彼に対して、突然、遠方から謎の光球が飛び込んできた。
「!?」
驚いたリュディガーであったが、すぐさまそこにアストライアが割って入る。
「させません」
アストライアはそう言いながら刀でその光球を真っ二つに切り裂く。そして、その光球の飛んで来た方向には、先刻の魔道士ダレスとよく似た装束を身に纏った者の姿があった。しかし、その下半身は不気味な触手のような何かで構成されている。
|
+
|
触手のような下半身を持つ者 |
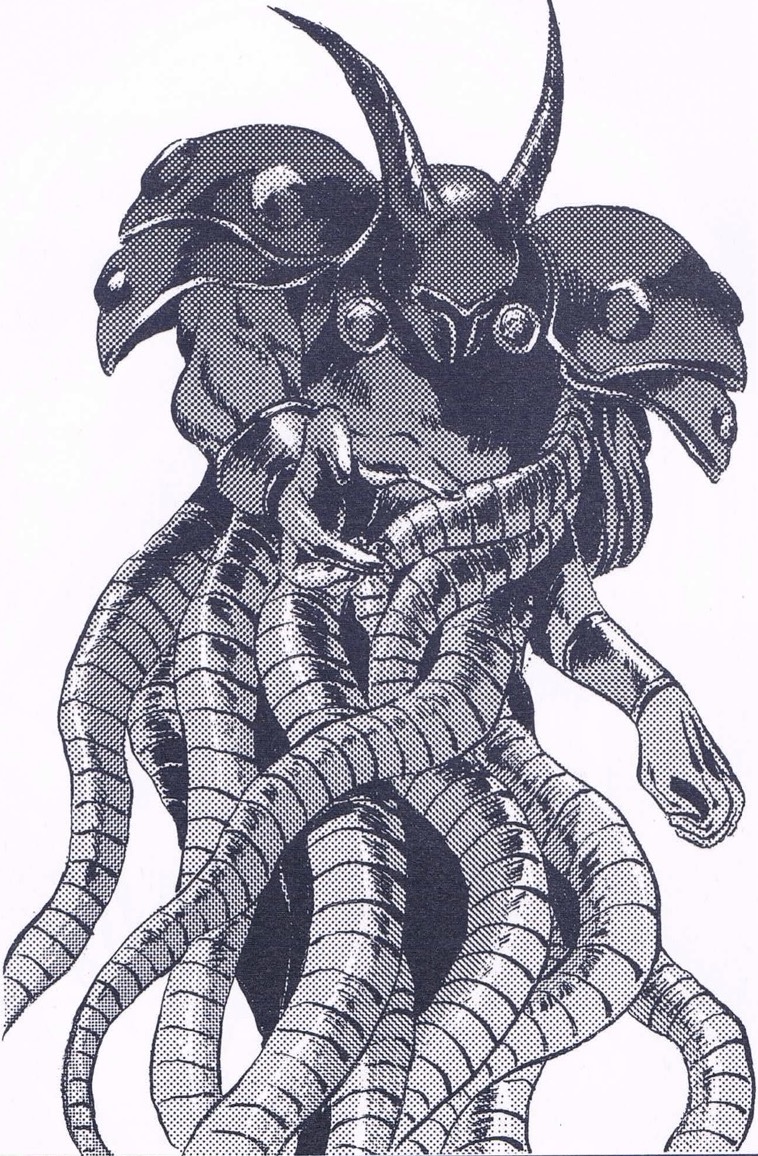
出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.138
|
「彼はザバ! ダームの配下で、彼もまた魔王の一人です!」
フィーナがそう叫ぶと、ラマンが《小さき友の印》を解除した上で、即座に騎乗状態となり、そのままザバに対して突撃する。
(領主殿に「あちらの魔王」の対応に専念してもらうためにも、こちらは私が引き受けよう)
ラマンはそんな思いを胸にザバに対して斬りかかるが、今ひとつ手応えを感じられない。ただ、現状の目標は「鐘の破壊」である以上、無理にこの敵を殲滅することにはこだわらず、ひとまずリュディガーへの攻撃を防ぐことが出来れば良いと割り切った上で、このザバという魔王と対峙する。ザバはそれでも光球をリュディガーに向かって放とうとするが、鐘へと向かう彼の背後を守るようにアストライアが立ちはだかり、全て斬り伏せられる。
一方、イーヴォはラマンを支援するためにザバへと向けて弓を構えた。
(ここは少しでも敵の気をそらすことが重要……)
彼は前回の魔境での任務を思い出しながら、今の自分の果たすべき役割を考えた上で、あえて聖印の光を強く掲げ、ザバの視線を自身へと向けさせた上で、ザバへと向かって矢を放つ。その矢はあっさりとかわされるが、イーヴォとしてはそれも織り込み済みであった。
(これでいい。おそらく、今のオレの矢は強大な投影体相手には通用しないだろう。それでも、聖印の光は彼等にとっては未知の存在だからこそ、警戒心を呼び起こすことが出来る。その意味では、むしろ避けてくれた方がいい。命中して「大した威力ではない」と思われてしまったら、注意を引き付けることすら出来なくなってしまうからな……)
イーヴォはそう判断した上で、ザバからの光球に警戒しつつ、再び弓を構えようとするが、ここで横からティカの声が響き渡る。
「イーヴォさん、後ろ!」
その声に反応してイーヴォが振り返ると、「大型の蝙蝠」が彼の後方から迫りつつあった。その形状は、以前にカルタキアの図書館で現れた群体の蝙蝠とは明らかに別種であり、より禍々しい気配を放っている。
|
+
|
大型の蝙蝠 |

出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.138
|
「…ッ!! いつの間に!?」
つい先刻まで、飛行生物の気配など全く感じなかったのだが、その蝙蝠は確かに鋭い牙を剥き出しにして、イーヴォに対して襲いかかろうとしている。
(困ったな……、こないだの模擬戦で分かったことだけど、接近戦は苦手なんだよ……)
イーヴォは咄嗟にサイドステップでかわそうとするが、蝙蝠はすぐに軌道を変えて彼との距離を詰める。しかし、そこに割って入った者がいた。ノルマである。
「下がってください!」
そう叫びながら、彼女はイーヴォを守るように盾を構えようとする。だが、直前までソフィアとフィーナに視線を向けていたこともあり、その防御動作が一瞬遅れてしまった結果、彼女の鎧の継ぎ目に、蝙蝠に牙が突き立てられる。
(くっ……!)
兜で隠されたノルマの素顔は苦痛に歪むが、彼女は歯を食いしばりながら、体勢を崩さぬように必死でその場で蝙蝠を相手に立ちはだかり続ける。だが、その様子を見ていたニナには、ノルマの動作が微妙に不自然な挙動となっていることが分かる。
(もしかして、毒を受けている……?)
医療関係の知識が豊富なニナは、(傍目には平静を装っている)ノルマの身体に異変が発生していることを察した上で、彼女に向かって聖印を掲げた。
(今の私の聖印で、どこまで出来るかは分からないけど、こういう時のために、私はメサイアになったんだから!)
ニナのそんな想いを込めた聖印の輝きはノルマの身体を照らし出す。すると、ノルマは自分の身体を蝕んでいた何かが消滅したことを実感する。本来、ニナの聖印には毒を治療する力(《浄化の印》もしくは《快癒の印》)は備わっていない筈なのだが、ニナが自身の知識を駆使してノルマの中に入り込んだ「身体に変調を与えている何か」が存在すると思える場所に向けて重点的に聖印の光を掲げた結果、その毒の効果を打ち消すことが出来たのだろう。
「……ありがとうございます!」
ノルマはニナに一瞬だけ視線を向けつつ、そのまま蝙蝠に対して対峙する。ノルマの体調が回復した様子を見て、ニナはほっと一息をつくが、その直後、今度はニナの背後から、また別の(同種の)蝙蝠の羽音が聞こえてきた。どうやら、別の場所に隠れていた蝙蝠が、ニナの掲げた聖印に反応して姿を現したらしい。
「……え!?」
慌てて振り返ったニナであったが、彼女の視界に蝙蝠が映ったと思った直後、その視界は「見慣れた背中」によって遮られた。
「ニ、ニナさんも……、さ、ささ……、さがって、ください……!」
シューネがニナの前に立ちはだかったのである。彼女は大鎌を振るって、蝙蝠が近付かないように牽制する。その足は微妙に震えながらも、瞳はしっかりと目の前の敵を見据えていた。
一方、ノルマのおかげで難を逃れたイーヴォは、周囲を見渡しながら、弓兵としての自分の特性を活かせそうな立地を探す。すると、程良く身を隠せそうな「遮蔽物」を発見した。
(……悪いな、ここは戦場だ。利用出来るものは利用させてもらう)
彼は内心でそう呟きながら、次々とソフィアによってこの地に召喚(交換)されていく「石化された村人達」が溜まっていく場所へと向かう(魔王ダームは「置き換え」ではなく単体での瞬間移動なので、結果的に石像の数は次々と増え続けていた)。
「……オレは主力ではないが、少なくとも敵さんにとっては”最悪の位置で陣取ってる厄介なヤツ”でありたいよ。そのためにこの戦場に来たんだ」
彼はそう呟きつつ、まずはノルマとシューネを支援すべく、彼女達がそれぞれ対峙している蝙蝠達に向けて矢をつがえる。
そんな中、セレンは(ラマンと対峙している)魔王ザバの様子を伺いながら、背中側へと回り込もうとしていた。
(あの魔物、そもそも視界がどこを向いてるのかもよく分からないけど、それでもラマンさんを相手にしているなら、きっと反対側までは気が回らない筈……)
そんな思惑を抱きつつ、一撃必殺の不意打ちをかけようと、セレンが自身の聖印の力をその剣に込めようとしたところで、彼の視界にまたしても「別の蝙蝠」が姿を現した。
「三匹目!?」
セレンはやむなく、標的をその「蝙蝠」へと変更した上で斬りかかる。そして、ここまであえて前線には立たずに後方から戦況を見守っていたティカは、これまでに出現した蝙蝠達から、その出現傾向を分析していた。
「あの蝙蝠達、聖印の力に反応しているような……」
これに対して、隣にいたウェーリーが問いかける。
「聖印が蝙蝠達の投影の触媒になっている、ということか?」
「いえ、混沌の揺らぎは発生していないので、彼等はもともと、この魔境内に存在していた蝙蝠でしょう。おそらく、『あの触手の魔王』と共に、この鐘つき堂を守るために配備されていた伏兵ではないかと」
今回のティカは戦況把握に専念していたため、この戦場における「混沌」の気配に対しても細かく観察していた。そして、「リュディガーが鐘を破壊しようとした時に出現した魔王ザバ」と連携する形で現れたように見えたのである。
「なるほど。聖印が新たな魔物を呼び込んでしまっているのだとしたら、迂闊に使わない方がいいかもしれないと思ったが、そういうことなら、むしろ先に敵の戦力の総勢を確認させてもらった方がいいのかもしれないな」
「そうですね。そしておそらく、次に出てくるとしたら……」
ティカはそう言いながら、部屋の四隅のうちの一角を指差す。ティカの認識が正しければ、その方角からはまだ蝙蝠は出現していない。そしておそらく、ここまで出現した三匹は、他の三つの「隅」の方角から出現していた。
「そういうことなら、ここで引きずり出させてもらおう。迎撃は任せていいかな?」
ウェーリーがそう呟くと、ティカは頷いて剣と盾を構える。そしてウェーリーは、自身の頭上に高らかに聖印を掲げた。彼は出陣前にラマンに言われていたことを思い出しながら、これまであまり使って来なかった聖印に、自身の魂を強く込める。
(僕の魂が目指すべき道は……)
すると、ウェーリーの聖印は、まだスタイルすらも定まっていない不定形な状態ながらも、これまでに見たことがない程の強烈な輝きを発する。
そして、その聖印の光に反応して、ティカが予想していた方角から、「四体目」の蝙蝠が現れた。
(これで最後、だといいのだけど)
ティカはその蝙蝠に対して斬りかかりつつ、周囲に更なる混沌の気配が出現しないかどうか気を配る。そしてウェーリーもまた、聖印の力を更に強めつつ、周囲の戦況を確認しようとしたところで、戦場全体に巨大な「轟音」が響き渡った。リュディガーの大槌が、巨大な鐘に叩きつけられたのである。
この時、リュディガーは確かな手応えを感じていたが、それでも、鐘には傷が付いたようには見えない。
「さすがに、一撃では無理ですね……」
彼は続けて何度も鐘に対して大槌を振るい続ける。その様子を見ていたウェーリーは、あることに気付き、近くにいたヨルゴに声をかける。
「あの鐘の反対側に行って、抑えてきてくれないか?」
リュディガーの大槌が鐘を叩く度に、当然のことながら鐘は大きく揺れる。その振動を反対側から誰かが抑え込むことで、より大きな衝撃を鐘に与えられるであろう、と考えたのである。リュディガーの近くにはアストライアもいるが、ザバからの光球がいつまた飛んでくるかも分からない状況においては、その迎撃に専念してもらった方が安全であり、現状における余剰戦力は、ヨルゴしか残っていなかった。
「あー……、了解ですー」
おそらく、その「抑え役」は相当な振動を受け止め続けなければならないのだろう、ということに気付いたヨルゴは、あまり乗り気ではなかったが、あの鐘を壊さなければ浄化が完了しないのであれば、ここは手伝う他に道はないだろう。
彼は全力でリュディガーの元へと駆け寄ると、この時点でリュディガーは既に埃まみれの状態になっていた。どうやら、長年放置されていた鐘を叩き続けたことで、上から積年の埃が降ってきていたらしい。そして、既に何度も鐘を叩き続けている間に、彼の額には大量の汗が流れ、やや息も上がっていた。
「え? だ、大丈夫……?」
心配そうに声をかけるヨルゴであったが、リュディガーは力強く答える。
「慣れたもんです、薪割りの斧や鉈とそう変わりませんから!」
彼がそう言いながら再び大槌を振りかぶると、ヨルゴは言われた通りに彼の反対側へと回って鐘を抑えつつ、リュディガーの繰り出す衝撃を受け止める。
(こ、これは……、思ってたよりもキツい、かも……)
ヨルゴは内心でそう思いながらも、微妙に身体の角度を調整することで振動を逃がす術を模索しつつ、二人がかりでの鐘の破壊作業を続けていくのであった。
******
それからしばらくの間、フィーナが戦場全体に「女神の加護」を張り巡らせた状態のまま、二人の魔王と四匹の蝙蝠を相手にした君主達の総力戦が展開されることになる。
ソフィアとダームの転移合戦は果てしなく続き、鐘つき堂には次々と「村人の石像」が山積みになっていく、一方で、それらを遮蔽物として利用しながら射撃戦を展開していたイーヴォは、四匹の蝙蝠と対峙するノルマ、シューネ、セレン、ティカの四人の戦況を確認しつつ、必要に応じて援護射撃をおこなっていた。
(今のこの戦場で優先すべきは、戦力の損失を防ぐこと)
前回の浄化作戦の時、カエラは「より多様な駒」を残すことを優先して、従騎士達の戦力を温存することを前提に行動していた。この時のイーヴォもまた、「敵を倒すこと」よりも「味方を死なせないこと」に重点を置く形での援護射撃に徹していたのである。
(やはり、空を飛ぶ相手は厄介だな。四人とも苦戦している。比較的余裕がありそうなのは「彼」のようだが……)
イーヴォのその視線の先には、ティカの姿があった。実際、彼はまだほぼ無傷で、体力的にも余裕がありそうだったが、それは彼があくまで「牽制」に徹していたからであり、蝙蝠の方もまた全く無傷の状態であった。
(今回の僕の役目は、敵を倒すことじゃない。あくまで戦局を見渡して、敵の戦力を探ること)
ティカはそう自分に言い聞かせつつ、目の前の蝙蝠の動きを観察しながら、戦場全体の状況をに目を配り続けていた。そして、やがて彼は奇妙な違和感に気付く。それは、ラマンと戦っている魔王ザバの様子であった。
(あの魔物……、ラマン殿の攻撃に対して、そもそも避けようとすらしていない。どれだけ斬りつけられても死なないという絶対的な自信があるのか……、いや、もしそれが「自信」ではなく、純然たる「事実」なのだとしたら……?)
ティカの中で様々な可能性へと憶測が広がる中、やがてこの戦場の膠着状態が一変する。シューネと戦っていた蝙蝠が彼女の腕へと噛みつき、その激痛からシューネが大鎌を落としてしまったのである。
「あ……!」
シューネが激痛に苦しむ中、丸腰状態となった彼女の頭上から蝙蝠が襲いかかろうとする。しかし、ここでイーヴォが聖印の力を込めて牽制の矢を放つと、蝙蝠の視線はイーヴォへと移り、イーヴォはそのまま、あえて石像の山から抜け出て蝙蝠を挑発するように聖印を光を掲げる。
その隙にシューネは鎌を拾おうとするが、激痛と恐怖から、その場に座り込んで動けなくなってしまう。
(また……、また私は、やってしまった……。やっぱり、私には無理だったの……? 塔の時は、たまたま上手くいっただけで、私には戦いなんて……)
彼女の心が絶望に打ちひしがれようとした時、彼女の視界に眩い光が灯される。それは、ウェーリーが掲げている聖印の輝きであった。先刻から、ただひたすらに気力を込め続けていた彼の聖印から、特殊な力がその場にいる従騎士達に流れ込んでくる。
その光の正体にいち早く気付いたのは、ウェーリーの上官のラマンであった。
(どうやら、微弱ながらも《奮迅の印》の力の片鱗が発動したようだな)
それは(特定のスタイルに依らない)君主としての基礎的な聖印の力の一つであり、味方の戦意を回復させる効果をもたらす光である。その光を受けたシューネは絶望の淵でギリギリ踏み留まり、そして彼女の右腕に対して、駆け込んだニナが聖印で治療を始める。
「しっかりして下さい、シューネさん!」
「ニナさん……、わ、私は……」
「あなたが助けてくれたから、私は今もこうして戦場にいられるんです!」
それは、先刻の一件だけではない。塔での戦いの時から、ニナにとっては、シューネの存在そのものが心の支えでもあった。
「私とあなたでは、進むべき道は違うのかもしれない。私では、あなたの隣に立つことは出来ないかもしれない。それでも、一緒に『前』に進んでいきたいんです!」
ニナにそう言われたシューネは、恐怖を振り払って再び大鎌を手に立ち上がる。この時点で、彼女と対峙していた蝙蝠は既にイーヴォへと向かって飛びかかろうとしていたが、彼女は全力でその大鎌を振るい、横から一気にその蝙蝠を薙ぎ払う。
(怖いけど、でも……、これが私のできること!)
シューネのそんな想いを込めたその一撃は、イーヴォに気を取られていた蝙蝠にとっては完全な不意打ちとなったこともあり、その身体はあっさりと真っ二つに引き裂かれた。
そして次の瞬間、ラマンと戦っていたザバの動きに、何かアクシデントが生じたかのような異変が発生したのを、ティカは見逃さなかった。
「そうか……、皆さん! あの魔物、『蝙蝠達と繋がった存在』なのだと思います!」
魔物達の中には、複数体で「命(心臓?)」を共有する者達もいるという話を、ティカはエーラムの魔法師から聞いたことがある。もし、ザバの「生命」が蝙蝠達と連動した存在なのだとしたら、蝙蝠達を倒すことによって、ザバを無力化出来る可能性もある。
ティカのその言葉を受けた上で、ウェーリーは聖印を掲げた状態のまま、皆に声をかける。
「ならば一体ずつ、着実に倒していこう! まずはセレン君に支援を!」
ウェーリーがそう判断したのは、この時点で最も疲弊しているのが、セレンと対峙している蝙蝠のように見えたからである。イーヴォが弓矢をそちらに向け、そしてシューネも大鎌を手に駆け込もうとすると、その蝙蝠は恐怖を感じてその場から飛び去ろうとする。だが、その蝙蝠が背を向けた瞬間、セレンが跳び上がりながら剣を突き刺す。
「人間も動物も、逃げる時が無防備なんだよね」
笑顔でセレンがそう呟くと、蝙蝠は空中でそのまま絶命する。そして予想通り、ラマンと戦っているザバは更に動きが鈍くなり始めた。
「よし、これであと二体……!」
イーヴォがそう呟きつつ、ノルマとティカに視線を向けるが、彼等と対峙していた蝙蝠達は、この時点でどちらも一斉にその場から飛び去り始めていた。
「……仕方ない、せめて一匹だけでも!」
彼は即座に矢を放った結果、ひとまずノルマと戦っていた方の蝙蝠の撃墜には成功する。だが、その次の瞬間、射程外へ逃げ去ったと思われた残り一体の蝙蝠が、突然、「村人達の石像」の山の中から現れる。
「!?」
突然の出来事に皆が困惑する中、反射的に一人の従騎士がその蝙蝠に向かって走り込んでいった。セレンである。
「二匹目、いただき!」
彼はそう叫びながら、突剣でその蝙蝠を串刺しにすると、その直後に蝙蝠は息絶え、そしてラマンと戦っていたザバもまた、混沌の塵となって消滅していく。
「うむ、ご苦労じゃったな」
石像の山の一角からソフィアがそう呟くことで、従騎士達がようやく状況を理解した。今の現象もまた、ソフィアによる《瞬換の印》の効果なのだろう。だが、ここで当然、皆が同じ疑問に辿り着く。
(魔王ダームは……?)
先刻までソフィアとの転移合戦を繰り返していた筈のダームの姿が、いつの間にかどこにも出現しなくなっている。
「おそらく、魔力が尽きたのじゃろう。もしくは、根負けして、今はランスの村で、何か別の方法を企んでおるのかも知れぬが……」
ソフィアがそこまで言いかけたところで、彼女の視界に映っていたニナ、シューネ、イーヴォの三人が、驚愕の表情を浮かべる。
「え……?」
「これって……?」
「まさか……?」
その三人が、何に困惑しているのか、他の者達には分からない。一方で、リュディガーとヨルゴによる鐘の破壊活動はここまで順調に進行しており、既に鐘にはヒビが入りかけていたのだが、ここで最後に追い込みをかけようとしていたリュディガーもまた(上記の三人と同じタイミングで)突然その手を止める。
「レ、レオさま……!?」
「ん? どうした?」
ヨルゴがリュディガーにそう問いかけると、彼は明らかに焦燥した声で答える。
「私の聖印と繋がっていた筈のレオノール閣下の気配が、消えました……」
彼がそう呟くと、少し離れた場所にいたニナも反応する。
「やっぱり、そうですよね!?」
そして、シューネとイーヴォもまた顔を見合わせる。
「カエラ様の聖印が……?」
「……あぁ、状況は分からないが、今、オレの聖印は独立聖印化したようだ」
従属聖印の本来の持ち主である君主が死亡、もしくは聖印を失うようなことがあれば、彼等の聖印は独立聖印化する。だが、彼等の主人であるレオノールとカエラは、いずれも現在はカルタキアで結婚式場の建設に勤しんでいる筈であり、危険な任務に就いている訳ではない。それ以外の可能性として、彼等が何らかの事情で従属君主達を意図的に独立聖印化した(自身の聖印との関係を断ち切った)か、それ以外の特殊な異常事態が発生している可能性もゼロとは言えないが、今のところ、思い当たる節は誰にもない。
一方で、その四人以外の従属君主達の聖印には異常は発生していないようだが、指揮官達も含めて、(事情を全く理解出来ていないフィーナ以外の)この場にいる者達全員の心に動揺が広がる。そんな中、ソフィアは冷静な声で皆に語りかける。
「ふむ……、とりあえず、カルタキアに戻って確認するしかなかろう。鐘の方もあと一息で破壊出来そうじゃし、ひとまずお主達は先に……」
彼女はそこまで言いかけたところで、唐突に天井を見上げる。そこには、鐘を吊るしていた屋根が存在するのだが、彼女はその屋根の先から、何かを感じ取っていた。
「この気配……、まさか……」
ソフィアがそう呟いた次の瞬間、唐突にその天井が破壊され、謎の怪光線が全員に向かって降り注がれそうになるのだが、その光はアストライア一人に向かって集約していった。集団に対する攻撃を自分一人に集約させる《城塞の印》を、アストライアが発動させたのである。
この怪光線の正体が何なのか、誰にも分からない。ただ、それを一身で受け止めたアストライアの身体は、これまでに見たことがない程の深手を負っていた。
「団長!」
「団長殿!」
セレンとティカがそう叫ぶ中、アストライアは片膝を付きながらも、いつもと変わらぬ穏やかな笑顔を浮かべながら答える。
「心配ないよ。これが『パラディンの聖印』を持つ者の使命なのだから」
アストライアはそう呟きつつ、《治癒の印》を自分自身に施しつつ、立ち上がる。そして皆が頭上に視線を移すと、そこには既に天井は存在せず、青い空が広がっている。だが、ここでソフィアがぼそりと呟いた。
「どうやら、この空の先に、もう一つ『別の魔境』があるようじゃな」
彼女のその発言を受けて皆が目を凝らして空を見上げるが、誰もそれらしきものを見つけることが出来ない。だが、やがてそんな彼等の視界に「謎の映像」が浮かび上がる。
「これは……、《サイレントイメージ》? それとも、《クリエイトイメージ》でしょうか?」
アストライアがそう呟く。いずれもエーラムの魔法師が用いる「空間に映像を生み出す魔法」なのだが、実際のところは、そのどちらでもない。そして、その映像に映されていたのは、異界の装束(宇宙服)を着た、眼鏡をかけた男であった。彼は奇妙なポーズを取りながら口を動かし、それと同時に音声も聞こえてくる。
「我が名はキョウジ・カスガ! この世界の人類に反省を促すためにコロニーレーザーを放ったのだが、それすらも受け止めるとは、やはりアトラタンのロードは化け物のようだな」
唐突に訳の分からないことを言われた従騎士達は困惑するが、ソフィアは薄ら笑いを浮かべながら淡々と声を掛ける。
「ディアボロスか? なんじゃその格好は? 気でも触れたか?」
すると、どうやらその声は「彼」にも届いているようで、こちらもまた余裕の笑みを浮かべながら答える。
「言っただろう、我が名はキョウジ・カスガ。貴様の知っているディアボロスではない。いわば、奴の『影の兄弟』のような存在だ」
ソフィアはその言葉の意味はよく分からなかったが、それでも状況は概ね理解する。
「なるほど……、そういえば《ブラム=ストーカー》の力も有しておるのじゃったな。《従者》は作らぬ主義かと思うておったが、今頃になって『我の真似事』を始めたのか?」
「何とでも言うがいい。『俺達』はお前を倒して、この世界を『俺達の世界』へと書き換える。そのための『今の一撃』であったが、それでも沈められぬというのであれば、次は『コロニーそのもの』を落とすしか無さそうだな。貴様等の中途半端な抵抗が、更なる破滅を招いたことを後悔するがいい」
不気味な笑顔を浮かべながら、キョウジを映した映像は消えていく。ただでさえ動揺していた従騎士達の心に更なる困惑が広がる中、ソフィアは改めて皆に対して語りかける。
「どうやら、今の男はこの空の先に存在する『宇宙の魔境』に存在するようじゃ」
「宇宙……?」
聞き慣れない言葉を聞いて、従騎士達の困惑に更に拍車がかかるが、彼女は気にせずそのまま語り続ける。
「ひとまず、今から予定通りにお主達を地上に戻した上で、我とラマン提督でこの魔境を破壊する。その上で、我等はその《宇宙の魔境》へと向かおうと思うのじゃが、良いか?」
ソフィアがラマンに対してそう問いかけると、彼は今ひとつこの状況を理解しきれていない様子ながらも、落ち着いた口調で答える。
「構いません。私のペルーサで辿り着ける範囲なのであれば」
「正直なところ、辿り着けるかどうかは分からぬが、《天騎の印》を使っても無理なら、それはもうどうにもならない話じゃからのう」
二人がそんな会話を交わしているところで、横からアストライアが割って入る。
「ラマン殿、あなたの愛馬は、もう一人同乗者を増やすことは可能ですか?」
その言葉の意図を、ラマンはすぐに察する。
「まぁ、本来ならば二人乗りが限界ですが、領主様と団長殿であれば、二人で『重戦士一人分』程度の重さですからな。乗せられぬことはありませぬぞ」
彼がそう答えると、今度はソフィアがアストライアに問いかける。
「そんな手負いの状態でついて来るというのか?」
「ご心配なく。到着までの間に自力で傷は治しますから」
アストライアは意味深な笑顔を浮かべながら、そう答える。「ソフィアの正体を見極める」とういう使命を果たすためにも、ここで退くわけにはいかなかった。
一方で、従騎士達もまた、指揮官達の間で唐突に「次の作戦」が進みつつあることに対して異を唱えようとする者もいたが、現状において「空が飛べる乗騎」は一つしかない以上、誰もついていくことは出来ない。とはいえ、いざとなればソフィアの《瞬換の印》で戦力を入れ替えることは可能なので、まずはこの三人で乗り込むのが正解であるように思えた。
「では、ひとまずカルタキアの様子を確認しに行くのじゃ。よろしく頼むぞ」
ソフィアは従騎士達にそう告げると、彼等に対して《瞬換の印》を施し、「地上に残っていたレア」と入れ替える。
「……!?」
従騎士達に変わってソフィア達の前の前に現れたレアは、突然の出来事に一瞬驚くが、すぐにフィーナが駆け寄って状況を説明する(と言っても、「もう一つの魔境」などについてはフィーナも全く理解出来ていないので、伝えられるのは情報には限度があったのだが)。
「なるほど……、では、まだ魔王ダームは健在なのですか?」
レアがソフィアに対してそう問いかけると、ソフィアは淡々と答える。
「その通りじゃ。故に、もうあまり時間はかけられぬ。一瞬でこの魔境を消滅させてもらうが、良いな?」
これに対してはレアとフィーナが黙って頷くと、ソフィアとアストライアはラマンの愛馬ペルーサに同乗し、そしてラマンは自身の武器に「女神の力」を施してもらった上で、鐘に向かって突撃を敢行すると、既に半壊状態だった鐘は粉々に破壊され、そして巨大な混沌核が姿を現す。その直後、同乗していたソフィアが自らの聖印でその混沌核を浄化吸収することで、この「天空の魔境」は消滅していくことになった。大地と共に消えゆく二人の女神は、最後まで笑顔を浮かべながらラマン達の姿を見送るが、彼等が二人のことを振り返ることなく、そのまま「更なる天空」へと向かって飛び上がっていくのであった。
******
一方、地上に戻った従騎士達は、ひとまず街の人々に状況を確認しようとするが、その過程において、カエラとレオノール以外の指揮官達の従属君主達の聖印もまた(他の魔境に向かっていた者達と同様に)次々と「独立聖印」と化していく。
皆の中で更なる困惑が広がっていく中、やがて彼等は他の従騎士達と合流した上で、衝撃的な真実を告げられることになるのであった(
FR
に続く)。
☆合計達成値:139(22[加算分]+117[今回分])/100
→成長カウント1上昇、次回の最終クエスト(FC)の達成値に19点加算
カルタキア沖に出現した人口島「久遠ヶ原学園」は、21世紀の地球から投影された魔境の一つである。カルタキア近辺にはなぜか「21世紀の地球」からの魔境が数多く出現しているが、それらの大半は互いに平行世界の関係にある別世界であり、その構造は大きく異なる。
この「久遠ヶ原学園」の投影元の地球は、「天界」の住人である天使と、「魔界/冥界」の住人である悪魔からの侵略を受けており、これら「天魔」と戦うための撃退士を養成するために人類が設立した教育機関がこの学園島なのだが、その人類もまた一枚岩ではなく、この学園内で育成される撃退士達の中にも、撃退士としての力を用いて人類社会の主導権を握ろうとする「世界征服同好会」と呼ばれる反学園組織が存在しているらしい。
そして、現在カルタキアに出現している「久遠ヶ原学園」には、なぜか地球人達は一切投影されず、天使と悪魔だけが闊歩している状態なのだが、この魔境全体の混沌核は、天使でも悪魔でも学園内の施設でもなく、その世界征服同好会を構成する下部組織の一つである科学者集団「P9P」が生み出した「人造撃退士」と呼ばれる存在であるということが、先日の調査で明らかになった。
「人造撃退士とは、この異世界の人類が開発した『クローン』と呼ばれる技術を用いて生み出した、超常的な力を持つ人型兵器らしいです。外見は美しい少女のような姿をしていますが、感情はなく、ただひたすらに、侵入者に対して無慈悲で正確な攻撃を繰り出す戦闘人形として、現在は学園内の『図書館』を守っているのだとか」
カルタキアの領主の館の一角に設置された会議室において、前回の調査任務にも参加していた幽幻の血盟の
アシーナ・マルティネス
は、生徒会室で入手した資料に目を通しながら、出席者達に対してそう告げた(なお、この日も彼女の腕にも「緑の腕章」が装着されている)。
あくまで資料に基づいた説明でしかないので、その人造撃退士の戦闘力がいかほどなのかはアシーナにも分からないのだが、ここまでの話を聞いた段階で、鋼球走破隊の
ファニル・リンドヴルム
が手を挙げた。
「その人造撃退士ってのは、『一体』なのか?」
この問いに対する返答如何によって、マローダーであるファニルの戦い方は大きく変わるのだが、これに対しては、アシーナの隣に座っていた(彼女の恋人でもある)
グレイス・ノーレッジ
が答える。
「実際に図書館に踏み込んだ調査隊が見たのは『一体』だったそうですが、他にも潜んでいる可能性はあるでしょう。そもそも『クローン』というのは、同じ生き物の複製体を作るための技術らしいですから」
アシーナ同様、前回の調査隊にも参加していたグレイスは、今回の会議に先立って、このカルタキアの地に残されていた21世紀の地球に関する様々な文献などを調べていた。もし、この仮説が正しいとすれば、絶対に倒さなければならない『魔境全体の混沌核』に相当する人造撃退士が少なくとも一体存在することは確定とした上で、それと同等の戦闘力を持つ個体が他にも存在するかもしれない、ということになる。
更に、今回の浄化作戦に関しては、それに加えて厄介な問題が存在する。調査隊の報告によれば、その人造撃退士が存在する図書館は、学園内における「天使」と「悪魔」のそれぞれの縄張りの中間地点であり、図書館に突入する前に、両陣営から襲撃を受ける可能性がある。彼等にとって人間の「感情」や「魂」は「獲物」であり、しかも前回の調査隊が図書館から出てくるところを目撃されているため、図書館近辺で目を光らせている可能性が高い。
とはいえ、図書館には特殊な結界が存在するため、一度図書館の中にさえ入ってしまえば、彼等と戦う必要はない。そう考えると、ここで必要となるのは「陽動役」である。
「とりあえず、俺はいつも通り、派手に暴れて天使や悪魔の目を引きつければいいんだよな?」
鋼球走破隊のタウロスがニヤリと笑いながらそう呟くと、直属の部下であるファニルはやや首を傾げる。
「なんか、いつもより嬉しそうだな」
「あぁ。ここまでの報告を聞く限り、今回に関しては、魔境の大将首よりも、天使や悪魔の方が戦力としては上のような気がするからな」
「そうか? 人造撃退士の方だって、総戦力はまだ分からないんだし、図書館の奥に隠し玉が潜んでる可能性もあるぞ」
「確かにな。だから、そっちはお前に任せる。一つの戦場に、マローダーは二人もいらないだろ?」
「お、おぅ。まぁ、そうだな」
この時、ファニルの目には、タウロスの表情がこれまでとは少し違って見えた。以前は「弟子」を見るような眼差しであった彼の視線が、今は「相棒」に語りかける時の瞳のように見えたのである。
(ちっとは俺のことも認めてくれてる、ってことか……?)
ファニルはそんな感慨を抱きつつも、自分が図書館への突入組に加わることには素直に同意する。一方で、天使と悪魔を図書館から引き剥がすための陽動役には、三人の従騎士が名乗りを上げた。
一人目は、幽幻の血盟の
ルーカス・クライスト
である。
「俺の強みは視野の広さだからな。屋内戦よりは屋外戦の方が向いてる」
彼としては、今回もまた遠方から戦局全体を見通しつつ、弓矢を用いて敵を撹乱させながら誘導する役回りを担当する心算であった。
二人目は、ヴァーミリオン騎士団の
シオン・アスター
である。
「僕も、そちらに回ろうと思います。悪魔とは、前に一度戦ってますし……」
誘拐騒動の時に、シオンは下級の悪魔を一体、撃破している。あの時は同僚のアルスが敵の注意を引きつけてくれたからこその殊勲だったということもあってか、今回は自分が陽動役の方に回ろうと考えたようである。
そして最後の一人は、星屑十字軍の
ポレット
であった。
「悪意を持って人々を襲う投影体と戦うことが、私達の使命ですから」
これまで実際にカルタキアの人々に対して直接的な危害を加えていた天使や悪魔に対する憎悪の感情を瞳に宿しながら、ポレットはそう呟いた。実際のところ、先日の誘拐事件においても、10年前の混沌災害においても、実害を出しているのは天使や悪魔であり、人造撃退士から攻撃を受けたのは、図書館に侵入した調査部隊の者達だけである。
おそらく、人造撃退士は悪意どころか感情すら持ち合わせていない。ただ純粋に、侵入者を撃退するという命令だけを実行しているだけの存在である。本来ならば、天使や悪魔から(元の世界における)人間を守るべき存在だったのだろう。そう考えると、天使や悪魔に対して並々ならぬ敵意を抱くアシーナとしても内心は複雑であったが、彼女は今回はあえて、その人造撃退士と戦う「突入部隊」への参加を志願していた。
(この場にいない彼らに代わり、責任は果たすべき、なのでしょう)
アシーナはかつて、地球人の投影体達と共に旅をしていた。投影前の彼等は、実はこの「久遠ヶ原学園」の撃退士達だったのである。アシーナは彼等から、天使と悪魔がどれほど忌むべき存在なのかを教えられており、いずれ彼女の前にそれらが現れた時のために、彼女に対して天魔との戦い方も伝授していた。
その一つに「人であったモノを壊してでも人を助けよ」という言葉がある。天使や悪魔は人間を自らの下僕へと作り変えた上で人間を襲わせる。一度そうなってしまった者達は人間には戻れない。今回の「人造撃退士」は天魔ではなく人間によって生み出された存在だが、それでも「人であったモノ」であることには変わりない。だからこそ、彼女(達?)を「終わらせる」必要がある。アシーナは密かにそんな決意を抱いていた。
(それが結果的に天魔を退け、この地に平和をもたらすのなら……。たとえ彼女が、本来は立派な同志で、天魔を相手に戦い続けた、尊敬に値する者であったとしても……)
心の中で自分に対してそう言い聞かせるアシーナのことを、隣でグレイスは心配そうに見つめていた。本来ならば彼もまた弓使いであるため、屋外戦の方が向いているのだろうが、今回はアシーナと共に突入部隊に参加する予定である。
そして、その突入部隊の指揮を採るのはヴェント・アウレオのエイシスであり、彼の従属君主である
アリア・レジーナ
、
ヴァルタ・デルトラプス
、
ラオリス・デルトラプス
の三人もまた、彼に同行する。
「私に出来ることがあれば、何なりとお申し付け下さい」
アリアはエイシスに対して、恭しくそう告げる。彼女は基本的には今回も医療班として従軍する予定ではあるが、それ以外の点でも、エイシスの力になれることがあれば積極的に協力したいと考えていた。
「今回も、お手伝いするよ」
「姉さんと一緒に、頑張ります」
ラオリスとヴァルタは、今回は前線要員としての参戦である。特にラオリスは、先日セイバーとしての聖印の力に覚醒したばかり、ということもあり、その聖印の力加減を確認したい、という思いもあった。
そして、もう一人の指揮官である潮流戦線のジーベンもまた突入部隊に参加予定であり、彼の直属の部下である
セーラ・ドルク
もまた、当然の如く彼に同行する。
「ジーベン、なにすればいい?」
「……いつも通り、目の前に現れた敵を倒せ。それだけでいい」
「うん、まかせて!」
一見すると、それは今までと変わらぬ「この二人のいつもの会話」のように見えたが、実はセーラの中では微妙な変化が生じていた。これまでの彼女は、戦いそのものを楽しむことを目的に戦場に立っていたが、今の彼女は「仲間を助けたい」という思いが強まり、そのために必要なことが何なのかを知るために、ジーベンに指示を仰いだのである。
これに対して、ジーベンもまたセーラのそんな心境の変化に気付いた上で、あえてこれまで通りのシンプルな指示を彼女に伝えた。彼女の持ち味を活かすには、結局、それが一番だと判断したのである。そしてセーラもまた、それが仲間を助けることになると信じた上で、彼の指示に従うことを決意したのであった。
そんな「特攻役」としてのセーラやデルトラプス姉弟を支える補佐役として従軍予定なのが、ヴァーミリオン騎士団の
アルス・ギルフォード
と、星屑十字軍の
リューヌ・エスパス
である。
「今回は、この盾で皆さんを守る役回りに徹したいと思います」
アルスのギルフォード流わらしべ盾術は攻防一体の戦闘術である。しかし、本格的にパラディンとしての道を歩み始めたアルスとしては「人を守る役割」を己の心にはっきりと刻むために、あえて今回は殲滅役は他の者達に任せて、守りに徹するつもりであった。ちなみに、アシーナ曰く、撃退士には「三つの武器を素早く切り替えて扱う」という特徴があるらしいので、人造撃退士もそれと同様かは分からないが、幅広い射程からの攻撃を想定した守備陣形が必要になるだろう。
「後方支援は私にお任せくださいませ。前線の皆様は、戦いに専念してくだされば結構です」
リューヌはリューヌで、メサイアとしての道をまっとうすべく、治療道具と聖印の力を併用した上での治療要員として参戦を表明していた。メサイアとしては圧倒的にい格上のエイシスに加えて、彼の側近のアリアも医療班として参戦予定ではあるが、状況によっては彼等の手が回らない状況になることもあり得る以上、治療技術を持つ者は一人でも多いに越したことはない。
そしてもう一人、金剛不壊の
ルイス・ウィルドール
もまた、今回は突入部隊への参加を表明していた。そんな彼に対して、エイシスが問いかける。
「意外ですね、あなたが『こちら側』に志願するとは」
軍略家であるルイスの智謀を活かすなら、むしろ天使と悪魔を図書館から引き剥がす役回りの方が向いているようにエイシスには思えたのだが、ルイスもまた事前に「久遠ヶ原学園の天使と悪魔」について入念に調べた上で、今回は彼等を相手にした戦いには向かないという判断に至っていた。
「恐らく、天使や悪魔は、相反する力に弱いんです。文献では、カオスレートって表現されていました。だから、そっちの戦場は光や闇の力とか、あるいは何か特殊な生まれを持ったような人が向いているんです」
確かに、元の世界において光の力を持つ者にはプラス、闇の力を持つ者にはマイナスの「カオスレート」と呼ばれる力が存在すると言われている。一般的に、前者は天使、後者は悪魔の力と言われているが、撃退士達の中にも、その特性に応じて一定のカオスレートが存在するらしい。
「僕は『普通』です。だからこそ、今回はこの戦場を選びました」
ルイスはそう語るが、その解釈に対して、アシーナはやや疑念を抱く。
「しかし、それを言うなら、私達は全員『普通』なのでは? そもそもカオスレートとは、彼等の世界の中の概念なのですから、私達には関係ないと思いますし……」
アシーナはそこまで言いかけたところで、今度は自分のその言葉に疑念を抱く。
(……本当に、関係ないのでしょうか? もしかして、前回の調査の時に、私の身体が「結界」に反応したのは……?)
彼女の中で「嫌な予感」が広がる。だが、彼女はすぐにその考えを打ち消した。
(……そんな筈はありません。プラスやマイナスのカオスレートを持つ人は撃退士の中にもいるのだから、もし仮に私の身体に「彼らの残滓」が宿っていたとしても、その程度の力に反応するなら、誰も生徒会室に入れなくなってしまう。だから、関係ない筈です。そう、関係ない筈……)
唐突にアシーナが黙り込んだことで微妙な沈黙が流れるが、彼女がそれ以上何かを言おうとしている訳ではないことを確認した上で、ルイスは答える。
「確かに、そうかもしれません。でも、この世界に出現する投影体は、あくまで『混沌の力で生み出された類似品』であって、元の世界の彼等と全く同一の存在という訳ではない以上、この世界における『プラス』と『マイナス』に相当する何かが、彼等にとっての『カオスレートの相性』に相当する形で影響を与えるかもしれない、と思ったんです。もちろん、あくまで一つの仮説にすぎないですけどね」
その仮説に基づいて考えた上で、ルイスは自分のことを「普通(カオスレート:ゼロ)」と判断したらしい。その解釈が妥当か否かは不明だが、タウロスは興味深そうな顔を浮かべる。
「なるほどな。そういう意味では、投影体の血を引く『特殊な生まれ』である俺は、やっぱり天使や悪魔との戦いの方が向いてるってことだな」
これに対して、ファニルは微妙な表情を浮かべる。
(いや、それを言うなら、俺もそうかもしれないんだが……、まぁ、いいか)
実際のところ、ファニルに出自は不明である。明らかに人外の角や尾を生やしている以上、おそらく投影体の血が流れているのではないかとファニル自身も思ってはいるが、自分の親が何者かも知らない彼女としては、確かめようがなかった。
そしてもう一人、明らかに「異界の血」をその身に宿した従騎士がこの場にいた。タウロスやファニルの妹分の
ヘルヘイム
である。
「ヘルは、伏兵などに警戒する索敵役を担当したいと思います。今回は、陽動班も突入班も戦力は十分のようですし、より確実に勝利へと繋げるためにも、兄さま達の邪魔をするような乱入者への対応に回ろうかと」
これまでは積極的に最前線での戦いに身を投じることが多かった彼女であるが、今回は珍しく、一歩引いた立場で参戦する道を選んだ。戦力バランス的にそれが適切と考えたのもあるが、彼女の中にはもう一つ、個人的な思惑もあった。
(この機会に、ジーベンさまから「戦場での立ち回り方」を学ばせて頂きたいのです……)
セイバーの聖印を手に入れたヘルヘイムは、これまで手本としてきたタウロスやファニルとは異なる「セイバーの戦い方」を学ぶ必要性を実感していた。そこで、セイバーの聖印を持つ前線指揮官であるジーベンの戦い方を少し離れた場所から観察することで、「戦場で味方の役に立つような動き」を学びたいと考えていたのである。
こうして各自の役割が明確化したところで、最後にエイシスが「重大な注意事項」を伝える。
「今回の魔境は『海』に出現しています。魔境の浄化が完了した後は『足場』がなくなりますから、島に停泊していた船が救助に行くまでは、どうにか自力で泳ぎ続けてもらう必要がありますので、泳ぎに自信がない人は、私が生み出す《聖地の印》と《地の利の印》の範囲から離れないようにして下さい」
島の海岸に接舷した状態の船が、学園内の図書館にまで到達するには、どれだけ早くても数分を要するが、エイシスの《聖地の印》と《地の利の印》の範囲にいれば生存能力も身体能力も大幅に増幅する上、泳ぎが苦手な者でも、どうにか耐え続けることは出来るだろう。その意味では、突入部隊はなるべく離れずに行動した上で、陽動部隊は彼等の突入を確認した時点で船へと戻る必要がある。
その上で、今回の上陸作戦において皆が乗船する船には、ヴェント・アウレオの母船である「グランシャリオ」が選ばれた。全体の指揮官がエイシスだから、という事情もあるが、この船には七隻の小型艇が付随しているため、短時間で多くの従騎士達を海から引き上げるという意味でも適任という判断に至ったのである。作戦中の船の管理については一般船員達に任せるという前提の上で、ひとまず浄化部隊の面々はこの船へと乗り込むことになるのであった。
******
「さぁ、来てやったぞ、天魔ども! この俺の極上の魂と感情、欲しけりゃくれてやる! かかってきな!」
図書館の近くの広場にて、タウロスは聖印を高らかに掲げながらそう叫ぶ。すると、その周囲で徐々に混沌濃度が高まってくるのを彼は感じていた。しかし、なかなかその実態は表そうとしない。
(様子を伺っているのか……、それなら!)
タウロスは、周囲に漂ういくつかの混沌の気配の一つに対して、モーニングスターを振りかざし、《暴風の印》を叩き込む。すると、そこから狼のような姿の二足歩行の怪物達が現れ、タウロスに向かって襲いかかってくる。
「来やがったか! お前ら、どっち側だ? まぁ、どっちでもいいけどな!」
タウロスはそう叫びながら彼等に向かって突進すると、彼等の後方から更におぞましい姿の怪物たちが次々と現れてくるのが見える。
(どうやら、こっちは「悪魔側」ということか?)
そんな憶測を立てながら、彼はあえて派手に立ち振る舞うことでより多くの怪物達の目を自分に引きつける。一方、そんな彼の行動を物陰から見ていたルーカスは、彼が向かった方向とは反対側に視線を向ける。
(もし、あそこにいるのが『天使』だとするなら……、疲弊したところを狙って襲う算段か?)
ルーカスはそんな予想を立てつつ、ひとまず自身の弓矢に聖印の力を込めようと試みる。まだ「まっさらな聖印」しか持たない彼には《光弾の印》を発動することは出来ない。しかし、それでも微弱な聖印の光を灯すくらいの技術は備わっていた。
(これで、少しでも気を引ければいいんだがな……)
彼はそう念じながら、混沌の気配が漂う図書館の近くの施設に向かって光矢を放つ。だが、それに対してこれといった反応は起きない。続けて彼はその周囲に対して矢を放ち続けていくが、やはり明確な変化が起きているようには見えない。
(今の俺の聖印が生み出す程度の光じゃ、意味がないってことか……?)
そんな考えが脳裏を過ぎった直後、唐突にルーカスは自身の背後に何かが近付いて来るのを感じ取る。振り返ると、そこに現れたのは空を飛ぶ巨大な鮫のような何かであった。それ自体も不気味な存在であるが、その開いた口の中には人間の上半身が埋まっているように見える。
「な……、いつの間に!?」
驚いたルーカスが慌てて距離を取ろうとするが、既にかなりの距離にまで接敵されている。
(こいつは確か天使の眷族だと、軍議の時に誰かが言ってたような……)
おそらく、ルーカスの弓に反応した天使陣営が、彼の視界の外側から送り込んで来たのだろう。今のこの状況から、弓を使える射程まで逃げるのは厳しいことは分かる。だが、そこへ横から別の従騎士が駆け込んで来た。シオンである。
(鮫はこちらを見ていない……、今なら無防備なその横腹を!)
シオンはレイピアを鮫の脇へと突き立てようとする。しかし、威力が足りなかったのか、あっさりと弾かれてしまった。
「か、硬い……」
そして次の瞬間、鮫はシオンの方へと向きを変えようとするが、そこへ反対側から、今度はポレットが駆け込んできた。
「やらせません!」
《破邪の印》の力が込められた彼女の棍は鮫の頭部に直撃し、その一撃で鮫は混沌の藻屑と化して消えていく……。
「す、すごい……」
シオンは、自分の突剣では全く刃が立たなかった相手を一撃で葬ったその威力に感服する。そしてポレット自身もまた、今の自分の力に驚いていた。
(以前の私では、投影体を相手にこんな威力を発揮出来る筈もなかった……。これが、パニッシャーの聖印の力……)
彼女はそう実感しつつ、そこに至るまでの道筋を思い返す。
(そう、私のこの聖印は、このカルタキアに来てから乗り越えてきた数多の試練の末に手に入れたもの……、そして、その過程で出会った全ての人々の御助力の結晶でもあるのですね……)
ポレットがそんな感慨に浸りかけたところで、すぐさま今の巨大鮫と同じ形状と思しき怪物が一匹、同じ方向から近付いてくるのを察知する。
「ルーカスさんは、そのまま距離を取って下さい! シオンさん、ここは食い止めましょう!」
「おう!」
「分かりました!」
ポレットの掛け声に合わせて三人はすぐさま迎撃のフォーメーションに入る。そして、同い年の少女が繰り出した聖印の力を目の当たりにしたシオンは、改めて自身の聖印を掲げる。それは、既にパニッシャーとして《破邪の印》の力を宿す程の力を備えているポレットの聖印とは対象的な、(ルーカスと同様の)まだ何者でもない「まっさらな聖印」であった。
(僕の聖印は、まだ何の未来も示していません。それでも、今のこの状況を乗り越えるための力が、この聖印の中に眠っている可能性があるのなら……)
シオンはそう念じながら、自分の聖印に想いを込める。すると、彼のレイピアは今までに見たことがない光を放ち始める。
(こ、これが、聖印の光……?)
彼がその光に戸惑っている中、飛び込んで来た巨大鮫はポレットへと襲いかかるが、ポレットは巧みな杖術でその攻撃を受け止める。
「ここから先は、誰も通しません!」
ポレットによって完全に巨大鮫の勢いが殺されたところで、シオンは横に回り込み、先刻と同じように鮫の脇腹へと光剣を突き刺そうとする。
(今のこの剣なら……!)
彼のその想いを込めた一撃は、今度は確かに鮫の体皮を深々と突き破り、鮫(の中の人型の何か?)は不気味な叫び声を上げる。この時点で、シオンは自分が発動した光の正体が《武器の印》であることを確信する。それは、スタイルに関係なくどんな君主でも発動可能な、武器を強化する力であった。あくまでも一時的に発動した力に過ぎないが、シオンもようやく、自分の聖印の本格的な使い方を身体で覚え始めたようである。
そして、その直後に今度は後方からルーカスが放った矢が巨大鮫に激突し、鮫は更に苦しみの声を上げながら、その場でのたうち回り始める。その次の瞬間、ポレットはとどめの一撃を叩き込もうとするが、その前に彼女の視界に、別の投影体達の姿が映った。彼等は巨大鮫の叫び声を聞いて、明らかにポレット達に対して敵意を向けている。
(今は、敵を倒すことよりも、彼等を図書館から遠ざける方が優先……)
彼女はそう判断した上で、改めて聖印の輝きを強める。
「タウロス様と合流した上で、海岸まで退きましょう」
既に陽動役としての仕事は果たしたと判断した二人は黙って頷きつつ、それぞれの聖印を掲げることで敵の目を引きながら、図書館から遠ざかり始める。そんな中、ポレットは改めて、自分の立場の変化を感じていた。
(私が、他の部隊の人達の指揮を採っている……? 今までずっと、色々な人達に支えられてきた私が……?)
聖印を覚醒させたことで、自分の果たすべき役割も変わりつつあることを実感しつつ、ポレットはまだその立場の変化に微妙に戸惑っていた。
そして、三人が自分の方に向かって来たのを見て、タウロスは彼等を追ってくる天使の下僕達の数と距離を確認する。
(今回は、あくまで囮役だからな。敵を警戒させすぎてもダメだし、ここはもうしばらく本気を出すのは控えておくか)
タウロスはそう割り切りつつ、ひとまずは三人と合流した上で、彼等を守りながら程々に応戦を続けることにしたのであった。
******
「今です! 行きましょう!」
少し離れた建物の影から状況を伺っていた突入部隊の面々は、エイシスのその掛け声に従い、図書館へと向かって一気に駆け出していく。それに対して、陽動部隊を追いかけていた天使や悪魔の一部は反応するが、彼等に対しては、ジーベンが殿軍となって立ちはだかる。
「お前達は先に行け!」
ジーベンのその声を背中に受けながら、エイシスと従騎士達は次々と図書館内へと突入していく。そして、ジーベン自身も身体は敵を向いた状態のまま、バックステップで(他の従騎士達が全力疾走するのとほぼ同じ速度で)図書館へと向かって移動しつつ、様々な角度から迫り来る敵に対して、その間合いを計算しながら一体ずつ距離を詰め、着実に仕留めていた。
(なんて器用な戦い方……、まるで後ろに……、いえ、全方面に目が付いているみたいです)
少し離れたところで戦局を観察していたヘルヘイムは、内心でそう呟いた。彼女は今、戦場全体の動向を見渡すことに全神経を集中しているが、ジーベンは自分と同じように幅広い視野を維持しながら、移動と迎撃を着実にこなしている。
(これが、幾多の戦場を渡り歩いたセイバーの境地、ですか……)
ヘルヘイムは素直に感服しながらも、今は自分の果たすべき役割を果たそうと、改めて周囲に視線を向ける。すると、ここで彼女は少し離れた場所にある校舎の屋上に「人影」を発見する。
(あれは……?)
そこにいたのは、異界の軍服のような装束をまとった、眼鏡をかけた男であり、遠方にいる誰かに対して指示を出しているようにも見えるが、少なくとも、現時点でヘルヘイムの視界にいる天使や悪魔達は彼に対して特に何の反応も見せていない。おそらく、その存在にすら気付いていないようだった。
しかし、ヘルヘイムは直感的に、この男が「ただの投影体」ではないことを察する。かなり離れた場所にはいるが、明らかに通常の混沌核とは異なるレベルのオーラが漂っていることを感じ取った彼女は、あえてその身を衆目に晒すことを覚悟の上で、全力で叫んだ。
「ジーベンさま! あそこに、誰かいます!」
そう言って彼女が校舎の屋上を指差すと、その男はすぐさま姿を消す。ジーベンはその男の姿を確認することは出来なかったが、その消えた直後にその周囲に漂っている「強大な混沌の残滓」は、うっすらと感じ取っていた。彼は目の前の怪物との戦いを継続しつつ、ヘルヘイムに問いかける。
「どんな奴だった!? 若い女か!?」
この魔境の混沌核と目されている人造撃退士は、若い女性の姿をしていたという報告を聞いている。しかし、それはヘルヘイムの見た人物の特徴とは真逆であった。
「いえ、中年の男性です。髪はオールバックで、眼鏡をかけていて……」
彼女がその特徴を告げたところで、ジーベンは表情を一変させ、一瞬だけ動きが止まる。そんな彼の異変に、彼のすぐ後ろにいたセーラは気付いた。
「ジーベン?」
この時点で、セーラとジーベン以外の面々は既に図書館への突入を完了していた。その状況を確認した上で、ジーベンはヘルヘイムに向かって叫ぶ。
「今から、その男を探しに行く!」
「分かりました! お供します!」
ヘルヘイムがそう答えると、当然の如くセーラも声を上げる。
「じゃあ、セーラも……」
「お前は図書館に入れ。俺の分まで、お前のその剣で敵を倒せ。いいな」
「…………分かった!」
それが今の自分が果たすべき役割だと理解したセーラは、予定通りに仲間達を追って図書館の中へと突入する。一方、ヘルヘイムがジーベンの元へと駆け寄って来ると、ジーベンは怪物達を薙ぎ払うことで道を切り開き、そしてヘルヘイムと共に「眼鏡の男」がいた校舎の方面へと向かって走り出しつつ、天に向って聖印を掲げた。それは「突入完了」の合図であり、離れた場所にいた陽動部隊の面々の目にもはっきりと映る。
「よし! じゃあ、俺達の仕事は終わりだな。撤退だ!」
タウロスは三人の従騎士にそう告げつつ、最後に《万軍撃破の印》を放って周囲の投影体達を一掃する。その上で、更なる敵が出現する前に、四人は海岸に停泊した船へと全速力で向かうのであった。
******
一方、図書館へと突入した従騎士達は、慎重に奥へと歩を進めていく。そんな中、グレイスは傍らに立つアシーナに声をかけた。
「大丈夫か? アシーナ?」
「……大丈夫、と言いたいけど、やっぱり、『あの時』と同じように、少しずつ身体がおかしくなっているような……」
表情を歪めながら、アシーナはそう呟く。先日の潜入捜査の時に生徒会室に入った時と同様、今回もまた、図書館内に入った直後から、彼女は明らかに体調を崩していた。なお、彼女以外の面々に関しては、最後に入って来たセーラも含めて、誰も特に変調は起こしていない。
そんな彼女に対して、エイシスは《浄化の印》を用いて、彼女の身体を蝕む要因の除去を試みてみた。
「どうですか?」
「……あ、えーっと……、今、一瞬治った気がしたんですけど、そのすぐ後に、またもう一度、同じような何かが少しずつ入り込んで来ているみたいで……」
「なるほど。やはり、この図書館内の結界が影響しているのだとしたら、対症療法にしかならないようですね」
「はい……、でも、一度かけてもらえば、変調が身体全体に回るまでに時間はかかりますし、これでしばらくは戦えます」
アシーナがそう答えたところで、図書館の奥の方から、誰かが歩いて近付いて来る音が聞こえてくる。その足音自体は「人」のそれと変わらなかったが、それと同時に強大な混沌の気配が漂ってくるのも従騎士達は感じていた。
エイシスはすぐさま《聖地の印》と《地の利の印》をその場に発動させると、従騎士達は警戒態勢に入る。そして、やがて彼等の前に一人の「奇妙な装束の少女」が現れる。衣服と呼べる程の服はまとわず、身体の各所に謎の装置を植え付け、そして特殊な形状の剣を手にしたその少女の姿は、調査隊から聞いていた「人造撃退士の少女」の姿そのものであった。
|
+
|
人造撃退士 |

出典:『恋と冒険の学園TRPGエリュシオン』p.135
|
「コノ気配、人間ノ集団ト……」
その少女は無感情な声色でそう語りながら、アシーナに視線を向ける。
「……堕天使? 使徒?」
明らかに自分に対して告げられたその言葉に対して、アシーナは困惑する。「堕天使」とは、天使でありながら人間に手を貸すようになった者のことであり、「使徒」とは、天使によって身体を作り変えられた「元人間」を指す言葉である。
「な、なにを言っているのですか……?」
動揺する彼女に対して、人造撃退士はその瞳の奥に組み込まれた観察機能を用いて、アシーナの身体を調べ上げる。
「身体ノ構成要素ノ約50%ガ天使……、人間ト天使ノ混血児ノ可能性大。最優先排除対象」
人造撃退士はそう呟くと同時に、一瞬にしてアシーナの目の前へと移動し、彼女に対して斬りかかる。唐突に告げられた情報に当惑したアシーナは反応が遅れるが、すぐさま間にアルスが割って入った。
「くっ……」
アルスは盾でその攻撃を受け止めるが、盾越しに強烈な衝撃が彼女の身体を襲う。しかし、その直後に掲げられたエイシスの聖印の輝きによって、瞬時にアルスの身体の損傷は回復する。
「大丈夫ですか?」
「はい、ありがとうございます!」
エイシスに対して、アルスはそう答える。一方、人造撃退士の少女は、自分の立っている場所から発生している「謎の違和感」の存在に気付いた。
「未知ノ戦闘フィールドノ発生ヲ確認。コノ空間内デノ接近戦ハ不利ト判断。遠距離戦二移行。増援ヲ要請」
彼女はそう呟くと同時に、瞬時に先刻までいた場所(エイシスの《聖地の印》の範囲外)へと戻り、その武器を銃へと持ち替える。そして、後方から、彼女とよく似た姿の、銃を持った少女達が現れた。
「うわー、いっぱいいるねー」
「でも、あまり強力な混沌の気配は感じない。多分、性能はかなり劣ると思うよ」
ラオリスとヴァルタがそんな反応を見せる一方で、アシーナはまだ呆然とした様子で立ち尽くしていた。
「私が、天使との混血児……? あの、人間の感情を貪り喰らう、多くの人々にとって忌むべき存在である天使の血が、私の中に……?」
信じられない様子のアシーナであったが、確かにアシーナは両親のことは何も知らない。そして、天魔に対する結界によってアシーナだけが体調を崩していることについても、それが真実ならば辻褄は合う。
「アシーナ!」
グレイスのその声で、アシーナはハッと我に返る。
「敵の声に惑わされるな! 彼女が君の何を知っている?」
そう訴えかけるグレイスの横で、ファニルもまた声を掛ける。
「自分に誰の血が流れてるとか、どうでも良くねえか?」
異形の尾を床に叩きつけながらファニルがそう呟いた後、エイシスもまた声を掛ける。
「あなたが何者であろうと、聖印を預かる者として、やるべきことは一つです。そうでしょう?」
エイシスがそう言い終えた直後、人造撃退士達はアシーナに対して一斉に銃口を向ける。そしてアシーナは、自分に対する明確な「敵意」の存在を目の当たりにして、ここが「戦場」であることを改めて思い出した。
(そうです、私は、この魔境を浄化するためにここに来た。そのために、ここまで準備を重ねてきたのです。まずは、その使命を果たすことに専念しましょう。それ以外のことについては、今は考えるべき時ではない……)
アシーナは自分にそう言い聞かせつつ、全神経を集中して敵の銃口の角度から銃弾の軌道を予想する。
「射程範囲内ノ貴重書不在ヲ確認。斉射!」
指揮官と思しき(最初にいた)人造撃退士のその声に合わせて、彼女達は一斉に引き金を引くが、アシーナはその一瞬前にその弾丸の軌道の外へと跳び跳ね、全弾の回避に成功する。
だが、その結果として、銃弾は流れ弾となって他の従騎士達へと向かうことになった。ラオリスだけは持ち前の反射神経でそれをかわすことに成功し、そしてアルスは咄嗟に手近にいた(最も軽装の従騎士の一人である)ルイスを《庇護の印》で庇うが、他の者達は軒並み被弾してしまう。即座にエイシスが聖印の力を駆使して皆の傷を癒そうとするが、革鎧すら着ていなかったセーラとヴァルタは傷が深く、エイシスの回復力だけでは間に合いそうにない。
「いたたたた……」
セーラが痛みでうずくまっていると、リューヌはすぐさま駆け寄りつつ、ポシェットから手当道具を取り出す。
「大丈夫……、ではなさそうですね。お待ちください。すぐに治療いたします」
彼女はそう呟きつつ、間近でセーラの様態を確認すると、その傷の深さから、ここは《救難の印》を使うべきときだと考え、聖印を掲げる。
「ありがとう……、でも、おねーさんも、きずを……」
セーラはリューヌの革鎧にも血が内側から滲み出ていることに気付く。
「私の傷口は、先程のエイシス様の聖印の御力によって、もう塞がっています。ですから、ご心配ならさず、貴方はどうかそのまま戦闘を続けてくださいませ!!」
彼女がそう言い切ると、セーラの傷もまた(《聖地の印》の効果で回復力そのものが大きく向上していることもあり)見る見るうちに完治していく。
「救護が私の戦場ですわ。皆様は私が支援いたしますわ!」
リューヌがそう宣言する傍らでは、アリアがヴァルタに駆け寄り、治療道具を用いて手当を施していた。ヴァルタ自身もメサイアの力に覚醒してはいるが、まだ《救難の印》を使える段階にまでは達しておらず、ヴァルタの聖印による治療よりも、医療知識に長けたアリアの応急手当の方が回復が早い。彼女はすぐさま薬と包帯を取り出して、ヴァルタの傷口を塞いでいく。
「ヴァル、大丈夫?」
ラオリスが心配そうに見つめるが、そんな彼女に対してアリアは言い放つ。
「お前はこちらを見ている暇があったら、前を向いて戦いに専念しなさい!」
それに続けてヴァルタも答える。
「心配ないよ、姉さん。アリアさんの薬のおかげで、すぐに痛みは収まったし」
「エイシス様の結界の中にいるのだから、当然だわ。お前達は気にせず、敵の殲滅のことだけ考えていれば良いのです」
救護班の二人がそんな気概を見せながら治療に専念している一方で、アシーナは改めて「今の自分がやるべきこと」を考える。
(彼女達は明らかに私を狙っている以上、私がここにいると皆を巻き込んでしまう。だったら……)
アシーナは意を決して、エイシス達の元から駆け出し、彼の《聖地の印》の効果が及ぶギリギリの場所まですると、案の定、第二射の準備を整えていた人造撃退士達の銃口は、再び彼女へと向けられる。
「あなた達の攻撃は、もう見切りました!」
アシーナはそう叫ぶと、実際に彼女に向かって放たれた二度目の一斉射撃を難なく避けきることに成功する。
(敵が私一人を狙ってくれるなら、それはそれで好都合です。皆を信じて、私は囮に専念しましょう。どうにもならなくなったら、最後は気合です。「全てに準備して、それでもどうしようもなかったら最後は気合で立っていればいいのです」)
かつて共に旅した隊長の言葉を思い出しながらアシーナがそんな決意を固めている一方で、ファニルもまた「自分の果たすべき役割」に気付いていた。
(ここでやらなきゃ、いつやるってんだよ!)
彼女は、人造撃退士達が一箇所に集まっているこの状況で、あえて一人で彼女達の元へと駆け込んでいく。その意を察したエイシスは、すぐに彼女の駆け込んだ先にも《聖地の印》と《地の利の印》を施すと、ファニルは大剣を大きく振りかざした。
「全員、吹き飛べ!」
そう叫ぶと同時に、ファニルは《暴風の印》を発動する。周囲の本棚に並んでいた書物をも吹き飛ばす勢いで放たれたその衝撃波によって、人造撃退士達の大半は半壊状態・機能停止状態へと追い込まれるが、「魔境の混沌核」と思しき指揮官の少女だけは、その一撃を受けてもまだ平然とした表情を浮かべながら、即座に武器を再び剣へと持ち替えて、ファニルの身体を真正面から突き刺す。
「ぐはっ……」
その一撃でファニルは瀕死の重症を負い、その場に倒れそうになるが、すぐさま後方からリューヌが《救難の印》を放つことで一命を取り留め、その直後に駆け込んだアルスが盾を掲げて人造撃退士の前に立ちはだかると、人造撃退士は再び武器を銃へと持ち替えた上で、《聖地の印》の外側へと即座に移動する。そして、一歩遅れて駆け込んだアリアが、ファニルの治療を始めた。
「とりあえず、雑魚は片付けた。あとはたの……」
「黙りなさい! 少しでも動くと、傷口が開くわ!」
アリアが叱責しながら治療を続ける傍らで、傷が癒えたセーラとヴァルタはラオリスと共に人造撃退士に向かって斬りかかろうとするが、人造撃退士は図書館内を縦横無尽に駆け巡りながら従騎士達を翻弄し、彼等との距離を保ち続ける。
「あー、もう、はやすぎるよー」
俊敏さには自身のあるセーラでも、彼女の動きにはついていけない。それはヴァルタやラオリスも同様であった。
「接近戦に持ち込めば、手数の差で有利に戦えそうなんだけど……」
「そもそも、本棚が邪魔だよ! なんでこんなにあるの!? いらなくない!?」
実際、人造撃退士はこの大量の本棚を遮蔽物として上手く利用しながら立ち回っている。そのため、遠方から弓で射掛けようと試みていたグレイスもまた、狙いを絞りきれずにいた。
「せめて、牽制や誘導だけでも出来ればと思っていたのですが、この戦場ではそれすらもままなりませんね……」
現状、アシーナもまた全力で人造撃退士の攻撃を避け続けているため、硬直状態が続いている。グレイスとしては、恋人が囮となっている状況を一刻も早く終わらせたかったのだが、どうにも突破口を見つけられずにいた。
そんな中、ルイスは先刻の人造撃退士の発言が気にかかっていた。
「彼女は銃を打つ前に『射程内ノ貴重書不在ヲ確認』と言っていた。ということは、射程内に貴重な書物がある場合は、銃は使えないのかも……」
彼女達を生み出したのが学園内の科学者集団であることを考えれば、図書館内の貴重な文献を傷つけることを禁じられている可能性は十分にある。だとすれば、「背後に貴重書がある状態」であれば、彼女達は(流れ弾で本が破損する可能性がある以上)銃は使えないのかもしれない。
(本を盾にするなんて、もしこの場にシャルがいたら怒られるかもしれないけど、でも、ここは図書館であると同時に「戦場」でもあるからね……)
遠く離れたエーラムで研鑽を積む妹のことを思い出しつつ、ルイスは周囲を見渡すと、壁際の一角に「地下」へと続く階段が存在することに気付く。
(この間取りの図書館なら、多分、貴重書は地下に所蔵されている可能性が高い……?)
ルイスはそう判断した上で、エイシスに問いかける。
「《聖地の印》と《地の利の印》は、まだ増やせますか?」
「はい。あと数ヶ所程度なら、問題なく」
エイシスがそう答えると、ルイスは自身の考えを伝える。それに対してエイシスは頷きつつ、従騎士達に対して告げた。
「皆さん! 今、動ける人は、地下に来て下さい!」
彼がそう叫ぶと、まだ傷が癒えていないファニルと彼女を治療中のアリアとリューヌ以外の面々が、エイシスに従って下り階段へと向かっていく。その動きに対して、人造撃退士は文字通りに「目の色」を変えた。
「貴重書強奪ノ可能性アリ、全力デ阻止」
彼女はそう呟きつつ、すぐさま従騎士達を追って地下へと向かっていくのであった。
******
地下の書庫へと到達したエイシスは、聖印で周囲を照らしつつ、特に重要そうな書物が収められていそうな区画を間取りから推測しつつ、その一帯に対して《聖地の印》と《地の利の印》を発動する。そして、アシーナを含めた全員がその結界内へと入り込むと、追いかけてきた人造撃退士は、銃を剣へと持ち替えた上で、改めてアシーナへと接敵しようとする。
(やっぱり、ここでは銃は使えないんだな)
ルイスがそう判断すると同時に、人造撃退士の前にアルスが立ちはだかる。
「あなたの剣の動きは、もう見切っています!」
そう叫びながら、人造撃退士の剣を再び盾で受け止めるアルスであったが、ここで人造撃退士は阿修羅の如き形相を浮かべながら、その剣圧を増していく。
「出力限定解除、《鬼神一閃》!」
彼女がそう言い終えると同時に、その剣圧でアルスの巨大な盾が弾き飛ばされる。
「そんな……!?」
驚愕の表情を浮かべるアルスであったが、その直後に今度はヴァルタが現れて人造撃退士に斬りかかる。
(それだけ大振りの攻撃の後なら、すぐに守備体制には入れない筈……)
そう判断しながら振り下ろしたヴァルタの長剣は確かに彼女の露出した肩口に命中するが、見た目には生身であるにもかかわらず、ヴァルタの刃はその血管にすら届かない。しかし、ヴァルタの中ではこれも想定内であった。
(やっぱり、鎧を着てないってことは、そういうことだよね。でも……)
彼はすぐさま横にその身をスライドさせ、その直後に後方からラオリスが追撃を掛ける。
(セイバーとしての力に目覚めた今、剣士としての力は姉さんの方が上。こっちが本命だよ)
彼のそんな思惑通りに、ラオリスの剣が「ヴァルタの剣が生み出した僅かな傷口」に対して突き立てられると、ようやく人造撃退士の身体から、かすかに不気味な色の血液が滴り始める。更にそれに続けて、セーラが天井ギリギリの高さまで跳び上がりながら、人造撃退士の頭上へと大剣を叩きつけようとする。
「さっきの、おかえし!」
セーラのその一撃を、人造撃退士は剣で受け止める。だが、そこで生じた隙を狙って、ヴァルタとラオリスの連携攻撃が繰り出され、今度は彼女の脇腹に軽症を負わせることに成功する。
「いいカンジ! このまま行くよ、ヴァル!」
「うん、姉さん!」
こうして前衛部隊による奮戦が繰り広げられる中、グレイスは遠方から改めて人造撃退士の動きを観察しつつ、効果的な一撃を打ち込む算段を立てる。ジーベンもタウロスもいないこの戦場において、《光弾の印》を発動可能なグレイスは、戦局を打開する切り札となりうる存在であるという自覚はあった。
(一撃で射抜くなら、弱点を狙うしかない……)
従騎士達の攻撃に対する彼女の反応を見る限り、胴体を狙っているラオリスとヴァルタよりも、空中から頭部を攻撃してくるセーラに対して、より敏感に反応しているように見える。
(おそらく、あの頭部のクリスタルが弱点。しかし、それが遠方からも狙われていると分かれば、より防備は固くなる。確実に一撃で仕留めないと……)
彼が弓を構えつつ、そのタイミングを見計らっているところで、ラオリスとヴァルタの動きに変化が生じる。ここまで、ヴァルタが先導、ラオリスが追撃、というコンビネーションで連撃を繰り返していたが、敵がその動きに順応してきたのを察知した二人は(特に何のコンタクトも取らないまま)阿吽の呼吸で立ち位置を入れ替え、ラオリスが先導役へと切り替わったのである。
この想定外の動きに対し、人造撃退士の対応は乱れ、そしてこれまで彼女達の攻撃を受け続けたことで蓄積した損傷の影響も出たのか、これまで微動だにしなかったその身体のバランスが一瞬崩れる。その瞬間、セーラが大剣を薙ぎ払う形で彼女の首を狙いに行く。
「もらったよ!」
だが、そんなセーラの大剣が届くよりも一歩早く、追い詰められた人造撃退士は「切り札」を発動しようとする。
「アウル発動、クイック……」
しかし、人造撃退士がそこまで言いかけたところで、既に丸腰となっていたアルスが二人の間に生身のまま立ちはだかる。アルスは人造撃退士の剣で身体を貫かれるが、彼女はそのまま人造撃退士を羽交い締めにした。
「!?」
突然の行動で人造撃退士が困惑する中、その動きが封じられたことを確認したグレイスが、渾身の力を込めた《光弾の印》を放つ。
「アシーナを、そして皆を苦しめた罪、その身で贖え!」
彼の放った矢は狙い通りに人造撃退士の頭部のクリスタルを撃ち抜き、その直後、彼女は機能を停止する。
「お見事です!」
アルスは振り向きざまに笑顔でグレイスにそう告げつつ、その場に倒れそうになるが、すぐさまエイシスが放った《救難の印》によって、どうにか体勢を崩さずに踏み留まる。
そして、動かなくなった人造撃退士に対して、アシーナはボソリと呟いた。
「あなたは最後まで、使命をまっとうしたのですよね。でも、もうこれで終わりです。静かにお眠り下さい」
彼女が語った「自分の正体」が真実なのかどうか、アシーナには確かめる術はない。ただ、自分自身が「この世界」と深く関わりを持つ者であることは間違いない、ということを改めて自覚したアシーナは、周囲を見渡しながら声を掛ける。
「グレイス、そして皆さん、ありがとうございました」
彼女がそう言いながら深々と頭を下げると、グレイスが静かに彼女の元へと向かい、そっとその身を抱き締める。
だが、その直後、グレイスは自身の聖印に「異変」が発生したことに気付いた。
「提督……!?」
「どうしたの、グレイス?」
怪訝そうな上目遣いで見上げるアシーナに対し、グレイスは青ざめた表情で答える。
「……カエラ提督との聖印の繋がりが、切れた」
その言葉に対して、その場にいる者達が絶句する。そして、しばしの沈黙の後、階段を駆け下りて来る者が現れた。
「今、私とレオノール様の従属関係が、断ち切られました!」
そう言って、リューヌが皆の前に姿を現す。その後方には、アリアと、そして(二人の治療によって体調を回復した)ファニルの姿もある。
突然のその二人の申告に対し、皆が動揺する中、エイシスは冷静に状況を分析する。
「あの二人は、カルタキアで結婚式場の建設に協力していた筈です。おそらく、カルタキアで何か起きている可能性が高い。ここは、一刻も早くこの魔境を混沌を浄化して、帰還することにしましょう」
エイシスはそう言いながら、自身の聖印を掲げ、混沌核の吸収を始めるのであった。
******
ここで、少し時を遡る。校舎の屋上に現れた「謎の男」を追走していたジーベンとヘルヘイムは、その近辺の建物の混沌の気配を探っていくうちに、やがて「購買部」の近くまで来たところで、複数の投影体の気配を感じ取る。
「ジーベンさま、この気配……」
「『人間』だな。それも、それなりの数だ」
この「久遠ヶ原学園」には、元の世界の人間は投影されていない筈である。しかし、購買部には生徒会室や図書館と同様に「結界」が存在する以上、その中にいる者は天使や悪魔ではありえない。元の世界の人間が密かに潜んでいたのか、あるいは、遅れて投影されたのか。
様々な可能性が考えられる中、二人は購買部に向けて慎重に歩を進める。すると、建物の内側から、男性の声が聞こえてきた。
「撃て!」
その声に応じて、購買部の窓ガラスを突き破る形で無数の銃弾がジーベンに向かって放たれるが、ジーベンはその攻撃を察知してすぐさま後方に退避したことで、直撃を免れる。そして、その直後に購買部から一人の男が姿を現した。それは間違いなく、ヘルヘイムが先刻、校舎の屋上で発見した人物であった。
「あの男です!」
ヘルヘイムがそう叫ぶと、ジーベンは落ち着いた口調でその男に問いかける。
「何者だ? この学園の人間か?」
それに対して、男は薄ら笑いを浮かべながら答える。
「残念ながら、ハズレだ。もっとも、状況次第では、この学園を『私のモノ』にしてしまっても良かったのだがね。優秀な若者が投影されているなら、我がカスガー・ユーゲントの一員に迎え入れるつもりで潜伏していたのだが、残念ながら、ここには学生は一人も存在しないようだ」
「カスガー・ユーゲント?」
ジーベンが怪訝な顔を浮かべていると、購買部の中から、ライフル銃を持った軍服姿の男達が次々と姿を現す。
「ハイル、カスガー!」
「ハイル、カスガー!」
彼等が右手を掲げながら次々とそう叫ぶ中、その男は語り続ける。
「我が名は、総統カスガー。ディアブロ帝国の最高指導者にして、いずれ『他の世界の私達』と共に、この世界を統べることにな……」
彼がそこまで口にしたところで、突然、彼等の「足場」が消滅する。エイシスの手によって、魔境の混沌核が破壊されたのである。総統カスガーも、彼の配下の兵士達も、ジーベンも、ヘルヘイムも、突然のその出来事に気付いた時には、海の中にその身が投げ出されていたのであった。
******
一方、その間にタウロス、ポレット、シオン、ルーカスの四人は、無事に海岸に停泊していた海賊船「グランシャリオ」まで帰り着いていたのだが、グレイスやリューヌの聖印に異変が起きたのと同じタイミングで、ポレットの聖印にもまた、同様の変化が発生する。
「そんな……、どうして私の聖印が急に……、一体、総帥様の身に何が……?」
唐突に独立聖印化した自身の聖印を目の当たりにしてポレットが困惑する中、やがて魔境が浄化されていくのをタウロス達は確認する。
「とりあえず、今は彼等との合流が先決だ。小型艇で救助に向かうぞ!」
タウロスがそう告げると、彼等はそれぞれに「平穏化」した海へと繰り出す。すると、すぐに彼等は会場に浮かぶ「エイシスの聖印」を発見し、現地へと急行した上で、彼等を次々と小型艇で救い上げる。そして、やがてそこにジーベンとヘルヘイムもまた(二人共、もともと身体能力に優れていたこともあり)自力で泳いで彼等の元へと合流することに成功した。
だが、そんな中、やがて彼等は海中から、謎の巨大な投影体の気配を感じ取る。それは、幾人かの従騎士達にとっては、微妙に既視感のある気配であった。
(あの時の「飛空船」のオーラと似ている……?)
それは確かに「巨大な乗騎」の気配であった。彼等がその正体を見極められずにいる中、やがてその「乗騎」はゆっくりと海面に姿を現す。それは一隻の巨大な潜水艦であった。その上部の搭乗口が開くと、そこから(海水で髪型が乱れた状態の)総統カスガーが姿を現す。
「問答の途中でいきなり魔境を破壊するとは、やはりこの世界の君主達は野蛮な者達揃いだな。だが、こんなこともあろうかと、学園内のプールにこの『強襲潜水艦エーギル』を忍ばせておいたのだ。私の計画に抜かりはない」
その潜水艦の名は、一部の従騎士達にとっては聞き覚えのある呼称だったが、そんなことを知る由もない総統カスガーはそのまま語り続ける。
「さて、カルタキアの君主諸君、この私から寛大なる忠告を伝えてやろう。まもなく君達の街は、我が軍が手に入れた超兵器“雷霆”によって、灰燼に帰す。命が惜しければ、72時間以内に白旗を掲げることだ。そうすれば、我がディアブロ帝国の一員として迎え入れてやろう」
従騎士達の大半が、彼の言っていることの意味が理解出来ないまま呆然と見つめる中、彼は艦内へと戻り、そして潜水艦は北方へと向かって出航していく。
そして、この時点でエイシスが遠眼鏡を用いて確認してみたところ、その先には「明らかに異世界の島」と思しき何かが投影されていることが分かった。
「どうやら、彼等は『久遠ヶ原学園』とはまた別の世界から出現した魔境の住人のようですね」
エイシスはそう呟きつつ、周囲を見渡しながら、思案を巡らせる。
(ジーベン師団長とタウロス隊長には、まだまだ余力がある。一方で、既に従騎士達の大半は力を使い果たして満身創痍。そして、カルタキアでも何か異変が起きていることも間違いない。おそらく、「北方に出現している魔境」もそれと連動している可能性が高いと考えられる……)
そこまで考えた上で、エイシスは決断を下した。
「従騎士の皆さんは、このままグランシャリオでカルタキアに戻って下さい。私とジーベン師団長とタウロス隊長の三人は、小型艇であの潜水艦を追跡します。おそらく、いずれ『天空の魔境』から領主様達が戻られるでしょうから、そちらと合流した上で、余力があれば援軍を送って下さい」
三人だけで未知の境に突入するのは危険ではあるが、もし先刻の総統カスガーの発言がハッタリではないとしたら、早急に状況を確認する必要がある。とはいえ、今の疲弊した従騎士達がついて行っても足手まといにしかならないし、カルタキアで何が起きているかも分からない以上、ひとまず今はそちらの調査の方に彼等を向かわせるべき、というのがエイシスの判断であった。
従騎士達の中にはこの決定を不服に思う者もいたかもしれないが、今はエイシスか総司令官である以上、彼の方針に従うしかない。ひとまず指揮官三人が小型艇「メグレス」で北へと向かうのを見送りつつ、他の者達はカルタキアへと帰還することになった。
だが、その帰路の途上で、今度はアシーナ、ルーカス、ルイス、アルス、シオンの五人の聖印が「独立聖印化」してしまう。それはすなわち、『天空の魔境』へと向かった三人の指揮官の身にも「何か」が起きていることを示していた。
更なる動揺が広がる中、街に戻った彼等が調査を開始したところで、今度は残りの面々の聖印もまた、それぞれの指揮官との「従属関係」が断ち切られてしまう。全くの想定外の出来事に従騎士達が絶望に苛まれようとする中、彼等の前に一人の人物が現れ、衝撃的な真実を告げることになるのであった(
FR
に続く)。
☆合計達成値:280(17[加算分]+263[今回分])/100
→成長カウント1上昇、次回の最終クエスト(FD)の達成値に90点加算
最終更新:2022年06月04日 23:38