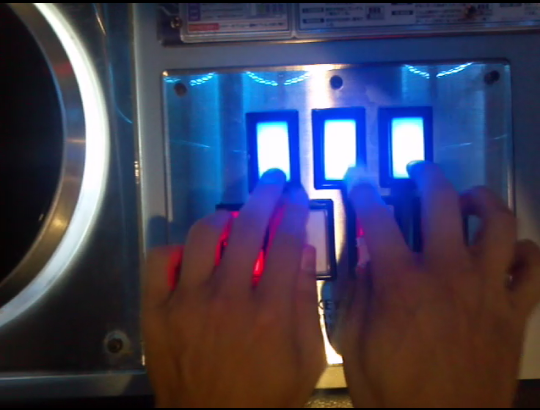目次
指の配置
1P側
| ◯ |
|
L3 |
(L2) R2 |
R3 |
|
| L4 |
L1 |
R1 |
R4 |
2P側の方は反転して考えてください。
L3とか
R2とはなんぞ?という方は→
画像
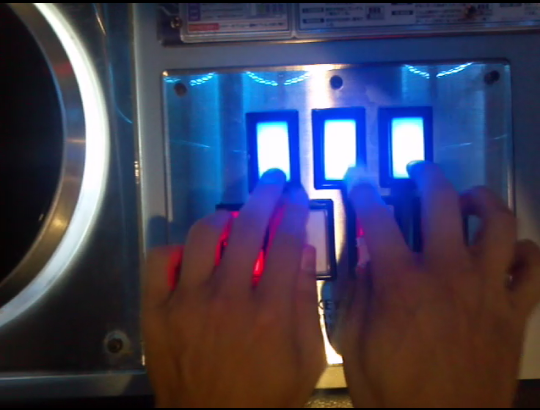
対称固定という名前は、4鍵を軸にして線対称な手になることから付けられたと思われます。
一つの鍵盤に一つの指が対応しているため、鍵盤のみが降って来ている場合はその対応でのみ打鍵します。つまり、上の図のように必ず、
1鍵→
L4, 2鍵→
L3, 3鍵→
L1,
4鍵→
R2, 5鍵→
R1, 6鍵→
R3, 7鍵→
R4
で叩きます。
ただし、対称固定は皿に指が届かないので、皿が降ってきたときは
3:5半固定やベチャ押しなどに移行します。つまり、
皿が降って来た時のために、3:5半固定も並行して習得していかなくてはなりません。
長所
- 比較的指の形が自然であるため、手に変な力が入らず、感覚的にも分かりやすい。力を抜いて手を鍵盤に置いてみると、5鍵の親指以外は勝手に乗ります。
- 鍵盤に集中している運指であり、使える指の数が8本と多く、結果4鍵をどちらの手でも取れるなど、融通が利く。といっても大半の4鍵は右手人差し指で取ります。
- べちゃ押しに移行しやすい。3:5半固定に移行する際は、2・3鍵と皿が絡む譜面に対応しやすい。
短所
- L4が1鍵に拘束されるので左手が皿から遠い。だから皿が来たときのために3:5半固定は必修。
やはりこれが最大の弱点です。皿まで遠いということは、
3:5半固定に移行するのも、そこから対称固定に戻るのも大変で、精度の高い切り替えが求められます。さらに、使う頻度が高い
押し皿から対称固定に戻るのが大変です。
- 12鍵トリルが取りにくい。67トリルも取りにくいのはほとんどの運指で同じですが、12トリルは他の運指より苦手としています。
12鍵
トリルは、指に余裕があれば3:5半固定で対処すると良いです。
もう少し詳細な非皿側の手の話
対称固定の両手がかたどるこの手の形、1048式やドルチェ式でも右手は同じ形になるのですが、この形には、二つのタイプがあるようです。上から見たとき、
- タイプA
- 親指の第一関節が、人差し指の付け根の下にある。
- タイプB
- 親指の第一関節が、人差し指の付け根の横にある。
タイプA、タイプBという呼び方は適当に決めました。ここだけの呼び名です。
タイプAは、1P対称固定の右手に適しています。理由は、4鍵を取っているときに5鍵がとりやすいからです。
タイプBは、1P対称固定の左手に適しています。理由は、左手はあまり4鍵をとる必要が無いこと、そして、人差し指を左に寄せて2鍵の近くに浮かせておくことで、3:5半固定に移行しやすくなるためです。
このような感じで私は、左手はタイプB、右手はタイプAを推奨します。
|
+
|
←クリック!画像が畳んであります |


|
こうしてしまうと、もはや対称ではありませんね。
ところで、このままだと左手人差し指での4鍵補助は、左手が相当暇なときしかできません。私はそれで良いと思いますが、それがいやならば逆サイドでプレイするなりして左手でタイプBが出来るように練習しましょう。
タイプBからタイプAへの矯正方法
非皿側の手はタイプAにした方が良いのですが、今までの練習でタイプBに慣れてしまったため、タイプAに矯正してみようという方がいらっしゃると思います。
その矯正の参考になるように、タイプAの理想の形を詳しく書いていきます。
- 手の平が真下を向いていて、手の平から鍵盤まで5cmくらいの隙間がある。
- 手に卵を握るような感じの空間が手のひらにある。
- 手のひらが内側(4鍵がある方)を向いて、中指薬指が窮屈になったり、人差し指が4鍵に届かなくてピンと伸びてしまうのはダメ
- 手のひらが下がっているのはダメ(手が潰れてしまってはダメ)。
- 親指の指先が人差し指と中指の間から見えているような位置で、親指の外側(爪の横)(腹ではない)で鍵盤を打つ。
- 鍵盤を押す時、親指の第一関節はほとんど曲げ伸ばしをしない。曲げっぱなしか伸ばしっぱなしにする。(?怪しい)
- 人差し指、中指、薬指は、指先が鍵盤に対して上から垂直近い角度になるように、指先で上から押す。
- 人差し指がピンと伸びて、人差し指の腹で4鍵盤を押すのはダメ。
要するに、親指は手の平の下に無いといけなくて、そのためには手のひらの下にスペースが必要ということです。
タイプBからタイプAへの矯正するときに使える方法として、5cmくらいの物体を5鍵と7鍵の間に立てて手首に当たるようにして、つっかえ棒として置いておくというものがあります。
最終更新:2018年11月22日 02:04