日本 ウィキ
スーパーファミコン
最終更新:
asaahingaeaw
-
view
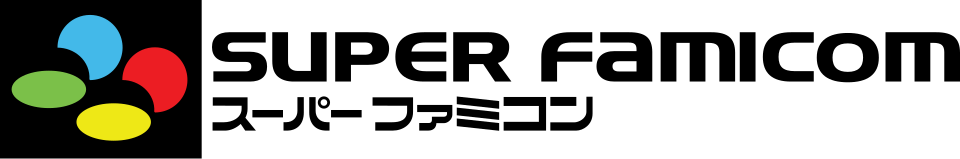

スーパーファミコンとはファミリーコンピュータの後継機として開発された。同世代機の中では後発であったが、ファミリーコンピュータに引き続き、最多出荷台数を記録した。製造年は1990年。日本発売は同年11月21日。生産終了は2003年9月。
性能
| 製造年 | 1990年 |
| 発売価格(当時) | 25,000円 |
| UPU | 16-bit 65C816 Ricoh 5A22 3.58MHz |
| 画質 | 16 bit |
| 音質 | モノラル 16 bit |
| 外部接続 | 28ピン拡張コネクタ |
| 売上台数 | 4910万台 |
| 前任機 | ファミリーコンピュータ |
| 後継機 | Nintendo 64 |
概要
開発当初は、当時最大の市場シェアを持っていたファミリーコンピュータとの互換性を維持するため、接続コードで繋ぐことによって映像音声出力およびコントローラを共通化した外部入力装置「ファミコンアダプタ」の使用が提示されていた。最終的には互換性の維持を断念し、新規プラットフォームとして発売された。ハードウェアのスペックとしては、16ビットCPU 、32,768色(15bpp)から選択可能な16色のカラーパレットと、それらのカラーを適用可能な16色スプライト、一画面あたり最大128個のスプライト同時表示、背景の多重スクロールと回転・拡大・縮小表示機能、ソニーのDSPによるPCM音源の採用など、カタログスペックとしては同時代の一線級のものを取り揃えている。これによりファミリーコンピュータと比べ、表示や音源の処理能力が格段に向上した。CPUクロック周波数は、3.58MHzと低めに設定されたため、演算速度は競合機に比べ高速ではなかった。また、音の品質にメモリ容量が大きく関わるPCMを音源としながら、その音源用DSPに用意されたバッファは64KBであり、他のゲーム機で多く使われたFM音源や、波形メモリ音源、PSGなどと異なる活用ノウハウを求められた。これによって多彩な表現を可能にしたが、特定の音色のみの品質が高くなったり、不自然な鳴り方になるなど、高品質な再生までには時間を要した。カセット差し込み口シャッターは、ファミリーコンピュータ時代の手動式からスプリングによる自動開閉式に変更された。カセットを差し込む動きでシャッター部分が本体内部側へと倒れ、抜き出すと元に戻る。また電源スイッチを入れるとカセット差込口内部にツメが出る機構が備えられており、カセット前面下部のくぼみを引っかけロックされる。これによって電源スイッチを入れたままカセットを抜き差しすることはできなくなった。イジェクトレバーはボタン式に変更された。通電時には電源ランプが点灯する。
ソフトウェア
スーパーファミコンはファミコンより期待値が上がり、当時の少年達は欲しがった。特に16 bitは当時8 bitであったファミコンを大きく上回る存在であった。スーパーファミコンのソフトウェアはファミコンよりも多く、スーパーマリオワールド(売上本数2061万本)、ゼルダの伝説 神々のトライフォース(売上本数461万本)、ファイアーエムブレム紋章の謎(売上本数77万6338万本)、続く次作のファイアーエムブレム聖戦の系譜(売上本数49万8216本)、エニックスのドラゴンクエスト3(売上本数390万本)、スクウェアのファイナルファンタジーIV(売上本数約144万本)、ロマンシング サ・ガ(売上本数132万本)、スーパーマリオカート(売上本数876万本)、真・女神転生(売上本数不明)、三國志III SFC移植版(売上本数不明)などここから皆がよく知るソフトウェアが揃ってきてこれらからスーパーファミコンはかなり売れたと推察される。
