翠浪臨海鉄道(すいのなみりんかいてつどう、英:Suinonami Rinkai Railway Co.,ltd.)は、
海内府翠浪市において貨物および旅客鉄道事業を行っている鉄道事業者。
あざみない鉄道・
海内府・翠浪市などが出資する第三セクター鉄道(臨海鉄道)の1つである。
| 翠浪臨海鉄道株式会社 |
| Suinonami Rinkai Railway Co.,ltd. |
| 種類 |
株式会社 |
| 略称 |
すいりん |
| 本社所在地 |
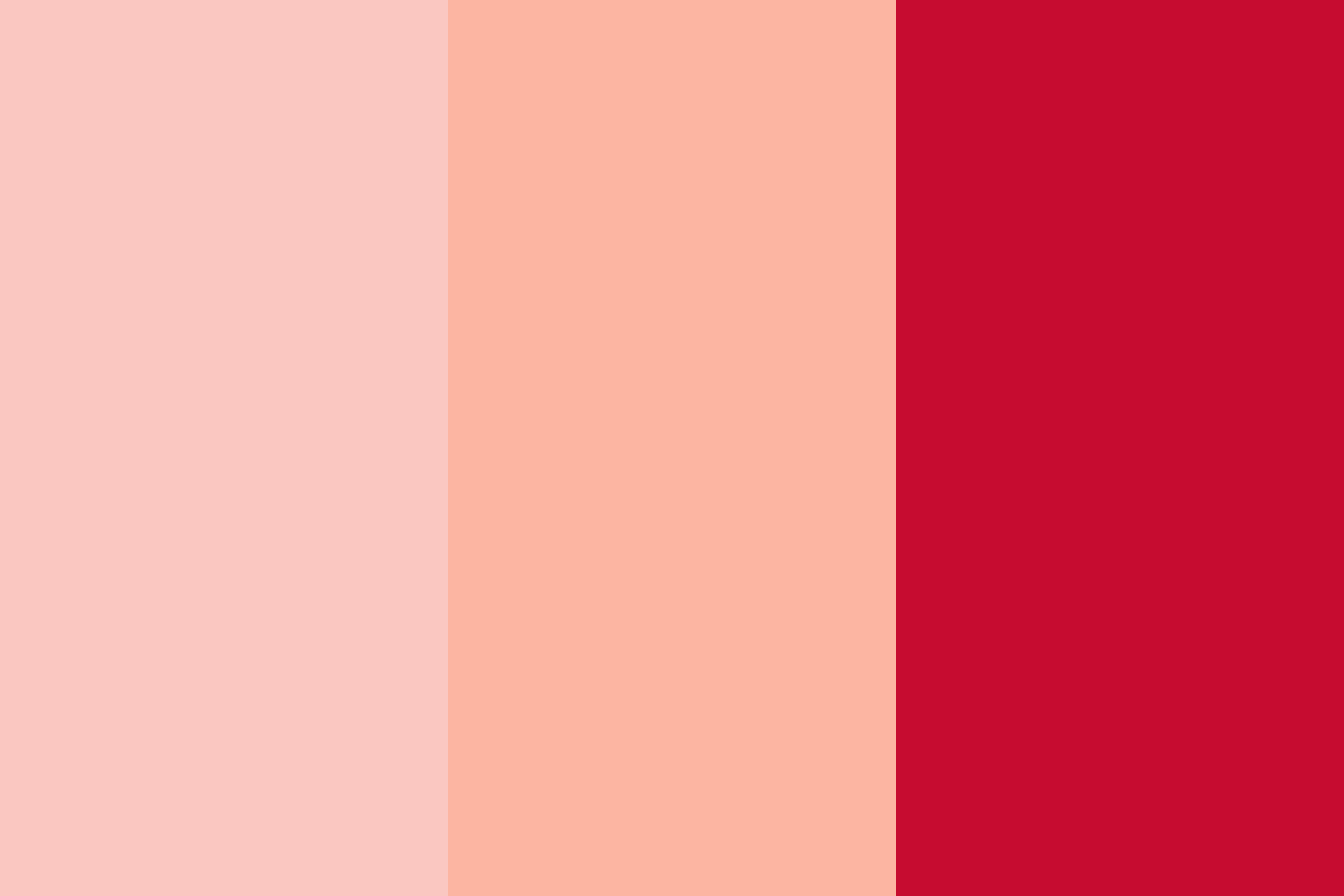 七浜
海内府翠浪市
七浜
海内府翠浪市 |
| 設立 |
1963年8月1日 |
| 業種 |
陸運業 |
| 事業内容 |
鉄道事業
倉庫事業
不動産事業
あざみない鉄道に係る業務の受託 |
| 代表者 |
代表取締役社長 鮫宮 末継 |
| 株主・出資比率 |
あざみない鉄道48.95%
翠浪市40.5%
海内府5%
あざみない通運1.23%
あざみない石油1.1%
翠浪化学1.02%
翠浪倉庫0.8%
あざみないセメント0.6%
あざみない製粉0.35%
あざみない製紙0.25%
あざみない食品0.2% |
概要
|
+
|
... |
あざみない鉄道・ 海内府・ 翠浪市などが出資する第三セクター方式の臨海鉄道である。設立は1963年であるが、前身は1911年に開業した翠浪馬車軌道であり、改軌し翠浪臨港鉄道となった同社は1922年に翠浪市が買収し、翠浪市営鉄道となっていた。これを1963年に第三セクター方式の臨海鉄道としたのが翠浪臨海鉄道である。
|
歴史
|
+
|
... |
※なお、翠浪市発足~2024年までは翠浪の字体は翠飲浪であったが、分かりやすさのためこの欄においては翠浪に統一する。
翠浪臨海鉄道は 翠浪鉄道(あざみない鉄道の前身企業の1つ)の翠浪駅と翠浪港間の貨物輸送のために1911年に開業した翠浪馬車軌道が前身であり、同軌道は1920年には工業地帯化した翠浪港関連の貨物輸送量の増加で動力を馬から蒸気機関車に変え、1067mm軌間に改軌・ 翠浪鉄道と貨車の直通運転を開始し、翠浪臨港鉄道と社名を変更した。
一方、同鉄道は貨物輸送の片手間に旅客列車も運転しており、翠浪市内の貴重な交通機関の1つであったため、日本など近隣国の主要都市で市営の路面電車の開業や既存の路面電車の市営化が始まると、翠浪市では市電の建設要望だけでなく、貨物優先により旅客列車の本数が少なく、運賃が高い臨港鉄道の市営化の要望が出るようになった。そのため、翠浪市は市電の建設を進めるとともに翠浪臨港鉄道を市営化し、市自ら運営することとし、1922年、翠浪市が翠浪臨港鉄道を買収・市営化し、翠浪市営鉄道が誕生した。
その後は翠浪市交通局により運営されていたが、第二次世界大戦後、七浜国でも1960年頃からエネルギー革命が起こり、石油化学産業が発達し、翠浪港にコンビナートが建設されると、貨物輸送の増強のため、翠浪市営鉄道は 翠浪鉄道(当時)・翠浪市・ 海内県(当時)・利用企業の出資による第三セクター方式の臨海鉄道とすることになった。こうして1963年8月1日、 翠浪鉄道(当時)・翠浪市・ 海内県(当時)・利用企業の出資により翠浪臨海鉄道が設立され、10月1日に翠浪市交通局から翠浪臨海鉄道に旧翠浪臨港鉄道の路線の大部分が分離・譲渡され、翠浪臨海鉄道として再開業した。このとき分離されなかった路線の一部は現在も翠浪市が保有し、企業が利用する翠浪市公共専用線となっている。
なお、翠浪市営鉄道であった経緯から、旅客部門においては あざみない鉄道だけでなく、翠浪市電とも連絡運輸・乗継割引が設定されており、旅客運賃も比較的安く抑えられている。また翠浪臨海鉄道への翠浪市の出資比率は筆頭株主である あざみない鉄道に次ぐ40.5%となっている。
|
路線
|
+
|
... |
駅ナンバリングで使われる路線記号はRF。
駅ナンバリングで使われる路線記号はRS。
駅ナンバリングで使われる路線記号はRA。
|
車両
|
+
|
... |
現有車両
|
+
|
... |
※()内は形式のうち在籍している車両
|
+
|
... |
2019年から導入が始まった自重60トンの新型ディーゼル機関車である。石油・セメント・石灰石などの重量貨物に対応するため、600psのエンジンを2基搭載しており、重連総括設備を備えている。既存のSND56形を置き換え、主力機となっている。最高運転速度は110km/h。冷房装置を搭載している。車体はSND56形同様、日本のDD13形ディーゼル機関車を範として作られている。全車メーカーはあざみない車両。
|
|
+
|
... |
翠浪臨海鉄道移行時の1963年~2000年まで合計12両が製造された自重56トンのディーゼル機関車である。0・100・200・1000番台があったが、現在は SND60形への置き換えなどにより1000番台のみ在籍している。車体は日本のDD13形ディーゼル機関車を範として作られている。臨海鉄道開業前から重量貨物の牽引が想定されたことから550psのエンジンを2基搭載しており、重連総括制御装置を備えている。最高運転速度は100km/h。なお、1000番台のみ600psのエンジンを2基搭載しており、最高速度は110km/hとなっている。全車メーカーは翠浪車両(現あざみない車両)。
SND56形番台別詳細
|
+
|
... |
|
+
|
... |
1963年の臨海鉄道移行時に導入。翠浪市営鉄道時代の蒸気機関車SN100形を置き換えるために製造された。1986年に200番台の導入により、3・4が廃車され、海内セメント(現あざみないセメント)専用線に売却されたが、2019年に100番台の102・103に置き換えられて解体された。残った1・2は2000年まで活躍し、1000番台に置き換えられて廃車された。現在は1号機が他の保存車両とともに翠浪臨海鉄道翠浪機関区で保存されている。
|
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道から引き継いだ SND50形の置き換えのために1973年に製造された。0番台から前照灯や尾灯の形状や台車が変更されている。2019年に後継の SND60形が導入されたことにより全車が廃車され、101は あざみない鉄道に譲渡、102・103はあざみないセメント専用線に売却された。現在は101号機が あざみない鉄道水沙季工場で保存されている。
|
|
+
|
... |
1986年に0番台の一部車両を置き換えるために製造された。0・100番台からは車体形状の一部変更と使用エンジンの変更がされている。2020年に後継の SND60形導入により、 あざみない鉄道に譲渡され、 あざみない鉄道翠浪工場入換機として使用されている。
|
|
+
|
... |
残っていた0番台を置き換えるために2000年に製造された。他の番台より高出力の600psエンジンを2基搭載し、制御装置を最新型のものにするなどして最高速度を向上させている。また翠浪臨海鉄道で初めて冷房装置が搭載された。
|
|
|
|
+
|
... |
2022年から旅客用の S2000形気動車を置き換えるために製造された旅客用の新型気動車である。営業最高速度は140km/h。車体は鋼製のS2000形が晩年、海の潮風などで老朽化が進行していたことから、本形式ではステンレス製となっている。また、本形式より あざみない鉄道線への直通が開始され、 あざみない鉄道線内では電車車両との併結運転・最高速度140km運転となったため、乗り入れ用の機器だけでなく、 あざみない鉄道の電車車両との協調運転機器、最高速度140km/hに対応する機器を搭載している。全車メーカーはあざみない車両。
|
|
+
|
... |
1990年に保線用に使用されていた ト70形8両(ト83~90)を置き換えるために4両が製造されたホッパ車である。車体は日本のホキ800形貨車を範として作られている。最高運転速度は当初75kmであったが、2013年に台車交換により、100km/hに向上した。全車メーカーは翠浪車両(現あざみない車両)。
|
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道時代の1935年から1939年にかけてワフ71~80の10両が製造された鋼製有蓋緩急車。当初は走り装置が一段リンク式であったため、最高運転速度は65km/hであった。1969年に二段リンク式に改造され、最高運転速度は75km/hに向上した。当初は緩急車としても運用されていたが、翠浪臨海鉄道での緩急車連結が1989年に廃止されると9両(ワフ71~79)が廃車され、最終製造車のワフ80のみが残存し、現在も救援車として使用されている。
|
|
過去の車両
|
+
|
... |
※()内は形式のうち廃車された車両
- SND56形(1~4、101~104、201・202)
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道から引き継いだ S1000形を置き換えるため、1986年に15両が製造された旅客用気動車である。営業最高速度は110km/h。車体は鋼製であったが、現役末期には海の潮風で老朽化が進行していた(※このことから後継の S3000形では車体がステンレス製となっている)。全車メーカーは翠浪車両(現あざみない車両)。 S3000形への置き換えにより、2024年に最後まで残った2013~2015が廃車され、形式消滅した。現在は2001が翠浪臨海鉄道翠浪機関区に保存されている。
|
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道時代の1956年に翠浪市中心部での運用効率化を目的に15両が製造された旅客用気動車である。営業最高速度は95km/h。全車メーカーは翠浪車両(現あざみない車両)。1986年に S2000形への置き換えにより、全車が廃車され、形式消滅した。現在は1001が翠浪臨海鉄道翠浪機関区で保存されている。
当形式の製造当時、翠浪市営鉄道では旅客用の車両は第二次世界大戦以前に製造された古く小型な気動車・客車しかなく、翠浪市の人口が増加するにあたって翠浪市中心部の駅では、従来の車両で朝夕時間帯を中心に積み残しが発生し、深刻な問題となっていた。また、客車では機関車の付け替えが必要になり、朝夕時間帯の増発が困難になっていた。そのため大型気動車を投入し、朝夕時間帯の混雑緩和を目指すことにした。これが本形式である。実際に導入後の本形式は朝夕時間帯においてその大型な車体と扉の多さから積み残しが大幅に減少したという。
|
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道時代の1941年に翠浪鉄道(あざみない鉄道の前身)から20両(翠浪鉄道ト91~110)を譲り受けた木造の2軸無蓋貨車。最高運転速度は65km/h。元々は1913年に翠浪車両製作所(のちの翠浪車両を経て現あざみない車両)で40両(ト71~ト110)が製造された翠浪鉄道の木造2軸無蓋貨車ト70形である。翠浪市営鉄道ではそのうちのト91~110を譲り受け、ト71~90と改番した。
翠浪市営鉄道→翠浪臨海鉄道でも引き続き一般貨物列車用として使われたが、次第に貨物の大型化により運用が無くなると、1960年に12両(ト71~82)が廃車された。残った8両(ト83~90)は保線用に転用され、臨海鉄道線内のバラスト散布、深夜に翠浪鉄道~海内鉄道~水沙季鉄道(いずれもあざみない鉄道の前身)まで直通(※最高速度が65km/hと遅く、列車の高速化が進む他社において、高速の列車が走る日中に走れなかったため。)し、臨海鉄道までのバラスト輸送に使用されたが、最高速度が遅く、扱いにくくなったこと、老朽化が進んだことで1990年に後継の ホキ8000形への置き換えにより、廃車され、形式消滅した。なお、翠浪臨海鉄道での廃車時に翠浪鉄道(現あざみない鉄道)へ1両(ト90(元翠浪鉄道ト110))が返還され、翠浪鉄道時代の姿に復元されて現在も あざみない鉄道水沙季工場にて保存されている。
|
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道時代の1941年に翠浪鉄道から ト70形とともに譲り受けたダブルルーフの木造2軸客車である。最高運転速度は65km/h。元々は1927年に翠浪車両(現あざみない車両)で20両(ハフ71〜90)が製造された翠浪鉄道の木造2軸客車ハフ70形である。翠浪市営鉄道ではそのうちのハフ79〜90を譲り受け、ハフ71〜82と改番した。
翠浪市営鉄道では主に客車列車に使用されたが、1956年に S1000形が導入されると客車列車が全廃され、8両(ハフ71〜78)が廃車された。残った4両(ハフ79〜82)は客車を貨物列車に併結する「混合列車」(※翠浪市営鉄道および翠浪臨海鉄道では乗客が少なかった日中の末端区間で運行されていた)に使用されていたが、2000年代に入り、翠浪東港駅が最寄りの翠浪漁港周辺に 翠浪港歴史資料館を併設する翠浪港観光センターが建設されるなど、翠浪漁港が観光スポットとして整備されるようになると、臨海東港線では土休日を中心に乗客が激増し、古く小型の当形式では予備車を増結し、2両としても乗車定員が少ないため慢性的な積み残しを発生させた上、冷暖房が無かったため乗客から苦情が殺到した。さらに、度重なる混雑による重みで床に亀裂が発生するなど車体の痛みが進行していた。
これを重く見た翠浪臨海鉄道は、当形式の臨海東港線運用を大型気動車 S2000形に置き換え(※ S2000形は運用数に対して予備の車両が少なかったため、当時6両あった予備車の活用だけでなく、定期列車の運行区間延長など運用変更で捻出した)、当形式に大規模な整備工事を行った。
残った臨海埠頭線と臨海西港線の運用も2003年3月ダイヤ改正で老朽化とサービス向上を理由に S2000形に全て置き換えられ(※前述の通り、そのままの運用では車両不足のため定期列車の運行区間を延長して捻出した)、運用を離脱した。
なお、翠浪臨海鉄道での運用離脱後は4両全車が あざみない鉄道(翠浪鉄道の後身)へ返還され、検査や大規模修繕を受けた上で冷ヶ水線の各種イベント列車で運転されている。
|
|
+
|
... |
翠浪市営鉄道時代の1955年に合計4両が製造された自重50トンのディーゼル機関車である。500psのエンジンを2基備えており、重量貨物列車牽引のため重連総括制御装置が搭載されていた。最高運転速度は70km/h。全車メーカーは翠浪車両(現あざみない車両)。当時の蒸気機関車SN100形4両(101〜104)を置き換えた。
翠浪臨海鉄道移行後も貨物列車を中心に活躍したが、1973年に SND56形100番台に置き換えられ、全車が廃車された。3・4は海内セメント(現あざみないセメント)専用線に売却され、入換機として使用されたが、1986年に SND56形0番台の3・4に置き換えられ、4は翠浪臨海鉄道に返還された。現在は4が翠浪臨海鉄道翠浪機関区で保存されている。
|
|
|

