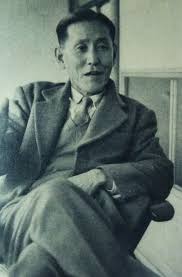
今西進化論とは
今西進化論とは、日本の生態学者・今西錦司(いまにしきんじ)が提唱した独自の進化理論である。従来のダーウィン進化論が「個体間の競争と自然淘汰」を軸としているのに対し、今西進化論は「種の主体性」と「共存」に焦点を当てている。生物は単に環境に適応するのではなく、環境の中で自らの在り方を選び取る主体的な存在であり、進化はその選択の積み重ねによって起きるとされる。
棲み分け理論
今西進化論の中心概念のひとつが「棲み分け理論」である。これは、異なる種が競争を避けるように自然と異なる生態的地位(ニッチ)に分化していくという理論であり、結果として生態系内での共存が可能になるとされる。種同士の「共存の論理」に重きを置く点で、競争と淘汰を前提としたダーウィン進化論とは根本的に異なる発想である。
主体性と進化
今西は、生物個体ではなく「種」そのものに進化の主体を見出した。進化は偶然の変異と自然淘汰による機械的なプロセスではなく、種が環境と関わる中で一定の方向性を持って変化していく現象であるとする。この「種の主体性」という考え方は、従来の進化論では軽視されがちであった「全体性」や「集団レベルでの適応」を重視している。
ダーウィン進化論との相違
ダーウィン進化論では、個体変異に対する自然淘汰が進化の原動力とされている。対して今西進化論では、淘汰や偶然性を進化の主要因とはせず、環境との相互作用において種が主体的に「どうあるべきか」を選び取る過程が進化であると考えられている。これは、目的論的とも受け取られる立場ではあるが、生態系全体を視野に入れた「構造的な進化論」として特徴づけられる。
関連性と評価
今西進化論は一部では「日本的進化論」と呼ばれ、西洋中心の科学思想とは異なる進化観として注目を浴びた。一方で、目的論的・集団選択的要素を含む点については、生物学界から批判も多く、主流の進化生物学とは一線を画した立場にある。ただし、文化進化論や人類学・哲学の領域では、その思想的価値が再評価されつつある。
添付ファイル










