21世紀の船(マストと索具)
こちらはオランダのバーク船Europa。マストに繋がってる紐がぜ~んぶ索具。
マストの先っぽでピロピロしてるのは国旗や信号旗。
信号旗が使われるのは18世紀になってから。係留中の船は昼間はN旗、夜間は緑色灯をウンヌンって規則があるみたい。
wikipedia
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_全体.JPG) |
下から |
上から |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_索具(下).JPG) |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_索具(上).JPG) |
| 裏から |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_索具(裏).JPG) |
船の各部名称(細かい部品は全部無視だ)
部品の名称は船によってイロイロ。
実際はロープを下げるロープや滑車にまでお名前が…。それぞれのお仕事はこちら
【船の各部名称】ざっくり一覧をどうぞ。
見比べたらちょびっとは乗り越えられそう。
こちらはイギリス海軍士官キャプテン・クックが乗ってたHMS Endeavour(Bark 1768)の模型。索具がかなりシンプル。
ハリヤードは間違ってるかも。ふえええ、索具ってムズカシイ…。
あとセイル広げると檣楼が前見えないっぽいです。ホンモノの船(写真)でも見えないっぽいです。裾をペロってめくるの?
静索(Standing rigging)
マストや帆を支えるための棒とロープ。
| コース |
トップ |
トップゲルン |
ロイヤル |
| 斜檣 |
| a1 |
Bowsprit |
a2 |
Jib-boom |
|
|
|
|
| トップ(檣楼) |
|
|
b1 |
Fore, Main, Mizen top |
b2 |
Fo, Ma, Mi crosstree |
|
|
| マスト(檣、帆柱) |
| c1 |
Fo, Ma, Mi mast |
c2 |
Fo, Ma, Mi top mast |
c3 |
Fo, Ma, Mi top-gallant mast |
c4 |
Fo, Ma, Mi royal mast |
| ステイ(前支索)…マストを支えるロープ |
| a1 |
Bob, Martingal stay |
a2 |
Fo, Ma, Mi stay |
a3 |
Fo, Ma, Mi top stay |
a4 |
Fo, Ma, Mi top-gallant stay |
| シュラウド(横静索)…マストに登る縄梯子 |
| b1 |
Fo, Ma, Mi shroud |
b2 |
Fo, Ma, Mi futtock shroud |
b3 |
Fo, Ma, Mi top shroud |
b4 |
Fo, Ma, Mi top-gallant shroud |
| バックステイ(後支索)…マストを支えるロープ |
|
|
|
|
c1 |
Fo, Ma, Mi top standing backstay |
c2 |
Fo, Ma, Mi top-gallant standing backstay |
| その他 |
| d1 |
Fo, Ma, Mi chain |
d2 |
Fore, Main stay tackle |
|
|
|
|
動索(Running rigging)
帆を操作する棒とロープ。
| コース |
トップ |
トップゲルン |
ロイヤル |
| ヤード(帆桁)…横帆を張る棒 |
| a1 |
Sprit-sail yard |
a2 |
Sprit-topsail yard |
|
|
|
|
| b1 |
Fore, Main, Cross-jack yard |
b2 |
Fore, Main, Mizen top yard |
b3 |
Fo, Ma, Mi top-gallant yard |
b4 |
Fo, Ma, Mi royal yard |
| c1 |
Spanker-boom |
c2 |
Spanker-gaff |
|
|
|
|
| ヤードリフト…ヤードを吊っているロープ |
| a1 |
Sprit-sail, Sprit-topsail lift |
|
|
|
|
|
|
| a2 |
Fore, Main, Cross-jack lift |
a3 |
Fo, Ma, Mi top lift |
a4 |
Fo, Ma, Mi top-gallant lift |
|
|
| a5 |
Spanker lift |
|
|
|
|
|
|
| ブレース…ヤードを動かすロープ |
| b1 |
Sprit-sail, Sprit-topsail brace |
|
|
|
|
|
|
| b2 |
Fore, Main, Cross-jack brace |
b3 |
Fo, Ma, Mi top brace |
b4 |
Fo, Ma, Mi top-gallant brace |
|
|
| ハリヤード…帆を上げ下げするロープ |
| c1 |
Sprit-sail, Sprit-topsail halyard |
|
|
|
|
|
|
|
|
c2 |
Fore, Main top halyard |
c3 |
Fo, Ma, Mi top-gallant halyard |
c4 |
Fore, Main royal halyard |
| c5 |
Spanker halyard |
|
|
|
|
|
|
| その他 |
| d1 |
Fore yard tackle |
d2 |
Foot rope |
|
|
|
|
マスト/檣(しょう)/帆柱(Mast)
マストはセイルを張る大事な柱で、たいていの船はフォア・メイン・ミズンの3本マスト。
それぞれのマストは、電柱みたいに1本ズドーンとした棒。20世紀になると船が大きくなって数本つなげるようになった。
wikipedia
 |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (マスト_折れた.JPG) げっ、折れた |
マストは船体の底にある檣座(檣根座:Mast step、檣根枠:Tabernacle)にプスッと刺さってる。
船体の上ではステイ、バック・ステイ、シュラウドで支えてる。
もしマストが折れてリニューアルなんてことになったら、そりゃもう大変なお仕事。
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (マスト_支える(檣座).PNG) |
 甲板から見上げると 甲板から見上げると |
檣楼(Top)とクロスツリー(Crosstree)
檣楼は見張り、操帆、射撃する場所。出入りは索具を通すラバーズ・ホール(檣楼昇降口)の穴からどうぞ。
クロスツリー(檣楼のもっと上にある)はヤードを吊る棒。
wikipedia
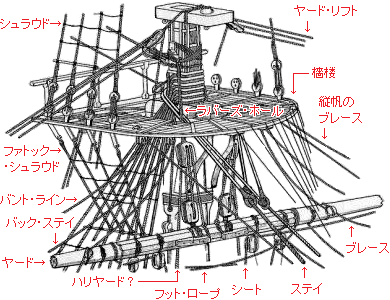 檣楼 檣楼 |
 クロスツリー クロスツリー |
※このマストは数本の棒をつないぐタイプ。
シュラウド(Shroud)とファトック・シュラウド(Futtock shroud)
シュラウド(横静索)はマストを支えるロープ。シュラウドにラットライン(段索)が合体して縄梯子になってる。
荷物を運ぶときは、
ファトック・シュラウド
(檣楼下横静索)からどうぞ。
習熟した船乗りならここから檣楼へ登れる。こんなことホイホイできちゃうジェフリーってすごいっっっ!
wikipedia
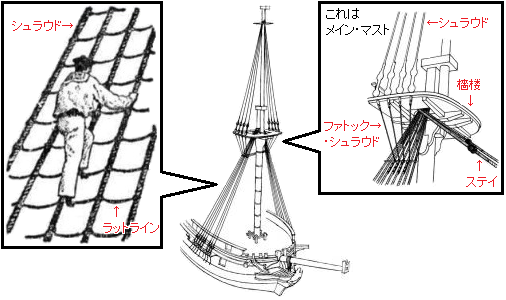 |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (シュラウドとファトック・シュラウド_ファトック・シュラウド.JPG) 習熟した人 |
ヤード(Yard)とフット・ロープ(Foot rope)とガスケット(Gasket)
ヤードはセイルを張る棒。行き方はシュラウドを登る→ヤードに到着→フット・ロープで横移動です。
とっても高いところだから、21世紀はヤードに安全ベルトをかけてお仕事してる。
畳んだセイル(畳帆)は
ガスケット
で縛る。セイルを拡げたら(展帆)、ガスケットはクルクル(gasket coil)しておく。
wikipedia
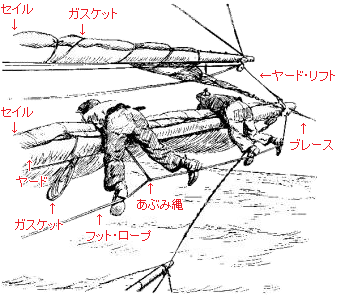 |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ヤードとフットロープ_畳帆.JPG) 畳帆中。高所恐怖症の人はムリそう |
ステイ・テークル(Stay tackle)とヤード・テークル(Yard tackle)
テークル(滑車装置)は
荷役
(貨物の上げ下ろし)に使うロープと
滑車
を組み合わせた装置です。クレーン車の先っぽのアレ。
ステイ、ヤード、…アチコチにぶら下がってる。
貨物の大きさ重さによってやり方はイロイロ。たぶん時代によってもイロイロ、船によってもイロイロです。
wikipedia
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル.JPG)
|
+
|
滑車ってスゴイ♥ |
滑車は小さい力で重い物を持ち上げたり、力の方向を変えたりする装置です。ボートや錨の上げ下ろしに大活躍。
大活躍だからアチコチにアリ。
16世紀は人間が引き縄を引っ張って持ち上げてます。電気なんて無くったってヘッチャラさ!
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(滑車).JPG) イングランドのガレオン船(1607年:
Jamestown Settlement
)
小さい力で重い物を持ち上げる
滑車には「定滑車」と「動滑車」の2種類があります。
- 定滑車…荷物が上がる方向と人間が力を出す方向を変える装置。荷物は持ち上げるより引っ張る方が楽チンだもんね。
- 動滑車…人間と天井で引っ張る力を半分こする装置。荷物が上がる距離も半分になるからロープは2倍引っ張ってね。
その合わせ技が「組み合せ滑車=テークル」。とーっても便利だから船はテークルをいっぱい使ってます。
wikipedia
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(滑車:小さい力で重い物).JPG) 滑車と仕事(中学理科で習います)
|
|
+
|
テークルを使えば重いボートだってホイホイ下ろせちゃうぜ! |
こちらはステイ・テークルとヤード・テークルを使ったボートの上げ下ろし方法です。説明が見つからなかったので詳細不明。
画の中に
引き縄
(Guy)が登場しないけど使わないのかしら?
ボートを上げるときはご活躍しそうな感じがします。テークルをウニウニするときはボートが傾かないように気をつけてね!
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(ボート).JPG)
ボート・ブームでボートをホイホイ下ろせちゃうぜ!
こちらはマストに設置されたクレーンの
ボート・ブーム
(Boat boom)を使ったボートの上げ下ろし方法です。
16世紀も使ってるかは不明。
③でボートに乗り込みます。ブームを使うときは
ステイスル
(マストとマストの間に張る三角の帆)を畳んでね!
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(ボート:ボート・ブーム).JPG)
Götheborg号
(1745年:スウェーデン)
|
投鉛台、投錨台(Chain/Channel)
投鉛台は測鉛手(chainsman)が海の深さを測る「バイ・ザ・マーク・テン」の場所。測深のやり方はこちら
【船】航海をどうぞ。
船の両側に付いてる。
横支索留め板(chainwale)が張り出してるおかげで、シュラウドの傾斜も緩やかになる。
wikipedia
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (投鉛台.PNG) |
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (投鉛台_測鉛.JPG) 測鉛(左舷で測ってる) |
フォアは投錨台と呼ぶのでしょうか?アンカーをアータラカータラするの?調べたけど分からなかったです。
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (投鉛台_投錨台.JPG)
HMSヴィクトリー号(18世紀)
最終更新:2016年07月03日 12:26