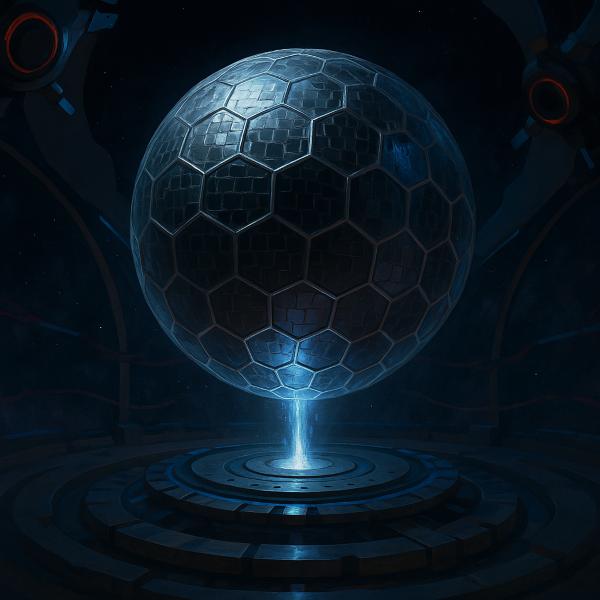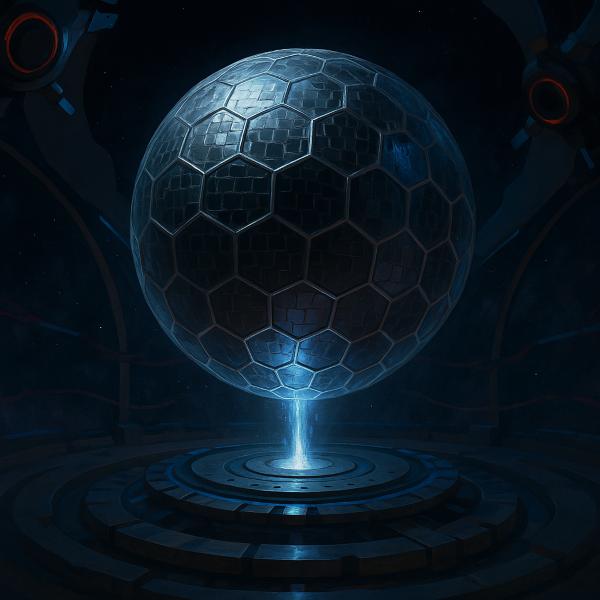
*オープンAI チャットGPT4o image generator |
11次元ポータルエンジンシステム(通称:エリス・ドライブ)は、超ひも理論に基づく革新的な技術であり、異なる次元や世界線への移動を可能にするシステム。このシステムは、物理学の最前線での理論を応用し、宇宙の構造を理解するための新たな手段を提供できる。
1. エリス・ドライブの基本概念
エリス・ドライブは、11次元超ひも理論に基づいて設計された革新的な次元移動装置です。この理論では、宇宙の基本構造を1次元の「ひも」として捉え、それらの振動状態によって異なる素粒子や力が生まれるとされ、従来の4次元時空(3次元空間+1次元時間)に加え、さらに7次元を内包するこの理論により、重力を含めた全ての基本力の統一的理解が可能となりる。
エリス・ドライブは、この高次元構造を応用し、通常の時空を超えて、異なる次元や平行世界線へのアクセスを可能にする装置。
これにより、特定の時空間座標を指定することで、現実とは異なる物理法則や歴史を持つ世界に到達することができ、人類の宇宙認識に革命をもたらしました。(詳しいポータル理論は
こちら)
2. ポータルの構造と機能
エリス・ドライブの中核には、球体状のポータルが存在し、その内部には超高密度のエネルギー場が形成されている。このエネルギー場は、ひもの振動を精密に制御することで発生し、空間の局所的な時空構造を変化させる役割を持つ。ポータルが開く際には、空間の断裂が発生し、その裂け目が通路として機能するため、特定の次元や時代に接続することが可能となる。
ポータルは、通常は封印された状態で存在しており、開閉には高度なエネルギー制御と演算処理が必要である。また、ポータルが繋がる先は完全に制御されたものであり、同じ世界線内の過去未来はもちろん、まったく別の物理法則に基づいた世界へのアクセスも可能である。この特性から、エリス・ドライブは探索・救出・研究の各分野で不可欠な存在である。
2.1. 時空間座標と地球相対座標
ポータルの目的地は、「時空間座標」と「地球相対座標」の2つの基準で設定される。時空間座標は、宇宙の全体構造における位置と時間を示し、これにより宇宙全体の中での具体的な場所と時点が指定される。
一方、地球相対座標は、地球を基準とした位置座標であり、人類にとって直感的に理解しやすい基準点として利用されている。
この座標設定によって、ポータル使用者は過去・未来へのタイムトラベルのみならず、宇宙の遥か彼方や並行世界への移動を実現できる。これにより、
ピースギアの調査隊は未踏の次元へのアクセスや異星文明とのファーストコンタクトも可能となり、これまで未知であった宇宙の構造解明が進展している。
2.2. 探索モードの機能
探索モードは、エリス・ドライブのもう一つの重要な機能であり、既知の座標に依存せず、量子確率に基づいてランダムに時空間座標を生成するモードである。この機能は、量子重ね合わせの原理を応用しており、ポータルは複数の可能性に同時にアクセスする状態に入ることができる。
探索モードでは、ユーザーが設定したテーマや条件(例:生命存在率、技術水準、重力環境など)に基づいて候補となる座標を複数生成し、その中からランダムまたは確率的に最も適した世界へと転移することができる。これにより、人類が発見していない知的生命体や技術、資源の獲得を目的とした次元航行が可能となる。
今回共立機構へ転移した際に使用した条件は、生命存在率を100%に設定したのみだった。
3. 理論的背景
エリス・ドライブの理論的基盤は、主に「超ひも理論」と「量子力学」の融合によって構築されている。超ひも理論は、あらゆる物理現象を1次元的なひもの振動として統一的に記述するものであり、重力を含む全ての力を説明することができる。この理論により、高次元空間の存在が予測され、異なる世界線や並行宇宙の存在が理論上証明可能となった。
同時に、量子力学の視点では、ポータルの不確定性やランダム性を説明する重要な要素が含まれている。ポータルの動作は確率論的であり、観測されるまで状態が確定しないという量子論の原理が、探索モードの設計や動作原理に直結している。これにより、エリス・ドライブは極めて高い柔軟性と可能性を持つ技術となっている。
3.1. 量子力学との関連
ポータルの機能には、いくつかの量子現象が不可欠である。その代表例が「量子もつれ」と呼ばれる現象であり、2つの粒子が空間を超えて情報を共有し合うという特性を持つ。この現象を応用することで、エリス・ドライブを用いた次元間通信が理論上可能となり、次元の壁を超えたリアルタイム情報交換が視野に入る。これが「ポータル通信」である。
また、ポータルの転移先の決定には、確率的な性質が関与しており、観測するまでは複数の転移先が同時に存在し得る状態が保たれる。これにより、探索モードでは転移先を人為的に完全には予測できず、ある意味で「選ばれる」ことになる点が量子力学的である。この不確定性が、未知へのアクセスを可能にしつつも危険性を孕んでいるといえる。
4.技術成立の背景
エリス・ドライブが誕生するきっかけとなったのは、「クデュック時代」に発生した物体消失事件である。この事件では、地球上の複数の物体が突如として消滅し、その直後に空間上に未知のポータルが出現した。当時のクデュックはこのポータルを調査し、消失した物体が次元を超えて転移していたことを突き止めた。
この現象の解析を進めるうちに、ポータルが11次元超ひも理論に基づいた構造であることが明らかになり、それを逆解析・再構築することで、現在のエリス・ドライブの元の技術が確立されたのである。
5. エリス・ドライブの応用
エリス・ドライブはその多次元的な応用性から、さまざまな分野で活用されている。宇宙探査では、通常の推進装置では到達できない銀河の彼方への移動が可能となり、既知の宇宙を超えた観測が行われている。また、並行世界へのアクセスにより、他の文明の技術や文化との接触も可能となり、急速な技術発展の一因となっている。
さらに、未知のエネルギー源の発見、絶滅危惧種の保護、災害が発生する前の世界線からの資源回収など、倫理的・実用的な使い方も模索されている。
6.デメリット
エネルギー問題:
エリス・ドライブの最大の課題の一つがエネルギー消費である。既に訪れた世界線に再び転移する場合には、空間の記憶効果によりエネルギー消費を抑えることができるが、全く未踏の次元にアクセスする場合は膨大なエネルギーが必要となる。特に赤色矮星クラスの恒星のエネルギーが必要となるケースもあり、エネルギー供給体制の確立が運用上の制約となっている。
探索モードの不確実性:
探索モードでは、転移先が確定していないため、到着地点が岩石の中や密閉空間であるリスクが常に存在する。また、平和な世界にたどり着けるとは限らず、戦争状態や文明崩壊中の世界、あるいは人類と敵対的な存在が支配する次元に出現する可能性もある。これにより、バタフライエフェクトのように他の世界線にまで影響が及び、世界線崩壊や融合が引き起こされる危険性もある。
このため、探索モードの使用は慎重に行うべきであり、基本的には既知の安全な座標への転移が推奨されている。)
最終更新:2025年07月14日 20:18