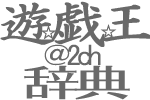死のデッキ破壊ウイルス(しのでっきはかいういるす)
死のデッキ破壊
ウイルスカード
闇属性で攻撃力1000以下の生贄を媒体にウイルスカードは発動する。
相手の手札及びデッキ内の攻撃力1500以上のしもべはすべて破壊する。
海馬瀬人が愛用するカードの1枚。
相手のデッキを一撃で壊滅に追い込む超強力カードであり、青眼の白龍やミノタウルスと並び海馬デッキのパワーを象徴する存在である。
テキストには場のモンスターがどうなるのか書かれていないが、場のモンスターも攻撃力1500以上ならしっかり破壊される。
相手のデッキを一撃で壊滅に追い込む超強力カードであり、青眼の白龍やミノタウルスと並び海馬デッキのパワーを象徴する存在である。
テキストには場のモンスターがどうなるのか書かれていないが、場のモンスターも攻撃力1500以上ならしっかり破壊される。
闇属性・攻撃力1000以下のモンスターが戦闘で破壊された時に発動できる。(*1)
王国編ではもっぱら闇・道化師のサギーを、BC編以降はブラッド・ヴォルスなどのアタッカーを収縮で攻撃力を半減させて媒介にすることが多い。
どのタイミングで媒体を設定するのかは定かではないが、「海馬vsペガサス」ではサギーの攻撃力が1000を超えた時点でこのカードも破壊されている。
発動に成功した場合、即座に相手の場と手札の攻撃力1500以上のモンスターは消滅する。
デッキ内のモンスターであるが、遊戯に発動した時は「ドローした際に破壊される」ペガサス・イシズ戦では「即座に全て墓地に送られる」と挙動が異なっていた。
王国編ではもっぱら闇・道化師のサギーを、BC編以降はブラッド・ヴォルスなどのアタッカーを収縮で攻撃力を半減させて媒介にすることが多い。
どのタイミングで媒体を設定するのかは定かではないが、「海馬vsペガサス」ではサギーの攻撃力が1000を超えた時点でこのカードも破壊されている。
発動に成功した場合、即座に相手の場と手札の攻撃力1500以上のモンスターは消滅する。
デッキ内のモンスターであるが、遊戯に発動した時は「ドローした際に破壊される」ペガサス・イシズ戦では「即座に全て墓地に送られる」と挙動が異なっていた。
このカードの特徴はとにかく成功しない事。
以下が死のデッキ破壊ウイルスの華々しい戦績である。
以下が死のデッキ破壊ウイルスの華々しい戦績である。
1 vs遊戯(王国編) 発動成功。
2 vsペガサス 《闇・エナジー》でサギーの攻撃力を上げられ発動失敗、《コピーキャット》でペガサスに使用され海馬にトドメを刺す。
3 vsイシズ 発動に成功するも《現世と冥界の逆転》の布石にされ自滅(最終的には勝ったが)。
(以下アニメのみ)
4 vs大門 大門のデッキマスター《人造人間-サイコ・ショッカー》の効果で発動失敗。
5 vs乃亜 《賢者ケイローン》に破壊され発動失敗。
6 vs城之内 発動成功。まぁ凡骨だし・・・
7 vsアメルダ 《王宮のお触れ》により発動失敗。ただし、のちに《クリティウスの牙》と融合し《デス・ウイルス・ドラゴン》となって引き分けに持ち込む。
(遊戯王R)
8 vsウィラー・メット 《カード・ヘキサチーフ》により発動失敗。
海馬の成功回数はたったのアニメを入れて3回であり、しかも一つは相手がわざと受けている。さらにペガサスにはいいように使用されている。
ここまで何をしても上手くいかないカードはドジリスか究極竜、青血さんくらいではなかろうか?
ここまで何をしても上手くいかないカードはドジリスか究極竜、青血さんくらいではなかろうか?
ちなみに、原作での分類は罠でも魔法でもなく「ウイルスカード」。
原作では《魔法除去細菌兵器》、Rで《α波の放散》が他にウイルスカードとして登場している。
また、一部のゲームではこのカード自体のカード名が「ウイルスカード」になっていて魔法カードである。おいおい。
原作では《魔法除去細菌兵器》、Rで《α波の放散》が他にウイルスカードとして登場している。
また、一部のゲームではこのカード自体のカード名が「ウイルスカード」になっていて魔法カードである。おいおい。
ちなみにGXにおいては、「十代vsカイバーマン」戦でカイバーマンのデッキに投入されていることが確認できる。
また、「丸藤翔vs猪爪」戦では猪爪がOCG版効果のこのカードを使用した。
何故か《サイバー・フェニックス》の効果でドローしたカードを確認しなかった。
また、「丸藤翔vs猪爪」戦では猪爪がOCG版効果のこのカードを使用した。
何故か《サイバー・フェニックス》の効果でドローしたカードを確認しなかった。
OCGにおけるテキスト
通常罠
自分フィールド上の攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体を生け贄に捧げる。
相手のフィールド上モンスターと手札、発動後(相手ターンで数えて)3ターンの間に
相手がドローしたカードを全て確認し、攻撃力1500以上のモンスターを破壊する。
さすがに原作効果のままだとムチャクチャなので、効果範囲が3ターンに縮まっているが十分に壊れ。
無制限期には「攻撃力1500以上だとデメリット」という意味不明な状況が発生したこともある。
無制限期には「攻撃力1500以上だとデメリット」という意味不明な状況が発生したこともある。
原作効果に無い点として手札とドローカードを確認できるというとんでもない物を持っている。
発動時の手札と以降3ターンの手札は相手に筒抜けになるので、主力モンスターを剥奪された上に戦略も読み放題になってしまう。
おまけに《クリッター》などの使いやすい生贄要員が数多く存在したため、2009年の夏に禁止化。
むしろ8年間も禁止にならなかったのが不思議なカードであった。
発動時の手札と以降3ターンの手札は相手に筒抜けになるので、主力モンスターを剥奪された上に戦略も読み放題になってしまう。
おまけに《クリッター》などの使いやすい生贄要員が数多く存在したため、2009年の夏に禁止化。
むしろ8年間も禁止にならなかったのが不思議なカードであった。
類似品の《魔のデッキ破壊ウイルス》と《闇のデッキ破壊ウイルス》が存在し、それぞれ媒体カードの条件と破壊カードの条件が変更されている。
これらは発動条件が本家より厳しい代わりに禁止指定される事は無く、デッキは選ぶが強力なカードとして度々注目されている。
これらは発動条件が本家より厳しい代わりに禁止指定される事は無く、デッキは選ぶが強力なカードとして度々注目されている。
2015年の1月には以下のテキストにエラッタされて制限復帰した。
通常罠
(1):自分フィールドの攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。
相手フィールドのモンスター及び相手の手札を全て確認し、
その内の攻撃力1500以上のモンスターを全て破壊する。
その後、相手はデッキから攻撃力1500以上のモンスターを3体まで選んで破壊できる。
このカードの発動後、次のターンの終了時まで相手が受ける全てのダメージは0になる。
ドローカードのピーピングがなくなり、相手に墓地肥やしを許す上に次の相手ターン終了時まで一切のダメージが与えられなくなるという総合的な弱体化を受けた。