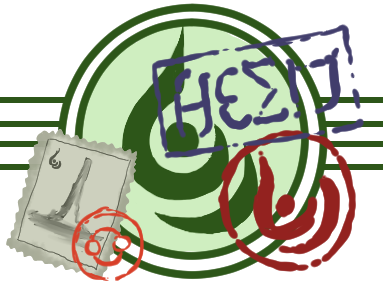
兵器一覧

第二紀世代
どっしりしている
| 乗員 |
46名 96名(満載時) |
| 動力 | 生体器官
x4 循環器 x2 |
| 代謝 | 87q |
| 最大速度 | 90km/h |
| 武装 |
三連装中型速射砲 x1 重機関砲 x2 10fin榴弾 x5 その他機銃 |
帝国の強襲揚陸艇。ベースとなったのは夜間強襲艇ラーヴァナ。
上部に指揮艦橋、下部に収容区画が設けてある。着陸後は司令部として運用ができるすぐれものだ。
噂によるとこの艦には接合部に爆砕ボルトが仕込まれており、非常時には収容区画を切り離し指揮艦橋が脱出できるようになっているとか…?
「ありえん!」――帝国軍宣伝省

第二紀世代
がっしりしている
| 乗員 |
33名 78名(満載時) |
| 動力 | 生体器官
x4 循環器 x2 |
| 代謝 | 79q |
| 最大速度 | 108km/h |
| 武装 |
六連装ロケット x1 重機関砲 x2 対地榴弾砲 x2 尾部両用砲 x1 その他機銃 |
帝国の強襲揚陸艇。ドゥルガの改良型、妹分だ。
作りが簡素化され、純粋な白兵戦を目的に建造がおこなわれた。
やはり非常時には収容区画を切り離し指揮艦橋が脱出できるようになっているらしい…?
「そんなはことはない!」――帝国軍宣伝省

第二紀世代
| 乗員 | 5名 |
| 動力 | グラウエンジン |
| 出力 | 27ps |
| 最大速度 | 10km/h |
| 装甲(前/横/背) | 10mm/3mm/3mm |
| 武装 | 21fin榴弾砲 |
帝人自走車製
第二紀帝国軍を支えた主力自走砲。
初期の帝国陸軍にとって、近代的な装備を持つ敵勢力が皆無だったことから、彼らにとって戦車といえば牽引式の野砲や自走砲そのものだった。
よって、これらの自走砲は純粋な戦車の登場後も便宜的に"戦車"と呼ばれていることが、後世のミリタリー愛好家を混乱に貶めている。
ダック210は空中艦で空輸可能であり、その21finという巨大な口径の割に限界まで軽量化・小型化されている。
コンパクトにまとまっているので生産性がよかったが、最後まで貧弱なエンジンは改良されず、空挺されたあとの展開には難があった。

第二紀世代
| 乗員 | 5名 |
| 動力 | カノマークエンジン |
| 出力 | 80ps |
| 最大速度 | 30km/h |
| 装甲(前/横/背) | 15mm/5mm/5mm |
| 武装 | 12.2fin榴弾砲 |
帝人自走車製
第二紀で戦場を荒らしまくったダック自走砲の正統進化版。
属国オージア製の貧弱なエンジンが引き続き使われている。
名前の由来はその独特な機関音から。
連邦軍がまともな装甲戦闘車両を繰り出してくると前線から姿を消した。
砲塔は限定的ながら旋回が可能となったので味方後方からの支援砲撃に徹することでその能力を示した。
技術的な問題から次世代の装輪戦闘車両が開発されるまでは時間を要した。

第二紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 |
パ式発動機PV-3 循環ポンプ |
| 出力 | 90ps |
| 最大速度 |
30km/h(整地) 9km/h(不整地) |
| 装甲(前/横/背) | 32mm/12mm/12mm |
| 武装 | 15.2fin榴弾砲 |
コンセプトデザイン:アイス民
機動力に難があったダックやドットルを置き換える目的で生産された装輪戦闘車両。
空輸による迅速な兵力展開を意識して設計された、空挺戦車の始祖でもある。
南パンノニアに生産させた内燃機関を装備しており、生体器官に頼らない走行が可能となっている。
生体に頼らないぶん器官の疲労などは無視できるようになったが、工作精度がよろしくない帝国の工場では
内燃機関を大量生産することは叶わず、物流コストの面からもその多くが南パンノニアで生産されている。
車体装甲は鋳造・溶接を駆使しており、第二紀の量産兵器としては高レベル。
主砲は203mmをぶちかますバカをやめて、信頼性の高い152mm砲に変更された。
発射レート、装弾数、軽量化を考慮に入れた上の最適解だった。

第三紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 | パ式発動機PD-5 |
| 出力 | 130ps |
| 最大速度 |
44km/h(整地) 11km/h(不整地) |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/20mm/20mm |
| 武装 | 15.2fin戦車砲(AP) |
コンセプトデザイン:ハインケル
空挺戦車ゼクセルシエ(後述)と同時期に生産された装輪戦闘車両。
先代のヴァゼと似ているが、本車両の設計思想は当初から"ゼクセルシエとのハイローミックス"だった。
戦略兵器であり、特別な補給物資を大量に必要とするゼクセルシエをサポートできるように
内燃機関で駆動する戦闘車両が打診された結果うまれたのがクローゼである。
舗装された路上や踏み固められた道であればまあまあのスピードを出すことができたが
車輪といってもゴムを塗布した鉄輪に変わりなく、サスペンションなどと行った機械設備はなく、
車というよりは貨車といったほうが正確なようだ。

第二紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 | モイ式接地筋足 |
| 代謝 | 8q |
| 最大速度 | 15km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/30mm/10mm |
| 武装 |
7.5fin榴弾砲 同軸擲弾砲 同軸機銃 車載機銃 x3 |
ナーメーケー社
その奇妙な見た目は味方をもどことなく不安にさせる。
戦車のように見えて戦車ではなく、歩兵に追従する自走火力支援車両という位置づけだ。
その設計は安直だが同時に堅実でもあり、後発の帝国のモイ式戦車シリーズに多大な影響を与えた車両。
注目すべきは車体底部にびっしりと生えているイボイボの推進装置。
キャタピラ付きの戦車を作る技術がなかった帝国が苦肉の策で生み出したタイプである。
北半球国家と違って生体技術に多くの面を頼る帝国では均一なキャタピラの大量製造が苦手であり、内燃機関の技術の遅れも相まって砲の自走化が大きな課題となっていた。
北半球の戦車を真似た実験的な履帯付き戦車を作る試みも失敗に終わっており、帝国はこれを生体技術で打破しようと発想を転換したのである。
それがこのモイ式推進装置、正式名称:モイモ・バイゼルだ。
これは戦車の底面にびっしりとフジツボのような軟イボが並んでおり、これをうねるように動かして戦車を前進させるという仕組みになっている。イモムシが足を使って葉の上を歩く姿をイメージしてもらうとわかりやすい。
そんなネメッケはトップヘビーでとても横転しやすかったものの、そばにいると頼もしいことから兵士からは各車両にあだ名を付けられ愛されていた。

第二紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 | モイ式接地筋足 |
| 代謝 | 7q |
| 最大速度 | 16km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/30mm/10mm |
| 武装 | 5.5fin榴弾砲 |
第二紀にひっそりと登場した帝国の砲戦車。
改良されたイボ配列により高い接地圧を実現し、履帯と同じように左右に推進装置が分かれて超信地旋回ができるようになるなど汎用性は高かった。
しかしながら、何トンもの車重からくる乳酸の発生量は尋常ではなく長距離走行には極めて不向きであった。
そのためゲシュは長年戦場に出ることもなく、連邦軍にもほぼ認知されていなかった。
第三紀にカノッサ湿地帯での戦車戦が苛烈になって、ようやく基地防衛用として空輸されるようになった。
中途半端な傾斜装甲は車重削減を目的に、可能な限り体積を減らそうとした為であったが、それが本車両に避弾経始の効果をもたらしたのは全くの偶然であった。
ちなみに、ゲシュとはオージア地方でよく見られるとんがり帽のことである。

第二紀世代
| 乗員 | 6名 |
| 動力 | モイ式接地筋足 |
| 代謝 | 16q |
| 最大速度 | 12km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) |
60mm/60mm/60mm |
| 武装 | 11.5fin榴弾砲 |
コンセプトデザイン:アイス民
砲戦車ゲシュの発展型でその巨体と重装甲が特徴。
全周60mmの重装甲と大口径の榴弾砲が合わさり、連邦の戦車乗りに恐怖を与えた。
連邦軍が繰り出す75mmの榴弾砲や30-50mmクラスの徹甲弾をことごとく跳ね返し、ジリジリと迫りくるバログはKV重戦車のような存在だ。
だが、バログはいくつかの問題を抱えていた。
重量である。上部構造に対して足回りが貧弱すぎるという難題は、砲戦車ゲシュの比ではなかったのだ。
その重量が災いし、当時の帝国では空輸手段が限られていたためほとんどが内地で埃を被っている有様だった。
生産数の少なさも悩みの種で、無数の強靭なイボを養成する能力も当時の培養ラインでは限界があり、車体だけが工場に積み重なっている状態だった。
そうこうしている間に帝国軍は浮遊式戦車の開発に成功し、活躍の場はゼクセルシエに奪われてしまう。
ところがこの話には続きがある。連邦軍がゼクセルシエ対策として、新砲塔型のトエイ戦車を投入してくると帝国軍はこのバログを空輸し、その重装甲で連邦軍の進軍を食い止めたという数十年越しの活躍をしてみせたのである。ミーレ・インペリウム。
後年、バログはその優秀な車体設計から改良型がほそぼそと作られ、一説によれば余った車体を浮遊式にした ”バログント(巨人)”
なるキメラがパンノニア戦線で目撃されたとか言われているが、その証言の正確性にはいささか疑問が残る。

第三紀世代
| 乗員 | 3名 |
| 動力 |
生体器官 循環ポンプ |
| 代謝 | 8q |
| 最大速度 | 70km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 45mm/45mm/40mm |
| 武装 |
5.5fin戦車砲 (AP/HE) |
コンセプトデザイン:ねれいどん
第三紀に登場した帝国の新型戦車。その登場は連邦軍に”ゼクセルシエ・ショック”を与えた。
もともと履帯(キャタピラ)の技術を持たない帝国は他国の戦車と数世代のブランクが開いており、帝国はそれをひたすら大口径化で対処してきた。従来の軽戦車ですら21finの主砲を積んでいる有り様だ。
だが、この戦車の登場により帝国軍の戦車は機動面においては数世代を跳躍する大進化を遂げた。この戦車は、宙に浮くのである。
帝国のお家芸、生体器官を導入し地面との摩擦抵抗はほぼゼロ。どんな悪路もスイスイと走り回ることができる。そのうえ車体前部の凶悪的なくさび形装甲は実質90mmレベルの装甲厚を実現させた。主砲は帝国軍にしてはかなり小さな5.5finであるが、この戦車の機動性と装甲と相まって優秀な効果を発揮するだろう。
機嫌を損ねると途端に運動神経が鈍化して座り込んでしまうなど、生体器官ゆずりのデメリットも。
帝国軍内での愛称は”ゼキ”。
かなりの数が生産されており、様々な戦線で出没するので創作でもとりあえずこれを出しておけば様になるというものである。

第三紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 |
生体器官 循環ポンプ |
| 代謝 | 9q |
| 最大速度 | 20km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 45mm/45mm/40mm |
| 武装 | 21fin榴弾砲 |
コンセプトデザイン:アイス民
戦車として芸術的なまでに完成された空挺戦車ゼクセルシエに、榴弾バカと砲兵崇拝信者が21fin砲を搭載した。
この21finは帝国の露天鈍亀棺桶ダック軽戦車のものである。ここにきて原点回帰。なぜもどした!?
案の定、重量増により自慢の浮遊能力は殆ど失われたうえ、沈み込んで接地してるのとほとんど変わらなくなっている。ズブスブ…
もちろん速度も大幅低下。その上砲塔が大型化したことでやたら目立ち、砲塔はさながら火薬のすし詰め状態。
砲塔の上にちょこんと乗っている暗視装置は敵に照射して狙うというよりも、夜間に敵に察知されずに僚機と発光信号でやりとりできるようにしたものである。
従って、受像装置は無線手席にしかない。敵が居そうな場所の座標を共有し、一斉制圧砲撃を行うドクトリンを採用している。
6両が無許可に製造されカノッサ湿地帯に投入されるも、西の青いあんちくしょうの某巨人戦車に赤外線を察知され逆に夜間に狙撃されるとか散々だった模様。
ついたあだ名は"ドーゼック(のろまなゼック)"。

連邦も同じことしている。
似た者同士とはこのことである。

第三紀世代
| 乗員 | 2-3名 |
| 動力 |
生体器官 循環ポンプ |
| 代謝 | 7q |
| 最大速度 | 55km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 45mm/40mm/40mm |
| 武装 |
5.5fin戦車砲(AP/HE) 同軸機銃 x1 |
ゼクセルシエ・モミは、皇国戦線向けに小柄の個体を選別した一連のタイプ。
器官容積が2割ほど絞られており、より小型で火力は据え置きといういいとこ取りの中戦車だ。
といってもただでさえ狭い車内はさらに窮屈になっており、2名体制での運用が望ましい。
後発のアッシュと共に開発されたが、どれも運用側の不平不満が噴出した。
愛称は"モミ"(ひき肉饅頭)。肉がギュウギュウに詰まっている様から。

第三紀世代
| 乗員 | 3名 |
| 動力 | 生体器官 |
| 代謝 | 10q |
| 最大速度 | 40km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/30mm/30mm |
| 武装 |
5.5fin榴弾砲 同軸機銃 x1 |
傑作空挺戦車であるゼクセルシエをベースに、歩兵に随伴する車両として設計された。
車体は被弾を減らすためよりコンパクトに潰されたフォルムへと変貌。
純粋な歩兵戦に対応するため、砲換装が行われて徹甲弾が撃てなくなっている。
そのかわりに高レートの榴弾投射能力をもっており、へなちょこの連邦軍戦車にとっては脅威であった。
規定乗組員は3名だが、非常に狭いため2人体制での運用が目立った。
40両あまりがチビチビと生産され、大型車両の搬入が難しいテルスタリ戦線に投入された。
しかしながら、相手が想定された戦術をとってこないために思うような活躍ができなかったという。
また、最後の数両はパンノニア事変で投入されたことが確認されている。

第三紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 | 生体器官 |
| 代謝 | 13q |
| 最大速度 | 69km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 70mm/40mm/30mm |
| 武装 |
8.2fin榴弾砲 同軸機銃 x1 |
ゼクセルシエ戦車を撃破するべく連邦軍が送り出したトエイ中戦車は、帝国戦車兵の恐怖の象徴だった。
それに対応するべくして開発されたのが、このノイゼン戦車である。
猛将ノイゼン・ヴァル将軍の名を冠したこの中戦車は走・攻・守ともにバランスが良く、連邦軍を混乱に陥れた。
前方の触覚は感応地雷や蛸壺兵の脅威を察知できたが、主戦場となったカノッサ湿地帯ではクルカや原生生物にかじられるなどして
役に立たなかったためこの機能は後期生産型ではオミットされた。
新砲塔トエイ中戦車に対しては上位互換のような存在であったが、生産コストと主砲精度に問題があったために大きく戦況を覆すことはできなかった。
不幸にもロールアウト直後には連邦軍がヂトチン重戦車を投入しており、画期的な設計の割にはあまり目立たない戦車である。
パンノニア事変での投入が確認されている。

前期型

後期型
第三紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 |
生体器官 循環ポンプ |
| 代謝 | 18q |
| 最大速度 | 65km/h(整地) |
| 装甲(前/横/背) | 90mm/70mm/40mm |
| 武装 | 23fin榴弾砲 |
帝国が送り出した、南北戦争時最強の重戦車。
惑星パルエの陸上兵器の中でもその大きさ、攻撃力、防御力ともに桁外れの性能を誇っている。
主砲は固定式のように思えて実際はかなり可動し、積極的な攻撃が可能だ。
属国たちが条約制限の抜け穴をついてやりたい放題やっているので「少しでも怪しい動きを見せたらぶっ潰すぞ」というメッセージ性を込めて生産された趣が強く、その生産数は無論少数に留まっている。
とはいえ、駄作兵器デパートと化している惑星パルエでは珍しく非常に強力な戦略兵器で、パルエ世界に舞い降りたIS-3重戦車といった印象である。

▲あまりにも重装甲でありとあらゆる砲弾を弾き、とうとう連邦軍がしびれを切らしてワンオフの自走砲を作ってしまったほど。
生産コストはとても高く、平地で使えば艦砲の餌食となり、密林湿地で使っても生体器官がグズるわ長所の高速ホバーも活かせないわで散々な結果となった。
ただし車両自体の設計は優秀であり存在しているだけで抑止力になっているのは事実で、けっして無用の長物ではなかったことは確かだ。
対空型が数量存在する。

第一紀世代
| 乗員 | 5名 |
| 動力 |
生体器官 循環ポンプ |
| 出力 | 3q |
| 最大速度 | 30km/h |
| 装甲(前/横/背) | 5mm/5mm/5mm |
| 武装 | 38.1fin重榴弾砲 |
初期の自走砲。
自走砲というよりは攻城砲・臼砲としての性格が強く、南方民族の城塞攻略にはダンヒの姿がよく確認された。
装填には外部操作式の筋肉クレーンを用いるが、それでも1発の装填に40分を要する。
破滅的な攻撃力とは裏腹に射撃反動を逃がすことができず、乗員が振り落とされる事例多数。
第二紀までには全車が退役し、いくつかの臼砲は取り外され防衛兵器として転用された。

第二紀世代
| 乗員 | 5名 |
| 動力 | 生体器官 |
| 出力 | 12q |
| 最大速度 | 70km/h |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/5mm/0mm |
| 武装 | 21fin榴弾砲 |
軽戦車ダック210を浮遊できるように改造した浮き砲台といったユニットである。
浮遊能力を駆使して、地上目標に対して柔軟な運用が可能だった。
砲撃支援などに従事した。

第一紀世代
| 乗員 | 4-15名 |
| 動力 | 生体器官 |
| 出力 | 9q |
| 最大速度 | 40km/h |
| 装甲(前/横/背) | 0mm/0mm/0mm |
| 武装 |
自衛用固定機銃 x2 (10mmカビラム弾) |
上空から指揮を撮るために開発された浮遊プラットフォームである。
連邦軍から格好の攻撃目標となり、第一紀が終わることには全てが退役した。
…が、一部は野砲などを積載して浮き砲台として使われた記録が残っている。
運搬任務や戦車回収用途などでは第二紀まで活躍していた。

第二紀世代
| 乗員 | 4名 |
| 動力 | 生体器官 |
| 出力 | 9q |
| 最大速度 | 40km/h |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/5mm/0mm |
| 武装 | 11.5fin榴弾砲 |
自走砲砲バンキャシャの次世代型であり、自走砲なのか戦車なのかはっきりしない車両。
主砲は重戦車バログと同じ11.5fin榴弾砲を装備しており、それでいてオープントップで中途半端な印象である。
だが、基礎コンポーネントは優秀であり空挺戦車ゼクセルシエの嚆矢となった。
生産数は6両。南パンノニアにスクラップとして売却されるが…

第二紀世代
| 乗員 | 1名 |
| 動力 |
ジャコ脚 体温維持ストーブ |
| 代謝 | 2q |
| 最大速度 |
18km/h…巡航 45km/h…瞬発 |
| 装甲(前/横/背) | 5mm/2mm/2mm |
| 武装 | 四連煙幕投射機 |
コンセプトデザイン:アイス民
北の連邦快速豆戦車ダッカーならば、南のヴァ型…?
悪路も物ともせずジャッカジャッカと激しく走る。
足を伸ばしきれば、はしご車のように遠くを見据えることもできるすぐれもの。
多量に算出される乳酸の処理が追いつかず、すぐにバテてしまうので長時間の難姿勢の強要は禁物である。
煙幕弾ポッドを機関銃やロケット砲に付け替えた現地改修型も存在しているようだ。。

第三紀世代
| 乗員 | 1名 + クルカ1匹 |
| 動力 |
ジャコ脚3型 固形脂肪燃焼器 |
| 代謝 | 4q |
| 最大速度 |
20km/h…巡航 40km/h…瞬発 |
| 装甲(前/横/背) | 10mm/2mm/2mm |
| 武装 |
対艦榴弾砲 x1 パンプキンス機関銃 x1 デーデット焼夷擲弾 x1 対甲殻獣ガス筒 x4 シカーダ対甲ラケーテ x1 PK-5.5対物ライフル x1 重擲弾投射筒 x1 四連装対地ラケーテ発射基 x1 |
対皇国戦線に投入されたヴァ型の現地改修型である。
歩兵戦車顔負けの強力な制圧能力を持ち、全方向から襲いかかる皇国兵を範囲攻撃で仕留めようという算段だ。
マーギット第3中隊に所属し多くの将兵を救ったが、クレット盆地の戦いで孤立。
部隊が撤退する中最期まで殿を務め、仁王立ちのまま事切れた。
全身に無数の毒槍が突き刺さったその光景は現地部族に言い伝えられる神の化身に瓜二つであり、その亡骸は丁重に埋葬されたという。

第三紀世代
| 乗員 | 13名 |
| 動力 | 原生生物 ガドン |
| 代謝 | 22q |
| 最大速度 | 12~20km/h |
| 装甲(前/横/背) | 160mm/90mm/90mm |
| 武装 |
36fin重榴弾砲
x1 5.5fin戦車砲(副砲) x1 10.5fin榴弾砲 x2 対空速射砲 x8 下部機関銃 x2 尾部ネネツ鋼スパイク |
原生生物の頭部を切断し、帝国のお家芸である生体手術を行って自由に操縦可能にした歩行要塞。
吸盤のように広がる巨大な脚で湿地もへっちゃら。空挺戦車ゼクセルシエを更に発展させた傾斜装甲は連邦軍の戦車では撃破は不可能だろう。
前部装甲である顎のような部分を岩場に押し付け、そこを軸に体制を変えて仰角を補うことも可能だ。
三半規管を用いた非常に優秀な"オートバランサー"を備えている。
弱点は無論脚部と腹。

主砲は重砲艦アトラトルの重砲を軽量化したもの。
帝国軍部は、火力の豊富な帝国軍に対抗するべく連邦軍がカノッサ湿地帯において要塞を構築することを予想。その撃破のためにこのヌタが生産された。

第三紀世代
| 乗員 | 3+8名 |
| 動力 |
サザン・トラクトル バイネン・ホイーラ |
| 代謝 |
90ps 11q |
| 最大速度 |
60km/h(整地) 42km/h(不整地) |
| 装甲(前/横/背) | 30mm/30mm/30mm |
| 武装 |
VM75マジソンス重機関銃 x2 バルマン軽機関銃 x1 |
コダックス・ホーエン社製
第三紀に突如登場した近代的な歩兵輸送車両。
平凡な見た目だが、この車両の肝はそのシャーシにある。
バイネン・ホイーラ式という、モイ式推進器官を車輪に巻きつけた駆動輪を持ち、泥土などにスタックしても
車輪にびっしりと貼られたイボがモゾモゾと動いて脱出する様は異様な光景だろう。
これらはカノッサなどの泥土に派兵するために開発されたが、実際の戦場はパンノニア平原や市街であることが多く後期型では普通のタイヤを履かされている。