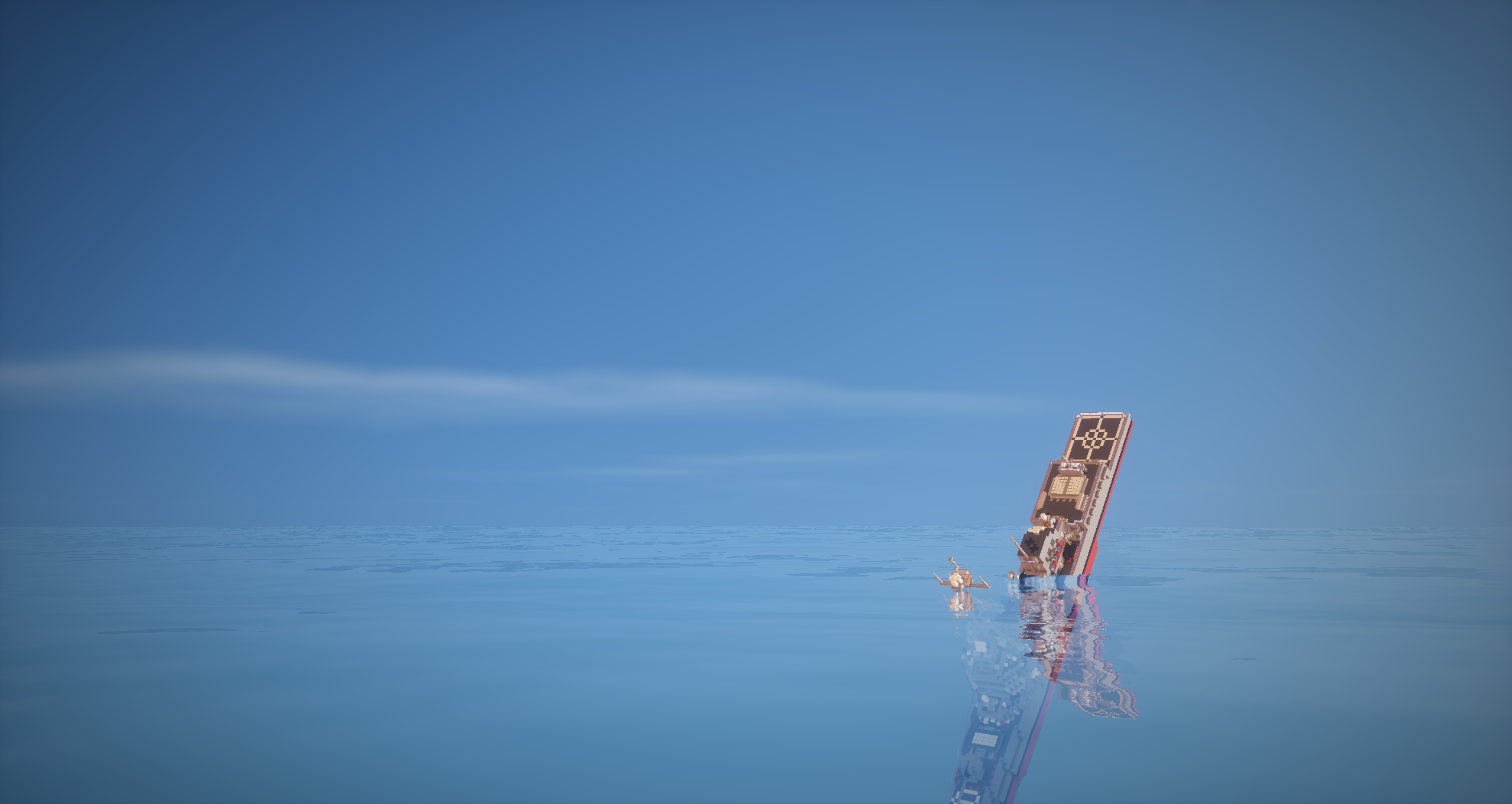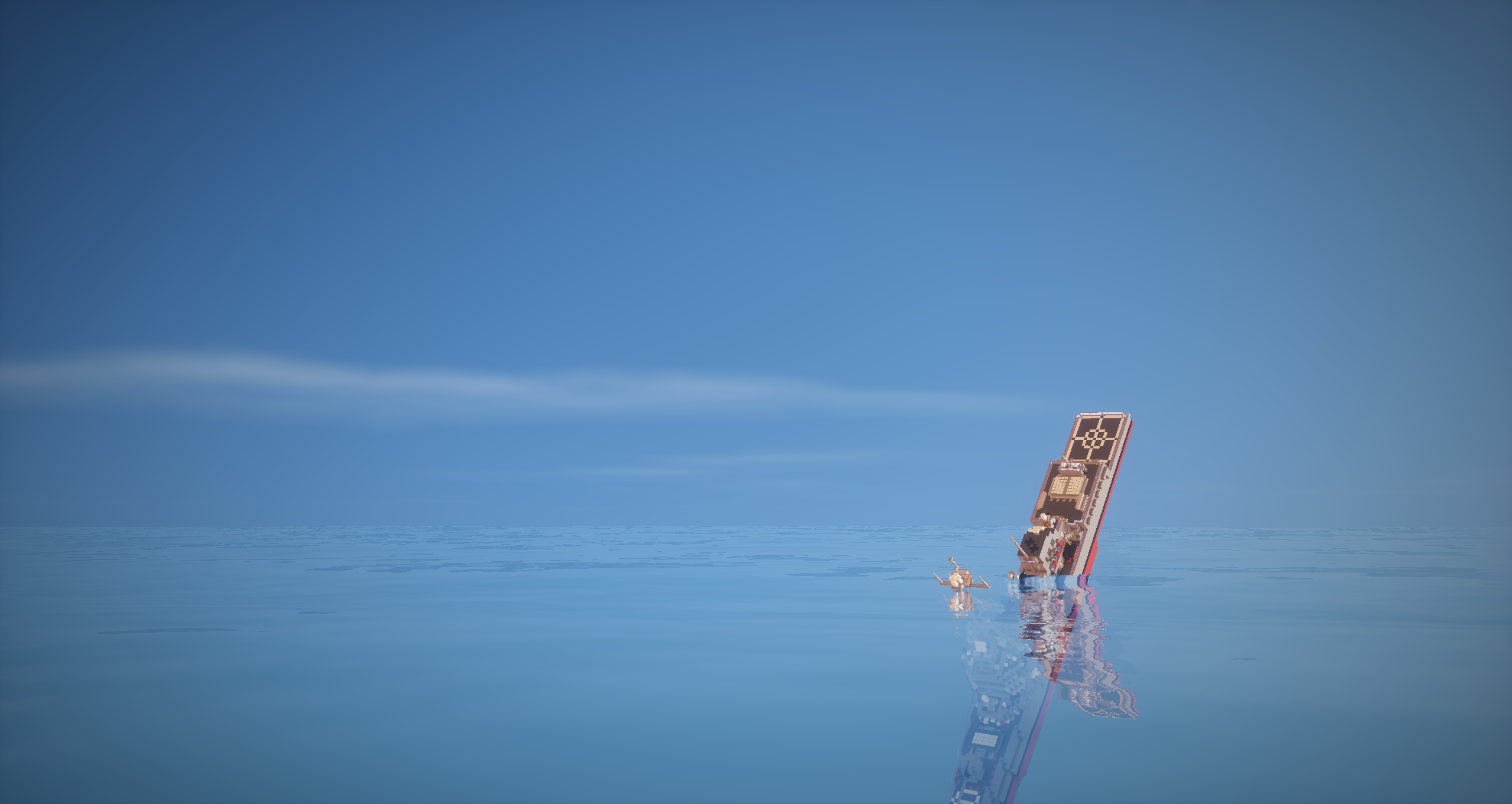ニューイングランド事変
System=話し合い
| ニューイングランド事変(ニューイングランド事変、獅:New England Freak、水:Новой Англии Инцидента)は、レグルス第二帝国の北アメリカ進出をきっかけとした一連の武力紛争である。その期間において両陣営は一度も宣戦布告を行わなかったため法的には戦争とされていないが、数年間続き数十万人の被害者を出した。 |
| 目次[非表示] |
|
1 背景
1.1 レグルス帝国の策謀
1.2 ニューイングランド共産党の拡大
1.3 ニューイングランド独立宣言
2 経過
2.1 ボストン上陸作戦
2.2 北連本土逆侵攻
2.3 前線の停滞
2.4 冬季大攻勢
2.5 ラブラドール海戦
2.6 ニューイングランド攻防戦
3 結末
3.1 レグルス帝国主義への影響
3.2 ニューイングランドの再編
4 影響
4.1 北連抑留
|
|
ラブラドル海戦 |
imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。冬季大攻勢 |
| 戦争:ニューイングランド事変 |
| 年月日:131年12月1日 - 133年8月3日 |
| 場所:北極諸島、アメリカ東部、大西洋 |
| 結果:レグルスの北アメリカにおける影響力喪失 |
| 交戦勢力 |
|
スィヴェールヌイ諸島共和国
|
|
レグルス第二帝国
|
|
スティーブ・クラフタリア同盟連邦
|
|
ニューイングランド独立国 |
| 指導者・指揮官 |
|
アンドレエヴィチ = ポトリツィン |
|
ギース・クロムウェル |
|
スティーブ・ぺルソン |
|
ロジャース・ラインハルト |
| 参戦兵力 |
|
たくさん |
|
大西洋艦隊
陸軍兵員約15万人 |
|
たくさん |
|
正規軍約11万人
民兵30万人 |
背景 |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
レグルス帝国の策謀
131年にギース・クロムウェルによる国家社会主義体制を構築したレグルス第二帝国は
CELTO
との対立を深めていた。しかしCELTOの主要な基盤地域である北アメリカ大陸はレグルスの影響圏からほど遠く、拠点となる場所も存在しなかった。これは他のCELTOとの対抗勢力にとっても同様であり、北アメリカはCELTOにとってある種の聖域だった。そこでレグルスはCELTOとの対立で有利に立つために当時政治的に混乱していたアパラチア連邦共和国への介入を行った。
アパラチア連邦共和国は親CELTOの議会制民主主義国家で、ミシシッピ以東の北アメリカ中部を支配していた。しかし政治的腐敗や強大化しすぎた州権によって中央政府の権威は著しく衰え軍閥割拠状態となっていた。レグルスはこの弱みに付け込みバージニア事件のような武力脅迫や政治ロビーを通じた誘導によって影響力を高めた。しかしこの動きはCELTO諸国の危機感をあおり、その成果は急進的なレグルス政府を満足させるものではなかった。
そのため東海岸での鉄道敷設権を承認したニューアーク条約以降、レグルスはアパラチア中央政府ではなく軍閥勢力と協同する方針に転換する。
当時アパラチアで最も独立の機運が高かったのはフロリダ半島だった。レグルス帝国はこの独立運動に武器援助を送るなどして支援した。その結果129年のフロリダ事件ではフロリダ・エスパニア共和国が独立を宣言したものの、CELTO連合軍の迅速な介入によって共和国はわずか1週間で崩壊した。レグルス帝国はフロリダの失敗をレグルス北米権益の中核である北東部から離れていたために介入が遅れたこと、事件の規模が小さかったことが原因だと分析、アパラチア東北部を支配し以前から接触のあったニューイングランド共産党との正式な提携を決断した。
|
ニューイングランド共産党の拡大
ニューイングランド共産党はその名の通り社会主義政党ではあったが、社会ダーウィニズムやロシア的社会主義の影響を受けた組織で南北アメリカで支配的な民主社会系の組織とは一線を画していた。またWASPによって構成された民族主義的な側面を持ち、どちらかというと多民族・カトリック的なアパラチア中央からのニューイングランド(ここでは中部アメリカ東岸のWASP優勢の地域)の独立を唱える民族主義的な性格も有していた。そのためニューイングランド共産党はアパラチア中央政府からは排除対象とされていた。
125年から130年にかけてニューイングランド共産党は以前から保有していた準軍事組織"レッドライン"を急速に発展させ、その支配領域を武力で拡大していた。その影響力は日増しに高まり続け、アパラチア中央からの分離独立も現実味を帯びていた。しかし実際に独立を宣言すればCELTOの介入は確定的で、それに対処する能力は共産党にはなく支援を必要としていた。またニューイングランド共産党の掲げるニューイングランド社会主義は同時期に高揚したレグルスの国家社会主義と相互に影響を与えあっており、党指導者のラインハルトを始めとしてレグルスとイデオロギー的共感を覚える者は少なくなかった。そのためこのレグルスの申し出はニューイングランド共産党にとっては渡りに船といえるものだった。
しかしニューイングランド共産党とレグルスの関係はCELTOにとっては全く予期せぬことだった。レグルス帝国の反共主義は広く知られており、仮にも共産党と名のついた組織と提携するなど考え難い事だった。全くそのような意見が上がらななったわけではなく、一部の識者はニューイングランド共産党とレグルスの国家社会主義思想の類似点や武器取引疑惑を指摘したものの、それらの考えが広く支持されれる事はなかった。
ニューイングランド共産党は130年に東海岸最大の都市ニューヨークを包囲戦の末に攻略した。ラインハルトは東アパラチア自治政府の成立をアパラチア中央政府の同意なしに宣言した。介入する能力のないアパラチア政府はこの宣言を否定はしたものの、それ以上の行動をとる事はなかった。
一方でレグルス帝国にとってはこれらの動きは共産党との密約で連絡されていた既定事項ではあったが、対外的には自治政府に敵対的な反応を示し駐屯地・鉄道附属地への軍増派を繰り返した。自治政府は建前上この動きに抗議したものの敢えて弱腰な姿勢を見せ、ラインハルトはこれに反発した党員を粛清し地盤固めを行った。この両者の動きについてCELTOは完全に黙認しており、その裏には両者共倒れが最も利益になるという打算があった。
131年にはニューイングランド共産党がコンコードの戦いでジョン・プレストン・ガービー隷下のニューイングランド軍閥を破りボストンに入城し北東部一帯を占領した。ニューイングランド軍閥の崩壊によってアパラチア以東東海岸では中央政府系軍閥は消滅した。
ニューイングランドの掌握によって自治政府はアメリカのアングロサクソン系が優勢を占める地域の大部分を抑えることになった。この勝利によってラインハルトの党の指導的地位を確固たるものとし、指導者原理を確立した。またその一方で東部における戦争がひと段落したことで自治政府と中央政府・レグルス帝国との全面衝突が現実味を帯びて語られるようになった。 |
ニューイングランド独立宣言
自治政府とレグルスの緊張は、131年12月1日にバージニア沖レグルスの砲艦レオニード・イヴァンが沿岸砲によって撃沈されたイヴァン号事件をきっかけに急速に高まり、両軍は各地に大部隊を展開した。
その緊張の最中にウェストバージニア、チャールストン郊外にあったレグルスREPトランスポート社の鉄道が爆破された(チャールストン事件)。この事件を受けたレグルス政府はアパラチア中央政府が実行犯であると断定し、アパラチア政府による邦人権益侵害を保護するための軍事行動に出ると宣言しニューイングランドへの進駐を開始した。
この動きは自治政府とレグルスが共謀した謀略だった。進駐を受けた自治政府はレグルスと同様に外国権益を突如攻撃した中央政府を非難、ニューイングランド独立国を宣言した。ラインハルトはこれに合わせてアパラチア政府からの保護を名目にレグルスに全土への進駐を要請するとともに、混乱を抑えるため全国戒厳令を布告した。昨日まで敵国だったレグルスの進駐を受け入れよという矛盾した命令に一部では離反や混乱が起こり進駐するレグルス軍との交戦が起こったものの、全体としてレグルス軍の進駐は鉄道を抑えていたこともあって極めて迅速に推移した。進駐は僅か2週間で完了し、ニューイングランドは完全にアパラチアから切り離されることになった。
この間ニューイングランド政府はレグルス帝国による国家承認を受け、続くアンドロメダ=フラガ協定でレグルス権益の保証とレグルス軍による安全保障が明文化された。一方で謀られた事を理解したCELTO諸国はニューイングランド国の承認を拒否した。また以前よりレグルス軍の増派に危機感を抱いていた北連とクラフタリアはニューイングランド国家の解体とレグルス軍の北米からの全面撤退を突きつけた。) |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
経過 |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
ボストン上陸作戦
72時間を期限とした最後通牒が無視されたことで、北連とクラフタリア両国は開戦を決意した。両国は事前に用意されていたニューイングランド地域への進駐作戦に従いボストンへの上陸を発動した。作戦の主力を担当したのは北連軍の6個師団でボストン、ニューヨーク、オーシャンシティ、バージニビーチを占領し後続を待つ計画であった。
しかしながら、この作戦は現状に即したものではなかった。この作戦はもともと反レグルスの現地勢力の支援が得られるという前提の下で組まれた計画で敵前上陸を意図したものではなく、部隊にはそのような作戦を行うための訓練や装備が不足していた。またこの前提のため、作戦上大規模な上陸支援を行うことは想定されておらず、作戦決行にあたっても時間的・地理的制限のために新たに支援を与えることは困難であった。加えて作戦が実行された2月の北大西洋は波が荒く上陸作戦に適した気候ではなかった。
このような杜撰な作戦計画に基づいて行われた上陸作戦が成功するはずがなかった。真っ先に上陸したボストンの部隊は現地勢力の歓迎を受けるどころか痛烈な反撃を受け橋頭保の構築に失敗、僅か36時間で撤退を余儀なくされた。この作戦はもともと政治的な強い要請の下で行われた作戦で、作戦の実行に懐疑的だった作戦司令部はボストンの部隊が強力な反撃を受けたという情報を得た時点で作戦中止を宣言しボストン以外への上陸は行われなかった。 |
北連本土逆侵攻
CELTOのニューイングランド侵攻と失敗の連絡を受けたレグルス指導部は増長し、北連への侵攻作戦を軍に命じた。侵攻にはニューイングランドを守るために派遣された15万の兵員の大多数と大西洋艦隊が充当されることになった。軍はこの投機的な作戦に強く反対し、北極諸島の冬の厳しさや補給の困難さ、相手への大義を与えかねないなどの理由から作戦の中止を求めた。しかし北連侵攻は今ここで北連を下し北米におけるレグルスの優勢を構築すべしという一撃論によって支持され、冬までに勝利すればよいという論法で実行が決定された。なお誤解されがちだが、ここでいう北連の撃破はあくまで条件付き講和を目的としたもので、後世で言われるように北連全域の占領と国家体制の破壊を目指したものではなかった。
北連侵攻作戦"エイリーク"は寒波が落ち着いた5月2日に実行に移された。作戦初期の目標は北連最大の島バフィン島南部の占領で、その後全島を攻略する予定だった。レグルス指導部の見込みでは経済的に重要なバフィン島が陥落した時点で北連は和平に応じるであろうと考えられていた。またもし仮に失敗してもすぐに撤退すれば政治的衝撃は少ないという見込みもあった。
バフィン島侵攻で先陣を切ったのは空挺部隊であった。3万を超える大部隊が奇襲的にバフィン島最南端の都市レニングラードを包囲するように展開し、同都市を陥落させた。こうもあっさりと空挺降下が成功し北連の防空戦力が機能しなかった背景には、政治的・戦略的に本土侵攻はないだろうという油断があり、レグルス側に敵前上陸の動きがなかったこともこれを助長した。実際レグルス軍は空挺部隊による港湾確保に作戦の全てを賭けており、敵前上陸の準備など最初からしていなかった(というより本来ニューイングランドを防衛するための部隊であったため最準備のしようがなかった)。またレグルス軍の海上輸送の動きはレグルス本土からニューイングランドへの兵員輸送に偽装されていた。
レニングラードの陥落は北連全体に衝撃を与え、非常事態を発令し全域での動員を開始した。一方のレグルス軍も増援をレニングラードから送り込み早急な全土制圧に向け北進を開始した。 |
前線の停滞
レグルス軍は追撃と北進を急いだが、北連軍は焦土作戦や地形を知り尽くした市民によるゲリラ戦を展開しレグルス軍の進出を妨害した。最終的にレグルス軍の進撃はバフィン島中央部で停止し、塹壕戦が展開された。
この動きに焦ったのがレグルス指導部である。冬までにこの戦争は終わらせる必要があり、仮にそれが不可能だったとしても北連軍の反攻は阻止しなければならなかった。既にレグルス軍はあまりにも深く進軍しており、当初の計画のような迅速な撤退は不可能であった。そのためレグルス軍はニューイングランドに戦略爆撃機・弾道ミサイル部隊を展開しバフィン島北部を爆撃したが、北連軍の巧妙な偽装や地下陣地、悪天候や照準の甘さなどの複数の要因に阻まれてによってほとんど成果は上がらなかった。
|
冬季大攻勢
そして11月になり、前線が極夜に包まれたところで北連軍は全力攻勢を開始した。元々北極諸島の過酷な環境下に生まれ育ち、そこで訓練を行ってきた北連軍にとっては極夜など大したことはなかったが、南の砂漠で生まれ育ったレグルス兵にとって氷点下10度以下の常に夜という環境はまさに地獄であった。士気を喪失し補給線をゲリラに脅かされたレグルス軍の前線は驚くほどあっさりと崩壊した。レグルス指導部は個々にようやく作戦の失敗を認め撤退を命じた。しかし時期は既に逸しており、撤退命令によってかえって前線の混乱を拡大させた。更にそこでラブラドル海戦による制海権の喪失によってレグルス軍の指揮統制の崩壊は頂点に達し、レグルス軍は崩壊した。最終的にニューイングランド本土から撤退できたのは北連に派遣されたレグルス軍約13万のうち半数にも満たなかった |
imageプラグインエラー : 画像URLまたは画像ファイル名を指定してください。北連軍は極夜の闇に紛れてレグルス軍を撃破していった |
ラブラドール海戦
ラブラドル海戦は132年12月10日にバフィン島南部で起こった海戦である。北連・クラフタリア連合艦隊とレグルス大西洋艦隊が交戦した。
海戦はニューイングランド-北連戦線を繋ぐ補給船団を北連哨戒艦隊が水上襲撃を行ったことで始まった。この船団を守るためレニングラードで現存艦隊主義を取っていたレグルス大西洋艦隊が出撃し、これを迎撃するためCELTO艦隊が動いたことで戦いは瞬く間に大海戦に発展した。
海戦は規模に劣り、輸送船団という荷物を抱え込んだレグルス大西洋艦隊の敗北に終わった。この敗北によってレグルスは大西洋での制海権を失い、大規模な船団輸送が不可能になった。これによって北連本土からの撤退が困難になり、特に重装備の輸送は不可能になった。また兵員の撤退もバラバラの輸送船で襲撃を避けるようにバラバラに行わなければならず、効率が著しく低下した。 |
|
ニューイングランド攻防戦
北連本土での攻防の結果、大西洋でのパワーバランスは完全にCELTO側に傾いた。北連軍を中心とするcelto軍はこれを好機と見做し第二次新英蘭侵攻作戦を計画し、一方のレグルスはニューイングランドを見捨てる決断を下した。
第二次ニューイングランド本土侵攻作戦"春の目覚め"は作戦の北連侵攻作戦と同様に冬が明けた5月に実行されることになった。作戦には総勢15万以上の戦力が投入される予定で、ニューイングランド側の戦力を合わせると事変最大の戦いとなった。
一方、上陸を迎え撃つことになったニューイングランド側の状況は芳しくなかった。大西洋の制海権の喪失によってニューイングランド経済は崩壊を始めており、戦う前から国家が自壊しかねない状況であった。ニューイングランド軍は北連侵攻に関与しなかったため戦力は維持されていたが士気は著しく低下しており、その数も練度と士気を考えればCELTO軍を相手するには不十分だった。やむなくニューイングランドは一時は解散した民兵を再招集したが、これは正規軍よりもなおさら練度も装備も士気も劣り到底役に立つとは思えなかった。また北連本土からの撤退してきたレグルス軍の兵力は大幅に減少しており、敗北によってモラルブレイクも起こしていたためニューイングランド側が期待していたほど役に立つ戦力ではなかった。最終的にニューイングランドが用意できた戦力は正規軍11万と民兵30万に達したが、その内実はごく苦しいものであった。
5月26日、反攻作戦「春の目覚め」作戦が発動された。まず北連軍が第一段階として再びボストンに上陸、今度は上陸作戦のために準備された重武装の部隊で海空軍の支援も十全に受けていた。この動きをある程度予測していたニューイングランド軍は民兵の大部隊を配備していたが、いくら練度の差による影響が小さい市街地戦と言えども質に劣る民兵部隊はボストン市街地戦の激戦後撃破された。ボストンを攻略した北連軍はニューイングランド軍を南北に分断すべくオンタリオ湖に向けて進撃を開始した。
彼我の戦力差から水際防衛しかないと理解していたニューイングランド軍はボストンの即時奪還を図ったが、6月3日にはアパラチア共和国内に展開したCELTO軍がケンタッキーからウェストバージニアに侵攻、南西戦線が形成された。この侵攻も事前に予期されてはいたものの、これに対処すべき戦力は既に払底しており、ポトマック川を防衛線としてバージニアは放棄された。
北部と南部からの圧力に晒されたニューイングランド軍は急速に崩壊していった。6月30日にボストンに上陸した北連軍の先鋒がオンタリオ湖に到達、地理的ニューイングランドを本土から分断し南進に転じた。ポトマック川防衛線も6月終わりまでに全域で瓦解し、7月2日には南部の工業都市ピッツバーグが陥落した。ポトマック川防衛線の崩壊を受け政府は6月25日にバッファローへ移転した。
7月19日、南進を続ける北連軍と北進を続けるクラフタリア軍がペンシルベニアとニューヨークの境界線近くの都市ポートジャービスで邂逅、ニューイングランドは東西に大きく分断された。
この分断は電話線に頼っていたニューイングランドの指揮系統をも分断することになり、西部ではニューイングランド政府が、東部ではニューヨークに残留したカイデル陸相が指揮を取る事態となった。
カイデル陸相は防衛線の縮小の観点から半包囲下にあったボルチモアや各戦線からの撤退を指令し、フィラデルフィアとニューヨークの二都市に防衛戦を絞った。しかしこの動きを知った西部政府はカイデルを撤退禁止命令に違反したとしてカイデル召還、銃殺刑とした。撤退戦中に司令官が不在となったことで東部の指揮系統は瓦解、ニューヨークでの自発的戦闘を除いて大部分がCELTOの手に落ちた。
指揮系統を保った西部でも劣勢は明らかであった。各地でニューイングランド軍・民兵は敗北し戦線は崩壊状態となった。軍はバッファロー都市圏を盾とした最終防衛線を敷いたが、7月30日に突破されバッファローの戦いが生起した。
バッファローの戦いではモラルブレイクを起こしていた軍の士気を高揚させるためラインハルト含む閣僚自身が戦線に出向くなど最後の抵抗が行われた。しかし劣勢はもはやどうすることもできずに8月2日、ラインハルトは自殺し翌日にバッファローは陥落、ニューイングランド独立国が崩壊したことで事変は終結した。 |
imageプラグインエラー : 画像URLまたは画像ファイル名を指定してください。両軍ともに多大な死者を出した |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
結末 |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
レグルス帝国主義への影響
ニューイングランドでの敗北はレグルスの対外拡張における最初の、そしてレグルス戦争を除けば最大の挫折であった。ニューイングランドの崩壊によってレグルスは大西洋艦隊と十万を越えるの将兵とともに北アメリカでの拠点とこれまでの投資の成果を失った。失われた戦力は再建することが可能だったが、新大陸における拠点の喪失はレグルスの対CELTO戦略に大きく影響を与えた。北米に進出する機会を失ったレグルスはその後も南米の
グランタイア合衆国
への介入を進めるなど新大陸への橋頭保獲得を試みたが、ニューイングランドの失敗によって大西洋を越えた大規模な介入に及び腰になり、ついに滅亡まで新大陸に大規模な地盤を築くことができなかった。
しかしながら、ニューイングランドでの失敗がレグルスの政治全体に影響を与えたわけではない。確かに事変の敗北によって事変に関与した軍人や官僚は鋼鉄を受けたが、レグルスの拡大政策や国家体制にはほとんど影響を及ぼさなかった。レグルスの指導部はこの失敗から国民の目をそらし批判を避けるため、プロパガンダを通して問題の矮小化を図った。事変は遠い国での地域的な敗北に過ぎないということにされ、国民の意識はより近隣の紛争地域に遠ざけられた。レグルス人がニューイングランドで負った実際の被害の規模を知るのはレグルス崩壊後に情報が開示されてからであった。 |
ニューイングランドの再編
ニューイングランド独立国の国家機構は本土決戦によって崩壊し、その領土はアパラチアに再統合された。ブライムス・ヨーデルリンゲンを始めとする一部の要人はレグルスに亡命して亡命政権を設立したが、もとよりレグルスからしか承認を受けていない国家の亡命政府はどこからも相手にされず、レグルスからすらも主権組織としての承認は得られなかった。
事変の結果、戦場となったニューイングランドは大きな損害を出した。長年の共産党のずさんな統治もあって経済的な損害が大きく、戦後しばらく餓死者や凍死者が後を絶たなかった。もともと先進地域で高度なインフラに頼っていたことが、インフラの破壊によって裏目に出た形だった。しかも破壊されたインフラや資本を修復するだけの能力はアパラチアにはなく、修復可能な設備も野ざらしのまま放置され壊れていった。北連やクラフタリアもレグルスを追放したことで満足し、外国からの援助も乏十分得られなかった。
社会的な損失も大きかった。ニューイングランド独立国に与した人員のパージや処罰が行われたことで旧来の官僚機構が破壊され、その再建もアパラチアにとっては重荷だった。また社会でも共産党の人種政策から人種間の相互不信が残り社会不安の火種となった。
以上のようにアパラチアはニューイングランドを再統合する機会を得たが、それ以上に破壊されたニューイングランドは負債でしかなかった。結果中央政府は再びニューイングランドへの投資を停止し、再びニューイングランドは中央政府の手を離れることになる。 |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
影響 |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
北連抑留
この事件はその期間において一度も宣戦布告が行われず、あくまで戦争ではなく事変に過ぎなかった。そのため終結も明確な宣言や条約が交わされたわけでもなく、北連本土決戦の際に撤退に失敗し捕虜となった多数のレグルス兵の扱いが問題となった。レグルスは事変以降度々北連に捕虜の返還を要求したが、本土決戦を行い反レグルス感情が高まっていた北連はこれを拒否し続けた。捕虜たちは本土侵攻に対する報復として極寒の地で強制労働に従事させられ、彼らの多くは祖国に帰ることなく息絶えた。レグルス帝国はその後149年にレグルス戦争によって滅亡し彼らは無国籍人となったが、その後レグルスは無政府状態に陥り帰還は叶わなかった。更にその後起こった仏連=celto戦争で北連は滅亡した。抑留された彼らは北連からの脱出を目指したが、彼らの扱いは北連人より扱いが低かったため、ここでも多くの犠牲が出た。約2万とされる抑留捕虜のうち、故郷に帰れたのは300人程度であるとされている。 |
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
ニューイングランド独立国
| 国家概要 |
|
| 国名 |
ニューイングランド独立国 |
| 建国 |
統一暦131年12月19日
2020年3月18日 |
| 政治体制 |
ニューイングランド社会主義
国家社会主義 |
| 指導者 |
ロジャース・ヴォルガ・ラインハルト |
| 領域 |
北アメリカ東海岸北部地域 |
| 同盟国 |
レグルス第二帝国
|
| 首都 |
ニューヨーク |
| 通貨 |
新英蘭ドル |
ニューイングランド独立国(Indipendent State of New England)もしくはニューイングランド独立帝国(Independent Reich of New England)はかつて北米に短期間存在したレグルス帝国の傀儡国家。ニューイングランド事変中にレグルス帝国によって成立したが、翌年にCELTO軍の総攻撃を受けて崩壊した。その存在期間中レグルス以外からの国家承認を受けることはなかった。
首都はニューヨークとされていたが、その僅かな存在期間中に複数回移転した。その領土はニューイングランドに留まらず、バージニアまでの広大な領土を保持した。
国名
正式名称はニューイングランド独立国、現地語表記はIndependent State of New Englandとなる。この名称はニューイングランド独立宣言、およびその後に布告されたニューイングランド独立国家布告1号で規定されている。
漢字表記では新英蘭独立国となり、古い文献ではこの表記がしばしば見られる。
またレグルス帝国ではニューイングランドの政治体制が自国の体制と類似することからニューイングランド独立帝国と呼ばれることもあったが、現在ではほとんど使われていない。
歴史
前史
120年代当時、ミシシッピ川以東の地域は親CELTOの
アパラチア連邦共和国の領土であった。しかしアパラチアの中央集権化は殆ど進んでいなかった。元々地域主義の強い中部北アメリカでは分権派・分離独立派の活動が活発で、その傾向は特に共和国の中心である西部から遠い海岸部で顕著だった。当時CELTOとの対立を強めていたレグルスはこの弱みに漬け込み北米の橋頭堡とすることを画策した。
当初レグルスは不安定なアパラチア政府を利用することを計画していた。
バージニア事件のような武力脅迫や、後に判明するアパラチア政府内への侵入、親レグルス派ロビーへの資金援助などがこれにあたる。
この計画はボストン協定による東部三州(バージニア・ロードアイランド・ニュージャージー)への駐屯権確保やニューアーク条約による鉄道敷設権の獲得など一定の成果を挙げたものの、内陸に本拠地を置くアパラチア政府にはレグルスの砲艦外交のインパクトが薄く脅迫の効果が薄く漸進的な成果を挙げるにとどまり、急進的なレグルス政府を満足させるものではなかった。またレグルス帝国の新大陸への目に見える拡大はCELTO諸国、特に北連とクラフタリアの危機感を煽り、これ以上の成果獲得は困難なものになった。そのためニューアーク条約以降レグルスはアパラチアの地方勢力と協同する方針に転換する。
レグルスはこの弱みに付け込み
バージニア事件のような武力脅迫や政治ロビーを通じた誘導によって影響力を高めた。しかしこの動きはCELTO諸国の危機感をあおり、急進的なレグルス政府を満足させるものではなかった。またレグルス帝国の新大陸への目に見える拡大はCELTO諸国、特に北連とクラフタリアの危機感を煽り、これ以上の成果獲得は困難なものになった。そのため東海岸での鉄道敷設権を承認したニューアーク条約以降、レグルスはアパラチア中央政府ではなく軍閥勢力と協同する方針に転換する。当時アパラチアで最も独立の機運が高かったのはフロリダ半島だった。レグルス帝国はこの独立運動に武器援助を送るなどして支援した。その結果129年のフロリダ事件ではフロリダ・エスパニア共和国が独立を宣言したものの、CELTO連合軍の迅速な介入によって共和国はわずか1週間で崩壊した。
レグルス帝国はフロリダの失敗をレグルス北米権益の中核である北東部から離れていたために介入が遅れたこと、事件の規模が小さかったことが原因だと分析、アパラチア東北部を支配し以前から接触のあったニューイングランド共産党との正式な提携を決断した。
ニューイングランド共産党はその名の通り社会主義政党ではあったが、社会ダーウィニズムやロシア的社会主義の影響を受けた組織で南北アメリカで支配的な民主社会系の組織とは一線を画していた。またWASPによって構成された民族主義的な側面を持ち、どちらかというと多民族・カトリック的なアパラチア中央からのニューイングランド(ここでは中部アメリカ東岸のWASP優勢の地域)の独立を唱える民族主義的な性格も有していた。そのためニューイングランド共産党はアパラチア中央政府からは排除対象とされていた。
125年から130年にかけてニューイングランド共産党は以前から保有していた準軍事組織"レッドライン"を急速に発展させ、その支配領域を武力で拡大していた。その影響力は日増しに高まり続け、アパラチア中央からの分離独立も現実味を帯びていた。しかし実際に独立を宣言すればCELTOの介入は確定的で、それに対処する能力は共産党にはなく支援を必要としていた。またニューイングランド共産党の掲げるニューイングランド社会主義は同時期に高揚したレグルスの国家社会主義と相互に影響を与えあっており、党指導者のラインハルトを始めとしてレグルスとイデオロギー的共感を覚える者は少なくなかった。そのためこのレグルスの申し出はニューイングランド共産党にとっては渡りに船といえるものだった。
しかしニューイングランド共産党とレグルスの関係はCELTOにとっては全く予期せぬことだった。レグルス帝国の反共主義は広く知られており、仮にも共産党と名のついた組織と提携するなど考え難い事だった。全くそのような意見が上がらななったわけではなく、一部の識者はニューイングランド共産党とレグルスの国家社会主義思想の類似点や武器取引疑惑を指摘したものの、それらの考えが広く支持されれる事はなかった。
ニューイングランド共産党は130年に東海岸最大の都市ニューヨークを包囲戦の末に攻略した。ラインハルトは東アパラチア自治政府の成立をアパラチア中央政府の同意なしに宣言した。介入する能力のないアパラチア政府はこの宣言を否定はしたものの、それ以上の行動をとる事はなかった。
一方でレグルス帝国にとってはこれらの動きは共産党との密約で連絡されていた既定事項ではあったが、対外的には自治政府に敵対的な反応を示し駐屯地・鉄道附属地への軍増派を繰り返した。自治政府は建前上この動きに抗議したものの敢えて弱腰な姿勢を見せ、ラインハルトはこれに反発した党員を粛清し地盤固めを行った。この両者の動きについてCELTOは完全に黙認しており、その裏には両者共倒れが最も利益になるという打算があった。
131年にはニューイングランド共産党がコンコードの戦いでジョン・プレストン・ガービー隷下のニューイングランド軍閥を破りボストンに入城し北東部一帯を占領した。ニューイングランド軍閥の崩壊によってアパラチア以東東海岸では中央政府系軍閥は消滅した。
ニューイングランドの掌握によって自治政府はアメリカのアングロサクソン系が優勢を占める地域の大部分を抑えることになった。この勝利によってラインハルトの党の指導的地位を確固たるものとし、指導者原理を確立した。またその一方で東部における戦争がひと段落したことで自治政府と中央政府・レグルス帝国との全面衝突が現実味を帯びて語られるようになった。
独立国の成立
自治政府とレグルスの緊張は、131年12月1日にバージニア沖レグルスの砲艦
レオニード・イヴァンが沿岸砲によって撃沈された
イヴァン号事件をきっかけに急速に高まり、両軍は各地に大部隊を展開した。
その緊張の最中にウェストバージニア、チャールストン郊外にあったレグルスREPトランスポート社の鉄道が爆破された(
チャールストン事件)。この事件を受けたレグルス政府はアパラチア中央政府が実行犯であると断定し、アパラチア政府による邦人権益侵害を保護するための軍事行動に出ると宣言しニューイングランドへの進駐を開始した。
当然、この動きは自治政府とレグルスが共謀した謀略だった。進駐を受けた自治政府はレグルスと同様に外国権益を突如攻撃した中央政府を非難、
ニューイングランド独立国を宣言した。ラインハルトはこれに合わせてアパラチア政府からの保護を名目にレグルスに全土への進駐を要請するとともに、混乱を抑えるため全国戒厳令を布告した。昨日まで敵国だったレグルスの進駐を受け入れよという矛盾した命令に一部では離反や混乱が起こり進駐するレグルス軍との交戦が起こったものの、全体としてレグルス軍の進駐は鉄道を抑えていたこともあって極めて迅速に推移した。進駐は僅か2週間で完了し、ニューイングランドは完全にアパラチアから切り離されることになった。
この間ニューイングランド政府はレグルス帝国による国家承認を受け、続く
アンドロメダ=フラガ協定でレグルス権益の保証とレグルス軍による安全保障が明文化された。一方で謀られた事を理解したCELTO諸国はニューイングランド国の承認を拒否した。また以前よりレグルス軍の増派に危機感を抱いていた北連とクラフタリアはニューイングランド国家の解体とレグルス軍の北米からの全面撤退を突きつけた。
レグルス帝国・ニューイングランド政府がこの要求を拒否すると北連とクラフタリアは以前から準備されていたボストンへの海上侵攻を開始した。しかしこの侵攻は事前予測よりもニューイングランド軍が精強であったために港湾の確保に失敗、撃退されることになった。(
第一次ボストン攻防戦)
中期
第一ボストン攻防戦後、集団安全保障を事由にレグルス帝国は北連本土へ侵攻したが、ニューイングランドは後方支援にとどまり実際に北連本土に人員を送る事はなかった。
独立国の首相兼大統領となったラインハルトは国家組織の確立に注力した。秘密警察ベルガの創設やレグルスを規範とした法整備がそれにあたる。
CELTO軍が本格的な反撃に転じた事変中期以降はニューイングランド全体が爆撃・通商破壊に晒された。国土の多くがメガロポリスに属する人口密集地であるニューイングランドでは戦略爆撃によって多大な死傷者を出した。また工業製品の輸出や食糧の輸入がアパラチア政府との関係断絶や諸外国からの禁輸で停滞し、レグルスとの貿易も通商破壊によって途絶したことでニューイングランドは経済的に破綻していった。特に食糧輸入が滞ったことでニューイングランドの大都市では戦後しばらくまで飢餓状態が続いた。
本土侵攻と崩壊
レグルス軍による北連侵攻はラブラドル海戦の敗北によって失敗が濃厚となった。制海権を喪失しつつあった事実をレグルス政府はニューイングランド政府に伝えなかったが、レグルス海軍の艦艇が明らかに減少していることやCELTOによる通商破壊の規模が拡大していることで何が起こっているかは凡そ推し量ることができた。
実際には北連侵攻が失敗した時点でレグルスは今次事変での敗北を受け入れており、残存戦力の可能な限りの脱出を決定していた。この時点でニューイングランドはレグルスから見捨てられていただった。
しかし北連本土から撤退してきたレグルス軍の惨状を見たフランベレー・シュタイナー親衛隊指導者の提言によってニューイングランド国内ではレグルス軍を差し置いて独自に本土決戦への準備を進めた。
ニューイングランドの各地の工場では鉄パイプを加工した簡易な火器が量産され、自治政府時代の民兵組織を利用して市民の動員が進んだ。市街地や海岸では侵攻を防ぐための障害物の設置や有事の際の避難・動員計画が練られた。だがこれらの動きは物質的困窮によって滞った。
133年5月26日にCELTO軍による本土侵攻が始まった(
春の目覚め作戦)。第一次攻撃を受けたのは再びボストンだった。このCELTO軍の動きを事前に察知していたニューイングランド・レグルス両国はレグルス残存兵と民兵を多数投入して防戦に当たった。この部隊は装備で大きくCELTO軍に劣っていたがよく奮戦し、一時は撤退寸前に追い込んだ。しかし最終的に火力で圧倒され後退を余儀なくされ、掃討戦によって壊滅した。
また6月3日にはアパラチア共和国内に展開したCELTO軍がケンタッキーからウェストバージニアに侵攻、南西戦線が形成された。この侵攻も事前に予期されてはいたものの、これに対処すべき部隊は既に払底しており、ポトマック川を防衛線としてバージニアは放棄された。
北部と南部からの圧力に晒されたニューイングランド軍は急速に崩壊していった。6月30日にボストンに上陸した北連軍の先鋒が五大湖に到達、地理的ニューイングランドを本土から分断し南進に転じた。ポトマック川防衛線も6月終わりまでに全域で瓦解し、7月2日には南部の工業都市ピッツバーグが陥落した。ポトマック川防衛線の崩壊を受け政府は6月25日にバッファローへ移転した。
7月19日、南進を続ける北連軍と北進を続けるクラフタリア軍がペンシルベニアとニューヨークの境界線近くの都市ポートジャービスで邂逅、ニューイングランドは東西に大きく分断された。
この分断は電話線に頼っていたニューイングランドの指揮系統をも分断することになり、西部ではニューイングランド政府が、東部ではニューヨークに残留したカイデル陸相が指揮を取る事態となった。
カイデル陸相は防衛線の縮小の観点から半包囲下にあったボルチモアや各戦線からの撤退を指令し、フィラデルフィアとニューヨークの二都市に防衛戦を絞った。しかしこの動きを知った西部政府はカイデルを撤退禁止命令に違反したとしてカイデル召還、銃殺刑とした。撤退戦中に司令官が不在となったことで東部の指揮系統は瓦解、ニューヨークでの自発的戦闘を除いて大部分がCELTOの手に落ちた。
指揮系統を保った西部でも劣勢は明らかであった。各地でニューイングランド軍・民兵は敗北し戦線は崩壊状態となった。軍は
バッファロー都市圏を盾とした最終防衛線を敷いたが、7月30日に突破されバッファローの戦いが生起した。
バッファローの戦いではモラルブレイクを起こしていた軍の士気を高揚させるためラインハルト含む閣僚自身が戦線に出向くなど最後の抵抗が行われた。しかし劣勢はもはやどうすることもできずに8月2日、ラインハルトは自殺し翌日にバッファローは陥落した。バッファローは国境に程近かったにも関わらず閣僚の多くが亡命を選ばず戦死、あるいは自殺している。
一連の本土決戦によってニューイングランド独立国は建国から僅か1年と半年で崩壊した。ナイアガラ川を越えたか船舶・航空機で脱出を果たした数少ない政治家・軍人はレグルスに亡命した。しかしレグルス帝国指導部はニューイングランド事変での敗戦を隠したがっており、また彼らの多くが共産党出身であることから、彼らの多くは冷遇されるか適当な理由をつけて監視下に置かれることが多かった。例外的に経済相であったバルオベリ・シグナスはレグルスとのコネクションを活かしてレグルス政府に参入、
レグルス戦争時には同じく経済相の地位にまで上り詰めた。
地理
中部アメリカ北東部、アパラチア山脈東部沿岸地域の領土を支配した。その領土はアパラチア連邦共和国のメイン以南ヴァージニア以北の北東12州と一致する。
主な都市
ボスウォッシュをはじめとする世界有数の都市化された地域を領内に持ち、大都市を多数擁していた。
首都
- フィラデルフィア
- ボストン
- ピッツバーグ
- バッファロー
行政区分
メイン州
ニューハンプシャー州
バーモント州
マサチューセッツ州
ロードアイランド州
コネチカット州
ニューヨーク州
ニュージャージー州
ペンシルベニア州
キーストン州(ウェストペンシルベニア州)
デラウェア州
メリーランド州
バージニア州
国民
人口動態
ニューイングランド独立国の正確な人口統計は存在しない。参考となるデータは東アパラチア自治政府時代の130年に行われた国勢調査である。
内務省が行ったこの調査によれば総人口は6982万人だった。そのうちアングロサクソン人は48%、それ以外の白人が26%、有色人種が25%、1%がユダヤ人だった。
差別・迫害
ニューイングランド共産党はアングロサクソン優位の白人至上主義を掲げていた。そのため自治政府時代から社会階級としてアングロサクソン>ゲルマン系>ラテン系>有色人種の階層が構築された。またユダヤ人は国際資本家の手先として白人であるにも関わらず強力に迫害された。ユダヤ人迫害はしばしば公のコントロールを越える場合もあり、133年のリッチモンドで起きた虐殺ではユダヤ人が魔女の手先として古典的な魔女裁判に掛けられて火炙りで処刑されることもあった。
差別の程度の指標としてはアングロサクソンが一級、ゲルマン系が準一級としておおよそ完全な市民権を得ていた。ラテン系は表面上アングロサクソン系と同様に扱われたものの、内在的な差別や個々人による差別が強かった。有色人種・ユダヤ人は公的な強制力を伴う差別対象となり、財産没収や私刑、良い場合でも人種隔離の対象であった。黒人差別が最も強力だったのはバージニアで、バージニアでは黒人を手当たり次第に何かしら適当な違法行為で検挙し囚人として奴隷労働させることが横行していた。
国家体制
ニューイングランド独立国の行政府であるニューイングランド国家政府はニューイングランドの国家行政の最高機関だった。国家政府は総統であるロジャース・ラインハルトを頂点とする独裁政権であり、その形態は国家社会主義を掲げ、ニューイングランドの実質的な宗主国であるレグルス第二帝国の体制を模倣・修正したものだった。
ニューイングランド独立国はラインハルトを絶対的指導者とする指導者原理が敷かれた。この原理の下で国家体制は全面的に総統の権力と結びつき、厳格に統制された。ラインハルトは特に官僚機構・軍事作戦の子細な部分へ度々介入しプロセスを混乱させたが、この介入を正当化したのも指導者原理だった。
ニューイングランド独立国の政府・官僚機構は東アパラチア自治政府のものを継続・発展させたものだった。東アパラチア自治政府はニューイングランドの独立宣言後の131年12月29日にラインハルトが署名した
国家政府編成に関する指令によってニューイングランド国家政府へと再編された。この指令によって国家政府はニューイングランドの行政権を掌握する唯一の機関であると宣言され、総統への忠誠と責任が確認された。しかしこの指令とそれに伴う再編は形式的なもので、政府の原型は殆ど自治政府時代に完成していた。指令による変更は名称変更などの独立国家としての体裁を整えるための小さなものだった。
戦後CELTOはニューイングランド独立国の非合法を再宣言したが、内務相と法務相を務めたブライムス・ヨーデルリンゲンを中心にレグルス帝国へ亡命した一部の要人はニューイングランド独立国亡命政府を組織した。亡命政府はレグルス戦争中に
レグルス領ルークリア
に疎開し、戦後は独立したルークリア国内で活動を継続した。亡命政府は151年のヨ―デルリンゲンの死まで活動した。
政治理念
ニューイングランド独立国はラインハルトと彼の共産党の政治的意志に従属する国家だった。ニューイングランド共産党は公式にはマルクスレーニン主義政党だったが、ラインハルトとともにホワイトパワー(白人至上主義)と反新大陸民主主義思想の影響を強く受けていた。このため思想的に国家社会主義方面へ傾倒していき、世界で唯一の国家社会主義国であったレグルスとの接近をもたらした。
ニューイングランド社会主義はラインハルトが提唱したニューイングランド共産党の公式イデオロギーである。ニューイングランド社会主義は強い中央集権、民主集中制、そして社会ダーウィニズムを基盤としている。ニューイングランド社会主義の支持者は自身を共産主義者だと定義しているが、殆どの共産主義勢力や政治学者はこの見解を否定している。
党国体制
ニューイングランドの成立後、ニューイングランド共産党はニューイングランド人を代表する組織でありニューイングランド国家と不可分の存在であると宣言された。自治政府時代から政府は共産党の人員で構成され共産党のイデオロギーに従っていたが、アパラチアの中央に配慮する形で形式上政府と党の関係はあいまいで、非公式なものだった。しかしアパラチアからの独立後は共産党と政府の関係は公式なものとなり、それまであくまで非公式に行われていた反共産党勢力の排除に公的な承認が下りる形になった。
統治機構
東アパラチア自治政府時代から政府の統治機構を共産党のイデオロギーに従属させる試みが行われてきた。アパラチアの特徴である連邦制・強い地方自治は否定されその実質的権力を中央に奪われ、独立国成立にあたって地方政府は公式にその権能を内務省地方行政局に奪われた。
またアパラチアの民主的システムは軍閥時代の始まりからその機能を殆ど停止していたが、それはニューイングランドでも例外ではなかった。ニューイングランド共産党は民主集中制・指導者原理の観点から新大陸的民主主義を否定し、政府組織から民主的プロセスを排除し、指導部への絶対的忠誠へと置き換えていった。この反民主主義思想の影響は閣議の形骸化や市議会の廃止など広範に及んだ。
法制度
ニューイングランドの法制度は新大陸的民主主義思想からの脱却として旧来の英米法系からレグルスと同様の大陸法への移行が行われ、実際に憲法に相当するニューイングランド独立国憲章などに見られるようなレグルスを模範とした法体系への置き換えが進められた。しかし実際には物質的・時間的コストの問題などからほとんどの法律は自治政府時代から変更されていなかった。そもそも長年英米法の下で統治されてきたニューイングランドには大陸法を専門とする法律家が不足しており、全面的な法改正は最初から現実的ではなかったとする指摘もある。
治安政策
共産党の支配地域では反体制派・有色人種に対する苛烈な弾圧が存在した。この弾圧の主体は共産党の私兵であるレッドラインであったが、民兵に過ぎず統制の行き届いていない彼らはしばしば統制を離れて暴走することがあった。このため自治政府時代からレッドラインの縮小や統制の強化が行われた。当初は軍事上の必要性や幹部の反対(レッドラインの指導部は概して反ラインハルト的だった)に遭い統制はうまくいかなかったが、正規軍である政府軍の存在感の拡大やラインハルトの絶対的支配の確立によって抵抗は徐々になくなっていった。ニューイングランド成立前夜の130年にレッドラインは解散に追いやられた。
解散されたレッドラインに代わって反体制派弾圧を行ったのがベルガである。ベルガは自治政府時代に構想されてラインハルトの承認を受けていたが編成に難航しその成立はニューイングランドの成立後となった。ベルガは正式名称を法権威執行局(BELGA, Breau for Enforcement of Law and General Autority)という。実働部隊はベルガの編成・運用の責任者であったブライアム・クィンガルがレッドラインの中から抽出した「政治的に信頼できる部隊」であり、レグルス親衛隊の指導を受けた。このためベルガは統率された暴徒に過ぎなかったレッドラインよりも遥かに高度な秘密警察として完成し、その制服の色から「赤黒のベルガ」として恐れられた。しかし戦後にはベルガの隊員は市民や有色人種による報復の対象となった。
閣僚
| 役職 |
氏名 |
出身 |
その他の役職 |
備考 |
| 総統 |
ロジャース・ヴォルガ・ラインハルト |
ニューイングランド共産党 |
ニューイングランド共産党指導者
大統領及び首相を兼任
国防軍最高司令官 |
131年~133年(自殺) |
| 内務大臣 |
ブライムス・ヨーデルリンゲン |
ニューイングランド共産党 |
法務相兼任
ニューイングランド独立国亡命政府主席(134年~151年) |
131年~133年 |
| 法務大臣 |
同上 |
- |
内務相兼任 |
131年~133年 |
| 経済大臣 |
バルオベリ・シグナス |
無所属 |
レグルス帝国経済相(144年~146年) |
131年~133年 |
| 外務大臣 |
サラヴァ・アンドロメダ |
ニューイングランド共産党 |
|
131年~133年(暗殺) |
| 外務大臣代行 |
ユリウス・フリック |
ニューイングランド共産党 |
共産党官房 |
133年 |
| 国民啓蒙・宣伝大臣 |
ヨーゼフ・ゲッペルス |
ニューイングランド共産党 |
国防軍上級大将
国民義勇軍司令官 |
131年~133年(自殺) |
| 陸軍大臣 |
ショーペンバウア・カイデル |
無所属
陸軍 |
陸軍元帥 |
131年~133年(銃殺) |
| 刑事大臣 |
ブライアム・クィンガル |
ニューイングランド共産党 |
ベルガ総監 |
131年~133年(戦死) |
| 無任所大臣 |
フランベレー・シュタイナー |
ニューイングランド共産党 |
親衛隊元帥(親衛隊最高司令官) |
131年~133年(自殺) |
ロジャース・ヴォルガ・ラインハルト
|
+
|
... |
新英蘭独立国総統。ニューイングランド共産党指導者。レグルス第二帝国の国家社会主義運動に共感し協働、ニューイングランド独立国を建国した。レグルスの傀儡とみなされているが、レグルス帝国と対等な国家を建設することを目指していた。。
事変末期のバッファローの戦いにおいて自殺、遺体は彼の命令によって最後の拠点であったバッファロー市庁舎とともに破壊された。
|
ブライムス・ヨーデルリンゲン
|
+
|
... |
ラインハルト内閣で内務省と法務相を兼任。ニューイングランド共産の最古参でありラインハルト政権の事実上のナンバーツーであった。
事変末期に独自に降伏交渉を行うも失敗、戦後はレグルスに逃れ亡命政府を組織した。亡命政府はレグルス戦争中にレグルス領ルークリアに疎開し、戦後は独立したルークリア国内で活動を継続した。亡命政府は151年にヨ―デルリンゲンが死去するまで活動した。
|
バルオベリ・シグナス
|
+
|
... |
独立国経済相。ニューイングランド出身の経済学者。共産党員ではなかったが、ラインハルトとは旧知の仲でそのコネで就任を依頼された。戦後はレグルス第二帝国に亡命し経済学者に復職、国家社会主義経済と計画経済を支持する理論構築を行いレグルス政府に重用された。 レグルス戦争時には経済相にまで上り詰めた。レグルス戦争後にはレグルス領バングラディシュにさらに亡命、継承順位規則によってレグルス亡命政府臨時大統領となったが150年にアンドレイア・レヴィツェンスクのクーデターによって捕らえられ処刑された。その名はレグルス国民国の国営企業である シグナス国家工場に残されている。
|
サラヴァ・アンドロメダ
|
+
|
... |
外務大臣。ラインハルト内閣唯一の女性閣僚であった。特に親レグルス的な人物で知られ、レグルスの特権的地位を認める アンドロメダ=フラガ協定を結んだ。
ニューイングランド攻防戦の初期に現地レジスタンスにより殺害された。
|
ユリウス・フリック
|
+
|
... |
外務次官。アンドロメダの死後に外務大臣代行に就任したが、具体的な活動を行う前にニューイングランドが崩壊した。
戦後行方不明となった。
|
ヨーゼフ・ゲッペルス
|
+
|
... |
ニューイングランド共産党の古参メンバーの一人。過去には改革派の主要人物とみなされていたが、綱領派の優位を悟る綱領派の中で頭角を現しつつあったラインハルトに接近した。ラインハルト内閣では宣伝相を勤め独立国の正統性向上・戦争プロパガンダを積極的に広めた。本土決戦が迫ると民兵の再招集を提言し、自ら国民義勇軍司令を務め自殺的戦闘に国民を動員した。
バッファローの戦いでラインハルトの後を追い自殺。
過去の人物であるヨーゼフ・ゲッベルスに心酔しており、共産党での活動名としてその名を取った。そのため実名はまた別にあると思われるが、それについての資料は残っていない。
|
ショーペンバウア・カイデル
|
+
|
... |
陸軍大臣。ニューイングランドには海空軍がなかったため事実上全軍の司令官だった。レグルス第二帝国からニューイングランド軍を援助するとともに監視するため送り込まれた顧問の一人。レグルス陸軍中将であった。
第二次新英蘭攻防戦において撤退戦を指揮、命令違反により銃殺刑に処された。
|
ブライアム・クィンガル
|
+
|
... |
刑事大臣。軍閥時代から共産党の下で反体制派摘発を仕事とし、東アパラチア自治政府成立後は国内の警察機構を掌握し反体制派を掃討した。また秘密警察ベルガを独自に創設し国内の治安維持において大きな役割を果たした。
第二次新英蘭攻防戦バッファローの戦いにて戦死。
|
フランベレー・シュタイナー
|
+
|
... |
ニューイングランド親衛隊指導者。ラインハルトに心酔しておりその忠誠心から親衛隊司令に抜擢された。ピッツバーグの戦いでcelto軍に包囲、終戦まで抵抗するも終戦と共に部隊の武装解除を命じた後自殺。
|
外交
独立宣言の直後、レグルスはニューイングランド国家の独立を承認した。北連・クラフタリアは独立宣言を拒絶し、アパラチア連邦共和国からの分離独立は全て違法であると宣言した。
その成立から滅亡までニューイングランドを正式に国家承認した国家はレグルスのみだったが、OFC各国や親OFC国家はニューイングランドの代表に認可状を与え事実上国家として承認する姿勢を見せた。
外交活動
ニューイングランドでの外交活動は首都と宣言されたニューヨークで行われ、大使館・領事館はいずれもニューヨーク市内に置かれていた。しかし133年には本土侵攻の危険が高まったとしてバッファローに移転した。
軍事
ニューイングランドの国軍であるニューイングランド国防軍は前身の東アパラチア自治政府軍をそのまま引き継ぐ形で建国と同時に成立した。国防軍には当初陸軍と艦隊、航空隊があり、事変後期には民兵組織として国民義勇軍が設置された。艦隊、航空隊は将来的に海軍、空軍に発展するものとされていたが、ニューイングランドの滅亡によって行われることはなかった。
国民義勇軍は事変後期、本土決戦が現実味を増していた時期に設置された民兵組織であり、国防軍に編入するほどでもない人員を戦力化するための組織だった。彼らは後方任務を行うことで正規軍を支援することが目的であり、正面戦闘に投入することは避けるものとされていた。しかし実際には義勇軍司令官であったゲッペルスの意向もありまともな武器も持たされず露払い・弾除けとして積極的に危険な戦闘に投入され大きな損害を出した。
国軍以外の軍事組織としてはレグルスの親衛隊を参考に作られた総統親衛隊が存在する。秘密警察としてベルガが既に存在したニューイングランドでは秘密警察を兼ねていたレグルスの親衛隊と異なり純粋な警備隊・軍事組織だった。親衛隊はレッドラインや政府軍から引き抜かれた精鋭で構成されたエリート部隊であり、戦闘の要所要所で投入された。親衛隊は装備面や待遇面で優遇を受け、総統への忠誠も高かった。最後の戦場となったバッファローの戦いでも最後まで戦闘を続けたのは親衛隊の大統領直衛であったと言われている。
経済
計画経済
共産党は国家全体の統制を党是としており、言うまでもなく経済もその対象であった。自治政府時代から共産党の支配地域では企業の国有化や国主導の強制的な企業合併が繰り返された。この政策は当初こそ経営効率化の成果を上げたが徐々にその非効率性が明らかになっていった。しかし共産党はあくまで計画経済にこだわり、経済悪化の責任をユダヤ人を中心とする「寄生人種」や内部の第五列に転嫁した。このような抜本的対策のない中で内戦によって疲弊していた国民経済はさらに低迷し、過去には世界有数の経済地域であった東海岸の経済力は低下していった。一般にニューイングランドの経済は事変末期の海上封鎖やインフレによって破滅したと言われているが、独立国の成立時点で破綻に片足を突っ込んでいたというのが今日の主流な見解である。
戦時経済
ニューイングランドの経済は額面上世界有数のものがあったが、上記の事情やサービス業を主体としていた経済構造から実行工業生産力は意外なほど小さかった。そのため戦時経済に移行しとしても指導部が予想したほどの生産能力を得られなかった。それでも指導部の提示したノルマを達成するため数字の滅裂な改ざんや製品の濫造、無理な動員が行われ更に生産力は低下していった。末期にはこれまでの経済的失敗や封鎖によってニューイングランド経済は大混乱に陥り、133年には総生産が10年前の半分までに低下し、大量の餓死者・凍死者をも出すことになった。
通貨
法定通貨は独立国成立後に発行されたニューイングランドドルだった。ニューイングランドドルには補助通貨としてニューイングランドセントがあった。しかし実際には戦争の混乱もあって発行と兌換が間に合わず、以前から用いられた東アパラチアドルが引き続き用いられた。しかしこれも事変後期から激しいインフレが始まり、インフレ率は1万を超えた。そのため市民は中央アパラチアドルやエメラルドといった外国通貨や物々交換を行った。こうした非法定通貨を用いた取引は違法であり取り締まりの対象だったが、弾圧の結果却って取引が地下化し実態を把握できなくなってしまった。
交通
鉄道
東海岸ではニューイングランド独立国成立以前からレグルスに鉄道敷設権が与えられていた。REPトランスポートはレグルス帝国の国営鉄道会社であり、自治政府時代から幹線鉄道や沿線開発を主導した。
最終更新:2025年02月01日 16:22