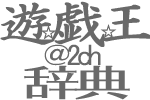禁止カード(きんしかーど)
OCGで、「あまりに強すぎた、矛盾していてルールに混乱をきたす」等の理由で公式大会で「一枚もデッキに入れてはならない」という制限を受けたカードのこと。
遊戯王以外の多くのTCGでも一般的に使用される用語で(*1)、それらの場合、「時代に合わない(*2)」などの理由もある。
OCGでは半年に一度、環境の変化などを考慮して改定される。大抵、禁止と同時にカードの値段が暴落し、逆に禁止が解除されると暴騰するため、
改訂の発表前はこれを当て込んだカードの売買が行われ、デュエリストは発表と同時に一喜一憂する事に。
OCGにおける半年に一度の大イベントである。
遊戯王以外の多くのTCGでも一般的に使用される用語で(*1)、それらの場合、「時代に合わない(*2)」などの理由もある。
OCGでは半年に一度、環境の変化などを考慮して改定される。大抵、禁止と同時にカードの値段が暴落し、逆に禁止が解除されると暴騰するため、
改訂の発表前はこれを当て込んだカードの売買が行われ、デュエリストは発表と同時に一喜一憂する事に。
OCGにおける半年に一度の大イベントである。
ちなみに「一枚なら入れてよい」が制限カードであり「二枚まで入れてよい」が準制限カード。
TCGによっては稀に大会レギュレーションではなく、カードそれ自身がこれは制限カードだというルールをもつものがある。
TCGによっては稀に大会レギュレーションではなく、カードそれ自身がこれは制限カードだというルールをもつものがある。
元々OCGで使用されない前提で刷られた、デュエルで使用出来ない特別なカードもあるが、これは一般的には禁止カードとは呼ばず使用不可カードと呼ばれる。
OCGでは世界大会の賞品であるマッチキルモンスター、アニメではKCグランプリ編で登場した《シュトロームベルクの金の城》がこれに該当する。
OCGでは世界大会の賞品であるマッチキルモンスター、アニメではKCグランプリ編で登場した《シュトロームベルクの金の城》がこれに該当する。
原作バトルシティ編では、「プレイヤーに直接ダメージを与えるカードや、モンスターを破壊するカードは使用不可」と言う形で禁止カードが制定されている。
ただ、《千本ナイフ》や《エネミーコントローラー》等の例外もあるので、詳しい所は不明。
しかし、前者は黒魔術師が場に存在していることが発動条件、後者はライフコストが存在するので、条件(≒デメリット)の有無が分かれ目なのかも知れない。
また、《死者蘇生》は制限カードとして扱われている。
ただ、《千本ナイフ》や《エネミーコントローラー》等の例外もあるので、詳しい所は不明。
しかし、前者は黒魔術師が場に存在していることが発動条件、後者はライフコストが存在するので、条件(≒デメリット)の有無が分かれ目なのかも知れない。
また、《死者蘇生》は制限カードとして扱われている。
アニメでは、GXにおいて《混沌帝龍 -終焉の使者-》が禁止カードだと語られている。
また、GXにおける《強欲な壺》のように、OCGで禁止されるとアニメでも使用されなくなる傾向がある。
《死者蘇生》は5D'sの放映開始の時点では禁止カードと制限カードをフラフラしていたため5D's劇中で一度も使用されていないが、
ZEXAL放映開始の頃はすでに制限カードが定着していたため、劇中で多用されている。
また、GXにおける《強欲な壺》のように、OCGで禁止されるとアニメでも使用されなくなる傾向がある。
《死者蘇生》は5D'sの放映開始の時点では禁止カードと制限カードをフラフラしていたため5D's劇中で一度も使用されていないが、
ZEXAL放映開始の頃はすでに制限カードが定着していたため、劇中で多用されている。
OCGにおける原作出身の禁止カードは《ハーピィの羽根帚》《現世と冥界の逆転》《王家の神殿》など多数存在する。
アニメGXからは《D-HERO ディスクガイ》と《未来融合-フューチャー・フュージョン》、
アニメ5D'sからは《ダーク・ダイブ・ボンバー》と《ゴヨウ・ガーディアン》が禁止カードに指定されている。
ちなみに、《ダーク・ダイブ・ボンバー》は、《混沌帝龍 -終焉の使者-》を超え、遊戯王史上最速(当時(*3))で禁止カードにされたカードであり、
更に、制限や準制限をすっとばして直接禁止リストに入っている。
《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》など、発売当時は見向きもされなかったが後発のカードとのシナジーが強力という理由で突然禁止カードになったものも多い。
アニメGXからは《D-HERO ディスクガイ》と《未来融合-フューチャー・フュージョン》、
アニメ5D'sからは《ダーク・ダイブ・ボンバー》と《ゴヨウ・ガーディアン》が禁止カードに指定されている。
ちなみに、《ダーク・ダイブ・ボンバー》は、《混沌帝龍 -終焉の使者-》を超え、遊戯王史上最速(当時(*3))で禁止カードにされたカードであり、
更に、制限や準制限をすっとばして直接禁止リストに入っている。
《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》など、発売当時は見向きもされなかったが後発のカードとのシナジーが強力という理由で突然禁止カードになったものも多い。
《サンダー・ボルト》等の強力なカードはもはや永久に禁止だろうと声も多いが、《ブラック・ホール》にせよ《死者蘇生》にせよ、
「もう戻らないだろう」と言うカードが制限復帰する事も多々あるのであまり当てにならない。
ゲームを破壊するレベルのカードと称され流石に戻ってこないと思われていた《八汰烏》ですら、環境の変化によって禁止解除させたりすることからもお分かりになるだろう。
近年では、禁止カードネタがカードの絵柄として扱われており《エクストラネット》や《サモン・ゲート》などが有名。
「もう戻らないだろう」と言うカードが制限復帰する事も多々あるのであまり当てにならない。
ゲームを破壊するレベルのカードと称され流石に戻ってこないと思われていた《八汰烏》ですら、環境の変化によって禁止解除させたりすることからもお分かりになるだろう。
近年では、禁止カードネタがカードの絵柄として扱われており《エクストラネット》や《サモン・ゲート》などが有名。
そんな中、あのDDBがテキストを修正された形で復活し、2015年の制限改正では、DMのリマスターが放送されることもあってか禁止されている原作カードがテキストを修正したうえで解禁される模様。
「禁止カードにするくらいなら最初からそんなカード作らなければ良いのに」という意見が出ることもあるが、
前述の通りカードの強さは環境によって変化していくので(特に遊戯王OCGは裁定による評価の変化が著しい)、
一概にはそうは言えないのが現状である。
前述の通りカードの強さは環境によって変化していくので(特に遊戯王OCGは裁定による評価の変化が著しい)、
一概にはそうは言えないのが現状である。