第4章 風土的環境倫理の骨格と基礎論点(p.119-162)
“人間と自然の共生”を基本理念とする環境倫理を風土的環境倫理へと具体化することを試みる
風土的環境倫理とはさしあたり、環境倫理において
①風土を基本的舞台と捉え、
②風土における倫理を基本モデルと位置づけ、
③風土という基本的枠組みを基礎として理論的に位置づけることを意味する
①風土を基本的舞台と捉え、
②風土における倫理を基本モデルと位置づけ、
③風土という基本的枠組みを基礎として理論的に位置づけることを意味する
一 風土的環境倫理はなぜ必要か?(p.119-125)
風土が注目される理論的理由
①環境倫理はまずもって地域の具体的な環境問題にそくして、地域の歴史的文化的個性を通して多様に発見・構築されるべきというローカリズムの方向性
⇔欧米発の「環境倫理学」、その裏返しとしての日本的自然観・東洋的自然観の称揚
※人間中心vs自然中心、内在的価値、自然の権利などの諸問題の焦点は人間と自然の関わり方にある。この視点からすればこれらは近代主義的普遍主義(西欧或いは東洋中心主義)に囚われていた
②環境的自然は人間の存在を前提して初めて意味を持ち、そこから価値的自然としての保護すべき自然には必然的に、地域によって異なる価値観や社会的文化的要因が刻印されていること
→「保護すべき自然」とは本質的には「人間にとって好ましい自然」=価値的自然である
→価値的自然とはまず関わりの具体的な場面で存在するものとして考察されねばならない
→価値的自然とはまず関わりの具体的な場面で存在するものとして考察されねばならない
⇒広範囲で問題となる場合の「保護すべき自然」も、具体的自然に即し、社会と地域によって異なる多様で個性的な価値的自然を基礎として初めて存在可能になる
風土が注目される実践的理由
ア.環境の要素還元主義の問題
地球規模の環境問題のグローバル化が強調される⇒自然のエレメンタール*化
→環境とは何より生活者にとっての生きた自然・目前の地表的自然であるという視点の欠如
→汚染問題をクリアすれば生活者にとっての生きた自然の開発の倫理的是非は問われない
→汚染問題をクリアすれば生活者にとっての生きた自然の開発の倫理的是非は問われない
※非居住域(エレーム)。通常人間の居住・往来しない「具体空間」⇔居住域(エクメーネ) (A.ベルク1992)
イ.環境の「絵画化」の問題
緑地の量的確保・維持への短絡、効率性重視・質の度外視⇒環境的自然の画一的平面化・「絵画化」
→環境問題と地域固有の生態系保全問題の結び付きの視点の欠如
→市民との交流的自然の回復ないし人間の身体性や自然との交感能力の回復という視点の欠如
→市民との交流的自然の回復ないし人間の身体性や自然との交感能力の回復という視点の欠如
ウ.生態系保全、外来種の問題
生態系保全では、地域の多様な生物が共存可能な全体的な生態系ないし生態系システムが問題
→連続した生態系の地域的個性はいかに把握されるか
→外来種の移入は既存生態系の変容をもたらすが、そこから直ちに導入が否定されるのか
→人間による変容は原理的前提事項だが、それは無原則的な変容を是とすることになるのか
→外来種の移入は既存生態系の変容をもたらすが、そこから直ちに導入が否定されるのか
→人間による変容は原理的前提事項だが、それは無原則的な変容を是とすることになるのか
エ.自然の歴史性・文化性と自然変容の限界の問題
保護すべき自然は本質的に文化的歴史的自然⇒自然への不干渉や自然開発の否定は不可能
→問題は開発のあり方・関わり方、その基準ないし限度をどう位置付けるか
→自然と歴史・文化と一体となった地域のあり方全体に求めざるを得ない
→自然と歴史・文化と一体となった地域のあり方全体に求めざるを得ない
オ.ありふれた自然の保護の論拠
尾瀬などの希少な生態系、諫早湾埋め立て問題など生態系の広範囲に影響をもたらす場合には、その保護の論拠自体はそれなりに明らか
→「まっとうな理由」による地域振興のために犠牲にされがちな「どこにでもある」「ありふれた自然」・「小さな自然」を保護する説得的根拠の解明、積極的な理由付けが求められる
カ.自然との共生関係のモデル
以上を総括すると、環境問題の根本的課題は
①近代的な都市型ライフスタイルが喪失した自然と人間との直接的で全体的な関わりの回復であり、
②それを可能にする生活的自然の回復であり、
③人間の自然性・身体性の回復である。
①近代的な都市型ライフスタイルが喪失した自然と人間との直接的で全体的な関わりの回復であり、
②それを可能にする生活的自然の回復であり、
③人間の自然性・身体性の回復である。
→基本的に科学技術文明に依拠せざるを得ない現代で、「田舎」の単純復活は不可能
⇒重要なのは、自然と人間の直接的全体的関わりとして、現代的フェーズで人間と自然の共生の視点から「田舎」の人間自然関係の構造を、モデルとすること
※求められる風土論・風土概念はこれら実践的問題の解決の方向性を示しうるものでなければならない
二 和辻哲郎の風土論の意義と理論的難点(p.125-132)
和辻哲郎の風土の理論化とその問題点
和辻は『風土』(1979)において、「風土」に初めて哲学的反省を加え、理論的キーワードに仕立てた
和辻風土論のポイント:
・風土の定義と風土理解の理論的枠組み
・風土の型(類型化)と風土の記述 ←難点アリ
・風土の定義と風土理解の理論的枠組み
・風土の型(類型化)と風土の記述 ←難点アリ
和辻による風土の類型化:
東アジア・モンスーン型=湿潤 ⇒多神教・自然信仰、非合理主義・情緒的傾向、「間柄」主義、…
中東アラブ・砂漠型=乾燥
西欧・牧場型=適潤 ⇒一神教・超越神信仰、合理主義・論理的傾向、個人主義、…
東アジア・モンスーン型=湿潤 ⇒多神教・自然信仰、非合理主義・情緒的傾向、「間柄」主義、…
中東アラブ・砂漠型=乾燥
西欧・牧場型=適潤 ⇒一神教・超越神信仰、合理主義・論理的傾向、個人主義、…
→一面では一定の説得力を持ち、日本の精神的文化的特徴が、生活様式や民俗(とくに「もの」や「形」)を通して具体的に叙述される点でも斬新だったが、根本的欠陥があった
①その記述が和辻の恣意的な構想物でしかなく、各地域の具体的風土とは大きく乖離する点
②東洋と日本を同質化し、かつ日本の風土も均一で単一な風土として記述されている点
→単一的、恒久普遍の日本文化・民俗・民族論というフレームは天皇主義と結びつく近代ナショナリズムのイデオロギーでしかない(画一化された西欧思想・文化の型も同様)
→単一的、恒久普遍の日本文化・民俗・民族論というフレームは天皇主義と結びつく近代ナショナリズムのイデオロギーでしかない(画一化された西欧思想・文化の型も同様)
③知識人の目線で記述され、「一般住民の日常生活とはかけ離れた存在」だという点
和辻風土論の根本的難点
④自身の風土概念と矛盾し、風土が自然条件によって形成されるとする自然決定論に陥っている点
→和辻は風土概念を確立する際、現象学の立場から客観的な自然を認めず、文化が自然によって決定されるとする見方を徹底的に否定することを根本的課題とした
→風土を自然条件に還元する見方、風土が自然環境に決定されるとする見方、風土を自然を基盤とする人間と自然の相互交渉の産物とみる見方(マルクス)などすべて否定
⇒和辻の風土類型論・風土記述は自身の風土概念と根本的に乖離しているため、風土概念については独自に改めて検討する必要がある
和辻の風土概念:
それまでの風土理解の2つの方向(自然条件=土地の気候・地形・土質と、気風と地域=土地の人々の気質・精神・文化)を1つに総合
それまでの風土理解の2つの方向(自然条件=土地の気候・地形・土質と、気風と地域=土地の人々の気質・精神・文化)を1つに総合
→風土を自然現象にも文化・精神現象にも還元せずそれらの一体のものとし、「人間存在の型」であり人間の「自己了解の仕方」であると捉えた
(和辻によれば、「ある土地の気候、気象、地質、地味、地形、景観など」とともに「文芸、美術、宗教、風習等あらゆる人間生活の表現」も「風土の現象」である)
(和辻によれば、「ある土地の気候、気象、地質、地味、地形、景観など」とともに「文芸、美術、宗教、風習等あらゆる人間生活の表現」も「風土の現象」である)
和辻風土論の理論的意義
→近代の二元論を批判する現象学、とくにあらゆる現象を関わりの経験(志向性Intentionalität)と捉える立場から構想、重要な視点を含む
①風土を人間と自然の関わり、人間の共同を介した関わりを基軸にしてとらえた点
⇒風土における自然は人間的文化的性格を持つ
②風土をその土地の人間の共同的なあり方(存在の型)ととらえ、人間を、単に精神や内面的意識状態からでなく、物や身体性レベルで現れる生活様式において理解する視点
⇒「風土は人間の肉体である」
③風土は人間存在の型として歴史的であり、風土性は歴史性と一体であるとする視点
致命的な弱点:
人間と区別された自然や、自然の客観性を見る視点を失い、人間と自然の相互作用や風土における自然と文化の相互関係を分析する視角を持たないこと(現象学の方法的立場に由来)
人間と区別された自然や、自然の客観性を見る視点を失い、人間と自然の相互作用や風土における自然と文化の相互関係を分析する視角を持たないこと(現象学の方法的立場に由来)
三 風土とは何か――風土の概念と性格(p.132-141)
A.ベルクの風土論:
和辻風土論の主情主義的側面を批判しつつその全体性を継承し、風土の客観的側面と文化的歴史的側面の統一として風土概念を再構築
和辻風土論の主情主義的側面を批判しつつその全体性を継承し、風土の客観的側面と文化的歴史的側面の統一として風土概念を再構築
→現象学への原理的検討がなく、また自然=非文化、文化=非自然と見る図式が依然強い
風土概念の基礎としての人間観と自然観
フォイエルバッハの人間学的唯物論:
人間を、根源的には自然に依存し、共同関係において存在する文化的な身体的主体と捉える
(人間の何であるかは思想・観念からでなくその身体的行為の全体から理解される)
人間を、根源的には自然に依存し、共同関係において存在する文化的な身体的主体と捉える
(人間の何であるかは思想・観念からでなくその身体的行為の全体から理解される)
→生物学的身体に加え文化的社会的身体のレベルで自然に根源的に依存
⇒自然の根源的規定性
→身体的人間は共同関係において社会的文化的性質、自然に対する能動性・主体性を獲得
⇒自然との主体客体関係
→要請される風土概念にとって重要な、自然との関わりにおける社会と諸個人の責任と規範を問題にするために必要な理論的位置づけ
ここでの自然=生活的自然・経験的自然:
本質的に人間とともに存在し、人間との関わりの度合いに応じて文化的刻印を帯びた歴史的自然
(半自然・二次的自然が中核)
本質的に人間とともに存在し、人間との関わりの度合いに応じて文化的刻印を帯びた歴史的自然
(半自然・二次的自然が中核)
⇔環境的自然:
方法的に人間とのかかわりを捨象した人間の周囲世界・外界・非人間的ないし客観的現象
(自然史的自然の一部⇒半自然・二次的自然も客観的自然の一部とみる)
方法的に人間とのかかわりを捨象した人間の周囲世界・外界・非人間的ないし客観的現象
(自然史的自然の一部⇒半自然・二次的自然も客観的自然の一部とみる)
⇒どちらも人間的身体の外部の自己運動する諸存在を指すという意味で自然であり、ここでは文化に対する自然の対置は本質的意味を持たない
風土とは何か――風土の定義
{風土Landschaft:
一定の地理的空間における共同社会と生活的自然との一体的かかわりの全体}
一定の地理的空間における共同社会と生活的自然との一体的かかわりの全体}
風土の三つの基本ポイント:
①共同性(諸個人の共同関係、文化生活様式の共有性、身体的振る舞いと感覚の同一性)
②生活的自然の諸事象との具体的身体的な関わり
③この関わりの自然調和性・場所的一体性
①共同性(諸個人の共同関係、文化生活様式の共有性、身体的振る舞いと感覚の同一性)
②生活的自然の諸事象との具体的身体的な関わり
③この関わりの自然調和性・場所的一体性
※この三ポイントの一部ないし全てを欠如ないし喪失した空間は、風土とはいえない
風土における“関わり”の全体性と風土の範囲
風土概念のポイント補足:
①共同社会と生活的自然の関わりとは、精神的活動を含む人間の全活動を意味する
①共同社会と生活的自然の関わりとは、精神的活動を含む人間の全活動を意味する
→農作業・土地開発・衣食住などに加え、信仰や精神など(意味的象徴的関わり)もすべて、どこまでも身体の活動として理解し、振る舞いの次元で解釈する
→風土における共同性社会性も諸個人の身体とその振る舞いにおいて現実に存在する
⇒物質的、肉体的、社会的、共同的、精神的など人間的特徴の全てを備える自然との身体的関わりの多様さと全面性が風土の中核をなす
②身体的関わりが中核をなすゆえに、風土は空間的広がりを持った場所であるという性格を持つ
→この場所としての風土とその個性が地域の範囲を限定
a.身体次元で日常的に関わる生活的自然の特徴
→地形、気候など
→地形、気候など
b.生活的自然との身体次元での関わり方(身体的技芸)
→主要生産物、道具など
→主要生産物、道具など
c.諸個人が身体的次元で相互に関わりかつそこで諸個人が形成される、共同関係と文化
→居住形態、共同関係、支配的宗教など
→居住形態、共同関係、支配的宗教など
※風土の空間の内実は身体に注目した人間と自然との、人間と人間との多様で多元的な関わりのまとまりをもった総体である点に注意(風土=場所)
⇒環境問題解決の主体としての地域=風土的地域と想定するのが妥当
人間の現実態としての風土、及び風土的自然
③場所としての風土は人間の共同的存在の現実的存在形態であり、人間の自己了解の磁場をなす
→人間とは何かは、人間というものの分析によってではなく人間が具体的になしていることの総体に示される
⇒風土がその土地の人間の何であるかの現実的形態であり、風土において諸個人は自己の共同的存在をその歴史も含めて了解する
④以上をふまえた、風土の自然性の意味:場所としての風土における人工的存在と自然との関係
→風土および風土の中の自然が、人為的産物を含みつつ人間と自然の調和を保つという風土の基本的関係はいかなる意味でどのように可能か?
(1)風土においては人工的自然物が他の生活的自然との生態系の面で一体性を保ち、それ自身豊かな生物を育む生命的自然(風土の中の自然)の有機体的一部となること
Ex)有機農法の田畑⇔ビニールハウス
(2)非自然的人工物が風土の中の自然の生態系システム、とくに生命的自然としての性格に根本的影響を与えないこと
→風土的地域における非自然的人工物の量的限界に留意する
→都市など非自然的人工物の多い場所でもその内部に生態系システムを原理的に確保する
→都市など非自然的人工物の多い場所でもその内部に生態系システムを原理的に確保する
(3)風土における人間の共同的なかかわりが風土の中の自然ないし風土的地域の生態系システムの保全を前提とし、関わり自体がそのシステムの一環としての限界内にとどまること
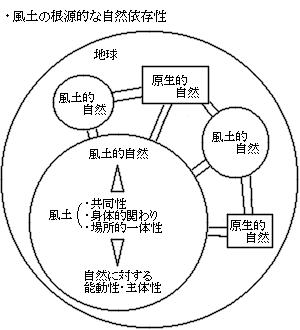
※図は菊地が作成
〇感想・論点
- 現代の日本において風土が実際にある地域は?
- 3ポイントに優先順位はあるか。例えば東京の新しい団地で風土を新しく構築しようとするとき、どれから作っていくか。
〇参考文献
A.ベルク著、篠田勝英訳 『風土の日本』 ちくま学芸文庫,1992
添付ファイル
