クリックで大きい画像
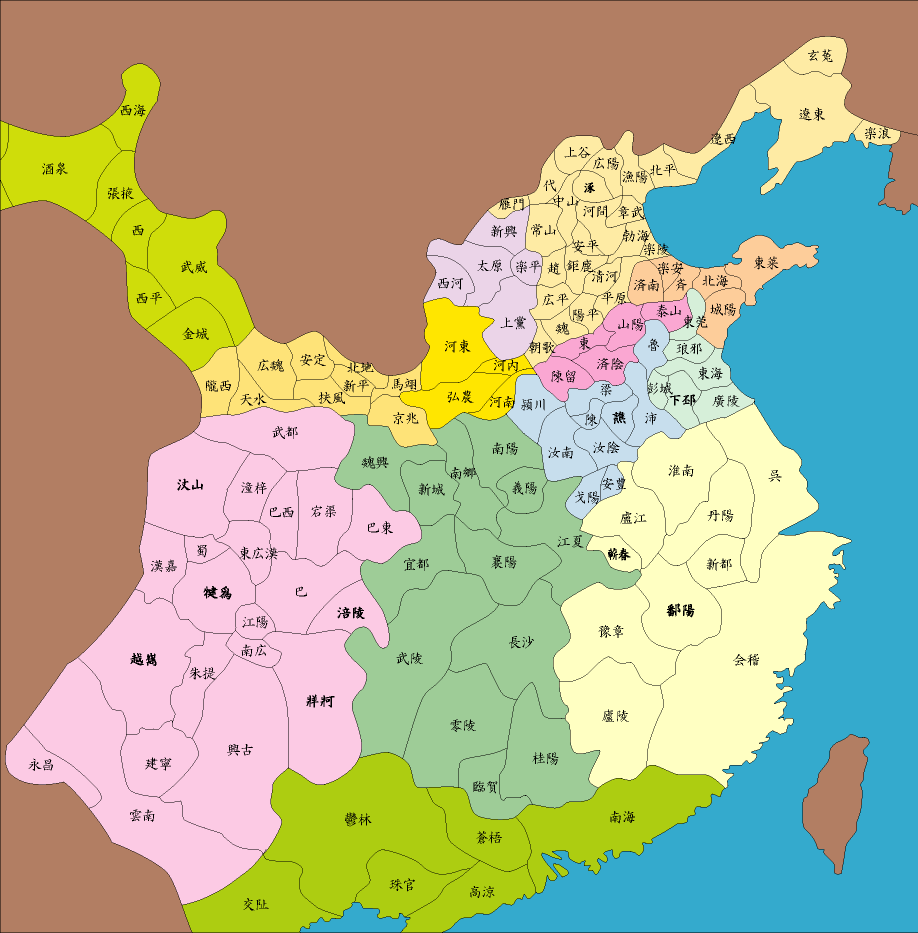
地形説明
- 酒泉(しゅせん):シルクロード上のオアシス都市。酒の味がする水が湧く泉があったことから命名されたという。
- 居延(きょえん):西海の東、この図には表記はない。
三国時代には巨大な湖・居延沢(居延海とも)があったが、14世紀頃砂漠化に伴って湖は消滅した。
- 張掖(ちょうえき):涼州に属するオアシス都市。董卓配下の将・郭汜らはこの郡の出身である。
- 武威(ぶい):涼州の主要都市のひとつ。曹操に抵抗した張シュウや賈クらは、この郡の出身である。
- 金城(きんじょう):涼州所属の郡。馬騰・馬超父子それぞれと組み反乱を起こした韓遂は、この郡の出身である。
- 天水(てんすい):涼州に属する郡で「漢陽」ともいう。後期の蜀漢を支えた武将・姜維の出身地でもある。
- 安定(あんてい):涼州の主要都市のひとつで漢の将・皇甫嵩の出身地でもある。魏の時代には雍州に移管された。
- 隴西(ろうせい):涼州に属する郡で董卓の出身地でもある。諸葛亮が北伐の際に攻撃を仕掛けた。
- 雁門(がんもん):并州にあった群。北方から異民族が進出していた。魏の名将・張遼の出身地でもある。
- 北平(ほくへい):幽州の中心都市で漢の時代に右北平郡が置かれた。呉の武将・程普の出身地でもある。
- 遼西(りょうせい):幽州に属する郡。漢民族と異民族が雑居していた。後漢末の群雄・公孫サンはこの地の出身である。
- 渤海(ぼっかい):黄河が注ぐ渤海湾に面した郡で、中心都市は南皮。後漢末の群雄・袁紹が当初、本拠とした地でもある。
- 常山(じょうざん):冀州に属する郡。蜀漢の猛将・趙雲は常山郡真定県の出身である。
- 太原(たいげん):并州に属する郡で中心都市は晋陽。戦国時代に趙の首都が置かれた重要都市。
- 東莱(とうらい):青州所属の郡。孫策と戦った劉ヨウや、その配下の将だった太史慈の出身地。
- 北海(ほっかい):青州に所属する国。著名な学者の孔融が相を務めたこともある。劉備配下の将・孫乾の出身地でもある。
- 琅邪(ろうや):徐州に含まれる郡で、諸葛亮の出身地として有名。琅邪出身の王氏らは南北朝時代貴族として活躍した。
- 東郡(とうぐん):エン州所属の郡で中心都市は濮陽。呂布の軍師・陳宮や曹操の腹心の程昱、呉の潘璋らの出身地。
- 河内(かだい):都・洛陽から見て黄河の対岸にある孟津を含む郡。司馬懿の一族の本貫(出身地)でもある。
- 河東(かとう):岩塩の産地である解池がある解県は、関羽の出身地として有名。他に魏の将・徐晃も河東の出身である。
- 弘農(こうのう):司隷校尉管轄下の郡。董卓に廃された皇帝・劉弁は弘農王に任命されている。
- 陳留(ちんりゅう):猛将・典韋の出身地。後漢最後の皇帝となる献帝は、董卓に擁立される前は陳留王の位にあった。
- 沛国(はいこく):漢王朝を建てた高祖・劉邦の出身地。曹操や夏侯惇の一族も本拠とする。神医・華佗もこの地の出身。
- 汝南(じょなん):呂蒙・袁紹・袁術らの出身地。黄巾の乱では激戦が演じられ、平定後も黄巾賊の残党が長く占拠した。
- 東海(とうかい):徐州に所属する郡。劉備の配下となる糜竺や孫策と戦ったのち曹操に仕えた王朗などの出身地。
- 九江(きゅうこう):揚州所属の軍。中心都市の寿春は袁術が本拠として皇帝を称した。呉の武将・周泰や蒋欽の出身地。
- 呉(ご):孫氏一族や陸遜の出身地。呉の四姓といわれた名族「張陸朱顧」の4氏は後世まで貴族として活躍した。
- 柴桑(さいそう):長江沿いにあった孫呉水軍の前線基地があった郡。周瑜や孫権が遠征の際、たびたび駐屯した。
- 会稽(かいけい):漢の将軍・朱儁や呉の董襲らの出身地。戦国時代に越王・勾践が呉に敗れた「会稽の恥」の故事で有名。
- 予章(よしょう):揚州に属する郡。中心都市は南昌。諸葛亮の叔父・諸葛玄が太守を務めていた地。
- 廬陵(ろりょう):孫策が予章郡の一部を分割して設置した軍。山越と呼ばれる民族が多く住み、呉の武将たちと戦った。
- 長沙(ちょうさ):荊州南部。太守・韓玄は劉備と敵対。配下の黄忠が関羽と互角に戦うが、魏延の寝返りにより陥落した。
- 江夏(こうか):荊州の要地。劉璋の出身地。劉表が任命した太守・黄祖は、孫策や孫権と壮絶な攻防を繰り返した。
- 襄陽(じょうよう):荊州の中心都市。劉表の統治下、戦乱の中でも学問の栄える文化都市となった。ホウ統や馬良の出身地。
- 江陵(こうりょう):荊州に属する南郡の中心都市。赤壁の戦いののち、曹操から守備を任された曹仁が守り抜いた。
- 武陵(ぶりょう):荊州南部の郡。赤壁の戦いの後、荊州に進出していた劉備の先鋒として、張飛が太守・金旋を降している。
- 零陵(れいりょう):荊州南部の郡。赤壁の戦いののち勢力を拡げた劉備が占拠した。呉の猛将・黄蓋の出身地でもある。
- 潁川(えいせん):予州に所属する郡。曹操を支えた文官である荀彧や鍾ヨウ、郭嘉などの優秀な人材を輩出した。
- 上庸(じょうよう):荊州と益州の境にあり、魏と蜀が争奪し合った地。太守・孟達を司馬懿が電光石火の速さで攻略した。
- 永安(えいあん):元は白帝城と呼ばれ、劉備の最期の地となった。夷陵の戦いののち、永安と改名された。
- 漢中(かんちゅう):張魯が布教した五斗米道と呼ばれる教団の本拠地。諸葛亮は北伐の際、要地・漢中の確保にこだわった。
- 武都(ぶと):漢中に隣接する要衝。諸葛亮の北伐に従軍した陳式が攻略した。
- 巴西(はせい):呉の猛将・甘寧や、蜀漢の武将・王平らの出身地。元は巴郡であったが後漢末に3つに分割された。
- 陰平(いんぺい):諸葛亮が北伐の際に攻略道として確保した地。のち鄧艾が蜀を攻めた際には逆方向の進攻路となった。
- 梓潼(しどう):劉備が益州に進攻した際、劉璋軍との激戦が行われた地。のち広漢郡から分割して梓潼郡とした。
- 南安(なんあん):内陸塩田や茶の産地として知られる郡。四川の霊峰として名高い峨眉山がそびえる。
- 建寧(けんねい):益州南部。漢人のほか少数民族も雑居する。南中王と称される孟獲はこの地の出身ともいわれる。
- 雲南(うんなん):益州南部。諸葛亮が雍ガイや孟獲の乱を制圧したのち、建寧郡から分割された。少数民族が多く住む。
- 永昌(えいしょう):益州南部の郡。元は建寧郡の一部であったが諸葛亮の南方制圧ののち、分割された。蜀の呂凱の出身地。
- 南海(なんかい):現在の香港、マカオなどを含む郡。交州に属した。インド方面との交易が行われていたともいう。
- 桂林(けいりん):交州の郡。カルスト地形の柱が林立し、美しい鍾乳岩洞があることから古来より絶景をうたわれた。
- 交趾(こうし):現在のハノイ。「三国志演義」には登場しないが、太守の士燮はベトナムに儒教を伝えたことで有名。
最終更新:2011年04月08日 18:13