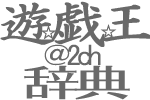トラゴエディア(とらごえでぃあ)
元々は古代エジプトのクル・エルナ村出身の占星術師であったのだが、千年アイテムを作るために村民が皆殺しにされたのを知り、心の中に魔物を生みだす。
その後王宮に侵入して捕えられた時に魔物としての正体を現し神官たちを圧倒するが、ハネクリボーに心臓を封印されていたため本来の力が発揮できず、石板に封印された。
3000年後ピラミッドの発掘隊によって封印が解かれ、経緯は不明だが現在はアメリカ・アカデミア校長であるマックの父に憑依している。
復活の鍵たる精霊を宿すハネクリボーとプラネットシリーズを用いた決闘者達の生命力集めを目的としており、マックやデイビットなどを操って暗躍している。
そしてついにハネクリボーがデュエル・アカデミアに存在することを突き止めたトラゴエディアはアメリカ・アカデミア校長という立場を利用して自らその回収に乗り出し、これを掌握する。
マックの父であるMr.マッケンジーを自身の器とする以前はエドの父親であるカードデザイナーのフェニックス氏を器としており、
その後王宮に侵入して捕えられた時に魔物としての正体を現し神官たちを圧倒するが、ハネクリボーに心臓を封印されていたため本来の力が発揮できず、石板に封印された。
3000年後ピラミッドの発掘隊によって封印が解かれ、経緯は不明だが現在はアメリカ・アカデミア校長であるマックの父に憑依している。
復活の鍵たる精霊を宿すハネクリボーとプラネットシリーズを用いた決闘者達の生命力集めを目的としており、マックやデイビットなどを操って暗躍している。
そしてついにハネクリボーがデュエル・アカデミアに存在することを突き止めたトラゴエディアはアメリカ・アカデミア校長という立場を利用して自らその回収に乗り出し、これを掌握する。
マックの父であるMr.マッケンジーを自身の器とする以前はエドの父親であるカードデザイナーのフェニックス氏を器としており、
- プラネットシリーズとは、トラゴエディアが自分の復活という目的のためだけに作られたカードであるということ
- エドがMr.マッケンジーと自分の父親であるフェニックスを重ねて見てしまうのは両者が精神的に同一人物ゆえにあること
- トラゴエディアがフェニックスである時からエドを自分の復活に必要な道具として育てていたこと
などをエドに明かした後、闇のデュエルによってエドの生命力を奪い、ついに復活を果たす。
そして、十代と万丈目を同時に相手取り、最終決戦を迎える。
そして、十代と万丈目を同時に相手取り、最終決戦を迎える。
使用したのは古代エジプトの意匠を持つ【アンデット族】のデッキ。
「デッキとは決闘者の運命」という理念から作成され、「自他全ての運命を操れる」と豪語したトラゴエディアのデッキは、
入っている全てのカードが自身の手により作り出された専用品、という凄まじいシロモノ。何処のダーツだお前は
伏せ二枚の状態からわざと攻撃を受けきりドローゴーという綱渡りのような立ち回りから、大量のライフ回復から絶対的な安全圏を築く等、正に命を弄ぶようなプレイングをする。
エースモンスターはイレギュラーのプラネットシリーズ《The supremacy SUN》(ザ・スプレマシー・サン)。
無限の再生効果を持ち、単体で十代と万丈目のエースモンスター達を圧倒した。
紅葉やエドを倒したことなどから本来の決闘者としての実力は非常に高い。
油断を誘えたという意味では爆発力を隠しながらもその時点では未熟だった十代と万丈目だからこそ倒せた相手ともいえる。
「デッキとは決闘者の運命」という理念から作成され、「自他全ての運命を操れる」と豪語したトラゴエディアのデッキは、
入っている全てのカードが自身の手により作り出された専用品、という凄まじいシロモノ。
伏せ二枚の状態からわざと攻撃を受けきりドローゴーという綱渡りのような立ち回りから、大量のライフ回復から絶対的な安全圏を築く等、正に命を弄ぶようなプレイングをする。
エースモンスターはイレギュラーのプラネットシリーズ《The supremacy SUN》(ザ・スプレマシー・サン)。
無限の再生効果を持ち、単体で十代と万丈目のエースモンスター達を圧倒した。
紅葉やエドを倒したことなどから本来の決闘者としての実力は非常に高い。
油断を誘えたという意味では爆発力を隠しながらもその時点では未熟だった十代と万丈目だからこそ倒せた相手ともいえる。
嫌いなものは退屈、神官、千年アイテム、マアトの羽ェェ。アダ名は「バケモノ」。
人間のことを「虫ケラ」と呼ぶ。怪人みたいな鋏がキュート。
自他問わずカードの貸し借りはきちんとする。借りたカードに関しては漂白までしてくれる辺り律儀なジェントルメンである。
精神を操って傀儡にしているはずの部下共に反逆を画策されたり、舌打ちされるのが最近の悩み。
人間のことを「虫ケラ」と呼ぶ。怪人みたいな鋏がキュート。
自他問わずカードの貸し借りはきちんとする。借りたカードに関しては漂白までしてくれる辺り律儀なジェントルメンである。
精神を操って傀儡にしているはずの部下共に反逆を画策されたり、舌打ちされるのが最近の悩み。
特殊召喚される《光と闇の竜》、召喚条件がOCG仕様の《E・HERO ガイア》、《マアト》召喚、オカルトグッズがカンニンググッズと化してフォレッセ・ドロー等、主人公側から度重なる反則が行われても、「怒らない。」そして「ずるい!」とも言わない。
「やってはいけない10のこと」を遵守した素晴らしいリスペクト・デュエルを展開し、「表示を消したのはちょっとした演出だ」さえ除けば、正々堂々と戦い抜き、そして敗れさった真の決闘者である。
紅葉さんを人質にとって攻撃を躊躇させるなんてMr.マッケンジーの娘みたいな卑怯なマネは考えもしない。
手札にそれこそ《トラゴエディア》でもいれば暫し延命できたかも知れなかったが、そんなものは無い。
敗北後に改めてリアルファイトを挑むが、自分から始めた闇のデュエルによってすでに深刻な大ダメージを負っており、逆に精霊二体から返り討ちにされてしまう。
トラゴエディアの最後の言葉は「封印などされてたまるかァ」。この後、滞り無く封印は完了し、悲しい魂の旅は終点を迎えた。
ちなみに事件後、マッケンジー氏は生存していた模様である。
「やってはいけない10のこと」を遵守した素晴らしいリスペクト・デュエルを展開し、
紅葉さんを人質にとって攻撃を躊躇させるなんてMr.マッケンジーの娘みたいな卑怯なマネは考えもしない。
手札にそれこそ《トラゴエディア》でもいれば暫し延命できたかも知れなかったが、そんなものは無い。
敗北後に改めてリアルファイトを挑むが、自分から始めた闇のデュエルによってすでに深刻な大ダメージを負っており、逆に精霊二体から返り討ちにされてしまう。
トラゴエディアの最後の言葉は「封印などされてたまるかァ」。この後、滞り無く封印は完了し、悲しい魂の旅は終点を迎えた。
ちなみに事件後、マッケンジー氏は生存していた模様である。
| + | その恐るべき悪行の数々 |
人生上のプレイングミスが多いように思えるが、これに関してはトラゴエディアが自身の復活にあたる最大目的を「世界征服」や「復讐」ではなく「退屈しのぎ」として捕らえており楽しむことを至上していたから(*1)である。
「負けた方は死ぬ」と謳っておきながら実際は昏睡状態に落とし込んでいく闇のデュエルの矛盾は、彼にとっての死が「生命活動の停止」ではなく「束縛されていること」にあったことがうかがえ、
プロの地位が賭かった重要な闘いもあくまで楽しもうとするヨハンに賛同の意を示すなど単純な勝敗に括られない充足感を求めていたような一面が見受けられる。
十代・万丈目との最終決戦に関しても「デュエルせずに完全復活した自身の力で物理的に粉砕する」という、安易で確実な選択肢を蹴ってまでデュエルに興じており、
自身の敗北を露ほども疑っていなかったであろうことを差し引いても、退屈を是としないトラゴエディアは十分に快楽至上主義者であると言える。
このような退屈や束縛を疎う享楽的嗜好は三千年幽閉されたことで形成された偏執的な狂気であり、行動の非合理性にはある意味で必然性がある。
「楽しむ」ことに対する純粋かつ真摯な追求者という意味ではトラゴエディアは「遊城十代」(又は響紅葉)に対する鏡像的存在といえるが、
十代が他者を背負う責任感から楽しむことを喪失し、最後にハネクリボーを授けてくれた最強の存在と闘うことで再び「楽しい決闘」を取り戻す一方で、
トラゴエディアは他者を振り回す事こそが楽しみであり、最終的にその価値観こそが弱者に対する最大の敗因としてしか働かなかったというそれぞれの顛末はアンチテーゼ的でもある。
「負けた方は死ぬ」と謳っておきながら実際は昏睡状態に落とし込んでいく闇のデュエルの矛盾は、彼にとっての死が「生命活動の停止」ではなく「束縛されていること」にあったことがうかがえ、
プロの地位が賭かった重要な闘いもあくまで楽しもうとするヨハンに賛同の意を示すなど単純な勝敗に括られない充足感を求めていたような一面が見受けられる。
十代・万丈目との最終決戦に関しても「デュエルせずに完全復活した自身の力で物理的に粉砕する」という、安易で確実な選択肢を蹴ってまでデュエルに興じており、
自身の敗北を露ほども疑っていなかったであろうことを差し引いても、退屈を是としないトラゴエディアは十分に快楽至上主義者であると言える。
このような退屈や束縛を疎う享楽的嗜好は三千年幽閉されたことで形成された偏執的な狂気であり、行動の非合理性にはある意味で必然性がある。
「楽しむ」ことに対する純粋かつ真摯な追求者という意味ではトラゴエディアは「遊城十代」(又は響紅葉)に対する鏡像的存在といえるが、
十代が他者を背負う責任感から楽しむことを喪失し、最後にハネクリボーを授けてくれた最強の存在と闘うことで再び「楽しい決闘」を取り戻す一方で、
トラゴエディアは他者を振り回す事こそが楽しみであり、最終的にその価値観こそが弱者に対する最大の敗因としてしか働かなかったというそれぞれの顛末はアンチテーゼ的でもある。
なお、効果モンスターとしてOCG化もされており、《冥府の使者ゴーズ》を調整したような効果を持つ。
星10/闇属性/悪魔族/攻 ?/守 ?
自分が戦闘ダメージを受けた時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。
このカードの攻撃力・守備力は自分の手札の枚数×600ポイントアップする。
1ターンに1度、手札のモンスター1体を墓地へ送る事で、
そのモンスターと同じレベルの相手フィールド上に表側表示で存在する
モンスター1体を選択してコントロールを得る。
また、1ターンに1度、自分の墓地に存在するモンスター1体を選択し、
このカードのレベルをエンドフェイズ時まで、選択したモンスターと同じレベルにする事ができる。
優秀なコントロール奪取効果と縛りの緩い特殊召喚条件を持つ使い勝手のいいカード。
レベル変更効果の方もシンクロ・エクシーズ素材とする場合に活用でき、何より除外したりする必要がないのは地味に大きい。
攻撃力が手札の枚数で決定されるのが少々難点だが、序盤であれば上級打点を維持することも容易くアタッカーとしても働ける。
一時期環境デッキであった【コアガジェット】では性質上手札が減りづらい事とシンクロ召喚に使いやすいことから積極的に採用され、
ふとした時に急襲してくる上に素材としても優秀な強力アタッカーとして恐れられた。
【コアガジェット】以外でも積極的に使われまくった為、一時期は制限カードにすら指定され、
完全に制限解除が成されるまで実に5年近くを要したのも頷ける強さである。さすがはラスボス。
レベル変更効果の方もシンクロ・エクシーズ素材とする場合に活用でき、何より除外したりする必要がないのは地味に大きい。
攻撃力が手札の枚数で決定されるのが少々難点だが、序盤であれば上級打点を維持することも容易くアタッカーとしても働ける。
一時期環境デッキであった【コアガジェット】では性質上手札が減りづらい事とシンクロ召喚に使いやすいことから積極的に採用され、
ふとした時に急襲してくる上に素材としても優秀な強力アタッカーとして恐れられた。
【コアガジェット】以外でも積極的に使われまくった為、一時期は制限カードにすら指定され、
完全に制限解除が成されるまで実に5年近くを要したのも頷ける強さである。さすがはラスボス。
ちなみにOCG版《トラゴエディア》は遊戯王5D'sにも出演を果たした。が、クロウとジャックの攻撃宣言によって、ミラフォで二回もブッ飛ばされる羽目にあった。「コ…コゾォ」
後《デーモンの斧》を装備しておきながら、それをガン無視してブレス攻撃放つのはどうなのだろう。
敵の大ボスでありながら緩い召喚条件から「強い」というよりは「便利」な印象を受ける。
シンクロやエクシーズの素材として有能なのでそれで満足しようぜ!
後《デーモンの斧》を装備しておきながら、それをガン無視してブレス攻撃放つのはどうなのだろう。
敵の大ボスでありながら緩い召喚条件から「強い」というよりは「便利」な印象を受ける。
シンクロやエクシーズの素材として有能なのでそれで満足しようぜ!