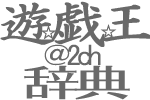ラーの翼神竜(らーのよくしんりゅう)
テキスト欄にはデュエルディスクにセットすると古代神官文字が浮かび上がる加工がしてある。
これはペガサスが発見した石版に書いてあったラーの効果を示す古代神官文字を解読できなかったためであり、これを読めないとラーを使うことは不可能である。
バトル・シティにおいて孔雀舞が召喚したものの古代神官文字を読めなかったために攻撃宣言できず、闇マリクにラーのコントロールを奪われた。
ちなみにラーの効果について、表マリクはその全容を把握できていなかったが、闇マリクは全ての能力を熟知した上でデッキを組んでいた。
オベリスクの特殊効果発動後に闇マリクが明らかにしたこの俺ルールは、流石にデュエルの流れを無視しすぎていると判断されたためか、DMでは闇マリクが事前に伏せていた速攻魔法《階級制度》の効果によるものとの修正が加えられ、神のランクによる耐性は無くなった。
- 舞VS闇マリク戦では、原作の《ハーピィ・レディ》の代わりに《ハーピィ・レディ・SB》を生け贄に使用したため、攻撃力が1300×3から1800×3に底上げされた(何故か守備力は原作のままだったが)。
- バクラVS闇マリク戦では、バクラの戦術が「ラーを墓地に置く」から「ラーを奪う」方向になった。
そのため《闇の指名者》と《死なばもろとも》を使う順番が原作とは逆になっている。
バクラは《エクスチェンジ》でラーを奪うことに成功するも、《死者蘇生》を交換したのが仇となってしまい《歓喜の断末魔》のライフ回復効果で原作よりも大幅に攻撃力がアップしたラーの攻撃を受けて敗北。 - 闇遊戯VS闇マリクの最終局面で、原作の《ディメンション・マジック》に代わり速攻魔法《
神々の黄昏 》(*1)が使用され、遊戯のデッキのモンスター総動員でラーを破壊した。
原作における効果
- 罠・モンスター(他の幻神獣も含む)の効果を一切受けつけず、魔法カードの効果も1ターンのみしか受けつけない。 (*2)
- このカードの攻撃力・守備力は、召喚時に生け贄にしたモンスターの攻撃力・守備力をそれぞれ合計した数値となる。
- 召喚した直後は
球体形 で現れ、古代神官文字を正確に唱えない限り戦闘に参加できない。(*3) - 古代神官文字を正確に唱えた場合、
戦闘 モードとなって戦闘できるようになる。
(相手プレイヤーが先に唱えた場合、相手がコントロールを得ると思われる) - オシリス・オベリスクは特殊召喚したターンの攻撃はできないが、このカードだけはその制限を無視できる速攻能力を持つ。
- 《死者蘇生》や《闇からの奇襲》などの効果で特殊召喚された場合、以下の効果のどちらかを発動できる。
- プレイヤーのライフポイントを1残しその数値だけラーの攻撃力・守備力に加算する。(1ターンキルモード)
更に自分フィールドの他のモンスターを生け贄にすることで、その攻撃力を吸収できる。
この時、ラーはプレイヤーとの融合モンスター扱いとなるため《融合解除》を使うことでラーの攻撃力を0に戻し、0になる前のラーの攻撃力分だけプレイヤーのライフポイントを回復できる。(*4)
また、このモードでの攻撃時に相手フィールドのモンスターと相手ライフを瞬時に葬り去る効果もある。
(相手フィールドのモンスター全てに戦闘ダメージ&ライフへの超過分戦闘ダメージと思われるが、この効果が発揮されたのがバクラVS闇マリク戦のみであり、バクラのモンスターが全て攻撃表示だった場合、バクラのライフは原作・DM共に全体攻撃でなくても削り切れる数値だったため、詳細不明) - 1000ライフポイントを払うことで相手モンスター1体をステータスや特殊効果に関係なく破壊する。(ゴッドフェニックス)
神のカードにも有効(*5)。
この状態の時は無敵であり、オシリスの攻撃と効果を無効化している。
- プレイヤーのライフポイントを1残しその数値だけラーの攻撃力・守備力に加算する。(1ターンキルモード)
その時は、
- 攻撃力4000 守備力4000 自分と相手の墓地の一番上にあるモンスターを特殊召喚し、その後自分のモンスターゾーンの空きの数だけ相手フィールド上のモンスターのコントロールを得る。
DM4では効果モンスターの効果を使えるのは場に出てから1度だけで、効果を使用したターンの攻撃ができなくなるものの、
それ以外のモンスターの攻撃で大幅にライフを削ることができるという、凶悪な性能だった。
I2社から盗んだコピーカードを、同社の社員であるフランツが使用した。
通常、コピーカードを使うと神の怒りに触れて命を落としたりするはずなのだが、彼は《神縛りの塚》というフィールド魔法を使用し、ラーを自分の下僕のように使用した。
この時の効果はほぼ原作そのままであったが、古代神官文字を唱える必要はなく、墓地から特殊召喚した場合でなくても効果を発動することができた。リシド涙目である。
恐らく、十代の想いにラーが応えたためと思われるが、この時期の十代は墓守達から貰った千年アイテムに似たペンダントをつけていたために神の裁きを受けなかった可能性もある。
- 召喚時や召喚後に生け贄にしたモンスターの攻守を吸収する能力が無かったことにされ、1ターンキルモードの内、ライフのみがステータス決定に関係する効果となる。
- 魔法の効果を1ターンのみ受ける、罠・モンスター効果を受けない能力がアドバンス召喚時しか発揮されなくなった。
- そもそも特殊召喚自体が不可能になる。(闇マリクのデッキは特殊召喚の多用によるラーの連続使用がウリだった)
- 破壊効果と攻撃力変換効果が、基本的には召喚時にどちらか片方しか使えなくなった。(*7)
星10/神属性/幻神獣族/攻 ?/守 ?
このカードは特殊召喚できない。
このカードを通常召喚する場合、
自分フィールドのモンスター3体をリリースして自分フィールドに召喚、
または相手フィールドのモンスター3体をリリースして相手フィールドに召喚しなければならず、
召喚したこのカードのコントロールは次のターンのエンドフェイズに元々の持ち主に戻る。
(1):このカードは攻撃できず、相手の攻撃・効果の対象にならない。
(2):このカードをリリースして発動できる。
手札・デッキから「ラーの翼神竜」1体を、召喚条件を無視し、攻撃力・守備力を4000にして特殊召喚する。
一番の強みは相手のモンスターをリリースできることだが、3体居なければ相手の場には呼べず、「壊獣」モンスターや《溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム》などと比べると少し重い。
とはいえ、トークンを押し付けるカードはそれなりにあり、今の環境では先攻で複数のモンスターが並ぶことは珍しくないため、呼ぶ機会はそれなりにある。
さらにコイツ自身は単独ではただの壁でしかないため、相手のデッキにラーがなければ棒立ちとなる。
《星態龍》とか《超弩級砲塔列車グスタフ・マックス》の素材にされる恐れもあり、昨今では縛りの緩いリンク召喚の素材としてあっさり処理されてしまう可能性も高い。
また、墓地に落としておけば《ファントム・オブ・カオス》で効果をコピーすることでアドバンス召喚せずとも効果を使える。
正直なところ、ラーを単体で呼ぶことはまずなく、コイツを介するのが常道である。
星10/神属性/幻神獣族/攻4000/守4000
このカードは通常召喚できず、このカードの効果でのみ特殊召喚できる。
(1):このカードが墓地に存在し、
「ラーの翼神竜」がフィールドから自分の墓地へ送られた場合に発動する。
このカードを特殊召喚する。
この効果の発動に対して効果は発動できない。
(2):このカードは他のカードの効果を受けない。
(3):1000LPを払って発動できる。
フィールドのモンスター1体を選んで墓地へ送る。
(4):エンドフェイズに発動する。
このカードを墓地へ送り、自分の手札・デッキ・墓地から
「ラーの翼神竜-球体形」1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。
ただし、原作では墓地に戻ったら蘇生されるまでそれっきりだったのが、墓地から
これにより、沈んでは上る太陽の如き不死身っぷりを発揮できるようになった。
《サイバネット・ユニバース》であれば使い減りしないため毎ターン回収することができ、まさに沈んでは上る太陽となる。
ただし、それでも《始祖竜ワイアーム》だけはどうやっても突破できない。
十全に生かしたいならば、
ただし、除去効果については対象を取らない=効果解決時にモンスターを選ぶことが仇となり、チェーンする形で他のモンスターが全て排除された場合、自身が墓地送りになってしまう上に
また墓地利用の典型であるため、除外対策に《王宮の鉄壁》も貼っておきたいところだが、その場合は《ファントム・オブ・カオス》が使用できなくなるため、デッキ構築はよく考えたい。