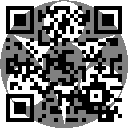235+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/24(土) 06:28:16
やぁ、ひさしぶり。じゃあ、最近考えてたことなどを書いていきますー
まず、非斉次?の行列多項方程式について考えてました。m次行列 X と実数係数 v_i について
Σ_{i=1}^n v_i X^i = M = Θ Λ' Θ^T (Θはm×n正規直交行列、Λ'はn次ジョルダン行列)
が成り立つとする。X = Θ X' Θ^Tとし、Λ'の n'_i次k_i乗ジョルダンλ_iブロック Λ_{O k_i}とすれば、
Σ_{i=1}^n v_i (X'のn'_i次ブロック)^i = Λ_{O k_i} = λ_i E + O_{k_i} (O_{k_i}はn'_i次k_i乗冪零行列)と分解できる。
上式は、((Σ_{i=1}^n v_i (X'のn'_i次ブロック)^i) - λ_i E)^{k_i} = O と変形できるので、条件に応じて導出される
この式を満たす解を (X'のn'_i次ブロック)=Λ_{i X'} とすれば、同様に導出できる i以外の(X'のn'_i次ブロック)も全て
用いて対角成分に並べた X' = Λ' […, Λ_{i X'}, …] = Λ'_X を使って、「 X = Θ Λ'_X Θ^T 」と導ける。…と思いましたが、
どうでしょうか?この非斉次行列多項方程式(と↑を勝手に仮に呼んでます)は 線型システムの話では結構出てくる
と思って いろいろ検索してましたが、引っかかるのは微分方程式系ばかりで この解法のヒントは発見できませんでした。
↑だといろいろおかしいし、つっこみどころ満載だと思いますので、誰か何か情報をくれるとありがたいです。。
236 :132人目の素数さん [] :2009/01/25(日) 01:01:45
次に、県内の一番大きい本屋に行っていろいろ見てきたんだけど目新しい情報は
Plucker relations(といっても名前だけは大学で聞いてた)ぐらいだったので、それについて書きます。
プリュッカー関係式は位置行列について通常より1列多い同次座標系で成り立つ関係式のような気が
しますが、大事なのはm×n方向行列Lとその中の方向ベクトルl_iをあわせた行列 (L l_i) の中から
(n+1)列選んだ行列の行列式が0になるという( _m C_(n+1) )×n通り(多分独立な関係式はその
中でも n(n-1)/2通りぐらい)の関係式が成り立つということだと思いました、が使い道は不明…
Plucker coordinates - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCcker_coordinates
あとは、m次元ユークリッド空間 U^m 内のあるn次元部分空間の基底を表すm×n行列を L とすれば、
m次元ユークリッド空間内のベクトルなどをその n次元部分空間へ正射影するm次基底変換行列
(正射影行列)は W[L] = L (L^T L)^{-1} L^T と書けるということが、↓の Orthogonal projections
の項で既に世界に概出してたのを発見しました。
Projection (linear algebra) - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Projection_(linear_algebra)
しかしまだ、位置行列 P と余因子行列 C[] と余因子総和行列 \tilde{C}[] を用いて 正射影行列が
W[L] = \frac{P \tilde{C}[P^T P] P^T}{1^T C[P^T P] 1} = \tilde{W}[P] と書き換えれることや、
U^m内での L の直交補空間の基底 Y に対して W[L] W[Y] = O, W[L] + W[Y] = E(単位行列)
となることや、始点は同じ基底 L と L' で作られる和空間の基底が Θ[L ∪ L'] = Θ[W[L] + W[L']]
(Θ[ ] は []内で与えられる空間や行列の基底を 列の基本変形や特異値分解によって返す関数)
であったり、積空間の基底は Θ[L ∩ L'] = Θ[ E - W[W[ E - W[L] ] + W[ E - W[L'] ]] ] と表せたり
するようなことは、世界に概出してない!こともないか… という雑感。。
237+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/25(日) 02:37:40
そういえば、あまり関係ない簡単な話ですが、任意のn次元列ベクトル \bm{a} について、
\bm{a}^T \bm{a} = 1 のとき、-√n ≦ \bm{1}^T \bm{a} ≦ √n (原点から単位超球上へのベクトルと\bm{1}の内積)が成り立ち、
また、\bm{1}^T \bm{a} = 1 のとき、\bm{a}^T \bm{a} ≧ 1/n (\bm{1}/nを通る\bm{1}/nの直交補空間上へ原点から向かうベクトルの長さ)
という関係式が成り立つと思われ。。美しいちゃ美しいけど、トリビアっちゃあトリビアル。
238+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/25(日) 06:08:29
「線形代数/線型代数 5」の416さんの問題
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/416
>任意の正整数 n に対して次の条件を満たす4n×4n行列Aが存在する.
>(1) Aの成分は±1, (2) A A^T = 4n I
成分が±1/(√m)であるm次正規直交行列Θ(Θ^T Θ = E)は存在するか?だとすれば、
i≠jでθ_i^T θ_j = 0より、互いに半分の成分の符号が違わねばならず、満たすとすれば
m=2のときの[1/√2, 1/√2; 1/√2, -1/√2]のみでそれ以外のmでは存在しない?
>実数 a_1, ..., a_n が非負行列の固有値となる必要十分条件は何か.
m≧nのあるm×n正規直交行列Θに対して その非負行列が ΘΣ[a_1, ..., a_n]Θ^T と書けること?
だと思いました。先方のスレでは華麗にスルーするふいんき(←)を感じた。。
239 :132人目の素数さん [] :2009/01/26(月) 05:51:58
「線形代数/線型代数 5」の話
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/392-393
先方のスレでは、449さんがスルーしない空気を作りましたが、俺は こっちの>>238で恥ずかしいこと
書いてしまったので、あっちでマルチもリンクも書けない!やっちまったなぁー。こっちにだけ書く!
>(392の意訳) n次正則行列 A, B を並べた行列 [A B] の n次部分行列 C で perm(C) ≠ 0 なるものが存在する。
この条件なら、A=B=Cとしてもいいと思うので、perm(正則行列C) ≠ 0 なるもの、存在する。
>(393の意訳) 有限体Fを剰余類Z/kZ (k≧4)とする。F上の任意のn次正則行列 A に対し、
> 全ての成分に零元 [0]_k を含まないF上のn次元列ベクトル x, y で A x = y を満たすものが存在する。
例えば、Aを単位行列 A=[E]_k とすれば、[0]_kを含まないベクトル A x = x = y が存在するのはわかりますが、
任意の正則行列Aとなると、たぶん存在すると思いますが、どう証明すればいいのかちょっと浮かびません…
ーーここまでーー
というのが向こうで未解決問題と言われてるもののの全てかな。さすが、難しいーぉ。。
240+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/27(火) 07:13:14
「線形代数/線型代数 5」の455さんの問題について
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/455
向こうの流れを妨げたくないので、例によって、問題を意訳しつつこっちにパクリます。
(1)n次元ベクトル a, x とおいたとき、xに対して成分積 a ⊙ x を対応させる線型変換は、
a ⊙ x = Σ[a] xより、aの成分を対角に持つ対角行列 Σ[a] で表せる。
(2)n次行列 A のi列 a_i をn次元列ベクトル x で置き換えてできるn次行列を A_i(x) = \underset{(a_i ← x)}{A}
としたとき、行列式について |[ \underset{(a_i ← x)}{A} ]| = e_i^T C[A] x と(e_i は i成分が1の単位ベクトル)
書ける。これより、xから n次元列ベクトル [A_1(x), …, A_n(x)]^T = C[A] x への線型変換に対応する行列は
Aの転置余因子行列 C[A] で表せる。
(3) |[ A ]| = |[ (a_1 a_2 a_3) ]| = 1 のとき、f(x) = |[ ((3x+6)a_1+3a_2+(2x-1)a_3, -4a_1+(x+7)a_2-a_3, 5a_1+5a_3) ]|
= |[ A ]| |[ [(3x-6), -4, 5], [3, (x+7), 0], [(2x-1), -1, 5] ]| = 5 ((x+1)^2 -27)となることから、この行列式 f(x) は
x=-1のとき最小値 f(-1) = -135をとり、f(x)の絶対値の最小値は0でそのときはx=-1±3√3のどちらかである。
(2)はn次元単体を作る基底 L やその基底と座標 a = [a_1, …, a_n]^T で表される点を l_a = L a としたとき、
a_i は n次元単体のi点を除くi対面と点 l_a によって作られるn次元単体の体積を 元のn次元単体の体積で
割った値(以下、正規i分積)である(a_i = |[\underset{(l_i ← l_a)}{L}^T \underset{(l_i ← l_a)}{L}]| / |[L^T L]|)
となること、つまり、点を表す基底の座標ベクトル a は そのまんま 「点が基底を分割する体積比」であることを
表している!しかし、こっちで書いてる俺独特の表記を使っていろいろ書きたかっただけだった気持ちもあった…
241 :132人目の素数さん [↓] :2009/01/27(火) 08:35:42
「微分幾何学2」の13さんの情報
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1181801767/13
意訳>平面上にある2つの閉曲線の距離がどこも r なら、
その外側と内側の閉曲線における周の長さの差は 2 π r である。
と、昨日見て、うわっすげぇーと思いつつ、曲率半径が r 未満の曲率中心方向には囲めないとか、
n次元多様体に拡張して距離 r で囲んだら表面の差は 半径rのn次元超球面と同じにはならない(!)
とか考えてました。同心超球とか萌え。しかし、n次元多様体で成り立つ関係式がなんかあった気がしたんだが…
いや、そして、何もオチはないですが… さて、m次元ユークリッド幾何学っと。。
242+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/28(水) 07:19:14
>>240 の(正規i分積)=(p_a= P \tilde{a} で表される内部点の単体座標 \tilde{a} のi成分(i=0~n))= a_i は
(n次元単体を作る(n+1)点への位置ベクトルを列挙した位置行列 P も線型独立(原点から
n次元単体への垂線ベクトルp_y= P C[P^T P] 1 / (1^T C[P^T P] 1) ≠ \bm{0})のときでなければ、
P \tilde{a}_\bm{0} = \bm{0}と任意のαで P \tilde{a} = P (\tilde{a} + \tilde{a}_\bm{0} α)に注意)
a_i = √(|[\underset{(l_i ← l_a)}{L}^T \underset{(l_i ← l_a)}{L}]| / |[L^T L]|)でした(ルート忘れてた)。
(↑はi=1~nで、a_0 = √(|[(L - l_a 1^T)^T (L - l_a 1^T)]| / |[L^T L]|) = |[(E - a 1^T)]| = 1 - 1^T a)
a_i を 位置行列 P で書き換えると、a_i = √(1^T C[\underset{(p_i ← p_a)}{P}^T \underset{(p_i ← p_a)}{P}] 1) / √(1^T C[P^T P] 1)
であるので、Σ_{i=0}^n a_i = 1^T \tilde{a} = 1よりΣ_{i=0}^n √(1^T C[\underset{(p_i ← p_a)}{P}^T \underset{(p_i ← p_a)}{P}] 1) = √(1^T C[P^T P] 1)
(n次元単体Pの超体積は、そのn次元単体を内部点p_aによって(n+1)個のn次元単体に分けたi分積の総和に等しい)が成り立つ。
これは、Σ_{i=0}^n √(1^T C^T[\underset{(\tilde{e}_i ← \tilde{a}_i)}{\tilde{E}}] X C[\underset{(\tilde{e}_i ← \tilde{a}_i)}{\tilde{E}}] 1) = √(1^T X 1)
(ただし、1^T \tilde{a} = 1、a_i ≧ 0)であることを表していると思うが、まだ計算で左辺から右辺に持っていけてはないです。。
このことを用いれば、n次元単体Pについて、その重心 p_G = P \tilde{a}_G = P \tilde{1}/(n+1) により分けられるi分積は全て等しい(a_{iG} = a_{j G} = 1/(n+1))、
および、その重心から各i対面への距離(下ろした垂線の長さ)の比が 元のn次元単体の各i垂線の長さの比に等しい(i対面×垂線=超体積)
などが言えます。とここに適当に掻い摘んでダラダラ書いたところでただのオナニーでしかなく、ちゃんと@wikiとかにまとめなきゃいけねーんだなぁー大変だなぁー
243 :132人目の素数さん [↓] :2009/01/30(金) 23:57:17
いろいろ迷って止まってます…このご時世で2月3月は暇そうなので がんばろうと思てます…
【PDF形式】132人目の素数さん『m次元ユークリッド空間内でのn次元単体の五心などの導出』【最新】
ttp://www7.atwiki.jp/neetubot/pub/neetubot.pdf
244 :132人目の素数さん [] :2009/02/02(月) 17:53:19
「線形代数/線型代数 5」の497さんの問題
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/497
(意訳)> m次元ユークリッド空間で、0-点(8,0,0,0…)・1-点(0,4,0,0…)・2-点(0,0,8/3,0…)を通る平面に対し、
3-点(5,4,3,0…)からの垂線と垂足を求めよ。(解は垂線(-1,-2,-3,0…)、垂足(4,2,0,0…)のようだ。)
をこっち的に言えば、m次元ユークリッド空間内の3次元単体の3点目の頂点からの3-垂線と3-垂足を
求めるという問題なので、各i点(i=0~3)をm次元列ベクトルp_iで表し、p_iを列挙した位置行列をm×4行列P
とすれば、(3-垂線)=-(P \tilde{C}[P^T P] e_3)/(e_3^T \tilde{C}[P^T P] e_3)、(3-垂足)=p_3+(3-垂線)より、
(ただし、余因子総和行列\tilde{C}[X]の[j,i]成分は、正方行列Xからi行とj列を除いた小行列X_{ij}の余因子行列C[X_{ij}]の
全ての成分の和1^T C[X_{ij}] 1に(-1)^{i+j}を掛けた値、すなわち、e_j^T \tilde{C}[X] e_i = (-1)^{i+j} 1^T C[X_{ij}] 1とする)
| 8 0 0 5 | | 6496/9 896/3 -672 -7168/9 |
P = | 0 4 0 4 | 、 \tilde{C}[P^T P] = | 896/3 12544/9 -896 -7168/9 | であることから、
| 0 0 8/3 3 | | -672 -896 1120 0 |
|↓0 0 0 0 | |-7168/9 -7168/9 0 14336/9 |
3-垂線(-1,-2,-3,0…)、3-垂足(4,2,0,0…)となる。(ちなみに、0-垂足(160/29, 80/29, 168/29, 0…)、1-垂足(8/7, 16/7, 24/7, 0…)、
2-垂足(24/5, 16/5, 0, 0…)と解ける。)この例では計算重いし、ぱっと見で あってるかわからないので、
以上より、@wikiとかに書く例は、原点とi点(…0, r_i, 0…)(i=1~n)で作られるn次元直交単体(n=2,3,n)の五心がいいなと。。
245 :132人目の素数さん [] :2009/04/08(水) 10:23:16
2ヶ月間 超だらけてたけど またがんばります。
以下、最近 考えてたことなど↓
線形代数/線型代数 5 のレス 790-797
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/790-797
から、任意の n次実行列Aが、ある n次正規直交行列Θと n次上三角行列Λを用いて、
1: A=ΘΛΘ^T と分解できる?(上三角分解?)
2: ケイリーハミルトンの定理より、Aの固有値λについての固有方程式を f_A (λ) = |[ λE - A ]| = 0 とすれば、f_A (A) = 0
3: k=0,1,…,nについて ||Λ^k p|| = 1 および |[Λ]| = 1 なら、k=n+1,…についても ||Λ^k p|| = 1 となる?
とか考えました。上のスレでもまだ答えは出てないようです。
n次元列ベクトル pを Λの正規一般固有ベクトル p_i (i=1~n)の線型結合で表して、
f_Λ (Λ) = 0とかも使ってグリグリ計算すると答え出る気がしないでもないですが、うーん…
246+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/08(水) 11:49:18
今まで転置余因子行列をC[・]で表してたけど、これから余因子行列をC[・]で表し 前述をC^T[・]で表そうと思いました。
理由は、n次元列ベクトル x_i (i=1~n)の列挙で作られる n×n行列 X=[x_1, …, x_n] とすれば、
Xの余因子行列を C[X] = [c_1, …, c_n] (c_i はC[X]のi列ベクトル)と書いたときに、
X^T C[X] = C^T[X] X = E |[X]| (Eは n×n単位行列、|[X]|は Xの行列式)と書けて、
c_i と x_j の内積 c_i^T x_j が i=jのとき|[X]|で i≠jのとき0と言えるので、
x_i をn次元ユークリッド空間内のn次元単体の 0点からi点への有向辺ベクトルと考えれば、
c_i = C[X] e_i は そのn次元単体のi点を除く(n-1)次元単体である i対面を表すベクトルとも考えられる。
ちなみに このとき、i点からi対面への i垂線ベクトルは 「 - c_i (|[X]| / (c_i^T c_i)) 」と表せる。
(ちなみに、このXで表されるn次元単体の超体積は|(|[X]|)|/(n!)、i対面の(n-1)次元超体積は(√(c_i^T c_i))/((n-1)!)。)
(個人的な趣味(位置行列Pと方向行列Lの間に成り立つ関係式を 1^T C[P^T P] 1 = |[ L^T L ]| と書きたかった)から
行列式を|[・]|で表してたけど、行列ノルムとして || L || = √( |[ L^T L ]| ) と書いていいなら、さっき使った苦肉の策の
行列式の絶対値を |(|[X]|)| = || X || と書けるのになぁと思った。そのうち、Wikipediaにある行列ノルムが満たすべき性質
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%88%97%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%A0 を満たすか調べようと思った。)
あと、全く関係ないですが、質問者→回答者よりも、出題者→解答者という言葉のが好きかな、とか。という備忘録
247+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/08(水) 18:06:53
下手の考え休むに似たり
248 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/08(水) 19:22:41
>>247 まぁ、あなたがどれほど上手で
僕に何を求めてるかはわかりませんが、
休むと休まざるとでは似て非なるものでしょう?(笑)
249 :132人目の素数さん [] :2009/04/08(水) 22:56:17
>>246 は、今まで、m次元ユークリッド空間内のn次元部分空間を表すL (以下、U^m ⊇ U_{p_0}^n [L] と書く)で
やってたものを、n次元ユークリッド空間内のn次元部分空間を表すX (以下、U^n ⊇ U_{p_0}^n [X])を用いたら、
余因子行列C[・]が意味するところ(C[X]は Xの 直交行列)は 幾何学的には「0対面以外の対面を表す行列」
と言えるのではと提言しました。ちなみに、0対面を表すベクトルは c_0 = - C[X] \bm{1} / n と書けると考えてます。
ちなみに、U^(n+1)内で n次元単体を位置行列Pで表す場合(以下、斉次を区別する記法\tilde{・}を\{・}で略す)は、
\{U}^(n+1) ⊇ \{U}^n [P] とか書き、(n+1)×(n+1)の余因子総和行列 \{C}[P] がそのまま「0~n対面を表す行列」
になるかと思ってますが、これはまだ詳しく試してません。
>>246 の過程から、ベクトルの大きさを表すユークリッドノルムのm×n行列(例えば L)への拡張として、
|| L || = (√( |[ L^T L ]| )) / (n!) と考えようと思いました。これを「単体積ノルム」とか呼びたいのですが、
Wikipediaにある || L || > 0 以外のノルムの性質?( || L α || = || L || | α^n | ≠ || L || | α | や他の
条件)を満たさないようなので、いいものかどうか…
とりあえず、わかってるところまでは書いてる気がするし、先人も全く見つけられないなか 暗中模索しながらやってるので、
あとは新しい情報や考えが浮かんでくるまで、みなさんも気長に読んだり書いたり ゆっくりしていってね!!!
250 :132人目の素数さん [] :2009/04/08(水) 23:39:30
U^m ⊇ U_{p_0}^n [L] のとき、n次元単体を作るL=[l_1, …, l_n]の各l_i はn次元部分空間を張るので線型独立となる。
しかし、\{U}^m ⊇ \{U}^n [P] で原点\bm{0}から Pで表されるn次元単体の各頂点へのベクトル p_i (i=0~n) は
1次元だけ線型従属となる(p_0がLの線型結合で表せる)場合があり、このときは P \{a}_\bm{0} = \bm{0} でも
\{a}_\bm{0} が零ベクトル以外の 1次元の任意性を表す解を持ち、原点\bm{0}から Pで表されるn次元単体への
垂線ベクトルも p_y = P ((C[P^T P] \bm{1}) / (\bm{1}^T C[P^T P] \bm{1})) = \bm{0} と書ける。このことから、
Pが線型独立の場合、P \{a}_\bm{0} = \bm{0} なら \{a}_\bm{0} = \bm{0}_n でしかなく、p_y ≠ \bm{0} 。
Pが線型従属の場合、P \{a}_\bm{0} = \bm{0} でも \{a}_\bm{0} ≠ \bm{0}_n が存在し、p_y = \bm{0} でもあるため、
\{a}_\bm{0} = ((C[P^T P] \bm{1}) / (\bm{1}^T C[P^T P] \bm{1})) α (αは任意の実数) という式が成り立つと思う。
しかし この式は、p_i = \bm{0} を含む場合や、Pが線型独立の場合との整合性などが怪しいので確かめたい。
そろそろ一年やってみて、この先 一年くらいは これまでの成果などを まとめるターンかと 個人的に思ってますが、
同じような事を何度も書くのは けっこうトリビアルだとも思って 休んでしまうときもあるので、 …ゆっくりしていってね!!!
251+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/09(木) 08:11:08
今日、たぶんもうdat落ちしている「シンプルで難しい問題」スレにあった
「凸五角形Sと その対角線によって作られる内部の凸五角形S'の 面積比S/S'の最大値を求めよ」
という問題に興味を持ちました。昔の数セミの問題らしいけど僕にエクセレントな回答は思い浮かびそうも無いので、
xy平面上の5点を[x0,y0],…,[x4,y4]として面積比を出して 凸の条件から導出するくらいしか考えつかないなぁー。
例えば、凸四角形と その頂点からその頂点を含まない2つの対辺の中点へ向かう線の組み合わせで
得られる内部の凸四角形との面積比とかなら、よりやりやすい気もした。 n次元(n+1)点複体ならどうか…zzz
平面の話ということで、これまた気になってたクリフォードの定理などと結び付けられたら面白くなりそうだな、と思った。
252+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/10(金) 04:53:25
>>251 まず問題は「凸5角形の面積をS、対角線で作られる小5角形の面積をS'とするとき、S'/Sの最大値を求めよ。 」と逆でした。
最小値は凸5角形じゃなくなるときのS'/S=0かな。俺がやったのは、小五角形の内部点から凸五角形の5点への2次元ベクトルを
x_i = [r_i cosθ_i, r_i sinθ_i] (極座標のように)として、x_iの始点から反対側にある小五角形の点への2次元ベクトルを y_i とすれば、
y_0 = (1-a) x_1 + a x_3 = (1-b) x_2 + b x_4などからy_iが出て、S'/S=(y_0×y_1 +…)/(x_0×x_1 +…)で定式化できると考えましたが、
計算が重すぎて、いろいろやったあげく、4 √(5+2√5) = (1+√5) √(10+2√5) という等式が成り立つのを見つけたところでギブアップ。
ということで、答えを探した結果、五角形の面積比問題
http://cheese.2ch.net/math/kako/955/955485321.html
で解である 「正五角形のとき S'/S=(7-3√5)/2≒0.146」 (小さすぎる?)が最大値というのと、
証明らしきものが載ってましたが、よくわからなかった。それより下記が気になった↓
106 名前: 甘美なノルム空間 投稿日: 2000/12/21(木) 05:01
凸N角形の面積をS、
頂点を反時計回りにV(0), v(1), ..., V(N-1)とし
V(x)とv((x+2)mod N)を結んで小N角形をつくる。
小N角形の面積をS'と するとき、
Q1.正N角形の場合、NについてS'/Sを求めるの関数を求めよ。
Q2. S'/Sの最大値をNについて求める関数を存在するか。
Q3. N=5のとき、S'/Sの最大値を求めよ。
↑の凸N角形の縮小変換を再帰的に行って収束する点を求める問題とかも面白いかも。
時計回りに点を選んで逆方向で縮小変換を繰り返したら 反時計回りと違う点に収束するかも!?
253 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 06:56:06
「面白い問題おしえてーな 九問目」スレ
http://www3.tokai.or.jp/meta/gokudo-/omoshi-log/1093676103.html
176 名前:132人目の素数さん:04/09/17 06:14:35
別スレみてて思いついた
――問題――
P1・・・P(n+1)をn次元ユークリッド空間の点としてΔをその凸包とする。
行列A=(aij)を次でさだめる。
aij=
0 (i=j)
1 (i≠j, n+2∈{i,j})
d(Pi,Pj)^2 (otherwise)
(ただしd(Q,R)はQとRの距離)
このときdetA=-(-2)^n(n!volΔ)^2が成立することをしめせ。
――――――
たぶんいけると思うんだけど。
179 名前:132人目の素数さん:04/09/18 20:27:35
>>176の公式ってなんか名前ついてんの?
というやりとりを発見しましたが、この後この発言にはレスが付いてませんでした。当スレでは >>20さんの情報から これは「Heron の公式の高次元版」として公知であると思ってます。
私的には、m次元ユークリッド空間内の(n+1)点への位置ベクトルを p_i (i=0~n)として、b_{ji}=(p_j-p_i)^T (p_j-p_i) / 2 を (j+1)行(i+1)列の成分に持つ(n+1)×(n+1)行列 \{B} (辺乗行列と
呼んでいる)とすれば、-\{B}の余因子行列 C[-\{B}] と 全ての成分が1のベクトル \{1}を用いて、
p_i (i=0~n)で表される(n+1)点の凸包であるn次元単体Lの超体積||L||は √(\{1}^T C[-\{B}] \{1}) / (n!)と書くと美しいと思ってます。(参考:http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/16.html)
個人的に使っているこの辺乗行列\{B}を用いれば、i番目の斉次n次元単位ベクトル\{e}_iや余因子総和行列\{C}[・]を使って、
辺乗行列が\{B}となるn次元単体の外接超球の半径 r_O が r_O = √(|[ - \{B} ]| / (\{1}^T C[-\{B}] \{1})) と書けたり、
そのn次元単体の内接超球の半径 r_I が r_I = 1/(Σ_{i=0}^n √((\{e}_i^T \{C}[-\{B}] \{e}_i) / (\{1}^T C[-\{B}] \{1})))
と書けたり、n次元単体の重心と各頂点との自乗距離の総和が (\{1}^T \{B} \{1}) と書けると思います。という宣伝。
254+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 07:05:45
>>237 で自分で書いときながら、半分忘れてて、↓スレで質問しつつ、回答から拡張してたのの備忘録↓
分からない問題はここに書いてね305
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1239022787/40
40 名前:132人目の素数さん[] 投稿日:2009/04/07(火) 15:00:47
「x_1 + x_2 + … + x_n = 1 のとき、x_1^2 + x_2^2 + … + x_n^2 ≧ 1/n」
のような不等式(とその名前)を何処かで見かけた気がするのですが、誰か知ってませんか?
コーシーシュワルツやヘルダーの不等式の関係っぽい気もしましたが、うまく導けない…
71 名前:40[] 投稿日:2009/04/08(水) 00:03:49
>>43 さんのように、コーシーシュワルツの不等式 (Σ_{i=1}^n x_i^2)(Σ_{i=1}^n y_i^2) ≧ (Σ_{i=1}^n x_i y_i)^2
に y_1=y_2=…=y_n=1 と仮定のΣ_{i=1}^n x_i = 1を代入して Σ_{i=1}^n x_i^2 ≧ 1/n を導く方法と、
>>44 さんのように、数学的帰納法を使って証明するやり方を納得できました。 ありがとうございます!
このような不等式をヘルダーの不等式にあてはめて考えて、
「 Σ_{i=1}^n | x_i | = a のとき、p > 1 なら Σ_{i=1}^n | x_i |^p ≧ (a^p)/(n^(p-1))、
0 < p < 1 なら Σ_{i=1}^n | x_i |^p ≦ (a^p)/(n^(p-1)) 」という不等式も出ました。
これは、第1象限で n次元超平面と n変数p次曲面の位置を比べてるとも考えられたりして、
ヘルダーの方の式で 絶対値をとれるかとか p < 0 の場合どうなるかとかも考えてみたいと思いました。
というのを また忘れそうなので、このスレにコピペしおてく。。
今日こそ、2ヶ月いやもっと長く戦ってきた見えない敵(垂足単体の内心が元のn次元単体の垂心となるか)に決着を付けたい…
255 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 08:04:26
任意のm×n行列L (m≧n)について、m×n正規直交行列Θと n×n上三角行列Λを用いて、
L = Θ Λ と分解できないかな?m=nの場合に成り立つならできそうだけど…何分解だっけか…
何がしたいかというと、任意のn次元単体は うまく回転変形すれば n次元空間で拡縮を含むせん断変形(shear)成分だけになる
と言いたい感じです。そして、この成分をn乗Λ^nして…ってことじゃなかった気がしたけど…あれ?なんだったっけ
256 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 08:26:39
「面白い問題おしえてーな 九問目」スレ
http://www3.tokai.or.jp/meta/gokudo-/omoshi-log/1093676103.html
248 名前:132人目の素数さん:04/10/01 04:30:50
三角形の内部に点Pを取る。
点Pから三角形の各頂点への距離の和をS
点Pから三角形の各辺への距離の和をTとするとき
S≧2Tを示し、等号成立条件を求めよ。
同様に、四面体において内部に点Pを取り
点Pから四面体の各頂点への距離の和をS
点Pから四面体の各辺への距離の和をTとするとき、
S≧T√8を示し、等号成立条件を求めよ。
284 名前:132人目の素数さん:04/10/05 22:26:33
http://www.geocities.jp/ikuro_kotaro/koramu/hutou1.htm
…中略…
まぁ、俺が張ったアドレスの方が間違いって言う可能性もあるんだし、
とりあえず、証明出てくるまでは、2ch的未解決っていうことで。
2ch的未解決問題か…オラ ワクワクしてきた!
ということで、このスレ見てる方いらしたら、出題とか質問とか 何でもしてくれたらうれしいです
257 :132人目の素数さん [] :2009/04/11(土) 07:46:18
>>252 凸(n+1)角形の頂点を二点おきに結ぶなら、時計回りも逆回りも関係なく同じ縮小(n+1)角形が作られるだろうに。何を勘違いしてたんだ私は…
凸5角形の各頂点を反時計回りにi点(i=0~4)と呼び、0点からi点(i=1~4)へのベクトルをl_iとして、l_2,l_3をl_1,l_4の線型結合で表して解こうとしましたが、
わかったことは、mをnで割った余りを[m]_nで表すとき、i点と[i+2]_5点および [i+1]_5点と[i+3]_5点を結ぶ線の交点を小i'点とすれば、下記のことでした。
・i点と小[i+1]_5点を結ぶ 5つの線は一点で交わらない。
・凸5角形の重心と、小i'点で作られる小5角形の重心は一致しない。
・凸5角形に外接する楕円は一意に求まるが、その外接楕円の中心と小5角形の外接楕円の中心は一致しない。
最後のは目見当ですが…。凸5角形の各辺の中点を結ぶことで再帰的に小5角形を作る場合なら、元の凸5角形の重心に収束しそうなのに、
って、やべぇ、これは決定的なアイディアが浮かんでしまったか!?でも収束するなら重心しか考えられないけど…それは少しやだなぁ…
凸(n+1)角形(n+1≧5)の頂点をk個(k=2~⌊n/2⌋)飛ばしで結び、内部にできる縮小(n+1)角形についても同じ縮小変換を繰り返すとき、
この操作を無限回行うことで収束する点を 「凸(n+1)角形k点飛縮収束点」と仮に呼び、以後これらの問題を 形縮収束点の問題とでも呼ぶぉ。
258+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/12(日) 08:49:54
凸5角形の各頂点を反時計回りにi点(i=0~4)と呼ぶ。
0点からi点(i=1~4)へのベクトルをl_iとして、l_2 = l_1 s_2 + l_4 t_2、 l_3 = l_1 s_3 + l_4 t_3となるとする。
(このとき凸5角形という条件から、s_2 > s_3 > 0、 t_3 > t_2 > 0、 s_2 + t_2 > 1、 s_3 + t_3 > 1であると考えられる。)
凸5角形の周上のi点と[i+1]_5点の中点で囲まれる小5角形をS'とし、S'の元の凸5角形Sに対する面積比をFとする(0<F<1)。
この場合、 F=1/2 + (s_2 + t_3 - 1)/(4(s_2 t_3 - s_3 t_2 + s_3 + t_2)) と導出でき、
たぶん(s_2 = t_3、s_3 = t_2としてしか試してないが…)凸5角形の条件下で∂F/∂s_2 = ∂F/∂s_3 = ∂F/∂t_2 = ∂F/∂t_3 = 0 となる
s_2 = t_3 = (1+√5)/2、 s_3 = t_2 = 1 の場合に、Fが最大値 max[F]=(3+√5)/8 をとることが示せる。
ちなみに、Fの式から(s_2=s_3=t_2=t_3=1/2に近づくとき)Fは最小値1/2に限りなく近づくと考えられ、「1/2 < F ≦ (3+√5)/8」 だと思う。
このことは、正5角形でない適当な l_1とl_4でも成り立つので、凸(n+1)角形k点飛縮面積比が最大のときも正5角形とも限らないと予想できる。
また、一般的な凸(n+1)角形の各辺の中点(一定比の内分点でも同じか?)で囲まれる小(n+1)角形について、
常にその凸(n+1)角形と小(n+1)角形の内部にある重心が一致することから、再帰的にこの小(n+1)角形を作るとき、
その小小…(n+1)角形が 元の凸(n+1)角形の重心に向かって収束していくことが容易に想像できる。
これを仮に、「凸(n+1)角形辺中囲縮収束点はその凸(n+1)角形の重心となる」と言うことにする。
あと仮に、「n=4のときの凸(n+1)角形辺中囲縮面積比F(n+1)は 1/2 < F(5) ≦ (3+√5)/8 となる(F(3)=F(4)=1/2?)」とも書くことにする。
見てる方、ぜひ感想などをカキコしてくださるとありがたいです。
259+2 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/12(日) 09:24:32
ちなみに、凸5角形 2点飛縮 小5角形 と、凸5角形 辺中囲縮 小5角形 の
対応する周囲の辺は5組全て平行となるが、この2つの小5角形が相似であるとはいえないようだ。
少なくとも、この2つの小5角形の面積比が明確であるなら 凸(n+1)角形辺中囲縮面積比の答えを使えるのだが…
今後は、k点飛縮にも応用できる補助(n+1)角形をどうにか見つけようとするか、
凸5角形2点飛縮収束点を求めるために 凸5角形 外接楕円 を導出する式をちゃんと作るか、って感じー
後者は例えば、長方形の横に一点加えた凸5角形について、その外接楕円の中心と その凸5角形の重心が
ぱっと見で異なってしまうことからも、あまりいい式になるとは思いませんが…
U^m内で凸5角形の各頂点への位置ベクトルをp_i(i=0~4)とすると a x^2 + b x y + c y^2 + d x + e y + f = 0 の…
x y うわぁぁああぁあ(AA略)
260+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/12(日) 10:04:14
凸5角形は内接楕円も一意に定めることが出来るのか?
例えば、三角形と それをその重心を中心にその平面内で180度回転させた三角形をあわせた
魔方陣?のような図形が、外接楕円と内接楕円を一意に持つことからも、出来る気がするけど。
(この場合、対称性で1次元分?落ちる6点と6辺では成り立つからという意味)
外接楕円も、2次元内の5点という10変数から 楕円(というか2次曲線)の6変数
(中心点で2変数、長径短径で2変数、長軸の回転角と定数倍で2変数分)
を導出するという 供給過剰っぷりはどうか と思ってたら、全成分1のベクトル\bm{1}を用いて、
[a/f, b/f, c/f, d/f, e/f]^T = - […, [x_i^2, x_i y_i, y_i^2, x_i, y_i], …]^{-1} \bm{1} で(i=0~4)
ぴったり導出できますね。しかし、欲しいのは楕円の中心へのベクトルですから、残念。
261 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/12(日) 13:57:41
>>258 凸(n+1)角形辺中囲縮面積比F(n+1)は常に F(3)=1/4、 F(4)=1/2 でした。
>>260 円に外接する野球のホームプレート型の凸5角形に外接する楕円を考えれば、
凸5角形の内接楕円と外接楕円の中心は異なる場合があることが ぱっと見わかる。
262 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/15(水) 06:19:09
分からない問題はここに書いてね305
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1239022787/378
長さlの針金を l = l_1 + … + l_m に分け、それぞれのl_iで正n_i角形を作る時、
その全ての面積の和Sは S(m; n_1, …, n_m) = Σ_{i=1}^m (l_i^2 / (4 n_i tan(π/n_i))) と表せて、
>>254 のコーシーシュワルツの不等式で x_i = l_i / √(4 n_i tan(π/n_i)) および y_i = √(4 n_i tan(π/n_i)) と考えれば、
等号成立条件の x_i:x_j=y_i:y_j つまり l_i : l_j = n_i tan(π/n_i) : n_j tan(π/n_j) という比で針金を分けるときに
Sは最小値 min[ S(m; n_1, …, n_m) ] = l^2 / (4 Σ_{i=1}^m (n_i tan(π/n_i))) をとることが分かる。
端的に書くと、「Σ_{i=1}^m l_i = l のとき、a_i > 0 とすれば、
Σ_{i=1}^m (l_i^2 / a_i) ≧ l^2 / (Σ_{i=1}^m a_i) が成り立つ
(等号成立は l_i /a_i = l_j /a_j のとき)。」ということである。
ところで、「雑談はここに書け!【34】」スレで
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1234800000/506
で当スレが紹介されてました!あざーす!
263+4 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/19(日) 09:50:31
いやー数学板って荒れてますねーU^m内のn次元楕円体について考えたこと書きます。
まず、U^m内のU^n_{p_0} [L]で(m次元ユークリッド空間内の 始点p_0からのn次元部分空間を張る基底Lで)
m次元列ベクトルl_i(i=1…n)をi列成分に持つm×n方向行列Lを特異値分解すると L=ΘΣA^T となるとする。
(Θ=[θ_1, …, θ_n]はm次元正規直交ベクトルθ_iを列挙したm×n行列、Σは対角成分にn個の特異値σ_iを持つn次対角行列、Aはn次正規直交行列)
(ちなみに、Lは基底なのでA A^Tも単位行列Eとなり、内積行列 L^T L = AΣA^T と分散行列 L L^T = ΘΣΘ^T と固有値分解できる。)
このとき、Lの始点p_0を中心として Lのそれぞれの終点を通る n次元楕円体のm次元半径ベクトルは r_i=θ_i σ_i (i=1…nのn本)で表せる
(R=[r_1, …, r_n]=ΘΣ、および、e_{θ_i}^T e_{θ_i}=1となるn次元正規ベクトルe_{θ_i}を用いて、それぞれ l_i =R e_{θ_i} と書けるので)。
ここまでは固有値・固有ベクトルの性質として公知のものと思います。(参考→ ttp://q.hatena.ne.jp/1215959307)
264+4 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/19(日) 11:24:34
(訂正: >>263 5行目: 内積行列 L^T L = A Σ^2 A^T と分散行列 L L^T = Θ Σ^2 Θ^T (= R R^T) と固有値分解できる。)
しかし、>>263 は U^m内で n次元単体の0点を中心として 1点…n点を通る n次元楕円体を求めるという方法である。
今回、中心は不明の状態で、n'個の点に適切なn次元楕円体をfitting(以下、当嵌と言う)したい。>>259 の方法を見れば、
n次元楕円体を当嵌するのに必要な点の数は2次超曲面の係数の数以上なければならない気がするので n'≧n(n+3)/2 とする。
一般的のように、2次超曲面の2次係数のn×n対称行列をQ、1次係数のn次元列ベクトルをq_~、定数倍の不定性を表す項をq_{~~}としたとき、
この2次超曲面上の点pを f_Q [p] = p^T Q p + p^T q_~ + q_{~~} = 0 で表したいが、これはpがn次元ベクトルのときしか使えない。
そこで、最初に U^m内のn'個の点を表すm次元列ベクトルp'_i (i=1…n') から、この点が全て入ってるn次元部分空間を求めておくといいと思った。
以下は私的な考えであるが、この全ての点を表す行列 P'=[p'_1, …, p'_n'] とすれば、この全ての点の重心 p'_G = P' 1/(n'+1) を
中心に放射線状に各点へ出るベクトルを固有値分解する感じで得られる (P'-p'_G 1^T)(P'-p'_G 1^T) = P' P'^T - (n'+1) p_G p_G^T = R' R'^T
のR'(重心中心として簡易にn次元楕円体を当嵌したn本の半径の行列)、および、p_i = R' ρ_i となるn次元座標ベクトルρ_i (i=1~n')を最初に求めておく。
そうすれば、この2次超曲面上の点pを表す座標(p'_GからR'で測った座標R'^† p_i=)ρで、
f_Q [ρ] = ρ^T Q ρ + ρ^T q_~ + q_{~~} = 0 と書けるので、次の方法でρからQ,q_~および
全ての点p_i (i=1~n')にとって適切な当嵌であるn次元楕円体の中心とn本の半径ベクトルが求まる…と思う。
265+4 :132人目の素数さん [] :2009/04/19(日) 13:52:21
(訂正: >>263 下から5行目: = P' P'^T - (n'+1) p'_G p'_G^T、下から4行目: p'_i = p'_G + R' ρ_i、
下から3行目:座標R'^† (p - p'_G)=(ただし、R'の一般化逆行列R'^†=[r_1/(r_1^T r_1), …, r_n/(r_n^T r_n)]))
U^m内で点p'_i (i=1…n')をp'_GからR'で測ったn次元座標ベクトルをρ_i = [ρ_{1i}, …, ρ_{ni}]^T (i=1…n')とし、Qのj行i列成分q_{ji} とq_~のi行成分q_{i~} に対し
\ddot{q} = ([q_{11}, q_{12}, q_{22}, …, q_{nn}, q_{1~}, …, q_{n~}]/q_{~~})^T、および、υ_i=[ρ_{1i}^2, 2 ρ_{1i} ρ_{2i}, ρ_{2i}^2, …, ρ_{ni}^2, ρ_{1i}, …, ρ_{ni}]、
υ_iをi行成分に持つn'×(n(n+3)/2)行列をΥとすれば、f_Q [ρ] = ρ_i^T Q ρ_i + 2 ρ_i^T q_~ + q_{~~} = (υ_i \ddot{q} + 1)q_{~~} = 0より、Υ \ddot{q} = -1 となり、
【Υ^T Υが正則の時】 \ddot{q} = - (Υ^T Υ)^{-1} Υ^T 1 と n次元楕円体が通る点の座標の成分の行列Υから n次元楕円体を表す係数\ddot{q}が求まる。
また、このn次元楕円体の中心を表す座標をρ_Q、n次元楕円体のこの座標における半径ベクトルr_i (i=1…n)を列挙したn×n直交行列をRとすれば、
n次元正規ベクトルe_{θ_i}を用いて、(ρ_i - ρ_Q) = R e_{θ_i} と表せることから、ρ_i^T (R R^T)^{-1} ρ_i - 2 ρ_i^T (R R^T)^{-1} ρ_Q + q_{~~} = 0
【q_{~~} = ρ_Q^T (R R^T)^{-1} ρ_Q - 1とした】。ここで求まった係数\ddot{q}を Q/q_{~~}と q_~/q_{~~}=[O E] \ddot{q}の各成分に代入しなおし比べる。
上記をふまえて、Qを固有値分解すれば Q=ΘΣ[λ]Θ^T=(R R^T)^{-1} (Σ[λ]は対角成分がベクトルλの成分となる対角行列)となることから、
n次元楕円体の座標の半径行列は R = ΘΣ^{-1/2}[λ] と求まり、n次元楕円体の座標の中心は ρ_Q = R R^T [O E] (Υ^T Υ)^{-1} Υ^T 1 と求まる。
「このことから、U^m内で 【凸複体を作る】 n'個の点 P'=[p'_1, …, p'_n'] に対して 適切に当嵌できるn次元楕円体は、
中心が p'_G + R' R R^T [O E] (Υ^T Υ)^{-1} Υ^T 1 であり、半径行列が R' R = R' ΘΣ^{-1/2}[λ] である。」と考えられる。
(n'≧n(n+3)/2 だが、特にn'=n(n+3)/2 のとき、上式で与えられるn次元楕円体は 全てのn'個の点を通る。)
266+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/19(日) 14:00:26
>>263-265 は「点列へのn元2次超曲面の当嵌」について一般解を目指した導出のアルゴリズムです。あまり綺麗な式にならなかった。
凸複体を作る n'=n(n+3)/2 点に当嵌するとき、Υが正則になるなら、この式でその凸複体への外接楕円体が作れると思います。
内接楕円体については、複体では出せる気がしないので、n次元単体の重心を中心とする辺接楕円体(前述したっけ?)をのみ考えたいです。
267+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/19(日) 17:54:07
なんかもったいなかったので「球・球面の性質を1000個あげるスレ」を保守しました。みなさんもよろしく、とか言ってみたり
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1108524401/
あと、>>266 ではアンカーを>>264-265として、>>265-266では n次元凸複体とかn次元外接楕円体とか言うべきだと思いました。
ところで、(n+1)個のi点(i=0…n)で作られる n次元単体の重心p_Gを中心とする n次元辺接楕円体は、
>>264 をふまえて、>>265 から ρ_Q = R'^† (p_G - p_G) = 0であるので f_Q [ρ] = ρ^T (R R^T)^{-1} ρ - 1 = 0 として、
n次元単体のj点とi点を結ぶ線分上での辺接楕円体との接点を p_{d_ji} = p_j t + p_i (1-t) とすれば、
このp_{d_ji}の座標ρ→ρ_{d_ji} = R'^† (p_{d_ji} - p_G)で d[f_Q]=2 d^T[ρ] (R R^T)^{-1} ρ→0 となることから、
R'^‡=(R'^†)^T、M=R'^‡ (R R^T)^{-1} R'^†として、上式よりtを消去すれば、
接点は p_{d_ji} = (p_j (p_G - p_i)^T - p_i (p_j - p_G)^T) M (p_j - p_i) / ((p_j - p_i)^T M (p_j - p_i)) と書ける。
この接点の全てがn次元辺接楕円体上にあることから、ρ_{d_ji}^T (R R^T)^{-1} ρ_{d_ji} = 1 の全てを用いて R を求めればよい…
…うーん…重い…簡易に固有値分解で出せる R' と、真のn次元重中辺接楕円体の半径 R' R の違いは、大変興味があるのですが…
268+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/21(火) 02:58:40
(訂正: >>267 下から3行目: 接点は p_{d_ji} = (p_j (p_G - p_i)^T + p_i (p_j - p_G)^T) M …)
ここで、Δ_{G_ij} = p_j (p_G - p_i)^T + p_i (p_j - p_G)^T + p_G (p_i - p_j)^T とすれば、このm×m行列Δ_{G_ij}は、
掛けることによって p_G, p_i, p_j によって作られる三角形の法線方向への外積のようなものが出る行列だと思う。
例えば、√|(p_G - p_i)^T Δ_{G_ij} (p_j - p_G)|/2 がその三角形の面積になると昔計算したような気がする。
上記より、(p_j - p_i)^T M Δ_{G_ij}^T M Δ_{G_ij} M (p_j - p_i) = (p_j - p_i)^T M (p_j - p_i) (p_j - p_i)^T M (p_j - p_i)
から、n次元単体の各頂点P=[p_0, …, p_n]と その重心p_G=P 1/(n+1)で作る 分散行列を固有値分解して得られる
P P^T - (n+1) p_G p_G^T = R' R'^T の式を用いて、M=(R' R)^‡ (R' R)^† より n×n【直交】行列 R が求まる…
…んだがどうすりゃいいんだ…ぱっと見、Δ_{G_ij}^T M Δ_{G_ij} = (p_j - p_i) (p_j - p_i)^T と見えるのだが…
Rが対角行列となれば、n次元重中辺接楕円体のn本の半径ベクトルの方向が P P^T - (n+1) p_G p_G^Tの
固有ベクトルの方向と一致すると言えて、幸せになれるのだが、式の数はn(n+1)/2で直交Rにはピッタリっぽいし…
269+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/21(火) 21:53:58
>>268 で式の形からは、U^m内でn次元単体の重心p_Gからその各ij辺の垂線x_{G_ij}をn(n+1)/2本分列挙したm×(n(n+1)/2)行列
X = [x_{G_01}, x_{G_02}, …, x_{G_(n-1)n}] の分散行列を固有値分解することによって X X^T = (R' R) (R' R)^T となるm×n直交行列
(重中辺接楕円体の半径行列)R' Rが求まり、その「n次元単体の重中辺接楕円体」(と仮に呼ぶ)が出せると予想します。
しかし、計算の方は全然できないので保留します。数値計算ソフトでいろんな分散行列を固有値分解して図示して確かめたいなぁー
話は変わりますが、「数学の本 第33巻」スレの401さん情報
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1236443234/401
401 名前:132人目の素数さん[sage] 投稿日:2009/04/18(土) 21:27:12
google book って数学書がほとんどのページ見られたりするけど大丈夫なのかこれ。
とのことで、ありがとうございます!やったー!このときを待っていた!
>>20 さんのは日本の本だからか見つけられませんでしたが、原著と同じ人の本で似てる本↓
http://books.google.co.jp/books?id=aE_-qdthsWcC&pg=PP1&dq=Ronald+L.+Graham+discrete+Mathematics&lr=&as_brr=3
>>34 さんのは http://books.google.co.jp/books?id=iWvXsVInpgMC&printsec=frontcover&dq=Coxeter+Regular+Polytopes&as_brr=3
>>35 さんのは http://books.google.co.jp/books?id=upYwZ6cQumoC&printsec=frontcover&dq=Sphere+packings&as_brr=3
で発見できました!代数幾何学とか日本語の本もたくさんあった。Googleまじ神!!!
270 :132人目の素数さん [] :2009/04/21(火) 23:51:21
あと、猫先生(?)関係のスレでarXivという論文投稿サーバ(?)というのを知りました。
URI→http://arxiv.org/archive/math
このサイトの分類だと当スレの分野はEuclidianのある math.MG - Metric Geometry かな?
代数幾何学や位相幾何学は難しいので、わかりやすい解析幾何学を生涯かけてやりたいです。
271+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/26(日) 03:43:29
>>269 上の計算じゃ合いません。考えた結果、U^m内でn'個の点列\P=[\p_1…\p_n']があり、その点列の重心\p_G
を中心として 半径を表す直交行列\R=[\r_1…\r_n]で作られるn次元楕円体上にその点列が全てある特別な場合は、
「(\P \P^T - \p_G \p_G^T) (2/n') = \R \R^T」と書けて、重心から点列への行列\P-\p_G \1^Tの各特異値の√(2/n')倍が
そのn'個の点列を通るn次元楕円体の各半径の長さになると言えると思いました。
n'個の点列\Pが楕円体上でなくn次元正規分布に従う時、\Pの重心から点列への\P-\p_G \1^Tの特異値の√(1/n')倍が
その正規分布の標準偏差であるとも考えました。これより、正規分布に従う点列で作る分散行列\P \P^T - \p_G \p_G^Tと
その標準偏差の1/√2倍の半径の楕円体上にある同じ数の点列(その重心は楕円体の中心)で作る分散行列は一致する
と言えると思ってます。これらはもう少し考えたいので、これらを「楕円体当嵌の問題」と呼び、後でまとめたいと思います。
272+3 :132人目の素数さん [] :2009/04/29(水) 16:50:32
(訂正: >>271 とかいろいろ:U^m内でn'個の点列\P=[\p_0…\p_n']に最小自乗当嵌される、中心\p_G=(\P \1)/(n'+1)で
半径\R=[\r_1…\r_n]のn次元楕円体は (\P \P^T - (n'+1) \p_G \p_G^T)(n/(n'+1)) = \R \R^T を満たす。という予想)
>>264-265 より点列\p_i (i=0…n')にn次元楕円体を当嵌したい場合は、\p_i = \p_G + \R \ρ_i (\ρ_i =[ρ_{1i}…ρ_{ni}])
とすれば、一次独立なυ_i=[ρ_{1i}^2, 2 ρ_{1i} ρ_{2i}, …, ρ_{ni}^2, ρ_{1i}, …, ρ_{ni}]が係数分n(n+3)/2個必要なため
(このとき\p_i (i=0…n')はn次元を張る二次独立な基底で作られると言う)、最低でも n'≧n(n+1)/2 の点列が必要である。
このn次元二次超曲面(楕円体)を当嵌できる点列を、仮に「n次元二次位底以上の(n'+1)点」(n'≧n(n+1)/2)と呼ぶ。
(ちなみに、n次元部分空間(超平面)を定めれるような点列を、仮に「n次元一次位底以上の(n'+1)点」(n'≧n)と呼ぶ。)
また、「標準偏差σの正規分布と、値±σを同確率でとる二値分布は、同じサンプル数なら分散(標準偏差)が等しい」
と統計学関連から言えると思い、多変量解析に応用すれば「標準偏差σ_i (i=1…n)のn次元正規分布と、半径σ_iの
楕円体上の点(と中心をはさんでその反対側の点)を同確率でとる分布は、同じサンプル数なら分散行列が等しい」
と言えると思いました。
ところで、中心を\p_Qと固定してn次元一次位底以上の(n'+1)点にn次元楕円体を当嵌する場合、この(n'+1)点\P_+に
対して中心\p_Qをはさんでその反対側にある(n'+1)点\P_- = 2 \p_Q \1^T - \P_+も一緒に2(n'+1)点\P=[\P_+, \P_-]
と考えれば、中心\p_Q=\P \1/(2(n'+1))=\p_Gと考えれば、本来 分散行列(\P_+ - \p_Q \1^T) (\P_+ - \p_Q \1^T)^T
で計算するところを、前述の分散行列 (\P_+ \P_+^T - (n'+1) \p_Q \p_Q^T)(n/(n'+1)) = \R \R^T の式に帰着できる。
これは、>>271 では中心は重心だけとしていたが、別に任意の中心\p_Qと固定しても上式で一次位底以上の(n'+1)点にn次元楕円体を当嵌できることを示している。
273+2 :132人目の素数さん [] :2009/05/07(木) 01:42:05
(訂正: >>272 上から1行目: U^m内で(n'+1)個の点列\P=[\p_0…\p_n'])
ところで、「m次元ユークリッド空間内における n次元二次超曲面 f_Q[\p]=\p^T \Q \p + 2 \p^T \q_~ + q_{~~}=0の
概形と、点\p'での接線\d'と、点\p'で接線\d'での曲率半径r'_Qなどを、例によって行列で計算しました。
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/61.html
http://www7.atwiki.jp/neetubot/?plugin=ref&page=%E5%8D%98%E4%BD%93%E5%BF%9C%E7%94%A8%2F%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%B6%85%E6%9B%B2%E9%9D%A2&file=fq.JPG
これより、特にU^m内において、中心\p_Qと直交半径行列\R_Qで作られるn次元楕円体上の点を\p'=\p_Q + \R_Q \e_θ
(\e_θ^T \e_θ=1)で表せば、その点\p'上での接線\d'は\e_θ^T \e'_θ=0および\e'_θ^T \e'_θ=1となる\e'_θを用いて
\d'=\R_Q \e'_θと書けて、その点\p'上で接線\d'の方向に対する曲率半径\r'_Qは下記のように書けることが言える。
\r'_Q = - \R_Q (\R_Q^T \R_Q)^{-1} \e_θ (\e'_θ^T \R_Q^T \R_Q \e'_θ)。」と考えました。どこかで見たかも、微分幾何学か?
274+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/07(木) 02:03:24
>>273 「二次曲面 - Wikipedia:」↓では楕円体の体積の式も載ってました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%9B%B2%E9%9D%A2
でも、↑ではm=n(かm=n-1)で固定してる気がする。 おやすみ。
275 :132人目の素数さん [] :2009/05/15(金) 02:56:04
今日のコマ大の問題は、http://tv.dee.cc/jlab-maru/s/maru1242318622236.jpgで、
三角形ABCの外接円上の点PからAB・ACにおろした垂足M・N間の長さが最大になるのは、
APが外接円の中心を通るときで、そのときM・NはB・Cに一致するという話が出てました。
これを、始点を固定したn本の基底\L=[\l_1…\l_n]の始点と終点で囲まれるn次元単体に拡張すれば、
その外接超球上の点から\l_iにおろした垂足が作る(n-1)次元単体の超体積が最大となる点\l_xは、
始点から外接超球の中心へのベクトル\l_Oの2倍の点\l_x=\L (\L^T \L)^{-1} Σ[\L^T \L]と言えそう。
この点を仮に外心対称0点と呼び、n次元単体の外心対称を外心対称単体などとでも仮に呼びます。
すると、n次元単体の重中外接楕円体はその重心対称単体の重中外接楕円体と一致するとか言えます。
一般次元では超楕円体と呼ぶのが普通なら、それは長すぎて嫌で、むしろn次元超楕球とか呼びたい気…
ちなみに、n次元単体の外接超球上の点からそのi対面(i=1…n)におろした垂足が作る(n-1)次元単体の
超体積が最大となる点と考えても、外心対称0点しかありえない気がして、そのときこの垂足(n-1)次元単体
が上記の\l_iへの垂足が作る(n-1)次元単体と超体積が同じになっちゃったりするのか、…おやすみ…
276 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/15(金) 03:09:52
今、n次元単体の外接超球上の点から、i対面への垂足(n-1)次元単体の超体積の最大値の方が、
\l_iへの垂足(n-1)次元単体の超体積の最大値(このとき0対面となる)より小さい気がしました。
ちなみに、>>274の最後の行は、m=n(かm=n+1)と言うべきでした。
277 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/15(金) 18:23:04
『楕円』関係のスレ
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1220920513/14
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1220920513/22
で、二次超曲面とある点との距離(の最小値)について質問みたいのがあって、
n次元楕円体とある点の距離なら>>273とか使って、空間ごとn次元超球と
ある点との距離に帰着すればいいと思ったけど、なんか計算うまくいかん…
278 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/15(金) 18:47:40
垂足三角形の内心が垂心となるのは、元が鋭角三角形のときだけらしく、
あるn次元単体の垂足単体の内心の点(名前知らない)が垂心となるためには、
けっこう複雑な条件がある気もしました…直角以上があると一致すらしないし…
279 :neetubot [] :2009/05/15(金) 19:20:05
雑談はここに書け!【34】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1234800000/741
でおもろないって言われてたし、ネタも尽きたので、
これからコテつけて質問とかに答えるスレにしたいぉ!
なんか言ってみそ
280+1 :neetubot [↓] :2009/05/26(火) 08:34:48
http://blog.livedoor.jp/melbo2_oko3re/
で3次元以下の単体の五心はうまくまとめられてる気がした。
http://blog.livedoor.jp/melbo2_oko3re/archives/488155.html
で『「位相幾何学」のホモロジー群の計算にでてくる「単体の重心座標」』という言葉がありビックリ!
重心座標はここでいうところの、n次元単体の位置行列\Pと同じ空間にある点\p_a=\P \~aの\~aの部分で、
点\p_aによって単体\Pが(n+1)個の単体に分かれるときの体積の2乗の比を表すので単体座標\~aとか>>242で呼んでた気がした。
あと、上で三線座標・四線座標(ある点に対するi対面からの距離比)と呼ばれてるものはここでは、
単体座標\~aをn次元単体の各i対面の超表面積の2乗で割った\~x(つまり、\P \~a=\P \Σ[\~C[\P^T \P]] \~x)を用いれば、
この\~xはまさしく点\p_aに対するn次元単体のi対面からの距離の2乗の比となり、ここでは分面座標と呼んだ気がした。
また、三角形の各頂点からの距離の比を座標にしたものは、三角座標?trianglar functionだっけ?とか呼ばれてるようで、
これはn次元単体に拡張してもこの座標を指定しても満たす点が内分点と外分点のように2点あるのであまり流行ってないっぽく、
しかし、n次元単体の各i頂点からある点\p_aの距離の比をt_iとして、i=0…nのt_i^2をi行成分に持つ\tとすれば、
そのn単体の外心\p_Oから\p_aへのベクトルの方向が\P \~C[\P^T \P] \t (=α(\p_a-\p_O))となると思い、
ここでは分点座標と呼ぼうと思ってた気がした。参考→http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/21.html
ベクトルで出すより、ベクトルから座標出すほうが需要があるのか…誰か興味あるなら本気出します(笑)
281+1 :neetubot [] :2009/05/26(火) 09:09:55
\Pが一本分一次従属のとき(\P \~a' = \0)があるのを考えてなかった。
たぶんこのとき\~a'=\C[\P^T \P] \1と書けるけど、いや関係ないか…
あと、\undersetや\oversetを{↓(⊖ \l_i)\L}や{↑[m×m]\E}と書こうと思った。
282+2 :132人目の素数さん [] :2009/05/28(木) 00:31:24
(【訂正】 >>272の上から6行目: 体積の2乗の比→体積の比、上から8行目:
各i対面の超表面積で割った\~x(つまり、\P \~a=\P \Σ^{1/2}[\~C[\P^T \P]] \~x)、
上から9行目:i対面からの距離の比となり、ここでは分面座標)
上をふまえて、n次元単体の位置行列\Pである点\p_aを表すときの座標として、単体座標\~a,(\p_a=\P \~a)、
点\p_aとn次元単体のi対面で作られるi分積の値を用いる分積座標\~v^{n-1},(\p_a=(\P \~v^{n-1})/(v^n))、
点\p_aとn次元単体のi対面からの距離の値を用いる分面座標\~j,(\p_a=(\P \Σ^{1/2}[\~C[\P^T \P]] \~j)/(v^n))、
点\p_aとn次元単体のi点からの距離の値を用いる分点座標\~t,(\p_a-\p_O=r_a (\P \~C[\P^T \P] (\~t)^2/2))
(ただし、分点座標によって定まるある点\p_aは普通は内分点心と外分点心の2点存在する)などと書く。
ちなみに、成分を総和して1になるベクトルを比ベクトル、成分を自乗和して1になるベクトルを正規ベクトル\^{}
とか言ったりし、単体座標は分積座標比ベクトルとか、外心からの正規分点向外線\^x_T上に、とか言ったりします。
あと、n次元単体において分面座標が全て等しい点を内心、1個だけ負で等しい点を傍心と呼び、
内心・傍心を含む分面座標の絶対値が等しい2^n個ある点を広義傍心と呼ぶことにした。
283 :neetubot [↓] :2009/05/28(木) 20:29:44
この分野の先人は、>>280 の上のリンクやある御仁のメールから、一松信さんっぽい雰囲気を感じました!
284 :neetubot [↓] :2009/05/29(金) 14:42:01
2次元単体→n次元単体
重心座標(barycentric coordinates)→分積座標
三線座標(triliner coordinates)→分面座標
三点座標(tripolar coordinates)→分点座標
と呼びたいけど、http://blog.livedoor.jp/melbo2_oko3re/では四面体で四線座標って言ってる、
3次元単体なら四点で六線で四面なのに、…あぁ垂線は四線ですもんね。やっぱ分面座標っしょ
285 :neetubot [] :2009/05/30(土) 06:06:58
2ちゃんねる10周年おめでとうございます!
この「【行列で】m次元ユークリッド幾何学【n単体の5心】」スレ
を始めてからちょうど1年たちまして、皆様ありがとうございました。
とりあえず、このスレで解いたりした問題の項目だけPDFにしておきました。
今後は、neetubot名義で小出しにPDFを書き溜めながら1つにまとめることも考えたいです。
【PDF形式】132人目の素数さん『m次元ユークリッド空間内でのn次元単体の五心などの導出』【0.1】
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pub/neetubot-0.1.pdf
286+3 :132人目の素数さん [] :2009/05/30(土) 06:59:33
それでは一年の集大成として、最近思いついた今までで一番美しい公式の予想を紹介して、終わりたいと思います。
↓
m次元ユークリッド空間内で、原点から各(n+1)点(m≧n≧2)への列ベクトル\p_iを
(i=0…n)列挙したm×(n+1)の位置行列\P=[\p_0…\p_n]でn次元単体A^nが作られる場合、
A^nの重心を\p_G=\P \1/(n+1)としたとき、A^nの頂点のうち(k+1)点(0≦k≦n-1)で
作られるk次元面の{_(n+1) C_(k+1)}通り全てに接する\p_Gを中心とするn次元超楕円体
(n次元単体の重中k次元面接超楕円体)の直交半径行列\R_Qは、次式のような
固有値分解する式で解けると予想する。
(n-k)/((n+1)(k+1)) (\P \P^T-(n+1)\p_G \p_G^T) = (n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P^T) = \R_Q \R_Q^T
↑
定数倍の補正項はn次元正単体のk次元面接超球の半径を参考にし、>>272にあてはめたら
思いつきました。(参考→http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/26.html)
これは成り立たなくても、近似解などに使えると思いました。
それでは1年間、関係者各位、本当にありがとうございました。
287 :132人目の素数さん [] :2009/06/01(月) 14:45:41
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□□
□■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□□
□□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□
□□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□
□□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□□
□□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□
288+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/06/02(火) 07:21:57
>>286で出る楕円体はk次元面接ではなくn次元単体の全てのk次元面単体の重心\p'_jを通るものでした。
それなら、Σ_{j=0}^{_(n+1) C_(k+1) - 1} (\p'_j -\p_G) (\p'_j -\p_G)^T = … = n(k+1)/(n-k) (\P \P^T-(n+1)\p_G \p_G^T)
で証明できそうです。これを、n次元単体の重中k次元重通超楕円体に改名し面接の方の近似となるとか言いたいです。
289+5 :132人目の素数さん [] :2009/06/03(水) 21:38:03
m次元ユークリッド空間内で、\p_Qを中心として 位置ベクトル\p'_i (i=1…n')で表されるn'個の点を通るn次元超楕円体が
一意に定められる場合、その超楕円体の互いに直交するn本の半径ベクトルを列挙した\R_Q=[\r_{1Q}…\r_{nQ}]
について、「(n/n') Σ_{i=1…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = \R_Q \R_Q^T」という公式が成り立つ証明↓
(証明)n'=nのとき、\l_i=\p'_i - \p_Qとすれば、題意のn次元超楕円体が定められる場合は、\l_iが互いに一次独立
である必要がある。これをふまえると、\L=[\l_1…\l_n]を特異値分解により\L=\Θ \Σ \A = \R_Q \Aと分解したとき、
\Aはn×n正規直交行列(\A^T \A = \A \A^T = \E)で書ける。これより、Σ_{i=1…n} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T =
Σ_{i=1…n} \l_i \l_i^T = \L \L^T = \R_Q \A \A^T \R_Q^T = \R_Q \R_Q^Tとなるので、与式が成り立つ。
また、n'で題意を満たす「(n/n') Σ_{i=1…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = \R_Q \R_Q^T」が成り立つと仮定してn'+1のとき、
(n/(n'+1)) Σ_{i=0…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = n/(n' (n'+1)) (n' Σ_{i=0…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T)
= n/(n' (n'+1)) Σ_{j=0…n'} (Σ_{i=0…n', j≠i} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T) = n/(n' (n'+1)) Σ_{j=0…n'} (n'/n \R_Q \R_Q^T)
= \R_Q \R_Q^Tとなるため、与式が成り立つ。よって、この数学的帰納法によりn'≧nで、中心\p_Qから n'個の\p_iのうちから
選んだn点へのベクトルが互いに一次独立という性質が _n' C_n通りの\p_iの全ての選び方で成り立つときに限り、
中心を\p_Qとして n'個の\p_iを通る n次元超楕円体が一意に上記の公式から求められる ということがわかる。■
…中心を指定してn'点を通るn次元超楕円体を導出するとき、中心からn点へのベクトルが一次従属なのを含むとダメなのか?
中心からn'点へのベクトルがn次元部分空間を張っている時は、この公式で中心を指定したn'点への楕円当嵌としたいけど…
\p'_i - \p_Q = \R_Q \θ'_i とすれば、与式から(n/n') Σ_{i=1…n'} \θ'_i \θ'_i^T = \Eというおかしな式になるので、上の証明もどこか違う気が…
290+2 :132人目の素数さん [] :2009/06/04(木) 07:42:13
>>286>>288は少し間違ってました。>>289を前提とすれば、下記のように証明できたので、書き換えます。
↓
m次元ユークリッド空間内で、原点から各(n+1)点(m≧n≧2)への列ベクトル\p_iを
(i=0…n)列挙したm×(n+1)の位置行列\P=[\p_0…\p_n]でn次元単体A^nが作られる場合、
A^nの重心を\p_G=\P \1/(n+1)としたとき、A^nの頂点のうち(k+1)点(0≦k≦n-1)で
作られるk次元単体の重心\p'_jの{_(n+1) C_(k+1)}=n'通り全てを通り \p_Gを中心とする
n次元超楕円体(n次元単体の重中k次元重通超楕円体)の直交半径行列\R_{G_k}は、
「(n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P^T) = \R_{G_k} \R_{G_k}^T」という公式で導出できる。
(証明)>>289の公式から式変形していけば、\R_{G_k} \R_{G_k}^T = (n/n') Σ_{j=1…n'} (\p'_j - \p_G) (\p'_j - \p_G)^T
= (n/n') ( (Σ_{j=1…n'} \p'_j \p'_j^T) - 2 ((_n C_k)(n+1)/(k+1) \p_G) \p_G^T + (_(n+1) C_(k+1)) \p_G \p_G^T )
= (n/n') ( ((_n C_k)-(_(n-1) C_(k-1)))/(k+1)^2 \P \P^T + (_(n-1) C_(k-1))(n+1)^2/(k+1)^2 \p_G \p_G^T - (_(n+1) C_(k+1)) \p_G \p_G^T )
= (n/n') ( (_n C_k)(n-k)/(n (k+1)^2) \P \P^T - (_(n+1) C_(k+1))(n-k)/(n (k+1)) \p_G \p_G^T )
= (n-k)/((n+1)(k+1)) (\P \P^T-(n+1)\p_G \p_G^T) = (n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P^T)と書ける。■
↑
この公式で、m×(n+1)の位置行列\Pで表されるn次元単体の重中k次元重通超楕円体の直交半径行列\R_{G_k}が求まります。
この重中k次元重通超楕円体が通るn次元単体内のk次元面単体の重心でちょうど全てのk次元面と接する(条件のあうi,jにおいて
(\p'_j - \p_G)^T (\p'_j - \p_i) = 0)、つまり、重中k次元重通超楕円体=重中k次元面接超楕円体となりそうなので、今感動してます。
291+1 :neetubot [↓] :2009/06/04(木) 08:08:33
>>290で一番下の感動したところが間違ってました。
正しくは、条件のあうi,jにおいて、\p'_j - \p_G = \R_Q \θ'_j としたとき、 \p'_j - \p_i = \R_Q \θ_i α
(ただし、\θ'_j^T \θ_i = 0)となれば、その超楕円体とn次元単体内のk次元面単体が接するので、
\Xの擬似逆行列を\X^†と書けば、(\p'_j - \p_G)^T (\R_Q \R_Q^T)^† (\p'_j - \p_i) = 0 となることが
重通と面接が一致する条件でした。式の形的には成り立ちそうだけど、今一度のブレイクスルーが必要です…
292+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/06/07(日) 10:45:32
>>291が下記のように解けました。\p'_j - \p_G = \P \~a, \p'_j - \p_i = \P \~bとすれば、\~1^T \~a=0, \~1^T \~b=0, \~a^T \~b=0
であることを使います。ちなみに、成分が全て1のn次元ベクトルを\1、それの(n+1)次元ベクトルを\~1のように分けて書きます。
なお、n×n単位行列\E、(n+1)×(n+1)単位行列\~E、\Xの擬似逆行列を\X^†、\X^†の転置行列\X^‡などが登場します。
(証明) (\p'_j - \p_G)^T (\R_{G_k} \R_{G_k}^T)^† (\p'_j - \p_i)
= (n-k)/((n+1)(k+1)) \~a^T \P^T (\P (\~E - (\~1 \~1^T)/(\~1^T \~1)) \P^T)^† \P \~b
= α \~a^T ([\0, \L] - \p_0 \~1^T)^T (\L (\E - (\1 \1^T)/(\~1^T \~1)) \L)^† [\0, \L] \~b
= α (\~a^T [\0, \E]^T \L^T \L^‡ (\E - (\1 \1^T)/(\~1^T \~1))^{-1} \L^† \L [\0, \E] \~b + 0)
= α (\~a^T [\0, \E]^T (\E + (\1 \1^T)) [\0, \E] \~b + \~a^T (\~1 \~e_0^T + \~e_0 \~1^T - \~1 \~1) \~b)
= α \~a^T \~E \~b = (n-k)/((n+1)(k+1)) \~a^T \~b = 0 ■
>>289>>290>>292より、「m次元ユークリッド空間(m≧n≧2)においてn次元単体A^nがm×(n+1)行列\Pで位置表記される場合、
A^nの重心を中心とし A^nの頂点のうち(k+1)点(0≦k≦n-1)で作られるk次元単体の{_(n+1) C_(k+1)}通り全てに接する
重中k次元面接超楕円体の直交半径行列\R_{G_k}は、(n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\~E - (\~1 \~1^T)/(\~1^T \~1)) \P^T) = \R_{G_k} \R_{G_k}^T
という公式で導出できる。ちなみに、n次元単体の重中k次元面接超楕円体とそれぞれのk次元単体の接点は、対象のk次元単体の重心となる。」
が言える。>>289の一番下の部分がまだ腑に落ちてませんが、>>286であってるし接点まで重心できれいに出ると確信を持ちました。
293 :neetubot [] :2009/06/07(日) 14:08:16
□□□□匿名で公知にしておきたい部分は上までで一応終了です。□□□□
この一年では、m次元ユークリッド空間内のn次元単体の五心(重心・垂心・内心・傍心・外心)を導出する公式を
方向表記・位置表記(・辺乗表記)で解き、広義傍心が2^n個で、角心(フェルマトリチェリ点)は4次方程式に帰着でき、
分面心・分点心や単体による座標も出し、シムソン面・k次元面心・●心○足単体・対面●心単体・○心対称単体は失敗し、
トレミーを拡張し複体外接超球の定理を導き、広義垂心・非斉次行列多項方程式・形縮面積比・形縮収束点について言及し、
最後のほうで、n次元単体とn次元超楕円体の関係について解いてたら、n次元単体の重中k次元面接超楕円体を導出できた、
という感じです。あと、今気になってる問題は↓の2つですが、今ログ読み返したら他にもいろいろありそうでした。
・n次元正単体のk次元面単体の重心{_(n+1) C_(k+1)}通り全てで作られる図形はn次元正複体(正多胞体)と呼べるか
・m次元ユークリッド空間内の2次制約がn元の二次超曲面(全体では(m-1)次元あった)の同相という概念による分類
とりあえず今年はだらだらまとめてどこかに投稿とかしたいです。お手伝いできることやご意見ご感想など何でもこのスレや
>>1の@ウィキhttp://www7.atwiki.jp/neetubot/のフォームやメール(要JavaScript)とかでおっしゃってくださるとありがたいです。
294 :neetubot [↓] :2009/06/07(日) 16:14:22
危険な場所に誤爆しちゃったテヘッ。>>292は、位置行列\Pで表される任意のn次元単体について、
その重心から直交半径行列\R_{G_k}^†=\R_{G_k} (\R_{G_k}^T \R_{G_k})^{-1}で逆に拡縮変換すると、
n次元単位超球にk次元面が全て接するn次元正(?)単体に変換できるということを表していると思う。
つまり、n次元単体の重心から重中k次元面接超楕円体の接点(k次元面重心)への{_(n+1) C_(k+1)}=n'通りの
ベクトルを\R_Q \θ'_j (\θ'_j^T \θ'_j = 1)と書けば(j=1…n')、n次元正単体のk次元面がn次元単位超球に
接する時の中心からその接点へのベクトルが\θ'_j で表せて、(n/n') Σ_{j=1…n'} \θ'_j \θ'_j^T = \Eとなると思う。
>>289の疑問は(n/(n'+1)) Σ_{i=0…n'} \θ'_i \θ'_i^T = \Eから\θ'_0 \θ'_0^T = (1/n) \Eとなるのがおかしいと思ったが、
>>289の上のほうの再帰的に計算するほうで計算するならうまくいきそうです。なんぞこれ…
295 :neetubot [↓] :2009/06/17(水) 21:36:44
遅自己レスでスマソですが、>>289はあっさり成り立つようなもんじゃない気がしてきたので、
重心中心の制約か、はたまた点の分布に等方性まで課さないとダメなのかって感じです今。
あと、n単体の各頂点からの距離の比がある一定値である分点心関係の応用ですが、
各頂点のi点の場所に質量がm_iの質点がそれぞれあるとき、その質量中心の場所を
考えると、その点への各i点からの距離の比がt_i=1-(m_i / (Σ_{i=0…n} m_i))となる感じです今。
296 :neetubot [↓] :2009/06/17(水) 22:28:43
また、n単体の各頂点のi点\p_iの場所にある質量がm_iの質点から受ける万有引力が
等しいもとい つりあう場所\p_Mを考えたい。万有引力定数Gとして、\p_Mにある質量Mの
質点が\p_iの質点から受ける万有引力ベクトルは G M m_i (\p_M - \p_i) / ((\p_M - \p_i)^T (\p_M - \p_i))^(3/2)
などと書ける。(←今ここまで)そこで、上のレスの方を体重中心、こっちを体重衡心とか呼ぼうかとか…
あと、三角形ABCの場合には、等力点という仰々しい名前のついた点(各点A・B・Cの対辺をa・b・cと
すれば、各点A・B・Cからの距離の比が 1/a : 1/b : 1/c となる内分点(?))という点があるらしいですが、
これをn次元単体に普通に拡張すれば、各i対面の(n-1)次元超体積をv_i^(n-1)としたときの
各i点からの距離の比が1/v_0^(n-1) : 1/v_1^(n-1) : … : 1/v_n^(n-1)となる内分点心にあたると考えてます。
ここら辺は、http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/21.htmlにテキトウに書いてある 分点心の位置表記
をちゃんともう一回解いて定式化しとかなきゃ怪しいので、めんどくさいって感じです。あと、n次元単体の
角心(フェルマ・トリチェリ点)の四次方程式について、\l_j^T (\l_j - \l_i)の値とか加味したり
3次元単体以上とか前提に連立方程式化すれば三次や二次方程式まで落とせる気がしてますが、こちらも…
というように、拡張がいろいろできて、ユークリッド幾何学前提なので式は綺麗になるはずなので、
線型代数が得意な人とか、是非いっしょに超立体解析幾何学(高次元計量幾何学)?やりませんか?
297 :neetubot [↓] :2009/06/23(火) 21:00:52
これからは、行列計算ネタとかWikipediaで英語→日本語の訳とかやって英語覚えながら、
arXivに英語論文みたいなの投稿すること考えてて、私的には下記のような対訳を考えてます。
これらのcategory : 多変量解析幾何学 ⇔ Euclidian Metric Geometry
U^m : m次元ユークリッド空間 ⇔ m-Euclidian Space
A^n (\p_G) : n次元単体(重心位置) ⇔ n-Simplex (Centroid Position)
~S^n (~S'^n) : n次元超球体(超楕円体) ⇔ n-Hyperball (Hyperellipsoid)
S^(n-1) (S'^(n-1)) : (n-1)次元超球面(超楕円面) ⇔ (n-1)-Hypersphere (Hyperellipse)
Q_~^(n-1) : (m-1)次元(n-1)元二次超曲面 ⇔ Quadric Hypersurface
ところで、「専門家に論文を見て貰う方法」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3247881.htmlを見て、
これらは大学院か精神病院でやった方が良かったのかと思いましたが、内容的には単体の五心などを
導出する公式を見かけないので作ったよ的な簡単な行列計算の話ですし、俺のような数学科でもない崩れが
金かけずにネタをみんなで共有するためには、2ちゃんのネタとして公知にするのが一番面白いと思ったんだけど…
あとは怪しいか難しいネタしか残ってないので、時間かかるしホントに日記っぽくなりそうなので、ホントに誰か発言していただけるとありがたいです
298+1 :132人目の素数さん [] :2009/06/23(火) 21:19:15
あたまがおかしいと思います
299 :neetubot [↓] :2009/06/23(火) 21:51:47
>>298 自演乙
300 :neetubot [] :2009/07/04(土) 09:35:03
自分で300ゲトTT。最近は英語見すぎて嫌になってきました。ところで、この分野って Geometric Algebra なのかと感じてきました。
あと、ここで単体への位置ベクトルと言ってたものは、アフィン独立なベクトルっていう便利な言葉を使えばいいようだった。
Geometric Calculus International
http://sinai.mech.fukui-u.ac.jp/gcj/gc_int.html
Geometric Algebra Primer [PDF] Jaap Suter - University of Twente, The Netherlands
http://www.lomont.org/Math/GeometricAlgebra/Geometric%20Algebra%20Primer%20-%20Suter%20-%202003.pdf
\Lを特異値分解すると\S \Σ \A^Tとなるとき \Lのムーアペンローズ型擬似逆行列\L^†の転置行列は \L^‡=\S \Σ^{-1} \A^Tと書けると思うので、
↑でベクトル\aのInversion of a vector \a^{-1}と書かれているものは、\a^‡=\a/(\a^T \a)と書いたほうが個人的には純粋な拡張で表せると思った。
例えば、任意のn次元単体の垂線\h_iの逆ベクトル(n+1)本全ての総和は\sum_{i=0…n} \h_i^‡ = \0のように零ベクトルになる(逆垂線総和定理(仮))とか使えるし。
Geometric Algebraについて語ろう
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1142437103/
301+2 :neetubot [↓] :2009/07/04(土) 13:59:12
n次元単体における逆垂線総和定理(仮)から今思いついたのは、ある点\p_xを始点と固定すれば
元のn次元単体の(n+1)本の逆垂線ベクトルの(n+1)終点が作るn次元単体(逆垂線単体と呼ぶ)ができて、
このとき、ある点\p_xは逆垂線総和定理より逆垂線単体の重心となると言えるということです。
これは、五心の中で唯一つ超球と無縁と思われた垂心に、逆垂線単体の重均超球の半径の逆数を半径とする
超球を定義できるかもという光明が見えます。しかし、そのときの中心を広義垂心としていいのか悪いのかだし、むしろ
逆垂線単体自体が何かと相似とか対応してくれるとありがたい。ちなみに、↓をふまえて何か不等式公式が作れそうな気も…
不等式への招待 第3章
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1179000000/863
863 名前:132人目の素数さん[] 投稿日:2009/04/16(木) 01:49:31
問題投下
3辺がa,b,cの三角形の面積と3辺が1/a,1/b,1/cの三角形の面積の積が3/16を超えないことを示せ
ヘロンでどぞー
302 :neetubot [↓] :2009/07/04(土) 14:18:27
逆垂線単体と垂足単体が相似…ではないか…全然違う。チッ
まてよ、i対面からそれぞれi垂線の長さの逆数の比になる分面心が>>301の\p_xで、
その分面心から各i対面に下ろした(n+1)垂足が作る単体が 逆垂線単体と相似じゃないか?
おいおいホントかよ!?仮にこれを擬似逆垂線単体、\p_xの方は擬似逆垂線重心とでも名付けておこう!
303+1 :neetubot [↓] :2009/07/05(日) 06:04:59
位置行列\Pで表されるn次元単体において、各i対面からの距離の比がそれぞれ j_i (i=0…n)
となる分面心は\p_J=\P [j_0/√(\h_0^T \h_0), …, j_n/√(\h_n^T \h_n)]^T / (\1^T [j_0/√(\h_0^T \h_0), …, j_n/√(\h_n^T \h_n)]^T)
(\h_iはそのn次元単体のi垂線ベクトル)のように表せる。 これをふまえて、j_i についてそれぞれ比が1/√(\h_i^T \h_i)になる
擬似逆垂線重心は\p_x=\P [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T / (\1^T [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T)と解ける。
この\p_xの解は、垂心が存在するときの垂心の解 \p_H=\P [1/ν_0, …, 1/ν_n]^T / (\1^T [1/ν_0, …, 1/ν_n]^T)
(ただし、すべての i ≠ j ≠ k ≠i に対して ν_i = (\p_i - \p_j)^T (\p_i - \p_k)となるときに限る)に酷似(ν_i ~ \h_i^T \h_i)しており、
このとき擬似逆垂線単体の対応するi頂点\p_{x_i}は \p_xのi垂足として \p_{x_i} = \p_x - \h_i α_i
(ただし、\p_{x_i} = \P […, [i] 0, …]、つまり、α_i = (定数倍)/(\h_i^T \h_i))のように求まる。
この点\p_xは、広義の垂心の一種として このスレのどこかで触れてた 垂足単体の内心であるような気がしてきた。それはいいとしても、
この点\p_xは、この点から対象のn次元単体の対面に垂足を下ろして作った擬似逆垂線単体の 重心となるという美しい性質を持っており、
以後、この点は 「逆垂心 \p_{/H}」、その垂足単体は 「逆垂足単体 \P_{/H}」 と呼んで位置表記などする。次回、逆垂超球
304+2 :neetubot [↓] :2009/07/05(日) 08:26:46
まとめると、n次元単体の逆垂心への位置ベクトルは \p_{/H} = (\P [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T) / (\1^T [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T) と書けて、
逆垂心からi対面に下ろした垂足(i逆垂足)への位置ベクトルを \p_{i/H} = \p_{/H} - \h_i α_i = \p_{/H} - r_{/H}^2 \h_i/(\h_i^T \h_i)
(ただし、このとき r_{/H} = √( 1 / (\sum_{i=0…n} 1/(\h_i^T \h_i)) であり、これを「逆垂半径」と呼ぶ) と書き表せば、
逆垂足単体は \P_{/H} = \p_{/H} \1^T - r_{/H}^2 [\h_0^‡, …, \h_n^‡] という位置行列で表せる。
以上をふまえて、 n次元単体において、逆垂心 \p_{/H} を中心とし、そのn次元単体と同じ空間にある 半径 r_{/H} のn元超球を
仮にその「n次元単体の逆垂超球 S_{\p_{/H}}^n [r_{/H}] ≡ S_{/H}」と呼ぶ。 これは、垂心関係の超球の定義としては最も自然なものであると考えられる。
今後は、>>301 の下側の不等式を応用して、逆垂半径ひいては逆垂超球を使った関係式などを導出したい。 それにしても美しい式だった(自賛)
305+2 :neetubot [] :2009/07/05(日) 16:27:00
たぶん、n次元単体の逆垂心は、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの自乗距離の調和平均が単体内部において最大となる点のような気がする。
そして、n次元単体の内心が、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの距離の調和平均が単体内部において最大となる点のような気がする。
ちなみに、n次元単体の角心(拡張フェルマ・トリチェリ点)は、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの距離の算術平均(相加平均・総和)が(単体内部において)最小となる点だったと思う。
n次元単体の重心は、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの自乗距離の算術平均が(単体内部において)最小となる点であり(この証明は微分すれば一発)、
このときの自乗距離の算術平均の平方根をここでは重均半径と呼んでいる。統計学的にはこの重均半径と実際のn次元単体の頂点からの距離のずれの値を出せるので
それをここでは重均偏差と呼んでいる。重心から重均半径で作られる重均超球は、n次元単体の各頂点との自乗距離の算術平均に関する超球当て嵌めの際に最適であると感じるが、
一方で逆垂超球は、n次元単体の各対面(facet)との自乗距離の調和平均に関する超球当て嵌めの際に最適であると感じる。重均偏差に対して逆垂偏差も定義できると思う。
まとめると、n次元単体での 重均超球および逆垂超球の役割は、それぞれ自乗距離に関する外接超球および内接超球のようなもののn次元単体への当て嵌めであると考えられる。
306+1 :neetubot [↓] :2009/07/05(日) 18:20:45
(訂正: >>305 1行目:n次元単体の(n+1)通りある対面からの自乗距離の調和平均、
2行目:n次元単体の(n+1)通りある対面からの距離の調和平均、とします。とりあえず、頂点からでは違うようです。)
単体の対面からの距離の(絶対値or自乗の)逆数の総和の逆数(以下、単に(絶対or自乗)調和、もしくはsum of harmonicsとかと呼ぶ)(ちなみに、harmonic sum=1+1/2+1/3+…っぽい)
の振る舞いを考えると、とりあえずどこでも非負で、どこかの対面平面上で一つでも0があれば0、距離が全部無限になるなら無限大となる、みたいな性質のようです。
交互に無限に繰り返す系の 算術調和平均や調和算術平均(違うのか)とかは、n次元単体で言えば重足逆垂足単体収束点や逆垂足重足単体収束点となるのか?そもそも逆垂足単体収束点は逆垂心ではない気が…
たぶんn次元単体の六心目までは幾何平均(相乗平均)と相性は悪そうですが、(k+1)次元面単体への垂足がその内心となる感じのk次元面心で使えないかな、ダメだろうな。
307 :neetubot [↓] :2009/07/07(火) 01:16:39
垂足三角形とその周辺の話題
http://komurokunio-id.hp.infoseek.co.jp/index3.html
四面体との類似と相違
http://homepage2.nifty.com/PAF00305/math/triangle/node7.html
308+1 :neetubot [↓] :2009/07/07(火) 06:05:07
X(6) = SYMMEDIAN POINT (LEMOINE POINT, GREBE POINT)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html
および http://mathworld.wolfram.com/SymmedianPoint.html より、
逆垂心 ⇔ lemoine-symmedian center、逆垂足単体 ⇔ symmedian pedal simplex などと対訳する。
>>303-304あたりをちゃんと書くと、アフィン独立なm×(n+1)位置行列\Pで表されるm次元ユークリッド空間内のn次元単体A^nについて、
正方行列\Xの対角成分のみの対角行列を\Σ[\X]、\Xの[j,i]小行列の全ての余因子を総和した値を[j,i]成分に持つ行列を余因子総和行列\~C[\X]とすれば、
原点からA^nの逆垂心への位置ベクトルは\p_{/H} = (\P \Σ[\~C[\P^T \P]] \1) / (\1^T \Σ[\~C[\P^T \P]] \1)とも書ける、という感じです。これは、
原点からA^nの内心への位置ベクトル\p_I = (\P \Σ^(1/2)[\~C[\P^T \P]] \1) / (\1^T \Σ^(1/2)[\~C[\P^T \P]] \1)と式形が似ています。
また、内接半径はr_I = (\1^T \C[\P^T \P] \1)^(1/2) / (\1^T \Σ^(1/2)[\~C[\P^T \P]] \1)、(ただし、\C[\X]は\Xの余因子行列)
逆垂半径はr_{/H} = ((\1^T \C[\P^T \P] \1) / (\1^T \Σ[\~C[\P^T \P]] \1))^(1/2)と書けて、辺乗行列\Bで表してもこれと同様の式となります。
ちなみに、重心 ⇔ centroid、分積座標 ⇔ barycentric coordinates、角心 ⇔ fermat-torricelli center などとも対訳します。なお、
2次元単体(三角形)の重中0次元面接(外接)超楕円はhttp://mathworld.wolfram.com/SteinerCircumellipse.html、
2次元単体(三角形)の重中1次元面接(内接)超楕円はhttp://mathworld.wolfram.com/SteinerInellipse.html、
として既にあり、性質も拙稿のn次元単体の重中k次元面接超楕円のn=2でk=0,1のときと同じようなので安心しました。
309+1 :neetubot [↓] :2009/07/08(水) 19:49:56
>>305-306 についてですが、n次元単体の逆垂心は単純に、n次元単体の(n+1)通りある対面からの距離の自乗算術平均が最小となる点でした。
証明は、n次元単体の各i垂線を\h_iとすれば、各i対面への距離が j_i である任意の分面心に対して、
その分面心でn次元単体を分けた各i分積の総和が単体の超体積となることより \sum_{i=0…n} (j_i / √(\h_i^T \h_i)) = 1 なので、
n次元単体の(n+1)通りある対面からの距離の自乗算術平均は r'_{/H}^2 = (\sum_{i=0…n} j_i^2) / (n+1) と書け、
ラグランジュの未定乗数法より f_{/H} = r'_{/H}^2 + λ (- 1 + \sum_{i=0…n} (j_i / √(\h_i^T \h_i)) ) を最小化する各 j_i の組(分面座標)を求める問題に帰着できる。
これより、f_{/H}が各変数j_iについて下に凸な放物線であるので、i成分にj_iを持つベクトル \j で f_{/H} を微分した値が\0になる \j のとき、この制約下でr'_{/H}^2も最小値となる。
計算すると、f_{/H} が最小となるとき \j = [1/√(\h_0^T \h_0), …, 1/√(\h_n^T \h_n)]^T / (\sum_{i=0…n} (1 / (\h_i^T \h_i))) であり、そのときのr'_{/H}^2の最小値
r_{/H}^2 = min[r'_{/H}^2] = (1/(n+1)) / (\sum_{i=0…n} (1 / (\h_i^T \h_i))) となる。これより、 >>304 のr_{/H}について√(n+1)で割ったものを新しく逆垂半径と訂正する。
つまり、以上より、逆垂超球は、n次元単体において各i対面からの距離を用いた最小自乗法による超球当て嵌めであると言える。
そのときの実際の距離とのずれである逆垂偏差は ε_{/H} = √(\sum_{i=0…n} (j_i - r_{/H})^2 ) / (n+1) = r_{/H} √(2 (1 - (r_{/H}/r_I)))
と書けそうである。このときの r_I はn次元単体の内接超球の半径であり、任意のn次元単体について常に r_I ≧ r_{/H} であることが計算するとわかる。
310+2 :neetubot [↓] :2009/07/08(水) 22:52:14
(訂正:>>309 下から2行目:ε_{/H} = √( (\sum_{i=0…n} (j_i - r_{/H})^2) / (n+1) ) = …)
>>309から(r_{/H}+ε_{/H} ≧) r_I ≧ r_{/H} ではあるようだが、直感的に r_G ≧ r_O (≧ r_G-ε_G) とも言えそうである。
ちなみに対訳は、S_G (r_G・ε_G) : 重均超球(半径・偏差) ⇔ Centroid Least-Square Hypersphere(Circum-radius・Circum-deviation)
S_{/H} (r_{/H}・ε_{/H}) : 逆垂超球(半径・偏差) ⇔ Symmedian Least-Square Hypersphere(In-radius・In-deviation) のようにしたい。
以上より、n次元単体における重均半径r_G・逆垂半径r_{/H}・内接半径r_I・広義傍接半径r_{J_j}・k次元面接半径r_{K_k}・外接半径r_Oには下式の関係があると思われる。
(r_{J_{1…(2^n -1)}} >> ) r_G ≧ r_O = r_{K_0} ( > r_{K_1} > … > r_{K_{n-2}} > ) r_{K_{n-1}} = r_{J_0} = r_I ≧ r_{/H}
あとは、重中k次元面接超楕円のn本ある半径の長さr_{i G_k}の自乗算術平均 √((r_{1 G_k}^2+…+r_{n G_k}^2) / (n+1))でもr_{K_k}に関係してくれたら嬉しいのだが。
311+1 :132人目の素数さん [↑] :2009/07/09(木) 07:34:54
sage
312+1 :「猫」∈社会の屑 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/07/09(木) 10:14:38
コレは数学の話なんだし、無理してsageんでもエエがな!
313 :neetubot [] :2009/07/09(木) 12:17:21
(訂正:>>310 下から1行目:自乗算術平均 √((r_{1 G_k}^2+…+r_{n G_k}^2) / n)でもr_{K_k}に)
>>312 猫先生、このスレでははじめまして!見つけてもらってしまった感じで、ありがとうございます!
僕は、2ちゃんねるの読み書きに2ch専用ブラウザJaneDoeView( http://www.geocities.jp/jview2000/ )
というのを使ってるんですが、これに限らず専ブラってのは なぜかデフォルトでメール欄にsageが入ってるようで、
あまり意識しないで書くときが多いので基本sage進行になってました…これから、意識してageageでいきますね。
そういえば、この前2ヶ月以上くらい書き込むの忘れてたら、スレ番号最後の方でスレ落ちかかっててビックリしました。
このスレでやってる分野は、数学の話といっても、まだ先人も見つけられず、あまり流行ってないのかなぁーとか思って、
あまり話しかけてももらえずに、まったりやっておりました。でも今、猫先生にカキコしてもらえてとても嬉しいです!
ちなみに、>>311 は自分でageテストやってました。ちょうど >>310 で区切りがついてネタも尽きてしまった感じだったので…ネーター環
314+1 :neetubot [] :2009/07/10(金) 06:35:15
(訂正:>>310 上から2行目:直感的に (r_G+ε_G ≧) r_O ≧ r_G とも言えそうである、
下から2行目:r_O = r_{K_0} ≧ r_G ( > r_{K_1} > … > r_{K_{n-2}} > ) r_{K_{n-1}} = r_I ≧ r_{/H} )
訂正の件ですが、n次元単体において 各i点からの距離の自乗平均の最小値となるのが重均半径であるので、
min[ (\sum_{i=0…n} (\p_i - \p_X)^T (\p_i - \p_X)) / (n+1) ] = (\sum_{i=0…n} (\p_i -\p_G)^T (\p_i - \p_G)) / (n+1) = r_G^2
という式が成り立ち、これを外接半径にあてはめれば、(\sum_{i=0…n} (\p_i - \p_O)^T (\p_i - \p_O)) / (n+1) = r_O^2 ≧r_G^2
なので、任意のn次元単体で r_O ≧ r_G でした。これより、n次元単体の内部点からk次元面への距離の自乗平均の最小値を
r_{G_k}および偏差をε_{G_k}とでもすれば、(r_{K_{k-1}} > ) r_{G_k}+ε_{G_k} ≧ r_{K_k} ≧ r_{G_k} ( > r_{K_{k+1}}) と思いました。
このように、距離の自乗平均最小値はとてもいい性質を持つので、r_{G_k}をk次元面均半径と呼ぶことにし、
そのときの中心を k次元面均心(それへの位置ベクトル\p_{G_k})とでもすれば、重心は0次元面均心で外均心?で
逆垂心は(n-1)次元面均心で内均心か?これが、k=1…(n-2)のときに唯一つに定まるかとか対訳も含めて考え直します。
ちなみに、r_I ≧ r_{/H} が任意のn次元単体の辺乗行列 \Bで成り立つことも考えれば、対角成分が0の任意の対称行列 \B について
((n+1) / (\1^T \Σ^(1/2)[ \C[- \B] ] \1))^2 ≧ (n+1) / (\1^T \Σ[ \C[- \B] ] \1)) という、自乗算術平均が絶対算術平均より大きい
というよく見る式(上の実際の式ではその2乗の逆数を比べている)が成り立つ。驚くのは、r_O ≧ r_G にこの方法を用いたときで、
対角成分が0の任意の対称行列 \B について det[- \B] / (\1^T \C[- \B] \1) ≧ (\1^T \B \1) / ((n+1)^2) という公式が成り立つ
と思う。n次元単体の外接半径が r_O = √(det[- \B] / (\1^T \C[- \B] \1)) と表せるかは、まだちゃんと証明してないんだけど…
315 :neetubot [] :2009/07/10(金) 23:03:36
(訂正:>>314 対角成分が0で「行列式が0とならない」任意の対称行列 \B について det[- \B] / (\1^T \C[- \B] \1) ≧ (\1^T \B \1) / ((n+1)^2) } )
r_Oの\Bを使った表記(ここでは辺乗表記と呼んでいる)は、n次元単体の外心からi対面への垂足がそのi対面の外心になることを使った気がしましたよ>俺
316 :neetubot [] :2009/07/11(土) 07:44:44
今日は特にネタはない
317+1 :「猫」∈社会の屑 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/07/11(土) 08:42:21
数学者というもの、ネタが無いと辛いですね、判ります。
まあそやけど「そういう日」もある訳で、そんな時は
散歩でもしはったらどうでっしゃろ?
ワシも今日はちょっと疲れてしもうてですナ
まあちょっと電車に乗って遊びに行こうかと
思ってますねん
ちょっと遠くまで行くと魚が美味いっちゅう話も聞きましたしね
そんで「5心」ですが、猫は今ある人と一緒に重心で遊んでますよ
318 :neetubot [] :2009/07/11(土) 09:30:16
>>317 ご心配ありがとうございます(TT) この頃、新しく何かひらめかないと、手詰まりでネタ無しで辛いです。
散歩いいですよね。私も考え事しながら、半径2mくらいでひたすらグルグル歩き回ってるときがあります(謎)
猫先生に判るって言ってもらえて嬉しいです!魚いいですね、海とかこの時期は人魚さん達がいらっしゃ…
川とか当県の近くに来たときは是非お声をお掛けくださいね。私は超インドア派なのであまり詳しくないですが…
「5心」やってるんですか!?重心は、n次元単体内の各k次元面に接する超楕円面のとき、すごくお世話になったので、
5心の中では一番好きです。猫先生が重心で遊ぶなんておっしゃられると、かなりものすごい事やってそうで恐ろしいですっ
もしよろしければ、お話とか聞かせて頂けると、とてもありがたいです。むしろ、是非よろしくお願いしますm(_ _)m
319 :neetubot [] :2009/07/13(月) 05:56:16
対訳の方向性が定まりました。面均をFacetargetedに対訳しようと目論見ました。
外心・外接超球(面)(Circumcenter・Circumscribed Hypersphere)
k次元面心・面接超球(面)(Constrained k-Facescribed Midcenter・Hypersphere)
内心・内接超球(面)(Incenter・Inscribed Hypersphere)
重心・重均超球(面)(Centroid・Centroid 0-Facetargeted Hypersphere)
k次元面均心・面均超球(面)(Least-Square k-Facetargeted Midcenter・Hypersphere)
逆垂心・逆垂超球(面)(Lemoine-Symmedian Center・Symmedian (n-1)-Facetargeted Hypersphere)
それぞれの半径や偏差の対訳は、Circum-・Mid-・In-とradius・deviationを組み合わせた名前で、上の適な場所を
置き換える感じで。あと、珍しいところでは、重中k次元面接超楕円(面)(Centroid k-Facescribed Hyperellipse)とか。
320+2 :neetubot [] :2009/07/13(月) 12:24:05
m次元ユークリッド空間内の n次元単体の k次元面均心について、ひらめきました。
まず、k次元面均心\p_{Φ_k}=\P \a_{Φ_k} (ただし、\1^T \a_{Φ_k} = 1)からあるk次元面Φへの垂足\p_Φについて、
k次元面の内部点\p_Φの単体座標値の(n-k)個が0となることから、ΦからΦに含まれる点以外のi点への垂線\h_{i←Φ}を使って、
\p_{Φ_k} - \p_Φ = \sum_{i \not\in Φ} \h_{i←Φ} a_{i Φ_k} が成り立つ。ここで、n次元単体のk次元面全ての集合を\Φとする。
これまでの、自乗算術平均が最小になる条件をふまえると、n次元単体におけるk次元面Φからk次元面均心\p_{Φ_k}への垂線のΦ全ての和が
ゼロベクトル\0になると考えられる。つまり、\sum_{Φ \in \Φ} (\p_{Φ_k} - \p_Φ) = \sum_{Φ \in \Φ} \sum_{i \not\in Φ} \h_{i←Φ} a_{i Φ_k}
= \sum_{i=0…n} \sum_{Φ \in \Φ, Φ \not\ni i} \h_{i←Φ} a_{i Φ_k} = \0 となると予想できる。
上式は、\h'_{iΦ} = \sum_{Φ \in \Φ, Φ \not\ni i} \h_{i←Φ} と書けば、[\h'_{0Φ},…,\h'_{nΦ] \a_{Φ_k} = H'_Φ \a_{Φ_k} = \0 となる
ということを表している。以上より、コンピュータで地道に計算して出るn階(n+1)×(n+1)行列 H'_Φ に垂直で \1^T \a_{Φ_k} = 1
となる座標ベクトル\a_{Φ_k} を一意に求めることができて、k次元面均心\p_{Φ_k}=\P \a_{Φ_k} を導出できるという方向性が見える。
今後は、i点以外のk次元面Φからi点への垂線を全てのΦについて平均したベクトルを列挙した行列 H'_Φ をきれいな式にして、完全に解きたい。
321+2 :neetubot [] :2009/07/14(火) 18:06:07
(訂正:>>320 下から4行目:[ \h'_{0Φ}, …, \h'_{nΦ} ] \a_{Φ_k} = H'_Φ \a_{Φ_k} = \0、下から2行目:n階m×(n+1)行列 H'_Φ)
>>320 を次のように書き換えます。まず、n次元単体における全てのk次元面の集合を{φ}とし、{φ}の元である あるk次元面をφで表す。
すると、k次元面均心\p_{Φ_k}=\P \~a_{Φ_k} (ただし、\1^T \~a_{Φ_k} = 1)からφへの垂線\r_φと垂足\p_φについて、
φに含まれないi点からφへの垂線 \h_{i→φ} = ([\p_i, \P_φ] \~C[[\p_i, \P_φ]^T [\p_i, \P_φ]] \~e_0) / (\~e_0^T \~C[[\p_i, \P_φ]^T [\p_i, \P_φ]] \~e_0)
(ただし、\P_φはk次元単体φの部分だけのm×(k+1)位置行列)を使って、\r_φ = \p_φ - \p_{Φ_k} = \sum_{i=0…n, i \not\in φ} \h_{i→φ} ~a_{i Φ_k} が成り立つ。
【たぶん、\r_φの自乗算術平均が最小値 r_{Φ_k} = min[√(\sum_{φ \in {φ}} \r_φ^T \r_φ) / (_(n+1) C_(k+1)))] となるとき、\sum_{φ \in {φ}} \r_φ = \0 となるので、】
\sum_{φ \in {φ}} \r_φ = \sum_{φ \in {φ}} \sum_{i=0…n, i \not\in φ} \h_{i→φ} ~a_{i Φ_k} = \sum_{i=0…n} \sum_{φ \in {φ}, φ \not\ni i} \h_{i→φ} ~a_{i Φ_k} = \0
、ここで、i点からi点を含まない全てのφへの垂線の平均ベクトル(以下、k次元i垂均)\h'_{iΦ_k} = (\sum_{φ \in {φ}, φ \not\ni i} \h_{i→φ}) / (_n C_(k+1)) を考え、
\~e_j^T \~Φ_k \~e_i = \~e_j^T [[j ≠ i] \sum_{φ \in {φ}, φ \ni j, φ \not\ni i} (-1)^(i+j) (\1^T \C[\underset{(\p_j ← \p_i)}{\P_φ}^T \P_φ] \1) / (\1^T \C[\P_φ^T \P_φ] \1)
/ (_n C _(k+1) or [j=i] 1] \~e_i となる(n+1)×(n+1)の面因子平均行列 \~Φ_k を導入すれば、k次元垂均行列 H'_{Φ_k}= [\h'_{0Φ_k},…,\h'_{nΦ_k}] = - \P \~Φ_k と書けることから、
\sum_{φ \in {φ}} \r_φ = H'_{Φ_k} \~a_{Φ_k} = - \P \~Φ_k \~a_{Φ_k} = \0 が成り立つ。
以上をふまえれば、m次元ユークリッド空間内のn次元単体において、(_(n+1) C_(k+1))通りあるk次元面からの距離の全ての自乗算術平均が最小となる点、すなわち
k次元面均心 \p_{Φ_k} = \P \~a_{Φ_k} を導出するには、面因子平均行列 \~Φ_k を計算し、\~Φ_k \~a_{Φ_k} = \0(ただし、\1^T \~a_{Φ_k} = 1)となる\~a_{Φ_k}を求めればよいことがわかる。
322+1 :neetubot [] :2009/07/15(水) 03:29:12
m次元ユークリッド空間内の n次元単体の k次元面心について、ひらめきました。
>>321 と同様に、n次元単体内のあるk次元面をφ、φに含まれないj点とφで作られる(k+1)次元面をjφで表す。
すると、k次元面接超球が存在するためには、k次元面心\p_{K_k}=\P \~a_{K_k} (ただし、\1^T \~a_{K_k} = 1)から
jφに下ろした垂線\r_{jφ}の垂足がjφの内心となり、\p_{K_k}からφに下ろした垂線\r_φの垂足が jφの内足となることが
必要十分条件であるので、\r_{jφ}-\r_φ = (\P_{jφ} \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \~e_0) / (\~e_0^T \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \~e_0) ε_{jφ}
(ただし、ε_{j/jφ} = √(\~e_0^T \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \~e_0) / (\1^T \Σ^(1/2)[ \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] ] \1))が成り立つ。
この式の、\p_jの単体座標について比べると、\p_{K_k}からφへの垂足の\p_{K_k}+\r_φでは0、\p_{K_k}からjφへの垂足の\p_{K_k}+\r_{jφ}では
\sum_{i \not\in φ} (-1)^(i+j) (\1^T \C[\underset{(\p_j ← \p_i)}{\P_{jφ}}^T \P_φ] \1) / (\1^T \C[\P_φ^T \P_φ] \1) ~a_{i K_k} = \~e_j^T \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k}
(このとき、\Φ_(k+1)を面因子行列と呼ぶ)であるため、\r_{jφ}-\r_φの\p_jの単体座標について \~e_j^T \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} = ε_{jφ}
と書ける。これは、【k次元面心の単体座標\~a_{K_k}の部分について全てのφで \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} = \ε_φ】が成り立たなければならない
制約を表している。この式の平均は、前述の(k+1)次元面因子平均行列 \~Φ_(k+1) を用いて、\sum_{jφ \in {jφ}} \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} =
\~Φ_(k+1) \~a_{K_k} = \~ε_φ(ただし、~ε_{jφ} = (\sum_{φ \in {φ}, φ \not\ni j} ε_{jφ})/(_n C_(k+1))である?)と書ける気がするので、
前述の(k+1)次元面均心と 存在するならこのk次元面心は違う点となると思う。(分母の係数が前述の面因子平均行列とあってないかも)
さて、心はいい行列が見つかって良かったが、それぞれの半径はどうなることやら…
323 :neetubot [] :2009/07/15(水) 07:23:56
(訂正:>>320 上から8行目:\sum_{i \not\in φ} (-1)^(i+j) (\1^T \C[\P_{iφ}^T \P_{jφ}] \1) / (\1^T \C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \1) ~a_{i K_k}
= \~e_j^T \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} (以下、>>281の記法もふまえたい。))お、おかしいぞ、半径がきれいな式になる気が全くしない…
324+1 :neetubot [] :2009/07/15(水) 17:14:33
m次元ユークリッド幾何学スレまとめ@ウィキ 「使用する用語」
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/51.html
に、そのウィキやこのスレで使っている単体五心関係の用語と式などを少しまとめてみました。
325+1 :neetubot [] :2009/07/16(木) 23:59:00
内積・外積の逆演算を考えよう。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1045048250/
の問題は解けそうなので、紹介します。
1:ユークリッド空間内で、ベクトル集合 \L = [\l_1,…,\l_n] と位置ベクトル \a の内積値が一定値 \b となるとき、点 \a の存在する空間を求めよ(内積の逆演算?)。
\L^T \a = \b より、\L = \S \Σ \A^Tと特異値分解されるときの\Lのムーアペンローズ型擬似逆行列\L^†の転置行列 \L^‡ = \S \Σ^(-1) \A^Tを用いて、
拡大係数行列[\L^T, \b]の次元が係数行列\L^Tの次元と等しい場合(以下、u[\L^T, \b]=u[\L^T]と書く) \a = \L^‡ \b + (E - \L^‡ \L^T) \α
(ただし、\αは任意の実ベクトル)と書ける。これは、u[\L^T, \b] = u[\L^T]なら、位置ベクトル\aで表される点は、原点から \L^‡ \b の場所を通り
(E - \L^‡ \L^T)で張られる\Lの直交補空間上に存在すると言える。また、u[\L^T, \b]≧u[\L^T]となる場合は、この式を満たす\aは存在しないことは自明である。
(ちなみに、このスレでは \L \a = \b すなわち\bを表す【基底】\Lの座標 \a を求める問題があり、u[\L, \b] = u[\L]のとき\a = \L^† \b = (\L^T \L)^(-1) \L^T \b とか使った)
とここまで書いて、この問題についてはこのスレで前に言及したような記憶があり、\l_1のみでの略解も上記スレの100にもあったのに気付いた。
外積の逆演算はn次元拡張しても直交補空間ですで終わる話だと思たので、もう一つスレ紹介↓
楕円→放物線→双曲線の順は正しいのか
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1247644637/
のスレの6さんが言うとおり、傾いた円の透視投影において その円の半径を無限小から無限大へ増やしていけば、
透視投影される像の二次曲線が 円 楕円 放物線 双曲線 直線 の順に変化することが、そのシステムにおいては想像できる。
しかし、二次曲線を一般化した f_Q = \p^T \Q \p + 2 \p^T \q_y + \q_{yy} = 0 で表される二次超曲面を平面で切った形を考えると、
その平面の基底における二次係数 \Q の固有値については 楕円・双曲線は2個 放物線は1個であるので、これらは違う形といえる。
私的な考えでは、二次超曲面をn次元平面で切った形の分類において、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%9B%B2%E9%9D%A2
を参考に、放物軸…あ、バイト数が
326 :neetubot [] :2009/07/18(土) 06:06:18
(訂正:>>325 上から約8行目:u[\L^T, \b]>u[\L^T]となる場合は、この式を満たす\aは存在しない)
>>322 のk次元面心は、全てのφにおいて \~Φ_(k+1) ↓{[\not\in φ]}{\~a_{K_k}} = ↓{[\not\in φ]}{\~ε_{φ k}}
となる場合に限り、\p_{K_k}=(\P \C^T[\~Φ_(k+1)] \~1) / (\~1^T \C[\~Φ_(k+1)] \~1) + \P \~C^T[\~Φ_(k+1)] \~ε_k
と位置ベクトルが書けそうです。>>321 のk次元面均心は、\p_Φ_k = (\P \C^T[\~Φ_k] \~1) / (\~1^T \C[\~Φ_k] \~1)
と位置ベクトルが書けそうです。>>324 のページで式の形が画像で見れると思いますので、良かったらどうぞー
327+1 :neetubot [] :2009/07/18(土) 13:06:42
今回、k次元面心・面均心の式の形の方向性が見えた(それぞれの半径の導出は今はあきらめました)ということで、
重心=第1心、(広義)垂心=第2心、内心・広義傍心=第3心、k次元面心=第4心、外心=第5心、角心=第6心とし
(たぶん明示的に使うことはないですが…)、来週は角心(Fermat-Torricelli Center)について思い当たってることを解決したいです。
328+1 :neetubot [] :2009/07/20(月) 11:18:22
アフィン独立なベクトルを列挙した\Pの擬似逆行列の転置行列\P^‡と正射影行列を絡めて考えてたら、
任意の正方行列\Xの行列式|[\X]|・余因子行列\C[\X]・余因子総和行列\~C[\X]に対して、
\Pが線型従属の場合 \P^‡ = \P (\~C[\P^T \P]) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)となりそうなんですが、
\Pが線型独立の場合 \P^‡ = \P ((\C[\P^T \P] \1 \1^T \C[\P^T \P]) / |[\P^T \P]| + \~C[\P^T \P]) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)
= \P \C[\P^T \P] / |[\P^T \P]| = \P (\P^T \P)^(-1) となると思うので、任意の正則対称行列\Xに対して
\X^(-1) = \C[\X] / |[\X]| = ((\C[\X] \1 \1^T \C[\X]) / |[\X]| + \~C[\X]) / (\1^T \C[\X] \1)となり、たぶん
任意の正則行列\Xに対して \C[\X] \1 \1^T \C[\X]^T = \C[\X] (\1^T \C[\X] \1) - \~C[\X] |[\X]| でも成り立って、
\X^T \~C[\X] + \1 \1^T \C[\X]^T = \C[\X] \1 \1^T + \~C[\X]^T \X = \E (\1^T \C[\X] \1) っぽくなりそうです。
果たしてどうなんでしょうか?対称行列×違う対称行列は 普通は対称行列にならないっぽい!ご意見お待ちしておりますー
329 :neetubot [] :2009/07/22(水) 20:18:51
m次元ユークリッド空間内でn次元単体の位置行列を\Pとし、
n次元単体があるn次元部分空間上の点への位置ベクトルを\p_Xとすれば、
>>328より、\P^T \p_X = \~b_X となるとき、 \p_X = \p_y + \P^‡ \~b_X と書ける
(ただし、原点からn次元部分空間\p_y=(\P \C[\P^T \P] \1) / (\1^T \C[\P^T \P] \1))。
しかし、\p_X = \p_y + \P^‡ \~b_X であっても、\P^T \p_X が \~b_X となるとは限らない、と思う。
ということで、\p_X = \p_y + \P^‡ \~b_X となる \~b_X を辺乗座標(Half-squared Edge Coordinates)と呼ぶ。
330 :neetubot [] :2009/07/26(日) 01:08:44
ある点への辺乗座標が\~b_Xと書けるなら、\P^T \P^‡ \~b_Xもまたその点への辺乗座標である。また、位置行列\Pに対し、
(\P^T \P \~C[\P^T \P] \P^T \P) / (\1^T \C[\P^T \P] \1) = \P^T \P - (\1 |[\P^T \P]| \1^T) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)
という式も成り立つ。と思った。
331 :neetubot [] :2009/08/14(金) 17:11:10
φは空集合だと思われるといけなかったので、表記をいろいろ変えました↓
単体導入 > 使用する用語
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/51.html
332 :neetubot [] :2009/08/15(土) 14:52:23
平石司さん『高次元単体の諸心』
http://homepage2.nifty.com/hiraishi-tsukasa/Folder_SimplexesOfHighDimensions/SimplexesOfHighDimensions.htm
のページにn次元単体の五心の性質から、三角形における九点円をn次元単体へ拡張したp次の面重心球面、
および、任意のn次元単体に存在するp次の面重心球面の中心に相当する「究点」という新しい概念など、
非常に素晴らしくまとまっており、私的にも「究点」を方向表記で導出し確認できたので、ここでも紹介します!
平石さんにはとてもお世話になっており、大変ありがたく思っております!
333 :neetubot [] :2009/08/20(木) 01:36:48
@ウィキのほうのトップページ/メニューでライセンスの項目を
-#image(http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.1/jp/88x31.png,http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/)
-This Work by 132人目の素数さん is licensed under a [[Creative Commons 表示-非営利 2.1 日本 License>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/]]
+#image(http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/88x31.png,http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)
+This Work by 132人目の素数さん・他 is licensed under a [[Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/]].
と変えました。英語論文はneetubot名義のCC-by-ncでいきたいのと2chだしncかなってのをふまえてます。
334+1 :neetubot [] :2009/09/05(土) 12:30:42
たけしのコマ大数学科 Part11
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1243708405/568-600
の番組を見て、「m次元ユークリッド空間内のn次元部分空間にある(n+1)個のn次元超球体の全てに接する超球の分類」
について、「m=n=2で一直線上に無く互いに重ならない3個の円の全てに接する円は8通りある」らしいようなこと言ってました。
この問題をこのスレっぽく言えば、「U^m内のn次元単体のi-頂点からの距離がそれぞれ(r±ε_i)となる分点心と
そのときのrの組を求めよ」って感じだと思うのですが、この場合、内分点心と外分点心のうちどちらかしか満たさない
(かどちらも一致する)ような気がしますし、最高で広義傍心系の2倍の2^(n+1)通り求まる気がしますが、うーん…
(たぶん、この解があれば、n次元音源位置推定で時間測定誤差があるとき、音源が存在しうる位置の範囲が求められる)
335+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/09/05(土) 16:19:45
「m=n=2で一直線上に無く互いに重ならない3個の円の全てに接する円は8通りある」
配置による。
8通りあるためにはどの1つの円と他の2つの円との間に
円に接さない直線で境界が引ける程度に各円が離れている必要がある。
336 :neetubot [] :2009/09/06(日) 07:55:04
>>335さんフォローありがとうございます!コマ大スレで議論が行われてるようですが、>>335さんの条件に同意です。
2つの円に内接しもう1つの円に外接する円っぽい場合には8通り無い状況が私も想像でき、>>334ではダメなことがわかりました。
この接する円がなくなる場合には、漸近線が直交する双曲線として接しているという状態なのか、とかにも興味がありますし、また、
この条件をn次元に拡張したような「U^mでn次元単体を作る(n+1)点のうち、(k+1)点を選んで作られる k次元部分単体(m≧n≧2, (n-1)≧k≧0)と
それに含まれない(n-k)点で作られる部分対面との間に 各i-頂点からの距離がそれぞれ(r+ε_i)となる部分境界(n-1)次元超平面があり
r>0となるとき、部分単体の方に含まれるそれぞれのi-頂点を中心とし半径ε_iのn次元超球体の全てに内接し 部分対面の方に含まれる
それぞれのi-頂点を中心とし半径ε_iのn次元超球体の全てに外接するっぽい超球が必ず1つ求まる。」とかを言うためのn次元単体の
k次元部分境界(n-1)次元超平面~U_{ψ≠ψ}[\ε]とそのときのrを求めたいと思いました。このとき、n次元単体の~U_{ψ≠ψ}[\ε]
が2^n通り(∵部分単体と部分対面が逆の場合も同じ物なので)全部存在する場合に限り最高の2^(n+1)通りの接超球が求まるみたいな…
今後とも是非また宜しくお願い致します。
337 :neetubot [] :2009/09/06(日) 11:39:56
(n+1)個の超球の全てに内接する超球と関係するn次元部分単体のとき、および、
(n+1)個の超球の全てに外接する超球と関係する(-1)次元部分単体(便宜上0個の
点から作られる何も無い図形を表す)のとき(k=nのとき、および、k=-1のとき)を失念しておりました。
前者の部分境界超平面はn次元単体があるn次元部分空間の無限遠面全体(r→∞)と考えられるが、
(n+1)個の超球のうち1つが1つを内包してしまうときなどに全てに内接する超球(外接超球?)は存在しなくなる。
(各頂点から部分境界超平面への距離の間を他の超球面が横切ってはいけないなどの条件を加えればよいか…)
後者の部分境界超平面はn次元単体内部において各i-頂点からの距離がそれぞれ(r+ε_i)となる1点となり、
r>0なら全てに外接する超球(内接超球?)が存在する。(r=0のときは部分境界超平面と同じ1点に縮退する)
338 :neetubot [] :2009/09/08(火) 08:30:43
今日はAGEたい気分・・
339 :猫は残飯 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/09/08(火) 08:43:47
そうでっか、AGEな気分でっか。
ワシなんかはEGAな気分やでー
IHESで買って来たヤツ全巻持ってるさかいナ。
アンタも読んでみはりまっか?
340 :neetubot [] :2009/09/08(火) 09:47:10
EGA・・江頭2:50っすか!? というのは冗談として、
Alexander Grothendieck 『Elements de Geometrie Algebrique』
http://people.math.jussieu.fr/~leila/grothendieckcircle/pubtexts.php
のリンク先などでSGAもFGAもフランス語のpdfなら入手できそうですが、読めなそうなので、
【Motifs】グロタンディーク 8【Topos】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1149181307/
でも紹介されている、黒田貞玖作「EGA日本語翻訳計画」
http://grothende.gozaru.jp/の完成を待ちながら、入門から勉強したいと思います><
猫先生はフランスのI.H.E.S(Institut des Hautes Etudes Scientifiques)
http://ja.wikipedia.org/wiki/IH%C3%89S
の研究所に行った事があるっすか!? なんかすごい・・
と一通り調べないと話についていけなかった私です…今度メール返信でがんばりますっ
341 :猫は残飯 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/09/08(火) 09:55:51
この聖書は絶対に翻訳するべきではない。
学ぶ者はフランス語の原典に当たるべき。
そもそも神が著わしたものに人間が手を加える
等は僭越至極なので、翻訳等は即刻止めるべき。
342 :neetubot [] :2009/09/08(火) 11:22:18
黒田貞玖さんの更新が滞っているようなのは、そういう理由なのかもしれません。
私のような門外漢には解説書ぐらいの勢いで原文+対訳っぽい感じで何かあると
手が付けやすいのですが…確かに原典や原著をご存知の方から一手に非難を浴びそうですね。
自分で出来る範囲で何かアウトプットしたいという気持ちはすごく共感や好意が持てますし、
2ちゃんねるで言うところの改変コピペみたいなのはその分野をより多くの人に知ってもらう
ためなどに効果があると思いますが、やはり原著者に対する敬意やその分野への造詣や見識の
深さなどが求められるとこかもしれません。などとは私に言えることではありませんでした。ご容赦下さい。
343 :neetubot [] :2009/11/05(木) 01:33:03
ついでに保守。最近やる気でてない間も、@Wikiの方には各所からお越し頂いていたようで、その節はどうもありがとうございます。
ここに質問など書いて頂いたら、できるだけ即レスします!
344+1 :neetubot [] :2010/01/02(土) 13:06:42
あけましておめでとうございますー 今年もよろしくお願いしますー
数学板では最近は四色問題が流行っているようで、じゃあ、
「(n-1)次元超球面(とそれをリーマン球面の考え方で変換できる(n-1)次元超平面)と同相な図形(単体的複体)は、
(その図形を単体分割すれば(n+1)面あるn次元単体に分割できることから、)たかだか(n+1)色で塗り分けられる」
とざっくり考えました。。あまり深く考えてませんが、みなさん、よい数学お年をー
345 :132人目の素数さん [↓] :2010/01/03(日) 12:19:04
_,,....,,_ _人人人人人人人人人人人人人人人_
-''":::::::::::::`''> ゆっくり幾何学していってね!!! <
ヽ::::::::::::::::::::: ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
|::::::;ノ´ ̄\:::::::::::\_,. -‐ァ __ _____ ______
|::::ノ ヽ、ヽr-r'"´ (.__ ,´ _,, '-´ ̄ ̄`-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_ _,.ヘーァ'二ハ二ヽ、へ,_7 'r ´ ヽ、ン、
::::::rー''7コ-‐'"´ ; ', `ヽ/`7 ,'==─- -─==', i
r-'ァ'"´/ /! ハ ハ ! iヾ_ノ i イ iゝ、イ人レ/_ルヽイ i |
!イ´ ,' | /__,.!/ V 、!__ハ ,' ,ゝ レリイi (ヒ_] ヒ_ン ).| .|、i .||
`! !/レi' (ヒ_] ヒ_ン レ'i ノ !Y!"" ,___, "" 「 !ノ i |
,' ノ !'" ,___, "' i .レ' L.',. ヽ _ン L」 ノ| .|
( ,ハ ヽ _ン 人! | ||ヽ、 ,イ| ||イ| /
,.ヘ,)、 )>,、 _____, ,.イ ハ レ ル` ー--─ ´ルレ レ´
346 :neetubot [] :2010/01/05(火) 18:00:04
>>344 の(n-1)次元超球面と同相な複体表面の彩色問題については、
表面が全て(n-1)次元単体となる複体表面Aの場合を数学的帰納法で証明した後、
1点まわりの点全てがある(n-1)次元超平面上にあるとき この多胞体錐のまわり
が高々n色で彩色でき、Aの各部分で多胞体錐を取り除いた任意の複体表面も(n+1)色で
彩色できることを証明すればいいと思ったが、いろいろダメそうなので、
Hadwiger氏のように(n+2)完全グラフ以上が書けないことを証明した方がいいとも思った。
あと、2次元多様体の分類定理における全ての曲面の彩色問題について少し調べた所、
「ヒーウッドの公式について(http://www.geocities.jp/ikuro_kotaro/koramu/270_heawood.htm)」
あたりが詳しかった。射影平面とクラインの壺上では6色、トーラス上では7色必要らすぃ!!??すげぇ
347+3 :neetubot [] :2010/01/10(日) 01:07:19
猫先生のどんな質問にもマジレスするスレ(弐)(http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1262693441/)
の14でも触れましたが、改めてこのスレで下記の問題について解いていこうと思います。
「m次元ユークリッド空間内でn次元単体を作る(n+1)個の頂点列\P=[\p_0…\p_n]と
その単体の内部点\p_a=\P [a_0…a_n]^T (ただし、全てのa_i≧0, \sum_{i=0…n} a_i =1)があるとき、
頂点\p_iおよび\p_aを結ぶ直線と \p_i以外の頂点で作られる(n-1)次元単体との 交点を\p'_iとすれば、
\p'_0…\p'_nで作られる内部n次元単体(Cevian Simplex)の超体積がこのとき取りうる値の範囲を求めよ。」
348+2 :neetubot [] :2010/01/10(日) 04:52:05
http://www7.atwiki.jp/neetubot/?plugin=ref&serial=37
>>347 のCevian Simplexを方向表記(Simplex Direction Formula 上図左)で表すと、
\l'_i=(\p'_i-\p_0)-(\p'_0-\p_0)=\L (\a (1/(1-a_i)-1/(1-a_0)) - \e_i (a_i/(1-a_i)))
と書けるため、\L'=\L (\a (\1-\a)^{-T} - \a/(1-a_0) \1^T - \Σ^{-1}[\1-\a] \Σ[\a])
と略記でき、|[\L'^T \L']| = |[\L^T \L]| ( |[\a […,1/(1-a_i)-1/(1-a_0),…]^T - \Σ[…,a_i/(1-a_i),…]]| )^2
となるため、http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_determinant_lemmaより、
√( |[\L'^T \L']| / |[\L^T \L]| ) = |-(1- […,1/(1-a_i)-1/(1-a_0),…]^T \Σ^(-1)[…,a_i/(1-a_i),…] \a)| |[\Σ[…,a_i/(1-a_i),…]]|
= |([…,1/(1-a_i)-1/(1-a_0),…]^T […,(1-a_i),…]-1)| (\prod_{i=1…n} (a_i/(1-a_i)))
= n \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) ≧ 0 (条件より全て0≦a_i≦1であるため)が成り立つ。
この形から上限はa_0=…=a_n=1/(n+1)のとき、√( |[\L'^T \L']| / |[\L^T \L]| ) ≦ 1/(n^n)であると予想する(証明まだ)
349+2 :neetubot [] :2010/01/10(日) 13:33:44
http://www7.atwiki.jp/neetubot/?plugin=ref&serial=37
>>347 のCevian Simplex(以下、点足単体と呼ぶ)を位置表記(Simplex Position Formula 上図右)
で表すと、\p'_i=(\p_a-\p_i a_i)/(1-a_i)となるため、点足単体の位置行列は
\P'=\P \A' = \P (\a […,1/(1-a_i),…]^T-\Σ[…,a_i/(1-a_i),…])と書ける。
ここで、元の単体の超体積はv^n=√(\1^T \C[\P^T \P] \1)/(n !)であり、
点足単体の超体積はv'^n=√(\1^T \C[\P'^T \P'] \1)/(n !)=√(\1^T \C[\A']^T \C[\P^T \P] \C[\A'] \1)/(n !)
と表せることから、\C[\P^T \P]=\A' \X \A'^Tを代入することで v'^n = |( |[\A']| )| v^nが成り立つ。
したがって、|( |[\A']| )|はhttp://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_determinant_lemmaより、
|( |[\A']| )| = |( -(1-[…,1/(1-a_i),…]^T \Σ^{-1}[…,a_i/(1-a_i),…] \a) \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) )|
= n |( Π_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) )| と解けるため、この問題は、\p_aが単体内部点となる条件の
「\sum_{i=0…n} a_i = 1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i(≦1) 」の範囲(単位単体内部条件)で
「v'^n/v^n = |( |[\A']| )| = n \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) 」の値の範囲を求める問題に帰着できる。
この問題は、一見 相加相乗平均を使いそうだがうまくいかず、今 数学的帰納法で導出を試みている。
350 :neetubot [] :2010/01/10(日) 22:47:23
>>348>>349 のつづき。a_0+a_1=αのとき、\prod_{i=0…1} (a_i/(α-a_i)) =1である。
また、\sum_{i=0…(n-1)} a_i =αで \prod_{i=0…(n-1)} (a_i/(α-a_i)) ≦1/(n-1)^n
が成り立つと仮定したとき、\sum_{i=0…n} a_i =αとすれば \prod_{i=0…n} (a_i/(α-a_i))
…うーんダメだな。\prod_{i=0…n} ((1-a_i)/a_i)を展開して各項に相加相乗平均を使うか…
351 :neetubot [] :2010/01/11(月) 04:20:43
>>348>>349 のつづき。\sum_{i=0…n} a_i = 1 ≧ (n+1) (\prod_{i=0…n} a_i)^(1/(n+1)) = (n+1) x ≧ 0とおく。
同じく相加相乗平均を用いて、\prod_{i=0…n} ((1-a_i)/a_i)=(1-(Σ a_i)+(Σ a_i a_j)-…+(-x)^(n+1))/x^(n+1)
≧ (1 - (n+1) x + (n+1)C2 x^2 - (n+1)C3 x^3 + … +(-x)^(n+1))/x^(n+1) = ((1-x)/x)^(n+1)
ここで、仮定より0≦x≦1/(n+1)であり、この範囲で(1-x)/x=(1/x)-1は単調減少関数であるため、
\prod_{i=0…n} ((1-a_i)/a_i) ≧ ((1/x)-1)^(n+1) ≧ n^(n+1)
(等号成立条件は a_0=…=a_n=1/(n+1) のとき)となる。
よって、「\sum_{i=0…n} a_i =1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i(≦1)」の範囲(単位単体内部条件)で
>>347の解「0 ≦ v'^n/v^n = |( |[\A']| )| = n \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) ≦ 1/(n^n)」が成り立ち、
超体積v^nの単体の内部ではその重心で作られる点足単体(Cevian Simplex)の超体積v^n/(n^n)が最大であることがわかった。
QED
352 :neetubot [] :2010/01/11(月) 04:32:54
次は、点足単体が元の単体と相似となる条件は \A'が全て等しい固有値を持つことなのかや、
点垂足単体の超体積が最大値をとる点(内心?)などを求めたいです。
353 :neetubot [] :2010/01/11(月) 18:13:51
点足単体(Cevian Simplex) http://mathworld.wolfram.com/CevianTriangle.html
点反足単体(Anticevian Simplex) http://mathworld.wolfram.com/AnticevianTriangle.html
点垂足単体(Pedal Simplex) http://mathworld.wolfram.com/PedalTriangle.html
点反垂足単体(Antipedal Simplex) http://mathworld.wolfram.com/AntipedalTriangle.html
垂足単体(Orthic Simplex) http://mathworld.wolfram.com/OrthicTriangle.html
について http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/51.html に追記しています。
354 :neetubot [] :2010/01/12(火) 07:40:45
位置行列\Pから点足座標行列\A'で点足単体\P \A'まで出るのはいいが、
点反足座標行列\A'^†で\P \A' \A'^† = \P \A'^† \A' = \Pとなるはずはない気がする、、
355 :neetubot [] :2010/01/12(火) 21:10:52
|[ \~A' ]| ≠ 0 だから普通に点足座標行列\~A'の逆行列\~A'^{-1}出ました。
点反足座標行列\~A'^{-1}=([…,(1-a_i),…] […,1/(n a_i),…]^T - \Σ[…,(1-a_i)/a_i,…])
でした。ちゃんと、(\P \A') \A'^{-1} = (\P \A'^{-1}) \A' = \Pで元の単体に戻ります。
356 :neetubot [] :2010/01/17(日) 01:09:10
点垂足単体の超体積が最大値をとる点はたぶん逆垂心だな。
と書こうと思って放置しとった。今までn次元単体のある内部点
を通して(n-1)次元単体面に作られる図形を点足単体と呼んでいたが、
これを拡張し、n次元単体の一内部点からk次元面に作られる図形を
「n次元単体のk次元点足(_(n+1) C_(k+1)点)複体P'_k」と呼ぶことにし以下に示す。
これで、高々(n+1)点(とその一内部点)が決まれば作れる複体の全てが表せることになる(と思う。)
357+1 :neetubot「n次元単体のk次元点足複体」 [] :2010/01/17(日) 06:01:53
次レスで0次元点足単体から簡単に定義できることを示すが、
あえてここで地道なn次元点足単体からの定義を示す。
まず、m次元ユークリッド空間内で原点からのアフィン独立な
位置ベクトル\p_0…\p_nが表す点が囲むn次元単体を
m×(n+1)行列 \P=[\p_0, …, \p_n] で表す。
ここで、n次元単体\Pの内部点を位置ベクトル \p_a = \P [a_0, …, a_n]^T = \P \a
(内部点なので、\sum_{i=0…n} a_i = \1^T \a = 1、全て a_i ≧ 0)で表すとき、
\Pの頂点\p_iから\p_aを通る直線と \p_i以外の頂点で作られる(n-1)次元単体面との
交点を\p'_{i (n-1)}すれば、全てのi=0…nの点\p'_{i (n-1)}で作られるn次元単体は
(n-1)次元点足複体 \P'_{(n-1)}=[\p'_{0 (n-1)}, …, \p'_{n (n-1)}] と書ける。
また、\p_0から\p'_1を通る直線と \p_1から\p'_0を通る直線の交点を計算すると
\p_2…\p_nで作られる(n-2)次元単体面上の点\p'_{j (n-2)}=\P [0, 0, a_2/(1-a_0-a_1), …, a_n/(1-a_0-a_1)]^Tとなる。
ここで、(n+1)個の成分のうち(k+1)個が1で残り(n-k)個が0の列ベクトルを
全て列挙した (n+1)×(_(n+1) C_(k+1))行列 \~E'_{C_k^n} を定義すると
(例えば、\~E'_{C_1^2} = [[1,1,0]^T, [1,0,1]^T, [0,1,1]^T]となる)、
n次元単体の全ての(n-2)次元単体面上で点\p'_{j (n-2)}のような(_(n+1) C_(n-1))点
\P'_{(n-2)}=[\p'_{0 (n-2)}, …, \p'_{(_(n+1) C_(n-1) - 1) (n-2)}]が計算でき、
この行列\P'_{(n-2)}で表される複体を(n-2)次元点足複体と呼ぶ。
上記のように(k+1)次元点足複体\P'_{(k+1)}が作られると仮定したとき、
例えば元のn次元単体のある頂点\p_i(i=(k+1)…(n+1))と\p_0…\p_kで作られる
(k+1)次元単体面にある\P'_{(k+1)}の頂点を\p'_{i (k+1)}とすれば、
\p_iと\p'_{i (k+1)}を通る直線は全て\p'_{ j k}=\P [0, …, 0, a_(k+1)/(1-a_0…-a_k), …, a_n/(1-a_0…-a_k)]^T
で交わることがわかり「\P'_k = \P \Σ[\a] \~E'_{C_k^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_k^n}^T \a] = \P \A'_k」
が成り立つと言える。
この操作でk次元点足複体\P'_kを作りつづけると、1次元点足単体\P'_1は
元のn次元単体の頂点\p_iと頂点\p_jを結ぶ辺をa_j : a_iに内分する点が頂点
(全部で(_(n+1) C_2個)で、最後に0次元点足単体\P'_0は元の単体自体となる。
358+1 :neetubot「n次元単体のk次元点足複体」 [] :2010/01/17(日) 14:29:32
まず、m次元ユークリッド空間内で原点からのアフィン独立な
位置ベクトル\p_0…\p_nが表す点が囲むn次元単体を
m×(n+1)行列 \P=[\p_0, …, \p_n] で表す。
ここで、ある(n+1)個の定数a_0, …, a_nと添字i,j,l=0,…,nを用いて、
n次元単体\Pの頂点\p_iと頂点\p_jを結ぶ辺をa_j : a_iに内分する点
\p'_{t 1}の全ての組み合わせを頂点とする1次元点足((_(n+1) C_2)点)複体\P'_1を作る。
次に、\Pの\p_iと\p_jと\p_lが作る三角形で、上記\p'_{t 1}と
\p_lの間をa_l : (a_i+a_j)に内分する点を\p'_{t 2}とすれば
(この\p'_{t 2}は、\p_jと\p_lをa_l:a_jに内分する点と \p_iを a_i:(a_j+a_l)に内分する点であり、
またこのとき、\p_lと\p_iをa_i:a_lに内分する点と \p_jを a_j:(a_l+a_i)に内分する点である)、
このような\p'_{t 2}の全ての組み合わせを頂点とする2次元点足((_(n+1) C_3)点)複体\P'_2を作る。
上記のような計算操作で、n次元単体\Pの(k-1)次元点足複体が下式で決定されると仮定すると
「\P'_{(k-1)} = \P \Σ[\a] \~E'_{C_{(k-1)}^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_{(k-1)}^n}^T \a] = \P \A'_{(k-1)}」、
例えばこのn次元単体\Pの頂点\p_0…\p_{(k-1)}と \p_i(i=k…(n+1))で作られるk次元単体面では、
\p_0…\p_{(k-1)}で作られる(k-1)次元単体面上に存在する\P'_{(k-1)}の頂点と
\p_iをa_i:(a_0+…+a_{(k-1)})で内分する点が\P'_kの頂点ということができ全ての組み合わせで
「\P'_k = \P \Σ[\a] \~E'_{C_k^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_k^n}^T \a] = \P \A'_k」と計算できる。
この数学的帰納法で次々に導出できるk次元点足複体\P'_kは、\P'_{(n-1)}=
\P (\a […,1/(1-a_i),…]^T-\Σ[…,a_i/(1-a_i),…])となりこれは確かに前述の(n-1)次元点足単体であり、
\P'_nを最後にむりやり計算すれば単体の内部点\p_a自体となることが導出できる。
以上より、n次元単体\Pが一つ決まれば、定数a_0, …, a_nの値によって、
0次元点足複体\P'_0(元の単体\P自体)からn次元点足複体\P'_n(単体内部点\p_a)まで
一意に決定され、これらのk次元点足(n次元(_(n+1) C_(k+1))点)複体は
n次元単体同様に使いやすく、超体積が簡単に導出できたり、
これら複体は常に外心などを持つなどの美しい性質が期待できる。
359 :neetubot [] :2010/01/17(日) 15:06:22
これらは、
分からない問題はここに書いてね327
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1262413352/260
260 :251:2010/01/16(土) 16:10:07
>>259
よく確認をしたら垂心の考え方を使って垂心hの位置ベクトルoh→を求める問題でした
ご迷惑おかけしました。 問題書き直しましたのでよろしくおねがいします
△abcでa,b,cの位置ベクトルをoa→、ob→、oc→
垂心をh、ahとbcの交点をdとすると
dはbcをtanc:tanbに内分する
またhはadを(tanb+tanc):tanaに内分する点だから(ここでどうしてこのような内分比になるか教えていただけませんか?)
oh→=tanaoa→+tanbab→+tancoc→/tana+tanb+tanc
をn次元拡張して思いつきました。上の場合、ただの平面幾何ですが>>357>>358あたりをふまえれば
2次元単体(鋭角三角形とする)ABCの周囲をそれぞれtanb:tana・tanc:tanb・tana:tancに内分する点で作られる
三角形FDEが1次元点足(2次元3点)複体であり、AD・BE・CFをそれぞれ(tanb+tanc):tana・
(tanc+tana):tanb・(tana+tanb):tancに内分する点が一致し、それは2次元単体ABCと
定数a_0, a_1, a_2=tana/(tana+tanb+tanc), tanb/(tana+tanb+tanc), tanc/(tana+tanb+tanc)
の値によって作られる2次元点足(2次元1点)複体の単体内部点\p_aにほかならないと言えよう。
?計算いいのか?
360 :neetubot [] :2010/01/17(日) 20:45:05
さて、n次元単体\Pのk次元点足複体\P'_k = \P \Σ[\a] \~E'_{C_k^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_k^n}^T \a] = \P \A'_k
のn次元超体積は、k次元点足複体\P'_kの内部には必ずn次元点足複体\P'_n(単体内部点\p_a)
があるといえるので、\P'_kのそれぞれの(n-1)次元面と\P'_nで作られる複体錐を足し合わせることで
超体積求まると思いきや…4次元単体(五胞体)の1と2次元点足複体は↓なので、
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectified_5-cell
4次元までは切頂で超体積求まるのか!?けっこう難しい…あと、外接超球面ではなく外接超楕円面の方が都合良さそう
361+1 :neetubot [] :2010/01/17(日) 22:26:22
m次元ユークリッド空間内でn次元単体\Pの定数a_0, …, a_nの値によって決まる
1次元点足複体\P'_1の超体積 v^n[\P'_1] は、\Pの超体積を単にv^nで表せば、
v^n[\P'_1] = ( 1 - \sum_{i=0…n} \prod_{j=0…n≠i} (a_j)/(a_i+a_j) ) v^n
と書ける、と感じた。これはnは2で1/4, 3で1/2, 4で11/16と、nが大きくなるにつれn次元単体に近づく(!?)
しかし、各頂点周りの単体を取り除く方法はこの1次元点足(n次元(_(n+1) C_2点)複体にしか使えないだろう。
362+1 :neetubot [] :2010/01/18(月) 00:12:23
>>361 の>これはnは2で1/4, 3で1/2, 4で11/16と、nが大きくなるにつれn次元単体に近づく
のは、超体積が最大値をとると思われるa_0=…=a_n=1/(n+1)のときでした。
\sum_{i=0…n} a_i =1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i のとき、
F=\sum_{i=0…n} 2/( \prod_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) ) ≧ (n+1)/(2^n)
(F≦1)を証明…できん…
363 :neetubot [] :2010/01/21(木) 05:58:33
>>362 \sum_{i=0…n} a_i =1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i とすれば、F_0=\sum_{i=0…n} 2/( \prod_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) )
(算術平均≧幾何平均 より、) F_0≧2(n+1)/(( \prod_{i=0…n} \prod_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) )^( 1/(n+1) ))=F_1
(1/(幾何平均)≧1/(算術平均) より、) F_1≧2(n+1)^(2n+3) / ( \sum_{i=0…n} \sum_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) )^(n+1)
=2(n+1)^(2n+3) / ( (n+1)^2 + \sum_{j=0…n} (\sum_{i=0…n} a_i/a_j) )^(n+1)=2(n+1)^(2n+3) / ( (n+1)^2 + (\sum_{j=0…n} 1/a_j) )^(n+1)=F_2
(仮定より、調和平均 \sum_{j=0…n} 1/a_j ≧ (n+1)^2 となるので、) F_2 ≦ (n+1)/(2^n) …えっ!?
ムリタポ…
やぁ、ひさしぶり。じゃあ、最近考えてたことなどを書いていきますー
まず、非斉次?の行列多項方程式について考えてました。m次行列 X と実数係数 v_i について
Σ_{i=1}^n v_i X^i = M = Θ Λ' Θ^T (Θはm×n正規直交行列、Λ'はn次ジョルダン行列)
が成り立つとする。X = Θ X' Θ^Tとし、Λ'の n'_i次k_i乗ジョルダンλ_iブロック Λ_{O k_i}とすれば、
Σ_{i=1}^n v_i (X'のn'_i次ブロック)^i = Λ_{O k_i} = λ_i E + O_{k_i} (O_{k_i}はn'_i次k_i乗冪零行列)と分解できる。
上式は、((Σ_{i=1}^n v_i (X'のn'_i次ブロック)^i) - λ_i E)^{k_i} = O と変形できるので、条件に応じて導出される
この式を満たす解を (X'のn'_i次ブロック)=Λ_{i X'} とすれば、同様に導出できる i以外の(X'のn'_i次ブロック)も全て
用いて対角成分に並べた X' = Λ' […, Λ_{i X'}, …] = Λ'_X を使って、「 X = Θ Λ'_X Θ^T 」と導ける。…と思いましたが、
どうでしょうか?この非斉次行列多項方程式(と↑を勝手に仮に呼んでます)は 線型システムの話では結構出てくる
と思って いろいろ検索してましたが、引っかかるのは微分方程式系ばかりで この解法のヒントは発見できませんでした。
↑だといろいろおかしいし、つっこみどころ満載だと思いますので、誰か何か情報をくれるとありがたいです。。
236 :132人目の素数さん [] :2009/01/25(日) 01:01:45
次に、県内の一番大きい本屋に行っていろいろ見てきたんだけど目新しい情報は
Plucker relations(といっても名前だけは大学で聞いてた)ぐらいだったので、それについて書きます。
プリュッカー関係式は位置行列について通常より1列多い同次座標系で成り立つ関係式のような気が
しますが、大事なのはm×n方向行列Lとその中の方向ベクトルl_iをあわせた行列 (L l_i) の中から
(n+1)列選んだ行列の行列式が0になるという( _m C_(n+1) )×n通り(多分独立な関係式はその
中でも n(n-1)/2通りぐらい)の関係式が成り立つということだと思いました、が使い道は不明…
Plucker coordinates - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCcker_coordinates
あとは、m次元ユークリッド空間 U^m 内のあるn次元部分空間の基底を表すm×n行列を L とすれば、
m次元ユークリッド空間内のベクトルなどをその n次元部分空間へ正射影するm次基底変換行列
(正射影行列)は W[L] = L (L^T L)^{-1} L^T と書けるということが、↓の Orthogonal projections
の項で既に世界に概出してたのを発見しました。
Projection (linear algebra) - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Projection_(linear_algebra)
しかしまだ、位置行列 P と余因子行列 C[] と余因子総和行列 \tilde{C}[] を用いて 正射影行列が
W[L] = \frac{P \tilde{C}[P^T P] P^T}{1^T C[P^T P] 1} = \tilde{W}[P] と書き換えれることや、
U^m内での L の直交補空間の基底 Y に対して W[L] W[Y] = O, W[L] + W[Y] = E(単位行列)
となることや、始点は同じ基底 L と L' で作られる和空間の基底が Θ[L ∪ L'] = Θ[W[L] + W[L']]
(Θ[ ] は []内で与えられる空間や行列の基底を 列の基本変形や特異値分解によって返す関数)
であったり、積空間の基底は Θ[L ∩ L'] = Θ[ E - W[W[ E - W[L] ] + W[ E - W[L'] ]] ] と表せたり
するようなことは、世界に概出してない!こともないか… という雑感。。
237+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/25(日) 02:37:40
そういえば、あまり関係ない簡単な話ですが、任意のn次元列ベクトル \bm{a} について、
\bm{a}^T \bm{a} = 1 のとき、-√n ≦ \bm{1}^T \bm{a} ≦ √n (原点から単位超球上へのベクトルと\bm{1}の内積)が成り立ち、
また、\bm{1}^T \bm{a} = 1 のとき、\bm{a}^T \bm{a} ≧ 1/n (\bm{1}/nを通る\bm{1}/nの直交補空間上へ原点から向かうベクトルの長さ)
という関係式が成り立つと思われ。。美しいちゃ美しいけど、トリビアっちゃあトリビアル。
238+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/25(日) 06:08:29
「線形代数/線型代数 5」の416さんの問題
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/416
>任意の正整数 n に対して次の条件を満たす4n×4n行列Aが存在する.
>(1) Aの成分は±1, (2) A A^T = 4n I
成分が±1/(√m)であるm次正規直交行列Θ(Θ^T Θ = E)は存在するか?だとすれば、
i≠jでθ_i^T θ_j = 0より、互いに半分の成分の符号が違わねばならず、満たすとすれば
m=2のときの[1/√2, 1/√2; 1/√2, -1/√2]のみでそれ以外のmでは存在しない?
>実数 a_1, ..., a_n が非負行列の固有値となる必要十分条件は何か.
m≧nのあるm×n正規直交行列Θに対して その非負行列が ΘΣ[a_1, ..., a_n]Θ^T と書けること?
だと思いました。先方のスレでは華麗にスルーするふいんき(←)を感じた。。
239 :132人目の素数さん [] :2009/01/26(月) 05:51:58
「線形代数/線型代数 5」の話
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/392-393
先方のスレでは、449さんがスルーしない空気を作りましたが、俺は こっちの>>238で恥ずかしいこと
書いてしまったので、あっちでマルチもリンクも書けない!やっちまったなぁー。こっちにだけ書く!
>(392の意訳) n次正則行列 A, B を並べた行列 [A B] の n次部分行列 C で perm(C) ≠ 0 なるものが存在する。
この条件なら、A=B=Cとしてもいいと思うので、perm(正則行列C) ≠ 0 なるもの、存在する。
>(393の意訳) 有限体Fを剰余類Z/kZ (k≧4)とする。F上の任意のn次正則行列 A に対し、
> 全ての成分に零元 [0]_k を含まないF上のn次元列ベクトル x, y で A x = y を満たすものが存在する。
例えば、Aを単位行列 A=[E]_k とすれば、[0]_kを含まないベクトル A x = x = y が存在するのはわかりますが、
任意の正則行列Aとなると、たぶん存在すると思いますが、どう証明すればいいのかちょっと浮かびません…
ーーここまでーー
というのが向こうで未解決問題と言われてるもののの全てかな。さすが、難しいーぉ。。
240+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/27(火) 07:13:14
「線形代数/線型代数 5」の455さんの問題について
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/455
向こうの流れを妨げたくないので、例によって、問題を意訳しつつこっちにパクリます。
(1)n次元ベクトル a, x とおいたとき、xに対して成分積 a ⊙ x を対応させる線型変換は、
a ⊙ x = Σ[a] xより、aの成分を対角に持つ対角行列 Σ[a] で表せる。
(2)n次行列 A のi列 a_i をn次元列ベクトル x で置き換えてできるn次行列を A_i(x) = \underset{(a_i ← x)}{A}
としたとき、行列式について |[ \underset{(a_i ← x)}{A} ]| = e_i^T C[A] x と(e_i は i成分が1の単位ベクトル)
書ける。これより、xから n次元列ベクトル [A_1(x), …, A_n(x)]^T = C[A] x への線型変換に対応する行列は
Aの転置余因子行列 C[A] で表せる。
(3) |[ A ]| = |[ (a_1 a_2 a_3) ]| = 1 のとき、f(x) = |[ ((3x+6)a_1+3a_2+(2x-1)a_3, -4a_1+(x+7)a_2-a_3, 5a_1+5a_3) ]|
= |[ A ]| |[ [(3x-6), -4, 5], [3, (x+7), 0], [(2x-1), -1, 5] ]| = 5 ((x+1)^2 -27)となることから、この行列式 f(x) は
x=-1のとき最小値 f(-1) = -135をとり、f(x)の絶対値の最小値は0でそのときはx=-1±3√3のどちらかである。
(2)はn次元単体を作る基底 L やその基底と座標 a = [a_1, …, a_n]^T で表される点を l_a = L a としたとき、
a_i は n次元単体のi点を除くi対面と点 l_a によって作られるn次元単体の体積を 元のn次元単体の体積で
割った値(以下、正規i分積)である(a_i = |[\underset{(l_i ← l_a)}{L}^T \underset{(l_i ← l_a)}{L}]| / |[L^T L]|)
となること、つまり、点を表す基底の座標ベクトル a は そのまんま 「点が基底を分割する体積比」であることを
表している!しかし、こっちで書いてる俺独特の表記を使っていろいろ書きたかっただけだった気持ちもあった…
241 :132人目の素数さん [↓] :2009/01/27(火) 08:35:42
「微分幾何学2」の13さんの情報
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1181801767/13
意訳>平面上にある2つの閉曲線の距離がどこも r なら、
その外側と内側の閉曲線における周の長さの差は 2 π r である。
と、昨日見て、うわっすげぇーと思いつつ、曲率半径が r 未満の曲率中心方向には囲めないとか、
n次元多様体に拡張して距離 r で囲んだら表面の差は 半径rのn次元超球面と同じにはならない(!)
とか考えてました。同心超球とか萌え。しかし、n次元多様体で成り立つ関係式がなんかあった気がしたんだが…
いや、そして、何もオチはないですが… さて、m次元ユークリッド幾何学っと。。
242+1 :132人目の素数さん [] :2009/01/28(水) 07:19:14
>>240 の(正規i分積)=(p_a= P \tilde{a} で表される内部点の単体座標 \tilde{a} のi成分(i=0~n))= a_i は
(n次元単体を作る(n+1)点への位置ベクトルを列挙した位置行列 P も線型独立(原点から
n次元単体への垂線ベクトルp_y= P C[P^T P] 1 / (1^T C[P^T P] 1) ≠ \bm{0})のときでなければ、
P \tilde{a}_\bm{0} = \bm{0}と任意のαで P \tilde{a} = P (\tilde{a} + \tilde{a}_\bm{0} α)に注意)
a_i = √(|[\underset{(l_i ← l_a)}{L}^T \underset{(l_i ← l_a)}{L}]| / |[L^T L]|)でした(ルート忘れてた)。
(↑はi=1~nで、a_0 = √(|[(L - l_a 1^T)^T (L - l_a 1^T)]| / |[L^T L]|) = |[(E - a 1^T)]| = 1 - 1^T a)
a_i を 位置行列 P で書き換えると、a_i = √(1^T C[\underset{(p_i ← p_a)}{P}^T \underset{(p_i ← p_a)}{P}] 1) / √(1^T C[P^T P] 1)
であるので、Σ_{i=0}^n a_i = 1^T \tilde{a} = 1よりΣ_{i=0}^n √(1^T C[\underset{(p_i ← p_a)}{P}^T \underset{(p_i ← p_a)}{P}] 1) = √(1^T C[P^T P] 1)
(n次元単体Pの超体積は、そのn次元単体を内部点p_aによって(n+1)個のn次元単体に分けたi分積の総和に等しい)が成り立つ。
これは、Σ_{i=0}^n √(1^T C^T[\underset{(\tilde{e}_i ← \tilde{a}_i)}{\tilde{E}}] X C[\underset{(\tilde{e}_i ← \tilde{a}_i)}{\tilde{E}}] 1) = √(1^T X 1)
(ただし、1^T \tilde{a} = 1、a_i ≧ 0)であることを表していると思うが、まだ計算で左辺から右辺に持っていけてはないです。。
このことを用いれば、n次元単体Pについて、その重心 p_G = P \tilde{a}_G = P \tilde{1}/(n+1) により分けられるi分積は全て等しい(a_{iG} = a_{j G} = 1/(n+1))、
および、その重心から各i対面への距離(下ろした垂線の長さ)の比が 元のn次元単体の各i垂線の長さの比に等しい(i対面×垂線=超体積)
などが言えます。とここに適当に掻い摘んでダラダラ書いたところでただのオナニーでしかなく、ちゃんと@wikiとかにまとめなきゃいけねーんだなぁー大変だなぁー
243 :132人目の素数さん [↓] :2009/01/30(金) 23:57:17
いろいろ迷って止まってます…このご時世で2月3月は暇そうなので がんばろうと思てます…
【PDF形式】132人目の素数さん『m次元ユークリッド空間内でのn次元単体の五心などの導出』【最新】
ttp://www7.atwiki.jp/neetubot/pub/neetubot.pdf
244 :132人目の素数さん [] :2009/02/02(月) 17:53:19
「線形代数/線型代数 5」の497さんの問題
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/497
(意訳)> m次元ユークリッド空間で、0-点(8,0,0,0…)・1-点(0,4,0,0…)・2-点(0,0,8/3,0…)を通る平面に対し、
3-点(5,4,3,0…)からの垂線と垂足を求めよ。(解は垂線(-1,-2,-3,0…)、垂足(4,2,0,0…)のようだ。)
をこっち的に言えば、m次元ユークリッド空間内の3次元単体の3点目の頂点からの3-垂線と3-垂足を
求めるという問題なので、各i点(i=0~3)をm次元列ベクトルp_iで表し、p_iを列挙した位置行列をm×4行列P
とすれば、(3-垂線)=-(P \tilde{C}[P^T P] e_3)/(e_3^T \tilde{C}[P^T P] e_3)、(3-垂足)=p_3+(3-垂線)より、
(ただし、余因子総和行列\tilde{C}[X]の[j,i]成分は、正方行列Xからi行とj列を除いた小行列X_{ij}の余因子行列C[X_{ij}]の
全ての成分の和1^T C[X_{ij}] 1に(-1)^{i+j}を掛けた値、すなわち、e_j^T \tilde{C}[X] e_i = (-1)^{i+j} 1^T C[X_{ij}] 1とする)
| 8 0 0 5 | | 6496/9 896/3 -672 -7168/9 |
P = | 0 4 0 4 | 、 \tilde{C}[P^T P] = | 896/3 12544/9 -896 -7168/9 | であることから、
| 0 0 8/3 3 | | -672 -896 1120 0 |
|↓0 0 0 0 | |-7168/9 -7168/9 0 14336/9 |
3-垂線(-1,-2,-3,0…)、3-垂足(4,2,0,0…)となる。(ちなみに、0-垂足(160/29, 80/29, 168/29, 0…)、1-垂足(8/7, 16/7, 24/7, 0…)、
2-垂足(24/5, 16/5, 0, 0…)と解ける。)この例では計算重いし、ぱっと見で あってるかわからないので、
以上より、@wikiとかに書く例は、原点とi点(…0, r_i, 0…)(i=1~n)で作られるn次元直交単体(n=2,3,n)の五心がいいなと。。
245 :132人目の素数さん [] :2009/04/08(水) 10:23:16
2ヶ月間 超だらけてたけど またがんばります。
以下、最近 考えてたことなど↓
線形代数/線型代数 5 のレス 790-797
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1225800000/790-797
から、任意の n次実行列Aが、ある n次正規直交行列Θと n次上三角行列Λを用いて、
1: A=ΘΛΘ^T と分解できる?(上三角分解?)
2: ケイリーハミルトンの定理より、Aの固有値λについての固有方程式を f_A (λ) = |[ λE - A ]| = 0 とすれば、f_A (A) = 0
3: k=0,1,…,nについて ||Λ^k p|| = 1 および |[Λ]| = 1 なら、k=n+1,…についても ||Λ^k p|| = 1 となる?
とか考えました。上のスレでもまだ答えは出てないようです。
n次元列ベクトル pを Λの正規一般固有ベクトル p_i (i=1~n)の線型結合で表して、
f_Λ (Λ) = 0とかも使ってグリグリ計算すると答え出る気がしないでもないですが、うーん…
246+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/08(水) 11:49:18
今まで転置余因子行列をC[・]で表してたけど、これから余因子行列をC[・]で表し 前述をC^T[・]で表そうと思いました。
理由は、n次元列ベクトル x_i (i=1~n)の列挙で作られる n×n行列 X=[x_1, …, x_n] とすれば、
Xの余因子行列を C[X] = [c_1, …, c_n] (c_i はC[X]のi列ベクトル)と書いたときに、
X^T C[X] = C^T[X] X = E |[X]| (Eは n×n単位行列、|[X]|は Xの行列式)と書けて、
c_i と x_j の内積 c_i^T x_j が i=jのとき|[X]|で i≠jのとき0と言えるので、
x_i をn次元ユークリッド空間内のn次元単体の 0点からi点への有向辺ベクトルと考えれば、
c_i = C[X] e_i は そのn次元単体のi点を除く(n-1)次元単体である i対面を表すベクトルとも考えられる。
ちなみに このとき、i点からi対面への i垂線ベクトルは 「 - c_i (|[X]| / (c_i^T c_i)) 」と表せる。
(ちなみに、このXで表されるn次元単体の超体積は|(|[X]|)|/(n!)、i対面の(n-1)次元超体積は(√(c_i^T c_i))/((n-1)!)。)
(個人的な趣味(位置行列Pと方向行列Lの間に成り立つ関係式を 1^T C[P^T P] 1 = |[ L^T L ]| と書きたかった)から
行列式を|[・]|で表してたけど、行列ノルムとして || L || = √( |[ L^T L ]| ) と書いていいなら、さっき使った苦肉の策の
行列式の絶対値を |(|[X]|)| = || X || と書けるのになぁと思った。そのうち、Wikipediaにある行列ノルムが満たすべき性質
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%88%97%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%A0 を満たすか調べようと思った。)
あと、全く関係ないですが、質問者→回答者よりも、出題者→解答者という言葉のが好きかな、とか。という備忘録
247+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/08(水) 18:06:53
下手の考え休むに似たり
248 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/08(水) 19:22:41
>>247 まぁ、あなたがどれほど上手で
僕に何を求めてるかはわかりませんが、
休むと休まざるとでは似て非なるものでしょう?(笑)
249 :132人目の素数さん [] :2009/04/08(水) 22:56:17
>>246 は、今まで、m次元ユークリッド空間内のn次元部分空間を表すL (以下、U^m ⊇ U_{p_0}^n [L] と書く)で
やってたものを、n次元ユークリッド空間内のn次元部分空間を表すX (以下、U^n ⊇ U_{p_0}^n [X])を用いたら、
余因子行列C[・]が意味するところ(C[X]は Xの 直交行列)は 幾何学的には「0対面以外の対面を表す行列」
と言えるのではと提言しました。ちなみに、0対面を表すベクトルは c_0 = - C[X] \bm{1} / n と書けると考えてます。
ちなみに、U^(n+1)内で n次元単体を位置行列Pで表す場合(以下、斉次を区別する記法\tilde{・}を\{・}で略す)は、
\{U}^(n+1) ⊇ \{U}^n [P] とか書き、(n+1)×(n+1)の余因子総和行列 \{C}[P] がそのまま「0~n対面を表す行列」
になるかと思ってますが、これはまだ詳しく試してません。
>>246 の過程から、ベクトルの大きさを表すユークリッドノルムのm×n行列(例えば L)への拡張として、
|| L || = (√( |[ L^T L ]| )) / (n!) と考えようと思いました。これを「単体積ノルム」とか呼びたいのですが、
Wikipediaにある || L || > 0 以外のノルムの性質?( || L α || = || L || | α^n | ≠ || L || | α | や他の
条件)を満たさないようなので、いいものかどうか…
とりあえず、わかってるところまでは書いてる気がするし、先人も全く見つけられないなか 暗中模索しながらやってるので、
あとは新しい情報や考えが浮かんでくるまで、みなさんも気長に読んだり書いたり ゆっくりしていってね!!!
250 :132人目の素数さん [] :2009/04/08(水) 23:39:30
U^m ⊇ U_{p_0}^n [L] のとき、n次元単体を作るL=[l_1, …, l_n]の各l_i はn次元部分空間を張るので線型独立となる。
しかし、\{U}^m ⊇ \{U}^n [P] で原点\bm{0}から Pで表されるn次元単体の各頂点へのベクトル p_i (i=0~n) は
1次元だけ線型従属となる(p_0がLの線型結合で表せる)場合があり、このときは P \{a}_\bm{0} = \bm{0} でも
\{a}_\bm{0} が零ベクトル以外の 1次元の任意性を表す解を持ち、原点\bm{0}から Pで表されるn次元単体への
垂線ベクトルも p_y = P ((C[P^T P] \bm{1}) / (\bm{1}^T C[P^T P] \bm{1})) = \bm{0} と書ける。このことから、
Pが線型独立の場合、P \{a}_\bm{0} = \bm{0} なら \{a}_\bm{0} = \bm{0}_n でしかなく、p_y ≠ \bm{0} 。
Pが線型従属の場合、P \{a}_\bm{0} = \bm{0} でも \{a}_\bm{0} ≠ \bm{0}_n が存在し、p_y = \bm{0} でもあるため、
\{a}_\bm{0} = ((C[P^T P] \bm{1}) / (\bm{1}^T C[P^T P] \bm{1})) α (αは任意の実数) という式が成り立つと思う。
しかし この式は、p_i = \bm{0} を含む場合や、Pが線型独立の場合との整合性などが怪しいので確かめたい。
そろそろ一年やってみて、この先 一年くらいは これまでの成果などを まとめるターンかと 個人的に思ってますが、
同じような事を何度も書くのは けっこうトリビアルだとも思って 休んでしまうときもあるので、 …ゆっくりしていってね!!!
251+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/09(木) 08:11:08
今日、たぶんもうdat落ちしている「シンプルで難しい問題」スレにあった
「凸五角形Sと その対角線によって作られる内部の凸五角形S'の 面積比S/S'の最大値を求めよ」
という問題に興味を持ちました。昔の数セミの問題らしいけど僕にエクセレントな回答は思い浮かびそうも無いので、
xy平面上の5点を[x0,y0],…,[x4,y4]として面積比を出して 凸の条件から導出するくらいしか考えつかないなぁー。
例えば、凸四角形と その頂点からその頂点を含まない2つの対辺の中点へ向かう線の組み合わせで
得られる内部の凸四角形との面積比とかなら、よりやりやすい気もした。 n次元(n+1)点複体ならどうか…zzz
平面の話ということで、これまた気になってたクリフォードの定理などと結び付けられたら面白くなりそうだな、と思った。
252+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/10(金) 04:53:25
>>251 まず問題は「凸5角形の面積をS、対角線で作られる小5角形の面積をS'とするとき、S'/Sの最大値を求めよ。 」と逆でした。
最小値は凸5角形じゃなくなるときのS'/S=0かな。俺がやったのは、小五角形の内部点から凸五角形の5点への2次元ベクトルを
x_i = [r_i cosθ_i, r_i sinθ_i] (極座標のように)として、x_iの始点から反対側にある小五角形の点への2次元ベクトルを y_i とすれば、
y_0 = (1-a) x_1 + a x_3 = (1-b) x_2 + b x_4などからy_iが出て、S'/S=(y_0×y_1 +…)/(x_0×x_1 +…)で定式化できると考えましたが、
計算が重すぎて、いろいろやったあげく、4 √(5+2√5) = (1+√5) √(10+2√5) という等式が成り立つのを見つけたところでギブアップ。
ということで、答えを探した結果、五角形の面積比問題
http://cheese.2ch.net/math/kako/955/955485321.html
で解である 「正五角形のとき S'/S=(7-3√5)/2≒0.146」 (小さすぎる?)が最大値というのと、
証明らしきものが載ってましたが、よくわからなかった。それより下記が気になった↓
106 名前: 甘美なノルム空間 投稿日: 2000/12/21(木) 05:01
凸N角形の面積をS、
頂点を反時計回りにV(0), v(1), ..., V(N-1)とし
V(x)とv((x+2)mod N)を結んで小N角形をつくる。
小N角形の面積をS'と するとき、
Q1.正N角形の場合、NについてS'/Sを求めるの関数を求めよ。
Q2. S'/Sの最大値をNについて求める関数を存在するか。
Q3. N=5のとき、S'/Sの最大値を求めよ。
↑の凸N角形の縮小変換を再帰的に行って収束する点を求める問題とかも面白いかも。
時計回りに点を選んで逆方向で縮小変換を繰り返したら 反時計回りと違う点に収束するかも!?
253 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 06:56:06
「面白い問題おしえてーな 九問目」スレ
http://www3.tokai.or.jp/meta/gokudo-/omoshi-log/1093676103.html
176 名前:132人目の素数さん:04/09/17 06:14:35
別スレみてて思いついた
――問題――
P1・・・P(n+1)をn次元ユークリッド空間の点としてΔをその凸包とする。
行列A=(aij)を次でさだめる。
aij=
0 (i=j)
1 (i≠j, n+2∈{i,j})
d(Pi,Pj)^2 (otherwise)
(ただしd(Q,R)はQとRの距離)
このときdetA=-(-2)^n(n!volΔ)^2が成立することをしめせ。
――――――
たぶんいけると思うんだけど。
179 名前:132人目の素数さん:04/09/18 20:27:35
>>176の公式ってなんか名前ついてんの?
というやりとりを発見しましたが、この後この発言にはレスが付いてませんでした。当スレでは >>20さんの情報から これは「Heron の公式の高次元版」として公知であると思ってます。
私的には、m次元ユークリッド空間内の(n+1)点への位置ベクトルを p_i (i=0~n)として、b_{ji}=(p_j-p_i)^T (p_j-p_i) / 2 を (j+1)行(i+1)列の成分に持つ(n+1)×(n+1)行列 \{B} (辺乗行列と
呼んでいる)とすれば、-\{B}の余因子行列 C[-\{B}] と 全ての成分が1のベクトル \{1}を用いて、
p_i (i=0~n)で表される(n+1)点の凸包であるn次元単体Lの超体積||L||は √(\{1}^T C[-\{B}] \{1}) / (n!)と書くと美しいと思ってます。(参考:http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/16.html)
個人的に使っているこの辺乗行列\{B}を用いれば、i番目の斉次n次元単位ベクトル\{e}_iや余因子総和行列\{C}[・]を使って、
辺乗行列が\{B}となるn次元単体の外接超球の半径 r_O が r_O = √(|[ - \{B} ]| / (\{1}^T C[-\{B}] \{1})) と書けたり、
そのn次元単体の内接超球の半径 r_I が r_I = 1/(Σ_{i=0}^n √((\{e}_i^T \{C}[-\{B}] \{e}_i) / (\{1}^T C[-\{B}] \{1})))
と書けたり、n次元単体の重心と各頂点との自乗距離の総和が (\{1}^T \{B} \{1}) と書けると思います。という宣伝。
254+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 07:05:45
>>237 で自分で書いときながら、半分忘れてて、↓スレで質問しつつ、回答から拡張してたのの備忘録↓
分からない問題はここに書いてね305
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1239022787/40
40 名前:132人目の素数さん[] 投稿日:2009/04/07(火) 15:00:47
「x_1 + x_2 + … + x_n = 1 のとき、x_1^2 + x_2^2 + … + x_n^2 ≧ 1/n」
のような不等式(とその名前)を何処かで見かけた気がするのですが、誰か知ってませんか?
コーシーシュワルツやヘルダーの不等式の関係っぽい気もしましたが、うまく導けない…
71 名前:40[] 投稿日:2009/04/08(水) 00:03:49
>>43 さんのように、コーシーシュワルツの不等式 (Σ_{i=1}^n x_i^2)(Σ_{i=1}^n y_i^2) ≧ (Σ_{i=1}^n x_i y_i)^2
に y_1=y_2=…=y_n=1 と仮定のΣ_{i=1}^n x_i = 1を代入して Σ_{i=1}^n x_i^2 ≧ 1/n を導く方法と、
>>44 さんのように、数学的帰納法を使って証明するやり方を納得できました。 ありがとうございます!
このような不等式をヘルダーの不等式にあてはめて考えて、
「 Σ_{i=1}^n | x_i | = a のとき、p > 1 なら Σ_{i=1}^n | x_i |^p ≧ (a^p)/(n^(p-1))、
0 < p < 1 なら Σ_{i=1}^n | x_i |^p ≦ (a^p)/(n^(p-1)) 」という不等式も出ました。
これは、第1象限で n次元超平面と n変数p次曲面の位置を比べてるとも考えられたりして、
ヘルダーの方の式で 絶対値をとれるかとか p < 0 の場合どうなるかとかも考えてみたいと思いました。
というのを また忘れそうなので、このスレにコピペしおてく。。
今日こそ、2ヶ月いやもっと長く戦ってきた見えない敵(垂足単体の内心が元のn次元単体の垂心となるか)に決着を付けたい…
255 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 08:04:26
任意のm×n行列L (m≧n)について、m×n正規直交行列Θと n×n上三角行列Λを用いて、
L = Θ Λ と分解できないかな?m=nの場合に成り立つならできそうだけど…何分解だっけか…
何がしたいかというと、任意のn次元単体は うまく回転変形すれば n次元空間で拡縮を含むせん断変形(shear)成分だけになる
と言いたい感じです。そして、この成分をn乗Λ^nして…ってことじゃなかった気がしたけど…あれ?なんだったっけ
256 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/10(金) 08:26:39
「面白い問題おしえてーな 九問目」スレ
http://www3.tokai.or.jp/meta/gokudo-/omoshi-log/1093676103.html
248 名前:132人目の素数さん:04/10/01 04:30:50
三角形の内部に点Pを取る。
点Pから三角形の各頂点への距離の和をS
点Pから三角形の各辺への距離の和をTとするとき
S≧2Tを示し、等号成立条件を求めよ。
同様に、四面体において内部に点Pを取り
点Pから四面体の各頂点への距離の和をS
点Pから四面体の各辺への距離の和をTとするとき、
S≧T√8を示し、等号成立条件を求めよ。
284 名前:132人目の素数さん:04/10/05 22:26:33
http://www.geocities.jp/ikuro_kotaro/koramu/hutou1.htm
…中略…
まぁ、俺が張ったアドレスの方が間違いって言う可能性もあるんだし、
とりあえず、証明出てくるまでは、2ch的未解決っていうことで。
2ch的未解決問題か…オラ ワクワクしてきた!
ということで、このスレ見てる方いらしたら、出題とか質問とか 何でもしてくれたらうれしいです
257 :132人目の素数さん [] :2009/04/11(土) 07:46:18
>>252 凸(n+1)角形の頂点を二点おきに結ぶなら、時計回りも逆回りも関係なく同じ縮小(n+1)角形が作られるだろうに。何を勘違いしてたんだ私は…
凸5角形の各頂点を反時計回りにi点(i=0~4)と呼び、0点からi点(i=1~4)へのベクトルをl_iとして、l_2,l_3をl_1,l_4の線型結合で表して解こうとしましたが、
わかったことは、mをnで割った余りを[m]_nで表すとき、i点と[i+2]_5点および [i+1]_5点と[i+3]_5点を結ぶ線の交点を小i'点とすれば、下記のことでした。
・i点と小[i+1]_5点を結ぶ 5つの線は一点で交わらない。
・凸5角形の重心と、小i'点で作られる小5角形の重心は一致しない。
・凸5角形に外接する楕円は一意に求まるが、その外接楕円の中心と小5角形の外接楕円の中心は一致しない。
最後のは目見当ですが…。凸5角形の各辺の中点を結ぶことで再帰的に小5角形を作る場合なら、元の凸5角形の重心に収束しそうなのに、
って、やべぇ、これは決定的なアイディアが浮かんでしまったか!?でも収束するなら重心しか考えられないけど…それは少しやだなぁ…
凸(n+1)角形(n+1≧5)の頂点をk個(k=2~⌊n/2⌋)飛ばしで結び、内部にできる縮小(n+1)角形についても同じ縮小変換を繰り返すとき、
この操作を無限回行うことで収束する点を 「凸(n+1)角形k点飛縮収束点」と仮に呼び、以後これらの問題を 形縮収束点の問題とでも呼ぶぉ。
258+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/12(日) 08:49:54
凸5角形の各頂点を反時計回りにi点(i=0~4)と呼ぶ。
0点からi点(i=1~4)へのベクトルをl_iとして、l_2 = l_1 s_2 + l_4 t_2、 l_3 = l_1 s_3 + l_4 t_3となるとする。
(このとき凸5角形という条件から、s_2 > s_3 > 0、 t_3 > t_2 > 0、 s_2 + t_2 > 1、 s_3 + t_3 > 1であると考えられる。)
凸5角形の周上のi点と[i+1]_5点の中点で囲まれる小5角形をS'とし、S'の元の凸5角形Sに対する面積比をFとする(0<F<1)。
この場合、 F=1/2 + (s_2 + t_3 - 1)/(4(s_2 t_3 - s_3 t_2 + s_3 + t_2)) と導出でき、
たぶん(s_2 = t_3、s_3 = t_2としてしか試してないが…)凸5角形の条件下で∂F/∂s_2 = ∂F/∂s_3 = ∂F/∂t_2 = ∂F/∂t_3 = 0 となる
s_2 = t_3 = (1+√5)/2、 s_3 = t_2 = 1 の場合に、Fが最大値 max[F]=(3+√5)/8 をとることが示せる。
ちなみに、Fの式から(s_2=s_3=t_2=t_3=1/2に近づくとき)Fは最小値1/2に限りなく近づくと考えられ、「1/2 < F ≦ (3+√5)/8」 だと思う。
このことは、正5角形でない適当な l_1とl_4でも成り立つので、凸(n+1)角形k点飛縮面積比が最大のときも正5角形とも限らないと予想できる。
また、一般的な凸(n+1)角形の各辺の中点(一定比の内分点でも同じか?)で囲まれる小(n+1)角形について、
常にその凸(n+1)角形と小(n+1)角形の内部にある重心が一致することから、再帰的にこの小(n+1)角形を作るとき、
その小小…(n+1)角形が 元の凸(n+1)角形の重心に向かって収束していくことが容易に想像できる。
これを仮に、「凸(n+1)角形辺中囲縮収束点はその凸(n+1)角形の重心となる」と言うことにする。
あと仮に、「n=4のときの凸(n+1)角形辺中囲縮面積比F(n+1)は 1/2 < F(5) ≦ (3+√5)/8 となる(F(3)=F(4)=1/2?)」とも書くことにする。
見てる方、ぜひ感想などをカキコしてくださるとありがたいです。
259+2 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/12(日) 09:24:32
ちなみに、凸5角形 2点飛縮 小5角形 と、凸5角形 辺中囲縮 小5角形 の
対応する周囲の辺は5組全て平行となるが、この2つの小5角形が相似であるとはいえないようだ。
少なくとも、この2つの小5角形の面積比が明確であるなら 凸(n+1)角形辺中囲縮面積比の答えを使えるのだが…
今後は、k点飛縮にも応用できる補助(n+1)角形をどうにか見つけようとするか、
凸5角形2点飛縮収束点を求めるために 凸5角形 外接楕円 を導出する式をちゃんと作るか、って感じー
後者は例えば、長方形の横に一点加えた凸5角形について、その外接楕円の中心と その凸5角形の重心が
ぱっと見で異なってしまうことからも、あまりいい式になるとは思いませんが…
U^m内で凸5角形の各頂点への位置ベクトルをp_i(i=0~4)とすると a x^2 + b x y + c y^2 + d x + e y + f = 0 の…
x y うわぁぁああぁあ(AA略)
260+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/12(日) 10:04:14
凸5角形は内接楕円も一意に定めることが出来るのか?
例えば、三角形と それをその重心を中心にその平面内で180度回転させた三角形をあわせた
魔方陣?のような図形が、外接楕円と内接楕円を一意に持つことからも、出来る気がするけど。
(この場合、対称性で1次元分?落ちる6点と6辺では成り立つからという意味)
外接楕円も、2次元内の5点という10変数から 楕円(というか2次曲線)の6変数
(中心点で2変数、長径短径で2変数、長軸の回転角と定数倍で2変数分)
を導出するという 供給過剰っぷりはどうか と思ってたら、全成分1のベクトル\bm{1}を用いて、
[a/f, b/f, c/f, d/f, e/f]^T = - […, [x_i^2, x_i y_i, y_i^2, x_i, y_i], …]^{-1} \bm{1} で(i=0~4)
ぴったり導出できますね。しかし、欲しいのは楕円の中心へのベクトルですから、残念。
261 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/12(日) 13:57:41
>>258 凸(n+1)角形辺中囲縮面積比F(n+1)は常に F(3)=1/4、 F(4)=1/2 でした。
>>260 円に外接する野球のホームプレート型の凸5角形に外接する楕円を考えれば、
凸5角形の内接楕円と外接楕円の中心は異なる場合があることが ぱっと見わかる。
262 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/15(水) 06:19:09
分からない問題はここに書いてね305
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1239022787/378
長さlの針金を l = l_1 + … + l_m に分け、それぞれのl_iで正n_i角形を作る時、
その全ての面積の和Sは S(m; n_1, …, n_m) = Σ_{i=1}^m (l_i^2 / (4 n_i tan(π/n_i))) と表せて、
>>254 のコーシーシュワルツの不等式で x_i = l_i / √(4 n_i tan(π/n_i)) および y_i = √(4 n_i tan(π/n_i)) と考えれば、
等号成立条件の x_i:x_j=y_i:y_j つまり l_i : l_j = n_i tan(π/n_i) : n_j tan(π/n_j) という比で針金を分けるときに
Sは最小値 min[ S(m; n_1, …, n_m) ] = l^2 / (4 Σ_{i=1}^m (n_i tan(π/n_i))) をとることが分かる。
端的に書くと、「Σ_{i=1}^m l_i = l のとき、a_i > 0 とすれば、
Σ_{i=1}^m (l_i^2 / a_i) ≧ l^2 / (Σ_{i=1}^m a_i) が成り立つ
(等号成立は l_i /a_i = l_j /a_j のとき)。」ということである。
ところで、「雑談はここに書け!【34】」スレで
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1234800000/506
で当スレが紹介されてました!あざーす!
263+4 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/19(日) 09:50:31
いやー数学板って荒れてますねーU^m内のn次元楕円体について考えたこと書きます。
まず、U^m内のU^n_{p_0} [L]で(m次元ユークリッド空間内の 始点p_0からのn次元部分空間を張る基底Lで)
m次元列ベクトルl_i(i=1…n)をi列成分に持つm×n方向行列Lを特異値分解すると L=ΘΣA^T となるとする。
(Θ=[θ_1, …, θ_n]はm次元正規直交ベクトルθ_iを列挙したm×n行列、Σは対角成分にn個の特異値σ_iを持つn次対角行列、Aはn次正規直交行列)
(ちなみに、Lは基底なのでA A^Tも単位行列Eとなり、内積行列 L^T L = AΣA^T と分散行列 L L^T = ΘΣΘ^T と固有値分解できる。)
このとき、Lの始点p_0を中心として Lのそれぞれの終点を通る n次元楕円体のm次元半径ベクトルは r_i=θ_i σ_i (i=1…nのn本)で表せる
(R=[r_1, …, r_n]=ΘΣ、および、e_{θ_i}^T e_{θ_i}=1となるn次元正規ベクトルe_{θ_i}を用いて、それぞれ l_i =R e_{θ_i} と書けるので)。
ここまでは固有値・固有ベクトルの性質として公知のものと思います。(参考→ ttp://q.hatena.ne.jp/1215959307)
264+4 :132人目の素数さん [↓] :2009/04/19(日) 11:24:34
(訂正: >>263 5行目: 内積行列 L^T L = A Σ^2 A^T と分散行列 L L^T = Θ Σ^2 Θ^T (= R R^T) と固有値分解できる。)
しかし、>>263 は U^m内で n次元単体の0点を中心として 1点…n点を通る n次元楕円体を求めるという方法である。
今回、中心は不明の状態で、n'個の点に適切なn次元楕円体をfitting(以下、当嵌と言う)したい。>>259 の方法を見れば、
n次元楕円体を当嵌するのに必要な点の数は2次超曲面の係数の数以上なければならない気がするので n'≧n(n+3)/2 とする。
一般的のように、2次超曲面の2次係数のn×n対称行列をQ、1次係数のn次元列ベクトルをq_~、定数倍の不定性を表す項をq_{~~}としたとき、
この2次超曲面上の点pを f_Q [p] = p^T Q p + p^T q_~ + q_{~~} = 0 で表したいが、これはpがn次元ベクトルのときしか使えない。
そこで、最初に U^m内のn'個の点を表すm次元列ベクトルp'_i (i=1…n') から、この点が全て入ってるn次元部分空間を求めておくといいと思った。
以下は私的な考えであるが、この全ての点を表す行列 P'=[p'_1, …, p'_n'] とすれば、この全ての点の重心 p'_G = P' 1/(n'+1) を
中心に放射線状に各点へ出るベクトルを固有値分解する感じで得られる (P'-p'_G 1^T)(P'-p'_G 1^T) = P' P'^T - (n'+1) p_G p_G^T = R' R'^T
のR'(重心中心として簡易にn次元楕円体を当嵌したn本の半径の行列)、および、p_i = R' ρ_i となるn次元座標ベクトルρ_i (i=1~n')を最初に求めておく。
そうすれば、この2次超曲面上の点pを表す座標(p'_GからR'で測った座標R'^† p_i=)ρで、
f_Q [ρ] = ρ^T Q ρ + ρ^T q_~ + q_{~~} = 0 と書けるので、次の方法でρからQ,q_~および
全ての点p_i (i=1~n')にとって適切な当嵌であるn次元楕円体の中心とn本の半径ベクトルが求まる…と思う。
265+4 :132人目の素数さん [] :2009/04/19(日) 13:52:21
(訂正: >>263 下から5行目: = P' P'^T - (n'+1) p'_G p'_G^T、下から4行目: p'_i = p'_G + R' ρ_i、
下から3行目:座標R'^† (p - p'_G)=(ただし、R'の一般化逆行列R'^†=[r_1/(r_1^T r_1), …, r_n/(r_n^T r_n)]))
U^m内で点p'_i (i=1…n')をp'_GからR'で測ったn次元座標ベクトルをρ_i = [ρ_{1i}, …, ρ_{ni}]^T (i=1…n')とし、Qのj行i列成分q_{ji} とq_~のi行成分q_{i~} に対し
\ddot{q} = ([q_{11}, q_{12}, q_{22}, …, q_{nn}, q_{1~}, …, q_{n~}]/q_{~~})^T、および、υ_i=[ρ_{1i}^2, 2 ρ_{1i} ρ_{2i}, ρ_{2i}^2, …, ρ_{ni}^2, ρ_{1i}, …, ρ_{ni}]、
υ_iをi行成分に持つn'×(n(n+3)/2)行列をΥとすれば、f_Q [ρ] = ρ_i^T Q ρ_i + 2 ρ_i^T q_~ + q_{~~} = (υ_i \ddot{q} + 1)q_{~~} = 0より、Υ \ddot{q} = -1 となり、
【Υ^T Υが正則の時】 \ddot{q} = - (Υ^T Υ)^{-1} Υ^T 1 と n次元楕円体が通る点の座標の成分の行列Υから n次元楕円体を表す係数\ddot{q}が求まる。
また、このn次元楕円体の中心を表す座標をρ_Q、n次元楕円体のこの座標における半径ベクトルr_i (i=1…n)を列挙したn×n直交行列をRとすれば、
n次元正規ベクトルe_{θ_i}を用いて、(ρ_i - ρ_Q) = R e_{θ_i} と表せることから、ρ_i^T (R R^T)^{-1} ρ_i - 2 ρ_i^T (R R^T)^{-1} ρ_Q + q_{~~} = 0
【q_{~~} = ρ_Q^T (R R^T)^{-1} ρ_Q - 1とした】。ここで求まった係数\ddot{q}を Q/q_{~~}と q_~/q_{~~}=[O E] \ddot{q}の各成分に代入しなおし比べる。
上記をふまえて、Qを固有値分解すれば Q=ΘΣ[λ]Θ^T=(R R^T)^{-1} (Σ[λ]は対角成分がベクトルλの成分となる対角行列)となることから、
n次元楕円体の座標の半径行列は R = ΘΣ^{-1/2}[λ] と求まり、n次元楕円体の座標の中心は ρ_Q = R R^T [O E] (Υ^T Υ)^{-1} Υ^T 1 と求まる。
「このことから、U^m内で 【凸複体を作る】 n'個の点 P'=[p'_1, …, p'_n'] に対して 適切に当嵌できるn次元楕円体は、
中心が p'_G + R' R R^T [O E] (Υ^T Υ)^{-1} Υ^T 1 であり、半径行列が R' R = R' ΘΣ^{-1/2}[λ] である。」と考えられる。
(n'≧n(n+3)/2 だが、特にn'=n(n+3)/2 のとき、上式で与えられるn次元楕円体は 全てのn'個の点を通る。)
266+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/19(日) 14:00:26
>>263-265 は「点列へのn元2次超曲面の当嵌」について一般解を目指した導出のアルゴリズムです。あまり綺麗な式にならなかった。
凸複体を作る n'=n(n+3)/2 点に当嵌するとき、Υが正則になるなら、この式でその凸複体への外接楕円体が作れると思います。
内接楕円体については、複体では出せる気がしないので、n次元単体の重心を中心とする辺接楕円体(前述したっけ?)をのみ考えたいです。
267+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/19(日) 17:54:07
なんかもったいなかったので「球・球面の性質を1000個あげるスレ」を保守しました。みなさんもよろしく、とか言ってみたり
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1108524401/
あと、>>266 ではアンカーを>>264-265として、>>265-266では n次元凸複体とかn次元外接楕円体とか言うべきだと思いました。
ところで、(n+1)個のi点(i=0…n)で作られる n次元単体の重心p_Gを中心とする n次元辺接楕円体は、
>>264 をふまえて、>>265 から ρ_Q = R'^† (p_G - p_G) = 0であるので f_Q [ρ] = ρ^T (R R^T)^{-1} ρ - 1 = 0 として、
n次元単体のj点とi点を結ぶ線分上での辺接楕円体との接点を p_{d_ji} = p_j t + p_i (1-t) とすれば、
このp_{d_ji}の座標ρ→ρ_{d_ji} = R'^† (p_{d_ji} - p_G)で d[f_Q]=2 d^T[ρ] (R R^T)^{-1} ρ→0 となることから、
R'^‡=(R'^†)^T、M=R'^‡ (R R^T)^{-1} R'^†として、上式よりtを消去すれば、
接点は p_{d_ji} = (p_j (p_G - p_i)^T - p_i (p_j - p_G)^T) M (p_j - p_i) / ((p_j - p_i)^T M (p_j - p_i)) と書ける。
この接点の全てがn次元辺接楕円体上にあることから、ρ_{d_ji}^T (R R^T)^{-1} ρ_{d_ji} = 1 の全てを用いて R を求めればよい…
…うーん…重い…簡易に固有値分解で出せる R' と、真のn次元重中辺接楕円体の半径 R' R の違いは、大変興味があるのですが…
268+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/21(火) 02:58:40
(訂正: >>267 下から3行目: 接点は p_{d_ji} = (p_j (p_G - p_i)^T + p_i (p_j - p_G)^T) M …)
ここで、Δ_{G_ij} = p_j (p_G - p_i)^T + p_i (p_j - p_G)^T + p_G (p_i - p_j)^T とすれば、このm×m行列Δ_{G_ij}は、
掛けることによって p_G, p_i, p_j によって作られる三角形の法線方向への外積のようなものが出る行列だと思う。
例えば、√|(p_G - p_i)^T Δ_{G_ij} (p_j - p_G)|/2 がその三角形の面積になると昔計算したような気がする。
上記より、(p_j - p_i)^T M Δ_{G_ij}^T M Δ_{G_ij} M (p_j - p_i) = (p_j - p_i)^T M (p_j - p_i) (p_j - p_i)^T M (p_j - p_i)
から、n次元単体の各頂点P=[p_0, …, p_n]と その重心p_G=P 1/(n+1)で作る 分散行列を固有値分解して得られる
P P^T - (n+1) p_G p_G^T = R' R'^T の式を用いて、M=(R' R)^‡ (R' R)^† より n×n【直交】行列 R が求まる…
…んだがどうすりゃいいんだ…ぱっと見、Δ_{G_ij}^T M Δ_{G_ij} = (p_j - p_i) (p_j - p_i)^T と見えるのだが…
Rが対角行列となれば、n次元重中辺接楕円体のn本の半径ベクトルの方向が P P^T - (n+1) p_G p_G^Tの
固有ベクトルの方向と一致すると言えて、幸せになれるのだが、式の数はn(n+1)/2で直交Rにはピッタリっぽいし…
269+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/21(火) 21:53:58
>>268 で式の形からは、U^m内でn次元単体の重心p_Gからその各ij辺の垂線x_{G_ij}をn(n+1)/2本分列挙したm×(n(n+1)/2)行列
X = [x_{G_01}, x_{G_02}, …, x_{G_(n-1)n}] の分散行列を固有値分解することによって X X^T = (R' R) (R' R)^T となるm×n直交行列
(重中辺接楕円体の半径行列)R' Rが求まり、その「n次元単体の重中辺接楕円体」(と仮に呼ぶ)が出せると予想します。
しかし、計算の方は全然できないので保留します。数値計算ソフトでいろんな分散行列を固有値分解して図示して確かめたいなぁー
話は変わりますが、「数学の本 第33巻」スレの401さん情報
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1236443234/401
401 名前:132人目の素数さん[sage] 投稿日:2009/04/18(土) 21:27:12
google book って数学書がほとんどのページ見られたりするけど大丈夫なのかこれ。
とのことで、ありがとうございます!やったー!このときを待っていた!
>>20 さんのは日本の本だからか見つけられませんでしたが、原著と同じ人の本で似てる本↓
http://books.google.co.jp/books?id=aE_-qdthsWcC&pg=PP1&dq=Ronald+L.+Graham+discrete+Mathematics&lr=&as_brr=3
>>34 さんのは http://books.google.co.jp/books?id=iWvXsVInpgMC&printsec=frontcover&dq=Coxeter+Regular+Polytopes&as_brr=3
>>35 さんのは http://books.google.co.jp/books?id=upYwZ6cQumoC&printsec=frontcover&dq=Sphere+packings&as_brr=3
で発見できました!代数幾何学とか日本語の本もたくさんあった。Googleまじ神!!!
270 :132人目の素数さん [] :2009/04/21(火) 23:51:21
あと、猫先生(?)関係のスレでarXivという論文投稿サーバ(?)というのを知りました。
URI→http://arxiv.org/archive/math
このサイトの分類だと当スレの分野はEuclidianのある math.MG - Metric Geometry かな?
代数幾何学や位相幾何学は難しいので、わかりやすい解析幾何学を生涯かけてやりたいです。
271+1 :132人目の素数さん [] :2009/04/26(日) 03:43:29
>>269 上の計算じゃ合いません。考えた結果、U^m内でn'個の点列\P=[\p_1…\p_n']があり、その点列の重心\p_G
を中心として 半径を表す直交行列\R=[\r_1…\r_n]で作られるn次元楕円体上にその点列が全てある特別な場合は、
「(\P \P^T - \p_G \p_G^T) (2/n') = \R \R^T」と書けて、重心から点列への行列\P-\p_G \1^Tの各特異値の√(2/n')倍が
そのn'個の点列を通るn次元楕円体の各半径の長さになると言えると思いました。
n'個の点列\Pが楕円体上でなくn次元正規分布に従う時、\Pの重心から点列への\P-\p_G \1^Tの特異値の√(1/n')倍が
その正規分布の標準偏差であるとも考えました。これより、正規分布に従う点列で作る分散行列\P \P^T - \p_G \p_G^Tと
その標準偏差の1/√2倍の半径の楕円体上にある同じ数の点列(その重心は楕円体の中心)で作る分散行列は一致する
と言えると思ってます。これらはもう少し考えたいので、これらを「楕円体当嵌の問題」と呼び、後でまとめたいと思います。
272+3 :132人目の素数さん [] :2009/04/29(水) 16:50:32
(訂正: >>271 とかいろいろ:U^m内でn'個の点列\P=[\p_0…\p_n']に最小自乗当嵌される、中心\p_G=(\P \1)/(n'+1)で
半径\R=[\r_1…\r_n]のn次元楕円体は (\P \P^T - (n'+1) \p_G \p_G^T)(n/(n'+1)) = \R \R^T を満たす。という予想)
>>264-265 より点列\p_i (i=0…n')にn次元楕円体を当嵌したい場合は、\p_i = \p_G + \R \ρ_i (\ρ_i =[ρ_{1i}…ρ_{ni}])
とすれば、一次独立なυ_i=[ρ_{1i}^2, 2 ρ_{1i} ρ_{2i}, …, ρ_{ni}^2, ρ_{1i}, …, ρ_{ni}]が係数分n(n+3)/2個必要なため
(このとき\p_i (i=0…n')はn次元を張る二次独立な基底で作られると言う)、最低でも n'≧n(n+1)/2 の点列が必要である。
このn次元二次超曲面(楕円体)を当嵌できる点列を、仮に「n次元二次位底以上の(n'+1)点」(n'≧n(n+1)/2)と呼ぶ。
(ちなみに、n次元部分空間(超平面)を定めれるような点列を、仮に「n次元一次位底以上の(n'+1)点」(n'≧n)と呼ぶ。)
また、「標準偏差σの正規分布と、値±σを同確率でとる二値分布は、同じサンプル数なら分散(標準偏差)が等しい」
と統計学関連から言えると思い、多変量解析に応用すれば「標準偏差σ_i (i=1…n)のn次元正規分布と、半径σ_iの
楕円体上の点(と中心をはさんでその反対側の点)を同確率でとる分布は、同じサンプル数なら分散行列が等しい」
と言えると思いました。
ところで、中心を\p_Qと固定してn次元一次位底以上の(n'+1)点にn次元楕円体を当嵌する場合、この(n'+1)点\P_+に
対して中心\p_Qをはさんでその反対側にある(n'+1)点\P_- = 2 \p_Q \1^T - \P_+も一緒に2(n'+1)点\P=[\P_+, \P_-]
と考えれば、中心\p_Q=\P \1/(2(n'+1))=\p_Gと考えれば、本来 分散行列(\P_+ - \p_Q \1^T) (\P_+ - \p_Q \1^T)^T
で計算するところを、前述の分散行列 (\P_+ \P_+^T - (n'+1) \p_Q \p_Q^T)(n/(n'+1)) = \R \R^T の式に帰着できる。
これは、>>271 では中心は重心だけとしていたが、別に任意の中心\p_Qと固定しても上式で一次位底以上の(n'+1)点にn次元楕円体を当嵌できることを示している。
273+2 :132人目の素数さん [] :2009/05/07(木) 01:42:05
(訂正: >>272 上から1行目: U^m内で(n'+1)個の点列\P=[\p_0…\p_n'])
ところで、「m次元ユークリッド空間内における n次元二次超曲面 f_Q[\p]=\p^T \Q \p + 2 \p^T \q_~ + q_{~~}=0の
概形と、点\p'での接線\d'と、点\p'で接線\d'での曲率半径r'_Qなどを、例によって行列で計算しました。
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/61.html
http://www7.atwiki.jp/neetubot/?plugin=ref&page=%E5%8D%98%E4%BD%93%E5%BF%9C%E7%94%A8%2F%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%B6%85%E6%9B%B2%E9%9D%A2&file=fq.JPG
これより、特にU^m内において、中心\p_Qと直交半径行列\R_Qで作られるn次元楕円体上の点を\p'=\p_Q + \R_Q \e_θ
(\e_θ^T \e_θ=1)で表せば、その点\p'上での接線\d'は\e_θ^T \e'_θ=0および\e'_θ^T \e'_θ=1となる\e'_θを用いて
\d'=\R_Q \e'_θと書けて、その点\p'上で接線\d'の方向に対する曲率半径\r'_Qは下記のように書けることが言える。
\r'_Q = - \R_Q (\R_Q^T \R_Q)^{-1} \e_θ (\e'_θ^T \R_Q^T \R_Q \e'_θ)。」と考えました。どこかで見たかも、微分幾何学か?
274+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/07(木) 02:03:24
>>273 「二次曲面 - Wikipedia:」↓では楕円体の体積の式も載ってました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%9B%B2%E9%9D%A2
でも、↑ではm=n(かm=n-1)で固定してる気がする。 おやすみ。
275 :132人目の素数さん [] :2009/05/15(金) 02:56:04
今日のコマ大の問題は、http://tv.dee.cc/jlab-maru/s/maru1242318622236.jpgで、
三角形ABCの外接円上の点PからAB・ACにおろした垂足M・N間の長さが最大になるのは、
APが外接円の中心を通るときで、そのときM・NはB・Cに一致するという話が出てました。
これを、始点を固定したn本の基底\L=[\l_1…\l_n]の始点と終点で囲まれるn次元単体に拡張すれば、
その外接超球上の点から\l_iにおろした垂足が作る(n-1)次元単体の超体積が最大となる点\l_xは、
始点から外接超球の中心へのベクトル\l_Oの2倍の点\l_x=\L (\L^T \L)^{-1} Σ[\L^T \L]と言えそう。
この点を仮に外心対称0点と呼び、n次元単体の外心対称を外心対称単体などとでも仮に呼びます。
すると、n次元単体の重中外接楕円体はその重心対称単体の重中外接楕円体と一致するとか言えます。
一般次元では超楕円体と呼ぶのが普通なら、それは長すぎて嫌で、むしろn次元超楕球とか呼びたい気…
ちなみに、n次元単体の外接超球上の点からそのi対面(i=1…n)におろした垂足が作る(n-1)次元単体の
超体積が最大となる点と考えても、外心対称0点しかありえない気がして、そのときこの垂足(n-1)次元単体
が上記の\l_iへの垂足が作る(n-1)次元単体と超体積が同じになっちゃったりするのか、…おやすみ…
276 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/15(金) 03:09:52
今、n次元単体の外接超球上の点から、i対面への垂足(n-1)次元単体の超体積の最大値の方が、
\l_iへの垂足(n-1)次元単体の超体積の最大値(このとき0対面となる)より小さい気がしました。
ちなみに、>>274の最後の行は、m=n(かm=n+1)と言うべきでした。
277 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/15(金) 18:23:04
『楕円』関係のスレ
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1220920513/14
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1220920513/22
で、二次超曲面とある点との距離(の最小値)について質問みたいのがあって、
n次元楕円体とある点の距離なら>>273とか使って、空間ごとn次元超球と
ある点との距離に帰着すればいいと思ったけど、なんか計算うまくいかん…
278 :132人目の素数さん [↓] :2009/05/15(金) 18:47:40
垂足三角形の内心が垂心となるのは、元が鋭角三角形のときだけらしく、
あるn次元単体の垂足単体の内心の点(名前知らない)が垂心となるためには、
けっこう複雑な条件がある気もしました…直角以上があると一致すらしないし…
279 :neetubot [] :2009/05/15(金) 19:20:05
雑談はここに書け!【34】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1234800000/741
でおもろないって言われてたし、ネタも尽きたので、
これからコテつけて質問とかに答えるスレにしたいぉ!
なんか言ってみそ
280+1 :neetubot [↓] :2009/05/26(火) 08:34:48
http://blog.livedoor.jp/melbo2_oko3re/
で3次元以下の単体の五心はうまくまとめられてる気がした。
http://blog.livedoor.jp/melbo2_oko3re/archives/488155.html
で『「位相幾何学」のホモロジー群の計算にでてくる「単体の重心座標」』という言葉がありビックリ!
重心座標はここでいうところの、n次元単体の位置行列\Pと同じ空間にある点\p_a=\P \~aの\~aの部分で、
点\p_aによって単体\Pが(n+1)個の単体に分かれるときの体積の2乗の比を表すので単体座標\~aとか>>242で呼んでた気がした。
あと、上で三線座標・四線座標(ある点に対するi対面からの距離比)と呼ばれてるものはここでは、
単体座標\~aをn次元単体の各i対面の超表面積の2乗で割った\~x(つまり、\P \~a=\P \Σ[\~C[\P^T \P]] \~x)を用いれば、
この\~xはまさしく点\p_aに対するn次元単体のi対面からの距離の2乗の比となり、ここでは分面座標と呼んだ気がした。
また、三角形の各頂点からの距離の比を座標にしたものは、三角座標?trianglar functionだっけ?とか呼ばれてるようで、
これはn次元単体に拡張してもこの座標を指定しても満たす点が内分点と外分点のように2点あるのであまり流行ってないっぽく、
しかし、n次元単体の各i頂点からある点\p_aの距離の比をt_iとして、i=0…nのt_i^2をi行成分に持つ\tとすれば、
そのn単体の外心\p_Oから\p_aへのベクトルの方向が\P \~C[\P^T \P] \t (=α(\p_a-\p_O))となると思い、
ここでは分点座標と呼ぼうと思ってた気がした。参考→http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/21.html
ベクトルで出すより、ベクトルから座標出すほうが需要があるのか…誰か興味あるなら本気出します(笑)
281+1 :neetubot [] :2009/05/26(火) 09:09:55
\Pが一本分一次従属のとき(\P \~a' = \0)があるのを考えてなかった。
たぶんこのとき\~a'=\C[\P^T \P] \1と書けるけど、いや関係ないか…
あと、\undersetや\oversetを{↓(⊖ \l_i)\L}や{↑[m×m]\E}と書こうと思った。
282+2 :132人目の素数さん [] :2009/05/28(木) 00:31:24
(【訂正】 >>272の上から6行目: 体積の2乗の比→体積の比、上から8行目:
各i対面の超表面積で割った\~x(つまり、\P \~a=\P \Σ^{1/2}[\~C[\P^T \P]] \~x)、
上から9行目:i対面からの距離の比となり、ここでは分面座標)
上をふまえて、n次元単体の位置行列\Pである点\p_aを表すときの座標として、単体座標\~a,(\p_a=\P \~a)、
点\p_aとn次元単体のi対面で作られるi分積の値を用いる分積座標\~v^{n-1},(\p_a=(\P \~v^{n-1})/(v^n))、
点\p_aとn次元単体のi対面からの距離の値を用いる分面座標\~j,(\p_a=(\P \Σ^{1/2}[\~C[\P^T \P]] \~j)/(v^n))、
点\p_aとn次元単体のi点からの距離の値を用いる分点座標\~t,(\p_a-\p_O=r_a (\P \~C[\P^T \P] (\~t)^2/2))
(ただし、分点座標によって定まるある点\p_aは普通は内分点心と外分点心の2点存在する)などと書く。
ちなみに、成分を総和して1になるベクトルを比ベクトル、成分を自乗和して1になるベクトルを正規ベクトル\^{}
とか言ったりし、単体座標は分積座標比ベクトルとか、外心からの正規分点向外線\^x_T上に、とか言ったりします。
あと、n次元単体において分面座標が全て等しい点を内心、1個だけ負で等しい点を傍心と呼び、
内心・傍心を含む分面座標の絶対値が等しい2^n個ある点を広義傍心と呼ぶことにした。
283 :neetubot [↓] :2009/05/28(木) 20:29:44
この分野の先人は、>>280 の上のリンクやある御仁のメールから、一松信さんっぽい雰囲気を感じました!
284 :neetubot [↓] :2009/05/29(金) 14:42:01
2次元単体→n次元単体
重心座標(barycentric coordinates)→分積座標
三線座標(triliner coordinates)→分面座標
三点座標(tripolar coordinates)→分点座標
と呼びたいけど、http://blog.livedoor.jp/melbo2_oko3re/では四面体で四線座標って言ってる、
3次元単体なら四点で六線で四面なのに、…あぁ垂線は四線ですもんね。やっぱ分面座標っしょ
285 :neetubot [] :2009/05/30(土) 06:06:58
2ちゃんねる10周年おめでとうございます!
この「【行列で】m次元ユークリッド幾何学【n単体の5心】」スレ
を始めてからちょうど1年たちまして、皆様ありがとうございました。
とりあえず、このスレで解いたりした問題の項目だけPDFにしておきました。
今後は、neetubot名義で小出しにPDFを書き溜めながら1つにまとめることも考えたいです。
【PDF形式】132人目の素数さん『m次元ユークリッド空間内でのn次元単体の五心などの導出』【0.1】
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pub/neetubot-0.1.pdf
286+3 :132人目の素数さん [] :2009/05/30(土) 06:59:33
それでは一年の集大成として、最近思いついた今までで一番美しい公式の予想を紹介して、終わりたいと思います。
↓
m次元ユークリッド空間内で、原点から各(n+1)点(m≧n≧2)への列ベクトル\p_iを
(i=0…n)列挙したm×(n+1)の位置行列\P=[\p_0…\p_n]でn次元単体A^nが作られる場合、
A^nの重心を\p_G=\P \1/(n+1)としたとき、A^nの頂点のうち(k+1)点(0≦k≦n-1)で
作られるk次元面の{_(n+1) C_(k+1)}通り全てに接する\p_Gを中心とするn次元超楕円体
(n次元単体の重中k次元面接超楕円体)の直交半径行列\R_Qは、次式のような
固有値分解する式で解けると予想する。
(n-k)/((n+1)(k+1)) (\P \P^T-(n+1)\p_G \p_G^T) = (n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P^T) = \R_Q \R_Q^T
↑
定数倍の補正項はn次元正単体のk次元面接超球の半径を参考にし、>>272にあてはめたら
思いつきました。(参考→http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/26.html)
これは成り立たなくても、近似解などに使えると思いました。
それでは1年間、関係者各位、本当にありがとうございました。
287 :132人目の素数さん [] :2009/06/01(月) 14:45:41
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□□
□■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□□
□□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□
□□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□
□□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□□
□□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□
288+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/06/02(火) 07:21:57
>>286で出る楕円体はk次元面接ではなくn次元単体の全てのk次元面単体の重心\p'_jを通るものでした。
それなら、Σ_{j=0}^{_(n+1) C_(k+1) - 1} (\p'_j -\p_G) (\p'_j -\p_G)^T = … = n(k+1)/(n-k) (\P \P^T-(n+1)\p_G \p_G^T)
で証明できそうです。これを、n次元単体の重中k次元重通超楕円体に改名し面接の方の近似となるとか言いたいです。
289+5 :132人目の素数さん [] :2009/06/03(水) 21:38:03
m次元ユークリッド空間内で、\p_Qを中心として 位置ベクトル\p'_i (i=1…n')で表されるn'個の点を通るn次元超楕円体が
一意に定められる場合、その超楕円体の互いに直交するn本の半径ベクトルを列挙した\R_Q=[\r_{1Q}…\r_{nQ}]
について、「(n/n') Σ_{i=1…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = \R_Q \R_Q^T」という公式が成り立つ証明↓
(証明)n'=nのとき、\l_i=\p'_i - \p_Qとすれば、題意のn次元超楕円体が定められる場合は、\l_iが互いに一次独立
である必要がある。これをふまえると、\L=[\l_1…\l_n]を特異値分解により\L=\Θ \Σ \A = \R_Q \Aと分解したとき、
\Aはn×n正規直交行列(\A^T \A = \A \A^T = \E)で書ける。これより、Σ_{i=1…n} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T =
Σ_{i=1…n} \l_i \l_i^T = \L \L^T = \R_Q \A \A^T \R_Q^T = \R_Q \R_Q^Tとなるので、与式が成り立つ。
また、n'で題意を満たす「(n/n') Σ_{i=1…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = \R_Q \R_Q^T」が成り立つと仮定してn'+1のとき、
(n/(n'+1)) Σ_{i=0…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = n/(n' (n'+1)) (n' Σ_{i=0…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T)
= n/(n' (n'+1)) Σ_{j=0…n'} (Σ_{i=0…n', j≠i} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T) = n/(n' (n'+1)) Σ_{j=0…n'} (n'/n \R_Q \R_Q^T)
= \R_Q \R_Q^Tとなるため、与式が成り立つ。よって、この数学的帰納法によりn'≧nで、中心\p_Qから n'個の\p_iのうちから
選んだn点へのベクトルが互いに一次独立という性質が _n' C_n通りの\p_iの全ての選び方で成り立つときに限り、
中心を\p_Qとして n'個の\p_iを通る n次元超楕円体が一意に上記の公式から求められる ということがわかる。■
…中心を指定してn'点を通るn次元超楕円体を導出するとき、中心からn点へのベクトルが一次従属なのを含むとダメなのか?
中心からn'点へのベクトルがn次元部分空間を張っている時は、この公式で中心を指定したn'点への楕円当嵌としたいけど…
\p'_i - \p_Q = \R_Q \θ'_i とすれば、与式から(n/n') Σ_{i=1…n'} \θ'_i \θ'_i^T = \Eというおかしな式になるので、上の証明もどこか違う気が…
290+2 :132人目の素数さん [] :2009/06/04(木) 07:42:13
>>286>>288は少し間違ってました。>>289を前提とすれば、下記のように証明できたので、書き換えます。
↓
m次元ユークリッド空間内で、原点から各(n+1)点(m≧n≧2)への列ベクトル\p_iを
(i=0…n)列挙したm×(n+1)の位置行列\P=[\p_0…\p_n]でn次元単体A^nが作られる場合、
A^nの重心を\p_G=\P \1/(n+1)としたとき、A^nの頂点のうち(k+1)点(0≦k≦n-1)で
作られるk次元単体の重心\p'_jの{_(n+1) C_(k+1)}=n'通り全てを通り \p_Gを中心とする
n次元超楕円体(n次元単体の重中k次元重通超楕円体)の直交半径行列\R_{G_k}は、
「(n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P^T) = \R_{G_k} \R_{G_k}^T」という公式で導出できる。
(証明)>>289の公式から式変形していけば、\R_{G_k} \R_{G_k}^T = (n/n') Σ_{j=1…n'} (\p'_j - \p_G) (\p'_j - \p_G)^T
= (n/n') ( (Σ_{j=1…n'} \p'_j \p'_j^T) - 2 ((_n C_k)(n+1)/(k+1) \p_G) \p_G^T + (_(n+1) C_(k+1)) \p_G \p_G^T )
= (n/n') ( ((_n C_k)-(_(n-1) C_(k-1)))/(k+1)^2 \P \P^T + (_(n-1) C_(k-1))(n+1)^2/(k+1)^2 \p_G \p_G^T - (_(n+1) C_(k+1)) \p_G \p_G^T )
= (n/n') ( (_n C_k)(n-k)/(n (k+1)^2) \P \P^T - (_(n+1) C_(k+1))(n-k)/(n (k+1)) \p_G \p_G^T )
= (n-k)/((n+1)(k+1)) (\P \P^T-(n+1)\p_G \p_G^T) = (n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P^T)と書ける。■
↑
この公式で、m×(n+1)の位置行列\Pで表されるn次元単体の重中k次元重通超楕円体の直交半径行列\R_{G_k}が求まります。
この重中k次元重通超楕円体が通るn次元単体内のk次元面単体の重心でちょうど全てのk次元面と接する(条件のあうi,jにおいて
(\p'_j - \p_G)^T (\p'_j - \p_i) = 0)、つまり、重中k次元重通超楕円体=重中k次元面接超楕円体となりそうなので、今感動してます。
291+1 :neetubot [↓] :2009/06/04(木) 08:08:33
>>290で一番下の感動したところが間違ってました。
正しくは、条件のあうi,jにおいて、\p'_j - \p_G = \R_Q \θ'_j としたとき、 \p'_j - \p_i = \R_Q \θ_i α
(ただし、\θ'_j^T \θ_i = 0)となれば、その超楕円体とn次元単体内のk次元面単体が接するので、
\Xの擬似逆行列を\X^†と書けば、(\p'_j - \p_G)^T (\R_Q \R_Q^T)^† (\p'_j - \p_i) = 0 となることが
重通と面接が一致する条件でした。式の形的には成り立ちそうだけど、今一度のブレイクスルーが必要です…
292+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/06/07(日) 10:45:32
>>291が下記のように解けました。\p'_j - \p_G = \P \~a, \p'_j - \p_i = \P \~bとすれば、\~1^T \~a=0, \~1^T \~b=0, \~a^T \~b=0
であることを使います。ちなみに、成分が全て1のn次元ベクトルを\1、それの(n+1)次元ベクトルを\~1のように分けて書きます。
なお、n×n単位行列\E、(n+1)×(n+1)単位行列\~E、\Xの擬似逆行列を\X^†、\X^†の転置行列\X^‡などが登場します。
(証明) (\p'_j - \p_G)^T (\R_{G_k} \R_{G_k}^T)^† (\p'_j - \p_i)
= (n-k)/((n+1)(k+1)) \~a^T \P^T (\P (\~E - (\~1 \~1^T)/(\~1^T \~1)) \P^T)^† \P \~b
= α \~a^T ([\0, \L] - \p_0 \~1^T)^T (\L (\E - (\1 \1^T)/(\~1^T \~1)) \L)^† [\0, \L] \~b
= α (\~a^T [\0, \E]^T \L^T \L^‡ (\E - (\1 \1^T)/(\~1^T \~1))^{-1} \L^† \L [\0, \E] \~b + 0)
= α (\~a^T [\0, \E]^T (\E + (\1 \1^T)) [\0, \E] \~b + \~a^T (\~1 \~e_0^T + \~e_0 \~1^T - \~1 \~1) \~b)
= α \~a^T \~E \~b = (n-k)/((n+1)(k+1)) \~a^T \~b = 0 ■
>>289>>290>>292より、「m次元ユークリッド空間(m≧n≧2)においてn次元単体A^nがm×(n+1)行列\Pで位置表記される場合、
A^nの重心を中心とし A^nの頂点のうち(k+1)点(0≦k≦n-1)で作られるk次元単体の{_(n+1) C_(k+1)}通り全てに接する
重中k次元面接超楕円体の直交半径行列\R_{G_k}は、(n-k)/((n+1)(k+1)) (\P (\~E - (\~1 \~1^T)/(\~1^T \~1)) \P^T) = \R_{G_k} \R_{G_k}^T
という公式で導出できる。ちなみに、n次元単体の重中k次元面接超楕円体とそれぞれのk次元単体の接点は、対象のk次元単体の重心となる。」
が言える。>>289の一番下の部分がまだ腑に落ちてませんが、>>286であってるし接点まで重心できれいに出ると確信を持ちました。
293 :neetubot [] :2009/06/07(日) 14:08:16
□□□□匿名で公知にしておきたい部分は上までで一応終了です。□□□□
この一年では、m次元ユークリッド空間内のn次元単体の五心(重心・垂心・内心・傍心・外心)を導出する公式を
方向表記・位置表記(・辺乗表記)で解き、広義傍心が2^n個で、角心(フェルマトリチェリ点)は4次方程式に帰着でき、
分面心・分点心や単体による座標も出し、シムソン面・k次元面心・●心○足単体・対面●心単体・○心対称単体は失敗し、
トレミーを拡張し複体外接超球の定理を導き、広義垂心・非斉次行列多項方程式・形縮面積比・形縮収束点について言及し、
最後のほうで、n次元単体とn次元超楕円体の関係について解いてたら、n次元単体の重中k次元面接超楕円体を導出できた、
という感じです。あと、今気になってる問題は↓の2つですが、今ログ読み返したら他にもいろいろありそうでした。
・n次元正単体のk次元面単体の重心{_(n+1) C_(k+1)}通り全てで作られる図形はn次元正複体(正多胞体)と呼べるか
・m次元ユークリッド空間内の2次制約がn元の二次超曲面(全体では(m-1)次元あった)の同相という概念による分類
とりあえず今年はだらだらまとめてどこかに投稿とかしたいです。お手伝いできることやご意見ご感想など何でもこのスレや
>>1の@ウィキhttp://www7.atwiki.jp/neetubot/のフォームやメール(要JavaScript)とかでおっしゃってくださるとありがたいです。
294 :neetubot [↓] :2009/06/07(日) 16:14:22
危険な場所に誤爆しちゃったテヘッ。>>292は、位置行列\Pで表される任意のn次元単体について、
その重心から直交半径行列\R_{G_k}^†=\R_{G_k} (\R_{G_k}^T \R_{G_k})^{-1}で逆に拡縮変換すると、
n次元単位超球にk次元面が全て接するn次元正(?)単体に変換できるということを表していると思う。
つまり、n次元単体の重心から重中k次元面接超楕円体の接点(k次元面重心)への{_(n+1) C_(k+1)}=n'通りの
ベクトルを\R_Q \θ'_j (\θ'_j^T \θ'_j = 1)と書けば(j=1…n')、n次元正単体のk次元面がn次元単位超球に
接する時の中心からその接点へのベクトルが\θ'_j で表せて、(n/n') Σ_{j=1…n'} \θ'_j \θ'_j^T = \Eとなると思う。
>>289の疑問は(n/(n'+1)) Σ_{i=0…n'} \θ'_i \θ'_i^T = \Eから\θ'_0 \θ'_0^T = (1/n) \Eとなるのがおかしいと思ったが、
>>289の上のほうの再帰的に計算するほうで計算するならうまくいきそうです。なんぞこれ…
295 :neetubot [↓] :2009/06/17(水) 21:36:44
遅自己レスでスマソですが、>>289はあっさり成り立つようなもんじゃない気がしてきたので、
重心中心の制約か、はたまた点の分布に等方性まで課さないとダメなのかって感じです今。
あと、n単体の各頂点からの距離の比がある一定値である分点心関係の応用ですが、
各頂点のi点の場所に質量がm_iの質点がそれぞれあるとき、その質量中心の場所を
考えると、その点への各i点からの距離の比がt_i=1-(m_i / (Σ_{i=0…n} m_i))となる感じです今。
296 :neetubot [↓] :2009/06/17(水) 22:28:43
また、n単体の各頂点のi点\p_iの場所にある質量がm_iの質点から受ける万有引力が
等しいもとい つりあう場所\p_Mを考えたい。万有引力定数Gとして、\p_Mにある質量Mの
質点が\p_iの質点から受ける万有引力ベクトルは G M m_i (\p_M - \p_i) / ((\p_M - \p_i)^T (\p_M - \p_i))^(3/2)
などと書ける。(←今ここまで)そこで、上のレスの方を体重中心、こっちを体重衡心とか呼ぼうかとか…
あと、三角形ABCの場合には、等力点という仰々しい名前のついた点(各点A・B・Cの対辺をa・b・cと
すれば、各点A・B・Cからの距離の比が 1/a : 1/b : 1/c となる内分点(?))という点があるらしいですが、
これをn次元単体に普通に拡張すれば、各i対面の(n-1)次元超体積をv_i^(n-1)としたときの
各i点からの距離の比が1/v_0^(n-1) : 1/v_1^(n-1) : … : 1/v_n^(n-1)となる内分点心にあたると考えてます。
ここら辺は、http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/21.htmlにテキトウに書いてある 分点心の位置表記
をちゃんともう一回解いて定式化しとかなきゃ怪しいので、めんどくさいって感じです。あと、n次元単体の
角心(フェルマ・トリチェリ点)の四次方程式について、\l_j^T (\l_j - \l_i)の値とか加味したり
3次元単体以上とか前提に連立方程式化すれば三次や二次方程式まで落とせる気がしてますが、こちらも…
というように、拡張がいろいろできて、ユークリッド幾何学前提なので式は綺麗になるはずなので、
線型代数が得意な人とか、是非いっしょに超立体解析幾何学(高次元計量幾何学)?やりませんか?
297 :neetubot [↓] :2009/06/23(火) 21:00:52
これからは、行列計算ネタとかWikipediaで英語→日本語の訳とかやって英語覚えながら、
arXivに英語論文みたいなの投稿すること考えてて、私的には下記のような対訳を考えてます。
これらのcategory : 多変量解析幾何学 ⇔ Euclidian Metric Geometry
U^m : m次元ユークリッド空間 ⇔ m-Euclidian Space
A^n (\p_G) : n次元単体(重心位置) ⇔ n-Simplex (Centroid Position)
~S^n (~S'^n) : n次元超球体(超楕円体) ⇔ n-Hyperball (Hyperellipsoid)
S^(n-1) (S'^(n-1)) : (n-1)次元超球面(超楕円面) ⇔ (n-1)-Hypersphere (Hyperellipse)
Q_~^(n-1) : (m-1)次元(n-1)元二次超曲面 ⇔ Quadric Hypersurface
ところで、「専門家に論文を見て貰う方法」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3247881.htmlを見て、
これらは大学院か精神病院でやった方が良かったのかと思いましたが、内容的には単体の五心などを
導出する公式を見かけないので作ったよ的な簡単な行列計算の話ですし、俺のような数学科でもない崩れが
金かけずにネタをみんなで共有するためには、2ちゃんのネタとして公知にするのが一番面白いと思ったんだけど…
あとは怪しいか難しいネタしか残ってないので、時間かかるしホントに日記っぽくなりそうなので、ホントに誰か発言していただけるとありがたいです
298+1 :132人目の素数さん [] :2009/06/23(火) 21:19:15
あたまがおかしいと思います
299 :neetubot [↓] :2009/06/23(火) 21:51:47
>>298 自演乙
300 :neetubot [] :2009/07/04(土) 09:35:03
自分で300ゲトTT。最近は英語見すぎて嫌になってきました。ところで、この分野って Geometric Algebra なのかと感じてきました。
あと、ここで単体への位置ベクトルと言ってたものは、アフィン独立なベクトルっていう便利な言葉を使えばいいようだった。
Geometric Calculus International
http://sinai.mech.fukui-u.ac.jp/gcj/gc_int.html
Geometric Algebra Primer [PDF] Jaap Suter - University of Twente, The Netherlands
http://www.lomont.org/Math/GeometricAlgebra/Geometric%20Algebra%20Primer%20-%20Suter%20-%202003.pdf
\Lを特異値分解すると\S \Σ \A^Tとなるとき \Lのムーアペンローズ型擬似逆行列\L^†の転置行列は \L^‡=\S \Σ^{-1} \A^Tと書けると思うので、
↑でベクトル\aのInversion of a vector \a^{-1}と書かれているものは、\a^‡=\a/(\a^T \a)と書いたほうが個人的には純粋な拡張で表せると思った。
例えば、任意のn次元単体の垂線\h_iの逆ベクトル(n+1)本全ての総和は\sum_{i=0…n} \h_i^‡ = \0のように零ベクトルになる(逆垂線総和定理(仮))とか使えるし。
Geometric Algebraについて語ろう
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1142437103/
301+2 :neetubot [↓] :2009/07/04(土) 13:59:12
n次元単体における逆垂線総和定理(仮)から今思いついたのは、ある点\p_xを始点と固定すれば
元のn次元単体の(n+1)本の逆垂線ベクトルの(n+1)終点が作るn次元単体(逆垂線単体と呼ぶ)ができて、
このとき、ある点\p_xは逆垂線総和定理より逆垂線単体の重心となると言えるということです。
これは、五心の中で唯一つ超球と無縁と思われた垂心に、逆垂線単体の重均超球の半径の逆数を半径とする
超球を定義できるかもという光明が見えます。しかし、そのときの中心を広義垂心としていいのか悪いのかだし、むしろ
逆垂線単体自体が何かと相似とか対応してくれるとありがたい。ちなみに、↓をふまえて何か不等式公式が作れそうな気も…
不等式への招待 第3章
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1179000000/863
863 名前:132人目の素数さん[] 投稿日:2009/04/16(木) 01:49:31
問題投下
3辺がa,b,cの三角形の面積と3辺が1/a,1/b,1/cの三角形の面積の積が3/16を超えないことを示せ
ヘロンでどぞー
302 :neetubot [↓] :2009/07/04(土) 14:18:27
逆垂線単体と垂足単体が相似…ではないか…全然違う。チッ
まてよ、i対面からそれぞれi垂線の長さの逆数の比になる分面心が>>301の\p_xで、
その分面心から各i対面に下ろした(n+1)垂足が作る単体が 逆垂線単体と相似じゃないか?
おいおいホントかよ!?仮にこれを擬似逆垂線単体、\p_xの方は擬似逆垂線重心とでも名付けておこう!
303+1 :neetubot [↓] :2009/07/05(日) 06:04:59
位置行列\Pで表されるn次元単体において、各i対面からの距離の比がそれぞれ j_i (i=0…n)
となる分面心は\p_J=\P [j_0/√(\h_0^T \h_0), …, j_n/√(\h_n^T \h_n)]^T / (\1^T [j_0/√(\h_0^T \h_0), …, j_n/√(\h_n^T \h_n)]^T)
(\h_iはそのn次元単体のi垂線ベクトル)のように表せる。 これをふまえて、j_i についてそれぞれ比が1/√(\h_i^T \h_i)になる
擬似逆垂線重心は\p_x=\P [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T / (\1^T [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T)と解ける。
この\p_xの解は、垂心が存在するときの垂心の解 \p_H=\P [1/ν_0, …, 1/ν_n]^T / (\1^T [1/ν_0, …, 1/ν_n]^T)
(ただし、すべての i ≠ j ≠ k ≠i に対して ν_i = (\p_i - \p_j)^T (\p_i - \p_k)となるときに限る)に酷似(ν_i ~ \h_i^T \h_i)しており、
このとき擬似逆垂線単体の対応するi頂点\p_{x_i}は \p_xのi垂足として \p_{x_i} = \p_x - \h_i α_i
(ただし、\p_{x_i} = \P […, [i] 0, …]、つまり、α_i = (定数倍)/(\h_i^T \h_i))のように求まる。
この点\p_xは、広義の垂心の一種として このスレのどこかで触れてた 垂足単体の内心であるような気がしてきた。それはいいとしても、
この点\p_xは、この点から対象のn次元単体の対面に垂足を下ろして作った擬似逆垂線単体の 重心となるという美しい性質を持っており、
以後、この点は 「逆垂心 \p_{/H}」、その垂足単体は 「逆垂足単体 \P_{/H}」 と呼んで位置表記などする。次回、逆垂超球
304+2 :neetubot [↓] :2009/07/05(日) 08:26:46
まとめると、n次元単体の逆垂心への位置ベクトルは \p_{/H} = (\P [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T) / (\1^T [1/(\h_0^T \h_0), …, 1/(\h_n^T \h_n)]^T) と書けて、
逆垂心からi対面に下ろした垂足(i逆垂足)への位置ベクトルを \p_{i/H} = \p_{/H} - \h_i α_i = \p_{/H} - r_{/H}^2 \h_i/(\h_i^T \h_i)
(ただし、このとき r_{/H} = √( 1 / (\sum_{i=0…n} 1/(\h_i^T \h_i)) であり、これを「逆垂半径」と呼ぶ) と書き表せば、
逆垂足単体は \P_{/H} = \p_{/H} \1^T - r_{/H}^2 [\h_0^‡, …, \h_n^‡] という位置行列で表せる。
以上をふまえて、 n次元単体において、逆垂心 \p_{/H} を中心とし、そのn次元単体と同じ空間にある 半径 r_{/H} のn元超球を
仮にその「n次元単体の逆垂超球 S_{\p_{/H}}^n [r_{/H}] ≡ S_{/H}」と呼ぶ。 これは、垂心関係の超球の定義としては最も自然なものであると考えられる。
今後は、>>301 の下側の不等式を応用して、逆垂半径ひいては逆垂超球を使った関係式などを導出したい。 それにしても美しい式だった(自賛)
305+2 :neetubot [] :2009/07/05(日) 16:27:00
たぶん、n次元単体の逆垂心は、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの自乗距離の調和平均が単体内部において最大となる点のような気がする。
そして、n次元単体の内心が、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの距離の調和平均が単体内部において最大となる点のような気がする。
ちなみに、n次元単体の角心(拡張フェルマ・トリチェリ点)は、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの距離の算術平均(相加平均・総和)が(単体内部において)最小となる点だったと思う。
n次元単体の重心は、n次元単体の(n+1)個ある頂点からの自乗距離の算術平均が(単体内部において)最小となる点であり(この証明は微分すれば一発)、
このときの自乗距離の算術平均の平方根をここでは重均半径と呼んでいる。統計学的にはこの重均半径と実際のn次元単体の頂点からの距離のずれの値を出せるので
それをここでは重均偏差と呼んでいる。重心から重均半径で作られる重均超球は、n次元単体の各頂点との自乗距離の算術平均に関する超球当て嵌めの際に最適であると感じるが、
一方で逆垂超球は、n次元単体の各対面(facet)との自乗距離の調和平均に関する超球当て嵌めの際に最適であると感じる。重均偏差に対して逆垂偏差も定義できると思う。
まとめると、n次元単体での 重均超球および逆垂超球の役割は、それぞれ自乗距離に関する外接超球および内接超球のようなもののn次元単体への当て嵌めであると考えられる。
306+1 :neetubot [↓] :2009/07/05(日) 18:20:45
(訂正: >>305 1行目:n次元単体の(n+1)通りある対面からの自乗距離の調和平均、
2行目:n次元単体の(n+1)通りある対面からの距離の調和平均、とします。とりあえず、頂点からでは違うようです。)
単体の対面からの距離の(絶対値or自乗の)逆数の総和の逆数(以下、単に(絶対or自乗)調和、もしくはsum of harmonicsとかと呼ぶ)(ちなみに、harmonic sum=1+1/2+1/3+…っぽい)
の振る舞いを考えると、とりあえずどこでも非負で、どこかの対面平面上で一つでも0があれば0、距離が全部無限になるなら無限大となる、みたいな性質のようです。
交互に無限に繰り返す系の 算術調和平均や調和算術平均(違うのか)とかは、n次元単体で言えば重足逆垂足単体収束点や逆垂足重足単体収束点となるのか?そもそも逆垂足単体収束点は逆垂心ではない気が…
たぶんn次元単体の六心目までは幾何平均(相乗平均)と相性は悪そうですが、(k+1)次元面単体への垂足がその内心となる感じのk次元面心で使えないかな、ダメだろうな。
307 :neetubot [↓] :2009/07/07(火) 01:16:39
垂足三角形とその周辺の話題
http://komurokunio-id.hp.infoseek.co.jp/index3.html
四面体との類似と相違
http://homepage2.nifty.com/PAF00305/math/triangle/node7.html
308+1 :neetubot [↓] :2009/07/07(火) 06:05:07
X(6) = SYMMEDIAN POINT (LEMOINE POINT, GREBE POINT)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html
および http://mathworld.wolfram.com/SymmedianPoint.html より、
逆垂心 ⇔ lemoine-symmedian center、逆垂足単体 ⇔ symmedian pedal simplex などと対訳する。
>>303-304あたりをちゃんと書くと、アフィン独立なm×(n+1)位置行列\Pで表されるm次元ユークリッド空間内のn次元単体A^nについて、
正方行列\Xの対角成分のみの対角行列を\Σ[\X]、\Xの[j,i]小行列の全ての余因子を総和した値を[j,i]成分に持つ行列を余因子総和行列\~C[\X]とすれば、
原点からA^nの逆垂心への位置ベクトルは\p_{/H} = (\P \Σ[\~C[\P^T \P]] \1) / (\1^T \Σ[\~C[\P^T \P]] \1)とも書ける、という感じです。これは、
原点からA^nの内心への位置ベクトル\p_I = (\P \Σ^(1/2)[\~C[\P^T \P]] \1) / (\1^T \Σ^(1/2)[\~C[\P^T \P]] \1)と式形が似ています。
また、内接半径はr_I = (\1^T \C[\P^T \P] \1)^(1/2) / (\1^T \Σ^(1/2)[\~C[\P^T \P]] \1)、(ただし、\C[\X]は\Xの余因子行列)
逆垂半径はr_{/H} = ((\1^T \C[\P^T \P] \1) / (\1^T \Σ[\~C[\P^T \P]] \1))^(1/2)と書けて、辺乗行列\Bで表してもこれと同様の式となります。
ちなみに、重心 ⇔ centroid、分積座標 ⇔ barycentric coordinates、角心 ⇔ fermat-torricelli center などとも対訳します。なお、
2次元単体(三角形)の重中0次元面接(外接)超楕円はhttp://mathworld.wolfram.com/SteinerCircumellipse.html、
2次元単体(三角形)の重中1次元面接(内接)超楕円はhttp://mathworld.wolfram.com/SteinerInellipse.html、
として既にあり、性質も拙稿のn次元単体の重中k次元面接超楕円のn=2でk=0,1のときと同じようなので安心しました。
309+1 :neetubot [↓] :2009/07/08(水) 19:49:56
>>305-306 についてですが、n次元単体の逆垂心は単純に、n次元単体の(n+1)通りある対面からの距離の自乗算術平均が最小となる点でした。
証明は、n次元単体の各i垂線を\h_iとすれば、各i対面への距離が j_i である任意の分面心に対して、
その分面心でn次元単体を分けた各i分積の総和が単体の超体積となることより \sum_{i=0…n} (j_i / √(\h_i^T \h_i)) = 1 なので、
n次元単体の(n+1)通りある対面からの距離の自乗算術平均は r'_{/H}^2 = (\sum_{i=0…n} j_i^2) / (n+1) と書け、
ラグランジュの未定乗数法より f_{/H} = r'_{/H}^2 + λ (- 1 + \sum_{i=0…n} (j_i / √(\h_i^T \h_i)) ) を最小化する各 j_i の組(分面座標)を求める問題に帰着できる。
これより、f_{/H}が各変数j_iについて下に凸な放物線であるので、i成分にj_iを持つベクトル \j で f_{/H} を微分した値が\0になる \j のとき、この制約下でr'_{/H}^2も最小値となる。
計算すると、f_{/H} が最小となるとき \j = [1/√(\h_0^T \h_0), …, 1/√(\h_n^T \h_n)]^T / (\sum_{i=0…n} (1 / (\h_i^T \h_i))) であり、そのときのr'_{/H}^2の最小値
r_{/H}^2 = min[r'_{/H}^2] = (1/(n+1)) / (\sum_{i=0…n} (1 / (\h_i^T \h_i))) となる。これより、 >>304 のr_{/H}について√(n+1)で割ったものを新しく逆垂半径と訂正する。
つまり、以上より、逆垂超球は、n次元単体において各i対面からの距離を用いた最小自乗法による超球当て嵌めであると言える。
そのときの実際の距離とのずれである逆垂偏差は ε_{/H} = √(\sum_{i=0…n} (j_i - r_{/H})^2 ) / (n+1) = r_{/H} √(2 (1 - (r_{/H}/r_I)))
と書けそうである。このときの r_I はn次元単体の内接超球の半径であり、任意のn次元単体について常に r_I ≧ r_{/H} であることが計算するとわかる。
310+2 :neetubot [↓] :2009/07/08(水) 22:52:14
(訂正:>>309 下から2行目:ε_{/H} = √( (\sum_{i=0…n} (j_i - r_{/H})^2) / (n+1) ) = …)
>>309から(r_{/H}+ε_{/H} ≧) r_I ≧ r_{/H} ではあるようだが、直感的に r_G ≧ r_O (≧ r_G-ε_G) とも言えそうである。
ちなみに対訳は、S_G (r_G・ε_G) : 重均超球(半径・偏差) ⇔ Centroid Least-Square Hypersphere(Circum-radius・Circum-deviation)
S_{/H} (r_{/H}・ε_{/H}) : 逆垂超球(半径・偏差) ⇔ Symmedian Least-Square Hypersphere(In-radius・In-deviation) のようにしたい。
以上より、n次元単体における重均半径r_G・逆垂半径r_{/H}・内接半径r_I・広義傍接半径r_{J_j}・k次元面接半径r_{K_k}・外接半径r_Oには下式の関係があると思われる。
(r_{J_{1…(2^n -1)}} >> ) r_G ≧ r_O = r_{K_0} ( > r_{K_1} > … > r_{K_{n-2}} > ) r_{K_{n-1}} = r_{J_0} = r_I ≧ r_{/H}
あとは、重中k次元面接超楕円のn本ある半径の長さr_{i G_k}の自乗算術平均 √((r_{1 G_k}^2+…+r_{n G_k}^2) / (n+1))でもr_{K_k}に関係してくれたら嬉しいのだが。
311+1 :132人目の素数さん [↑] :2009/07/09(木) 07:34:54
sage
312+1 :「猫」∈社会の屑 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/07/09(木) 10:14:38
コレは数学の話なんだし、無理してsageんでもエエがな!
313 :neetubot [] :2009/07/09(木) 12:17:21
(訂正:>>310 下から1行目:自乗算術平均 √((r_{1 G_k}^2+…+r_{n G_k}^2) / n)でもr_{K_k}に)
>>312 猫先生、このスレでははじめまして!見つけてもらってしまった感じで、ありがとうございます!
僕は、2ちゃんねるの読み書きに2ch専用ブラウザJaneDoeView( http://www.geocities.jp/jview2000/ )
というのを使ってるんですが、これに限らず専ブラってのは なぜかデフォルトでメール欄にsageが入ってるようで、
あまり意識しないで書くときが多いので基本sage進行になってました…これから、意識してageageでいきますね。
そういえば、この前2ヶ月以上くらい書き込むの忘れてたら、スレ番号最後の方でスレ落ちかかっててビックリしました。
このスレでやってる分野は、数学の話といっても、まだ先人も見つけられず、あまり流行ってないのかなぁーとか思って、
あまり話しかけてももらえずに、まったりやっておりました。でも今、猫先生にカキコしてもらえてとても嬉しいです!
ちなみに、>>311 は自分でageテストやってました。ちょうど >>310 で区切りがついてネタも尽きてしまった感じだったので…ネーター環
314+1 :neetubot [] :2009/07/10(金) 06:35:15
(訂正:>>310 上から2行目:直感的に (r_G+ε_G ≧) r_O ≧ r_G とも言えそうである、
下から2行目:r_O = r_{K_0} ≧ r_G ( > r_{K_1} > … > r_{K_{n-2}} > ) r_{K_{n-1}} = r_I ≧ r_{/H} )
訂正の件ですが、n次元単体において 各i点からの距離の自乗平均の最小値となるのが重均半径であるので、
min[ (\sum_{i=0…n} (\p_i - \p_X)^T (\p_i - \p_X)) / (n+1) ] = (\sum_{i=0…n} (\p_i -\p_G)^T (\p_i - \p_G)) / (n+1) = r_G^2
という式が成り立ち、これを外接半径にあてはめれば、(\sum_{i=0…n} (\p_i - \p_O)^T (\p_i - \p_O)) / (n+1) = r_O^2 ≧r_G^2
なので、任意のn次元単体で r_O ≧ r_G でした。これより、n次元単体の内部点からk次元面への距離の自乗平均の最小値を
r_{G_k}および偏差をε_{G_k}とでもすれば、(r_{K_{k-1}} > ) r_{G_k}+ε_{G_k} ≧ r_{K_k} ≧ r_{G_k} ( > r_{K_{k+1}}) と思いました。
このように、距離の自乗平均最小値はとてもいい性質を持つので、r_{G_k}をk次元面均半径と呼ぶことにし、
そのときの中心を k次元面均心(それへの位置ベクトル\p_{G_k})とでもすれば、重心は0次元面均心で外均心?で
逆垂心は(n-1)次元面均心で内均心か?これが、k=1…(n-2)のときに唯一つに定まるかとか対訳も含めて考え直します。
ちなみに、r_I ≧ r_{/H} が任意のn次元単体の辺乗行列 \Bで成り立つことも考えれば、対角成分が0の任意の対称行列 \B について
((n+1) / (\1^T \Σ^(1/2)[ \C[- \B] ] \1))^2 ≧ (n+1) / (\1^T \Σ[ \C[- \B] ] \1)) という、自乗算術平均が絶対算術平均より大きい
というよく見る式(上の実際の式ではその2乗の逆数を比べている)が成り立つ。驚くのは、r_O ≧ r_G にこの方法を用いたときで、
対角成分が0の任意の対称行列 \B について det[- \B] / (\1^T \C[- \B] \1) ≧ (\1^T \B \1) / ((n+1)^2) という公式が成り立つ
と思う。n次元単体の外接半径が r_O = √(det[- \B] / (\1^T \C[- \B] \1)) と表せるかは、まだちゃんと証明してないんだけど…
315 :neetubot [] :2009/07/10(金) 23:03:36
(訂正:>>314 対角成分が0で「行列式が0とならない」任意の対称行列 \B について det[- \B] / (\1^T \C[- \B] \1) ≧ (\1^T \B \1) / ((n+1)^2) } )
r_Oの\Bを使った表記(ここでは辺乗表記と呼んでいる)は、n次元単体の外心からi対面への垂足がそのi対面の外心になることを使った気がしましたよ>俺
316 :neetubot [] :2009/07/11(土) 07:44:44
今日は特にネタはない
317+1 :「猫」∈社会の屑 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/07/11(土) 08:42:21
数学者というもの、ネタが無いと辛いですね、判ります。
まあそやけど「そういう日」もある訳で、そんな時は
散歩でもしはったらどうでっしゃろ?
ワシも今日はちょっと疲れてしもうてですナ
まあちょっと電車に乗って遊びに行こうかと
思ってますねん
ちょっと遠くまで行くと魚が美味いっちゅう話も聞きましたしね
そんで「5心」ですが、猫は今ある人と一緒に重心で遊んでますよ
318 :neetubot [] :2009/07/11(土) 09:30:16
>>317 ご心配ありがとうございます(TT) この頃、新しく何かひらめかないと、手詰まりでネタ無しで辛いです。
散歩いいですよね。私も考え事しながら、半径2mくらいでひたすらグルグル歩き回ってるときがあります(謎)
猫先生に判るって言ってもらえて嬉しいです!魚いいですね、海とかこの時期は人魚さん達がいらっしゃ…
川とか当県の近くに来たときは是非お声をお掛けくださいね。私は超インドア派なのであまり詳しくないですが…
「5心」やってるんですか!?重心は、n次元単体内の各k次元面に接する超楕円面のとき、すごくお世話になったので、
5心の中では一番好きです。猫先生が重心で遊ぶなんておっしゃられると、かなりものすごい事やってそうで恐ろしいですっ
もしよろしければ、お話とか聞かせて頂けると、とてもありがたいです。むしろ、是非よろしくお願いしますm(_ _)m
319 :neetubot [] :2009/07/13(月) 05:56:16
対訳の方向性が定まりました。面均をFacetargetedに対訳しようと目論見ました。
外心・外接超球(面)(Circumcenter・Circumscribed Hypersphere)
k次元面心・面接超球(面)(Constrained k-Facescribed Midcenter・Hypersphere)
内心・内接超球(面)(Incenter・Inscribed Hypersphere)
重心・重均超球(面)(Centroid・Centroid 0-Facetargeted Hypersphere)
k次元面均心・面均超球(面)(Least-Square k-Facetargeted Midcenter・Hypersphere)
逆垂心・逆垂超球(面)(Lemoine-Symmedian Center・Symmedian (n-1)-Facetargeted Hypersphere)
それぞれの半径や偏差の対訳は、Circum-・Mid-・In-とradius・deviationを組み合わせた名前で、上の適な場所を
置き換える感じで。あと、珍しいところでは、重中k次元面接超楕円(面)(Centroid k-Facescribed Hyperellipse)とか。
320+2 :neetubot [] :2009/07/13(月) 12:24:05
m次元ユークリッド空間内の n次元単体の k次元面均心について、ひらめきました。
まず、k次元面均心\p_{Φ_k}=\P \a_{Φ_k} (ただし、\1^T \a_{Φ_k} = 1)からあるk次元面Φへの垂足\p_Φについて、
k次元面の内部点\p_Φの単体座標値の(n-k)個が0となることから、ΦからΦに含まれる点以外のi点への垂線\h_{i←Φ}を使って、
\p_{Φ_k} - \p_Φ = \sum_{i \not\in Φ} \h_{i←Φ} a_{i Φ_k} が成り立つ。ここで、n次元単体のk次元面全ての集合を\Φとする。
これまでの、自乗算術平均が最小になる条件をふまえると、n次元単体におけるk次元面Φからk次元面均心\p_{Φ_k}への垂線のΦ全ての和が
ゼロベクトル\0になると考えられる。つまり、\sum_{Φ \in \Φ} (\p_{Φ_k} - \p_Φ) = \sum_{Φ \in \Φ} \sum_{i \not\in Φ} \h_{i←Φ} a_{i Φ_k}
= \sum_{i=0…n} \sum_{Φ \in \Φ, Φ \not\ni i} \h_{i←Φ} a_{i Φ_k} = \0 となると予想できる。
上式は、\h'_{iΦ} = \sum_{Φ \in \Φ, Φ \not\ni i} \h_{i←Φ} と書けば、[\h'_{0Φ},…,\h'_{nΦ] \a_{Φ_k} = H'_Φ \a_{Φ_k} = \0 となる
ということを表している。以上より、コンピュータで地道に計算して出るn階(n+1)×(n+1)行列 H'_Φ に垂直で \1^T \a_{Φ_k} = 1
となる座標ベクトル\a_{Φ_k} を一意に求めることができて、k次元面均心\p_{Φ_k}=\P \a_{Φ_k} を導出できるという方向性が見える。
今後は、i点以外のk次元面Φからi点への垂線を全てのΦについて平均したベクトルを列挙した行列 H'_Φ をきれいな式にして、完全に解きたい。
321+2 :neetubot [] :2009/07/14(火) 18:06:07
(訂正:>>320 下から4行目:[ \h'_{0Φ}, …, \h'_{nΦ} ] \a_{Φ_k} = H'_Φ \a_{Φ_k} = \0、下から2行目:n階m×(n+1)行列 H'_Φ)
>>320 を次のように書き換えます。まず、n次元単体における全てのk次元面の集合を{φ}とし、{φ}の元である あるk次元面をφで表す。
すると、k次元面均心\p_{Φ_k}=\P \~a_{Φ_k} (ただし、\1^T \~a_{Φ_k} = 1)からφへの垂線\r_φと垂足\p_φについて、
φに含まれないi点からφへの垂線 \h_{i→φ} = ([\p_i, \P_φ] \~C[[\p_i, \P_φ]^T [\p_i, \P_φ]] \~e_0) / (\~e_0^T \~C[[\p_i, \P_φ]^T [\p_i, \P_φ]] \~e_0)
(ただし、\P_φはk次元単体φの部分だけのm×(k+1)位置行列)を使って、\r_φ = \p_φ - \p_{Φ_k} = \sum_{i=0…n, i \not\in φ} \h_{i→φ} ~a_{i Φ_k} が成り立つ。
【たぶん、\r_φの自乗算術平均が最小値 r_{Φ_k} = min[√(\sum_{φ \in {φ}} \r_φ^T \r_φ) / (_(n+1) C_(k+1)))] となるとき、\sum_{φ \in {φ}} \r_φ = \0 となるので、】
\sum_{φ \in {φ}} \r_φ = \sum_{φ \in {φ}} \sum_{i=0…n, i \not\in φ} \h_{i→φ} ~a_{i Φ_k} = \sum_{i=0…n} \sum_{φ \in {φ}, φ \not\ni i} \h_{i→φ} ~a_{i Φ_k} = \0
、ここで、i点からi点を含まない全てのφへの垂線の平均ベクトル(以下、k次元i垂均)\h'_{iΦ_k} = (\sum_{φ \in {φ}, φ \not\ni i} \h_{i→φ}) / (_n C_(k+1)) を考え、
\~e_j^T \~Φ_k \~e_i = \~e_j^T [[j ≠ i] \sum_{φ \in {φ}, φ \ni j, φ \not\ni i} (-1)^(i+j) (\1^T \C[\underset{(\p_j ← \p_i)}{\P_φ}^T \P_φ] \1) / (\1^T \C[\P_φ^T \P_φ] \1)
/ (_n C _(k+1) or [j=i] 1] \~e_i となる(n+1)×(n+1)の面因子平均行列 \~Φ_k を導入すれば、k次元垂均行列 H'_{Φ_k}= [\h'_{0Φ_k},…,\h'_{nΦ_k}] = - \P \~Φ_k と書けることから、
\sum_{φ \in {φ}} \r_φ = H'_{Φ_k} \~a_{Φ_k} = - \P \~Φ_k \~a_{Φ_k} = \0 が成り立つ。
以上をふまえれば、m次元ユークリッド空間内のn次元単体において、(_(n+1) C_(k+1))通りあるk次元面からの距離の全ての自乗算術平均が最小となる点、すなわち
k次元面均心 \p_{Φ_k} = \P \~a_{Φ_k} を導出するには、面因子平均行列 \~Φ_k を計算し、\~Φ_k \~a_{Φ_k} = \0(ただし、\1^T \~a_{Φ_k} = 1)となる\~a_{Φ_k}を求めればよいことがわかる。
322+1 :neetubot [] :2009/07/15(水) 03:29:12
m次元ユークリッド空間内の n次元単体の k次元面心について、ひらめきました。
>>321 と同様に、n次元単体内のあるk次元面をφ、φに含まれないj点とφで作られる(k+1)次元面をjφで表す。
すると、k次元面接超球が存在するためには、k次元面心\p_{K_k}=\P \~a_{K_k} (ただし、\1^T \~a_{K_k} = 1)から
jφに下ろした垂線\r_{jφ}の垂足がjφの内心となり、\p_{K_k}からφに下ろした垂線\r_φの垂足が jφの内足となることが
必要十分条件であるので、\r_{jφ}-\r_φ = (\P_{jφ} \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \~e_0) / (\~e_0^T \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \~e_0) ε_{jφ}
(ただし、ε_{j/jφ} = √(\~e_0^T \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \~e_0) / (\1^T \Σ^(1/2)[ \~C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] ] \1))が成り立つ。
この式の、\p_jの単体座標について比べると、\p_{K_k}からφへの垂足の\p_{K_k}+\r_φでは0、\p_{K_k}からjφへの垂足の\p_{K_k}+\r_{jφ}では
\sum_{i \not\in φ} (-1)^(i+j) (\1^T \C[\underset{(\p_j ← \p_i)}{\P_{jφ}}^T \P_φ] \1) / (\1^T \C[\P_φ^T \P_φ] \1) ~a_{i K_k} = \~e_j^T \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k}
(このとき、\Φ_(k+1)を面因子行列と呼ぶ)であるため、\r_{jφ}-\r_φの\p_jの単体座標について \~e_j^T \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} = ε_{jφ}
と書ける。これは、【k次元面心の単体座標\~a_{K_k}の部分について全てのφで \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} = \ε_φ】が成り立たなければならない
制約を表している。この式の平均は、前述の(k+1)次元面因子平均行列 \~Φ_(k+1) を用いて、\sum_{jφ \in {jφ}} \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} =
\~Φ_(k+1) \~a_{K_k} = \~ε_φ(ただし、~ε_{jφ} = (\sum_{φ \in {φ}, φ \not\ni j} ε_{jφ})/(_n C_(k+1))である?)と書ける気がするので、
前述の(k+1)次元面均心と 存在するならこのk次元面心は違う点となると思う。(分母の係数が前述の面因子平均行列とあってないかも)
さて、心はいい行列が見つかって良かったが、それぞれの半径はどうなることやら…
323 :neetubot [] :2009/07/15(水) 07:23:56
(訂正:>>320 上から8行目:\sum_{i \not\in φ} (-1)^(i+j) (\1^T \C[\P_{iφ}^T \P_{jφ}] \1) / (\1^T \C[\P_{jφ}^T \P_{jφ}] \1) ~a_{i K_k}
= \~e_j^T \Φ_(k+1) \~a_{[\not\in φ]K_k} (以下、>>281の記法もふまえたい。))お、おかしいぞ、半径がきれいな式になる気が全くしない…
324+1 :neetubot [] :2009/07/15(水) 17:14:33
m次元ユークリッド幾何学スレまとめ@ウィキ 「使用する用語」
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/51.html
に、そのウィキやこのスレで使っている単体五心関係の用語と式などを少しまとめてみました。
325+1 :neetubot [] :2009/07/16(木) 23:59:00
内積・外積の逆演算を考えよう。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1045048250/
の問題は解けそうなので、紹介します。
1:ユークリッド空間内で、ベクトル集合 \L = [\l_1,…,\l_n] と位置ベクトル \a の内積値が一定値 \b となるとき、点 \a の存在する空間を求めよ(内積の逆演算?)。
\L^T \a = \b より、\L = \S \Σ \A^Tと特異値分解されるときの\Lのムーアペンローズ型擬似逆行列\L^†の転置行列 \L^‡ = \S \Σ^(-1) \A^Tを用いて、
拡大係数行列[\L^T, \b]の次元が係数行列\L^Tの次元と等しい場合(以下、u[\L^T, \b]=u[\L^T]と書く) \a = \L^‡ \b + (E - \L^‡ \L^T) \α
(ただし、\αは任意の実ベクトル)と書ける。これは、u[\L^T, \b] = u[\L^T]なら、位置ベクトル\aで表される点は、原点から \L^‡ \b の場所を通り
(E - \L^‡ \L^T)で張られる\Lの直交補空間上に存在すると言える。また、u[\L^T, \b]≧u[\L^T]となる場合は、この式を満たす\aは存在しないことは自明である。
(ちなみに、このスレでは \L \a = \b すなわち\bを表す【基底】\Lの座標 \a を求める問題があり、u[\L, \b] = u[\L]のとき\a = \L^† \b = (\L^T \L)^(-1) \L^T \b とか使った)
とここまで書いて、この問題についてはこのスレで前に言及したような記憶があり、\l_1のみでの略解も上記スレの100にもあったのに気付いた。
外積の逆演算はn次元拡張しても直交補空間ですで終わる話だと思たので、もう一つスレ紹介↓
楕円→放物線→双曲線の順は正しいのか
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1247644637/
のスレの6さんが言うとおり、傾いた円の透視投影において その円の半径を無限小から無限大へ増やしていけば、
透視投影される像の二次曲線が 円 楕円 放物線 双曲線 直線 の順に変化することが、そのシステムにおいては想像できる。
しかし、二次曲線を一般化した f_Q = \p^T \Q \p + 2 \p^T \q_y + \q_{yy} = 0 で表される二次超曲面を平面で切った形を考えると、
その平面の基底における二次係数 \Q の固有値については 楕円・双曲線は2個 放物線は1個であるので、これらは違う形といえる。
私的な考えでは、二次超曲面をn次元平面で切った形の分類において、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%9B%B2%E9%9D%A2
を参考に、放物軸…あ、バイト数が
326 :neetubot [] :2009/07/18(土) 06:06:18
(訂正:>>325 上から約8行目:u[\L^T, \b]>u[\L^T]となる場合は、この式を満たす\aは存在しない)
>>322 のk次元面心は、全てのφにおいて \~Φ_(k+1) ↓{[\not\in φ]}{\~a_{K_k}} = ↓{[\not\in φ]}{\~ε_{φ k}}
となる場合に限り、\p_{K_k}=(\P \C^T[\~Φ_(k+1)] \~1) / (\~1^T \C[\~Φ_(k+1)] \~1) + \P \~C^T[\~Φ_(k+1)] \~ε_k
と位置ベクトルが書けそうです。>>321 のk次元面均心は、\p_Φ_k = (\P \C^T[\~Φ_k] \~1) / (\~1^T \C[\~Φ_k] \~1)
と位置ベクトルが書けそうです。>>324 のページで式の形が画像で見れると思いますので、良かったらどうぞー
327+1 :neetubot [] :2009/07/18(土) 13:06:42
今回、k次元面心・面均心の式の形の方向性が見えた(それぞれの半径の導出は今はあきらめました)ということで、
重心=第1心、(広義)垂心=第2心、内心・広義傍心=第3心、k次元面心=第4心、外心=第5心、角心=第6心とし
(たぶん明示的に使うことはないですが…)、来週は角心(Fermat-Torricelli Center)について思い当たってることを解決したいです。
328+1 :neetubot [] :2009/07/20(月) 11:18:22
アフィン独立なベクトルを列挙した\Pの擬似逆行列の転置行列\P^‡と正射影行列を絡めて考えてたら、
任意の正方行列\Xの行列式|[\X]|・余因子行列\C[\X]・余因子総和行列\~C[\X]に対して、
\Pが線型従属の場合 \P^‡ = \P (\~C[\P^T \P]) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)となりそうなんですが、
\Pが線型独立の場合 \P^‡ = \P ((\C[\P^T \P] \1 \1^T \C[\P^T \P]) / |[\P^T \P]| + \~C[\P^T \P]) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)
= \P \C[\P^T \P] / |[\P^T \P]| = \P (\P^T \P)^(-1) となると思うので、任意の正則対称行列\Xに対して
\X^(-1) = \C[\X] / |[\X]| = ((\C[\X] \1 \1^T \C[\X]) / |[\X]| + \~C[\X]) / (\1^T \C[\X] \1)となり、たぶん
任意の正則行列\Xに対して \C[\X] \1 \1^T \C[\X]^T = \C[\X] (\1^T \C[\X] \1) - \~C[\X] |[\X]| でも成り立って、
\X^T \~C[\X] + \1 \1^T \C[\X]^T = \C[\X] \1 \1^T + \~C[\X]^T \X = \E (\1^T \C[\X] \1) っぽくなりそうです。
果たしてどうなんでしょうか?対称行列×違う対称行列は 普通は対称行列にならないっぽい!ご意見お待ちしておりますー
329 :neetubot [] :2009/07/22(水) 20:18:51
m次元ユークリッド空間内でn次元単体の位置行列を\Pとし、
n次元単体があるn次元部分空間上の点への位置ベクトルを\p_Xとすれば、
>>328より、\P^T \p_X = \~b_X となるとき、 \p_X = \p_y + \P^‡ \~b_X と書ける
(ただし、原点からn次元部分空間\p_y=(\P \C[\P^T \P] \1) / (\1^T \C[\P^T \P] \1))。
しかし、\p_X = \p_y + \P^‡ \~b_X であっても、\P^T \p_X が \~b_X となるとは限らない、と思う。
ということで、\p_X = \p_y + \P^‡ \~b_X となる \~b_X を辺乗座標(Half-squared Edge Coordinates)と呼ぶ。
330 :neetubot [] :2009/07/26(日) 01:08:44
ある点への辺乗座標が\~b_Xと書けるなら、\P^T \P^‡ \~b_Xもまたその点への辺乗座標である。また、位置行列\Pに対し、
(\P^T \P \~C[\P^T \P] \P^T \P) / (\1^T \C[\P^T \P] \1) = \P^T \P - (\1 |[\P^T \P]| \1^T) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)
という式も成り立つ。と思った。
331 :neetubot [] :2009/08/14(金) 17:11:10
φは空集合だと思われるといけなかったので、表記をいろいろ変えました↓
単体導入 > 使用する用語
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/51.html
332 :neetubot [] :2009/08/15(土) 14:52:23
平石司さん『高次元単体の諸心』
http://homepage2.nifty.com/hiraishi-tsukasa/Folder_SimplexesOfHighDimensions/SimplexesOfHighDimensions.htm
のページにn次元単体の五心の性質から、三角形における九点円をn次元単体へ拡張したp次の面重心球面、
および、任意のn次元単体に存在するp次の面重心球面の中心に相当する「究点」という新しい概念など、
非常に素晴らしくまとまっており、私的にも「究点」を方向表記で導出し確認できたので、ここでも紹介します!
平石さんにはとてもお世話になっており、大変ありがたく思っております!
333 :neetubot [] :2009/08/20(木) 01:36:48
@ウィキのほうのトップページ/メニューでライセンスの項目を
-#image(http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.1/jp/88x31.png,http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/)
-This Work by 132人目の素数さん is licensed under a [[Creative Commons 表示-非営利 2.1 日本 License>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/]]
+#image(http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/88x31.png,http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)
+This Work by 132人目の素数さん・他 is licensed under a [[Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/]].
と変えました。英語論文はneetubot名義のCC-by-ncでいきたいのと2chだしncかなってのをふまえてます。
334+1 :neetubot [] :2009/09/05(土) 12:30:42
たけしのコマ大数学科 Part11
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1243708405/568-600
の番組を見て、「m次元ユークリッド空間内のn次元部分空間にある(n+1)個のn次元超球体の全てに接する超球の分類」
について、「m=n=2で一直線上に無く互いに重ならない3個の円の全てに接する円は8通りある」らしいようなこと言ってました。
この問題をこのスレっぽく言えば、「U^m内のn次元単体のi-頂点からの距離がそれぞれ(r±ε_i)となる分点心と
そのときのrの組を求めよ」って感じだと思うのですが、この場合、内分点心と外分点心のうちどちらかしか満たさない
(かどちらも一致する)ような気がしますし、最高で広義傍心系の2倍の2^(n+1)通り求まる気がしますが、うーん…
(たぶん、この解があれば、n次元音源位置推定で時間測定誤差があるとき、音源が存在しうる位置の範囲が求められる)
335+1 :132人目の素数さん [↓] :2009/09/05(土) 16:19:45
「m=n=2で一直線上に無く互いに重ならない3個の円の全てに接する円は8通りある」
配置による。
8通りあるためにはどの1つの円と他の2つの円との間に
円に接さない直線で境界が引ける程度に各円が離れている必要がある。
336 :neetubot [] :2009/09/06(日) 07:55:04
>>335さんフォローありがとうございます!コマ大スレで議論が行われてるようですが、>>335さんの条件に同意です。
2つの円に内接しもう1つの円に外接する円っぽい場合には8通り無い状況が私も想像でき、>>334ではダメなことがわかりました。
この接する円がなくなる場合には、漸近線が直交する双曲線として接しているという状態なのか、とかにも興味がありますし、また、
この条件をn次元に拡張したような「U^mでn次元単体を作る(n+1)点のうち、(k+1)点を選んで作られる k次元部分単体(m≧n≧2, (n-1)≧k≧0)と
それに含まれない(n-k)点で作られる部分対面との間に 各i-頂点からの距離がそれぞれ(r+ε_i)となる部分境界(n-1)次元超平面があり
r>0となるとき、部分単体の方に含まれるそれぞれのi-頂点を中心とし半径ε_iのn次元超球体の全てに内接し 部分対面の方に含まれる
それぞれのi-頂点を中心とし半径ε_iのn次元超球体の全てに外接するっぽい超球が必ず1つ求まる。」とかを言うためのn次元単体の
k次元部分境界(n-1)次元超平面~U_{ψ≠ψ}[\ε]とそのときのrを求めたいと思いました。このとき、n次元単体の~U_{ψ≠ψ}[\ε]
が2^n通り(∵部分単体と部分対面が逆の場合も同じ物なので)全部存在する場合に限り最高の2^(n+1)通りの接超球が求まるみたいな…
今後とも是非また宜しくお願い致します。
337 :neetubot [] :2009/09/06(日) 11:39:56
(n+1)個の超球の全てに内接する超球と関係するn次元部分単体のとき、および、
(n+1)個の超球の全てに外接する超球と関係する(-1)次元部分単体(便宜上0個の
点から作られる何も無い図形を表す)のとき(k=nのとき、および、k=-1のとき)を失念しておりました。
前者の部分境界超平面はn次元単体があるn次元部分空間の無限遠面全体(r→∞)と考えられるが、
(n+1)個の超球のうち1つが1つを内包してしまうときなどに全てに内接する超球(外接超球?)は存在しなくなる。
(各頂点から部分境界超平面への距離の間を他の超球面が横切ってはいけないなどの条件を加えればよいか…)
後者の部分境界超平面はn次元単体内部において各i-頂点からの距離がそれぞれ(r+ε_i)となる1点となり、
r>0なら全てに外接する超球(内接超球?)が存在する。(r=0のときは部分境界超平面と同じ1点に縮退する)
338 :neetubot [] :2009/09/08(火) 08:30:43
今日はAGEたい気分・・
339 :猫は残飯 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/09/08(火) 08:43:47
そうでっか、AGEな気分でっか。
ワシなんかはEGAな気分やでー
IHESで買って来たヤツ全巻持ってるさかいナ。
アンタも読んでみはりまっか?
340 :neetubot [] :2009/09/08(火) 09:47:10
EGA・・江頭2:50っすか!? というのは冗談として、
Alexander Grothendieck 『Elements de Geometrie Algebrique』
http://people.math.jussieu.fr/~leila/grothendieckcircle/pubtexts.php
のリンク先などでSGAもFGAもフランス語のpdfなら入手できそうですが、読めなそうなので、
【Motifs】グロタンディーク 8【Topos】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1149181307/
でも紹介されている、黒田貞玖作「EGA日本語翻訳計画」
http://grothende.gozaru.jp/の完成を待ちながら、入門から勉強したいと思います><
猫先生はフランスのI.H.E.S(Institut des Hautes Etudes Scientifiques)
http://ja.wikipedia.org/wiki/IH%C3%89S
の研究所に行った事があるっすか!? なんかすごい・・
と一通り調べないと話についていけなかった私です…今度メール返信でがんばりますっ
341 :猫は残飯 ◆ghclfYsc82 [↓] :2009/09/08(火) 09:55:51
この聖書は絶対に翻訳するべきではない。
学ぶ者はフランス語の原典に当たるべき。
そもそも神が著わしたものに人間が手を加える
等は僭越至極なので、翻訳等は即刻止めるべき。
342 :neetubot [] :2009/09/08(火) 11:22:18
黒田貞玖さんの更新が滞っているようなのは、そういう理由なのかもしれません。
私のような門外漢には解説書ぐらいの勢いで原文+対訳っぽい感じで何かあると
手が付けやすいのですが…確かに原典や原著をご存知の方から一手に非難を浴びそうですね。
自分で出来る範囲で何かアウトプットしたいという気持ちはすごく共感や好意が持てますし、
2ちゃんねるで言うところの改変コピペみたいなのはその分野をより多くの人に知ってもらう
ためなどに効果があると思いますが、やはり原著者に対する敬意やその分野への造詣や見識の
深さなどが求められるとこかもしれません。などとは私に言えることではありませんでした。ご容赦下さい。
343 :neetubot [] :2009/11/05(木) 01:33:03
ついでに保守。最近やる気でてない間も、@Wikiの方には各所からお越し頂いていたようで、その節はどうもありがとうございます。
ここに質問など書いて頂いたら、できるだけ即レスします!
344+1 :neetubot [] :2010/01/02(土) 13:06:42
あけましておめでとうございますー 今年もよろしくお願いしますー
数学板では最近は四色問題が流行っているようで、じゃあ、
「(n-1)次元超球面(とそれをリーマン球面の考え方で変換できる(n-1)次元超平面)と同相な図形(単体的複体)は、
(その図形を単体分割すれば(n+1)面あるn次元単体に分割できることから、)たかだか(n+1)色で塗り分けられる」
とざっくり考えました。。あまり深く考えてませんが、みなさん、よい数学お年をー
345 :132人目の素数さん [↓] :2010/01/03(日) 12:19:04
_,,....,,_ _人人人人人人人人人人人人人人人_
-''":::::::::::::`''> ゆっくり幾何学していってね!!! <
ヽ::::::::::::::::::::: ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
|::::::;ノ´ ̄\:::::::::::\_,. -‐ァ __ _____ ______
|::::ノ ヽ、ヽr-r'"´ (.__ ,´ _,, '-´ ̄ ̄`-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_ _,.ヘーァ'二ハ二ヽ、へ,_7 'r ´ ヽ、ン、
::::::rー''7コ-‐'"´ ; ', `ヽ/`7 ,'==─- -─==', i
r-'ァ'"´/ /! ハ ハ ! iヾ_ノ i イ iゝ、イ人レ/_ルヽイ i |
!イ´ ,' | /__,.!/ V 、!__ハ ,' ,ゝ レリイi (ヒ_] ヒ_ン ).| .|、i .||
`! !/レi' (ヒ_] ヒ_ン レ'i ノ !Y!"" ,___, "" 「 !ノ i |
,' ノ !'" ,___, "' i .レ' L.',. ヽ _ン L」 ノ| .|
( ,ハ ヽ _ン 人! | ||ヽ、 ,イ| ||イ| /
,.ヘ,)、 )>,、 _____, ,.イ ハ レ ル` ー--─ ´ルレ レ´
346 :neetubot [] :2010/01/05(火) 18:00:04
>>344 の(n-1)次元超球面と同相な複体表面の彩色問題については、
表面が全て(n-1)次元単体となる複体表面Aの場合を数学的帰納法で証明した後、
1点まわりの点全てがある(n-1)次元超平面上にあるとき この多胞体錐のまわり
が高々n色で彩色でき、Aの各部分で多胞体錐を取り除いた任意の複体表面も(n+1)色で
彩色できることを証明すればいいと思ったが、いろいろダメそうなので、
Hadwiger氏のように(n+2)完全グラフ以上が書けないことを証明した方がいいとも思った。
あと、2次元多様体の分類定理における全ての曲面の彩色問題について少し調べた所、
「ヒーウッドの公式について(http://www.geocities.jp/ikuro_kotaro/koramu/270_heawood.htm)」
あたりが詳しかった。射影平面とクラインの壺上では6色、トーラス上では7色必要らすぃ!!??すげぇ
347+3 :neetubot [] :2010/01/10(日) 01:07:19
猫先生のどんな質問にもマジレスするスレ(弐)(http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1262693441/)
の14でも触れましたが、改めてこのスレで下記の問題について解いていこうと思います。
「m次元ユークリッド空間内でn次元単体を作る(n+1)個の頂点列\P=[\p_0…\p_n]と
その単体の内部点\p_a=\P [a_0…a_n]^T (ただし、全てのa_i≧0, \sum_{i=0…n} a_i =1)があるとき、
頂点\p_iおよび\p_aを結ぶ直線と \p_i以外の頂点で作られる(n-1)次元単体との 交点を\p'_iとすれば、
\p'_0…\p'_nで作られる内部n次元単体(Cevian Simplex)の超体積がこのとき取りうる値の範囲を求めよ。」
348+2 :neetubot [] :2010/01/10(日) 04:52:05
http://www7.atwiki.jp/neetubot/?plugin=ref&serial=37
>>347 のCevian Simplexを方向表記(Simplex Direction Formula 上図左)で表すと、
\l'_i=(\p'_i-\p_0)-(\p'_0-\p_0)=\L (\a (1/(1-a_i)-1/(1-a_0)) - \e_i (a_i/(1-a_i)))
と書けるため、\L'=\L (\a (\1-\a)^{-T} - \a/(1-a_0) \1^T - \Σ^{-1}[\1-\a] \Σ[\a])
と略記でき、|[\L'^T \L']| = |[\L^T \L]| ( |[\a […,1/(1-a_i)-1/(1-a_0),…]^T - \Σ[…,a_i/(1-a_i),…]]| )^2
となるため、http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_determinant_lemmaより、
√( |[\L'^T \L']| / |[\L^T \L]| ) = |-(1- […,1/(1-a_i)-1/(1-a_0),…]^T \Σ^(-1)[…,a_i/(1-a_i),…] \a)| |[\Σ[…,a_i/(1-a_i),…]]|
= |([…,1/(1-a_i)-1/(1-a_0),…]^T […,(1-a_i),…]-1)| (\prod_{i=1…n} (a_i/(1-a_i)))
= n \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) ≧ 0 (条件より全て0≦a_i≦1であるため)が成り立つ。
この形から上限はa_0=…=a_n=1/(n+1)のとき、√( |[\L'^T \L']| / |[\L^T \L]| ) ≦ 1/(n^n)であると予想する(証明まだ)
349+2 :neetubot [] :2010/01/10(日) 13:33:44
http://www7.atwiki.jp/neetubot/?plugin=ref&serial=37
>>347 のCevian Simplex(以下、点足単体と呼ぶ)を位置表記(Simplex Position Formula 上図右)
で表すと、\p'_i=(\p_a-\p_i a_i)/(1-a_i)となるため、点足単体の位置行列は
\P'=\P \A' = \P (\a […,1/(1-a_i),…]^T-\Σ[…,a_i/(1-a_i),…])と書ける。
ここで、元の単体の超体積はv^n=√(\1^T \C[\P^T \P] \1)/(n !)であり、
点足単体の超体積はv'^n=√(\1^T \C[\P'^T \P'] \1)/(n !)=√(\1^T \C[\A']^T \C[\P^T \P] \C[\A'] \1)/(n !)
と表せることから、\C[\P^T \P]=\A' \X \A'^Tを代入することで v'^n = |( |[\A']| )| v^nが成り立つ。
したがって、|( |[\A']| )|はhttp://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_determinant_lemmaより、
|( |[\A']| )| = |( -(1-[…,1/(1-a_i),…]^T \Σ^{-1}[…,a_i/(1-a_i),…] \a) \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) )|
= n |( Π_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) )| と解けるため、この問題は、\p_aが単体内部点となる条件の
「\sum_{i=0…n} a_i = 1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i(≦1) 」の範囲(単位単体内部条件)で
「v'^n/v^n = |( |[\A']| )| = n \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) 」の値の範囲を求める問題に帰着できる。
この問題は、一見 相加相乗平均を使いそうだがうまくいかず、今 数学的帰納法で導出を試みている。
350 :neetubot [] :2010/01/10(日) 22:47:23
>>348>>349 のつづき。a_0+a_1=αのとき、\prod_{i=0…1} (a_i/(α-a_i)) =1である。
また、\sum_{i=0…(n-1)} a_i =αで \prod_{i=0…(n-1)} (a_i/(α-a_i)) ≦1/(n-1)^n
が成り立つと仮定したとき、\sum_{i=0…n} a_i =αとすれば \prod_{i=0…n} (a_i/(α-a_i))
…うーんダメだな。\prod_{i=0…n} ((1-a_i)/a_i)を展開して各項に相加相乗平均を使うか…
351 :neetubot [] :2010/01/11(月) 04:20:43
>>348>>349 のつづき。\sum_{i=0…n} a_i = 1 ≧ (n+1) (\prod_{i=0…n} a_i)^(1/(n+1)) = (n+1) x ≧ 0とおく。
同じく相加相乗平均を用いて、\prod_{i=0…n} ((1-a_i)/a_i)=(1-(Σ a_i)+(Σ a_i a_j)-…+(-x)^(n+1))/x^(n+1)
≧ (1 - (n+1) x + (n+1)C2 x^2 - (n+1)C3 x^3 + … +(-x)^(n+1))/x^(n+1) = ((1-x)/x)^(n+1)
ここで、仮定より0≦x≦1/(n+1)であり、この範囲で(1-x)/x=(1/x)-1は単調減少関数であるため、
\prod_{i=0…n} ((1-a_i)/a_i) ≧ ((1/x)-1)^(n+1) ≧ n^(n+1)
(等号成立条件は a_0=…=a_n=1/(n+1) のとき)となる。
よって、「\sum_{i=0…n} a_i =1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i(≦1)」の範囲(単位単体内部条件)で
>>347の解「0 ≦ v'^n/v^n = |( |[\A']| )| = n \prod_{i=0…n} (a_i/(1-a_i)) ≦ 1/(n^n)」が成り立ち、
超体積v^nの単体の内部ではその重心で作られる点足単体(Cevian Simplex)の超体積v^n/(n^n)が最大であることがわかった。
QED
352 :neetubot [] :2010/01/11(月) 04:32:54
次は、点足単体が元の単体と相似となる条件は \A'が全て等しい固有値を持つことなのかや、
点垂足単体の超体積が最大値をとる点(内心?)などを求めたいです。
353 :neetubot [] :2010/01/11(月) 18:13:51
点足単体(Cevian Simplex) http://mathworld.wolfram.com/CevianTriangle.html
点反足単体(Anticevian Simplex) http://mathworld.wolfram.com/AnticevianTriangle.html
点垂足単体(Pedal Simplex) http://mathworld.wolfram.com/PedalTriangle.html
点反垂足単体(Antipedal Simplex) http://mathworld.wolfram.com/AntipedalTriangle.html
垂足単体(Orthic Simplex) http://mathworld.wolfram.com/OrthicTriangle.html
について http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/51.html に追記しています。
354 :neetubot [] :2010/01/12(火) 07:40:45
位置行列\Pから点足座標行列\A'で点足単体\P \A'まで出るのはいいが、
点反足座標行列\A'^†で\P \A' \A'^† = \P \A'^† \A' = \Pとなるはずはない気がする、、
355 :neetubot [] :2010/01/12(火) 21:10:52
|[ \~A' ]| ≠ 0 だから普通に点足座標行列\~A'の逆行列\~A'^{-1}出ました。
点反足座標行列\~A'^{-1}=([…,(1-a_i),…] […,1/(n a_i),…]^T - \Σ[…,(1-a_i)/a_i,…])
でした。ちゃんと、(\P \A') \A'^{-1} = (\P \A'^{-1}) \A' = \Pで元の単体に戻ります。
356 :neetubot [] :2010/01/17(日) 01:09:10
点垂足単体の超体積が最大値をとる点はたぶん逆垂心だな。
と書こうと思って放置しとった。今までn次元単体のある内部点
を通して(n-1)次元単体面に作られる図形を点足単体と呼んでいたが、
これを拡張し、n次元単体の一内部点からk次元面に作られる図形を
「n次元単体のk次元点足(_(n+1) C_(k+1)点)複体P'_k」と呼ぶことにし以下に示す。
これで、高々(n+1)点(とその一内部点)が決まれば作れる複体の全てが表せることになる(と思う。)
357+1 :neetubot「n次元単体のk次元点足複体」 [] :2010/01/17(日) 06:01:53
次レスで0次元点足単体から簡単に定義できることを示すが、
あえてここで地道なn次元点足単体からの定義を示す。
まず、m次元ユークリッド空間内で原点からのアフィン独立な
位置ベクトル\p_0…\p_nが表す点が囲むn次元単体を
m×(n+1)行列 \P=[\p_0, …, \p_n] で表す。
ここで、n次元単体\Pの内部点を位置ベクトル \p_a = \P [a_0, …, a_n]^T = \P \a
(内部点なので、\sum_{i=0…n} a_i = \1^T \a = 1、全て a_i ≧ 0)で表すとき、
\Pの頂点\p_iから\p_aを通る直線と \p_i以外の頂点で作られる(n-1)次元単体面との
交点を\p'_{i (n-1)}すれば、全てのi=0…nの点\p'_{i (n-1)}で作られるn次元単体は
(n-1)次元点足複体 \P'_{(n-1)}=[\p'_{0 (n-1)}, …, \p'_{n (n-1)}] と書ける。
また、\p_0から\p'_1を通る直線と \p_1から\p'_0を通る直線の交点を計算すると
\p_2…\p_nで作られる(n-2)次元単体面上の点\p'_{j (n-2)}=\P [0, 0, a_2/(1-a_0-a_1), …, a_n/(1-a_0-a_1)]^Tとなる。
ここで、(n+1)個の成分のうち(k+1)個が1で残り(n-k)個が0の列ベクトルを
全て列挙した (n+1)×(_(n+1) C_(k+1))行列 \~E'_{C_k^n} を定義すると
(例えば、\~E'_{C_1^2} = [[1,1,0]^T, [1,0,1]^T, [0,1,1]^T]となる)、
n次元単体の全ての(n-2)次元単体面上で点\p'_{j (n-2)}のような(_(n+1) C_(n-1))点
\P'_{(n-2)}=[\p'_{0 (n-2)}, …, \p'_{(_(n+1) C_(n-1) - 1) (n-2)}]が計算でき、
この行列\P'_{(n-2)}で表される複体を(n-2)次元点足複体と呼ぶ。
上記のように(k+1)次元点足複体\P'_{(k+1)}が作られると仮定したとき、
例えば元のn次元単体のある頂点\p_i(i=(k+1)…(n+1))と\p_0…\p_kで作られる
(k+1)次元単体面にある\P'_{(k+1)}の頂点を\p'_{i (k+1)}とすれば、
\p_iと\p'_{i (k+1)}を通る直線は全て\p'_{ j k}=\P [0, …, 0, a_(k+1)/(1-a_0…-a_k), …, a_n/(1-a_0…-a_k)]^T
で交わることがわかり「\P'_k = \P \Σ[\a] \~E'_{C_k^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_k^n}^T \a] = \P \A'_k」
が成り立つと言える。
この操作でk次元点足複体\P'_kを作りつづけると、1次元点足単体\P'_1は
元のn次元単体の頂点\p_iと頂点\p_jを結ぶ辺をa_j : a_iに内分する点が頂点
(全部で(_(n+1) C_2個)で、最後に0次元点足単体\P'_0は元の単体自体となる。
358+1 :neetubot「n次元単体のk次元点足複体」 [] :2010/01/17(日) 14:29:32
まず、m次元ユークリッド空間内で原点からのアフィン独立な
位置ベクトル\p_0…\p_nが表す点が囲むn次元単体を
m×(n+1)行列 \P=[\p_0, …, \p_n] で表す。
ここで、ある(n+1)個の定数a_0, …, a_nと添字i,j,l=0,…,nを用いて、
n次元単体\Pの頂点\p_iと頂点\p_jを結ぶ辺をa_j : a_iに内分する点
\p'_{t 1}の全ての組み合わせを頂点とする1次元点足((_(n+1) C_2)点)複体\P'_1を作る。
次に、\Pの\p_iと\p_jと\p_lが作る三角形で、上記\p'_{t 1}と
\p_lの間をa_l : (a_i+a_j)に内分する点を\p'_{t 2}とすれば
(この\p'_{t 2}は、\p_jと\p_lをa_l:a_jに内分する点と \p_iを a_i:(a_j+a_l)に内分する点であり、
またこのとき、\p_lと\p_iをa_i:a_lに内分する点と \p_jを a_j:(a_l+a_i)に内分する点である)、
このような\p'_{t 2}の全ての組み合わせを頂点とする2次元点足((_(n+1) C_3)点)複体\P'_2を作る。
上記のような計算操作で、n次元単体\Pの(k-1)次元点足複体が下式で決定されると仮定すると
「\P'_{(k-1)} = \P \Σ[\a] \~E'_{C_{(k-1)}^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_{(k-1)}^n}^T \a] = \P \A'_{(k-1)}」、
例えばこのn次元単体\Pの頂点\p_0…\p_{(k-1)}と \p_i(i=k…(n+1))で作られるk次元単体面では、
\p_0…\p_{(k-1)}で作られる(k-1)次元単体面上に存在する\P'_{(k-1)}の頂点と
\p_iをa_i:(a_0+…+a_{(k-1)})で内分する点が\P'_kの頂点ということができ全ての組み合わせで
「\P'_k = \P \Σ[\a] \~E'_{C_k^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_k^n}^T \a] = \P \A'_k」と計算できる。
この数学的帰納法で次々に導出できるk次元点足複体\P'_kは、\P'_{(n-1)}=
\P (\a […,1/(1-a_i),…]^T-\Σ[…,a_i/(1-a_i),…])となりこれは確かに前述の(n-1)次元点足単体であり、
\P'_nを最後にむりやり計算すれば単体の内部点\p_a自体となることが導出できる。
以上より、n次元単体\Pが一つ決まれば、定数a_0, …, a_nの値によって、
0次元点足複体\P'_0(元の単体\P自体)からn次元点足複体\P'_n(単体内部点\p_a)まで
一意に決定され、これらのk次元点足(n次元(_(n+1) C_(k+1))点)複体は
n次元単体同様に使いやすく、超体積が簡単に導出できたり、
これら複体は常に外心などを持つなどの美しい性質が期待できる。
359 :neetubot [] :2010/01/17(日) 15:06:22
これらは、
分からない問題はここに書いてね327
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1262413352/260
260 :251:2010/01/16(土) 16:10:07
>>259
よく確認をしたら垂心の考え方を使って垂心hの位置ベクトルoh→を求める問題でした
ご迷惑おかけしました。 問題書き直しましたのでよろしくおねがいします
△abcでa,b,cの位置ベクトルをoa→、ob→、oc→
垂心をh、ahとbcの交点をdとすると
dはbcをtanc:tanbに内分する
またhはadを(tanb+tanc):tanaに内分する点だから(ここでどうしてこのような内分比になるか教えていただけませんか?)
oh→=tanaoa→+tanbab→+tancoc→/tana+tanb+tanc
をn次元拡張して思いつきました。上の場合、ただの平面幾何ですが>>357>>358あたりをふまえれば
2次元単体(鋭角三角形とする)ABCの周囲をそれぞれtanb:tana・tanc:tanb・tana:tancに内分する点で作られる
三角形FDEが1次元点足(2次元3点)複体であり、AD・BE・CFをそれぞれ(tanb+tanc):tana・
(tanc+tana):tanb・(tana+tanb):tancに内分する点が一致し、それは2次元単体ABCと
定数a_0, a_1, a_2=tana/(tana+tanb+tanc), tanb/(tana+tanb+tanc), tanc/(tana+tanb+tanc)
の値によって作られる2次元点足(2次元1点)複体の単体内部点\p_aにほかならないと言えよう。
?計算いいのか?
360 :neetubot [] :2010/01/17(日) 20:45:05
さて、n次元単体\Pのk次元点足複体\P'_k = \P \Σ[\a] \~E'_{C_k^n} \Σ^{-1}[\~E'_{C_k^n}^T \a] = \P \A'_k
のn次元超体積は、k次元点足複体\P'_kの内部には必ずn次元点足複体\P'_n(単体内部点\p_a)
があるといえるので、\P'_kのそれぞれの(n-1)次元面と\P'_nで作られる複体錐を足し合わせることで
超体積求まると思いきや…4次元単体(五胞体)の1と2次元点足複体は↓なので、
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectified_5-cell
4次元までは切頂で超体積求まるのか!?けっこう難しい…あと、外接超球面ではなく外接超楕円面の方が都合良さそう
361+1 :neetubot [] :2010/01/17(日) 22:26:22
m次元ユークリッド空間内でn次元単体\Pの定数a_0, …, a_nの値によって決まる
1次元点足複体\P'_1の超体積 v^n[\P'_1] は、\Pの超体積を単にv^nで表せば、
v^n[\P'_1] = ( 1 - \sum_{i=0…n} \prod_{j=0…n≠i} (a_j)/(a_i+a_j) ) v^n
と書ける、と感じた。これはnは2で1/4, 3で1/2, 4で11/16と、nが大きくなるにつれn次元単体に近づく(!?)
しかし、各頂点周りの単体を取り除く方法はこの1次元点足(n次元(_(n+1) C_2点)複体にしか使えないだろう。
362+1 :neetubot [] :2010/01/18(月) 00:12:23
>>361 の>これはnは2で1/4, 3で1/2, 4で11/16と、nが大きくなるにつれn次元単体に近づく
のは、超体積が最大値をとると思われるa_0=…=a_n=1/(n+1)のときでした。
\sum_{i=0…n} a_i =1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i のとき、
F=\sum_{i=0…n} 2/( \prod_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) ) ≧ (n+1)/(2^n)
(F≦1)を証明…できん…
363 :neetubot [] :2010/01/21(木) 05:58:33
>>362 \sum_{i=0…n} a_i =1 で全てのi=0…nに対し 0≦a_i とすれば、F_0=\sum_{i=0…n} 2/( \prod_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) )
(算術平均≧幾何平均 より、) F_0≧2(n+1)/(( \prod_{i=0…n} \prod_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) )^( 1/(n+1) ))=F_1
(1/(幾何平均)≧1/(算術平均) より、) F_1≧2(n+1)^(2n+3) / ( \sum_{i=0…n} \sum_{j=0…n} (1 + a_i/a_j) )^(n+1)
=2(n+1)^(2n+3) / ( (n+1)^2 + \sum_{j=0…n} (\sum_{i=0…n} a_i/a_j) )^(n+1)=2(n+1)^(2n+3) / ( (n+1)^2 + (\sum_{j=0…n} 1/a_j) )^(n+1)=F_2
(仮定より、調和平均 \sum_{j=0…n} 1/a_j ≧ (n+1)^2 となるので、) F_2 ≦ (n+1)/(2^n) …えっ!?
ムリタポ…