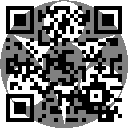364 :猫@2ch数学神 ◇ghclfYsc82 [mail] :2010/01/23(土) 07:19:52
前略、neetubotという猫先生の代理のものです。遅れましたが、代理でメッセージをお伝えします!
------------------------以下、猫先生からのメッセージ--------------------------
今ちょっとプロバイダーの問題でネットが止まっています。現在プロバイダーとやり取りをする
為に準備中で、一時的にネット接続が通っていますがまた直ぐに切れてしまいます。なので
2ちゃんへの書き込みが出来ません。
実はネット接続が切れたのは1月20日(つまり昨日)の午前中で、明日の朝10時にまたネット
の接続が切れてしまうそうです。私としてはきちんと話し合いをして状況を理解してから物事
に対して対応しようと考えていますので、取り敢えずは2ちゃんにはカキコはしない考えです。
とにかく何かとこの世は厄介ですが、毅然とした態度で臨む考えです。
取り敢えずは早急に何とかしてネット接続を確保してから事態を分析しなければならないので、
暫くは2ちゃんではROMになってしまう事を恐れますが、でも私がめげるという考えは皆無な
のでどうかご安心下さい。
なるべく早急に2ちゃんに復活してバリバリとカキコを開始したいと考えています。なので、
もし機会がありましたらこの「私のメッセージ」を2ちゃんの皆様にも貴方様からお伝え下さい。
敬具
猫は淫獣拝
2010年1月21日
------------------------以上、猫先生からのメッセージ--------------------------
私も、猫先生のご復活を祈り、応援しております!かしこ!
365 :neetubot [] :2010/01/23(土) 20:42:11
さて、バカやってないでがんばるか…
m次元ユークリッド空間内でn次元単体のk次元点足複体の各頂点\P'からの
自乗距離が最小になる点は、他ならぬ\P'の重心\p_G[\P']=\P' \1 / (_(n+1) C_(k+1))である。
\P'にk次元外接n次元超楕円面が存在するとすれば、元のn次元単体と
点足単体のk次元外接n次元超楕円面の中心を考えれば、
\P'のk次元外接n次元超楕円面は\p_G[\P']が中心であると考えられる。
それをふまえて、次に、この\P'のk次元外接n次元超楕円面の半径行列を求める。
366+2 :neetubot [] :2010/01/23(土) 21:13:58
正確には、m次元ユークリッド空間U^m内の位置行列\P'で作られるn次元単体の(m≧n≧2)
内部点\p_aによるk次元点足複体\P'_kの(n≧k≧0)のk'次元面(n≧k'≧0)全てに
接する(n-1)次元超楕円面(たぶん、存在するとしたら重心を中心として全ての面の重心で接する)
なので、仮にn次元単体の k次元点足 重中 k'次元面接((n-1)次元) 超楕円面S'_{A_k^k'}^(n-1)と呼…
誰の超スーパー必殺技だよw
367+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/01/23(土) 23:28:30
まったく、もっとまともな議論をしたらどう?
猫とかに構っているとお粗末になるのか?
368 :neetubot [] :2010/01/24(日) 00:03:57
>>367 ん?はじめましてwどんな議論がお望みですか?
猫先生に構ってなかった頃はお粗末ではなかった所までは読んでくれたんですか?
どこまで理解できてますか?
369 :neetubot [] :2010/01/24(日) 00:05:59
>>366 の2行目:k'次元表面
過去ログ見てたらすげぇいかれてるぜw 数学は楽しいなぁ
>>289 より、(n/n') Σ_{i=1…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = \R_Q \R_Q^T
までは見つけた。
370 :neetubot [] :2010/01/24(日) 13:10:33
>>366 の2行目:((n-1)≧k≧0) ((n-1)≧k'≧0)
k次元点足複体\P'_k に対し、そのk'次元表面の重心全てを\P'_{a_k^k'}で表せば、
n次元単体のk次元点足重中k'次元面接超楕円面の半径行列\R_{a_k^k'}に対し、
\R_{a_k^k'} \R_{a_k^k'}^T = (n/n') Σ_{i=0…(n'-1)} (\p'_{i a_k^k'} - \p_G[\P'_{a_k^k'}]) (\p'_{i a_k^k'} - \p_G[\P'_{a_k^k'}])^T
= (n/n') \P'_{a_k^k'} (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P'_{a_k^k'}]^T = \P \X \P^T
となる。このサイクリックな式形からk'の値のみが違うこの超楕円面は全て相似になると推測する。厳密な計算はそのうち…
371 :132人目の素数さん [↓] :2010/01/24(日) 14:22:48
http://www.youtube.com/watch?v=xJMdAcPWs-c
http://www.youtube.com/watch?v=FRqJ2gZYBmA
http://www.youtube.com/watch?v=8gIP4FKjr9Q
http://www.youtube.com/watch?v=LVpydYb1B6E
http://www.youtube.com/watch?v=xJMdAcPWs-c
http://www.youtube.com/watch?v=qxWy19lQyLk
http://www.youtube.com/watch?v=z-SCVL3aZXg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-Tl23hSSiuA&feature=related
372 :neetubot [] :2010/01/24(日) 17:53:33
盛大にAKB48を誤爆しましたねw
誰が好きなんですか?言われてもわかりませんが。
373 :neetubot [] :2010/01/24(日) 20:47:07
k次元点足複体\P'_k に対し そのk'次元表面の重心全てを\P'_{a_k^k'}で表したとき、
\P'_{a_k^k'}の頂点の全てからの自乗距離が最小となる点\p_Xは、F'_G[\p_X]=
\sum_{i=0…n'-1} (\p'_{i a_k^k'}-\p_X)^T (\p'_{i a_k^k'}-\p_X) →最小となればよいので、
\p_X = \p_G[\P'_{a_k^k'}] = \p_G[\P'_k] であり、このときF'_G[ \p_G[\P'_k] ] = n' r_{a_k^k'}^2が最小値となる。
上記は、\P'_{a_k^k'}の全ての頂点は\p_G[\P'_k]からだいたい最小の自乗平均距離 r_{a_k^k'}
(統計学的に標準偏差も定義すれば r_{a_k^k'}±ε_{a_k^k'})の位置にあると見込むことが出来る。
ということで、\P'_kの重心\p_G[\P'_k]を中心とし半径r_{a_k^k'}の超球を仮にk次元点足k'次元面重重均超球S_{a_k^k'}と呼ぶ。
点足複体の関係で美しい性質を持つと考えられる概念は今の所はこれぐらいです。不等式の玉手箱や~
374 :neetubot [] :2010/02/05(金) 00:02:55
n次元単体\Pに対して(その同じ部分空間内の)点\p_a = \P \a(ただし、\1^T \a = 1)を使って
点足単体\P_A=\P \Aの点足単体\P \A \Aの点足単体\P \A \A …と無限回繰り返して
作られる点足無限単体は \P \A^∞ = \P \a \1^T と収束するはずなので、点足k回単体と同じ部分空間内の
どんな点\P \A^k \b / (\1^T \b)でも点足無限収束点は \P \a自身であると考えられる。
上記をふまえて、点反足k回単体 \P \A^(-k) に対してその同じ部分空間内の点\P \A^(-k) \b / (\1^T \b)
を定義したとき、点反足無限単体に対してこの点反足無限発散点\P \A^(-∞) \b / (\1^T \b)はどこに行くだろうか?
\A^Tを固有値分解(ひとつは固有値1に対する固有ベクトル\1とか)できれば求まる気がするんだけど…朝青龍…
375+1 :neetubot [] :2010/02/28(日) 02:44:29
↑はまだ計算できてはいませんが、\P \A^(-∞) \bは\P \a と \P \b が通る直線の無限遠点だと思います。
ところで、全てのn次元単体は、n次元正単体を剪断拡縮・回転・平行移動して作られることから、
このスレではその座標行列である(n+1)×(n+1)アフィン変換行列(群?)全体の性質を調べていたようです。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1267096322/67
> http://anond.hatelabo.jp/20100226161245
> 数学的には何もない空間は何次元になるんですか
というとても興味深いレスを発見し、このスレでもどこかで便宜上-1次元を使った
記憶もありますが、1次元増やして計算する斉次座標系というかアフィン変換で
n次元部分空間というかm次元ユークリッド空間全体考える時に垂直で常に存在する虚軸を
一本入れて常に1次元増やした系で計算するとうまくいきそうで、今ちょうど計算してます。
ということで、上記の質問に関して、何次元だろうが何もない空間は普通にいくらでもありますが、
美しく考えるためにどうしても必要だと思われる-1次元単体というものが何を表しているか
という質問だと思えば、何もない空間か無限遠全体の空間か虚軸方向も入れて何か定義するか
、特に先行研究に思い当たる節がないので、今自分で考えるところです、みたいな感じです。
まぁ、みなさんは興味ないかもしれませんが、n次元単体の重中k次元面接超楕円面の証明に
オイラー公式やリーマン球っぽく個人的趣味でどうしても虚軸方向を加味したいので、
まぁ、うまくできたらUPします。実数体でなく複素数体で考えたら、頭がフットーしそうだよおっっ(
376 :neetubot [] :2010/03/02(火) 22:55:40
>>375 は別に虚軸じゃなくて、もととなるm次元ユークリッド空間の1軸からm軸まで
全てに垂直な実数の0軸を入れて考える、つまり、普通の斉次ベクトルで考えた方が、
複素数体に拡張するときにもいいと思うので、そうします。っていうかそっちのが計算しやすかった。
座標の斉次と違って計算に一時的にしか出てこないし、これが射影幾何学のように
分母になるための項だと言えるなら、そのときは私も斉次も同次も同じだと主張します。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1261794262/291
の二つの二次曲線の交点の問題ですが、二つの二次曲線をそれぞれ
線型化したときの係数ベクトルを \a=[a, b, c, d, e, f]^T, \a'=[a', b', c', d', e', f']と
すれば、二つの二次曲線両方の上に存在する点 \x=[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^T に
対し、次の自乗和の式 α(\a^T \x)^2 + α'(\a'^T \x)^2 がこのとき最小値0をとる。
ということで、上式の\xについての最小自乗法から(\a α \a^T + \a' α' \a'^T) \x = \0
となる \x で各成分が条件[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^Tを満たすものが最大4点あるらしいと…
これじゃ4次方程式どころじゃねぇ解けねぇ。という2ch復活記念カキコ
377 :neetubot [] :2010/03/02(火) 23:01:47
最小自乗法じゃなくても連立方程式から [\a, \a']^T \x = \0
となる \x で各成分が条件[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^Tを満たす…と同じことでした。
意味もなく難しく言っちゃった。てへっ。しかし、以下同文です。
378+2 :neetubot [] :2010/03/07(日) 22:33:44
連立方程式から [\a, \a']^T \x = \A^T \x = \0 より、固有値分解によって得られる
\Aに直交する\Bを介して \x = (\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T) \y = [\b_1, \b_2, \b_3, \b_4] \t
= [\s_1, …, \s_6]^T \t と表せば、[x^2, x y, y^2, x, y, 1] = [\s_1^T \t, …, \s_6^T \t] であるので、
直交行列\Bの4変数の座標\tに対して、下記の\tについての4式
\t^T \s_4 \s_4^T \t = \s_1^T \t
\t^T \s_4 \s_5^T \t = \s_2^T \t
\t^T \s_5 \s_5^T \t = \s_3^T \t
1 = \s_6^T \t
のような四元二次連立方程式を解くことに帰着できる。
と、ここまでです。この4式から、線型変換で一元四次方程式を解くことに帰着するか、
あわよくば非線型変換で四元一次連立方程式にでもなればと思ったのですが…
1 = \s_6^T \tはオフセット付3次元部分空間(アフィン空間?)だから、\tの解を3次元正単体の
アフィン変換で表すとしたら解が4通り出るのが謎としても、二次形式の拡大係数行列
自体のアフィン変換で単位超球や超平面に帰着するとかかな、難しいなー
379+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/07(日) 22:41:23
非線型は解法を知らないと難しいですから
たしか以前に、非線形連立を線型連立で解こうとしてましたよね?
380 :neetubot [] :2010/03/13(土) 21:42:11
>>379 おっ、いつのまに、、知ってる方のようですのでお久しぶりです。
>>378 の件と思いますが、二次までなら線型化でいけると思いきや、
例えば二次曲線 \a^T \x = 0 で 座標 \x=[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^Tの点列から
一通り求まるような係数 \a=[a, b, c, d, e, f]^Tを当嵌するのは >>263-265 あたりでうまくいきましたが、
今回の件は、2つの二次曲線の係数 [\a, \a'] = \A から交わる点の座標を求めるということで、
\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T = \B \B^T と直交行列を求めれば >>378 の式形から
\x = \B \t / (\e_6^T \B \t) さらには \x = \B \C[\B^T \Λ \B] \1 / (\e_6^T \B \C[\B^T \Λ \B] \1)
のような形に導出できそうな気がしてます。
まとめると、線型化した座標の方の導出はそれ自身に条件が入るので難しいと思っている、ということです。
しかし、二次までの幾何学ということで、固有値問題などに帰着すれば美しい解法はあるもんだと思ってがんばってます。
>>379 さん、何か非線型な行列方程式の解放などご存知でしたらご助言頂けるとありがたいです。
381+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/13(土) 22:13:06
お聞きしたいのは私の方なんですが、そうですね…その行き詰まり方だとケーハミ定理の復習ですかね(affineも考えると3x3)。
線型と累乗を深く理解できるようになるでしょうね。
普通は3x3をちゃんと勉強することもないと思いますが…
382+1 :neetubot [] :2010/03/13(土) 23:00:34
数学系質問掲示板について語るスレ2
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1206831469/911
楕円面の族
2010年03月08日 12:13:44 KM
お願い致します。
x^2 + 2*y^2 + 3*z^2 + w^2 = 1, 3*x + 2*y + 3*z + 5*w = k
の交わりをx,y,z空間に正射影し、
(1)得られる曲面が楕円面になるkの範囲を定め
楕円面の主軸を求めよ。
(2)上の楕円面の族の包絡面を求めよ。
(3)楕円面が点に退化するようなkを求めよ。
という、4次元ユークリッド空間内で、3次元超楕円面と kで定まる3次元超平面
との共通部分(前者を後者で切った断面)をx,y,z空間に正射影したもの
(w=(k - 3*x - 2*y - 3*z)/5 を前者に代入しwの成分を消したもの)の問題を解きます。
(1)、後者をベクトル[x,y,z,w]=[3t,2t,3t,5t]の点を通りそのベクトルに直交する
3次元部分空間と考えれば、(3t)^2+2(2t)^2+3(3t)^2+(5t)^2 = 69 t^2 = 1より
-1/(√69) < t < 1/(√69) が求めるものなので、-47/(√69) < k < 47/(√69) ■
で共通部分が楕円面となるが、この楕円面の3つの軸はアレじゃないですか…
(2)、3次元超楕円面の周囲をくまなく3次元超平面で輪切りにしてx,y,z空間に正射影
してるだけなので、求める2次元楕円面は x^2 + 2*y^2 + 3*z^2 = 1 で表せる ■
(3)、(1)より k=±47/(√69) ■
ということで私は、全ての二次超曲面は、超球面を透視投影すれば得られると思って
ますが、まぁ同じことですが最近は、n次元ユークリッド空間内の(n-1)次元超球面を使って
直交する0軸方向に超球錘を作り、それをアフィン変換したものと元のn次元ユークリッド空間
との共通部分(断面)によって全ての二次超曲面が表せると考えた方が都合良さそう
と思いました。というのは、今後、二次超曲面と超平面の共通部分や最小最大距離を
考えるための備忘録として、ここに書きました。とりあえずゴメンナサイ
383 :neetubot [] :2010/03/13(土) 23:14:23
>>381 コメント速いっすねー 私が遊んでる間に…
>>378 では\x = (\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T) \y = [\b_1, \b_2, \b_3, \b_4] \t / (\s_6^T \t)
とおいた瞬間に、普通に二次曲線同士の交点を求める四次方程式が
固有値分解をすることに帰着されたと私は信じたいので、あとは定数倍が関係ない
\t^T \s_4 \s_4^T \t = \t^T \s_6 \s_1^T \t
\t^T \s_4 \s_5^T \t = \t^T \s_6 \s_2^T \t
\t^T \s_5 \s_5^T \t = \t^T \s_6 \s_3^T \t
の3式を満たすように \tの3変数分を解けば、きれいな公式が作れる気がしてます。
いやほんとに \x = \B \C[\B^T \Λ \B] \1 / (\e_6^T \B \C[\B^T \Λ \B] \1)
の形で(\C[]を余因子行列として)6×6制約行列\Λに3変数分入って4通り導出できると
私は信じて疑わない!と言っていてもあとで式から覆ることが何度もあるこのスレ
384+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/13(土) 23:30:35
>>382
ガウス先生は複素数根の真意を悟った者がまた一人増えたので大喜びでしょうね。
385+1 :neetubot [] :2010/03/14(日) 01:12:50
>> ケーハミ定理って略は初めて聞きました。n次元拡張もなら↓が詳しいです。
Cayley?Hamilton theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Cayley%E2%80%93Hamilton_theorem
しかし、私的には使うと逆に式が長くなるという印象があり、ぶっちゃけ使い方よくわかりません。
というのも、固有値分解(特異値分解)は、ある部分空間に直交する部分空間
を求める場合などに、ソフトで出せる固有値と固有ベクトルとかのセットで出せば、
それが幾何学的に何を表しているか想像や図示できるような感じですが、
こと固有値を求めるための固有方程式(とそれを応用したケーハミ定理)については
幾何学的に全く想像ができないからです。
このスレでも、>>235 あたりで非斉次行列多項方程式を解くみたいな事やりましたが(!?)、
同じアフィン変換を何回もかけるとかじゃなく、n×n行列をn回かけるというような状況でもなく、
今回ただの二次形式なのでいける気がしてますが、今までにこれらをベクトルで定式化した
という話は聞いたことがないので、実際やれと言われたら地道に4次方程式解く方法で私もいくと思います。
>>384 複素数根の真意なんて滅相もございません。とりあえず二次超曲面と二次超曲面の共通部分考える
前に、二次超曲面と超平面の共通部分(たぶん二次超曲面)を考えたほうがいいとわかった、いい問題でした。
386+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/14(日) 07:27:52
>>385
A X + B = C #=>mat
X = A^-1 (C-B) #=>mat
A X A^1 = (C-B) A^1 #=>mat
(A X + B)(u) = C(v) #=>vec
387 :neetubot [] :2010/03/20(土) 00:16:49
>>386 ?2つの二次曲線の交点のベクトル解の定式化ですか?
たぶん2次拡張座標の方を X = [x, y, 1]^T [x, y, 1] のように3×3行列化する
まだ私は考えたことがない方法のようでしたので、少し考えました。
まず、全ての二次曲線が [a_1, a_2, a_3] [x, y, 1]^T [x, y, 1] [a_4, a_5, a_6] = 0
の形で表すことができるかですが、[x, y, 1] A [x, y, 1]^T = [x, y, 1] [a_1, a_2, a_3]^T [a_4, a_5, a_6] [x, y, 1]^T
と分解できるためには拡大係数行列 A の階数が1でなければならないので無理でした。
また、Xを上三角行列などのよく見る形にしようとしても、係数の自由度が足りず
任意の二次曲線を表す形にはできませんでした。A X の形には9つの等式が必要で無理です。
ということで、座標から係数出すとき使った[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^T [x^2, x y, y^2, x, y, 1]を使うのか…
余計大変です。[x^2, x y, y^2]^T=\B_{上} \t と [x, y, 1]^T=\B_{下} \t で分けるんじゃね?
870 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/19(金) 00:15:37
>>833
>>842
長い間2元2次交点の難問に付き合っていただきありがとうございます。
ベクトル空間(体はC^1など)で考えていたのでその完全な証明は幾何ベクトルを使った証明で知っていましたが、
解法の1つとして、行列成分(行列式)として扱った場合の根(この場合は交点)の最適な配置場所がわかりませんでした。
行列による解法は別のアプローチを研究中ですが、余因子展開の方法もじっくり検討してみます。
また良い問題をありがとうございました。
俺も興味あるし、このスレで一緒に考えようぜっ!
とりあえず、四次方程式の解法・解の公式は↓が詳しいよ。
http://www.akamon-kai.co.jp/yomimono/kai/kai.html
388 :neetubot [] :2010/03/20(土) 00:26:47
とりあえず、↓の人、超好きです。
分からない問題はここに書いてね329
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1267096322/842
842 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/18(木) 18:38:41
>>833
n*n行列で考える
xI_n-A_n = B_n = [
[x-2,-1,0,...,0]
[-1,x-2,-1,0,...,0]
[0,-1,x-2,-1,0,...,0]
...
[0,0,0,......,0,-1,x-2]]
を余因子で展開すると
|B_n| = (x-2)|B_{n-1}| - |B_{n-2}|, |B_1|=x-2, |B_2|=(x-2)^2-1
だからx-2=2cosθとおけば帰納的に|B_n|=(sin(n+1)θ)/sinθが得られ
A_nの固有値λ_kとその固有ベクトルu_kはλ_k=2+2cos(kπ/(n+1)),
u_k=t[sin(kπ/(n+1)),sin(2kπ/(n+1)),...,sin(nkπ/(n+1))]
(k=1,2,...,n)
n=4の場合の固有値は{2+2cos(kπ/5)|k=1,2,3,4}={(5±√5)/2,(3±√5)/2}
この行列、何か名前ついてなかったっけ?
(n+1)×(n+1)行列で考えたときどんな図形の座標を表すのかとか、
3次方程式を三倍角の公式に帰着するようにn次方程式をn倍角に…(それは無理か…)
とか興味深い行列!バンデルモンドだっけ?(適当)
389 :neetubot [] :2010/03/20(土) 18:53:00
異なる二次係数 \a, \a' で表される二次曲線の交点(x, y)を求める問題を、
[\a, \a']^T [x^2, x y, y^2, x, y, 1]^T = \A^T \x = [0, 0]^T と定式化すれば、
\x = (\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T) \α = [\s_1, \s_2, \s_3, \s_4, \s_5, \s_6]^T \t / (\s_6^T \t)
と表せて、二次拡張座標 \x 自身の制約から(中身が対称行列となるように変形すれば)
\t^T (\s_4 \s_4^T - (\s_6 \s_1^T + \s_1 \s_6^T)/2) \t = \t^T \F_1 \t = 0,
\t^T ((\s_4 \s_5^T + \s_5 \s_4^T)/2-(\s_6 \s_2^T + \s_2 \s_6^T)/2) \t = \t^T \F_2 \t = 0,
\t^T (\s_5 \s_5^T-(\s_6 \s_3^T + \s_3 \s_6^T)/2) \t = \t^T \F_3 \t = 0 の3式が
成り立たなければならない。これは、3つの決まった4×4変換行列 \F_1, \F_2, \F_3をかけた
ベクトルが元のベクトルと全て垂直となるような4次元列ベクトル \t を求める問題に帰着できたことを表している。
つまり \t は、\F_1 \t = \0, \F_2 \t =\0, \F_3 \t = \0となるkernelの共通部分、
よって、[\F_1^T, \F_2^T, \F_3^T]^T \t = \0 で \s_6^T \t = 1 となる \t に対して
[x, y]^T = [\s_4, \s_5]^T \t のように解ける?と思いきや、これでは解が一通りに定まって
しまうような感じで とても4通り求まらないので、どこか2段落目とかでおかしいことやらかしたな…
とはいえ、あとは通常の4次方程式に帰着する計算と整合性を付ければいいような気がするので、
この解き方ではこれが限界かなぁ。
同じように4次方程式に帰着できる「二次曲線とある点との距離(およびある点を通る接線)」
「n次元単体の等角中心」の問題とともに、これからもこの問題は私のタスクリストに入れときます。
390+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/20(土) 19:10:27
タスクリストってのがるんですか。
同じように4次方程式に帰着できる
「二次曲線とある点との距離(およびある点を通る接線)」
「n次元単体の等角中心」
「二次曲線の交点(x, y)を求める問題」
他のタスクは何かあるんでしょうか?
391+5 :neetubot [] :2010/03/20(土) 20:46:04
ちなみに、二次超曲面とある点との距離(およびある点を通る接線)は…
と書いてるうちにコメントが来ました、ありがとうございます!
>>390 漠然と自分の中で考えてるだけでしたので、ここでちゃんとリスト化します。
1:アフィン変換とSimplex Steiner Hyperellipse(5月31日迄)
(始点が同じ(n+1)単位行列で表されるベクトルの終点全てはn次元正単体となり、
そのn次元正単体の重心まわりのアフィン変換で全てのn次元単体が表せることを用いて、
全てのn次元単体にはその重心を中心とし各k次元面に接するような超楕円体が存在することを示す)
2:n次元単体の五心と平石究点(ナルハヤ)
(2次元単体(三角形)と同じように、n次元単体にも五心(重心・垂心(存在条件あり)・
広義傍心(内心含む)・k次元面心(k=1…(n-2) 存在条件あり)・外心)が定義でき、
特に重心と外心を結ぶオイラー線上に広義垂心や様々な性質を持つ点が存在することを示す。)
3:n次元単体の諸性質の応用
(アフィン独立な(n+1)点と一定の距離比にある分点心と一定の距離差にある部分境界超平面の関係・
従属な1点を加えたときに外接超球が存在する条件(複体外接超球)・n次元単体とそのある内部点
で一意に決まる点足複体の超体積や無限収束点や外接楕円体などの諸性質など)
4:二次超曲面と解析射影幾何学
(二次超曲面上のある点での接空間およびその中のある接線方向に対する曲率半径・
二次超曲面とある点の距離との距離(およびある点を通る接線)・二次超曲面とある
超平面の共通部分と超球錐の図との関係・「二次曲線同士の交点」(←new!))
5:数学板の気になった問題を解く
ぐらいですか。。最近、5しかやってねぇ!というわけでもない、ゆっくりしていってね!!!
392 :neetubot [] :2010/03/20(土) 20:54:57
n次元単体の第6心の等角中心(Simplex Fermat-Torricelli Center)
略して単体角心を忘れてました。結局3かもしくは4と関係するならとても嬉しいという感じです。
一応、3次の項がない 下記の一元4次方程式 を解くことに帰着できているつもりです。
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/22.html
ここらへんは、一つのアイディアで芋づるだなどと思って、保留してます。俺人生保留中
393+2 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/20(土) 21:37:29
三線座標と重心座標(12)
三角形の中心
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%8E%A5%E5%86%86
とかはやらないんですか?
それと、離散ついでで整数(4)やベクトル(36)は関係してないんですか?
というよりも「面積」のことが良く分かってないみたいで、幾何学上の面積すら意味付けが出来てないって感じですけど・・・
えぬ次元というからには、ABC3点を通る外接円の外心点のベクトル式はすぐ求められますよね。そういことじゃないんですか?
394+1 :neetubot [] :2010/03/20(土) 23:59:46
>>393 面積(2次元超体積)がわからないんですか?http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D
ここでは、n次元単体の超体積 http://en.wikipedia.org/wiki/Simplex#Geometric_properties
がわかっているとして話をしますが、まず↑より、m次元ユークリッド空間内で原点からn次元単体の各i頂点
(i=0…n)への位置ベクトルを \p_i で表せば、正方行列\Xの余因子行列を\C[\X]としたとき 定義より
n次元単体の超体積 v=√(det([\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0]^T [\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0])) / (n !)
=√(\1^T \C[0, \0^T; \0, [\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0]^T [\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0]] \1)/(n !)
=√(\1^T \C[ [\p_0, \p_1, …, \p_n]^T [\p_0, \p_1, …, \p_n] ] \1) / (n !) と表せます■
(ちなみに、超体積の意味は、方向行列の内積行列の行列式の平方根に比例する量であり、
図形自体の大きさを示す、昔の人がうまく定義した計量だと思いますw いいものですね)
で、三角形の重心座標ですが、このスレでは拡張してn次元単体の分積座標と呼び、>>282あたりでやりました。
分積座標\aは、n次元単体のあるi頂点(i=0…n)以外のn個の頂点で作られる(n-1)次元単体面をi対面と呼べば、
n次元単体の内部点 \p_A = \p_0 a_0 + … + \p_n a_n (全てのiでa_i>0)と例えば0対面で作られる
内部n次元単体の超体積 v_0 は、内部の列や行の足し引きで値が変わらない行列式の性質から
v_0 =√(\1^T \C[ [\p_A, \p_1, …, \p_n]^T [\p_A, \p_1, …, \p_n] ] \1) / (n !)
=√(\1^T \C[ [\p_0 a_0, \p_1, …, \p_n]^T [\p_0 a_0, \p_1, …, \p_n] ] \1) / (n !) = a_0 v
となり、これは\p_Aの絶対分積座標の値a_0が内部超体積と元の超体積の比v_0/vとなることを表しています。
続きますー
395+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 01:27:31
「図形」の「大きさ」ですか。
では「角度」はどうやって定義して、表現してるんですか?
それと、位置ベクトル(普通の[a,b,c]のやつ)と行列(正方n x nやm x n)に何かしらの違いを見出しているか否か?
群は =>matのみか、=>vecのみか、=>mat or vecを考えているかなど何かしらの自分の公理を定義して「交点を出す」「面積を出す」のに適したなどの目的・目標を定めて計算してるんでしょうか?
それとも何らの目的も無くただ行列計算(一次変換)したいだけの「超」一般化なんですか。
396+2 :neetubot [] :2010/03/21(日) 01:40:36
>>393 また、三角形での三線座標・四面体での四線(面?)座標は、このスレでは拡張してn次元単体の分面座標と呼んでいます。
定式化は、i対面からの距離がそれぞれj_iとなるn次元単体の内部点を分面心 \p_J と呼ぶと下式のように導出できます。
まず、i対面と分面心 \p_J で作られる内部n次元単体のn次元超体積v_iは元のn次元単体の超体積vの
j_i / √(\h_i^T \h_i)倍(\h_iはi頂点からi対面への垂線ベクトル)となっているので、>>394 の分積(重心)座標より、
\p_J = \p_0 j_0 / √(\h_0^T \h_0) + … + \p_n j_n / √(\h_n^T \h_n) と導出できます。
(このとき、v_0+v_1+…+v_n=vであるため j_0 / √(\h_0^T \h_0)+…+ j_n / √(\h_n^T \h_n)=1
となる(絶対分面座標の条件))
これらは http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_center#Trivia の範囲であり、>>391の2か3かトリビアです
>えぬ次元というからには、ABC3点を通る外接円の外心点のベクトル式はすぐ求められますよね。そういことじゃないんですか?
そういうことですよ。そのWikipediaの外接円の式は、岩波数学辞典にも載っていますが、拡張性に優れず、私はあまり好きじゃないです。
このスレでは、古いですが http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html などから、(m次元ユークリッド空間内で)
原点から\P = [\p_a, \p_b, \p_c]の終点で作られる2次元単体ABCの外心\p_Oについて下記のように導出します。
まず、(\p_a - \p_O)^T (\p_a - \p_O) = (\p_b - \p_O)^T (\p_b - \p_O) = (\p_c - \p_O)^T (\p_c - \p_O)
= r_O^2 (外接円の半径の自乗) から、例えば\p_a^T \p_a + (\p_O^T \p_O - r_O^2) = 2 \p_a^T \p_Oとなるので、
[\p_a, \p_b, \p_c]^T \p_O = \P^T \p_O = [\p_a^T \p_a, \p_b^T \p_b, \p_c^T \p_c]^T/2 + \1 (\p_O^T \p_O - r_O^2)/2
で、ごにょごにょして
\~b_σ = [(\p_a^T \p_a)/2, (\p_b^T \p_b)/2, (\p_c^T \p_c)/2]^Tとすれば、
\p_O = \P (\C[\P^T \P] \1 + \~C[\P^T \P] \~b_σ) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)と導出できます。
このとき、外接円の半径 r_O は だいたいhttp://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html のようにごにょごにょです。
ごにょごにょの部分は明日のこの時間までに http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html あたりをいじって報告します
397 :neetubot [] :2010/03/21(日) 02:38:41
>>395 一般的に単位ベクトル\l_1,\l_2同士の「角度」は内積値のアークコサインθ=Cos^{-1} (\l_1^T \l_2)じゃね?
この場合の「面積」なら(√det[[\l_1,\l_2]^T [\l_1,\l_2]])/2=(√det[[1, cosθ], [cosθ, 1]])/2=|sinθ|/2となる
(単位円内の2半径が作る三角形の面積を求めた)し。えー何が言いたいかというと、「面積」「角度」は普通の
ユークリッド空間で使われるものと同じで、それじゃない定義や意味(n次元超立体角とか自分で定義すること)は
今のところないです。別に普通の高校生が直交座標系でやってることと同じというか(まぁ行列計算は使いますが)
私はほとんどベクトルを列で表しますし、行列は列ベクトルを行方向に並べたもの(方向行列\Lとか)として使う場合もあれば、
ある意味を持った変換行列(特に正射影行列\W=\L (\L^T \L)^{-1} \L^Tとか)として使うこともある感じですか。
いや、行列はただの入れ物としてその都度幾何学的意味があれば勝手に名前つけて呼んだり、いろいろ考えます。
アフィン変換群としてなら(n+1)×(n+1)行列で、m次元ユークリッド空間内で位置ベクトル\pや方向ベクトル\lなら
m次元列ベクトル、その中でn次元単体を表すアフィン独立の位置行列ならm×(n+1)行列\P・線型独立の
方向行列ならm×n行列\Lと言うような名前と記号を付けてますね、計算しやすいように。
>何かしらの自分の公理を定義して「交点を出す」「面積を出す」のに適したなどの目的・目標を定めて計算してるんでしょうか?
普通の「ユークリッド空間内で」と前置きすることによって、天下りするユークリッドの公理を基に、
普通の行列計算がうまくできる普通の直交座標系で、「n次元単体の五心を出す」とか >>391 に例示した
いろいろな幾何学的性質を普通のユークリッド空間内で行列計算によって美しく解くというのが目的・目標です。
398 :neetubot [] :2010/03/21(日) 02:47:28
>それとも何らの目的も無くただ行列計算(一次変換)したいだけの「超」一般化なんですか。
?確かに俺は行列の式に美しさを感じる変態で、幾何学的な量を導出するための行列計算はホントに美しいぜw
しかし、目的はあくまで幾何学的性質を一発で導出するための定式化で、そのための行列計算はただの必要な手段にすぎません。
まぁ、あんまり深く考えずに、ネットで見つからないんだけど、こんな感じでできるんじゃねーのって公開してるだけじゃね?
コンピュータチェビチェフさんの目的は何ですか?おやすみなさい。
399+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 14:41:54
ん?何か誤解しているようですね?w
「超」とか付いてると見てるほうも何をやってるかさっぱりで、スレにコメントも少なく、
当の本人もなんだか分かってないまま目標もあまりない見たいなんで、少しダメ出ししてやらないとなぁ…って感じでしたけどw
私はいつもは横ベクトルを使いますけど、A dot transopose[B]
ニートさんは普段は縦ベクトルなんですか。なら何も成分表示にこだわらず、transopose[B] dot Aと表記すれば十分な感じですが…
確かマテマテカとかマキシマとか扱えたですよね?成分のときはPCやテキスト表記で面倒が無いようにしてるので具体的に計算するときは
例えば教科書にあるような通常の A x = y は x A = y となり x = y . inverse[A] です。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=-%7B%7Bu%2Cv%7D%5D+%2B+%7B%7Bx%2Cy%7D%7D+.+inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D
行列式化(det)など成分表示で意味があるときは当然必要ですが、そうでないなら体を自分で定義して四則で十分で成分はまったく気にかけなくていいかなって感じです。
行列で突き進むなら普通に環ですし、数学畑の人は多項式で突き進むのでしょうし、ベクトルの割り算を頑張って定義してる人も多いですが、それぞれにその公理と演算の目的があります。
成分表示したところで有限次元なわけで「超」とかいいつつも成分に依拠しているなら実際は一般化しているわけでなく2、3、4元と同じです。
しかも行列写像なのに #=> vec が中心ならそれって行列演算じゃなくてベクトル演算(一次変換とも言う)じゃないのかなーってな感じですがいかがですか?
また成分表示ならそのための中心となるベクトル(原点)があるわけですが、その中心は別の原点を基点として求めるなら堂堂巡りですよね?
私なんか環どころは「+」とスカラー倍しかないんでかなり辛いです…T_T
…しかしこのモデルはコンピュータの理論構造(但しカウンティングの場合)と同じだったりします。
400+2 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 15:20:40
一次変換はもう高校じゃやらないから別の言い方の方がよかったかな。
一次変換じゃなくて、行列の積(写像)に関心があるならその「超」で整合するんですが、そうすると行列の「積」の定義とその意味付けの議論です。
旺盛な探究心をお持ちならテンソル積なんかもここと同じでしょうか。
ベクトル空間で自分行列の体のため演算「積」について、自分数学で自分計量で必要となった「積」の定義と自分解釈意味付け
ってことです(通常は行列は環で定義して、「割り算」は現在では逆元A^-1でごまかしますが)。
このとき行列の成分に関心を寄せる必要はまったくありません。
えーなんでしたっけ?……角度ですか?
「角度」を未だにrad, atan, acosとかいってるようではたいした抽象かも出来てないようです。
このままではニートさんは現在自分数学を構築しているにもかかわらず日本数学(積分微分定義が多い)や高校数学(一応radだけど「角度」の定義すらなく曖昧)から脱皮できないと思います。
ただ、「角度」をちゃんと理解して使いこなせるようになるには5年以上必要ですからね…w
私が見たところあなたがやりたいのは、mathematics(数理)じゃなくてarithmetic(算術)だと思います。
401+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 15:26:23
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B%7Bx%2Cy%7D%7D+.+inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D
http://www.wolframalpha.com/input/?i=inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D+.+%7B%7Bx%2Cy%7D%7D
402+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 15:28:12
こっちだった
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B%7Bx%2Cy%7D%7D+.+inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D
http://www.wolframalpha.com/input/?i=inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D+.+%7B%7Bx%7D%2C%7By%7D%7D
403 :neetubot [] :2010/03/21(日) 18:14:26
>>399-400 終始煽り口調なので、まだざっと読んだだけですが、3点気になりました。
>私が見たところあなたがやりたいのは、mathematics(数理)じゃなくてarithmetic(算術)だと思います。
簡単に言えば、私が「理論屋ではなく計算屋ですよね」、って話だと思いますが、一目瞭然まったくもってそのとおりです。
理論は面倒くさいので、ユークリッド空間内と前置きすることで、実数体上とか明示しないで複素数使っても知らんぷりです。
抽象か具体かといえば具体ですし、ただの立体解析幾何学を一般化した線型代数の練習問題ぐらいなもんですか。
>「角度」を未だにrad, atan, acosとかいってるようではたいした抽象かも出来てないようです。
例えば、ユークリッド空間内で2つの超平面が成す「角度」をあなたならどう定義しどう導出しますか?
天下った式を使う身分で恐れ多いことですが「面積は外積みたいな行列式に関係する計量です」と言うのは
いいとしても、こと「角度」をn次元に一般化するのは内積以外にもいろいろ考えられると思いますし、
特に角度ということで使う需要もないので、普通に考えたら内積に関する計量じゃねくらいな勢いです。
>横ベクトルがいい、成分表示をするな、ベクトル演算と呼べ、wolframalpha記法を使え
参考にします。主に「行列なら環だろ?」という話だと思いますが、アフィン変換といえど1次元拡大して平行移動も含め
演算は乗法一本でいくので n次一般線型変換群 のようにあえてアフィン変換群(モノイドかな?)と呼びました。
群論とか素人ですが、一部の分野の人には↓のような記法を使った方がわかりやすいかと思って、手を広げてます。
http://pantodon.shinshu-u.ac.jp/topology/literature/matrix_group.html
「スレにコメントも少なく」の部分は、式や根幹に関わる批評はあまりないので、ほのぼのやってます。
あとは、当然人間分からない部分も勉強してる部分もあるが ある程度分かってなきゃ定式化なんてできねぇぜってことと、
目標はとりあえず >>391 ということと、あなたの趣味趣向は垣間見えるが ダメ出しの部分があまり見えないということですか
404 :neetubot [] :2010/03/21(日) 18:21:43
>>401-402 は横ベクトルも縦ベクトル表記も転置すれば同じということを伝えようとしましたか?
transpose[inverse[{{a,b},{c,d}}] transpose[{{x,y}}]]={{x,y}} inverse[{{a,c},{b,d}}]
http://www.wolframalpha.com/input/?i=transpose[inverse[{{a%2Cb}%2C{c%2Cd}}]+transpose[{{x%2Cy}}]]%3D{{x%2Cy}}+inverse[{{a%2Cc}%2C{b%2Cd}}]
Trueとか出るんすね。マセマティカは昔使いましたが、便利ですね。
405+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 20:36:36
ずいぶんとダメ出ししてもらえたようがが・・・
406+1 :neetubot [] :2010/03/22(月) 01:38:28
>>405 横ベクトルがいい、成分表示をするな、ベクトル演算と呼べ、wolframalpha記法を使え などは、
個人の趣味趣向の範疇であり、根幹に関わる批評ではないと見たので、ダメ出しと大言壮語するからには
どこがダメでどうしてほしいか、簡単な事やトリビアではなく、根幹について何か言ってほしいなと思っただけです。
「角度」が何だって??
>>396 の件で外心について http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html を改変しました。
ごにょごにょはまた明日にするとして、n次元単体に対して、普通の分積座標で表される内部点\P \aから
i対面に下ろした垂線の足が\P (\E - (\~C[\P^T \P] \e_i \e_i^T)/(\e_i^T \~C[\P^T \P] \e_i)) \a
と表せることがわかりました。良かった。。
407+1 :132人目の素数さん [] :2010/03/22(月) 01:51:09
ニ、ニ、ニートが発狂したぁぁぁ!!
408+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 01:56:52
>>406
このスレでいくらかコメントしてくれた人がいると思いますが、その方々と同じようにその人もあなたに対してコメントすることはもう無いと思いますよ。
409+2 :132人目の素数さん [] :2010/03/22(月) 02:21:11
「超」とか逝ってるけど、ここは高校受験用ベクトル問題集の写本スレだろ(笑)
410+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 02:29:09
だなw
411+1 :132人目の素数さん [] :2010/03/22(月) 02:57:31
ここはただのキチガイのスレだったのか・・・(しかもニート)
412+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 11:34:54
>>409
だなw
413+2 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 13:02:02
??
高卒ニート専用の隔離スレじゃなかったの?w
414+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 17:54:28
さっき「タミフル~」とか叫びながら窓から飛び降り自殺したらしい
見えない敵と戦いすぎたらしくて「ボクにはタミフルを倒せませんでした生まれてきてごめんなさい」とかなんとか言って生き絶えたって話し
415+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 19:19:27
ついに死んだのか
416+2 : ◆27Tn7FHaVY [↓] :2010/03/23(火) 00:09:16
ちょっと前に、「働いている」っていってたけど・・・?
417+4 :neetubot [] :2010/03/23(火) 01:18:00
>>407-415 コンピュータ君…こんな過疎スレでそんなになるほど感情的負荷を与えてしまってゴメンナサイ。
雑談スレを見まして、本当に「自分はいいけど、他人はだめ」みたいな考え方の人なのかつっついてみました。
未成年なら笑って許しますが、「大人になれよ三井!」とだけ、私も僭越ながらダメ出し しておきます。
>>416 こんにちはー http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1261794262/291
とかのことですね。明日いやもう今日かからまた雑務をこなしに逝ってきますぉ
ところで、>>396 の件で、http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html のように
n次元単体の外心が\p_O = \P (\C[\P^T \P] \1 + \~C[\P^T \P] \~b_σ) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)
の位置にあるのは出てるとして、ここから外接円の半径の自乗を r_O^2=(\p_O - \p_0)^T (\p_O - \p_0)
=(\p_O - \p_n)^T (\p_O - \p_n) = (\sum_{i=0…n} (\p_O - \p_i)^T (\p_O - \p_i)) / (n+1)
(ここで、n次元単体の重心\p_Gを用いれば、)= (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) + ごにょごにょ
で話せば長いんですが、計算すると http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/12.html の最小自乗平均(n-1)次元
超球面の半径(重均半径)r_Gを用いて、r_O^2= (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) + r_G^2 と解けました!
上式は、n次元単体の外心を中心とした半径r_Oの外接超球面と、それと同じn次元単体の
重心を中心とした半径r_Gの最小自乗平均(n-1)次元超球面(重均超球)との共通部分が、
そのn次元単体の重心を中心として半径r_Gの(n-2)次元超球面(n次元単体が存在する空間から
オイラー線(重心と外心を結ぶ直線)の方向を除いた部分空間(重心を通る)上に存在)となることを示しています。
ということで、スレも伸びたことですし、このn次元単体の重均超球と外接超球の共通部分の
(n-2)次元超球面の名前を来週まで公募しますーこのスレかメールneetubot◎gmail.comまでどうぞー
特に無いようでしたら、この分野の名無しの名 neetubot で仮に「重均外接共通重中(n-2)次元超球面」
とでも付けちゃいますよ、なげぇ。(っていうか、本当にあるのかなぁこれ)
418+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/23(火) 01:55:48
>>416-417
自演乙
419 :neetubot [] :2010/03/23(火) 02:00:04
n次元単体が正単体となるときに限り、重心と外心が一致((\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G)=0)し、
重均超球も外接超球も「重均外接共通重中超球面(仮)」(このとき(n-1)次元になる)
も一致する。ということを、書き忘れるところだった、よかった、おやすみー
420+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/25(木) 23:31:30
>>413
(笑)
421 :neetubot [] :2010/03/28(日) 12:40:05
>>418>>420 特に(n-2)次元超球面の名前の案でもないようなので(笑)、
>>417 のは「重均外接共通重中超球面」と仮に呼ぶことにします。
さて、n次元単体の外接超球にその「重均外接共通重中超球面」で直交する
同じ空間内のn次元超球の中心\p_Xと半径r_Xを考える。これは相似比から、
中心\p_X=(\p_G r_O^2 - \p_O r_G^2)/( (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) ) (広義垂心ではないorz)
半径r_X=(r_O r_G)/√( (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) ) と導出できる。
ただし、n次元単体が正単体となる lim_{\p_O → \p_G} の場合を考えると、
式の上では、中心 lim \p_X=\p_O=\p_G となるが、半径 lim r_X→∞ となってしまう。
きれいな式ですが、「重均外接共通重中超球面」と共にあまり使えなそうだなぁー
n次元単体の内接超球と逆垂超球、あるいは、k次元面接超球とk次元面均超球でも似たように
なるだろうか?とりあえず今日は、\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1)の軌跡を調べたい。
422+1 :neetubot [] :2010/03/28(日) 21:28:30
アフィン独立な位置行列\Pで表されるn次元単体の重心
\p_G = \P \1 / (\1^T \1)から任意の内部点\P \a / (\1^T \a)
を通る曲線上の点\p_σを、対角成分にσ_i(全てのi=0…nでσ_i>0)を持つ
(n+1)対角行列\Σと実数t≧0によって\p_σ=\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1)
のように表す。(仮にn次元単体の座標冪乗曲線と呼ぶ)
(t≦0は http://mathworld.wolfram.com/IsotomicConjugate.html
で座標を変えればt≧0と同じ)
n次元単体の座標冪乗曲線はt→∞で、座標a_iが一番大きい値となる
番号iの位置\p_i(重複がk個あればそれらが作るk次元部分単体面の重心)
へ収束する。今後、d(\p_σ)/dt や d^2 (\p_σ)/dt^2も求めたい。
…なんだろうこのデジャビュー
423 :neetubot [] :2010/03/28(日) 21:51:54
(n次元単体の座標冪乗曲線は、アフィン変換かける前の
n次元正単体の重心から出る方向の単位ベクトル\e_θ
によって、全て分類され記述できると考えた…)
424 :neetubot [] :2010/04/02(金) 22:33:59
それでは、これからneetubotゼミを始めます。礼。
それでは、おもむろにベクトル
\p_σ=\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1) = \sum_{i=0…n} ( (\p_i σ_i^t) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t) )
をtで微分します。すごいことになりま…
425 :neetubot [] :2010/04/02(金) 23:31:28
d(\p_σ)/dt = \sum_{i=0…n} \p_i {σ_i^t log(σ_i) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)
- σ_i^t (\sum_{j=0…n} σ_j^t log(σ_j) ) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)^2 }
= \sum_{i=0…n} ( {(\p_i σ_i^t) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)}
{log(σ_i) - (\sum_{j=0…n} σ_j^t log(σ_j) ) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)} )
426 :neetubot [] :2010/04/03(土) 09:32:16
d(\p_σ)/dt = \sum_{i=0…n} ( {(\p_i σ_i^t) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)}
{(\sum_{j=0…n} σ_j^t log(σ_i / σ_j)) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)} )
となることから、d(\p_σ)/dt |_{t→+0} = \sum_{i=0…n} ( {\p_i / (n+1)^2}
{ log(σ_i^(n+1) / (\prod_{j=0…n} σ_j)) } = \sum_{i=0…n} (\p_i {
log(σ_i)/( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) - 1/(n+1)} {( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) / (n+1)}
= {( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) / (n+1)} \sum_{i=0…n} {(\p_i log(σ_i)/( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) - \p_G}
と変形できる。これは、>>422 のn次元単体の重心\p_Gから内部点 \P \a
(ただし、a_i > 0)を通る座標累乗曲線(\p_σ=\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1)上の点の軌跡)が、
t→+0の重心近傍において\sum_{i=0…n} (\p_i log(a_i)/( \sum_{j=0…n} log(a_j) ))を
見込む方向に出発することを表している。
427 :neetubot [] :2010/04/03(土) 09:44:33
逆に、m次元ユークリッド空間内で各列成分がアフィン独立となるm×(n+1)行列
\P=[\p_0,…,\p_n]が表すn次元単体で、t→+0の重心近傍において
\sum_{i=0…n} (\p_i ω_i)/( \sum_{j=0…n} ω_j ))を見込む方向に出発する
座標累乗曲線上の点は \p_ω = \sum_{i=0…n} \p_i e^(ω_i t) / ( \sum_{j=0…n} e^(ω_j t) )
を通ると言える。(のか?これ行列で表したいなぁ)次、これを2階微分しま…
428+1 :neetubot [] :2010/04/03(土) 15:35:21
ここで、a_{iω} = a_{iω}[t] = e^(ω_i t) / ( \sum_{j=0…n} e^(ω_j t) ) とおく。
前述より、d(\p_ω)/dt = \sum_{i=0…n} \p_i d(a_{iω})/dt = \sum_{i=0…n} \p_i ({ω_i e^(ω_i t)
/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))} - {e^(ω_i t) (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))^2} )
= \sum_{i=0…n} ( \p_i a_{iω} {ω_i - (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))} )
また、(d/dt)(d(\p_ω)/dt) = \sum_{i=0…n} \p_i ( {d(a_{iω})/dt (ω_i - (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t))
/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) )} - {a_{iω} (d/dt)((\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)))}
これはめんどくせぇ式だな、途中だけど図書館行ってくるわー(あと、今日は重心拡大・重心縮小を定義しよう…)
429 :neetubot [] :2010/04/03(土) 20:46:35
>>428 >/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) )} - {a_{iω} (d/dt)((\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)))}
/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) )} + {a_{iω} (d/dt)((\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)))}
と間違いを直せば、(d/dt)(d(\p_ω)/dt) = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} (
{ω_i - (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))}^2
+ {(\sum_{j=0…n} ω_j^2 e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))}
- {(\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))}^2 )
= \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} (ω_i^2 - 2 ω_i (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))
+ {(\sum_{j=0…n} ω_j^2 e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))})
ちょっと手間取ったが、あとは通分して(d/dt)(d(\p_σ)/dt) |_{t→+0} = 0?を示すのみか…
430 :neetubot [] :2010/04/03(土) 21:20:37
ということで、(d/dt)(d(\p_ω)/dt) = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} {
\sum_{j=0…n} (ω_i - ω_j)^2 e^(ω_j t) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) }
と解けます。いやーすごいよねーこれ。ということは、
d(\p_ω)/dt = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} {
\sum_{j=0…n} (ω_i - ω_j) e^(ω_j t) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) }
と書いたほうが美しいな。で、ここから曲率半径ってどうやるんだっけ?
431 :neetubot [] :2010/04/04(日) 00:43:42
二次超曲面の曲率半径はスカラーをベクトルで微分してたので、全く違う感じにいきます。
まず、( d(\p_ω)/dt )^T ( (d/dt)(d(\p_ω)/dt) - s d(\p_ω)/dt) = 0 を考えることにより、
ベクトル (d/dt)(d(\p_ω)/dt) の ベクトル d(\p_ω)/dt に直交するベクトル成分は
( \E - (( d(\p_ω)/dt ) ( d(\p_ω)/dt )^T)/(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) ) (d/dt)(d(\p_ω)/dt)
と求まる。
ある点における力学での曲率半径 \r が、その点での速度\vと 速度に直交する成分の
加速度\aに対して、\r = ((\v^T \v) / (\a^T \a)) \a と書ける気がする(←自信ない)
ので、座標累乗曲線上のtでの点における曲率半径は
( \E - (( d(\p_ω)/dt ) ( d(\p_ω)/dt )^T)/(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) ) (d/dt)(d(\p_ω)/dt)
(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) / { ((d/dt)(d(\p_ω)/dt))^T ( \E - (( d(\p_ω)/dt ) ( d(\p_ω)/dt )^T)
/(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) ) (d/dt)(d(\p_ω)/dt) } となる?これはどうでもいいな…
つまり、これは n次元単体内部の曲線分を表す 普通の指数関数の最も簡易な拡張であり、その上の点を
\p_ω = \sum_{i=0…n} \p_i e^(ω_i t) / ( \sum_{j=0…n} e^(ω_j t) ) = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω}
とおけば、t→+0の重心近傍において \sum_{i=0…n} (\p_i ω_i)/( \sum_{j=0…n} ω_j )) を見込む方向に出発し、
(d/dt)^n [\p_ω] = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} (\sum_{j=0…n} (ω_i - ω_j)^n e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))
が成り立つ?というところが、このネタの一番の綺麗どころっすかねーこの名前は今日から「指数座標曲線」にしる!
432 :neetubot [] :2010/04/04(日) 10:55:45
指数座標曲線は重心(任意の内部点でもいける)を中心にn次元単体の内部
(境界を含まない)をくまなく走査できる曲線分であり、n次元単体の全ての内部点を
指数座標曲線のt→+0の初速方向で重心まわりの超球面にくまなくマッピングできる。
重心まわりということで、正単体の基底の拡縮変換に対してのn次元立体角を
考えたりするのに役立つと期待する。そこで下記の重心拡大・重心縮小を定義する。
m次元ユークリッド空間内で各列成分がアフィン独立となるm×(n+1)行列
\P=[\p_0,…,\p_n]が表すn次元単体で、n次元単体のi頂点以外の点を使って
i頂点\p_iが重心となるように拡大する新しいi頂点の位置を「重心拡大i頂点」
\p'_i=(n+2)\p_i-(\sum_{j=0…n} \p_j)と呼ぶ。
また、n次元単体のi頂点以外の点を使って、そのn次元単体の重心を
新しくi頂点と見立てた位置を「重心縮小i頂点」\p''_i=\p_Gと呼ぶ。
さらに、i頂点以外の点と重心縮小i頂点で作られる単体を重心縮小i頂点単体
とかi=0…nの重心縮小i頂点単体の重心で作られる単体を重心縮小重心単体
とか呼ぶ。しかし、あまり使わないような気もする。
ところで、n次元単体の内接超球に対して、>>417 のようになる超球はなぜか
逆垂超球と勘違いしてましたが、普通に考えて正しくは内足重均超球ですぉ。
ちょっと気になると言えば、普通に考えた超平面同士の成す角度など、
まぁこれらは、また来週くらいまで。以上、9レス分の今週のneetubotゼミ終了ー
433 :neetubot [] :2010/04/04(日) 11:10:08
そういえば先週、>>417 の2次元バージョンの証明をしてくださった方がいて、とてもありがとうございます。
分からない問題はここに書いてね330
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1269099055/147
147 :132人目の素数さん [sage] :2010/03/28(日) 16:06:55
>>145
ベクトルで計算したら一致することになった。
以下の問題に置き換えられる。
重心G, 外心Pとして、 GP, √(a^2+b^2+c^2)/3 , 外接円の半径を3辺の長さとする三角形は、外接円の半径を斜辺の長さとする直角三角形となるか。
三角形の頂点をO,A,Bとし、
OA=a, OA↑=a↑, OB=b, OB↑=b↑, OP=p, OP↑=p↑, OG↑=g↑ とする。
PとCAの中点を結ぶと、CAと垂直になるので、
a↑・(p↑-(1/2)a↑) = 0
同様にb↑・ (p↑-(1/2)b↑) = 0
変形すれば、a↑・p↑ = (1/2)a^2, b↑・p↑ = (1/2)b^2
g↑=(1/3)(a↑+b↑)なので、
GP^2 = |p↑ - (1/3)(a↑+b↑)|^2 = |p↑|^2 - (2/3)p↑・(a↑+b↑) + |(1/3)(a↑+b↑)|^2
= p^2 - (2/3)(a↑・p↑+b↑・p↑) + (1/9)(a^2 + 2a↑・b↑ + b^2)
= p^2 - (2/3)((1/2)a^2+(1/2)a^2) + (1/9)(a^2 + 2a↑・b↑ + b^2)
= p^2 - (2/9)(a^2 - a↑・b↑ + b^2)
(√(a^2+b^2+c^2)/3)^2 = (a^2+b^2+c^2)/9
= (a^2+b^2+|a↑-b↑|^2)/9 = (a^2+b^2+a^2-2a↑・b↑+b^2)/9
= (2/9)(a^2-a↑・b↑+b^2)
以上より、GP^2 + (√(a^2+b^2+c^2)/3)^2 = p^2 (証明終わり)
ということで、このスレ見ていらっしゃったら、>>417 にあなたの命名する名前を付けたいので、メールとか連絡頂けるとありがたいです。
434+1 :neetubot [] :2010/04/10(土) 07:02:46
今週のneetubotゼミは、同じ次元の任意の実数成分の列ベクトル\a,\bに対し、
- (\a \b^T - \b \a^T)^3 / ((\a^T \a \b^T \b) - (\a^T \b)^2)
= - (\a \b^T \a \b^T - \a \b^T \b \a^T - \b \a^T \a \b^T + \b \a^T \b \a^T)
(\a \b^T - \b \a^T) / ((\a^T \a \b^T \b) - (\a^T \b)^2)
= (\a \b^T - \b \a^T) となることがミソです。これリー群の式と似てるけど関係あるのかなぁ?
435 :neetubot [] :2010/04/10(土) 07:13:41
別に実数成分と仮定しないでよかた。。
では、次元は適当にmとでもしたユークリッド空間内で,
二点間の距離d_{0 0}から二平面間の距離d_{2 2}と角度θ_{2 2}まで求めますー
436 :neetubot [] :2010/04/10(土) 12:36:22
例えば、このスレでは普通に考えて、m次元ユークリッド空間内(m≧n≧0≦n'≦m)で、
n次元単体Aが存在するn次元部分空間U上の点と
n'次元単体A'が存在するn'次元部分空間U'上の点
との距離の最小値を「UとU'の距離」と呼ぶ。
また、UとU'の距離が0になるように平行移動したとき、
UとU'の共通部分空間∩に対し、U-∩内のベクトルと
U'-∩内のベクトルの成す角の最小値を「UとU'の角度」
と呼ぶのが、順当だと思いますコンピュータ君。
437 :neetubot [] :2010/04/10(土) 16:07:54
最終的に興味があるのは、二つの単体間の計量ではあるが、
正単体を拡縮変形後に回転変形させ平行移動したもので任意のn次元単体が表せると考えれば、
任意のn次元単体は(元の正単体の回転の自由度はあるが)その重心とn次元基底で表せるため、
下記の方向表記でまず解いておけば、有用であると考える
438+1 :neetubot [] :2010/04/10(土) 16:56:23
まず、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\p=[p_1,…,p_m]^T
で表される点から、位置ベクトル\p'=[p'_1,…,p'_m]^T で表される点への、
距離ベクトルが \d[\p→\p'] = \p' - \p となることから、
この二点間の距離d_{0 0}は、普通に考えて、
d_{0 0} = √(\d[\p→\p']^T \d[\p→\p']) = √(\d[\p'→\p]^T \d[\p'→\p])
= √((\p' - \p)^T (\p' - \p)) = √( \sum_{i=1…n} (p'_i - p_i)^2 ) と表せる。
(普通のユークリッドノルム)
439+2 :neetubot [] :2010/04/10(土) 19:57:38
訂正: >>438 √( \sum_{i=1…n} (p'_i - p_i)^2 ) じゃなくて √( \sum_{i=1…m} (p'_i - p_i)^2 ) だった。心の目で大目に見て!
次に、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\p=[p_1,…,p_m]^T
で表される点を通り 方向ベクトル\l=[l_1,…,l_m]^Tの方向の直線Uから、
位置ベクトル\p'=[p'_1,…,p'_m]^T で表される点U'への、距離ベクトルを
\d[\p_d→\p'] (ただし、\p_dは点U'から直線Uに下ろした足の位置ベクトル)とする。
すると、\p_d = \p + (\l \l^T)/(\l^T \l) (\p'-\p) より、m×m単位行列\Eに対して、
\d[\p_d→\p'] = \p' - \p_d = (\E - (\l \l^T)/(\l^T \l)) (\p'-\p) と書ける。
つまり、上記のように表した場合の直線Uと点U'の距離d_{1 0}は、普通に考えて、
d_{1 0} = √(\d[\p_d→\p']^T \d[\p_d→\p']) = √((\p' - \p)^T (\E - (\l \l^T)/(\l^T \l)) (\p' - \p)) となる。
ここまでなら線型代数の教科書のグラムシュミット直交化あたりとかに普通に載ってる話です。
例えば、d_{1 0}を2次元ユークリッド空間(xy平面)内の
直線 a x + b y + c = 0 (条件略)と点(x'_0, y'_0)の距離
に当て嵌めれば、直線 a x + b y + c = 0 が点(x_0, y_0)
を通り傾き(-b, a)であるとしたとき c = - a x_0 - b y_0 であるので、
d_{1 0} = √( (x'_0-x_0, y'_0-y_0) ( \E - ((-b, a)^T (-b, a))/((-b, a) (-b, a)^T) ) (x'_0-x_0, y'_0-y_0)^T )
= √( (a^2 (x'_0-x_0)^2 + 2 a b (x'_0-x_0) (y'_0-y_0) + b^2 (y'_0-y_0)^2) / (a^2 + b^2) )
= | a (x'_0-x_0) + b (y'_0-y_0) | / √(a^2 + b^2)
= | a x'_0 + b y'_0 + c | / √(a^2 + b^2)
となり、昔習った拡張性はないが美しい式にちゃんと一致する。
440+2 :neetubot [] :2010/04/10(土) 20:49:52
また、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\p=[p_1,…,p_m]^T
で表される点を通り 方向ベクトル\l=[l_1,…,l_m]^Tの方向の直線Uと、
位置ベクトル\p'=[p'_1,…,p'_m]^T を通り 方向ベクトル\l'=[l'_1,…,l'_m]^T
の方向の直線U'との、距離ベクトルを\d[\p_d→\p'_d] と書く。
このとき、\p_d = \p + \l a および \p'_d = \p' + \l' a' とすれば、
二点\p_d, \p'_d間の距離d_{1 1}の大きさが係数 a, a' の値において
最小となるとき、直線Uと直線U'との距離となる。
つまり、最小自乗法より ∂(d_{1 1}^2)/∂a=∂(d_{1 1}^2)/∂a'=0 となることを用れば、
d_{1 1}^2 = ((\p'-\p) + \l' a' - \l a)^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a)であることから、
\l^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = \l'^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = 0 を満たすと言える。
(これは、距離ベクトル\d[\p_d→\p'_d]に対し 直線Uあよび直線U'が直交することを表している)
この a, a' を解けばよいのだが、めんどくさいので、ちょっちタンマ(笑)
441+4 :neetubot [] :2010/04/11(日) 00:26:09
>>440 の\l^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = \l'^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = 0より、
(a, a')^T = ({{\l^T \l, -\l^T \l'}, {-\l'^T \l, \l'^T \l'}})^{-1} {{\l^T (\p'-\p)}, {-\l'^T (\p'-\p)}}なので、
a=\l'^T (\l' \l^T - \l \l'^T) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) および
a'=\l^T (\l' \l^T - \l \l'^T) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)と解ける。
したがって、\d[\p_d→\p'_d] = \p'_d - \p_d = (\p' - \p) +
(\l' \l^T - \l \l'^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
= ( \E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) ) (\p' - \p)
が成り立つ。(ただし、\l^T \l \l'^T \l' = (\l^T \l')^2、つまり、直線Uと直線U'が平行でない場合に限る)
ここで、\l' \l^T - \l \l'^Tは歪対称行列だが、
\E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / ( (\l^T \l) (\l'^T \l') - (\l^T \l')^2 ) = \M は対称行列となり、
\M^2 = \E + 2 (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) + (\l' \l^T - \l \l'^T)^4 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)^2
= \E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) = \M であるため冪等行列ともなる。
これは、(\p' - \p)がちょうどすでに直線Uあよび直線U'に直交している
(\p' - \p) = \M (\p' - \p) 場合にも(そしてたとえ何度 \M を掛けて変換したとしても)
\d[\p_d→\p'_d] = \M (\p' - \p) = \M^n (\p' - \p) となるのは、当然だということを表している。
以上を用いれば、この直線Uと直線U'との距離は d_{1 1} = √( (\p' - \p)^T \M (\p' - \p) )
√( (\p' - \p)^T (\E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)) (\p' - \p) )
と書けることがわかる。明日までに、ねじれの位置だけでなく平行な場合や交わったり一致する場合
の条件を確認しておきます。あとは、d_{n 0}、d_{2 1}、d_{2 2}を求めたいなぁー
442+1 :neetubot [] :2010/04/11(日) 00:52:28
>>434 でミソって言ったのは、>>441 で使った
(\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
が冪等行列になるということに帰着されますた。
こっちの方は、二回外積掛けてるような感じなのですが、
2直線の方向に向かって正射影するようなもんなので、
名前付けるとしたら双正射影行列とかかなぁー。
>>441 の \M = \E - (\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) の方は、
2直線に直交する方向に等長(?)変換するため、
名前付けるとしたら双直交射行列とかかなぁー。
まぁそれらは、2つの部分空間の距離とかまで拡張したところで考えればいいことか…
443 :neetubot「二直線間の距離の細かい所」 [] :2010/04/11(日) 16:28:05
訂正:>>440>>441 直線Uあよび直線U' →(爆笑)→ および。二回もかよ!?
双正射影行列 \W'=(\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
とすれば、ざっくり lim_{\l'→\l} \W' = lim_{\l'→\l} 2 \l (\l^T \l - \l^T \l) \l^T / ((\l^T \l - \l^T \l) (\l^T \l + \l^T \l))
= \l \l^T / \l^T \l (これは、直線Uと直線U'が平行な場合、その平行な方向への正射影行列となる
ということを表す。)と計算できるため、同様に双直交射行列 \Y' = \E - \W' もlim_{\l'→\l} \Y'
= \E - (\l \l^T)/(\l^T \l) となる。
以上より、二直線間の距離は、二直線が平行な((\l^T \) (\l'^T \l') = (\l^T \l')^2)場合には、
\l'を考えずに、>>439 のような直線Uと点\p'の距離に帰着されることが言える。
また、二直線が交わる必要十分条件は、二直線間の距離ベクトルが
\d[\p_d→\p'_d] = \Y' (\p' - \p) = \0 となることであり、これは、
(\p' - \p) = \W' \t を満たすm次元列ベクトル解 \t が存在するという
問題に置き換えて、最終的に、「rank[\W', (\p' - \p)] = rank[\W']」 を
満たすことがm次元ユークリッド空間内で二直線が交わる必要十分条件と言える。
この二直線が交わる条件式「rank[\W', (\p' - \p)] = rank[\W']」は、
基本的な演算のみを用いて導出されたものであり、ねじれの位置だけでなく
平行な場合や交わったり一致する場合など、あらゆる条件下で使える式である。
444 :neetubot「二直線間の計量」 [] :2010/04/11(日) 19:53:31
二直線間の距離の中点への位置ベクトル\p_Dも
綺麗に書けると思うので、やってみっかー
普通に考えて(←前置きがめんどくさくなってきた)、
\p_D = \p_d + \d[\p_d→\p'_d] / 2 = \p + \l \l'^T (\l' \l^T - \l \l'^T)
(\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) + \Y' (\p' - \p) / 2
= (\p' + \p) / 2 + (\l \l'^T + (\l' \l^T - \l \l'^T)/2) (\l' \l^T - \l \l'^T)
(\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
= (\p + \p')/2 + (\l a + \l' a')/2
= {(\p + \p') + ((\l' \l^T)^2 - (\l \l'^T)^2) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)}/2
まぁ、この結果は、普通に考えて、二直線の通る点の中点から、二直線
の通る点から距離の足へのベクトルを足して2で割った方向にあるのは自明ですよと。
この点 \p_D は、二直線上のそれぞれの点からの距離の自乗の和が最小となる点
(m次元ユークリッド空間内で一意にこの点)そのものであると、ちょっとがんばれば簡単に示せます。
なお、ねじれの位置にあっても二直線の成す角度θ_{1 1}は、距離ベクトルが
0ベクトルになるように平行移動して考えれば、ただの二直線の方向
ベクトル\l, \l'の成す角度として θ_{1 1} = arccos(\l^T \l' / √(\l^T \l \l'^T \l')) で求められる。
ということで、m次元ユークリッド空間内で、任意の二直線を表すためには、
距離の中点\p_Dおよび二直線の方向\l, \l'とそれに直交する距離ベクトルの半分\d/2
というパラメータで表せば(これでは右回り左回りの配置かとかがわからんが)一番いい感じがするよと。
445+2 :neetubot「二直線間の疑問」 [] :2010/04/11(日) 20:31:34
傾き\lの直線U上の点と 傾き\l'の直線U'上の点とを 結ぶ線分の中点の軌跡
の方向ベクトルは、上でちょっと出てるけど、
{((\l' \l^T)^2 - (\l \l'^T)^2) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)} \t と言えるだろうか?
なぜ、\l と \l' の角の二等分線の方向と一致しないのだろうか?
なぜ、双正射影行列 \W'=(\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
が示す方向と違うのだろうか?
という三点ぐらいが疑問として残りました。\l と \l' とそれらに直交する距離ベクトルの
実質3次元分しか出てこないけど、存外難しいではないか、あはははあばばー
446 :neetubot「n次元部分空間と点との距離」 [] :2010/04/11(日) 21:10:25
訂正:>>441 下から3行目 = √( (\p' - \p)^T (\E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)) (\p' - \p) )
ところで、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\pで表される点を通り
n本の基底 \L=[\l_1,…,\l_n] で作られるn次元超平面Uから
位置ベクトル\p'で表される点U'への 距離ベクトルを\d[\p_d→\p'] と書く。
(ただし、\p_dは\p'からn次元超平面Uに下ろした垂線の足とする。)
仮定より、n次元超平面Uに対する直交射行列 \Y = (\E - \L (\L^T \L)^{-1} \L^T)
を用いて、\d[\p_d→\p'] = \Y (\p' - \p) = (\E - \L (\L^T \L)^{-1} \L^T) (\p' - \p)
と書ける。また、このn次元超平面Uと点U'との 距離 d_{n 0} は
d_{n 0} = √( (\p' - \p)^T \Y (\p' - \p) )
= √( (\p' - \p)^T (\E - \L (\L^T \L)^{-1} \L^T) (\p' - \p) )
と書ける。これも、線型代数の本の射影行列という項に載ってたりすることもあると思う。
d_{n 0}は >>439 の 直線Uと点U'の距離d_{1 0}の 純粋なn次元拡張であります。
447 :neetubot [] :2010/04/11(日) 21:40:23
>>445 傾き\lの直線U上の点と 傾き\l'の直線U'上の点とを 結ぶ線分の中点の軌跡
じゃいろんな点になるなぁー直線になんないしー①と②・②と③が違うのはわかった。
しかし、①と③は中点連結定理で同じじゃないんかのぅー
d_{2 1}、d_{2 2}は共通部分があって、まんどくせーので、また来週。
448+1 :neetubot [] :2010/04/12(月) 00:35:02
よく考えたら、>>445 の①は(\p_d+\p'_d)/2に関係する
実際の中点間の方向で、③は(\p'_d-\p_d)に関係する
平行移動して差し引きした分の量だから全然違った。
>>445 はどれも違う重要な量なんだなぁー(
この場合、距離ベクトルの方向に三角柱と考えるのがいいが、
d_{n n'}の場合、k次元共通正規直交基底\S''と 空間Uから共通基底を
除外した正規直交基底\Sと 空間U'から共通基底を除外した正規直交基底\S'
として、空間Uの通る点\p と 空間Uの通る点\p' から \S と \S' に 直交する
距離\dを出し、\S''の方向を除外したものを距離としていいと思う。
449+1 :132人目の素数さん [] :2010/04/12(月) 09:07:13
「5心」を英訳すると「Four Centers of a Triangle(4心)」だね。
内心と傍心は同じ種類の中心だから、まとめて「1個」と数える。
もっとも、「Kimberling Centers(3587心)」のほうが、今では市民権を得ているが。
次の2つのWEBは基礎知識として必ず見てね。
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html
http://www.xtec.es/~qcastell/ttw/ttweng/portada.html
X(n)の三角形座標(trilinears)、重心座標(barycentrics)による中心の表示を見れば、
幾つかはすぐ高次元化できるね。
450 :neetubot [] :2010/04/13(火) 01:43:56
今日もお疲れコンピューター!>>449 有用な情報ありがとうございます!!
ホントに"Four Centers of a Triangle"でググるとFiveより圧倒的ですね。
>内心と傍心は同じ種類の中心だから、まとめて「1個」と数える。
私も、>>327 ではまとめて「第3心」で数えました。n次元単体では、
傍心のように各(n-1)次元表面から全て等距離にある点は、内心を含めて
2^n個定義できる(このスレでは >>282 あたりから広義傍心と呼んでいる)と考えてます。
ETCについては >>308 や http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/11.html
で触れてますが、個人的に参考知識として上げたいのは http://mathworld.wolfram.com/
の方がよくまとまってますし好きですね。ETCの市民権についてはmathworldで頻出なので同感です。
>X(n)の三角形座標(trilinears)、重心座標(barycentrics)による中心の表示を見れば、
>幾つかはすぐ高次元化できるね。
幾何学的性質や意味まで含めて式で高次元拡張しようとし、
座標は定式化の手段というか、副次的なものとしてしか捉えていなかったので、
座標だけで拡張しようとする考えは斬新ですね。
というのも、まぁ下記はたとえ話ですが、
三角形(2次元単体)の心から n次元単体の心に拡張するという事は、
ある数列の初項から 第二項・第三項…と性質を見た上で
第n項の一般的な式を導出することのようだ、と私は思っていて、
それが 等差数列や 等比数列のような簡単な性質ではなく
幾何学的性質を保つような列となるということが結構難しいよと、
例えば私は思うわけですが。まぁ、個人的印象にすぎませんがw
451 :neetubot [] :2010/04/18(日) 17:42:05
今週のneetubotゼミはお休みにしますー
452 :neetubot [] :2010/05/02(日) 21:03:10
そしてここから、伝説が始まる(笑)
453 :neetubot [] :2010/05/03(月) 12:43:05
まず、単位行列 \E などの基本をおさらいする。以下はm次元ユークリッド空間内とする。
ここで、正規直交行列\S, \Aと対角行列\Σによって、特異値分解 \L = \S \Σ \A^T
となるとき、擬似逆行列 \L^† = \A \Σ^{-1} \S^T と書ける。
このとき、ベクトル\pを、列ベクトルを並べた行列\Lが作る部分空間内の
ベクトル\L \aと、その部分空間に直交するベクトル\p - \L \aに分けるとすれば、
\L^T (\p - \L \a) = \A \Σ \S^T (\p - \S \Σ \A^T \a) = \0 より、
\Σ^{-1} \S^T \p = \A^T \a であることから \p = (\L \a) + (\p - \L \a)
= \S \S^T \p + (\E - \S \S^T) \p = \L \L^† \p + (\E - \L \L^†) \p と書ける。
このことより、\Lに対する正射影行列を \W[\L] = \L \L^† = \S \S^T と定義し、
\Lに対する直交射行列を \Y[\L] = \E - \L \L^† = \E - \S \S^T と定義する。
これをふまえれば、さきのベクトル\pの\Lに対する直交分解は
\p = \E \p = \W[\L] \p + \Y[\L] \p と書ける。
454 :neetubot [] :2010/05/03(月) 21:59:41
ということをふまえて、基底\Lで作られるn次元部分空間 U と
基底\L'で作られるn'次元部分空間 U' との 共通k次元部分空間
(以下 n ≧ n' ≧ k とする)の正規直交基底\S''などを求める。
まず、求めやすい U と U' の和空間(次元は n + n' - k )の
正規直交基底 \S_W については、\S_W \S_W^T = \W[\L, \L'] = [\L, \L'] [\L, \L']^†
(\Lと\L'をくっつけたm×(n+n')行列[\L, \L']に対する正射影行列)
によって求められる。ちなみに、U と U' の和空間の直交補空間
(UでもU'でもない (m - (n + n' - k))次元部分空間)の
正規直交基底 \S_Y については、\S_Y \S_Y^T = \Y[\L, \L'] = \E - \W[\L, \L']
によって求まる(それぞれ固有値1の正規直交な固有ベクトル列として)。
ただし、この2つはあまり使わないと思われる。どーん
455+1 :neetubot「2つの部分空間(超平面)の共通部分空間など」 [] :2010/05/03(月) 22:33:58
つーことで、本題の共通k次元部分空間の正規直交基底\S''の求め方だがや。
和空間なら出せることから、U の直交補空間の\Y[\L]と
U' の直交補空間の\Y[\L']との和空間全体の 直交補空間
\Y[\Y[\L], \Y[\L']] = \S'' \S''^T で求まるちゅーわけじゃんかー
いやーこれでも求まるっちゃーきたねぇんじゃけんどよー
また、Uから共通k次元部分空間を除いた空間(仮に左差空間とでも呼ぶ)
の正規直交基底 \S は \S \S^T = \Y[\Y[\L], \L'] = \Y[\Y[\L], \W[\L']] によって出せるし、
U'から共通k次元部分空間を除いた空間(仮に右差空間とでも呼ぶ)
の正規直交基底 \S' は \S' \S'^T = \Y[\L, \Y[\L']] = \Y[\W[\L], \Y[\L']] によって出せる。
つーか、これらは前にもやった気がするし…けど、今回も式の整形には至らんかった…
地道でめんどくせぇ計算だけど、とりあえず任意の2つの基底から各部の正規直交基底が
出せるよってことが、次の2つの基底(による2つの超平面)の角度を求めるのに重要です。
456+1 :neetubot「2つの部分空間(超平面)の距離」 [] :2010/05/04(火) 01:46:28
(上のめんどくせぇ計算とは、\S''を求めるために、まず
m×(2m)行列 [(\E-\L (\L^T \L)^{-1} \L^T), (\E-\L' (\L'^T \L')^{-1} \L'^T)]
の(m-k)本の左特異ベクトルからなる\S''の直交補空間の正規直交基底 \S''' とかを求めて、
次にm×m行列(\E-\S''' \S'''^T)のk本の左特異ベクトルからなる\S''が求まるという
計算のことです。さらに\L, \L'が基底でなければ 計4回ものSVD計算が必要となるので大変です。)
と角度の前に、2つの部分空間(超平面)の距離やります。超単純でした。
(ちなみに、基底\Lで張られる部分空間Uは、直交する(要証明?)
正規直交基底\Sと\S''でも張られるので、\W[\L] = \W[\S, \S''] = \S \S^T + \S'' \S''^T
となるというような計算は、以下では明記しないかもしれないけど、こっそりよく使ってます。)
さて、2つの超平面 U, U' 間の距離について >>448 などのように考えれば、
距離d_{n n'}とUとの交点を\p_d = \p + \L \a、距離d_{n n'}とU'との交点を\p'_d = \p' + \L' \a'
としたとき、超平面Uから超平面U'への距離ベクトルは
\d[\p_d→\p'_d] = (\p' + \L' \a') - (\p + \L \a) = \p' - \p - [\L, \L'] [\a; -\a']
と書けて、これは点\pを通り[\L, \L']で作られる超平面から点\p'への距離ベクトルと
全く同じように考えられるということを表している。
それはさておき、ここの過去ログや最小自乗法をふまえて、距離ベクトルは
[\L, \L']^T \d[\p_d→\p'_d] = [\L, \L']^T (\p' - \p) - [\L, \L']^T [\L, \L'] [\a; -\a'] = \0
を満たすことより、\d[\p_d→\p'_d] = \Y[\L, \L'] (\p' - \p) と書ける。
(ここで、前述の\S''で張られる共通部分空間があるために、距離ベクトルの足
\p_dおよび\p'_dは一意には定まらない。しかし、2つの部分空間(超平面)の距離の中点
への位置ベクトル\p_Dを後述する際に、\p, \p'の位置をふまえた\p_d, \p'_dのある意味最適な
とるべき位置を一意に定義しようと思う。)
よって、「m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\pで表される点を通り
基底\Lで張られるn次元超平面Uから、位置ベクトル\p'で表される点を通り
基底\L'で張られるn'次元超平面U'への、距離の大きさは
d_{n n'}=√( (\p' - \p)^T \Y[\L, \L'] (\p' - \p) ) で表せる。(m≧n≧n'≧0)」
457 :neetubot [] :2010/05/04(火) 02:08:24
いらんことごちゃごちゃ書いとったら、文字数制限やでー
>>456 の最後の式で俺の一ヶ月全て一般化され表されてもーた。
つーか、双直交射行列の正体が\Y[\L, \L']=\Y[\S, \S'', \S']っていうのが
驚きやなー >>441-442の直線間距離はこれを展開して計算してあの
特殊な形というわけですわー まぁ
http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix#Blockwise_inversion
に習って >>456 も展開したらと思ったけど、まだ全然わかんねぇー
明日、角度、あよび、距離中点位置、を出して、なんぼ
458 :neetubot「2つの部分空間(超平面)が成す角度」 [] :2010/05/04(火) 12:31:30
ほな、超平面同士の角度やりますわー
3次元空間内で交わる二平面の成す角度と言われて、
「0です」て答える人いないと思われ、片方をどっちかに何度回転
さしたら二平面が一致するのんかーいう話に当然なるんやろー
だけん、上の方で言う所の、\Lと\L'の成す角度と言われても、
共通な\S''を除いた UとU'内の それぞれの単位方向
\S \u (\u^T \S^T \S \u = \u^T \u = 1)と \S' \v (\v^T \S'^T \S' \v = \v^T \v = 1)
の成す角度としてθ_{n n'} = arccos( (\u^T \S^T \S' \v) / √(\u^T \u \v^T \v) )
によってその成しうる角度全てが記述される。
この方向余弦をラグランジュの未定乗数法を用いて定式化すれば、
cos(θ_{n n'}) = \u^T \S^T \S' \v - σ_a (\u^T \u - 1) - σ_a' (\v^T \v - 1)
と書けて、それぞれの変数に対して極値をとるときの条件を求めると、
∂cos(θ_{n n'})/(∂\u) = \S^T \S' \v - 2 σ_a \u = \0、
∂cos(θ_{n n'})/(∂\v) = \S'^T \S \u - 2 σ_a' \v = \0、のようになることから、
\S^T \S' = [\u_1, …, \u_n'] \∑[σ_1, …, σ_k' (, 0, …, 0)] [\v_1, …, \v_n']^T = \U \∑ \V^T
(ただし、|σ_1|≧…≧|σ_k'|>0 とする) と特異値分解されるとすれば、二超平面が成す角度
cos(θ_{n n'}) = ±√((\u^T \S^T \S' \v) / (\u^T \u)) √((\u^T \S^T \S' \v) / (\v^T \v)) = ±2√(σ_a σ_a')
のとりうる値の範囲は、直交半径の大きさがそれぞれσ_1, …, σ_k'の超楕円面
(特異値がn'個ない(0 ≦ k' < n')の場合は内部も含めた超楕円体)上の点から
その超楕円の中心への距離の大きさの範囲として、全く同値として考えられる。
この超楕円を仮に方向余弦超楕円と呼ぶ。このように考えれば、「方向行列がそれぞれ
共通方向がない正規直交基底\S, \S'(任意の基底\L, \L'が与えられても >>455 の計算でこれを求める)
で張られる2つの部分空間が成す角度cos(θ_{n n'})の範囲は、\S^T \S'の特異値がフルランクで
求まる場合は 絶対値が最大の特異値σ_1と 絶対値が最小の特異値σ_n'に対して
-|σ_1|≦cos(θ_{n n'})≦-|σ_n'|, |σ_n'|≦cos(θ_{n n'})≦|σ_1|となり、
多くの\S^T \S'の特異値がフルランクで求まらない場合は -|σ_1|≦cos(θ_{n n'})≦|σ_1|となる。」
が言える。キター
459+1 :neetubot [] :2010/05/04(火) 13:29:57
基底\L, \L'の共通方向をそれぞれ除いた正規直交基底\S, \S'が直交する
(\S^T \S' = \O(零行列))となる この特別な最も単純な場合を考えれば、、
特異値は0しかないので常に cos(θ_{n n'})=0 、つまり直交ですよと。。
そういえば、共通方向\S''がある場合には特異値に1か-1入れて -1≦cos(θ_{n n'})≦1 とかでいいじゃん。
どっちにしろ、どんな「方向余弦半径超楕円」も 単位超球面の境界を含む内部に存在すると言えるぉ。
以上、>>400 のコンピュータ君のために、「角度」を普通に内積と acos のみで考えて、
m次元ユークリッド内のn次元超平面とn'次元超平面の成す角度の範囲を
解析幾何学的に導出したまでの話ですた。「角度」が何だって??(笑)
以上を >>391 の1に絡めて応用すれば、クラスタリングっぽい話から、
一般化されたユークリッド空間内での二単体間のある意味最短距離経路が
求められると思っております。ASAP ではまた
460 :neetubot [] :2010/05/04(火) 18:46:51
Bibliography
河田敬義, "アフィン幾何・射影幾何", 岩波書店, 岩波講座 基礎数学, 1976/5/27
H. S. M. Coxeter, 銀林浩(訳), "幾何学入門 上", ちくま学芸文庫, ISBN978-4-480-09241-0, 2009/9/10
H. S. M. Coxeter, "Introduction to Geometry Second Edition", Wiley Classics Library Series, 1989
Melvin Hausner, "A Vector Space Approach to Geometry", Dover Pubns, 1998/06
http://books.google.com/books?id=L4ZnoQ6mCAwC&printsec=frontcover
Jon Dattorro, "Convex Optimization & Euclidean Distance Geometry", Lulu.Com, 2006/7/30,
http://books.google.com/books?id=byqvt2ArOLQC&printsec=frontcover
MIROSLAV FIEDLER, "MATRICES AND GRAPHS IN EUCLIDEAN GEOMETRY",
Electronic Journal of Linear Algebra ISSN 1081-3810, Volume 14, pp. 51-58, 2005/09,
http://hermite.cii.fc.ul.pt/iic/ela/ela-articles/articles/vol14_pp51-58.pdf
Allan L. Edmonds, Mowaffaq Hajja, Horst Martini, "Coincidences of simplex centers and related facial structures", arXiv:math.MG, 2004/11/04,
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0411/0411093v1.pdf
Allan L. Edmonds, Mowaffaq Hajja, Horst Martini, "Orthocentric simplices and their centers", arXiv:math.MG, 2005/08/03,
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0508/0508080v1.pdf
Allan L. Edmonds, "The Geometry of an Equifacetal Simplex", arXiv:math.MG, 2006/10/06,
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0408/0408132v2.pdf
461 :neetubot [] :2010/05/09(日) 20:34:42
>>459 方向ベクトル同士の余弦については、
正負どっちでもいいっちゃいいので 0≦|cos(θ_{n n'})|≦1 と書くぉ。
二面角 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9D%A2%E8%A7%92
を見れば、対象とする部分空間内の各超平面の法線ベクトルが成す角度
(の範囲)という定義が本筋っぽいので、共通部分は除外で後は同じようにやるぉ。
>>391 の1は一般化されたユークリッド空間内で、二複体のそれぞれの点列を含む
最小の部分空間(やはり私はこれをアフィン空間とは呼べない)同士 が成す角度の
範囲(方向余弦半径超楕円による)が応用のメインで、複体の点列の重心から
Singular Value Decompositionによって求まるCentroid SVD Hyperellipse
の特殊な場合である Simplex Steiner Hyperellipse が基礎のメインとします。
ということで、タイトルは
"Dual Subspace Distance apllied Centroid SVD Hyperellipse
of Simplicial Complex in Homogeneous Euclidean Geometry"
ぐらいしにて、基礎の基礎で単体・複体・特異値分解・疑似逆行列・正射影行列
・直交分解・アフィン変換あたりを、全体の空間をあらかじめ1次元過剰な斉次系で
考える Homogeneous Euclidean Space によって、このスレの基礎とするものを
全て記述できる気がしてます。間に合うかなぁー
462 :neetubot [] :2010/05/09(日) 23:07:47
このスレで辺乗行列\Bと呼んでいたものは Euclidean Distance Matrix (主にDらしい)
の全ての成分に1/2掛けたものっぽいです。まだ諸説ありよくわかりませんが、、
っていうか今回関係なく使いませんが…
John Clifford Gower, "Euclidean distance geometry"
http://scholar.google.co.jp/scholar?q=euclidean+distance+matrix+gower
とりあえず、↑のGower神関係の文献をあたれば良さそうです。ク、クリフォード??
Jon Dattorro, "Euclidean Distance Matrix"
https://ccrma.stanford.edu/~dattorro/EDM.pdf
↑の弟子っぽいDattorroさんも良さそうです。ともすれば工学の中の応用数学の分野
とも言えそうですが、このニッチな分野の近況がだんだん見えてきましたよ。
あと、任意の連立方程式の(最小自乗)解法については、
宮岡 悦良, 眞田 克典, "応用線形代数", 共立出版
あたりに載ってます。クラメルの解法どまりの本が多いですが、
(正)射影行列(および直交射行列と書いてあるのは今のところ見ませんが)
や特異値分解まで出てくる本もどっかで見た気がします。
今回、arXivに出そうと思ってるのは、どこかのウェブサイトかGoogle Scholar や
Google Books にpdfがある文献のみReferenceにしようと思ってます。
463 :neetubot [] :2010/05/10(月) 01:55:19
elsevierの"Linear Algebra and its Applications"
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/522483/description
にあるH Kurata, T Sakuma, "A group majorization ordering for Euclidean distance matrices", 2007
が気になるなぁーじゃあ5月31日まで集中します、何かあったらお気軽にどうぞ
464 :neetubot [] :2010/05/22(土) 11:21:29
Allan L. Edmonds, Mowaffaq Hajja, Horst Martini,
"Coincidences of Simplex Centers and Related Facial Structures"
http://www.emis.ams.org/journals/BAG/vol.46/no.2/b46h2ehm.pdf
"Orthocentric simplices and their centers"
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0508/0508080v1.pdf
の参考文献や
Malgorzata Buba-Brzozowa,
"Ceva's and Menelaus' Theorems for the n-Dimensional Space"
http://www.heldermann-verlag.de/jgg/jgg01_05/jgg0410.pdf
を発見した!研究者名でまとめたいなぁー
ところで,私がarXiv(Math.MG)へ投稿していいという承認を,
↓のURIから誰かして頂けると大変ありがたいです。
http://arxiv.org/auth/endorse.php?x=S433L3
465+1 :neetubot [] :2010/05/22(土) 15:50:14
立体行列
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1246851207/
立体行列?について当スレの内容から常識的に考えると、
m次元ユークリッド空間内のある点を表す斉次座標の(m+1)次元
列ベクトル \~p_i に対して、アフィン変換する(m+1)×(m+1)行列
\~M_i を掛けたときに、別の点を表す(m+1)次元列ベクトル
\~p'_i ( = \~M_i \~p_i ) となるとすれば、この式を i=0…n に対して
奥行き方向に並べた式 \~P' = \\~M \~P (↑)の \\~M として立体行列
(階数3のテンソル、または、3次元配列)が得られる。(ただし、行列の標準内積ベースの演算を使っている)
ここで、\~P' および \~P が互いにn次元単体を表す一般的な点列の位置座標だとすれば、
標準的に空間ごと別のアフィン変換をする(m+1)×(m+1)行列 \~M’ を用いて
普通の行列演算で \~P' = \~M’ \~P と書けるはずである。これは、さきの
立体行列 \\~M の各奥行き方向の(n+1)個ある(m+1)×(m+1)行列 \~M_i に対して、
一つの(m+1)×(m+1)行列 \~M’ が一意的に定まる \~M’= f[ \~M_0, …, \~M_n ]
のような奥行き方向の変換式が存在するということになる。
以上より、アフィン変換行列群の例における立体行列は、
普通の一つのアフィン変換行列に帰着できてしまうことになる。
これによって、立体行列による多重線型変換(?)による拡縮・回転・平行移動
の成分がさきの \~M’= f[ \\~M ] を解くことによって一意に求まる.気がする。
466+1 :neetubot [] :2010/05/22(土) 16:33:34
面白い問題おしえて~な 十六問目
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1254690000/186
>186 :132人目の素数さん :2010/05/21(金) 08:45:41
>時計の時針・分針・秒針の全てが同じ長さ・同じ重さだったとする。
>
>
>時計が一番つらい時間は何時何分何秒か?
等速で均質な針が動く時計において、12時ちょうどから時計回りの方向に
時針(長さl・重さm)がθだけ回転したときには、分針(長さl'・重さm')は12θ
だけ回転し、秒針(長さl''・重さm'')は720θだけ回転していると考えられる。
この連続理想時計で、ちょうど6時の方向に重力加速度gがかかる場合、
時針・分針・秒針の重さによって時計中心にかかるモーメントの大きさの総和 N は、
N = ( l m g |sinθ| + l' m' g |sin(12θ)| + l'' m'' g |sin(720θ)| )/2 と表せる。
よって、Nが最大となるときのθは…絶対値が外れる条件で微分…するのはめんどいし、
結論: これは離散的な数値計算した方がいいな…
っていうか、そんなに気になるなら、時計を寝かせて使うか、時を止めてしまえっ!
むしろ、論文書くの間に合ってないので、私のために世界の時を止めて下さいザワールド
467 :neetubot [] :2010/05/23(日) 15:15:14
>>465 \~M’= (\~M_0 + … + \~M_n) / (n + 1)としか
予想できんが、証明なんてできそうにないなこれ。
>>466 この連続理想時計の3つの針が12時ちょうど以外の12時間で
ちょうど重なることはあるか考える。まず、時針・分針が重なるとき
0<θ<2πで θ+2kπ=12θ(k=1,…,10)となればよいので、
θ=2kπ/11 (12時を基準に1周を11等分した10箇所)で時針・分針が重なる。
同様に計算すると、分針・秒針が重なるのは59等分された58箇所で、
時針・秒針が重なるのは719等分された718箇所であるため、
11と59と719がそれぞれ互いに素であることから時針・分針・秒針が
全て重なりあうことはこの連続理想時計では12時ちょうど以外には
ありえないということが導ける。同じように24時間時計でも離散的に
動くとしてもありえないとは思うけど、本スレの針交換の意味がわからん。
まぁ、俺の考えなどどうでもいいことだから、向こうのスレを汚さずこっちでやりますた
468 :132人目の素数さん [↓] :2010/08/06(金) 02:40:52
386
前略、neetubotという猫先生の代理のものです。遅れましたが、代理でメッセージをお伝えします!
------------------------以下、猫先生からのメッセージ--------------------------
今ちょっとプロバイダーの問題でネットが止まっています。現在プロバイダーとやり取りをする
為に準備中で、一時的にネット接続が通っていますがまた直ぐに切れてしまいます。なので
2ちゃんへの書き込みが出来ません。
実はネット接続が切れたのは1月20日(つまり昨日)の午前中で、明日の朝10時にまたネット
の接続が切れてしまうそうです。私としてはきちんと話し合いをして状況を理解してから物事
に対して対応しようと考えていますので、取り敢えずは2ちゃんにはカキコはしない考えです。
とにかく何かとこの世は厄介ですが、毅然とした態度で臨む考えです。
取り敢えずは早急に何とかしてネット接続を確保してから事態を分析しなければならないので、
暫くは2ちゃんではROMになってしまう事を恐れますが、でも私がめげるという考えは皆無な
のでどうかご安心下さい。
なるべく早急に2ちゃんに復活してバリバリとカキコを開始したいと考えています。なので、
もし機会がありましたらこの「私のメッセージ」を2ちゃんの皆様にも貴方様からお伝え下さい。
敬具
猫は淫獣拝
2010年1月21日
------------------------以上、猫先生からのメッセージ--------------------------
私も、猫先生のご復活を祈り、応援しております!かしこ!
365 :neetubot [] :2010/01/23(土) 20:42:11
さて、バカやってないでがんばるか…
m次元ユークリッド空間内でn次元単体のk次元点足複体の各頂点\P'からの
自乗距離が最小になる点は、他ならぬ\P'の重心\p_G[\P']=\P' \1 / (_(n+1) C_(k+1))である。
\P'にk次元外接n次元超楕円面が存在するとすれば、元のn次元単体と
点足単体のk次元外接n次元超楕円面の中心を考えれば、
\P'のk次元外接n次元超楕円面は\p_G[\P']が中心であると考えられる。
それをふまえて、次に、この\P'のk次元外接n次元超楕円面の半径行列を求める。
366+2 :neetubot [] :2010/01/23(土) 21:13:58
正確には、m次元ユークリッド空間U^m内の位置行列\P'で作られるn次元単体の(m≧n≧2)
内部点\p_aによるk次元点足複体\P'_kの(n≧k≧0)のk'次元面(n≧k'≧0)全てに
接する(n-1)次元超楕円面(たぶん、存在するとしたら重心を中心として全ての面の重心で接する)
なので、仮にn次元単体の k次元点足 重中 k'次元面接((n-1)次元) 超楕円面S'_{A_k^k'}^(n-1)と呼…
誰の超スーパー必殺技だよw
367+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/01/23(土) 23:28:30
まったく、もっとまともな議論をしたらどう?
猫とかに構っているとお粗末になるのか?
368 :neetubot [] :2010/01/24(日) 00:03:57
>>367 ん?はじめましてwどんな議論がお望みですか?
猫先生に構ってなかった頃はお粗末ではなかった所までは読んでくれたんですか?
どこまで理解できてますか?
369 :neetubot [] :2010/01/24(日) 00:05:59
>>366 の2行目:k'次元表面
過去ログ見てたらすげぇいかれてるぜw 数学は楽しいなぁ
>>289 より、(n/n') Σ_{i=1…n'} (\p'_i - \p_Q) (\p'_i - \p_Q)^T = \R_Q \R_Q^T
までは見つけた。
370 :neetubot [] :2010/01/24(日) 13:10:33
>>366 の2行目:((n-1)≧k≧0) ((n-1)≧k'≧0)
k次元点足複体\P'_k に対し、そのk'次元表面の重心全てを\P'_{a_k^k'}で表せば、
n次元単体のk次元点足重中k'次元面接超楕円面の半径行列\R_{a_k^k'}に対し、
\R_{a_k^k'} \R_{a_k^k'}^T = (n/n') Σ_{i=0…(n'-1)} (\p'_{i a_k^k'} - \p_G[\P'_{a_k^k'}]) (\p'_{i a_k^k'} - \p_G[\P'_{a_k^k'}])^T
= (n/n') \P'_{a_k^k'} (\E - (\1 \1^T)/(\1^T \1)) \P'_{a_k^k'}]^T = \P \X \P^T
となる。このサイクリックな式形からk'の値のみが違うこの超楕円面は全て相似になると推測する。厳密な計算はそのうち…
371 :132人目の素数さん [↓] :2010/01/24(日) 14:22:48
http://www.youtube.com/watch?v=xJMdAcPWs-c
http://www.youtube.com/watch?v=FRqJ2gZYBmA
http://www.youtube.com/watch?v=8gIP4FKjr9Q
http://www.youtube.com/watch?v=LVpydYb1B6E
http://www.youtube.com/watch?v=xJMdAcPWs-c
http://www.youtube.com/watch?v=qxWy19lQyLk
http://www.youtube.com/watch?v=z-SCVL3aZXg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-Tl23hSSiuA&feature=related
372 :neetubot [] :2010/01/24(日) 17:53:33
盛大にAKB48を誤爆しましたねw
誰が好きなんですか?言われてもわかりませんが。
373 :neetubot [] :2010/01/24(日) 20:47:07
k次元点足複体\P'_k に対し そのk'次元表面の重心全てを\P'_{a_k^k'}で表したとき、
\P'_{a_k^k'}の頂点の全てからの自乗距離が最小となる点\p_Xは、F'_G[\p_X]=
\sum_{i=0…n'-1} (\p'_{i a_k^k'}-\p_X)^T (\p'_{i a_k^k'}-\p_X) →最小となればよいので、
\p_X = \p_G[\P'_{a_k^k'}] = \p_G[\P'_k] であり、このときF'_G[ \p_G[\P'_k] ] = n' r_{a_k^k'}^2が最小値となる。
上記は、\P'_{a_k^k'}の全ての頂点は\p_G[\P'_k]からだいたい最小の自乗平均距離 r_{a_k^k'}
(統計学的に標準偏差も定義すれば r_{a_k^k'}±ε_{a_k^k'})の位置にあると見込むことが出来る。
ということで、\P'_kの重心\p_G[\P'_k]を中心とし半径r_{a_k^k'}の超球を仮にk次元点足k'次元面重重均超球S_{a_k^k'}と呼ぶ。
点足複体の関係で美しい性質を持つと考えられる概念は今の所はこれぐらいです。不等式の玉手箱や~
374 :neetubot [] :2010/02/05(金) 00:02:55
n次元単体\Pに対して(その同じ部分空間内の)点\p_a = \P \a(ただし、\1^T \a = 1)を使って
点足単体\P_A=\P \Aの点足単体\P \A \Aの点足単体\P \A \A …と無限回繰り返して
作られる点足無限単体は \P \A^∞ = \P \a \1^T と収束するはずなので、点足k回単体と同じ部分空間内の
どんな点\P \A^k \b / (\1^T \b)でも点足無限収束点は \P \a自身であると考えられる。
上記をふまえて、点反足k回単体 \P \A^(-k) に対してその同じ部分空間内の点\P \A^(-k) \b / (\1^T \b)
を定義したとき、点反足無限単体に対してこの点反足無限発散点\P \A^(-∞) \b / (\1^T \b)はどこに行くだろうか?
\A^Tを固有値分解(ひとつは固有値1に対する固有ベクトル\1とか)できれば求まる気がするんだけど…朝青龍…
375+1 :neetubot [] :2010/02/28(日) 02:44:29
↑はまだ計算できてはいませんが、\P \A^(-∞) \bは\P \a と \P \b が通る直線の無限遠点だと思います。
ところで、全てのn次元単体は、n次元正単体を剪断拡縮・回転・平行移動して作られることから、
このスレではその座標行列である(n+1)×(n+1)アフィン変換行列(群?)全体の性質を調べていたようです。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1267096322/67
> http://anond.hatelabo.jp/20100226161245
> 数学的には何もない空間は何次元になるんですか
というとても興味深いレスを発見し、このスレでもどこかで便宜上-1次元を使った
記憶もありますが、1次元増やして計算する斉次座標系というかアフィン変換で
n次元部分空間というかm次元ユークリッド空間全体考える時に垂直で常に存在する虚軸を
一本入れて常に1次元増やした系で計算するとうまくいきそうで、今ちょうど計算してます。
ということで、上記の質問に関して、何次元だろうが何もない空間は普通にいくらでもありますが、
美しく考えるためにどうしても必要だと思われる-1次元単体というものが何を表しているか
という質問だと思えば、何もない空間か無限遠全体の空間か虚軸方向も入れて何か定義するか
、特に先行研究に思い当たる節がないので、今自分で考えるところです、みたいな感じです。
まぁ、みなさんは興味ないかもしれませんが、n次元単体の重中k次元面接超楕円面の証明に
オイラー公式やリーマン球っぽく個人的趣味でどうしても虚軸方向を加味したいので、
まぁ、うまくできたらUPします。実数体でなく複素数体で考えたら、頭がフットーしそうだよおっっ(
376 :neetubot [] :2010/03/02(火) 22:55:40
>>375 は別に虚軸じゃなくて、もととなるm次元ユークリッド空間の1軸からm軸まで
全てに垂直な実数の0軸を入れて考える、つまり、普通の斉次ベクトルで考えた方が、
複素数体に拡張するときにもいいと思うので、そうします。っていうかそっちのが計算しやすかった。
座標の斉次と違って計算に一時的にしか出てこないし、これが射影幾何学のように
分母になるための項だと言えるなら、そのときは私も斉次も同次も同じだと主張します。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1261794262/291
の二つの二次曲線の交点の問題ですが、二つの二次曲線をそれぞれ
線型化したときの係数ベクトルを \a=[a, b, c, d, e, f]^T, \a'=[a', b', c', d', e', f']と
すれば、二つの二次曲線両方の上に存在する点 \x=[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^T に
対し、次の自乗和の式 α(\a^T \x)^2 + α'(\a'^T \x)^2 がこのとき最小値0をとる。
ということで、上式の\xについての最小自乗法から(\a α \a^T + \a' α' \a'^T) \x = \0
となる \x で各成分が条件[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^Tを満たすものが最大4点あるらしいと…
これじゃ4次方程式どころじゃねぇ解けねぇ。という2ch復活記念カキコ
377 :neetubot [] :2010/03/02(火) 23:01:47
最小自乗法じゃなくても連立方程式から [\a, \a']^T \x = \0
となる \x で各成分が条件[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^Tを満たす…と同じことでした。
意味もなく難しく言っちゃった。てへっ。しかし、以下同文です。
378+2 :neetubot [] :2010/03/07(日) 22:33:44
連立方程式から [\a, \a']^T \x = \A^T \x = \0 より、固有値分解によって得られる
\Aに直交する\Bを介して \x = (\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T) \y = [\b_1, \b_2, \b_3, \b_4] \t
= [\s_1, …, \s_6]^T \t と表せば、[x^2, x y, y^2, x, y, 1] = [\s_1^T \t, …, \s_6^T \t] であるので、
直交行列\Bの4変数の座標\tに対して、下記の\tについての4式
\t^T \s_4 \s_4^T \t = \s_1^T \t
\t^T \s_4 \s_5^T \t = \s_2^T \t
\t^T \s_5 \s_5^T \t = \s_3^T \t
1 = \s_6^T \t
のような四元二次連立方程式を解くことに帰着できる。
と、ここまでです。この4式から、線型変換で一元四次方程式を解くことに帰着するか、
あわよくば非線型変換で四元一次連立方程式にでもなればと思ったのですが…
1 = \s_6^T \tはオフセット付3次元部分空間(アフィン空間?)だから、\tの解を3次元正単体の
アフィン変換で表すとしたら解が4通り出るのが謎としても、二次形式の拡大係数行列
自体のアフィン変換で単位超球や超平面に帰着するとかかな、難しいなー
379+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/07(日) 22:41:23
非線型は解法を知らないと難しいですから
たしか以前に、非線形連立を線型連立で解こうとしてましたよね?
380 :neetubot [] :2010/03/13(土) 21:42:11
>>379 おっ、いつのまに、、知ってる方のようですのでお久しぶりです。
>>378 の件と思いますが、二次までなら線型化でいけると思いきや、
例えば二次曲線 \a^T \x = 0 で 座標 \x=[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^Tの点列から
一通り求まるような係数 \a=[a, b, c, d, e, f]^Tを当嵌するのは >>263-265 あたりでうまくいきましたが、
今回の件は、2つの二次曲線の係数 [\a, \a'] = \A から交わる点の座標を求めるということで、
\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T = \B \B^T と直交行列を求めれば >>378 の式形から
\x = \B \t / (\e_6^T \B \t) さらには \x = \B \C[\B^T \Λ \B] \1 / (\e_6^T \B \C[\B^T \Λ \B] \1)
のような形に導出できそうな気がしてます。
まとめると、線型化した座標の方の導出はそれ自身に条件が入るので難しいと思っている、ということです。
しかし、二次までの幾何学ということで、固有値問題などに帰着すれば美しい解法はあるもんだと思ってがんばってます。
>>379 さん、何か非線型な行列方程式の解放などご存知でしたらご助言頂けるとありがたいです。
381+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/13(土) 22:13:06
お聞きしたいのは私の方なんですが、そうですね…その行き詰まり方だとケーハミ定理の復習ですかね(affineも考えると3x3)。
線型と累乗を深く理解できるようになるでしょうね。
普通は3x3をちゃんと勉強することもないと思いますが…
382+1 :neetubot [] :2010/03/13(土) 23:00:34
数学系質問掲示板について語るスレ2
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1206831469/911
楕円面の族
2010年03月08日 12:13:44 KM
お願い致します。
x^2 + 2*y^2 + 3*z^2 + w^2 = 1, 3*x + 2*y + 3*z + 5*w = k
の交わりをx,y,z空間に正射影し、
(1)得られる曲面が楕円面になるkの範囲を定め
楕円面の主軸を求めよ。
(2)上の楕円面の族の包絡面を求めよ。
(3)楕円面が点に退化するようなkを求めよ。
という、4次元ユークリッド空間内で、3次元超楕円面と kで定まる3次元超平面
との共通部分(前者を後者で切った断面)をx,y,z空間に正射影したもの
(w=(k - 3*x - 2*y - 3*z)/5 を前者に代入しwの成分を消したもの)の問題を解きます。
(1)、後者をベクトル[x,y,z,w]=[3t,2t,3t,5t]の点を通りそのベクトルに直交する
3次元部分空間と考えれば、(3t)^2+2(2t)^2+3(3t)^2+(5t)^2 = 69 t^2 = 1より
-1/(√69) < t < 1/(√69) が求めるものなので、-47/(√69) < k < 47/(√69) ■
で共通部分が楕円面となるが、この楕円面の3つの軸はアレじゃないですか…
(2)、3次元超楕円面の周囲をくまなく3次元超平面で輪切りにしてx,y,z空間に正射影
してるだけなので、求める2次元楕円面は x^2 + 2*y^2 + 3*z^2 = 1 で表せる ■
(3)、(1)より k=±47/(√69) ■
ということで私は、全ての二次超曲面は、超球面を透視投影すれば得られると思って
ますが、まぁ同じことですが最近は、n次元ユークリッド空間内の(n-1)次元超球面を使って
直交する0軸方向に超球錘を作り、それをアフィン変換したものと元のn次元ユークリッド空間
との共通部分(断面)によって全ての二次超曲面が表せると考えた方が都合良さそう
と思いました。というのは、今後、二次超曲面と超平面の共通部分や最小最大距離を
考えるための備忘録として、ここに書きました。とりあえずゴメンナサイ
383 :neetubot [] :2010/03/13(土) 23:14:23
>>381 コメント速いっすねー 私が遊んでる間に…
>>378 では\x = (\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T) \y = [\b_1, \b_2, \b_3, \b_4] \t / (\s_6^T \t)
とおいた瞬間に、普通に二次曲線同士の交点を求める四次方程式が
固有値分解をすることに帰着されたと私は信じたいので、あとは定数倍が関係ない
\t^T \s_4 \s_4^T \t = \t^T \s_6 \s_1^T \t
\t^T \s_4 \s_5^T \t = \t^T \s_6 \s_2^T \t
\t^T \s_5 \s_5^T \t = \t^T \s_6 \s_3^T \t
の3式を満たすように \tの3変数分を解けば、きれいな公式が作れる気がしてます。
いやほんとに \x = \B \C[\B^T \Λ \B] \1 / (\e_6^T \B \C[\B^T \Λ \B] \1)
の形で(\C[]を余因子行列として)6×6制約行列\Λに3変数分入って4通り導出できると
私は信じて疑わない!と言っていてもあとで式から覆ることが何度もあるこのスレ
384+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/13(土) 23:30:35
>>382
ガウス先生は複素数根の真意を悟った者がまた一人増えたので大喜びでしょうね。
385+1 :neetubot [] :2010/03/14(日) 01:12:50
>> ケーハミ定理って略は初めて聞きました。n次元拡張もなら↓が詳しいです。
Cayley?Hamilton theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Cayley%E2%80%93Hamilton_theorem
しかし、私的には使うと逆に式が長くなるという印象があり、ぶっちゃけ使い方よくわかりません。
というのも、固有値分解(特異値分解)は、ある部分空間に直交する部分空間
を求める場合などに、ソフトで出せる固有値と固有ベクトルとかのセットで出せば、
それが幾何学的に何を表しているか想像や図示できるような感じですが、
こと固有値を求めるための固有方程式(とそれを応用したケーハミ定理)については
幾何学的に全く想像ができないからです。
このスレでも、>>235 あたりで非斉次行列多項方程式を解くみたいな事やりましたが(!?)、
同じアフィン変換を何回もかけるとかじゃなく、n×n行列をn回かけるというような状況でもなく、
今回ただの二次形式なのでいける気がしてますが、今までにこれらをベクトルで定式化した
という話は聞いたことがないので、実際やれと言われたら地道に4次方程式解く方法で私もいくと思います。
>>384 複素数根の真意なんて滅相もございません。とりあえず二次超曲面と二次超曲面の共通部分考える
前に、二次超曲面と超平面の共通部分(たぶん二次超曲面)を考えたほうがいいとわかった、いい問題でした。
386+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/14(日) 07:27:52
>>385
A X + B = C #=>mat
X = A^-1 (C-B) #=>mat
A X A^1 = (C-B) A^1 #=>mat
(A X + B)(u) = C(v) #=>vec
387 :neetubot [] :2010/03/20(土) 00:16:49
>>386 ?2つの二次曲線の交点のベクトル解の定式化ですか?
たぶん2次拡張座標の方を X = [x, y, 1]^T [x, y, 1] のように3×3行列化する
まだ私は考えたことがない方法のようでしたので、少し考えました。
まず、全ての二次曲線が [a_1, a_2, a_3] [x, y, 1]^T [x, y, 1] [a_4, a_5, a_6] = 0
の形で表すことができるかですが、[x, y, 1] A [x, y, 1]^T = [x, y, 1] [a_1, a_2, a_3]^T [a_4, a_5, a_6] [x, y, 1]^T
と分解できるためには拡大係数行列 A の階数が1でなければならないので無理でした。
また、Xを上三角行列などのよく見る形にしようとしても、係数の自由度が足りず
任意の二次曲線を表す形にはできませんでした。A X の形には9つの等式が必要で無理です。
ということで、座標から係数出すとき使った[x^2, x y, y^2, x, y, 1]^T [x^2, x y, y^2, x, y, 1]を使うのか…
余計大変です。[x^2, x y, y^2]^T=\B_{上} \t と [x, y, 1]^T=\B_{下} \t で分けるんじゃね?
870 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/19(金) 00:15:37
>>833
>>842
長い間2元2次交点の難問に付き合っていただきありがとうございます。
ベクトル空間(体はC^1など)で考えていたのでその完全な証明は幾何ベクトルを使った証明で知っていましたが、
解法の1つとして、行列成分(行列式)として扱った場合の根(この場合は交点)の最適な配置場所がわかりませんでした。
行列による解法は別のアプローチを研究中ですが、余因子展開の方法もじっくり検討してみます。
また良い問題をありがとうございました。
俺も興味あるし、このスレで一緒に考えようぜっ!
とりあえず、四次方程式の解法・解の公式は↓が詳しいよ。
http://www.akamon-kai.co.jp/yomimono/kai/kai.html
388 :neetubot [] :2010/03/20(土) 00:26:47
とりあえず、↓の人、超好きです。
分からない問題はここに書いてね329
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1267096322/842
842 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/18(木) 18:38:41
>>833
n*n行列で考える
xI_n-A_n = B_n = [
[x-2,-1,0,...,0]
[-1,x-2,-1,0,...,0]
[0,-1,x-2,-1,0,...,0]
...
[0,0,0,......,0,-1,x-2]]
を余因子で展開すると
|B_n| = (x-2)|B_{n-1}| - |B_{n-2}|, |B_1|=x-2, |B_2|=(x-2)^2-1
だからx-2=2cosθとおけば帰納的に|B_n|=(sin(n+1)θ)/sinθが得られ
A_nの固有値λ_kとその固有ベクトルu_kはλ_k=2+2cos(kπ/(n+1)),
u_k=t[sin(kπ/(n+1)),sin(2kπ/(n+1)),...,sin(nkπ/(n+1))]
(k=1,2,...,n)
n=4の場合の固有値は{2+2cos(kπ/5)|k=1,2,3,4}={(5±√5)/2,(3±√5)/2}
この行列、何か名前ついてなかったっけ?
(n+1)×(n+1)行列で考えたときどんな図形の座標を表すのかとか、
3次方程式を三倍角の公式に帰着するようにn次方程式をn倍角に…(それは無理か…)
とか興味深い行列!バンデルモンドだっけ?(適当)
389 :neetubot [] :2010/03/20(土) 18:53:00
異なる二次係数 \a, \a' で表される二次曲線の交点(x, y)を求める問題を、
[\a, \a']^T [x^2, x y, y^2, x, y, 1]^T = \A^T \x = [0, 0]^T と定式化すれば、
\x = (\E - \A (\A^T \A)^(-1) \A^T) \α = [\s_1, \s_2, \s_3, \s_4, \s_5, \s_6]^T \t / (\s_6^T \t)
と表せて、二次拡張座標 \x 自身の制約から(中身が対称行列となるように変形すれば)
\t^T (\s_4 \s_4^T - (\s_6 \s_1^T + \s_1 \s_6^T)/2) \t = \t^T \F_1 \t = 0,
\t^T ((\s_4 \s_5^T + \s_5 \s_4^T)/2-(\s_6 \s_2^T + \s_2 \s_6^T)/2) \t = \t^T \F_2 \t = 0,
\t^T (\s_5 \s_5^T-(\s_6 \s_3^T + \s_3 \s_6^T)/2) \t = \t^T \F_3 \t = 0 の3式が
成り立たなければならない。これは、3つの決まった4×4変換行列 \F_1, \F_2, \F_3をかけた
ベクトルが元のベクトルと全て垂直となるような4次元列ベクトル \t を求める問題に帰着できたことを表している。
つまり \t は、\F_1 \t = \0, \F_2 \t =\0, \F_3 \t = \0となるkernelの共通部分、
よって、[\F_1^T, \F_2^T, \F_3^T]^T \t = \0 で \s_6^T \t = 1 となる \t に対して
[x, y]^T = [\s_4, \s_5]^T \t のように解ける?と思いきや、これでは解が一通りに定まって
しまうような感じで とても4通り求まらないので、どこか2段落目とかでおかしいことやらかしたな…
とはいえ、あとは通常の4次方程式に帰着する計算と整合性を付ければいいような気がするので、
この解き方ではこれが限界かなぁ。
同じように4次方程式に帰着できる「二次曲線とある点との距離(およびある点を通る接線)」
「n次元単体の等角中心」の問題とともに、これからもこの問題は私のタスクリストに入れときます。
390+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/20(土) 19:10:27
タスクリストってのがるんですか。
同じように4次方程式に帰着できる
「二次曲線とある点との距離(およびある点を通る接線)」
「n次元単体の等角中心」
「二次曲線の交点(x, y)を求める問題」
他のタスクは何かあるんでしょうか?
391+5 :neetubot [] :2010/03/20(土) 20:46:04
ちなみに、二次超曲面とある点との距離(およびある点を通る接線)は…
と書いてるうちにコメントが来ました、ありがとうございます!
>>390 漠然と自分の中で考えてるだけでしたので、ここでちゃんとリスト化します。
1:アフィン変換とSimplex Steiner Hyperellipse(5月31日迄)
(始点が同じ(n+1)単位行列で表されるベクトルの終点全てはn次元正単体となり、
そのn次元正単体の重心まわりのアフィン変換で全てのn次元単体が表せることを用いて、
全てのn次元単体にはその重心を中心とし各k次元面に接するような超楕円体が存在することを示す)
2:n次元単体の五心と平石究点(ナルハヤ)
(2次元単体(三角形)と同じように、n次元単体にも五心(重心・垂心(存在条件あり)・
広義傍心(内心含む)・k次元面心(k=1…(n-2) 存在条件あり)・外心)が定義でき、
特に重心と外心を結ぶオイラー線上に広義垂心や様々な性質を持つ点が存在することを示す。)
3:n次元単体の諸性質の応用
(アフィン独立な(n+1)点と一定の距離比にある分点心と一定の距離差にある部分境界超平面の関係・
従属な1点を加えたときに外接超球が存在する条件(複体外接超球)・n次元単体とそのある内部点
で一意に決まる点足複体の超体積や無限収束点や外接楕円体などの諸性質など)
4:二次超曲面と解析射影幾何学
(二次超曲面上のある点での接空間およびその中のある接線方向に対する曲率半径・
二次超曲面とある点の距離との距離(およびある点を通る接線)・二次超曲面とある
超平面の共通部分と超球錐の図との関係・「二次曲線同士の交点」(←new!))
5:数学板の気になった問題を解く
ぐらいですか。。最近、5しかやってねぇ!というわけでもない、ゆっくりしていってね!!!
392 :neetubot [] :2010/03/20(土) 20:54:57
n次元単体の第6心の等角中心(Simplex Fermat-Torricelli Center)
略して単体角心を忘れてました。結局3かもしくは4と関係するならとても嬉しいという感じです。
一応、3次の項がない 下記の一元4次方程式 を解くことに帰着できているつもりです。
http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/22.html
ここらへんは、一つのアイディアで芋づるだなどと思って、保留してます。俺人生保留中
393+2 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/20(土) 21:37:29
三線座標と重心座標(12)
三角形の中心
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%8E%A5%E5%86%86
とかはやらないんですか?
それと、離散ついでで整数(4)やベクトル(36)は関係してないんですか?
というよりも「面積」のことが良く分かってないみたいで、幾何学上の面積すら意味付けが出来てないって感じですけど・・・
えぬ次元というからには、ABC3点を通る外接円の外心点のベクトル式はすぐ求められますよね。そういことじゃないんですか?
394+1 :neetubot [] :2010/03/20(土) 23:59:46
>>393 面積(2次元超体積)がわからないんですか?http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D
ここでは、n次元単体の超体積 http://en.wikipedia.org/wiki/Simplex#Geometric_properties
がわかっているとして話をしますが、まず↑より、m次元ユークリッド空間内で原点からn次元単体の各i頂点
(i=0…n)への位置ベクトルを \p_i で表せば、正方行列\Xの余因子行列を\C[\X]としたとき 定義より
n次元単体の超体積 v=√(det([\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0]^T [\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0])) / (n !)
=√(\1^T \C[0, \0^T; \0, [\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0]^T [\p_1-\p_0, …, \p_n-\p_0]] \1)/(n !)
=√(\1^T \C[ [\p_0, \p_1, …, \p_n]^T [\p_0, \p_1, …, \p_n] ] \1) / (n !) と表せます■
(ちなみに、超体積の意味は、方向行列の内積行列の行列式の平方根に比例する量であり、
図形自体の大きさを示す、昔の人がうまく定義した計量だと思いますw いいものですね)
で、三角形の重心座標ですが、このスレでは拡張してn次元単体の分積座標と呼び、>>282あたりでやりました。
分積座標\aは、n次元単体のあるi頂点(i=0…n)以外のn個の頂点で作られる(n-1)次元単体面をi対面と呼べば、
n次元単体の内部点 \p_A = \p_0 a_0 + … + \p_n a_n (全てのiでa_i>0)と例えば0対面で作られる
内部n次元単体の超体積 v_0 は、内部の列や行の足し引きで値が変わらない行列式の性質から
v_0 =√(\1^T \C[ [\p_A, \p_1, …, \p_n]^T [\p_A, \p_1, …, \p_n] ] \1) / (n !)
=√(\1^T \C[ [\p_0 a_0, \p_1, …, \p_n]^T [\p_0 a_0, \p_1, …, \p_n] ] \1) / (n !) = a_0 v
となり、これは\p_Aの絶対分積座標の値a_0が内部超体積と元の超体積の比v_0/vとなることを表しています。
続きますー
395+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 01:27:31
「図形」の「大きさ」ですか。
では「角度」はどうやって定義して、表現してるんですか?
それと、位置ベクトル(普通の[a,b,c]のやつ)と行列(正方n x nやm x n)に何かしらの違いを見出しているか否か?
群は =>matのみか、=>vecのみか、=>mat or vecを考えているかなど何かしらの自分の公理を定義して「交点を出す」「面積を出す」のに適したなどの目的・目標を定めて計算してるんでしょうか?
それとも何らの目的も無くただ行列計算(一次変換)したいだけの「超」一般化なんですか。
396+2 :neetubot [] :2010/03/21(日) 01:40:36
>>393 また、三角形での三線座標・四面体での四線(面?)座標は、このスレでは拡張してn次元単体の分面座標と呼んでいます。
定式化は、i対面からの距離がそれぞれj_iとなるn次元単体の内部点を分面心 \p_J と呼ぶと下式のように導出できます。
まず、i対面と分面心 \p_J で作られる内部n次元単体のn次元超体積v_iは元のn次元単体の超体積vの
j_i / √(\h_i^T \h_i)倍(\h_iはi頂点からi対面への垂線ベクトル)となっているので、>>394 の分積(重心)座標より、
\p_J = \p_0 j_0 / √(\h_0^T \h_0) + … + \p_n j_n / √(\h_n^T \h_n) と導出できます。
(このとき、v_0+v_1+…+v_n=vであるため j_0 / √(\h_0^T \h_0)+…+ j_n / √(\h_n^T \h_n)=1
となる(絶対分面座標の条件))
これらは http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_center#Trivia の範囲であり、>>391の2か3かトリビアです
>えぬ次元というからには、ABC3点を通る外接円の外心点のベクトル式はすぐ求められますよね。そういことじゃないんですか?
そういうことですよ。そのWikipediaの外接円の式は、岩波数学辞典にも載っていますが、拡張性に優れず、私はあまり好きじゃないです。
このスレでは、古いですが http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html などから、(m次元ユークリッド空間内で)
原点から\P = [\p_a, \p_b, \p_c]の終点で作られる2次元単体ABCの外心\p_Oについて下記のように導出します。
まず、(\p_a - \p_O)^T (\p_a - \p_O) = (\p_b - \p_O)^T (\p_b - \p_O) = (\p_c - \p_O)^T (\p_c - \p_O)
= r_O^2 (外接円の半径の自乗) から、例えば\p_a^T \p_a + (\p_O^T \p_O - r_O^2) = 2 \p_a^T \p_Oとなるので、
[\p_a, \p_b, \p_c]^T \p_O = \P^T \p_O = [\p_a^T \p_a, \p_b^T \p_b, \p_c^T \p_c]^T/2 + \1 (\p_O^T \p_O - r_O^2)/2
で、ごにょごにょして
\~b_σ = [(\p_a^T \p_a)/2, (\p_b^T \p_b)/2, (\p_c^T \p_c)/2]^Tとすれば、
\p_O = \P (\C[\P^T \P] \1 + \~C[\P^T \P] \~b_σ) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)と導出できます。
このとき、外接円の半径 r_O は だいたいhttp://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html のようにごにょごにょです。
ごにょごにょの部分は明日のこの時間までに http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html あたりをいじって報告します
397 :neetubot [] :2010/03/21(日) 02:38:41
>>395 一般的に単位ベクトル\l_1,\l_2同士の「角度」は内積値のアークコサインθ=Cos^{-1} (\l_1^T \l_2)じゃね?
この場合の「面積」なら(√det[[\l_1,\l_2]^T [\l_1,\l_2]])/2=(√det[[1, cosθ], [cosθ, 1]])/2=|sinθ|/2となる
(単位円内の2半径が作る三角形の面積を求めた)し。えー何が言いたいかというと、「面積」「角度」は普通の
ユークリッド空間で使われるものと同じで、それじゃない定義や意味(n次元超立体角とか自分で定義すること)は
今のところないです。別に普通の高校生が直交座標系でやってることと同じというか(まぁ行列計算は使いますが)
私はほとんどベクトルを列で表しますし、行列は列ベクトルを行方向に並べたもの(方向行列\Lとか)として使う場合もあれば、
ある意味を持った変換行列(特に正射影行列\W=\L (\L^T \L)^{-1} \L^Tとか)として使うこともある感じですか。
いや、行列はただの入れ物としてその都度幾何学的意味があれば勝手に名前つけて呼んだり、いろいろ考えます。
アフィン変換群としてなら(n+1)×(n+1)行列で、m次元ユークリッド空間内で位置ベクトル\pや方向ベクトル\lなら
m次元列ベクトル、その中でn次元単体を表すアフィン独立の位置行列ならm×(n+1)行列\P・線型独立の
方向行列ならm×n行列\Lと言うような名前と記号を付けてますね、計算しやすいように。
>何かしらの自分の公理を定義して「交点を出す」「面積を出す」のに適したなどの目的・目標を定めて計算してるんでしょうか?
普通の「ユークリッド空間内で」と前置きすることによって、天下りするユークリッドの公理を基に、
普通の行列計算がうまくできる普通の直交座標系で、「n次元単体の五心を出す」とか >>391 に例示した
いろいろな幾何学的性質を普通のユークリッド空間内で行列計算によって美しく解くというのが目的・目標です。
398 :neetubot [] :2010/03/21(日) 02:47:28
>それとも何らの目的も無くただ行列計算(一次変換)したいだけの「超」一般化なんですか。
?確かに俺は行列の式に美しさを感じる変態で、幾何学的な量を導出するための行列計算はホントに美しいぜw
しかし、目的はあくまで幾何学的性質を一発で導出するための定式化で、そのための行列計算はただの必要な手段にすぎません。
まぁ、あんまり深く考えずに、ネットで見つからないんだけど、こんな感じでできるんじゃねーのって公開してるだけじゃね?
コンピュータチェビチェフさんの目的は何ですか?おやすみなさい。
399+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 14:41:54
ん?何か誤解しているようですね?w
「超」とか付いてると見てるほうも何をやってるかさっぱりで、スレにコメントも少なく、
当の本人もなんだか分かってないまま目標もあまりない見たいなんで、少しダメ出ししてやらないとなぁ…って感じでしたけどw
私はいつもは横ベクトルを使いますけど、A dot transopose[B]
ニートさんは普段は縦ベクトルなんですか。なら何も成分表示にこだわらず、transopose[B] dot Aと表記すれば十分な感じですが…
確かマテマテカとかマキシマとか扱えたですよね?成分のときはPCやテキスト表記で面倒が無いようにしてるので具体的に計算するときは
例えば教科書にあるような通常の A x = y は x A = y となり x = y . inverse[A] です。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=-%7B%7Bu%2Cv%7D%5D+%2B+%7B%7Bx%2Cy%7D%7D+.+inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D
行列式化(det)など成分表示で意味があるときは当然必要ですが、そうでないなら体を自分で定義して四則で十分で成分はまったく気にかけなくていいかなって感じです。
行列で突き進むなら普通に環ですし、数学畑の人は多項式で突き進むのでしょうし、ベクトルの割り算を頑張って定義してる人も多いですが、それぞれにその公理と演算の目的があります。
成分表示したところで有限次元なわけで「超」とかいいつつも成分に依拠しているなら実際は一般化しているわけでなく2、3、4元と同じです。
しかも行列写像なのに #=> vec が中心ならそれって行列演算じゃなくてベクトル演算(一次変換とも言う)じゃないのかなーってな感じですがいかがですか?
また成分表示ならそのための中心となるベクトル(原点)があるわけですが、その中心は別の原点を基点として求めるなら堂堂巡りですよね?
私なんか環どころは「+」とスカラー倍しかないんでかなり辛いです…T_T
…しかしこのモデルはコンピュータの理論構造(但しカウンティングの場合)と同じだったりします。
400+2 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 15:20:40
一次変換はもう高校じゃやらないから別の言い方の方がよかったかな。
一次変換じゃなくて、行列の積(写像)に関心があるならその「超」で整合するんですが、そうすると行列の「積」の定義とその意味付けの議論です。
旺盛な探究心をお持ちならテンソル積なんかもここと同じでしょうか。
ベクトル空間で自分行列の体のため演算「積」について、自分数学で自分計量で必要となった「積」の定義と自分解釈意味付け
ってことです(通常は行列は環で定義して、「割り算」は現在では逆元A^-1でごまかしますが)。
このとき行列の成分に関心を寄せる必要はまったくありません。
えーなんでしたっけ?……角度ですか?
「角度」を未だにrad, atan, acosとかいってるようではたいした抽象かも出来てないようです。
このままではニートさんは現在自分数学を構築しているにもかかわらず日本数学(積分微分定義が多い)や高校数学(一応radだけど「角度」の定義すらなく曖昧)から脱皮できないと思います。
ただ、「角度」をちゃんと理解して使いこなせるようになるには5年以上必要ですからね…w
私が見たところあなたがやりたいのは、mathematics(数理)じゃなくてarithmetic(算術)だと思います。
401+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 15:26:23
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B%7Bx%2Cy%7D%7D+.+inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D
http://www.wolframalpha.com/input/?i=inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D+.+%7B%7Bx%2Cy%7D%7D
402+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 15:28:12
こっちだった
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B%7Bx%2Cy%7D%7D+.+inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D
http://www.wolframalpha.com/input/?i=inverse%5B%7B%7Ba%2Cb%7D%2C%7Bc%2Cd%7D%7D%5D+.+%7B%7Bx%7D%2C%7By%7D%7D
403 :neetubot [] :2010/03/21(日) 18:14:26
>>399-400 終始煽り口調なので、まだざっと読んだだけですが、3点気になりました。
>私が見たところあなたがやりたいのは、mathematics(数理)じゃなくてarithmetic(算術)だと思います。
簡単に言えば、私が「理論屋ではなく計算屋ですよね」、って話だと思いますが、一目瞭然まったくもってそのとおりです。
理論は面倒くさいので、ユークリッド空間内と前置きすることで、実数体上とか明示しないで複素数使っても知らんぷりです。
抽象か具体かといえば具体ですし、ただの立体解析幾何学を一般化した線型代数の練習問題ぐらいなもんですか。
>「角度」を未だにrad, atan, acosとかいってるようではたいした抽象かも出来てないようです。
例えば、ユークリッド空間内で2つの超平面が成す「角度」をあなたならどう定義しどう導出しますか?
天下った式を使う身分で恐れ多いことですが「面積は外積みたいな行列式に関係する計量です」と言うのは
いいとしても、こと「角度」をn次元に一般化するのは内積以外にもいろいろ考えられると思いますし、
特に角度ということで使う需要もないので、普通に考えたら内積に関する計量じゃねくらいな勢いです。
>横ベクトルがいい、成分表示をするな、ベクトル演算と呼べ、wolframalpha記法を使え
参考にします。主に「行列なら環だろ?」という話だと思いますが、アフィン変換といえど1次元拡大して平行移動も含め
演算は乗法一本でいくので n次一般線型変換群 のようにあえてアフィン変換群(モノイドかな?)と呼びました。
群論とか素人ですが、一部の分野の人には↓のような記法を使った方がわかりやすいかと思って、手を広げてます。
http://pantodon.shinshu-u.ac.jp/topology/literature/matrix_group.html
「スレにコメントも少なく」の部分は、式や根幹に関わる批評はあまりないので、ほのぼのやってます。
あとは、当然人間分からない部分も勉強してる部分もあるが ある程度分かってなきゃ定式化なんてできねぇぜってことと、
目標はとりあえず >>391 ということと、あなたの趣味趣向は垣間見えるが ダメ出しの部分があまり見えないということですか
404 :neetubot [] :2010/03/21(日) 18:21:43
>>401-402 は横ベクトルも縦ベクトル表記も転置すれば同じということを伝えようとしましたか?
transpose[inverse[{{a,b},{c,d}}] transpose[{{x,y}}]]={{x,y}} inverse[{{a,c},{b,d}}]
http://www.wolframalpha.com/input/?i=transpose[inverse[{{a%2Cb}%2C{c%2Cd}}]+transpose[{{x%2Cy}}]]%3D{{x%2Cy}}+inverse[{{a%2Cc}%2C{b%2Cd}}]
Trueとか出るんすね。マセマティカは昔使いましたが、便利ですね。
405+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/21(日) 20:36:36
ずいぶんとダメ出ししてもらえたようがが・・・
406+1 :neetubot [] :2010/03/22(月) 01:38:28
>>405 横ベクトルがいい、成分表示をするな、ベクトル演算と呼べ、wolframalpha記法を使え などは、
個人の趣味趣向の範疇であり、根幹に関わる批評ではないと見たので、ダメ出しと大言壮語するからには
どこがダメでどうしてほしいか、簡単な事やトリビアではなく、根幹について何か言ってほしいなと思っただけです。
「角度」が何だって??
>>396 の件で外心について http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html を改変しました。
ごにょごにょはまた明日にするとして、n次元単体に対して、普通の分積座標で表される内部点\P \aから
i対面に下ろした垂線の足が\P (\E - (\~C[\P^T \P] \e_i \e_i^T)/(\e_i^T \~C[\P^T \P] \e_i)) \a
と表せることがわかりました。良かった。。
407+1 :132人目の素数さん [] :2010/03/22(月) 01:51:09
ニ、ニ、ニートが発狂したぁぁぁ!!
408+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 01:56:52
>>406
このスレでいくらかコメントしてくれた人がいると思いますが、その方々と同じようにその人もあなたに対してコメントすることはもう無いと思いますよ。
409+2 :132人目の素数さん [] :2010/03/22(月) 02:21:11
「超」とか逝ってるけど、ここは高校受験用ベクトル問題集の写本スレだろ(笑)
410+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 02:29:09
だなw
411+1 :132人目の素数さん [] :2010/03/22(月) 02:57:31
ここはただのキチガイのスレだったのか・・・(しかもニート)
412+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 11:34:54
>>409
だなw
413+2 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 13:02:02
??
高卒ニート専用の隔離スレじゃなかったの?w
414+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 17:54:28
さっき「タミフル~」とか叫びながら窓から飛び降り自殺したらしい
見えない敵と戦いすぎたらしくて「ボクにはタミフルを倒せませんでした生まれてきてごめんなさい」とかなんとか言って生き絶えたって話し
415+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/22(月) 19:19:27
ついに死んだのか
416+2 : ◆27Tn7FHaVY [↓] :2010/03/23(火) 00:09:16
ちょっと前に、「働いている」っていってたけど・・・?
417+4 :neetubot [] :2010/03/23(火) 01:18:00
>>407-415 コンピュータ君…こんな過疎スレでそんなになるほど感情的負荷を与えてしまってゴメンナサイ。
雑談スレを見まして、本当に「自分はいいけど、他人はだめ」みたいな考え方の人なのかつっついてみました。
未成年なら笑って許しますが、「大人になれよ三井!」とだけ、私も僭越ながらダメ出し しておきます。
>>416 こんにちはー http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1261794262/291
とかのことですね。明日いやもう今日かからまた雑務をこなしに逝ってきますぉ
ところで、>>396 の件で、http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/20.html のように
n次元単体の外心が\p_O = \P (\C[\P^T \P] \1 + \~C[\P^T \P] \~b_σ) / (\1^T \C[\P^T \P] \1)
の位置にあるのは出てるとして、ここから外接円の半径の自乗を r_O^2=(\p_O - \p_0)^T (\p_O - \p_0)
=(\p_O - \p_n)^T (\p_O - \p_n) = (\sum_{i=0…n} (\p_O - \p_i)^T (\p_O - \p_i)) / (n+1)
(ここで、n次元単体の重心\p_Gを用いれば、)= (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) + ごにょごにょ
で話せば長いんですが、計算すると http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/12.html の最小自乗平均(n-1)次元
超球面の半径(重均半径)r_Gを用いて、r_O^2= (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) + r_G^2 と解けました!
上式は、n次元単体の外心を中心とした半径r_Oの外接超球面と、それと同じn次元単体の
重心を中心とした半径r_Gの最小自乗平均(n-1)次元超球面(重均超球)との共通部分が、
そのn次元単体の重心を中心として半径r_Gの(n-2)次元超球面(n次元単体が存在する空間から
オイラー線(重心と外心を結ぶ直線)の方向を除いた部分空間(重心を通る)上に存在)となることを示しています。
ということで、スレも伸びたことですし、このn次元単体の重均超球と外接超球の共通部分の
(n-2)次元超球面の名前を来週まで公募しますーこのスレかメールneetubot◎gmail.comまでどうぞー
特に無いようでしたら、この分野の名無しの名 neetubot で仮に「重均外接共通重中(n-2)次元超球面」
とでも付けちゃいますよ、なげぇ。(っていうか、本当にあるのかなぁこれ)
418+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/23(火) 01:55:48
>>416-417
自演乙
419 :neetubot [] :2010/03/23(火) 02:00:04
n次元単体が正単体となるときに限り、重心と外心が一致((\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G)=0)し、
重均超球も外接超球も「重均外接共通重中超球面(仮)」(このとき(n-1)次元になる)
も一致する。ということを、書き忘れるところだった、よかった、おやすみー
420+1 :132人目の素数さん [↓] :2010/03/25(木) 23:31:30
>>413
(笑)
421 :neetubot [] :2010/03/28(日) 12:40:05
>>418>>420 特に(n-2)次元超球面の名前の案でもないようなので(笑)、
>>417 のは「重均外接共通重中超球面」と仮に呼ぶことにします。
さて、n次元単体の外接超球にその「重均外接共通重中超球面」で直交する
同じ空間内のn次元超球の中心\p_Xと半径r_Xを考える。これは相似比から、
中心\p_X=(\p_G r_O^2 - \p_O r_G^2)/( (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) ) (広義垂心ではないorz)
半径r_X=(r_O r_G)/√( (\p_O - \p_G)^T (\p_O - \p_G) ) と導出できる。
ただし、n次元単体が正単体となる lim_{\p_O → \p_G} の場合を考えると、
式の上では、中心 lim \p_X=\p_O=\p_G となるが、半径 lim r_X→∞ となってしまう。
きれいな式ですが、「重均外接共通重中超球面」と共にあまり使えなそうだなぁー
n次元単体の内接超球と逆垂超球、あるいは、k次元面接超球とk次元面均超球でも似たように
なるだろうか?とりあえず今日は、\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1)の軌跡を調べたい。
422+1 :neetubot [] :2010/03/28(日) 21:28:30
アフィン独立な位置行列\Pで表されるn次元単体の重心
\p_G = \P \1 / (\1^T \1)から任意の内部点\P \a / (\1^T \a)
を通る曲線上の点\p_σを、対角成分にσ_i(全てのi=0…nでσ_i>0)を持つ
(n+1)対角行列\Σと実数t≧0によって\p_σ=\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1)
のように表す。(仮にn次元単体の座標冪乗曲線と呼ぶ)
(t≦0は http://mathworld.wolfram.com/IsotomicConjugate.html
で座標を変えればt≧0と同じ)
n次元単体の座標冪乗曲線はt→∞で、座標a_iが一番大きい値となる
番号iの位置\p_i(重複がk個あればそれらが作るk次元部分単体面の重心)
へ収束する。今後、d(\p_σ)/dt や d^2 (\p_σ)/dt^2も求めたい。
…なんだろうこのデジャビュー
423 :neetubot [] :2010/03/28(日) 21:51:54
(n次元単体の座標冪乗曲線は、アフィン変換かける前の
n次元正単体の重心から出る方向の単位ベクトル\e_θ
によって、全て分類され記述できると考えた…)
424 :neetubot [] :2010/04/02(金) 22:33:59
それでは、これからneetubotゼミを始めます。礼。
それでは、おもむろにベクトル
\p_σ=\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1) = \sum_{i=0…n} ( (\p_i σ_i^t) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t) )
をtで微分します。すごいことになりま…
425 :neetubot [] :2010/04/02(金) 23:31:28
d(\p_σ)/dt = \sum_{i=0…n} \p_i {σ_i^t log(σ_i) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)
- σ_i^t (\sum_{j=0…n} σ_j^t log(σ_j) ) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)^2 }
= \sum_{i=0…n} ( {(\p_i σ_i^t) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)}
{log(σ_i) - (\sum_{j=0…n} σ_j^t log(σ_j) ) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)} )
426 :neetubot [] :2010/04/03(土) 09:32:16
d(\p_σ)/dt = \sum_{i=0…n} ( {(\p_i σ_i^t) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)}
{(\sum_{j=0…n} σ_j^t log(σ_i / σ_j)) / (\sum_{j=0…n} σ_j^t)} )
となることから、d(\p_σ)/dt |_{t→+0} = \sum_{i=0…n} ( {\p_i / (n+1)^2}
{ log(σ_i^(n+1) / (\prod_{j=0…n} σ_j)) } = \sum_{i=0…n} (\p_i {
log(σ_i)/( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) - 1/(n+1)} {( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) / (n+1)}
= {( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) / (n+1)} \sum_{i=0…n} {(\p_i log(σ_i)/( \sum_{j=0…n} log(σ_j) ) - \p_G}
と変形できる。これは、>>422 のn次元単体の重心\p_Gから内部点 \P \a
(ただし、a_i > 0)を通る座標累乗曲線(\p_σ=\P \Σ^t \1 / (\1^T \Σ^t \1)上の点の軌跡)が、
t→+0の重心近傍において\sum_{i=0…n} (\p_i log(a_i)/( \sum_{j=0…n} log(a_j) ))を
見込む方向に出発することを表している。
427 :neetubot [] :2010/04/03(土) 09:44:33
逆に、m次元ユークリッド空間内で各列成分がアフィン独立となるm×(n+1)行列
\P=[\p_0,…,\p_n]が表すn次元単体で、t→+0の重心近傍において
\sum_{i=0…n} (\p_i ω_i)/( \sum_{j=0…n} ω_j ))を見込む方向に出発する
座標累乗曲線上の点は \p_ω = \sum_{i=0…n} \p_i e^(ω_i t) / ( \sum_{j=0…n} e^(ω_j t) )
を通ると言える。(のか?これ行列で表したいなぁ)次、これを2階微分しま…
428+1 :neetubot [] :2010/04/03(土) 15:35:21
ここで、a_{iω} = a_{iω}[t] = e^(ω_i t) / ( \sum_{j=0…n} e^(ω_j t) ) とおく。
前述より、d(\p_ω)/dt = \sum_{i=0…n} \p_i d(a_{iω})/dt = \sum_{i=0…n} \p_i ({ω_i e^(ω_i t)
/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))} - {e^(ω_i t) (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))^2} )
= \sum_{i=0…n} ( \p_i a_{iω} {ω_i - (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))} )
また、(d/dt)(d(\p_ω)/dt) = \sum_{i=0…n} \p_i ( {d(a_{iω})/dt (ω_i - (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t))
/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) )} - {a_{iω} (d/dt)((\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)))}
これはめんどくせぇ式だな、途中だけど図書館行ってくるわー(あと、今日は重心拡大・重心縮小を定義しよう…)
429 :neetubot [] :2010/04/03(土) 20:46:35
>>428 >/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) )} - {a_{iω} (d/dt)((\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)))}
/ (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) )} + {a_{iω} (d/dt)((\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)))}
と間違いを直せば、(d/dt)(d(\p_ω)/dt) = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} (
{ω_i - (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))}^2
+ {(\sum_{j=0…n} ω_j^2 e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))}
- {(\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))}^2 )
= \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} (ω_i^2 - 2 ω_i (\sum_{j=0…n} ω_j e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))
+ {(\sum_{j=0…n} ω_j^2 e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))})
ちょっと手間取ったが、あとは通分して(d/dt)(d(\p_σ)/dt) |_{t→+0} = 0?を示すのみか…
430 :neetubot [] :2010/04/03(土) 21:20:37
ということで、(d/dt)(d(\p_ω)/dt) = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} {
\sum_{j=0…n} (ω_i - ω_j)^2 e^(ω_j t) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) }
と解けます。いやーすごいよねーこれ。ということは、
d(\p_ω)/dt = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} {
\sum_{j=0…n} (ω_i - ω_j) e^(ω_j t) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t)) }
と書いたほうが美しいな。で、ここから曲率半径ってどうやるんだっけ?
431 :neetubot [] :2010/04/04(日) 00:43:42
二次超曲面の曲率半径はスカラーをベクトルで微分してたので、全く違う感じにいきます。
まず、( d(\p_ω)/dt )^T ( (d/dt)(d(\p_ω)/dt) - s d(\p_ω)/dt) = 0 を考えることにより、
ベクトル (d/dt)(d(\p_ω)/dt) の ベクトル d(\p_ω)/dt に直交するベクトル成分は
( \E - (( d(\p_ω)/dt ) ( d(\p_ω)/dt )^T)/(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) ) (d/dt)(d(\p_ω)/dt)
と求まる。
ある点における力学での曲率半径 \r が、その点での速度\vと 速度に直交する成分の
加速度\aに対して、\r = ((\v^T \v) / (\a^T \a)) \a と書ける気がする(←自信ない)
ので、座標累乗曲線上のtでの点における曲率半径は
( \E - (( d(\p_ω)/dt ) ( d(\p_ω)/dt )^T)/(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) ) (d/dt)(d(\p_ω)/dt)
(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) / { ((d/dt)(d(\p_ω)/dt))^T ( \E - (( d(\p_ω)/dt ) ( d(\p_ω)/dt )^T)
/(( d(\p_ω)/dt )^T ( d(\p_ω)/dt )) ) (d/dt)(d(\p_ω)/dt) } となる?これはどうでもいいな…
つまり、これは n次元単体内部の曲線分を表す 普通の指数関数の最も簡易な拡張であり、その上の点を
\p_ω = \sum_{i=0…n} \p_i e^(ω_i t) / ( \sum_{j=0…n} e^(ω_j t) ) = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω}
とおけば、t→+0の重心近傍において \sum_{i=0…n} (\p_i ω_i)/( \sum_{j=0…n} ω_j )) を見込む方向に出発し、
(d/dt)^n [\p_ω] = \sum_{i=0…n} \p_i a_{iω} (\sum_{j=0…n} (ω_i - ω_j)^n e^(ω_j t)) / (\sum_{j=0…n} e^(ω_j t))
が成り立つ?というところが、このネタの一番の綺麗どころっすかねーこの名前は今日から「指数座標曲線」にしる!
432 :neetubot [] :2010/04/04(日) 10:55:45
指数座標曲線は重心(任意の内部点でもいける)を中心にn次元単体の内部
(境界を含まない)をくまなく走査できる曲線分であり、n次元単体の全ての内部点を
指数座標曲線のt→+0の初速方向で重心まわりの超球面にくまなくマッピングできる。
重心まわりということで、正単体の基底の拡縮変換に対してのn次元立体角を
考えたりするのに役立つと期待する。そこで下記の重心拡大・重心縮小を定義する。
m次元ユークリッド空間内で各列成分がアフィン独立となるm×(n+1)行列
\P=[\p_0,…,\p_n]が表すn次元単体で、n次元単体のi頂点以外の点を使って
i頂点\p_iが重心となるように拡大する新しいi頂点の位置を「重心拡大i頂点」
\p'_i=(n+2)\p_i-(\sum_{j=0…n} \p_j)と呼ぶ。
また、n次元単体のi頂点以外の点を使って、そのn次元単体の重心を
新しくi頂点と見立てた位置を「重心縮小i頂点」\p''_i=\p_Gと呼ぶ。
さらに、i頂点以外の点と重心縮小i頂点で作られる単体を重心縮小i頂点単体
とかi=0…nの重心縮小i頂点単体の重心で作られる単体を重心縮小重心単体
とか呼ぶ。しかし、あまり使わないような気もする。
ところで、n次元単体の内接超球に対して、>>417 のようになる超球はなぜか
逆垂超球と勘違いしてましたが、普通に考えて正しくは内足重均超球ですぉ。
ちょっと気になると言えば、普通に考えた超平面同士の成す角度など、
まぁこれらは、また来週くらいまで。以上、9レス分の今週のneetubotゼミ終了ー
433 :neetubot [] :2010/04/04(日) 11:10:08
そういえば先週、>>417 の2次元バージョンの証明をしてくださった方がいて、とてもありがとうございます。
分からない問題はここに書いてね330
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1269099055/147
147 :132人目の素数さん [sage] :2010/03/28(日) 16:06:55
>>145
ベクトルで計算したら一致することになった。
以下の問題に置き換えられる。
重心G, 外心Pとして、 GP, √(a^2+b^2+c^2)/3 , 外接円の半径を3辺の長さとする三角形は、外接円の半径を斜辺の長さとする直角三角形となるか。
三角形の頂点をO,A,Bとし、
OA=a, OA↑=a↑, OB=b, OB↑=b↑, OP=p, OP↑=p↑, OG↑=g↑ とする。
PとCAの中点を結ぶと、CAと垂直になるので、
a↑・(p↑-(1/2)a↑) = 0
同様にb↑・ (p↑-(1/2)b↑) = 0
変形すれば、a↑・p↑ = (1/2)a^2, b↑・p↑ = (1/2)b^2
g↑=(1/3)(a↑+b↑)なので、
GP^2 = |p↑ - (1/3)(a↑+b↑)|^2 = |p↑|^2 - (2/3)p↑・(a↑+b↑) + |(1/3)(a↑+b↑)|^2
= p^2 - (2/3)(a↑・p↑+b↑・p↑) + (1/9)(a^2 + 2a↑・b↑ + b^2)
= p^2 - (2/3)((1/2)a^2+(1/2)a^2) + (1/9)(a^2 + 2a↑・b↑ + b^2)
= p^2 - (2/9)(a^2 - a↑・b↑ + b^2)
(√(a^2+b^2+c^2)/3)^2 = (a^2+b^2+c^2)/9
= (a^2+b^2+|a↑-b↑|^2)/9 = (a^2+b^2+a^2-2a↑・b↑+b^2)/9
= (2/9)(a^2-a↑・b↑+b^2)
以上より、GP^2 + (√(a^2+b^2+c^2)/3)^2 = p^2 (証明終わり)
ということで、このスレ見ていらっしゃったら、>>417 にあなたの命名する名前を付けたいので、メールとか連絡頂けるとありがたいです。
434+1 :neetubot [] :2010/04/10(土) 07:02:46
今週のneetubotゼミは、同じ次元の任意の実数成分の列ベクトル\a,\bに対し、
- (\a \b^T - \b \a^T)^3 / ((\a^T \a \b^T \b) - (\a^T \b)^2)
= - (\a \b^T \a \b^T - \a \b^T \b \a^T - \b \a^T \a \b^T + \b \a^T \b \a^T)
(\a \b^T - \b \a^T) / ((\a^T \a \b^T \b) - (\a^T \b)^2)
= (\a \b^T - \b \a^T) となることがミソです。これリー群の式と似てるけど関係あるのかなぁ?
435 :neetubot [] :2010/04/10(土) 07:13:41
別に実数成分と仮定しないでよかた。。
では、次元は適当にmとでもしたユークリッド空間内で,
二点間の距離d_{0 0}から二平面間の距離d_{2 2}と角度θ_{2 2}まで求めますー
436 :neetubot [] :2010/04/10(土) 12:36:22
例えば、このスレでは普通に考えて、m次元ユークリッド空間内(m≧n≧0≦n'≦m)で、
n次元単体Aが存在するn次元部分空間U上の点と
n'次元単体A'が存在するn'次元部分空間U'上の点
との距離の最小値を「UとU'の距離」と呼ぶ。
また、UとU'の距離が0になるように平行移動したとき、
UとU'の共通部分空間∩に対し、U-∩内のベクトルと
U'-∩内のベクトルの成す角の最小値を「UとU'の角度」
と呼ぶのが、順当だと思いますコンピュータ君。
437 :neetubot [] :2010/04/10(土) 16:07:54
最終的に興味があるのは、二つの単体間の計量ではあるが、
正単体を拡縮変形後に回転変形させ平行移動したもので任意のn次元単体が表せると考えれば、
任意のn次元単体は(元の正単体の回転の自由度はあるが)その重心とn次元基底で表せるため、
下記の方向表記でまず解いておけば、有用であると考える
438+1 :neetubot [] :2010/04/10(土) 16:56:23
まず、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\p=[p_1,…,p_m]^T
で表される点から、位置ベクトル\p'=[p'_1,…,p'_m]^T で表される点への、
距離ベクトルが \d[\p→\p'] = \p' - \p となることから、
この二点間の距離d_{0 0}は、普通に考えて、
d_{0 0} = √(\d[\p→\p']^T \d[\p→\p']) = √(\d[\p'→\p]^T \d[\p'→\p])
= √((\p' - \p)^T (\p' - \p)) = √( \sum_{i=1…n} (p'_i - p_i)^2 ) と表せる。
(普通のユークリッドノルム)
439+2 :neetubot [] :2010/04/10(土) 19:57:38
訂正: >>438 √( \sum_{i=1…n} (p'_i - p_i)^2 ) じゃなくて √( \sum_{i=1…m} (p'_i - p_i)^2 ) だった。心の目で大目に見て!
次に、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\p=[p_1,…,p_m]^T
で表される点を通り 方向ベクトル\l=[l_1,…,l_m]^Tの方向の直線Uから、
位置ベクトル\p'=[p'_1,…,p'_m]^T で表される点U'への、距離ベクトルを
\d[\p_d→\p'] (ただし、\p_dは点U'から直線Uに下ろした足の位置ベクトル)とする。
すると、\p_d = \p + (\l \l^T)/(\l^T \l) (\p'-\p) より、m×m単位行列\Eに対して、
\d[\p_d→\p'] = \p' - \p_d = (\E - (\l \l^T)/(\l^T \l)) (\p'-\p) と書ける。
つまり、上記のように表した場合の直線Uと点U'の距離d_{1 0}は、普通に考えて、
d_{1 0} = √(\d[\p_d→\p']^T \d[\p_d→\p']) = √((\p' - \p)^T (\E - (\l \l^T)/(\l^T \l)) (\p' - \p)) となる。
ここまでなら線型代数の教科書のグラムシュミット直交化あたりとかに普通に載ってる話です。
例えば、d_{1 0}を2次元ユークリッド空間(xy平面)内の
直線 a x + b y + c = 0 (条件略)と点(x'_0, y'_0)の距離
に当て嵌めれば、直線 a x + b y + c = 0 が点(x_0, y_0)
を通り傾き(-b, a)であるとしたとき c = - a x_0 - b y_0 であるので、
d_{1 0} = √( (x'_0-x_0, y'_0-y_0) ( \E - ((-b, a)^T (-b, a))/((-b, a) (-b, a)^T) ) (x'_0-x_0, y'_0-y_0)^T )
= √( (a^2 (x'_0-x_0)^2 + 2 a b (x'_0-x_0) (y'_0-y_0) + b^2 (y'_0-y_0)^2) / (a^2 + b^2) )
= | a (x'_0-x_0) + b (y'_0-y_0) | / √(a^2 + b^2)
= | a x'_0 + b y'_0 + c | / √(a^2 + b^2)
となり、昔習った拡張性はないが美しい式にちゃんと一致する。
440+2 :neetubot [] :2010/04/10(土) 20:49:52
また、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\p=[p_1,…,p_m]^T
で表される点を通り 方向ベクトル\l=[l_1,…,l_m]^Tの方向の直線Uと、
位置ベクトル\p'=[p'_1,…,p'_m]^T を通り 方向ベクトル\l'=[l'_1,…,l'_m]^T
の方向の直線U'との、距離ベクトルを\d[\p_d→\p'_d] と書く。
このとき、\p_d = \p + \l a および \p'_d = \p' + \l' a' とすれば、
二点\p_d, \p'_d間の距離d_{1 1}の大きさが係数 a, a' の値において
最小となるとき、直線Uと直線U'との距離となる。
つまり、最小自乗法より ∂(d_{1 1}^2)/∂a=∂(d_{1 1}^2)/∂a'=0 となることを用れば、
d_{1 1}^2 = ((\p'-\p) + \l' a' - \l a)^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a)であることから、
\l^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = \l'^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = 0 を満たすと言える。
(これは、距離ベクトル\d[\p_d→\p'_d]に対し 直線Uあよび直線U'が直交することを表している)
この a, a' を解けばよいのだが、めんどくさいので、ちょっちタンマ(笑)
441+4 :neetubot [] :2010/04/11(日) 00:26:09
>>440 の\l^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = \l'^T ((\p'-\p) + \l' a' - \l a) = 0より、
(a, a')^T = ({{\l^T \l, -\l^T \l'}, {-\l'^T \l, \l'^T \l'}})^{-1} {{\l^T (\p'-\p)}, {-\l'^T (\p'-\p)}}なので、
a=\l'^T (\l' \l^T - \l \l'^T) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) および
a'=\l^T (\l' \l^T - \l \l'^T) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)と解ける。
したがって、\d[\p_d→\p'_d] = \p'_d - \p_d = (\p' - \p) +
(\l' \l^T - \l \l'^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
= ( \E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) ) (\p' - \p)
が成り立つ。(ただし、\l^T \l \l'^T \l' = (\l^T \l')^2、つまり、直線Uと直線U'が平行でない場合に限る)
ここで、\l' \l^T - \l \l'^Tは歪対称行列だが、
\E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / ( (\l^T \l) (\l'^T \l') - (\l^T \l')^2 ) = \M は対称行列となり、
\M^2 = \E + 2 (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) + (\l' \l^T - \l \l'^T)^4 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)^2
= \E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) = \M であるため冪等行列ともなる。
これは、(\p' - \p)がちょうどすでに直線Uあよび直線U'に直交している
(\p' - \p) = \M (\p' - \p) 場合にも(そしてたとえ何度 \M を掛けて変換したとしても)
\d[\p_d→\p'_d] = \M (\p' - \p) = \M^n (\p' - \p) となるのは、当然だということを表している。
以上を用いれば、この直線Uと直線U'との距離は d_{1 1} = √( (\p' - \p)^T \M (\p' - \p) )
√( (\p' - \p)^T (\E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)) (\p' - \p) )
と書けることがわかる。明日までに、ねじれの位置だけでなく平行な場合や交わったり一致する場合
の条件を確認しておきます。あとは、d_{n 0}、d_{2 1}、d_{2 2}を求めたいなぁー
442+1 :neetubot [] :2010/04/11(日) 00:52:28
>>434 でミソって言ったのは、>>441 で使った
(\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
が冪等行列になるということに帰着されますた。
こっちの方は、二回外積掛けてるような感じなのですが、
2直線の方向に向かって正射影するようなもんなので、
名前付けるとしたら双正射影行列とかかなぁー。
>>441 の \M = \E - (\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) の方は、
2直線に直交する方向に等長(?)変換するため、
名前付けるとしたら双直交射行列とかかなぁー。
まぁそれらは、2つの部分空間の距離とかまで拡張したところで考えればいいことか…
443 :neetubot「二直線間の距離の細かい所」 [] :2010/04/11(日) 16:28:05
訂正:>>440>>441 直線Uあよび直線U' →(爆笑)→ および。二回もかよ!?
双正射影行列 \W'=(\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
とすれば、ざっくり lim_{\l'→\l} \W' = lim_{\l'→\l} 2 \l (\l^T \l - \l^T \l) \l^T / ((\l^T \l - \l^T \l) (\l^T \l + \l^T \l))
= \l \l^T / \l^T \l (これは、直線Uと直線U'が平行な場合、その平行な方向への正射影行列となる
ということを表す。)と計算できるため、同様に双直交射行列 \Y' = \E - \W' もlim_{\l'→\l} \Y'
= \E - (\l \l^T)/(\l^T \l) となる。
以上より、二直線間の距離は、二直線が平行な((\l^T \) (\l'^T \l') = (\l^T \l')^2)場合には、
\l'を考えずに、>>439 のような直線Uと点\p'の距離に帰着されることが言える。
また、二直線が交わる必要十分条件は、二直線間の距離ベクトルが
\d[\p_d→\p'_d] = \Y' (\p' - \p) = \0 となることであり、これは、
(\p' - \p) = \W' \t を満たすm次元列ベクトル解 \t が存在するという
問題に置き換えて、最終的に、「rank[\W', (\p' - \p)] = rank[\W']」 を
満たすことがm次元ユークリッド空間内で二直線が交わる必要十分条件と言える。
この二直線が交わる条件式「rank[\W', (\p' - \p)] = rank[\W']」は、
基本的な演算のみを用いて導出されたものであり、ねじれの位置だけでなく
平行な場合や交わったり一致する場合など、あらゆる条件下で使える式である。
444 :neetubot「二直線間の計量」 [] :2010/04/11(日) 19:53:31
二直線間の距離の中点への位置ベクトル\p_Dも
綺麗に書けると思うので、やってみっかー
普通に考えて(←前置きがめんどくさくなってきた)、
\p_D = \p_d + \d[\p_d→\p'_d] / 2 = \p + \l \l'^T (\l' \l^T - \l \l'^T)
(\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2) + \Y' (\p' - \p) / 2
= (\p' + \p) / 2 + (\l \l'^T + (\l' \l^T - \l \l'^T)/2) (\l' \l^T - \l \l'^T)
(\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
= (\p + \p')/2 + (\l a + \l' a')/2
= {(\p + \p') + ((\l' \l^T)^2 - (\l \l'^T)^2) (\p' - \p) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)}/2
まぁ、この結果は、普通に考えて、二直線の通る点の中点から、二直線
の通る点から距離の足へのベクトルを足して2で割った方向にあるのは自明ですよと。
この点 \p_D は、二直線上のそれぞれの点からの距離の自乗の和が最小となる点
(m次元ユークリッド空間内で一意にこの点)そのものであると、ちょっとがんばれば簡単に示せます。
なお、ねじれの位置にあっても二直線の成す角度θ_{1 1}は、距離ベクトルが
0ベクトルになるように平行移動して考えれば、ただの二直線の方向
ベクトル\l, \l'の成す角度として θ_{1 1} = arccos(\l^T \l' / √(\l^T \l \l'^T \l')) で求められる。
ということで、m次元ユークリッド空間内で、任意の二直線を表すためには、
距離の中点\p_Dおよび二直線の方向\l, \l'とそれに直交する距離ベクトルの半分\d/2
というパラメータで表せば(これでは右回り左回りの配置かとかがわからんが)一番いい感じがするよと。
445+2 :neetubot「二直線間の疑問」 [] :2010/04/11(日) 20:31:34
傾き\lの直線U上の点と 傾き\l'の直線U'上の点とを 結ぶ線分の中点の軌跡
の方向ベクトルは、上でちょっと出てるけど、
{((\l' \l^T)^2 - (\l \l'^T)^2) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)} \t と言えるだろうか?
なぜ、\l と \l' の角の二等分線の方向と一致しないのだろうか?
なぜ、双正射影行列 \W'=(\l \l'^T - \l' \l^T) (\l' \l^T - \l \l'^T) / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)
が示す方向と違うのだろうか?
という三点ぐらいが疑問として残りました。\l と \l' とそれらに直交する距離ベクトルの
実質3次元分しか出てこないけど、存外難しいではないか、あはははあばばー
446 :neetubot「n次元部分空間と点との距離」 [] :2010/04/11(日) 21:10:25
訂正:>>441 下から3行目 = √( (\p' - \p)^T (\E + (\l' \l^T - \l \l'^T)^2 / (\l^T \l \l'^T \l' - (\l^T \l')^2)) (\p' - \p) )
ところで、m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\pで表される点を通り
n本の基底 \L=[\l_1,…,\l_n] で作られるn次元超平面Uから
位置ベクトル\p'で表される点U'への 距離ベクトルを\d[\p_d→\p'] と書く。
(ただし、\p_dは\p'からn次元超平面Uに下ろした垂線の足とする。)
仮定より、n次元超平面Uに対する直交射行列 \Y = (\E - \L (\L^T \L)^{-1} \L^T)
を用いて、\d[\p_d→\p'] = \Y (\p' - \p) = (\E - \L (\L^T \L)^{-1} \L^T) (\p' - \p)
と書ける。また、このn次元超平面Uと点U'との 距離 d_{n 0} は
d_{n 0} = √( (\p' - \p)^T \Y (\p' - \p) )
= √( (\p' - \p)^T (\E - \L (\L^T \L)^{-1} \L^T) (\p' - \p) )
と書ける。これも、線型代数の本の射影行列という項に載ってたりすることもあると思う。
d_{n 0}は >>439 の 直線Uと点U'の距離d_{1 0}の 純粋なn次元拡張であります。
447 :neetubot [] :2010/04/11(日) 21:40:23
>>445 傾き\lの直線U上の点と 傾き\l'の直線U'上の点とを 結ぶ線分の中点の軌跡
じゃいろんな点になるなぁー直線になんないしー①と②・②と③が違うのはわかった。
しかし、①と③は中点連結定理で同じじゃないんかのぅー
d_{2 1}、d_{2 2}は共通部分があって、まんどくせーので、また来週。
448+1 :neetubot [] :2010/04/12(月) 00:35:02
よく考えたら、>>445 の①は(\p_d+\p'_d)/2に関係する
実際の中点間の方向で、③は(\p'_d-\p_d)に関係する
平行移動して差し引きした分の量だから全然違った。
>>445 はどれも違う重要な量なんだなぁー(
この場合、距離ベクトルの方向に三角柱と考えるのがいいが、
d_{n n'}の場合、k次元共通正規直交基底\S''と 空間Uから共通基底を
除外した正規直交基底\Sと 空間U'から共通基底を除外した正規直交基底\S'
として、空間Uの通る点\p と 空間Uの通る点\p' から \S と \S' に 直交する
距離\dを出し、\S''の方向を除外したものを距離としていいと思う。
449+1 :132人目の素数さん [] :2010/04/12(月) 09:07:13
「5心」を英訳すると「Four Centers of a Triangle(4心)」だね。
内心と傍心は同じ種類の中心だから、まとめて「1個」と数える。
もっとも、「Kimberling Centers(3587心)」のほうが、今では市民権を得ているが。
次の2つのWEBは基礎知識として必ず見てね。
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html
http://www.xtec.es/~qcastell/ttw/ttweng/portada.html
X(n)の三角形座標(trilinears)、重心座標(barycentrics)による中心の表示を見れば、
幾つかはすぐ高次元化できるね。
450 :neetubot [] :2010/04/13(火) 01:43:56
今日もお疲れコンピューター!>>449 有用な情報ありがとうございます!!
ホントに"Four Centers of a Triangle"でググるとFiveより圧倒的ですね。
>内心と傍心は同じ種類の中心だから、まとめて「1個」と数える。
私も、>>327 ではまとめて「第3心」で数えました。n次元単体では、
傍心のように各(n-1)次元表面から全て等距離にある点は、内心を含めて
2^n個定義できる(このスレでは >>282 あたりから広義傍心と呼んでいる)と考えてます。
ETCについては >>308 や http://www7.atwiki.jp/neetubot/pages/11.html
で触れてますが、個人的に参考知識として上げたいのは http://mathworld.wolfram.com/
の方がよくまとまってますし好きですね。ETCの市民権についてはmathworldで頻出なので同感です。
>X(n)の三角形座標(trilinears)、重心座標(barycentrics)による中心の表示を見れば、
>幾つかはすぐ高次元化できるね。
幾何学的性質や意味まで含めて式で高次元拡張しようとし、
座標は定式化の手段というか、副次的なものとしてしか捉えていなかったので、
座標だけで拡張しようとする考えは斬新ですね。
というのも、まぁ下記はたとえ話ですが、
三角形(2次元単体)の心から n次元単体の心に拡張するという事は、
ある数列の初項から 第二項・第三項…と性質を見た上で
第n項の一般的な式を導出することのようだ、と私は思っていて、
それが 等差数列や 等比数列のような簡単な性質ではなく
幾何学的性質を保つような列となるということが結構難しいよと、
例えば私は思うわけですが。まぁ、個人的印象にすぎませんがw
451 :neetubot [] :2010/04/18(日) 17:42:05
今週のneetubotゼミはお休みにしますー
452 :neetubot [] :2010/05/02(日) 21:03:10
そしてここから、伝説が始まる(笑)
453 :neetubot [] :2010/05/03(月) 12:43:05
まず、単位行列 \E などの基本をおさらいする。以下はm次元ユークリッド空間内とする。
ここで、正規直交行列\S, \Aと対角行列\Σによって、特異値分解 \L = \S \Σ \A^T
となるとき、擬似逆行列 \L^† = \A \Σ^{-1} \S^T と書ける。
このとき、ベクトル\pを、列ベクトルを並べた行列\Lが作る部分空間内の
ベクトル\L \aと、その部分空間に直交するベクトル\p - \L \aに分けるとすれば、
\L^T (\p - \L \a) = \A \Σ \S^T (\p - \S \Σ \A^T \a) = \0 より、
\Σ^{-1} \S^T \p = \A^T \a であることから \p = (\L \a) + (\p - \L \a)
= \S \S^T \p + (\E - \S \S^T) \p = \L \L^† \p + (\E - \L \L^†) \p と書ける。
このことより、\Lに対する正射影行列を \W[\L] = \L \L^† = \S \S^T と定義し、
\Lに対する直交射行列を \Y[\L] = \E - \L \L^† = \E - \S \S^T と定義する。
これをふまえれば、さきのベクトル\pの\Lに対する直交分解は
\p = \E \p = \W[\L] \p + \Y[\L] \p と書ける。
454 :neetubot [] :2010/05/03(月) 21:59:41
ということをふまえて、基底\Lで作られるn次元部分空間 U と
基底\L'で作られるn'次元部分空間 U' との 共通k次元部分空間
(以下 n ≧ n' ≧ k とする)の正規直交基底\S''などを求める。
まず、求めやすい U と U' の和空間(次元は n + n' - k )の
正規直交基底 \S_W については、\S_W \S_W^T = \W[\L, \L'] = [\L, \L'] [\L, \L']^†
(\Lと\L'をくっつけたm×(n+n')行列[\L, \L']に対する正射影行列)
によって求められる。ちなみに、U と U' の和空間の直交補空間
(UでもU'でもない (m - (n + n' - k))次元部分空間)の
正規直交基底 \S_Y については、\S_Y \S_Y^T = \Y[\L, \L'] = \E - \W[\L, \L']
によって求まる(それぞれ固有値1の正規直交な固有ベクトル列として)。
ただし、この2つはあまり使わないと思われる。どーん
455+1 :neetubot「2つの部分空間(超平面)の共通部分空間など」 [] :2010/05/03(月) 22:33:58
つーことで、本題の共通k次元部分空間の正規直交基底\S''の求め方だがや。
和空間なら出せることから、U の直交補空間の\Y[\L]と
U' の直交補空間の\Y[\L']との和空間全体の 直交補空間
\Y[\Y[\L], \Y[\L']] = \S'' \S''^T で求まるちゅーわけじゃんかー
いやーこれでも求まるっちゃーきたねぇんじゃけんどよー
また、Uから共通k次元部分空間を除いた空間(仮に左差空間とでも呼ぶ)
の正規直交基底 \S は \S \S^T = \Y[\Y[\L], \L'] = \Y[\Y[\L], \W[\L']] によって出せるし、
U'から共通k次元部分空間を除いた空間(仮に右差空間とでも呼ぶ)
の正規直交基底 \S' は \S' \S'^T = \Y[\L, \Y[\L']] = \Y[\W[\L], \Y[\L']] によって出せる。
つーか、これらは前にもやった気がするし…けど、今回も式の整形には至らんかった…
地道でめんどくせぇ計算だけど、とりあえず任意の2つの基底から各部の正規直交基底が
出せるよってことが、次の2つの基底(による2つの超平面)の角度を求めるのに重要です。
456+1 :neetubot「2つの部分空間(超平面)の距離」 [] :2010/05/04(火) 01:46:28
(上のめんどくせぇ計算とは、\S''を求めるために、まず
m×(2m)行列 [(\E-\L (\L^T \L)^{-1} \L^T), (\E-\L' (\L'^T \L')^{-1} \L'^T)]
の(m-k)本の左特異ベクトルからなる\S''の直交補空間の正規直交基底 \S''' とかを求めて、
次にm×m行列(\E-\S''' \S'''^T)のk本の左特異ベクトルからなる\S''が求まるという
計算のことです。さらに\L, \L'が基底でなければ 計4回ものSVD計算が必要となるので大変です。)
と角度の前に、2つの部分空間(超平面)の距離やります。超単純でした。
(ちなみに、基底\Lで張られる部分空間Uは、直交する(要証明?)
正規直交基底\Sと\S''でも張られるので、\W[\L] = \W[\S, \S''] = \S \S^T + \S'' \S''^T
となるというような計算は、以下では明記しないかもしれないけど、こっそりよく使ってます。)
さて、2つの超平面 U, U' 間の距離について >>448 などのように考えれば、
距離d_{n n'}とUとの交点を\p_d = \p + \L \a、距離d_{n n'}とU'との交点を\p'_d = \p' + \L' \a'
としたとき、超平面Uから超平面U'への距離ベクトルは
\d[\p_d→\p'_d] = (\p' + \L' \a') - (\p + \L \a) = \p' - \p - [\L, \L'] [\a; -\a']
と書けて、これは点\pを通り[\L, \L']で作られる超平面から点\p'への距離ベクトルと
全く同じように考えられるということを表している。
それはさておき、ここの過去ログや最小自乗法をふまえて、距離ベクトルは
[\L, \L']^T \d[\p_d→\p'_d] = [\L, \L']^T (\p' - \p) - [\L, \L']^T [\L, \L'] [\a; -\a'] = \0
を満たすことより、\d[\p_d→\p'_d] = \Y[\L, \L'] (\p' - \p) と書ける。
(ここで、前述の\S''で張られる共通部分空間があるために、距離ベクトルの足
\p_dおよび\p'_dは一意には定まらない。しかし、2つの部分空間(超平面)の距離の中点
への位置ベクトル\p_Dを後述する際に、\p, \p'の位置をふまえた\p_d, \p'_dのある意味最適な
とるべき位置を一意に定義しようと思う。)
よって、「m次元ユークリッド空間内で、位置ベクトル\pで表される点を通り
基底\Lで張られるn次元超平面Uから、位置ベクトル\p'で表される点を通り
基底\L'で張られるn'次元超平面U'への、距離の大きさは
d_{n n'}=√( (\p' - \p)^T \Y[\L, \L'] (\p' - \p) ) で表せる。(m≧n≧n'≧0)」
457 :neetubot [] :2010/05/04(火) 02:08:24
いらんことごちゃごちゃ書いとったら、文字数制限やでー
>>456 の最後の式で俺の一ヶ月全て一般化され表されてもーた。
つーか、双直交射行列の正体が\Y[\L, \L']=\Y[\S, \S'', \S']っていうのが
驚きやなー >>441-442の直線間距離はこれを展開して計算してあの
特殊な形というわけですわー まぁ
http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix#Blockwise_inversion
に習って >>456 も展開したらと思ったけど、まだ全然わかんねぇー
明日、角度、あよび、距離中点位置、を出して、なんぼ
458 :neetubot「2つの部分空間(超平面)が成す角度」 [] :2010/05/04(火) 12:31:30
ほな、超平面同士の角度やりますわー
3次元空間内で交わる二平面の成す角度と言われて、
「0です」て答える人いないと思われ、片方をどっちかに何度回転
さしたら二平面が一致するのんかーいう話に当然なるんやろー
だけん、上の方で言う所の、\Lと\L'の成す角度と言われても、
共通な\S''を除いた UとU'内の それぞれの単位方向
\S \u (\u^T \S^T \S \u = \u^T \u = 1)と \S' \v (\v^T \S'^T \S' \v = \v^T \v = 1)
の成す角度としてθ_{n n'} = arccos( (\u^T \S^T \S' \v) / √(\u^T \u \v^T \v) )
によってその成しうる角度全てが記述される。
この方向余弦をラグランジュの未定乗数法を用いて定式化すれば、
cos(θ_{n n'}) = \u^T \S^T \S' \v - σ_a (\u^T \u - 1) - σ_a' (\v^T \v - 1)
と書けて、それぞれの変数に対して極値をとるときの条件を求めると、
∂cos(θ_{n n'})/(∂\u) = \S^T \S' \v - 2 σ_a \u = \0、
∂cos(θ_{n n'})/(∂\v) = \S'^T \S \u - 2 σ_a' \v = \0、のようになることから、
\S^T \S' = [\u_1, …, \u_n'] \∑[σ_1, …, σ_k' (, 0, …, 0)] [\v_1, …, \v_n']^T = \U \∑ \V^T
(ただし、|σ_1|≧…≧|σ_k'|>0 とする) と特異値分解されるとすれば、二超平面が成す角度
cos(θ_{n n'}) = ±√((\u^T \S^T \S' \v) / (\u^T \u)) √((\u^T \S^T \S' \v) / (\v^T \v)) = ±2√(σ_a σ_a')
のとりうる値の範囲は、直交半径の大きさがそれぞれσ_1, …, σ_k'の超楕円面
(特異値がn'個ない(0 ≦ k' < n')の場合は内部も含めた超楕円体)上の点から
その超楕円の中心への距離の大きさの範囲として、全く同値として考えられる。
この超楕円を仮に方向余弦超楕円と呼ぶ。このように考えれば、「方向行列がそれぞれ
共通方向がない正規直交基底\S, \S'(任意の基底\L, \L'が与えられても >>455 の計算でこれを求める)
で張られる2つの部分空間が成す角度cos(θ_{n n'})の範囲は、\S^T \S'の特異値がフルランクで
求まる場合は 絶対値が最大の特異値σ_1と 絶対値が最小の特異値σ_n'に対して
-|σ_1|≦cos(θ_{n n'})≦-|σ_n'|, |σ_n'|≦cos(θ_{n n'})≦|σ_1|となり、
多くの\S^T \S'の特異値がフルランクで求まらない場合は -|σ_1|≦cos(θ_{n n'})≦|σ_1|となる。」
が言える。キター
459+1 :neetubot [] :2010/05/04(火) 13:29:57
基底\L, \L'の共通方向をそれぞれ除いた正規直交基底\S, \S'が直交する
(\S^T \S' = \O(零行列))となる この特別な最も単純な場合を考えれば、、
特異値は0しかないので常に cos(θ_{n n'})=0 、つまり直交ですよと。。
そういえば、共通方向\S''がある場合には特異値に1か-1入れて -1≦cos(θ_{n n'})≦1 とかでいいじゃん。
どっちにしろ、どんな「方向余弦半径超楕円」も 単位超球面の境界を含む内部に存在すると言えるぉ。
以上、>>400 のコンピュータ君のために、「角度」を普通に内積と acos のみで考えて、
m次元ユークリッド内のn次元超平面とn'次元超平面の成す角度の範囲を
解析幾何学的に導出したまでの話ですた。「角度」が何だって??(笑)
以上を >>391 の1に絡めて応用すれば、クラスタリングっぽい話から、
一般化されたユークリッド空間内での二単体間のある意味最短距離経路が
求められると思っております。ASAP ではまた
460 :neetubot [] :2010/05/04(火) 18:46:51
Bibliography
河田敬義, "アフィン幾何・射影幾何", 岩波書店, 岩波講座 基礎数学, 1976/5/27
H. S. M. Coxeter, 銀林浩(訳), "幾何学入門 上", ちくま学芸文庫, ISBN978-4-480-09241-0, 2009/9/10
H. S. M. Coxeter, "Introduction to Geometry Second Edition", Wiley Classics Library Series, 1989
Melvin Hausner, "A Vector Space Approach to Geometry", Dover Pubns, 1998/06
http://books.google.com/books?id=L4ZnoQ6mCAwC&printsec=frontcover
Jon Dattorro, "Convex Optimization & Euclidean Distance Geometry", Lulu.Com, 2006/7/30,
http://books.google.com/books?id=byqvt2ArOLQC&printsec=frontcover
MIROSLAV FIEDLER, "MATRICES AND GRAPHS IN EUCLIDEAN GEOMETRY",
Electronic Journal of Linear Algebra ISSN 1081-3810, Volume 14, pp. 51-58, 2005/09,
http://hermite.cii.fc.ul.pt/iic/ela/ela-articles/articles/vol14_pp51-58.pdf
Allan L. Edmonds, Mowaffaq Hajja, Horst Martini, "Coincidences of simplex centers and related facial structures", arXiv:math.MG, 2004/11/04,
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0411/0411093v1.pdf
Allan L. Edmonds, Mowaffaq Hajja, Horst Martini, "Orthocentric simplices and their centers", arXiv:math.MG, 2005/08/03,
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0508/0508080v1.pdf
Allan L. Edmonds, "The Geometry of an Equifacetal Simplex", arXiv:math.MG, 2006/10/06,
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0408/0408132v2.pdf
461 :neetubot [] :2010/05/09(日) 20:34:42
>>459 方向ベクトル同士の余弦については、
正負どっちでもいいっちゃいいので 0≦|cos(θ_{n n'})|≦1 と書くぉ。
二面角 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9D%A2%E8%A7%92
を見れば、対象とする部分空間内の各超平面の法線ベクトルが成す角度
(の範囲)という定義が本筋っぽいので、共通部分は除外で後は同じようにやるぉ。
>>391 の1は一般化されたユークリッド空間内で、二複体のそれぞれの点列を含む
最小の部分空間(やはり私はこれをアフィン空間とは呼べない)同士 が成す角度の
範囲(方向余弦半径超楕円による)が応用のメインで、複体の点列の重心から
Singular Value Decompositionによって求まるCentroid SVD Hyperellipse
の特殊な場合である Simplex Steiner Hyperellipse が基礎のメインとします。
ということで、タイトルは
"Dual Subspace Distance apllied Centroid SVD Hyperellipse
of Simplicial Complex in Homogeneous Euclidean Geometry"
ぐらいしにて、基礎の基礎で単体・複体・特異値分解・疑似逆行列・正射影行列
・直交分解・アフィン変換あたりを、全体の空間をあらかじめ1次元過剰な斉次系で
考える Homogeneous Euclidean Space によって、このスレの基礎とするものを
全て記述できる気がしてます。間に合うかなぁー
462 :neetubot [] :2010/05/09(日) 23:07:47
このスレで辺乗行列\Bと呼んでいたものは Euclidean Distance Matrix (主にDらしい)
の全ての成分に1/2掛けたものっぽいです。まだ諸説ありよくわかりませんが、、
っていうか今回関係なく使いませんが…
John Clifford Gower, "Euclidean distance geometry"
http://scholar.google.co.jp/scholar?q=euclidean+distance+matrix+gower
とりあえず、↑のGower神関係の文献をあたれば良さそうです。ク、クリフォード??
Jon Dattorro, "Euclidean Distance Matrix"
https://ccrma.stanford.edu/~dattorro/EDM.pdf
↑の弟子っぽいDattorroさんも良さそうです。ともすれば工学の中の応用数学の分野
とも言えそうですが、このニッチな分野の近況がだんだん見えてきましたよ。
あと、任意の連立方程式の(最小自乗)解法については、
宮岡 悦良, 眞田 克典, "応用線形代数", 共立出版
あたりに載ってます。クラメルの解法どまりの本が多いですが、
(正)射影行列(および直交射行列と書いてあるのは今のところ見ませんが)
や特異値分解まで出てくる本もどっかで見た気がします。
今回、arXivに出そうと思ってるのは、どこかのウェブサイトかGoogle Scholar や
Google Books にpdfがある文献のみReferenceにしようと思ってます。
463 :neetubot [] :2010/05/10(月) 01:55:19
elsevierの"Linear Algebra and its Applications"
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/522483/description
にあるH Kurata, T Sakuma, "A group majorization ordering for Euclidean distance matrices", 2007
が気になるなぁーじゃあ5月31日まで集中します、何かあったらお気軽にどうぞ
464 :neetubot [] :2010/05/22(土) 11:21:29
Allan L. Edmonds, Mowaffaq Hajja, Horst Martini,
"Coincidences of Simplex Centers and Related Facial Structures"
http://www.emis.ams.org/journals/BAG/vol.46/no.2/b46h2ehm.pdf
"Orthocentric simplices and their centers"
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0508/0508080v1.pdf
の参考文献や
Malgorzata Buba-Brzozowa,
"Ceva's and Menelaus' Theorems for the n-Dimensional Space"
http://www.heldermann-verlag.de/jgg/jgg01_05/jgg0410.pdf
を発見した!研究者名でまとめたいなぁー
ところで,私がarXiv(Math.MG)へ投稿していいという承認を,
↓のURIから誰かして頂けると大変ありがたいです。
http://arxiv.org/auth/endorse.php?x=S433L3
465+1 :neetubot [] :2010/05/22(土) 15:50:14
立体行列
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1246851207/
立体行列?について当スレの内容から常識的に考えると、
m次元ユークリッド空間内のある点を表す斉次座標の(m+1)次元
列ベクトル \~p_i に対して、アフィン変換する(m+1)×(m+1)行列
\~M_i を掛けたときに、別の点を表す(m+1)次元列ベクトル
\~p'_i ( = \~M_i \~p_i ) となるとすれば、この式を i=0…n に対して
奥行き方向に並べた式 \~P' = \\~M \~P (↑)の \\~M として立体行列
(階数3のテンソル、または、3次元配列)が得られる。(ただし、行列の標準内積ベースの演算を使っている)
ここで、\~P' および \~P が互いにn次元単体を表す一般的な点列の位置座標だとすれば、
標準的に空間ごと別のアフィン変換をする(m+1)×(m+1)行列 \~M’ を用いて
普通の行列演算で \~P' = \~M’ \~P と書けるはずである。これは、さきの
立体行列 \\~M の各奥行き方向の(n+1)個ある(m+1)×(m+1)行列 \~M_i に対して、
一つの(m+1)×(m+1)行列 \~M’ が一意的に定まる \~M’= f[ \~M_0, …, \~M_n ]
のような奥行き方向の変換式が存在するということになる。
以上より、アフィン変換行列群の例における立体行列は、
普通の一つのアフィン変換行列に帰着できてしまうことになる。
これによって、立体行列による多重線型変換(?)による拡縮・回転・平行移動
の成分がさきの \~M’= f[ \\~M ] を解くことによって一意に求まる.気がする。
466+1 :neetubot [] :2010/05/22(土) 16:33:34
面白い問題おしえて~な 十六問目
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1254690000/186
>186 :132人目の素数さん :2010/05/21(金) 08:45:41
>時計の時針・分針・秒針の全てが同じ長さ・同じ重さだったとする。
>
>
>時計が一番つらい時間は何時何分何秒か?
等速で均質な針が動く時計において、12時ちょうどから時計回りの方向に
時針(長さl・重さm)がθだけ回転したときには、分針(長さl'・重さm')は12θ
だけ回転し、秒針(長さl''・重さm'')は720θだけ回転していると考えられる。
この連続理想時計で、ちょうど6時の方向に重力加速度gがかかる場合、
時針・分針・秒針の重さによって時計中心にかかるモーメントの大きさの総和 N は、
N = ( l m g |sinθ| + l' m' g |sin(12θ)| + l'' m'' g |sin(720θ)| )/2 と表せる。
よって、Nが最大となるときのθは…絶対値が外れる条件で微分…するのはめんどいし、
結論: これは離散的な数値計算した方がいいな…
っていうか、そんなに気になるなら、時計を寝かせて使うか、時を止めてしまえっ!
むしろ、論文書くの間に合ってないので、私のために世界の時を止めて下さいザワールド
467 :neetubot [] :2010/05/23(日) 15:15:14
>>465 \~M’= (\~M_0 + … + \~M_n) / (n + 1)としか
予想できんが、証明なんてできそうにないなこれ。
>>466 この連続理想時計の3つの針が12時ちょうど以外の12時間で
ちょうど重なることはあるか考える。まず、時針・分針が重なるとき
0<θ<2πで θ+2kπ=12θ(k=1,…,10)となればよいので、
θ=2kπ/11 (12時を基準に1周を11等分した10箇所)で時針・分針が重なる。
同様に計算すると、分針・秒針が重なるのは59等分された58箇所で、
時針・秒針が重なるのは719等分された718箇所であるため、
11と59と719がそれぞれ互いに素であることから時針・分針・秒針が
全て重なりあうことはこの連続理想時計では12時ちょうど以外には
ありえないということが導ける。同じように24時間時計でも離散的に
動くとしてもありえないとは思うけど、本スレの針交換の意味がわからん。
まぁ、俺の考えなどどうでもいいことだから、向こうのスレを汚さずこっちでやりますた
468 :132人目の素数さん [↓] :2010/08/06(金) 02:40:52
386