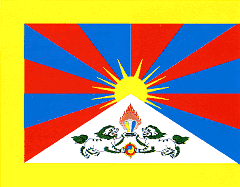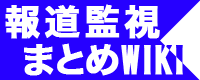
情報操作の手法
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
権力やマスコミだけでなくこのWIKIも含めたあらゆる情報にこれらの手法はあふれています。ここに列挙されているのが全てでもありません。
情報操作の手法 目次
情報封鎖
報道の自由がない状態。情報支配と密接に関係しており、当局の一方的な情報が流される。中国・北朝鮮・ビルマ・イラクでは、国全体に情報封鎖がされている。またサウジアラビアは外国メディアの内政取材を一切許さない。 広い意味では記者クラブも含まれる。
- 具体例
報道しない自由
報道の自由の悪用。事実を捏造はしないが、都合よく取捨選択する事で、意味を変える、ずらす。
- 多数の事件から何を報道するかの選択
- ある事件の情報から何をを報道するかの選択
例2 オバマ大統領の天皇陛下へのお辞儀の角度の選択による各社の意図

朝日
http://s01.megalodon.jp/2009-1114-1525-45/www.asahi.com/national/update/1114/TKY200911140177.html
http://s01.megalodon.jp/2009-1114-1525-45/www.asahi.com/national/update/1114/TKY200911140177.html

imageプラグインエラー : ご指定のURLまたはファイルはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLまたはファイルを指定してください。
事実としては産経の写真のような深く腰を折る最大級の敬意の表明があったわけですが
その前後の陛下と対等のような印象のタイミングの写真や皇后陛下との握手の写真も「嘘」ではありません。
写真自体を扱わないという読売の姿勢もまた異なった手法です。
その前後の陛下と対等のような印象のタイミングの写真や皇后陛下との握手の写真も「嘘」ではありません。
写真自体を扱わないという読売の姿勢もまた異なった手法です。
問題は「忠誠・愛国心」や「天皇陛下の権威」の是非以前に、それらに対するマスコミの情報操作が行われているという事です。
この件に限らず事の是非や印象の好悪の決定は、本来操作のない情報の元で受け取り手側が判断するべきです。
この件に限らず事の是非や印象の好悪の決定は、本来操作のない情報の元で受け取り手側が判断するべきです。
付記 その後の話題への対応
オバマ大統領の両陛下への「お辞儀」、米で波紋
11月16日11時12分配信 読売新聞
http://s04.megalodon.jp/2009-1116-1734-01/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091116-00000480-yom-int
朝日・毎日が好んで扱いそうな話題でありながら、皮肉にも先に深いお辞儀を隠蔽したためこの件の報道はないようです。
オバマ大統領の両陛下への「お辞儀」、米で波紋
11月16日11時12分配信 読売新聞
http://s04.megalodon.jp/2009-1116-1734-01/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091116-00000480-yom-int
朝日・毎日が好んで扱いそうな話題でありながら、皮肉にも先に深いお辞儀を隠蔽したためこの件の報道はないようです。
統計でウソをつく法
アンケートの統計結果などを利用して嘘をつくのは常套手段です。
そのアンケート結果が信頼に値するかどうかは、ある程度以下で判断できます。
そのアンケート結果が信頼に値するかどうかは、ある程度以下で判断できます。
a.アンケート回答者が対象の事柄について十分な理解がある
b.実施人数、有効回答数などが統計データとして十分である
b.実施人数、有効回答数などが統計データとして十分である
a.については、たとえば報道番組などで政治的なアンケートをとった場合、その対象となる政策について、その辺を歩いている一般的な人(自分自身も含めて)が十分な理解をできていそうかどうか。偏見ありきのアンケート結果は、当然ながら信頼に値しません。
b.については、統計というのは最低でも1000以上はないと信頼に値するデータは得られないとされています。実際、よく見るとテレビなどでのアンケートは100人程度であったりと、回答者たちに十分なばらつきがあるとは思えない場合が多いです。
また、ある一定の地域のみ限定でのアンケートであったり、実施人数は多くてもあまりにも有効回答率が低かったりするアンケートも同様の理由で信頼には値しません。大体アンケートの実施者などは「こういう結果が欲しい」を前提に実施していることがほとんどなわけで、自分の求める結果が得られやすい地域・対象年齢・対象性別で行っている可能性も否定できません。
b.については、統計というのは最低でも1000以上はないと信頼に値するデータは得られないとされています。実際、よく見るとテレビなどでのアンケートは100人程度であったりと、回答者たちに十分なばらつきがあるとは思えない場合が多いです。
また、ある一定の地域のみ限定でのアンケートであったり、実施人数は多くてもあまりにも有効回答率が低かったりするアンケートも同様の理由で信頼には値しません。大体アンケートの実施者などは「こういう結果が欲しい」を前提に実施していることがほとんどなわけで、自分の求める結果が得られやすい地域・対象年齢・対象性別で行っている可能性も否定できません。
また、統計データにはアンケート以外にも平均値などもあります。
これもまた、データを元に嘘をつくには格好の材料となることが多いです。
たとえば、昼夜で非常に寒暖の差の激しい砂漠のような場所でも、「夏季の昼は40度、冬季の夜はマイナス10度」と書かずに「平均気温は20度前後!」などとうたえば、まるですごしやすい快適な場所のように受け取られてしまいます。どちらも、嘘はついていないわけですが。
これもまた、データを元に嘘をつくには格好の材料となることが多いです。
たとえば、昼夜で非常に寒暖の差の激しい砂漠のような場所でも、「夏季の昼は40度、冬季の夜はマイナス10度」と書かずに「平均気温は20度前後!」などとうたえば、まるですごしやすい快適な場所のように受け取られてしまいます。どちらも、嘘はついていないわけですが。
フィードバック
予め特定の結論が得られるような質問や選択肢を作成しておき、一般の視聴者の回答を受けて、視聴者全体の意見に偽装する。テレビの電話投票やネット投票等。
質問内容や選択肢を隠して回答結果だけを報道することでより効果を発揮する手法。
失敗例
質問内容や選択肢を隠して回答結果だけを報道することでより効果を発揮する手法。
失敗例

2009年6月放送 日本テレビのテレゴング 2択アンケート「政権交代すると日本はよくなる?」
A良くなる
B良くならない
選択肢に「悪くなる」がなく、「A良くなる」を選択させようとする意図がみえみえ。その割りに「A良くなる」へ誘導するテクニックがなにもなく、生放送での電話アンケートというごまかしの効かない状況で皮肉な結果に。
通常フィードバックはもっと巧妙に行われ質問の裏の意図は隠されたまま誘導されてしまいます。
A良くなる
B良くならない
選択肢に「悪くなる」がなく、「A良くなる」を選択させようとする意図がみえみえ。その割りに「A良くなる」へ誘導するテクニックがなにもなく、生放送での電話アンケートというごまかしの効かない状況で皮肉な結果に。
通常フィードバックはもっと巧妙に行われ質問の裏の意図は隠されたまま誘導されてしまいます。
ソースロンダリング
信憑性の薄い噂などを、あたかも真実であるかのように見せかけるために、社会的に信用のあるメディアや人物を介することで「情報源(ソース)の洗浄」を図り、信憑性を高める手法である。
資金洗浄(マネー・ローンダリング)をもじった造語。
自分の言いたいことを「~の声もある」「~と言われている」と、世間の声であるかのように伝えたり、ソースを明かさないで「事情通は~」「関係者は~」と書く。
たしかに「私は○○と思うのだが」と言うよりも「○○と言われている」の方が客観的な印象に。わざわざ「それは誰がそう言ったんだ?」と聞く人は少ないので、多用されるテクニック。
資金洗浄(マネー・ローンダリング)をもじった造語。
自分の言いたいことを「~の声もある」「~と言われている」と、世間の声であるかのように伝えたり、ソースを明かさないで「事情通は~」「関係者は~」と書く。
たしかに「私は○○と思うのだが」と言うよりも「○○と言われている」の方が客観的な印象に。わざわざ「それは誰がそう言ったんだ?」と聞く人は少ないので、多用されるテクニック。
ソースの自作自演
「一部報道では~」と自社や系列機関からのソースを利用。
実例(※見透かされて失敗しています)
2011年6月9日午後、党本部・平河クラブ会見場で行われた、谷垣禎一総裁の定例記者会見にて
http://www.youtube.com/watch?v=Rb9Vaf__wTs
8:50あたり
朝日「一部報道では大連立の可能性とありますが、谷垣総裁はどうお考えでしょう?」
谷垣総裁「一部報道って、どこのふざけた報道ですかそれは?私、知りません」
朝日「週刊誌に載ってたんです‥週刊朝日の報道です」
会場:あっはっはっ(みなわらう)
谷垣総裁「‥あぁ、御社が出しておられる週刊誌‥」(苦笑)
会場爆笑
谷垣総裁「まぁ、御社の週刊誌に対して、あまり過激な事を言うつもりはありません」
実例(※見透かされて失敗しています)
2011年6月9日午後、党本部・平河クラブ会見場で行われた、谷垣禎一総裁の定例記者会見にて
http://www.youtube.com/watch?v=Rb9Vaf__wTs
8:50あたり
朝日「一部報道では大連立の可能性とありますが、谷垣総裁はどうお考えでしょう?」
谷垣総裁「一部報道って、どこのふざけた報道ですかそれは?私、知りません」
朝日「週刊誌に載ってたんです‥週刊朝日の報道です」
会場:あっはっはっ(みなわらう)
谷垣総裁「‥あぁ、御社が出しておられる週刊誌‥」(苦笑)
会場爆笑
谷垣総裁「まぁ、御社の週刊誌に対して、あまり過激な事を言うつもりはありません」
匿名の権威
「消息(信頼すべき)筋によれば…」等のフレーズで始まり、記事の内容に権威を与える。海外メディアを利用するケースもある。
社会的同意
社会全体が報道の中の意見に同意しているような印象を与える。「国民(庶民・市民)の声は、、」など一般大衆の代弁という印象を与える。逆の手法(社会全体がその意見に不同意)は、社会的不同意。
仲介者の利用
集団に対して情報操作を行うために、その集団のオピニオン・リーダーに狙いを定めて工作する。しばしば、オピニオン・リーダーは金品等で買収されることもある。
- 具体例 中国は公式見解として「天安門事件では軍隊はデモ隊を殺さなかった」と代表的なデモ参加者に証言させ発表。NHKはそれを事実として報道
思考や感情の誘導
連想の創出
隠喩、比喩を駆使して、好意的、又は否定的に印象を操作。効果音やBGMの選択などでも印象はかわる。
- 具体例
直接かかわりのない「在日特権を許さない市民の会」と経済評論家の三橋貴明氏を同じコラムにまとめて無意識での同一視を誘う編集意図。
(世論挑発 煽動社会というコラムテーマが皮肉、、)
クリックで拡大
クリックで拡大
感情共鳴
デモや集会等における群集の扇動からの応用。群集を理性ではなく、感情レベルで反応させる。
- 具体例 報道における「酷いですねえ」「許せませんねえ」「おそろしいですねえ」「感動的ですねえ」などのコメント
心理的ショック
感情共鳴のピークを利用する。生々しい戦災や事件現場の映像が利用される。
- 具体例 湾岸戦争の 『油まみれの黒い鳥』のやらせ映像
反復
同じフレーズを反復して、人々の記憶に刻み込ませる。嘘も百回言えば真実となる(ヨーゼフ・ゲッベルスの言葉)。
サブリミナル
サブリミナル効果(サブリミナルこうか)とは、意識と潜在意識の境界領域より下に刺激を与えることで表れるとされている効果のこと。
1973年には、ゲーム「Hūsker Dū?」の宣伝にサブリミナル刺激が用いられ、それが使われたという事実がウィルソン・ブライアン・キイの著書で指摘されたことで、米国連邦通信委員会で公聴会が開かれ、サブリミナル広告は禁止されることになった。日本では1995年に日本放送協会(NHK)が、1999年に日本民間放送連盟が、それぞれの番組放送基準でサブリミナル的表現方法を禁止することを明文化した。
現在、映画やテレビ放送などではほとんどの場合、使用を禁止されている。
1973年には、ゲーム「Hūsker Dū?」の宣伝にサブリミナル刺激が用いられ、それが使われたという事実がウィルソン・ブライアン・キイの著書で指摘されたことで、米国連邦通信委員会で公聴会が開かれ、サブリミナル広告は禁止されることになった。日本では1995年に日本放送協会(NHK)が、1999年に日本民間放送連盟が、それぞれの番組放送基準でサブリミナル的表現方法を禁止することを明文化した。
現在、映画やテレビ放送などではほとんどの場合、使用を禁止されている。
- 具体例 フジTV韓流サブリミナル疑惑
半真実
虚偽の中に一面的な真実を織り交ぜ、記事全体を真実に見せかける。
誤解を意図的に利用する
たとえば、「東大の入試試験で落ちませんでした」というと、さも東大に合格したかのようです。しかし、事実はそもそも受験していないだけです。くだらないと言われればくだらないのですが、この論法は相手をだますのには有効です。
たとえばマルチ商法などの場合。「これで損をしたやつはいない」などという言い方をされる場合があります(「絶対に儲かる」は逆に使いません)。マルチ商法の多くは、販売代理店として在庫を抱える代わりに子の代理店契約を行ってそいつにまた在庫を抱えさせることで自分が儲かる、といったネズミ講まがいのシステムが多いわけです。
たとえ借金をして在庫を抱えて、それなのに自分の子になってくれる代理店の契約ができなかったとしても、それは「損はしていない」わけです。だって、親の代理店に払ったお金は「権利と在庫分の代金」であるので、価値は減じてない、と解釈できるからです。
たとえばマルチ商法などの場合。「これで損をしたやつはいない」などという言い方をされる場合があります(「絶対に儲かる」は逆に使いません)。マルチ商法の多くは、販売代理店として在庫を抱える代わりに子の代理店契約を行ってそいつにまた在庫を抱えさせることで自分が儲かる、といったネズミ講まがいのシステムが多いわけです。
たとえ借金をして在庫を抱えて、それなのに自分の子になってくれる代理店の契約ができなかったとしても、それは「損はしていない」わけです。だって、親の代理店に払ったお金は「権利と在庫分の代金」であるので、価値は減じてない、と解釈できるからです。
このように、言葉の上で嘘をつかずに、うまく相手の考えを誘導するには、一般的な言い回しだが一般的ではない使い方をして「相手がそう思いたがっている」ということを利用すれば比較的容易に相手を騙すことができてしまいます。
写真を意図的に誤解させる例
相手の考えを固定する(ロックオン)
判断材料をあえて少なくすることで相手の選択肢を狭めて正常な判断ができない状況にしてしまう、というのも常套手段として存在します。
よくあるパターンとしては、たとえば原発推進などで、
「あなたは電気を使いますね?」
→「じゃあ発電所は必要ですね?」
→「じゃあ原発に賛成ですよね?」
と、どんどん相手の視野を狭めて選択の余地をなくしてしまうというわけです。心理学用語では「ロックオン」というそうですね。
この論法の特徴は、まったく逆の結論でも同じような論法を行うことができることです。先の原発の例で言うなら、
「核は危ないですよね?」
→「じゃあ原発も危ないですね?」
→「じゃあ原発に反対ですね?」
また、プレゼンテーションなどで有効な手段として、「最初に結論を言う」というのがあります。
結論から入って、その説明を行うことでわかりやすくする効果もあるのですが、相手の考えを最初に傾けておくというのは相手を誘導する上でも有効な手段であるからです。これもある種の「ロックオン」であるといえるでしょう。
よくあるパターンとしては、たとえば原発推進などで、
「あなたは電気を使いますね?」
→「じゃあ発電所は必要ですね?」
→「じゃあ原発に賛成ですよね?」
と、どんどん相手の視野を狭めて選択の余地をなくしてしまうというわけです。心理学用語では「ロックオン」というそうですね。
この論法の特徴は、まったく逆の結論でも同じような論法を行うことができることです。先の原発の例で言うなら、
「核は危ないですよね?」
→「じゃあ原発も危ないですね?」
→「じゃあ原発に反対ですね?」
また、プレゼンテーションなどで有効な手段として、「最初に結論を言う」というのがあります。
結論から入って、その説明を行うことでわかりやすくする効果もあるのですが、相手の考えを最初に傾けておくというのは相手を誘導する上でも有効な手段であるからです。これもある種の「ロックオン」であるといえるでしょう。
強調点の転移
事実は改編しないが、強調点を転移して事実の意味を変えてしまう。
直接嘘を用いなくても効果を出せる。(さらに嘘を組み合わせ効果を高める事も)
直接嘘を用いなくても効果を出せる。(さらに嘘を組み合わせ効果を高める事も)
- 一例 郵政改革を焦点とする事で改革賛成・反対以外の分類が選挙で問われない状況を作った小泉元総理とマスコミ。
ケンカ両成敗
批判したくない側を批判せざるを得ない時に「お互いに…」という表現にして両成敗にして問題をうやむやに。
分類表
決まりきった単語、フレーズを使用することで、事件がどのようなものなのか分類してしまう。
格付け
例えば、選挙の立候補者の能力や当選の可能性、スポーツ選手の能力等の格付けを行い、世論を誘導する。その為には無関係な要素も導入。
- 具体例 フィギュアスケートの浅田真央選手と韓国の金妍児選手のスポンサーの数まで比較するTV報道
脅威の創出
敵対者(反対意見)の危険性を強調して、よりましな(マスコミに好都合な)選択肢を選ばせる。
毒入りサンドウィッチ
序文と結論に否定的報道をおいて、肯定的な報道を挟み込み、肯定的な報道の意義を低下させる。
逆の手法(肯定的報道で否定的報道を挟み込む)は、「砂糖入りサンドウィッチ」と呼ばれる。
逆の手法(肯定的報道で否定的報道を挟み込む)は、「砂糖入りサンドウィッチ」と呼ばれる。
撹乱
価値の低い大量の情報を流し、事件そのものに対する関心を低下させる。いわゆる情報ノイズ。
言葉のすり替え
否定的な意味を有する言葉を受け入れ易い言葉(またはその逆)に置き換える婉曲的手法。たとえば、テロリストはレジスタンスとなり、略奪行為は抗議デモと報道される。 「人権」「環境」「グローバリズム」など口当たりのいい言葉が使われる場合にも、すり替えに注意が必要。
- 具体例 実際は人権弾圧法案という疑いが強い「人権擁護法案」
新造語
外来語や新しい表現を導入することで本質的には変わりない事に興味を持続させる。またイメージUPをはかる。
- 具体例 環境問題 ⇒ エコ スローライフ⇒ロハス
説明責任を煙にまくため、無用にカタカナ語をつかう。
- 具体例 ホワイトバンドの非難に対する釈明で用いられる「アドボカシー」
仮定の話をいつの間にか事実のように語る
「もし○○なら」と、あくまで仮定の話としながらも、推論を進めていき、それがあたかも事実であるかのように思わせる。追及されたら仮定の話と反論。
関係ない事柄を、関係あるかのように言う
たとえば支持率の落ちた政治家が、ゴルフをやってバンカーに入ったりしたら、それが支持率の低下と関係あるかのように言う。「脱出は難しい」とか、何をやってもダメという印象を与える。
論理のすり替え
たとえば、昨今話題の「女系天皇」問題などでも、「過去に推古天皇、持統天皇など女性の天皇がいたんだから」という言い方をする人がいますが、その代限りの「女性天皇」と系統が継続する「女系天皇」は異なる概念です。「女性天皇」がいたということがイコールとして「女系」で天皇位を継承していく制度の根拠とはなりえません。
事件のすり替え
受け入れにくい事件Aに対して、表面的には似ている受け入れやすい事件Bを集中的に報道し、Aから注意をそらす。さらにBの刷り込みがなされている段階で報道していたという「アリバイづくり」にわずかにAの報道をし、疑問をいだかせず受け入れさせる。その後もBの報道を繰り返しAの事は忘れさせる。長いスパンでの「砂糖入りサンドウィッチ」報道。
- 具体例 A国籍法改正を成立までほとんど扱わず、Bフィリピン人親子の報道を繰り返す報道
その他手法
予告打撃
世論の否定的反応を引き起こす政策を採る際、情報を事前にリークし、決定採択時までに世論の関心を低下させる(飽きさせる)。
アリバイづくり
重要な案件を報道していなかったという批判をかわすため、早朝や深夜のニュースで短時間だけとりあげる。また報道番組の終了時間まぎわに短時間だけとりあげるなど。
- 具体例 西松建設の裏金問題での小沢一郎の秘書逮捕よりまえのTV報道では、献金関連の議員名は早朝や番組終了直前で短時間にしか報道されなかった。
泥棒捕り
↓「一次効果 」の応用。何らかの事件に対して批判・責任を問われる人物が、他者に先駆けて事件を批判し、怒りを他方向に向けさせる。
- 具体例 消えた年金問題の主犯である自治労とそれを支持母体とする民主党が、政府の追及が出始めると、マスコミに問題をリーク、政府に責任転嫁。自治労出身の議員ですら自民党政府(当時)を叩いた。
一次効果
最初に発信された情報は、後発の情報よりも優先され、信用されやすいという原理に基づく。
プレゼンス効果
事件現場から発信される情報は、人々に現実のものと受け取られやすい。臨場感を演出するために、しばしば、やらせが行われる。
アドバルーン
世論の反応を見るため、試験的な情報・報道を流す。反応に応じその後の報道方針を決める。
情報の波の創出
情報の一次波を起こし、不特定多数による大規模な二次波を発生させる。いわゆるブログの炎上。
ほめ殺し
竹下元首相に対する街宣右翼の攻撃、「お金儲けの上手な竹下さん」「恩人を裏切る華麗な“芸”を持つ竹下さん」など、“誉めて”いるようで非難する手口から「ほめ殺し」と表現された。同様のケースに愛人スキャンダル下を狙った「女性に優しい中川秀直さん」といった攻撃などがある。
- 具体例 民主党北海道へ抗議?ほめ殺し編
なりすまし
一般的にネガティブな印象の存在からの支持を受けている事が公になれば第三者にはマイナス印象になる。それを利用して、街宣右翼やカルト宗教信者、オカルティスト、陰謀論者などを装い信頼性を低下させたい相手の仲間として振舞う。そもそも街宣右翼自体が保守・愛国思想を貶めるための「なりすまし右翼」だという見方がある。ほめ殺しと組み合わされる場合もある。
具体例 在日外国人が右翼に「なりすまし」活動、「通名」での日本人への「なりすまし」も。
皇民党幹部ら3人逮捕 不正に車検を受けた容疑 大阪府警
2009.10.15 産経
http://megalodon.jp/2010-0119-1319-46/sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091015/crm0910152327041-n1.htm
2009.10.15 産経
http://megalodon.jp/2010-0119-1319-46/sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091015/crm0910152327041-n1.htm
八千代銀に利益供与要求 総会屋を逮捕
2009.6.26 産経
http://megalodon.jp/2009-0810-1738-51/sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090626/crm0906260003000-n1.htm
2009.6.26 産経
http://megalodon.jp/2009-0810-1738-51/sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090626/crm0906260003000-n1.htm
ネット上でのなりすまし
「日の丸・君が代」強制反対ホットライン・大阪HPのソースに なぜか韓国雑貨オンラインショップの痕跡
ブラウザでページのソースを表示すると以下のMETA contentからこのHPを韓国サイドの人が作った事がわかります
<META content=" お隣の国、韓国・ソウルから直接買い付けた、モダンでハイセンスな韓国雑貨のオンラインショップです。 ポジャギ、韓国茶器、李朝家具など、キュートでちょっと渋い雑貨を多数取りそろえております。" name="description" ,>
※もしページソースから削除されていたら 2011/6/10現在以前の魚拓を確認してください
魚拓
http://megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww7a.biglobe.ne.jp%2F~hotline-osk%2F&type=simple
魚拓
http://megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww7a.biglobe.ne.jp%2F~hotline-osk%2F&type=simple
実際には、上で述べたようなことが複合的に使用されることが多いです。
たとえば日本とアメリカの関係について、
「日本の安全保障のためにアメリカとは仲良くしなくてはいけないから、牛肉輸入問題などを早期かつ円満に解決すべき」
などといった場合、「ロックオン」と「論理のすり替え」が行われているわけです(どこがそうかは、わかりますか?)。
たとえば日本とアメリカの関係について、
「日本の安全保障のためにアメリカとは仲良くしなくてはいけないから、牛肉輸入問題などを早期かつ円満に解決すべき」
などといった場合、「ロックオン」と「論理のすり替え」が行われているわけです(どこがそうかは、わかりますか?)。
これらの「騙しのテクニック」j情報操作に騙されないためには、まさに上の逆を行けばいいわけです。
一 メディアを偏らせない。つまり多角的なメディアから情報を吸収すること。
二 結論を急がず、思い込みを深くしない。常に、(偏見を排した)柔軟な思考を心掛けること。
三 今何を対象として論じているかを把握し他人(メディア含む)との(情緒的よりも論理的な)意見交換を通じて自分の思考に刺激を与えること。(議論の仕方)
四 情報の発信者の意図を推察してみること。
五 情報は(何に役立てるかなど)目的意識を持って能動的に取り入れること。
二 結論を急がず、思い込みを深くしない。常に、(偏見を排した)柔軟な思考を心掛けること。
三 今何を対象として論じているかを把握し他人(メディア含む)との(情緒的よりも論理的な)意見交換を通じて自分の思考に刺激を与えること。(議論の仕方)
四 情報の発信者の意図を推察してみること。
五 情報は(何に役立てるかなど)目的意識を持って能動的に取り入れること。
以上に気をつけ、手に入れた情報の精度を高めましょう。
関連サイト
(↓自動検索による外部リンクリストです。)
#bf
#bf
#bf
※以下広告