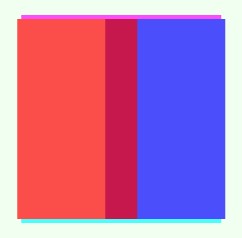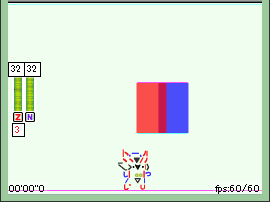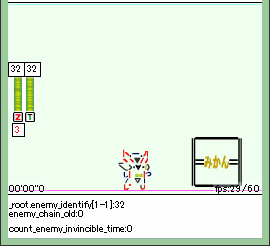・概要
恐らく、このwikiを普通に閲覧しただけでは、アクションゲームの制作に関して、何から始めれば良いのか、殆ど分からないと思われる。
そこで、個人的に推奨する制作の順序を紹介する。以下の順序で制作すれば、アクションゲームにおける基礎的な内容を一通り構築できる(はず)。
・hitrectを用意し、キー入力により移動させる
・・hitrectを用意する
・・キー入力関連の記述をする
・・キー入力によりhitrectを左右に移動させる
「矩形をキー入力により移動させる」ことが、アクションゲームの制作における基礎の基礎となる。
・・「通常状態」「歩き」に関する記述をする
「アクションの状態」「アクションの移行」に関して把握しておく。
・アクション、地形の追加
・・重力加速度の付加
・・「床」を用意し、接触判定を取得する
・・「ジャンプ」関連の処理を記述する
・・「天井」を用意し、接触判定を取得する
「床」の処理を応用する。
・・「壁」を用意し、接触判定を取得する
「床」の処理を応用する。
・・「壁ずり落ち」「壁蹴り」の処理を記述する
・・「移動量」「地形めり込み量の最大値」に関する記述をする
地形との接触判定の「・「移動量」「地形めり込み量の最大値」に関する処理+「接触判定」+「位置調整」」を参照。
・・「ブロック」を用意し、接触判定を取得する
「ブロック」は、壁・床・天井を組み合わせた地形のことを指す。
↓「ブロック」。
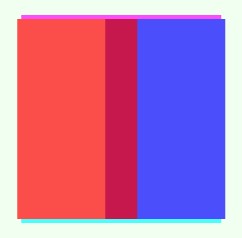
「移動量」「地形めり込み量の最大値」に関する記述を行うことで、「ブロック」との接触判定を正確に行うことができる。
↓「ブロック」との接触判定。
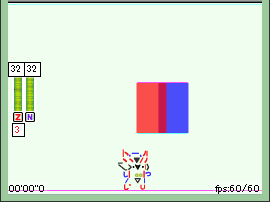
・・「ダッシュ」の処理を記述する
ダッシュを参照。hitrectの変化に関して把握しておく。
地形との接触判定の「・「移動量」「地形めり込み量の最大値」に関する処理+「接触判定」+「位置調整」」の「・・地形めり込み量の最大値(初期値)」の「・・・hitrectの変化を考慮した補正」も参照。
・「バスター(非チャージ)」「敵」の制作
・・「バスター(非チャージ)」を制作する
・・「敵」を制作する
最初は、下に示すような、極めて単純な敵を制作することを推奨する。
↓ブロックみかん。
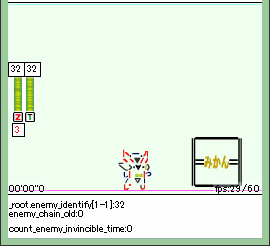
・・「バスター(非チャージ)」と「敵」との接触判定を取得する
上記の「ブロックみかん」には「検証用の記述」をしている。これにより、敵が受けた攻撃に関して検証できる。
ASのファイル:enemy_block_mikan.txt
trace(enemy_hit_attack_type+"/"+_root.enemy_identify[number_enemy-1]+"/"+enemy_hit_attack_element+"/"+enemy_hit_attack+"/"+Math.floor(radian_enemy_hit_attack/Math.PI*180)+"/"+enemy_chain) //検証用
・・「操作キャラクター」と「敵」との接触判定を取得する
・・「破壊」に関する記述をする
・応用
上記の内容を全て構築し終えた場合は、応用の段階に入ることになる。
応用の例に関しては、左のメニューの項目を参照。
最終更新:2020年12月19日 11:15