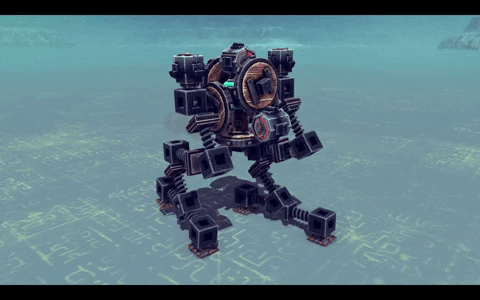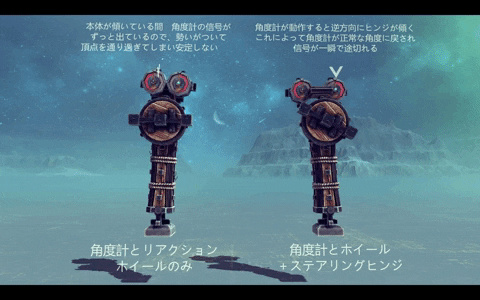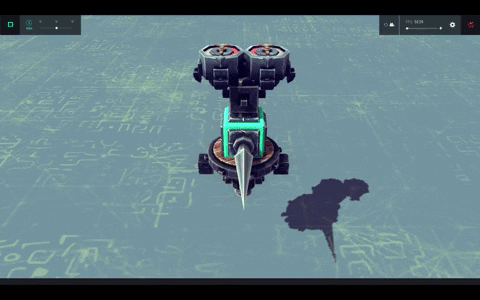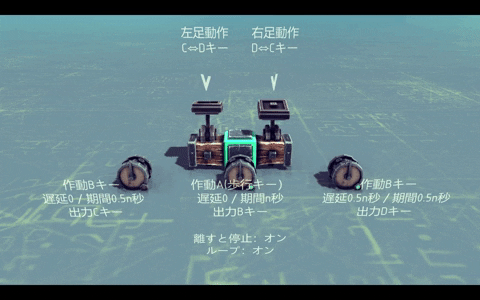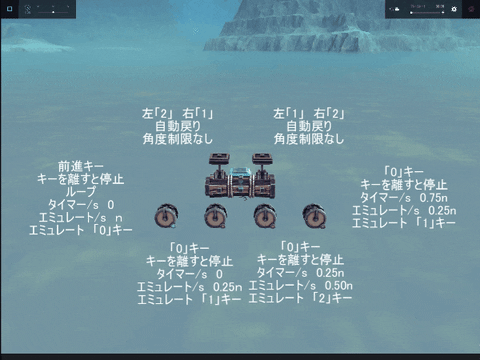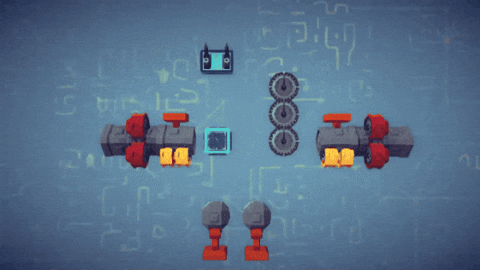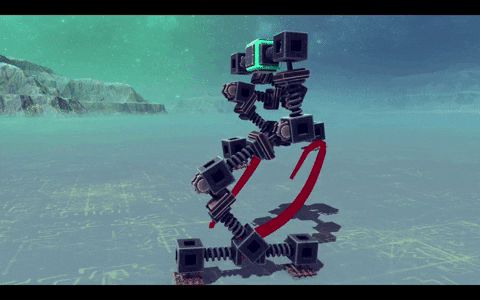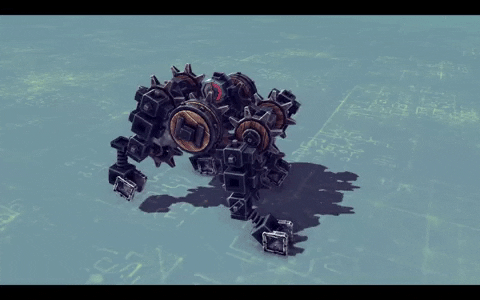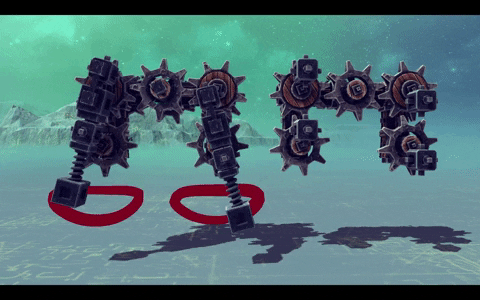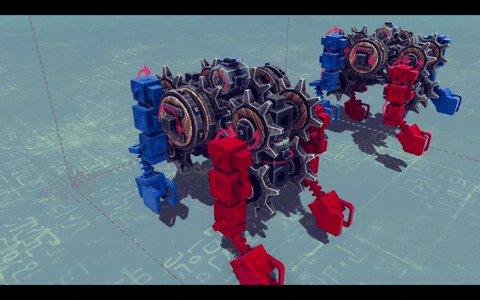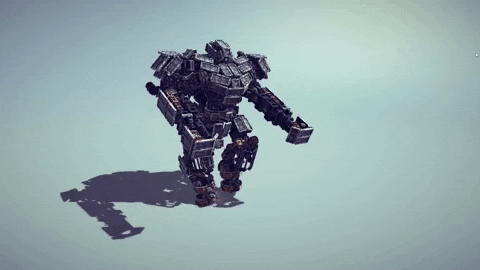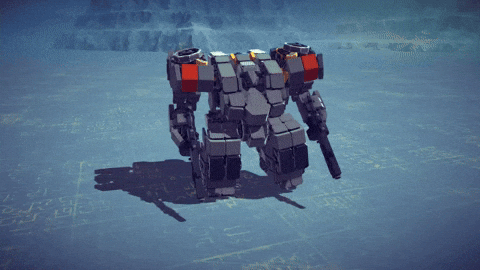はじめに
ここでは歩行機の作り方について学びます。歩行機といっても様々で、四足以上の歩行機はほとんどホイール走行マシンと同じくらい気軽に作れます。しかし二足歩行になると、バランサーやリピートタイマーなどいくつかの要素を組み合わせる必要が出てきます。また、いくつかのMODを使用することで工程を簡略化し、かつより洗練された歩行モーションを実現させることができます。
歩行アシスト機構
転倒防止をはじめとした、歩行機に必要な補助機構です。
水平制御スタビライザー
※
Stabilizer Modなどを使用すればこの項目はスキップ可能。
各軸二つずつの角度計で傾きを検知し、リアクションホイール(→
構造図鑑)でそれを修正するのが基本的な仕組みです。
二つの
角度計はそれぞれ回転軸に対して右回りと左回りへの傾きを検知しています。上図のように前後左右の傾きを制御する場合は、
計4つの角度計が必要になります。
ただし、単純にこの二つのみで制御しようとすると逆に振れが増幅したり、うまくまっすぐ立たなかったりします(下図左)。
これを防ぐために角度計を同軸上で回転する
ステアリングヒンジ上に設置します(下図右)。
各ブロックのパラメータは下記のように設定します。
- ホイール+ブレース
- 機体が完全に横倒しになった状態から復帰可能な強度。回転数を上げるよりブレースを増やすほうが安定する。
- 角度計
- 1°~180°、180°~-1°(±1°の傾きで作動)
- エミュレートキーはホイールの動作キーと同じ
- ステアリングヒンジ
- 角度制限:±10°前後。大きいほど許容する傾きが増える。小さすぎると振動が収まりにくい。二足歩行機の場合、左右の許容値は小さめ、前後の許容値はやや大きめ(±15°)のほうが歩行しやすい。
- 回転速度:0.5が基準。早いほど信号が短くなるので、戻ろうとする力も弱くなる。遅すぎると信号遮断の効果自体が弱くなる
- 自動で戻る:オン
- キー設定はホイール・角度計と同じ。方向に注意(角度計を0度に戻そうとするようにする)
方向制御スタビライザー
歩行機がまっすぐ歩き続けるのは実は非常に難しいことです。特に2足歩行の場合、どれほど精密なつくりをしてもマシンは左右どちらかに曲がっていきます。様々な要因がありますが、少なくとも右足から踏み出すか、左足から踏み出すかという時点で左右非対称な構造をしているものなので根本的な解決方法はありません。
これを解決するために、水平制御
スタビライザーの応用でマシンの進行方向を制御する仕組みを作ります。
上図のように二つの角度計で左右の回転を検知し、底部のリアクションホイールで元の角度に戻す仕組みです。これだけでは意図的な方向転換も不可能なので、角度計をステアリングブロック上に設置します。
ステアリングブロックを回転させるとその下のブロックの角度が相対的にずれるので、マシン全体の方向転換が可能になり、さらにキーを離すと回転後の角度に再び固定されます。
交互信号型ステアリングヒンジ歩行
おもにステアリングヒンジを使用し左右の足を交互に踏み出す仕組みです。
必ずキーを二つ使用するため従来は操作が難しいとされてきましたが、
センサー系ブロックの登場により制御の簡易化が図られ、
現在では主流となっています。
交互信号タイマー
二本の足を動かすために、歩行キーを押し続けている間A→B→A→Bと交互に信号を発生させるタイマーを組み込みます。
キー設定と
タイマー設定は上図のとおりで、中央のタイマーが歩行キーAによって作動するとn秒間信号Bを出力、
左のタイマーがn秒の中で前半の0.5n秒間信号Cを出力し、後半の0.5n秒は右のタイマーが信号Dを出力します。
秒数nは片足を踏み出し、もう片方の足を踏み出す1セットの動作時間に相当します。
ステアリングヒンジの回転速度と制限角度は、このn秒の間に無理なく1往復できる程度にしておきます。
角度制限に縛られないタイマー
タイマーの数を1つ増やすことで、ステアリングヒンジの角度制限に縛られず任意の往復運動をさせることができます。
タイマーの設定は上図の通りで、ステアリングヒンジの回転速度、タイマーの時間nを調整することで歩幅が決まります。
角度制限が自由に付けられるため、変形機や格闘機などで無暗に関節を増やしたくない場合に有効です。
また、事前にほか操作で傾かせておくことで、その角度からの往復運動も行えます。一つのステヒンで複数の往復運動を行える、非常に柔軟性の高い機構です。
交互信号タイマー+角度計
タイマーの信号を直接ステアリングヒンジに送るのではなく、間に角度計を挟んで信号を送ることで任意の角度に設定した複数の歩行パターンを実装することが出来ます。
色のついたブロックの役割はそれぞれ
赤 任意の角度
黄 自動戻り
青 自動戻りオン/オフ(NOT回路)
白 交互信号タイマー
オレンジ 出力先
交互信号A→Bに対応する角度計A-Bが設定した角度まで傾くようにステアリングヒンジに信号を送ることで歩行パターンを形成します。(上図)
詳しいパラメータは
サンプルを参照
脚部の駆動
脚部には一本につき最低2つの間接又は
ピストン等の伸縮機構が必要です。
要は蛇腹折のバネで地面を蹴っていくことになりますので、関節は3つ以上が推奨です。
逆関節、獣脚、人型、様々な形が考えられますが、次の要件を満たすことがスムーズな歩行の近道です。
- 蹴り足(後ろに伸ばす足)は踏み足(前に出す足)よりも下に位置するようにする。
- 地面に接する箇所(足の裏)は水平を保つ。
- ※厳密には水平がベストではなく、足を蹴りだす際につま先でも地面を押すなどの動作を加えることでより効率の良い歩行が可能。ただこれは調整が難しく、上手く歩けない際の原因究明をより困難にするので、まずは水平を意識する方がよい。
- 足の先端部の動きは、前方斜め上⇔後方斜め下の往復運動を意識する(下図)。
- 足を振り子のように前後に振るようにすると、力がうまく地面に伝わらず前進しない。
サンプル
クランク型歯車歩行
クランク式歯車歩行ではタイマーを使用せず、一つのキーを押しっぱなしでなめらかな歩行を行うことができます。ただし、足の上下可動域に制約があるので荷重を適切に分散させないと足が持ち上がりません。このことから、どちらかといえば多脚歩行に向いた機構です。
脚部の駆動
上下に動力付き歯車と無動力歯車を並べ、その間を無動力歯車で繋いで各部の回転をリンクさせます。さらに中間部の無動力歯車をブレースで反対側とリンクさせれば、それをれの脚を同じリズムで動かすことができます。
上下に並んだ歯車には、それぞれ中心から0.5ずらしてスイベル(または速度0の
スピニングブロック)を設置します(上図右)。
これらを接続すればクランクの完成ですが、歯車の回転中にスイベルの距離は微妙に変わります(上図左、接続部のピストンが伸び縮みしている)ので接続には
サスペンション、
スライダー又はピストンを使用します。
スイベルの接続位置の上下は前後、左右の足で互い違いにすれば、前後左右の足を交互に踏み出すようになります。
- 動力歯車のスピードは0.5~1、それ以上にする場合はスタビライザーが必要
- 荷重にもよるが、早すぎると地面を蹴る力が強すぎてひっくり返ってしまうのでスタビライザーで補助する
脚の設置位置
上図赤が歯車の中心部から0.5下げた位置、青が0.5上げた位置。歯車はそれぞれ速度1.5。
スタビライザーはX軸(車体前後の安定)と、Y軸(方向の安定)でZ軸(車体左右の安定)は省略。
前後左右とも互い違いにしたものは静止時に2点支持になるので安定しないが走り出しはスムーズです。
左右をそろえたものは静止時に4点支持で安定しますが、スピードに乗るまでにややもたつきがあります。
サンプル
歩行機製作例
上記の水平制御スタビライザー・交互信号タイマー・方向制御スタビライザーの三つを用いて製作した機体。
水平制御スタビライザー・交互信号タイマー+角度計の二つを用いて製作した機体
前後移動が可能
サンプル
最終更新:2025年03月08日 20:35