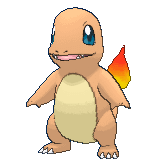
分類:とかげポケモン
タイプ:ほのお
高さ:0.6m
重さ:8.5kg
特性:もうか(HPが1/3以下の時に炎技の威力が1.5倍になる)
隠れ特性:サンパワー(晴れの時に特攻が1.5倍になるが、ターン終了時にHPが1/8減少する)
しずかな ところに つれていくと
シッポが もえてる ちいさな おとが きこえてくるよ。
|
+
|
担当声優 |
-
三木眞一郎
- アニポケ、『スマブラ』シリーズ、『ポケパークWii』
-
阪口大助
- 『不思議のダンジョン 救助隊ガンバルズ』
-
古島清孝
- 『XY』
- 須嵜成幸
- 『THE ORIGIN』
三木氏は コジロウ他、図鑑や様々なポケモンの役を兼任。
|
任天堂の育成RPG『
ポケットモンスター』に登場するポケモンの一匹。
フシギダネ、
ゼニガメと並んで第1世代のカントー御三家に数えられている最古参である。
名前の由来は「火蜥蜴」(「人影」ではない)。なので英名は蜥蜴の姿をした
炎の精霊サラマンダー(Salamander)を捩った「Charmander」
(厳密にはサラマンダーは
トカゲ(爬虫類)ではなくサンショウウオ(両生類)だが)。
生まれた時から尻尾の先に炎が点っているのが特徴。
この炎はヒトカゲの感情や生命力と直結しており、怒ったり悲しんだり驚いた時などで炎の強さが変化する。
この炎が消えるのはヒトカゲの命が終わる事を意味する……と説明されているが、これが
「炎が消える=死ぬ」と誤解される事が非常に多く
*1、
そこから派生して「炎が消える要因(水など)で簡単に命の危機」などと
某命の軽い探検家的な解釈がされる事も多い
(特に初期のメディアミックスにおいて、「尻尾の炎が消えれば死ぬ」はある種の鉄板ネタの一つだった)。
後年の図鑑などの説明を見る限りでは、炎はむしろヒトカゲの生命力のバロメータのようなものであり、
「炎が消えると死ぬ」のではなく「弱っている時炎も弱まり、最終的に死と共に炎も消える」と解釈するのが正しいようだ。
レベルを上げるとリザードを経て
リザードンに進化する。
アニメの展開やリザードンの格好良さもあってか、ヒトカゲもまた人気が高い。
|
+
|
しかし… |
第1世代当時、 御三家でヒトカゲを選ぶのは激ハードモードかつ苦行として知られていた。
何故なら序盤のジム戦であるニビジムとハナダジムがそれぞれ岩タイプと水タイプという、
炎タイプが苦手なポケモンを使ってくるためであった。
ポケモンでは最初のジムでタイプ相性を実戦形式でチュートリアル代わりに学ぶように作られる事は珍しくないが、
ニビの時点では岩タイプに弱点を突けるような技を持つポケモンを入手できず、
弱点を突けるゼニガメやフシギダネを選んだ場合と比較して難易度がべらぼうに高い。
おまけにタケシはなんでもなおしを使ってくるため、火傷による状態異常でごり押しも不可能。
一応 イワークの特殊が低いという突破口があるが、当時はタイプで物理特殊が判定されており、
この時点で入手可能な特殊アタッカーは、育てるのに相当な手間のかかるバタフリー程度。
よって育てる手間を惜しみ効果が今一つな物理技でチマチマ削ったプレイヤーは数知れない。
アニメ『ポケットモンスターTHE ORIGIN』ではレッドは正にこの通りの戦いをしており、
多くのプレイヤーは共感すると共に懐かしさを抱いた。
…と語られてはいたのは事実だが、現在、実はタケシ戦でヒトカゲはそこまで難易度が高いわけではない事が分かってきている。
そもそもイワークは攻撃力がポッポと同数値かつノーマル技しか使用しないので低火力な事に加えてひのこは特殊攻撃判定で、
なんでもなおしを使われるといってもイワークはとくしゅがたったの30なのでそもそもの通りがかなり良い。
すばやさの種族値もフシギダネやゼニガメよりも20以上高いのできゅうしょにあたりやすい
(『初代』の急所率は一部技以外はすばやさの種族値に影響する)。
なので、レベル10前後で(時間こそかかるのは本当だが)既に突破可能であり、
対抗馬のゼニガメが「あわ」で無双するため難易度が低すぎるが故の錯覚に近いものであった。
とはいえ、当時のポケモンはRPGとしては斬新な存在だったためフシギダネの育成も手間に感じないユーザーも多数おり、
個人の主観次第だが、相対的にバトルの勝利に時間がかかるヒトカゲの方が面倒に感じてしまうのも仕方のないことではあった。
ちなみに、タイプ相性的に有利なはずのフシギダネだが、
弱点をつける攻撃技「つるのムチ」を覚えるのがLv13と遅めであり育てる手間がかかる事から、
「フシギダネこそ最初のジム戦が一番きつい」とする声もある。
つるのムチに頼らない場合ダメージソースはイワークに半減される「たいあたり」、
そしてHPを1/8削る「やどりぎのタネ」も初代では半分の1/16と雀の涙しか削れないがそれでもダメージはそれ頼りとなり、かなりの耐久戦を強いられる。
削る量が少ないため当然回復量も少ないがそれでも無いよりはずっと良い、イワークも先述した通り低火力なため時間がかなりかかる。
更に、その前のイシツブテも非常にダメージの通りが悪い上にまるくなるを使われるとたいあたりではほぼ1ずつしか削れないのでダメージは1/16でも削れるやどりぎのタネ頼りとなるので二戦連続で非常に時間がかかる。
レベル上げをしてつるのムチを覚えると戦闘時間は瞬間的に終わっていくが、そこまでに必要な準備時間か上げずに持久戦を行う戦闘時間何方に時間をかけるにしてもフシギダネが一番長くなってしまう。
『ピカチュウ』ではタケシの手持ちのレベルが2低くされ、難易度が大幅に下がったのだが、
そもそも入手はハナダの北なのでヒトカゲには関係の無い調整であった。
そして、本当にきついのはハナダの スターミーでイワークとは比べ物にならない鬼門。
まともに戦えばまずバブルこうせんで瞬殺されてしまう。
一応トキワの森で ピカチュウを捕まえるか、近隣でナゾノクサorマダツボミが捕獲できる救済措置はあるが、
『初代』の敵トレーナーはAIが甘い中、 所謂二面ボスのカスミは珍しく無駄行動が全く無いフルアタであり、
更にはディフェンダーで防御力を底上げしたり、スターミーの素早さの高さも相まって油断はできない。
こちらも弱点を突けるフシギダネや半減で受けれるゼニガメと比較すると、
ヒトカゲは完全に戦力外か盾代わりにしかならないため、難易度は激増する。
その事も製作陣は分かっていたのか、先にマサキの家~クチバのジム以外までをハナダジムをクリアする前に先行で行く事が出来るので、
取り敢えずカスミは後回しにしてレベル上げを確りしてから挑める救済処置を与えられていた。
まぁ、当時はまだ製作者達が手探りだったのと、 ヒトカゲだけでなく炎タイプ全体が不遇だったため仕方がないのだが。
リメイク作品などではサブウェポンの増加や野生ポケモンの見直しにより改善されている。
一方で、ヒトカゲ自身としてはタケシ戦が最も難易度が高くなったのはリメイク版である『ファイアレッド・リーフグリーン』であり、
この作品では『ピカチュウ』であったレベルの低下は無くなり、再度レベル12のイシツブテと14のイワークになった。
一応なんでもなおしを使わなくはなったのだが、そんなものは些細な変更と言えるくらいの強化として、
イワークが「がんせきふうじ」を使うようになってしまった。
『初代』ではたいあたりしか自発的な攻撃は無く、威力もたった35なので、低いこうげき種族値もあってそれなりに耐えられたのだが、
がんせきふうじは威力50のタイプ一致で威力1.5倍に加え、
炎タイプには岩タイプが効果抜群なので実質威力150と4倍以上の超高火力化してしまった。
故になんでもなおしを使わなくなったとは言え、やけどに出来ても差し引きは完全に『初代』に比べてマイナスになってしまっている。
ヒトカゲ自身はメタルクローをこの作品のみ12レベルで覚えるようにはなったのだが、上記の通りイワークはぼうぎょの種族値が非常に高く、
タイプも不一致なので抜群の割にはあまり減らないという事に加えて、第二世代以降とくしゅが特攻と特防に分かれたが、
イワークはよりにもよって特防が第一世代のとくしゅよりも高くなってしまったため、頼みのひのこの通りすらも悪くなってしまったのである。
こうなってしまっては第一世代のようなレベル10前後での突破など到底無理な話であり、ヒトカゲとしては非常につらい時代となった。
|
|
+
|
他作品におけるヒトカゲ |
アニメでは無印第11話「はぐれポケモン・ヒトカゲ」で登場。
元々はダイスケというトレーナーのポケモンだったが、「弱い」という理由で捨てられ、
命の危機に瀕していた所を サトシに救われて手持ちに加わった経緯を持つ。
自分からサトシのモンスターボールに入っていくシーンが印象に残ってる視聴者もいるだろう。
サトシが最初に捕獲した御三家の中でも特に悲惨な過去の持ち主であり、
そのオマージュか、以降の作品でもサトシがゲットした炎タイプの御三家は何かしらの形でタチの悪いトレーナーと縁があった個体達である。
サトシに引き取られた後も「弱い」と見下された事へのトラウマは払拭していなかったようで、
リザードンに進化後にサトシへの感謝を忘れて一時期大きく増長したのも、
当時のサトシのトレーナーとしてのレベルの低さもある(原作で言う「親=捕まえたトレーナーが違うと言う事を聞かなくなる」)が、
念願の力を得て酔い痴れていたためでもあった。
ちなみに、喋る事はできないが、字幕では(ピカチュウを除く)他のポケモン達が元ギャングだったり現役の悪役だった事で口調が荒い中、
ヒトカゲは礼儀正しく丁寧語だった。
世界線の異なる劇場版『キミにきめた!』でもクロスというトレーナーに捨てられた末にサトシの手持ちになっている
(なお、何気にヒトカゲが劇場作品に登場した初のケースである)。
こちらのヒトカゲも進化をしているが、TV版とは異なり懐いたままとなっている。
漫画『ポケットモンスターSPECIAL』ではグリーン及びエックスが手持ちに入れていた。
『 大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズでは、『初代』の「ヤマブキシティ」の やくものとして登場。
ステージのメインとなる中央のビルのペントハウスから飛び出してきて「かえんほうしゃ」で攻撃する。
出てくるだけで何もしない事があったりする他、攻撃を加えて吹っ飛ばす事もできる。
|
MUGENにおけるヒトカゲ
YochiIsC00lest333(Николай Бессонов)氏とStarPlatnum4658氏による共同製作のキャラが公開中。
未進化ポケモンだけあってリーチや性能は控えめだが、
「ひっかく」や「ひのこ」など原作の技は一通り再現されている。
超必殺技に「かえんほうしゃ」がある。
AIは未搭載。
出場大会
*1
これは初代(『赤・緑』)の図鑑で「ほのおが きえたとき その いのちは おわって しまう」とだけ説明されていた事が大きな要因だろう。
確かにこの文面だと炎が水を被ったりなどするとヒトカゲも死んでしまうように解釈出来てしまうが、
これが後年の『クリスタル』の図鑑では「しっぽの さきの ほのおは げんきなら すこしくらい ぬれても きえることなく もえさかる」という風に説明され、
多少の水なら即ヒトカゲの死に直結するという事は完全に否定されるようになった。
最終更新:2024年03月26日 16:39
