「マンダの生贄にせよ!」
1963年公開の東宝映画『海底軍艦』に登場した
怪獣。
別名「怪竜」「守護竜」。全長150m、体重3万t。
東洋の龍のような姿をしており、主に水中に出現する場合が多い。
光線技のような特殊能力は持たないが、相手に巻き付いて締め付ける攻撃を得意とする。
名前の由来は「
マンモススネーク→マンモス
蛇→マンダ」。
竜なのに名前の由来が蛇なのは当初大蛇の怪獣として登場する予定であったが、
映画公開の翌年(1964年)が辰年なので竜の怪獣になった経緯からである。
『海底軍艦』では、海底から地上征服を企むムウ帝国の守護神として登場。
地上を守るためムウ帝国に挑む
轟天号に襲い掛かって巻き付くが、
轟天号の放つ高圧電流に傷付き、そのまま轟天号が発射した冷線砲を喰らって息絶えた。
その後1968年公開の『怪獣総進撃』では角やヒゲが無い2代目が登場。ゴジラ達と共に怪獣ランドで暮らしており、地上でも元気に活動している。
モノレールの高架を締め付けて破壊したが、キングギドラと戦うシーンは無かった。
その後長らく出番は無かったが、2004年公開の『ゴジラ FINAL WARS』では、
体長300m、体重6万tにまでスケールアップして登場。
物語冒頭においてノルマンディー沖深度6700メートル付近の深海で、新・轟天号と闘う。
初代同様、長い体を活かした締め技「バインディング・ブリーカー」で新・轟天号を攻撃するが、
艦長のゴードン大佐の機転によって新・轟天号がミサイルで海底火山を噴火させ、
その中に巻き付いた新・轟天号もろとも突っ込まされる。
さすがのマンダも高熱による超高温には耐えられず体が燃え上がってしまい引きはがされてしまう。
燃え上ってもなお新・轟天号に襲い掛かるもそこを冷凍メーサー砲で氷漬けにされた直後に艦首鋼鉄ドリルで粉砕された。
劇中では描写されていないが、設定上は新・轟天号との交戦以前に戦艦を3艦撃沈しているとの事。
撃破されたのは序盤だったものの、新・轟天号はこのマンダとの戦いで72%を損傷したため修理ドッグ入り。
本部の主力艦を失いかける無茶な作戦をとったゴードン大佐は、軍法会議にかけられた挙句上官を殴って懲罰房送りとなるなど、与えた被害は大きかった。
……のだが、この一件で懲罰房に籠っていたおかげでゴードン大佐は本作の黒幕であるX星人による上層部入れ替わりを免れ、
新・轟天号も地下の修理ドッグに入っていたおかげで怪獣達の一斉攻撃の被害を受けずに済んだため、
ゴードン大佐が指揮する新・轟天号によって
地球最強の兵器を目覚めさせ、
X星人が操る怪獣軍団を撃退する「オペレーション・ファイナルウォーズ」が始動する事となった。
2021年放送のアニメ『ゴジラS.P』では、甲殻類のような体節のある甲冑魚の如き奇怪な外観で出現
(雑誌インタビューで「ムカデがモチーフ」との言及あり)。
当初から三体以上の群れで出現。漁船を転覆させ、救助ヘリを叩き墜とそうとするなど直接的な被害を出したため、
東京湾に現れた群れ相手には海自も出動して迎撃に当たった。群れの大半の撃退に成功したものの、
撃ち漏らして隅田川を遡上したものが
追ってきた超巨大生物に食い千切られる所が目撃される。
東京湾の群れはこれから逃げていただけだったのだ。
この他にも房総半島の海岸に同様に超巨大生物に捕食されたと思しきマンダが打ち上げられたが、
こちらはまた別の怪生物に死肉を貪られた形跡があり、後に付近の工場で営巣する
クモンガが目撃された。
そして東京に上陸した大型の個体が最終進化を遂げたゴジラウルティマ相手に挑みかかるが、
全身に巻き付き首元に食らい付いた所で
原子ビームで瞬殺された。
……喰われたりかませ犬になったりで、総じて本作では不遇枠と言えそうである。
(以上、Wikipediaより一部抜粋・改変)
怪竜
後述するようにMUGENキャラの怪竜もこのページで扱うため、怪竜についてもここで述べる。
『ウルトラQ』第6話「育てよ!カメ」に登場した怪獣。
別名「万蛇怪獣」。身長20m、体重500t。
見れば分かるが操演用のミニチュアは前述したマンダそのものである(まあ、マンダ自体が東洋龍そのまんまだが)。
その後『怪獣総進撃』で再度マンダとして利用される。
龍宮城で暮らす乙姫のボティーガードを務める怪獣。
変身能力を兼ね備えており、劇中では乙姫が乗っているロケットの姿から竜の姿の姿へと変身していた。
口から怪光線を発射する事も可能で、これを用いて太郎少年の搭乗する
ガメロンを打ち落とした。
同作は夢オチとも取れるラストのため、ガメロン共々『ウルトラシリーズ』世界に実在している存在なのかは不明。
(以上、Wikipediaより一部抜粋・改変)
レプティリカス
後述するようにMUGENキャラのレプティリカスもこのページで扱うため、レプティリカスについてもここで述べる。
1961年公開のデンマーク製怪獣映画『Reptilicus』に登場する怪獣。
なお「reptilicus」とはラテン語で「爬虫類(reptile)+関する・派生したもの(-icus)」という意味なので、
この怪獣の種族名というより見たまんまを指している。
日本では『原始獣レプティリカス』や『原始獣レプティリカス 冷凍凶獣の惨殺』の邦題が付けられビデオ化されており、
レプティリカスの名前はこれが由来となっている。
ツンドラ地帯の鉱山で巨大な生物の一部が発見され、科学者による解析の結果爬虫類と哺乳類の中間の進化段階にある古代生物のものであると判明する。
その肉片はデンマークに運ばれ培養液に入れられるが、強力な再生能力を持っていたので短時間に巨大怪獣へと変化、そのまま人間を襲って海に姿を消す。
再出現時には海軍が出動して爆雷攻撃を行なうが、爆発で怪獣の体が破壊されたら再生して多くの個体ができるという科学者の警告も空しく、
レプティリカスの前足を爆雷で吹き飛ばしてしまい、おまけに致命傷を与えるまでに至らず逃亡を許してしまう。
その後レプティリカスは再びデンマークに上陸し、コペンハーゲンの市街地を荒らし回り、口から強酸の液を吐いて人間を殺害。
またまた軍が迎撃するも、その硬い鱗の前には大砲も役に立たず万事休すと思われたが、
口内は柔らかい事に気付いた軍によって怪獣の口に強力な麻酔弾を撃ち込んで倒す。
一件落着かと思いきや海底に沈んだ前足は徐々に成長しつつあった…。
本作はデンマーク軍が全面協力しており、戦車や駆逐艦や野戦砲の描写や群衆シーンは素晴らしいものとなっている一方、
レプティリカス自体は操演を使って表現されており、怪獣の描写や合成が同時期の他の怪獣映画に比べてお粗末…という意見もあり、
一般的にはB級映画やカルト映画扱いされているのも事実である。
(以上、Wikipediaより一部抜粋・改変)
ティアマット
モンスターバースシリーズに登場する怪獣。資料によっては「
ティアマト」とも表記される。
第3作目『キング・オブ・モンスターズ』で存在こそ明かされたものの、名前のみの登場でコンセプトアートもない正体不明の怪獣だったが、
その後日談となるアメコミ『ゴジラ:ドミニオン』にて、同じく第3作では名前のみの登場だった怪獣・アムルックと共に登場して詳細が明かされ、
そして時系列的に『ドミニオン』の後になる第5作『ゴジラx
コング:新たなる帝国』でついに映像作品に登場を果たした。
全長は847フィート(約258メートル)と、モンスターバースシリーズの怪獣では最大の体躯を誇る。
また、口から毒液を吐く能力を備えている。
非常にナワバリ意識が強く、おまけにナワバリの拡張にも意欲的な性格の持ち主。
『ドミニオン』では、コングの先祖の一人が住んでいた地下空洞のとある洞窟を(勝手に)ナワバリにしていたところで、
ゴジラと交戦の末に叩き伏せられてしまった。
『新たなる帝国』では太古に一度は勝利したがトドメは刺せず地下空洞に閉じ込めるのが精一杯だったスカーキングの侵攻、
そして使役されている
シーモと程なく交戦する事を察知したゴジラがフランス・モンタニャックの原子力発電所を襲撃して核エネルギーを簒奪後、
さらなるエネルギーを求めてティアマットのナワバリである太陽風による莫大な量のエネルギーが滞留されていた北極海に向かってきたため、
これを侵略行為とみなして迎撃し、再戦となる。
巻き付き攻撃で攻め立ててゴジラを怯ませるも、怪獣王には敵わず無惨にも体をバラバラにされて絶命してしまった。
MUGENにおけるマンダ
カーベィ氏により『ゴジラトレーディングバトル』の
スプライトを使用した初代と二代目が存在。
後にkMIKEj氏が描いたマンダのスプライトを用いて作られた怪竜が同じくカーベィ氏によって公開され、
こちらはdefファイル登録でマンダとしても使用可能である。
その後2024年1月1日にはこの怪竜の改変キャラとしてレプティリカス、
2025年5月2日にはティアマットが公開された。
なお、いずれも『
パチモン怪獣大熱戦』の仕様がベースとなっている。
|
+
|
カーベィ氏製作 マンダ |
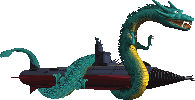 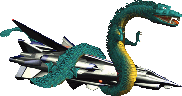
見た目は空中を飛行する轟天号にマンダが巻き付いたもので、空飛ぶのりもののようなキャラ
(と言うか、MUGENにおける轟天号単体もジェット戦闘機シリーズに分類されている)。
『パチモン怪獣大熱戦』仕様に近いアーマーがあり、仰け反りはするが投げなどのステートを奪う攻撃は無効。
ジャンプとしゃがみも無く、高度制限は一応あるものの空中を自由に飛行できる。
操作性と特徴は飛行できる『パチモン怪獣大熱戦』仕様キャラと言った所。
技としてはマンダ部分の頭で攻撃したり轟天号ごと体当たりする技などが登載。
轟天号から放つ高圧電流でマンダごと触れた相手を感電させる技や、マンダが巻き付いている間に轟天号のドリルで相手を攻撃する技は、
原作の描写を元に面白い発想でMUGENキャラの技を作っており、原作ファンならニヤリとできるかもしれない。
別バージョンとして『怪獣総進撃』に登場した宇宙戦闘機ムーンライトSY-3に2代目マンダが巻き付いた「マンダ2代目」も公開中。
ほとんどの基本性能は同じだが、轟天号の攻撃の代わりにSY-3のミサイル攻撃が登載されるなど、性能や演出が違う技もあり、
超必殺技も『怪獣総進撃』でキングギドラと戦うシーンが無かった仲間のバラン、バラゴンと連携攻撃するものになっている。
挙動、性能共に特殊で投げも効かず、空中を自由に飛行するため、一般的な性能のキャラの AIでは対応が難しく、
搭載されているAIも優先的に飛行しようとするので、普通のキャラだと対応できずにグダグダな試合になる事が多い。
AI戦ではなく プレイヤー操作で楽しむといいだろう。
|
|
+
|
カーベィ氏製作 怪竜 |
こちらはkMIKEj氏が描いたスプライトを基に作られたキャラ。
公開当初は上記のマンダ同様『パチモン怪獣大熱戦』仕様に近いアーマーがあり、
仰け反りはするが投げなどのステートを奪う攻撃は無効だったが、
2024年1月1日の更新で投げが有効となった。
ジャンプとしゃがみも無く、高度制限は一応あるものの空中を自由に飛行できる。
操作性と特徴は飛行できる『パチモン怪獣大熱戦』仕様キャラに近い。
怪竜単体なので近接攻撃が中心だが、飛び道具として怪光線を発射可能。
必殺技は「必殺怪光線」と相手に絡み付く「バインディング・ブリーカー」の二種類。
またdefファイル登録によって初代マンダと二代目マンダを使用する事もでき、その場合は「怪光線」が「超音波砲」となる。
また同じく2024年1月1日には『ゴジラ FINAL WARS』版のマンダも公開された。
性能や技構成は同じものとなっている。
2025年の更新によりマンダと怪竜はそれぞれ独立キャラとなった。
いずれもAIはデフォルトで搭載されている。
|
|
+
|
カーベィ氏製作 レプティリカス |
怪竜と同じくkMIKEj氏が描いたスプライトを基に作られたキャラ。
上記の怪竜の改変キャラとなっており、性能や技構成も同じである。
こちらもAIはデフォルトで搭載されている。
|
|
+
|
カーベィ氏製作 ティアマット |
上記の怪竜の改変キャラとなっており、性能や技構成も酷似しているが、
こちらは超必殺技に「必殺毒液」が搭載されている。
AIはデフォルトで搭載されている。
|
出場大会
最終更新:2025年10月02日 09:34






