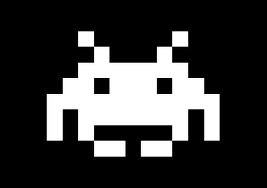1978年にタイトーから発売された世界で一番有名と言われているSTGの名称、
及びそのゲームに登場する敵キャラクターの総称。直訳すれば「
宇宙の侵略者」。
企画段階での題名は「スペースモンスター」(宇宙の怪物)だったが、
海外営業部から「海外ではインベーダーの方が受ける」との意見を受け変更されたのだとか
(何故本作完成前から海外営業部を持っているのか?と疑問に思う人が居るかもしれないが、タイトーは元々「太東貿易」と言う貿易会社であり、
本作開発前から『ポン(
獄長テレビテニス)』や『ブレイクアウト(ブロックくずし)』等の輸入販売を行っていたからである)。
1980年にアメリカ製のゲーム機Atari 2600にへ移植されたのを皮切りに、今なお様々なゲーム機へ移植されている。
「敵キャラクターが
能動的な攻撃を仕掛けてくる初のゲーム」として世界で大ヒットしたゲーム。
画面上方から迫り来るインベーダー(敵キャラクター)を自機である移動砲台で撃ち、全滅させる事を目的とする。
時々上空に母艦の
UFOが出現し、これを撃ち落とすとボーナス点を獲得できる。
このゲームの登場が社会現象となり、ゲームセンターが次々に開店し、
喫茶店やスナックのテーブルの多くがインベーダーゲーム用のテーブルに変わった。
当作品は日本のシューティングゲーム始祖の一つとされる。
|
+
|
ゲーム画面とゲーム内容 |
画面の中央やや上方に縦5段、横11列の計55体のインベーダーが現れる。
インベーダーは軍団状で、隊列状態でまとまって横移動をしながら、
端にたどり着く度に一段下がり、下がり終えると進行方向を逆方向に変えて再び移動し始める。
これを繰り返す事によって、段々と下に降りてくる。
インベーダーが画面最下部のプレイヤーの位置まで降りてきたら、自陣が占領された事になり、
残機があってもゲームオーバーとなるために、それまでにインベーダーを全滅させなければならない。
自機に関しては、ビーム砲(自機)が1門、画面の下段に表示される。
ビーム砲は左右にしか動けず、弾を撃つ場合でも1発限定で、しかも自分が撃った飛翔中の弾がどこかに着弾するまでは、次の弾が撃てない。
ビーム砲の上にはいくつかトーチカ(防壁のようなもの)があり、ビーム砲を敵の攻撃から護る役割を最初は果たしているが、
トーチカはインベーダーからの攻撃を受けた場合も、またビーム砲がトーチカ下方からビームを撃った場合も、少しずつ破損してゆき、
さらには降りてきたインベーダーが触れる事でも削られてしまう。
プレイヤーはトーチカの下にまるで傘に入るようにしてインベーダーからの攻撃を避けたり、そこから出てインベーダーを攻撃したりする事になる。
なお、画面がスクロールする事は無く、インベーダーやビーム砲が画面からはみ出す事なども無い。
ゼロ距離まで引き付けた敵の攻撃は当たらない事を利用した「名古屋撃ち」というテクニックは有名。
インベーダーを撃墜した際の得点は一番上の段が30点、その下の2段が20点、
その下の2段が10点である。画面最上段にはUFOが通過するゾーンがある。
逆に敵インベーダーからの攻撃でビーム砲が被弾した場合、ミスとなりビーム砲を1門失う。
インベーダーは撃墜されて数が減るにつれ、徐々に移動速度が速くなっていく。
残り10体を切るとかなりの速度になり、しっかり狙って撃たないと弾が当たらず、
狙いが外れたと気付いても着弾するまでは次の弾が撃てず、あれよあれよという間に何段も降りてくる。
このため、「どんどん速くなる敵を正確に狙い撃つ」というプレイヤーの技術が必要となる。
ただ、インベーダーの移動速度は、右方向よりも左方向への移動の方がやや遅いため、
これを利用して、左方向へ移動中に攻撃すると弾が命中しやすい。
インベーダーが最下段に降りる前に画面内のインベーダーを全滅させるとゲームは続行され、
前の面よりも一段下にインベーダーの軍団が配置され、前の面よりも近い位置から攻撃してくる。
つまり、面が進むにつれ難度が上がるようになっているが、
9面目をクリアした時は一旦2面目の位置に戻ってそこから再び面ごとに下がり、以降8面ごとの繰り返しになる。
当初の設計ではこれがどんどん下がっていき、遂には絶対にクリアできない状況になるように設計されていたが、
プログラムの バグにより8面をクリアすると9面目に行かずに、2面目に戻るようになってしまっていた
(このバグは次回作である『スペースインベーダー パート2』から正式に仕様として採用されている)。
これにより、そこまでをミスせずにクリアできる腕があれば、理論上永久にゲームを続ける事ができるという、
永久パターン(厳密には「実力永パ *1」)に陥って、最悪1日の売り上げが百円で終わってしまう事が店側から問題視されていた。
後発のアーケードゲームで「エンディング」と言う名の強制終了が導入されるようになったのは、このためである。
人気の理由は、敵が自機を認識して攻撃してくるアルゴリズムにある。
TVゲーム黎明期だった当時、例えばレースゲームでは「真上から車が降ってくる」と揶揄されていたように、
「障害物が車の形をしているだけ」の(幅寄せ等はしない)疑似的な攻撃だった。
しかし、スペースインベーダーは、敵キャラクターがある程度自機の位置を認識し攻撃を仕掛け、更には本体と攻撃(弾)を分けた事で、
コンピュータと対戦しているという、攻防の要素が加味されたのもヒットの要因と言われている。
|
|
+
|
流行と影響 |
当時のタイトー社員の体験談なども含む。
- 流行により「インベーダーハウス」と呼ばれるゲームセンターが各地に乱立した。
- パチンコ業界はメーカーがインベーダーゲームをモチーフにした台を販売するも人気を得ず全国的に客入りが衰えるなど冬の時代を迎えた。
1980年フィーバーの登場までパチンコ業界は厳しい時代となる。
- テーブルの代わりに後述するテーブル筐体を設置した喫茶店「インベーダー喫茶」なども出現した。
- 駄菓子屋の店先、待合室などでも、10円から50円と格安なアップライト筐体による稼動があった。
- 同時期に活動を開始したイエロー・マジック・オーケストラは、ファーストアルバムで、
「Computer Game -Theme from the invader-」という曲を収録している。
当初メンバーは実機より直接録音を試みたが、最終的にシンセサイザーでプレイ中のサウンドを再現しトラックを作成した。
- 神田お茶の水では学生街という事もあってか「インヴェーダーあります」というような看板等が見られたという。
- 当時、タイトー新入社員のボーナスが100万円だったという都市伝説がある。
- 販売当初の価格は10万円だったものが最盛期には数百万円に跳ね上がっても売れていったという。
- このブームに続けとばかりに様々な会社がクローンゲームを出していた
(もちろん、タイトーからライセンスを取って出している会社もあった)。
特にニチブツが出した『ムーンベース』はあまりに似すぎていてタイトーに怒られたと言われている。
- タイトー本社は当時、平河町(砂防会館の真前)にあり、永田町と近隣であった。
そのため、インベーダーを納入するように業者から依頼された国会議員がお忍びで「5000万円で売れ!」などと談判に来たというエピソードもあった。
また、以下の話もある。
- 硬貨
- 集金袋を回収するのにライトバンでは到底間に合わず、4トントラックで回収を行っていた。
- しかしその4トントラックですら板バネサスペンションが100円玉の重みに耐えきれず、曲がってしまう事故が頻発していた。
- ちなみにこれに派生する都市伝説として、トラックから機械や硬貨を上げ下げする事から重迫病を患う者が続出したため、
- タイトーが三菱ふそうに相談してトラックの後部に装着する電動リフトを日本で最初に発明した
- (ないしはタイトーは「今後の世の中への貢献」を理由にこれについての特許などを取得していない)と言ったものがあるが、
- パワーゲートは1964年に極東開発工業が開発したものであるため、明らかに誤りである。
- 風評被害
- 「インベーダーハウス」に代表される、林立するゲームセンターは不良の温床であるとして、多くの学校で入場禁止の通達を出す措置が講じられた。
- 家庭用ゲーム機が広く普及し、ゲーセンの治安改善が追求される現在でも、
- ゲームセンターやコンピュータゲームに対する偏見は教育関係者らを中心に未だに残っている。
-
|
(以上、Wikipediaより抜粋及び一部改変)
2008年にフジテレビの番組『ゲームセンターCX』とのコラボ企画により、
一部のシステム音が「有野課長(よゐこ有野晋哉)」の声に差し替えられているバージョン『SPACE INVADERS × CX』を製作。
各基地に「GCCX」と書かれていたり、UFOが有野課長を表現した絵になっていたりと細かく変わっている。
尚ゲームのシステム自体はほぼ初代と同じである。
MUGENにおけるスペースインベーダー
|
+
|
Ironcommando氏製作 |
クリスマスツリー等でお馴染みのIroncommando氏によるもの。キャラ名及びディスプレイネームは「Invader」。
現在は氏のサイトの移転に伴い公開停止。
攻撃は原作通りビームだが、このビームは当たるとなんと 即死である。ただしビームはガード可能。
移動も原作通り動きが遅く移動間隔は約0.5秒。
また、 一発でも攻撃を喰らえばダメージ無しでも即死するかみキャラで、正に「殺るか殺られるか」を体現したキャラ。
デフォルトで原作のような動きをする AIが搭載されている。
ちなみにカラーによって外見や色が変化する。
紹介動画(公開先へのリンクは古いものなので注意)
|
|
|
+
|
オー氏製作 INVADER-UFO |
『スペースインベーダーエクストリーム2』のスプライトを利用した 神キャラ。
インベーダーを大量に召喚して戦う。カラー差は無い。
|
出場大会
*1
基本的に
ループゲームを実力でやり続けるのが「実力永パ」、バグや設定ミス等を利用するのが「永パ」と区別される。
そのため『ゲーメスト』等のハイスコア集計では、永パが発覚すると即刻打ち切りになるが、
実力永パの場合はカウンターストップするまでは集計が続けられた(
一部ゲームでは、カンストまでの時間や手数の少なさで競う事も)。
なお格ゲーでいう「
永久」は対戦相手が倒れるなり
制限時間が来れば強制終了なので別物である。
バグ昇竜?聞こえんなぁ~。そもそもハイスコア争いには影響無いし
また、エンディングこそ存在しないものの、面数を数えているゲームでは255面を超えるとバグを起こして強制終了してしまう作品も存在した
(対策をしていないと、面数が
255(1バイト)を上回った際に、
桁の繰り上がりに伴い隣のメモリを書き換えてしまう事でプログラムを破壊する「
メモリクラッシュ」が起きてしまうため。
なお電源をリセットしてプログラムを読み直せば治る。どの道強制終了だが)。
分類が難しいのが『
ドルアーガの塔』や『
魔界村』シリーズ、及び『
バブルボブル』等で、わざとエンディングを迎えない事で実力永パが可能である。
『ドルアーガ』は様々なクリア条件を満たしていないと下層階に落とされ、
『魔界村』シリーズは
ラスボス直前に武器が特定の物でないと前の面(『魔界村』なら5面)に戻され、
『バブルボブル』(厳密には裏モードの『スーパーバブルボブル』
※)に至っては「二人同時プレイでないと前の面に戻される」という
仕様のため、
エンディングの存在するゲームながらも、バグも設定ミスも使わずに永久ループが可能(広義には設定ミスと言えなくもないが)。
一応ゲーメスト等では実力永パ扱いで、カンストするまで集計が続けられていた。
こういったペナルティで前の面に戻されるものは『ドルアーガ』での表記から「ZAP」(英語における破裂音)と呼ばれている。
当然のごとく、当時のゲーセンには「ZAP禁止」と書かれた紙が貼られている事が多かった。
※
『スーパーバブルボブル』をプレイするにはスタートボタンを押す前に(コイン投入前でもOK)
裏コマンドを入力する必要があるのだが、
そもそもノーマルモードのエンディングが、このコマンドを(暗号で)表示して「続きはスーパーモードで」なので、実は裏コマンドでさえない
(解読するための暗号表も、ノーミスで20面に辿り着くと入れるボーナスステージの背景に描かれている)。
そしてスーパーモードを(二人同時プレイで)クリアする事で、やっとエンディングに辿り着ける仕様だったのだ
(クリア時に二人同時であればいいので、ラスボスを倒す直前に参加しても問題ない)。
最終更新:2024年02月15日 15:05