「勝手なことを言うな。怪獣をおびき出したのはあんた達だ!」
1971年の特撮作品『
帰ってきたウルトラマン』の傑作エピソードにして問題作とされている第33話「怪獣使いと少年」に登場する
怪獣。
別名「巨大魚怪獣」。身長48m、体重1万t。
魚型の怪獣にしては珍しく二足直立型のデザインとなっている他、水中戦のシーンが極めて少ない(というか昭和作品ではない)。
名前の由来は東アジアに分布する肉食性の大型淡水魚カムルチー、
あるいは沖縄県の屋良漏池(やらむるち)に伝わる大蛇伝説に由来したという二つの説がある。
武器は口からの赤い破壊光線。
|
+
|
原作でのムルチの詳しい説明。
なお資格無しで閲覧した者に対する人権を政府及びGUYSは保証出来ません。
|
第33話のあらすじ
偶然にも地球の怪獣ムルチを封印することに成功したメイツ星人は、そもそもは地球の測量を目的にやって来た善良な宇宙人であった。
だが、彼は地球の大気汚染の影響で衰弱し、地中に隠した自らの UFOを呼び出せなくなったため、
母星に帰れず、心優しい地球人の孤児・佐久間 良に匿われ、廃墟で共同生活を送っていた。
佐久間少年はそんなメイツ星人に代わってUFOを探すため、一人で誰にも事情を告げず河川敷を掘り返しまくっているのだが、
そういった奇行や、少年の周囲で度々起こる怪現象(=メイツ星人が虐められる少年を守るために陰から使った超能力)に地域の市民は不信や畏怖を募らせ、
やがて暴徒と化した民衆から少年を庇ってメイツ星人は惨殺されてしまう。 *1
そして彼の施した封印から解かれたムルチが地中より復活し、暴れ出す……。
同じ宇宙人であり地球人でもある主人公・郷秀樹(= ウルトラマンジャック)は最悪の事態を避けようと奮闘するが結局失敗し、
上記の経緯故、人々の悲鳴や「早く倒してくれ」という懇願に対しこの項目冒頭にもある怒りの呟き、
「勝手なことを言うな。怪獣をおびき出したのはあんた達だ!」を口にして一時は戦いを拒む。
しかし、やはり怪獣から逃げ惑う地球人を見捨てることは出来ず、郷はウルトラマンへと変身し戦闘を開始、
豪雨の中の激闘の末にスペシウム光線でムルチに止めを刺すのだった。
佐久間少年は、メイツ星人が死んだ後も穴を掘り続けた。
それを眺めていた郷と仲間たちは、少年がこの星に愛想を尽かし、地球に別れを告げようとしているのだと思わずにいられなかった……。
このエピソードは「11月の傑作群」の1つとされていて、ファンの間では特に高い評価を得ている。
また、宇宙人と疑われた少年に対して凄惨な仕打ちをする人々や正体を明かしたメイツ星人への仕打ちなど、
差別と偏見、異形の存在を恐れる人間の心に潜む恐ろしさを表現したシリーズ屈指の問題作とも言える。 *2
なお、監督と脚本はテレビ局上層部からあまりにも救いが無さすぎるもん放送すんなと激怒され、一時業界を干されました
なお、「傑作群」という呼び名のため誤解されやすいが『帰ってきたウルトラマン』は別に 社会派作品や実験作品というわけではない。
他にも特撮ヒーロー作品としてストレートな方向で面白い話は多いので、誤解なきよう。
どちらかと言うと、「11月の異色作群」が正しい表現である。ストーリーや演出的に考えて。
とはいえウルトラシリーズは巨大ヒーローを扱った作品であるのは確かだが、
同時にSFとしての側面を色濃く持つ作品でもあって、 こういうエピソードが挟まれることは少なくない。
単なるヒーロー物と捉えず、違った視線で見ると面白いのではないだろうか。
「日本人は美しい花を作る手を持ちながら、
一旦その手に刃を握るとどんな残忍極まりない行為をすることか」
後述のゾアムルチの存在もあり、よくメイツ星出身の怪獣と誤解されがちだが(当時の学年誌にもそう記載されたことがある)、
上述したようにれっきとした地球生まれの怪獣である
(ただしサブタイの「怪獣使い」に思い当たるのが他にいないので「当初はメイツ星人のペット設定だったのでは?」という説も存在する。
もっとも劇中描写を見る限り、仮にそうでも勝手にムルチが暴れてメイツ星人が止めていたとかいった状況だろうが)。
放映当時の70年代前半から現れ始めた、環境汚染によって生まれた奇形魚がモチーフなのだとか。
ついでに「メイツ星人」という名も、メイツ=mate(英)=「仲間、相棒」という皮肉ぶり。
|
+
|
メイツ星人に対する悲しい現実 |
2001年に出版された「空想科学読本」シリーズの兄弟『空想法律読本』第1巻では、
「日本国憲法3章では宇宙人に基本的人権を認めていないので、
日本にいる限りメイツ星人に生命の保障をする必要は無い。
よって、宇宙人相手ならいくら残忍にブッ殺そうが民衆も警官も無罪!」
という非情の結論で〆られていた。哀れ。
尤も、宇宙人にも基本的人権を認めると、
ウルトラマンが活躍出来なくなってしまう(宇宙人を倒すと良くて過剰防衛、最悪殺人罪に問われる)ので 仕方ないとも言える。
なお、『空想法律読本』ではメイツ星人の検証以後は、「宇宙人にも人権を適応すべきだ!」と主張した上で、
(ウルトラマン含む)宇宙人も“人間”(=外国人)扱いし、人権を適応した上で検証を行っている。
宇宙人ネタを全て「人権が無い」で片付ける様な本じゃ売れるわけないし
|
ただしメイツ星人側に全く非がないのかと言えばそんなことはなく、宇宙人の侵略が頻発していた時代に、
無断で地球に侵入して環境調査を行うのは侵略のためのスパイ行為と取られても仕方なくもある微妙な行為であり、
後述する『 ウルトラマンメビウス アンデレスホリゾント』ではメイツ星の側でも、
「地球人の同胞に対する虐殺を追求しない代わりに、こちらの無断侵入と調査についても謝罪しない」
とされており、このメイツ星人の存在自体が故郷と地球の両方でタブー扱いされているという、これはこれで酷いことが語られた
……なんというか、とことん報われない人である。
余談だが『 ウルトラセブン』に登場する アンノン星人と ペダン星人は、
「地球の観測ロケットを侵略のための偵察行為と見なして報復攻撃に来た」と言う立場が逆の話である。
いずれもそれぞれの惑星に知的生命体はいない、という地球側の誤認が生んだ誤解であったが、
こちらもこちらで軽率と言えるだろう。前者は幸いにもセブンの説得で事なきを得たが、後者は……。
更にはメビウスの防衛組織GUYSが所持する歴代防衛組織の記録「アーカイブドキュメント」では、
メイツ星人事件や ジャミラの正体に関しては一般隊員閲覧禁止の「ドキュメント フォビドゥン」に分類されており、
(ジャミラの話ではあるが)公表しようとした人物に対しては非合法手段(冤罪)を使うまでして排除している。
ここを開く際の「人権を保障出来ない」という警告は そういう意味である。
その『 ウルトラマンメビウス』では、強化型の ゾアムルチが登場している。
第32話『怪獣使いの遺産』にてメイツ星人ビオ(実は殺されたメイツ星人の息子)が連れてきた怪獣であり、
過去に密かに地球を訪れた際回収した、帰マンが倒したムルチの細胞を元に再生・改造した個体である。
ベースとなったムルチとは異なり、口から青い破壊光線を発射する。ビオの脳波によって操られており、彼の感情に応じて行動する。
ビオはメイツ星と地球との和平の使者として訪れ、ミライ(メビウス)に近付いてあくまで穏便にことを進めようとした。
だが、過剰に警戒したリュウ隊員に撃たれた *3ことで激怒、父の復讐も兼ねて円盤とゾアムルチによる破壊活動を開始。
その後、かつて殺されたメイツ星人と共に暮らしていた少年に昔会っていたという保育園の園長の説得と、
その教えを受けた子供達が見せた優しさに思い留まるが、理性では理解しても憎しみという感情自体は消せず、
メビウスに「私の憎しみを消し去ってくれ!」とゾアムルチを倒すよう懇願。
こちらも雨の中での戦いとなり、最後はメビウスのメビュームシュートを受けゾアムルチは倒された。
その後ビオは謝罪し、リュウも撃ったことを悔い改め和解。
握手を求められたことに対しては「父の遺産の咲かせた花を認めてから」と言い残したものの、
メイツ星と地球との間に、ひとまずの友好関係が結ばれた。ビオはミライとリュウに見守られ、地球を去る。
|
+
|
小説版『アンデレスホリゾント』 |
この話の脚本を手がけた朱川湊人氏が書いた小説版『ウルトラマンメビウス アンデレスホリゾント』では、
ビオの目的はもっとストレートに、
平和使節を口実に地球に侵入し、わざと挑発的な言動を繰り返して攻撃を受けることで
「地球人は和平の使者も攻撃する野蛮な人種」ということにして地球攻撃の大義名分を手に入れ、
父の復讐を果たすことだと語られている。
最後も改心などはせず、彼と似たような境遇にある地球人が自らの命を投げ出そうとした所を助け、
地球人という存在全体を見極めるためにゾアムルチを地中に封印して地球に残っている。
なお、前述した通りメイツ星ではあの事件に関しては全てタブー扱いになっており、ビオは故郷に帰ると死刑は確実らしい。
(そもそも親善大使として行ったのに戦争を誘発しようとしたのだから、タブー扱い関係なく重罪であろう)
|
ちなみに円盤を掘っていた少年は青年になっても諦めずに円盤を掘り続けており、
最終的には恐らくメイツ星に行けたと思われる……というより信じたいものである。
「彼は地球にさよならが言いたいんだ」
……と、メイツ星人について中心に語ったが、ムルチ(ゾアムルチ)からしてみれば、
せっかく生き返ったのに改造されて、更に故郷にやって来たと思ったら操られて殺されるという、
何とも不遇な生涯である。
|

『帰ってきたウルトラマン』以外では、『ウルトラマンA』の「怪獣対超獣対宇宙人」、「太陽の命エースの命」の前後編にも登場。
初代と異なり体色が銀色をしている。出現した理由などは不明
(エースらの戦闘で目を覚ましたか、妖星ゴラン接近の影響だろうか?)。
蛾超獣ドラゴリー、
幻覚宇宙人メトロン星人Jrと3匹かかりで
エースを苦しめるが、
戦いの最中にドラゴリーと正面衝突してしまい、怒ったドラゴリーに
半身を引き裂かれてしまう。
このシーンは大変グロテスクで、ファンの間で一種のネタとなっている。
|
+
|
『ウルトラマンA』に登場したムルチに関する余談 |
このシーン自体は「超獣が怪獣より強い設定を表すシーン」で、つまりムルチは 引き立て役なのだが、
実は劇中で使用された着ぐるみはイベント用に作られたもので 借り物であった上、
八つ裂きにしてしまったことにより 使用不能となってしまったため、 撮影班は大目玉を食らってしまった。
元々借り物な上に、怪獣や星人の着ぐるみを一つ作るのに相当な費用と時間が掛かるので、怒られるのは当然の結果である。
ある意味前作に負けず劣らずの(スタッフの)悲劇だろう。
また、当時カルビーが発売していたカード付きスナック菓子「テレビスナックウルトラマンエース」のカードとして、
この2代目ムルチのドラゴリーに 引き裂かれた下顎の肉片のスチール写真が何故か 「さかれたムルチ」としてカード化されている。
いくら第2次怪獣ブーム全盛期だからといってこの斜め上にハイブロウな謎すぎるチョイスが子供にウケるはずもなく
ハズレ扱いで捨てられまくった結果、今では コレクターの間ではレアアイテム化しているとか。
|
『
ウルトラマンギンガS』では
ガッツ星人ボルストがゾアムルチにモンスライブした。
本作ではボルストの怒りに反応したのか、チブルサーキットによって強化されていたためなのか異常に強く、
ウルトラマンギンガ、ウルトラマンビクトリー、
メトロン星人ジェイスの三人を圧倒するが
(この戦闘シーンは、初代メトロン星人戦と初代ムルチ戦の双方をオマージュしたものとなっている)、
アイドルになる夢を叶えた前作レギュラーキャラ、久野千草が「ウルトラマンギンガの歌」を歌う姿と、
ジェイスの
ヲタ芸に気を取られている隙に両ウルトラマンの必殺技を受けて倒された。
ソーシャルゲーム『ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ』でもゾアムルチが参戦している。
固有スキル「増大する敵意」は味方のHPが0になったとき攻撃力を中アップさせる効果を持つ。
更に覚醒スキルの解放により、スキル効果を攻撃力を超アップ、HPと防御力を大アップに強化できる。
このスキルと
復活、
蘇生スキルを持った怪獣を併用すれば仲間が死ぬ度にステータスが向上し、
最終的に戦闘力(ステータス合計値)が三倍以上にパワーアップした最強怪獣になる事が可能。
『ギンガS』での異常な強さは、このスキルの効果だったのかもしれない
|
+
|
ホラ! こいつを火で焼くとうまいんだぜ! |
漫画『ウルトラマン STORY 0』では、ジャックの流れ着いた地表の殆どが海に覆われた星(地球ではない)に生息していた。
ただし怪獣ではなく ただの魚で、ジャックと交流した水棲人間達(『 ウルトラマン』の ラゴンが元ネタ)の主食としての登場であった。
ついでに タッコングにも食われていた(上の画像の直後)。
「フン! 焼いたムルチを食ったことないくせに!」
「なんじゃとォ!!」
原作との辻褄を合わせるなら、「異星人によって食料として地球に持ち込まれ、その後野生化して怪獣に変異した」
……と、その辺りが妥当な解釈だろうか。
|
MUGENにおけるムルチ
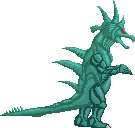

zektard氏による手描きキャラが2009年7月29日に公開開始。
超必殺技ではゾアムルチに変身して口から光線を発射する。
勝利ポーズは少々グロ注意……だがファン必見である。
また改変自由のため、
2代目ゼットンや
ガタノゾーアを製作したmuu氏が『Fighting Evolution』シリーズ風に改変し、
AIを搭載したものを公開しており、新規モーションも数枚追加されている。
|
+
|
zektard氏製作 |
ニコニコでは後述の改変版をよく見かけるが、防御力などの各能力はこちらの方が強力。
また、ゾアムルチに変身する超必殺技には暗転演出があるので、使用前に相手に動かれて超必が当たらないということも少ない。
2013年2月8日の更新によりスプライトほぼ全てが一新され、より実写的なスプライトに差し替えられた。
長らくAIが未搭載であったが、2022年7月にIX氏により外部AIが公開された。
キャラのステータスを低下させたものも同梱されており、相手によって使い分けるといいだろう。
|
|
+
|
muu氏製作 ムルチFE |
上記のムルチを改変したもの。
AIが搭載されいてよく動き、能力も調整されてバランスがいいので、動画使用に適している。
ゾアムルチに変身する技には暗転が無いので回避も可能だが、AI戦で避けられることは稀だろう。
口からの光線は威力が高く2足歩行の怪獣相手にはかなり有効だが、相手が背の低い四足怪獣だと当たらないこともある。
また「怒りの同調」という新技が搭載されており、使うと体が緑色になり、画面内のヘルパーの数に応じて攻撃力が増加する。
怪獣の中での強さのランクは同作者のアレンジ版 ガギや ガボラと同じ位で、戦わせると中々いい勝負をしてくれる。
|
また2023年のエイプリルフールには、
dummyの改変としてドラゴリーに裂かれた状態の画像を使用した「さかれたムルチ」がカーベィ氏によって公開された。
出場大会
【zektard氏製】
【ムルチFE】
出演ストーリー
プレイヤー操作
*1
当初は
竹槍で殺害するシーンだったのだが、流石にヤバ過ぎると判断されたのか射殺に変更されている。
……それを
弱者を守るべき存在であるはずの警官がやっちゃう分、ヤバさはどっこいな気もするが。
*2
ちなみに、同じく「11月の傑作群」に数えられる第31話「悪魔と天使の間に…」は、
ウルトラマンジャックの抹殺を画策するゼラン星人が聾唖の少年に変装して地球人の同情を集め、
一方の郷秀樹はゼラン星人からテレパシーで殺害予告を受けるものの証拠がないために手出し出来ず苦戦を強いられるという、
「怪獣使いと少年」とは全く対照的なエピソードである。
併せて見てみると、宇宙人と接することの難しさやウルトラマンの苦労が浮かび上がってくる両話でもある。
あと、両話の本筋には関係しないが、メイツ星人のマスクはゼラン星人のマスクを改造したものらしい。
*3
とは言え、この話の直前に地球を狙う圧倒的な力を持つ存在がいることが明らかになっており、
実際に大量の円盤群がメビウス抹殺を目的とする
円盤生物と共に地球に侵入した事件が起きた直後だったため、
リュウ隊員だけを責める訳にはいかないのも事実であるのだが。
小説版『ウルトラマンメビウス アンデレスホリゾント』では前述の経緯もあり、
保育園の子供に近寄って「子供を襲うのでは?」と疑心暗鬼を煽り、自身を撃たせることでゾアムルチを暴れさせる大義名分を作るという、
ビオの意図的な策略として描写されている。
最終更新:2024年03月03日 08:29

