登録日:2010/06/27 Sun 00:01:15
更新日:2025/08/26 Tue 19:38:09
所要時間:約 86 分で読めます
________
▽▽▽▽▽▽▽▽
大海の王者
△△△△△△△△
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
『
モンスターハンター』シリーズに登場するモンスターの一種。
初登場は『モンスターハンター3(トライ)』(MH3)。
◆もくじ
◆概要
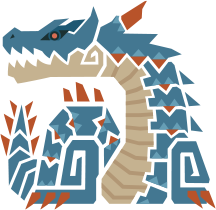
種族:
海竜種
分類:海竜目 海竜亜目 電殻竜下目 ラギアクルス科
別名:
海竜
危険度:☆5
青い鱗と皮に身を包む大型の水棲モンスター。
ワニを思わせる顔立ちと身体、そして長大なヒレ状の尻尾をもつ。
四肢は比較的短いが、前脚には長く鋭い鉤爪がある。ヒレに進化する途上であるため、これを使って攻撃してくることはほとんど無いが、狩りの際には使用する姿も確認されている。一方で後肢は完全なヒレ状に進化しているが、強靭な筋力を有しており、水中移動の補助の役割をもつ。
頭には立派な角が2本、後方に向かって生えている。泳ぐ姿を遠目で見ると、さながら東洋の龍のようである。
水中を棲家とする生物の中でもとりわけ大型の体躯を持ち、他に追随を許さない水中機動力と、他の大型モンスターにも積極的に襲いかかる獰猛性から、水中における生息域では生態系の頂点としての地位を獲得している。
その実力の高さ、危険性の高さを総合し、『大海の王者』『大洋の支配者』などと称されており、種全体を代表して『海竜』と呼ばれている。
『大海の王者』を銘打つだけあって遊泳力は非常に優れている。
遊泳の際の推進力は、ヒレ状の後肢と長い尻尾を用いて生み出しており、その巨体からは想像もつかない速度で泳ぐことが可能。
また、頭部の形状は進行の際の水圧を軽減できるように先鋭化しており、更に左右に突き出した部分は進行方向の微妙な調整をするのに役立っている。
これらを駆使し、水中では圧倒的な高速機動を実現している。その遊泳力から繰り出される突進やタックルの威力は、一撃で岩や船を容易く粉砕するほど。
それこそ泳いだだけで大抵の障害を簡単に押し流してしまうほどの水流を発生させるため、ラギアクルスが大きく周回するように泳いだ際には海上からも見えるほどの大渦が発生する。
このことから、『渦潮を起こす者』との異名を取ることもある。
そして、なんといってもラギアクルス最大の特徴は、水中を生息域としていながら大規模な放電行動が行えるという点である。
ラギアクルスは体表付近の筋肉に「発電細胞」を持ち、小刻みに筋肉収縮を行う事で細胞を活性化させて発電、「背電殻」と呼ばれる背中の水晶状の器官に蓄電していく。背電殻には発電細胞と対になる「蓄電細胞」が存在しており、電力の蓄電と放出を可能にしている。
背電殼はある程度蓄電されると、もともと鈍い赤だった色が青白く輝く。最大限まで蓄電された際の光は船上からも確認できるらしい。
そしてピークに達した電気を一気に解放した際の電力は、落雷に相当するレベルのエネルギーをもっており、ラギアクルス周辺の海水を瞬時に沸き上がらせる。
この時の光景は、海上からはまるで雷が海から天へ昇っていくかのように見えるという。
その雷光が見えることは船乗りや漁師達にとって凶事である他無く、しばしば『海凶』などと称され、恐れられる。
また体内で発電した電気は少しずつ消費していくことも可能で、前述した突進やタックルなどの直接攻撃の際には、まるで雷を身に纏うかのように放電しながら行うこともある。
更に口内の粘液に通電させ、その粘液を吐き出すことで、さながら飛竜種の「ブレス」のように雷の塊を吐き出すこともできる。
このように雷をも自由自在に操るかのような能力から、『青藍の雷公』の異名ももつ。
狩りや戦闘の際には、優れた遊泳力から獲物の周りに大渦を作り出して閉じ込め、そして自身から作り出した電気を放出して仕留める戦法をとる。
「ラギアクルス」という名称は「雷光」を意味するラギアと、「大渦」を意味するクルス、という単語から付けたとされており、『雷光を放つ大渦』の意味をもつ。
ほぼ完全な水棲生物として進化しているが、魚類とは異なり肺呼吸である。
が、一息で半日は余裕を持って潜水できるほどの肺活量を誇る。また喉の骨には水中で口を開いても水が流れ込まないよう、蓋のような構造が付いている模様。
基本水中で生活するが、水中でめぼしい獲物が見つからない場合、陸に上がって獲物を探す姿も目撃されている。
水中ほどではないものの陸上でもある程度の行動は可能で、短時間ならば四肢を用いて腹這いの姿勢で動き、それなりの速度で獲物を追いかけることができる。
場合によっては
『空の王者』と名高い
火竜リオレウスと対峙し、地上の獲物の取り合いをする姿も確認されている。
また、発電と放電は非常に強力である一方、激しい筋肉運動を要するため使用するたびに極端に疲弊してしまう弱点がある。疲労した際に休息のため陸上に上がる姿もしばしば確認されている。
「海竜」とは呼ばれているものの、自身のサイズに見合う水深ならば淡水でも生息可能であるらしく、大海原だけでなく水没林といった大河にも出現することもある。
ラギアクルス亜種

別名:
白海竜
危険度:☆5
美しい白色の甲殻に身を包んだラギアクルスの亜種。
赤い色の背電殻が差し色になっている通常種に対し、こちらは青色なのが特徴的。
目撃例が非常に少なく、滅多にお目にかかれない幻の存在。
体格は通常種と比べてそれほど差はないが、性格は通常種と同様、若しくはそれに輪をかけて獰猛。
青色の背電殻は、導電率が非常に高く、通常種以上に膨大な電力を溜め込むことができる。
そこから放出されるエネルギー量は絶大で、劇中ではあの
雷狼竜ジンオウガの放電攻撃すら上回るとされるほど。
さらにこの背電殻は導電率の高さ故に冷却すら不要であるらしく、短いスパンでの再使用が可能。したがって本種は通常種以上に積極的に蓄電・放電行動を取る傾向にある。
本種の甲殻にはこのように強力な電力から身を守るため、高い絶縁性と低い誘電損失をもつ「石英」が多く含まれている。
本種が白い体色を持っているのはこのため。
そしてなにより、本種最大の特徴は、水棲生物として進化したラギアクルスでありながら陸上にも高い適応を遂げている点である。
生活のほとんどを水中で過ごす通常種に対し、こちらは積極的に水から出て陸地を歩き回る傾向が強く、むしろ陸の方が快適と言わんばかりに陸地に上がっての活動を好む。
逆に潜水する際は、陸上でめぼしい獲物が得られなくなった時か、エアードームに作った巣に逃げ込む時程度。
陸上での機動力はかなりのものであり、腹滑りによる猛烈な速度の突進や、巨体を生かしたタックルなど、素早く獲物を追い詰めることが可能。
それに加えて前述した強力な放電攻撃をもつことから、下手な陸上生物を遥かに凌駕する危険度を誇る。
これほど陸上に特化した動きを取るからには、通常種と比べて水中は苦手かと思いきや決してそんなこともなく、遊泳力はむしろ通常種以上に高い水準にあるという。
水陸ともに隙がなく、圧倒的な強さを誇ることから、劇中では『双界の覇者』とも謳われる。
ゲーム内のストーリーでは、MH3、そしてMH3Gの舞台である「モガの村」の村長を
ハンター廃業に追いやった張本人として登場する。
かつて本種と相見えた村長は、得意の
水中戦で本種を瀕死にまで追い詰めたそうであるが、上陸した本種が放った大放電により手痛い傷を貰い、敗北してしまったとのこと。
このことからハンター業を引退した村長にとっては、ラギアクルス亜種は因縁の存在である。
ラギアクルス希少種

別名:
冥海竜
危険度:☆6
ギルドが保管する古文書にのみその存在が確認され、遥か深海に生息するとされるラギアクルスの希少種。
曰く、『海神の化身』と称されており、劇中では『冥府の王』、『冥帝』とも謳われる。
◆テーマ曲
MH3から登場するフィールド「孤島」の汎用
BGM。
ド派手なイントロから始まり、最後まで激しい曲調が続く。さらに曲の中盤から終盤にかけて、MH3のテーマ曲「生命ある者へ」のフレーズが使われていることでも有名。
広大な大海原での戦闘をイメージした明るく力強い
オーケストラによる演奏が特徴的で、海中で激しく暴れ回るラギアクルスの姿と非常に良くマッチしている。
しかし水中戦だけでなく陸地での戦いで流れていても全く違和感がない。
「モンハンの曲は壮大な感じがする」というイメージを持つ人は多いようであるが、まさしくそんなインパクトを与えてくる。
モンスターハンターの長い歴史で見ても屈指の名曲と評価されるほど人気の高い曲である。
ちなみにラギアクルスと言えば、
リオレウスと対をなす存在としてデザインされたモンスターとしても知られているが、
この曲もリオレウスのテーマ曲
「咆哮」を意識して構成されたことが明かされている。
また、テーマとなる曲ではあるが、ゲーム内ではあくまで汎用BGMとして扱われている。
つまり彼もリオレウス同様、
看板モンスターの身でありながら専用曲として流れることはない。
水没林で出現すればチャナガブルのテーマ曲が流れる
リオレウスをリスペクトしたからだろうか…
リオレウス共々、せっかくの看板モンスターなんだから専用曲として流してもいいのでは…と言う声も少なくない
『海と陸の共震/ラギアクルス(Wilds version)』
初登場したMH3より16年。
看板モンスターでありながら、ずっと専用曲をもらえなかったラギアクルスだったが、MHWildsにてめでたく
名実共に「ラギアクルスの専用曲」として流れることになった。
今作では、何かと因縁の深いリオレウスがやっと専用曲を与えられるというサプライズを受けており、DLCにてラギアクルスの復活が予告された際は、早々に期待する声も多かった。
そして、そんな多くの期待の声を裏切ることなく、この曲は懐かしのMH3のまま、いやそれ以上の豪華仕様にアレンジされて帰ってきた。
とは言えこの曲自体、MH3の時点でかなり完成度が高いものだったためか、それほど大胆なアレンジはされていない。
オーケストラの迫力は相変わず見事なものの、全体的な激しさは意外にもやや控えめ。原曲と違いストリングスが主旋律となっているため、勢いがあったあちらと比べると優雅で気品すら感じる。
原曲は雄大な大海原である『孤島』をテーマとしていたが、こちらは色とりどりの植物に豊富な水源が美しい「豊穣期」の『緋の森』に雰囲気を合わせたのかもしれない。
実際にこの曲をバックにすると、綺麗に透き通った湖での激しい水中戦が見事に映える。
問題は水中戦が激しすぎてのんびり聴いてるヒマがない点だが
極め付けはご存じMH3のメインテーマ、「生命ある者へ」のフレーズ。
もとより一部分に少し加えられていたのだが、本バージョンはクライマックスにほぼ原曲がたっぷり盛り込まれている。こちらも主旋律は今回のテーマに合わせてストリングス。
古参のハンターなら周知の通りだが、アレンジ曲にそのモンスターが初登場した作品のメインテーマが流れる演出は、言わばその作品の代表者であることを示している。
MH3を代表する看板モンスターのテーマとして、かなりの特別待遇をされているわけである。
余談だが、過去作のMHW:Iにて
煌黒龍アルバトリオンが再登場した際は、こちらもテーマ曲にがっつりと盛り込まれていた。
これもMH3からの参戦者であることを強く主張するためだろう。
あとアイツも
先輩であるリオレウスと同じく、テーマ曲を持ちながら何故かずっと専用曲として与えられてこなかった彼だが、ここにきてようやく報われることに。
初期の彼を知っているハンターほど目頭が熱くなるような演出である。
『緋の森』の汎用BGMや
頂点捕食者のテーマは偉大ながら不気味な雰囲気が強い分、こちらは強さの中に、さながら
夏の海のような爽やかさすら感じるだろう。
淡水だけど
ちなみに、今作ではラギアクルスの狩猟笛、「ラギアホーン」が続投している。
MH3Gにて初登場し、MHX系列にも登場したこの武器だが、演奏してもこの曲ではなく、海を思わせる効果音のようなものしか流れていなかったが、今作にてしっかり採用されている。
しかも戦闘時のものとは毛色が異なるオーケストラ仕様。これはこれで聴き応えのある音色である。
今作のラギア笛はかなり強化されているのも追い風
また、今作では一度でもラギアクルスと相対していると、キャンプにてこの曲を流すことも可能。
ラギアクルスが好きなハンターは是非選曲しよう。
◆劇中での活躍
MH3のメインモンスターとして登場。のちのMH3Gを含め、本編のストーリーに深く関わる。
海の上に位置し、漁業を生業とするモガの村にとって、ラギアクルスの存在はある意味では身近な存在であり、絶対に刃向かってはならない自然の脅威として恐れられていた。
モガの村人たちは彼の縄張りにはなるべく近寄らず、刺激しないように立ち回るなど、上手く共存して生活していた。
しかし、最近になってモガの村に原因不明の大地震が頻発するという事件が発生。
同時期にラギアクルスが自身の縄張りから外れてモガの村周辺の海域にまで現れ、猟船を襲い始めるようになる。
このままでは地震で村が沈むばかりか、その前にラギアクルスに資源を食い尽くされてしまう。
そこで、モガの人々は
近海に現れた
ラギアクルスの狩猟と
海の底から
発生する地震の原因解明という2つの問題のためにギルドからハンターを派遣。
我らがハンターはモガの村を取り巻く2つの問題を解決し、まずは手近に存在するラギアクルスを打倒するため、奮闘する
…というのがMH3のストーリーである。
さて、モガの村に訪れたハンターであるが、モガの村では他の村と毛色が異なり、水中戦という技術を用いてモンスターと戦う技術を持つことが判明。
モガの村長は「まずは村の風習と、文化に馴染んでほしい」とのことから、簡単なクエストを依頼する。
ハンターは村長から水中戦の手解きを学んでいくのである。
その一環として、こんなクエストを依頼される。
| 村長 |
クエストLV:★ |
| 採取クエスト |
| 美味なるキモを求めて |
|
| 目的地 |
成功条件 |
| 孤島<昼> |
モンスターのキモ3個の納品 |
| 契約金 |
報酬金 |
| 100z |
800z |
| 制限時間 |
特殊条件 |
| 50分 |
なし |
|
| 依頼主 |
領主館の料理長 |
次の満月の日に、我が主人のお屋敷
で晩餐会が開催されるのです。
高貴な方々のために最高のお料理
でおもてなしせねばなりません。
その為にもエピオスから取れる
モンスターのキモを、一刻も早く
手に入れて頂きたい! |
エピオスとは、水中に生息する大人しい草食竜。
水中での狩りの練習にはまさにうってつけと早速海へ飛び込んでいくハンターであるが…
海を泳ぐエピオスに、信じがたい速度で襲いかかる巨大な影。
エピオスを仕留めた青い影は、赤い眼光を走らせながら、獲物に食らいつく…
…何を隠そうこのクエスト、海竜ラギアクルスとの初邂逅となるクエストだったのである。
しかもこのクエスト、「狩猟環境安定」としっかり書かれている。安心し切っていたところへとんだ災難である。
リオレウスの卵運搬クエストから始まり、最早シリーズ恒例となった、いわゆる「
トラウマクエスト」の一つ。
シリーズを体験してきた古参のハンターなら
あぁ…となったところだろうが、
初めてのモンハンだった新参のハンターにとっては、モガの村の看板娘のアイシャの狼狽ぶりも相まって、
本気でちびりそうになるほど恐ろしい演出だったのは間違いない。
アイシャの警告通り、ジャギィ程度に苦戦している今のハンターがラギアクルスと戦うなど無謀にも程があるため、
ラギアクルスのいないエリアに落ち着いて退避し、エピオスを迅速に狩ってキモを採取することになる。
もしちんたらやってラギアクルスに見つかろうものなら…
が、中には恐れずやってやろうじゃんとばかりに息巻いて挑んだハンターもいたようである。
しかしこのクエストに出現するラギアクルスは今後もストーリーに関わり続けていくという設定となっているため、残念ながら絶対に討伐も捕獲も出来ないようになっている。
大人しくキモだけ採取して村に帰ろう。
散々な目にあったハンターだったが、今すぐ再び挑むにはラギアクルスはあまりにも強敵。
とりあえずは目の前の依頼をこなしていき、打倒ラギアクルスを目指して腕を磨いていくことになる。
着実に力をつけていくハンターに、さらにとある依頼にて奇面族のチャチャが仲間として加わる。
仲間と共に目覚ましい活躍を見せるハンターだったが、やがてとうとう目当ての事態が舞い込んでくる。
| 村長 |
クエストLV:★★★★ |
| 撃退クエスト |
| 海竜ラギアクルスに挑め! |
|
| 目的地 |
成功条件 |
| 孤島<昼> |
ラギアクルス1頭の撃退 |
| 契約金 |
報酬金 |
| 200z |
2100z |
| 制限時間 |
特殊条件 |
| 50分 |
なし |
|
| 依頼主 |
モガの村の村長 |
うんむ。これほど早く、この日が
来ようとは。お前さんの実力には
感嘆するばかりだ。
ラギアクルスはまさしく海の王。
これまでの相手とはケタが違う。
倒すことはできなくとも、せめて
撃退に持ち込めれば…。 |
ラギアクルスが再びモガの村周辺に姿を現すことになる。
とはいえこの時点でもラギアクルスはまだまだ強敵。倒すというよりは、海へ追い返すことがメインとなる。
初めて遭遇した時こそ半泣きで逃げることしかできなかったハンターだが、今は昔とは比べ物にならないほど力もつき、装備も整った。頼れる仲間もいる。
ハンターは上陸していたラギアクルスに挑み、死力を尽くし、どうにかこれを海へ追い返すことに成功する。
傷を負い逃走したラギアクルスだったが、どうやら彼は休息のため陸地に上がっていた真っ最中だったらしく、全く本腰の状態ではなかったことが発覚する。
次こそはと決意を新たにするハンターだったが、その時は意外にも早く訪れた。
| 村長 |
クエストLV:★★★★★ |
| 狩猟クエスト |
| ラギアクルスを仕留めろ! |
|
| 目的地 |
成功条件 |
| 孤島<昼> |
ラギアクルス1頭の狩猟 |
| 契約金 |
報酬金 |
| 410z |
4500z |
| 制限時間 |
特殊条件 |
| 50分 |
なし |
|
| 依頼主 |
モガの村の村長 |
今こそ、雌雄を決する時だ…!
大海の王ラギアクルスと、数々の
モンスターを制した一流の狩人。
その強さは、誰よりも互いが一番
よく知っていよう。さぁ、準備は
よいか。全ての力と技、誇りを
懸けた極限の勝負に挑むのだ! |
みたびモガの村周辺の海域に現れたラギアクルス。
さらにその個体は、ハンターに手傷を負わされたことから怒りに染まっており、ハンターを「好敵手」と認め、まっすぐモガの村を目指しているという。
今まで生態系の頂点に君臨していた身として、ここまで追い詰められたことは彼にとっても初めてのことだったのだろう。今こそ屈辱を晴らさんとばかりに復讐しに来たのである。
受けて立つと出陣するハンター。
しかし前回とは違い、今回は相手のホームグラウンドたる水中での戦い。本気のラギアクルス相手に、水中戦に慣れていないハンターほど予想以上の大苦戦を強いられることになる。
しかし今までの体験を生かし、あらゆる技術を駆使し、最後に死闘を制したのは、ハンターであった。
モガの村の物流や漁業を妨害する元凶をついに仕留めたのである。
喜び勇んでラギアクルス討伐の報告のため村へ戻ったハンターだったが…
危機はまだ終わらなかった。
モガの村の存亡に関わる地震の発生理由に、
ラギアクルスは全く無関係だったことがハンターによって判明。
というかここまで書いた通り主人公ハンターに依頼した時点のゲーム内テキストでは
モガの村長は「ラギアクルスの出現」と「地震」は近い時期に(同時に、ではない)連続して発生しただけの別の問題と認識していたのだがいつの間にかラギアクルスが地震の原因でそれを倒せば全て解決すると思い込んでしまったらしい。
後発のモンハン3Gでは大人の事情で「地震」を「地鳴り」に変更しているがそれ以外のテキストは変わっていない。そして3Gの追加ストーリーで「若い頃の村長はラギアクルスと何度も戦っており、原種も亜種も巨大な地震を起こす力はないとわかっているはず」という設定も付与された。
仕方なく村長はギルドの手を借り、改めて地震の原因を探ることになる。
そして調査の結果、それは
生物の規範を超えた存在によるものだったことが判明するのだが…
それはまた別のお話。
…つまり、MH3のストーリーにおけるラギアクルスは、どっちみち村のために倒さねばならないのは確かだが地震については冤罪である。
この事がきっかけでMH3をプレイした一部の人からは「地震とかマジかよラギアクルス最低だな」「おのれ大地震!ラギアクルスを…潰す!」などなど、冤罪ネタで散々茶化されるハメになってしまった。
とはいえそもそもの話、モガの村周辺には姿を見せなかったラギアクルスがなぜ出没するようになったのかと言えば、その「真の元凶」が現れて気が立っていたということもある。
繰り返すが地震とは関係ないといっても村の生活に欠かせない猟船を問答無用でぶっ壊しており、決して人間と共生できるようなモンスターでもなく、地震の誤認がなくても最初から村としては討伐依頼が正式に発令されていた。
それに自らを脅かす力と意思を持つ存在がいることが分かっていながら、決着をつけるためにわざわざ戻ってきたのはラギアクルス自身である。
ここは彼の覚悟に全力で応えるのが礼儀ではなかろうか。
◆登場作品
【MH3/MH3G】
水中戦という全く新しいプレイスタイルを提げた作品の看板モンスター…というだけあり、まさに
水棲モンスターの頂点ともいえるほど、水中での彼は凶悪の一言に尽きる。
ラギアクルスとの戦闘の前には
水獣ロアルドロス、
灯魚竜チャナガブルといった水棲モンスターとも戦うことになるが、本種の戦闘力はそれとは比べ物にならない。
あくまで「水中戦メイン」がコンセプトのモンスターであるため、戦闘のほとんどを水中で行うことになる。イメージとしては、ロアルドロスが陸上7割で水中3割、チャナガブルは陸上5割で水中5割、そしてラギアクルスは陸上3割で水中7割ぐらいの比重になる。
全く陸上に上がらないことはないが、早い段階から水中での操作に慣れておくことをお勧めする。
基本的には
ロアルドロスの行動をベースに、あらゆる動作が高速で行われることになる。特に突進のスピードは初見で目を疑うこと間違いなしである。
しかもロアルドロスの倍以上もあろうかといえる程巨大な体躯が繰り出すものだから、あらゆる攻撃動作の範囲がとても広い。
怒り状態になると動きがさらに早くなるばかりか、追加行動も増えてくるため、ますます手がつけられなくなる。
ガードできない武器種は回避のタイミングに苦労することになるが、そこは陸上ではできない水中での利点、つまり3次元の動きを利用すれば上手く立ち回ることができる。
それぞれの攻撃は上下、左右の判定が緩くなっている部分があるため、この攻撃の時は上下に、この攻撃は横に…といった具合に、相手の動きをよく理解する事が重要になってくる。
そしてやはり、なんといっても重要なのは放電攻撃だろう。
ラギアクルスは戦闘の際、
発電して背電殻に蓄電→
蓄電した電気を消費して攻撃→
消費した分を再度発電して蓄電→
蓄電量が2以上の状態で、しばらくすると大技「大放電」を繰り出す→
蓄電量が0に戻り、再度発電…→
という行動を繰り返しながら戦う。
蓄電されると、あらゆる直接行動に電気が伴うようになるのが特徴。
単純に攻撃に雷属性が付与されるだけでなく、攻撃範囲が広くなるため厄介。
蓄電されているときは背電殻が青白く輝いているためわかりやすい。
一回の発電行動で蓄電できる電気量を仮に2とすると、発電行動は連発しても2回まで。つまり、最大蓄電量は4までとなっている模様。
電気を伴った攻撃(雷ブレスを除く)を繰り出す度に蓄電量を1消費していくシステムで、0になると輝いていた背電殻は元の赤色に戻り、電気が纏えなくなる。
そして、蓄電量が2以上の状態でラギアクルスがおもむろに身をかがめ始めた時は要注意。
雄叫びと同時に、蓄電した電気を一気に消費、周囲の水が煮立つほどの電気を放電し、非常に広い範囲を吹き飛ばす。
無論、食らえば大ダメージ、下手な雷耐性なら即死もありうる。
蓄電していた電気量が多いほど威力、攻撃範囲はパワーアップしていくため、それこそ最大の4まで蓄電された状態から繰り出された大放電の攻撃性能は凄まじい。
場合によっては大放電までいかず、ガンガン電力を消費することもあり、結局最後まで大放電を出さずに倒されてまうということもあったりする。
…が、逆に発電行動を連発していきなり大放電をぶっ放してくることもある。
こればかりはラギアクルスの機嫌次第である。
帯電攻撃を貰い雷属性やられに陥り、気絶値が高くなったところへ矢継ぎ早に攻撃を繰り出されて気絶、そして大技を喰らい何もできず1乙…なんてことになることは珍しくない。
気絶耐性のスキルをつけると幾分か安心できる。そうでなければせめて雷耐性を上げて挑みたい。
なお、背電殻の部位破壊が成功すれば蓄電能力に支障をきたすようになる。
つまり一切蓄電できなくなる…というわけではない。
ただし蓄電量が1以上は溜まらなくなるため、必然的に大放電を封印することができる。
大きな不安要素の一つが消えるので是非とも狙いたいところだが、耐久値が物凄く高い点には注意。狙いにくい背中にあるため、無理して狙おうとするとかえって狩猟時間が長くなる場合もある。自身の腕と相談しよう。
電気ばかりに目が行きがちだが、それ以外にも
水属性やられにしてくる攻撃もある。
ただでさえ機動力の落ちる水中でスタミナまで持っていかれたら本当にどうしようもないため、雷対策のためにもウチケシの実は持参しておきたい。
動きの節々に水流が発生するため、動きを止められる場合もしばしばある。水流無効スキルもあると幾分かは楽になるだろう。
以上がラギアクルスの大まかな行動になるが、やはり他の水棲モンスターとはケタが違うと称される通り、かなりの強敵である。慣れるまでは辛い戦いを続けることになるだろう。
…しかし、これはあくまで水中戦でのラギアクルス。なら地上ではどんなものかと言われれば…
ホントもうびっくりするくらい可愛らしい存在に成り下がる。
というのもラギアクルスは水中行動の多彩さに反して、地上行動のレパートリーがものすごく少なく、目立って危険な行動が全くないのだ。
ロアルドロスですら広い攻撃範囲をもつ横転攻撃があるというのに、ラギアクルスにはそういった警戒すべき攻撃がない。発電行動すらできない。
そのため陸揚げされたラギアクルスはロアルドロスにすら劣ると言われている(あくまでゲームの敵としての評価)。
疲弊すると陸で休息を取ろうとするため、どうしても水中のラギアクルスが苦手だというハンターは、水中では一撃離脱を徹底して、疲労状態の時をメインに攻撃することを意識して立ち回ってみてもいいかもしれない。
しかしあくまで水中戦メインのモンスターであるため、時間がかかることは覚悟すること。
…とここまでは通常種の話。
相手がMH3Gに登場する亜種となれば、こうはいかない。
「陸上に特化した」という設定通り、陸上では本当にラギアクルスかと言いたくなるぐらいアグレッシブに動きまくる。
全体的に鈍かった通常種に対して、こちらはとにかく機敏。まるで水中にいるが如く矢継ぎ早に攻撃を繰り出してくる。
特に腹這い突進やタックルなど、一部の攻撃はホーミング性能がズバ抜けて高くなっているため、非常に回避し辛い。
更にそれに加え、通常種が出来なかった蓄電行動もこちらは何の問題もなく可能。
頻繁に蓄電し、雷撃を繰り出そうとしてくる。
雷撃の規模は通常種とはもはや比べ物にならないレベルに強化されており、地面に着弾すると広範囲を吹き飛ばすかのように放電が拡散するブレスを吐き出してくる。
威力の方は気絶を通り越してそのまま致命傷になるレベルに強化されている。
帯電攻撃ももちろん完備しており、前述したただでさえ避けにくい直接攻撃の範囲がさらに広がる。
地上大放電の威力のほどは…最早言うまでもないだろう。
ちなみに、水中での行動は通常種の据え置きである。水中に追い込んだとしても油断できない。
尤も、本種はむしろ水中に潜る事が珍しいレベルで陸戦に傾倒しているため、そんな機会はそうそうないかもしれないが。
総じて、遠近共に明確な弱点のない強力なモンスターに仕上がっている。
たかだか通常種が陸上で動けるようになった程度だろうぐらいの感覚で挑めば確実に痛い目に遭う。
全体的に痛い、早い、広いの3拍子が揃った攻撃を連発しまくるため、回避性能スキルを積んでいたとしても、その圧倒的な攻撃範囲の広さゆえに躱し切れないと言う事態が発生する。
ガードできる武器種ならともかくとして、できないものとの相性は非常に悪い。
通常種もいろんな意味で武器を選ぶ相手ではあるが、こちらもこちらで得物を選ぶ相手である。
とはいえ、圧倒的不利な水中戦での戦いを強要する通常種に比べ、亜種はこちらにとっても不利な要素は少ない陸戦主体なため、やはり人によっては通常種よりも戦いやすいと言う声もあったりする。
他の水棲モンスター同様、水中にいる時は(非怒り状態時に限り)音爆弾が有効になるが、他と違い大きく体勢を崩したりせず、軽く怯んで落とし物をする程度。
が、攻撃を中断させる事ができるため、行動をやめさせたい時などにはある程度有効。
ロアルドロス同様、こちらを発見していない状態の時、水中エリアの定点でとぐろをまいて休憩する。寝ているわけではないので目が開いている。
この休憩だが、何故か瀕死状態の休眠よりもスタミナと体力回復量が大きいため、エリア移動されてもたついているとどんどん回復される恐れがあるので注意。
前述した通り、ラギアクルスは淡水でも生活可能で、水没林にも出没する。
それはいいとして、どうしたことか彼の登場するクエストでは舞台が海となる孤島よりも、水没林であることの方が妙に多い。
下位クエストでは孤島なのだが、上位からG級ともなるとほぼほぼ水没林である。「海の」王者では無かったのか。
いくら水深があるとは言え、川よりも海の方が広いし、獲物も多そうだし、電気も扱うんなら淡水よりも海水の方が通りが良さそうなものだが…
ちなみにラギアクルスと水没林の相性は悪い意味ですこぶる良いことで有名。
水没林の水中エリアは一部を除いてどこも濁っており視界が悪く、なおかつ海と違ってとにかく狭い。
そこへ苦もなく動き回る巨体のラギアクルスはまさにベストマッチなモンスターであり、ただでさえ水中戦が苦手なハンターは悲鳴を上げることになる。
このことから、水没林の出没率が高いことも相まって、一部のハンターからは「水没林の王者」と皮肉混じりに言われてしまうこともあったりする。
【MH4/MH4G】
ラギアクルスと言えば水中戦。
したがって水中戦が実装されていない作品には必然的に登場することができず、MH4シリーズには参戦を逃してしまった。
一応ロアルドロスは水中戦がないMHP3に顔を出していたものの、彼方は水辺であれば陸上生活も可能、という水陸両用の設定があったので違和感はなかった。
一方で、ほぼ完全な水棲種であるラギアクルスはますます登場機会に恵まれないということに…
…まぁMH4シリーズに関しては
そもそも海竜種が全員リストラされてしまったシリーズとなっているため、設定云々というよりそれ以前の問題だったかもしれないが。
でも
魚竜種は参戦している。
…アレは参戦していると言えるのか?
ちなみに世界観的には商人の間で素材が流通しているらしく、
竜人問屋にて、上位
グラビモス亜種の素材を渡すとラギアクルスの上位素材、G級
リオレウスの素材を渡すとG級素材と交換してくれる。
更に、G級リオレウス亜種の素材を渡せば
亜種のG級素材と交換できるように。
これを活用すれば、本人不在の中でもラギア装備と、一部武器なら作製可能となっている。
が、亜種武具は武器しか作れないので注意。
【MHX/MHXX】
MH4Gの次回作として、MHXの発売が決定。
続々と過去に登場できなかったモンスター達の再登場が告知される中、無情にも伝えられたのは水中戦のオミット。
パッケージモンスターとはいえ、水中エリアがないのではどうしようもないか。
そう肩を落としたハンターたちに待っていたのは…
予想外すぎる告知に、ハンター界隈から驚愕と歓喜の声が上がった。
とはいえ、水中戦が無いのではラギアクルスは必然的に陸上戦を強いられることになる。亜種ならともかく、MH3シリーズでの通常種は陸上戦ではカカシも同然なのは周知の通り。
危険度の低いモンスターとして扱われるのではないか、と様々な予想が飛び交ったが、クエストを受注したハンターたちに待ち受けていたのは、
そんな予想を吹き飛ばす、超絶大変身を遂げ遥かにパワーアップしたラギアクルスの姿だった。
まず、基本的な行動は陸上特化型の亜種のモーションを全て踏襲。
距離が離れているからと油断していると超ホーミング性能の突進であっという間に距離を詰められ、範囲の広いタックルなどの近接攻撃でガンガン攻められる。
本種の象徴たる雷撃に至っては、更に強化されている。
亜種が使用していたブレス以上に爆散範囲も威力も上がった拡散型ブレス、
地面に着弾した後、まるで本種を守るバリケードのように電流を流す設置型ブレス、
雷を口に含み、噛みつきと同時に炸裂させ、ハンターを吹っ飛ばす帯電噛みつき
…などなど、亜種以上に強力かつ、バリエーション豊富な電撃技が多数追加されているのが特徴的。
お馴染みの大放電は、以前が一定範囲内でランダムに電撃を起こす仕様だったのが、
今作ではラギアクルスを中心に段階的に連鎖爆破を起こすような仕様に変化しており、最終的にはエリアの半分を吹っ飛ばしかねないレベルまで爆発が広がる超規模の危険技と化している。
剣士は従来の範囲まで逃げても安心せず、即座に武器をしまって緊急回避の準備をするぐらいの気持ちでいよう。
これだけでも十分目を見張るレベルの強化だが、極め付けなのはもう一つ。
放電しながらその場で回転し、ラギアクルスの周囲に2つの雷球を発生させる大技が追加。
この雷球は本種を中心に衛星のように回転しながら本種から離れていく挙動をとるが、その間本種は普通に次の行動をとっている。
ハンターは周囲を飛び交う雷球と、本種の動きに注意しながら戦うことになるわけである。
ちなみに、雷球の数は基本2つだが、蓄電量によっては3つにまで増え、さらに回避が難しくなる。
威力も高く厄介な技なのだが、それにしたってハタから見ると
巨大な雷球を地を這わすでもなく宙に発生させ、自由自在に操るという
とんでもない絵面の攻撃であるため、
ただでさえ注目が集まっていた本種が繰り出したこの新技は殊更インパクトが強く、
「魔法使いにでもなったのか」「種族間違ってない?」「MHFの世界に片足突っ込んでる」など、大勢のハンターたちを震撼させた。
ジンオウガですら雷光虫を飛ばしているという説明があるというのに…
なお今作において、蓄電と放電の仕様がガラッと変わっている。
簡単に言うと、以前は明確に蓄電量の概念があったが、今回は形態変化的なシステムになっている様子。
蓄電状態は二段階に分かれており、背電殻の色は通常時は赤色、一段階目は青色、二段階目はお馴染みの色に光り、電流が激しく走るエフェクトが現れる。
まず一段階目の状態になると各種電撃ブレスや雷球攻撃を使用してくるが、物理攻撃に雷を纏う技は使用しなくなった。
いくら本種が技を繰り出しても蓄電量が消費されることはないが、その代わり時間経過で通常状態に戻ってしまう。
通常状態では疲労状態と同じく、物理攻撃しか出来なくなる。
よって今作のラギアクルスは経過した時間を上書きするためか、頻繁に蓄電行動を取りまくる。その頻度があまりに高いので、普通に戦ってて通常状態に戻ることはほぼないと思っていい。
二段階目は特殊で、一段階目の状態でなおかつ怒り状態時に蓄電行動をとると到達できる。
非怒り状態でいくら蓄電行動を連発しようとこの段階に至ることはない。
二段階目になると雷撃ブレスや雷球攻撃が強化され、お馴染みの雷纏い攻撃や、大放電を繰り出すようになる。
以前の大放電は全ての電力を解き放つ攻撃だったため、繰り出した後は蓄電量が0になっていたが、こちらは一段階目に戻るだけ。
二段階目も時間経過で一段階目に戻ってしまうが、どうやら本種は時間が迫るとハンターが近くに居ようが居まいが、その場で適当に大放電をぶっ放すルーチンがある様子。
また一段階目に戻ってしまうと、再度また蓄電行動をとり元に戻ろうとするため、
大放電を放って間髪入れずに蓄電し、すぐさま大放電をぶちかますというめちゃくちゃな戦法を取ることもある。
こういった仕様から、今作では大放電を拝む頻度がやたらと高くなっている。
怒り状態時に限定されたのが救いか。
さらにさらに厄介な事に、背電殻を破壊した時の仕様が、「蓄電量が抑えられる」という以前の仕様から、「蓄電行動の頻度が抑えられる」というものに変更されてしまった。
…つまり、再使用までのスパンが長くなるだけで、蓄電さえ完了すれば普通に大放電が繰り出せてしまう。
しかも今作は水中戦が無い都合上、背中が攻撃しづらい。耐久力も当たり前のように高く、以前には無かった乗りシステムがあるとはいえ、たかだか数回乗ったぐらいでは容易に破壊できない。
仮に破壊できたとしても大抵その頃にはラギアクルスも瀕死だし、戦略的にも行動パターンが著しく変わるわけでもないため、今作での背中の部位破壊は無視しても構わないだろう。
とにかく、近距離、遠距離問わずありとあらゆる手段でハンターを追い詰めてくる。
本当に同じモンスターなのかと疑いたくなるレベルの要素がてんこ盛りなため、従来までの立ち回り方は一旦捨て去り、全く同じ姿をした新モンスターぐらいの気持ちで挑んだ方がいいかもしれない
怒り状態になると以前は電気が混じった白い息を吐いていたのだが、今作では角が青白く帯電し、放電し始めるというような演出になっている。
ご存知の通り本種は発電細胞とやらを体内に有しており、それを活性化して電気を生み出し、背電殻に蓄えていくのだが、角に電気に関わる仕組みがあるなどと言うような設定が言及されたことは一度もない。
別に今作で角を用いた攻撃があるわけでもない。謎である。細かいことはいいんだよかっこいいんだから
MHP2G以前では
ガノトトスから入手できた
キングロブスタの素材が、本種からも低確率で入手できるようになった。
が、やはりというか
ガノトトスからの方が入手確率は高い。食性の違いだろうか。
それにしてもラギアクルスの牙でも噛み砕けず、胃酸をもってしても消化できないとは…
やや
ネタバレになるが、
とある古龍種に捕食され、骨格の一部を武器として利用されている描写が確認できる。
その一部というのが背電殻なのだが、どういうわけだかその古龍はこの背電殻を使って
電撃を行ってくる。
背電殻はあくまで蓄電する部位で、発電自体はラギアクルスの体内細胞で行われているはずなのだが…
背電殻に細胞がこびりついているのかもしれない
と思いきや、この辺はきちんと説明されており、電気石などの発電できる自然物を組み合わせて使用しているようである。
そういう意味では、強力な電力を攻撃として出力できるラギアクルスの背電殻はまさにうってつけだろう。
ちなみに電気石といえば、
クルペッコ亜種由来のものだろうか。
今作でのモンスターリストには、それぞれのモンスターの攻略のポイントが書かれており、本種の項には「背部の器官を壊せば蓄電できなくなる」とあるのだが、
前述の通り別に背電殻を破壊したからといって蓄電できなくなることはないし、大放電だって普通にできる。
「陸上に特化したラギアクルスが発見されたのはつい最近で、手元にある情報はMH3時代の古いもの」と解釈しておこう…
ラギアクルスに限った話ではなく今作のモンスターリストの内容は割といい加減なことが多いような
本領だった水中戦がオミットされたため仕方ないことだが、あまりの変貌ぶりに以前の本種を知るファンからは「ここまでくるとラギアクルスである必要がないのでは」と復活したこと自体を疑問視する声も上がっている。
さらに「陸上に特化した」という設定の亜種の存在意義が奪われてしまったことを嘆く声も少なくない。
反面、以前から「陸上では雑魚」などとナメられていた扱いを見事に返上した、水中戦が苦手だったのでこれでようやくまともに戦いを楽しむ事ができた、
など、好意的な声も多数ある。
【MHWilds】
映えある看板モンスターでありながら、技術的な要素に阻まれ、何かと不遇な扱いにおらざるを得なかったラギアクルスだったが、
最新作MHWilds、夏のDLC第二弾にて、ついに、
MHWilds発売当初では影も形もなく、また見送られてしまったのか、と落胆されていたのだが、このまさかの復活。長年彼を推していたハンターの興奮は如何許りだったか想像に難くない。
開発陣側としても、彼をMHWorldに登場させようとして断念した背景があるため、今回は双方にとって大願成就と言ったところだろう。
最後に登場したMHXXから実に8年ぶりとかなり長かったが、これに関しては
ゲリョスや
グラビモスといったモンスターも同じ待遇である。
とは言えラギアクルスはこれまでMH4系列にも参加できなかった経緯があるため、体感的には相当久しぶりに感じるのも無理もないかもしれない。
MHX系列の彼はなんか違う感じがしたし
サイドミッションにおいては、
『緋の森』を主な生活拠点とする
火竜リオレウスが、何故か異常なほど興奮状態に陥っていることから物語が始まる。
怒れる火竜の暴れ方は尋常でないらしく、『緋の森』へ他の土地から物資の交換に来た人々にも見境なく襲いかかっており、ハンターがその原因の調査を依頼されることになる。
なおこの時、『緋の森』を拠点にしている「星の隊」の生物学者、エリックが最も事情に詳しいこともあり、ハンターの相棒であるアルマに代わってエリックが編纂者を務める。
森を調査していると、リオレウスのものと思しき痕跡を発見。跡を辿っていくと、戦闘があったらしい焼け焦げた跡に混じり、仄かに電流を感じる痕跡。
更にすぐその先の湖に行ってみると、なんと感電し、動けなくなってしまっているダルトドンの姿が。
『緋の森』に電気を扱うモンスターなどいないはず、と首を傾げるエリック達だったが、やがて生き餌に釣られて寄ってきたか、ピラギル達の群れが登場。
ここは一旦退こうと距離を取った次の瞬間、
上空から『大空の王者』リオレウスが突如として来襲。
恐らくダルトドンを狙って寄ってきたものと思われたが、いつになく気が立っており、苛立ちをぶつけるかのようにピラギル達を追い払う。
そんな光景を呆然と眺めていると…
何を隠そう、ダルトドンを感電させた張本人とは、かの『大海の王者』ラギアクルスだったのである。
恐らくリオレウスが苛立っていた理由は、獲物の取り合いで頻繁に彼と争っていたためであり、今回の現場も、恐らく先に襲いかかっていたダルトドンをラギアクルスに横取りされそうになっていたから。
ともあれ、本来『緋の森』にはいないはずのラギアクルスの姿に大興奮のエリックをよそに、やがて2体の『王者』が争いを始める。
両雄睨み合ったのち、まずはリオレウスが先制。尻尾による殴打を喰らわせるが、ラギアクルスには今ひとつ。ならばと火球ブレスを容赦なく浴びせるも、ラギアクルスは怯みこそすれ、余裕の表情。
今度はこちらの番とラギアクルスが噛みつくが、リオレウスは獲物を確保しつつ空へ回避。今度は上空から火球ブレスを浴びせるが、ラギアクルスは意にも介さずそのまま上空のリオレウスへ飛び上がり噛みつこうとする…が、すんでのところでこれも回避される。
しかし、この衝撃でリオレウスは獲物を落としてしまう。地上にラギアクルスがいる状況で拾いに戻るのは危険と判断したか、リオレウスはそのまま空へと飛び去ってしまった。
ラギアクルスは今回の戦いの勲章をゆっくりと堪能するのであった。
興奮しきりのエリックだったが、ラギアクルスは言ってしまえば「外来種」であり、強大な捕食者。これを野放しにしてしまうと『緋の森』の生態系が破壊されかねず、何より周辺住民にも被害が出る。
やむなくエリックはハンターにラギアクルスの「討伐」を命じようとする…が、ハンターは「長期的に様子を見てからでも良いのではないか」という考えから、「捕獲」を提案。
生捕りを目指し、ラギアクルスと対峙することになる。
激しい戦闘の末、ラギアクルスは捕獲。
捕まえたラギアクルスを詳しく見たところ、彼は『緋の森』のずっと遠い場所からやってきていた事が判明。
『緋の森』にやってきたのは、その豊富な資源に寄せられたためと推察する。
ラギアクルスは調査後に元の場所に戻されるが、また森に訪れるとも限らない。その際は、場合によってハンターが対処し、引き続き成り行きを見守っていく、ということになったのだった。
…と、一連の事件はこういった具合に幕を下ろす。
古参のハンターならもちろんご存知とは思うが、この戦闘シーンはラギアクルスの初登場作品であるMH3のOPムービーのオマージュとなっている。
比較してみると明らかな通り、リオレウスが小型モンスターから獲物を守っている間にラギアクルス登場、両者睨み合う姿はまんまあの時の焼き直しといった具合である。
しかし、異なるのは勝敗。MH3ではリオレウスはラギアクルスから獲物を守りきり、そのまま悠然と飛び去ってしまうのだが、今回は逆に獲物を奪われている。
ラギアクルスからしてみると「あの時の意趣返しをしてやった」といった所だろうか。
どちらも最初にリオレウスが捕らえた獲物だけども
また、ラギアクルスとの戦闘の際にすぐ分かることになるが、MH3で登場したフィールド『孤島』の汎用曲扱いだった
彼のテーマ曲、『海と陸の共震』が専用BGMとして流れるようになった。
今作ではリオレウスも20年の時を経て『咆哮』を我が物としている。
アップデートにてラギアクルスの登場が決定した際、「ラギアクルスもようやく専用曲持ちになれるのでは…」と期待されていたが、大方の期待に応える形となった。
更に更に後述するが、今作の彼は今までのモンハンシリーズを覆すような新ギミックまで引っ提げている。
懐かしの演出に、豪華な待遇の数々。ラギアクルスにとっても、長年復活を我慢してきたご褒美と言えるかもしれない。
ちなみに、このストーリーの一回限りの演出だが、無事ラギアクルスを捕獲すると、普段のクエストクリア時のBGMではなく、MH3系列のクリア曲、『成功!!!』が流れる。
懐かしの要素を潜り抜け、クライマックスでこの曲を聴いたハンターには目頭が熱くなるような演出だろう。
気になる戦闘面だが、大体のモーションはMH3Gに登場した陸戦特化型のラギアクルス、亜種のものに準拠している。
相変わらずその巨体を活かした範囲の広い近接攻撃や、何より超強力な雷撃を駆使して襲いかかってくる。
今作は割と初心者向けの難易度となっており、大抵のモンスターは動きが読みやすかったり、隙も多めに盛り込まれていたりするのだが、彼に関してはむしろ逆。
正直、今作の中でもかなり難易度の高いモンスターとして仕上がっている。
予備動作自体は長いし隙もしっかりあるのだが、それを補って余りあるぐらいの高火力と範囲の広さを持つ攻撃を矢継ぎ早に加えてくるのが特徴。
最悪、ガード持ちの武器種であればなんとか対処はできるが、そうでない武器だと判断に出遅れた場合、どの攻撃も咄嗟の回避はかなり困難。まずはしっかり動きに慣れておく必要がある。
加えて今作は近接攻撃のレパートリーがかなり増えているため、陸上だからと油断しているとものの見事に叩きのめされることになる。
十八番の「蓄電」および「放電」の仕様だが、今回もまた若干異なっている。
MHX系列では帯電状態がほぼ形態変化の扱いであり、「蓄電」は単なる攻撃手段となっていたが、MH3系列と同じく、「蓄電」で段階を上げ「放電」で消費していく、という形に戻っている。
ただし後述するが、今作では電力を消費するのに特定の条件がつくようになったため、戦闘時間の8割強は帯電状態にいると思っておいたほうがいい。
帯電状態もこれまで通り二段階で、一段階目は背電殻の色は変わらないが背中の表皮が仄かに青く光り、二段階目は背電殻自体が光り輝く。
ちなみに角が光り出す演出は無くなっている。
一段階目は1回の蓄電ですぐに移行するが、二段階目へはさらに蓄電を2〜3回ほど繰り返し、徐々に電力を溜めていくことで移行が完了する。
一段階目は単純に攻撃に雷が付与されたような状態だが、二段階目まで強化された状態は特に凶悪。
通常モーションが大幅に強化され、ただでさえ広かった攻撃範囲は更に広く、ただでさえ痛かった攻撃はもはや一撃一撃が瀕死クラスの高火力にまで極まる。また、この段階限定の大技も解禁される。
二段階目が言わばフルパワーの状態であり、この段階に至るまでには時間がかかるものの、いざ移行されるとかなり危険。
この状態を長く維持させないように立ち回りたい。
二段階目で解禁される大技の一つ、「大放電」の威力は相変わらず凄まじく、多段ヒットする特性も健在。
前述したように彼と戦う上でガード持ち武器は比較的有利だが、大放電だけは絶対にガードしないこと。冗談抜きで削りダメージだけで死に直結しかねない。
また、今作では大放電を放っても帯電状態は0に戻らない。
蓄電された電力が0に戻る条件は、「大放電を3回以上発動すること」または「一定ダメージを与えられること」。
MH3の頃の大放電は「蓄電された電力を全て解き放つ」という設定のはずだったのだが、とんでもない強化っぷりである。『緋の森』の環境のおかげで送電効率が上がったのだろうか…
当然3回も連発されていてはたまったものじゃないので、基本的には一定ダメージを与えて解除を狙っていく形になる。
ダメージはどの部位に与えても良い。一定量に達すると特殊ダウンも取れ、背電殻が狙いやすい位置まで落ちてくる。恐れず積極的に攻めていきたい。
雷撃はこれまでと同様、「背電殻」を破壊することで弱体化させることができる。
破壊による恩恵は、直近のMHX系列では「蓄電の頻度低減」という仕様になっていたが、今作では「蓄電の必要数増加」という形に変更となっている。
大放電といった大技を封印すること自体はできないが、目に見えて二段階目に至る時間が稼げる点は大きい。狙えるなら狙っていきたい。
これまでの作品では相当高い部位破壊耐久値を持っていた背電殻だが、今作ではかなり引き下げられている。
尚且つ部位の判定も広がっているようで、背中の真上あたりにしかなかった判定が、胴体上半分に至るまで広がっている。リーチの長い武器種ならラギアクルスの側面を攻撃するだけで破壊できてしまうことも。
そうでない武器種でも、ダウンを数回取れればその間に破壊できる。
これらの攻撃だけでも十分目を見張るだけの強さであるが、何より今作のラギアクルス戦には、今までのモンハンシリーズの常識を覆すような特大ギミックが施されている。
それは、
技術的にかなりの労力を必要とする複雑な要素であり、MHWildsどころか今後のモンハンシリーズに復活することすら最早不可能かと噂されていたこの要素が、なんとここに来て、しかもラギアクルスのためだけに大復活を遂げた。
言うなれば、ラギアクルスは『水中戦』の代表者。
彼の一番の特徴なのに、登場させる上でどうしても再現できなかったハードルを、今回ようやく越えることができたのだろう。
ラギアクルス実装時、『緋の森』におけるラギアクルスの根城として、新たに「エリア19」がフィールドに追加されている。
このエリアは滝の先に広がる洞窟となっており、中はかなり深い湖に面している。ある程度地上で彼を追い詰めると、ラギアクルスはこのエリアへと移動し、湖へと飛び込む。
オトモの発言から分かるが、ラギアクルスが水中に潜り込んだのは超強力な大技を準備するため。つまり、水中で彼を止めなければ手痛い反撃をもらうことになる。
そのまま地上で待っていても大技を繰り出すまで上がってこないため、湖のへりまで近づくと「飛び込む」の文字が。
そしてラギアクルスを追い、湖へと飛び込むと、そのまま『海の王者』との激しい水中戦が繰り広げられることとなる。
淡水だけど
水中でのラギアクルスだが、基本的なモーションはほぼ懐かしのMH3の頃のまま。
しかし一口に水中戦とは言っても、さすがにあの頃の完全再現という形ではなく、ハンター側の行動はある程度制限されている。
具体的にハンターが取れる行動は、
- 三次元方向への遊泳
- 真上、真下への遊泳
- 瞬間的な高速回避
- スリンガー弾の射出
- フックスリンガーでのしがみつき、攻撃
に限られる。
遊泳や回避でラギアクルスの攻撃を凌ぎ、隙を見てスリンガー弾を発射、またはフックスリンガーでラギアクルスにしがみついて直接攻撃を加えていき、大技の発生を食い止める…という流れになる。
でも水中ではあの頃のように、思うように動けないもっさり挙動…と思われるかもしれないが、今作においてはハンターの水中機動力は大幅に上昇。
遊泳速度はさほど変わらないが、「回避」のスピードと距離はかなり性能が高くなっている。更に、今作の新要素である「集中モード」を利用すると、視点を向けた方向に自由に移動可能。
基本これを連発するだけで水中を縦横無尽に泳ぎ回ることができるため、以前ほど不自由に感じることはないだろう。
なお、水中では「酸素ゲージ」の概念はない。
時間の許す限り、窒息に怯えることなく自由に行動できる。
モガのハンターより適性があるのでは
主体となるのは「しがみつき」からの攻撃。フックスリンガーを中距離から飛ばし、ラギアクルスを掴んで自分を引き寄せ、しがみつくことができる。最初は距離感が掴めずスリンガーが水を切ることになるのは御愛嬌
言ってしまえばこの仕様は「乗り攻撃」の延長のようなものであり、しがみつくとナイフか武器による攻撃ができる。
武器攻撃は威力が高く一撃離脱式であるため、動きの激しいラギアクルスに堅実にダメージを与えていける。こちらをメインに使っていくと良い。
ナイフ攻撃はダメージ量が少ないため一見無意味に感じるが、「傷口」を容易に作ることができる。ある程度慣れてくれば、ナイフで作った傷口を武器で破壊して離脱…なんて芸当もできる。
スリンガー弾に関しては、「尖った蔓脚類の群生」という採取ポイントから「スリンガー螺旋貫通弾」が手に入る。
スリンガー弾の中では中々強力で、貫通する性質から、上手く当てれば良いダメージソースとなる。攻撃が激しく近付けない時は積極的に使っていきたい。ただ、撃った後の反動がやや大きいので無闇に撃たないように。
なおスリンガー螺旋貫通弾はラギアクルスを攻撃すると出る落とし物、「剥がれ落ちた付着生物」からも入手できる。
一方で、水中におけるラギアクルスはまさに『海の王者』の本領発揮と言わんばかりの強さを誇る。
前述した通り基本的なモーションはMH3系列時代とほぼ同じ。つまり多くのハンターに悪夢を見せたあの頃の強さのままということを意味する。
とてつもないスピードを誇る突進、理不尽なほどに範囲が広いタックル…などなど、新規のみならず、古参ハンターですら手を焼くだろう。
こちらの機動力も多少上がっているとはいえ、ラギアクルスの帯電状態が二段階の状態ともなると手数が大幅に増え、もはや手がつけられない。激しい雷撃を掻い潜りながらの戦闘となる。
そのためにも、蓄電量は可能な限り0の状態で、できれば背電殻の破壊も地上で済ませておきたい。難しいが、これだけでかなり難易度が下がる。
本当にピンチになった際は一応、地上への退避も可能。
ただ飛び込んだ岸までわざわざ移動しなければならないのでリスクが高い。基本的には被弾を極力控えた戦闘を求められる。
厄介な仕様だが、こちらにも取れる手段は多い。
まず、湖の中には「水没している瓦礫」という落石ポイントがあり、タイミングよくフックスリンガーで起動させてやれば大ダメージとダウンが取れる。
わざわざ起動させなくとも、ラギアクルスの突進を誘発させてぶつけると、勝手に引っかかってくれる事も。
落石ポイントは2箇所。かなり大きなダメージソースとなるため、1つは少なくとも当てたいところ。
ラギアクルスの攻撃は激しく、一見するとしがみつく間もないように感じるが、一部の攻撃には「特殊弱点部位」が発生するものがある。
このタイミングでフックスリンガーを飛ばせば、確定で怯んでくれるため、安全に武器攻撃を加えることが可能。
攻撃後に赤く光る部位を見逃さないようにしよう。
また、ラギアクルスの攻撃には明確に指向性が存在しているようで、突進や尻尾攻撃などは左右へ回避、悪名高いタックルは上下に移動するだけで簡単に回避できる。焦らず行動を見極めれば被弾は抑えられる。
更に、ラギアクルスの「傷口」を破壊するか、一定のダメージを与えるとしばらくの間ぐったりとダウンしてしまう。
ダウンの時間はだいぶ長く、さらなる追撃のチャンス。ここぞとばかりにタコ殴りにしてやろう。
激しい争いの末、ラギアクルスへのダメージが一定量に達すると特殊演出が発生。
攻撃を受け大きく怯んだラギアクルスの頭部に、ハンターがフックスリンガーを飛ばしてしがみつく。
頭の上に陣取ったハンターはラギアクルスの眉間を思いっきりナイフで一刺し。
思わず口を開いたところへトドメとしてスリンガー弾を口内にブチ込むという容赦ない一撃を繰り出す。
さしものラギアクルスもあまりの衝撃に大暴れしながら水面まで上昇。そのまま地上へと引き摺り出すことができる。
これが「成功」演出であり、ラギアクルスの超大技を防ぐことができる。
なおこの演出の際、湖の中にあるトゲのような珊瑚が大量に生えている珊瑚礁がラギアクルスの近くにあると、衝撃で吹き飛ばされたラギアクルスはトゲまみれの珊瑚礁にゴリゴリと背中を打ち付けながら上昇し、地上に投げ出されたのちにダウンしてしまう。
狙いにくい背中にかなりの大ダメージを与えられるほかダウンまで取れるため、トドメが近いと判断したら是非とも狙っていきたい。
制限時間内にダメージを稼げなかった場合、ラギアクルスは超大技を発動。
湖の中心まで泳いだ後、その場で高速で回転し始める。やがてラギアクルスの回転の影響から、湖に雷を伴った竜巻のように巨大な渦が発生。
そして大渦の中心で勢いをつけ、ラギアクルスは水上へと一気に飛び出し…
着水の瞬間、
これが「失敗」演出であり、電撃は水中だけでなくエリア19の地上全域にまで至る。
そのド派手な演出に違わず威力は凄まじいものであるが、即死技というわけではないため、防具次第ではなんとか耐えることも可能。また、水中に居ても中心位置から限界まで離れていると当たらない。
ただし、こうなった場合は当然ながら追加ダメージもダウンも取れない。
制限時間内に限られた手段でダメージを与えていかなくてはならないため、慣れていないうちは焦りがちだが、猶予時間は長い。
スリンガー弾や落石を駆使し、確実に訪れる隙を狙って堅実に攻めていけば、しっかりトドメまで追い込める。
水中戦を切り抜けると、再び地上戦へ。ここまで来るとラギアクルスもかなり追い詰められており、ほどほどに攻撃を与えていけば瀕死になる。
最後っ屁にやられないよう油断せずに仕上げにかかろう。
上述もしたが、今作のラギアクルスは今作の中でもかなりの強敵として設定されている。
水中だけでなく地上では、新技に加えて攻撃の間隔も短くなっており、これまで以上に勢いが激しい。特に回避が主体の武器種は、まず何より逃げるタイミングを図ることが肝要になる。
幸い飛び道具は少なく設置技のような厭らしい技は無いので、危ないと感じたらすぐに距離を離そう。慣れてくれば、強力ではあるが癖の少ないモンスターであることに気付くハズ。
MHX時代の魔法使い染みた攻撃もしてこないし
各地の頂点クラスのモンスター、およびDLCより追加されたモンスターには、新難易度⭐︎8歴戦個体が実装されており、ラギアクルスもその例に漏れず、堂々の⭐︎8ランクの歴戦個体がフィールドに登場する。
DLC第二弾より趣向が変わったのか、追加モンスターのレア素材、ラギアクルスなら「海竜の蒼玉」が該当するが、これが歴戦個体からでないとほぼ手に入らないという仕様となっている。
その上、ラギアクルスの武具には大量に蒼玉が要求されるようになったため、武具を揃えたいハンターは否が応でも最強クラスの歴戦個体と連戦させられる羽目になる。
ただでさえ半端ない威力の攻撃を多く備えるラギアクルスの歴戦個体となるともう凄まじく、最大まで防御力を上げた最高ランクの防具を持ってしても、大技はだいたい即死圏内。
たとえ小技であっても4割は消し飛ぶほど強烈なため、基本は一発も攻撃を喰らわないぐらいの気概で行かないと攻略は本当に難しい。
ここまで攻撃力が高いとガード持ち武器ですら削りダメージでガンガン体力を消費していくので、どの武器でも危険な存在となってしまっている。
何より、一番の問題はべらぼうに高い体力。
流石に超大型モンスターのジン・ダハドには劣るが、それでも低く見積もってHP35,000ぐらいの半ばヤケクソ染みた体力量であり、同じ箇所をどれだけ攻撃しても一向に「傷口」が出てこないほどガッチガチ。
単純に事故死の確率が高いラギアクルス相手に長期戦を余儀なくされると言うだけで、とんでもなく難易度が跳ね上がっている。
体力が高いということは必然的に蓄電を解除するのに必要なダメージ量も多くなることでもあるため、歴戦個体のラギアクルスは冗談抜きでほぼ全ての時間が帯電二段階状態でいることが多い。
死に物狂いで攻撃しても解除までダメージが足らず、大放電を3連発され、また蓄電され、また大放電を連発され…という流れが延々と続く恐れがある。
最悪なのは『水中戦』との噛み合わせの悪さ。
こちらは行動に枷に付けられた状態で、痛い・速い・超タフの3拍子を手に入れたラギアクルスとの戦いを強制されることになる。
成功演出に至るダメージ量も当然のようにかなり多く、こちらの武器攻撃を何回当ててもダウンどころか怯みすら全然取れない。
とは言え、水中では割合ダメージを与えてくれる落石があるため、これを当てられればかなり有利になる。…が、逆に言うと落石が当てられなければ武器だけでの成功はほぼ不可能なレベル。
一応めちゃくちゃ頑張れば落石なしでも成功まで持っていけるが、猛烈に強化された攻撃力を前にしがみつきが何度行えるか…
このように、水中に関してはかなり一方的な戦いが展開されるため、正直やや理不尽な域にまで達している。
このため、歴戦⭐︎8のラギアクルスに関しては水中戦に付き合わないという戦略を割と真面目に取っているハンターもいる。
せっかく復活した「水中戦」であるが、今のところ賛否両論の評価であり、ほぼほぼこの歴戦個体との戦いに不満が集中している様子である。
そんなわけで、歴戦⭐︎8のラギアクルスは現時点で
悪名高い歴戦⭐︎8ゴア・マガラと同等レベルの強敵との呼び声が高い。
特にマルチプレイではとにかく事故が多く、
環境はまさに地獄の様相を呈している。
成功率がとんでもなく低いため、負けながらでもソロで行った方が多少はマシと言える。かなりキツイ相手であることを前提として割り切り、練習あるのみである。
ラギアクルスがエリア19に行くまでの体力量は5割未満ほどと決まっており、体力が一定値まで減ると、初期エリアがどこであろうと直行しようとする。
ただ、あくまで普通のエリア移動扱いのため、その気になれば罠や怯み、状態異常を駆使して阻止しまくり、水中戦に持ち込ませないまま倒すことも可能。
とはいえ相当上手くやらないと難しいので、あまり現実的な攻略法とは言えない。歴戦個体ならなおさら
水中での大技は、ハンターがエリア19内にいないと発動しない。
このため、ラギアクルスが水中に入ってからエリア外でぼーっとしていても、ラギアクルスは一生地上に上がってこない。そしてそろそろかなとエリアに入った瞬間、大技をかましてくることになる。
これを逆手に取り、ラギアクルスと他のモンスターとの2体同時クエストの場合、ラギアクルスが水中に入るのを確認した後、その間に別のモンスターと戦い、水中戦をスキップしつつ時間を有効活用する手法が取られることがある。
ラギアクルス通常個体との戦いなら別にこんなことをする必要はないのだが、それぐらい歴戦ラギアクルスの水中戦をしんどいと感じるハンターは多い。
逆に歴戦個体が相手でも安定して水中戦を制する腕があるハンターは、真の意味で『海の王者』と言えるだろう。得意だと言う人は誇っていい。淡水だけど
…と、ここまでDLC第二弾配信以降も色々と話題になっていた彼だが、やがて舌の根も乾かないうちに驚愕の難易度⭐︎9歴戦個体の実装が告知された。
⭐︎9歴戦個体とは、スキルをランダムで発動する「光るお守り」が報酬で入手できるガチャエンドコンテンツ要素の一つであり、結果によっては強力な護石が手に入る可能性がある反面、⭐︎8歴戦個体以上に凶悪なほど強化された個体となっている。
実装の対象になったモンスターは⭐︎8歴戦個体と同様、アルシュベルド、各地の頂点捕食者モンスター群、そしてDLCで追加されたモンスター群。
もちろん、ラギアクルスも登場した。
⭐︎8の歴戦個体ですら散々な地獄を見せてきたラギアクルスに⭐︎9である。これはもう地獄という表現すら生温い悪鬼羅刹が顕現しているのでは…
…と思われていたが、ぶっちゃけた話、⭐︎8からあんまり変わっていない。
厳密に言えば
体力の増強、攻撃力増大、落石ダメージのカットなど、確かに強化はされているのだが、総合的に見ると
他の⭐︎9歴戦個体と比べて明らかに強化幅が小さい。
特に体力に関して、⭐︎8では
ゴア・マガラ、ジン・ダハド、
ウズ・トゥナに次いで四番目に高かったはずなのだが、⭐︎9になった途端、
最低のレ・ダウに次いで二番目に低い体力量に成り下がっている。
攻撃力に関しても⭐︎8からあまり差がない。
ここまで低い値に抑えられているのは、恐らく単純にゴア・マガラと同様⭐︎8で強くしすぎたと言うのが予想として挙げられる。おっかなびっくり挑んでみたら、意外と労せずに倒せてしまったというハンターも多いだろう。
ラギアクルスは⭐︎9歴戦個体の中では報酬が多めに設定されているため、⭐︎8から一転、狩猟人気の高いモンスターに選ばれているようである。
…しかし、これはあくまでラギアクルスに慣れていればの話。
⭐︎8歴戦個体に苦労しているハンターにとっては依然強敵だし、体力も低いとは言っても「比較的」というだけで、実際のところは脅威のHP40,000弱。
攻撃力に差はないとは言ったが、これももともと即死クラスの技が多かったから多少上がったところで何も変わらないという意味合いが強い。
安易に挑むべき相手では絶対にないことだけは覚悟しておこう。
水源が豊かな地域が今のところ『緋の森』しかないため、現状ここにしか出現しない。
多くの歴戦個体が集う魔境となった『竜都の跡形』にも確認されていない。メタ的に言うと、竜都には水中戦ができるようなエリアが用意できないためだろう。
もともと豊富な資源に惹かれてやってきているので、「豊穣期」に現れやすい。...というかほぼ確定で出現する。
一応「荒廃期」にも現れることもあるが、確率は低い上、その時期に狙うメリットはあまり無い。なお、獲物が減ってしまうためか「集中豪雨」の時に姿を現すことはない。
『緋の森』では新参の彼だが、「王者」らしく堂々と我が物顔で練り歩く姿が見られる。
普段は水の流れに沿って森を歩き回り、時折、頭部のヒレや腹部の鱗、背電殻を念入りに手入れしている。
なおこの時、落とし物として「擦り落ちた鱗片」、「剥がれ落ちた背電殻の欠片」を拾うことができる。特に後者は普通に戦っていると中々手に入らない背電殻が手に入る。目についたら拾っておこう。
寝床は前述した通り新たにできたエリア19。休息を取る時や弱った際はここまで泳ぎ、陸上で休眠する。
空腹になると、
タマミツネや
ウズ・トゥナのように、エリア12の川や17の湖で狩りを行う。意外にもムービーの時のようにダルトドンといった陸棲の草食種を襲うことはない。
リオレウスが何か言いたげだぞ
もちろん食べるのは魚類...と言いたいところだが、実はラギアクルスに限っては
捕食対象が2種類あり、それぞれに捕食モーションがある。
まず1パターン目は、
沢山の小魚が集まっている地点で深く潜水。魚には襲い掛からずそのまま水中で待機する。すると、魚の群れを狙って空から翼竜のハルプスが飛来。ハルプスは群れめがけて空中から勢いよく水中へ飛び込み、小魚をキャッチした次の瞬間、
潜水していたラギアクルスが猛然と浮上。水上へ飛び出しながらハルプスに食らいつき、捕食してしまう。
と、中々見ごたえのあるシーンとなっている。あまりの迫力から、
某映画の
ワンシーンを思いだしたと言うハンターも多い。
そして2パターン目は魚類を捕食する姿...なのだが、これがまた豪快。
水中へ潜りこんだのち、魚が集まりそうなポイントまで泳ぐと、その場で超高速で回転。ラギアクルスが回転した影響で水中には大きな渦が発生し、近くで泳いでいた魚たちは小物、大物問わずどんどん巻き込まれていってしまう。そして渦に十分に魚が集まったのを見計らい、
渦の中心で放電を一閃。水が沸き立つ程の威力に集まっていた魚たちは絶命し、水面に浮上してきたところを纏めてかっさらう。
このパターンもまたかなりの迫力だが、特にモンハンのコアなファンならピンと来たことだろう。実はこの「渦を作って獲物の逃げ場を無くし、放電でとどめを刺す」という描写は、ラギアクルスが初登場したMH3からあった設定である。
そして恐らく、エリア19で繰り出してくる大技に関しても、狩りに用いる戦法をそのまま攻撃に転じている格好になる。まさにラギアクルスに狙われた獲物の気分を味わえることだろう。
どのパターンでも、ラギアクルスは小魚には目をくれず、大物の魚類や、はたまた翼竜を優先的に狙うようである。
ラギアクルスは非常に強力な電撃を操ることができる一方、その分体力の消耗が激しいため、効率よく大物を狙おうとしているのかもしれない。
そう考えると、ラギアクルスが大物魚類も多く集まる肥沃な『緋の森』に惹かれてしまうのも納得である。リオレウスが(ry
また、捕食シーンや大技に限らず、今作では以前からあった設定描写が再現されている箇所が多い。
特に放電に関しては「あまりのエネルギーに周囲の水が沸き立つ」という設定があるが、使用している姿をよく見てみると、周辺の水分が一気に蒸発し、ボコボコと泡を立てながら霧散する瞬間を見ることができる。
また水中で発するものに至っては、水だけでなく周辺の地形まで崩落し、崩れ落ちた瓦礫が電撃に当たって次々と粉々になっていく様まで確認できる。
確かにこんなものを喰らってはひとたまりもないわけである。普通は即死だと思うが
細かい点に注目してみると、見た目に関しても設定が反映されている。
地上にいる際はまばたきしているのだが、この時、よく見ると瞬膜を展開している。これは水中にいる時にはっきりと分かるのだが、水中のラギアクルスの眼には薄い透明な膜が常に覆っている。これでラギアクルスは眼球を保護しつつ、水中でも周囲の状況を視認することができるのである。
また、水中にいる際に喉奥を見ると、口蓋弁があるのを確認できる。弁は地上にいる時はしっかり開いており、水中に入る際はこの弁で体内に水が入らないようにしっかり蓋をしている...という設定がここで表現されている。鳴き声を出せる原理は謎だけど
細部にも設定が多いモンハンであるが、ゲーム中に落とし込むには難しい点も多く、フレーバー的な要素が強かったが、技術的にできることも増えてようやく形にできたのだろう。
ラギアクルスのファンとしては嬉しいこだわりである。行動が激しすぎてじっくり見る暇が無いのが難点だが。
王者としての貫禄を見せつける彼だが、『緋の森』に棲む「王者」たちも黙ってはいない。ラギアクルスにも当然
「縄張り争い」が用意されている。
対戦カードは永遠のライバル、
火竜リオレウス。そして『緋の森』の支配者、
波衣竜ウズ・トゥナ。
さすがに錚々たるメンツである。
まず対リオレウス戦だが、なんとこの争いはこの2種だけの特別仕様となっている。
両者ともに睨みあうと、ラギアクルスが先制。地上から何度も噛みつこうとするが、リオレウスはこれをひらりと空中で回避。
やがてラギアクルスの真上を取ると、そのまま背電殻に向けて蹴りを連発。怯むラギアクルスだったが、背中に張り付いた瞬間を狙ってリオレウスに巻き付くことに成功する。
そのまま締め上げようとするも、なんとリオレウスはラギアクルスが巻き付いたまま跳躍。空中で反転し、ラギアクルスをひっくり返してしまう。
なすすべなくマウントポジションを取られたラギアクルスに対し、リオレウスは必殺の高出力火炎ブレスをゼロ距離で発射。これにはたまらずラギアクルスは吹っ飛び、立ち上がれなくなってしまう。
...結果から分かる通り、この争いはラギアクルスの「敗北」で終わってしまう。
が、これが異なった条件下では結果が一転する。
ラギアクルスがリオレウスに巻き付くところまでは同じなのだが、締め上げた際に背電殻が煌々と発光。
そしてリオレウスを締め上げたまま、必殺の大放電を密着状態で容赦なくブチかます。そのあまりにも凶悪な一撃によりリオレウスは絶叫を上げ、だらんと脱力。そのままラギアクルスに投げ飛ばされ、地上で悶えることになる。
この場合では、なんと
ラギアクルスの「勝利」となる。
つまり、この争いはMHW:Iにリオレウスと
ディノバルドとの間にあった、
特定条件で勝敗が分かれる特殊仕様となっているのである。
ディノバルドは「陸上版リオレウス」というコンセプトがあり、リオレウスとは特別な因縁があったため他とは違う演出が為されていたが、ラギアクルスも『空の王者』と対をなす
『海の王者』として、こちらも特別な扱いにしたのだろう。
少しでも両者にとって有利な条件が揃えば、それだけで勝敗が決まる紙一重な実力差であることが表現されている。
勝敗を分ける条件は、「ラギアクルスが帯電状態にいるかどうか」。帯電状態は段階に依らず、少しでも蓄電しているとラギアクルスは勝利する。
一見するとラギアクルスの方が有利なように思えるが、設定上、蓄電および放電はかなり体力を消耗する行為であるため、ラギアクルスにとっても簡単に切ることができない手段である。そう考えると、やはり手放しで優勢とは言えないだろう。
ただゲーム的に、ラギアクルスは戦闘中ほぼ常時帯電状態であるため、彼と戦っている際にリオレウスが乱入してくるとまずラギアクルスが勝ってしまう展開をよく見ることになるかもしれない。
他モンスターの縄張り争いもかなり激しいが、こちらは自身の持ちうる最大火力の攻撃をゼロ距離でかまし合うという殺意剥き出しの争いとなっている。
そのなんだか毛色の違う戦いっぷりに戦慄する声も多い。正にライバル同士の決闘である。
対ウズ・トゥナ戦では、
まずウズ・トゥナが巨体を活かしたボディプレスで先制。しかしラギアクルスはこれを苦もなく回避し、ウズ・トゥナに巻きついて首筋に喰らいつく。
しかし敵もさるもの。ウズ・トゥナはあろうことかラギアクルスが巻き付いたまま反転し、そのまま体重を乗せたフライングボディプレスをお見舞いする。
強烈な一撃に悶えるラギアクルスに、さらに追撃を加えようと掴みかかるウズ・トゥナだったが、ここでラギアクルスは大放電を発動。
至近距離からの大技に流石のヌシも弾き飛ばされ、争いを終える。
結果から、勝敗は「引き分け」という扱いになる。こちらは対リオレウス戦と異なり、ラギアクルスがどんな状態でも結果は変わらない。
頂点捕食者さえ怯んでしまう大放電の威力は相変わらず見事だが、属性相性が不利な相手に互角の勝負まで持っていってしまうウズ・トゥナも大概バケモノである。
ラギアクルスも属性での有利を取れていたとはいえ、本来水中に特化した形態でありながらその地の頂点に地上で渡り合えてしまうという実力の高さを見せつけた争いであると言える。
流石は『大海の王者』である。淡水だけど
惜しむらくは活動時期であり、ラギアクルスは「豊穣期」に活発化する反面、ウズ・トゥナは「集中豪雨」を主な活動時期としている。
ラギアクルスの性質的に、ウズ・トゥナがごく稀に「豊穣期」に現れない限りは実現することがないマッチングである。そう言う意味では、案外『緋の森』の環境は安定しているのかもしれない。
なお、今作の看板モンスター、
鎖刃竜アルシュベルドとも縄張り争いが存在するが、やはりと言うか
雑巾絞り流用モーションで
「完敗」する。
これに関してはもう予定調和である
【MHST/MHST2】
通常種はストーリーの途中で特殊な個体と戦闘することになる。
亜種はオトモンとしてはトップクラスの能力なのだが、成長が晩成型なのが玉に瑕。エンドコンテンツで活躍させてあげよう。
種固有の絆遺伝子はどちらも雷属性ブレスのスキルが付くが、通常種は単体攻撃の「雷ブレス」、亜種は全体攻撃+マヒの「拡散豪雷ブレス」となっている。
雷属性攻撃に長けるだけでなく、有用な遺伝子を持っていることがあるので、「伝承の儀」で伝承元の個体としての出番も多くなる…気がする。
また、通常種は運が良ければ水属性攻撃が上がる遺伝子を所持することがあり、絆技の「キングストローム」が大渦の発生で始まり最後に属性ブレスを放つ演出であることから、「大洋の主」の異名に恥じない水属性型として育成するのも候補にはなる。
問題はMHSTの水属性の扱いがだいぶ悪いことだが
通常種はやはりストーリーの途中で戦闘イベントが発生するが、今度は通常個体。
亜種はそこから少し先、火山の麓や洞窟内と、これまでのイメージとは少しかけ離れた場所に生息しているが、付近に湖はあるのでそこまで困らないのだろう。
亜種は登場時期的に雷属性を弱点とする古龍との対峙がちらついており、
ジンオウガや
ライゼクスとともに、攻撃傾向がそれぞれ異なる雷属性組を如何に育て上げるかが重要になっている様子。
◆攻撃手段
【MH3/MH3G(攻撃)】
【水中】
- 咆哮
- 発見時、怒り状態移行時に吼える。
- 水棲生物のくせにバインドボイスを放つ。音圧は【小】。小魚ぐらいなら失神しそうである。
- ガードする時はしっかりラギアクルスの頭を向いてすること。
- 振り向き
- 水かきがついた前脚の片方を使い、こちらに向き直る。
- 前足の動きにあたるとダメージ。
ダメージは軽微だが、ランスのようにスーパーアーマー持ちでない武器種では、当たるとのけぞってしまうため地味に効く。
- 陸上にいる時と違い、最大180°身体の向きを変えられるため、水中では1回の振り向きでこちらに向き直ることができる。
- 前進
- 前脚を両方使い、距離を詰める。
- ラギアクルス自身に当たるとダメージ。
こちらも別に大したダメージではないが、喰らうとぶっ飛ばされてしまう。体勢を立て直しているところへ攻撃が飛んできたりするので注意。予備動作もないため地味に厄介。
- 後退
- 尻尾を使ってこちらを向きながら距離を離す。
- ダメージ判定は無いが、近くにいると水流【小】の煽りを喰らう。ラギアクルスが距離を離した時は大抵突進が飛んでくるため、無理に深追いせず、待ち構えるか回避の準備をしておこう。
- 噛みつき
- 体を蛇行させながら前方を2回噛み付く。
- 喰らうと吹っ飛ばされる。
- 水中では垂直に立つようにとっている姿勢がこの時は水平になっているため、尻尾を攻撃するチャンス。
- 回転攻撃
- 身体を捻るように噛みついて上半身だけ後ろを向き、そのまま尻尾で薙ぎ払う。
- 喰らうと吹っ飛ばされる。やや出が早く、慣れていないと不意を突かれやすい。
- 見ての通り横方向の判定が強いため、上下移動が有効。噛みつきは下へ、尻尾攻撃は上へ避けるとかわしやすい。
ラギアクルスの胸元には判定が無いので、懐に潜り込んでも回避できる。
- 尻尾を切断すると2回目の尻尾攻撃のリーチが短くなる。
- 垂直尻尾攻撃
属性:水属性やられ【大】- 一瞬腰を引いたあと、勢いよく尻尾を下から上へかち上げるように撃ち払う。
- 尻尾に当たらずとも付近に水流【大】が発生しており、煽られると水属性やられを発症してしまう。
割と頻度が高い攻撃な上に出が早く避けづらいため、喰らうことを前提としてウチケシの実は忘れずに。
- 尻尾を切断しておくと単純にリーチが短くなるほか、水流も水属性も発生しなくなる。
- タックル
属性:雷属性やられ【大】(帯電時)- 素早く身を巻き、水平に構えたあと、タックルを繰り出す。
- 水中時で最も注意すべき技。
ラギアクルスの巨体が遺憾無く発揮される攻撃で、胴体に物凄く広い判定があり、猛烈に避け難い。
縦方向の判定は乏しいので、上下に回避すればあっさり避けられたりする。
またラギアクルスの首から上の判定もやや緩いため、動作が見えたら頭のある方向に回避しても避けられる。
- 怒り状態になると2回連続でぶっ放すようになり、危険度が倍増する。
2回目もしっかりとこちらに位置調整して繰り出してくるため、上下回避で下手な避け方をすると2回目を貰う場合がある。
横に逃げる時は、1回目2回目ともにラギアクルスの頭がある方向へ急いで逃げること。
1回目を回避するときに頭に向かってすれ違うように回避すると、角度調整が間に合わなくなるのか、2回目が明後日の方向に飛んでいく。ただ難易度は高いので注意。
ガードすると反動がデカいため、2回目を見事に喰らう事になるが、ランスなら2回目にギリギリ対応できる。
- 帯電していると雷を纏うため余計に凶悪な技に変わる。
範囲が広がるため、かなり早い段階で避けなければ引っ掛けられる恐れがある。
蓄電量は1回のタックルで1消費するため、背電殻を破壊していると、必然的に帯電2連タックルは封印できる。
- 突進(弱)
属性:雷属性やられ【大】(帯電時)- 突然蛇行しながら高速で突っ込んでくる。こちらを通過したあと、折り返して再度突進することもある。
- 周囲に水流【小】が発生。
予備動作がほとんどないため、出されたら確実にビックリする技。ホーミング性能はそこまでないので、咄嗟に回避できれば案外かわせる。
- 帯電していると雷を纏いながら突っ込んでくる。威力はもとより範囲も広くなるため危険。消費蓄電量は1。
- 突進(強)
属性:水属性やられ【大】、雷属性やられ【大】(帯電時)- 頭だけこちらを向きながら、遠ざかるように外周を泳ぐ行動を1、2回繰り返した後、遠方でとぐろを巻いてこちらを見据え、スクリュー回転しながら超高速で突っ込んでくる。
- 一見しても分かりやすいが、周囲に水流【大】が発生している。しかも煽られると水属性やられに陥る。
見た目通り相当な威力を誇るが、予備動作が非常に大きいため読みやすい。が、最後の角度調整の際はハンターが真上にいようが真下にいようが正確に捕捉してくるため油断しないように。
- 攻撃前も後も、ものすごい勢いで距離を離されるため、予備動作が見えたら武器をしまい、下手に追いかけず突進の回避に専念。避け切ってから追いかけよう。
- 帯電していると水流の代わりに雷を纏いながら突っ込んでくる。思った以上に範囲が広がるため、横着せず確実に避ける事。消費蓄電量は1。
- 雷球ブレス
属性:雷属性やられ【大】- 大きくのけぞった後、口から雷の塊を吐き出す。
- リオレウスの火球ブレスのように一直線に飛んでいく。予備動作も大きいので避けやすいが、放つ直前に後ろへやや移動するため、胸元あたりにいるとちょうど直撃する恐れがある。
- 怒り状態時は2回連続で繰り出す場合がある。
- 蓄電量に影響しないらしく、いくら出しても消費されることはない。
- 蓄電
属性:雷属性やられ【大】- 唸りながら体内で発電する。周囲に電気が漏れ出し、背電殻が青白く輝き始める。
- 背電殻に電気を蓄える行動で、厳密には攻撃ではないのだが、発電する際に思いっきり周囲に電気が漏れているため、初見ではこれが放電攻撃かと勘違いされがち。
漏れている電気に触れると吹っ飛ばされる。ラギアクルスの近くにいるほど避けづらいため、喰らいやすい攻撃の一つ。
- 連続して行うこともあるが、2回まで。蓄電されると背電殻の色が変化していき、何もされていなければ赤、1回の蓄電で淡い青になり、2回で激しく輝く。
- 蓄電量は1回につき2ずつ増えていく。最大蓄電量は4まで。
背電殻を破壊すると大幅に弱体化し、1しか蓄電できなくなる。厄介な攻撃を抑えることができるため狙いたいところだが、耐久値が高いため、しっかり狙えるよう要練習。
- 大放電
属性:雷属性やられ【大】- ゆっくりと身体を屈めた後、背電殻に蓄電した電力の全てを解き放つ。ラギアクルス周囲の水が一気に煮立つほどの大規模な電流が走り、爆発的な電撃が迸る。
- ラギアクルス最大の技。もちろん威力は伊達ではない。
攻撃としてはラギアクルス周辺に強力な放電域、そしてその領域に雷球がランダム位置に無数に発生する、という構造になっている。放電自体はガードできるが、周囲を取り巻く雷球はガード不可。
- 雷球はガード強化をつければガードできるが、放電中連続して発生し続ける。防いでしまえば殴り放題、とはいかない。むしろ喰らいまくってスタミナごと削り殺される危険性があるため、絶対にガードしないように。予備動作が見えたら一目散に退避しよう。
- 判定も結構な長さであるため、終わったのを見計らって近づこうとすると、雷球の最後っ屁に巻き込まれる可能性がある。ラギアクルスが次の行動に移るまで待つのが無難。
- 危険要素が多く、いざ放たれるとラギアクルスに近づいているほど対処が難しくなるので、戦闘する上で物凄いプレッシャーになる。
欠点として、この攻撃はかなり疲労が伴うらしく、放ったあとは大抵疲労状態に陥る。うまくいなしたあとは反撃のチャンスである。
- 必要蓄電量は2以上。蓄電量によって攻撃の性能も上がるらしく、単純に多ければ多いほど放電域と雷球の発生域の範囲が広がる。最低量の2と最大量の4との差は顕著。
4まで蓄電された状態での大放電はそれはもう凄まじく、大袈裟なぐらい離れないと被弾するばかりか、ラギアクルスの至近距離で喰らった場合、運が悪いと吹っ飛ばされた先でまた雷球に直撃するという大惨事も本気で起こりかねない。
- 背電殻を破壊すると必然的にこの技を封印できる。メリットは大きいが、無理に狙って狩猟時間が伸びると、この攻撃を繰り出されるリスクも高くなるため、うまく対処できるようになる練習も重要である。
【陸上】
- 這いずり移動
- 這いずりながら移動する。
- こちらとの距離を詰めるときに使用。脚に当たると尻餅をつきダメージ。
なぜかそれなりに高いダメージ量なので注意。
- 後退
- 這いずりながら後退する。
- 脚にダメージ。特に脅威はないが、距離をとった時は大抵突進が飛んでくるため油断しないように。
- 噛みつき
- 2回連続で前方を噛み付く。
- 出は早いが判定が狭いので至近距離にいればまず当たらない。
- ボディプレス
- 上体を起こして倒れ込む。
- 予備動作は比較的大きいため対処しやすい。ロアルドロスのように水属性がついているわけでもなければ、アグナコトルのように震動がついてるわけでもないので、特に注意すべきことはない。
- 回転攻撃
- 身体を捻りながら上体だけ後ろを向くように噛みつき、そのまま尻尾で薙ぎ払うように攻撃する。
- 水中で繰り出してくるものよりゆっくりした挙動で読みやすいが、最初の噛みつきは胸元にも判定があるので危険。
- 尻尾攻撃は噛みつきを回避できる位置にいるようならまず当たらない。切断しているなら尚更当たらない。
- タックル
- こちらに側面を向け、素早く身体を滑らせてタックルを繰り出す。
- それなりのスピードがあるが、繰り出すまでが水中と比べ物にならないくらい遅いため対処しやすい。
横方向の範囲はやはり広いが、タックルの移動距離は短いので、横方向よりは距離を取る方向へ回避すると安定しやすい。
- 亜種の繰り出すものは凄まじいホーミング性能をもっており、至近距離だと武器をしまって全力ダッシュしても引っ掛けられるレベル。
が、やはり移動距離は短いので、予備動作が見えたら離れる方向に移動しよう。
- 這いずり突進
属性:雷属性やられ【大】(帯電時)- 腹這いになり、勢いよく滑って高速で突進する。
- スピードは速いが予備動作が大きく、ホーミング性能もほとんどないため対処は容易。
- 亜種が繰り出してくるものは予備動作がほとんどなく、ホーミング性能が凄まじく高いため、見てから回避は非常に困難。
出してくるタイミングは大抵こちらとの距離が離れている時か、後退した時であるため、警戒していれば対処は可能。
- 帯電していると雷を纏いながら突っ込んでくる場合がある。範囲が広がるため、もともと攻撃性能の低い通常種ならともかく亜種はえげつないまでに避けづらくなる。消費蓄電量は1。
- 振り向き噛みつき
- 自身の後脚付近を狙うように勢いよく噛みつき、向きを変える。
- 亜種限定行動。特に注意すべき攻撃その1。
亜種の頭と、前脚から尻尾の付け根のあたりまでに及び、非常に広い範囲をもつ。反面、胸元には判定はない。喰らうと吹っ飛ばされる。予備動作がほとんどない上、かなり痛い。
しなっている尻尾にも判定があるが、こちらは喰らっても尻餅をつくだけ。が、なぜかこっちもそれなりの威力がある。
- 出が早く、範囲が広く、威力も高い、と一見すればちょっとした攻撃のくせにやたら危険度の高い技。後方から攻撃する場合は警戒しよう。
- 雷球ブレス
属性:雷属性やられ【大】- 大きく首をのけぞらせ、口から雷の塊を吐き出す。
- 予備動作も大きい上にホーミング性能も皆無なため、棒立ちでもしていなければ当たることはない。使用頻度も低い。
- 亜種は3回連続で雷球ブレスを放ってくる。おまけに一発放つごとに後退しながら角度を調整してくるため、精度もそれなりに上がっている。
逆に至近距離にいればほとんど脅威にならないが、どんどん後ろに下がっていくのであまり攻撃のチャンスにならない。とはいえ隙自体はデカイので、チャチャを狙っているならまるまる攻撃チャンスになる。
- 水中同様、蓄電量に影響しない。
- 高出力雷球ブレス
属性:雷属性やられ【大】- 首をしならせるように振った後、地面に着弾すると広範囲に雷撃が拡散するブレスを口から吐き出す。
- 亜種限定行動。
さながら火竜が放つ高出力火炎ブレスのような技。威力は凄まじく高く、並の雷耐性なら一撃でかなりの体力を持っていかれる。
雷撃は非常に広範囲な上、持続時間も比較的長く、着弾した地点はしばらく危険地帯になる。
- 単体で繰り出すこともあるが、通常の雷球ブレスや、3連雷球ブレスの途中に挟むように繰り出してくるパターンもある。
- 中途半端な位置にいるほど危険なため、亜種の足元、胸元にいれば喰らうことはない。が、3連雷球ブレスで距離を離されていた場合は危険度が一気に増す。
- 厄介な技だが、こちらも蓄電量に影響しないため、亜種は遠慮なくバカスカ放ってくる。
- 蓄電
属性:雷属性やられ【大】- 一瞬構えた後、身体から電気を放出しながら発電、蓄電された背電殻が青白く輝き始める。
- 亜種限定行動。特に注意すべき攻撃その2。
通常種が出来なかった陸上での蓄電。仕様としては水中とほぼ変わらないのだが、何故か構えてから放電するまでの時間が異様に短い。その上、放電の範囲が異様に広い。
予備動作が見えて全力で回避に専念しようとても、回避性能を積んでいようが範囲外に逃げられないレベルである。
- こういった性質上、ガードできる武器種ならともかく、できないものに対する対処法はその武器で来るな、という以外に全く無い。
おまけにやたらと頻度が高いため、しょっちゅう被弾するハメになるのは覚悟したほうがいい。
- 大放電
属性:雷属性やられ【大】- 首と尻尾を丸め、背電殻に蓄電した電力の全てを解き放つ。
- 亜種限定行動。
通常種が水中で放つものの陸上ver.といったところ。技の仕様も全く同じものと思ってくれていい。つまり、危険度は非常に高い。
- とはいえ水中と違い、陸上では緊急回避が使えるため、幾分か対処はしやすいかもしれない。
【MHX/MHXX(攻撃)】
- 咆哮
- 特に変更なし。
- 音圧は【小】なのも変わりはない…のだが、なぜか喰らった時の硬直がやたら長くなっている。
次に放ってくる攻撃も場合によっては普通に喰らうレベルに長いので、余裕があれば耳栓を積んでいくのも悪くない。ブシドーのジャスト回避、ブレイヴのいなし、エリアルの踏みつけもしくは吹っ飛びとといった回避方法もアリ。
- 振り向き噛みつき
- モーション自体に変更なし。
- 予備動作が少し長くなり、喰らっても膝をつく程度になり、高すぎた威力もかなり良心的になった。
- が、気絶値が非常に高く設定されている。攻撃の前にダメージを負っていたり、雷属性やられに陥ってると1撃で気絶するため注意。
- タックル
属性:雷属性やられ【大】(帯電時)- モーション自体に変更なし。
- 移動距離がかなり長くなった。従来通り離れる方向へ逃げると普通に轢かれてしまうので注意。ただし亜種ほどのホーミング性能は無い。
- 蓄電二段階目に雷を纏うようになった。ただでさえ広い範囲がかなり広がることに。
- 這いずり突進
属性:雷属性やられ【大】(帯電時)- モーション自体に変更はなし。繰り出したあとは軽く威嚇する。
- 相変わらず速いが、亜種が繰り出してきたものと違い、予備動作なしでいきなり突っ込んでくることは無い。ホーミング性能も控えめ。
- 蓄電二段階目では以前と同じように雷を纏いながら突っ込んでくる。
- 雷球ブレス
属性:雷属性やられ【小】- こちらと位置が近いと、放つ際に大きく後退しながら位置を調整するようになった。
- やや精度が上がったため、以前のような感覚でいると普通に当たる。
- 電流設置ブレス
属性:雷属性やられ【小】- 上体を起こしながらハンター周辺に雷球を放つ。地面に設置された雷球は電流を流し、地面に一本の電流の束を作る。
- 新モーション。
設置攻撃。発生した電流の束はラギアクルスを守るバリケードのように滞留し続けるのが特徴。
喰らっても膝をつく程度なのだが、これがなかなか厄介で、今作で攻撃が激しくなったラギアクルスの前で隙を見せる格好になってしまう。
しっかり雷属性やられにされるのもいやらしい。
- ラギアクルス自身もそれを狙っているのか、電流束を作った後、即座にタックルや突進につなげる場合が多い。
- 怒り状態時には雷球を2発放ち、2本の電流束を設置してくる。
- 高出力雷球ブレス
属性:雷属性やられ【大】- 亜種が行ってきたものと同じモーションで繰り出してくる。吐き出す直前、口から紫色の電流が迸っているのが特徴。
- 着弾した後の拡散の仕方が変わっており、以前は着弾範囲に電流が激しく走るような攻撃だったものが、
着弾点を起点にして、三段階に分けて爆発が拡大するような技に変更された。
喰らうと大ダメージと共に、真上にかちあげられる。
- 拡大方向は三方向、扇状に外側に向かって爆発していく。爆破方向には一瞬だが予兆電流が走るため、電流が走った方向に慌てて逃げないように注意。
- 螺旋放電
属性:雷属性やられ【大】- 放電しながらその場でスピンした後、ラギアクルスの周りに巨大な雷球が2つ発生。雷球はラギアクルスを中心に衛星のように回りながら離れていき、一定距離を離すと地面に落下して消失する。
- 新モーション。
色々と物議を醸したファンタジー全開の攻撃。ラギアクルスを守るオールレンジ攻撃のようなもので、繰り出されると雷球の動きと本種の動きの両方に目を配らなければならなくなる。
- 雷球の速度はラギアクルス付近にいるほど早く、離れるほど遅くなる。一旦本種から離れ、遅くなったタイミングで円の中に入るように回避するのがセオリー。
が、ラギアクルスもその点を理解しているのか、雷球を発生させた後、間髪入れずに蓄電行動を取り、近づいてきたハンターを返り討ちにしようとしてくるため、迂闊に近寄らないように注意。
- 蓄電二段階目では雷球が3つに増える。単純に弾の感覚が狭くなるため、避けづらくなる。まるで弾幕系のゲームである
- 帯電噛みつき
属性:雷属性やられ【大】- 口に紫色の電流を走らせながらいきなりのけぞり、一拍おいてから勢いよく噛みつき、噛みつきと同時に雷撃を炸裂させる。
- G級限定の新モーション。今作のラギアクルスで最も注意すべき技。
這いずり突進の終わりにいきなり繰り出してくる場合が多い。
- 噛み付く前ののけぞりの際、最大90°以上向きを変えて高精度に当ててくる上に、攻撃判定がラギアクルスの首が届く範囲+電撃が炸裂する範囲と物凄く広い。
至近距離に判定は無いのだが、繰り出す直前の後退で一気に距離を離されるため、懐に潜り込んで回避するのはまず不可能。
更に恐ろしいことに、繰り出した後の隙が一切ないため、連続して繰り出される場合がある。
- これだけ凶悪な技の割に、威力はなんと大放電と同等。喰らうと凄い勢いで水平に吹っ飛ばされる。
威力が高い、追尾性能が高い、範囲が広い、隙がない、とまるで弱点のない完全なる出し得攻撃である。
回避性能を積んでギリギリまで引きつけてから回避するか、せめて雷耐性を上げて被弾に備えておきたい。
- 蓄電
属性:雷属性やられ【小】- 今作で仕様が大幅に変わったが、モーション自体に変更なし。
- 演出が変わっており、一段階目は背電殻は光らず青く染まるだけ。二段階目になると青白く光り輝き、さらに電流が激しく走る、というようなド派手な演出となった。以前よりも視覚的にわかりやすくなったと言える。
- 仕様の変更によりかなり頻繁に繰り出すようになったが、以前問題だった放電するまでの猶予はかなり長くなり、放電範囲も狭くなった。見てからでもしっかり対処できるだろう。
が、背電殻付近には構えた時点で攻撃判定が発生する。喰らっても大したダメージではないものの、吹っ飛ばされてしまう。
- また一段階目、および二段階目の蓄電行動の際、放電と同時にラギアクルスの周囲4点に落雷が発生するようになった。
放電域にいないからと安心していると被弾してしまう。要するにその位置にいるハンター対策である。
4点の落雷位置は常に等間隔で、ラギアクルスを中心に円を書くように並ぶ。うちの1点は蓄電行動を開始する瞬間にいたハンターの位置になる。
- 落雷の発生は蓄電行動を開始した時点で確定するらしく、仮に蓄電行動を妨害できたとしても普通に雷が降ってくる点には注意。
- 咆哮の後は高確率で繰り出してくるが、硬直が解けた後に回避すればギリギリ避けられるようになっている。
- 大放電
属性:雷属性やられ【大】- モーション自体に変更なし。蓄電二段階目を解除して、凄まじい規模の電撃を放出する。
放電する予兆として、ラギアクルス周辺の大気がぼんやりと紫色に光る。
繰り出した後は必ず威嚇する。- 放電の仕方が変わっており、以前は一定の放電域に雷球を無数に発生させて攻撃、というものだったが
ラギアクルスの周囲4箇所に雷撃が発生し、そこを起点に三段階に分けて電撃の爆発が拡大していくような仕様になった。
- 着弾した高出力雷球ブレスと同じような仕様で、上から見るとXを描くように広がっていくのが特徴。爆発の進行方向には予兆として紫色の電流が走るため、回避する時はそこを目安にするといい。
- 雷球の発生で攻撃範囲にややランダム性があった以前と違い、こちらは単純に決まった範囲を確実に吹き飛ばす。
規模が以前よりもかなり広がっているため、適当に回避するよりは素直に武器をしまって対処した方が無難。
- 一度爆発した地点は攻撃判定がなくなるため、1段階目の爆発、つまりラギアクルスに一番近い地点が爆発した後は、思い切って懐に潜り込めれば反撃のチャンスにもつながる。
- 今作のラギアクルスは蓄電行動の頻度がかなり高い上に、大放電を放つハードルも低くなっているため、何度もこの攻撃を拝むことになる。
準備は抜かりないように。
- ちなみに、蓄電二段階目の解除は三段目の爆発が終了した時点で確定する。つまり大放電中に中途半端に怯ませて中断させてしまうと蓄電二段階目を維持してしまい、場合によっては再度大放電を繰り出してくるというトンデモ展開になる可能性も。
◆破壊可能部位
- 頭
- 角が折れる。
- MH3シリーズでは角は破壊報酬でしか入手できないため、狙っていきたいところ。角だけでなく、逆鱗や宝玉、天鱗といったレア素材も含まれているし、弱点でもあるので一石三鳥である。
水中で破壊に成功すると大きく体勢を崩し、少しの間もがき続ける。
- 胸
- 皮に傷が入る。
- 水中、陸上ともに恐らく一番狙いやすいであろう部位。
破壊報酬は剥ぎ取りでも基本報酬でも手に入る皮系。あまり美味しくはないが、攻撃の通りもいいため気がついたら勝手に破壊されていることも多い。
- 前脚
- 鉤爪が欠ける。
- 爪系が欲しい時は積極的に狙いたい。
ちなみに陸上にいるときに前脚に攻撃を与えて怯ませると、横にぶっ倒れてこちらに背を向ける。続けて背電殻を狙うチャンス。
- 背中
- 背電殻が砕ける。
- 破壊報酬はもちろん背電殻系。
耐久値が高く、3回怯ませることでようやく破壊可能になる。物理攻撃にも強いのでなかなか骨が折れる。
水中では1回怯ませると体勢を崩し、けっこう長い間もがき続けるため、続けて攻撃を加えてやろう。
MH3シリーズでは戦略的メリットも高いため狙えるなら狙いたいところ。
- MHXシリーズは乗りシステムがあるものの非常に狙いづらい上、さほどメリットもないため無視してもいい。
- 尻尾
- 切断可能。
- リーチが短くなるため一部攻撃は避けやすくなり、水中では水流や水属性やられも無効化できる。
剥ぎ取り素材は尻尾系だけでなく、レア素材の入手確率も高いので是非狙いたい。
ただ水中のラギアクルスは常に垂直の姿勢であるため、かなり狙いにくいのが辛いところ。狙うなら陸上に上がった時である。
◆弱点属性・部位
【MH3/MH3G】
- 弱点属性
- 通常種は火>氷=龍。
ただ氷と龍は火ほど効きは良くない。- 属性の効きやすさは最大ラインで25%と、微妙な部類。その代わり部位ごとの効きやすさにあまりムラが無い。
背中は一番弱いため、早めに背電殻を破壊したいなら担ぐのも悪くない。爆破属性で行くなら別に困ることはないが
- 亜種は火=龍>氷。
- こちらは通常種と一転して属性の効きが良い。頭には効果が薄いが、それ以外の部位ならどこでもそれなりに効く。
- 弱点部位
- 通常種は斬撃なら胸>頭、打撃なら頭=胸=背中>胴=尻尾、射撃なら頭>胸が有効。
- 全体的に肉質は柔らかい方なのだが、打撃と射撃は一番よく通る部位でも40%であり、ギリギリ「弱点特効」が発動するのは斬撃の胸のみ。
とは言えラギアクルスは体力が低いため、目に見えて戦いに支障が出るほどではないのだが。
- ちなみに、肉質も硬く部位耐久値も高い背中なのだが、打撃にだけは40%と目に見えて弱い。打撃属性武器持ちなら破壊も積極的に狙っていこう。
- 亜種は斬撃なら背中>胸、打撃なら背中>尻尾、射撃なら尻尾>背中。
- 通常種とガラッと変わり、頭は斬撃と射撃なら18%、打撃なら15%とガッチガチに固く、唯一「弱点特効」が発動する部位はよりによって陸上では狙いにくい背中である。
ただし上で挙げているように属性に対しては通常種以上に弱いため、亜種と戦う際は手数の多い属性偏重武器を担いでいくとダメージを稼ぎやすい。
【MHX/MHXX】
- 弱点属性
- 過去作から変わらず、火>氷=龍。
- 傾向に変更はないが、もともとやや高めだった属性耐性が更に高くなった。
- 弱点部位
- 斬撃なら胸>頭、打撃なら頭=胸>背中、射撃なら頭>胸。
- 陸上戦闘が大幅に強化され、属性耐性が引き上げられた代わりか、肉質は更に柔らかくなり、弱点特効が発動する部位も増えた。特に、もともと柔らかかった胸は斬撃なら55%も通る。
- そんな中でも背中は相変わらず硬いが、打撃には弱いのも変わらず。今作は背中の部位破壊が困難だが、限られた隙で狙っていくなら打撃武器だろう。
◆武器
どの武器もラギアクルスの外皮の鮮やかな青色に染まっており、ところどころに爪や角、背電殻の色である赤色がアクセントとして入っている。
属性はもちろん雷属性。
初登場したMH3ではパッケージモンスターの武器なだけあってかなり優遇されていたばかりか、唯一の雷属性武器であったため、ライバルとなりうる武器が無くまさに一強状態だった。
MH3Gでは
クルペッコ亜種、
ギギネブラ亜種、そして
ジンオウガと、雷属性の使い手が多数参戦したため唯一とは言えなくなったが、それでも総合的な性能で言えばトップクラスである。
今作では強化していくと、途中から亜種の素材を要求され始め、最終的には
美しい白色の武器へと変化する。
MH4/MH4Gでは本竜はいないものの、竜人問屋の素材交換で一部の武器は作製可能である。
しかし本シリーズに再登場となった
ラージャン、
キリンといった強力な雷属性の使い手の存在は大きく、かつての威光は隠れがちになってしまった。
が、のちのMHX/MHXXでは強化次第で武器格差が縮まる場合が多くなり、上記の武器にも負けない存在感を放つようになった。
特にラージャンとキリン武器は攻撃力や属性値に偏りがあり、クセが強いものが多く、バランスや使い勝手の良さで此方を愛用するハンターも少なくない。
どの作品でも
ライバルとなりうるのは、やはりジンオウガの武器群。物理攻撃力や斬れ味、属性値で優劣があり、総合的に見るとどっこいとなるものが多い。
対峙するモンスターに適したもので順次使い分けていこう。
もちろん愛着で担いでいくのも悪くない。
◆防具
武器と同じように青色をベースに赤色の差し色が入った、西洋風の甲冑といった装い。
スキルは「属性攻撃強化」や「覚醒」など、属性攻撃関係のものがつくほか、剣士、ガンナー用ともに「集中」「弱点特化」といった優秀かつ汎用性が高いものを備えている。
水中戦のある作品には「スイマー」がついているものもある。
亜種の防具は白色をベースに紺色の差し色が入ったカラーリング。
スキルは「属性やられ無効」といった属性防御関係のものがつき、「攻撃力UP」「破壊王」というような攻撃的なものを備える。
通常種とは毛色の違うスキルだが、これまた汎用性が高く、どの武器でも着て行きやすいのが魅力。
ちなみに、MH4Gでは素材交換で亜種の素材も得られるが、防具は作製できない。
MH4Gまでスキルの傾向はあまり変わらなかったが、MHXシリーズになると様変わりし、何故か「ガード性能」「スタミナ急速回復」といったガード関係のものがつき、主にランス使いには嬉しい装備となった。
水中戦で猛威を振るったランスの威光を表現しているのかもしれない。
総じて、どの作品でも優秀な装備となっている。単純に見た目もスマートで格好良い。
当然の如く雷に対する耐性が高いが、火にはめっぽう弱い。
◆余談
- リオレウスとの関係
- コンセプトとして、「大空の王者」たるリオレウスと対をなす「大海の王者」としてデザインされたモンスターであり、作中でもまるでライバル関係のような描写がなされることがある。
…ただ、本竜たちの生息域が空と海でまるで異なるため、共演する機会があまりないのが惜しいところ。
- MH3のOPムービーではリオレウスが確保した獲物をラギアクルスが奪おうとしたり、MH3GのOPムービーではリオレウス亜種が狙っていた海中の獲物をラギアクルス亜種が横取りする姿が確認できる。
- 色合い的にも意識しているところが多く、通常種の背電殻の色はリオレウスと同じ赤色で、亜種の色はリオレウス亜種と同じ青色である。
- 水中モーション
- 現状MH3シリーズでしか見られないラギアクルスの水中モーションだが、水中戦が無い作品では嵐龍アマツマガツチにモーションが流用されている。
かの古龍には「嵐を引き起こし、皮膜で風を受け、泳ぐように空を舞う」という設定があるため、まさにそれを表現するのにぴったりな発想である。
- 幼体
- 実はラギアクルスの幼体は未だに発見例がないらしく、繁殖方法についても謎が多いとのこと。
- …が、外伝作品のMHSTやスピリッツでは普通にタマゴから生まれるラギアクルスの幼体が拝めてしまう。ギルドですら見つけられなかった幼体がこんな…
とはいえあくまで外伝なため、二次創作として見ればいいだろう。
- 交尾の観察例もないことから、本種は単為生殖を行うのではないか、という説もあるという。単為生殖はご存知の通り、単独で子を作ることを指し、実際のサメ、トカゲにも確認されている。
さらに本種が胎生ならば親と全く同じ形態の子が産まれるため、尚のこと目立たないだろう。
…が、仮にこの説が正しいなら、ラギアクルスは雌の個体しかいないことになる。「王者」と呼ばれてるのに
あくまで仮説だが、もしかすると…
- 名前の由来
- 公式によると、「雷光を放つ大渦」という意味であり、ラギアとは雷光を、クルスとは大渦を意味するらしい。
- が、モンハン世界の言葉であるようで、現実世界で該当する意味の似たような発音を持つ単語は未だ見つかっていない。調べれば割とらしいものが出てくるモンハンには珍しく、明確な由来は不明である。ラギアもクルスも何かしらの単語をもじったものか、造語である可能性が高い。
まさか「ギラギラ」眩しくて「クルクル」渦巻いているからとか言うんじゃないだろうな
- ラテン語で「光」を意味する「lux(ルクス)」と、その女性系である「lucia(ルキア)」を組み合わせたのではないか、と言う説がある。
- ラテン語で「王」を意味する「regia(レギア)」と、英語のcruiseの由来になった「crux(クルクス)」を組み合わせると「巡洋する王」ぐらいの意味合いにはなるか。無理矢理感が否めないが。
- ちなみに某人気漫画では名前の一部に「ギアクル」とつく水の龍で攻撃する技が登場する。
…まぁだからなんだと言う話だが。
- 不遇な遍歴
- 水中戦がメインのモンスターという事もあって(MHXシリーズのようなぶっ飛んだ例外は除いて)参戦しにくい作品が多く、看板でありながらどうしても扱いは悪くなりがち。
いっそ陸戦に切り替えたとしても、どうやらプログラム的な点で課題も多いらしい。
- MHWorldでは当初は参戦を予告されていたが、残念ながら欠席となってしまった。
理由は、プロトタイプでラギアクルスを動かしてみたところ、海竜種特有の接地面が多い体型とMHWorldの起伏に富んだ地形との相性が非常に悪く、処理負荷の問題で泣く泣く没になってしまったとのこと。
当初は構想まで練られていただけに、非常に惜しい。
- MHRiseではロアルドロスやタマミツネなど他の海竜種は復帰したが、ラギアクルスは未登場。
同じ海竜種でも、タマミツネのような微妙に腹を浮かせて歩く骨格であるなら問題はないが、ラギアクルスのような地面にへばりつくような歩き方をする海竜種はやはり難しかったとのこと。残念ながらこちらでも欠席となってしまった。
- しかし、MHWildsでは新たな海竜種の沙海竜バーラハーラが登場。バーラハーラはラギアクルスのように一見地面にへばりついて歩くモンスターに見えるが…
- そして上述した通り、モンスターハンターシリーズ20周年記念作品という大きな節目となるMHWildsにて、とうとう念願の復活を果たした。
しかも陸上での不具合を見事に乗り越えられただけでなく、「水中戦」まで実装されている。今までの不遇な来歴を過去にするかのような超豪華待遇に、長年彼を推し続けていたハンターにとっても嬉しい展開となったことだろう。
その代わりめっちゃ強くなったけど
蒼海の首飾りを手に入れた者から追記・修正お願いします。
- 水中戦の廃止は正直嬉しかった -- 名無しさん (2014-03-14 22:43:52)
- 4Gでゴア・マガラと戦闘したときと同じく船上戦闘で出てこないかな -- 名無しさん (2014-04-30 23:32:36)
- 4シリーズが空中戦(陸上での立体戦闘)意識してるから、5でどうなるかだな。 -- 名無しさん (2014-12-09 12:38:09)
- 希少種は楽しかったな・・・ ランスでチクチクプレイが最高 -- 名無しさん (2014-12-09 12:52:50)
- 復活するってホントか? -- 名無しさん (2015-09-01 23:27:44)
- クロスでの復活おめでとう。 -- 名無しさん (2015-09-02 07:31:25)
- 水中ないから雑魚確定? -- 名無しさん (2015-09-03 15:29:50)
- ライゼクスとジンオウガがいるから、ラギアは強さ控えめかもね。もしくは亜種のモーションを一部輸入して強化するとか? -- 名無しさん (2015-09-04 01:03:45)
- 地上戦をそつなくこなせるように調整されて復活するらしい -- 名無しさん (2015-11-16 21:29:56)
- フルフル、ライゼクス、ジンオウガ、キリン、ラージャン、鉱石系、にラギア復活とあって雷属性武器が前代未聞の大激戦状態に。クルペッコ亜種やギギネブラ亜種がいなくて本当によかったな・・・。 -- 名無しさん (2015-12-07 12:04:43)
- まさかのファンネル使いになるとは… -- 名無しさん (2015-12-12 15:45:55)
- ↑2 なおそのおかげで雷耐性を持つ防具が重宝するらしい -- 名無しさん (2016-01-06 21:13:20)
- クロスで初めて戦ったが結構楽しい良モンス。本領ともいうべき水中型のこいつとも戦ってみたいと欲が沸いたよ。 -- 名無しさん (2016-01-06 23:40:05)
- Xのこいつは種族を間違えてる気がする -- 名無しさん (2016-03-08 19:49:29)
- 個人的に一番好きなモンスターなのでリオレウスやそれに続くと思われるティガレックスのようにリボルテック化してほしいな -- 名無しさん (2017-01-16 12:47:01)
- ぶっちゃけXだとキリンより雷の使い方が古龍してる気が… -- 名無しさん (2017-05-29 14:36:49)
- 未だに繁殖方法謎という地味に重要な設定。海中を自在に泳げはするが卵は人知れない場でひっそりと行ってんだろうか -- 名無しさん (2021-03-13 08:14:44)
- 水中戦好きだったのでまた日の目を見てほしい -- 名無しさん (2021-03-22 01:33:54)
- もしライズで復活するんだったらリオレウスとの縄張り争いが見たい -- 名無しさん (2021-05-20 21:22:46)
- 残念なことに公式のTwitter(英語)で出演できないと明言されちゃったね・・・ どうやら地面にへばりつく骨格が原因でライズ・サンブレイクの地形と相性が悪く断念したんだとか。 だから新登場の海竜種が全てタマミツネと同じ骨格が使われてるのか。 -- 名無しさん (2022-06-20 04:12:12)
- 祝:モンハンワイルズ不参戦決定! -- 名無しさん (2025-02-12 10:56:32)
- ところが繭にそれっぽいのがいるらしい…? -- 名無しさん (2025-03-25 17:11:36)
- やっと戻ってきたか… -- 名無しさん (2025-03-25 23:22:36)
- 復活ですねー -- 名無しさん (2025-03-26 01:20:37)
- 青い甲殻、特徴的な背中の突起、赤みがかった爪…もう確定でしょ -- 名無しさん (2025-03-26 01:25:31)
- ワイルズで同じ骨格のジン・ダバドと戦っている際、壁際だと変な挙動をすることが多いから、やはりこの骨格は動かしづらいんだろうなぁ、と思った -- 名無しさん (2025-03-26 07:07:36)
- 祝復活。水辺の生息地的に緋の森になりそうだけど頂点捕食者さん... -- 名無しさん (2025-03-26 09:35:04)
- ベースキャンプでたまに学者達が「エスカナイトの甲殻硬過ぎるだろ。動きを犠牲にしてまでなんのためだよ」という会話してるけど、これがラギアクルス登場の伏線だった…? -- 名無しさん (2025-03-26 22:44:22)
- 復活おめ。疑似水中戦実装のために時間かかったのかな -- 名無しさん (2025-06-27 07:45:46)
- ↑4ジン・ダハドの壁際で変な挙動するのって突進の際に壁に張り付くあれの事?あれは別に変な挙動じゃなくて冷気で壁に張り付く生態を反映しただけだと思うよ -- 名無しさん (2025-06-27 18:53:14)
- ↑壁に張り付くまではいいんだけど、立ち往生しちゃうことがあるんで、それのことだと思う。 -- 名無しさん (2025-06-27 19:10:58)
- 海竜(海がない土地にも平然と現れる) -- 名無しさん (2025-06-30 12:48:10)
- ラギアクルスってたまに空飛ぶよね -- 名無しさん (2025-06-30 22:07:15)
- 色々言われはしてるけど、最新グラフィックでこいつを拝めたのは素直に嬉しいし、擬似的ではあるけど、水中戦が再現されてるのもワクワクした。それだけに本編が荒れまくってるのが悲しいわ… -- 名無しさん (2025-07-03 13:27:19)
- ワイルズのはラギアクルスの皮を被ったアマツマガツチだぞ -- 名無しさん (2025-08-06 13:25:28)
最終更新:2025年08月26日 19:38