名前:ケフカ・パラッツォ
ジョブ:
大魔導士
年齢:35歳
身長:167cm
体重:48kg
誕生日:11月19日
血液型:AB型
好きなもの:鏡
嫌いなもの:レオ将軍
趣味:人形遊び
「命… 夢… 希望…
どこから来て どこへ行く?
そんなものは… このわたしが 破壊する!!」
スクウェアソフト(現スクウェア・エニックス)が1994年に発売したRPG『ファイナルファンタジーVI』(FF6)の
ラスボス。
テーマ曲と共に事あるごとに聞ける笑い声が印象に残っている人も多いだろう。
ゲームの序盤から登場し、(敵対組織と繋がる)同盟国フィガロへの偵察、ナルシェ侵攻、首都ベクタを襲った幻獣討伐など、帝国の数々の作戦を指揮している。
ただ人望はほとんど無く、帝国の一般兵からも「ケフカの野郎」「あんな奴が将軍になるんだったら実家に帰らせてもらう」と方々で辛辣な陰口を叩かれる始末。
ドマ侵攻時には篭城の構えを取る敵に対して堀に繋がる
川に毒を流し、
自軍の捕虜も気にせず大量虐殺を行うという非人道的行為を、
司令官のレオに無断でやってのけている
(ただ、レオ自身はこの作戦の直前に本国への帰還命令を受けており、彼がいなくなった為に一応ケフカはドマ侵攻における司令官のトップ。
レオはそのまま篭城戦に付き合うつもりだったが、ケフカは「手っ取り早くやってやる」との言葉通り短期攻略を果たしている。
ガストラ皇帝自身も腹芸ができる人物なので、高潔なレオを後ろに下げて汚れ仕事をこなせるケフカを重用していた様子がある)。
主人公達の後をつけて封魔壁を開かせ大量の幻獣を呼び込んだ結果、帝国の首都ベクタは幻獣の総攻撃を受けて壊滅してしまう。
皇帝ガストラは休戦の証の一つとしてドマで毒を使用したケフカを一旦は戦争犯罪人として投獄するが、実際はただのポーズにすぎず、
まもなくその休戦を反故にして敵対組織を一網打尽にしようとした後、首都ベクタを襲撃した幻獣を倒す切り札として彼を出獄させる。
ケフカが魔力を得るため次々幻獣達を葬り去る姿を見て、住処に残っていた残りの幻獣達も加勢に現れるが、まるで相手にならず返り討ちとなってしまう。
その後、ガストラ皇帝と共に空き家となった幻獣の住処に潜入して浮遊大陸「魔大陸」を始動させ、その中で幻獣と魔法の神「三闘神」を目覚めさせる。
魔大陸の最深部で、帝国を裏切った元帝国将軍セリスを含む主人公達一行と対峙するシーンが中盤のクライマックスとなる。
三闘神の力を得たガストラは主人公らを術で拘束するが、元部下であるセリスに対しては「お前だけは特別だ」「ケフカと共に子をなせ」と言う
(セリスもケフカと同じ魔導実験の被験者であり、帝国が生んだ人造魔導士がこの2人だけという事を大いに踏まえた発言であろう事は想像に難くない。
設定上ガストラの年齢は59を超えているので、発言の意図としては「自分の死後も帝国を繁栄させろ」と言っているのだと思われる)。
その際、ケフカは「仲間達を始末する事で裏切りを水に流してやる」と一振りの剣を渡すがセリスはこれに反発、逆にケフカを刺してしまう。
それによってケフカは逆上し、三闘神の力を解放しようとする。
流石に世界が滅ぶ危機を招くのでガストラはこれを制止する(ガストラの目的は飽くまで
世界征服であり、
征服すべき世界の崩壊は望んでいない)も、
ケフカは「奴等に三闘神の力を見せるチャンス(この時はまだ忠誠心はあり、ガストラに敬語を使っていた)」と命令を聞こうともしない。
ガストラは「役に立たぬ」と遂に魔法で粛清を試みるも、ケフカが三闘神の像の真ん中に立っていたため全て不発に終わる。
ケフカは逆にガストラに三闘神の攻撃を浴びせ「役立たず以下」とこき下ろした挙句、大陸から突き落として殺害。三闘神の像を動かして、世界の均衡を崩した。
その後は自ら
神となって世界を崩壊させ、三闘神から奪った力で自分に歯向かう者や、その者の家、村などを容赦なく破壊、虐殺していった。
世界中の瓦礫を集めて建てられたケフカの居城「がれきの塔」に乗り込み、ケフカを滅ぼす事がゲームの最終目的となる。
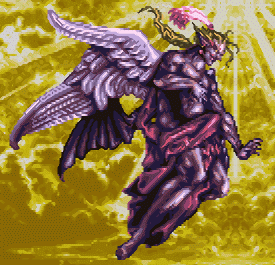
その所業や
いかにも三下風味の性格でありながらラスボスに上り詰めた事から、プレイヤーに強いインパクトを与えた。
が、攻撃力インフレ気味なFFシリーズがバランスを模索していた時期のボスであるため、壊滅的にHPが足りないなどの素敵な欠陥がある
(一応最大HP62000は今作第2位<1位は三闘神の1体・魔神の63000>なのだが、今作では「一発で9999ダメージ」が鍛えれば普通に出せるので…)。
特定の分野に特化せず漫然と育てたパーティで挑むとそれなりに苦戦するのだが、キャラクターのレベルと装備・アビリティが極まっていれば、
登場演出でページ上部の台詞を言い終える前に、一個前の前座と一緒にまとめて殺せる。
この台詞は「FinalRound Fight!」のコールに相当する戦闘開始の合図なのだが、その前に
フライングで無言のまま死ぬ。シンジラレナーイ。
かくして高いパーティ構成・育成自由度の煽りも受けて、
VIIのイカと並んで、シリーズを代表する弱ボスとなっている。
しかし好き勝手に世界をボロボロにした挙句、無責任に呆気なく死ぬという姿は、キャラ的にそれらしい調整と言えば言えるのかもしれない。
また、最終決戦時の演出はスーパーファミコンの全ゲームで見てもトップクラスと言える出来で、
当時のドット技術の粋を感じさせる描き込みと、敵を倒すごとにせり上がりが行われる場面転換の演出は大変素晴らしい。
この際の
BGM「
妖星乱舞」はRPGのBGMでありながら全4楽章構成(形態が変化するごとに楽章が移る)となっており、
サウンドトラック換算で
約18分
に及ぶ長さを持つFFシリーズ屈指のボリュームを誇る曲で、そちらも人気が高い。
ちなみに同時期のRPG『新桃太郎伝説』でも偶然の一致で似たようなキャラが登場しており、
両方をプレイした人間からは外道ラスボスコンビとしてネタにされる事がある。
尤もバランス調整の結果、相対的にHPが少ない事から弱ボスと言われているこちらとは対照的に、
あちらはゲーム中最高のHPや序盤の4回攻撃などから手強いボスとなっている。
そんな彼だが、一方で非常にコミカルな描写が多いのが特徴である。
その最たる例としては、その迷言の多さがあげられる。
「シンジラレナーイ!」「つまらん!」「ちっくしょーーーーー!!!」「
役立たず以下なのだー」「
…で、結局何がしたい?」「
脳みそまで筋肉でしょ?」など、
枚挙に暇が無い。
しかし、その一方で「滅ぶと分かって、なぜ作る?死ぬと分かっていて、なぜ生きようとする?」といった深みのある発言もしており、
ギャップのある二面性がキャラクターとしての人気を作っている一因だろう。
また、一人称も「私」「おれ様」「ぼくちん」など、状況に応じてコロコロ変化する。
このあたりは、変身するごとに一人称の変わる
彼に似ていると言えよう。
『FF』リーズの歴代主人公とボスが
クロスオーバー出演したアクションゲーム『ディシディア ファイナルファンタジー』にも、
『FF6』の主人公代表である
ティナと共に、カオスサイドとして参戦した。
元となる『FF6』に音声はないが、『ディシディア』での声は
ラディッツや
北斗の拳のナレーションでお馴染みの
千葉繁
氏。
この作品にケフカを出す事が確定した時から既に声優は千葉氏にと決めていたほどで、
氏特有のアドリブ(千葉リブ)もあいまって、原作以上にコミカル度がさらに高まっている。
興味のある人は是非やって確かめて頂きたい。
なお、千葉氏は後に発売された『いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』においてもケフカを担当している。
英語吹替声優は
Dave Wittenberg
氏。
『ディシディア』の前日譚にあたる『ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー』でも引き続き登場。
セフィロスに小細工を吹き込んだり、
洗脳をしていたり、裏切り者への制裁を下していたりなど、
存分に悪役としての活躍をしつつもコミカルな言動は相変わらず。道化と侮られながらも腹黒い彼の活躍は一見の価値あり。
ただ、
同僚の元部下である
ギルガメッシュ(FF5)には「ケフカ・パパラ……読めんぞ!」と名前の事がネタにされているが。
|
+
|
ボイス集 |
| 千葉氏 |
『ディシディア』
|
『ディシディアNT』
|
Wittenberg氏(『ディシディアNT』)
|
|
|
|
+
|
ディシディアでの性能 |
特異な軌道の魔法で相手を翻弄する「トリックスター」
結論から言うと 弱い。
最弱候補、断言して最弱と言い切る人も。
最大の理由として、このゲームでは、一部の魔法攻撃をガードかエアダッシュで跳ね返せるというシステムがあるのだが、
ケフカの主力となるブレイブ攻撃のほとんどがこれに当てはまり、さらに跳ね返された時の被害が大きいというのがある。
典型的な魔法使い系のキャラなので接近戦に弱いのに、相手の接近を防ぐ有効な手段がほとんど無いのである。
それを抜きにしても、技の前後の隙が大きかったり、弾速が遅かったりとあまり強い点が見当たらない。
同じように主砲技を跳ね返されるなど弱いとされる 皇帝(FF2)と違い、ケフカには特に相性が良い相手もいないというのが悲惨。
スタッフも流石に弱すぎると思ったのか、UT版ではかなりの強化がなされた。
「くねくねファイガ」と「アルテマ」でガードを崩せるようになり、作中屈指の 死に技であった「ハイパードライブ」が全く別物の実用的な技になった。
総じて人は選ぶものの、上手い人が使えばかなりの強さを発揮するテクニカルなキャラになっている。
『ディオデシムで』は 新技が幾つか追加されたキャラがいるが、ケフカは新技無し
(『ディシディア』の時点でセフィロスの持ち技となった「こころないてんし」を除き、
最終決戦時に使用した技全てが採用されているので技数自体は元々多い).
UT版の調整を元にバランスを取られており、それなりの性能となっている。
|
しかし、残酷でありながらひょうきんかつコミカルであり、シリーズでも稀有なラスボスは、かつて千葉氏が演じた
某破壊大帝を連想させる。
他にも千葉氏が演じた
道化師の悪役という繋がりで『ONE PIECE』の道化の
バギーも普段はコミカルな一面が目立つ一方で、
裏切り者や敵には冷酷な制裁を加える点もケフカを彷彿とさせるが、部下達に
恐れられつつも慕われている点はケフカとは真逆である。
FFとドラクエ双方の30周年を記念する『いたスト30th』ではFF6からの代表としてプレイヤーキャラ化。
ザキ・ザラキを連発するクリフトをおちょくったり、
ゴルベーザを
「いいですとも野郎」呼ばわりするなどのはっちゃけぶりを見せつけた。
なお、ゲーム中では帝国の酒場で一般市民からわずかに語られるだけであるものの
*1、
前述のように彼の精神崩壊は実験段階だった魔導実験の副作用によるものである。
ある意味で帝国が生み出した「魔導」の被害者とも見る事ができる人物であり、それを考えるとこの物語はより重い。
(以上、Wikipedia及びファイナルファンタジー用語辞典Wikiから転載・改変)
MUGENにおけるケフカ・パラッツォ
En氏が製作したものが存在していたが、現在は代理公開していたdoloop氏のサイト廃業により入手不可。
『FF6』のラスボス戦を再現したもので、いかにして倒すかを楽しむ主旨のキャラなのでプレイヤー操作は不可。
前座として登場する神々の像との3連戦の後ケフカが登場し、全て倒して初めてKOとなる。
神々の像は原作を反映して複数の喰らい
判定を持ち、
アビス同様倒すと変身……と言うか、次の部位との連戦となる。
攻撃方法もその度に変化していき、画面全体攻撃や
一撃必殺技など強力な技を持っており、
喰らい判定に
AIが対応できず、プレイヤー操作でもないと倒すのは困難。
もっとも、ケフカ本体まで勝ち抜いていけるだけの対応力・攻撃力があるようなキャラクターならば、
喰らい判定が最も大きく、攻撃の手も緩いケフカに苦戦する理由は全く無いのでほぼ消化試合となってしまう。
前座の方に苦戦するというのは、ある意味で
原作再現とも言える。
出場大会
更新停止中
凍結
削除済み
*1
本作では、話す必要の全く無いただの町人・村人が、そこでしか聞けない人物・世界設定に関する重要事項をさらっと話すという例が複数見られる。
しかもゲームの進行でその人物と話す機会がなくなったり台詞が変わったりするため、聞く機会を逃してしまう場合もある
(実際、他媒体でケフカの元々の境遇について初めて知ったというプレイヤーもいくらか見られる)。
他の例では、「あるパーティキャラと他のパーティキャラは
実は本当の親戚ではない
」という話などがこれにあたる。
ちなみに精神崩壊前のケフカがどういう人間だったのかについてははっきりしないが、魔導研究所脱出前のイベントでシド博士が
「ケフカに脅されて幻獣から魔力を取り出す研究をしていた」というような事を言っているので、博士の勘違いや嘘でないなら、
元々ケフカは「魔導実験(幻獣から魔力を取り出す→それを人間に注入して改造)にシド博士を脅してでもやるほど乗り気」だったが、
その最初の被験者に自分を使用している(前述の内容的に無理やりやられたのは考えにくい)あたり、一応最後の良識はあったようである。
最終更新:2025年10月25日 16:00
